食生活が乱れている
雑食に近い肉食動物である犬の体は、必要な栄養や成分がきちんと吸収されないと栄養不足や消化不良による体調不良を起こしやすくなります。 「偏った食事が多い」「人の食べ物を与えている」「オヤツが多い」など思い当たることがあれば、すぐに食生活の見直しを行っていきましょう。 ビタミン・ミネラル・酵素がしっかり含まれているフードは、犬の体を健やかな状態へ導き維持してくれます。 また、多すぎても体に異常をもたらすこともあるので、愛犬の体重や運動量に合わせてしっかり量ってください。 オヤツは愛犬とのコミュニケーションにもなりますのでやめる必要はありません。 ただ回数はそのままに、あげる量を減らします。 信頼関係を損なわずに愛犬が満足してくれる方法で一日の適量を与えましょう。犬同士で体をなめ合う理由
 多頭飼いや散歩中に出会う犬に、愛情や仲間意識からお互いの顔を舐め合うことがあります。
とても微笑ましい光景でもあり敵意のないことを確かめ合うコミュニケーションの方法ですので、そのまま様子をみても問題ないでしょう。
犬は、挨拶やお互いの性格や年齢など確認する目的のためにお尻の肛門腺のニオイを確認します。
相手の犬のニオイが強かった場合、ペロッと舐めてしまうこともあります。
性格にもよりますがその行動がエスカレートしてしまうとトラブルに繋がりかねません。
散歩中に出会う犬と挨拶させる場合は、よく愛犬の様子を観察して時には引き離すことも大切です。
多頭飼いや散歩中に出会う犬に、愛情や仲間意識からお互いの顔を舐め合うことがあります。
とても微笑ましい光景でもあり敵意のないことを確かめ合うコミュニケーションの方法ですので、そのまま様子をみても問題ないでしょう。
犬は、挨拶やお互いの性格や年齢など確認する目的のためにお尻の肛門腺のニオイを確認します。
相手の犬のニオイが強かった場合、ペロッと舐めてしまうこともあります。
性格にもよりますがその行動がエスカレートしてしまうとトラブルに繋がりかねません。
散歩中に出会う犬と挨拶させる場合は、よく愛犬の様子を観察して時には引き離すことも大切です。
犬が床をなめる理由
愛犬が床を舐めるときは、そこに食べ物のニオイが残っていたり気になるニオイに惹かれて舐めていると考えられます。 キッチンやダイニングなどは犬にとって危険な食べ物が落ちていたり拭き取ったあとのニオイが残っていたりする場合も多く、できるだけ近寄らせないよう仕切りで区切ると安心です。 また、衛生面からも残らないようにしっかりと拭き取りを心掛けましょう。まとめ
 ペロペロと舐める姿は、見ていて可愛い姿でもあります。
しかし実際は体や心の問題や痛みなど犬にとって良いことばかりではないのも事実です。
言葉を話せない愛犬からのボディメッセージに早めに気付いてあげられるように注意してあげましょう。
ペロペロと舐める姿は、見ていて可愛い姿でもあります。
しかし実際は体や心の問題や痛みなど犬にとって良いことばかりではないのも事実です。
言葉を話せない愛犬からのボディメッセージに早めに気付いてあげられるように注意してあげましょう。 犬は加熱したエビなら食べても大丈夫
 人が普通に食べることができる食材でも犬に与えてはいけない食材がいくつかあります。
その一つにエビがあり、加熱しているのであれば食べさせることができます。
エビにはタンパク質が多く含まれているので栄養価の面において優れています。
しかし、エビにはチアミナーゼという成分が含まれており、犬が接種してしまうとチアミン欠乏症になってしまうリスクがあります。
チアミナーゼは熱を加えるとなくなるので犬にエビを与えるのであれば必ず加熱するようにしましょう。
人が普通に食べることができる食材でも犬に与えてはいけない食材がいくつかあります。
その一つにエビがあり、加熱しているのであれば食べさせることができます。
エビにはタンパク質が多く含まれているので栄養価の面において優れています。
しかし、エビにはチアミナーゼという成分が含まれており、犬が接種してしまうとチアミン欠乏症になってしまうリスクがあります。
チアミナーゼは熱を加えるとなくなるので犬にエビを与えるのであれば必ず加熱するようにしましょう。
犬にエビを与える方法
 上記では犬にエビを与える際に加熱すれば問題ないと紹介しましたが、正しい与え方をしなければなりません。
いくら加熱すれば食べることができるエビでも間違った与え方をしてしまうと体調を崩してしまう原因になってしまいます。
次に、犬にエビを与える方法を紹介するので参考にしてください。
上記では犬にエビを与える際に加熱すれば問題ないと紹介しましたが、正しい与え方をしなければなりません。
いくら加熱すれば食べることができるエビでも間違った与え方をしてしまうと体調を崩してしまう原因になってしまいます。
次に、犬にエビを与える方法を紹介するので参考にしてください。
少量だけ与える
犬にエビを与えるのであれば少量に控えるようにしましょう。 犬はあまり魚介類を食べることに優れた体を持っているわけではなく、消化しにくい特徴があります。 そのため、一度にたくさん与えてしまうと、消化不良になったり下痢や嘔吐をしてしまう可能性も出てきます。 そのため、エビを与える際はフードのメインとして使用するのではなく、トッピングに使用したり、おやつの代わりに与えるようにしましょう。 エビを与える目安は一日に摂取すべきカロリーの1割程度です。絶対に加熱する
 上記でも紹介したようにエビを生のまま与えてしまうとチアミン欠乏症になってしまうので必ず加熱するようにしましょう。
しっかり熱を加えることはもちろんですが、食べやすいように小さく切ることも大切です。
小さく切ることで食べやすくなるだけではなく、加熱しやすくなるメリットもあるため、生焼けの状態になることを未然に防ぎます。
エビは加熱すると色が変わるので見分けやすいですが、表面だけの色で加熱できているかどうかを確認していると中まで熱が加わっていないこともあるので気をつけましょう。
上記でも紹介したようにエビを生のまま与えてしまうとチアミン欠乏症になってしまうので必ず加熱するようにしましょう。
しっかり熱を加えることはもちろんですが、食べやすいように小さく切ることも大切です。
小さく切ることで食べやすくなるだけではなく、加熱しやすくなるメリットもあるため、生焼けの状態になることを未然に防ぎます。
エビは加熱すると色が変わるので見分けやすいですが、表面だけの色で加熱できているかどうかを確認していると中まで熱が加わっていないこともあるので気をつけましょう。
エビの尻尾や殻は与えない
人がエビを食べる際には殻をとって尻尾も食べることはありません。 そのため、犬にエビを与える際にも同じく殻を取り、尻尾も与えないようにしましょう。 犬は骨のような硬いものを食べてしまうイメージが強いため、殻や尻尾も食べることができると思い、そのまま与えてしまうことも少なくありません。 確かにそのまま与えても犬は食べますが、消化しずらい部分でもあるため、しっかり加熱していても消化不良になりやすいです。 また、硬い部分でもあるので胃や腸を傷つけてしまう原因にもなります。人間用えびせん&乾燥エビは食べさせない
エビの食材は加熱してそのまま食べてもおいしいですが、せんべいなどに加工されている場合や乾燥させているエビもあります。 どちらも生の状態ではないため、犬に与えても大丈夫と考えてしまいやすいですが、 あくまでも人が食べるように加工されているので塩分が多く含まれている可能性が高く、あまり与えることは好ましくありません。 その代わりに犬用に作られているエビせんべいであれば塩分も控えめになっているので与えても問題ありません。犬が生のエビを生で食べてしまった時の対処法
 犬に生のエビを与えてはいけないことを知っていても食卓に並べていた生のエビを知らない間に食べてしまうこともあります。
もし食べてしまったのであれば正しい対応をすることが求められ、症状が悪化してしまうことを未然に防ぐこともできます。
犬に生のエビを与えてはいけないことを知っていても食卓に並べていた生のエビを知らない間に食べてしまうこともあります。
もし食べてしまったのであれば正しい対応をすることが求められ、症状が悪化してしまうことを未然に防ぐこともできます。
犬の様子をしっかりと観察する
まずは、犬の様子をしっかり観察するようにしましょう。 犬が生のエビを食べてしまったら下痢や嘔吐を繰り返すようになったり、痙攣や体がかゆくなるなどの症状があらわれます。 食べる量が少なければ少し軟便になったり、少量吐き出すこともありますが、落ち着いてくることもあります。 生のエビを食べてしまったときにあらわれる症状は個体差があるのでまったく症状があらわれない犬もいればすぐに症状があらわれてしまうのでよく観察しましょう。動物病院に必ず連絡する
 犬が生のエビを食べてしまったのであれば症状に関わらず必ず動物病院に連絡するようにしましょう。
いつ食べたのかや食べた量、現在の症状などを詳しく伝えましょう。
できるだけ正確に伝えることで正しい選択を行うことができます。
犬を飼っていればいつ体調を崩してしまうかわからないので事前に動物病院の場所や連絡先を確認しておくことも大切です。
特に、休日などは動物病院に連絡ができない場合もあるので休日や深夜でも連絡ができる動物病院も確認しておけばより安心です。
犬が生のエビを食べてしまったのであれば症状に関わらず必ず動物病院に連絡するようにしましょう。
いつ食べたのかや食べた量、現在の症状などを詳しく伝えましょう。
できるだけ正確に伝えることで正しい選択を行うことができます。
犬を飼っていればいつ体調を崩してしまうかわからないので事前に動物病院の場所や連絡先を確認しておくことも大切です。
特に、休日などは動物病院に連絡ができない場合もあるので休日や深夜でも連絡ができる動物病院も確認しておけばより安心です。
動物病院で行われる治療や処置
動物病院では食べた量にもよりますが、まず吐かせる催吐処置を行い、生のエビを吐き出させます。 体に湿疹や痒みが出ているのであればアレルギー反応を起こしているので症状を抑える薬が投与され、嘔吐や下痢が酷いのであれば整腸剤や下痢止めの処方がされます。 下痢や嘔吐を繰り返しているとそれだけ水分も体外に排出していることになり、脱水症状になっている可能性もあるので場合によって点滴を打たれることもあります。 手術になることはありませんが、様子見を兼ねて入院する場合も考えられます。まとめ
犬には生のエビを与えることは危険であるため、もしエビを与えたいのであれば必ずしっかり加熱するようにしましょう。 また、万が一生のエビを食べてしまう可能性もゼロではないので正しい対処方法を把握したり、連絡する動物病院をいくつかリストアップしておくこともおすすめです。ペットロスになりやすい人とは?
 毎日、当たり前に側にいてくれたペットがある日突然いなくなってしまうと、一緒に暮らしていた年月に関わらず例えようもない寂しさや悲しみを感じるのは当然の心の反応です。
しかし、その心の反応が強く出すぎてしまうと「ペットロス」になりやすくなるといわれています。
ペットロスは、ペットとどのように接していたかによって程度や期間も様々あり、普段の生活にも支障が出てくる場合もあります。
ではどのような人がペットロスになりやすいのでしょうか。
毎日、当たり前に側にいてくれたペットがある日突然いなくなってしまうと、一緒に暮らしていた年月に関わらず例えようもない寂しさや悲しみを感じるのは当然の心の反応です。
しかし、その心の反応が強く出すぎてしまうと「ペットロス」になりやすくなるといわれています。
ペットロスは、ペットとどのように接していたかによって程度や期間も様々あり、普段の生活にも支障が出てくる場合もあります。
ではどのような人がペットロスになりやすいのでしょうか。
生前の飼育方法に後悔を感じている
言葉を話せないペットは、体の不調や痛みを隠すといわれています。 近くで見ている飼い主さんが体調不良に気づくことが大切ですが、「大丈夫だろう」「食欲はあるし、様子を見よう」と判断することも度々あるはずです。 その後にもし、ペットの体調が急変したり手遅れになってしまった場合、飼い主様の後悔は深くなるでしょう。 「あの時病院へ行っていたら」「自分のせいだ」と自分を責め、ペットのために出来ることがあったはずと考えるといつまでも死を受け入れられなくなってしまいます。 この後悔がペットロスへのきっかけとなる場合があります。ペットの寿命を意識していない
 ペットの平均寿命は栄養価の高いフードやワクチン接種などの普及によって飛躍的に伸びており、例えば犬の場合は10~15才といわれています。
20年以上共に生活する猫も多くいますので一概には言えませんが、ペットの毎日の様子で体の衰えや出来なくなってしまった事をしっかり把握し寿命を考えることが大切です。
このままずっと一緒に生活できると錯覚してしまうと、その瞬間が訪れた時に別れの準備が出来ていなかった飼い主様のショックは想像を絶するものがあります。
「最後の時なんか考えたくない」と思う飼い主様もいらっしゃるでしょう。
楽しい毎日をずっと大切なペットと共に過ごしたいのは誰でも願う気持ちです。
しかし、人より早く年を取るペットの老いを理解するのも飼い主様の大切な役目となります。
ペットの平均寿命は栄養価の高いフードやワクチン接種などの普及によって飛躍的に伸びており、例えば犬の場合は10~15才といわれています。
20年以上共に生活する猫も多くいますので一概には言えませんが、ペットの毎日の様子で体の衰えや出来なくなってしまった事をしっかり把握し寿命を考えることが大切です。
このままずっと一緒に生活できると錯覚してしまうと、その瞬間が訪れた時に別れの準備が出来ていなかった飼い主様のショックは想像を絶するものがあります。
「最後の時なんか考えたくない」と思う飼い主様もいらっしゃるでしょう。
楽しい毎日をずっと大切なペットと共に過ごしたいのは誰でも願う気持ちです。
しかし、人より早く年を取るペットの老いを理解するのも飼い主様の大切な役目となります。
ペットを子どもとして可愛がっていた
ペットロスになる人の特徴として、ペットを人として考えて接していたことが挙げられます。 大切に愛情深く接してきたペットは、家族同然の存在でしょう。 しかし、例えばお子様がいないご家庭や独立してご夫婦のみの生活をされていると、小さくて一匹では生きていけない存在をまるで我が子として可愛がる傾向があります。 ご飯やお水・トイレの掃除やお散歩など、飼い主様のお世話が欠かせないペットを「自分の子ども」として捉えてしまうと、 お別れの時には「子ども同然のペットが亡くなった」のではなく、「子どもが亡くなった」感覚に陥ってしまい、より悲しみが深く強く現れます。ペットロスの症状
 大切なペットを失うことによって起こるペットロスは、学校や会社に行けなくなったり気力や体力を失うなどといった生活に支障が出てくる症状が現れます。
誰にでも起こり得るペットロスによる体や心の症状についてご説明していきます。
大切なペットを失うことによって起こるペットロスは、学校や会社に行けなくなったり気力や体力を失うなどといった生活に支障が出てくる症状が現れます。
誰にでも起こり得るペットロスによる体や心の症状についてご説明していきます。
常にだるいと感じる
ペットを失った悲しみからくる心身の脱力感やストレス、虚無感によって体が重くだるさを感じることがあります。 体自体の疲れではなく心の問題が体を支配して感じる症状なので、悲しみを理解し前へ進みはじめれば少しずつ回復へと向かうでしょう。 ですが無理に立ち直る必要はありません。 体も心も辛い症状ではありますが、ゆっくりと変化を受け止めて体を休めるようにしてください。何に対してもやる気が出ない
 今まで一緒に生活し楽しいことを共有していたペットが、自分とは違う世界へ旅立ってしまったことによる無力感や喪失感を引き起こし、どんなことにも気持ちが動かずやる気が出ない症状です。
変わらずにいつも側にいてくれた存在がいなくなることで、頑張る目的や楽しむ意味が無くなってしまうことが要因です。
集中力の低下も見受けられます。
人によっては「あのコがいない世界でなぜ自分は生きているのか」「こんな世界にいるのは無意味」と感じ、死にたいと思う場合もあるようです。
今まで一緒に生活し楽しいことを共有していたペットが、自分とは違う世界へ旅立ってしまったことによる無力感や喪失感を引き起こし、どんなことにも気持ちが動かずやる気が出ない症状です。
変わらずにいつも側にいてくれた存在がいなくなることで、頑張る目的や楽しむ意味が無くなってしまうことが要因です。
集中力の低下も見受けられます。
人によっては「あのコがいない世界でなぜ自分は生きているのか」「こんな世界にいるのは無意味」と感じ、死にたいと思う場合もあるようです。
物事への興味や関心が無くなる
興味や関心とは、心に余裕がないと生まれない気持ちのひとつではないでしょうか。 ペットの死を深く悲しんでいる状態の気持ちに他のことを考える余裕はありません。 また、日頃からペットと一緒に趣味を楽しんでいたり行動を共にしたりしていると、ペットを思い浮かべてしまう趣味を行う余裕がなくなり行動ができなくなったりしてしまいます。突然涙が溢れてしまう
ふとした瞬間に涙が出て止まらない症状は、外を歩いている時や仕事中などどんなタイミングでも起こります。 愛情深く接していたペットが突然いなくなってしまった時、関連する何かを見たり感じたりすることで悲しみが涙となって現れます。 一緒に暮らした部屋の中や毎日散歩した道・お見送りしてくれた玄関や窓辺といった至るところに思い出がたくさん残っていますよね。 ペットへの愛情と一緒に悲しみが溢れて涙が止まらなくなる症状は、ペットを失った人の半数以上が経験しているといわれています。 我慢せずに、一人になれる場所で思いっきり泣きましょう。 人によっては「このくらいで泣いていられない」と頑張ってしまい、ペットロスを長引かせてしまうこともあります。ペットロスが重症化してしまう原因とは?
 ペットロスは精神に影響する症状が現れた状態ですので、家族同様のペットを亡くす辛い状態から抜け出すことが出来ないでいると、不眠や不安の症状が強くなり重症化する場合もあります。
重症化する場合、ペットとのお別れがどのようなものだったかも影響します。
ではどのような原因が考えられるのでしょうか。
ペットロスは精神に影響する症状が現れた状態ですので、家族同様のペットを亡くす辛い状態から抜け出すことが出来ないでいると、不眠や不安の症状が強くなり重症化する場合もあります。
重症化する場合、ペットとのお別れがどのようなものだったかも影響します。
ではどのような原因が考えられるのでしょうか。
重症化の原因①:亡くなったタイミングや亡くなり方
ペットに向けられていた愛情や思い出が心に溜まり、後悔や罪悪感の他にも自分を含めて他者への怒りや恨みなど複雑な感情が湧いていきます。 突然の思いもかけない別れには、看取ってあげられなかった場合や治療や病気の発見への遅れなど様々な要因がありますが、「あんなに元気だったのに」という思いが特に強くあります。 ペットの死を受け入れられずに絶望してしまう不安定な状態が続くことによって、症状が重症化する場合があります。重症化の原因②:ペットの死に対する考え方
 「もっと自分がちゃんとしていれば」と、ペットとの接し方について苦しみや怒りといったマイナスの感情に支配されてしまう場合もあります。
ペットの死を自分のせいだと考える飼い主様の多くは、深く広い愛情を惜しみなく注ぎペット中心の生活を送っていたという傾向があります。
人の数倍も早いスピードで年を取っていくペットはもちろん命あるものは、いつか必ずお別れの時を迎えます。
家族同然の存在として楽しい時も悲しい時も気持ちを共有してきたペットとのお別れを経験することによって、悲しみと喪失感の中で症状が強く現れてしまうのです。
「もっと自分がちゃんとしていれば」と、ペットとの接し方について苦しみや怒りといったマイナスの感情に支配されてしまう場合もあります。
ペットの死を自分のせいだと考える飼い主様の多くは、深く広い愛情を惜しみなく注ぎペット中心の生活を送っていたという傾向があります。
人の数倍も早いスピードで年を取っていくペットはもちろん命あるものは、いつか必ずお別れの時を迎えます。
家族同然の存在として楽しい時も悲しい時も気持ちを共有してきたペットとのお別れを経験することによって、悲しみと喪失感の中で症状が強く現れてしまうのです。
重症化の原因③:周囲と価値観を共有できない
人とペットは違いますが、長い間一緒に暮らしてきたペットはかけがえのない存在であり、大切な家族でもあります。 そんなペットとお別れした時は悲しく辛い気持ちで一杯となり、周囲の人もそんな状態に気づくでしょう。 ペットと暮らした経験のない人は、どれほどの存在であったか想像することも難しいはずです。 中には心無い発言で、より悲しみを深くさせたり亡くなったペットに対して後悔を強めるような気持ちになってしまうこともあるかもしれません。 お仕事をしているとどんなに辛くても休めない場合もあるでしょう。 しっかり泣いて悲しむことが大切な時期に我慢することも原因となります。 周囲の人が出来ることとして、大切な家族であるペットのことを一番理解し悲しんでいる飼い主様の気持ちに寄り添い、共感してあげる気持ちで接することです。まとめ
 いつも一緒にいてくれた大切な家族であるペットとの別れは、深い悲しみと辛さや後悔が入り混じり心と体にペットロスという形で現れます。
症状の重さは人それぞれですが、悲しいときは涙を流して悲しんで決して無理をしたり我慢したりすることがないようにしましょう。
また、お近くにペットを亡くされて元気がない人がいたら言葉を掛けるよりまずお話しを聞いてあげてください。
いつも一緒にいてくれた大切な家族であるペットとの別れは、深い悲しみと辛さや後悔が入り混じり心と体にペットロスという形で現れます。
症状の重さは人それぞれですが、悲しいときは涙を流して悲しんで決して無理をしたり我慢したりすることがないようにしましょう。
また、お近くにペットを亡くされて元気がない人がいたら言葉を掛けるよりまずお話しを聞いてあげてください。 猫用おもちゃのおすすめ選び方
 猫を飼うのであれば猫用のおもちゃを用意してあげましょう。
おもちゃがあれば猫が勝手に遊んでくれることもあるので運動不足解消やストレス解消の効果が期待できます。
次に、猫用のおもちゃの選び方を紹介するので参考にしてください。
猫を飼うのであれば猫用のおもちゃを用意してあげましょう。
おもちゃがあれば猫が勝手に遊んでくれることもあるので運動不足解消やストレス解消の効果が期待できます。
次に、猫用のおもちゃの選び方を紹介するので参考にしてください。
猫の年齢に適した物を選ぶ
猫のおもちゃを購入するのであれば猫の年齢にあったおもちゃを選ぶようにしましょう。 子猫・成猫・老描それぞれにあっているおもちゃを与えることで遊んでくれる可能性が高まります。 子猫はどのようなおもちゃを好んで遊んでくれるのか判断がつかない場合も多いのでさまざまなおもちゃを与えるようにしましょう。 しかし、小さいおもちゃでは飲み込んでしまう危険があるので注意が必要です。 成猫にもなればおもちゃの好みも決まってくるのでどのようなおもちゃでよく遊んでいるかを確認しましょう。 老描になると遊ぶ頻度が少なくなりますが、最低限の運動をさせる必要もあるのでなにかしらのおもちゃで遊ばせてあげることも大切です。安全性を重視して選ぶ
 上記でも紹介しましたが、誤飲しないようなおもちゃを購入するようにしましょう。
おもちゃ自体のサイズが小さいと飲み込んでしまうリスクが高く、おもちゃが大きければ飲み込むリスクも低いです。
ただし、大きいおもちゃでもいくつかのパーツで出来合っているようなおもちゃでは小さなパーツが遊んでいる最中に外れてしまい、飲み込んでしまうことも考えられます。
なので分解されるようなおもちゃを選ばないようにして、壊れないようなおもちゃであるかも確認しましょう。
上記でも紹介しましたが、誤飲しないようなおもちゃを購入するようにしましょう。
おもちゃ自体のサイズが小さいと飲み込んでしまうリスクが高く、おもちゃが大きければ飲み込むリスクも低いです。
ただし、大きいおもちゃでもいくつかのパーツで出来合っているようなおもちゃでは小さなパーツが遊んでいる最中に外れてしまい、飲み込んでしまうことも考えられます。
なので分解されるようなおもちゃを選ばないようにして、壊れないようなおもちゃであるかも確認しましょう。
目的・用途別で選ぶ
猫用のおもちゃはいくつかの種類に分けることができ、バラエティも豊富です。 おもちゃにはさまざまな目的の元作られているものもあるので用途にあったおもちゃを選ぶようにしましょう。 単純に遊ばせることが目的であれば猫じゃらしなどが一般的です。 運動不足を解消させたいのであればボールなどより体を動かすことができるおもちゃがおすすめとなります。 なかには頭を使わせることができるおもちゃもあり、中におやつを入れて動かさないとおやつを食べることができない変わったおもちゃもあります。▼ひとり遊びをさせたい:ネズミのおもちゃ・ボール▼
 ひとり遊びをさせたいのであればネズミのおもちゃやボールがおすすめです。
この二つのおもちゃであれば転がして遊ぶことができるので一匹だけ猫を飼育している人におすすめです。
ボールは動きのあるおもちゃであるため、好奇心のある子猫であれば高い確率で遊んでくれます。
ネズミのおもちゃは野生の獲物獲得本能をくすぐるおもちゃであり、食べることができないとわかっていても追って遊んでくれます。
ポピュラーなおもちゃでもあるのでペットショップであれば高い確率で販売されています。
ひとり遊びをさせたいのであればネズミのおもちゃやボールがおすすめです。
この二つのおもちゃであれば転がして遊ぶことができるので一匹だけ猫を飼育している人におすすめです。
ボールは動きのあるおもちゃであるため、好奇心のある子猫であれば高い確率で遊んでくれます。
ネズミのおもちゃは野生の獲物獲得本能をくすぐるおもちゃであり、食べることができないとわかっていても追って遊んでくれます。
ポピュラーなおもちゃでもあるのでペットショップであれば高い確率で販売されています。
▼運動不足を解消させたい:釣竿型おもちゃ・猫じゃらし▼
 室内で飼っているとどうしても運動不足になりやすく、肥満体質にもなってしまいます。
そのようなことにならないためにも運動不足を解消するおもちゃも多く販売されており、釣り竿タイプや猫じゃらしが有名です。
猫じゃらしは猫の前に出すだけでもじゃれあうようにして遊んでくれ、飼い主は猫とのコミュニケーションをとることもできます。
釣り竿タイプは猫じゃらしの進化系ともいえるおもちゃであり、釣り竿の先端に猫の興味をそそるものを吊り下げ、猫に食いつかせたり、ジャンプさせることが可能になります。
室内で飼っているとどうしても運動不足になりやすく、肥満体質にもなってしまいます。
そのようなことにならないためにも運動不足を解消するおもちゃも多く販売されており、釣り竿タイプや猫じゃらしが有名です。
猫じゃらしは猫の前に出すだけでもじゃれあうようにして遊んでくれ、飼い主は猫とのコミュニケーションをとることもできます。
釣り竿タイプは猫じゃらしの進化系ともいえるおもちゃであり、釣り竿の先端に猫の興味をそそるものを吊り下げ、猫に食いつかせたり、ジャンプさせることが可能になります。
▼場所を選ばないで遊ばせたい:光るおもちゃ▼
場所を選ばないおもちゃであればどのような場所でも遊ばせることができます。 光るおもちゃは光を反射できるようになっているので暗い環境でも遊ばせることができます。 飼い主が仕事などで出かけている時にはどうしても室内が暗くなってしまいやすく、帰りが遅くなればなおさら暗くなります。 しかし、光るおもちゃであれば薄暗い環境でも遊ぶことができ、猫にストレスを与えません。 中には光がなくても動かすだけで光るようなおもちゃもあります。▼ストレスを発散させたい:けりぐるみ・ぬいぐるみ▼
 猫も人と同じようにさまざまなことに対してストレスをためてしまいます。
しかし、ストレスはおもちゃでも解消することができ、ぬいぐるみやけりぐるみがおすすめです。
ぬいぐるみはじゃれあったり、甘噛みする際におすすめのおもちゃで猫用のおもちゃのぬいぐるみでも必要になくなった一般的なぬいぐるみでも代用できます。
けりぐるみとは猫が後ろ足で蹴るためのぬいぐるみであり、ストレスからの八つ当たりを受け止めてくれます。
猫も人と同じようにさまざまなことに対してストレスをためてしまいます。
しかし、ストレスはおもちゃでも解消することができ、ぬいぐるみやけりぐるみがおすすめです。
ぬいぐるみはじゃれあったり、甘噛みする際におすすめのおもちゃで猫用のおもちゃのぬいぐるみでも必要になくなった一般的なぬいぐるみでも代用できます。
けりぐるみとは猫が後ろ足で蹴るためのぬいぐるみであり、ストレスからの八つ当たりを受け止めてくれます。
▼自動で動くおもちゃも便利:シッタータイプ▼
猫用のおもちゃには自動で動くものもあり、シッタータイプとも呼ばれています。 電源を入れれば自動で動いたり、光るなどの動作を行うので猫の遊び相手になってくれます。 自動で動きを見せることができるのでさまざまなおもちゃに興味がない猫でも興味を抱きやすいです。 購入していれば一人遊びをさせることができるのでおすすめですが、販売価格が高くなりやすいデメリットと電池交換が必要な欠点もあります。 飼い主がいないときにでも遊ばせてあげたい人におすすめです。猫用おもちゃで楽しく遊ぶ方法
 猫用のおもちゃは一人遊びできるものもありますが、飼い主も一緒に遊びに付き合うことができる場合も多いです。
そのため、おもちゃごとに遊び方を知っておけば猫がより快適に遊ぶことができます。
次に猫用のおもちゃで楽しく遊ぶ方法を紹介します。
猫用のおもちゃは一人遊びできるものもありますが、飼い主も一緒に遊びに付き合うことができる場合も多いです。
そのため、おもちゃごとに遊び方を知っておけば猫がより快適に遊ぶことができます。
次に猫用のおもちゃで楽しく遊ぶ方法を紹介します。
レーザーポインターの遊び方
レーザーポインターは飼い主が機器を持ち、向けられた場所に光を照射することができるおもちゃで最近人気も高まっています。 遊び方はいたって簡単であり、レーザーポインターで壁に光を照射するとそこに向かって猫が飛びついてきます。 光の場所を変えれば猫は追うように行動するので、猫だけではなく飼い主も一緒に遊ぶことができます。 しかし、猫に向けて照射しないように気を付ける必要があることと壁に引っかき傷ができてしまうリスクがあります。トンネルの遊び方
 猫じゃらしなどでトンネルの中に導いてあげましょう。
また、ボールやいつも遊んでいるおもちゃを入れるとトンネルに入ってくれるようになります。
もともと猫は狭い空間を好む傾向があるので勝手にトンネルに入ることも珍しくありません。
しかし、多頭飼いをしているのであればトンネル内で喧嘩をしてしまう可能性も高まってしまうので注意しましょう。
猫はテリトリーを重視する動物であるため、トンネルを縄張りにしていると他の猫が入ってきた際に喧嘩してしまいます。
猫じゃらしなどでトンネルの中に導いてあげましょう。
また、ボールやいつも遊んでいるおもちゃを入れるとトンネルに入ってくれるようになります。
もともと猫は狭い空間を好む傾向があるので勝手にトンネルに入ることも珍しくありません。
しかし、多頭飼いをしているのであればトンネル内で喧嘩をしてしまう可能性も高まってしまうので注意しましょう。
猫はテリトリーを重視する動物であるため、トンネルを縄張りにしていると他の猫が入ってきた際に喧嘩してしまいます。
ボールの遊び方
 猫も犬同様にボールで遊ばせることができます。
ボールを置いておくだけでも一人遊びしてくれる可能性もありますが、犬と比べて自発的に遊んでくれないことも多いです。
そのため、少し遠くに投げてボールに意識を向けてあげるようにしましょう。
また、ボールにアルミホイルを巻いてボールが音を出すようにして注目させることも一つの方法です。
しかし、ボールを噛む癖がある猫ではアルミホイルを飲み込んでしまうリスクがあるので注意しましょう。
猫も犬同様にボールで遊ばせることができます。
ボールを置いておくだけでも一人遊びしてくれる可能性もありますが、犬と比べて自発的に遊んでくれないことも多いです。
そのため、少し遠くに投げてボールに意識を向けてあげるようにしましょう。
また、ボールにアルミホイルを巻いてボールが音を出すようにして注目させることも一つの方法です。
しかし、ボールを噛む癖がある猫ではアルミホイルを飲み込んでしまうリスクがあるので注意しましょう。
猫じゃらしの遊び方
猫じゃらしは猫用のおもちゃの代名詞であり、多くの猫が興味を抱き遊びます。 しかし、一人遊びすることができないので飼い主が猫じゃらしを操作して一緒に遊ぶようにしましょう。 適当に動かすだけでも遊んでくれますが、床やカーペットの下でモゾモゾ動かすと高い確率で興味を抱き、そばに寄って来てくれます。 遊ぶときはもちろんですが、不機嫌な時や猫同士が喧嘩している際に使用すれば猫じゃらしに意識を持っていくことができ、落ち着かせることも可能です。猫用おもちゃの注意点
 おもちゃで遊ばせることは運動不足やストレス解消の効果が期待できますが、注意しなければならないポイントもいくつかあります。
場合によっては危険な目にあわせてしまう可能性もあるので注意点をしっかり理解しておもちゃを与えるようにしましょう。
おもちゃで遊ばせることは運動不足やストレス解消の効果が期待できますが、注意しなければならないポイントもいくつかあります。
場合によっては危険な目にあわせてしまう可能性もあるので注意点をしっかり理解しておもちゃを与えるようにしましょう。
遊ぶタイミングは飼い主が決める
猫とおもちゃで遊ぶ場合は飼い主が遊ぶタイミングを決めるようにしましょう。 個体によって違いますが、遊ぶことを催促して鳴いてくる猫もいます。 甘えてこられるとついつい遊んであげるようにしてしまいがちですが、そのような要望に応えることはおすすめしません。 鳴けば遊んでくれるという考えが染みついてしまうと頻繁に遊んでくれるように鳴いてきたり、遊んでくれるまで鳴きやまないようになってしまいます。 そのような状況にならないためにも遊ぶ時間帯や遊びを終わらせる時間帯を決めておくようにしましょう。おもちゃの誤飲に注意する
おもちゃによっては誤飲してしまう可能性があるので注意する必要があります。 猫用のおもちゃはさまざまな種類でいろいろなサイズで販売されています。 特に、小さいサイズのおもちゃほど誤飲してしまうリスクがあり、噛み癖がある猫にも気をつけましょう。 特に、紐がついているおもちゃは猫が大好きなおもちゃの種類でもあり、誤飲するケースも多いです。 紐を誤飲してしまうと腸に引っかかってしまい、最悪手術や内視鏡で取らなければならないので大事になってしまいます。遊ぶなら食前にする
上記では飼い主が遊ぶタイミングを決めることが重要と紹介しましたが、理想は食前に遊ぶようにしましょう。 空腹時であれば野生からの名残でもある狩猟本能が高まり、何かを捕まえなければという考えからアクティブな行動をしてくれます。 しかし、食欲を満たすために体を動かしているのであるため、遊ぶ時間を長くしすぎないようにして、遊んだ後にはしっかり食事を与えるようにしましょう。 逆に食後に遊ぶことは食べた物を戻してしまう原因になるので控えることをおすすめします。まとめ
 猫を遊ばせるためにはおもちゃを活用することをおすすめします。
運動不足やストレス発散の効果を期待することができる一方で、誤飲などのリスクもあるため、注意も必要です。
猫ごとに好みのおもちゃも異なるのでよく遊んでいるおもちゃを知り、購入するようにしましょう。
猫を遊ばせるためにはおもちゃを活用することをおすすめします。
運動不足やストレス発散の効果を期待することができる一方で、誤飲などのリスクもあるため、注意も必要です。
猫ごとに好みのおもちゃも異なるのでよく遊んでいるおもちゃを知り、購入するようにしましょう。 キャットタワーの選び方
 キャットタワーは名前の通り猫が遊ぶためのグッズであり、タワーのように登ることができるようになっています。
キャットタワーの選び方はまずは種類を確認するようにしましょう。
一般的に突っ張り棒タイプと据え置き型に分けることができます。
また、耐久性に優れていることや手入れのしやすさも確認して購入するようにしましょう。
そのほかにも猫の大きさや数に応じて適したキャットタワーを選ぶ必要もあり、多くの猫がいるにも関わらず、
小さいキャットタワー一つだけではすべての猫がキャットタワーを使用することができず、正しく購入できているとは言えません。
キャットタワーは名前の通り猫が遊ぶためのグッズであり、タワーのように登ることができるようになっています。
キャットタワーの選び方はまずは種類を確認するようにしましょう。
一般的に突っ張り棒タイプと据え置き型に分けることができます。
また、耐久性に優れていることや手入れのしやすさも確認して購入するようにしましょう。
そのほかにも猫の大きさや数に応じて適したキャットタワーを選ぶ必要もあり、多くの猫がいるにも関わらず、
小さいキャットタワー一つだけではすべての猫がキャットタワーを使用することができず、正しく購入できているとは言えません。
キャットタワー人気おすすめ商品:据え置きタイプ
 据え置きタイプはキャットタワーの中でも高さが低いのでさまざまな室内でも設置することができ、置くだけです。
そのため、活用できる場所が多く購入しやすいメリットもあります。
次に、据え置きタイプのキャットタワーを紹介します。
据え置きタイプはキャットタワーの中でも高さが低いのでさまざまな室内でも設置することができ、置くだけです。
そのため、活用できる場所が多く購入しやすいメリットもあります。
次に、据え置きタイプのキャットタワーを紹介します。
PAWZ Road キャットタワー
リンク
台が4つ用意されているキャットタワーであり、高さは低いですが、さまざまな場所でくつろぐことができます。
そのため、多頭飼いしている場合にもおすすめでき、猫が複数いてもそれぞれがお気に入りの場所でリラックスすることが可能です。
また、隠れ家的なボックスもあるので猫それぞれが好みの場所に行くことができます。
木目調に仕上げられていることで温かみを感じることができるだけではなく、手入れがしやすいメリットもあります。
Cific キャットタワー 隠れ家
リンク
見た目がキリンのようなデザインに仕上げられていることもあり、可愛らしいキャットタワーを購入したいと考えている人におすすめです。
キャットタワーのデザインが可愛らしいので猫がいるだけで愛おしい気持ちが芽生えやすいです。
キリンの胴体はトンネルのように空洞になっており、遊ぶことができたり、中でゆっくり休むこともできます。
全体がマイクロファイバーで作られているので、猫に優しく柔らかいです。
デザインに優れているおかげでインテリアの一部としても見ることができ、室内の雰囲気を阻害してしまうこともありません。
RAKU 猫用爪とぎ キャットハウス
リンク
ダンボールで仕上げられているキャットハウスであり、家のような構造になっています。
中に入ることができるだけではなく、上に乗ってくつろぐこともできます。
40㎏まで耐えることができるので複数の猫が同時に上に乗っても壊れてしまうことがありません。
ダンボールは猫が好きな素材であり、自然と寄ってくることも多いです。
そのため、キャットタワーを購入したもののあまり遊んでくれない猫におすすめです。
また、爪とぎとしての役割も果たしてくれ、通気性にも優れているので蒸れてしまったり、嫌なにおいが充満してしまうこともありません。
アイリスプラザ キャットタワー おうち付き
リンク
基本的に据え置き型のキャットタワーは高さが低いことが多いですが、高さがあるキャットタワーであるため、猫の本能をくすぐる仕上がりとなっています。
複数の台がポールの中間に設けられているだけではなく、ハウスも取り付けられています。
そのため、周囲の目を気にすることなく休むこともできます。
また、さらに上にはU字のベットが用意されており、猫に体にフィットしやすいのでお気に入りの場所にもなり得ます。
ポールは爪とぎとしての役割もあります。
ウミ 木製キャットタワー
リンク
休憩スポットが多く用意され、隠れる場所も多いです。
そのため、多頭飼いしている場合にもおすすめでき、すべての猫がそれぞれのお気に入りの場所を見つけることもできます。
素材が木材でもあるため、温かみを感じることができ、室内の雰囲気とも合いやすいです。
ポールはすべて爪とぎとなっているので複数の猫が爪とぎをしたい場合でも問題ありません。
ハンモックも取り付けられているので今まで体感することができないハンモックの心地よさを猫に体験させることもできます。
カリモク家具 キャットタワー
リンク
日本の家具メーカーでもあるカリモクが製造していることもあり、おしゃれで高級感を感じることもできます。
そのため、インテリアとしても見ることができるので室内の雰囲気を悪くしてしまうことはなく、よりおしゃれ感を演出することが可能です。
デザイン性に優れているだけではなく機能性にも優れ、猫が飛びやすいような設計にされていることや、
ベース部分と最上部には汚れが付きにくい素材が使用され、清潔感を保つこともできます。
GLAF キャットタワー
リンク
猫の肉球のデザインに仕上げられているクッションが採用されているので見た目が可愛らしいキャットタワーを使用したいと考えている人におすすめです。
台座がクッション素材であるため、柔らかく心地よさは抜群です。
そのほかにはハウスのように入り込むことができたり、遊び道具もついているのでさまざまな遊び方ができます。
安定感にも優れているのでやんちゃな猫が使用しても倒れる心配もありません。
XUDREZ キャットタワー
リンク
おもちゃを連想させるような可愛らしいポップの魅力があり、台座は花のデザインとなっています。
そのため、可愛らしいデザインのキャットタワーを使用したい人におすすめです。
表面には柔らかい素材でもあるカシミアが採用されているので子猫でも安心して遊ぶことができます。
すべての角は丸みが帯びているように加工されているので猫はもちろんですが、飼い主も怪我をしてしまうことがなく、安全性にも優れています。
台座が安定しているのでジャンプした際にしっかり力を支えることができ、飛び損ねることもありません。
コーナン オリジナル ふわふわ キャットツリー
リンク
シンプルなデザインでカラーもホワイト一色となっているので清潔感を感じることができ、さまざまな室内の雰囲気にもマッチしやすいです。
素材にはウレタンが使用され、柔らかい素材でもあるので猫の体に負担をかけてしまうことがありません。
また、高さもあるのでストレスを感じることなく思う存分遊ぶことも可能です。
組み立て式ですが、単純な作りでもあるので誰でも簡単に作り上げることができます。
綿ロープが支柱に採用されていることで耐久性にも優れ、見栄えが悪くなってしまうことも防ぎます。
アイリスオーヤマ キャットタワー ハンモック付き
リンク
たくさんのおもちゃが取り付けられているキャットタワーです。
猫はもともと獲物を捕獲する動物であるため、さまざまなおもちゃがあるので狩猟本能を満たすこともできます。
ハンモックも採用されているので揺らぎを楽しみつつゆっくり休むことも可能です。
ハンモックは安定性に優れているので子猫でも怖がることなく利用することができます。
ネズミのおもちゃは取り外すこともできるので猫が遊んでくれないのであれば外しても問題ありません。
Mwpo 富士山ようなハウス キャットタワー
リンク
富士山に似たハウスが中央に取り付けられているキャットタワーです。
富士山がデザインされていることは珍しく、印象的な部分でもあります。
富士山のハウスの中に入ることができ、猫が好みやすい狭さとなっています。
10箇所に爪研ぎスポットが用意されているので爪研ぎを猫が好きな時に行うことができます。
カラーはダークグレーとベージュの2種類から選ぶことができ、好みのカラーや室内にあるカラーを選ぶようにしましょう。
キャットタワー人気おすすめ商品:突っ張りタイプ
 突っ張りタイプは床と天井に突っ張り固定するキャットタワーです。
必然的に高さがある特徴があり、より上に移動したがる猫におすすめのタイプです。
購入する前に床から天井の長さを測定することをおすすめします。
一般的な家の天井よりも高い作りになっていると使用できない場合があります。
突っ張りタイプは床と天井に突っ張り固定するキャットタワーです。
必然的に高さがある特徴があり、より上に移動したがる猫におすすめのタイプです。
購入する前に床から天井の長さを測定することをおすすめします。
一般的な家の天井よりも高い作りになっていると使用できない場合があります。
アイリスプラザ キャットタワー 突っ張り式
リンク
一つ一つの台座の高さが低くなっているので子猫や老猫のようなうまく飛び上がることができない場合や体力がない場合でも登れます。
天井に触れる支柱は2本なのでより安定感が強いです。
スリム且つコンパクトな仕上がりでもあるので室内を圧迫してしまう要因にもなりません。
中心よりもやや高い場所にハウスが取り付けられ、ゆっくり休むこともできます。
部屋の角に設置することを前提として作られているので部屋の角が空いている場合は購入してみてはいかがでしょうか。
ワンモード キャットタワー 突っ張り型
リンク
高さが255㎝もあるので高さを求めている猫におすすめであり、家具などの上を移動している猫にもおすすめです。
天井に触れる部分は丸型になっており、広さも広いので安定感にも優れています。
そのため、やんちゃな猫が激しくキャットタワーに飛びついてもグラついてしまうこともありません。
転倒防止ベルトも2個セットになっているので活用すればより安定性が増し、転倒のリスクも下がります。
極太ネジで突っ張ることができることも安定性に優れている要因の一つです。
RAKU 木登りタワー シングル キャットタワー
リンク
木登りができるキャットタワーであり、猫の遊び場にもなります。
木登りの感覚を養うこともできるのでよりのびのびと室内で過ごすことができます。
台座と台座の感覚が広く取られているので子猫ではうまく上まで登ることができませんが、大人の猫であればポールにしがみつきながら登ることができ、より木登り感覚を味わえます。
室内飼いをしているとどうしても運動不足になりやすいですが、このキャットタワーがあれば室内でもしっかりと運動することができます。
タンスのゲン キャットタワー
リンク
5段階あるキャットタワーなので遊んだり休んだりすることができます。
一般的に突っ張りタイプのキャットタワーは縦長でスリムなデザインに仕上げられている場合が多いですが、横にも広がっているデザインなので多くの猫が一緒に利用することもできます。
5個の台座のほかに3つずつハウスとハンモックも用意されているので多頭飼いをしている場合におすすめのキャットタワーです。
キャットタワーでは珍しいグルーミングができるブラシのアーチも取り付けられているので体の汚れを落とすこともできます。
キャットタワー人気おすすめ商品:大型猫・多頭飼い向け
 キャットタワーはシンプルなデザインの物もあれば複雑な構造に仕上げられている場合もあります。
多頭飼いしている場合や大型の猫を飼育しているのであれば、大きいサイズや複雑な構造になっているほうがおすすめです。
次に、多頭飼いや大型の猫を飼っている人向けのキャットタワーを紹介します。
キャットタワーはシンプルなデザインの物もあれば複雑な構造に仕上げられている場合もあります。
多頭飼いしている場合や大型の猫を飼育しているのであれば、大きいサイズや複雑な構造になっているほうがおすすめです。
次に、多頭飼いや大型の猫を飼っている人向けのキャットタワーを紹介します。
RAKU 猫タワー 木製キャットタワー 据え置き型
リンク
木材で作られているキャットタワーであり、すべての角がとられている特徴があります。
そのため、猫が怪我をしてしまうリスクが少なく、安心して使用することができます。
一番下の台座は大きくなっているので安定感が強く、複数の猫が遊んでいても揺れてしまったり、倒れてしまうリスクもありません。
ハウスの中にはクッションが敷かれているので木の痛さを感じてしまうこともなく、安心して過ごすこともできます。
半球型のアクリルボウルがあり、下から猫のさまざまな姿を見て楽しむことも可能です。
FEANDREA キャットタワー
リンク
重量感のある太い支柱が採用されていることで安定感が増し、大型の猫が激しく動いてもブレてしまうことがありません。
また、魚のデザインが描かれているお皿が取り付けられており、下に降りなくてもおやつを食べたり、水を飲むこともできます。
台座などはすべて角が取られているだけではなく、柔らかい布が取り付けられていることで心地よさにも優れています。
最上部にはよりクッション性に優れている台座となっており、上からの景色を堪能しながら休むことも可能です。
Mwpo キャットタワー
リンク
爪研ぎの支柱以外はフワフワ素材が使用されているので猫に負担をかけたり、肉球を傷つけてしまう心配もありません。
人が触っても気持ちよさを感じることができるので猫も気持ちよさを求めて積極的にキャットタワーに集まるのではないでしょうか。
そのまま使用しても太い支柱が使用されていることで安定性に優れていますが、ベルトを使用して壁に固定することもできるのでより安定感を得ることができます。
昇り降りしやすいデザインでもあるので子猫でも十分に遊ぶことが可能です。
Petoru キャットタワー
リンク
猫の数が多くても遊べない猫が出ないようなデザインとなっているので多頭飼いをしている場合におすすめです。
キャットタワーで遊ぶことに飽きてしまう猫が出ないことでも人気のあるキャットタワーでもあります。
比較的コンパクトな仕上がりになっているので、多頭飼いしていても大型のキャットタワーを設置する場所を確保しづらい場合にもおすすめです。
組み立てることが苦手な人でも単純な作りになっているので女性一人でも十分組み立てることが可能です。
NEOLEAD キャットタワー スタジアム Sクラスモデル
リンク
高さが194㎝もあり、6段構造になっている大型のキャットタワーです。
大型のキャットタワーで大型の猫はもちろん子猫まで遊ぶことができるのでさまざまなサイズの猫を飼っている場合にもおすすめできます。
高さがあるとそれだけ安定感が失われてしまいやすいですが、一番下の台が分厚く重量もあるので安定感が劣ってしまうことを防いでいます。
人の体重にも耐えられる耐久性が備わっているので多くの猫や重量がある大型の猫が遊んでも壊れたり、倒れることもありません。
まとめ
 猫を室内で飼うのであればキャットタワーを購入することをおすすめします。
キャットタワーは遊ぶ目的だけではなく、猫に安らぎの場所を提供することもできます。
爪研ぎの機能が備わっている場合が多いので家具や壁を傷つけられてしまうリスクも下がります。
猫にあったキャットタワーを購入して室内でも快適に過ごせるように工夫しましょう。
猫を室内で飼うのであればキャットタワーを購入することをおすすめします。
キャットタワーは遊ぶ目的だけではなく、猫に安らぎの場所を提供することもできます。
爪研ぎの機能が備わっている場合が多いので家具や壁を傷つけられてしまうリスクも下がります。
猫にあったキャットタワーを購入して室内でも快適に過ごせるように工夫しましょう。 ハッカ油とは?
 虫除けスプレーとしてよく使われているハッカ油を知っていますか?
ハッカは漢字だと「薄荷」と書き、ハーブの種類であるミントのことです。
ハッカを乾燥させた後に抽出される油をハッカ油と言い、強い爽やかな香りが特徴的です。
ハッカ油はその香りで虫除け効果があり、犬にとっても虫除け対策として使われることが多いです。
虫除け以外のどんな効果があるのか、また使用時の注意点などについてもまとめてみました。
更に虫除けスプレーの作り方や市販のおすすめスプレーについても紹介しています。
虫除けスプレーとしてよく使われているハッカ油を知っていますか?
ハッカは漢字だと「薄荷」と書き、ハーブの種類であるミントのことです。
ハッカを乾燥させた後に抽出される油をハッカ油と言い、強い爽やかな香りが特徴的です。
ハッカ油はその香りで虫除け効果があり、犬にとっても虫除け対策として使われることが多いです。
虫除け以外のどんな効果があるのか、また使用時の注意点などについてもまとめてみました。
更に虫除けスプレーの作り方や市販のおすすめスプレーについても紹介しています。
ハッカ油が犬に与える良い効果
 ハッカ油は天然の植物由来のものなので犬にとって安全性が高いものです。
ハッカ入りの飴などをなめた時に感じるスーッとする感覚やレモン系の香りが気持ちをリフレッシュしてくれます。
犬に与える効果としては次の3つの効果があります。
ハッカ油は天然の植物由来のものなので犬にとって安全性が高いものです。
ハッカ入りの飴などをなめた時に感じるスーッとする感覚やレモン系の香りが気持ちをリフレッシュしてくれます。
犬に与える効果としては次の3つの効果があります。
効果①:消臭効果
ハッカ油で作ったスプレーを家庭の臭いが気になる場所に吹きかけると、ミントの爽やかな香りが漂います。 優れた消臭効果が発揮されるのでおすすめです。 生活の場である台所や靴箱などにも効果的ですが、犬のトイレ付近やクッション・カーペットなど犬の匂いが気になるところに使ってみてください。 ゲージなど洗濯できない場所にもスプレーすると犬独特の匂いが消えていきます。 来客時に気を使う犬の匂いを消すことができます。効果②:殺菌効果
 ハッカの葉に含まれているメントールという成分には抗菌性があり、天然の防腐剤としてタンスなどに入れて用いられています。
またハッカ油はカビ予防もしてくれます。
梅雨の時期、カビが発生しやすいところや犬と過ごす場所にハッカ油のスプレーをシュッとかけておくとカビが増えるのを防いでくれます。
手洗いすることが難しい場所やすぐに洗えない時にもハッカ油のスプレーで殺菌できるのは安心ですね。
人にも犬にも使える点もおすすめです。
ハッカの葉に含まれているメントールという成分には抗菌性があり、天然の防腐剤としてタンスなどに入れて用いられています。
またハッカ油はカビ予防もしてくれます。
梅雨の時期、カビが発生しやすいところや犬と過ごす場所にハッカ油のスプレーをシュッとかけておくとカビが増えるのを防いでくれます。
手洗いすることが難しい場所やすぐに洗えない時にもハッカ油のスプレーで殺菌できるのは安心ですね。
人にも犬にも使える点もおすすめです。
効果③:防虫効果
3つ目が飼い主には特に関心が高い防虫効果です。 犬の防虫対策としてダニ、蚊、ノミ以外にも、ハエやムカデ、ゴキブリにも防虫効果があります。 ダニなどの虫除けにはかなり気を使っている飼い主が多いことでしょう。 お散歩やアウトドアへのお出かけはもちろん、室内でもダニは発生しており、1年を通じて虫除けの必要性を感じている人もいると思います。 屋内のダニに対しては100%の殺ダニ効果があり、植物につくハダニに対しても高い効果が実証されています。 市販のスプレーにもハッカ油は利用されているので、その効果は高いです。ハッカ油を使った犬用防虫スプレーの作り方
 様々な効果が期待できるハッカ油を使った犬用防虫スプレーは手軽に作ることができます。
あまり費用もかからず簡単にできるので、ぜひ試してみてください。
次に材料と作り方を説明していきましょう。
様々な効果が期待できるハッカ油を使った犬用防虫スプレーは手軽に作ることができます。
あまり費用もかからず簡単にできるので、ぜひ試してみてください。
次に材料と作り方を説明していきましょう。
ハッカ油防虫スプレーに必要な材料
犬用防虫スプレーに必要な材料は ・ハッカ油 ・無水エタノール ・精製水 ・スプレーボトル の4つです。 材料はドラッグストアやネットで手に入るものです。 無水エタノールとは水が入っておらず、エタノールが99,5%以上のものです。 精製水は水道水から不純物を取り除いたもののことです。 スプレーボトルは100均でも売っていますが、材質を確認してください。 ポリスチレン製の容器はハッカ油の成分が溶かしてしまいますので使えません。 ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)・ガラス製の容器なら大丈夫です。ハッカ油防虫スプレーの作り方
❶ 無水エタノール10mlを容器に入れる。 ❷ ハッカ油を10~20滴たらしていれ、よく混ぜる。 ❸ さらに精製水90mlを入れて全部をよく混ぜる。 基本的に3つの材料がしっかりと混ざればOKです。 ただハッカ油を精製水と混ぜるには無水エタノールが必要なので、順番を間違えないようにするのがポイントです。 スプレー容器はポリスチレン以外のものであれば問題ないですが、遮光性のものでがあると太陽光の影響を受けにくく、外に持ち歩く際に便利です。 効果も長持ちしやすいでしょう。 量が多すぎる時には適宜減らして作ってください。ハッカ油防虫スプレーを実際に使う方法
 ハッカ油のスプレーができたら、使用する前にはもう一度よく振ってからスプレーしてください。
安全性が高いものですが、犬の顔周りにかけるときは、目や鼻などを避けて使うようにしましょう。
人間が利用するときも手の平にスプレーしてから塗るなどしてください。
犬の匂いが気になる場所やおもちゃの消臭などに使う場合は思い切ってスプレーして大丈夫です。
保存料などが一切含まれていないので、冷蔵庫保管をして1週間程度で使い切るようにしましょう。
ハッカ油のスプレーができたら、使用する前にはもう一度よく振ってからスプレーしてください。
安全性が高いものですが、犬の顔周りにかけるときは、目や鼻などを避けて使うようにしましょう。
人間が利用するときも手の平にスプレーしてから塗るなどしてください。
犬の匂いが気になる場所やおもちゃの消臭などに使う場合は思い切ってスプレーして大丈夫です。
保存料などが一切含まれていないので、冷蔵庫保管をして1週間程度で使い切るようにしましょう。
ハッカ油防虫スプレーを犬に使う際の注意点
 ハッカ油は昔から使われてきたもので、効能がいろいろとあります。
犬にとっても高い効果が期待できますが、使用する際の注意点がいくつかあります。
それを守らないと返って健康を損ねる場合もあるので、くれぐれも安全に使うようにしてください。
ハッカ油は昔から使われてきたもので、効能がいろいろとあります。
犬にとっても高い効果が期待できますが、使用する際の注意点がいくつかあります。
それを守らないと返って健康を損ねる場合もあるので、くれぐれも安全に使うようにしてください。
子犬や妊娠中の犬には使わない
ハッカ油の匂いを嗅いでみると爽やかですがしっかりとした匂いがあります。 子犬や妊娠中、病気の犬は匂いや刺激に対して敏感になっていることがあり、ちょっとした匂いでも大きなストレスとなります。 犬は人間の何十倍も嗅覚に優れているので、ほんの少しの匂いでも感じることができます。 それによるストレスはとても大きく、体に良くないことに繋がるのでできるだけ使用しないでください。きちんと希釈を行う
ハッカ油は濃度がとても高い液体で、人間も原液は有害です。 犬に対して原液そのままで使ってはいけません。 犬がいる場所、犬に対して使う時はしっかりと水で希釈してから使ってください。 ハッカ油の量が1%程度になるまで薄めることが大切です。 濃い濃度の方が効果が高いのでは?と考える人がいますが、ハッカ油はそうではありません。 良かれと思ってしたことが愛犬にとって危険なものになりますので必ず守ってください。原液やスプレーの管理を徹底する
 ハッカ油の原液は危険です。
犬がハッカ油の原液を舐めるのは、毒を摂取していることと同じです。
最悪の場合は死に至るので、よく注意しましょう。
匂いに惹かれてつい舐めてしまうこともありますので、管理を徹底することは大変重要です。
犬だけではなく、小さなお子さんがうっかり口にすることのないように簡単に手が届かない場所を工夫してしまっておきましょう。
ハッカ油の原液は危険です。
犬がハッカ油の原液を舐めるのは、毒を摂取していることと同じです。
最悪の場合は死に至るので、よく注意しましょう。
匂いに惹かれてつい舐めてしまうこともありますので、管理を徹底することは大変重要です。
犬だけではなく、小さなお子さんがうっかり口にすることのないように簡単に手が届かない場所を工夫してしまっておきましょう。
アレルギー反応に注意する
飼い犬がハッカアレルギーだった場合、体調を崩したり、顔が腫れたりする他、皮膚に炎症まで生じてしまいます。 アレルギー反応は程度の軽いものから重いものまで様々ですし、どの程度の濃度でアレルギー反応が起こるかも犬によって異なります。 中毒症状で下痢や嘔吐となる場合もありますので、最初にハッカ油スプレーを使う時にはいきなりたくさん使わないで、少しずつ様子を見て使ってあげてください。 もしアレルギー反応が出た場合は、すぐに使用をやめて病院で診察を受けましょう。ハッカ油犬用防虫スプレーの市販製品
 手軽に作れるハッカ油の防虫スプレーを紹介しましたが、市販でも同様の製品が売られています。
すぐにでも手に入れてみたい人はそれらを利用してみるのもいいですね。
次に数点紹介します。
手軽に作れるハッカ油の防虫スプレーを紹介しましたが、市販でも同様の製品が売られています。
すぐにでも手に入れてみたい人はそれらを利用してみるのもいいですね。
次に数点紹介します。
天然ハッカ油スプレー詰め替えセット(20mlスプレー+詰め替え20ml)
リンク
20mlスプレー&20ml詰め替えのおすすめセットです。
飲み物や食品、マスクにも安心して使えます。
ペパーミント商会のハッカ油は添加物製造業の許可がある食品添加物です。
爽やかなミントの香りとひんやりした感じが人気で、毎日バッグに入れてマスクの除菌用や手の消毒代わりに使っている人も多いです。
スプレータイプを一度利用してみて、使い心地を確かめるのに良いですね。
クマのマークが可愛いです。
天然和種ハッカ油100% 200ml+12mlスプレー1本セット
リンク
ハッカ油12mlスプレーが1本ついたお得な商品です。
こちらも安心の食品添加物ですので子供や犬にも優しい商品です。
アウトドア・キャンプ・ハイキング・釣りの防虫にも使えます。
携帯に便利なスプレー小瓶が付いているので、すぐに使え、小分けするのに便利なスポイトも付いています。
薬局等で売っているものより香り方が少しソフトで使いやすいという口コミがあります。
エアコンのフィルターにスプレーしてリラックスして安眠効果を得るという使い方もできます。
ガレージゼロ ハッカ油 100ml GZAK21
リンク
安全性の高い化粧品グレードで衣服やテント、蚊帳に使うハッカ油です。
部屋の消臭や芳香にも使用でき、ハッカ特有のすっきり爽やかな香りが楽しめます。
コスパの良い商品が欲しい人におすすめ。
大容量なので直射日光を避けて涼しいところに保管してください。
こちらは希釈する必要がありますので、防虫スプレーを作ってみた人が2回目以降に利用される方が良いでしょう。
まとめ
天然由来のハッカ油は防虫・消臭効果が高く、犬用の虫除けスプレーとして安全で最適です。 簡単にスプレーが手作りできるのも便利ですし、家のあちらこちらで消臭や殺菌に利用できる点も嬉しいポイントです。 使用する際には注意点を守って、体に害のないように気をつけてください。トイレハイとは?
 トイレハイという言葉を知っているでしょうか。
トイレハイとは、猫が排便をした後に急にテンションが高まってしまう行動であり、猫を飼っている人であれば思い当たる節があるの場合が多いです。
テンションが高まると急に走り出すなどの行動をするので初めてトイレハイに出くわすと驚いてしまうことも少なくありません。
しかし、病気ではないので問題視する必要性もありませんが、肛門にトラブルがある可能性もあるので一度確認してあげてみましょう。
トイレハイという言葉を知っているでしょうか。
トイレハイとは、猫が排便をした後に急にテンションが高まってしまう行動であり、猫を飼っている人であれば思い当たる節があるの場合が多いです。
テンションが高まると急に走り出すなどの行動をするので初めてトイレハイに出くわすと驚いてしまうことも少なくありません。
しかし、病気ではないので問題視する必要性もありませんが、肛門にトラブルがある可能性もあるので一度確認してあげてみましょう。
猫がトイレハイになる6つの原因
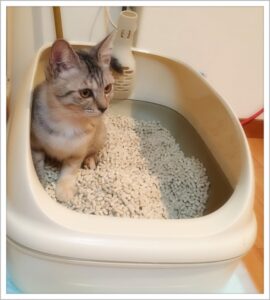 猫が排便した後にトイレハイになることがよくあることですが、いまだにどのようなメカニズムでそのような行動をしているのかは判明していません。
しかし、いくつかの仮説が立てられているので次に紹介します。
トイレハイの行動が謎すぎて気になるのであれば参考にしてください。
猫が排便した後にトイレハイになることがよくあることですが、いまだにどのようなメカニズムでそのような行動をしているのかは判明していません。
しかし、いくつかの仮説が立てられているので次に紹介します。
トイレハイの行動が謎すぎて気になるのであれば参考にしてください。
原因①:マーキング後の安心感で行う
猫は自分の存在をアピールするためにマーキングを行います。 マーキングは猫に限らず、さまざまな動物が行う行動です。 マーキングをする際には排便や排尿をする必要がありますが、最も無防備な状態でもあります。 そのため、マーキングをした後は無防備な状態が解除されているので安心感を得ることができ、そこからテンションが上がってしまうのではないかという仮説となっています。 しかし、さまざまな動物がマーキングをする中で猫だけがトイレハイになるのかは不明です。原因②:自分の匂いを隠したい
トイレハイは野生時代の名残ではないかという考えもあります。 野生の時にはライバル猫の存在や違う動物にも警戒をしなければならず、排便をすることは自分の存在をアピールしてしまうので外敵から狙われてしまうリスクがあります。 そのため、野生の猫は自分の縄張りから離れた場所で排便する習慣があり、排便後は素早く自分の縄張りに戻る必要があるのでダッシュで行動していたと考えられています。 トイレハイになると走り出す行動と一致するのでトイレハイの行動の理由である可能性も高いです。 また、トイレハイの行動には単に走り回るだけではなく、トイレの砂を必要以上にまき散らすこともあります。 この行動も排泄物のにおいを隠して自分の存在を隠すためといわれています。原因③:排便したことを飼い主に報告している
 排便したことを飼い主に報告するためにトイレハイになっている可能性もあります。
排便したことを飼い主に知らせる理由はいくつか考えることができ、
一つはトイレの掃除を促している可能性と無事に排泄することができたことの喜びを飼い主にも知らせたいという気持ちの二つと考えられています。
トイレが清潔にされていないと猫もうまく排泄することができない場合もあり、ストレスを感じてしまいます。
なので頻繁にトイレの砂を交換するようにしましょう。
トイレのしつけを教えたばかりであり、うまくトイレで排泄することができたのであればおやつを与えるなどしてほめてあげれば信頼性をより強く築くことができます。
排便したことを飼い主に報告するためにトイレハイになっている可能性もあります。
排便したことを飼い主に知らせる理由はいくつか考えることができ、
一つはトイレの掃除を促している可能性と無事に排泄することができたことの喜びを飼い主にも知らせたいという気持ちの二つと考えられています。
トイレが清潔にされていないと猫もうまく排泄することができない場合もあり、ストレスを感じてしまいます。
なので頻繁にトイレの砂を交換するようにしましょう。
トイレのしつけを教えたばかりであり、うまくトイレで排泄することができたのであればおやつを与えるなどしてほめてあげれば信頼性をより強く築くことができます。
原因④:トイレする前のトイレハイは抗議の意
トイレハイを起こす原因はトイレ関係で抗議の気持ちを示している可能性もあります。 猫はさまざまいる動物の中でも綺麗好きである生き物であり、テリトリーを重視している特徴もあります。 そのため、トイレの場所が変わると不満を感じてしまい、以前の場所に戻せという意味が込められている場合も考えられます。 また、綺麗好きでもあるのでいつまでも排便や排尿が残されていたり、猫砂やシートが古くなり、においがきついなどが原因でも抗議してくることもあります。原因⑤:リラックスしたから
 排便中は副交感神経が働きリラックスしています。
しかし、排便が終了すると交感神経が働き始めてテンションが高くなり、トイレハイの行動を行うと考えられています。
人にも同じことがいえ、排便中はリラックスをします。
ちなみに交感神経が働いてハイテンションの時には排便する意欲が減少することも多く、気持ちが緩んだ瞬間に便意や尿意を感じてしまうことも交感神経と副交感神経が関係しています。
副交感神経と交感神経の機能は体の機能であるため、トイレハイになってしまうことも問題ないといえます。
排便中は副交感神経が働きリラックスしています。
しかし、排便が終了すると交感神経が働き始めてテンションが高くなり、トイレハイの行動を行うと考えられています。
人にも同じことがいえ、排便中はリラックスをします。
ちなみに交感神経が働いてハイテンションの時には排便する意欲が減少することも多く、気持ちが緩んだ瞬間に便意や尿意を感じてしまうことも交感神経と副交感神経が関係しています。
副交感神経と交感神経の機能は体の機能であるため、トイレハイになってしまうことも問題ないといえます。
原因⑥:トイレハイを起こす病気の可能性も
トイレハイの原因はさまざまですが、ほとんどがそのまま放置していても問題ありません。 しかし、トイレハイになる原因に病気の可能性もあるのでこの場合は早急に病院に連れていく必要があります。 肛門が腫れていたり、排便時に痛がるようであれば病気の可能性が高く、放置してしまうと悪化するので早めに気づいてあげることが飼い主には求められます。 トイレハイの時に肛門の痛みから鳴き声をあげることもあり、見逃してしまうこともありますが、よく観察していればいつものトイレハイとは違うことがわかります。トイレハイの時の行動は?
 トイレハイを実際に見ているのであればどのような行動をするのかも把握している場合も多いですが、猫を飼ったことがない人であればなかなかトイレハイの行動を想像することができません。
初めてトイレハイの行動を見たときに驚かないためにも、どのような行動をするのかを知ることも大切です。
トイレハイを実際に見ているのであればどのような行動をするのかも把握している場合も多いですが、猫を飼ったことがない人であればなかなかトイレハイの行動を想像することができません。
初めてトイレハイの行動を見たときに驚かないためにも、どのような行動をするのかを知ることも大切です。
ひたすら爪を研ぐ
トイレハイになると爪を研ぐ行動をすることがあります。 普段でも爪を手入れするために自発的に爪研ぎをすることがあり、猫の本能による行動でもあります。 そのため、猫を飼うのであれ爪を研ぐグッズを用意してあげることも必要です。 トイレハイの時の爪研ぎは、普段の爪研ぎとは異なりかなり激しいです。 飼い主も驚いてしまうほどの激しさであり、爪がはがれてしまうのではと心配してしまうほどです。 しかし、トイレハイで激しく爪を研ぐことは特別問題視する必要はありません。 ただし、爪研ぎのグッズを用意していないとさまざまな家具を傷つけてしまう可能性もあります。ギャーと鳴き喚く
 トイレハイになると鳴き喚くこともあります。
普通の鳴き声とは全く違い、ボリュームが大きく叫び声に近いです。
トイレハイが原因で鳴き喚いているのであれば問題なく、そのままにしていれば落ち着いてきます。
しかし、排便時に鳴き喚く原因はトイレハイだけではなく、病気の時にも同じように鳴き喚きます。
そのため、排便時に鳴き喚いているのであれば安直にトイレハイが原因と決めつけるのではなく、一度肛門を確認してみたり、下痢をしていないかも確認するようにしましょう。
肛門の腫れや下痢の症状が出ているのであれば病気の可能性が高く、病院に連れて行くようにしましょう。
トイレハイになると鳴き喚くこともあります。
普通の鳴き声とは全く違い、ボリュームが大きく叫び声に近いです。
トイレハイが原因で鳴き喚いているのであれば問題なく、そのままにしていれば落ち着いてきます。
しかし、排便時に鳴き喚く原因はトイレハイだけではなく、病気の時にも同じように鳴き喚きます。
そのため、排便時に鳴き喚いているのであれば安直にトイレハイが原因と決めつけるのではなく、一度肛門を確認してみたり、下痢をしていないかも確認するようにしましょう。
肛門の腫れや下痢の症状が出ているのであれば病気の可能性が高く、病院に連れて行くようにしましょう。
豪快にトイレの砂を散らす
猫のトイレには、専用の砂を敷いて匂い防止や掃除のしやすくなります。 普通に排便や排尿をしても猫砂をかいて排便などを隠そうとします。 この行動は猫の本能であり、外敵から自分のにおいを消して狙われなくするためです。 しかし、トイレハイの時には普段の砂かけよりも激しくまき散らしてしまうほどです。 そのため、トイレの形状にもよりますが、猫砂がトイレから出てしまうことも珍しくありません。 トイレハイが原因で豪快に砂を散らす場合は排便時だけであり、排尿時は普通に砂かけをする特徴があります。部屋中を猛ダッシュ
トイレハイで最もみられる行動が部屋中を猛ダッシュすることです。 猫は子猫であれば遊びたい盛りでもあるため、部屋を走ることは珍しいことではありません。 しかし、猫の種類にもよりますが、大人になればおとなしくなる場合が多く、部屋の中を走ることもほとんどなくなります。 そのため、大人になってトイレハイになると珍しく走り回るので驚いてしまったり、なぜ興奮してしまっているのか謎に感じてしまうことも多いです。 場合によっては部屋を散らかしてしまうこともあるので飼い主を困らせてしまう行動でもあります。トイレハイになるのはウンチの時だけ
上記でも紹介しましたが、トイレハイになるのは排便時だけであり、排尿する際にはトイレハイになることはなく、部屋中をダッシュしたり、鳴き喚くこともありません。 トイレハイのメカニズムがいまだに解明されていない原因でもあり、なぜ排便時だけテンションが上がってしまうのかは謎です。 もし、排尿時にもトイレハイになるのであればいくつかの仮説に絞り込むこともできますが、実際は排便時だけで猫に直接聞いてみないとわからないかもしれません。まとめ
トイレハイになるとさまざまな異常な行動をしてしまいますが、肛門などの病気ではないのであれば本能でもあるので特に問題ではありません。 しかし、猫を初めて飼う人によっては異常すぎる行動でもあるので驚いたり、心配してしまうことも少なくありません。 トイレハイのことを理解して愛猫と過ごしましょう。アボカドは犬に与えない方が良い
 犬に手作り食や果物をあげたり、フードにトッピングをしたりする人は多いと思います。
体に良いものや喜ぶ様子は嬉しいですが、アレルギーなどの悪い影響については知っておく必要があります。
アボカドもその一つです。
アボカドは犬に食べさせてはいけません。
食べるとアレルギーや中毒症状を引き起こす可能性もあります。
この記事では考えられる危険性と食べてしまった場合の対処法を詳しくお伝えします。
ぜひ読んで参考にしてください。
犬に手作り食や果物をあげたり、フードにトッピングをしたりする人は多いと思います。
体に良いものや喜ぶ様子は嬉しいですが、アレルギーなどの悪い影響については知っておく必要があります。
アボカドもその一つです。
アボカドは犬に食べさせてはいけません。
食べるとアレルギーや中毒症状を引き起こす可能性もあります。
この記事では考えられる危険性と食べてしまった場合の対処法を詳しくお伝えします。
ぜひ読んで参考にしてください。
アボカドが犬に与える危険性は?
 アボカドは「森のバター」と言われるほど人間にとっては栄養が豊富な果物です。
しかし、アボカドのペルシンという成分が犬には有害となる可能性を持っています。
体質によってはアレルギー反応を起こし、重い中毒症状で亡くなったケースもあります。
どのような症状が出るのか、確認しておきましょう。
アボカドは「森のバター」と言われるほど人間にとっては栄養が豊富な果物です。
しかし、アボカドのペルシンという成分が犬には有害となる可能性を持っています。
体質によってはアレルギー反応を起こし、重い中毒症状で亡くなったケースもあります。
どのような症状が出るのか、確認しておきましょう。
食物アレルギーが出る
アボカドのアレルギーを持つ犬もおり、皮膚が赤くなったり、痒み、脱毛やフケなどの症状が現れます。 アレルギーを持っている時は、その食べ物は口にしないように注意してください。 家族全員がそれを理解し、うっかり食べさせることのないようにしましょう。 アボカドに限らず食べ物アレルギーは動物病院で検査できるため、気になる症状がある場合は検査を受けて確認しておくと安心です。 またラテックスアレルギーを持っている犬の場合、アボカドを食べるとその反応が誘発され、非常に早く症状が悪化すると言われています。 絶対に食べないようにしましょう。嘔吐や下痢
 ペルシンは多くの動物に毒性があり、特に鳥類は食べて数時間後に死に至ることもあります。
犬はそこまで重い症状になることは少ないですが、アボカドを食べて2、3日経ってから下痢や嘔吐などの症状が出る場合もあります。
すぐに治まれば問題はありませんがもし重症化したら、けいれんや呼吸困難などの症状も出ます。
アボカドはその実によって害となるペルシンの量が違ったりしますので、どれだけ食べれば中毒症状が出るかという目安はわかっていません。
一口だけでもアレルギーが出ることもあります。
脱水症状が起きることは怖いため、下痢や嘔吐がひどい場合や続くようならすぐに病院で相談しましょう。
ペルシンは多くの動物に毒性があり、特に鳥類は食べて数時間後に死に至ることもあります。
犬はそこまで重い症状になることは少ないですが、アボカドを食べて2、3日経ってから下痢や嘔吐などの症状が出る場合もあります。
すぐに治まれば問題はありませんがもし重症化したら、けいれんや呼吸困難などの症状も出ます。
アボカドはその実によって害となるペルシンの量が違ったりしますので、どれだけ食べれば中毒症状が出るかという目安はわかっていません。
一口だけでもアレルギーが出ることもあります。
脱水症状が起きることは怖いため、下痢や嘔吐がひどい場合や続くようならすぐに病院で相談しましょう。
種を誤飲した場合
アボカドの果肉を食べた時に下痢や嘔吐を起こすことがあるわけですが、最も危険なことは種を食べた場合です。 アボカドの種は毒性が強く、種を飲み込むと消化できずに開腹手術が必要となります。 また種は大きいため気管に詰まる可能性もあり、窒息して死亡に至るケースもあります。 そしてアボカドの皮もペルシンの毒性が強く、固いために口の中や胃腸を傷つけてしまうことが多いです。 消化不良の原因にもなります。 非常に危険性が高いのがアボカドの種と皮ですので、人間が調理する際にもよく管理して誤飲のないように注意を払ってください。アボカドを犬が食べてしまった時の対処方法
 犬がアボカドを食べてしまった時には、アレルギーが出ることなどを考えてまずしっかりと様子を観察しましょう。
そのうえで冷静に対応し、動物病院に連絡してください。
無理に吐かせるなどの処置を取らずに医師の判断を聞くことが大切です。
次に順を追って確認していきましょう。
犬がアボカドを食べてしまった時には、アレルギーが出ることなどを考えてまずしっかりと様子を観察しましょう。
そのうえで冷静に対応し、動物病院に連絡してください。
無理に吐かせるなどの処置を取らずに医師の判断を聞くことが大切です。
次に順を追って確認していきましょう。
犬の状態をよく観ながら状況の整理を行う
間違ってアボカドを食べてしまった時、どれぐらいの量で中毒症状が出るかということですが、残念ながらはっきりと分かっていません。 アボカドの品種や実によってもペンシルの量が違い、犬の体重や犬種によってもアレルギーの出方は違うからです。 一口でも危険性がある場合のことを考えて愛犬の姿をチェックしながら、いつ・何を・どれくらい食べたのか、メモや写真、アプリなどで整理し、病院へ行く準備をしましょう。 病院で正確に判断し、治療してもらうためにもアボカド以外の食べ物にアレルギーがあるのか、いつもと違う様子があったのかなど飼い主にしかわからないことを伝えることは大切です。様子がおかしいと思ったら迅速に動物病院へ向かう
 嘔吐や下痢の症状が出てきたり、ぐったりして元気がない、充血や皮膚がかゆそうにしているなど様子がおかしい場合は、即病院へ連れて行きましょう。
自己判断で勝手な処置を施さないように注意してください。
一番良いのはかかりつけの病院へ行くことです。
しかし時間外や休診日という場合、電話で確認してみましょう。
連絡がついたら獣医師の指示を聞くことができます。
遠くの病院につれていくしかない場合は一度電話で状況を伝えてみると良いでしょう。
飼い主の冷静な判断が必要です。
嘔吐や下痢の症状が出てきたり、ぐったりして元気がない、充血や皮膚がかゆそうにしているなど様子がおかしい場合は、即病院へ連れて行きましょう。
自己判断で勝手な処置を施さないように注意してください。
一番良いのはかかりつけの病院へ行くことです。
しかし時間外や休診日という場合、電話で確認してみましょう。
連絡がついたら獣医師の指示を聞くことができます。
遠くの病院につれていくしかない場合は一度電話で状況を伝えてみると良いでしょう。
飼い主の冷静な判断が必要です。
 猫は単独で行動をする動物ですので、子猫を迎える際は
猫は単独で行動をする動物ですので、子猫を迎える際は 先住猫がいつも通りに過ごせて、子猫も落ち着いて排泄や食事ができるようになったら、
先住猫がいつも通りに過ごせて、子猫も落ち着いて排泄や食事ができるようになったら、 子猫が新しい生活に慣れて先住猫との距離が、少しづつでも縮まってくれれば飼い主も安心できます。
2匹の猫が穏やかに過ごせるようにするには、
子猫が新しい生活に慣れて先住猫との距離が、少しづつでも縮まってくれれば飼い主も安心できます。
2匹の猫が穏やかに過ごせるようにするには、 多頭飼いがどうしても難しい場合は、
多頭飼いがどうしても難しい場合は、 まだあまり縄張り意識がなく歳がそんなに離れておらず、体力が同じくらいなどの
まだあまり縄張り意識がなく歳がそんなに離れておらず、体力が同じくらいなどの 人が高齢になれば介護が必要になる可能性が高くなるように、
人が高齢になれば介護が必要になる可能性が高くなるように、
 老犬の介護に慣れていないと疲れてしまうことが多く、悩みの種にもなりやすいです。
しかし、上記でも紹介したように一人で悩むことは良い方向に進まない場合が多いので誰かに話すように心がけましょう。
もし、近くに老犬の介護に疲れている人がいるのであれば積極的に話をしましょう。
自身の話を聞いてもらうことで肯定してくれることが多いので悩みを打ち明けやすくなり、
相手の話を聞けば同調できる部分も多くあるので自分だけが老犬の介護に疲れているのではないと思うことができ、心が軽くなります。
老犬の介護に慣れていないと疲れてしまうことが多く、悩みの種にもなりやすいです。
しかし、上記でも紹介したように一人で悩むことは良い方向に進まない場合が多いので誰かに話すように心がけましょう。
もし、近くに老犬の介護に疲れている人がいるのであれば積極的に話をしましょう。
自身の話を聞いてもらうことで肯定してくれることが多いので悩みを打ち明けやすくなり、
相手の話を聞けば同調できる部分も多くあるので自分だけが老犬の介護に疲れているのではないと思うことができ、心が軽くなります。
 老犬の介護をしているとどうしても疲れを感じてしまいます。
歳をとっても愛犬には変わりないため、戸惑ってしまう飼い主も多いのではないでしょうか。
次に、
老犬の介護をしているとどうしても疲れを感じてしまいます。
歳をとっても愛犬には変わりないため、戸惑ってしまう飼い主も多いのではないでしょうか。
次に、 老犬の介護をするとなるとどうしても
老犬の介護をするとなるとどうしても 老犬の介護をすることは決して楽ではなく、
老犬の介護をすることは決して楽ではなく、 介護グッズを使用することでも介護のつらさを軽減することができます。
最近では犬の寿命も延びているので
介護グッズを使用することでも介護のつらさを軽減することができます。
最近では犬の寿命も延びているので 愛犬も人と同じように歳をとり、人よりも寿命が短いので先に介護が必要になる場合が多いです。
飼い主であれば最後まで愛犬の世話をする義務があるので必然的に犬を飼うのであれば介護をする覚悟を決めておく必要があります。
初めて老犬の介護をする場合はどうしても疲れを感じてしまうので、いかに
愛犬も人と同じように歳をとり、人よりも寿命が短いので先に介護が必要になる場合が多いです。
飼い主であれば最後まで愛犬の世話をする義務があるので必然的に犬を飼うのであれば介護をする覚悟を決めておく必要があります。
初めて老犬の介護をする場合はどうしても疲れを感じてしまうので、いかに 愛犬が顔や手を舐めてくることはありませんか。
可愛い姿に嬉しくなってしまう飼い主様も多いはずです。
「何か美味しいニオイでもしたのかな」「なんで舐めるのだろう」と不思議に思うこの行動は、犬にとってちゃんと意味を持っているんです。
また、
愛犬が顔や手を舐めてくることはありませんか。
可愛い姿に嬉しくなってしまう飼い主様も多いはずです。
「何か美味しいニオイでもしたのかな」「なんで舐めるのだろう」と不思議に思うこの行動は、犬にとってちゃんと意味を持っているんです。
また、
 自分の気持を伝えるだけではなく、
自分の気持を伝えるだけではなく、 愛犬を怒ったときにペロペロと舐めてくるときの犬の心情は、
愛犬を怒ったときにペロペロと舐めてくるときの犬の心情は、 自分の体を舐めることがあります。
すぐにやめたり、肌や被毛の様子に変わったことがなければ問題ありませんが
自分の体を舐めることがあります。
すぐにやめたり、肌や被毛の様子に変わったことがなければ問題ありませんが 「最近忙しくて遊んであげていない」「天気が悪くて散歩に行けていない」など
「最近忙しくて遊んであげていない」「天気が悪くて散歩に行けていない」など