犬の歯磨きはなぜ必要?
犬の歯磨きがなぜ必要なのか知っていますか?
犬も人間と同様に歯磨きをしないと、歯石が溜まったり、口内で細菌が繁殖してしまいます。
そうなると、歯肉炎、やがては歯周病などへと…。
そういったことにならない為にも、ワンちゃんもしっかりとした歯磨きが必要となってくるのです。
犬が噛む!歯磨き中に噛まれる理由は?
 「歯磨きをしないといけないのは分かってるんだけど…噛まれちゃう…」という飼い主さんも多いはず。
そう、犬はそんな簡単に歯磨きをさせてはくれないんです。
では、犬が歯磨きをさせてくれない理由は何にあるのでしょうか?
「歯磨きをしないといけないのは分かってるんだけど…噛まれちゃう…」という飼い主さんも多いはず。
そう、犬はそんな簡単に歯磨きをさせてはくれないんです。
では、犬が歯磨きをさせてくれない理由は何にあるのでしょうか?
口内トラブル
犬が歯磨きをさせてくれない理由のひとつに「口内トラブル」が挙げられます。
例えば、歯磨きの頻度が少なかったりすると、すでに歯周病などになってしまっていることも…。
こういった時や、口の中を怪我している時には、患部を触られることを嫌がり、思わず飼い主さんの手を噛んでしまいます。
ストレス
また、犬にとって口の周りを触られることに強い抵抗があることも忘れてはいけません。
ワンちゃんにとって、口とは人間が思っている以上に触られたくない場所なのです。
そのため、口内に異物(歯ブラシなど)を入れられる歯磨きはストレスとなり、耐えきれずに噛んでしまうということがあります。”
犬が歯磨きを嫌がる!おすすめの手順は?
 犬が歯磨きを嫌がる理由はお分かり頂けたでしょうか?
それでも、飼い主である以上、愛犬の歯磨きは避けては通れない道。
ここからは「でも、どうしたらいいの?」という飼い主さんのために、まずは歯磨きを始める手順を紹介します。
犬が歯磨きを嫌がる理由はお分かり頂けたでしょうか?
それでも、飼い主である以上、愛犬の歯磨きは避けては通れない道。
ここからは「でも、どうしたらいいの?」という飼い主さんのために、まずは歯磨きを始める手順を紹介します。
歯磨きの頻度
まず最初に、歯磨きがどうしてもできないという場合は、最初から毎日する必要はありません。
犬の歯垢は3~5日経つと歯石に変化します。
そのため、少なくとも3日に1度は歯磨きをする必要がありますが、最初はこれをクリアしていればオッケー程度に考えておきましょう。
最初から素直に歯磨きをさせてくれる犬は滅多におらず、繰り返し歯磨きをすることでワンちゃんも次第に慣れていき、おとなしく歯磨きをさせてくれるようになるのです。
最初は口の周辺から触る
では、ここからは実際の歯磨きまでの手順です。
歯磨きをしたくても、いきなりワンちゃんの顔を押さえて始めてはいけません。
当然、ワンちゃんもびっくりしてしまいます!
最初は顔や口の周辺から触り、ワンちゃんを慣れさせることが大切。
慣れてきたなと感じたら、次は前歯、犬歯から奥歯というように徐々に触り、歯磨きではなく、「歯を触られること」をまず犬に慣れさせましょう。
ガーゼを使って犬の歯磨きをする
ワンちゃんが歯を触られることに慣れてきたら、次はガーゼを使いましょう。
ガーゼも順序通りの部位から触れ、今度は「歯をガーゼで擦ること」に慣れさせる必要があります。
これができないと、より異物感の強い歯ブラシを使っての歯磨きはできません。
歯ブラシを使って犬の歯磨きをする
ここからは、実際に歯ブラシに慣れさせていきます。
歯ブラシを使うときは、まず、歯ブラシの匂いを嗅がせたり、見せたりして、歯ブラシという存在を教えてあげましょう。
歯ブラシという存在に慣れてきたのであれば、その後は指やガーゼと同じ様に、前歯から少しずつ「歯ブラシで触られること」に慣れさせていきます。
これを繰り返していれば、次第にワンちゃんも歯磨きに抵抗をなくしていきます。
犬が歯磨きを嫌がる!できないを解決するコツは?
 それでもまだ「歯磨きを嫌がる、させてくれない!」という場合もあるかと思います。
そんな飼い主さんに、ここからは、歯磨きを嫌がる犬に歯磨きをするコツを5つ紹介します!
「どうしても歯磨きができない」という飼い主さんは必読ですよ!
それでもまだ「歯磨きを嫌がる、させてくれない!」という場合もあるかと思います。
そんな飼い主さんに、ここからは、歯磨きを嫌がる犬に歯磨きをするコツを5つ紹介します!
「どうしても歯磨きができない」という飼い主さんは必読ですよ!
長時間はしない
最初にコツと合わせて注意点を紹介します。
それは「長時間歯磨きをしないこと」です。
特に最初の方はワンちゃんも歯磨きを良いものとは思っていません。
そんな中、無理矢理長時間の歯磨きをすると、ワンちゃんの歯磨き嫌いはますますひどくなってしまいます。
そうなると、2回目、3回目はなおのこと難しいです…。
まずは、歯磨きは嫌なものではないということをワンちゃんに教えること。
これがワンちゃんの歯磨きを成功させる最初のコツとなります。
練習は早い時期に
これはワンちゃんを飼いだして間もない飼い主さんへ、将来気持ちよく歯磨きをするためのコツです。
犬は1歳以上になると、歯磨きに慣れさせることが困難になります。
そのため、ワンちゃんを家に迎えたばかりだという場合は、根気よく、子犬の内から歯磨きの練習をすることが大切になってきます。
2人がかりで犬の歯を磨く
次のコツは「無理して1人で歯磨きをしない」ということです。
無理に1人で行おうとすれば、意図せず犬を傷つけたりしてしまうことも考えられます。
そうなれば、「歯磨き=嫌なこと」と記憶してしまい、今後も歯磨きをすることは難しくなります。
1人で出来ないときは、2人がかりで歯磨きを行うのも手です。
そうすることで、ワンちゃんに「気持ちよい歯磨き」をすることができるかもしれません。
ご褒美と歯磨きをセットにする
次のコツは「ご褒美を与える」ということ。
歯磨きを何度やっても成功しない時には、ワンちゃんに「歯磨きを頑張ったご褒美」を与えてあげましょう!
ご褒美におやつなどを与えることで「歯磨きをする=良いことがある」と記憶させれば、おとなしく歯磨きをさせてくれる可能性がアップします。
どうしても嫌がる場合は動物病院へ
最後に紹介するのは、「一度病院に行ってみる」です。
強く歯磨きを拒む場合、既に何かしらの病気が進行していることも考えられます。
何をしてもダメだという時には、ワンちゃんを病院に連れて行き、一度診てもらうというのも飼い主としての役目となります。
犬が歯磨きを嫌がる時の便利グッズ
ここからは、ワンちゃんの歯磨きを簡単にできる「犬用歯磨きグッズ」を紹介します。
「歯磨きが苦手だな〜」と感じている飼い主さんは、是非一度使ってみて下さいね!
歯磨きガム
 歯磨きアイテムの中で最もメジャーなのが、犬用歯磨きガムです。
これは、ワンちゃんがおやつと思って、ガムを食べているだけで、歯磨きができる優れもの。
飼い主さんにとって、時間も労力もかからないが嬉しいポイントです。
ワンちゃんに歯磨きガムを与えるときは、犬の口幅より、少しだけ長めの物を選んで、噛ませてあげて下さい。
歯磨きアイテムの中で最もメジャーなのが、犬用歯磨きガムです。
これは、ワンちゃんがおやつと思って、ガムを食べているだけで、歯磨きができる優れもの。
飼い主さんにとって、時間も労力もかからないが嬉しいポイントです。
ワンちゃんに歯磨きガムを与えるときは、犬の口幅より、少しだけ長めの物を選んで、噛ませてあげて下さい。
スポンジブラシ
次に紹介するのは「スポンジブラシ」。
固い歯ブラシよりも柔らかいスポンジブラシを好むワンちゃんも多くいます。
歯ブラシになると急に嫌がる!というような子にはぜひ一度試してみて下さいね!
また、歯磨きの練習でガーゼの段階で嫌がるという場合にも、スポンジブラシを用いた歯磨き練習は効果的です。
歯磨き可能な犬のおもちゃ
 また、犬用おもちゃの中にも、歯のケアをすることができるものがあります。
歯磨きの頻度やレベルに心配があるという飼い主さんは、歯磨きガム同様に、こういった歯のケアをできるおもちゃを持つのもおすすめ。
ワンちゃんの噛む力や体格、犬種などに合わせて、おもちゃを選んであげて下さいね!
また、犬用おもちゃの中にも、歯のケアをすることができるものがあります。
歯磨きの頻度やレベルに心配があるという飼い主さんは、歯磨きガム同様に、こういった歯のケアをできるおもちゃを持つのもおすすめ。
ワンちゃんの噛む力や体格、犬種などに合わせて、おもちゃを選んであげて下さいね!
まとめ
この記事では、愛犬が歯磨きを嫌がる理由や対処法、歯磨きの仕方などを解説しました。
ワンちゃんの歯磨きは大変ですが、絶対にしないといけないことでもあります。
ぜひ、この記事も参考にしながら、可愛い愛犬の歯磨きをしてあげて下さいね!
猫の目やにの原因は?
いつも通りに愛猫を見ているとふと気になることが…!
「あれ?こんなに目やに出てたっけ?病気?」
一度そう思ってしまうと、気になって仕方がないものです。猫も人間同様に目やにが出ますが、その原因はなんなのでしょうか?
生理現象によるもの
猫も生理現象として、日常的に目やにを出しています。
これは、目に入ったホコリなどの老廃物を出すための自然現象です。
少量の目やにが、日常的にで続けている場合は、自然現象での目やになので、そんなに心配する必要はありません。
病気のサインかも…?
ですが、あまりにも目やにの量が多いと、飼い主としては「何か病気かな?」と不安になるもの。
実際に、猫の「目やに」は、隠れた病気のサインとなるものがあります。
もし、いつもの目やにとの違いを感じたり、目やにの異常を感じたら、動物病院に相談する、獣医師さんに診てもらうなどの対処をしましょう。
猫の目やにの色や症状は病気のサイン?
 では、実際にどのような「目やに」であれば病気のサインを疑わなくてはいけないのでしょうか?
ここからは「目やにの色」「猫ちゃんの症状」から、病気のサインである可能性があるもの見ていきましょう。
では、実際にどのような「目やに」であれば病気のサインを疑わなくてはいけないのでしょうか?
ここからは「目やにの色」「猫ちゃんの症状」から、病気のサインである可能性があるもの見ていきましょう。
黄色の目やに
まずは目やにの色が「黄色」である場合。
黄色の目やにが出ていて、ウインクするように片目を閉じていたり、痛そうにしている場合は、目を怪我している可能性があります。
外傷が見当たらなくても、眼球に傷がついている場合などがあるので放置は禁物です。
本来であれば、目薬だけで治っていたはずなのに、放置してしまったばかりに手術をしなくてはいけなくなった…なんてケースも。
怪我の可能性を感じたら、すぐに病院に行きましょう!
緑色の目やに
では、目やにが「緑色」だったときはどうでしょう?
目やにが緑色である場合は、主に細菌感染が疑われます。
結膜炎など、目のみに感染を起こしている場合もあれば、ヘルペスやクラミジアといった猫風邪の症状のひとつとして起こっている場合も。
こちらも放置をしてしまうと、猫ちゃんが目を擦ってしまい二次的に怪我に繋がる場合があるので早めに病院で診てもらいましょう。
赤茶色や茶色の目やに
目やにの色が「茶色」「赤茶色」の場合は自然現象の目やにと考えられます。
通常の目やにであれば、目の縁や目頭に少量だけ付着する様子が見受けられます。
ですが、もし目やにの量が異常に出ていたり、ドロドロとした目やにの場合は何か猫ちゃんにあったのかもしれません。
不安な場合は、一度動物病院に連れて行くことをお勧めします。
片目だけ白い目やに
次に、目やにの症状(目やにの出かた)も一緒に見ていきましょう。
「白い目やに」が片目だけ出ている場合。
このようなときは、黄色い目やにが出ているときと同様に、外傷による目やにが疑われます。
また、クラミジア感染によって、片目から炎症が進行している場合も…。
急いで動物病院で診察してもらうことをお勧めします。
涙のような目やに
次に、目やにの症状が「涙のように出ている」場合です。
このようなときは、なんらかのアレルギーである可能性が高いです。
多いのは、ハウスダストなどのアレルギー。
アレルギー反応のひとつとして目やにが出ている場合は、同時に顔や身体を痒がったり、くしゃみをする場合があります。
ドロドロした目やに
「ドロドロしたような目やに」が出ている場合は、何らかの感染症などが疑われます。
普通の目やには湿っていますが、決してドロドロというような状態ではありません。
もし、少しでもドロドロを感じたり、いつもと違うなと違和感を覚えたら、大事をとって動物病院に行くのもいいでしょう。
猫の目やにの取り方
 ここからは、猫の目やにの取り方を紹介します。
目元を触られるのを嫌がる猫も多いですが、目やにを放置していると、猫も痒がり、二次的に皮膚などを傷つけてしまうこともあります。
猫は自分ではめやにを取ることができないので、飼い主であるなたがしっかりと取ってあげましょう!
ここからは、猫の目やにの取り方を紹介します。
目元を触られるのを嫌がる猫も多いですが、目やにを放置していると、猫も痒がり、二次的に皮膚などを傷つけてしまうこともあります。
猫は自分ではめやにを取ることができないので、飼い主であるなたがしっかりと取ってあげましょう!
ガーゼやノンアルコールのウェットティッシュを使う
猫の目やにを取ってあげる場合は、なるべく柔らかい、湿ったもので拭き取ってあげましょう。
目やには時間が経つと乾燥し、固くなってしまいます。
ティッシュペーパーなどは紙も硬く、それで固まった目やにを無理に取ろうとすると猫の目や皮膚を傷つけてしまう可能性があります。
おすすめなのは、ちゃんとした犬・猫用のウェットティッシュ。
湿っているため、目やにがふやけ、取れやすくなります。
もし人間用のウェットティッシュを使う場合などは、ノンアルコールであるものを使うといった配慮も大切です。
また、湿らせたガーゼなどもおすすめです。
力を入れず撫でるように拭く
目やにを拭き取ってあげるときは「力を入れず、撫でるように」拭き取ってあげましょう。
間違って猫の目に指が入ってしまわないように、猫の頭を固定し、目元から鼻の方の向かって撫でるように拭き取るというのが基本です。
また、1回で全ての目やにが取れない場合は、優しく、数回に分けてを繰り返しましょう。
猫をリラックスさせる
 また、目やにをとる時は、猫をリラックスさせた状態にすることも大切です。
突然目の付近を触ると猫ちゃんもびっくりしてしまいます!
そうなると、当然猫ちゃんも大人しく目やにを拭き取らせてはくれません。
最初は、体や顔まわりを撫でながら、猫ちゃんがリラックスしてきたなと感じたら、撫でる動作のようにスムーズに拭き取ってあげましょう。
また、目やにをとる時は、猫をリラックスさせた状態にすることも大切です。
突然目の付近を触ると猫ちゃんもびっくりしてしまいます!
そうなると、当然猫ちゃんも大人しく目やにを拭き取らせてはくれません。
最初は、体や顔まわりを撫でながら、猫ちゃんがリラックスしてきたなと感じたら、撫でる動作のようにスムーズに拭き取ってあげましょう。
取りづらい目やにはどうする?
もし一度で拭き取れない目やにがあった場合は、濡れたガーゼなどでふやかさなければいけません。
目やには時間が経つと固まって拭き取りにくくなってしまいます。
無理に拭き取ろうとすると、目の周りの毛が抜けてしまったり、誤って猫ちゃんの目を傷つけてしまうことも考えられるので注意して下さいね!
まとめ
この記事では、猫の「目やに」について色や症状から分かる病気のサインや対処法などを解説しました。
目やにも猫ちゃんの具合を確認するための大事な指標です。
ぜひ、この記事も参考にしながら、猫ちゃんの体調を気遣ってあげて下さいね!
猫の多頭飼いで失敗しない方法や注意点
猫を見ていると、ほんとに癒されますよね!
飼い主の言うことを聞かずに、マイペースに自由気ままに生活している姿が、少し憎かったり、でもそれ以上に可愛かったりと…。
そんな猫ちゃんにもっと囲まれて生活したいと言う思いや、今いる猫の遊び相手にと多頭飼いを考えている飼い主さんも多いのではないでしょうか?
でも、猫の多頭飼いは簡単なものではありません。
とりあえず始めたけど、失敗した…なんてことも少なくないのです。
猫の多頭飼いを始める前に、まずは失敗しない方法や注意点を見ていきましょう!
先住猫が新入り猫に寛容か見極める
 まずは、先住猫(今すでに家にいる猫)が新入りの猫に寛容かを見極めましょう。
例えば、先住猫が飼い主さんを独り占めしたいタイプの場合、新入り猫を受け入れることはストレスになります。
そのストレスから体調を崩したり、今までしなかったような悪さをしてしまう子も…。
多頭飼いが難しそうであれば、先住猫のために諦めるか、相性の良い猫を迎えるなど、考慮や工夫が必要です。
まずは、先住猫(今すでに家にいる猫)が新入りの猫に寛容かを見極めましょう。
例えば、先住猫が飼い主さんを独り占めしたいタイプの場合、新入り猫を受け入れることはストレスになります。
そのストレスから体調を崩したり、今までしなかったような悪さをしてしまう子も…。
多頭飼いが難しそうであれば、先住猫のために諦めるか、相性の良い猫を迎えるなど、考慮や工夫が必要です。
先住猫を優先してあげる
また、実際に多頭飼いを始めたら「先住猫を優先する」ことも必要になってきます。
「この子(先住猫)は寛容だから大丈夫!」と思っていても、いざ新入り猫が入ってきて、その子ばかりを可愛がっていると先住猫は新入りを認めません。
ときには、新入り猫をいじめてしまうこともあります。
多頭飼いで一番大切なのは「どんな時でも先住猫を優先してあげる」こと。
新入り猫を可愛がりたい気持ちも分かりますが、先住猫のためにも、何事もこの子を優先してあげましょう。
例えば、ご飯を与えるときも、先住猫に与えてから、新入り猫に与えるといった配慮が必要になってきます。
多頭飼いができる環境を作る
多頭飼いを始める「事前の環境作り」も大切です。
猫を多頭飼いする前に、必ず物件(アパートやマンション)の契約書を確認し、多頭飼いをしても良いのか調べておいて下さい。
物件によっては、飼育頭数に制限があることも。
また、猫が増える分トイレの数も増やさないといけないなど、空間的な問題も生じます。
猫を多頭飼いできるだけのスペースはあるか?ここの見極めも大切になってきます。
防災グッズを用意しておく
最後に「防災グッズ」を用意しておくのも重要です。
災害が発生したり、住居に何かしたのトラブルが起きたときには、もちろん猫ちゃんたちも一緒に避難し、避難先でも守らなくてはいけません。
多頭飼いをしていれば、当然移動するのも一苦労です。
もしもの時を考えて、多頭飼いに適した大きなキャリーバックや食料、トイレなどの日用品を必ずそろえておきましょう。
猫の多頭飼いは相性が大切
 では、ここからは実際に猫を多頭飼いするときに、どのように新入り猫を選べばいいのかを、相性という観点から紹介します。
新入り猫を探しているという飼い主さんは必読ですよ!
では、ここからは実際に猫を多頭飼いするときに、どのように新入り猫を選べばいいのかを、相性という観点から紹介します。
新入り猫を探しているという飼い主さんは必読ですよ!
子猫(オス)と成猫(オス)
子猫(オス)と成猫(オス)の場合は注意が必要です。
去勢をしていない成猫の場合、本能的に子猫を攻撃する可能性があります。
最悪の場合は子猫を殺してしまうことも…。
オス同士で多頭飼いをする場合は、少なくとも子猫が成猫になるまでは、飼い主さんの目の届く範囲で飼育して下さい。
子猫と子猫
子猫と子猫の場合は、性別に関わらず、相性抜群!
1歳以下の子猫は環境に順応しやすく、子猫同士で仲良くなる可能性が非常に高いです。
猫の多頭飼いを考えた時には、もっとも最適な組み合わせとも言えます。
成猫(オス)と成猫(メス)
成猫(オス)と成猫(メス)の場合、多頭飼いは少し難しいかもしれません。
まず最初に、交配の予定がなければ避妊・去勢手術をしておく必要があります。
成猫同士の多頭飼いは複雑です。
というのも、それぞれの性格が既に確立しており、それによって相性が決まるためです。
成猫同士の多頭飼いを考えている時には、しっかりとトライアル期間を設けるなど、慎重なアプローチをすることが必要になってきます。
子猫(メス)と成猫(メス)
子猫(メス)と成猫(メス)の場合は、多少注意が必要なものの比較的安心です。
というのも、オス同士と違って縄張り争いなどがないためです。
その一方で、メス同士の場合は、どちらも神経質になってしまう場合があるので、お互いににストレスが溜まっていないかなどのチェックは必要になってきます。
年齢で相性は変わる?
 では、猫の年齢によって相性は変わってくるのでしょうか?
「子猫と成猫」の場合は、成猫の性格次第では比較的、良い相性が望めます。
成猫は自身の性格が確立しており、温厚な性格であれば、新入り子猫に対しては寛容に受け入れやすいからです。
一方で「シニア猫と子猫」になると注意が必要にもなります。
シニア猫は、毎日、新入りの子猫が遊びまわっているとそれをストレスに感じてしまうことがあるからです。
また、猫の年齢を見た時に、比較的同じ歳くらいの方が良いという見解もあります。
では、猫の年齢によって相性は変わってくるのでしょうか?
「子猫と成猫」の場合は、成猫の性格次第では比較的、良い相性が望めます。
成猫は自身の性格が確立しており、温厚な性格であれば、新入り子猫に対しては寛容に受け入れやすいからです。
一方で「シニア猫と子猫」になると注意が必要にもなります。
シニア猫は、毎日、新入りの子猫が遊びまわっているとそれをストレスに感じてしまうことがあるからです。
また、猫の年齢を見た時に、比較的同じ歳くらいの方が良いという見解もあります。
多頭飼いに向いてる猫の性格
 次に、どのような性格の先住猫であれば、多頭飼いに向いているかを見ていきましょう。
先住猫が甘えん坊、または寂しがり屋な性格の場合は多頭飼いに向いていると言えます。
その子がお留守番などが多いのであれば尚更です。
先住猫も家に1匹でいるのは寂しいもの。
そんな中、もう1匹遊び相手にでもなってくれる猫が現れれば、不安やストレスも解消されます。
場合によっては、むしろ多頭飼いをしてあげた方が良いかもしれません!
次に、どのような性格の先住猫であれば、多頭飼いに向いているかを見ていきましょう。
先住猫が甘えん坊、または寂しがり屋な性格の場合は多頭飼いに向いていると言えます。
その子がお留守番などが多いのであれば尚更です。
先住猫も家に1匹でいるのは寂しいもの。
そんな中、もう1匹遊び相手にでもなってくれる猫が現れれば、不安やストレスも解消されます。
場合によっては、むしろ多頭飼いをしてあげた方が良いかもしれません!
多頭飼いに向かない猫の性格
逆に、先住猫が「自立心の強い一匹狼タイプ」であれば多頭飼いは向かない性格と言えるでしょう。
新入り猫がくることで、自身の生活が乱され、それをストレスに感じることが多いためです。
もしも先住猫が「自立心の強い一匹狼タイプ」であれば、新入り猫も同様に「一匹狼タイプ」の子を選んであげれば、多頭飼いが成功する確率がアップします。
まとめ
この記事では、猫の多頭飼いについて「多頭飼いの注意点」や「相性の良い猫とは?」を解説しました。
猫の多頭飼いは簡単なものではありませんが、成功すると飼い主であるあなたにとっても、先住猫にとってもよいものとなります。
ぜひ、この記事を参考にしながら多頭飼いを成功させてみて下さいね!
猫の鼻水の色で病気が分かる?
「猫の鼻水が止まらなくて心配…」という悩みを抱える飼い主さんもいるでしょう。
しかも、鼻水が「ピンク色」「緑っぽい」となればなおさら心配ですよね。
実際に、鼻水の様子は、猫に潜んでいる病気のサインとなることも。
まずは「猫の鼻水の色」から分かる病気のサインを見ていきましょう。
ピンク色の鼻水
鼻水がピンク色の場合、血液が混じっている可能性があります。
血液が混じる主な原因は、怪我や鼻炎の悪化が原因で鼻粘膜から出血していることがあげられます。
ピンク色の鼻水が止まらなく、慢性化している時には、鼻腔内腫瘍(びくうないしゅよう)といった病気も考えられるので病院に連れて行きましょう。
緑がかった黄色
緑がかった黄色の鼻水はが出る場合は、細菌やウイルスによる感染症、歯周病が考えられます。
最初は色に驚くかもしれませんが、これはあまり心配せずとも大丈夫です。
緑がかった黄色になるのは、真菌や細菌の死骸が鼻水に混ざって体外に出ている証拠。このような場合は様子を見てもいいでしょう。
その一方で、同時に猫の口臭がきつくなったり、鼻水の強い粘り、といった場合は歯周病に関連しているものもあります。
このような時は、病院に連れていってあげましょう。
透明の鼻水
透明でサラサラした鼻水が出る場合はこんな時です。
・アレルギー性鼻炎の初期症状
・ウイルス性鼻炎の初期症状(後に緑や黄色に変化)
・異物刺激によるもの
いずれにせよ、この状態ではそこまで心配するような症状ではないと言えます。
ですが、次第に鼻水の色が変化していくことも…。
例えば、鼻水の透明がピンク色に変化していった時には、循環血液量過剰というのも考えられます。
赤(鼻血)
赤色の場合は、人間と同じでいわゆる「鼻血」です。
突発的に、1日で治るような場合は怪我が考えられます。
ですが、鼻血が慢性的な場合は、ピンク色の時と同様に鼻腔内腫瘍(びくうないしゅよう)による鼻出血が考えられます。
猫の鼻水に伴う症状と原因
 また、鼻水に伴う症状から猫にひそむ病気を見つけることもできます。
ここからは鼻水と合わせて確認しておきたい他の症状を見ていきましょう。
また、鼻水に伴う症状から猫にひそむ病気を見つけることもできます。
ここからは鼻水と合わせて確認しておきたい他の症状を見ていきましょう。
目やに
まずは「目やに」です。
目やにと鼻水が同時に出ている場合は、
・猫風邪(細菌やウイルスによる感染症)
・クラミジア感染症
・その他感染症
など多くの病気の可能性が考えられます。
目やにの発生が伴う病気の可能性は非常に多岐にわたるので、続く場合は一度病院で診てもらいましょう。
発熱
次に「発熱」です。
鼻水と発熱が同時に生じた場合は、細菌やウイルスによる呼吸器感染症が主に疑われます。
ですが、これだけで病気を確定することは難しく、素人では判断できません。
鼻水+発熱という症状も心配ですが、発熱により極度にごはんを食べなくなる猫もいます。
これに伴い栄養不足や脱水を起こす可能性もありますので、あまりにも猫がぐったりしている場合が急いで病院に連れていきましょう。
くしゃみ
次は「くしゃみ」を伴う場合です。
細菌やウイルスによる感染症にかかってしまった場合、猫も人間と同様に、鼻水と一緒にくしゃみをする時があります。
花粉やアレルギーなどの場合もくしゃみを伴います。
他の症状と比べて、重大な病気が隠れている可能性はやや低めなので、鼻水+くしゃみの時は少し様子を見てもいいかもしれません。
猫の鼻水が出た際の対処法や治し方
 猫の鼻水が出ているのに、それを放ったらかしにするわけにはいきませんよね?
ここからは、鼻水が出ている時にどのような対処や治し方があるのかを紹介します。
まずはこれを実践してみましょう。
猫の鼻水が出ているのに、それを放ったらかしにするわけにはいきませんよね?
ここからは、鼻水が出ている時にどのような対処や治し方があるのかを紹介します。
まずはこれを実践してみましょう。
鼻水の拭き取り方
猫の鼻水を拭いてあげる時は、ティッシュなどで「優しく」拭き取るが基本となります。
目頭から鼻の方へ向かって拭くことで猫も嫌がりません。
また、鼻水は時間が経ってしまうと固まってしまうので、こまめに拭いてあげるようにして下さい。
鼻水が固まってしまいティッシュじゃ取れないという時には、塗れたコットンやガーゼで固まった鼻水をふやかすと拭き取ることができます。
病院で診てもらう
飼い主と言えども、猫の病気に関しては素人です。
勝手な判断で病院に連れていかないことで、隠れた病気が進行し、猫もあなたも辛い思いをすることも考えられます。
猫の鼻水が止まらない、伴って体調が悪そうな場合は迅速に病院に連れていきましょう。
また、どんな症状だとしても、動物病院で獣医師さんに診てもらえれば、あなたの大きな不安も解消できます。
病院に連れて行く時には、その症状がいつからか、色や状態などはどうかをメモをしていくと便利です。
薬を出してもらう
動物病院に連れて行けばひとまずは安心しても良いでしょう。
猫ちゃんのために薬を処方された時は、用量・用法を守りながら、しっかり飲ませてあげて下さい。
猫は嫌がるかもしれませんが、根気強く飲ませ続けることが、その子のためにもなります。
まとめ
この記事では「猫の鼻水」について、色や伴う症状から分かる病気の可能性、そんな時の対処法などを解説しました。
猫の鼻水には、思いがけない病気が隠れていたり、反対に心配しすぎて病院に連れて行ったけど些細なことだったということもあります。
ですが、何もせずに後悔するような結果になるのが一番いけません。
些細な症状でもあなたが不安を抱えたり、猫が辛そうであれば病院に連れていってあげましょう。 犬はみかんを食べて大丈夫
 人が食べている食べ物の中にも、犬が食べて大丈夫な食べ物があります。
ではみかんはどうでしょうか?
結論、みかんは犬も食べることができます!
しかしいくつか注意しなければいけない点もあります。
最初に、みかんを食べるメリットと犬にみかんを与えるときの注意点をご紹介します。
みかんを食べさせる時は、メリットと注意点を把握した上で与えるようにしましょう。
人が食べている食べ物の中にも、犬が食べて大丈夫な食べ物があります。
ではみかんはどうでしょうか?
結論、みかんは犬も食べることができます!
しかしいくつか注意しなければいけない点もあります。
最初に、みかんを食べるメリットと犬にみかんを与えるときの注意点をご紹介します。
みかんを食べさせる時は、メリットと注意点を把握した上で与えるようにしましょう。
みかんの利点
 みかんには100gあたり35mgのビタミンCが含まれるため、人間のビタミンC補給には適した果物です。
しかし犬は、ビタミンCを食事で摂取しなくても自身の体内で生成することができるため、積極的に与える必要はありません。
ただ、犬は年齢を重ねるごとにビタミンを生成する力が不足すると考えられており、さらに夏場はビタミンCが不足しやすい季節となります。
高齢の犬や、夏場には、みかんを与えてビタミンCを補給してあげるのも良いかもしれませんね。
また、みかんにはビタミンCの他にも健康維持が期待できる成分がたくさん含まれています。
みかんには100gあたり35mgのビタミンCが含まれるため、人間のビタミンC補給には適した果物です。
しかし犬は、ビタミンCを食事で摂取しなくても自身の体内で生成することができるため、積極的に与える必要はありません。
ただ、犬は年齢を重ねるごとにビタミンを生成する力が不足すると考えられており、さらに夏場はビタミンCが不足しやすい季節となります。
高齢の犬や、夏場には、みかんを与えてビタミンCを補給してあげるのも良いかもしれませんね。
また、みかんにはビタミンCの他にも健康維持が期待できる成分がたくさん含まれています。
水分たっぷり
水を飲んでほしくてもなかなか飲んでくれないとき、特に熱中症が気になる季節には、水分補給をさせたくても飲んでくれないと困ることがあると思います。
そういったときには、甘味のあるみかんを与えることで水分を補給してあげるとよいでしょう。
与えすぎは下痢などの消化器症状につながる恐れがあるので、いつものお水にみかん汁を数滴たらして試してみましょう。
カリウム
カリウムは、体内で水分の調整を行う役割を担い、体内で増えすぎたナトリウムの排泄を促す働きもあります。
クエン酸
 柑橘系には疲労回復効果が期待できる栄養素「クエン酸」が多く含まれています。
細胞が酸化し、それを修復させようとする状態が疲労に繋がります。
この細胞修復にクエン酸が使われるため、疲労回復につながると考えられています。
柑橘系には疲労回復効果が期待できる栄養素「クエン酸」が多く含まれています。
細胞が酸化し、それを修復させようとする状態が疲労に繋がります。
この細胞修復にクエン酸が使われるため、疲労回復につながると考えられています。
セルロース(食物繊維)
みかんに多く含まれるセルロースには腸内環境を整える効果があるとされています。
動物病院では便秘気味の犬に食物繊維が多く含まれている食事を進められることはよくあります。
みかんのみで便秘が改善するかは個体差がありますが、腸内環境を整えてくれる効果はあると言えそうです。
犬にみかんを与える際の注意点
 犬にみかんを与えることは問題ないですが、以下の点を守らないと愛犬を危険な目に合わせてしまう可能性もあります。
必ずみかんを与える際は注意点があることを把握するようにしましょう。
犬にみかんを与えることは問題ないですが、以下の点を守らないと愛犬を危険な目に合わせてしまう可能性もあります。
必ずみかんを与える際は注意点があることを把握するようにしましょう。
与え過ぎない
 みかんは前述の通り、ビタミンCだけでなく水分も豊富に含まれています。
与え過ぎると下痢になるおそれがあります。
また、食物繊維も多いため、消化しにくいという側面もあります。
そのため、消化されずにうんちに混ざって出てくるという話もあります。
下痢や消化不良を起こさないためにも、与え過ぎには十分注意してください。
食べすぎを防ぐためにもトッピングやおやつにとどめることをおすすめします。
目安としては犬が1日に必要とするエネルギーの10%程度に収まるようにしましょう。
ドッグフードとの栄養バランスも考えながら取り入れてください。
ただし、みかんはカロリーが低めなので10%で計算すると量が多すぎ、お腹を壊す原因になりかねません。
必要なフード量の見た目が10%程度になるように調節する方法がおすすめです。
みかんは前述の通り、ビタミンCだけでなく水分も豊富に含まれています。
与え過ぎると下痢になるおそれがあります。
また、食物繊維も多いため、消化しにくいという側面もあります。
そのため、消化されずにうんちに混ざって出てくるという話もあります。
下痢や消化不良を起こさないためにも、与え過ぎには十分注意してください。
食べすぎを防ぐためにもトッピングやおやつにとどめることをおすすめします。
目安としては犬が1日に必要とするエネルギーの10%程度に収まるようにしましょう。
ドッグフードとの栄養バランスも考えながら取り入れてください。
ただし、みかんはカロリーが低めなので10%で計算すると量が多すぎ、お腹を壊す原因になりかねません。
必要なフード量の見た目が10%程度になるように調節する方法がおすすめです。
果実部分のみを与える
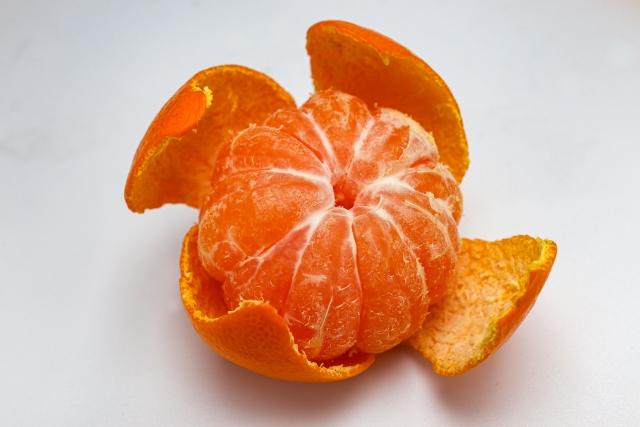 みかんの果実や薄皮には中毒性はないものの、外皮や種などには中毒性のある物質が含まれています。
与えるときは、皮や種の部分を取り除くのを忘れないようにしてください。
ちなみに、みかんに関わらず、柑橘系全般の外皮には、犬にとって中毒性のあるソラレンという物質が含まれています。
過剰摂取することで、嘔吐や下痢などの症状が現れる可能性があるので、与える際には外皮をむき、果実部分だけを与えるようにしましょう。
みかんの果実や薄皮には中毒性はないものの、外皮や種などには中毒性のある物質が含まれています。
与えるときは、皮や種の部分を取り除くのを忘れないようにしてください。
ちなみに、みかんに関わらず、柑橘系全般の外皮には、犬にとって中毒性のあるソラレンという物質が含まれています。
過剰摂取することで、嘔吐や下痢などの症状が現れる可能性があるので、与える際には外皮をむき、果実部分だけを与えるようにしましょう。
アレルギー
犬のなかにはみかんにアレルギーをもつ子もいます。
与えるときは、少量ずつ、様子を見ながらにしましょう。
万が一体調を崩した場合は、すぐに獣医師に相談してください。
病気
「心臓病」や「腎臓病」「腎不全」「癌」など「持病のある犬」「薬を飲んでいる犬」「療法食を食べている犬」は、みかんを与える前に必ずかかりつけの獣医師に相談してください。
みかんの成分(特にカリウム)が薬と作用したり、病状に影響を与えたりする可能性も考えられます。
犬にみかんの加工品を与えても大丈夫?
 みかんの缶詰やゼリー・ジュース等の加工品には砂糖が多く含まれていることがあるため、愛犬には与えないようにしましょう。
与える場合には、加工していないみかんを適量与えるのが安心です。
・みかんゼリー
・みかんジュース
・オレンジジュース
・冷凍みかん
・みかんアイス
などには注意が必要です。
みかんの缶詰やゼリー・ジュース等の加工品には砂糖が多く含まれていることがあるため、愛犬には与えないようにしましょう。
与える場合には、加工していないみかんを適量与えるのが安心です。
・みかんゼリー
・みかんジュース
・オレンジジュース
・冷凍みかん
・みかんアイス
などには注意が必要です。
グレープフルーツなどほかの柑橘類は食べられる?
 オレンジやグレープフルーツをはじめとする柑橘類は、犬が食べても問題はないですが、消化に良くないので熱心に与える必要はありません。
また、薬を服用中の犬にはグレープフルーツを食べさせないでください。
「フラノクマリン」という成分によって薬の分解が遅くなり、薬が効きすぎてしまう恐れがあります。
オレンジやグレープフルーツをはじめとする柑橘類は、犬が食べても問題はないですが、消化に良くないので熱心に与える必要はありません。
また、薬を服用中の犬にはグレープフルーツを食べさせないでください。
「フラノクマリン」という成分によって薬の分解が遅くなり、薬が効きすぎてしまう恐れがあります。
子犬や老犬にみかんを与えても大丈夫?
 離乳した子犬ならみかんを与えても大丈夫です。
ただ、酸味が強く、胃を荒らすこともありますので、様子を見ながら与え、量もほんの少しにしましょう。
また、「老犬」にはみかんの絞り汁を与えると食べやすくなります。
いずれの場合も、下痢や嘔吐、軟便が見られたらみかんを与えるのをやめて、動物病院を受診してください。
そのほか、シニア犬や薬を服用している犬の場合も、ビタミンCが不足しがちだと言われています。
犬がシニア世代に入っている、もしくは薬を服用させているという場合は、みかんを与えてみましょう。
ただし、薬を服用している場合は、食べ合わせの問題があるため、一度かかりつけの獣医師に相談してください。
離乳した子犬ならみかんを与えても大丈夫です。
ただ、酸味が強く、胃を荒らすこともありますので、様子を見ながら与え、量もほんの少しにしましょう。
また、「老犬」にはみかんの絞り汁を与えると食べやすくなります。
いずれの場合も、下痢や嘔吐、軟便が見られたらみかんを与えるのをやめて、動物病院を受診してください。
そのほか、シニア犬や薬を服用している犬の場合も、ビタミンCが不足しがちだと言われています。
犬がシニア世代に入っている、もしくは薬を服用させているという場合は、みかんを与えてみましょう。
ただし、薬を服用している場合は、食べ合わせの問題があるため、一度かかりつけの獣医師に相談してください。
まとめ
 みかんのメリットや与え方の注意点などをご紹介しました。
注意事項を押さえれば、犬にみかんを与えることは問題ありません。
ただし、主食はあくまでもドッグフードなどであり、みかんを主食にしないように注意しましょう。
食べさせる場合には、まずは少量のみ・果肉部分のみをおやつとしてあげてください。
愛犬の様子をきちんと観察しつつ、最適なあげ方をするようにしましょう!
みかんのメリットや与え方の注意点などをご紹介しました。
注意事項を押さえれば、犬にみかんを与えることは問題ありません。
ただし、主食はあくまでもドッグフードなどであり、みかんを主食にしないように注意しましょう。
食べさせる場合には、まずは少量のみ・果肉部分のみをおやつとしてあげてください。
愛犬の様子をきちんと観察しつつ、最適なあげ方をするようにしましょう!
犬はもやしを食べてもOK
犬にもやしを食べせるのは大丈夫です!
もやしは低価格で、飼い主にとっても魅力的な野菜と言えます。
ですが、少し注意したいのが「生では食べさせない方がいい」ということ。
人間でも、もやしを生で食べることはありませんよね?
海外では生でもやしを食べる地域もあるようですが、それは生で食べることを前提に育てられているからであり、日本ではおすすめされていません。
ワンちゃんに食べさせるときは、安全性や消化のしやすさなどを考えて、軽く茹でて食べさせるようにして下さいね!
犬がもやしを食べるメリットや栄養効果
 犬にとってももやしを食べることにはいくつかのメリットがあります。
ここからは、もやしが犬にもたらす栄養素やメリットを見ていきましょう!
犬にとってももやしを食べることにはいくつかのメリットがあります。
ここからは、もやしが犬にもたらす栄養素やメリットを見ていきましょう!
食物繊維のおかげで快便・快腸に!
まず最初のメリットは「快便・快腸」です。
もやしには、豊富な食物繊維が含まれています。
食物繊維には、腸内環境を改善してくれ、便の量を増やしたり、便通をスムーズにしてくれるという働きが!
もし愛犬が便秘気味なのであれば、ぜひ食べさせてあげて下さいね!
いっぱい食べても低カロリー
次のメリットは「低カロリー」ということ。
もやしは、実に約95%が水分であると言われています!
そのため、キャベツと同様にダイエット中のワンちゃんのご飯のかさましとして使用することができます。
たくさん食べても太らない!これがもやしなのです。
アミノ酸が豊富
次に紹介するのは「アミノ酸」が入っているということ。
先ほど紹介したように、もやしの約95%は水分と言われています。
そのため、多くの栄養効果は期待できませんが、アミノ酸が入っているため疲労回復や老化防止に効果的という側面もあります。
犬がもやしを食べる際の与え方や適量
 ここからは、犬にもやしを食べさせるときの正しい与え方や適量を見ていきましょう。
基本的には、もやしは与えても大丈夫な野菜ではありますが、正しい知識を持って、ワンちゃんの健康を気遣ってあげましょうね!
ここからは、犬にもやしを食べさせるときの正しい与え方や適量を見ていきましょう。
基本的には、もやしは与えても大丈夫な野菜ではありますが、正しい知識を持って、ワンちゃんの健康を気遣ってあげましょうね!
アレルギーに注意して少量から与える
もやしに限らず、犬の中には特定の食材でアレルギー反応を起こしてしまう子もいます。
これは、もやしも例外ではなく、無難そうに思えても、ワンちゃんによってはアレルギー反応が起きる可能性が!
初めてもやしを食べさせる時には「まずは少量」「万が一に備えいつでも病院に行ける時に」この2つを守りましょう。
適量はどのくらい?
次に注意したいのは「適量」です。
1日にワンちゃんにもやしを与えられる量は「1日の食事量の2割以下」とされています。
これは、おやつやご飯のトッピングとしてのもやしを使用したときの全量です。
具体的には、下記のような量が適量とされています。
茹でたもやしを1日に与えれる目安量
・超小型犬(2kg程度)…333g(1袋)
・小型犬(3~5kg程度)…425~623g(1.5~2袋)
・中型犬(6~15kg程度)…715~1423g(2~4袋)
・大型犬(20~30kg程度)…1765~2393g(5~7袋)
ご飯のトッピングとしてもやしを使用した場合は、ご飯の量もその分、減らすなどはしなくてはいけません。
上の目安量も参考にしながら、適切な量を食べさせてあげて下さいね!
犬がもやしを食べる際の注意点
 最後に、ワンちゃんにもやしを食べさせるときの注意点を解説します。
低価格でヘルシーだからと、どんどん食べさせるのではなく、飼い主さんがしっかり注意点を守って与えて下さいね!
最後に、ワンちゃんにもやしを食べさせるときの注意点を解説します。
低価格でヘルシーだからと、どんどん食べさせるのではなく、飼い主さんがしっかり注意点を守って与えて下さいね!
もやしは腐りやすい
もやしは他の野菜よりも新鮮さが重視されます。
腐るのも早く、万が一腐ったもやしをワンちゃんに与えてしまった場合、ワンちゃんはお腹を壊すハメに。
もやしを犬に与える時には、出来るだけ新鮮なものを使うようにしましょう!
もやしでお腹がいっぱいになる
先ほど紹介したように、もやしはご飯のかさましに使えるほどお腹を満たしてくれる野菜。
「低カロリーだから、ダイエットのために」と食べさせることもありますが、その一方で、エネルギーの源であるフードの方を食べなくなってしまう可能性もあります。
愛犬の様子を見ながら、フードと両立させることができるだけの適量を食べさせるようにしましょう!
まとめ
この記事では、犬はもやしを食べても大丈夫なのか?をテーマに、もやしの栄養素や与える時の注意点について解説しました。
ヘルシーで低価格と、ワンちゃんにとっても飼い主にとっても魅力的な野菜ですが、注意点もあります。
ぜひ、この記事を参考にしながらワンちゃんに食べさせてあげて下さいね!
犬は茄子を食べてもOK
犬に茄子を食べさせるのは大丈夫です!
ワンちゃんの体の毒になるようなものは入っていないので、基本的には生でも加熱してでも問題ありません。
ですが、注意したいことが一つあります。
それは「茎や葉」は大量に食べさせないということです。
茄子には天然毒素の「アルカロイド」という物質が含まれています。
それほど危険なものではないのですが、大量に摂取してしまうと下痢や嘔吐といった症状を引き起こすことも。
茄子の茎や葉は、特にこのアルカイドという毒素が多く含まれていると言われているため、大量の茎や葉は食べさせない方が良いでしょう!
犬が茄子を食べる際の栄養素やメリット
 では、犬にとって茄子を食べるメリットはあるのでしょうか?
実は茄子はワンちゃんにとってメリットとなる栄養素がいっぱい含まれているんです。
ここからは、茄子によって犬にもたらされる「栄養とメリット」を見ていきましょう。
では、犬にとって茄子を食べるメリットはあるのでしょうか?
実は茄子はワンちゃんにとってメリットとなる栄養素がいっぱい含まれているんです。
ここからは、茄子によって犬にもたらされる「栄養とメリット」を見ていきましょう。
ナスの主な栄養素は?
茄子に含まれる栄養素には以下のようなものがあります。
・カリウム
・アントシアニン
・コリン
・ナスニン(ポリフェノール)
・食物繊維
茄子の93%は水分で構成されているため、ビタミン類はあまりありません。
その一方で、カリウム、ナスニンを代表とした豊富な栄養素がたくさん含まれています。
カリウムによる血圧の低下
カリウムには、血圧を下げる作用があります。
そのため、血圧が少し高めなワンちゃんにはぜひおすすめです。
ただし、腎臓病を患っているワンちゃんはカリウムの量を制限しないといけない場合があるので注意が必要。
また、カリウムには利尿作用があり、体の老廃物を出してくれるというメリットもあります。
ナスニンによる体の酸化防止
茄子に含まれる「ナスニン」もワンちゃんにとって摂取するメリットがあります。
ナスニンは、ポリフェノールの一種で、茄子の皮の部分に多く含まれており、抗酸化作用があり、ガン予防になると言われています。
先ほど「茎や皮に注意」と紹介しましたが、少量であれば問題ありません。
この他にも、茄子に含まれる栄養素コリンによる認知症予防、水分の多さから夏バテ対策にといった食べるメリットというのが多数存在します。
犬が茄子を食べる際のおすすめな食べさせ方
 では、ここからは実際にワンちゃんに茄子を食べさせる時のおすすめの食べさせ方を見ていきましょう!
これを真似すれば、茄子の栄養をしっかりワンちゃんに届けることができますよ!
では、ここからは実際にワンちゃんに茄子を食べさせる時のおすすめの食べさせ方を見ていきましょう!
これを真似すれば、茄子の栄養をしっかりワンちゃんに届けることができますよ!
茄子を食べる際の適量とタイミング
最初のポイントは茄子を食べる時の「適量とタイミング」です。
茄子は、栄養成分に炭水化物や脂質があまりなく、カロリーが比較的低い野菜となります。
そのため、普段の主食にちょっと加えたり、ひとくちおやつとして食べさせてあげると良いでしょう!
もちろん茄子に限らず、カロリーが低いからと食べすぎるとお腹を壊したりするので、この点は他の野菜同様、注意が必要ですよ。
皮がついたまま細かく切る
次に紹介するのは「皮をついたまま」食べさせるです。
最初に紹介しましたが、茄子にはアルカロイドどいう毒素が含まれていますが、これは「大量に摂取すると少し危険」という程度のものです。
その一方で、茄子の皮にはナスニンという大きなメリットを持つ栄養が含まれています。
こちらのもたらすメリットの方が大きいので、ワンちゃんに茄子を食べさせる時は、ぜひ「皮がついたまま細かく切って」食べさせてあげましょう。
【最後に】食物アレルギーには注意
 「食物アレルギー」には注意して下さい!
人間同様に、ワンちゃんにも食物アレルギーを持っている子がいます。
これは茄子だけに限らず他の野菜でも言えることなので、ぜひ覚えておいて下さいね。
そのため、茄子などの野菜を初めて食べさせる時には、少量からスタートし、さらに万が一体調を崩した時のためにかかりつけの動物病院が空いている時間に食べさせるようにしましょう。
「食物アレルギー」には注意して下さい!
人間同様に、ワンちゃんにも食物アレルギーを持っている子がいます。
これは茄子だけに限らず他の野菜でも言えることなので、ぜひ覚えておいて下さいね。
そのため、茄子などの野菜を初めて食べさせる時には、少量からスタートし、さらに万が一体調を崩した時のためにかかりつけの動物病院が空いている時間に食べさせるようにしましょう。
まとめ
この記事では、愛犬に茄子を食べさせても大丈夫なのか?、茄子に含まれる栄養素や食べさせるときの注意点などを紹介しました。
茄子はワンちゃんにとっても非常に栄養のある野菜と言えます。
ぜひ、健康に気をつけながら食べさせてあげて下さい!
犬の肉球のひび割れの原因
あれ?いつの間にか可愛い愛犬の肉球がひび割れていて、心配!という飼い主さんもいらっしゃるのではないでしょうか?
この記事では、犬の肉球のひび割れについて、その原因や対処法を解説します。
それでは早速、ワンちゃんの肉球がひび割れてしまう原因を見ていきましょう!
散歩
 犬の肉球がひび割れてしまう原因の一つに「散歩」があります。
散歩の時に、ワンちゃんの肉球は長時間アスファルトに触れるわけなのですが、これが肉球のひび割れの原因となってしまいます。
理由としては、地面の熱が肉球の水分が吸いとり、さらに、走り回るワンちゃんの場合は肉球がアスファルトで擦れたりするためです。
犬の肉球がひび割れてしまう原因の一つに「散歩」があります。
散歩の時に、ワンちゃんの肉球は長時間アスファルトに触れるわけなのですが、これが肉球のひび割れの原因となってしまいます。
理由としては、地面の熱が肉球の水分が吸いとり、さらに、走り回るワンちゃんの場合は肉球がアスファルトで擦れたりするためです。
季節
「季節の影響」でも肉球はひび割れを起こします。
人間と同様に、冬場など空気が乾燥していると、ワンちゃんの肉球も乾燥状態になります。
また、暖房に長時間あたっていたりした場合もワンちゃんの肉球は乾燥してしまうので注意してあげて下さい。
アトピー性皮膚炎
次に紹介する理由は「アトピー性皮膚炎」です。
アトピー性皮膚炎とは、アレルゲンが体内に入ることで、皮膚のバリア機能が低下し引き起こされる皮膚炎のこと。
アトピー性皮膚炎の症状が肉球に現れた場合、肉球が乾燥しているだけでなく、ゴツゴツと肉球が硬くなってしまう苔癬化(たいせんか)という症状が現れます。
このような症状が現れた場合は病院で診てもらいましょう。
代謝機能の低下
「代謝機能の低下」も肉球がひび割れを起こす理由の一つです。
人間と同様に、犬も歳を取ると、代謝機能が低下します。
これに伴い、体内の水分量が減ってしまい、肉球も乾燥、ひび割れしてしまうのです。
老化は防ぎようがないことなので、シニア犬を飼っている場合はこまめに肉球の状態をチェックしてあげるようにしましょう。
洗いすぎ&拭きすぎ
 汚れや雑菌を落とすのために、まめにワンちゃんの肉球を洗っている、拭いているというあなた!
確かに雑菌の繁殖予防には効果的ですが、肉球のひび割れ対策には良くありません。
というのも、肉球の「洗いすぎ」「拭きすぎ」は、肉球を乾燥させてしまう可能性があるからです。
やりすぎには、くれぐれも注意して下さいね。
汚れや雑菌を落とすのために、まめにワンちゃんの肉球を洗っている、拭いているというあなた!
確かに雑菌の繁殖予防には効果的ですが、肉球のひび割れ対策には良くありません。
というのも、肉球の「洗いすぎ」「拭きすぎ」は、肉球を乾燥させてしまう可能性があるからです。
やりすぎには、くれぐれも注意して下さいね。
犬の肉球のひび割れの治療法
ここまでは、ワンちゃんの肉球がひび割れを起こす様々な原因を紹介しました。
正直なところ、どれも仕方のないことであり、なかなか予防をすることは難しいように思われますが、どうすれば良いのでしょうか?
実は、肉球のひび割れを予防、ケアするグッズが存在します。
例えば、肉球専用の保湿クリームやジェルです。
使い方は簡単で、毎日か数日に1回、肉球に塗ってあげるだけ。
さらに、このような肉球専用のクリームやジェルはワンちゃんが舐めてしまっても大丈夫なような素材で作られています。
冬場や散歩の回数が多いワンチャンにはぜひ、これを塗ってあげましょう!
犬の肉球のひび割れにはワセリンがおすすめ?
 また、犬の肉球のひび割れにはワセリンもおすすめです。
ワセリンは、もともと人間を対象とした保湿剤ですが、これがワンちゃんの肉球にも効果的なのです。
ワセリンを塗ることで、肉球に油膜ができ水分の蒸発を防いでくれます。
中でもおすすめなのは「白色ワセリン」。
白色ワセリンは、不純物の含有量が少なく、さらに匂いもないのでワンちゃんでも安心して使用することができます。
使い方は簡単で、クリーム同様に毎日か数日に1回、肉球に塗ってあげるだけです。
また、犬の肉球のひび割れにはワセリンもおすすめです。
ワセリンは、もともと人間を対象とした保湿剤ですが、これがワンちゃんの肉球にも効果的なのです。
ワセリンを塗ることで、肉球に油膜ができ水分の蒸発を防いでくれます。
中でもおすすめなのは「白色ワセリン」。
白色ワセリンは、不純物の含有量が少なく、さらに匂いもないのでワンちゃんでも安心して使用することができます。
使い方は簡単で、クリーム同様に毎日か数日に1回、肉球に塗ってあげるだけです。
犬の肉球のひび割れに効くクリーム
では、最後にワンちゃんの肉球のひび割れを心配しているあなたに、本当におすすめな「肉球のひび割れ対策グッズ」を3つ紹介します。
悩んでいる飼い主さんは必見ですよ!
プロテクタパッドクリーム
リンク
椿オイルと植物性のスクワランオイル。
無香料、無着色なので、ワンちゃんにストレスを与えることなく使用することができます。
また、肉球だけでなく、ワンちゃんの皮膚全体に使用しても大丈夫なのは嬉しいポイント!
みつばち本舗 みつろうクリーム
リンク
愛犬の肉球の乾燥、ヒビ割れ、アスファルト焼けのケアから、肘タコにまで使える万能クリーム。
天然素材成分を使用しているので、ワンちゃんが舐めても安心です。
また、ティーツリー配合なので殺菌力もあり、散歩終わりにも大活躍してくれます!
ペットクール オーガニックシアバター
リンク
厳選されたオーガニックシアバター配合の肉球クリーム。
ベタつきがなく滑らない、すばやく馴染んで長時間保湿がポイントとなるクリームです。
もちろん、植物エキスなので、舐めても安心!
まとめ
この記事では、犬の肉球のひび割れについて、原因や対策方法を解説しました。
肉球のひび割れはどうしても防ぐのが難しいことでもあるので、日々の徹底的なケアが大切となってきます。
ぜひ、今日紹介したケアグッズなどを使って愛犬を守ってあげて下さいね!
犬の平均睡眠時間とは?
大事にしている愛犬だからこそ、睡眠時間という些細なことでも気になってしまいますよね!
「ずっと寝ているけど、体調でも悪いのかな?」という疑問や、逆に「全然寝てないけど大丈夫?」という疑問を抱く飼い主さんも多いでしょう。
この記事では、そんなワンちゃんの睡眠について深ぼっていきます。
まず、そもそも犬とは平均的にどれくらい寝る生き物なのでしょうか?
成犬の平均睡眠時間
成犬の必要な睡眠時間は、およそ12~15時間とされており、1日の半分以上は眠っていることになります。
また、体が大きな犬になればなるほど睡眠時間は長い傾向にあるとも言われています。
寝過ぎな気もしますが、この長い睡眠がワンちゃんの体を支えているのです。
老犬の平均睡眠時間
では老犬の睡眠時間はどうなのでしょうか?
老犬の場合は、18時間〜19時間が睡眠時間として必要とされています。
歳をとっている犬の場合、やはり若い犬よりも体力の回復に時間がかかってしまうようです。
子犬の平均睡眠時間
さらに長い睡眠時間が必要なのは子犬の場合です。
子犬に必要な睡眠時間は18〜20時間。
子犬の場合は、起きている時には元気に遊び回りエネルギーを使うので、その分、たくさん寝て体力を回復・体を成長させるようです。
「寝る子は育つ」とはこのことですね!
犬種での違いは?
 では、犬種によって必要な睡眠時間は変化するのでしょうか?
先ほど少し紹介しましたが、一般的には体が大きな犬ほど長い睡眠傾向にあると言われています。
例えば、マスティフやセントバーナードなどの超大型犬は、行動するとエネルギーをたくさん使うので、長時間睡眠の傾向にあります。
また、体の大きさ以外にも犬種によって睡眠時間が変化する犬種もいます。
例えば、ボーダーコリーやシベリアンハスキーなどです。
この2犬種は作業犬であり、活動時間を長くするために、睡眠時間が短い傾向があると言われています。
では、犬種によって必要な睡眠時間は変化するのでしょうか?
先ほど少し紹介しましたが、一般的には体が大きな犬ほど長い睡眠傾向にあると言われています。
例えば、マスティフやセントバーナードなどの超大型犬は、行動するとエネルギーをたくさん使うので、長時間睡眠の傾向にあります。
また、体の大きさ以外にも犬種によって睡眠時間が変化する犬種もいます。
例えば、ボーダーコリーやシベリアンハスキーなどです。
この2犬種は作業犬であり、活動時間を長くするために、睡眠時間が短い傾向があると言われています。
犬が睡眠不足になったら…
犬には、人間よりもはるかに長い睡眠時間が必要であることはご理解頂けたでしょうか?
では、もしワンちゃんが何かしらの寝れない原因を抱えてしまい、睡眠不足になってしまうとどうなるのでしょう?
ここからは、ワンチャンに快適な睡眠をとってもらうために飼い主さんが知っておかなければいけないことを解説します。
まずは、睡眠不足によって引き起こされるワンちゃんへの危険を見ていきましょう。
寿命が縮まる
人間もそうですが、睡眠不足が続くと心身ともに疲れきってしまいます。
ワンちゃんも、睡眠不足の状態が続いてしまうと、心身共に疲れてしまい、結果的に寿命を縮めてしまうことがあります。
どんなに愛犬にかまいたくても、大切なパートーナーだからこそ大切な睡眠時間は守ってあげましょう。
ストレス状態
また、睡眠時間が短いとストレスが溜まった状態が続きます。
特に、家にやってきたばかりの子犬などは、突然環境が変化したこと、さらに、居住の変化により質の良い睡眠がとれない日々が続いたりと、強いストレスを抱えることになります。
強いストレスは、飼い主であるあなたの言うことを聞かずに、問題行動を起こす原因にもなるので、注意が必要です。
犬に快適な睡眠を届ける方法は?
犬の睡眠不足が、大変な事を引き起こしてしまうことは分かりましね!
では、実際に犬の睡眠不足を防ぐためにはどうしたら良いのでしょうか?
ここからは、愛犬に快適な睡眠を提供する方法を解説していきます。
快適な温度設定
 まず大切なのが「快適な温度」です。
人間でも寝る時に温度調整は大変ですが、ワンちゃんの場合は自身での体温調整ができないためもっと大変な作業になります。
犬種や年齢によってバラつきがあるので、次に紹介する目安の温度を参考に、愛犬の様子を見ながら調整してあげて下さい。
【参考室温】
〈シングルコート〉
夏季/約22~25度
冬季/約20~25度
〈ダブルコート〉
夏季/約23~26度
冬季/約19~23度
※シングルコート…季節によって毛が生え変わらない犬種
※ダブルコート…季節によって毛が生え変わる犬種
また、老犬や子犬は体温調節が不得意なので、冷えには特に注意してあげましょう!
まず大切なのが「快適な温度」です。
人間でも寝る時に温度調整は大変ですが、ワンちゃんの場合は自身での体温調整ができないためもっと大変な作業になります。
犬種や年齢によってバラつきがあるので、次に紹介する目安の温度を参考に、愛犬の様子を見ながら調整してあげて下さい。
【参考室温】
〈シングルコート〉
夏季/約22~25度
冬季/約20~25度
〈ダブルコート〉
夏季/約23~26度
冬季/約19~23度
※シングルコート…季節によって毛が生え変わらない犬種
※ダブルコート…季節によって毛が生え変わる犬種
また、老犬や子犬は体温調節が不得意なので、冷えには特に注意してあげましょう!
犬が安心できるベッド・寝床の確保
また、犬が安心して熟睡できるような寝床の確保も大切になってきます。
犬にとって安心・快適な寝床の条件とは、
・ちょうど良い固さのベッド
・夏はひんやり、冬はあったか素材のベッド
・地面よりも少し高いところ
・あごを乗せれるマクラ
・リビングなど家族がいるところ
このような事を満たしていると、犬にとって安心・快適な寝床と言えるでしょう。
適度な運動
 適度な運動も愛犬の熟睡を誘うには必要なこととなります。
犬とは元々走り回る動物です。
そのため、運動不足などエネルギーが余っていると、どうしても寝つきが悪くなります。
散歩に連れて行ったり、遊んであげたりと、その犬種によった適切な運動量をクリアできるように工夫をしてあげましょう。
適度な運動も愛犬の熟睡を誘うには必要なこととなります。
犬とは元々走り回る動物です。
そのため、運動不足などエネルギーが余っていると、どうしても寝つきが悪くなります。
散歩に連れて行ったり、遊んであげたりと、その犬種によった適切な運動量をクリアできるように工夫をしてあげましょう。
寝床を清潔にする
また、清潔面も考えて、寝床は定期的に洗濯、日干しなどをしましょう。
皆さんもできる限り、清潔でふかふかなベッドで寝たいですよね?ワンちゃんもそれは同じです!
月に1~2回程度を目安とし、寝床をきれいにしてあげることで、ワンちゃんも快適に眠ることができます。
犬が睡眠中にすぐ起きるのはなぜ?
 「散歩もたくさんした、寝床も気をつけている!なのになんですぐ起きちゃうのー?」なんて疑問を抱えている飼い主さんもいらっしゃるのではないでしょうか?
最後にこの疑問にお応えします!
ワンちゃんが睡眠中にすぐ起きてしまうのは、犬という動物の特性からです。
犬の睡眠は、8割が浅いレム睡眠で、熟睡状態は残りの2割となります。
これは野生の時の名残りで、寝ているというより、体を休ませているため。
なので、すぐに愛犬が起きてしまうからと心配する必要はありません!
「散歩もたくさんした、寝床も気をつけている!なのになんですぐ起きちゃうのー?」なんて疑問を抱えている飼い主さんもいらっしゃるのではないでしょうか?
最後にこの疑問にお応えします!
ワンちゃんが睡眠中にすぐ起きてしまうのは、犬という動物の特性からです。
犬の睡眠は、8割が浅いレム睡眠で、熟睡状態は残りの2割となります。
これは野生の時の名残りで、寝ているというより、体を休ませているため。
なので、すぐに愛犬が起きてしまうからと心配する必要はありません!
まとめ
この記事では「犬の睡眠」をテーマに、犬に必要な睡眠時間、快適な睡眠を届ける方法などを解説しました。
人も犬の睡眠というのはとても大切なことになります。
ぜひ、この記事を参考にあなたの愛犬の睡眠を守ってあげて下さいね!
愛犬に無視される5つの理由
普段あれだけ一緒に遊んでいるのに…
おやつを持っている時は言うことを聞いてくれるのに…
毎日可愛がっているのに…
「どうしてこの子はいきなり無視するの!?」
なんて経験をしたことがある飼い主さんも多いのではないでしょうか?
どんなに毎日大切に思いながら世話をしていても、犬はふと飼い主さんを無視することがあります。
ですが、これはワンちゃんが悪いわけでも、ましてや飼い主であるあなたが悪いわけでもありません!
この記事では、ワンちゃんが飼い主さんを無視してしまう理由と、飼い主であるあなたはどうしたらいいのかを解説します。
まずは、ワンちゃんがあなたを無視する理由を見ていきましょう!
恐怖や興奮で動けない
 ワンちゃんは恐怖や過度な興奮といった強い感情を抱くと、正常な判断ができなくなってしまうことがあります。
人間も同様ですよね。
そんな時、あなたが何を指示してもワンちゃんは言うことを効かず、飼い主からすれば無視されたという状態になります。
ですが決してワンちゃんに悪気があるわけではありません。
もし、犬が何かに怖がっているような時には、無理強いしないで、犬を安心させるよう努めましょう。
そうすることで、もっとあなたとワンちゃんの心の距離は近づくはずです。
ワンちゃんは恐怖や過度な興奮といった強い感情を抱くと、正常な判断ができなくなってしまうことがあります。
人間も同様ですよね。
そんな時、あなたが何を指示してもワンちゃんは言うことを効かず、飼い主からすれば無視されたという状態になります。
ですが決してワンちゃんに悪気があるわけではありません。
もし、犬が何かに怖がっているような時には、無理強いしないで、犬を安心させるよう努めましょう。
そうすることで、もっとあなたとワンちゃんの心の距離は近づくはずです。
飼い主を魅力的と思っていない
あなたにとって魅力的な人と、そうでない人が目の前にいた時、二人のうちどちらとより話したいと思いますか?
もちろん、魅力的な人と話したいでしょう。
非常に残念なことに、ワンちゃんも同じことを考え、行動してしまいます。
つまり、あなたの魅力が足りていないということです。
飼い主よりも他の人や犬に関心があったり、おもちゃ遊びが楽しかったりすると、飼い主を無視することがあります。
また、場合によっては飼い主の元へ行くと叱られると思って、近づかないワンちゃんもいます。
普段から叱ってばかりだなという場合には、褒めてあげる努力もしっかりとしていきましょう。
“犬語”を話していない
 人間同士では、共通の言語があるため、言葉でコミュニケーションをとることができますが、人と犬ではこの共通言語がありません。
つまり、そもそも愛犬が飼い主さんの言葉を理解できないことは当たり前のことなのです。
それでも賢い犬は「飼い主さんの声」だけを頼りに、自身の経験から”自分の名前”や”してはいけないこと”などを覚えていきます。
それにもかかわらず、飼い主さんが普段と「違う言葉」や「異なるイントネーション」でしつけをしたり、「小さく聞き取りづらい声」で話しかけたらどうでしょうか?
当然ワンちゃんにとっては理解が難しく、反応のしようがありません。これが、愛犬があなたを無視する原因です。
これを防ぐためには、「いつも通りに」「ハッキリと」愛犬に話しかけてあげることが必要になってきます。
さらに工夫としてジェスチャーを加えると、ワンちゃんも多少声が聞き取りづらくても「これをすればいいんだ!」と判断がつきやすくなります。
人間同士では、共通の言語があるため、言葉でコミュニケーションをとることができますが、人と犬ではこの共通言語がありません。
つまり、そもそも愛犬が飼い主さんの言葉を理解できないことは当たり前のことなのです。
それでも賢い犬は「飼い主さんの声」だけを頼りに、自身の経験から”自分の名前”や”してはいけないこと”などを覚えていきます。
それにもかかわらず、飼い主さんが普段と「違う言葉」や「異なるイントネーション」でしつけをしたり、「小さく聞き取りづらい声」で話しかけたらどうでしょうか?
当然ワンちゃんにとっては理解が難しく、反応のしようがありません。これが、愛犬があなたを無視する原因です。
これを防ぐためには、「いつも通りに」「ハッキリと」愛犬に話しかけてあげることが必要になってきます。
さらに工夫としてジェスチャーを加えると、ワンちゃんも多少声が聞き取りづらくても「これをすればいいんだ!」と判断がつきやすくなります。
聴力の低下
犬があなたを無視する理由のひとつに「ワンちゃんの聴力の低下」もあります。
飼い主にとっては考えたくないことですが、もしいつも通りに大きな声で呼んでも、犬が全く反応しなかったら、聴力の低下を疑い、病院で一度診てもらいましょう。
疲労で適切な判断ができない
 強い恐怖や興奮時と同様に、犬は精神的な疲労(ストレス)や肉体的な疲労を感じると、適切な判断ができなかったり、反応が鈍いことがあります。
犬はこのような時には、様々なサインを出します。
例えば、散歩中の疲れであればジッと飼い主さんを見つめたり、立ち止まったりです。
また、あくびにも「ストレスを感じたので、気分転換をしよう!」というワンちゃんの気持ちが隠されています。
このようなサインを見つけた時には、犬をしっかりと休ませてあげることが大切です。
強い恐怖や興奮時と同様に、犬は精神的な疲労(ストレス)や肉体的な疲労を感じると、適切な判断ができなかったり、反応が鈍いことがあります。
犬はこのような時には、様々なサインを出します。
例えば、散歩中の疲れであればジッと飼い主さんを見つめたり、立ち止まったりです。
また、あくびにも「ストレスを感じたので、気分転換をしよう!」というワンちゃんの気持ちが隠されています。
このようなサインを見つけた時には、犬をしっかりと休ませてあげることが大切です。
愛犬に無視される時の正しい接し方
愛犬があなたを無視する理由には、様々なことがあることが分かりました。
それでも、やっぱり愛犬には無視されずに好かれたいものですよね…。
そんなあなたに嬉しいお知らせが…!
一度無視されたからといって、手遅れではありません。あなたも努力次第で愛犬に好かれる方法があるんです。
信頼関係を築く
 まずは改めて、愛犬との信頼関係を築いていきましょう。
無視されることが続く時には、犬との根本的な関係を見直すことが必要です。
その中で特に重要なことは犬を叱らないこと。
できないことを叱るのではなく、褒めて伸ばすことで愛犬はあなたのことを怖がったり、嫌いになったりすることはありません。
犬がお手などのトリックを何かをしたら、ベタ褒めしてあげましょう!
まずは改めて、愛犬との信頼関係を築いていきましょう。
無視されることが続く時には、犬との根本的な関係を見直すことが必要です。
その中で特に重要なことは犬を叱らないこと。
できないことを叱るのではなく、褒めて伸ばすことで愛犬はあなたのことを怖がったり、嫌いになったりすることはありません。
犬がお手などのトリックを何かをしたら、ベタ褒めしてあげましょう!
好感度を上げる
また、シンプルに高感度を上げるというのも大切になってきます。
動物は、自分がしたことに対して何か良いことが起きればそれを経験とし、繰り返し同じ行動を行います。
その逆も然りで、嫌なことが起きればその行動は避けるようになります。
もし、あなたが愛犬に無視されているのであれば、あなたの元に行くことにネガティブな印象を持っているのかもしれません。
そんな時は、呼んだらお菓子をあげるなどの工夫をして、あなたに近づく=良いことが起きると認識させるようにしましょう。
まとめ
この記事では、愛犬に無視される理由とその解決策を紹介しました。
ワンちゃんは様々な理由で飼い主であるあなたを無視することがありますが、これはワンちゃんが悪いのではありません。
むしろその解決策は、あなたがもっと寄り添ってあげること。
ぜひ、この記事を参考に愛犬と良好な関係を築いていって下さいね。
 「歯磨きをしないといけないのは分かってるんだけど…噛まれちゃう…」という飼い主さんも多いはず。
そう、犬はそんな簡単に歯磨きをさせてはくれないんです。
では、犬が歯磨きをさせてくれない理由は何にあるのでしょうか?
「歯磨きをしないといけないのは分かってるんだけど…噛まれちゃう…」という飼い主さんも多いはず。
そう、犬はそんな簡単に歯磨きをさせてはくれないんです。
では、犬が歯磨きをさせてくれない理由は何にあるのでしょうか?
 犬が歯磨きを嫌がる理由はお分かり頂けたでしょうか?
それでも、飼い主である以上、愛犬の歯磨きは避けては通れない道。
ここからは「でも、どうしたらいいの?」という飼い主さんのために、まずは歯磨きを始める手順を紹介します。
犬が歯磨きを嫌がる理由はお分かり頂けたでしょうか?
それでも、飼い主である以上、愛犬の歯磨きは避けては通れない道。
ここからは「でも、どうしたらいいの?」という飼い主さんのために、まずは歯磨きを始める手順を紹介します。
 それでもまだ「歯磨きを嫌がる、させてくれない!」という場合もあるかと思います。
そんな飼い主さんに、ここからは、歯磨きを嫌がる犬に歯磨きをするコツを5つ紹介します!
「どうしても歯磨きができない」という飼い主さんは必読ですよ!
それでもまだ「歯磨きを嫌がる、させてくれない!」という場合もあるかと思います。
そんな飼い主さんに、ここからは、歯磨きを嫌がる犬に歯磨きをするコツを5つ紹介します!
「どうしても歯磨きができない」という飼い主さんは必読ですよ!
 歯磨きアイテムの中で最もメジャーなのが、犬用歯磨きガムです。
これは、ワンちゃんがおやつと思って、ガムを食べているだけで、歯磨きができる優れもの。
飼い主さんにとって、時間も労力もかからないが嬉しいポイントです。
ワンちゃんに歯磨きガムを与えるときは、犬の口幅より、少しだけ長めの物を選んで、噛ませてあげて下さい。
歯磨きアイテムの中で最もメジャーなのが、犬用歯磨きガムです。
これは、ワンちゃんがおやつと思って、ガムを食べているだけで、歯磨きができる優れもの。
飼い主さんにとって、時間も労力もかからないが嬉しいポイントです。
ワンちゃんに歯磨きガムを与えるときは、犬の口幅より、少しだけ長めの物を選んで、噛ませてあげて下さい。
 また、犬用おもちゃの中にも、歯のケアをすることができるものがあります。
歯磨きの頻度やレベルに心配があるという飼い主さんは、歯磨きガム同様に、こういった歯のケアをできるおもちゃを持つのもおすすめ。
ワンちゃんの噛む力や体格、犬種などに合わせて、おもちゃを選んであげて下さいね!
また、犬用おもちゃの中にも、歯のケアをすることができるものがあります。
歯磨きの頻度やレベルに心配があるという飼い主さんは、歯磨きガム同様に、こういった歯のケアをできるおもちゃを持つのもおすすめ。
ワンちゃんの噛む力や体格、犬種などに合わせて、おもちゃを選んであげて下さいね!
 では、実際にどのような「目やに」であれば病気のサインを疑わなくてはいけないのでしょうか?
ここからは「目やにの色」「猫ちゃんの症状」から、病気のサインである可能性があるもの見ていきましょう。
では、実際にどのような「目やに」であれば病気のサインを疑わなくてはいけないのでしょうか?
ここからは「目やにの色」「猫ちゃんの症状」から、病気のサインである可能性があるもの見ていきましょう。
 ここからは、猫の目やにの取り方を紹介します。
目元を触られるのを嫌がる猫も多いですが、目やにを放置していると、猫も痒がり、二次的に皮膚などを傷つけてしまうこともあります。
猫は自分ではめやにを取ることができないので、飼い主であるなたがしっかりと取ってあげましょう!
ここからは、猫の目やにの取り方を紹介します。
目元を触られるのを嫌がる猫も多いですが、目やにを放置していると、猫も痒がり、二次的に皮膚などを傷つけてしまうこともあります。
猫は自分ではめやにを取ることができないので、飼い主であるなたがしっかりと取ってあげましょう!
 また、目やにをとる時は、猫をリラックスさせた状態にすることも大切です。
突然目の付近を触ると猫ちゃんもびっくりしてしまいます!
そうなると、当然猫ちゃんも大人しく目やにを拭き取らせてはくれません。
最初は、体や顔まわりを撫でながら、猫ちゃんがリラックスしてきたなと感じたら、撫でる動作のようにスムーズに拭き取ってあげましょう。
また、目やにをとる時は、猫をリラックスさせた状態にすることも大切です。
突然目の付近を触ると猫ちゃんもびっくりしてしまいます!
そうなると、当然猫ちゃんも大人しく目やにを拭き取らせてはくれません。
最初は、体や顔まわりを撫でながら、猫ちゃんがリラックスしてきたなと感じたら、撫でる動作のようにスムーズに拭き取ってあげましょう。
 まずは、先住猫(今すでに家にいる猫)が新入りの猫に寛容かを見極めましょう。
例えば、先住猫が飼い主さんを独り占めしたいタイプの場合、新入り猫を受け入れることはストレスになります。
そのストレスから体調を崩したり、今までしなかったような悪さをしてしまう子も…。
多頭飼いが難しそうであれば、先住猫のために諦めるか、相性の良い猫を迎えるなど、考慮や工夫が必要です。
まずは、先住猫(今すでに家にいる猫)が新入りの猫に寛容かを見極めましょう。
例えば、先住猫が飼い主さんを独り占めしたいタイプの場合、新入り猫を受け入れることはストレスになります。
そのストレスから体調を崩したり、今までしなかったような悪さをしてしまう子も…。
多頭飼いが難しそうであれば、先住猫のために諦めるか、相性の良い猫を迎えるなど、考慮や工夫が必要です。
 では、ここからは実際に猫を多頭飼いするときに、どのように新入り猫を選べばいいのかを、相性という観点から紹介します。
新入り猫を探しているという飼い主さんは必読ですよ!
では、ここからは実際に猫を多頭飼いするときに、どのように新入り猫を選べばいいのかを、相性という観点から紹介します。
新入り猫を探しているという飼い主さんは必読ですよ!
 では、猫の年齢によって相性は変わってくるのでしょうか?
「子猫と成猫」の場合は、成猫の性格次第では比較的、良い相性が望めます。
成猫は自身の性格が確立しており、温厚な性格であれば、新入り子猫に対しては寛容に受け入れやすいからです。
一方で「シニア猫と子猫」になると注意が必要にもなります。
シニア猫は、毎日、新入りの子猫が遊びまわっているとそれをストレスに感じてしまうことがあるからです。
また、猫の年齢を見た時に、比較的同じ歳くらいの方が良いという見解もあります。
では、猫の年齢によって相性は変わってくるのでしょうか?
「子猫と成猫」の場合は、成猫の性格次第では比較的、良い相性が望めます。
成猫は自身の性格が確立しており、温厚な性格であれば、新入り子猫に対しては寛容に受け入れやすいからです。
一方で「シニア猫と子猫」になると注意が必要にもなります。
シニア猫は、毎日、新入りの子猫が遊びまわっているとそれをストレスに感じてしまうことがあるからです。
また、猫の年齢を見た時に、比較的同じ歳くらいの方が良いという見解もあります。
 次に、どのような性格の先住猫であれば、多頭飼いに向いているかを見ていきましょう。
先住猫が甘えん坊、または寂しがり屋な性格の場合は多頭飼いに向いていると言えます。
その子がお留守番などが多いのであれば尚更です。
先住猫も家に1匹でいるのは寂しいもの。
そんな中、もう1匹遊び相手にでもなってくれる猫が現れれば、不安やストレスも解消されます。
場合によっては、むしろ多頭飼いをしてあげた方が良いかもしれません!
次に、どのような性格の先住猫であれば、多頭飼いに向いているかを見ていきましょう。
先住猫が甘えん坊、または寂しがり屋な性格の場合は多頭飼いに向いていると言えます。
その子がお留守番などが多いのであれば尚更です。
先住猫も家に1匹でいるのは寂しいもの。
そんな中、もう1匹遊び相手にでもなってくれる猫が現れれば、不安やストレスも解消されます。
場合によっては、むしろ多頭飼いをしてあげた方が良いかもしれません!
 また、鼻水に伴う症状から猫にひそむ病気を見つけることもできます。
ここからは鼻水と合わせて確認しておきたい他の症状を見ていきましょう。
また、鼻水に伴う症状から猫にひそむ病気を見つけることもできます。
ここからは鼻水と合わせて確認しておきたい他の症状を見ていきましょう。
 猫の鼻水が出ているのに、それを放ったらかしにするわけにはいきませんよね?
ここからは、鼻水が出ている時にどのような対処や治し方があるのかを紹介します。
まずはこれを実践してみましょう。
猫の鼻水が出ているのに、それを放ったらかしにするわけにはいきませんよね?
ここからは、鼻水が出ている時にどのような対処や治し方があるのかを紹介します。
まずはこれを実践してみましょう。
 人が食べている食べ物の中にも、犬が食べて大丈夫な食べ物があります。
ではみかんはどうでしょうか?
結論、みかんは犬も食べることができます!
しかしいくつか注意しなければいけない点もあります。
最初に、みかんを食べるメリットと犬にみかんを与えるときの注意点をご紹介します。
みかんを食べさせる時は、メリットと注意点を把握した上で与えるようにしましょう。
人が食べている食べ物の中にも、犬が食べて大丈夫な食べ物があります。
ではみかんはどうでしょうか?
結論、みかんは犬も食べることができます!
しかしいくつか注意しなければいけない点もあります。
最初に、みかんを食べるメリットと犬にみかんを与えるときの注意点をご紹介します。
みかんを食べさせる時は、メリットと注意点を把握した上で与えるようにしましょう。
 みかんには100gあたり35mgのビタミンCが含まれるため、人間のビタミンC補給には適した果物です。
しかし犬は、ビタミンCを食事で摂取しなくても自身の体内で生成することができるため、積極的に与える必要はありません。
ただ、犬は年齢を重ねるごとにビタミンを生成する力が不足すると考えられており、さらに夏場はビタミンCが不足しやすい季節となります。
高齢の犬や、夏場には、みかんを与えてビタミンCを補給してあげるのも良いかもしれませんね。
また、みかんにはビタミンCの他にも健康維持が期待できる成分がたくさん含まれています。
みかんには100gあたり35mgのビタミンCが含まれるため、人間のビタミンC補給には適した果物です。
しかし犬は、ビタミンCを食事で摂取しなくても自身の体内で生成することができるため、積極的に与える必要はありません。
ただ、犬は年齢を重ねるごとにビタミンを生成する力が不足すると考えられており、さらに夏場はビタミンCが不足しやすい季節となります。
高齢の犬や、夏場には、みかんを与えてビタミンCを補給してあげるのも良いかもしれませんね。
また、みかんにはビタミンCの他にも健康維持が期待できる成分がたくさん含まれています。
 柑橘系には疲労回復効果が期待できる栄養素「クエン酸」が多く含まれています。
細胞が酸化し、それを修復させようとする状態が疲労に繋がります。
この細胞修復にクエン酸が使われるため、疲労回復につながると考えられています。
柑橘系には疲労回復効果が期待できる栄養素「クエン酸」が多く含まれています。
細胞が酸化し、それを修復させようとする状態が疲労に繋がります。
この細胞修復にクエン酸が使われるため、疲労回復につながると考えられています。
 犬にみかんを与えることは問題ないですが、以下の点を守らないと愛犬を危険な目に合わせてしまう可能性もあります。
必ずみかんを与える際は注意点があることを把握するようにしましょう。
犬にみかんを与えることは問題ないですが、以下の点を守らないと愛犬を危険な目に合わせてしまう可能性もあります。
必ずみかんを与える際は注意点があることを把握するようにしましょう。
 みかんは前述の通り、ビタミンCだけでなく水分も豊富に含まれています。
与え過ぎると下痢になるおそれがあります。
また、食物繊維も多いため、消化しにくいという側面もあります。
そのため、消化されずにうんちに混ざって出てくるという話もあります。
下痢や消化不良を起こさないためにも、与え過ぎには十分注意してください。
食べすぎを防ぐためにもトッピングやおやつにとどめることをおすすめします。
目安としては犬が1日に必要とするエネルギーの10%程度に収まるようにしましょう。
ドッグフードとの栄養バランスも考えながら取り入れてください。
ただし、みかんはカロリーが低めなので10%で計算すると量が多すぎ、お腹を壊す原因になりかねません。
必要なフード量の見た目が10%程度になるように調節する方法がおすすめです。
みかんは前述の通り、ビタミンCだけでなく水分も豊富に含まれています。
与え過ぎると下痢になるおそれがあります。
また、食物繊維も多いため、消化しにくいという側面もあります。
そのため、消化されずにうんちに混ざって出てくるという話もあります。
下痢や消化不良を起こさないためにも、与え過ぎには十分注意してください。
食べすぎを防ぐためにもトッピングやおやつにとどめることをおすすめします。
目安としては犬が1日に必要とするエネルギーの10%程度に収まるようにしましょう。
ドッグフードとの栄養バランスも考えながら取り入れてください。
ただし、みかんはカロリーが低めなので10%で計算すると量が多すぎ、お腹を壊す原因になりかねません。
必要なフード量の見た目が10%程度になるように調節する方法がおすすめです。
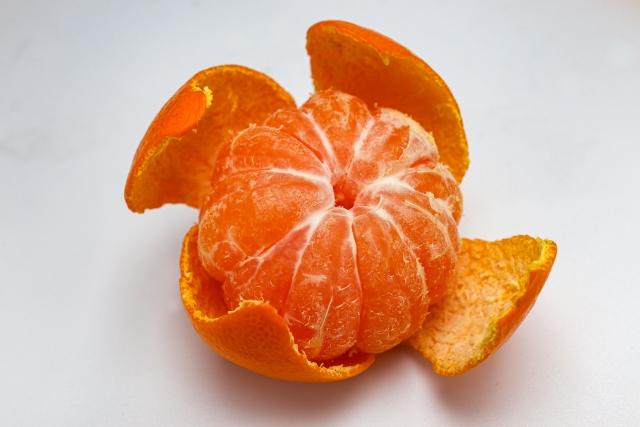 みかんの果実や薄皮には中毒性はないものの、外皮や種などには中毒性のある物質が含まれています。
与えるときは、皮や種の部分を取り除くのを忘れないようにしてください。
ちなみに、みかんに関わらず、柑橘系全般の外皮には、犬にとって中毒性のあるソラレンという物質が含まれています。
過剰摂取することで、嘔吐や下痢などの症状が現れる可能性があるので、与える際には外皮をむき、果実部分だけを与えるようにしましょう。
みかんの果実や薄皮には中毒性はないものの、外皮や種などには中毒性のある物質が含まれています。
与えるときは、皮や種の部分を取り除くのを忘れないようにしてください。
ちなみに、みかんに関わらず、柑橘系全般の外皮には、犬にとって中毒性のあるソラレンという物質が含まれています。
過剰摂取することで、嘔吐や下痢などの症状が現れる可能性があるので、与える際には外皮をむき、果実部分だけを与えるようにしましょう。
 みかんの缶詰やゼリー・ジュース等の加工品には砂糖が多く含まれていることがあるため、愛犬には与えないようにしましょう。
与える場合には、加工していないみかんを適量与えるのが安心です。
・みかんゼリー
・みかんジュース
・オレンジジュース
・冷凍みかん
・みかんアイス
などには注意が必要です。
みかんの缶詰やゼリー・ジュース等の加工品には砂糖が多く含まれていることがあるため、愛犬には与えないようにしましょう。
与える場合には、加工していないみかんを適量与えるのが安心です。
・みかんゼリー
・みかんジュース
・オレンジジュース
・冷凍みかん
・みかんアイス
などには注意が必要です。
 オレンジやグレープフルーツをはじめとする柑橘類は、犬が食べても問題はないですが、消化に良くないので熱心に与える必要はありません。
また、薬を服用中の犬にはグレープフルーツを食べさせないでください。
「フラノクマリン」という成分によって薬の分解が遅くなり、薬が効きすぎてしまう恐れがあります。
オレンジやグレープフルーツをはじめとする柑橘類は、犬が食べても問題はないですが、消化に良くないので熱心に与える必要はありません。
また、薬を服用中の犬にはグレープフルーツを食べさせないでください。
「フラノクマリン」という成分によって薬の分解が遅くなり、薬が効きすぎてしまう恐れがあります。
 離乳した子犬ならみかんを与えても大丈夫です。
ただ、酸味が強く、胃を荒らすこともありますので、様子を見ながら与え、量もほんの少しにしましょう。
また、「老犬」にはみかんの絞り汁を与えると食べやすくなります。
いずれの場合も、下痢や嘔吐、軟便が見られたらみかんを与えるのをやめて、動物病院を受診してください。
そのほか、シニア犬や薬を服用している犬の場合も、ビタミンCが不足しがちだと言われています。
犬がシニア世代に入っている、もしくは薬を服用させているという場合は、みかんを与えてみましょう。
ただし、薬を服用している場合は、食べ合わせの問題があるため、一度かかりつけの獣医師に相談してください。
離乳した子犬ならみかんを与えても大丈夫です。
ただ、酸味が強く、胃を荒らすこともありますので、様子を見ながら与え、量もほんの少しにしましょう。
また、「老犬」にはみかんの絞り汁を与えると食べやすくなります。
いずれの場合も、下痢や嘔吐、軟便が見られたらみかんを与えるのをやめて、動物病院を受診してください。
そのほか、シニア犬や薬を服用している犬の場合も、ビタミンCが不足しがちだと言われています。
犬がシニア世代に入っている、もしくは薬を服用させているという場合は、みかんを与えてみましょう。
ただし、薬を服用している場合は、食べ合わせの問題があるため、一度かかりつけの獣医師に相談してください。
 みかんのメリットや与え方の注意点などをご紹介しました。
注意事項を押さえれば、犬にみかんを与えることは問題ありません。
ただし、主食はあくまでもドッグフードなどであり、みかんを主食にしないように注意しましょう。
食べさせる場合には、まずは少量のみ・果肉部分のみをおやつとしてあげてください。
愛犬の様子をきちんと観察しつつ、最適なあげ方をするようにしましょう!
みかんのメリットや与え方の注意点などをご紹介しました。
注意事項を押さえれば、犬にみかんを与えることは問題ありません。
ただし、主食はあくまでもドッグフードなどであり、みかんを主食にしないように注意しましょう。
食べさせる場合には、まずは少量のみ・果肉部分のみをおやつとしてあげてください。
愛犬の様子をきちんと観察しつつ、最適なあげ方をするようにしましょう!  犬にとってももやしを食べることにはいくつかのメリットがあります。
ここからは、もやしが犬にもたらす栄養素やメリットを見ていきましょう!
犬にとってももやしを食べることにはいくつかのメリットがあります。
ここからは、もやしが犬にもたらす栄養素やメリットを見ていきましょう!
 ここからは、犬にもやしを食べさせるときの正しい与え方や適量を見ていきましょう。
基本的には、もやしは与えても大丈夫な野菜ではありますが、正しい知識を持って、ワンちゃんの健康を気遣ってあげましょうね!
ここからは、犬にもやしを食べさせるときの正しい与え方や適量を見ていきましょう。
基本的には、もやしは与えても大丈夫な野菜ではありますが、正しい知識を持って、ワンちゃんの健康を気遣ってあげましょうね!
 最後に、ワンちゃんにもやしを食べさせるときの注意点を解説します。
低価格でヘルシーだからと、どんどん食べさせるのではなく、飼い主さんがしっかり注意点を守って与えて下さいね!
最後に、ワンちゃんにもやしを食べさせるときの注意点を解説します。
低価格でヘルシーだからと、どんどん食べさせるのではなく、飼い主さんがしっかり注意点を守って与えて下さいね!
 では、犬にとって茄子を食べるメリットはあるのでしょうか?
実は茄子はワンちゃんにとってメリットとなる栄養素がいっぱい含まれているんです。
ここからは、茄子によって犬にもたらされる「栄養とメリット」を見ていきましょう。
では、犬にとって茄子を食べるメリットはあるのでしょうか?
実は茄子はワンちゃんにとってメリットとなる栄養素がいっぱい含まれているんです。
ここからは、茄子によって犬にもたらされる「栄養とメリット」を見ていきましょう。
 では、ここからは実際にワンちゃんに茄子を食べさせる時のおすすめの食べさせ方を見ていきましょう!
これを真似すれば、茄子の栄養をしっかりワンちゃんに届けることができますよ!
では、ここからは実際にワンちゃんに茄子を食べさせる時のおすすめの食べさせ方を見ていきましょう!
これを真似すれば、茄子の栄養をしっかりワンちゃんに届けることができますよ!
 「食物アレルギー」には注意して下さい!
人間同様に、ワンちゃんにも食物アレルギーを持っている子がいます。
これは茄子だけに限らず他の野菜でも言えることなので、ぜひ覚えておいて下さいね。
そのため、茄子などの野菜を初めて食べさせる時には、少量からスタートし、さらに万が一体調を崩した時のためにかかりつけの動物病院が空いている時間に食べさせるようにしましょう。
「食物アレルギー」には注意して下さい!
人間同様に、ワンちゃんにも食物アレルギーを持っている子がいます。
これは茄子だけに限らず他の野菜でも言えることなので、ぜひ覚えておいて下さいね。
そのため、茄子などの野菜を初めて食べさせる時には、少量からスタートし、さらに万が一体調を崩した時のためにかかりつけの動物病院が空いている時間に食べさせるようにしましょう。
 犬の肉球がひび割れてしまう原因の一つに「散歩」があります。
散歩の時に、ワンちゃんの肉球は長時間アスファルトに触れるわけなのですが、これが肉球のひび割れの原因となってしまいます。
理由としては、地面の熱が肉球の水分が吸いとり、さらに、走り回るワンちゃんの場合は肉球がアスファルトで擦れたりするためです。
犬の肉球がひび割れてしまう原因の一つに「散歩」があります。
散歩の時に、ワンちゃんの肉球は長時間アスファルトに触れるわけなのですが、これが肉球のひび割れの原因となってしまいます。
理由としては、地面の熱が肉球の水分が吸いとり、さらに、走り回るワンちゃんの場合は肉球がアスファルトで擦れたりするためです。
 汚れや雑菌を落とすのために、まめにワンちゃんの肉球を洗っている、拭いているというあなた!
確かに雑菌の繁殖予防には効果的ですが、肉球のひび割れ対策には良くありません。
というのも、肉球の「洗いすぎ」「拭きすぎ」は、肉球を乾燥させてしまう可能性があるからです。
やりすぎには、くれぐれも注意して下さいね。
汚れや雑菌を落とすのために、まめにワンちゃんの肉球を洗っている、拭いているというあなた!
確かに雑菌の繁殖予防には効果的ですが、肉球のひび割れ対策には良くありません。
というのも、肉球の「洗いすぎ」「拭きすぎ」は、肉球を乾燥させてしまう可能性があるからです。
やりすぎには、くれぐれも注意して下さいね。
 また、犬の肉球のひび割れにはワセリンもおすすめです。
ワセリンは、もともと人間を対象とした保湿剤ですが、これがワンちゃんの肉球にも効果的なのです。
ワセリンを塗ることで、肉球に油膜ができ水分の蒸発を防いでくれます。
中でもおすすめなのは「白色ワセリン」。
白色ワセリンは、不純物の含有量が少なく、さらに匂いもないのでワンちゃんでも安心して使用することができます。
使い方は簡単で、クリーム同様に毎日か数日に1回、肉球に塗ってあげるだけです。
また、犬の肉球のひび割れにはワセリンもおすすめです。
ワセリンは、もともと人間を対象とした保湿剤ですが、これがワンちゃんの肉球にも効果的なのです。
ワセリンを塗ることで、肉球に油膜ができ水分の蒸発を防いでくれます。
中でもおすすめなのは「白色ワセリン」。
白色ワセリンは、不純物の含有量が少なく、さらに匂いもないのでワンちゃんでも安心して使用することができます。
使い方は簡単で、クリーム同様に毎日か数日に1回、肉球に塗ってあげるだけです。
 では、犬種によって必要な睡眠時間は変化するのでしょうか?
先ほど少し紹介しましたが、一般的には体が大きな犬ほど長い睡眠傾向にあると言われています。
例えば、マスティフやセントバーナードなどの超大型犬は、行動するとエネルギーをたくさん使うので、長時間睡眠の傾向にあります。
また、体の大きさ以外にも犬種によって睡眠時間が変化する犬種もいます。
例えば、ボーダーコリーやシベリアンハスキーなどです。
この2犬種は作業犬であり、活動時間を長くするために、睡眠時間が短い傾向があると言われています。
では、犬種によって必要な睡眠時間は変化するのでしょうか?
先ほど少し紹介しましたが、一般的には体が大きな犬ほど長い睡眠傾向にあると言われています。
例えば、マスティフやセントバーナードなどの超大型犬は、行動するとエネルギーをたくさん使うので、長時間睡眠の傾向にあります。
また、体の大きさ以外にも犬種によって睡眠時間が変化する犬種もいます。
例えば、ボーダーコリーやシベリアンハスキーなどです。
この2犬種は作業犬であり、活動時間を長くするために、睡眠時間が短い傾向があると言われています。
 まず大切なのが「快適な温度」です。
人間でも寝る時に温度調整は大変ですが、ワンちゃんの場合は自身での体温調整ができないためもっと大変な作業になります。
犬種や年齢によってバラつきがあるので、次に紹介する目安の温度を参考に、愛犬の様子を見ながら調整してあげて下さい。
【参考室温】
〈シングルコート〉
夏季/約22~25度
冬季/約20~25度
〈ダブルコート〉
夏季/約23~26度
冬季/約19~23度
※シングルコート…季節によって毛が生え変わらない犬種
※ダブルコート…季節によって毛が生え変わる犬種
また、老犬や子犬は体温調節が不得意なので、冷えには特に注意してあげましょう!
まず大切なのが「快適な温度」です。
人間でも寝る時に温度調整は大変ですが、ワンちゃんの場合は自身での体温調整ができないためもっと大変な作業になります。
犬種や年齢によってバラつきがあるので、次に紹介する目安の温度を参考に、愛犬の様子を見ながら調整してあげて下さい。
【参考室温】
〈シングルコート〉
夏季/約22~25度
冬季/約20~25度
〈ダブルコート〉
夏季/約23~26度
冬季/約19~23度
※シングルコート…季節によって毛が生え変わらない犬種
※ダブルコート…季節によって毛が生え変わる犬種
また、老犬や子犬は体温調節が不得意なので、冷えには特に注意してあげましょう!
 適度な運動も愛犬の熟睡を誘うには必要なこととなります。
犬とは元々走り回る動物です。
そのため、運動不足などエネルギーが余っていると、どうしても寝つきが悪くなります。
散歩に連れて行ったり、遊んであげたりと、その犬種によった適切な運動量をクリアできるように工夫をしてあげましょう。
適度な運動も愛犬の熟睡を誘うには必要なこととなります。
犬とは元々走り回る動物です。
そのため、運動不足などエネルギーが余っていると、どうしても寝つきが悪くなります。
散歩に連れて行ったり、遊んであげたりと、その犬種によった適切な運動量をクリアできるように工夫をしてあげましょう。
 「散歩もたくさんした、寝床も気をつけている!なのになんですぐ起きちゃうのー?」なんて疑問を抱えている飼い主さんもいらっしゃるのではないでしょうか?
最後にこの疑問にお応えします!
ワンちゃんが睡眠中にすぐ起きてしまうのは、犬という動物の特性からです。
犬の睡眠は、8割が浅いレム睡眠で、熟睡状態は残りの2割となります。
これは野生の時の名残りで、寝ているというより、体を休ませているため。
なので、すぐに愛犬が起きてしまうからと心配する必要はありません!
「散歩もたくさんした、寝床も気をつけている!なのになんですぐ起きちゃうのー?」なんて疑問を抱えている飼い主さんもいらっしゃるのではないでしょうか?
最後にこの疑問にお応えします!
ワンちゃんが睡眠中にすぐ起きてしまうのは、犬という動物の特性からです。
犬の睡眠は、8割が浅いレム睡眠で、熟睡状態は残りの2割となります。
これは野生の時の名残りで、寝ているというより、体を休ませているため。
なので、すぐに愛犬が起きてしまうからと心配する必要はありません!
 ワンちゃんは恐怖や過度な興奮といった強い感情を抱くと、正常な判断ができなくなってしまうことがあります。
人間も同様ですよね。
そんな時、あなたが何を指示してもワンちゃんは言うことを効かず、飼い主からすれば無視されたという状態になります。
ですが決してワンちゃんに悪気があるわけではありません。
もし、犬が何かに怖がっているような時には、無理強いしないで、犬を安心させるよう努めましょう。
そうすることで、もっとあなたとワンちゃんの心の距離は近づくはずです。
ワンちゃんは恐怖や過度な興奮といった強い感情を抱くと、正常な判断ができなくなってしまうことがあります。
人間も同様ですよね。
そんな時、あなたが何を指示してもワンちゃんは言うことを効かず、飼い主からすれば無視されたという状態になります。
ですが決してワンちゃんに悪気があるわけではありません。
もし、犬が何かに怖がっているような時には、無理強いしないで、犬を安心させるよう努めましょう。
そうすることで、もっとあなたとワンちゃんの心の距離は近づくはずです。
 人間同士では、共通の言語があるため、言葉でコミュニケーションをとることができますが、人と犬ではこの共通言語がありません。
つまり、そもそも愛犬が飼い主さんの言葉を理解できないことは当たり前のことなのです。
それでも賢い犬は「飼い主さんの声」だけを頼りに、自身の経験から”自分の名前”や”してはいけないこと”などを覚えていきます。
それにもかかわらず、飼い主さんが普段と「違う言葉」や「異なるイントネーション」でしつけをしたり、「小さく聞き取りづらい声」で話しかけたらどうでしょうか?
当然ワンちゃんにとっては理解が難しく、反応のしようがありません。これが、愛犬があなたを無視する原因です。
これを防ぐためには、「いつも通りに」「ハッキリと」愛犬に話しかけてあげることが必要になってきます。
さらに工夫としてジェスチャーを加えると、ワンちゃんも多少声が聞き取りづらくても「これをすればいいんだ!」と判断がつきやすくなります。
人間同士では、共通の言語があるため、言葉でコミュニケーションをとることができますが、人と犬ではこの共通言語がありません。
つまり、そもそも愛犬が飼い主さんの言葉を理解できないことは当たり前のことなのです。
それでも賢い犬は「飼い主さんの声」だけを頼りに、自身の経験から”自分の名前”や”してはいけないこと”などを覚えていきます。
それにもかかわらず、飼い主さんが普段と「違う言葉」や「異なるイントネーション」でしつけをしたり、「小さく聞き取りづらい声」で話しかけたらどうでしょうか?
当然ワンちゃんにとっては理解が難しく、反応のしようがありません。これが、愛犬があなたを無視する原因です。
これを防ぐためには、「いつも通りに」「ハッキリと」愛犬に話しかけてあげることが必要になってきます。
さらに工夫としてジェスチャーを加えると、ワンちゃんも多少声が聞き取りづらくても「これをすればいいんだ!」と判断がつきやすくなります。
 強い恐怖や興奮時と同様に、犬は精神的な疲労(ストレス)や肉体的な疲労を感じると、適切な判断ができなかったり、反応が鈍いことがあります。
犬はこのような時には、様々なサインを出します。
例えば、散歩中の疲れであればジッと飼い主さんを見つめたり、立ち止まったりです。
また、あくびにも「ストレスを感じたので、気分転換をしよう!」というワンちゃんの気持ちが隠されています。
このようなサインを見つけた時には、犬をしっかりと休ませてあげることが大切です。
強い恐怖や興奮時と同様に、犬は精神的な疲労(ストレス)や肉体的な疲労を感じると、適切な判断ができなかったり、反応が鈍いことがあります。
犬はこのような時には、様々なサインを出します。
例えば、散歩中の疲れであればジッと飼い主さんを見つめたり、立ち止まったりです。
また、あくびにも「ストレスを感じたので、気分転換をしよう!」というワンちゃんの気持ちが隠されています。
このようなサインを見つけた時には、犬をしっかりと休ませてあげることが大切です。
 まずは改めて、愛犬との信頼関係を築いていきましょう。
無視されることが続く時には、犬との根本的な関係を見直すことが必要です。
その中で特に重要なことは犬を叱らないこと。
できないことを叱るのではなく、褒めて伸ばすことで愛犬はあなたのことを怖がったり、嫌いになったりすることはありません。
犬がお手などのトリックを何かをしたら、ベタ褒めしてあげましょう!
まずは改めて、愛犬との信頼関係を築いていきましょう。
無視されることが続く時には、犬との根本的な関係を見直すことが必要です。
その中で特に重要なことは犬を叱らないこと。
できないことを叱るのではなく、褒めて伸ばすことで愛犬はあなたのことを怖がったり、嫌いになったりすることはありません。
犬がお手などのトリックを何かをしたら、ベタ褒めしてあげましょう!