猫が日向ぼっこをする理由と効果
 猫は暖かい場所が大好きですよね。
特に日向ぼっこをしている猫を見ることが多く、とても気持ち良さそうにしている姿はほんと可愛いです。
ですが、猫にとって日向ぼっこは気持ちいいだけではなく、良いことがたくさんあることがわかりました。
そこでここでは、猫が日向ぼっこをする理由と効果についてご紹介していきます。
猫は暖かい場所が大好きですよね。
特に日向ぼっこをしている猫を見ることが多く、とても気持ち良さそうにしている姿はほんと可愛いです。
ですが、猫にとって日向ぼっこは気持ちいいだけではなく、良いことがたくさんあることがわかりました。
そこでここでは、猫が日向ぼっこをする理由と効果についてご紹介していきます。
体内時計を調整できる
動物のほとんどは人間のように時間を見ることができないため、同じ時間に目が覚めたり、空腹を訴えたりする時間が同じなのは体内時計を頼りに生活しているということになります。
日向ぼっこをすると太陽の高さや方向を無意識にキャッチすることができ、季節や時間を体感して、体内時計のずれを調節しているのです。
良質な睡眠がとれる
 日向ぼっこをしていると、猫は気持ち良さそうにウトウトしていますよね。
それは、暖かい日差しが布団のように心地よく、体が温まって眠くなってくるからです。
猫はもともと、体力温存のためによく寝る動物ですが、暖かい場所ではより睡眠の質が高まり、起きると活発になれると言われています。
日向ぼっこをしていると、猫は気持ち良さそうにウトウトしていますよね。
それは、暖かい日差しが布団のように心地よく、体が温まって眠くなってくるからです。
猫はもともと、体力温存のためによく寝る動物ですが、暖かい場所ではより睡眠の質が高まり、起きると活発になれると言われています。
精神を安定させる
猫も人間と同じで、太陽の光を浴びると幸せホルモンと言われている「セロトニン」の分泌が活性化されると言われています。
このセロトニンには、精神状態を整えてくれる作用があるとされており、分泌量が増えると情緒が安定するというデータも。
なので、猫がリラックスして日向ぼっこができるよう、窓際に外をよく眺められるような猫タワーを置いたり、よりくつげるよう猫ベッドや、ラックを設置するなどして愛猫のためのスペースを確保したあげることがおすすめです!
免疫力が高まる
 日向ぼっこをすると、体の体温があがり、全身の血流の流れが良くなります。
それによって、新陳代謝が活発になり、免疫力がアップ。
免疫力が高まるということは、病気を予防できたり長生きにも繋がるといっても過言ではないでしょう。
日向ぼっこをすると、体の体温があがり、全身の血流の流れが良くなります。
それによって、新陳代謝が活発になり、免疫力がアップ。
免疫力が高まるということは、病気を予防できたり長生きにも繋がるといっても過言ではないでしょう。
骨が強くなる
猫は日光を浴びると、皮脂腺でビタミンDが作られ、それを毛づくろいすることで、体内に取り込めるという説があります。
ビタミンDには、骨づくりに欠かせないカルシウムの吸収をサポートしてくれる大事な栄養素です。
ぜひ、日向ぼっこ中の愛猫の毛づくろいに注目してみてくださいね!
毛の手触りがフワフワになる
 湿気を多く含んだ被毛は、ジットリ、ベットリとして綺麗好きな猫にとっては不快以外のなにものでもありません。
そこで、日向ぼっこをすることで、毛に含まれる水分が蒸発してフワフワになるのです。
また、湿気によるジメジメが解消されることで、皮膚病にもかかりにくくなると言われています。
湿気を多く含んだ被毛は、ジットリ、ベットリとして綺麗好きな猫にとっては不快以外のなにものでもありません。
そこで、日向ぼっこをすることで、毛に含まれる水分が蒸発してフワフワになるのです。
また、湿気によるジメジメが解消されることで、皮膚病にもかかりにくくなると言われています。
被毛の消毒が可能
布団を干して日光消毒をしたり、医療器具を紫外線消毒器で殺菌するのと同じで、日向ぼっこをすると、日光に含まれる紫外線によって被毛が消毒されます。
また、ダニなどの寄生虫や体毛に付着したさまざまな細菌が繁殖しにくくなるのです。
綺麗好きな猫には嬉しい効果ですよね!
猫が日向ぼっこをする時の注意点
 猫が日向ぼっこを好きなことがわかりましたが、メリットばかりではなく注意しなければいけないこともあります。
猫自身が自分では気づけないことも多いので、飼い主さんが日頃から日向ぼっこをしている様子をしっかり観察してあげることが大切です。
ここでは猫が日向ぼっこをする際の注意点をご紹介します。
猫が日向ぼっこを好きなことがわかりましたが、メリットばかりではなく注意しなければいけないこともあります。
猫自身が自分では気づけないことも多いので、飼い主さんが日頃から日向ぼっこをしている様子をしっかり観察してあげることが大切です。
ここでは猫が日向ぼっこをする際の注意点をご紹介します。
熱中症
猫は比較的暑さに強いのですが、熱中症にならないわけではありません。
特に湿度が高く、気温が高い日本の夏には猫も熱中症を発症するリスクが高くなります。
猫は多少暑くでも日向ぼっこをする続ける傾向があり、その最中に知らず知らず熱中症になってしまうことも。
そのようなことがないように以下のような対策を取るようにしてあげてください。
・クーラーで室温の管理をする(28度程度が理想)
・レースのカーテンをつけることによって直射日光をさける
・水をすぐに飲める環境を作る
特に猫は、水が冷たかったり遠い場所にあったりなど少し気に入らない点があると、水を飲まないことがあります。
愛猫がお気に入りの日向ぼっこの場所から動きたがらない場合は、近くに飲み水を用意してあげると良いでしょう。
日向に置いた水は水温でぬるくなり猫が好んで飲んでくれます。
ただし、赤カビなどが発生しやすいため、毎日水を取り替えて容器をキレイに洗ってあげてくださいね。
紫外線
 皮膚がんを気にして紫外線対策をしている方も多いかと思いますが、猫も同様に皮膚がんになる可能性があります。
猫は頭や首の色素の薄い部位に発生する傾向があり、特に白猫に注意が必要です。
窓ガラスにUVカット機能のあるシートを貼ったり、窓ガラスそのものをUVカット機能のあるものにしたりするなどの工夫をしてあげてくださいね。
皮膚がんを気にして紫外線対策をしている方も多いかと思いますが、猫も同様に皮膚がんになる可能性があります。
猫は頭や首の色素の薄い部位に発生する傾向があり、特に白猫に注意が必要です。
窓ガラスにUVカット機能のあるシートを貼ったり、窓ガラスそのものをUVカット機能のあるものにしたりするなどの工夫をしてあげてくださいね。
高層症候群
猫の高層症候群とは、猫が2階以上の高い場所から落ちてケガをしてしまうことを言います。
別名「キャット・フライング・シンドローム」とも呼ばれていますが、猫は高い場所から飛び降りることはできても、建物の2階以上の高さから落ちてしまうことは普通ではありません。
なぜ数十メートル以上の高さから突然飛び降りてしまうのかの原因は、はっきりわかっていませんが、いくら猫といってもそんな高さから飛び降りれば死んでしまいます。
猫にとってお気に入りの場所だったとしても、2階以上のベランダやバルコニーからは出さないようにしましょう。
猫は高い場所から落ちても平気だと思っている人もいますが、そのようなことは決してありませんので、重傷を負ったり最悪の場合命を落とす可能性があります。
猫の日向ぼっこを室内飼いで行う方法
 野良猫の場合は、常に外にいるのでいつでも自由に日向ぼっこができますが、室内飼いの場合は、どうやって日向ぼっこをさせてあげればいいかと悩んでいる方もいるでしょう。
ここでは、猫の日向ぼっこを室内飼いで行う方法についてご紹介していきます。
野良猫の場合は、常に外にいるのでいつでも自由に日向ぼっこができますが、室内飼いの場合は、どうやって日向ぼっこをさせてあげればいいかと悩んでいる方もいるでしょう。
ここでは、猫の日向ぼっこを室内飼いで行う方法についてご紹介していきます。
猫がくつろげる場所を窓際につくる
室内でも猫に日向ぼっこをさせてあげる場合は、まず陽の当たる場に猫がくつろげる場所を作ってあげましょう。
窓が高くて床まで日光が入りにくい時には、棚やキャットタワーなどを置いて、窓と同じ高さに猫が行けるようにしてあげてください。
窓から外も見えるので、猫にとっては嬉しい場所となるでしょう。
クッションや箱などを置いたり、または物を片付けてスペースを作ったりして、猫がくつろいで寝転がったり座ったりできるようにしてあげるのもいいですね。
さらには、窓に直接つけることができる猫用のハンモックが販売されているので、家具を置けない時でも猫に日向ぼっこを楽しんでもらうことができます。
猫用の日向ぼっこの場所を用意する
 猫の日向ぼっこは、できればガラス越しではなく、日光浴ができるようにしたいもの。
網戸にして脱走防止の柵をつけておき、日光浴させるという方法も良いでしょう。
ベランダに直接出すのは危険ですが、ネットを張って脱走できないようにしたうえで出したり、大型ケージごとベランダや縁側に出したりといった方法で、ガラス越しでなくても日光を浴びることができます。
どんな状況でも外に出すことで、脱走や他の猫との接触の危険があるので、飼い主さんが必ず見ているようにしてあげてください。
猫の日向ぼっこは、できればガラス越しではなく、日光浴ができるようにしたいもの。
網戸にして脱走防止の柵をつけておき、日光浴させるという方法も良いでしょう。
ベランダに直接出すのは危険ですが、ネットを張って脱走できないようにしたうえで出したり、大型ケージごとベランダや縁側に出したりといった方法で、ガラス越しでなくても日光を浴びることができます。
どんな状況でも外に出すことで、脱走や他の猫との接触の危険があるので、飼い主さんが必ず見ているようにしてあげてください。
陽の当たる部屋の出入りを自由にする
猫が日向ぼっことをするには、陽の当たる場所に猫がいけるようにしなければいけません。
ただし、窓際だと何かの拍子で猫が脱走してしまう可能性もあるので、開けないように気をつけるだけではなく、脱走防止の網やネットをつけるなどしておくと良いでしょう。
猫が入ってもよい場所には、尖ったものや誤飲しそうな細かいもの、猫がかじってしまう観葉植物などを置かないようにして、心配なく猫に日向ぼっこをさせられるようにしてあげてください。
陽の当たる部屋はカーテンで締め切らないようにして、猫が日光浴ができるようにしてあげると良いでしょう。
そして、猫が自分の意思で日陰に行ったり、別の部屋に行ったりできるように、閉じ込めないようにしてくださいね。
まとめ
今回は猫の日向ぼっこについてご紹介してきました。
猫が日向ぼっこをしている姿を見ていると思わずこちらも眠たくなってしまうくらい気持ち良い表情をしていますが、注意しなければいけない点もあるので、日頃から飼い主さんの様子観察が必要です。
猫がキックする5つの理由
 猫が甘えてくる姿はとっても可愛いですが、高速でキックされるのは可愛いとばかりも言っていられず、「痛い!」と叫んでしまうこともあると思います。
猫キックは一体どんな時に、どんな気持ちでしてくるのでしょうか?
猫の気持ちから、5つの理由が考えられるのでそれを紹介します。
猫が甘えてくる姿はとっても可愛いですが、高速でキックされるのは可愛いとばかりも言っていられず、「痛い!」と叫んでしまうこともあると思います。
猫キックは一体どんな時に、どんな気持ちでしてくるのでしょうか?
猫の気持ちから、5つの理由が考えられるのでそれを紹介します。
理由①:構って欲しいと伝えている
猫キックをする理由でまず考えられるのは、「飼い主さん、構って!」という気持ちです。
何かに集中する飼い主さんや、出掛けようとする飼い主さんに、「こっちを見て!」と気を引くために、猫キックを繰り出すのです。
これを聞いただけでも、可愛くてもうメロメロになってしまいそうですね。
飼い主さんの気を引くときのキックはある程度加減をしていて、甘噛みもしてきたりします。
「ねぇねぇ、見て。」という猫の甘えたい気持ちが現れているのだと思うとむげにはできません。
理由②:やめて欲しいという意思表示
 2つ目の理由は①とは反対のものです。
人間に触られたくないなどの「嫌!」という気持ちをキックで示すことがあります。
表情や態度、声など色々なものを使い、猫は「やめて」と気持ちを伝えますが、しつこく嫌なことをされると、猫キックをしてその人物を攻撃するようです。
やめてほしいというキックは猫が本気でやっている時なので、怒っていてかなり痛いことが多いです。
しっぽをバタバタ振ったり、耳を横にしていたりすることもあるので、そういう時は猫をそっとしておいてあげてください。
2つ目の理由は①とは反対のものです。
人間に触られたくないなどの「嫌!」という気持ちをキックで示すことがあります。
表情や態度、声など色々なものを使い、猫は「やめて」と気持ちを伝えますが、しつこく嫌なことをされると、猫キックをしてその人物を攻撃するようです。
やめてほしいというキックは猫が本気でやっている時なので、怒っていてかなり痛いことが多いです。
しっぽをバタバタ振ったり、耳を横にしていたりすることもあるので、そういう時は猫をそっとしておいてあげてください。
理由③:遊びで狩りの練習をしている
元々猫は狩猟動物です。
たとえ家猫として生まれ、暮らしている時間が長くても、狩猟本能はなくなりません。
ですから、猫キックを完全にやめさせることは不可能です。
子猫の時からキックをして遊びで狩りの練習をすることは大切な一面でもあります。
最初は可愛い遊びでも興奮してきて、つい強くキックすることもあります。
さらに興奮すると噛み付くこともあるので、適度なところでやめさせてクールダウンするということも大切です。
理由④:運動不足やストレスから
 飼い主さんに対してではなく、何か物に対してキックを行うこともあります。
特に家の中にいる若い猫にはよく見られます。
クッションやソファなどに向けてキックを繰り返している場合は、運動やストレス解消のために体を動かしていると考えられます。
つまり退屈しているわけです。
人間のやんちゃな子供が家の中で暴れてしまうことがありますね。
それと同じ状態ですので、余っている体力を発散させてあげると解決することが多いです。
飼い主さんに対してではなく、何か物に対してキックを行うこともあります。
特に家の中にいる若い猫にはよく見られます。
クッションやソファなどに向けてキックを繰り返している場合は、運動やストレス解消のために体を動かしていると考えられます。
つまり退屈しているわけです。
人間のやんちゃな子供が家の中で暴れてしまうことがありますね。
それと同じ状態ですので、余っている体力を発散させてあげると解決することが多いです。
理由⑤:猫同士で行うコミュニケーション
最後は一緒に飼われている猫同士でキックをしている場合です。
猫同士の蹴り合いだと、ただコミュニケーションを取っているだけの可能性があります。
特に仔猫は狩猟本能の名残で、遊びのつもりでキックを行うことがあります。
また、猫同士が若くてお互いに運動不足の解消のため、プロレスごっこのように遊んでいるとも考えられます。
楽しいコミュニケーションならよいのですが、興奮しすぎて喧嘩になる場合もあるので要注意です。
猫が怪我をしないようによく観察してください。
猫キックをやめさせたい時の対処法
 猫キックの理由はさまざまあることがわかりました。
甘えているだけでも飼い主さんが痛いことも多く、猫のストレスや興奮状態を考えるとやめさせる手立ても知っておきたいものです。
次の対処法は効果があるので、困った際には一度試してみてください。
猫キックの理由はさまざまあることがわかりました。
甘えているだけでも飼い主さんが痛いことも多く、猫のストレスや興奮状態を考えるとやめさせる手立ても知っておきたいものです。
次の対処法は効果があるので、困った際には一度試してみてください。
しつこく構うのは止める
猫の方からじゃれついてきたとしても、途中で飽きてしまうと、猫は構われるのを嫌がり、解放されたくて猫キックをしてきます。
なので、しつこく構うのは止めましょう。
猫は気が変わりやすいので、その気分を察知してあげるのも飼い主さんの役目かもしれません。
あまりしつこいと、猫との関係性が悪くなることがあります。
キックが出たら、「おしまい」のサインと思いましょう。
キックされる前にエネルギーを使わせる
 特に若い猫の場合、運動不足や退屈を紛らわせるためにキックをしていることが多いです。
エネルギーがあり余っており、それを発散する機会がないのはかわいそうです。
猫キックが出る前に運動や遊びで解消させるということができれば、ストレスにもならずに済みます。
元気な猫の場合、1日に30分は遊んで運動しないとストレスに繋がると言われていますので、キャットタワーを作ってあげたり、飼い主さんとの遊び時間を増やしたりしてみるとエネルギーが発散されるでしょう。
特に若い猫の場合、運動不足や退屈を紛らわせるためにキックをしていることが多いです。
エネルギーがあり余っており、それを発散する機会がないのはかわいそうです。
猫キックが出る前に運動や遊びで解消させるということができれば、ストレスにもならずに済みます。
元気な猫の場合、1日に30分は遊んで運動しないとストレスに繋がると言われていますので、キャットタワーを作ってあげたり、飼い主さんとの遊び時間を増やしたりしてみるとエネルギーが発散されるでしょう。
おもちゃ(けりぐるみ)を与える
エネルギーの発散とも似ていますが、けりぐるみとなるおもちゃを与えてキックさせてしまうという方法があります。
人間の代わりとしてけりぐるみなどのおもちゃを与えることで、猫キックをする標的が人間からおもちゃに切り替わるので、怪我のリスクも減ります。
狩りの練習という猫の本能によることも多いので、専用グッズが販売されているものを活用している人も多いです。
猫が抱きつきやすい形をしていて、中にマタタビの実や粉末が入っているものや興味を引く音が出る仕掛けがあるものなど、工夫されています。
そのおもちゃを使って遊んであげるのもおすすめです。
顔に息を吹きかける
 猫は顔に息を吹きかけられると、強い嫌悪感を覚えます。
そのため、猫にキックされて痛いと思った時は、猫の顔に息を吹きかけて、猫キックを防ぎましょう。
息を吹きかけるという方法は、いたずらをやめさせるときにも有効なので覚えておくと役に立ちます。
驚いてキックをやめたり、その場から去っていったりします。
でも、何回も息を吹きかけていると猫に嫌われるので、気をつけてください。
猫は顔に息を吹きかけられると、強い嫌悪感を覚えます。
そのため、猫にキックされて痛いと思った時は、猫の顔に息を吹きかけて、猫キックを防ぎましょう。
息を吹きかけるという方法は、いたずらをやめさせるときにも有効なので覚えておくと役に立ちます。
驚いてキックをやめたり、その場から去っていったりします。
でも、何回も息を吹きかけていると猫に嫌われるので、気をつけてください。
まとめ
猫キックをする心理と対処法を紹介しました。
猫は飼い主さんと遊びたいという気持ちの表れの他、本能からの狩りの練習や運動不足の発散をしていることが多いのです。
キックで痛い目にあう前にけりぐるみを与えてあげたり、一緒に遊んであげたりすることでストレス発散にも繋がります。
対処法を参考に、愛猫の心理を察知して関係性をより高めてください。
猫に野菜は必要?
 大切なペットである猫の健康には気をつけたいですね。
食事内容にも注意して、野菜を食べたほうが良いのかどうか悩んでいる人もいると思います。
でも、結論から言って猫に野菜は必要ではありません。
完全な肉食動物ですので、野菜を食べなくても健康上問題は起こりません。
その点について詳しく、また食べても良い野菜・危険な野菜について解説します。
大切なペットである猫の健康には気をつけたいですね。
食事内容にも注意して、野菜を食べたほうが良いのかどうか悩んでいる人もいると思います。
でも、結論から言って猫に野菜は必要ではありません。
完全な肉食動物ですので、野菜を食べなくても健康上問題は起こりません。
その点について詳しく、また食べても良い野菜・危険な野菜について解説します。
必要な栄養は全てキャットフードに含まれている
猫はキャットフードをメインとして食生活が成り立っています。
商品によっては、野菜が原材料に使用されていることもあります。
猫にとって必要な栄養はキャットフードに含まれているので、それだけでも問題はありません。
ただ、フードに含まれている野菜は加工されているため、本来の栄養素は損なわれていると考えられます。
野菜の栄養素を与えたいのであれば、フードに少し加えるようにするとよいでしょう。
猫にとって野菜は消化しにくい
 野菜にはお肉に含まれていない栄養素や酵素が含まれているため、それらを補うために与えることは悪いことではありません。
しかし、野菜を生のまま与え過ぎると、消化不良を起こしてしまう可能性があるため、注意が必要です。
猫は腸が短く、野菜や果物の消化に適していません。
葉っぱをかじって毛玉を吐き出していることもあります。
野菜を与えるときはごく少量をゆでたり、刻んだりしてあげましょう。
野菜にはお肉に含まれていない栄養素や酵素が含まれているため、それらを補うために与えることは悪いことではありません。
しかし、野菜を生のまま与え過ぎると、消化不良を起こしてしまう可能性があるため、注意が必要です。
猫は腸が短く、野菜や果物の消化に適していません。
葉っぱをかじって毛玉を吐き出していることもあります。
野菜を与えるときはごく少量をゆでたり、刻んだりしてあげましょう。
猫にとって野菜は摂取する必要がない
猫の味覚は人間の10分の1以下なので、人間のように味わって野菜を食べることがないようです。
フードに含まれる肉や魚の匂いに反応するので、匂いの少ない野菜に興味を示さない猫も多いです。
フードに野菜を加えても全く食べようとしなければ、無理に食べさせなくてもかまいません。
必要な栄養分はキャットフードで賄うことが可能です。
もちろん、人間用の味付けした野菜や野菜ジュースなどの加工品は与えないようにしましょう。
猫が食べてもいい野菜
 猫は肉食動物なので野菜は必要ありませんが、ビタミンや食物繊維、酵素などが多く含まれるので栄養を補うものとして利用できます。
例えば皮膚の健康や便秘の解消などには効果があると言われています。
猫が食べても良い野菜について詳しく解説します。
猫は肉食動物なので野菜は必要ありませんが、ビタミンや食物繊維、酵素などが多く含まれるので栄養を補うものとして利用できます。
例えば皮膚の健康や便秘の解消などには効果があると言われています。
猫が食べても良い野菜について詳しく解説します。
大根
大根は猫にとって有害な野菜ではありません。
与え方によっては、そのまま生でも食べさせることが可能です。
大根は水分が豊富で、ビタミンB・Cや鉄分、カリウムなどのミネラルや酵素も含んでいます。
水分補給として利用すると良いでしょう。
与え方としては酵素を壊さない生の大根おろしがおすすめです。
ただし、大根はアブラナ科の野菜で甲状腺に負担をかけることがあるため、甲状腺に問題がある場合は注意しましょう。
きゅうり
 きゅうりは猫にとってほぼ悪影響はない野菜です。
きゅうりの90%以上は水分で出来ているため、脂肪分やナトリウムがとても少なく、低カロリーで健康的です。
夏の熱中症対策としてもおやつ代わりに与えられます。
利尿作用のあるカリウム、視力維持や皮膚を守るβカロチンなどの栄養があります。
体を冷やす野菜なので、与えすぎるとお腹が冷えて下痢になるかもしれません。
猫の口に合うように少量を小さくカットして与えるようにしてください。
きゅうりは猫にとってほぼ悪影響はない野菜です。
きゅうりの90%以上は水分で出来ているため、脂肪分やナトリウムがとても少なく、低カロリーで健康的です。
夏の熱中症対策としてもおやつ代わりに与えられます。
利尿作用のあるカリウム、視力維持や皮膚を守るβカロチンなどの栄養があります。
体を冷やす野菜なので、与えすぎるとお腹が冷えて下痢になるかもしれません。
猫の口に合うように少量を小さくカットして与えるようにしてください。
さつまいも
猫に人気で安全な野菜です。
さつまいもの味や食感が大好きだという猫も少なくありません。
ビタミンやミネラル、食物繊維が多く、便秘解消の効果があります。
ただしさつまいもは炭水化物をたくさん含んでいるので、食べ過ぎは肥満の元になります。
炭水化物の消化は猫にとって苦手なので、生よりも茹でたり焼き芋にしたりして、皮を取り少量をおやつとして与えるようにしましょう。
にんじん
 にんじんは低カロリー且つ栄養価もとても高いため、猫にとって健康的で良い野菜だと認められています。
そのため、トリーツなどに含まれていることも多い野菜です。
抗酸化作用を持つβカロチンが多いので疲労からの回復や老化防止に役立ちます。
食物繊維が豊富で便秘解消にも効果があります。
人参はすりおろして与えると、消化吸収もアップするのでおすすめです。
皮付きでも問題ありませんが、よく洗ってから使いましょう。
にんじんは低カロリー且つ栄養価もとても高いため、猫にとって健康的で良い野菜だと認められています。
そのため、トリーツなどに含まれていることも多い野菜です。
抗酸化作用を持つβカロチンが多いので疲労からの回復や老化防止に役立ちます。
食物繊維が豊富で便秘解消にも効果があります。
人参はすりおろして与えると、消化吸収もアップするのでおすすめです。
皮付きでも問題ありませんが、よく洗ってから使いましょう。
かぼちゃ
かぼちゃは栄養価が高いため、手作りのフードならば、かぼちゃもメニューに加えても良いかもしれません。
かぼちゃにはビタミン・カリウム・鉄分など豊富に含まれ、風邪予防や老化防止に効果があります。
高カロリーであるため、ダイエットには向きません。
与えすぎると肥満の原因にもなるので注意が必要です。
かぼちゃは加熱して柔らかくしてから与えましょう。
皮や種も取り除くようにしてください。
小松菜
 小松菜はほうれん草よりもアクが少量で、シュウ酸の含有量もほうれん草と比較して1/15程度しかないので、量を調整すれば安心です。
ビタミン類も豊富で肝臓のサポートもしてくれます。
骨や歯を丈夫にするカルシウムも多いので、若い時から少し与えると良いでしょう。
小松菜はアブラナ科の野菜で、甲状腺ホルモンに影響を及ぼすので、甲状腺機能が低下している場合は避けたほうが良いです。
与える際には火を通し、小さくカットして消化を助けるようにしましょう。
小松菜はほうれん草よりもアクが少量で、シュウ酸の含有量もほうれん草と比較して1/15程度しかないので、量を調整すれば安心です。
ビタミン類も豊富で肝臓のサポートもしてくれます。
骨や歯を丈夫にするカルシウムも多いので、若い時から少し与えると良いでしょう。
小松菜はアブラナ科の野菜で、甲状腺ホルモンに影響を及ぼすので、甲状腺機能が低下している場合は避けたほうが良いです。
与える際には火を通し、小さくカットして消化を助けるようにしましょう。
猫が食べてはいけない野菜
 猫に与えても問題のない野菜はいずれも消化の負担にならないように、加熱やサイズに注意して与えてください。
次に猫が食べてはいけない野菜を紹介します。
健康に影響を及ぼす可能性があるものなので、ぜひ覚えておいてください。
猫に与えても問題のない野菜はいずれも消化の負担にならないように、加熱やサイズに注意して与えてください。
次に猫が食べてはいけない野菜を紹介します。
健康に影響を及ぼす可能性があるものなので、ぜひ覚えておいてください。
ネギ・玉ねぎ
猫に食べさせてはいけない野菜はまずネギ・玉ねぎです。
食べてしまったネギ・玉ねぎの量によっては、生命を失うことを覚悟しなければならないほどの症状が出ることもあります。
ねぎ類に含まれる有機チオ硫酸化合物という成分が貧血を引き起こします。
貧血になると体内の細胞に十分酸素を送れなくなり、様々な症状が出てきます。
下痢や嘔吐、発熱、血尿、元気がないなどで軽いものであっても、放っておくとどんどん進むので大変危険です。
少量であっても絶対に与えてはいけない食べ物です。
にんにく
 にんにくはネギ属という分類の野菜で、ネギと同じ有機チオ硫酸化合物が含まれています。
にんにくは玉ねぎと比較すると、猛毒性が低くて、重症化はしづらいと言われています。
ですが、大量に食べると下痢などの不調を生み出します。
ネギ類と同様に貧血を起こしてしまうので、少量でも食べないように管理することが大切です。
調理に使うことが多いにんにくなので、すりおろしたものを猫がうっかりなめたりしないように注意してください。
にんにくはネギ属という分類の野菜で、ネギと同じ有機チオ硫酸化合物が含まれています。
にんにくは玉ねぎと比較すると、猛毒性が低くて、重症化はしづらいと言われています。
ですが、大量に食べると下痢などの不調を生み出します。
ネギ類と同様に貧血を起こしてしまうので、少量でも食べないように管理することが大切です。
調理に使うことが多いにんにくなので、すりおろしたものを猫がうっかりなめたりしないように注意してください。
ニラ
ニラもネギ類に含まれるため、有機チオ硫酸化合物が含まれ、中毒症状を引き起こす危険性があります。
加熱してもその成分は壊れることはありません。
ニラは猫草のように見えることがあるため、間違って食べることのないように買ってきたニラや家庭菜園では十分注意してください。
また食べたあとの中毒症状はすぐに出るわけではなく、数日後いきなり重度の貧血になってぐったりと意識がなくなることもあります。
アスパラガス
 生のアスパラガスも猫に与えてはいけない野菜です。
アスパラガスに含まれているアルカロイドは、薬効成分のある植物毒であるため、解毒能力の弱い猫にとっては摂取NGです。
食べると腹痛・嘔吐・痙攣を起こすことがあり、心臓や腎臓、呼吸器系にも影響が出ると言われています。
また茎の周りにあるはかまと言われる葉の部分にも中毒性があります。
茹でてからなら大丈夫という見解もありますが、特に猫に与える必要性はないため、アスパラガスは与えないようにしましょう。
生のアスパラガスも猫に与えてはいけない野菜です。
アスパラガスに含まれているアルカロイドは、薬効成分のある植物毒であるため、解毒能力の弱い猫にとっては摂取NGです。
食べると腹痛・嘔吐・痙攣を起こすことがあり、心臓や腎臓、呼吸器系にも影響が出ると言われています。
また茎の周りにあるはかまと言われる葉の部分にも中毒性があります。
茹でてからなら大丈夫という見解もありますが、特に猫に与える必要性はないため、アスパラガスは与えないようにしましょう。
アボカド
アボカドにはペルシンという毒素が含まれていて、人間には無害ですが猫には有害です。
アボカドをたくさん摂取すると、嘔吐や下痢などの症状を起こします。
胃腸の炎症や消化不良、呼吸不全も起こり得るので注意です。
外国のペットフードにアボカドが含まれていることもありますが、実はアボカドには千以上の種類があり、フードに入っているアボカドはペルシンが少なく、さらに無害になる工夫がしてあるものです。
日本で販売されているアボカドはペルシンの量が多いため、毒性が強く危険な野菜です。
まとめ
猫に与えても問題ない野菜もありますが、基本的には野菜類を与えなくても大丈夫です。
野菜全般に含まれるセルロースという成分を猫は分解することができないので、消化不良になりやすいからです。
食べても良い野菜でも量によってはかえって健康を損なうことがあります。
また危険な野菜を食べて中毒になることは絶対に避けなければいけません。
調理中にうっかり猫に食べられたりしないように、食品管理を厳重にすることが一番大切です。
猫が家に帰ってこない5つの理由とは?
 家の中で生活することを推奨される猫ですが、外と出入りが自由だったりドアを開けた隙を狙って飛び出してしまったりする場合があります。
家の中に不満がある場合はもちろんですが、快適で猫にとって暮らしやすい環境であっても、戻ってこない時の猫の気持ちについて考えてみました。
家の中で生活することを推奨される猫ですが、外と出入りが自由だったりドアを開けた隙を狙って飛び出してしまったりする場合があります。
家の中に不満がある場合はもちろんですが、快適で猫にとって暮らしやすい環境であっても、戻ってこない時の猫の気持ちについて考えてみました。
理由①:家にいることがストレス
変化を嫌う猫にとって、室内の模様替えや新しく家族になった後輩猫の存在など大きなストレスとなります。
面倒見の良い性格だと、他の猫や子猫のお世話を甲斐甲斐しくしてくれる猫もいますが、今まで自分だけだった空間に知らない猫が来るのですから大抵の場合は落ち着かなくなるでしょう。
また、近所で大きな工事による騒音が長期間続いている時なども、日頃聞き慣れない大きな音にストレスを感じているかもしれません。
その場から離れたい気持ちが強くなり、脱走の可能性も考えられる状態です。
理由②:帰り道が分からない
 外に出てしまった猫は、野良猫の存在や興味を惹かれるものを追ってしまい帰り道がわからなくなることがあります。
男の子の場合、縄張りを侵されたと思われその地域に住む野良猫に追われて帰れなくなることも考えられます。
不可抗力ですが、暖かく暗い場所を求めて車の荷台に入り込み遠くの場所へ運ばれてしまった猫のニュースも度々あります。
外に出てしまった猫は、野良猫の存在や興味を惹かれるものを追ってしまい帰り道がわからなくなることがあります。
男の子の場合、縄張りを侵されたと思われその地域に住む野良猫に追われて帰れなくなることも考えられます。
不可抗力ですが、暖かく暗い場所を求めて車の荷台に入り込み遠くの場所へ運ばれてしまった猫のニュースも度々あります。
理由③:発情期だから
去勢や避妊手術をしていない猫の場合、発情期を迎えることは避けられません。
基本的に、発情を迎えた女の子の鳴き声やフェロモンに反応して男の子が発情する仕組みとなっていますので、野良猫が発情した鳴き声を聞いたお家にいる男の子が、相手を探して家を出てしまう可能性が高いといえます。
猫の発情期は暖かい季節である春と秋の年2回ですが、夜間でも街灯やお店の明かりが眩しい環境の場合、年に3回以上発情する猫もいます。
理由④:外が魅力的に見えた
 野良猫の生活をしていた経験がある猫や、好奇心旺盛な性格の場合に外の世界に興味を持ち家から出てしまうこともあります。
鳥の存在や他の猫の姿を見つけて、面白そうだと感じて外に行きたい気持ちになる心理は当然でしょう。
また、家の中に猫の本能を刺激するような上下運動が出来なかったり遊びが足りなかったりして、退屈を感じていることもありますので環境作りも大切となります。
野良猫の生活をしていた経験がある猫や、好奇心旺盛な性格の場合に外の世界に興味を持ち家から出てしまうこともあります。
鳥の存在や他の猫の姿を見つけて、面白そうだと感じて外に行きたい気持ちになる心理は当然でしょう。
また、家の中に猫の本能を刺激するような上下運動が出来なかったり遊びが足りなかったりして、退屈を感じていることもありますので環境作りも大切となります。
理由⑤:事故に遭ってしまった
交通量の多い場所や人通りのある場所など、車による不慮の事故の他にも自転車との接触など交通事故に遭う危険性が高まります。
また、他の猫との喧嘩やイタズラによる負傷も考えられるでしょう。
怪我をした猫は、自力で動ける場合に物陰や目立たない場所でじっとしていることが多く、家に帰れない状態となります。
猫が帰ってこない時の探し方
 家から出てしまった猫が帰って来ない時、飼い主様は気が気ではないはずです。
ですが、闇雲に探し回るよりも他の人の手を借りて効率的に探したほうが早いかもしれません。
ここでは、どのような方法があるかご紹介していきます。
家から出てしまった猫が帰って来ない時、飼い主様は気が気ではないはずです。
ですが、闇雲に探し回るよりも他の人の手を借りて効率的に探したほうが早いかもしれません。
ここでは、どのような方法があるかご紹介していきます。
インターネットで情報を集める
ネットは、迷子のペット情報や掲示板の他に専用サイトなど数多くの情報に繋がります。
ご自宅周辺で保護された猫の情報や目撃情報も確認できるので、不特定多数の猫好きの目を借りて情報収集してみましょう。
また、保健所に収容された場合に保護日や体の特徴の他にも写真付きで情報がアップされます。
一般の人も簡単に閲覧できるので、こちらもしっかりチェックしましょう。
捜索チラシを作成する
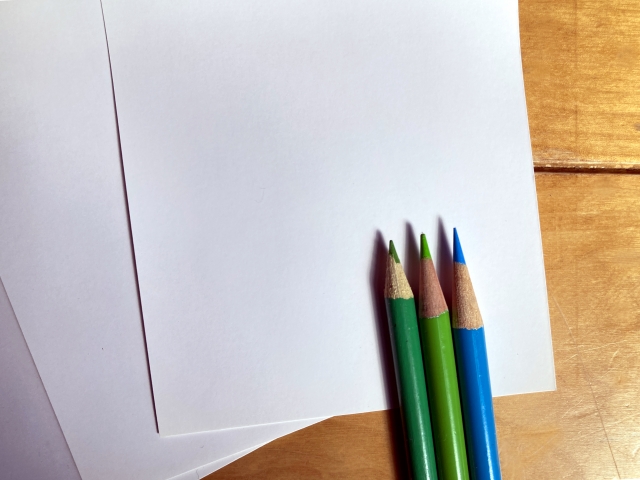 外の世界を知らない猫の場合、家の近くで動けなくなっていることがほとんどです。
いなくなってすぐであれば、猫の写真と特徴を記載したチラシを作って近所の方に周知してもらうのも効果的です。
住宅地であれば、庭の植え込みや物置の影などに隠れていることも多くあります。
また、コンビニやお店など多くの人が集まる場所にお願いして、店頭に貼らせてもらう人もいます。
内容やレイアウトに悩んでしまう場合は、捜索チラシの例文もインターネットで見つけることができますので利用してください。
外の世界を知らない猫の場合、家の近くで動けなくなっていることがほとんどです。
いなくなってすぐであれば、猫の写真と特徴を記載したチラシを作って近所の方に周知してもらうのも効果的です。
住宅地であれば、庭の植え込みや物置の影などに隠れていることも多くあります。
また、コンビニやお店など多くの人が集まる場所にお願いして、店頭に貼らせてもらう人もいます。
内容やレイアウトに悩んでしまう場合は、捜索チラシの例文もインターネットで見つけることができますので利用してください。
ペット探偵に捜索を依頼する
迷子になったペットを専門で探してくれる業者も多数あります。
捜索日数や範囲・業者によって料金に差がありますが、夜間の捜索にも対応してくれる場合がありますので飼い主様が動けない時間帯の捜索を任せることも可能です。
どこのペット探偵に頼むか、しっかりと見極めることも大切になりますので、口コミや評判を確認して納得の上で依頼をしましょう。
保健所や警察などに連絡する
 他に、保護されて保健所に収容されたり、警察に届けがある場合も考えられますので、最寄りの警察署や管轄の保健所へ必ず連絡をしてください。
特徴や居なくなったおおよその時間や日にちを詳しく連絡しておくことで、後日迷子猫の届けがあった場合に連絡をしてくれます。
他に、保護されて保健所に収容されたり、警察に届けがある場合も考えられますので、最寄りの警察署や管轄の保健所へ必ず連絡をしてください。
特徴や居なくなったおおよその時間や日にちを詳しく連絡しておくことで、後日迷子猫の届けがあった場合に連絡をしてくれます。
猫が帰ってこない事態を防ぐ対策
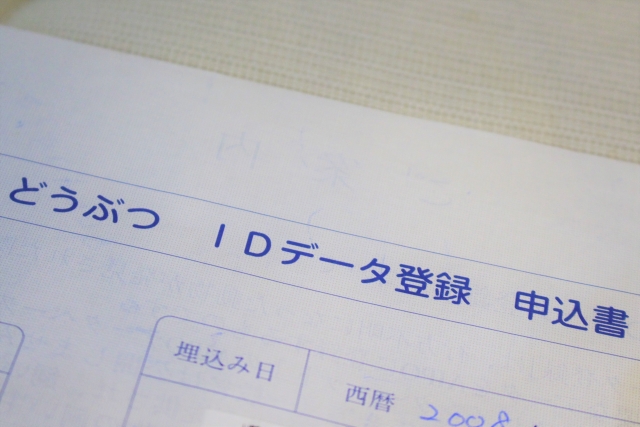 注意していても、隙を狙って外に出てしまう可能性があります。
しかし、飼い主として脱走の危険を限りなくゼロに近づける対策を行うことが大切です。
注意していても、隙を狙って外に出てしまう可能性があります。
しかし、飼い主として脱走の危険を限りなくゼロに近づける対策を行うことが大切です。
猫の姿を捉えた写真を撮影しておく
普段、よく猫の姿を撮影する方は多いかもしれません。
捜索チラシを作成する時や、インターネットを活用する時など全身が写っている写真があると特徴がよく伝わります。
また、尻尾の長さや模様・後ろ姿などがよくわかる写真を複数枚撮っておくと安心です。
網戸やドアなどの鍵のかけ忘れに注意する
 網戸のちょっとした隙間でも手を入れて開けてしまう猫も多く、「閉めているから大丈夫」とは言い切れません。
また、器用な猫ならドアノブに手を掛けて開けてしまう場合も考えられます。
戸建てのお家で一番多いのが、お風呂場の小窓の閉め忘れではないでしょうか。
換気のために開けていた窓から、出てしまうこともあります。
猫は思う以上に器用にどこからでも出入りしますので、万が一を考えて戸締りと鍵を掛けることを忘れないようにしたいですね。
網戸のちょっとした隙間でも手を入れて開けてしまう猫も多く、「閉めているから大丈夫」とは言い切れません。
また、器用な猫ならドアノブに手を掛けて開けてしまう場合も考えられます。
戸建てのお家で一番多いのが、お風呂場の小窓の閉め忘れではないでしょうか。
換気のために開けていた窓から、出てしまうこともあります。
猫は思う以上に器用にどこからでも出入りしますので、万が一を考えて戸締りと鍵を掛けることを忘れないようにしたいですね。
マイクロチップや迷子札を着用させる
猫にはまだまだ普及されている状態ではありませんが、マイクロチップの装着や首輪の迷子札が帰宅率をアップします。
迷子札は飼い主様の連絡先を記載しておけば、保護した人が連絡をくれる可能性が高くなりますのでぜひ装着させましょう。
マイクロチップは、動物病院や専門の施設で読み取り器を使用して、飼い主様の情報を確認します。
何らかの原因で首輪が外れてしまった場合、収容されている施設で確認することが可能となります。
まとめ
大切にしている家族が行方不明になったり事故にあったりして辛い思いをさせないように、戸締りはもちろん過ごしやすい環境を整えてあげましょう。
また、もし家から出てしまった場合は多くの人の手を借りてマンパワーで行動することが早い発見に繋がります。
この機会に、もしものことを考えて環境の見直しをしてみてはいかがでしょうか。
猫飼いが観葉植物を置く時の注意点
 猫を飼っている部屋に観葉植物はありますか?
肉食動物の猫ですが、植物で遊んでいてうっかり口に入れてしまうこともあります。
植物には毒性があって、下痢や嘔吐などの症状が出る危険なものもあるので、正しい知識を持っておくことが大切です。
この記事では観葉植物を置く時の注意点と安全な植物・危険な植物について解説します。
猫を飼っている部屋に観葉植物はありますか?
肉食動物の猫ですが、植物で遊んでいてうっかり口に入れてしまうこともあります。
植物には毒性があって、下痢や嘔吐などの症状が出る危険なものもあるので、正しい知識を持っておくことが大切です。
この記事では観葉植物を置く時の注意点と安全な植物・危険な植物について解説します。
風が当たりにくい場所に置く
観葉植物は必ず猫の安全を考えて置き場所を決めましょう。
まずは風が当たりにくい場所に置くことです。
扇風機やエアコンの風、窓から入ってくる風などで葉が揺れてしまうと、猫はついついじゃれついてしまいます。
それは猫が動くものに好奇心を抱いて追いかけたくなる習性があるからです。
じゃれて遊んでいるうちに、噛んでちぎれた葉っぱが口に入ったり、うっかり誤飲したりする可能性があるので注意しなければいけません。
窓側に置いて日光を植物に当てるときには、窓を閉めておきましょう。
天井に近くて高い場所に置く
 留守番中や目を離したすきに観葉植物を倒してしまったり、いたずらしたりすることも心配です。
また猫は丸い容器の中にいると落ち着くという習性があり、植木鉢が気になることがあります。
ですから、観葉植物を天井から吊るすなど、猫の手が届かない位置に置くことが大切です。
棚や窓辺などの足場が存在すると、飛び乗る危険性がありますので周囲をよく見渡して、その場所で大丈夫かどうかも確認しましょう。
高い場所に置いても猫は身軽で簡単に登れてしまうので、いたずらが可能かもしれません。
一緒に過ごせる時間帯にその場所に置いてみて、どんな行動をするか観察してみるなどの工夫をしてみてください。
留守番中や目を離したすきに観葉植物を倒してしまったり、いたずらしたりすることも心配です。
また猫は丸い容器の中にいると落ち着くという習性があり、植木鉢が気になることがあります。
ですから、観葉植物を天井から吊るすなど、猫の手が届かない位置に置くことが大切です。
棚や窓辺などの足場が存在すると、飛び乗る危険性がありますので周囲をよく見渡して、その場所で大丈夫かどうかも確認しましょう。
高い場所に置いても猫は身軽で簡単に登れてしまうので、いたずらが可能かもしれません。
一緒に過ごせる時間帯にその場所に置いてみて、どんな行動をするか観察してみるなどの工夫をしてみてください。
猫にも安全なおすすめ観葉植物一覧
 猫にとって安全で無害なおすすめの観葉植物を紹介します。
部屋のどこに置くと良いのかを考えたら、その場所に似合う観葉植物で猫にも安全な物を選んでください。
猫も観葉植物も癒やしてくれる存在になってくれることでしょう。
猫にとって安全で無害なおすすめの観葉植物を紹介します。
部屋のどこに置くと良いのかを考えたら、その場所に似合う観葉植物で猫にも安全な物を選んでください。
猫も観葉植物も癒やしてくれる存在になってくれることでしょう。
パキラ
パキラはブラジル原産の植物で、大きな葉とよじれた幹が特徴です。
人気のある観葉植物で、部屋の自然な雰囲気を盛り上げてくれます。
猫が食べても大丈夫な観葉植物で、ある程度高さがあるため、登ってしまったり、鉢を倒さないようにしたりと、置き方の工夫が必要となります。
パキラは適度な日当たりが必要なので、窓辺に置くのが良いでしょう。
エアコンの風が直接当たると枯れる原因になるので、風が当たらない場所に置いてください。
ガジュマル
 ガジュマルは沖縄などの暖かい地方で有名な植物で、「精霊の宿る木」と呼ばれています。
猫が食べても無害であるため、安心して屋内に置くことが可能です。
小さい木もあるのでテーブルに置く際は猫が落としたり、倒したりしないように対策しましょう。
ガジュマルは数年経てば、ベランダなどでも栽培できます。
夏の直射日光は当てないようにしないと葉やけするので、置き場所にも気をつけましょう。
ガジュマルは沖縄などの暖かい地方で有名な植物で、「精霊の宿る木」と呼ばれています。
猫が食べても無害であるため、安心して屋内に置くことが可能です。
小さい木もあるのでテーブルに置く際は猫が落としたり、倒したりしないように対策しましょう。
ガジュマルは数年経てば、ベランダなどでも栽培できます。
夏の直射日光は当てないようにしないと葉やけするので、置き場所にも気をつけましょう。
エバーフレッシュ
エバーフレッシュはネムノキの一種で熱帯が原産の植物なので、暑さに強いです。
ほっそりした葉は夜になると水分の蒸発を防ぐため閉じるので、ネムノキと呼ばれています。
猫が葉を食べても無害であるため、安心して屋内に置くことができます。
暑さに強いメリットと丈夫で育てやすいので観葉植物としての人気も高いです。
アジアンチックは雰囲気をプラスしてくれるのでおすすめです。
寒さに弱いので室内の温かいところに置いて冬越しさせましょう。
シュロチク
 シュロチクはヤシ科に分類される中国原産の観葉植物です。
日本では江戸時代から親しまれていて、アジアンテイストや和モダンな雰囲気にも合うスマートな印象です。
日差しが苦手で、半日陰でも育ちます。
耐寒性がすぐれているため、年間を通して、屋内でも屋外でも育てることができる初心者にもおすすめの植物です。
葉が細くて、猫がかじりやすいので、置き場所や置き方に工夫が必要です。
シュロチクはヤシ科に分類される中国原産の観葉植物です。
日本では江戸時代から親しまれていて、アジアンテイストや和モダンな雰囲気にも合うスマートな印象です。
日差しが苦手で、半日陰でも育ちます。
耐寒性がすぐれているため、年間を通して、屋内でも屋外でも育てることができる初心者にもおすすめの植物です。
葉が細くて、猫がかじりやすいので、置き場所や置き方に工夫が必要です。
テーブルヤシ
テーブルヤシはヤシの中でも小さい種類です。
名前の通り、テーブルの上などに置いて楽しめる観葉植物です。
トロピカルな雰囲気が好きな人におすすめです。
日当たりは必要ですが、陰でも大丈夫なので気温が安定した場所で育ててください。
猫が口にしても無害ですが、葉のサイズが小さく、食べやすい形なので、置き方や場所を工夫し、猫にもテーブルヤシにとっても安全な環境作りをしましょう。
猫にとって危険な観葉植物一覧
 次に猫にとって危険な観葉植物を解説します。
猫に毒性がある植物は700種類以上もあるので全てを覚えられませんが、名前が知られていて人気のある植物の中から危険なものをお伝えします。
選ぶ際にはこれらは避けておき、すでに家にある場合はその対策をしてください。
次に猫にとって危険な観葉植物を解説します。
猫に毒性がある植物は700種類以上もあるので全てを覚えられませんが、名前が知られていて人気のある植物の中から危険なものをお伝えします。
選ぶ際にはこれらは避けておき、すでに家にある場合はその対策をしてください。
ユリ
美しい花のユリを含めユリ科に分類される植物は、猫にとって最も危険な植物です。
花や花粉、葉や茎、球根など、全てに強い毒性を有しています。
拒食症的症状や嘔吐、腎臓機能不全を引き起こしてしまうため、最も気をつけるべき植物です。
花を生けている花瓶の水をなめただけでも中毒になることがあります。
猫を飼っている人は猫がいる部屋には置かないようにし、近づけない工夫をしてください。
ドラセナ
 ドラセナは葉の形や色が綺麗で人気がある観葉植物です。
「幸福の木」とも呼ばれ、贈り物でいただくこともあるでしょう。
しかし、全草に猛毒性があり、下痢や嘔吐、手足の腫れや麻痺などの症状を引き起こすことがあります。
こちらも猫のいる部屋には置かず、別の場所で管理するようにしましょう。
ドラセナは葉の形や色が綺麗で人気がある観葉植物です。
「幸福の木」とも呼ばれ、贈り物でいただくこともあるでしょう。
しかし、全草に猛毒性があり、下痢や嘔吐、手足の腫れや麻痺などの症状を引き起こすことがあります。
こちらも猫のいる部屋には置かず、別の場所で管理するようにしましょう。
アイビー
アイビーも馴染みのある植物で、簡単に育てられる初心者向けのものです。
観葉植物として人気のあるアイビーですが、腹痛や口の渇き、嘔吐や下痢という中毒症状を引き起こします。
アイビーの垂れ下がったツルは猫の興味を引きやすく、ついいたずらしたくなることが多いです。
口にするとかゆみが起こり、神経症状が出る場合もあります。
寄植えの中にも用いられることが多い植物なので、他の花と一緒に飾っていることもあるでしょう。
猫の体調を崩す恐れがあるので、同じ部屋に置くことは避けましょう。
ポトス
 ポトスは育てやすく人気がある植物です。
しかし、実は葉と茎に毒性があり、猫がかじってしまうと皮膚炎や口内の炎症などを引き起こすことがあります。
ポトスは部屋の天井など高いところから配置することがよく見られますが、それは猫にとっては絶好の遊び場です。
飛び乗って遊んでいるうちに葉をかじって、食欲がなくなって衰弱する危険性があります。
ポトスをすでに飾っている人は猫が入らない部屋で管理しましょう。
ポトスは育てやすく人気がある植物です。
しかし、実は葉と茎に毒性があり、猫がかじってしまうと皮膚炎や口内の炎症などを引き起こすことがあります。
ポトスは部屋の天井など高いところから配置することがよく見られますが、それは猫にとっては絶好の遊び場です。
飛び乗って遊んでいるうちに葉をかじって、食欲がなくなって衰弱する危険性があります。
ポトスをすでに飾っている人は猫が入らない部屋で管理しましょう。
ウンベラータ
ウンベラータは葉がハート形でおしゃれな観葉植物です。
明るいグリーンカラーでインテリアとして最適で、初心者にも育てやすい植物です。
人気の観葉植物ですが、かじると口内を刺激され、よだれや痒みなどの症状が出ます。
猫や犬などペットが誤飲すると痙攣を起こすケースがあります。
また小さな子供でもウンベラータの毒性が現れる可能性があるので、できるだけ避けたほうが良いでしょう。
猫が観葉植物で遊んでしまう時の対処法
 猫に安全で無害な観葉植物でも遊んでしまって、葉がボロボロになることがあります。
またひっくり返してしまうと部屋の中がたいへんなことになります。
特に若い猫は活発なため、遊びの対象になってしまうことが多いようです。
いたずらを避けるための方法をいくつか解説しますので、参考にしてください。
猫に安全で無害な観葉植物でも遊んでしまって、葉がボロボロになることがあります。
またひっくり返してしまうと部屋の中がたいへんなことになります。
特に若い猫は活発なため、遊びの対象になってしまうことが多いようです。
いたずらを避けるための方法をいくつか解説しますので、参考にしてください。
観葉植物にカバーをつける
猫に鉢を倒されたり、土を掘り返されたりなど、悩みがある場合は、プランターカバーの取り付けを推奨します。
カバーは鉢より大きく、ある程度重さがある方が倒れにくいので安全です。
土の上にウッドチップをかぶせておくことも猫が掘り起こすのを予防できます。
大きめの麻袋などを鉢ごと覆ってしまうのも一つの方法です。
植物を買ったお店で相談してみるのも良いですね。
木酢液をスプレーする
 木酢液はいたずら対策をしても、猫がどうしても植物で遊んでしまう時、土を掘り返してしまう場合などに使用しましょう。
木酢液は炭を焼くときに発生する煙を冷やし液体にしたもので、植物の病気や害虫予防のために使う害のない液体です。
ホームセンターで売っていますが、原液のままでは使えないので適切に薄めて使用するようにしましょう。
猫は柑橘系や酢の匂いが嫌なので、その習性を利用して木酢液を植物にかけることでいたずら対策になります。
木酢液はいたずら対策をしても、猫がどうしても植物で遊んでしまう時、土を掘り返してしまう場合などに使用しましょう。
木酢液は炭を焼くときに発生する煙を冷やし液体にしたもので、植物の病気や害虫予防のために使う害のない液体です。
ホームセンターで売っていますが、原液のままでは使えないので適切に薄めて使用するようにしましょう。
猫は柑橘系や酢の匂いが嫌なので、その習性を利用して木酢液を植物にかけることでいたずら対策になります。
まとめ
観葉植物は癒やしとなり、空気をきれいにする力も持っています。
でも、猫にとって危険な観葉植物は意外と多く、安全であってもいたずらしないような工夫が必要です。
観葉植物の種類や置く場所に注意して、猫の安全を確保できるようにしてください。
特に若い猫は好奇心が強く、思わぬ危険を呼ぶかもしれません。
しっかりと知識を持って猫との暮らしを大切に守ってあげてください。
猫に与えてはいけないとうもろこしの部分や商品
 猫にとうもろこしを与えても問題はありません。
特に中毒性がある野菜ではないからです。
しかし、とうもろこしは消化が悪いので胃腸炎を起こすこともあります。
肥満の原因になりやすく、腎臓や泌尿器系の疾患にかかりやすくなるとも言われていますので、与える量には注意をはらいましょう。
そして、粒以外の部分については危険性もありますので、次の詳しい解説をお読みください。
猫にとうもろこしを与えても問題はありません。
特に中毒性がある野菜ではないからです。
しかし、とうもろこしは消化が悪いので胃腸炎を起こすこともあります。
肥満の原因になりやすく、腎臓や泌尿器系の疾患にかかりやすくなるとも言われていますので、与える量には注意をはらいましょう。
そして、粒以外の部分については危険性もありますので、次の詳しい解説をお読みください。
とうもろこしの葉
多くの人がとうもろこしといえば、あの粒粒を思い浮かべ、葉っぱの部分は捨てていると思います。
葉っぱの部分は食べられるのか?というと、中毒成分が含まれていません。
しかし、農薬の化学薬品が含まれていたり、カビが生えている危険もあります。
葉の部分はやはり食べずに捨てるようにしましょう。
よく水洗いしてから粒を茹でて柔らかくして与えてください。
芯の部分を噛むおもちゃのようにすることがあるかもしれませんが、誤飲の可能性があるのでやめましょう。
とうもろこしのひげ
 次に意外にも重宝なのがとうもろこしの「ひげ」です。
ふさふさのひげがついているとうもろこしを買ったら、病気の予防や治療にも活用できるのです。
この部分は、炎症を抑制することに効果が高く、漢方薬として使用されています。
捨てられがちな「ひげ」ですが、猫が食べられるように乾燥させ、細かくしてフードに混ぜると、糖尿病や脂肪肝などに効きます。
そのような病気ではない場合も、太りやすい、雨の日には元気がなくなる、皮膚炎や目やになどが多い等の症状があれば、ひげはおすすめです。
使い方はひげをよく洗って2,3日乾燥させ、ハサミで小さくカットして、小さじ1ほど食事に混ぜて与えます。
次に意外にも重宝なのがとうもろこしの「ひげ」です。
ふさふさのひげがついているとうもろこしを買ったら、病気の予防や治療にも活用できるのです。
この部分は、炎症を抑制することに効果が高く、漢方薬として使用されています。
捨てられがちな「ひげ」ですが、猫が食べられるように乾燥させ、細かくしてフードに混ぜると、糖尿病や脂肪肝などに効きます。
そのような病気ではない場合も、太りやすい、雨の日には元気がなくなる、皮膚炎や目やになどが多い等の症状があれば、ひげはおすすめです。
使い方はひげをよく洗って2,3日乾燥させ、ハサミで小さくカットして、小さじ1ほど食事に混ぜて与えます。
缶詰のとうもろこし
人間には缶詰のとうもろこしは便利です。
でも缶詰は加工してあるものなので、塩分がたっぷり含まれている場合が少なくありません。
体の小さい猫に与えるのは塩分過多で健康を害するので、NGです。
猫はとうもろこしが好きなようですので、つい味に付いた物をあげてしまうとその味を覚えてしまい、飼い主さんの目を盗んでつまみ食いをしてしまうかもしれません。
とうもろこしは生のものを茹でてから与えることを忘れないでください。
猫にとうもろこしを与える時の注意点
 猫に安全にとうもろこしを食べさせるための注意点をここで確認しておきましょう。
何と言ってもペットの健康管理は飼い主さんの義務ですので、しっかりした知識を持って安心して食べられ、体に良いものをあげてください。
猫に安全にとうもろこしを食べさせるための注意点をここで確認しておきましょう。
何と言ってもペットの健康管理は飼い主さんの義務ですので、しっかりした知識を持って安心して食べられ、体に良いものをあげてください。
生のとうもろこしは与えない
野菜の多くに共通することですが、生で与えることはやめましょう。
人間も生では食べませんが、猫には必ず茹でて柔らかくしてから、あげましょう。
もちろん塩などは使わないでくださいね。
とうもろこしの細胞にはセルロースという成分がたくさんあり、そのセルロースを分解する力が猫にはありません。
ですから、生で食べると消化不良を起こしてしまい、かえって辛い思いをさせてしまうのです。
猫は穀物の消化が難しいので、茹でた後も細かく刻んだり、つぶして与えたりするほうがお腹に良いでしょう。
アレルギーに気をつける
 とうもろこしにはアレルギー成分が含まれますので、アレルギーには注意してください。
穀物アレルギー持つ猫ちゃんにとうもろこしを与えてはいけません。
猫にとって穀物アレルギーは意外と多く、とうもろこしや米、小麦にも反応することがあります。
アレルギーがあるのかどうか分からない場合は、少量を食べさせ、様子を見る方法があります。
かゆみや下痢・嘔吐など軽くても症状が出れば、獣医で診察を受けてください。
とうもろこしにはアレルギー成分が含まれますので、アレルギーには注意してください。
穀物アレルギー持つ猫ちゃんにとうもろこしを与えてはいけません。
猫にとって穀物アレルギーは意外と多く、とうもろこしや米、小麦にも反応することがあります。
アレルギーがあるのかどうか分からない場合は、少量を食べさせ、様子を見る方法があります。
かゆみや下痢・嘔吐など軽くても症状が出れば、獣医で診察を受けてください。
薄皮にも注意する
とうもろこしには薄皮が付いています。
この薄皮はセルロースの部分で消化が悪く、また喉に引っかかって食べにくい・喉に詰まるということもあります。
できるだけ薄皮は取り除いてから、刻んだりすりつぶしたりして与えるようにしましょう。
食べ過ぎは消化不良の原因となるため、薄皮を纏った状態であげる場合は、1粒ずつ食べさせてあげるようにしましょう。
とうもろこしの栄養素
 とうもろこしはキャットフードに含まれていることもあります。
とうもろこしの主な栄養素は、炭水化物・ビタミンB群・ビタミンC、E・カリウムなどです。
これらの栄養素はどのような役割を持つのか、解説していきます。
とうもろこしはキャットフードに含まれていることもあります。
とうもろこしの主な栄養素は、炭水化物・ビタミンB群・ビタミンC、E・カリウムなどです。
これらの栄養素はどのような役割を持つのか、解説していきます。
ビタミンB群は必要な栄養素
とうもろこしには多くのビタミンB群が含まれています。
ビタミンB群は、神経伝達物質の生成や、代謝に関係する「補酵素」であり、酵素の働きに必要となります。
体の成長に必須な栄養素で、免疫機能の維持も務め、疲労回復効果もあります。
特に葉酸は妊娠中の猫や成長期の子猫には必要な成分です。
これらの栄養素を効果的に摂取することは、健康面でも大切なことです。
またビタミンEや高血圧を防ぐカリウム、リノール酸なども含んでいてアンチエイジングにも効果があります。
ダイエットに効果的
 炭水化物は糖質と食物繊維から成っていて、猫は炭水化物の消化は苦手とされています。
しかし、糖質はエネルギー源として重要で、食物繊維は消化器官の働きを助ける効果があります。
とうもろこしにはセルロースという食物繊維があり、便の排泄を促す効果があるので、ダイエットにも向いています。
ですから低カロリーのフードを作るために、とうもろこしが利用されているようです。
アレルギーがなく、肥満気味の猫であれば、体重管理に役立つとうもろこし入りのフードも活用できます。
炭水化物は糖質と食物繊維から成っていて、猫は炭水化物の消化は苦手とされています。
しかし、糖質はエネルギー源として重要で、食物繊維は消化器官の働きを助ける効果があります。
とうもろこしにはセルロースという食物繊維があり、便の排泄を促す効果があるので、ダイエットにも向いています。
ですから低カロリーのフードを作るために、とうもろこしが利用されているようです。
アレルギーがなく、肥満気味の猫であれば、体重管理に役立つとうもろこし入りのフードも活用できます。
まとめ
世界三大穀物であるとうもろこしは栄養も豊富な食べ物です。
ただし、猫にとって穀物は消化の悪いものなので与え方にはくれぐれも注意を払ってください。
必ず加熱した柔らかいものを、薄皮をとってできれば刻んであげましょう。
ほんの数粒にして、与えすぎないようにしてください。
初めて食べる際には、アレルギー症状が出ないかどうか様子を見てあげることも大切です。
甘くて美味しいので、楽しいおやつとして利用できればいいですね。
猫にさつまいもはOK
 猫は色々な物を食べることができ、人が食べる物も多く食べる習性があります。
しかし、食べてはいけない物もあるので、猫を飼っているのであれば把握しておくことが求められます。
人であれば問題なく食べることができるさつまいもですが、猫にも与えても問題ない食材です。
ただし、与える際の注意点や適した与え方を守らなければ体調を崩してしまう原因となってしまいます。
ここでは、猫にさつまいもを与える際のことについて紹介しているので参考にしてください。
猫は色々な物を食べることができ、人が食べる物も多く食べる習性があります。
しかし、食べてはいけない物もあるので、猫を飼っているのであれば把握しておくことが求められます。
人であれば問題なく食べることができるさつまいもですが、猫にも与えても問題ない食材です。
ただし、与える際の注意点や適した与え方を守らなければ体調を崩してしまう原因となってしまいます。
ここでは、猫にさつまいもを与える際のことについて紹介しているので参考にしてください。
猫にさつまいもを与える効果
 猫にさつまいもを与えることでさまざまな効果を得ることができます。
そのため、さつまいもを与えることで猫の体調が改善されることも期待できます。
ただし、いくら猫に良い効果が期待できるからといって大量に与えてしまうことは逆効果になってしまうこともあるので注意が必要です。
次に、猫にさつまいもを与えた際に得られる効果を紹介していきます。
求めている効果があるのであれば適量のさつまいもをフードに混ぜたり、おやつ代わりに与えてみてはいかがでしょうか。
猫にさつまいもを与えることでさまざまな効果を得ることができます。
そのため、さつまいもを与えることで猫の体調が改善されることも期待できます。
ただし、いくら猫に良い効果が期待できるからといって大量に与えてしまうことは逆効果になってしまうこともあるので注意が必要です。
次に、猫にさつまいもを与えた際に得られる効果を紹介していきます。
求めている効果があるのであれば適量のさつまいもをフードに混ぜたり、おやつ代わりに与えてみてはいかがでしょうか。
カリウム:不要な塩分を排出
さつまいもにはカリウムという栄養素が含まれています。
カリウムは摂取した量だけ塩分を排出させる効果があります。
排出方法は主に尿であり、利尿作用を高めることもできます。
人にも言えることですが、塩分を多く摂取してしまうとさまざまな病気になる危険性があり、猫にも同じことが言えます。
猫の場合は塩分を過剰摂取し続けてしまうと網膜剥離や心肥大、運動失調などの病気になる可能性が高まってしまいます。
命にも関わる病気でもあるため、塩分をとりすぎることは危険です。
その点、さつまいものカリウムは多く摂取しすぎた塩分を体外に排出することができるので、塩分の過剰摂取による高血圧を防ぐことができます。
しかし、カリウムの摂りすぎも違う病気の原因となるので注意が必要です。
ヤラピン&食物繊維:便秘解消効果がある
 さつまいもにはヤラピンという成分と食物繊維が含まれている特徴があります。
食物繊維は便秘に良いとことを知っている人も多いのではないでしょうか。
そのため、猫にさつまいもを与えれば便秘解消の効果が期待できます。
食物繊維はわかってもヤラピンがどんな成分なのかわからない場合が多いと思いますが、さつまいもにしか含まれていない成分です。
ヤラピンには腸の働きを整える効果や緩下剤としての効果もあるため、さらに便秘解消の効果があります。
猫は自身の被毛を飲み込み定期的に吐き出したり、便として排出する習性がありますが、腸の活動が悪かったり、飲み込む被毛の量が多いと毛球症になるリスクがあります。
特に、換毛期や長毛種であれば毛球症になるリスクが高いです。
しかし、便秘解消の効果があるさつまいもを与えれば効率よく毛玉を排便と一緒に出すことができるので、毛球症予防の効果も期待できます。
さつまいもにはヤラピンという成分と食物繊維が含まれている特徴があります。
食物繊維は便秘に良いとことを知っている人も多いのではないでしょうか。
そのため、猫にさつまいもを与えれば便秘解消の効果が期待できます。
食物繊維はわかってもヤラピンがどんな成分なのかわからない場合が多いと思いますが、さつまいもにしか含まれていない成分です。
ヤラピンには腸の働きを整える効果や緩下剤としての効果もあるため、さらに便秘解消の効果があります。
猫は自身の被毛を飲み込み定期的に吐き出したり、便として排出する習性がありますが、腸の活動が悪かったり、飲み込む被毛の量が多いと毛球症になるリスクがあります。
特に、換毛期や長毛種であれば毛球症になるリスクが高いです。
しかし、便秘解消の効果があるさつまいもを与えれば効率よく毛玉を排便と一緒に出すことができるので、毛球症予防の効果も期待できます。
ビタミン:免疫力向上や抗酸化作用など
さつまいもには豊富なビタミンが含まれています。
ビタミンには抗酸化作用が期待でき、細胞が酸化によって劣化してしまうことを防ぎます。
細胞へのダメージを抑えることで免疫力向上の効果や皮膚の状態を改善する効果なども期待できます。
そのほかにも腎臓病に対する進行を遅らせるという効果もあるため、腎臓病になっている猫に与えることで症状を抑えることができ、がん予防などの効果も同時に期待することが可能です。
さらにさつまいもは妊娠中の猫にとってもおすすめできる食材です。
妊娠することで血中濃度が低下しやすく、そのような状態が続いてしまうと母体と胎児に悪影響が出てしまいやすいです。
ビタミンEが不足してしまいがちな妊娠中の猫にさつまいもを与えれば母子ともにも健康を維持できるます。
猫にさつまいもを正しく与える方法
 猫にさつまいもを与えるのであれば正しい方法で与えなければなりません。
そのため、猫にさつまいもを与えようと考えているのであれば把握しておくことをおすすめします。
正しい方法で与えることができていないと猫が体調を崩してしまう原因となってしまいます。
猫にさつまいもを与えるのであれば正しい方法で与えなければなりません。
そのため、猫にさつまいもを与えようと考えているのであれば把握しておくことをおすすめします。
正しい方法で与えることができていないと猫が体調を崩してしまう原因となってしまいます。
猫に与えるさつまいもは少量
猫にさつまいもを与えるのであれば少量だけにしましょう。
1日の目安はティースプーン一杯程度であり、かなり少ないです。
そのため、1日の目安であることを知らないと大概が多く与えてしまっている場合が多いです。
1日程度であれば規定量を超えても問題は起きにくいですが、毎日多くのさつまいもを与えることはやめましょう。
また、生のまま与えることは消化不良の原因となってしまい、下痢や嘔吐をしてしまう可能性が高まってしまいます。
なので、しっかり加熱して猫に与えるようにしましょう。
ちなみにさつまいもは干し芋や蒸かし芋などさまざまな食べ方がありますが、どの方法でも問題ありません。
ただし、猫は人とは違い甘みを感じにくいのであまり濃い味付けにしないようにしましょう。
加熱した後は冷ます
 上記では加熱してさつまいもを与えることが必須であることを紹介しましたが、加熱したものをすぐに与えるのではなく、冷ましてから与えるようにしましょう。
人も加熱したさつまいもをすぐに食べようとすると火傷してしまいます。
猫も同じように熱いままでは火傷してしまう危険性があります。
猫は人よりも温度に敏感な動物であり、0.5 ℃変わるだけでも違いが感知することができます。
適した温度は小動物の体温と同じ35℃前後がおすすめです。
上記では加熱してさつまいもを与えることが必須であることを紹介しましたが、加熱したものをすぐに与えるのではなく、冷ましてから与えるようにしましょう。
人も加熱したさつまいもをすぐに食べようとすると火傷してしまいます。
猫も同じように熱いままでは火傷してしまう危険性があります。
猫は人よりも温度に敏感な動物であり、0.5 ℃変わるだけでも違いが感知することができます。
適した温度は小動物の体温と同じ35℃前後がおすすめです。
味付けはしない
上記でも一部紹介したようにさつまいもを与える際に濃い味付けはもちろんですが、味付け自体しないようにしましょう。
人の場合は味付けをすることでよりおいしく食べることができますが、猫の場合は虫歯や肥満の原因となってしまいやすいです。
そのため、猫にさつまいもを与えるのであればそのまま加熱して冷やしたもので問題ありません。
さつまいもはそのままでも充分甘さを感じることができます。
なので人が食べるようなさつまいもを使用した料理は与えないようにしましょう。
猫が喜ぶさつまいもを使用したおやつのレシピ
 猫ちゃん用ごまさつまクッキーはさつまいもで作ったクッキーであり、ゴマで風味づけがされています。
材料はさつまいも70g・ベーキングパウダー小さじ半分・薄力粉30g・ゴマ5g・豆乳小さじ1杯です。
作り方は薄力粉とベーキングパウダーをふるいにかけて混ぜます。さつまいもはレンジで加熱してすり潰していきます。
さつまいもが冷えてしまうと固くなってしまうのでできるだけ熱いうちにつぶすようにしましょう。
豆乳を少し入れてつぶすことでつぶしやすくなります。
次に、ゴマをすり潰しベーキングパウダーと薄力粉を混ぜた中に入れ、すり潰したさつまいもの中に投入します。
粉っぽさがなくなるまで混ぜ、豆乳も少しずつ入れることがポイントです。
あとは出来上がった生地をラップに包み、綿棒で均一になるまで伸ばしていきましょう。
最後は型でくりぬいて180℃のオーブンで2分焼けば完成です。
猫ちゃん用ごまさつまクッキーはさつまいもで作ったクッキーであり、ゴマで風味づけがされています。
材料はさつまいも70g・ベーキングパウダー小さじ半分・薄力粉30g・ゴマ5g・豆乳小さじ1杯です。
作り方は薄力粉とベーキングパウダーをふるいにかけて混ぜます。さつまいもはレンジで加熱してすり潰していきます。
さつまいもが冷えてしまうと固くなってしまうのでできるだけ熱いうちにつぶすようにしましょう。
豆乳を少し入れてつぶすことでつぶしやすくなります。
次に、ゴマをすり潰しベーキングパウダーと薄力粉を混ぜた中に入れ、すり潰したさつまいもの中に投入します。
粉っぽさがなくなるまで混ぜ、豆乳も少しずつ入れることがポイントです。
あとは出来上がった生地をラップに包み、綿棒で均一になるまで伸ばしていきましょう。
最後は型でくりぬいて180℃のオーブンで2分焼けば完成です。
猫にさつまいもを与える時の注意点は?
 猫にさつまいもを与えても問題はありませんが、注意しなければならないポイントがいくつかあります。
そのため、知識なくさつまいもを与えることは危険なため、必ず注意点を把握してからさつまいもを猫に与えるようにしましょう。
猫にさつまいもを与えても問題はありませんが、注意しなければならないポイントがいくつかあります。
そのため、知識なくさつまいもを与えることは危険なため、必ず注意点を把握してからさつまいもを猫に与えるようにしましょう。
さつまいもアレルギーに注意
人も食べ物に対してアレルギー反応を起こしますが、猫も同様に食べ物に対してアレルギー反応を起こしてしまう恐れがあります。
さつまいもアレルギーも存在しており、さつまいもを食べてしまうと痒みや咳などの症状があらわれてしまいます。
さつまいもアレルギーである危険性も把握して、初めてさつまいもを猫に与えるのであれば少量だけにしてしばらくは経過観察をするようにしましょう。
もしアレルギー反応が出てしまったらすぐに動物病院に連れて行くようにしましょう。
そのため、さつまいもアレルギーの有無を確認する際には動物病院が開いているかを確認することも大切です。
皮による消化不良に注意
 さつまいもの皮は他の根菜と比べても皮が薄く食べやすかったり、栄養が豊富に含まれていることなどから皮がついたまま与えることも多いです。
しかし、皮は消化しにくい部分であるため、消化不良を起こしてしまう可能性があります。
そのため、普段から下痢をしてしまうような猫であればさつまいもを与えることを断念したり、皮を剥いた状態で与えるなどの一工夫を施すようにしましょう。
皮による消化不良は個体差があったり、その時の体調によって症状があらわれることもあります。
さつまいもの皮は他の根菜と比べても皮が薄く食べやすかったり、栄養が豊富に含まれていることなどから皮がついたまま与えることも多いです。
しかし、皮は消化しにくい部分であるため、消化不良を起こしてしまう可能性があります。
そのため、普段から下痢をしてしまうような猫であればさつまいもを与えることを断念したり、皮を剥いた状態で与えるなどの一工夫を施すようにしましょう。
皮による消化不良は個体差があったり、その時の体調によって症状があらわれることもあります。
まとめ
猫にさつまいもを与えても問題はなく、さまざまな栄養を摂取することができます。
また、さまざまなアレンジレシピにさつまいもは使いやすいメリットもあるので、おやつ作りの幅を広げることもできます。
しかし、消化不良を起こしてしまうリスクがあったり、事前にアレルギーがないのかも確認しなければなりません。
そのほかにも生で与えないようにしたり、蒸かすしたのであれば冷やすなどの一工夫も必要となってきます。
猫にさつまいもを与えたいのであればさまざまなひと手間を加えることが大切です。
猫にささみを与える良さや栄養効果
 ささみは低カロリーで高タンパク質な食べ物として評価されていて、猫のおやつの中でも人気が高く、アレルギーの心配がない限り食べても安心です。
安価で購入でき手軽にあげれるのも魅力ですが、猫に与えた場合の栄養効果を調べて見ました。
ささみは低カロリーで高タンパク質な食べ物として評価されていて、猫のおやつの中でも人気が高く、アレルギーの心配がない限り食べても安心です。
安価で購入でき手軽にあげれるのも魅力ですが、猫に与えた場合の栄養効果を調べて見ました。
脂質
脂質を多く摂ってしまうと肥満の元になってしまいますが、ダイエット中でも必要な栄養素で脂質が不足してしまうと皮膚のトラブルやストレスの原因にもなってしまいます。
ささみは他の肉類と比較をすると含まれている脂質が低く、ダイエットさせたい場合に適切でカロリーを抑えて栄養価の高い食事を与えたい時にもおすすめな食材です。
脂質は大切なエネルギー源だけではなく、ホルモンなどの構成や臓器の保護を行い皮下脂肪として体を寒冷から守る役割もあります。
タンパク質
 タンパク質は三大栄養素で、臓器や筋肉、被毛や皮膚など体を作る要素として非常に大切なものになります。
肉食である猫の臓器の作りは、植物性タンパク質よりも動物性タンパク質の方が消化しやすくなっています。
猫が1日に必要とするタンパク質は体重1㎏に対して1〜5gで、犬に比べて必要摂取量が多くなります。
猫は毎日タンパク質を消費しますので、タンパク質不足にならないよう注意が必要です。
タンパク質は三大栄養素で、臓器や筋肉、被毛や皮膚など体を作る要素として非常に大切なものになります。
肉食である猫の臓器の作りは、植物性タンパク質よりも動物性タンパク質の方が消化しやすくなっています。
猫が1日に必要とするタンパク質は体重1㎏に対して1〜5gで、犬に比べて必要摂取量が多くなります。
猫は毎日タンパク質を消費しますので、タンパク質不足にならないよう注意が必要です。
ビタミンB6
ビタミンB6は水溶性のビタミンの1つで、赤血球を作り出してくれます。
アミノ酸となるタンパク質を効率よく体に取り込むために欠かせなく、猫の生命維持や成長にも必要な栄養素です。
貧血予防効果や免疫機能を正常に保ち皮膚炎の予防効果があり、脂肪からエネルギーを生成する働きもあります。
不足してしまった場合には、皮膚炎や血液の異常を起こしてしまいます。
カリウム
 細胞がきちんと機能するために必要なミネラルとして働き、心臓や腎臓のサポートをする役割をしています。
猫にとってカリウムは、摂取量が多すぎても少なすぎても体に悪影響を与えてしまいます。
高カリウム血症と低カリウム血症はどちらも発症に気づきにくく、四股のしびれや筋肉の低下、吐き気などがあり悪化しやすいのが特徴です。
細胞がきちんと機能するために必要なミネラルとして働き、心臓や腎臓のサポートをする役割をしています。
猫にとってカリウムは、摂取量が多すぎても少なすぎても体に悪影響を与えてしまいます。
高カリウム血症と低カリウム血症はどちらも発症に気づきにくく、四股のしびれや筋肉の低下、吐き気などがあり悪化しやすいのが特徴です。
ナイアシン(ビタミンB3)
ナイアシンは三大栄養素として知られるタンパク質・炭水化物・脂質を代謝する際に必要な栄養素です。
猫は体内で合成できる量が少なく、生成されるよりも早く次から次へと分解されてしまいます。
尿に溶けて体内から失われやすい為、毎日必要量を食物から摂取しなくてはいけなくなります。
皮膚を乾燥から守ってくれる働きがあり、不足してしまうと皮膚炎を起こしてしまいます。
カルシウム
 カルシウムは骨の成長など体の発育に必要な栄養素で、不足したり多く摂ってしまうと尿路結石症や骨格異常になりやすくなります。
尿路結石症はカルシウムを多く摂ってしまった場合に、便として排出される「シエウ酸」がカルシウムと結合して体内に溜まり起ります。
発見が遅くなると命にかかわる場合もありますので、いつもよりもトイレに行く回数が増え尿の量が少なく臭いや鳴き声に異変を感じたら、早めに動物病院での診察を受けるようにします。
カルシウムは骨の成長など体の発育に必要な栄養素で、不足したり多く摂ってしまうと尿路結石症や骨格異常になりやすくなります。
尿路結石症はカルシウムを多く摂ってしまった場合に、便として排出される「シエウ酸」がカルシウムと結合して体内に溜まり起ります。
発見が遅くなると命にかかわる場合もありますので、いつもよりもトイレに行く回数が増え尿の量が少なく臭いや鳴き声に異変を感じたら、早めに動物病院での診察を受けるようにします。
リン
リンはカルシウムと共に骨の成長に関わってくる大切な栄養素で、多く摂ってしまうと腎臓に負担がかかってしまうためカルシウムとバランスよく摂取する必要があります。
ささみはリンが多く含まれているため、腎不全になるリスクが高くなってしまいます。
腎臓の役割である血中の老廃物をろ過したり、体内に必要な水分を調節する機能を衰えさせ尿毒症や脱水症状を引き起こしてしまいます。
猫にささみを与える時の注意点
 猫はタンパク質を主に摂取する肉食動物ですので、猫の食事にはタンパク質が必要になります。
ささみはタンパク質が豊富で消化が良く、他の栄養素も多く含まれています。
ささみを猫に与える際の注意点を調べて見ました。
猫はタンパク質を主に摂取する肉食動物ですので、猫の食事にはタンパク質が必要になります。
ささみはタンパク質が豊富で消化が良く、他の栄養素も多く含まれています。
ささみを猫に与える際の注意点を調べて見ました。
与えすぎは太る&腎臓病の原因にもなる
栄養が豊富なささみは猫にとっても健康に良いはずですが、あげすぎてしまうと摂取カロリーを大幅に超えて太ってしまう場合があります。
ささみにはタンパク質とカリウムの次にリンが含まれている為、猫が喜ぶからと好物のささみを毎日与えてしまうと過剰摂取となり腎臓病の原因になってしまいます。
腎臓にダメージを与えてしまうと完治するまでに時間がかかり、与える食事にも注意が必要になります。
食べさせる際は加熱しよう
 生のささみには細菌がいる可能性があり、スーパーで売られているささみは猫に生で食べさせられる鮮度ではありません。
感染症にかかる恐れがありますので、猫にささみを与える時は生ではなくきちんと加熱してから与えるようにします。
肉食動物の猫は生の方が好きなのではと思ってしまいますが、後で具合が悪くなる原因にもなってしまいますので茹でてからあげるようにすれば安心です。
生のささみには細菌がいる可能性があり、スーパーで売られているささみは猫に生で食べさせられる鮮度ではありません。
感染症にかかる恐れがありますので、猫にささみを与える時は生ではなくきちんと加熱してから与えるようにします。
肉食動物の猫は生の方が好きなのではと思ってしまいますが、後で具合が悪くなる原因にもなってしまいますので茹でてからあげるようにすれば安心です。
塩分量を抑えるために味付けはしない
猫は元々体に塩分が溜まりやすい体質で皮膚に発汗作用の機能はなく、発汗できるのは足の裏など体の中でも狭い範囲のみになります。
人間のように発汗して塩分を体内から放出できない為、猫の体に塩分を蓄積させないように塩分量を控えた食事を与える必要があります。
食材によって加工する前から塩分が含まれているものがあり、塩などの味付けをしてしまうと塩分の摂取量が増え体の負担になってしまいます。
ささみを購入する際は味付けがなってないものを選ぶようにし、調理をする時にも味付けはしないようにします。
初めて食べさせる時は下痢などのアレルギー症状に注意する
 猫のアレルギー症状で上位を占めているのはタンパク質です。
タンパク質を多く含んでいるささみを初めて与える時は、アレルギー症状を発症させないよう猫の様子を細かく観察するようにします。
アレルギーを発症すると食べたものを吐いたり、下痢をし皮膚や口元などに炎症が起きます。
ささみはアレルギー症状がなければドライフードよりもしっとりとした食感をしていますので、体調不良や食欲が落ちている時に与えるのに向いています。
猫のアレルギー症状で上位を占めているのはタンパク質です。
タンパク質を多く含んでいるささみを初めて与える時は、アレルギー症状を発症させないよう猫の様子を細かく観察するようにします。
アレルギーを発症すると食べたものを吐いたり、下痢をし皮膚や口元などに炎症が起きます。
ささみはアレルギー症状がなければドライフードよりもしっとりとした食感をしていますので、体調不良や食欲が落ちている時に与えるのに向いています。
猫が喜ぶささみを使用したおやつのレシピ
 【レシピ名:愛猫用 しっとり柔らか鶏肉ささみ♡】
材料:鶏肉(ささみ・もも肉・むね肉など) 3~6本
水 たくさん
作り方①:鍋の中にたっぷりの水と鶏肉を入れて中火にかけ、沸騰直前に弱火にします。
②:約15分茹でて中までしっかり火が通ったら出来上がり!
③:茹であがったらザルにあげて冷水で洗い、タッパーに割いて入れて保存します。
※冬場は3日以内、夏場は2日以内に使いきる様にします。
④:柔らかく茹でた人参、キャベツ、ごはんなどを猫ご飯に入れる場合は1割以下を目安にします。
⑤:夏バテで食欲がない時などは、猫缶に混ぜたり鶏肉のゆで汁を一緒に与えてるのもおすすめです。
【レシピ名:愛猫用 しっとり柔らか鶏肉ささみ♡】
材料:鶏肉(ささみ・もも肉・むね肉など) 3~6本
水 たくさん
作り方①:鍋の中にたっぷりの水と鶏肉を入れて中火にかけ、沸騰直前に弱火にします。
②:約15分茹でて中までしっかり火が通ったら出来上がり!
③:茹であがったらザルにあげて冷水で洗い、タッパーに割いて入れて保存します。
※冬場は3日以内、夏場は2日以内に使いきる様にします。
④:柔らかく茹でた人参、キャベツ、ごはんなどを猫ご飯に入れる場合は1割以下を目安にします。
⑤:夏バテで食欲がない時などは、猫缶に混ぜたり鶏肉のゆで汁を一緒に与えてるのもおすすめです。
まとめ
ささみは栄養が豊富で猫にも喜ばれる食材ですが、人間と同じように過剰に摂取をする事で体に害が及ぶ場合もあります。
猫が病気になってしまうと飼い主にとっては辛く、完治するまで気が休まらずかわいそうな愛猫の姿を見なくてはいけなくなってしまいます。
そうならない為にも生のままではなく加熱をして与え、いくら喜んでくれるからといっても摂取量を守ってあげる事が大切です。
手作りでできる【しっとり柔らか鶏肉ささみ】に挑戦してみるのもいいかもしれませんね!
猫にアロマは絶対NGの理由
 コロナ禍でストレスが溜まることが多い現在、アロマで心も体もリラックスしようと考えている方も多いでしょう。
自宅内で常にアロマを焚いている方も多いかと思うのですが、猫と一緒に暮らす上で注意しなければならないことがあります。
また猫にアロマは絶対にNGということも言われていますので、その理由についてご紹介します。
コロナ禍でストレスが溜まることが多い現在、アロマで心も体もリラックスしようと考えている方も多いでしょう。
自宅内で常にアロマを焚いている方も多いかと思うのですが、猫と一緒に暮らす上で注意しなければならないことがあります。
また猫にアロマは絶対にNGということも言われていますので、その理由についてご紹介します。
体を舐める習慣を持つ猫
アロマを焚くと室内中にアロマの香りが充満しとっても癒されますよね。
ということは一緒に暮らしている愛猫の体にもアロマの微量な成分がぴったりと付着するということになります。
そもそも猫は自分の体を舐める習性があるため、鼻から吸収されるだけでではなく、口からも体に取り込まれてしまうのです。
そうすると猫が口にしてはいけない成分も一緒に体内に取り込んでしまうということもゼロではないため、猫と一緒に生活している場合はアロマは使用しないことが安全と言えるでしょう。
嗅覚が優れている
 猫は、動物上の分類が肉食動物です。
見た目は愛らしいですが、野生の猫たちは新鮮な肉を獲物に選びます。
腐った肉は体に悪影響を及ぼすので、猫は悪い肉かどうかを選別しなければいけません。
自然で生き抜くため「腐った肉はNG、新鮮な肉を食べよう」という術が見に付いたことで発達したのが嗅覚なのです。
人間が良い香りと感じたからといって、それが猫にも同じように感じ取れるかは疑問に思います。
そのため、猫は人間よりはるかに香りに敏感な動物と言えます。
ということはアロマの香りは猫にとって「謎めいた香り」となり、嗅いでいるだけでストレスになってしまうことも
猫は、動物上の分類が肉食動物です。
見た目は愛らしいですが、野生の猫たちは新鮮な肉を獲物に選びます。
腐った肉は体に悪影響を及ぼすので、猫は悪い肉かどうかを選別しなければいけません。
自然で生き抜くため「腐った肉はNG、新鮮な肉を食べよう」という術が見に付いたことで発達したのが嗅覚なのです。
人間が良い香りと感じたからといって、それが猫にも同じように感じ取れるかは疑問に思います。
そのため、猫は人間よりはるかに香りに敏感な動物と言えます。
ということはアロマの香りは猫にとって「謎めいた香り」となり、嗅いでいるだけでストレスになってしまうことも
過度な香りは猫には刺激が強い
単に「香りを楽しむだけ」というアロマだとしても、油断は大敵。
猫はクンクンと香りを嗅いだときに、体内に成分を吸収するので、毎日アロマを嗅いでしまうと、少しずつ成分が取り込まれていきます。
人間にとっては優雅な香りと思えても、猫には刺激が大きい物です。
身体に害を及ぼす可能性が大きいですし、慣れない強い香りには猫はストレスをためてしまうことを考えなければいけませんね。
人間に効果的なアロマも猫には有害
 アロマは化合物を含んでおり人工的にブレンドされています。
ということは、猫の体内に入るとよくない成分も含まれているということになりますね。
飼い主さんと愛猫が一緒の空間にいるとき優れた嗅覚、体を舐める習性などがある体質の猫の方が体内に入り込みやすくなってしまいます。
一般的には健康や美容効果があるアロマでも人間と猫では違うという意識を持たなければ愛猫を守れないかもしれませんね。
アロマは化合物を含んでおり人工的にブレンドされています。
ということは、猫の体内に入るとよくない成分も含まれているということになりますね。
飼い主さんと愛猫が一緒の空間にいるとき優れた嗅覚、体を舐める習性などがある体質の猫の方が体内に入り込みやすくなってしまいます。
一般的には健康や美容効果があるアロマでも人間と猫では違うという意識を持たなければ愛猫を守れないかもしれませんね。
肝臓の病気になる可能性もある
猫が苦手とする成分が体内に入り込んでしまうため、猫の肝臓への負担が増えます。
愛猫の体重や体調・年齢などがあるので一概には言えませんが、ほんの少しのアロマでも猫の体への影響は大きいです。
次第に肝臓の病気になるかもしれないことを頭に入れておいた方がいいかもしれませんね。
香りを吸収しやすい薄い皮膚
 人間も動物も皮膚には刺激をシャットアウトし体を守る機能が備わっています。
基本的に、外部とふれ合い異物をバリアする表皮と表皮の下にあって肌を構成する真皮、もっとも内側にあってクッション材になっている皮下組織と皮膚公造は三層からなっています。
猫の表皮は人間に比べるとかなり薄く、人間も半分もないと言われているほど。
被毛に覆われているのでそんな風に思えないかもしれませんが、猫の皮膚はかなりデリケートな構造になっているので、アロマの香りが少量でも空気中にある微々たる成分が猫の体に付着して皮膚から体内に浸透していくでしょう。
人間も動物も皮膚には刺激をシャットアウトし体を守る機能が備わっています。
基本的に、外部とふれ合い異物をバリアする表皮と表皮の下にあって肌を構成する真皮、もっとも内側にあってクッション材になっている皮下組織と皮膚公造は三層からなっています。
猫の表皮は人間に比べるとかなり薄く、人間も半分もないと言われているほど。
被毛に覆われているのでそんな風に思えないかもしれませんが、猫の皮膚はかなりデリケートな構造になっているので、アロマの香りが少量でも空気中にある微々たる成分が猫の体に付着して皮膚から体内に浸透していくでしょう。
取り込まれた有害物質を解毒できない
猫の体内には植物を消化及び分解するという解毒作用、グルクロン酸抱合の能力が備わっていません。
そもそも肉食動物なので植物の有害物質を解毒作用がないのです。
アロマは香りなので、猫が直接触れなければいいと思うかもしれませんが、実際には鼻から体内に侵入し、粘膜や血管を通じて猫の体内に運ばれます。
しかし、人間のように解毒して排出する機能はないので、有害な物質も蓄積されていくことに。
そうなると、蓄積された成分の猫の肝臓を脅かすようになり、体に大きな負担がかかることになります。
結果、過敏反応を起こす量の有害物質となってしまうため、中毒症状を引き起こす危険性が出てきてしまいます。
特にオレンジ系のアロマは気をつけよう
 アロマにはさまざまな香りがあり、猫にとっては特にオレンジ系のアロマは要注意です。
オレンジ系のアロマには「リモネン」という成分が入っており、猫にとってかなり有害作用を引き起こすことが発見されています。
また、「ピネン」という成分にも過剰に反応し、この2種類はシトラス類の精油とパインの精油に最も含まれていると言われているため、猫にはアロマ全般使わないことをおすすめしますが、特にオレンジ系のものには注意しましょう。
アロマにはさまざまな香りがあり、猫にとっては特にオレンジ系のアロマは要注意です。
オレンジ系のアロマには「リモネン」という成分が入っており、猫にとってかなり有害作用を引き起こすことが発見されています。
また、「ピネン」という成分にも過剰に反応し、この2種類はシトラス類の精油とパインの精油に最も含まれていると言われているため、猫にはアロマ全般使わないことをおすすめしますが、特にオレンジ系のものには注意しましょう。
猫がアロマオイルを嗅いだ時の症状
 猫が誤ってアロマオイルを嗅いでしまった時にはさまざまな症状が出ることがわかっています。
ここでは、どのような症状が出るのか部位別にご紹介していきます。
猫が誤ってアロマオイルを嗅いでしまった時にはさまざまな症状が出ることがわかっています。
ここでは、どのような症状が出るのか部位別にご紹介していきます。
皮膚の症状
中毒症状には皮膚の異常も認められており、主に皮膚の赤みや痒み、腫れ、炎症などが見られることがあります。
いつもと違った皮膚症状が見られ、アロマを使用していたらアロマオイルを嗅いだことによる症状の可能性が高いため、悪化する前に受診するようにしましょう。
目の症状
猫がアロマオイルを嗅ぎ、中毒を引き起こした場合、「流涙(りゅうるい)」や「まぶしがる」などの症状が見られることがあります。
流涙とはその名の通り、涙が溢れるように出る症状のことです。
グルーミングを介して誤って目にオイルが入ってしまうと「角膜潰瘍」ができる可能性もあるとのこと。
角膜潰瘍とは、角膜の組織が深く損傷してしまう病変のことで強い痛みを伴います。
その他の症状では死亡ケースも
 アロマによる中毒症状は他にもたくさんあり以下のような症状が報告されています。
・下痢、嘔吐
・失禁
・元気がなくなる、食欲不振
・低体温
・筋肉の震え
・抑うつ状態
・口腔粘膜の炎症、よだれ
・肝臓の数値があがる
・死亡
他の薬物などで発祥する中毒症状と似ており、最悪の場合死亡する恐れもあります。
同居家族が複数いる場合は、猫にアロマは絶対ダメということを周知しておきましょう。
また、これらの症状はアロマ成分を取り込んでからすぐに発症するわけではなく、2~8時間ほどで起こることもあるのですが、数年間かけて体内に蓄積し、肝不全を起こすこともあると言われています。
アロマによる中毒症状は他にもたくさんあり以下のような症状が報告されています。
・下痢、嘔吐
・失禁
・元気がなくなる、食欲不振
・低体温
・筋肉の震え
・抑うつ状態
・口腔粘膜の炎症、よだれ
・肝臓の数値があがる
・死亡
他の薬物などで発祥する中毒症状と似ており、最悪の場合死亡する恐れもあります。
同居家族が複数いる場合は、猫にアロマは絶対ダメということを周知しておきましょう。
また、これらの症状はアロマ成分を取り込んでからすぐに発症するわけではなく、2~8時間ほどで起こることもあるのですが、数年間かけて体内に蓄積し、肝不全を起こすこともあると言われています。
猫飼いにはアロマのお風呂がおすすめ
 猫にはアロマは禁物とわかっていても、癒しを求めている方はどうしても使いたい場面もあるでしょう。
そんな時はアロマのお風呂がおすすめです。
しかし、お風呂場にアロマの成分が残ることになるので、日頃から猫が出入りしないことが原則です。
猫にはアロマは禁物とわかっていても、癒しを求めている方はどうしても使いたい場面もあるでしょう。
そんな時はアロマのお風呂がおすすめです。
しかし、お風呂場にアロマの成分が残ることになるので、日頃から猫が出入りしないことが原則です。
バスタブでアロマに癒される
バスタブに入れるアロマの量は、全身が浸かるお湯(約200ml)に1滴から5滴ほどが安全です。
半身浴で1滴から3滴くらいが目安。
お風呂だけでもリラックス効果が高いですが、アロマが加わることで相乗効果が期待できますよ。
ただ、バスタブで愛猫をシャンプーする場合はしっかり洗剤で洗い流しアロマが残らないようにしておきましょう。
部分浴なら手軽に楽しめる
 忙しいしバスタブには浸からないという方もいるでしょう。
そんな方は部分欲が安全でおすすめです。
作り方は洗面器やバケツにお湯をはり、精油を1~2滴たらすだけ。
手の手首部分まで浸すと上半身を、足であればくるぶしまで浸すと全身が驚くほどあたたまります。
体調がすぐれないときに全身浴をすると体力が奪われてしまいますが、部分欲であれば手軽なのもメリットですよね。
負担を減らしながらも血行をよくしてくれるでしょう。
注意点としては、愛猫に触れる前にしっかり洗い流すようにしてください。
忙しいしバスタブには浸からないという方もいるでしょう。
そんな方は部分欲が安全でおすすめです。
作り方は洗面器やバケツにお湯をはり、精油を1~2滴たらすだけ。
手の手首部分まで浸すと上半身を、足であればくるぶしまで浸すと全身が驚くほどあたたまります。
体調がすぐれないときに全身浴をすると体力が奪われてしまいますが、部分欲であれば手軽なのもメリットですよね。
負担を減らしながらも血行をよくしてくれるでしょう。
注意点としては、愛猫に触れる前にしっかり洗い流すようにしてください。
まとめ
今回は猫とアロマについてご紹介してきました。
人間にとっては癒しの香りでも、猫にとっては絶対NGだということがわかりましたね。
初めて知ったという方もいると思うので今回この記事を読んで頂いて方で猫を飼っている家庭はすぐにアロマを使用するのを辞めてお風呂で使用するようにしましょう。
猫はアイスを食べられる?
 暑い日のおやつはやっぱりアイスですが、猫にもアイスを上げてもいいのかな?と思う飼い主さんがいることでしょう。
猫にアイスを食べさせること自体は、悪いことではないのですが、そもそもアイスには猫の体に必要な栄養素は、あまり含まれていないのです。
また、アイスの味や含まれている成分などにより中毒を起こす可能性もあるので、よく確認しなければいけません。
ここではアイスを与えることで起こる危険性などについて詳しく解説していきます。
暑い日のおやつはやっぱりアイスですが、猫にもアイスを上げてもいいのかな?と思う飼い主さんがいることでしょう。
猫にアイスを食べさせること自体は、悪いことではないのですが、そもそもアイスには猫の体に必要な栄養素は、あまり含まれていないのです。
また、アイスの味や含まれている成分などにより中毒を起こす可能性もあるので、よく確認しなければいけません。
ここではアイスを与えることで起こる危険性などについて詳しく解説していきます。
猫にとって人用アイスが危険な理由
 猫にとって人間のアイスは危険な場合が多いものです。
その理由を詳しく紹介しますが、基本的に「冷たいもの」はあまりよくないのです。
また中毒症状を起こすリスクや人間が美味しいと感じる味付けは猫の健康を害します。
猫には不要の成分が多いので、正しい知識を持っておきましょう。
猫にとって人間のアイスは危険な場合が多いものです。
その理由を詳しく紹介しますが、基本的に「冷たいもの」はあまりよくないのです。
また中毒症状を起こすリスクや人間が美味しいと感じる味付けは猫の健康を害します。
猫には不要の成分が多いので、正しい知識を持っておきましょう。
アイスの成分で中毒や下痢を起こす可能性がある
まず一つ目の理由は健康を阻害するかもしれないという点です。
アイスの主な原料は牛乳や乳製品、糖類となります。
糖類を吸収や消化することは得意ではないため、猫の内臓に大きな負担がかかる可能性が考えられます。
牛乳に含まれる乳糖は猫の体内で分解できないので、下痢をすることがよくあります。
アイスに入っているナッツ類はアレルギーを持つ猫にはとても危険で、重い中毒を起こします。
さらにチョコレートやコーヒー味のアイスは数時間で中毒症状となり、興奮状態となったり、痙攣を起こす場合もあるので、食べさせてはいけません。
冷たいアイスは頭痛を起こす
 人間が冷たいアイスを食べたときに頭が痛くなることがありますが、猫にも同じことが起こります。
猫はアイスを食べた時や後に、動きを止めて目を細めたり、イライラしたような唸り声を出したり、口を開けながら白目をむいたりなど、様々な行動を取ります。
これをブレインフリーズと言います。
「冷たい!」という感覚が「痛み」と勘違いされて感じていると言われています。
脳みそが固まるという意味で、冷たいものを食べたとき、一時的に血流を増やして体温をあげようとして頭につながる血管が膨張し、頭痛を起こしているのです。
痛いのは可哀想ですよね。
特にアイスの栄養が必要ではないので、無理して与えることではありません。
人間が冷たいアイスを食べたときに頭が痛くなることがありますが、猫にも同じことが起こります。
猫はアイスを食べた時や後に、動きを止めて目を細めたり、イライラしたような唸り声を出したり、口を開けながら白目をむいたりなど、様々な行動を取ります。
これをブレインフリーズと言います。
「冷たい!」という感覚が「痛み」と勘違いされて感じていると言われています。
脳みそが固まるという意味で、冷たいものを食べたとき、一時的に血流を増やして体温をあげようとして頭につながる血管が膨張し、頭痛を起こしているのです。
痛いのは可哀想ですよね。
特にアイスの栄養が必要ではないので、無理して与えることではありません。
アレルギーを発症する可能性がある
先程アイスに含まれるナッツ類やチョコレートでアレルギーを起こすと述べましたが、他にもアレルギーの可能性があります。
アイスのコーンには小麦粉や卵が使用されているので、猫がアレルギーを起こすこともあり得ます。
初期にはフケが出たり、かゆみが出たりなどの皮膚疾患が現れることが多いです。
普段、アレルギーには気が付かないことも多いので、初めて食べたものでいきなり強いアレルギーを起こす猫もいます。
少量だけでも強いアレルギーを持っていたら、命の危険があるので猫に食べさせることは危険です。
食べ過ぎで肥満になってしまう
 最後は肥満の問題です。
アイスの糖分のせいで、猫が肥満に陥ることもあります。
猫にとって必要なカロリーやエネルギーは、総合栄養食のフードで充分に足りるので、おやつを与える必要は特にありません。
アイスはカロリーが高く、添加物も豊富に含まれているので、人間にとっても食べ過ぎは絶対に良くない食べ物です。
猫は人間と比べてとても小さな動物で、人間と同じように消化することも難しいので、猫の体に良いものではありません。
最後は肥満の問題です。
アイスの糖分のせいで、猫が肥満に陥ることもあります。
猫にとって必要なカロリーやエネルギーは、総合栄養食のフードで充分に足りるので、おやつを与える必要は特にありません。
アイスはカロリーが高く、添加物も豊富に含まれているので、人間にとっても食べ過ぎは絶対に良くない食べ物です。
猫は人間と比べてとても小さな動物で、人間と同じように消化することも難しいので、猫の体に良いものではありません。
猫が人用アイスを食べてしまった時の注意点や対応
 猫には人用アイスはを与えてはいけないことがわかったと思います。
猫の体重や年齢、アレルギーの有無等によっても対応が異なりますので、すぐに命に関わるとは限りませんが、対応の仕方を知っておくことは必要です。
次の注意点や対応を理解しておきましょう。
猫には人用アイスはを与えてはいけないことがわかったと思います。
猫の体重や年齢、アレルギーの有無等によっても対応が異なりますので、すぐに命に関わるとは限りませんが、対応の仕方を知っておくことは必要です。
次の注意点や対応を理解しておきましょう。
なるべく早めに獣医師に診てもらう
まずは、何のフレーバーのアイスを食べたのかを確認します。
中毒やアレルギーを引き起こす危険性もあるので、早めに獣医師に診てもらいましょう。
1歳になっていない子猫の場合は消化器官が未発達なので、特に警戒が必要です。
7歳以上のシニアも同様で、心臓が弱ってきていることもあるため、ブレインフリーズは命に関わります。
そして過去に食べて問題がないからと繰り返して与えることで健康を害するものとなるので、与えないことを徹底してください。
アイスの袋やカップはすぐに処理する
 人間のアイスを与えないと同時に、食べた後のカップや袋をすぐに片付けることも大切です。
食べ終わったアイスのフタや容器をそのまま置いておくと、猫がその容器を舐める恐れがあるためです。
体に悪いからと与えなかったのに、猫が舐めてしまったら悲しいですね。
食べている途中でうっかり置いてしまうことも避け、アイスの管理は注意深くしっかりとしてください。
人間のアイスを与えないと同時に、食べた後のカップや袋をすぐに片付けることも大切です。
食べ終わったアイスのフタや容器をそのまま置いておくと、猫がその容器を舐める恐れがあるためです。
体に悪いからと与えなかったのに、猫が舐めてしまったら悲しいですね。
食べている途中でうっかり置いてしまうことも避け、アイスの管理は注意深くしっかりとしてください。
猫にアイスを与えたい時の代替品
 飼い主さんが美味しそうに食べているアイスを欲しがる猫も多いようです。
また暑さが尋常ではない昨今、熱中症対策としてアイスを与えたいと考える飼い主さんにアイスの代わりとなるものを紹介します。
家で使えそうなものをうまく活用してみてください。
飼い主さんが美味しそうに食べているアイスを欲しがる猫も多いようです。
また暑さが尋常ではない昨今、熱中症対策としてアイスを与えたいと考える飼い主さんにアイスの代わりとなるものを紹介します。
家で使えそうなものをうまく活用してみてください。
猫用アイスやシャーベット
人用のアイスを食べさせなくても、猫が問題なく食べることができるペット専用アイスなども購入できます。
材料は猫用ミルクやさつまいも、魚などが多いです。
また猫のおやつ(ちゅうるなど)に水を混ぜて冷凍庫で凍らせるとアイスができあがります。
猫用アイスでも与えすぎはよくありませんので、少量にしてください。
また、アイスを与えるときのスプーンは人が使うものとは別にしましょう。
猫と人間の間で感染する「パスツレラ症」という感染症があり、人間が呼吸器疾患を起こすことがあります。
桃やリンゴ・スイカなどの果物
 種類によって、果物は猫の栄養バランスを手助けしてくれる味方です。
また、水分も豊富なので、水分補給の一環にもなることができます。
夏にはスイカを飼い主さんと一緒に少し味わうと楽しいです。
あまり冷たくしすぎないほうが猫には良いでしょう。
桃やすりおろしたりんごなども食欲が落ちているときには目先が変わって食べやすいおやつになります。
ほんの少し与えるようにしてください。
種類によって、果物は猫の栄養バランスを手助けしてくれる味方です。
また、水分も豊富なので、水分補給の一環にもなることができます。
夏にはスイカを飼い主さんと一緒に少し味わうと楽しいです。
あまり冷たくしすぎないほうが猫には良いでしょう。
桃やすりおろしたりんごなども食欲が落ちているときには目先が変わって食べやすいおやつになります。
ほんの少し与えるようにしてください。
ヨーグルト
水分補給という観点からもヨーグルトは良い食べ物です。
必ず無糖のものを選んで、猫の体の大きさから推測して、大さじ1〜3杯ほどで調整しながら、ヨーグルトをあげましょう。
人間と同様に腸内環境を整える効果が期待でき、乳酸菌は歯周病の原因になる細菌を減少させるとも言われています。
いろいろな効果があるヨーグルトですが、体に合わない猫もいて下痢になることもありますので、初めて与えた際は健康観察を十分にしてください。
まとめ
猫が人間のアイスを食べると健康を害してしまうので、それは絶対に避けましょう。
欲しがるからと何でも与えることはよくありません。
猫の口に入るものについて正しい知識を持っおくことはとても大切です。
健康管理をするのは飼い主さんの役目なので、猫用のアイスやヨーグルトなどを用意したり、涼しい場所を作ってあげたりして工夫してみてください。
 猫は暖かい場所が大好きですよね。
特に日向ぼっこをしている猫を見ることが多く、とても気持ち良さそうにしている姿はほんと可愛いです。
ですが、猫にとって日向ぼっこは気持ちいいだけではなく、良いことがたくさんあることがわかりました。
そこでここでは、猫が日向ぼっこをする理由と効果についてご紹介していきます。
猫は暖かい場所が大好きですよね。
特に日向ぼっこをしている猫を見ることが多く、とても気持ち良さそうにしている姿はほんと可愛いです。
ですが、猫にとって日向ぼっこは気持ちいいだけではなく、良いことがたくさんあることがわかりました。
そこでここでは、猫が日向ぼっこをする理由と効果についてご紹介していきます。
 日向ぼっこをしていると、猫は気持ち良さそうにウトウトしていますよね。
それは、暖かい日差しが布団のように心地よく、体が温まって眠くなってくるからです。
猫はもともと、体力温存のためによく寝る動物ですが、暖かい場所ではより睡眠の質が高まり、起きると活発になれると言われています。
日向ぼっこをしていると、猫は気持ち良さそうにウトウトしていますよね。
それは、暖かい日差しが布団のように心地よく、体が温まって眠くなってくるからです。
猫はもともと、体力温存のためによく寝る動物ですが、暖かい場所ではより睡眠の質が高まり、起きると活発になれると言われています。
 日向ぼっこをすると、体の体温があがり、全身の血流の流れが良くなります。
それによって、新陳代謝が活発になり、免疫力がアップ。
免疫力が高まるということは、病気を予防できたり長生きにも繋がるといっても過言ではないでしょう。
日向ぼっこをすると、体の体温があがり、全身の血流の流れが良くなります。
それによって、新陳代謝が活発になり、免疫力がアップ。
免疫力が高まるということは、病気を予防できたり長生きにも繋がるといっても過言ではないでしょう。
 湿気を多く含んだ被毛は、ジットリ、ベットリとして綺麗好きな猫にとっては不快以外のなにものでもありません。
そこで、日向ぼっこをすることで、毛に含まれる水分が蒸発してフワフワになるのです。
また、湿気によるジメジメが解消されることで、皮膚病にもかかりにくくなると言われています。
湿気を多く含んだ被毛は、ジットリ、ベットリとして綺麗好きな猫にとっては不快以外のなにものでもありません。
そこで、日向ぼっこをすることで、毛に含まれる水分が蒸発してフワフワになるのです。
また、湿気によるジメジメが解消されることで、皮膚病にもかかりにくくなると言われています。
 猫が日向ぼっこを好きなことがわかりましたが、メリットばかりではなく注意しなければいけないこともあります。
猫自身が自分では気づけないことも多いので、飼い主さんが日頃から日向ぼっこをしている様子をしっかり観察してあげることが大切です。
ここでは猫が日向ぼっこをする際の注意点をご紹介します。
猫が日向ぼっこを好きなことがわかりましたが、メリットばかりではなく注意しなければいけないこともあります。
猫自身が自分では気づけないことも多いので、飼い主さんが日頃から日向ぼっこをしている様子をしっかり観察してあげることが大切です。
ここでは猫が日向ぼっこをする際の注意点をご紹介します。
 皮膚がんを気にして紫外線対策をしている方も多いかと思いますが、猫も同様に皮膚がんになる可能性があります。
猫は頭や首の色素の薄い部位に発生する傾向があり、特に白猫に注意が必要です。
窓ガラスにUVカット機能のあるシートを貼ったり、窓ガラスそのものをUVカット機能のあるものにしたりするなどの工夫をしてあげてくださいね。
皮膚がんを気にして紫外線対策をしている方も多いかと思いますが、猫も同様に皮膚がんになる可能性があります。
猫は頭や首の色素の薄い部位に発生する傾向があり、特に白猫に注意が必要です。
窓ガラスにUVカット機能のあるシートを貼ったり、窓ガラスそのものをUVカット機能のあるものにしたりするなどの工夫をしてあげてくださいね。
 野良猫の場合は、常に外にいるのでいつでも自由に日向ぼっこができますが、室内飼いの場合は、どうやって日向ぼっこをさせてあげればいいかと悩んでいる方もいるでしょう。
ここでは、猫の日向ぼっこを室内飼いで行う方法についてご紹介していきます。
野良猫の場合は、常に外にいるのでいつでも自由に日向ぼっこができますが、室内飼いの場合は、どうやって日向ぼっこをさせてあげればいいかと悩んでいる方もいるでしょう。
ここでは、猫の日向ぼっこを室内飼いで行う方法についてご紹介していきます。
 猫の日向ぼっこは、できればガラス越しではなく、日光浴ができるようにしたいもの。
網戸にして脱走防止の柵をつけておき、日光浴させるという方法も良いでしょう。
ベランダに直接出すのは危険ですが、ネットを張って脱走できないようにしたうえで出したり、大型ケージごとベランダや縁側に出したりといった方法で、ガラス越しでなくても日光を浴びることができます。
どんな状況でも外に出すことで、脱走や他の猫との接触の危険があるので、飼い主さんが必ず見ているようにしてあげてください。
猫の日向ぼっこは、できればガラス越しではなく、日光浴ができるようにしたいもの。
網戸にして脱走防止の柵をつけておき、日光浴させるという方法も良いでしょう。
ベランダに直接出すのは危険ですが、ネットを張って脱走できないようにしたうえで出したり、大型ケージごとベランダや縁側に出したりといった方法で、ガラス越しでなくても日光を浴びることができます。
どんな状況でも外に出すことで、脱走や他の猫との接触の危険があるので、飼い主さんが必ず見ているようにしてあげてください。
 猫が甘えてくる姿はとっても可愛いですが、高速でキックされるのは可愛いとばかりも言っていられず、「痛い!」と叫んでしまうこともあると思います。
猫キックは一体どんな時に、どんな気持ちでしてくるのでしょうか?
猫の気持ちから、5つの理由が考えられるのでそれを紹介します。
猫が甘えてくる姿はとっても可愛いですが、高速でキックされるのは可愛いとばかりも言っていられず、「痛い!」と叫んでしまうこともあると思います。
猫キックは一体どんな時に、どんな気持ちでしてくるのでしょうか?
猫の気持ちから、5つの理由が考えられるのでそれを紹介します。
 2つ目の理由は①とは反対のものです。
人間に触られたくないなどの「嫌!」という気持ちをキックで示すことがあります。
表情や態度、声など色々なものを使い、猫は「やめて」と気持ちを伝えますが、しつこく嫌なことをされると、猫キックをしてその人物を攻撃するようです。
やめてほしいというキックは猫が本気でやっている時なので、怒っていてかなり痛いことが多いです。
しっぽをバタバタ振ったり、耳を横にしていたりすることもあるので、そういう時は猫をそっとしておいてあげてください。
2つ目の理由は①とは反対のものです。
人間に触られたくないなどの「嫌!」という気持ちをキックで示すことがあります。
表情や態度、声など色々なものを使い、猫は「やめて」と気持ちを伝えますが、しつこく嫌なことをされると、猫キックをしてその人物を攻撃するようです。
やめてほしいというキックは猫が本気でやっている時なので、怒っていてかなり痛いことが多いです。
しっぽをバタバタ振ったり、耳を横にしていたりすることもあるので、そういう時は猫をそっとしておいてあげてください。
 飼い主さんに対してではなく、何か物に対してキックを行うこともあります。
特に家の中にいる若い猫にはよく見られます。
クッションやソファなどに向けてキックを繰り返している場合は、運動やストレス解消のために体を動かしていると考えられます。
つまり退屈しているわけです。
人間のやんちゃな子供が家の中で暴れてしまうことがありますね。
それと同じ状態ですので、余っている体力を発散させてあげると解決することが多いです。
飼い主さんに対してではなく、何か物に対してキックを行うこともあります。
特に家の中にいる若い猫にはよく見られます。
クッションやソファなどに向けてキックを繰り返している場合は、運動やストレス解消のために体を動かしていると考えられます。
つまり退屈しているわけです。
人間のやんちゃな子供が家の中で暴れてしまうことがありますね。
それと同じ状態ですので、余っている体力を発散させてあげると解決することが多いです。
 猫キックの理由はさまざまあることがわかりました。
甘えているだけでも飼い主さんが痛いことも多く、猫のストレスや興奮状態を考えるとやめさせる手立ても知っておきたいものです。
次の対処法は効果があるので、困った際には一度試してみてください。
猫キックの理由はさまざまあることがわかりました。
甘えているだけでも飼い主さんが痛いことも多く、猫のストレスや興奮状態を考えるとやめさせる手立ても知っておきたいものです。
次の対処法は効果があるので、困った際には一度試してみてください。
 特に若い猫の場合、運動不足や退屈を紛らわせるためにキックをしていることが多いです。
エネルギーがあり余っており、それを発散する機会がないのはかわいそうです。
猫キックが出る前に運動や遊びで解消させるということができれば、ストレスにもならずに済みます。
元気な猫の場合、1日に30分は遊んで運動しないとストレスに繋がると言われていますので、キャットタワーを作ってあげたり、飼い主さんとの遊び時間を増やしたりしてみるとエネルギーが発散されるでしょう。
特に若い猫の場合、運動不足や退屈を紛らわせるためにキックをしていることが多いです。
エネルギーがあり余っており、それを発散する機会がないのはかわいそうです。
猫キックが出る前に運動や遊びで解消させるということができれば、ストレスにもならずに済みます。
元気な猫の場合、1日に30分は遊んで運動しないとストレスに繋がると言われていますので、キャットタワーを作ってあげたり、飼い主さんとの遊び時間を増やしたりしてみるとエネルギーが発散されるでしょう。
 猫は顔に息を吹きかけられると、強い嫌悪感を覚えます。
そのため、猫にキックされて痛いと思った時は、猫の顔に息を吹きかけて、猫キックを防ぎましょう。
息を吹きかけるという方法は、いたずらをやめさせるときにも有効なので覚えておくと役に立ちます。
驚いてキックをやめたり、その場から去っていったりします。
でも、何回も息を吹きかけていると猫に嫌われるので、気をつけてください。
猫は顔に息を吹きかけられると、強い嫌悪感を覚えます。
そのため、猫にキックされて痛いと思った時は、猫の顔に息を吹きかけて、猫キックを防ぎましょう。
息を吹きかけるという方法は、いたずらをやめさせるときにも有効なので覚えておくと役に立ちます。
驚いてキックをやめたり、その場から去っていったりします。
でも、何回も息を吹きかけていると猫に嫌われるので、気をつけてください。
 大切なペットである猫の健康には気をつけたいですね。
食事内容にも注意して、野菜を食べたほうが良いのかどうか悩んでいる人もいると思います。
でも、結論から言って猫に野菜は必要ではありません。
完全な肉食動物ですので、野菜を食べなくても健康上問題は起こりません。
その点について詳しく、また食べても良い野菜・危険な野菜について解説します。
大切なペットである猫の健康には気をつけたいですね。
食事内容にも注意して、野菜を食べたほうが良いのかどうか悩んでいる人もいると思います。
でも、結論から言って猫に野菜は必要ではありません。
完全な肉食動物ですので、野菜を食べなくても健康上問題は起こりません。
その点について詳しく、また食べても良い野菜・危険な野菜について解説します。
 野菜にはお肉に含まれていない栄養素や酵素が含まれているため、それらを補うために与えることは悪いことではありません。
しかし、野菜を生のまま与え過ぎると、消化不良を起こしてしまう可能性があるため、注意が必要です。
猫は腸が短く、野菜や果物の消化に適していません。
葉っぱをかじって毛玉を吐き出していることもあります。
野菜を与えるときはごく少量をゆでたり、刻んだりしてあげましょう。
野菜にはお肉に含まれていない栄養素や酵素が含まれているため、それらを補うために与えることは悪いことではありません。
しかし、野菜を生のまま与え過ぎると、消化不良を起こしてしまう可能性があるため、注意が必要です。
猫は腸が短く、野菜や果物の消化に適していません。
葉っぱをかじって毛玉を吐き出していることもあります。
野菜を与えるときはごく少量をゆでたり、刻んだりしてあげましょう。
 猫は肉食動物なので野菜は必要ありませんが、ビタミンや食物繊維、酵素などが多く含まれるので栄養を補うものとして利用できます。
例えば皮膚の健康や便秘の解消などには効果があると言われています。
猫が食べても良い野菜について詳しく解説します。
猫は肉食動物なので野菜は必要ありませんが、ビタミンや食物繊維、酵素などが多く含まれるので栄養を補うものとして利用できます。
例えば皮膚の健康や便秘の解消などには効果があると言われています。
猫が食べても良い野菜について詳しく解説します。
 きゅうりは猫にとってほぼ悪影響はない野菜です。
きゅうりの90%以上は水分で出来ているため、脂肪分やナトリウムがとても少なく、低カロリーで健康的です。
夏の熱中症対策としてもおやつ代わりに与えられます。
利尿作用のあるカリウム、視力維持や皮膚を守るβカロチンなどの栄養があります。
体を冷やす野菜なので、与えすぎるとお腹が冷えて下痢になるかもしれません。
猫の口に合うように少量を小さくカットして与えるようにしてください。
きゅうりは猫にとってほぼ悪影響はない野菜です。
きゅうりの90%以上は水分で出来ているため、脂肪分やナトリウムがとても少なく、低カロリーで健康的です。
夏の熱中症対策としてもおやつ代わりに与えられます。
利尿作用のあるカリウム、視力維持や皮膚を守るβカロチンなどの栄養があります。
体を冷やす野菜なので、与えすぎるとお腹が冷えて下痢になるかもしれません。
猫の口に合うように少量を小さくカットして与えるようにしてください。
 にんじんは低カロリー且つ栄養価もとても高いため、猫にとって健康的で良い野菜だと認められています。
そのため、トリーツなどに含まれていることも多い野菜です。
抗酸化作用を持つβカロチンが多いので疲労からの回復や老化防止に役立ちます。
食物繊維が豊富で便秘解消にも効果があります。
人参はすりおろして与えると、消化吸収もアップするのでおすすめです。
皮付きでも問題ありませんが、よく洗ってから使いましょう。
にんじんは低カロリー且つ栄養価もとても高いため、猫にとって健康的で良い野菜だと認められています。
そのため、トリーツなどに含まれていることも多い野菜です。
抗酸化作用を持つβカロチンが多いので疲労からの回復や老化防止に役立ちます。
食物繊維が豊富で便秘解消にも効果があります。
人参はすりおろして与えると、消化吸収もアップするのでおすすめです。
皮付きでも問題ありませんが、よく洗ってから使いましょう。
 小松菜はほうれん草よりもアクが少量で、シュウ酸の含有量もほうれん草と比較して1/15程度しかないので、量を調整すれば安心です。
ビタミン類も豊富で肝臓のサポートもしてくれます。
骨や歯を丈夫にするカルシウムも多いので、若い時から少し与えると良いでしょう。
小松菜はアブラナ科の野菜で、甲状腺ホルモンに影響を及ぼすので、甲状腺機能が低下している場合は避けたほうが良いです。
与える際には火を通し、小さくカットして消化を助けるようにしましょう。
小松菜はほうれん草よりもアクが少量で、シュウ酸の含有量もほうれん草と比較して1/15程度しかないので、量を調整すれば安心です。
ビタミン類も豊富で肝臓のサポートもしてくれます。
骨や歯を丈夫にするカルシウムも多いので、若い時から少し与えると良いでしょう。
小松菜はアブラナ科の野菜で、甲状腺ホルモンに影響を及ぼすので、甲状腺機能が低下している場合は避けたほうが良いです。
与える際には火を通し、小さくカットして消化を助けるようにしましょう。
 猫に与えても問題のない野菜はいずれも消化の負担にならないように、加熱やサイズに注意して与えてください。
次に猫が食べてはいけない野菜を紹介します。
健康に影響を及ぼす可能性があるものなので、ぜひ覚えておいてください。
猫に与えても問題のない野菜はいずれも消化の負担にならないように、加熱やサイズに注意して与えてください。
次に猫が食べてはいけない野菜を紹介します。
健康に影響を及ぼす可能性があるものなので、ぜひ覚えておいてください。
 にんにくはネギ属という分類の野菜で、ネギと同じ有機チオ硫酸化合物が含まれています。
にんにくは玉ねぎと比較すると、猛毒性が低くて、重症化はしづらいと言われています。
ですが、大量に食べると下痢などの不調を生み出します。
ネギ類と同様に貧血を起こしてしまうので、少量でも食べないように管理することが大切です。
調理に使うことが多いにんにくなので、すりおろしたものを猫がうっかりなめたりしないように注意してください。
にんにくはネギ属という分類の野菜で、ネギと同じ有機チオ硫酸化合物が含まれています。
にんにくは玉ねぎと比較すると、猛毒性が低くて、重症化はしづらいと言われています。
ですが、大量に食べると下痢などの不調を生み出します。
ネギ類と同様に貧血を起こしてしまうので、少量でも食べないように管理することが大切です。
調理に使うことが多いにんにくなので、すりおろしたものを猫がうっかりなめたりしないように注意してください。
 生のアスパラガスも猫に与えてはいけない野菜です。
アスパラガスに含まれているアルカロイドは、薬効成分のある植物毒であるため、解毒能力の弱い猫にとっては摂取NGです。
食べると腹痛・嘔吐・痙攣を起こすことがあり、心臓や腎臓、呼吸器系にも影響が出ると言われています。
また茎の周りにあるはかまと言われる葉の部分にも中毒性があります。
茹でてからなら大丈夫という見解もありますが、特に猫に与える必要性はないため、アスパラガスは与えないようにしましょう。
生のアスパラガスも猫に与えてはいけない野菜です。
アスパラガスに含まれているアルカロイドは、薬効成分のある植物毒であるため、解毒能力の弱い猫にとっては摂取NGです。
食べると腹痛・嘔吐・痙攣を起こすことがあり、心臓や腎臓、呼吸器系にも影響が出ると言われています。
また茎の周りにあるはかまと言われる葉の部分にも中毒性があります。
茹でてからなら大丈夫という見解もありますが、特に猫に与える必要性はないため、アスパラガスは与えないようにしましょう。
 家の中で生活することを推奨される猫ですが、外と出入りが自由だったりドアを開けた隙を狙って飛び出してしまったりする場合があります。
家の中に不満がある場合はもちろんですが、快適で猫にとって暮らしやすい環境であっても、戻ってこない時の猫の気持ちについて考えてみました。
家の中で生活することを推奨される猫ですが、外と出入りが自由だったりドアを開けた隙を狙って飛び出してしまったりする場合があります。
家の中に不満がある場合はもちろんですが、快適で猫にとって暮らしやすい環境であっても、戻ってこない時の猫の気持ちについて考えてみました。
 外に出てしまった猫は、野良猫の存在や興味を惹かれるものを追ってしまい帰り道がわからなくなることがあります。
男の子の場合、縄張りを侵されたと思われその地域に住む野良猫に追われて帰れなくなることも考えられます。
不可抗力ですが、暖かく暗い場所を求めて車の荷台に入り込み遠くの場所へ運ばれてしまった猫のニュースも度々あります。
外に出てしまった猫は、野良猫の存在や興味を惹かれるものを追ってしまい帰り道がわからなくなることがあります。
男の子の場合、縄張りを侵されたと思われその地域に住む野良猫に追われて帰れなくなることも考えられます。
不可抗力ですが、暖かく暗い場所を求めて車の荷台に入り込み遠くの場所へ運ばれてしまった猫のニュースも度々あります。
 野良猫の生活をしていた経験がある猫や、好奇心旺盛な性格の場合に外の世界に興味を持ち家から出てしまうこともあります。
鳥の存在や他の猫の姿を見つけて、面白そうだと感じて外に行きたい気持ちになる心理は当然でしょう。
また、家の中に猫の本能を刺激するような上下運動が出来なかったり遊びが足りなかったりして、退屈を感じていることもありますので環境作りも大切となります。
野良猫の生活をしていた経験がある猫や、好奇心旺盛な性格の場合に外の世界に興味を持ち家から出てしまうこともあります。
鳥の存在や他の猫の姿を見つけて、面白そうだと感じて外に行きたい気持ちになる心理は当然でしょう。
また、家の中に猫の本能を刺激するような上下運動が出来なかったり遊びが足りなかったりして、退屈を感じていることもありますので環境作りも大切となります。
 家から出てしまった猫が帰って来ない時、飼い主様は気が気ではないはずです。
ですが、闇雲に探し回るよりも他の人の手を借りて効率的に探したほうが早いかもしれません。
ここでは、どのような方法があるかご紹介していきます。
家から出てしまった猫が帰って来ない時、飼い主様は気が気ではないはずです。
ですが、闇雲に探し回るよりも他の人の手を借りて効率的に探したほうが早いかもしれません。
ここでは、どのような方法があるかご紹介していきます。
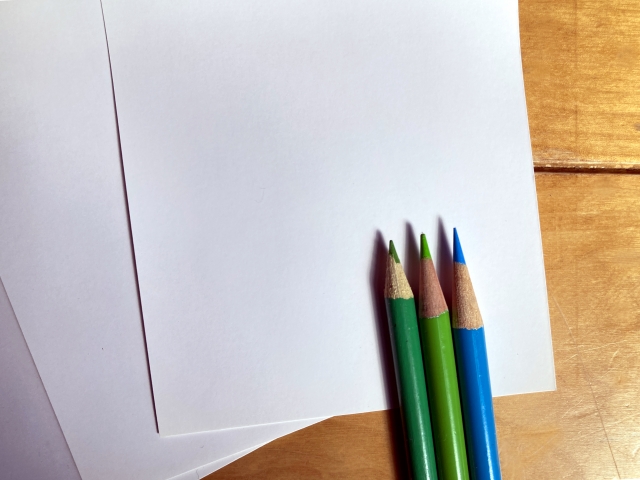 外の世界を知らない猫の場合、家の近くで動けなくなっていることがほとんどです。
いなくなってすぐであれば、猫の写真と特徴を記載したチラシを作って近所の方に周知してもらうのも効果的です。
住宅地であれば、庭の植え込みや物置の影などに隠れていることも多くあります。
また、コンビニやお店など多くの人が集まる場所にお願いして、店頭に貼らせてもらう人もいます。
内容やレイアウトに悩んでしまう場合は、捜索チラシの例文もインターネットで見つけることができますので利用してください。
外の世界を知らない猫の場合、家の近くで動けなくなっていることがほとんどです。
いなくなってすぐであれば、猫の写真と特徴を記載したチラシを作って近所の方に周知してもらうのも効果的です。
住宅地であれば、庭の植え込みや物置の影などに隠れていることも多くあります。
また、コンビニやお店など多くの人が集まる場所にお願いして、店頭に貼らせてもらう人もいます。
内容やレイアウトに悩んでしまう場合は、捜索チラシの例文もインターネットで見つけることができますので利用してください。
 他に、保護されて保健所に収容されたり、警察に届けがある場合も考えられますので、最寄りの警察署や管轄の保健所へ必ず連絡をしてください。
特徴や居なくなったおおよその時間や日にちを詳しく連絡しておくことで、後日迷子猫の届けがあった場合に連絡をしてくれます。
他に、保護されて保健所に収容されたり、警察に届けがある場合も考えられますので、最寄りの警察署や管轄の保健所へ必ず連絡をしてください。
特徴や居なくなったおおよその時間や日にちを詳しく連絡しておくことで、後日迷子猫の届けがあった場合に連絡をしてくれます。
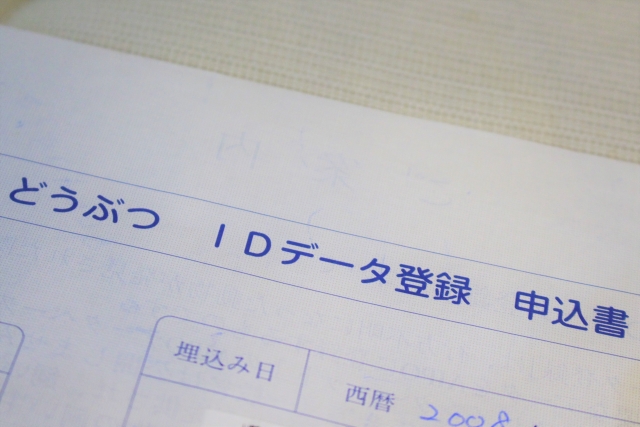 注意していても、隙を狙って外に出てしまう可能性があります。
しかし、飼い主として脱走の危険を限りなくゼロに近づける対策を行うことが大切です。
注意していても、隙を狙って外に出てしまう可能性があります。
しかし、飼い主として脱走の危険を限りなくゼロに近づける対策を行うことが大切です。
 網戸のちょっとした隙間でも手を入れて開けてしまう猫も多く、「閉めているから大丈夫」とは言い切れません。
また、器用な猫ならドアノブに手を掛けて開けてしまう場合も考えられます。
戸建てのお家で一番多いのが、お風呂場の小窓の閉め忘れではないでしょうか。
換気のために開けていた窓から、出てしまうこともあります。
猫は思う以上に器用にどこからでも出入りしますので、万が一を考えて戸締りと鍵を掛けることを忘れないようにしたいですね。
網戸のちょっとした隙間でも手を入れて開けてしまう猫も多く、「閉めているから大丈夫」とは言い切れません。
また、器用な猫ならドアノブに手を掛けて開けてしまう場合も考えられます。
戸建てのお家で一番多いのが、お風呂場の小窓の閉め忘れではないでしょうか。
換気のために開けていた窓から、出てしまうこともあります。
猫は思う以上に器用にどこからでも出入りしますので、万が一を考えて戸締りと鍵を掛けることを忘れないようにしたいですね。
 猫を飼っている部屋に観葉植物はありますか?
肉食動物の猫ですが、植物で遊んでいてうっかり口に入れてしまうこともあります。
植物には毒性があって、下痢や嘔吐などの症状が出る危険なものもあるので、正しい知識を持っておくことが大切です。
この記事では観葉植物を置く時の注意点と安全な植物・危険な植物について解説します。
猫を飼っている部屋に観葉植物はありますか?
肉食動物の猫ですが、植物で遊んでいてうっかり口に入れてしまうこともあります。
植物には毒性があって、下痢や嘔吐などの症状が出る危険なものもあるので、正しい知識を持っておくことが大切です。
この記事では観葉植物を置く時の注意点と安全な植物・危険な植物について解説します。
 留守番中や目を離したすきに観葉植物を倒してしまったり、いたずらしたりすることも心配です。
また猫は丸い容器の中にいると落ち着くという習性があり、植木鉢が気になることがあります。
ですから、観葉植物を天井から吊るすなど、猫の手が届かない位置に置くことが大切です。
棚や窓辺などの足場が存在すると、飛び乗る危険性がありますので周囲をよく見渡して、その場所で大丈夫かどうかも確認しましょう。
高い場所に置いても猫は身軽で簡単に登れてしまうので、いたずらが可能かもしれません。
一緒に過ごせる時間帯にその場所に置いてみて、どんな行動をするか観察してみるなどの工夫をしてみてください。
留守番中や目を離したすきに観葉植物を倒してしまったり、いたずらしたりすることも心配です。
また猫は丸い容器の中にいると落ち着くという習性があり、植木鉢が気になることがあります。
ですから、観葉植物を天井から吊るすなど、猫の手が届かない位置に置くことが大切です。
棚や窓辺などの足場が存在すると、飛び乗る危険性がありますので周囲をよく見渡して、その場所で大丈夫かどうかも確認しましょう。
高い場所に置いても猫は身軽で簡単に登れてしまうので、いたずらが可能かもしれません。
一緒に過ごせる時間帯にその場所に置いてみて、どんな行動をするか観察してみるなどの工夫をしてみてください。
 猫にとって安全で無害なおすすめの観葉植物を紹介します。
部屋のどこに置くと良いのかを考えたら、その場所に似合う観葉植物で猫にも安全な物を選んでください。
猫も観葉植物も癒やしてくれる存在になってくれることでしょう。
猫にとって安全で無害なおすすめの観葉植物を紹介します。
部屋のどこに置くと良いのかを考えたら、その場所に似合う観葉植物で猫にも安全な物を選んでください。
猫も観葉植物も癒やしてくれる存在になってくれることでしょう。
 ガジュマルは沖縄などの暖かい地方で有名な植物で、「精霊の宿る木」と呼ばれています。
猫が食べても無害であるため、安心して屋内に置くことが可能です。
小さい木もあるのでテーブルに置く際は猫が落としたり、倒したりしないように対策しましょう。
ガジュマルは数年経てば、ベランダなどでも栽培できます。
夏の直射日光は当てないようにしないと葉やけするので、置き場所にも気をつけましょう。
ガジュマルは沖縄などの暖かい地方で有名な植物で、「精霊の宿る木」と呼ばれています。
猫が食べても無害であるため、安心して屋内に置くことが可能です。
小さい木もあるのでテーブルに置く際は猫が落としたり、倒したりしないように対策しましょう。
ガジュマルは数年経てば、ベランダなどでも栽培できます。
夏の直射日光は当てないようにしないと葉やけするので、置き場所にも気をつけましょう。
 シュロチクはヤシ科に分類される中国原産の観葉植物です。
日本では江戸時代から親しまれていて、アジアンテイストや和モダンな雰囲気にも合うスマートな印象です。
日差しが苦手で、半日陰でも育ちます。
耐寒性がすぐれているため、年間を通して、屋内でも屋外でも育てることができる初心者にもおすすめの植物です。
葉が細くて、猫がかじりやすいので、置き場所や置き方に工夫が必要です。
シュロチクはヤシ科に分類される中国原産の観葉植物です。
日本では江戸時代から親しまれていて、アジアンテイストや和モダンな雰囲気にも合うスマートな印象です。
日差しが苦手で、半日陰でも育ちます。
耐寒性がすぐれているため、年間を通して、屋内でも屋外でも育てることができる初心者にもおすすめの植物です。
葉が細くて、猫がかじりやすいので、置き場所や置き方に工夫が必要です。
 次に猫にとって危険な観葉植物を解説します。
猫に毒性がある植物は700種類以上もあるので全てを覚えられませんが、名前が知られていて人気のある植物の中から危険なものをお伝えします。
選ぶ際にはこれらは避けておき、すでに家にある場合はその対策をしてください。
次に猫にとって危険な観葉植物を解説します。
猫に毒性がある植物は700種類以上もあるので全てを覚えられませんが、名前が知られていて人気のある植物の中から危険なものをお伝えします。
選ぶ際にはこれらは避けておき、すでに家にある場合はその対策をしてください。
 ドラセナは葉の形や色が綺麗で人気がある観葉植物です。
「幸福の木」とも呼ばれ、贈り物でいただくこともあるでしょう。
しかし、全草に猛毒性があり、下痢や嘔吐、手足の腫れや麻痺などの症状を引き起こすことがあります。
こちらも猫のいる部屋には置かず、別の場所で管理するようにしましょう。
ドラセナは葉の形や色が綺麗で人気がある観葉植物です。
「幸福の木」とも呼ばれ、贈り物でいただくこともあるでしょう。
しかし、全草に猛毒性があり、下痢や嘔吐、手足の腫れや麻痺などの症状を引き起こすことがあります。
こちらも猫のいる部屋には置かず、別の場所で管理するようにしましょう。
 ポトスは育てやすく人気がある植物です。
しかし、実は葉と茎に毒性があり、猫がかじってしまうと皮膚炎や口内の炎症などを引き起こすことがあります。
ポトスは部屋の天井など高いところから配置することがよく見られますが、それは猫にとっては絶好の遊び場です。
飛び乗って遊んでいるうちに葉をかじって、食欲がなくなって衰弱する危険性があります。
ポトスをすでに飾っている人は猫が入らない部屋で管理しましょう。
ポトスは育てやすく人気がある植物です。
しかし、実は葉と茎に毒性があり、猫がかじってしまうと皮膚炎や口内の炎症などを引き起こすことがあります。
ポトスは部屋の天井など高いところから配置することがよく見られますが、それは猫にとっては絶好の遊び場です。
飛び乗って遊んでいるうちに葉をかじって、食欲がなくなって衰弱する危険性があります。
ポトスをすでに飾っている人は猫が入らない部屋で管理しましょう。
 猫に安全で無害な観葉植物でも遊んでしまって、葉がボロボロになることがあります。
またひっくり返してしまうと部屋の中がたいへんなことになります。
特に若い猫は活発なため、遊びの対象になってしまうことが多いようです。
いたずらを避けるための方法をいくつか解説しますので、参考にしてください。
猫に安全で無害な観葉植物でも遊んでしまって、葉がボロボロになることがあります。
またひっくり返してしまうと部屋の中がたいへんなことになります。
特に若い猫は活発なため、遊びの対象になってしまうことが多いようです。
いたずらを避けるための方法をいくつか解説しますので、参考にしてください。
 木酢液はいたずら対策をしても、猫がどうしても植物で遊んでしまう時、土を掘り返してしまう場合などに使用しましょう。
木酢液は炭を焼くときに発生する煙を冷やし液体にしたもので、植物の病気や害虫予防のために使う害のない液体です。
ホームセンターで売っていますが、原液のままでは使えないので適切に薄めて使用するようにしましょう。
猫は柑橘系や酢の匂いが嫌なので、その習性を利用して木酢液を植物にかけることでいたずら対策になります。
木酢液はいたずら対策をしても、猫がどうしても植物で遊んでしまう時、土を掘り返してしまう場合などに使用しましょう。
木酢液は炭を焼くときに発生する煙を冷やし液体にしたもので、植物の病気や害虫予防のために使う害のない液体です。
ホームセンターで売っていますが、原液のままでは使えないので適切に薄めて使用するようにしましょう。
猫は柑橘系や酢の匂いが嫌なので、その習性を利用して木酢液を植物にかけることでいたずら対策になります。
 猫にとうもろこしを与えても問題はありません。
特に中毒性がある野菜ではないからです。
しかし、とうもろこしは消化が悪いので胃腸炎を起こすこともあります。
肥満の原因になりやすく、腎臓や泌尿器系の疾患にかかりやすくなるとも言われていますので、与える量には注意をはらいましょう。
そして、粒以外の部分については危険性もありますので、次の詳しい解説をお読みください。
猫にとうもろこしを与えても問題はありません。
特に中毒性がある野菜ではないからです。
しかし、とうもろこしは消化が悪いので胃腸炎を起こすこともあります。
肥満の原因になりやすく、腎臓や泌尿器系の疾患にかかりやすくなるとも言われていますので、与える量には注意をはらいましょう。
そして、粒以外の部分については危険性もありますので、次の詳しい解説をお読みください。
 次に意外にも重宝なのがとうもろこしの「ひげ」です。
ふさふさのひげがついているとうもろこしを買ったら、病気の予防や治療にも活用できるのです。
この部分は、炎症を抑制することに効果が高く、漢方薬として使用されています。
捨てられがちな「ひげ」ですが、猫が食べられるように乾燥させ、細かくしてフードに混ぜると、糖尿病や脂肪肝などに効きます。
そのような病気ではない場合も、太りやすい、雨の日には元気がなくなる、皮膚炎や目やになどが多い等の症状があれば、ひげはおすすめです。
使い方はひげをよく洗って2,3日乾燥させ、ハサミで小さくカットして、小さじ1ほど食事に混ぜて与えます。
次に意外にも重宝なのがとうもろこしの「ひげ」です。
ふさふさのひげがついているとうもろこしを買ったら、病気の予防や治療にも活用できるのです。
この部分は、炎症を抑制することに効果が高く、漢方薬として使用されています。
捨てられがちな「ひげ」ですが、猫が食べられるように乾燥させ、細かくしてフードに混ぜると、糖尿病や脂肪肝などに効きます。
そのような病気ではない場合も、太りやすい、雨の日には元気がなくなる、皮膚炎や目やになどが多い等の症状があれば、ひげはおすすめです。
使い方はひげをよく洗って2,3日乾燥させ、ハサミで小さくカットして、小さじ1ほど食事に混ぜて与えます。
 猫に安全にとうもろこしを食べさせるための注意点をここで確認しておきましょう。
何と言ってもペットの健康管理は飼い主さんの義務ですので、しっかりした知識を持って安心して食べられ、体に良いものをあげてください。
猫に安全にとうもろこしを食べさせるための注意点をここで確認しておきましょう。
何と言ってもペットの健康管理は飼い主さんの義務ですので、しっかりした知識を持って安心して食べられ、体に良いものをあげてください。
 とうもろこしにはアレルギー成分が含まれますので、アレルギーには注意してください。
穀物アレルギー持つ猫ちゃんにとうもろこしを与えてはいけません。
猫にとって穀物アレルギーは意外と多く、とうもろこしや米、小麦にも反応することがあります。
アレルギーがあるのかどうか分からない場合は、少量を食べさせ、様子を見る方法があります。
かゆみや下痢・嘔吐など軽くても症状が出れば、獣医で診察を受けてください。
とうもろこしにはアレルギー成分が含まれますので、アレルギーには注意してください。
穀物アレルギー持つ猫ちゃんにとうもろこしを与えてはいけません。
猫にとって穀物アレルギーは意外と多く、とうもろこしや米、小麦にも反応することがあります。
アレルギーがあるのかどうか分からない場合は、少量を食べさせ、様子を見る方法があります。
かゆみや下痢・嘔吐など軽くても症状が出れば、獣医で診察を受けてください。
 とうもろこしはキャットフードに含まれていることもあります。
とうもろこしの主な栄養素は、炭水化物・ビタミンB群・ビタミンC、E・カリウムなどです。
これらの栄養素はどのような役割を持つのか、解説していきます。
とうもろこしはキャットフードに含まれていることもあります。
とうもろこしの主な栄養素は、炭水化物・ビタミンB群・ビタミンC、E・カリウムなどです。
これらの栄養素はどのような役割を持つのか、解説していきます。
 炭水化物は糖質と食物繊維から成っていて、猫は炭水化物の消化は苦手とされています。
しかし、糖質はエネルギー源として重要で、食物繊維は消化器官の働きを助ける効果があります。
とうもろこしにはセルロースという食物繊維があり、便の排泄を促す効果があるので、ダイエットにも向いています。
ですから低カロリーのフードを作るために、とうもろこしが利用されているようです。
アレルギーがなく、肥満気味の猫であれば、体重管理に役立つとうもろこし入りのフードも活用できます。
炭水化物は糖質と食物繊維から成っていて、猫は炭水化物の消化は苦手とされています。
しかし、糖質はエネルギー源として重要で、食物繊維は消化器官の働きを助ける効果があります。
とうもろこしにはセルロースという食物繊維があり、便の排泄を促す効果があるので、ダイエットにも向いています。
ですから低カロリーのフードを作るために、とうもろこしが利用されているようです。
アレルギーがなく、肥満気味の猫であれば、体重管理に役立つとうもろこし入りのフードも活用できます。
 猫は色々な物を食べることができ、人が食べる物も多く食べる習性があります。
しかし、食べてはいけない物もあるので、猫を飼っているのであれば把握しておくことが求められます。
人であれば問題なく食べることができるさつまいもですが、猫にも与えても問題ない食材です。
ただし、与える際の注意点や適した与え方を守らなければ体調を崩してしまう原因となってしまいます。
ここでは、猫にさつまいもを与える際のことについて紹介しているので参考にしてください。
猫は色々な物を食べることができ、人が食べる物も多く食べる習性があります。
しかし、食べてはいけない物もあるので、猫を飼っているのであれば把握しておくことが求められます。
人であれば問題なく食べることができるさつまいもですが、猫にも与えても問題ない食材です。
ただし、与える際の注意点や適した与え方を守らなければ体調を崩してしまう原因となってしまいます。
ここでは、猫にさつまいもを与える際のことについて紹介しているので参考にしてください。
 猫にさつまいもを与えることでさまざまな効果を得ることができます。
そのため、さつまいもを与えることで猫の体調が改善されることも期待できます。
ただし、いくら猫に良い効果が期待できるからといって大量に与えてしまうことは逆効果になってしまうこともあるので注意が必要です。
次に、猫にさつまいもを与えた際に得られる効果を紹介していきます。
求めている効果があるのであれば適量のさつまいもをフードに混ぜたり、おやつ代わりに与えてみてはいかがでしょうか。
猫にさつまいもを与えることでさまざまな効果を得ることができます。
そのため、さつまいもを与えることで猫の体調が改善されることも期待できます。
ただし、いくら猫に良い効果が期待できるからといって大量に与えてしまうことは逆効果になってしまうこともあるので注意が必要です。
次に、猫にさつまいもを与えた際に得られる効果を紹介していきます。
求めている効果があるのであれば適量のさつまいもをフードに混ぜたり、おやつ代わりに与えてみてはいかがでしょうか。
 さつまいもにはヤラピンという成分と食物繊維が含まれている特徴があります。
食物繊維は便秘に良いとことを知っている人も多いのではないでしょうか。
そのため、猫にさつまいもを与えれば便秘解消の効果が期待できます。
食物繊維はわかってもヤラピンがどんな成分なのかわからない場合が多いと思いますが、さつまいもにしか含まれていない成分です。
ヤラピンには腸の働きを整える効果や緩下剤としての効果もあるため、さらに便秘解消の効果があります。
猫は自身の被毛を飲み込み定期的に吐き出したり、便として排出する習性がありますが、腸の活動が悪かったり、飲み込む被毛の量が多いと毛球症になるリスクがあります。
特に、換毛期や長毛種であれば毛球症になるリスクが高いです。
しかし、便秘解消の効果があるさつまいもを与えれば効率よく毛玉を排便と一緒に出すことができるので、毛球症予防の効果も期待できます。
さつまいもにはヤラピンという成分と食物繊維が含まれている特徴があります。
食物繊維は便秘に良いとことを知っている人も多いのではないでしょうか。
そのため、猫にさつまいもを与えれば便秘解消の効果が期待できます。
食物繊維はわかってもヤラピンがどんな成分なのかわからない場合が多いと思いますが、さつまいもにしか含まれていない成分です。
ヤラピンには腸の働きを整える効果や緩下剤としての効果もあるため、さらに便秘解消の効果があります。
猫は自身の被毛を飲み込み定期的に吐き出したり、便として排出する習性がありますが、腸の活動が悪かったり、飲み込む被毛の量が多いと毛球症になるリスクがあります。
特に、換毛期や長毛種であれば毛球症になるリスクが高いです。
しかし、便秘解消の効果があるさつまいもを与えれば効率よく毛玉を排便と一緒に出すことができるので、毛球症予防の効果も期待できます。
 猫にさつまいもを与えるのであれば正しい方法で与えなければなりません。
そのため、猫にさつまいもを与えようと考えているのであれば把握しておくことをおすすめします。
正しい方法で与えることができていないと猫が体調を崩してしまう原因となってしまいます。
猫にさつまいもを与えるのであれば正しい方法で与えなければなりません。
そのため、猫にさつまいもを与えようと考えているのであれば把握しておくことをおすすめします。
正しい方法で与えることができていないと猫が体調を崩してしまう原因となってしまいます。
 上記では加熱してさつまいもを与えることが必須であることを紹介しましたが、加熱したものをすぐに与えるのではなく、冷ましてから与えるようにしましょう。
人も加熱したさつまいもをすぐに食べようとすると火傷してしまいます。
猫も同じように熱いままでは火傷してしまう危険性があります。
猫は人よりも温度に敏感な動物であり、0.5 ℃変わるだけでも違いが感知することができます。
適した温度は小動物の体温と同じ35℃前後がおすすめです。
上記では加熱してさつまいもを与えることが必須であることを紹介しましたが、加熱したものをすぐに与えるのではなく、冷ましてから与えるようにしましょう。
人も加熱したさつまいもをすぐに食べようとすると火傷してしまいます。
猫も同じように熱いままでは火傷してしまう危険性があります。
猫は人よりも温度に敏感な動物であり、0.5 ℃変わるだけでも違いが感知することができます。
適した温度は小動物の体温と同じ35℃前後がおすすめです。
 猫ちゃん用ごまさつまクッキーはさつまいもで作ったクッキーであり、ゴマで風味づけがされています。
材料はさつまいも70g・ベーキングパウダー小さじ半分・薄力粉30g・ゴマ5g・豆乳小さじ1杯です。
作り方は薄力粉とベーキングパウダーをふるいにかけて混ぜます。さつまいもはレンジで加熱してすり潰していきます。
さつまいもが冷えてしまうと固くなってしまうのでできるだけ熱いうちにつぶすようにしましょう。
豆乳を少し入れてつぶすことでつぶしやすくなります。
次に、ゴマをすり潰しベーキングパウダーと薄力粉を混ぜた中に入れ、すり潰したさつまいもの中に投入します。
粉っぽさがなくなるまで混ぜ、豆乳も少しずつ入れることがポイントです。
あとは出来上がった生地をラップに包み、綿棒で均一になるまで伸ばしていきましょう。
最後は型でくりぬいて180℃のオーブンで2分焼けば完成です。
猫ちゃん用ごまさつまクッキーはさつまいもで作ったクッキーであり、ゴマで風味づけがされています。
材料はさつまいも70g・ベーキングパウダー小さじ半分・薄力粉30g・ゴマ5g・豆乳小さじ1杯です。
作り方は薄力粉とベーキングパウダーをふるいにかけて混ぜます。さつまいもはレンジで加熱してすり潰していきます。
さつまいもが冷えてしまうと固くなってしまうのでできるだけ熱いうちにつぶすようにしましょう。
豆乳を少し入れてつぶすことでつぶしやすくなります。
次に、ゴマをすり潰しベーキングパウダーと薄力粉を混ぜた中に入れ、すり潰したさつまいもの中に投入します。
粉っぽさがなくなるまで混ぜ、豆乳も少しずつ入れることがポイントです。
あとは出来上がった生地をラップに包み、綿棒で均一になるまで伸ばしていきましょう。
最後は型でくりぬいて180℃のオーブンで2分焼けば完成です。
 猫にさつまいもを与えても問題はありませんが、注意しなければならないポイントがいくつかあります。
そのため、知識なくさつまいもを与えることは危険なため、必ず注意点を把握してからさつまいもを猫に与えるようにしましょう。
猫にさつまいもを与えても問題はありませんが、注意しなければならないポイントがいくつかあります。
そのため、知識なくさつまいもを与えることは危険なため、必ず注意点を把握してからさつまいもを猫に与えるようにしましょう。
 さつまいもの皮は他の根菜と比べても皮が薄く食べやすかったり、栄養が豊富に含まれていることなどから皮がついたまま与えることも多いです。
しかし、皮は消化しにくい部分であるため、消化不良を起こしてしまう可能性があります。
そのため、普段から下痢をしてしまうような猫であればさつまいもを与えることを断念したり、皮を剥いた状態で与えるなどの一工夫を施すようにしましょう。
皮による消化不良は個体差があったり、その時の体調によって症状があらわれることもあります。
さつまいもの皮は他の根菜と比べても皮が薄く食べやすかったり、栄養が豊富に含まれていることなどから皮がついたまま与えることも多いです。
しかし、皮は消化しにくい部分であるため、消化不良を起こしてしまう可能性があります。
そのため、普段から下痢をしてしまうような猫であればさつまいもを与えることを断念したり、皮を剥いた状態で与えるなどの一工夫を施すようにしましょう。
皮による消化不良は個体差があったり、その時の体調によって症状があらわれることもあります。
 ささみは低カロリーで高タンパク質な食べ物として評価されていて、猫のおやつの中でも人気が高く、アレルギーの心配がない限り食べても安心です。
安価で購入でき手軽にあげれるのも魅力ですが、猫に与えた場合の栄養効果を調べて見ました。
ささみは低カロリーで高タンパク質な食べ物として評価されていて、猫のおやつの中でも人気が高く、アレルギーの心配がない限り食べても安心です。
安価で購入でき手軽にあげれるのも魅力ですが、猫に与えた場合の栄養効果を調べて見ました。
 タンパク質は三大栄養素で、臓器や筋肉、被毛や皮膚など体を作る要素として非常に大切なものになります。
肉食である猫の臓器の作りは、植物性タンパク質よりも動物性タンパク質の方が消化しやすくなっています。
猫が1日に必要とするタンパク質は体重1㎏に対して1〜5gで、犬に比べて必要摂取量が多くなります。
猫は毎日タンパク質を消費しますので、タンパク質不足にならないよう注意が必要です。
タンパク質は三大栄養素で、臓器や筋肉、被毛や皮膚など体を作る要素として非常に大切なものになります。
肉食である猫の臓器の作りは、植物性タンパク質よりも動物性タンパク質の方が消化しやすくなっています。
猫が1日に必要とするタンパク質は体重1㎏に対して1〜5gで、犬に比べて必要摂取量が多くなります。
猫は毎日タンパク質を消費しますので、タンパク質不足にならないよう注意が必要です。
 細胞がきちんと機能するために必要なミネラルとして働き、心臓や腎臓のサポートをする役割をしています。
猫にとってカリウムは、摂取量が多すぎても少なすぎても体に悪影響を与えてしまいます。
高カリウム血症と低カリウム血症はどちらも発症に気づきにくく、四股のしびれや筋肉の低下、吐き気などがあり悪化しやすいのが特徴です。
細胞がきちんと機能するために必要なミネラルとして働き、心臓や腎臓のサポートをする役割をしています。
猫にとってカリウムは、摂取量が多すぎても少なすぎても体に悪影響を与えてしまいます。
高カリウム血症と低カリウム血症はどちらも発症に気づきにくく、四股のしびれや筋肉の低下、吐き気などがあり悪化しやすいのが特徴です。
 カルシウムは骨の成長など体の発育に必要な栄養素で、不足したり多く摂ってしまうと尿路結石症や骨格異常になりやすくなります。
尿路結石症はカルシウムを多く摂ってしまった場合に、便として排出される「シエウ酸」がカルシウムと結合して体内に溜まり起ります。
発見が遅くなると命にかかわる場合もありますので、いつもよりもトイレに行く回数が増え尿の量が少なく臭いや鳴き声に異変を感じたら、早めに動物病院での診察を受けるようにします。
カルシウムは骨の成長など体の発育に必要な栄養素で、不足したり多く摂ってしまうと尿路結石症や骨格異常になりやすくなります。
尿路結石症はカルシウムを多く摂ってしまった場合に、便として排出される「シエウ酸」がカルシウムと結合して体内に溜まり起ります。
発見が遅くなると命にかかわる場合もありますので、いつもよりもトイレに行く回数が増え尿の量が少なく臭いや鳴き声に異変を感じたら、早めに動物病院での診察を受けるようにします。
 猫はタンパク質を主に摂取する肉食動物ですので、猫の食事にはタンパク質が必要になります。
ささみはタンパク質が豊富で消化が良く、他の栄養素も多く含まれています。
ささみを猫に与える際の注意点を調べて見ました。
猫はタンパク質を主に摂取する肉食動物ですので、猫の食事にはタンパク質が必要になります。
ささみはタンパク質が豊富で消化が良く、他の栄養素も多く含まれています。
ささみを猫に与える際の注意点を調べて見ました。
 生のささみには細菌がいる可能性があり、スーパーで売られているささみは猫に生で食べさせられる鮮度ではありません。
感染症にかかる恐れがありますので、猫にささみを与える時は生ではなくきちんと加熱してから与えるようにします。
肉食動物の猫は生の方が好きなのではと思ってしまいますが、後で具合が悪くなる原因にもなってしまいますので茹でてからあげるようにすれば安心です。
生のささみには細菌がいる可能性があり、スーパーで売られているささみは猫に生で食べさせられる鮮度ではありません。
感染症にかかる恐れがありますので、猫にささみを与える時は生ではなくきちんと加熱してから与えるようにします。
肉食動物の猫は生の方が好きなのではと思ってしまいますが、後で具合が悪くなる原因にもなってしまいますので茹でてからあげるようにすれば安心です。
 猫のアレルギー症状で上位を占めているのはタンパク質です。
タンパク質を多く含んでいるささみを初めて与える時は、アレルギー症状を発症させないよう猫の様子を細かく観察するようにします。
アレルギーを発症すると食べたものを吐いたり、下痢をし皮膚や口元などに炎症が起きます。
ささみはアレルギー症状がなければドライフードよりもしっとりとした食感をしていますので、体調不良や食欲が落ちている時に与えるのに向いています。
猫のアレルギー症状で上位を占めているのはタンパク質です。
タンパク質を多く含んでいるささみを初めて与える時は、アレルギー症状を発症させないよう猫の様子を細かく観察するようにします。
アレルギーを発症すると食べたものを吐いたり、下痢をし皮膚や口元などに炎症が起きます。
ささみはアレルギー症状がなければドライフードよりもしっとりとした食感をしていますので、体調不良や食欲が落ちている時に与えるのに向いています。
 【レシピ名:愛猫用 しっとり柔らか鶏肉ささみ♡】
材料:鶏肉(ささみ・もも肉・むね肉など) 3~6本
水 たくさん
作り方①:鍋の中にたっぷりの水と鶏肉を入れて中火にかけ、沸騰直前に弱火にします。
②:約15分茹でて中までしっかり火が通ったら出来上がり!
③:茹であがったらザルにあげて冷水で洗い、タッパーに割いて入れて保存します。
※冬場は3日以内、夏場は2日以内に使いきる様にします。
④:柔らかく茹でた人参、キャベツ、ごはんなどを猫ご飯に入れる場合は1割以下を目安にします。
⑤:夏バテで食欲がない時などは、猫缶に混ぜたり鶏肉のゆで汁を一緒に与えてるのもおすすめです。
【レシピ名:愛猫用 しっとり柔らか鶏肉ささみ♡】
材料:鶏肉(ささみ・もも肉・むね肉など) 3~6本
水 たくさん
作り方①:鍋の中にたっぷりの水と鶏肉を入れて中火にかけ、沸騰直前に弱火にします。
②:約15分茹でて中までしっかり火が通ったら出来上がり!
③:茹であがったらザルにあげて冷水で洗い、タッパーに割いて入れて保存します。
※冬場は3日以内、夏場は2日以内に使いきる様にします。
④:柔らかく茹でた人参、キャベツ、ごはんなどを猫ご飯に入れる場合は1割以下を目安にします。
⑤:夏バテで食欲がない時などは、猫缶に混ぜたり鶏肉のゆで汁を一緒に与えてるのもおすすめです。
 コロナ禍でストレスが溜まることが多い現在、アロマで心も体もリラックスしようと考えている方も多いでしょう。
自宅内で常にアロマを焚いている方も多いかと思うのですが、猫と一緒に暮らす上で注意しなければならないことがあります。
また猫にアロマは絶対にNGということも言われていますので、その理由についてご紹介します。
コロナ禍でストレスが溜まることが多い現在、アロマで心も体もリラックスしようと考えている方も多いでしょう。
自宅内で常にアロマを焚いている方も多いかと思うのですが、猫と一緒に暮らす上で注意しなければならないことがあります。
また猫にアロマは絶対にNGということも言われていますので、その理由についてご紹介します。
 猫は、動物上の分類が肉食動物です。
見た目は愛らしいですが、野生の猫たちは新鮮な肉を獲物に選びます。
腐った肉は体に悪影響を及ぼすので、猫は悪い肉かどうかを選別しなければいけません。
自然で生き抜くため「腐った肉はNG、新鮮な肉を食べよう」という術が見に付いたことで発達したのが嗅覚なのです。
人間が良い香りと感じたからといって、それが猫にも同じように感じ取れるかは疑問に思います。
そのため、猫は人間よりはるかに香りに敏感な動物と言えます。
ということはアロマの香りは猫にとって「謎めいた香り」となり、嗅いでいるだけでストレスになってしまうことも
猫は、動物上の分類が肉食動物です。
見た目は愛らしいですが、野生の猫たちは新鮮な肉を獲物に選びます。
腐った肉は体に悪影響を及ぼすので、猫は悪い肉かどうかを選別しなければいけません。
自然で生き抜くため「腐った肉はNG、新鮮な肉を食べよう」という術が見に付いたことで発達したのが嗅覚なのです。
人間が良い香りと感じたからといって、それが猫にも同じように感じ取れるかは疑問に思います。
そのため、猫は人間よりはるかに香りに敏感な動物と言えます。
ということはアロマの香りは猫にとって「謎めいた香り」となり、嗅いでいるだけでストレスになってしまうことも
 アロマは化合物を含んでおり人工的にブレンドされています。
ということは、猫の体内に入るとよくない成分も含まれているということになりますね。
飼い主さんと愛猫が一緒の空間にいるとき優れた嗅覚、体を舐める習性などがある体質の猫の方が体内に入り込みやすくなってしまいます。
一般的には健康や美容効果があるアロマでも人間と猫では違うという意識を持たなければ愛猫を守れないかもしれませんね。
アロマは化合物を含んでおり人工的にブレンドされています。
ということは、猫の体内に入るとよくない成分も含まれているということになりますね。
飼い主さんと愛猫が一緒の空間にいるとき優れた嗅覚、体を舐める習性などがある体質の猫の方が体内に入り込みやすくなってしまいます。
一般的には健康や美容効果があるアロマでも人間と猫では違うという意識を持たなければ愛猫を守れないかもしれませんね。
 人間も動物も皮膚には刺激をシャットアウトし体を守る機能が備わっています。
基本的に、外部とふれ合い異物をバリアする表皮と表皮の下にあって肌を構成する真皮、もっとも内側にあってクッション材になっている皮下組織と皮膚公造は三層からなっています。
猫の表皮は人間に比べるとかなり薄く、人間も半分もないと言われているほど。
被毛に覆われているのでそんな風に思えないかもしれませんが、猫の皮膚はかなりデリケートな構造になっているので、アロマの香りが少量でも空気中にある微々たる成分が猫の体に付着して皮膚から体内に浸透していくでしょう。
人間も動物も皮膚には刺激をシャットアウトし体を守る機能が備わっています。
基本的に、外部とふれ合い異物をバリアする表皮と表皮の下にあって肌を構成する真皮、もっとも内側にあってクッション材になっている皮下組織と皮膚公造は三層からなっています。
猫の表皮は人間に比べるとかなり薄く、人間も半分もないと言われているほど。
被毛に覆われているのでそんな風に思えないかもしれませんが、猫の皮膚はかなりデリケートな構造になっているので、アロマの香りが少量でも空気中にある微々たる成分が猫の体に付着して皮膚から体内に浸透していくでしょう。
 アロマにはさまざまな香りがあり、猫にとっては特にオレンジ系のアロマは要注意です。
オレンジ系のアロマには「リモネン」という成分が入っており、猫にとってかなり有害作用を引き起こすことが発見されています。
また、「ピネン」という成分にも過剰に反応し、この2種類はシトラス類の精油とパインの精油に最も含まれていると言われているため、猫にはアロマ全般使わないことをおすすめしますが、特にオレンジ系のものには注意しましょう。
アロマにはさまざまな香りがあり、猫にとっては特にオレンジ系のアロマは要注意です。
オレンジ系のアロマには「リモネン」という成分が入っており、猫にとってかなり有害作用を引き起こすことが発見されています。
また、「ピネン」という成分にも過剰に反応し、この2種類はシトラス類の精油とパインの精油に最も含まれていると言われているため、猫にはアロマ全般使わないことをおすすめしますが、特にオレンジ系のものには注意しましょう。
 猫が誤ってアロマオイルを嗅いでしまった時にはさまざまな症状が出ることがわかっています。
ここでは、どのような症状が出るのか部位別にご紹介していきます。
猫が誤ってアロマオイルを嗅いでしまった時にはさまざまな症状が出ることがわかっています。
ここでは、どのような症状が出るのか部位別にご紹介していきます。
 アロマによる中毒症状は他にもたくさんあり以下のような症状が報告されています。
・下痢、嘔吐
・失禁
・元気がなくなる、食欲不振
・低体温
・筋肉の震え
・抑うつ状態
・口腔粘膜の炎症、よだれ
・肝臓の数値があがる
・死亡
他の薬物などで発祥する中毒症状と似ており、最悪の場合死亡する恐れもあります。
同居家族が複数いる場合は、猫にアロマは絶対ダメということを周知しておきましょう。
また、これらの症状はアロマ成分を取り込んでからすぐに発症するわけではなく、2~8時間ほどで起こることもあるのですが、数年間かけて体内に蓄積し、肝不全を起こすこともあると言われています。
アロマによる中毒症状は他にもたくさんあり以下のような症状が報告されています。
・下痢、嘔吐
・失禁
・元気がなくなる、食欲不振
・低体温
・筋肉の震え
・抑うつ状態
・口腔粘膜の炎症、よだれ
・肝臓の数値があがる
・死亡
他の薬物などで発祥する中毒症状と似ており、最悪の場合死亡する恐れもあります。
同居家族が複数いる場合は、猫にアロマは絶対ダメということを周知しておきましょう。
また、これらの症状はアロマ成分を取り込んでからすぐに発症するわけではなく、2~8時間ほどで起こることもあるのですが、数年間かけて体内に蓄積し、肝不全を起こすこともあると言われています。
 猫にはアロマは禁物とわかっていても、癒しを求めている方はどうしても使いたい場面もあるでしょう。
そんな時はアロマのお風呂がおすすめです。
しかし、お風呂場にアロマの成分が残ることになるので、日頃から猫が出入りしないことが原則です。
猫にはアロマは禁物とわかっていても、癒しを求めている方はどうしても使いたい場面もあるでしょう。
そんな時はアロマのお風呂がおすすめです。
しかし、お風呂場にアロマの成分が残ることになるので、日頃から猫が出入りしないことが原則です。
 忙しいしバスタブには浸からないという方もいるでしょう。
そんな方は部分欲が安全でおすすめです。
作り方は洗面器やバケツにお湯をはり、精油を1~2滴たらすだけ。
手の手首部分まで浸すと上半身を、足であればくるぶしまで浸すと全身が驚くほどあたたまります。
体調がすぐれないときに全身浴をすると体力が奪われてしまいますが、部分欲であれば手軽なのもメリットですよね。
負担を減らしながらも血行をよくしてくれるでしょう。
注意点としては、愛猫に触れる前にしっかり洗い流すようにしてください。
忙しいしバスタブには浸からないという方もいるでしょう。
そんな方は部分欲が安全でおすすめです。
作り方は洗面器やバケツにお湯をはり、精油を1~2滴たらすだけ。
手の手首部分まで浸すと上半身を、足であればくるぶしまで浸すと全身が驚くほどあたたまります。
体調がすぐれないときに全身浴をすると体力が奪われてしまいますが、部分欲であれば手軽なのもメリットですよね。
負担を減らしながらも血行をよくしてくれるでしょう。
注意点としては、愛猫に触れる前にしっかり洗い流すようにしてください。
 暑い日のおやつはやっぱりアイスですが、猫にもアイスを上げてもいいのかな?と思う飼い主さんがいることでしょう。
猫にアイスを食べさせること自体は、悪いことではないのですが、そもそもアイスには猫の体に必要な栄養素は、あまり含まれていないのです。
また、アイスの味や含まれている成分などにより中毒を起こす可能性もあるので、よく確認しなければいけません。
ここではアイスを与えることで起こる危険性などについて詳しく解説していきます。
暑い日のおやつはやっぱりアイスですが、猫にもアイスを上げてもいいのかな?と思う飼い主さんがいることでしょう。
猫にアイスを食べさせること自体は、悪いことではないのですが、そもそもアイスには猫の体に必要な栄養素は、あまり含まれていないのです。
また、アイスの味や含まれている成分などにより中毒を起こす可能性もあるので、よく確認しなければいけません。
ここではアイスを与えることで起こる危険性などについて詳しく解説していきます。
 猫にとって人間のアイスは危険な場合が多いものです。
その理由を詳しく紹介しますが、基本的に「冷たいもの」はあまりよくないのです。
また中毒症状を起こすリスクや人間が美味しいと感じる味付けは猫の健康を害します。
猫には不要の成分が多いので、正しい知識を持っておきましょう。
猫にとって人間のアイスは危険な場合が多いものです。
その理由を詳しく紹介しますが、基本的に「冷たいもの」はあまりよくないのです。
また中毒症状を起こすリスクや人間が美味しいと感じる味付けは猫の健康を害します。
猫には不要の成分が多いので、正しい知識を持っておきましょう。
 人間が冷たいアイスを食べたときに頭が痛くなることがありますが、猫にも同じことが起こります。
猫はアイスを食べた時や後に、動きを止めて目を細めたり、イライラしたような唸り声を出したり、口を開けながら白目をむいたりなど、様々な行動を取ります。
これをブレインフリーズと言います。
「冷たい!」という感覚が「痛み」と勘違いされて感じていると言われています。
脳みそが固まるという意味で、冷たいものを食べたとき、一時的に血流を増やして体温をあげようとして頭につながる血管が膨張し、頭痛を起こしているのです。
痛いのは可哀想ですよね。
特にアイスの栄養が必要ではないので、無理して与えることではありません。
人間が冷たいアイスを食べたときに頭が痛くなることがありますが、猫にも同じことが起こります。
猫はアイスを食べた時や後に、動きを止めて目を細めたり、イライラしたような唸り声を出したり、口を開けながら白目をむいたりなど、様々な行動を取ります。
これをブレインフリーズと言います。
「冷たい!」という感覚が「痛み」と勘違いされて感じていると言われています。
脳みそが固まるという意味で、冷たいものを食べたとき、一時的に血流を増やして体温をあげようとして頭につながる血管が膨張し、頭痛を起こしているのです。
痛いのは可哀想ですよね。
特にアイスの栄養が必要ではないので、無理して与えることではありません。
 最後は肥満の問題です。
アイスの糖分のせいで、猫が肥満に陥ることもあります。
猫にとって必要なカロリーやエネルギーは、総合栄養食のフードで充分に足りるので、おやつを与える必要は特にありません。
アイスはカロリーが高く、添加物も豊富に含まれているので、人間にとっても食べ過ぎは絶対に良くない食べ物です。
猫は人間と比べてとても小さな動物で、人間と同じように消化することも難しいので、猫の体に良いものではありません。
最後は肥満の問題です。
アイスの糖分のせいで、猫が肥満に陥ることもあります。
猫にとって必要なカロリーやエネルギーは、総合栄養食のフードで充分に足りるので、おやつを与える必要は特にありません。
アイスはカロリーが高く、添加物も豊富に含まれているので、人間にとっても食べ過ぎは絶対に良くない食べ物です。
猫は人間と比べてとても小さな動物で、人間と同じように消化することも難しいので、猫の体に良いものではありません。
 猫には人用アイスはを与えてはいけないことがわかったと思います。
猫の体重や年齢、アレルギーの有無等によっても対応が異なりますので、すぐに命に関わるとは限りませんが、対応の仕方を知っておくことは必要です。
次の注意点や対応を理解しておきましょう。
猫には人用アイスはを与えてはいけないことがわかったと思います。
猫の体重や年齢、アレルギーの有無等によっても対応が異なりますので、すぐに命に関わるとは限りませんが、対応の仕方を知っておくことは必要です。
次の注意点や対応を理解しておきましょう。
 人間のアイスを与えないと同時に、食べた後のカップや袋をすぐに片付けることも大切です。
食べ終わったアイスのフタや容器をそのまま置いておくと、猫がその容器を舐める恐れがあるためです。
体に悪いからと与えなかったのに、猫が舐めてしまったら悲しいですね。
食べている途中でうっかり置いてしまうことも避け、アイスの管理は注意深くしっかりとしてください。
人間のアイスを与えないと同時に、食べた後のカップや袋をすぐに片付けることも大切です。
食べ終わったアイスのフタや容器をそのまま置いておくと、猫がその容器を舐める恐れがあるためです。
体に悪いからと与えなかったのに、猫が舐めてしまったら悲しいですね。
食べている途中でうっかり置いてしまうことも避け、アイスの管理は注意深くしっかりとしてください。
 飼い主さんが美味しそうに食べているアイスを欲しがる猫も多いようです。
また暑さが尋常ではない昨今、熱中症対策としてアイスを与えたいと考える飼い主さんにアイスの代わりとなるものを紹介します。
家で使えそうなものをうまく活用してみてください。
飼い主さんが美味しそうに食べているアイスを欲しがる猫も多いようです。
また暑さが尋常ではない昨今、熱中症対策としてアイスを与えたいと考える飼い主さんにアイスの代わりとなるものを紹介します。
家で使えそうなものをうまく活用してみてください。
 種類によって、果物は猫の栄養バランスを手助けしてくれる味方です。
また、水分も豊富なので、水分補給の一環にもなることができます。
夏にはスイカを飼い主さんと一緒に少し味わうと楽しいです。
あまり冷たくしすぎないほうが猫には良いでしょう。
桃やすりおろしたりんごなども食欲が落ちているときには目先が変わって食べやすいおやつになります。
ほんの少し与えるようにしてください。
種類によって、果物は猫の栄養バランスを手助けしてくれる味方です。
また、水分も豊富なので、水分補給の一環にもなることができます。
夏にはスイカを飼い主さんと一緒に少し味わうと楽しいです。
あまり冷たくしすぎないほうが猫には良いでしょう。
桃やすりおろしたりんごなども食欲が落ちているときには目先が変わって食べやすいおやつになります。
ほんの少し与えるようにしてください。