猫の膵炎の症状は?
 猫の膵炎ははっきりとした症状が出ないため、飼い主が気づきにくい病気です。
しかし放っておくと危険な状態にもなりかねないので、早期発見と治療が必要です。
ここでは急性膵炎と慢性膵炎の症状や合併症について解説します。
猫の膵炎ははっきりとした症状が出ないため、飼い主が気づきにくい病気です。
しかし放っておくと危険な状態にもなりかねないので、早期発見と治療が必要です。
ここでは急性膵炎と慢性膵炎の症状や合併症について解説します。
急性膵炎の症状
膵臓は消化酵素を作って十二指腸での食べ物の分解を助けます。
この消化酵素が十二指腸に届く前に活性化して、膵臓を溶かしてしまい炎症を起こすのが膵炎で、突然炎症を起こすのが急性膵炎です。
一般的な場合、1日に何度も下痢や嘔吐を繰り返し、食欲が突然無くなります。
さらに、上腹部の痛みが続き、腹部をかばう体勢をとったり、全体の動きが鈍くなる症状が急に現れます。
ただ、食欲不振や元気がないだけでわかりにくい場合もあり、様子を見ているうちに急に悪化することもあります。
慢性膵炎の症状
 慢性膵炎は長期間膵臓の炎症が続いて、機能が衰えていきます。
症状があったとしてもわずかなもので、下痢や嘔吐がある場合でも数日に1度など、頻度が比較的低く、軽度なことが多いです。
そのため診断する場合も非常に難しい面があり、初期では発見しにくいことが多いです。
猫では比較的多く、中高齢の猫に起こりやすい病気と言われています。
進行すると食欲がなくなって体重が減少し、毛艶が悪くなります。
早く治療を始めると改善しやすいので、少しでも変だなと感じたら病院で受診することが必要です。
慢性膵炎は長期間膵臓の炎症が続いて、機能が衰えていきます。
症状があったとしてもわずかなもので、下痢や嘔吐がある場合でも数日に1度など、頻度が比較的低く、軽度なことが多いです。
そのため診断する場合も非常に難しい面があり、初期では発見しにくいことが多いです。
猫では比較的多く、中高齢の猫に起こりやすい病気と言われています。
進行すると食欲がなくなって体重が減少し、毛艶が悪くなります。
早く治療を始めると改善しやすいので、少しでも変だなと感じたら病院で受診することが必要です。
合併症の症状
猫が膵炎を発症した場合、「三臓器炎」という症状が出現することもあり得ます。
三臓器炎とは膵炎、腸炎、肝臓と胆のう・胆管の炎症という3つがあわせて起こることです。
膵炎のおよそ半数が三臓器炎を併発していたという情報もあるほどです。
膵臓は肝臓や胆のう、十二指腸、胃腸の臓器と隣り合わせなので、これらの臓器も炎症を起こしやすくなります。
また、慢性膵炎では血糖値の調節ホルモンが分泌されにくくなるため糖尿病を併発するリスクもあります。
猫の膵炎の治療法
 膵炎の原因ははっきりとわかっておらず、治せる特効薬も今はまだありません。
炎症を起こした膵臓の血液循環の改善や消化器症状の治療などになります。
次に現在行われる膵炎の治療法について解説します。
膵炎の原因ははっきりとわかっておらず、治せる特効薬も今はまだありません。
炎症を起こした膵臓の血液循環の改善や消化器症状の治療などになります。
次に現在行われる膵炎の治療法について解説します。
栄養剤を投与する
この疾患になると、食べることを拒否する(食欲不振な)猫が多いです。
猫が食べなくなると、「肝リピドーシス」という肝臓機能が衰える状態になることがあります。
そのため、直接口から食事を取らない場合は鼻の穴から細いカテーテルを挿入し、食道まで通して栄養剤を補給させる必要があります。
膵炎の治療には栄養補給が大事です。
また膵外分泌不全を起こして、消化が十分に行われていない場合は消化酵素を補給することも行います。
投薬を行う
 急性膵炎になってしまった場合は、早期の発見・治療が非常に大切であり、入院して輸液(電解質や水分などの投与)をすることが必須となります。
輸液とは血管の静脈に点滴をすることです。
それにより、血液循環を良くすることができ、下痢や嘔吐などからくる脱水症状の改善にもなります。
吐き気や痛みを抑える薬も使用されます。
消化管の動きが悪く食欲不振になることも多いため、早めに吐き気止めや消化器の改善を図る薬によって、症状を和らげます。
急性膵炎になってしまった場合は、早期の発見・治療が非常に大切であり、入院して輸液(電解質や水分などの投与)をすることが必須となります。
輸液とは血管の静脈に点滴をすることです。
それにより、血液循環を良くすることができ、下痢や嘔吐などからくる脱水症状の改善にもなります。
吐き気や痛みを抑える薬も使用されます。
消化管の動きが悪く食欲不振になることも多いため、早めに吐き気止めや消化器の改善を図る薬によって、症状を和らげます。
猫の膵炎の急性と慢性の違い
 猫の膵炎には急性と慢性があります。
猫では慢性膵炎が多いと言われていますが、その違いはどんなところにあるのでしょうか。
次に解説していきますが、急性から慢性になったり、その逆の場合もあり、どちらも注意が必要な病気です。
猫の膵炎には急性と慢性があります。
猫では慢性膵炎が多いと言われていますが、その違いはどんなところにあるのでしょうか。
次に解説していきますが、急性から慢性になったり、その逆の場合もあり、どちらも注意が必要な病気です。
急性膵炎の特徴
慢性膵炎とは異なり、急性膵炎はその名の通り、急激に引き起こされる強い膵臓の炎症です。
膵臓と隣接する消化管などにも炎症が広がり、腹膜炎なども引き起こされます。
急性膵炎は下痢、嘔吐、腹痛、眠り続けるなどの症状が出るので、発見しやすいのが特徴です。
軽度であれば早期の適切な治療で膵臓の機能は回復されますが、対応の遅れは全身の炎症に及ぶことがあります。
最も危険なことは多臓器不全を起こすことで、命の危険があるので、とにかくすぐに診察を受けることが大切です。
慢性膵炎の特徴
 急激に炎症が起きる急性膵炎とは異なり、慢性膵炎は膵臓の炎症が長期的に続きます。
膵臓の機能が段々と破壊され、衰退していきます。
初期でははっきりした症状が出ないため、発見しにくいところも特徴的です。
一般的に7歳以降の中高齢の猫に多く、他の病気との併発も多いとされています。
病気が進行して痩せてから病院で診断されるケースもあり、飼い主が早期に発見することは難しい病気です。
できるだけ、定期的に健康診断を受け、病気の発見に努めましょう。
急激に炎症が起きる急性膵炎とは異なり、慢性膵炎は膵臓の炎症が長期的に続きます。
膵臓の機能が段々と破壊され、衰退していきます。
初期でははっきりした症状が出ないため、発見しにくいところも特徴的です。
一般的に7歳以降の中高齢の猫に多く、他の病気との併発も多いとされています。
病気が進行して痩せてから病院で診断されるケースもあり、飼い主が早期に発見することは難しい病気です。
できるだけ、定期的に健康診断を受け、病気の発見に努めましょう。
猫の膵炎の原因はある?
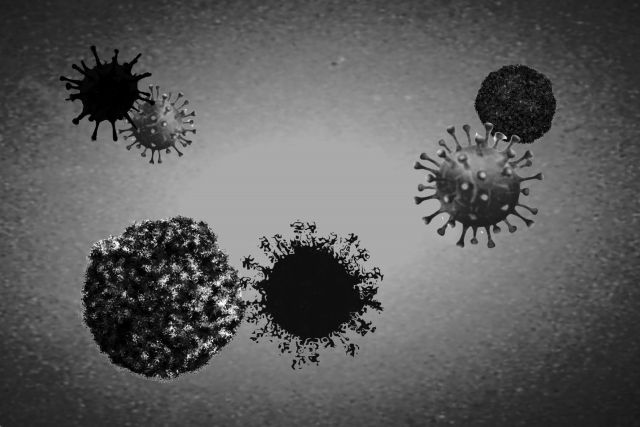 対応が遅れると、命の危険もある膵炎ですが、どのような原因で起こるのでしょうか。
実は、猫の膵炎の原因は未だ特定されていません。
しかし、原因と疑われているものは複数あり、膵臓の損傷やウイルス感染など多岐に渡っています。
例えば、トキソプラズマなどの寄生虫感染、胆管肝炎、薬物などの中毒、ヘルペスウィルスの感染などが考えられています。
どれが原因なのかは判明していませんが、いろいろな原因を考えて飼い主ができる予防について次にご紹介します。
対応が遅れると、命の危険もある膵炎ですが、どのような原因で起こるのでしょうか。
実は、猫の膵炎の原因は未だ特定されていません。
しかし、原因と疑われているものは複数あり、膵臓の損傷やウイルス感染など多岐に渡っています。
例えば、トキソプラズマなどの寄生虫感染、胆管肝炎、薬物などの中毒、ヘルペスウィルスの感染などが考えられています。
どれが原因なのかは判明していませんが、いろいろな原因を考えて飼い主ができる予防について次にご紹介します。
膵炎の予防法
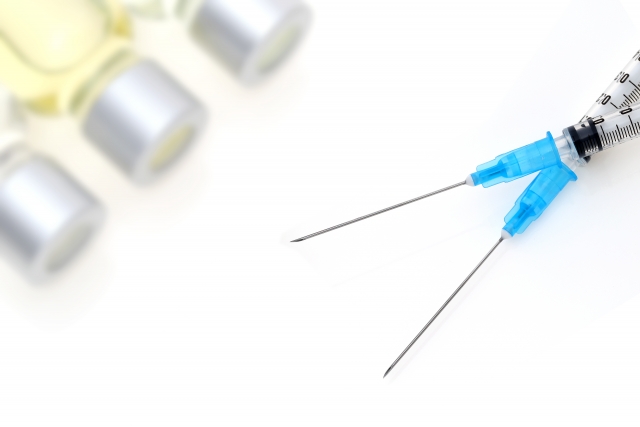 膵炎の予防法にはワクチン接種があり、ウイルス感染が原因の場合は、膵炎が引き起こされにくい状態になります。
また、慢性膵炎は定期健診などで予防できる可能性もあります。
特に中高齢になれば定期的に健康診断を受けることは重要で、膵臓に限らず肝臓や心臓などの状態も把握でき、様々な病気の早期発見に役立ちます。
それにより慢性膵炎の発症を予防できることにもつながるので、ワクチン接種や定期健診は積極的に受けましょう。
膵炎の予防法にはワクチン接種があり、ウイルス感染が原因の場合は、膵炎が引き起こされにくい状態になります。
また、慢性膵炎は定期健診などで予防できる可能性もあります。
特に中高齢になれば定期的に健康診断を受けることは重要で、膵臓に限らず肝臓や心臓などの状態も把握でき、様々な病気の早期発見に役立ちます。
それにより慢性膵炎の発症を予防できることにもつながるので、ワクチン接種や定期健診は積極的に受けましょう。
まとめ
猫の膵炎はまだ不明な部分が多く、病理検査でしか確定できない病気です。
症状や治療法をお伝えしましたが、慢性膵炎では症状があまり現れず飼い主が気づかないうちに、悪化してしますケースもあります。
食欲がないことや元気がない様子を「老化だから」と考えてしまわずに、猫の様子に変化を感じたら少し慎重になってあげてください。
早期に適切な治療を受けることで、軽度であれば完治する可能性が高く、重度の膵炎であっても治療の効果が期待できます。
日頃からよく猫の健康観察を行い、7歳からは定期的に動物病院で検診を受けましょう。
猫の疥癬とは?
 猫の疥癬を知っているでしょうか。
疥癬とは猫ヒゼンダニと呼ばれるダニが猫の体に寄生して、発症する病気です。
猫ヒゼンダニはさまざまな方法で感染してしまうため、たとえ室内の飼い猫であっても疥癬になる可能性はゼロではありません。
例えば疥癬に感染している猫に飼い猫が接触してしまうと感染してしまいます。
そのほかにも完全に室内の飼い猫でも飼い主が感染している猫と接触すれば衣服に猫ヒゼンダニが付着してしまう可能性もあり、そこから飼い猫に感染することもあります。
猫の疥癬を知っているでしょうか。
疥癬とは猫ヒゼンダニと呼ばれるダニが猫の体に寄生して、発症する病気です。
猫ヒゼンダニはさまざまな方法で感染してしまうため、たとえ室内の飼い猫であっても疥癬になる可能性はゼロではありません。
例えば疥癬に感染している猫に飼い猫が接触してしまうと感染してしまいます。
そのほかにも完全に室内の飼い猫でも飼い主が感染している猫と接触すれば衣服に猫ヒゼンダニが付着してしまう可能性もあり、そこから飼い猫に感染することもあります。
猫の疥癬の症状
 疥癬の病気のことを知らない人も多く、症状についても把握できていない場合も少なくありません。
疥癬になってしまうとあらわれる症状を理解していればいち早く疥癬に感染してしまっていることを疑うことができ、早期治療を行うこともできます。
多頭飼いしていればすべての猫に感染が広まってしまう可能性が高いですが、症状を確認したときに隔離することで感染予防することも可能です。
次に、猫が疥癬になってしまった際の症状を紹介するので参考にしてください。
疥癬の病気のことを知らない人も多く、症状についても把握できていない場合も少なくありません。
疥癬になってしまうとあらわれる症状を理解していればいち早く疥癬に感染してしまっていることを疑うことができ、早期治療を行うこともできます。
多頭飼いしていればすべての猫に感染が広まってしまう可能性が高いですが、症状を確認したときに隔離することで感染予防することも可能です。
次に、猫が疥癬になってしまった際の症状を紹介するので参考にしてください。
激しい痒みに襲われる
疥癬であらわれる症状の中でも酷いのが強い痒みがあることです。
痒みの症状があらわれると患部を搔きむしるようになってしまい、傷ついてしまったり、出血してしまうことがあります。
特に猫の場合は鋭い爪があるため、人が掻く場合よりも肌を傷つけてしまうリスクが高いです。
傷ついてしまった部分からさまざまな細菌が繁殖してしまうことで第2感染してしまうこともあり、回復が遅れてしまうだけではなく、症状が悪化してしまう原因にもなります。
猫の場合は爪で掻くだけではなく、噛んでしまうこともあり、余計に肌が傷ついてしまいやすいです。
猫は被毛に覆われているため、飼い主は被毛や皮膚のチェックをしなければ中々肌が傷ついてしまっていることに気付くことができない場合も多いです。
ストレスから食欲不振に陥ることも
 疥癬になると痒みがあらわれることを上記で紹介しましたが、常に痒みを感じていることにストレスを感じてしまい、食欲不振に陥ってしまうこともあります。
疥癬の初期症状であれば一部分だけに痒みがあらわれる程度ですが、病気が進行してしまうと全身に炎症が広がってしまい、耐えがたい痒みになってしまいます。
ヒゼンダニは猫の体温が上昇することで活動を活発化させるため、夏場であれば常に活動が活発であり、痒みがより激しくなってしまいます。
食欲不振になると当然栄養を摂取することができなくなってしまうため、栄養失調になってしまうことも少なくありません。
疥癬になると痒みがあらわれることを上記で紹介しましたが、常に痒みを感じていることにストレスを感じてしまい、食欲不振に陥ってしまうこともあります。
疥癬の初期症状であれば一部分だけに痒みがあらわれる程度ですが、病気が進行してしまうと全身に炎症が広がってしまい、耐えがたい痒みになってしまいます。
ヒゼンダニは猫の体温が上昇することで活動を活発化させるため、夏場であれば常に活動が活発であり、痒みがより激しくなってしまいます。
食欲不振になると当然栄養を摂取することができなくなってしまうため、栄養失調になってしまうことも少なくありません。
猫の疥癬の治療法
 疥癬になってしまった場合は治療を開始する必要があります。
一度感染してしまうと様子見していてもヒゼンダニがいなくなることはほとんどなく、治療しなければ症状が悪化するだけです。
次に、疥癬の治療方法について紹介するので、飼い主は把握しておきましょう。
疥癬になってしまった場合は治療を開始する必要があります。
一度感染してしまうと様子見していてもヒゼンダニがいなくなることはほとんどなく、治療しなければ症状が悪化するだけです。
次に、疥癬の治療方法について紹介するので、飼い主は把握しておきましょう。
治療法①:生活環境の改善
生活環境を改善することでヒゼンダニの繁殖を抑えることができます。
ヒゼンダニをそのままにしてしまうと繁殖を繰り返してしまい、より疥癬の症状が悪くなってしまいます。
ヒゼンダニは不衛生な環境で繁殖してしまうため、生活する環境を清潔にしていればそれだけ繁殖する力を抑制することができます。
ヒゼンダニに感染していても症状があらわれない個体もいますが、多頭飼いしていると他の猫に感染して症状があらわれてしまうこともあります。
生活環境を清潔にするほかにも消毒をすることも効果が期待できます。
治療法②:薬浴
 薬浴は殺虫効果のある薬剤をお湯に入れ、お風呂に入れる感覚で体に薬剤を浸透させていきます。
ヒゼンダニを死滅させる効果のある薬剤でもあるため、一般的に行われる治療法でもあります。
しかし、猫によってはお風呂を嫌がってしまう場合もあり、薬浴させることに悪戦苦闘してしまうことも少なくありません。
お風呂に慣れさせておけば薬浴させる手間もかからないため、おすすめです。
薬浴させることは動物病院の先生にやり方などを指導してもらうようにしましょう。
薬浴は殺虫効果のある薬剤をお湯に入れ、お風呂に入れる感覚で体に薬剤を浸透させていきます。
ヒゼンダニを死滅させる効果のある薬剤でもあるため、一般的に行われる治療法でもあります。
しかし、猫によってはお風呂を嫌がってしまう場合もあり、薬浴させることに悪戦苦闘してしまうことも少なくありません。
お風呂に慣れさせておけば薬浴させる手間もかからないため、おすすめです。
薬浴させることは動物病院の先生にやり方などを指導してもらうようにしましょう。
治療法③:投薬
投薬をすることでもヒゼンダニを死滅させることができます。
セラメクチンの成分が含まれている薬剤の効果が高いです。
最近ではスポットタイプの投薬もあり、滴下式も流通しています。
滴下タイプにはレボリューションという製品が使用されることが多く、疥癬が起きている患部に薬剤を落とすだけで効果が期待できます。
飼い主でも簡単に投薬することができるメリットはありますが、広範囲に疥癬の症状が出ている場合には適しません。
猫の疥癬の予後は?
 疥癬の治療方法は比較的効果があらわれやすく、治療を開始すれば完治する場合も多いです。
基本的に1~2か月程度で治療が完了することが多く、治療が長期間にわたってしまうこともありません。
ただし、治療を途中で中断してしまうなどしてしまうと完全にヒゼンダニが死滅していないため、再発してしまう可能性もあり、結果的に長く治療を続けなければならなくなってしまいます。
治療に適している環境かどうかは飼い主が独自で判断するのではなく、動物病院の先生の指導の元に判断するようにしましょう。
疥癬の治療方法は比較的効果があらわれやすく、治療を開始すれば完治する場合も多いです。
基本的に1~2か月程度で治療が完了することが多く、治療が長期間にわたってしまうこともありません。
ただし、治療を途中で中断してしまうなどしてしまうと完全にヒゼンダニが死滅していないため、再発してしまう可能性もあり、結果的に長く治療を続けなければならなくなってしまいます。
治療に適している環境かどうかは飼い主が独自で判断するのではなく、動物病院の先生の指導の元に判断するようにしましょう。
猫の疥癬が人にうつる危険性は?
 人もダニの影響で痒みの症状が起きることがあり、同じく疥癬になる可能性もあります。
次に、猫の疥癬が人にうつるかどうかを詳しく説明します。
飼い猫が疥癬になってしまって、自分にうつってしまうことに不安を感じている人は参考にしてください。
人もダニの影響で痒みの症状が起きることがあり、同じく疥癬になる可能性もあります。
次に、猫の疥癬が人にうつるかどうかを詳しく説明します。
飼い猫が疥癬になってしまって、自分にうつってしまうことに不安を感じている人は参考にしてください。
人間と猫に感染するダニは種類が違う
人間と猫に感染するダニの種類が異なるため、猫のヒゼンダニが人に感染することはありません。
ヒゼンダニはそれぞれの動物に寄生するため、ほかの動物に寄生しても繁殖することができません。
そのため、猫のヒゼンダニは人に寄生しても繁殖するはできません。
なので飼い猫が疥癬になってしまうと飼い主など人に感染することに必要以上に気を使う必要性はありません。
しかし、猫から猫には感染してしまう可能性が高いため、多頭飼いしているのであれば早急に隔離するなどの対応をしましょう。
ヒゼンダニが人に一時的に感染する?
 上記ではヒゼンダニは人に感染しないと紹介しましたが、一時的に感染してしまうことはあります。
矛盾していると感じてしまいやすいですが、上記で紹介したように猫のヒゼンダニが人の肌で繁殖することはできないため、一時的に人の肌に滞在するだけでそのあとは自然と死滅します。
基本的に猫のヒゼンダニは3週間程度しか人の皮膚で生きることができません。
しかし、一時的とはいえ感染してしまうことには変わりないため、猫と同じように疥癬の症状があらわれ、痒みなどの症状があらわれます。
上記ではヒゼンダニは人に感染しないと紹介しましたが、一時的に感染してしまうことはあります。
矛盾していると感じてしまいやすいですが、上記で紹介したように猫のヒゼンダニが人の肌で繁殖することはできないため、一時的に人の肌に滞在するだけでそのあとは自然と死滅します。
基本的に猫のヒゼンダニは3週間程度しか人の皮膚で生きることができません。
しかし、一時的とはいえ感染してしまうことには変わりないため、猫と同じように疥癬の症状があらわれ、痒みなどの症状があらわれます。
猫の疥癬の予防法
 猫の疥癬を予防することができれば猫を苦しませることがなくなり、飼い主に疥癬が広がってしまうこともありません。
疥癬を予防するためにはヒゼンダニに感染させないことが一番であるため、完全に室内飼いにすることが最も効果があります。
もし、室内で疥癬になる場合は飼い主が他の猫に触れて、ヒゼンダニを室内に入れてしまうぐらいしか考えられないため、それらの行動をしなければ飼い猫にヒゼンダニが付着し、繁殖してしまうこともありません。
もし、完全室内飼いが難しいのであれば定期的に駆除剤やダニ予防の薬を投与することで繁殖する前に死滅させることが期待できます。
猫の疥癬を予防することができれば猫を苦しませることがなくなり、飼い主に疥癬が広がってしまうこともありません。
疥癬を予防するためにはヒゼンダニに感染させないことが一番であるため、完全に室内飼いにすることが最も効果があります。
もし、室内で疥癬になる場合は飼い主が他の猫に触れて、ヒゼンダニを室内に入れてしまうぐらいしか考えられないため、それらの行動をしなければ飼い猫にヒゼンダニが付着し、繁殖してしまうこともありません。
もし、完全室内飼いが難しいのであれば定期的に駆除剤やダニ予防の薬を投与することで繁殖する前に死滅させることが期待できます。
まとめ
猫の疥癬はヒゼンダニというダニが皮膚や被毛で繁殖してしまい、激しい痒みが出る病気です。
放置してしまうとさらにヒゼンダニが繁殖してしまうため、症状も悪化してしまいます。
しかし、適切な治療を行えば1~2か月程度で治療を完了させることができるため、命に関わることはあまりありません。
早期発見することが治療短縮にもつながるため、猫が頻繁に痒がったり、元気がないのであれば疥癬になっている可能性があり、一度動物病院に連れて行くようにしましょう。
犬の嗅覚の仕組みや凄さ
 においを感じ取るのは、鼻の中の嗅上皮にある嗅細胞によって感知されます。
犬は、においを受け取る場所である嗅上皮の面積が広く、嗅細胞が多く存在するので、嗅覚が人に比べ優れており敏感に嗅ぎ取れることができるのです。
においを感じ取るのは、鼻の中の嗅上皮にある嗅細胞によって感知されます。
犬は、においを受け取る場所である嗅上皮の面積が広く、嗅細胞が多く存在するので、嗅覚が人に比べ優れており敏感に嗅ぎ取れることができるのです。
犬の鼻は人間の100倍の距離まで嗅ぎ取る
100倍の距離ではなく人間の鼻に存在する受容体の数が100倍と言われています。
膨大な臭気情報を処理するため、平均的な犬の嗅覚皮質(においを処理するための脳の部位)は人間の40倍も大きいです。
犬はにおいの情報処理を行なう嗅球とよばれる脳の部位が発達しているため、犬種によって異なりますが、犬の嗅覚は人に比べて100万倍から1億倍優れているといわれています。
果てしなく多く感じますね。
しかしこれはにおいを「100万倍強く感じている」「100万倍遠くからでも嗅ぎ取れる」というわけでなく、逆にその匂いが100万分の1の匂いになってもかぎ分けることができ、人間には感じ取ることができないほどの匂いもかぎ分けられるのだそうです。
犬の鼻は匂いを捕らえやすい
 犬のにおいの捕らえ方は、人間とは少し異なります。
人間はにおいだけでもにおいを感じ、また、味とにおいの組み合わせでもにおいを感じることができすが、犬の場合はにおいを単独で感じる事の割合が多いようです。
犬の嗅覚の優劣は、鼻の穴(鼻腔)の構造に左右され、鼻腔の表面(嗅上皮)内には臭いを感知するセンサーが(嗅細胞)があります。
人間の嗅上皮は約3~7平方センチメートルでだいたい1円玉~10円玉程の面積しかなく、含まれる嗅細胞の数は500万個程度です。
一方、犬種によって多少の変動はあるものの、犬の嗅上皮は約150~390平方センチメートルで人間の50倍以上!
ちょうど1000円札1枚ちょっとの面積に相当し、含まれる嗅細胞の数も約2億2千万個と、人間を圧倒しています。
表面積が大きいということは、それだけ多くの嗅細胞が存在することでにおいを捕らえ嗅覚が優れていると言えるでしょう。
犬のにおいの捕らえ方は、人間とは少し異なります。
人間はにおいだけでもにおいを感じ、また、味とにおいの組み合わせでもにおいを感じることができすが、犬の場合はにおいを単独で感じる事の割合が多いようです。
犬の嗅覚の優劣は、鼻の穴(鼻腔)の構造に左右され、鼻腔の表面(嗅上皮)内には臭いを感知するセンサーが(嗅細胞)があります。
人間の嗅上皮は約3~7平方センチメートルでだいたい1円玉~10円玉程の面積しかなく、含まれる嗅細胞の数は500万個程度です。
一方、犬種によって多少の変動はあるものの、犬の嗅上皮は約150~390平方センチメートルで人間の50倍以上!
ちょうど1000円札1枚ちょっとの面積に相当し、含まれる嗅細胞の数も約2億2千万個と、人間を圧倒しています。
表面積が大きいということは、それだけ多くの嗅細胞が存在することでにおいを捕らえ嗅覚が優れていると言えるでしょう。
犬の鼻は嗅ぎ分けのプロ
犬は敏感ににおいを嗅ぎ分けるため、得意なにおいと苦手なにおいがあります。
得意なにおいは、酢酸(人間の汗に含まれているびおい)で、人間と暮らすようになった犬が大好きな飼い主さんのにおいを覚えたという説があります。
もう一つは吉草酸(脂肪酸の一種)です。
分かりやすくいうと、足の裏のにおいのことです。
靴下には飼い主さんの足裏のにおいにが一番付いているため、靴下好きの犬が多いのは吉草酸に敏感に反応しているからかもしれません。
日常生活において基本的には、人間に支障ないレベルであれば、犬への影響もほぼないと考えても大丈夫ですが、人より嗅覚が優れた犬には化学物質などから作られた人工的な匂いや刺激臭が強すぎるものは苦手に感じているかもしれません。
犬の鼻は空気の制御もできる
 左右の鼻孔にある翼状の弁は、息を吐くときは閉じ、においを嗅ぐときに開くことで空気の流れを制御しています。
これにより、息を吸ったときに入ってくる別のにおいと、空気を脇に押しやることで、においと空気が混ざるのを防いでいます。
また、特殊な例としてブラッドハウンドの垂れ耳は、地面に引きずってにおいを舞い立たせることで、少しでも鼻に届きやすくしていると言います。
左右の鼻孔にある翼状の弁は、息を吐くときは閉じ、においを嗅ぐときに開くことで空気の流れを制御しています。
これにより、息を吸ったときに入ってくる別のにおいと、空気を脇に押しやることで、においと空気が混ざるのを防いでいます。
また、特殊な例としてブラッドハウンドの垂れ耳は、地面に引きずってにおいを舞い立たせることで、少しでも鼻に届きやすくしていると言います。
クンクンと嗅ぐのは交流のため
お散歩は、出会った人や犬と交流し毎日定期的に体を動かす事によって、健康維持や人との関わりのきっかけをつくり、犬だけでなく人にも良い効果をもたらします。
散歩中に地面や草花のにおいを嗅いだり、誰彼かまわず人のにおいを嗅いだりします。
これはにおいを通して社会的な交流を図っています。
犬にとってのにおいが人間で言う言葉を表現しているのと同じです。
初対面の相手を知るにはまず臭いをかぎ、相手の情報を収集しているのです。
犬はにおいで他の犬を識別するだけでなく、互いの口を嗅ぐことで相手が何を食べたかを理解しています。
犬は匂いを嗅いで時間管理を行う
 実は犬にも「体内時計」が存在するのです。
人間と同様に犬の体内時計も光を浴びることでリセットされ、一定のリズムを保ちます。
そのため、正しい体内時計を保つには外の散歩がとても必要となってきます。
もしも、外に出て日の光を浴びないと犬は朝なのか夜なのかが分からなくなります。
朝、散歩に行き朝の日差しを浴びることは、生活リズムを規則正しく保ちホルモンバランスを整えるなどとても重要な役割を果たしています。
また、犬は春から夏には皮下脂肪量を減らし夏毛になり、暑さに対応できる体をつくります。
そして秋になると冬に向けての準備として食欲を増し、皮下脂肪を増やして寒さに対応できる冬毛になろうとします。
犬が外に出て日光を浴びる事により季節もしっかり感じられるようにしましょう。
実は犬にも「体内時計」が存在するのです。
人間と同様に犬の体内時計も光を浴びることでリセットされ、一定のリズムを保ちます。
そのため、正しい体内時計を保つには外の散歩がとても必要となってきます。
もしも、外に出て日の光を浴びないと犬は朝なのか夜なのかが分からなくなります。
朝、散歩に行き朝の日差しを浴びることは、生活リズムを規則正しく保ちホルモンバランスを整えるなどとても重要な役割を果たしています。
また、犬は春から夏には皮下脂肪量を減らし夏毛になり、暑さに対応できる体をつくります。
そして秋になると冬に向けての準備として食欲を増し、皮下脂肪を増やして寒さに対応できる冬毛になろうとします。
犬が外に出て日光を浴びる事により季節もしっかり感じられるようにしましょう。
犬種による嗅覚の違いは?
 犬の嗅覚能力はマズル(鼻先)の長さが長いほど、優れているといわれています。
犬はマズルの長い順に長頭種、中頭種、短頭種の以下の三つのグループに分けられます。
犬の鼻内部には匂いを探知する細胞があり、鼻の長さ・大きさによって嗅覚に違いがあります。
犬の嗅覚能力はマズル(鼻先)の長さが長いほど、優れているといわれています。
犬はマズルの長い順に長頭種、中頭種、短頭種の以下の三つのグループに分けられます。
犬の鼻内部には匂いを探知する細胞があり、鼻の長さ・大きさによって嗅覚に違いがあります。
嗅覚が弱い短頭種
犬はにおいを受け取る場所(嗅上皮)の面積が人間より広いため、においを敏感に嗅ぎ取ることができます。
犬のマズルは種類によって違い、マズルの長さによって嗅覚は異なります。
狭く細胞の数が少ない短頭種のパグ、フレンチブルドッグ、ペキニーズ、ボストンテリアなどは呼吸がしずらいため、長頭種の犬と比べると嗅覚が少し弱いといえます。
さらに熱を逃すのが苦手なので、夏は熱中症にならないよう気をつけてあげましょう。
日本犬は猿追いが得意
 最近、日本の各地で農作物を荒らす猿が増えています。
農作物を守るために猿を山へ追い戻す使役犬「猿追い犬」=「モンキードッグ」が活躍しています。
いろんな種類の犬に訓練をおこない、さまざまなモンキードッグが誕生していますが、なかでも「猿追い」に向いた性質を持つといわれるのが、柴犬をはじめとする日本犬です。
日本犬は空気中の上方に漂う臭いを察知することに長けており、木の上の方にいる猿の臭いを感じ取ることを得意としています。
最近、日本の各地で農作物を荒らす猿が増えています。
農作物を守るために猿を山へ追い戻す使役犬「猿追い犬」=「モンキードッグ」が活躍しています。
いろんな種類の犬に訓練をおこない、さまざまなモンキードッグが誕生していますが、なかでも「猿追い」に向いた性質を持つといわれるのが、柴犬をはじめとする日本犬です。
日本犬は空気中の上方に漂う臭いを察知することに長けており、木の上の方にいる猿の臭いを感じ取ることを得意としています。
嗅覚に優れた嗅覚ハウンド
テリア犬を除いた狩猟犬のことを「ハウンド」と呼びます。
さらに「ハウンド」は「視覚ハウンド」と「嗅覚ハウンド」の2種に分類されます。
嗅覚ハウンドは、犬特有の能力である臭いを嗅ぎ分けることを生かして活躍してきました。
嗅覚ハウンドは「セント・ハウンド」とも呼ばれ、もともとは大型で非常に嗅覚に優れた犬種だったとされています。
地面に鼻を押し付けるように臭いを嗅ぎ、その鋭い嗅覚で獲物をどこまでも追い詰めてました。
最近は嗅覚ハウンドの多くも人間の家族として暮らしています。
代表的な嗅覚ハウンド①:ブラッドハウンド
フランスのアルデンヌ地方で暮らしていた大型ハウンドを11世紀イギリスへ持ち込み、外来種と交配させた犬種が「ブラッドハウンド」です。
並外れた嗅覚を持つ犬としても知られ、傷ついた獲物の足跡を発見することが得意なために「ブラッド」と名付けられたそうです。
日本では希少な犬種ですが、優れた嗅覚を生かして行方不明者の捜索などで警察犬として活躍するほど賢い犬です。
落ち着きのある穏やかな性格で、人とも犬とも仲よくできる社交性も持ち合わせています。
代表的な嗅覚ハウンド②:プチ・バセット・グリフォン・バンデーン
 16世紀頃、プチ・バセット・グリフォン・バンデーンは、フランスのバンデーン地方でウサギ狩りなどの猟犬として活躍していたとても古い犬種です。
大きな垂れ耳、胴長で短い足、硬い被毛が特徴で、陽気で元気いっぱいで家族には愛情深く接する優しい犬種です。
もともと猟犬だっため、落ち着いた家庭犬となるためには毎日たっぷりと運動させることも必要です。
愛犬とアウトドアライフを楽しみたい人には、運動神経もよく、外で活動することが大好きなのでピッタリです。
16世紀頃、プチ・バセット・グリフォン・バンデーンは、フランスのバンデーン地方でウサギ狩りなどの猟犬として活躍していたとても古い犬種です。
大きな垂れ耳、胴長で短い足、硬い被毛が特徴で、陽気で元気いっぱいで家族には愛情深く接する優しい犬種です。
もともと猟犬だっため、落ち着いた家庭犬となるためには毎日たっぷりと運動させることも必要です。
愛犬とアウトドアライフを楽しみたい人には、運動神経もよく、外で活動することが大好きなのでピッタリです。
代表的な嗅覚ハウンド③:ビーグル
 嗅覚ハウンドの中で一番小さな犬で、昔、イギリスではウサギ狩りのために珍重されていました。
「スヌーピー」のモデルとなった世界中で愛されている犬種ですが、優れた嗅覚で獲物を追いかける狩猟犬です。
好奇心が強いので、興味を持ったものを追いかけるのに夢中になりやすく猟犬に向いてると言えるでしょう。
性格は、非常に愛情深く、人なつっこく甘えん坊で人見知りをしないので家族ともほかの人や犬とも仲良くできる犬種です。
嗅覚ハウンドの中で一番小さな犬で、昔、イギリスではウサギ狩りのために珍重されていました。
「スヌーピー」のモデルとなった世界中で愛されている犬種ですが、優れた嗅覚で獲物を追いかける狩猟犬です。
好奇心が強いので、興味を持ったものを追いかけるのに夢中になりやすく猟犬に向いてると言えるでしょう。
性格は、非常に愛情深く、人なつっこく甘えん坊で人見知りをしないので家族ともほかの人や犬とも仲良くできる犬種です。
まとめ
ひとえに「犬は鼻が良い」と思っていましたが、人間の1億倍も優れた嗅覚でにおいを察知していたなんて驚きです。
複数のにおいを識別したり、人間にはキャッチできないわずかなにおいを感知したり、人間の鼻の機能とは大きく異なっていることが分かりました。
そのため猟犬や警察犬などで活躍している犬種も多くいます。
人間が良いにおい、と感じていても愛犬からすれば不快なにおいという可能性もあるため、一緒に生活する時は充分気をつけてあげましょう。
猫の嗅覚が優れている理由
 猫というと、発達した身体能力や柔らかい体つきを思う浮かべるかもしれません。
しかし、人間と比べると嗅覚が優れており、呼吸の他にも様々な情報収集を行う優れた器官として機能しています。
ここでは、そんな猫をよく知るきっかけとなるような嗅覚についてご紹介していきます。
猫というと、発達した身体能力や柔らかい体つきを思う浮かべるかもしれません。
しかし、人間と比べると嗅覚が優れており、呼吸の他にも様々な情報収集を行う優れた器官として機能しています。
ここでは、そんな猫をよく知るきっかけとなるような嗅覚についてご紹介していきます。
猫の嗅覚は大切な情報源
生まれたばかりの赤ちゃん猫は、お母さん猫から離れたら生きていくことが難しくなります。
生きる術として生まれてすぐでも嗅覚が発達している赤ちゃん猫は、おっぱいがどこにあるのかちゃんと見つけることが出来ます。
目がしっかりと開いて見えるほど成長しても、視力に頼らない生き物である猫は嗅覚で仲間の居場所やご飯の位置など判断することが多いといわれています。
他にも、敵の侵入や危険な存在の気配を嗅覚と聴覚で敏感に感じ取ることも可能で、安全な生活を送るための情報網として利用しています。
湿った鼻が嗅覚をサポート
 猫の鼻はいつも湿っているけれど何故?と、感じることはありませんか。
逆に熟睡している時や寝起きの時は、乾いていることが多いはずです。
また、脱水や老化現象として鼻が乾くこともありますが、健康でも乾いていることはよく見られるので気になる症状がなければ心配の必要はありません。
鼻の湿り気は、鼻腔内からの分泌液によるもので濡れていることによって匂いをより吸着しやすくする効果があります。
乾いた鼻は匂いをキャッチしにくい状態となり、感知能力が下がってしまいます。
猫の鼻はいつも湿っているけれど何故?と、感じることはありませんか。
逆に熟睡している時や寝起きの時は、乾いていることが多いはずです。
また、脱水や老化現象として鼻が乾くこともありますが、健康でも乾いていることはよく見られるので気になる症状がなければ心配の必要はありません。
鼻の湿り気は、鼻腔内からの分泌液によるもので濡れていることによって匂いをより吸着しやすくする効果があります。
乾いた鼻は匂いをキャッチしにくい状態となり、感知能力が下がってしまいます。
猫の嗅覚は人間よりも遥かに良い
人間と比べると、猫の嗅覚は約数万から数十万倍も発達しているといわれています。
これは、匂いを人間よりも強く感じているというよりも、ほんの僅かな匂いでも気づくことができるという優れた感度を意味しています。
野生で生活してきた肉食である猫の祖先は、生きるために獲物の位置や存在を正確に読み取っていました。
家族として一緒に生活している猫が、自分の匂いを飼い主様に擦り付けてきたり着ていた洋服の上で眠ってしまったりする行動も、人には感じない程の僅かな匂いに安心している証拠ででしょう。
猫の優れた嗅覚の役割
 生きるために大切な役割を持つ嗅覚を生まれた時から身に付けている猫ですが、身を守るためや猫同士の関係性にも関わると考えられています。
では、実際に嗅覚によってどんなことができるのでしょうか。
生きるために大切な役割を持つ嗅覚を生まれた時から身に付けている猫ですが、身を守るためや猫同士の関係性にも関わると考えられています。
では、実際に嗅覚によってどんなことができるのでしょうか。
役割①:縄張りを確認するため
猫は縄張りを持つ動物として、自分のテリトリーである場所に頬の両側や顎の下を擦り付ける様子がみられます。
この体の場所には臭腺という分泌線がありマーキングをするのですが、場所や家具の他に、飼い主様の体にもスリスリしてくることはありませんか。
縄張りや所有権を主張しているこの行動は、まさしく飼い主様が下僕と呼ばれる理由になっていますね。
また、匂いを確認してその場所がどの猫の縄張りなのかを判断しているといわれています。
役割②:挨拶をするため
 可愛い仕草として猫好きにはよく知られている鼻チューですが、本当にキスをしている訳ではなくお互いの鼻同士を寄せ合って匂いを確認しているんです。
仲が悪い猫同士では絶対にしない行動で、「こんにちは」「喧嘩するつもりはないよ」と挨拶をしています。
また、匂いによって行動や相手の情報を確かめているとも考えられていますが、親密度が高い猫同士は頻繁に行うので多頭飼いしている飼い主様はじっくりと観察してみてはいかがでしょうか。
可愛い仕草として猫好きにはよく知られている鼻チューですが、本当にキスをしている訳ではなくお互いの鼻同士を寄せ合って匂いを確認しているんです。
仲が悪い猫同士では絶対にしない行動で、「こんにちは」「喧嘩するつもりはないよ」と挨拶をしています。
また、匂いによって行動や相手の情報を確かめているとも考えられていますが、親密度が高い猫同士は頻繁に行うので多頭飼いしている飼い主様はじっくりと観察してみてはいかがでしょうか。
役割③:相手の情報を確認するため
鼻チューで確認し合ったら、より匂腺が強い体からお尻へと移動し相手をより良く知ろうとします。
肛門近くにある匂腺は、猫の体調や年齢に性別といった履歴書のような情報が組み込まれており自分より優位なのか発情しているのかも確認できます。
また、先にお尻を嗅いだ猫が優位に立つとも考えられており、単独行動を好む猫が背中を見せるのは不利な状況ともいえるでしょう。
役割④:食べ物の判別をするため
 嗅覚が発達している猫は、食べ物の匂いを念入りに嗅いで食べても大丈夫なのか、腐敗していないかをチェックしています。
味覚より嗅覚でご飯を食べるといわれている猫は、匂いによって美味しいかどうかの判断をします。
ねこ風邪や病気などで鼻が詰まった猫は、食べ物の認識がしづらく食欲不振になることもあるでしょう。
もし嗅覚が利かないことでご飯を食べなくなった場合は、匂いの強い嗜好性の高いオヤツをトッピングしたり少し温めて匂いを強くしてあげると食べてくれるかもしれません。
鼻が利かない状態は体調が悪いことを表していますが、食欲まで失われてしまうと余計回復が遅くなります。
そのくらい、匂いは猫にとって大切なんですね。
嗅覚が発達している猫は、食べ物の匂いを念入りに嗅いで食べても大丈夫なのか、腐敗していないかをチェックしています。
味覚より嗅覚でご飯を食べるといわれている猫は、匂いによって美味しいかどうかの判断をします。
ねこ風邪や病気などで鼻が詰まった猫は、食べ物の認識がしづらく食欲不振になることもあるでしょう。
もし嗅覚が利かないことでご飯を食べなくなった場合は、匂いの強い嗜好性の高いオヤツをトッピングしたり少し温めて匂いを強くしてあげると食べてくれるかもしれません。
鼻が利かない状態は体調が悪いことを表していますが、食欲まで失われてしまうと余計回復が遅くなります。
そのくらい、匂いは猫にとって大切なんですね。
猫の嗅覚が好む匂いは?
 猫は人間と同じく好きな匂いと嫌いな匂いがあり、どちらかというと強い匂いを好む傾向にあります。
また、嫌いな匂いがいつも近くにあるような環境は、大きなストレスとなりますので気をつけてあげましょう。
では、好きな匂いをいくつかご紹介していきます。
猫は人間と同じく好きな匂いと嫌いな匂いがあり、どちらかというと強い匂いを好む傾向にあります。
また、嫌いな匂いがいつも近くにあるような環境は、大きなストレスとなりますので気をつけてあげましょう。
では、好きな匂いをいくつかご紹介していきます。
魚類の匂い
猫といえば、魚が好きなイメージはありますよね。
キャットフードもカツオやアジにマグロといった、美味しいそうな香りのフードがたくさん販売されています。
飼い主様が、ご飯のおかずに焼き魚を用意すると近くまで寄ってきて、いかにも欲しそうな顔で見つめている姿はあるあるの光景ではないでしょうか。
匂いを嗅がせること自体は大丈夫ですが、塩分の多い身をお裾分けする行為は控えましょう。
猫の健康を脅かす原因となり、濃い味付けに慣れるとフードを食べてくれなくなる可能性もあります。
またたびの匂い
 キャットニップやまたたびは、うっとりとしたりテンションアップしたりしてお気に入りの猫が多いのではないでしょうか。
またたびに含まれる成分によって猫の中枢神経を刺激し、酩酊しているような状態が見られることから依存性の心配をされる方も多いのですが、その心配はないと考えられています。
ストレス解消や食欲アップなど、健康に良い効果を期待できますが、使い方によっては逆効果となる場合もあります。
刺激が弱い粉末タイプを、用法用量や対象年齢を守ってご褒美として与えましょう。
キャットニップやまたたびは、うっとりとしたりテンションアップしたりしてお気に入りの猫が多いのではないでしょうか。
またたびに含まれる成分によって猫の中枢神経を刺激し、酩酊しているような状態が見られることから依存性の心配をされる方も多いのですが、その心配はないと考えられています。
ストレス解消や食欲アップなど、健康に良い効果を期待できますが、使い方によっては逆効果となる場合もあります。
刺激が弱い粉末タイプを、用法用量や対象年齢を守ってご褒美として与えましょう。
飼い主の匂い
甘えん坊の猫や、飼い主様が大好きな猫は飼い主様の使ったタオルや布団、1日着ていた洋服などに付いた匂いが大好きです。
お留守番やペットホテルに預ける際に、飼い主様の匂いが付いた物を一緒に預けると落ち着いて過ごしてくれるはずです。
人間には感じ取れないわずかな匂いでも、鋭い嗅覚のおかげで大好きな飼い主様の匂いを感じ安心してくれるでしょう。
猫の嗅覚が嫌う匂いは?
 猫が嫌いな匂いには、本能的なものが一因しています。
もし誤って口にしてしまうと害となるものもありますので、「嫌いだから食べないはず」と思わず注意してあげてください。
猫が嫌いな匂いには、本能的なものが一因しています。
もし誤って口にしてしまうと害となるものもありますので、「嫌いだから食べないはず」と思わず注意してあげてください。
洗剤の匂い
洗剤の香料が苦手な猫は多いようです。
今現在たくさんの種類が販売されている柔軟剤は、人間には良い香りとして認識されますが洗濯後に放置したり、猫の通り道に容器を保管したりすることは避けましょう。
基本的に家の中で生活する猫が、家は嫌なものや敵がいない安全な空間として生活してもらうために注意します。
他にもペットベッドやウエアを洗濯する際は、ペット専用の洗剤を使用すると安心です。
スパイシー系の匂い
 胡椒や唐辛子といった香辛料の強い香りは、猫にとって刺激が強く苦手としています。
何でも好みに応じて食べる人間とは違い、辛さや刺激は猫にとって不要のものなのです。
万が一、口にしてしまうと胃腸を壊したり体調不良となったりする場合も考えられますので、人間の食べるものに何でも興味を持つ猫がいるご家庭は、誤食しないようにしてください。
キッチンに自由に猫が出入りしていると、床に落ちた香辛料が体に付着しグルーミングで舐め取ってしまう場合もあります。
使用後は面倒ですが、毎回拭いて残らないように気をつけてあげてください。
胡椒や唐辛子といった香辛料の強い香りは、猫にとって刺激が強く苦手としています。
何でも好みに応じて食べる人間とは違い、辛さや刺激は猫にとって不要のものなのです。
万が一、口にしてしまうと胃腸を壊したり体調不良となったりする場合も考えられますので、人間の食べるものに何でも興味を持つ猫がいるご家庭は、誤食しないようにしてください。
キッチンに自由に猫が出入りしていると、床に落ちた香辛料が体に付着しグルーミングで舐め取ってしまう場合もあります。
使用後は面倒ですが、毎回拭いて残らないように気をつけてあげてください。
メンソール系の匂い
ツンと鼻につく刺激が特徴のメンソールは、湿布や痒み止めなど身近にある商品によく使われています。
やはりこの刺激臭は猫にとって不快を感じるものとして知られており、使用する時は短時間で猫の近くでは使わないようにしましょう。
他にも制汗剤や清涼感が人気のあるシャンプーなどにも使われていますので、飼い主様=嫌な匂いと認識されないように猫ファーストで配慮してあげてください。
柑橘系の匂い
 甘味の中にも爽やかな酸味が美味しいオレンジやグレープフルーツなどの柑橘系は、猫にとって腐敗を連想させるようです。
匂いで食べられるものかどうか判断していることは先述の通りですが、柑橘系は本能から肉や魚が腐った匂いとして捉え、近寄ることも少ないはずです。
他にも柑橘類の皮に含まれるリモネンという成分は、もし猫の体に入った場合に代謝して分解することができず中毒症状を引き起こします。
最悪、命にも関わりますので絶対に与えないでください。
甘味の中にも爽やかな酸味が美味しいオレンジやグレープフルーツなどの柑橘系は、猫にとって腐敗を連想させるようです。
匂いで食べられるものかどうか判断していることは先述の通りですが、柑橘系は本能から肉や魚が腐った匂いとして捉え、近寄ることも少ないはずです。
他にも柑橘類の皮に含まれるリモネンという成分は、もし猫の体に入った場合に代謝して分解することができず中毒症状を引き起こします。
最悪、命にも関わりますので絶対に与えないでください。
まとめ
猫の嗅覚はとても発達していて、挨拶や食欲に縄張りなど様々な働きがあることがわかりました。
人間と良い距離感で共存していくために、嫌いな匂いや健康に関する匂いには十分注意してあげましょう。
ご自宅にいる猫やお外で暮らしている猫の様子をじっくり観察してみるのも楽しいでしょう。
猫も喘息になる?
 猫も人と同じように喘息になることを知っているでしょうか。
猫の場合は他の動物と比べても症状が人と似ているため、重篤になる前に早期発見する必要があり、異常にも比較的気づきやすいです。
喘息はうまく呼吸することができず、症状が悪化してしまうと呼吸困難になってしまうことも珍しくありません。
喘息になってしまう原因は様々であるため、もし猫が咳を頻繁にしているのであれば喘息になってしまっていることを疑いましょう。
猫も人と同じように喘息になることを知っているでしょうか。
猫の場合は他の動物と比べても症状が人と似ているため、重篤になる前に早期発見する必要があり、異常にも比較的気づきやすいです。
喘息はうまく呼吸することができず、症状が悪化してしまうと呼吸困難になってしまうことも珍しくありません。
喘息になってしまう原因は様々であるため、もし猫が咳を頻繁にしているのであれば喘息になってしまっていることを疑いましょう。
猫喘息の原因
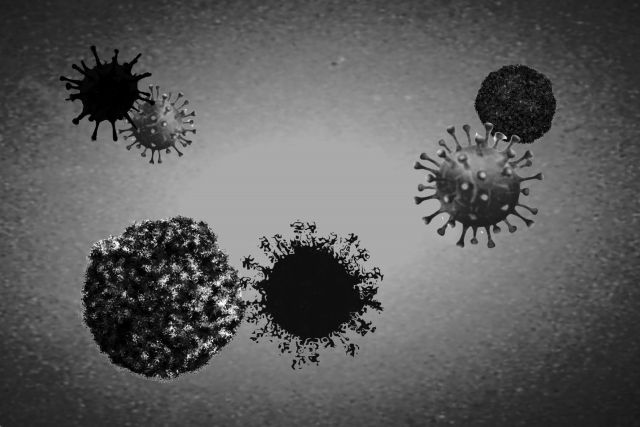 猫が喘息になってしまう原因はアレルギーが関係している場合が多いです。
アレルギーは特定の物質が体内に入ることでさまざまな症状を起こしてしまい、花粉やハウスダストは人もアレルギーの原因となる場合が多く、猫も同じようにアレルギー反応を起こしてしまいます。
それ以外にも消臭剤やヘアスプレー、洗浄剤、たばこの煙などを吸い込むことでもアレルギー反応を起こしてしまう可能性があるため、猫が喘息をしているのであればそれらのアレルギー物質が関係している可能性があります。
猫が喘息になってしまう原因はアレルギーが関係している場合が多いです。
アレルギーは特定の物質が体内に入ることでさまざまな症状を起こしてしまい、花粉やハウスダストは人もアレルギーの原因となる場合が多く、猫も同じようにアレルギー反応を起こしてしまいます。
それ以外にも消臭剤やヘアスプレー、洗浄剤、たばこの煙などを吸い込むことでもアレルギー反応を起こしてしまう可能性があるため、猫が喘息をしているのであればそれらのアレルギー物質が関係している可能性があります。
猫喘息の症状
 猫喘息になってしまうとどのような症状があらわれるようになるのか知っておけば猫喘息を発症していることに早期発見することも可能になります。
喘息は安静にしていれば症状が治まることもありますが、甘く見ていると呼吸困難になってしまうこともあります。
次に、猫喘息の症状を紹介するので、どのような症状があらわれるのか知りたい人は参考にしてください。
基本的に人の喘息と症状は似ているため、猫の様子を頻繁にチェックしていれば早期発見することも可能です。
猫喘息になってしまうとどのような症状があらわれるようになるのか知っておけば猫喘息を発症していることに早期発見することも可能になります。
喘息は安静にしていれば症状が治まることもありますが、甘く見ていると呼吸困難になってしまうこともあります。
次に、猫喘息の症状を紹介するので、どのような症状があらわれるのか知りたい人は参考にしてください。
基本的に人の喘息と症状は似ているため、猫の様子を頻繁にチェックしていれば早期発見することも可能です。
喘鳴(ぜんめい)
喘鳴の症状が出ていると喘息を疑い、早期に治療を受けさせることをおすすめします。
喘息は気管に炎症が起き、気道が狭くなるため、呼吸する際にヒューヒューとなるようになります。
人も同じような症状が出るため、一度でも喘息になった経験があるのであれば喘息を疑うことができます。
喘鳴の症状が出ているときは呼吸を思うように肺に入れることができないので、苦しい様子を見せることもあります。
喘鳴は音が鳴る症状でもあるため、比較的異常に気付きやすいです。
咳
 咳をしている場合も喘息であることを疑いましょう。
元々猫は頻繁に咳をする動物ではないため、繰り返し咳をしているのであれば喘息であったり、肺や気管に異常がある場合があります。
また、発作的に咳をしており、それが1分間以上続いているのであれば異常であるため、喘息になっている可能性があります。
人の場合はゲホゲホ咳をしますが、猫の場合はズーズーやゲッゲッと咳をする特徴があります。
また、咳をする際にはうつ伏せになり、舌を軽く出していることが多いです。
咳を連続していると最悪嘔吐してしまう可能性もあり、喘息の症状が悪化している可能性も出てきます。
咳をする頻度や回数を確認することで症状が和らいでいるのか進行しているのかを確認することができます。
咳をしている場合も喘息であることを疑いましょう。
元々猫は頻繁に咳をする動物ではないため、繰り返し咳をしているのであれば喘息であったり、肺や気管に異常がある場合があります。
また、発作的に咳をしており、それが1分間以上続いているのであれば異常であるため、喘息になっている可能性があります。
人の場合はゲホゲホ咳をしますが、猫の場合はズーズーやゲッゲッと咳をする特徴があります。
また、咳をする際にはうつ伏せになり、舌を軽く出していることが多いです。
咳を連続していると最悪嘔吐してしまう可能性もあり、喘息の症状が悪化している可能性も出てきます。
咳をする頻度や回数を確認することで症状が和らいでいるのか進行しているのかを確認することができます。
口を開けながら呼吸してチアノーゼを起こす
喘息になると口を空けながら呼吸をしてチアノーゼを起こしてしまうこともあります。
口で呼吸していることは鼻からの呼吸だけでは思うように酸素を取り入れることができていない状態であるため、非常に危険な状態とも言えます。
体に酸素をうまく取り入れることができていない状態のことをチアノーゼと言い、口周りや舌が紫色になる特徴があります。
喘息によるチアノーゼになってしまう可能性は必ず存在しており、急に体調が変わってしまうこともあるため、常に猫の様子をうかがうようにしましょう。
もしチアノーゼの状態になってしまったのであれば緊急に対処してもらう必要があり、動物病院に連れていくことが大切です。
普段から発作的に喘息をしている猫ほど気を付ける必要があります。
呼吸回数が多い・活動性の低下
 喘息の症状が進行してしまうと肺や気管の機能も低下してしまいます。
そのため、酸素を思うように体に取り入れることができず、呼吸する回数が多くなってしまいます。
また、正常な時よりも体に酸素が供給されていないのですぐに疲れてしまったり、遊ぶ時間も少なくなる傾向があります。
呼吸する回数が多く、時間が経過しても呼吸回数が落ち着かない場合は喘息であったり、呼吸器系に何かしらの異常が起きている可能性があります。
普段であれば活発に行動していた猫が急に元気なかったり、遊ばなくなったのであれば呼吸の回数を確認し、喘息かどうかを把握しましょう。
喘息の症状が進行してしまうと肺や気管の機能も低下してしまいます。
そのため、酸素を思うように体に取り入れることができず、呼吸する回数が多くなってしまいます。
また、正常な時よりも体に酸素が供給されていないのですぐに疲れてしまったり、遊ぶ時間も少なくなる傾向があります。
呼吸する回数が多く、時間が経過しても呼吸回数が落ち着かない場合は喘息であったり、呼吸器系に何かしらの異常が起きている可能性があります。
普段であれば活発に行動していた猫が急に元気なかったり、遊ばなくなったのであれば呼吸の回数を確認し、喘息かどうかを把握しましょう。
猫喘息の予防法
 猫喘息から猫を守るためには予防方法を行うことをおすすめします。
猫喘息の原因の大半はアレルギー反応を起こしているので、アレルギー物質を特定し、猫がアレルギー物質を吸い込まないように心がけることが最大の予防策と言えます。
反応してしまうアレルギー物質は猫の個体ごとに異なり、どのようなタイミングで喘息の症状が出ているのかを確認しましょう。
食べ物が関係していれば特定しやすいですが、消臭剤や洗浄剤など吸い込むことでアレルギー反応を起こしてしまう場合は特定するのに時間がかかってしまいやすいです。
猫喘息から猫を守るためには予防方法を行うことをおすすめします。
猫喘息の原因の大半はアレルギー反応を起こしているので、アレルギー物質を特定し、猫がアレルギー物質を吸い込まないように心がけることが最大の予防策と言えます。
反応してしまうアレルギー物質は猫の個体ごとに異なり、どのようなタイミングで喘息の症状が出ているのかを確認しましょう。
食べ物が関係していれば特定しやすいですが、消臭剤や洗浄剤など吸い込むことでアレルギー反応を起こしてしまう場合は特定するのに時間がかかってしまいやすいです。
猫喘息の治療法
 猫喘息になってしまったのであれば治療を開始する必要があります。
喘息を甘く見ていると死亡してしまうこともあるため、喘息の疑いがあるのであれば動物病院で診察してもらうようにしましょう。
猫喘息の治療法はいくつか用意されており、症状の具合や原因などによって治療法も変わってきます。
次に、猫喘息の治療方法について詳しく紹介します。
飼い猫が喘息になっている恐れがあるのであれば動物病院に連れて行くと同時にどのような治療が行われるのかも知っておきましょう。
猫喘息になってしまったのであれば治療を開始する必要があります。
喘息を甘く見ていると死亡してしまうこともあるため、喘息の疑いがあるのであれば動物病院で診察してもらうようにしましょう。
猫喘息の治療法はいくつか用意されており、症状の具合や原因などによって治療法も変わってきます。
次に、猫喘息の治療方法について詳しく紹介します。
飼い猫が喘息になっている恐れがあるのであれば動物病院に連れて行くと同時にどのような治療が行われるのかも知っておきましょう。
アレルゲンを排除する
アレルギーが原因であれば薬などで治療することもできますが、原因でもあるアレルゲンを体内に入れないことが最も大切なことになります。
いくら薬などで症状を緩和しても原因が取り除かれないのであれば再び喘息が再発してしまいます。
アレルギーが原因の場合はアレルゲン物質を特定することが求められますが、実際はなかなか難しいです。
猫の病歴を再確認したり、生活環境などを分析することである程度アレルゲンを特定することも可能です。
飼い主だけではアレルゲンを特定することは難しいので、動物病院の先生などと協力してアレルゲンを絞り込むようにしましょう。
アレルゲンを特定したり、絞り込むことができたのであれば猫が触れないようにすることで喘息の症状があらわれなくなります。
もし、症状が改善されないのであればアレルゲンが違う場合や違う原因である可能性があります。
抗炎症療法と気管支拡張療法
 喘息は薬でも治療することができ、主に抗炎症薬と気管支拡張薬が使用されます。
アレルギー反応を起こしてしまうと気管が炎症して気管が狭くなってしまっている可能性が高いです。
そのままでは完全に空気の通り道が遮断されてしまい、呼吸をすることができなくなってしまいます。
そのような状態にならないためにも炎症を抑える抗炎症薬や気管を広げる効果がある気管支拡張薬が使用されます。
最初は多めに投与されますが、症状が緩和されていれば徐々に投与する量を減らしていく場合が一般的です。
喘息は薬でも治療することができ、主に抗炎症薬と気管支拡張薬が使用されます。
アレルギー反応を起こしてしまうと気管が炎症して気管が狭くなってしまっている可能性が高いです。
そのままでは完全に空気の通り道が遮断されてしまい、呼吸をすることができなくなってしまいます。
そのような状態にならないためにも炎症を抑える抗炎症薬や気管を広げる効果がある気管支拡張薬が使用されます。
最初は多めに投与されますが、症状が緩和されていれば徐々に投与する量を減らしていく場合が一般的です。
まとめ
猫喘息は最悪命にも関わってくる病気でもあるため、軽視しないようにしましょう。
喘息のほとんどの原因がアレルギー物質によるアレルギー反応であるため、アレルギー物質を体内に入れないようにすることができれば喘息の症状も収まってきます。
まずは喘息の原因を解明して原因から遠ざけることが大切です。
喘息の症状は体力が消耗しやすいので、高齢になればなるほど体力が消耗しきってしまい、重症化してしまうリスクも高まってしまいやすいので注意が必要です。
猫が腕枕をしたがる5つの理由
 腕枕をしてもらいスヤスヤ気持ち良さそうに寝ている猫を、テレビや動画などでよく見かけます。
喉をゴロゴロ鳴らしながら腕にギュッと抱き着く様子は、とても愛おしく癒されます。
そんな猫の腕枕をしたがる5つの理由を紹介します。
腕枕をしてもらいスヤスヤ気持ち良さそうに寝ている猫を、テレビや動画などでよく見かけます。
喉をゴロゴロ鳴らしながら腕にギュッと抱き着く様子は、とても愛おしく癒されます。
そんな猫の腕枕をしたがる5つの理由を紹介します。
理由①:ここは自分の縄張りだとを主張している
猫は縄張りのマーキングをする際に、体を柱や人の足に擦りつける事があります。
飼い主さんにも同様に、額や顎の下にある臭腺から匂いを出して擦りつけ縄張りをアピールします。
腕枕をする事で飼い主さんにマーキングをし、「この人は自分のものだよ」と親愛の気持ちを伝えています。
飼い主さんと一緒の布団で寝る事で、ここは自分の縄張りであると主張しているのです。
理由②:腕の中が暖かい
 布団で一緒に眠る際に猫が腕枕を求めてくるのは、飼い主さんの腕の中がとても暖かいことを知っているからです。
猫にとって飼い主の腕の中はとても安心でき、くっついて一緒に眠ればおたがいの温もりを感じ合える事を知っています。
ふわふわ暖かい服を着ていれば猫にとっても心地が良く、寒い時期は特に腕枕をしたがります。
飼い主にとっても愛猫が安心して眠る姿には癒され、信頼されている実感がわきます。
布団で一緒に眠る際に猫が腕枕を求めてくるのは、飼い主さんの腕の中がとても暖かいことを知っているからです。
猫にとって飼い主の腕の中はとても安心でき、くっついて一緒に眠ればおたがいの温もりを感じ合える事を知っています。
ふわふわ暖かい服を着ていれば猫にとっても心地が良く、寒い時期は特に腕枕をしたがります。
飼い主にとっても愛猫が安心して眠る姿には癒され、信頼されている実感がわきます。
理由③:飼い主が大好きだから
猫は好き嫌いがはっきりしていて警戒心が強い動物で、嫌いなものや信頼できないものには決してつかずこうとはしません。
飼い主さんの腕枕で毎晩のように眠る猫は、強い愛情を飼い主さんに向けています。
腕枕の位置が顔に近い程猫の親愛の気持ちは強く、愛情と同時に深い信頼を寄せていると言えるでしょう。
猫なりに飼い主の傍にいれば、安心して眠れる事を感じ取っているのかもしれません。
理由④:母親の愛情を求めている
 毎日身の回りの世話をしてくれている飼い主さんは、猫にとってほとんど母親と同じような存在です。
飼い主さんから愛情をもらいたい時に、母親に甘えるように腕枕で眠る時があります。
腕枕をしてもらう事で一番安心でき、喉をゴロゴロ鳴らすのはリラックスをして嬉しいサインでもあります。
猫にとって腕枕は母親に愛情を求める愛情表現でもあります。
毎日身の回りの世話をしてくれている飼い主さんは、猫にとってほとんど母親と同じような存在です。
飼い主さんから愛情をもらいたい時に、母親に甘えるように腕枕で眠る時があります。
腕枕をしてもらう事で一番安心でき、喉をゴロゴロ鳴らすのはリラックスをして嬉しいサインでもあります。
猫にとって腕枕は母親に愛情を求める愛情表現でもあります。
理由⑤:安心感を抱いているから
普段から面倒を見てくれ可愛がってくれる飼い主さんに、猫は安心感を抱いています。
飼い主さんの声や足音などを聞き分けるように、猫は眠っていても外敵と思われるものには常に警戒しています。
腕の中で安心して眠っているようでも、いつもと違う音などには敏感に反応し様子を確認する場合もあります。
猫が熟睡し心地よさそうに眠る姿は、飼い主さんに対して安心感を抱いていない限り見られない行為です。
猫に腕枕をしたい時の方法
 全ての猫が腕枕が好きだとは限らず、飼い主さんの中には腕枕をしたくてもできない人もいます。
腕枕が嫌いな猫には過去に嫌な思い出があったり、ひとりで眠るのが好きな場合があります。
どうしても猫に腕枕をしたい方の為に方法を幾つか紹介します。
全ての猫が腕枕が好きだとは限らず、飼い主さんの中には腕枕をしたくてもできない人もいます。
腕枕が嫌いな猫には過去に嫌な思い出があったり、ひとりで眠るのが好きな場合があります。
どうしても猫に腕枕をしたい方の為に方法を幾つか紹介します。
寒い時期が狙い時
猫は寒さに弱く温もりを感じられる場所を好みますので、寒い季節になればそっと寄り添って眠ってくれる事もあります。
寒い時期は猫が布団の近くまで寄ってきやすくなりますので、猫が入りやすいように布団を開けておくと興味を示してくれる場合があります。
布団の中でじっと動かずに安全な場所だと分れば、自然と布団の中で寝てくれるようになります。
飼い主さんとくっついて眠る事が心地いいと感じられれば、いつかは腕枕をしてくれるかもしれません。
時間の経過を待つ
 猫は強制されるのを嫌いますので、腕枕をさせてくれるまで時間がかかる場合があります。
性格次第で腕枕を嫌がる猫もいますので、無理矢理抱いたりせずにのんびりと構えて待つ事も大切です。
猫が腕枕をしてくれるのは、飼い主さんとの信頼関係があってこそです。
早く腕枕がしたくて焦ってしまう飼い主さんもいると思いますが、一度失敗してしまうと余計時間がかかってしまう事もありますので注意が必要です。
猫は強制されるのを嫌いますので、腕枕をさせてくれるまで時間がかかる場合があります。
性格次第で腕枕を嫌がる猫もいますので、無理矢理抱いたりせずにのんびりと構えて待つ事も大切です。
猫が腕枕をしてくれるのは、飼い主さんとの信頼関係があってこそです。
早く腕枕がしたくて焦ってしまう飼い主さんもいると思いますが、一度失敗してしまうと余計時間がかかってしまう事もありますので注意が必要です。
一緒の部屋で眠る
別の部屋で寝ている場合は、おたがいの様子がわからず腕枕をするチャンスを逃してしまう事があります。
猫は警戒心がとても強い動物ですが、一緒の部屋で寝ていれば飼い主さんとの距離を縮めやすいと言われています。
飼い主さんがすやすや眠っていると傍に行きやすく、自分の思い通りに眠れるのが心地いいようです。
慣れてくると同じ時間帯にやって来て、自分のお気に入りの場所で毛づくろいをし飼い主さんの腕枕で寝るようになります。
猫の腕枕を外したい時のコツ
 猫は飼い主さんの腕枕に慣れてくると気を許して、長い時間眠り続ける事があります。
気持ち良さそうに寝ている猫を見てるだけで癒されますが、腕が疲れて腕枕を外したい時もあります。
そんな時の腕枕を外す方法を紹介します。
猫は飼い主さんの腕枕に慣れてくると気を許して、長い時間眠り続ける事があります。
気持ち良さそうに寝ている猫を見てるだけで癒されますが、腕が疲れて腕枕を外したい時もあります。
そんな時の腕枕を外す方法を紹介します。
腕枕から本物の枕にすり替える
小さな猫でも長い時間腕枕をしていると筋肉痛になるほどの重さを感じ、爆睡していても起きてしまう事があります。
腕枕をする場所はだいたい決まっていると思いますので、近くに猫用の枕を用意しておくようにします。
猫が気持ち良さそうに眠っている隙に、腕枕から本物の枕すり替えることも可能です。
頭の高さが変わらなければ腕枕を外された事に気づかず、安心してまた気持ち良さそうに眠ってくれます。
撫でながらそっと腕を抜く
 猫の背中や頭を撫でながら、気持ち良さそうにゴロゴロと喉を鳴らしている隙にそっと腕を抜く方法もあります。
この方法は高確率で猫を起こさずに腕枕を外す事ができ、猫は飼い主さんから撫でてもらっている事で気持ちが良く飼い主さんも腕のしびれから解放されます。
腕枕を外した後もそのまま優しく撫でてあげると、安心して眠り続けるようです。
猫の背中や頭を撫でながら、気持ち良さそうにゴロゴロと喉を鳴らしている隙にそっと腕を抜く方法もあります。
この方法は高確率で猫を起こさずに腕枕を外す事ができ、猫は飼い主さんから撫でてもらっている事で気持ちが良く飼い主さんも腕のしびれから解放されます。
腕枕を外した後もそのまま優しく撫でてあげると、安心して眠り続けるようです。
優しく声をかけて静かに外す
猫は飼い主さんの声に敏感に反応しますので、腕を動かして外す前に穏やかな声で「ごめんね」と声をかけるようにします。
そうする事で猫を驚かさずに済み、難なく腕を外すことが可能です。
急に腕枕を外してしまうと、気持ち良さそうに寝ていたのに睡眠を妨害してしまう事になります。
猫の睡眠を邪魔しないようにする為にも、腕を外す時は優しく声をかけてゆっくりしてあげるようにします。
まとめ
ほとんどの猫は飼い主さんの腕枕が心地よく、安心して眠れるようです。
猫にも人間と同じように性格があり、飼い主が嫌いなわけではないけれど腕枕が無理という場合もあります。
飼い主にとって腕枕ができないのは少々悲しい事ですが、焦らずに時間をかけて待ってあげる事も大切です。
どうしても駄目な時には、他の方法でコミュニケーションをとりながら信頼関係深めていく方法もあります。
猫と一緒にいる時間が長く成る程家族のような存在になり、姿が見えなかったり様子が違うだけで心配になってしまいます。
猫が心を許して飼い主の腕枕でスヤスヤ眠る姿は、とても可愛らしく癒され時間を忘れてしまいそうになりますね!
猫の老衰の6つのサインとは?
 猫が老衰した際のサインが6つあることを知っているでしょうか。
サインを確認することで猫が弱っていることを知ることができ、高齢の猫にしたほうがよいさまざまな対策を講じることもできます。
次に、猫が老衰した際のサインをいくつか紹介するので参考にしてください。
猫が老衰した際のサインが6つあることを知っているでしょうか。
サインを確認することで猫が弱っていることを知ることができ、高齢の猫にしたほうがよいさまざまな対策を講じることもできます。
次に、猫が老衰した際のサインをいくつか紹介するので参考にしてください。
サイン①:寝ている時間が長くなる
老衰してしまうと寝ている時間が長くなりやすい特徴があります。
元々猫は他の動物と比べても寝ている時間が長い生き物であるため、老衰して寝ている時間が長くなっても気づかない場合も多いです。
猫が活動する時間帯は朝か夕方が一般的です。
それ以外の時間帯は寝ている場合が多いですが、老衰するとより寝ている時間が長くなり、逆に活動する時間が減ります。
そのため、甘えてくる頻度や遊ぶ時間も減ってきますが、無理に遊んだりすると嫌がる場合も多いのでそっとしておくようにしましょう。
サイン②:食欲が低下して痩せる
 老衰すると食欲が低下してしまいます。
老衰のサインとしては早い段階であらわれる異変であるため、飼い主も気づきやすく、同じ量の餌を与えても残す場合が多くなってしまいます。
食欲が低下してしまう原因は活動する時間が減るためであり、必然的にお腹も減りにくくなってしまいます。
食欲が減れば十分なエネルギーを得ることができないため、思うように体が動かしにくくなり、そのせいで食欲も湧かず、負の連鎖に陥ってしまいます。
また、食事から栄養を摂取する量が減ることで痩せてしまうことが多くなります。
老衰すると食欲が低下してしまいます。
老衰のサインとしては早い段階であらわれる異変であるため、飼い主も気づきやすく、同じ量の餌を与えても残す場合が多くなってしまいます。
食欲が低下してしまう原因は活動する時間が減るためであり、必然的にお腹も減りにくくなってしまいます。
食欲が減れば十分なエネルギーを得ることができないため、思うように体が動かしにくくなり、そのせいで食欲も湧かず、負の連鎖に陥ってしまいます。
また、食事から栄養を摂取する量が減ることで痩せてしまうことが多くなります。
サイン③:歯が抜ける歯周病の症状
歯周病の影響で抜けてしまったり、色が黄ばんでくるなどの変化も老衰するとあらわれやすいです。
あまり知られていないサインではありますが、猫の歯の状況を確認することである程度年齢を知ることができる部分でもあります。
歯周病が悪化すれば歯が削がれ、最終的に歯が抜けていきます。
しかし、猫は元々咀嚼する習慣がない動物であるため、飼われている猫であれば歯がなくても物を食べることは可能です。
食べにくさを感じているようであればお湯などでフードを柔らかくしてあげましょう。
サイン④:毛艶や毛並みが悪くなる
 毛艶や毛並みが悪くことも老衰のサインの一つです。
被毛はさまざまな栄養素やタンパク質で正常な状態を維持することができ、艶が出たり毛並みもよくなります。
しかし、上記でも紹介したように老衰すると食欲が低下してしまうのでタンパク質やそのほかの栄養素も不足してしまいがちです。
その結果老衰すると毛並みなどが悪くなります。
さらに痩せてしまうことでさらに見た目が悪くなってしまいますが、改善することは難しく、余計な手を猫に加えてしまうと余計に体力を奪う原因となってしまいます。
毛艶や毛並みが悪くことも老衰のサインの一つです。
被毛はさまざまな栄養素やタンパク質で正常な状態を維持することができ、艶が出たり毛並みもよくなります。
しかし、上記でも紹介したように老衰すると食欲が低下してしまうのでタンパク質やそのほかの栄養素も不足してしまいがちです。
その結果老衰すると毛並みなどが悪くなります。
さらに痩せてしまうことでさらに見た目が悪くなってしまいますが、改善することは難しく、余計な手を猫に加えてしまうと余計に体力を奪う原因となってしまいます。
サイン⑤:運動能力が低下する
猫は歳をとると運動機能が低下してしまいます。
若い猫であれば活発に動く場合も多く、ジャンプ力も高いです。
しかし、高齢になると筋力が低下してしまい、思うように運動することができなくなります。
運動量が減ることでさらに筋力が減ってしまう原因となるため、老衰する前からできるだけ遊んだりして筋力低下を防いでおくことも大切です。
また、高齢になれば関節痛になることも多く、関節の痛みが原因で運動することが少なくなり、筋力が低下してしまうこともあります。
サイン⑥:夜鳴きや粗相が増える
 老衰すると夜泣きが酷くなったり、粗相が増える場合があります。
このような異常な行動をしてしまう原因は老衰による脳機能の低下であり、認知症になっているからです。
猫も人と同じように高齢になればなるほど認知症になるリスクが高まり、猫の場合はトイレの位置がわからなくなり、さまざまな場所で排泄してしまったり、夜中に突然大きな声で鳴くようにもなります。
認知症は治すことができない病気でもありますが、動物病院の先生に相談して正しい対処方法を身に付けるようにしましょう。
老衰すると夜泣きが酷くなったり、粗相が増える場合があります。
このような異常な行動をしてしまう原因は老衰による脳機能の低下であり、認知症になっているからです。
猫も人と同じように高齢になればなるほど認知症になるリスクが高まり、猫の場合はトイレの位置がわからなくなり、さまざまな場所で排泄してしまったり、夜中に突然大きな声で鳴くようにもなります。
認知症は治すことができない病気でもありますが、動物病院の先生に相談して正しい対処方法を身に付けるようにしましょう。
猫が老衰時にかかりやすい病気
 老衰することで異常な行動をするようになるだけではなく、さまざまな病気を誘発させてしまう原因にもなります。
なかには命にも関わる病気も含まれているため、飼い主であれば知っておいて損をすることはありません。
病気になってしまった際に大切なことは早期発見・早期治療が原則であるため、老衰しているサインを見かけるようになったのであればより一層猫の体調チェックをするようにしましょう。
次に、老衰することでなりやすい病気について紹介するので参考にして下さい。
老衰することで異常な行動をするようになるだけではなく、さまざまな病気を誘発させてしまう原因にもなります。
なかには命にも関わる病気も含まれているため、飼い主であれば知っておいて損をすることはありません。
病気になってしまった際に大切なことは早期発見・早期治療が原則であるため、老衰しているサインを見かけるようになったのであればより一層猫の体調チェックをするようにしましょう。
次に、老衰することでなりやすい病気について紹介するので参考にして下さい。
尿と関係のある病気
老衰すると尿に関する病気になる可能性があります。
猫は一定の年齢になると尿に関する病気になる割合が高く、病気で亡くなる猫の2割程度が尿の病気が原因であるとも言われています。
尿は元々毒素を体外に排出する行為であるため、尿を全くしていないと毒素が体内に渡ってしまい、急死してしまうことも少なくありません。
また、水分を全くとらない場合も尿関係の病気である可能性が高いです。
そのため、尿をしっかりしているかや水分をとっているかなどを確認するとともに、尿の量や色なども把握しましょう。
少しでも異変があるのであれば動物病院で診てもらいましょう。
完全室内飼いであれば尿のチェックもしやすいですが、放し飼いにしてしまっている場合はいつ尿をしているか把握することができないので、老衰してしまった猫は室内飼いにしておくことをおすすめします。
ガンになる猫が増えている
 猫の病気での死亡率の中でも最も高いのがガンであり、約4割の猫がガンで亡くなっているとも言われています。
現代社会では人も寿命が延びていますが、猫も同様に長生きするようになっています。
長く生きることになったことでガン細胞ができやすくなったとも言われ、さまざまなガンになるリスクが高まっていることがガンでの死亡率が高まっている原因です。
ガンの場合は急死してしまうことは少なく、治療を継続するようになることも珍しくありません。
その結果猫と少しでも長く共に生きることができますが、介護をしなければならないため、飼い主には介護の仕方などを身に付ける必要があります。
また、猫の医療のレベルも高まったことも猫が長生きできるようになった理由でもあります。
猫の病気での死亡率の中でも最も高いのがガンであり、約4割の猫がガンで亡くなっているとも言われています。
現代社会では人も寿命が延びていますが、猫も同様に長生きするようになっています。
長く生きることになったことでガン細胞ができやすくなったとも言われ、さまざまなガンになるリスクが高まっていることがガンでの死亡率が高まっている原因です。
ガンの場合は急死してしまうことは少なく、治療を継続するようになることも珍しくありません。
その結果猫と少しでも長く共に生きることができますが、介護をしなければならないため、飼い主には介護の仕方などを身に付ける必要があります。
また、猫の医療のレベルも高まったことも猫が長生きできるようになった理由でもあります。
猫の老衰時の最期にできること
 老衰してしまった猫に何ができるのか悩んでしまった経験がある人も多いのではないでしょうか。
老衰になるとどうしても最期の時が違うこともあるため、より一層最後にできることを考えやすいです。
次に、老衰した猫にしてあげることを紹介するので参考にしてください。
老衰してしまった猫に何ができるのか悩んでしまった経験がある人も多いのではないでしょうか。
老衰になるとどうしても最期の時が違うこともあるため、より一層最後にできることを考えやすいです。
次に、老衰した猫にしてあげることを紹介するので参考にしてください。
ポジティブな言葉をかける
老衰して最期の時期がわかればポジティブな言葉をかけてあげましょう。
「大好きだよ」や「ありがとう」などの言葉をかけることで猫も安心しやすいです。
猫が心配してしまうような言葉をかけてしまうことも多いですが、最後なので不安や寂しい気持ちは我慢して笑顔で声をかけるようにしましょう。
猫の状態によってはうまく視認することができなかったり、声を聞き取ることができない場合もありますが、そばにいるだけで雰囲気を察してくれるいる場合もあり、撫でてあげるだけでも猫は安心して旅立つことができます。
最期は猫が好む場所で迎えさせる
 猫の死に目に会うことが難しいことを知っているでしょうか。
例え飼い猫であったとしても老衰してしまい、最期が近くなると知らない間にどこかに行ってしまい、そのまま会うことがないことも珍しいことではありません。
猫は弱ると誰の目にも触れない場所に隠れる習慣があり、飼い猫でも変わりません。
そのため、老衰した猫がどこかにいってしまったのであればそのまま一匹で逝かせてあげることも一つの方法と言えます。
しかし、見送る側からすれば寂しい別れ方でもあります。
猫の死に目に会うことが難しいことを知っているでしょうか。
例え飼い猫であったとしても老衰してしまい、最期が近くなると知らない間にどこかに行ってしまい、そのまま会うことがないことも珍しいことではありません。
猫は弱ると誰の目にも触れない場所に隠れる習慣があり、飼い猫でも変わりません。
そのため、老衰した猫がどこかにいってしまったのであればそのまま一匹で逝かせてあげることも一つの方法と言えます。
しかし、見送る側からすれば寂しい別れ方でもあります。
最期は苦しむ場合もあると理解する
理想の最期は苦しむことなく、眠るように逝くことですが、中々そのような亡くなり方をしないことが多いです。
そのため、猫の最期が苦しむ可能性もあることも考慮しておきましょう。
飼い主からすれば猫が苦しんでしまうことは望んではいませんが、どうすることもできないのが現実であり、見守ることしかできません。
特に、体力が低下する老衰が原因ではなく、病気などが死因であればより苦しんでしまうリスクが高く、飼い主が覚悟しておかなければいざ死期が近づいた際に冷静な行動をとることができません。
猫の老衰の予防法はある?
 猫の老衰を予防することができるのか知りたい人もいるのではないでしょうか。
老衰してしまうことは猫に限らず生物であれば避けて通ることができない道ではありますが、少しの異常に早く気づくことができれば、長生きすることもあります。
次に、老衰することに対する予防方法を紹介します。
猫の老衰を予防することができるのか知りたい人もいるのではないでしょうか。
老衰してしまうことは猫に限らず生物であれば避けて通ることができない道ではありますが、少しの異常に早く気づくことができれば、長生きすることもあります。
次に、老衰することに対する予防方法を紹介します。
少しの違和感も見過ごさない
少しの違和感を感じたのであればすぐに動物病院に連れて行くようにしましょう。
特に老衰してしまっているときは小さなことでも命に関わってしまう可能性も高く、異常を見逃さないようにしましょう。
猫の異常を知るためには正常なことを知っておく必要があるため、元気な時はどのような行動をしているのか把握しておきましょう。
食事の量や排泄する頻度や量などがわかりやすく、皮膚などのチェックも忘れないようにしましょう。
普段から猫とコミュニケーションをとることで異常にも気が付くようになります。
健康診断を半年に1回受ける
 人も健康体を維持するために定期検診を受けますが、猫も健康診断を受けることをおすすめします。
若くてもどんな病気が潜んでいるのかわからないため、1歳から毎年1回は健康診断するようにしましょう。
しかし、高齢になればなるほど体に異常が起きてしまうリスクが高まるため、7歳以上から毎年2回健康診断を受けることをおすすめします。
飼い主にとっては健康診断の頻度を増やすことは経済的に苦しくなったり、面倒と感じてしまう場合もありますが、大きな病気を見逃してしまった際と比べれば負担は少ないです。
人も健康体を維持するために定期検診を受けますが、猫も健康診断を受けることをおすすめします。
若くてもどんな病気が潜んでいるのかわからないため、1歳から毎年1回は健康診断するようにしましょう。
しかし、高齢になればなるほど体に異常が起きてしまうリスクが高まるため、7歳以上から毎年2回健康診断を受けることをおすすめします。
飼い主にとっては健康診断の頻度を増やすことは経済的に苦しくなったり、面倒と感じてしまう場合もありますが、大きな病気を見逃してしまった際と比べれば負担は少ないです。
まとめ
猫が老衰してしまうとさまざまな異常が起きてしまい、普段と同じように生活できない場合が多くなってきます。
特に飼い主への負担が大きくなり、老衰した場合の接し方をしなければなりません。
老衰してしまった猫はいずれは最期の時を迎えるため、どのようなお別れをするのかを確認しておくようにしましょう。
長年一緒に生活していたのであれば最後にいいお別れができるように老衰に対する正しい知識や接し方を身に付けるようにしましょう。
猫の歴史:猫の起源を辿る
 猫は約9500年前から人間のパートナーとして、扱われていたと考えられています。
砂漠地帯に生息しているリビアヤマネコが猫の起源だとすると、エジプトからヨーロッパ、アジアへと広がり中国から日本にやって来たと考えるのが自然かもしれません。
猫がネズミを追いかけたり小さくて素早く動くものを捕らえようとする習性は、リビアヤマネコが小鳥やネズミなどの小動物を獲物にしていたからだと思われます。
現代で猫がペットとして人間と一緒に暮らすようになった過程には、どのような歴史があるのかを調べてみました。
猫は約9500年前から人間のパートナーとして、扱われていたと考えられています。
砂漠地帯に生息しているリビアヤマネコが猫の起源だとすると、エジプトからヨーロッパ、アジアへと広がり中国から日本にやって来たと考えるのが自然かもしれません。
猫がネズミを追いかけたり小さくて素早く動くものを捕らえようとする習性は、リビアヤマネコが小鳥やネズミなどの小動物を獲物にしていたからだと思われます。
現代で猫がペットとして人間と一緒に暮らすようになった過程には、どのような歴史があるのかを調べてみました。
猫(イエネコ)の起源はリビアヤマネコ
動物分類学で猫は「イエネコ」と呼ばれていて、哺乳類、食肉目、ネコ科、ネコ属に分類されリビアヤマネコが家畜化されたものです。
猫(イエネコ)の先祖となる「リビアヤマネコ」の生息地はサバンナや砂漠といった乾燥した暑い地域の為、子孫である猫が寒さや水を苦手としている理由が分かります。
リビアヤマネコの大きさは体長は50〜60㎝、尻尾の長さが20〜40㎝、体重は5㎏程度になり、色は砂漠で同化しそうな色合いで柄なども相対的に見えるキジトラに似ています。
現代飼われている猫には大きさの異なる猫もいますが、多くの猫がリビアヤマネコと同じくらいの体格をしています。
世界中に様々な種類の猫が存在しますが、全てはリビアヤマネコが起源で生活環境や歴史の中で変化をしたのかもしれません。
リビアヤマネコは人懐っこい
 猫(イエネコ)とリビアヤマネコの共通点は性格にも見られ、ネコ科の動物の中でも人懐っこい所が特徴です。
リビアヤマネコは比較的警戒心が薄く子猫の頃から人間に育てられると家族のような関係になれますが、ペットとして流通できる種類の猫ではなく飼うには無理があります。
海外の一部の動物園でリビアヤマネコを展示している所もあるようですが、残念ながら日本では見る事のできない猫です。
猫の祖先であるリビアヤマネコを実際に見たり飼うチャンスはありませんが、現代に存在している猫から想像できるのではないでしょうか?
猫(イエネコ)とリビアヤマネコの共通点は性格にも見られ、ネコ科の動物の中でも人懐っこい所が特徴です。
リビアヤマネコは比較的警戒心が薄く子猫の頃から人間に育てられると家族のような関係になれますが、ペットとして流通できる種類の猫ではなく飼うには無理があります。
海外の一部の動物園でリビアヤマネコを展示している所もあるようですが、残念ながら日本では見る事のできない猫です。
猫の祖先であるリビアヤマネコを実際に見たり飼うチャンスはありませんが、現代に存在している猫から想像できるのではないでしょうか?
猫の歴史:人が猫を飼い始めた理由
 海外と日本には、猫がネズミ捕りとして活躍してきた歴史があります。
世界中で可愛がられ人間の近くで生活を共にするようになったのは、愛らしい見た目や人懐こい性格の他にネズミによる被害を防ぐ為に飼いはじめたのが理由のひとつです。
ネズミは伝染病を媒介したり穀物を荒らしてしまう為、猫が捕らえる事で感染拡大の予防につながり人間の大切な食料を守ってくれます。
人間に危害を加えない点がどの国でも重宝され、ネコを飼いはじめた理由にあげられます。
海外と日本には、猫がネズミ捕りとして活躍してきた歴史があります。
世界中で可愛がられ人間の近くで生活を共にするようになったのは、愛らしい見た目や人懐こい性格の他にネズミによる被害を防ぐ為に飼いはじめたのが理由のひとつです。
ネズミは伝染病を媒介したり穀物を荒らしてしまう為、猫が捕らえる事で感染拡大の予防につながり人間の大切な食料を守ってくれます。
人間に危害を加えない点がどの国でも重宝され、ネコを飼いはじめた理由にあげられます。
エジプトで行われた猫の家畜化
紀元前4000~5000年頃のエジプトで猫は特異な地位を占めていて、猛毒を持つヘビ(コブラ)やネズミなどの害獣駆除を行う為に家畜化し始めたと言われています。
当時のエジプトにはジャングルキャットやリビアヤマネコがいましたが、ジャングルキャットは野性味が強く人間には懐かなかったようです。
リビアヤマネコは当時の人々の忍耐力と、リビアヤマネコの内部にある気質的な突然変異によって性格が温和化され家畜化が実現しました。
猫は王族の間ではペットとしても寵愛され、当時のエジプトの富裕層の間ではヒヒ、ライオン、ガゼルなどの野生動物を飼いならすのが一種のファッションだったようです。
中世ヨーロッパで迫害・飼育された猫
 7世紀にキリスト教が異端とみなしたグリーシス派を「黒猫に姿を変えた悪魔と手を組んでいる」と非難した事から猫が迫害されるようになります。
中世ヨーロッパの魔女裁判によって、猫は「魔女の手先」と疑われ大量虐殺が始まってしまいます。
しかし猫がいなくなった事でペストが大流行してしまい、その原因となるネズミを追い払うためヨーロッパの人々は迫害をやめて再び猫を飼育するようになります。
7世紀にキリスト教が異端とみなしたグリーシス派を「黒猫に姿を変えた悪魔と手を組んでいる」と非難した事から猫が迫害されるようになります。
中世ヨーロッパの魔女裁判によって、猫は「魔女の手先」と疑われ大量虐殺が始まってしまいます。
しかし猫がいなくなった事でペストが大流行してしまい、その原因となるネズミを追い払うためヨーロッパの人々は迫害をやめて再び猫を飼育するようになります。
猫の歴史:日本人と猫が歩んできた道
 日本では約2000年前の弥生時代から猫がいた形跡が残っていて、平安時代には宇多天皇の日記「寛平御記」に登場し古くから愛されていました。
ネズミを獲物とする猫は穀物の倉庫番として重宝され、人間と一緒に暮らす事によって双方に利益が生まれます。
猫は人間の傍にいれば水や食べ物がもらえて、天敵からも守られ安全に暮らせるようになります。
人間はネズミの害から救ってくれた猫を、富や豊かさの象徴や守り神としても親しむようになります。
日本では約2000年前の弥生時代から猫がいた形跡が残っていて、平安時代には宇多天皇の日記「寛平御記」に登場し古くから愛されていました。
ネズミを獲物とする猫は穀物の倉庫番として重宝され、人間と一緒に暮らす事によって双方に利益が生まれます。
猫は人間の傍にいれば水や食べ物がもらえて、天敵からも守られ安全に暮らせるようになります。
人間はネズミの害から救ってくれた猫を、富や豊かさの象徴や守り神としても親しむようになります。
弥生時代の日本人と猫
長崎県の離島にある壱岐島のカラカミ遺跡から猫らしい骨が見つかり、弥生時代に猫が存在していた事がわかりました。
大陸から稲作農耕が伝わった時に、ネズミから農作物を守る存在として伝来した説が濃厚のようです。
古代日本では愛玩目的で猫を飼育するというより、貯蔵していた穀物を昆虫やネズミから守るために猫を側に置いていたようです。
平安時代の日本人と猫
 平安時代になると、ようやく猫は現在のように愛玩動物として飼われるようになりました。
しかし貴重な存在だったため高貴な身分の限られた人物のみにしか飼育は許されず、貴族の間では猫を飼う事が密かに流行っていたようです。
887年に天皇に即位した宇多天皇は猫好きで知られていて、父親から譲り受けた黒猫を可愛がっていました。
「寛平御記」に綴られている猫の様子はよく観察されていて、現代の猫ブログのルーツになるかもしれません。
一条天皇も猫好きで知られていて、猫の誕生日を祝う儀式や飼っていた猫に階位を与えたという話もあります。
平安時代になると、ようやく猫は現在のように愛玩動物として飼われるようになりました。
しかし貴重な存在だったため高貴な身分の限られた人物のみにしか飼育は許されず、貴族の間では猫を飼う事が密かに流行っていたようです。
887年に天皇に即位した宇多天皇は猫好きで知られていて、父親から譲り受けた黒猫を可愛がっていました。
「寛平御記」に綴られている猫の様子はよく観察されていて、現代の猫ブログのルーツになるかもしれません。
一条天皇も猫好きで知られていて、猫の誕生日を祝う儀式や飼っていた猫に階位を与えたという話もあります。
安土桃山時代〜江戸時代の日本人と猫
江戸時代初期までは猫の数が増える事はなく存在は貴重で、少ない猫の代わりにネズミ駆除する力があるとして猫の絵が重宝されていてという史実もあります。
ネズミの害を減らすために猫を放し飼いするよう命令が出され、ネズミの害は激減し中々の効果が見られたようです。
縁起物の招き猫が生み出され猫は守り神としても人々に親しまれるようになり、庶民の間でもネズミを駆除するために猫を飼育する習慣が広がりました。
人間よりも小さく力のない猫が、ネズミを捕らえてくれる事で人々の生活を支えてくれていた事がわかります。
現代ではペットとして当たり前のように飼われていますが、昔は貴重な存在だったと実感させられました。
江戸時代〜現代の日本人と猫
 江戸時代後期には歌舞伎や浮世絵などのモチーフとして使われ、「猫ブーム」旋風が巻き起こっていました。
歌川国芳は江戸時代末期に活躍し、猫にまつわる浮世絵を数多く残した浮世絵師で愛猫家でも知られています。
明治には竹久夢二の美人画に描かれた猫が有名で、文芸作品でも猫が登場するものが多く見られ代表的なものには夏目漱石の「吾輩は猫である」があります。
世界でも、日本でも猫はいくつもの芸術のモチーフとされ、現在も多くの人々に愛され続け経済にも影響を与えるほどです。
第二次世界大戦が終わり庶民の生活にもゆとりがでてくると、猫を家族として飼う家庭も増えました。
猫の人気は年を追うごとに高まっていて、飼われている数も増え続けています。
江戸時代後期には歌舞伎や浮世絵などのモチーフとして使われ、「猫ブーム」旋風が巻き起こっていました。
歌川国芳は江戸時代末期に活躍し、猫にまつわる浮世絵を数多く残した浮世絵師で愛猫家でも知られています。
明治には竹久夢二の美人画に描かれた猫が有名で、文芸作品でも猫が登場するものが多く見られ代表的なものには夏目漱石の「吾輩は猫である」があります。
世界でも、日本でも猫はいくつもの芸術のモチーフとされ、現在も多くの人々に愛され続け経済にも影響を与えるほどです。
第二次世界大戦が終わり庶民の生活にもゆとりがでてくると、猫を家族として飼う家庭も増えました。
猫の人気は年を追うごとに高まっていて、飼われている数も増え続けています。
まとめ
猫の祖先はリビアヤマネコで、当時の人々の忍耐力で家畜化され人懐っこい性格や習性が引き継がれています。
人間に歴史があるように猫にもあり、尊い存在であることを実感させられました。
現代ではペットとして簡単に飼う事が可能ですが、昔は貴重で限られた人しか飼う事のできない存在でした。
捨て猫や飼育放棄など悲しいニュースもありますが、長い間人間の生活を支えてくれた猫に感謝する気持ちを忘れずにいたいものですね!
猫が落下しても平気な理由
 猫が高い場所から落ちても怪我をしない理由を知っているでしょうか。
人はもちろん他の動物では大けがをしたり、命を落としてしまうような高さから落ちてもほぼ怪我をすることがない猫ですが、その理由について次に紹介するので参考にしてください。
猫が高い場所から落ちても怪我をしない理由を知っているでしょうか。
人はもちろん他の動物では大けがをしたり、命を落としてしまうような高さから落ちてもほぼ怪我をすることがない猫ですが、その理由について次に紹介するので参考にしてください。
優れた運動神経とバランス感覚があるから
猫は平衡感覚に優れている動物であり、背中から落下していてもうまく体を操って足から着地することができるような体勢になります。
また、足をムササビのように広げて少しでも落下速度を緩めるような行動をしています。
落下している最中に体を半回転することは人では難しいですが、猫の場合は腹膜内にある内臓が移動することができる構造になっていることで、容易に体をひねることが可能になっています。
さらに両手足の裏には柔らかい肉球があるため、着地時の衝撃を吸収し、関節も柔らかいので、同じく着地時の衝撃を緩和することも可能です。
落ちても平気な高さがある
 猫は高い場所から落下しても上記で紹介した理由から怪我をすることがなく、簡単に着地することができます。
しかし、いくら猫でも耐えることができない高さが存在しており、6~7m程度の高さであれば問題ないと言われ、建物でいうと2階くらいの高さです。
猫も落下した際に耐えられる高さを本能的に把握しているため、無謀に飛び降りて怪我をしてしまうことはありません。
ただし、猫の運動能力の差や体重の違いによって耐えられる高さも変わってくるため、肥満体質であり、運動不足の猫では2階の高さから落ちても怪我をしてしまう可能性があります。
猫は高い場所から落下しても上記で紹介した理由から怪我をすることがなく、簡単に着地することができます。
しかし、いくら猫でも耐えることができない高さが存在しており、6~7m程度の高さであれば問題ないと言われ、建物でいうと2階くらいの高さです。
猫も落下した際に耐えられる高さを本能的に把握しているため、無謀に飛び降りて怪我をしてしまうことはありません。
ただし、猫の運動能力の差や体重の違いによって耐えられる高さも変わってくるため、肥満体質であり、運動不足の猫では2階の高さから落ちても怪我をしてしまう可能性があります。
高すぎる場所は逆に安全な可能性もある
上記では2階程度の高さであれば落下時の衝撃に耐えることができると紹介しましたが、場合によっては7~8階のようなより高い場所から落ちても安全な可能性もあります。
その理由は落下するまでの時間が長く、その間に着地姿勢を整えることができるからです。
しかし、あくまでも可能性であるため、当然怪我をしてしまう可能性も十分考えられます。
そもそも猫も本能的に7~8階の高さから飛び降りるような行動をしないため、現実的に起こりにくい状況と言えるでしょう。
猫が落下して怪我・死亡するケースもある
 猫は高い場所から落ちても無難に着地して怪我をしない印象を持たれやすいですが、条件がそろっていなければ怪我をしてしまったり、最悪死亡してしまうこともあります。
そのため、どのようなことで落下時に猫が怪我をしてしまうのかを把握しておくことをおすすめします。
猫は高い場所から落ちても無難に着地して怪我をしない印象を持たれやすいですが、条件がそろっていなければ怪我をしてしまったり、最悪死亡してしまうこともあります。
そのため、どのようなことで落下時に猫が怪我をしてしまうのかを把握しておくことをおすすめします。
建物の3階以上だと危険
建物の3階以上の高さから落下してしまった場合は怪我をしてしまったり、怪我をしてしまう可能性が高まります。
地面の状況などによっては怪我をしない場合もありますが、2階からの衝撃と比べるといくら衝撃を緩和できる柔らかい関節や肉球があっても耐えることができず、大怪我や命を落としてしまうことも充分考えられます。
そのため、面白半分で猫を高い場所から落とすような行為をしてはいけません。
3階以上の高さで猫と暮らしているのであれば落下しないような対策をしましょう。
滑ってしまった場合
 猫は本能的に落ちてはいけない高さを把握しているため、怪我をしてしまうような高さから自発的に飛び降りることはありません。
しかし、誤って滑ってしまい落ちてしまうことはあります。
猫は人と違って歩いている素材が滑りやすいのかそうではないのか判断することができないからです。
特にベランダの手すりは滑りやすい素材であり、表面がツルツルであるため、猫にとっては非常に滑りやすく、何かの対策を講じておくようにしましょう。
猫は本能的に落ちてはいけない高さを把握しているため、怪我をしてしまうような高さから自発的に飛び降りることはありません。
しかし、誤って滑ってしまい落ちてしまうことはあります。
猫は人と違って歩いている素材が滑りやすいのかそうではないのか判断することができないからです。
特にベランダの手すりは滑りやすい素材であり、表面がツルツルであるため、猫にとっては非常に滑りやすく、何かの対策を講じておくようにしましょう。
驚いてしまった場合
猫が何かの拍子に驚いてしまうと高い場所から落ちてしまうこともあります。
大きな物音や犬などの鳴き声でびっくりしてしまうこともあり、驚き慌ててしまうと普段冷静な時では普通にとることができる行動がとれなくなってしまい、着地の姿勢が悪く骨折してしまうことがあります。
犬などの鳴き声で驚いてしまうことはなかなか防ぎようがありませんが、生活をする上での物音はある程度小さくすることができたり、気を付けることも可能です。
元々猫はうるさい環境ではストレスを感じてしまうので、極力物音が出にくい環境づくりを心がけましょう。
運動不足だと着地に失敗することも
 運動不足では思うように体を動かすこともできなくなってしまい、体のキレも低下してしまいます。
そのような状態で高い場所から落ちてしまうと着地までに衝撃を緩和できる体勢をとることができず、着地失敗を招いてしまう原因となります。
そのため、運動不足の猫には運動をさせ肥満体質を解消させたり、高い場所に上ることができないような工夫をするようにしましょう。
また、運動不足では必然的に肥満体質になっている場合も多く、体重が重ければ着地時の衝撃も強くなってしまい、怪我の原因となります。
運動不足では思うように体を動かすこともできなくなってしまい、体のキレも低下してしまいます。
そのような状態で高い場所から落ちてしまうと着地までに衝撃を緩和できる体勢をとることができず、着地失敗を招いてしまう原因となります。
そのため、運動不足の猫には運動をさせ肥満体質を解消させたり、高い場所に上ることができないような工夫をするようにしましょう。
また、運動不足では必然的に肥満体質になっている場合も多く、体重が重ければ着地時の衝撃も強くなってしまい、怪我の原因となります。
猫の落下予防策は?
 猫も本能的に危険な高さであることがわかれば無謀に落ちるような行動をすることはありませんが、上記でも紹介したように不可抗力が原因で落ちてしまうことも充分考えられます。
次に、猫が高い場所から落下してしまうことを予防する方法を紹介します。
高層に住んでいる場合は参考にしてください。
猫も本能的に危険な高さであることがわかれば無謀に落ちるような行動をすることはありませんが、上記でも紹介したように不可抗力が原因で落ちてしまうことも充分考えられます。
次に、猫が高い場所から落下してしまうことを予防する方法を紹介します。
高層に住んでいる場合は参考にしてください。
窓の開けっぱなしはNG
窓の開けっぱなしは落下の原因になってしまうため、極力開けっ放しにはしないようにしましょう。
窓を開ける目的で換気や暑さ対策で行うこともありますが、網戸をするように心がけたり、窓を開けている際には目を離さないようにすることが大切です。
窓のサッシの部分は猫がつかまりやすく、間違って落下してしまう原因にもなります。
網戸をすれば落下防止になりますが、猫が爪を立ててしまい破いてしまうこともあり、網戸なしで開けっ放しにしてしまいやすいです。
しかし、網戸なしの窓の開放は一気に猫が落下してしまう可能性を高めてしまいます。
脱走防止柵の設置を行う
 脱走防止の柵を設置することで猫が部屋や家から出てしまうことを予防できます。
ちゃんと注意していれば猫が脱走してしまうことはないと考えてしまいやすいですが、いくら注意していても窓や玄関のドアを開けた隙に外に駆け出してしまうことも少なくありません。
窓などが開放されたと同時にジャンプして外に出ようとすることも多く、非常に危険な行動でもあります。
しかし、脱走防止柵を設置していれば不意に外に脱走されてしまうことがなくなり、猫を守ることができます。
脱走防止の柵を設置することで猫が部屋や家から出てしまうことを予防できます。
ちゃんと注意していれば猫が脱走してしまうことはないと考えてしまいやすいですが、いくら注意していても窓や玄関のドアを開けた隙に外に駆け出してしまうことも少なくありません。
窓などが開放されたと同時にジャンプして外に出ようとすることも多く、非常に危険な行動でもあります。
しかし、脱走防止柵を設置していれば不意に外に脱走されてしまうことがなくなり、猫を守ることができます。
家具の配置が適しているか確認する
家具の配置が適しているか確認することで猫が落下してしまうことを防ぐことができます。
基本的に室内にある家具から床に飛び降りても怪我をしてしまうことはありませんが、体調などが原因で着地に失敗してしまうこともあります。
そのため、猫が落下してしまうことで怪我をする危険性は外だけではなく、室内にもあることを知っておきましょう。
猫にとって危険になるような家具を置かないようにしたり、猫が移動したことで上から物が落ちてきてしまい、破損したり、飼い主に接触してしまうことがないかどうかを確認することも大切です。
猫が落下した後の注意点
 猫が落下してしまったのであれば注意しなければならないポイントがいくつかあります。
落下した後にしっかり様子見をして猫に異常がないかを確認することが大切です。
次に、猫が落下してしまった後の注意点をいくつか紹介するので、参考にしてください。
猫が落下してしまったのであれば注意しなければならないポイントがいくつかあります。
落下した後にしっかり様子見をして猫に異常がないかを確認することが大切です。
次に、猫が落下してしまった後の注意点をいくつか紹介するので、参考にしてください。
落下した後の内臓の状態を確認
落下した後に内臓の状態を確認することが大切です。
落下時に骨折をしてしまったり、擦り傷を負っているのであれば比較的発見しやすく、対処もしやすいです。
しかし、内臓は見ることができないため、見過ごしてしまいやすい部分です。
特に、肝臓は落下時の衝撃で破壊されてしまいやすく、症状もないため、より発見に遅れてしまいやすいです。
肝臓に異常があるかどうかは動物病院で血液検査をしてもらえばわかります。
落下時の怪我は外傷だけでなく、内側にも注意しなければなりません。
落下した際にすぐ確認するポイント
 落下した際にすぐに確認することができ、異常にいち早く気づくことができればそれだけ状態が重症化してしまうリスクを下げることができます。
落下した際に鼻血を流していないかやふらつきがないか、呼吸する速度が異常ではないかなどを確認しましょう。
どれか一つでも普段とは違う部分があるのであれば、何かしらの影響を受けている可能性が高いので動物病院で診察してもらいましょう。
脳になんらかの影響があれば上記で紹介したような症状があらわれやすいです。
落下した際にすぐに確認することができ、異常にいち早く気づくことができればそれだけ状態が重症化してしまうリスクを下げることができます。
落下した際に鼻血を流していないかやふらつきがないか、呼吸する速度が異常ではないかなどを確認しましょう。
どれか一つでも普段とは違う部分があるのであれば、何かしらの影響を受けている可能性が高いので動物病院で診察してもらいましょう。
脳になんらかの影響があれば上記で紹介したような症状があらわれやすいです。
まとめ
猫は高い場所から落下しても問題ないイメージが定着しており、実際他の動物と比べても落下時の衝撃を吸収することに優れています。
しかし、必ず怪我をしないわけではなく、条件が悪ければ大怪我をしてしまったり、最悪死亡してしまうこともあります。
また、落下後怪我などが見られなくても内側に酷い衝撃を受けている可能性もあるので、心配であれば異常が見られなくても動物病院で診察してもらうことが無難です。
子猫や肥満体質に猫、老描などには特に注意しましょう。
猫の骨折の原因とは?
 猫は人と同じように骨に強い衝撃が加わることで骨折してしまうことがあります。
次に、猫が骨折してしまう原因を紹介します。
知らない間に猫が骨折してしまったのであれば下記に紹介している原因に当てはまるものがないかを確認しましょう。
猫は人と同じように骨に強い衝撃が加わることで骨折してしまうことがあります。
次に、猫が骨折してしまう原因を紹介します。
知らない間に猫が骨折してしまったのであれば下記に紹介している原因に当てはまるものがないかを確認しましょう。
ベランダから落下する
ベランダなどの高い場所から落下してしまうと猫も骨折することがあります。
猫は落下時の衝撃を緩和することに優れている体の構造になっていますが、耐えられる衝撃にも限度があります。
普段からマンションやビルなどのベランダに出ているのであれば誤って落下している可能性も充分考えられます。
そのため、高層マンションに住んでおり、知らない間に骨折して帰ってきたのであれば落下による骨折である可能性が高いです。
もし、落下して骨折したのであれば内臓なども破損している可能性があるのですぐに動物病院に連れて行くようにしましょう。
低い場所から落下する
 落下することで骨折してしまうのは高い場所から落ちた時と考えてしまいがちですが、低い場所からの落下の方が骨折しやすいです。
特に、室内で飼われている猫ほど低い段差で骨折してしまうことがあります。
その理由は運動不足も関係していますが、落下した瞬間から着地するまでの時間が極端に短く、十分な着地体勢をとることができないからです。
そのため、ソファーのふちやバスタブなどの高さからの落下の方が骨折のリスクが高く、逆にタンスなどの高さからの落下では骨折することはほとんどありません。
落下することで骨折してしまうのは高い場所から落ちた時と考えてしまいがちですが、低い場所からの落下の方が骨折しやすいです。
特に、室内で飼われている猫ほど低い段差で骨折してしまうことがあります。
その理由は運動不足も関係していますが、落下した瞬間から着地するまでの時間が極端に短く、十分な着地体勢をとることができないからです。
そのため、ソファーのふちやバスタブなどの高さからの落下の方が骨折のリスクが高く、逆にタンスなどの高さからの落下では骨折することはほとんどありません。
子猫がケージで骨折する
子猫はケージで骨折してしまうことがあります。
子猫は好奇心旺盛でもあるため、さまざまな危険から子猫を守るためにケージ内で飼われることが多く、飼い主も安心してしまいやすいです。
しかし、安全のためのケージが逆に骨折の原因となることもあります。
子猫はケージに上ってしまうことが多く、この際に網の隙間に足が引っかかってしまい、無理な格好で骨折してしまったり、着地体勢が取れないまま落下してしまうこともあります。
そのほかにもカーテンなどにのぼり、そこから落ちることで骨折することもあるので、注意しましょう。
猫の骨折の見極め方
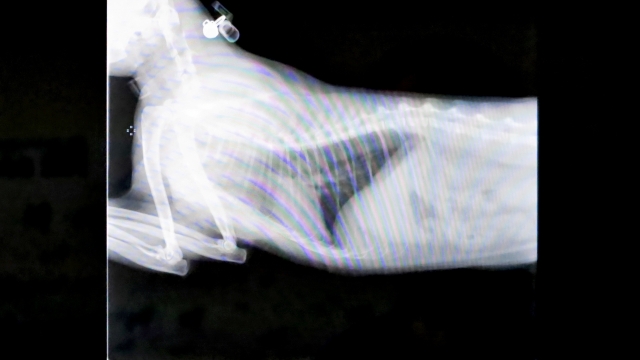 猫が骨折しているかどうかを確認することができれば素早い対応をすることができますが、なかなか見極めることは難しいです。
猫は骨折すると物陰に隠れていたり、食欲や元気がなくなる場合が多いです。
そのほかにも体に触れられることに嫌がったり、トイレでの排泄の格好が不自然になりやすく、足を引きずるように歩くようになります。
最後の足を引きずることは骨折していることを確認しやすいですが、物陰に隠れたり、元気や食欲がないだけでは骨折を疑わない場合も多く、発見が遅れてしまいやすいです。
普段から猫の様子をよく確認し、少しでもいつもと違う部分があると感じるのであればより注意深く観察しましょう。
元気がないことや食欲がないことは骨折以外が原因でもあるので、病院で詳しく検査してもらうようにすることをおすすめします。
猫が骨折しているかどうかを確認することができれば素早い対応をすることができますが、なかなか見極めることは難しいです。
猫は骨折すると物陰に隠れていたり、食欲や元気がなくなる場合が多いです。
そのほかにも体に触れられることに嫌がったり、トイレでの排泄の格好が不自然になりやすく、足を引きずるように歩くようになります。
最後の足を引きずることは骨折していることを確認しやすいですが、物陰に隠れたり、元気や食欲がないだけでは骨折を疑わない場合も多く、発見が遅れてしまいやすいです。
普段から猫の様子をよく確認し、少しでもいつもと違う部分があると感じるのであればより注意深く観察しましょう。
元気がないことや食欲がないことは骨折以外が原因でもあるので、病院で詳しく検査してもらうようにすることをおすすめします。
猫の骨折の治療法
 猫が骨折してしまったのであれば治療する必要があります。
治療が早ければ早いほど完治までの期間を短くすることもできます。
次に、猫の骨折の治療方法について詳しく紹介するため、どのような方法で骨折を治すのか知りたい人は参考にしてください。
猫が骨折してしまったのであれば治療する必要があります。
治療が早ければ早いほど完治までの期間を短くすることもできます。
次に、猫の骨折の治療方法について詳しく紹介するため、どのような方法で骨折を治すのか知りたい人は参考にしてください。
創外固定法
創外固定法とは、ネジ付きの金属製のピンで皮膚の外から骨を固定する方法であり、一般的な治療方法でもあります。
皮膚などを開いて治療することがないので、完治までの期間が短く、猫にも負担がかかりにくい治療法と言えます。
そのため、体力がない子猫や老描に対して適用されることが多いです。
新しい骨が生成されやすいメリットもあり、骨折による運動不足の影響も極力小さくすることが期待できます。
強い骨ができる治療法でもあるため、再び骨折してしまうリスクを下げることもできますが、固定しているピンが外からでも見えてしまうデメリットがあります。
プレート法
 プレート法の治療は骨折した場所を開き、金属の板で固定する方法です。
メリットは手術したその翌日には歩くことができることと骨折した骨を元の形に生成しやすいことです。
デメリットは骨が生成されるスピードが遅く、新しくできた骨の強度も低いので、再び骨折してしまうリスクが高いことです。
最悪プレートが折れてしまったり、外れてしまうリスクもあります。
金属製のプレートは骨が再構築された後も取り除くことはないため、その後も体の中に入ったままとなります。
プレート法の治療は骨折した場所を開き、金属の板で固定する方法です。
メリットは手術したその翌日には歩くことができることと骨折した骨を元の形に生成しやすいことです。
デメリットは骨が生成されるスピードが遅く、新しくできた骨の強度も低いので、再び骨折してしまうリスクが高いことです。
最悪プレートが折れてしまったり、外れてしまうリスクもあります。
金属製のプレートは骨が再構築された後も取り除くことはないため、その後も体の中に入ったままとなります。
副子固定法
副子固定法とはギプスで固定することです。
一見原始的な治療法と感じてしまいやすいですが、意外と治療法としては優れています。
副子固定法のメリットは治癒速度が速いことと強い骨が再構成されることです。
一方デメリットは元の形の骨になりにくいことや子猫の時にしか使用できない制限があることです。
強く固定しているわけではないため、骨が再構成される際に元の形にはなりませんが、子猫であれば自然と元の形に近づいていく傾向があります。
髄内ピン法
 髄内ピン法は骨髄部分に金属のピンを通し固定する方法です。
骨折部分を支えることはできますが、固定する力が弱いのでギプスを装着するようになります。
骨折部分を開く方法と開かない方法があり、開かなければ傷や骨折の治りも早いメリットがあります。
開いてしまうとあまりメリットになることは少なく、回復するスピードも遅くなってしまいます。
ギプスを使用しても他の治療法による固定力よりも弱いというデメリットがあります。
髄内ピン法は骨髄部分に金属のピンを通し固定する方法です。
骨折部分を支えることはできますが、固定する力が弱いのでギプスを装着するようになります。
骨折部分を開く方法と開かない方法があり、開かなければ傷や骨折の治りも早いメリットがあります。
開いてしまうとあまりメリットになることは少なく、回復するスピードも遅くなってしまいます。
ギプスを使用しても他の治療法による固定力よりも弱いというデメリットがあります。
猫の骨折の予防法
 猫はさまざまな原因で骨折してしまいます。
しかし、予防法を行っていればある程度骨折してしまうリスクを下げることができます。
次に、猫の骨折を予防する方法をいくつか紹介します。
過去に骨折をしてしまった経験がある場合やたびたび骨折しているのであれば参考にしてください。
猫はさまざまな原因で骨折してしまいます。
しかし、予防法を行っていればある程度骨折してしまうリスクを下げることができます。
次に、猫の骨折を予防する方法をいくつか紹介します。
過去に骨折をしてしまった経験がある場合やたびたび骨折しているのであれば参考にしてください。
落下事故を防止する
骨折をしてしまう原因の大半が高い場所からの落下事故です。
特にマンションなどの高層に住んでいるほど落下事故は多くなってしまいます。
転落事故を防ぐためにも窓の開けっぱなしはしないようにしたり、転落防止のグッズを活用しましょう。
飼い主は高い場所に住んでいる自覚がありますが、猫は高い場所で生活している自覚がないため、そこまで高さがないと思って開けられた窓から飛び出てしまうこともあります。
また、ベランダなどがある場合も落下してしまう可能性が高いため、基本的にベランダなど転落しやすい場所には移動できないようにしましょう。
猫を外に出さない
 猫を外に出さないようにすることも骨折予防になります。
外に出れば落下事故はもちろんですが、交通事故に巻き込まれてしまうリスクが高まってしまいます。
そのため、放し飼いにしていればそれだけ骨折してしまうトラブルに巻き込まれてしまいやすくなります。
猫に骨折させないためには室内飼いにして、極力室内で飼育するように心がけましょう。
以前までは放し飼いで急に室内飼いに慣れさせることは難しく、猫もストレスを感じやすくなるため、できるのであれば子猫の時から完全室内飼いをすることをおすすめします。
猫を外に出さないようにすることも骨折予防になります。
外に出れば落下事故はもちろんですが、交通事故に巻き込まれてしまうリスクが高まってしまいます。
そのため、放し飼いにしていればそれだけ骨折してしまうトラブルに巻き込まれてしまいやすくなります。
猫に骨折させないためには室内飼いにして、極力室内で飼育するように心がけましょう。
以前までは放し飼いで急に室内飼いに慣れさせることは難しく、猫もストレスを感じやすくなるため、できるのであれば子猫の時から完全室内飼いをすることをおすすめします。
猫が骨折した場合の治療費
 猫が骨折した際の治療費はいくら程度になるか知らない人も多いのではないでしょうか。
しかし、どのような原因で骨折してしまうかわからないため、どの程度治療費が必要になるかは知っておいて損することはありません。
骨折の治療費は骨折の具合や治療法によって変化しますが、治療・入院・薬代・検査など一式まとめて10~30万円程度かかる場合が多いです。
過去には80万円程度の治療費になってしまうこともあり、骨折してしまうと余計な費用がかかってしまうことは把握しておきましょう。
猫が骨折した際の治療費はいくら程度になるか知らない人も多いのではないでしょうか。
しかし、どのような原因で骨折してしまうかわからないため、どの程度治療費が必要になるかは知っておいて損することはありません。
骨折の治療費は骨折の具合や治療法によって変化しますが、治療・入院・薬代・検査など一式まとめて10~30万円程度かかる場合が多いです。
過去には80万円程度の治療費になってしまうこともあり、骨折してしまうと余計な費用がかかってしまうことは把握しておきましょう。
まとめ
猫はさまざまな理由から骨折してしまう可能性があり、落下した際や交通事故による骨折が多いです。
治療法は骨折の具合によって変わり、いくつかの治療法があるため、それぞれのメリットとデメリットも把握しておきましょう。
骨折してしまうと猫は痛く苦しい思いをしてしまうため、骨折する原因をできるだけ少なくしていかに骨折してしまうような場面にならないように気を付けることが大切です。
飼い主にとっても骨折の治療費は経済的に痛手となってしまいやすいです。
 猫の膵炎ははっきりとした症状が出ないため、飼い主が気づきにくい病気です。
しかし放っておくと危険な状態にもなりかねないので、早期発見と治療が必要です。
ここでは急性膵炎と慢性膵炎の症状や合併症について解説します。
猫の膵炎ははっきりとした症状が出ないため、飼い主が気づきにくい病気です。
しかし放っておくと危険な状態にもなりかねないので、早期発見と治療が必要です。
ここでは急性膵炎と慢性膵炎の症状や合併症について解説します。
 慢性膵炎は長期間膵臓の炎症が続いて、機能が衰えていきます。
症状があったとしてもわずかなもので、下痢や嘔吐がある場合でも数日に1度など、頻度が比較的低く、軽度なことが多いです。
そのため診断する場合も非常に難しい面があり、初期では発見しにくいことが多いです。
猫では比較的多く、中高齢の猫に起こりやすい病気と言われています。
進行すると食欲がなくなって体重が減少し、毛艶が悪くなります。
早く治療を始めると改善しやすいので、少しでも変だなと感じたら病院で受診することが必要です。
慢性膵炎は長期間膵臓の炎症が続いて、機能が衰えていきます。
症状があったとしてもわずかなもので、下痢や嘔吐がある場合でも数日に1度など、頻度が比較的低く、軽度なことが多いです。
そのため診断する場合も非常に難しい面があり、初期では発見しにくいことが多いです。
猫では比較的多く、中高齢の猫に起こりやすい病気と言われています。
進行すると食欲がなくなって体重が減少し、毛艶が悪くなります。
早く治療を始めると改善しやすいので、少しでも変だなと感じたら病院で受診することが必要です。
 膵炎の原因ははっきりとわかっておらず、治せる特効薬も今はまだありません。
炎症を起こした膵臓の血液循環の改善や消化器症状の治療などになります。
次に現在行われる膵炎の治療法について解説します。
膵炎の原因ははっきりとわかっておらず、治せる特効薬も今はまだありません。
炎症を起こした膵臓の血液循環の改善や消化器症状の治療などになります。
次に現在行われる膵炎の治療法について解説します。
 急性膵炎になってしまった場合は、早期の発見・治療が非常に大切であり、入院して輸液(電解質や水分などの投与)をすることが必須となります。
輸液とは血管の静脈に点滴をすることです。
それにより、血液循環を良くすることができ、下痢や嘔吐などからくる脱水症状の改善にもなります。
吐き気や痛みを抑える薬も使用されます。
消化管の動きが悪く食欲不振になることも多いため、早めに吐き気止めや消化器の改善を図る薬によって、症状を和らげます。
急性膵炎になってしまった場合は、早期の発見・治療が非常に大切であり、入院して輸液(電解質や水分などの投与)をすることが必須となります。
輸液とは血管の静脈に点滴をすることです。
それにより、血液循環を良くすることができ、下痢や嘔吐などからくる脱水症状の改善にもなります。
吐き気や痛みを抑える薬も使用されます。
消化管の動きが悪く食欲不振になることも多いため、早めに吐き気止めや消化器の改善を図る薬によって、症状を和らげます。
 猫の膵炎には急性と慢性があります。
猫では慢性膵炎が多いと言われていますが、その違いはどんなところにあるのでしょうか。
次に解説していきますが、急性から慢性になったり、その逆の場合もあり、どちらも注意が必要な病気です。
猫の膵炎には急性と慢性があります。
猫では慢性膵炎が多いと言われていますが、その違いはどんなところにあるのでしょうか。
次に解説していきますが、急性から慢性になったり、その逆の場合もあり、どちらも注意が必要な病気です。
 急激に炎症が起きる急性膵炎とは異なり、慢性膵炎は膵臓の炎症が長期的に続きます。
膵臓の機能が段々と破壊され、衰退していきます。
初期でははっきりした症状が出ないため、発見しにくいところも特徴的です。
一般的に7歳以降の中高齢の猫に多く、他の病気との併発も多いとされています。
病気が進行して痩せてから病院で診断されるケースもあり、飼い主が早期に発見することは難しい病気です。
できるだけ、定期的に健康診断を受け、病気の発見に努めましょう。
急激に炎症が起きる急性膵炎とは異なり、慢性膵炎は膵臓の炎症が長期的に続きます。
膵臓の機能が段々と破壊され、衰退していきます。
初期でははっきりした症状が出ないため、発見しにくいところも特徴的です。
一般的に7歳以降の中高齢の猫に多く、他の病気との併発も多いとされています。
病気が進行して痩せてから病院で診断されるケースもあり、飼い主が早期に発見することは難しい病気です。
できるだけ、定期的に健康診断を受け、病気の発見に努めましょう。
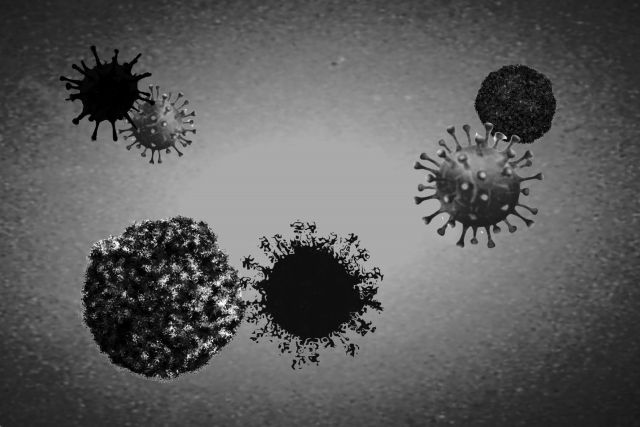 対応が遅れると、命の危険もある膵炎ですが、どのような原因で起こるのでしょうか。
実は、猫の膵炎の原因は未だ特定されていません。
しかし、原因と疑われているものは複数あり、膵臓の損傷やウイルス感染など多岐に渡っています。
例えば、トキソプラズマなどの寄生虫感染、胆管肝炎、薬物などの中毒、ヘルペスウィルスの感染などが考えられています。
どれが原因なのかは判明していませんが、いろいろな原因を考えて飼い主ができる予防について次にご紹介します。
対応が遅れると、命の危険もある膵炎ですが、どのような原因で起こるのでしょうか。
実は、猫の膵炎の原因は未だ特定されていません。
しかし、原因と疑われているものは複数あり、膵臓の損傷やウイルス感染など多岐に渡っています。
例えば、トキソプラズマなどの寄生虫感染、胆管肝炎、薬物などの中毒、ヘルペスウィルスの感染などが考えられています。
どれが原因なのかは判明していませんが、いろいろな原因を考えて飼い主ができる予防について次にご紹介します。
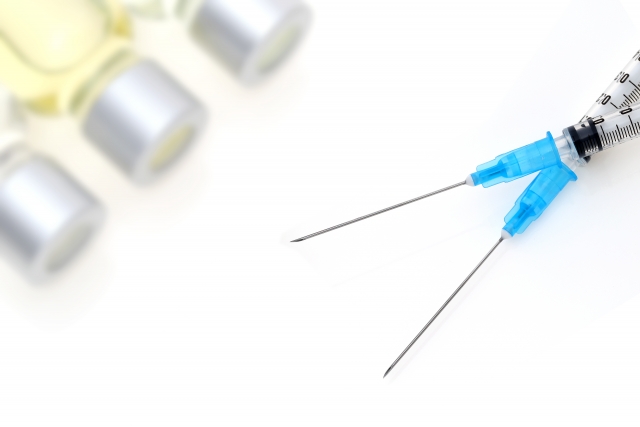 膵炎の予防法にはワクチン接種があり、ウイルス感染が原因の場合は、膵炎が引き起こされにくい状態になります。
また、慢性膵炎は定期健診などで予防できる可能性もあります。
特に中高齢になれば定期的に健康診断を受けることは重要で、膵臓に限らず肝臓や心臓などの状態も把握でき、様々な病気の早期発見に役立ちます。
それにより慢性膵炎の発症を予防できることにもつながるので、ワクチン接種や定期健診は積極的に受けましょう。
膵炎の予防法にはワクチン接種があり、ウイルス感染が原因の場合は、膵炎が引き起こされにくい状態になります。
また、慢性膵炎は定期健診などで予防できる可能性もあります。
特に中高齢になれば定期的に健康診断を受けることは重要で、膵臓に限らず肝臓や心臓などの状態も把握でき、様々な病気の早期発見に役立ちます。
それにより慢性膵炎の発症を予防できることにもつながるので、ワクチン接種や定期健診は積極的に受けましょう。
 猫の疥癬を知っているでしょうか。
疥癬とは猫ヒゼンダニと呼ばれるダニが猫の体に寄生して、発症する病気です。
猫ヒゼンダニはさまざまな方法で感染してしまうため、たとえ室内の飼い猫であっても疥癬になる可能性はゼロではありません。
例えば疥癬に感染している猫に飼い猫が接触してしまうと感染してしまいます。
そのほかにも完全に室内の飼い猫でも飼い主が感染している猫と接触すれば衣服に猫ヒゼンダニが付着してしまう可能性もあり、そこから飼い猫に感染することもあります。
猫の疥癬を知っているでしょうか。
疥癬とは猫ヒゼンダニと呼ばれるダニが猫の体に寄生して、発症する病気です。
猫ヒゼンダニはさまざまな方法で感染してしまうため、たとえ室内の飼い猫であっても疥癬になる可能性はゼロではありません。
例えば疥癬に感染している猫に飼い猫が接触してしまうと感染してしまいます。
そのほかにも完全に室内の飼い猫でも飼い主が感染している猫と接触すれば衣服に猫ヒゼンダニが付着してしまう可能性もあり、そこから飼い猫に感染することもあります。
 疥癬の病気のことを知らない人も多く、症状についても把握できていない場合も少なくありません。
疥癬になってしまうとあらわれる症状を理解していればいち早く疥癬に感染してしまっていることを疑うことができ、早期治療を行うこともできます。
多頭飼いしていればすべての猫に感染が広まってしまう可能性が高いですが、症状を確認したときに隔離することで感染予防することも可能です。
次に、猫が疥癬になってしまった際の症状を紹介するので参考にしてください。
疥癬の病気のことを知らない人も多く、症状についても把握できていない場合も少なくありません。
疥癬になってしまうとあらわれる症状を理解していればいち早く疥癬に感染してしまっていることを疑うことができ、早期治療を行うこともできます。
多頭飼いしていればすべての猫に感染が広まってしまう可能性が高いですが、症状を確認したときに隔離することで感染予防することも可能です。
次に、猫が疥癬になってしまった際の症状を紹介するので参考にしてください。
 疥癬になると痒みがあらわれることを上記で紹介しましたが、常に痒みを感じていることにストレスを感じてしまい、食欲不振に陥ってしまうこともあります。
疥癬の初期症状であれば一部分だけに痒みがあらわれる程度ですが、病気が進行してしまうと全身に炎症が広がってしまい、耐えがたい痒みになってしまいます。
ヒゼンダニは猫の体温が上昇することで活動を活発化させるため、夏場であれば常に活動が活発であり、痒みがより激しくなってしまいます。
食欲不振になると当然栄養を摂取することができなくなってしまうため、栄養失調になってしまうことも少なくありません。
疥癬になると痒みがあらわれることを上記で紹介しましたが、常に痒みを感じていることにストレスを感じてしまい、食欲不振に陥ってしまうこともあります。
疥癬の初期症状であれば一部分だけに痒みがあらわれる程度ですが、病気が進行してしまうと全身に炎症が広がってしまい、耐えがたい痒みになってしまいます。
ヒゼンダニは猫の体温が上昇することで活動を活発化させるため、夏場であれば常に活動が活発であり、痒みがより激しくなってしまいます。
食欲不振になると当然栄養を摂取することができなくなってしまうため、栄養失調になってしまうことも少なくありません。
 疥癬になってしまった場合は治療を開始する必要があります。
一度感染してしまうと様子見していてもヒゼンダニがいなくなることはほとんどなく、治療しなければ症状が悪化するだけです。
次に、疥癬の治療方法について紹介するので、飼い主は把握しておきましょう。
疥癬になってしまった場合は治療を開始する必要があります。
一度感染してしまうと様子見していてもヒゼンダニがいなくなることはほとんどなく、治療しなければ症状が悪化するだけです。
次に、疥癬の治療方法について紹介するので、飼い主は把握しておきましょう。
 薬浴は殺虫効果のある薬剤をお湯に入れ、お風呂に入れる感覚で体に薬剤を浸透させていきます。
ヒゼンダニを死滅させる効果のある薬剤でもあるため、一般的に行われる治療法でもあります。
しかし、猫によってはお風呂を嫌がってしまう場合もあり、薬浴させることに悪戦苦闘してしまうことも少なくありません。
お風呂に慣れさせておけば薬浴させる手間もかからないため、おすすめです。
薬浴させることは動物病院の先生にやり方などを指導してもらうようにしましょう。
薬浴は殺虫効果のある薬剤をお湯に入れ、お風呂に入れる感覚で体に薬剤を浸透させていきます。
ヒゼンダニを死滅させる効果のある薬剤でもあるため、一般的に行われる治療法でもあります。
しかし、猫によってはお風呂を嫌がってしまう場合もあり、薬浴させることに悪戦苦闘してしまうことも少なくありません。
お風呂に慣れさせておけば薬浴させる手間もかからないため、おすすめです。
薬浴させることは動物病院の先生にやり方などを指導してもらうようにしましょう。
 疥癬の治療方法は比較的効果があらわれやすく、治療を開始すれば完治する場合も多いです。
基本的に1~2か月程度で治療が完了することが多く、治療が長期間にわたってしまうこともありません。
ただし、治療を途中で中断してしまうなどしてしまうと完全にヒゼンダニが死滅していないため、再発してしまう可能性もあり、結果的に長く治療を続けなければならなくなってしまいます。
治療に適している環境かどうかは飼い主が独自で判断するのではなく、動物病院の先生の指導の元に判断するようにしましょう。
疥癬の治療方法は比較的効果があらわれやすく、治療を開始すれば完治する場合も多いです。
基本的に1~2か月程度で治療が完了することが多く、治療が長期間にわたってしまうこともありません。
ただし、治療を途中で中断してしまうなどしてしまうと完全にヒゼンダニが死滅していないため、再発してしまう可能性もあり、結果的に長く治療を続けなければならなくなってしまいます。
治療に適している環境かどうかは飼い主が独自で判断するのではなく、動物病院の先生の指導の元に判断するようにしましょう。
 人もダニの影響で痒みの症状が起きることがあり、同じく疥癬になる可能性もあります。
次に、猫の疥癬が人にうつるかどうかを詳しく説明します。
飼い猫が疥癬になってしまって、自分にうつってしまうことに不安を感じている人は参考にしてください。
人もダニの影響で痒みの症状が起きることがあり、同じく疥癬になる可能性もあります。
次に、猫の疥癬が人にうつるかどうかを詳しく説明します。
飼い猫が疥癬になってしまって、自分にうつってしまうことに不安を感じている人は参考にしてください。
 上記ではヒゼンダニは人に感染しないと紹介しましたが、一時的に感染してしまうことはあります。
矛盾していると感じてしまいやすいですが、上記で紹介したように猫のヒゼンダニが人の肌で繁殖することはできないため、一時的に人の肌に滞在するだけでそのあとは自然と死滅します。
基本的に猫のヒゼンダニは3週間程度しか人の皮膚で生きることができません。
しかし、一時的とはいえ感染してしまうことには変わりないため、猫と同じように疥癬の症状があらわれ、痒みなどの症状があらわれます。
上記ではヒゼンダニは人に感染しないと紹介しましたが、一時的に感染してしまうことはあります。
矛盾していると感じてしまいやすいですが、上記で紹介したように猫のヒゼンダニが人の肌で繁殖することはできないため、一時的に人の肌に滞在するだけでそのあとは自然と死滅します。
基本的に猫のヒゼンダニは3週間程度しか人の皮膚で生きることができません。
しかし、一時的とはいえ感染してしまうことには変わりないため、猫と同じように疥癬の症状があらわれ、痒みなどの症状があらわれます。
 猫の疥癬を予防することができれば猫を苦しませることがなくなり、飼い主に疥癬が広がってしまうこともありません。
疥癬を予防するためにはヒゼンダニに感染させないことが一番であるため、完全に室内飼いにすることが最も効果があります。
もし、室内で疥癬になる場合は飼い主が他の猫に触れて、ヒゼンダニを室内に入れてしまうぐらいしか考えられないため、それらの行動をしなければ飼い猫にヒゼンダニが付着し、繁殖してしまうこともありません。
もし、完全室内飼いが難しいのであれば定期的に駆除剤やダニ予防の薬を投与することで繁殖する前に死滅させることが期待できます。
猫の疥癬を予防することができれば猫を苦しませることがなくなり、飼い主に疥癬が広がってしまうこともありません。
疥癬を予防するためにはヒゼンダニに感染させないことが一番であるため、完全に室内飼いにすることが最も効果があります。
もし、室内で疥癬になる場合は飼い主が他の猫に触れて、ヒゼンダニを室内に入れてしまうぐらいしか考えられないため、それらの行動をしなければ飼い猫にヒゼンダニが付着し、繁殖してしまうこともありません。
もし、完全室内飼いが難しいのであれば定期的に駆除剤やダニ予防の薬を投与することで繁殖する前に死滅させることが期待できます。
 においを感じ取るのは、鼻の中の嗅上皮にある嗅細胞によって感知されます。
犬は、においを受け取る場所である嗅上皮の面積が広く、嗅細胞が多く存在するので、嗅覚が人に比べ優れており敏感に嗅ぎ取れることができるのです。
においを感じ取るのは、鼻の中の嗅上皮にある嗅細胞によって感知されます。
犬は、においを受け取る場所である嗅上皮の面積が広く、嗅細胞が多く存在するので、嗅覚が人に比べ優れており敏感に嗅ぎ取れることができるのです。
 犬のにおいの捕らえ方は、人間とは少し異なります。
人間はにおいだけでもにおいを感じ、また、味とにおいの組み合わせでもにおいを感じることができすが、犬の場合はにおいを単独で感じる事の割合が多いようです。
犬の嗅覚の優劣は、鼻の穴(鼻腔)の構造に左右され、鼻腔の表面(嗅上皮)内には臭いを感知するセンサーが(嗅細胞)があります。
人間の嗅上皮は約3~7平方センチメートルでだいたい1円玉~10円玉程の面積しかなく、含まれる嗅細胞の数は500万個程度です。
一方、犬種によって多少の変動はあるものの、犬の嗅上皮は約150~390平方センチメートルで人間の50倍以上!
ちょうど1000円札1枚ちょっとの面積に相当し、含まれる嗅細胞の数も約2億2千万個と、人間を圧倒しています。
表面積が大きいということは、それだけ多くの嗅細胞が存在することでにおいを捕らえ嗅覚が優れていると言えるでしょう。
犬のにおいの捕らえ方は、人間とは少し異なります。
人間はにおいだけでもにおいを感じ、また、味とにおいの組み合わせでもにおいを感じることができすが、犬の場合はにおいを単独で感じる事の割合が多いようです。
犬の嗅覚の優劣は、鼻の穴(鼻腔)の構造に左右され、鼻腔の表面(嗅上皮)内には臭いを感知するセンサーが(嗅細胞)があります。
人間の嗅上皮は約3~7平方センチメートルでだいたい1円玉~10円玉程の面積しかなく、含まれる嗅細胞の数は500万個程度です。
一方、犬種によって多少の変動はあるものの、犬の嗅上皮は約150~390平方センチメートルで人間の50倍以上!
ちょうど1000円札1枚ちょっとの面積に相当し、含まれる嗅細胞の数も約2億2千万個と、人間を圧倒しています。
表面積が大きいということは、それだけ多くの嗅細胞が存在することでにおいを捕らえ嗅覚が優れていると言えるでしょう。
 左右の鼻孔にある翼状の弁は、息を吐くときは閉じ、においを嗅ぐときに開くことで空気の流れを制御しています。
これにより、息を吸ったときに入ってくる別のにおいと、空気を脇に押しやることで、においと空気が混ざるのを防いでいます。
また、特殊な例としてブラッドハウンドの垂れ耳は、地面に引きずってにおいを舞い立たせることで、少しでも鼻に届きやすくしていると言います。
左右の鼻孔にある翼状の弁は、息を吐くときは閉じ、においを嗅ぐときに開くことで空気の流れを制御しています。
これにより、息を吸ったときに入ってくる別のにおいと、空気を脇に押しやることで、においと空気が混ざるのを防いでいます。
また、特殊な例としてブラッドハウンドの垂れ耳は、地面に引きずってにおいを舞い立たせることで、少しでも鼻に届きやすくしていると言います。
 実は犬にも「体内時計」が存在するのです。
人間と同様に犬の体内時計も光を浴びることでリセットされ、一定のリズムを保ちます。
そのため、正しい体内時計を保つには外の散歩がとても必要となってきます。
もしも、外に出て日の光を浴びないと犬は朝なのか夜なのかが分からなくなります。
朝、散歩に行き朝の日差しを浴びることは、生活リズムを規則正しく保ちホルモンバランスを整えるなどとても重要な役割を果たしています。
また、犬は春から夏には皮下脂肪量を減らし夏毛になり、暑さに対応できる体をつくります。
そして秋になると冬に向けての準備として食欲を増し、皮下脂肪を増やして寒さに対応できる冬毛になろうとします。
犬が外に出て日光を浴びる事により季節もしっかり感じられるようにしましょう。
実は犬にも「体内時計」が存在するのです。
人間と同様に犬の体内時計も光を浴びることでリセットされ、一定のリズムを保ちます。
そのため、正しい体内時計を保つには外の散歩がとても必要となってきます。
もしも、外に出て日の光を浴びないと犬は朝なのか夜なのかが分からなくなります。
朝、散歩に行き朝の日差しを浴びることは、生活リズムを規則正しく保ちホルモンバランスを整えるなどとても重要な役割を果たしています。
また、犬は春から夏には皮下脂肪量を減らし夏毛になり、暑さに対応できる体をつくります。
そして秋になると冬に向けての準備として食欲を増し、皮下脂肪を増やして寒さに対応できる冬毛になろうとします。
犬が外に出て日光を浴びる事により季節もしっかり感じられるようにしましょう。
 犬の嗅覚能力はマズル(鼻先)の長さが長いほど、優れているといわれています。
犬はマズルの長い順に長頭種、中頭種、短頭種の以下の三つのグループに分けられます。
犬の鼻内部には匂いを探知する細胞があり、鼻の長さ・大きさによって嗅覚に違いがあります。
犬の嗅覚能力はマズル(鼻先)の長さが長いほど、優れているといわれています。
犬はマズルの長い順に長頭種、中頭種、短頭種の以下の三つのグループに分けられます。
犬の鼻内部には匂いを探知する細胞があり、鼻の長さ・大きさによって嗅覚に違いがあります。
 最近、日本の各地で農作物を荒らす猿が増えています。
農作物を守るために猿を山へ追い戻す使役犬「猿追い犬」=「モンキードッグ」が活躍しています。
いろんな種類の犬に訓練をおこない、さまざまなモンキードッグが誕生していますが、なかでも「猿追い」に向いた性質を持つといわれるのが、柴犬をはじめとする日本犬です。
日本犬は空気中の上方に漂う臭いを察知することに長けており、木の上の方にいる猿の臭いを感じ取ることを得意としています。
最近、日本の各地で農作物を荒らす猿が増えています。
農作物を守るために猿を山へ追い戻す使役犬「猿追い犬」=「モンキードッグ」が活躍しています。
いろんな種類の犬に訓練をおこない、さまざまなモンキードッグが誕生していますが、なかでも「猿追い」に向いた性質を持つといわれるのが、柴犬をはじめとする日本犬です。
日本犬は空気中の上方に漂う臭いを察知することに長けており、木の上の方にいる猿の臭いを感じ取ることを得意としています。
 16世紀頃、プチ・バセット・グリフォン・バンデーンは、フランスのバンデーン地方でウサギ狩りなどの猟犬として活躍していたとても古い犬種です。
大きな垂れ耳、胴長で短い足、硬い被毛が特徴で、陽気で元気いっぱいで家族には愛情深く接する優しい犬種です。
もともと猟犬だっため、落ち着いた家庭犬となるためには毎日たっぷりと運動させることも必要です。
愛犬とアウトドアライフを楽しみたい人には、運動神経もよく、外で活動することが大好きなのでピッタリです。
16世紀頃、プチ・バセット・グリフォン・バンデーンは、フランスのバンデーン地方でウサギ狩りなどの猟犬として活躍していたとても古い犬種です。
大きな垂れ耳、胴長で短い足、硬い被毛が特徴で、陽気で元気いっぱいで家族には愛情深く接する優しい犬種です。
もともと猟犬だっため、落ち着いた家庭犬となるためには毎日たっぷりと運動させることも必要です。
愛犬とアウトドアライフを楽しみたい人には、運動神経もよく、外で活動することが大好きなのでピッタリです。
 嗅覚ハウンドの中で一番小さな犬で、昔、イギリスではウサギ狩りのために珍重されていました。
「スヌーピー」のモデルとなった世界中で愛されている犬種ですが、優れた嗅覚で獲物を追いかける狩猟犬です。
好奇心が強いので、興味を持ったものを追いかけるのに夢中になりやすく猟犬に向いてると言えるでしょう。
性格は、非常に愛情深く、人なつっこく甘えん坊で人見知りをしないので家族ともほかの人や犬とも仲良くできる犬種です。
嗅覚ハウンドの中で一番小さな犬で、昔、イギリスではウサギ狩りのために珍重されていました。
「スヌーピー」のモデルとなった世界中で愛されている犬種ですが、優れた嗅覚で獲物を追いかける狩猟犬です。
好奇心が強いので、興味を持ったものを追いかけるのに夢中になりやすく猟犬に向いてると言えるでしょう。
性格は、非常に愛情深く、人なつっこく甘えん坊で人見知りをしないので家族ともほかの人や犬とも仲良くできる犬種です。
 猫というと、発達した身体能力や柔らかい体つきを思う浮かべるかもしれません。
しかし、人間と比べると嗅覚が優れており、呼吸の他にも様々な情報収集を行う優れた器官として機能しています。
ここでは、そんな猫をよく知るきっかけとなるような嗅覚についてご紹介していきます。
猫というと、発達した身体能力や柔らかい体つきを思う浮かべるかもしれません。
しかし、人間と比べると嗅覚が優れており、呼吸の他にも様々な情報収集を行う優れた器官として機能しています。
ここでは、そんな猫をよく知るきっかけとなるような嗅覚についてご紹介していきます。
 猫の鼻はいつも湿っているけれど何故?と、感じることはありませんか。
逆に熟睡している時や寝起きの時は、乾いていることが多いはずです。
また、脱水や老化現象として鼻が乾くこともありますが、健康でも乾いていることはよく見られるので気になる症状がなければ心配の必要はありません。
鼻の湿り気は、鼻腔内からの分泌液によるもので濡れていることによって匂いをより吸着しやすくする効果があります。
乾いた鼻は匂いをキャッチしにくい状態となり、感知能力が下がってしまいます。
猫の鼻はいつも湿っているけれど何故?と、感じることはありませんか。
逆に熟睡している時や寝起きの時は、乾いていることが多いはずです。
また、脱水や老化現象として鼻が乾くこともありますが、健康でも乾いていることはよく見られるので気になる症状がなければ心配の必要はありません。
鼻の湿り気は、鼻腔内からの分泌液によるもので濡れていることによって匂いをより吸着しやすくする効果があります。
乾いた鼻は匂いをキャッチしにくい状態となり、感知能力が下がってしまいます。
 生きるために大切な役割を持つ嗅覚を生まれた時から身に付けている猫ですが、身を守るためや猫同士の関係性にも関わると考えられています。
では、実際に嗅覚によってどんなことができるのでしょうか。
生きるために大切な役割を持つ嗅覚を生まれた時から身に付けている猫ですが、身を守るためや猫同士の関係性にも関わると考えられています。
では、実際に嗅覚によってどんなことができるのでしょうか。
 可愛い仕草として猫好きにはよく知られている鼻チューですが、本当にキスをしている訳ではなくお互いの鼻同士を寄せ合って匂いを確認しているんです。
仲が悪い猫同士では絶対にしない行動で、「こんにちは」「喧嘩するつもりはないよ」と挨拶をしています。
また、匂いによって行動や相手の情報を確かめているとも考えられていますが、親密度が高い猫同士は頻繁に行うので多頭飼いしている飼い主様はじっくりと観察してみてはいかがでしょうか。
可愛い仕草として猫好きにはよく知られている鼻チューですが、本当にキスをしている訳ではなくお互いの鼻同士を寄せ合って匂いを確認しているんです。
仲が悪い猫同士では絶対にしない行動で、「こんにちは」「喧嘩するつもりはないよ」と挨拶をしています。
また、匂いによって行動や相手の情報を確かめているとも考えられていますが、親密度が高い猫同士は頻繁に行うので多頭飼いしている飼い主様はじっくりと観察してみてはいかがでしょうか。
 嗅覚が発達している猫は、食べ物の匂いを念入りに嗅いで食べても大丈夫なのか、腐敗していないかをチェックしています。
味覚より嗅覚でご飯を食べるといわれている猫は、匂いによって美味しいかどうかの判断をします。
ねこ風邪や病気などで鼻が詰まった猫は、食べ物の認識がしづらく食欲不振になることもあるでしょう。
もし嗅覚が利かないことでご飯を食べなくなった場合は、匂いの強い嗜好性の高いオヤツをトッピングしたり少し温めて匂いを強くしてあげると食べてくれるかもしれません。
鼻が利かない状態は体調が悪いことを表していますが、食欲まで失われてしまうと余計回復が遅くなります。
そのくらい、匂いは猫にとって大切なんですね。
嗅覚が発達している猫は、食べ物の匂いを念入りに嗅いで食べても大丈夫なのか、腐敗していないかをチェックしています。
味覚より嗅覚でご飯を食べるといわれている猫は、匂いによって美味しいかどうかの判断をします。
ねこ風邪や病気などで鼻が詰まった猫は、食べ物の認識がしづらく食欲不振になることもあるでしょう。
もし嗅覚が利かないことでご飯を食べなくなった場合は、匂いの強い嗜好性の高いオヤツをトッピングしたり少し温めて匂いを強くしてあげると食べてくれるかもしれません。
鼻が利かない状態は体調が悪いことを表していますが、食欲まで失われてしまうと余計回復が遅くなります。
そのくらい、匂いは猫にとって大切なんですね。
 猫は人間と同じく好きな匂いと嫌いな匂いがあり、どちらかというと強い匂いを好む傾向にあります。
また、嫌いな匂いがいつも近くにあるような環境は、大きなストレスとなりますので気をつけてあげましょう。
では、好きな匂いをいくつかご紹介していきます。
猫は人間と同じく好きな匂いと嫌いな匂いがあり、どちらかというと強い匂いを好む傾向にあります。
また、嫌いな匂いがいつも近くにあるような環境は、大きなストレスとなりますので気をつけてあげましょう。
では、好きな匂いをいくつかご紹介していきます。
 キャットニップやまたたびは、うっとりとしたりテンションアップしたりしてお気に入りの猫が多いのではないでしょうか。
またたびに含まれる成分によって猫の中枢神経を刺激し、酩酊しているような状態が見られることから依存性の心配をされる方も多いのですが、その心配はないと考えられています。
ストレス解消や食欲アップなど、健康に良い効果を期待できますが、使い方によっては逆効果となる場合もあります。
刺激が弱い粉末タイプを、用法用量や対象年齢を守ってご褒美として与えましょう。
キャットニップやまたたびは、うっとりとしたりテンションアップしたりしてお気に入りの猫が多いのではないでしょうか。
またたびに含まれる成分によって猫の中枢神経を刺激し、酩酊しているような状態が見られることから依存性の心配をされる方も多いのですが、その心配はないと考えられています。
ストレス解消や食欲アップなど、健康に良い効果を期待できますが、使い方によっては逆効果となる場合もあります。
刺激が弱い粉末タイプを、用法用量や対象年齢を守ってご褒美として与えましょう。
 猫が嫌いな匂いには、本能的なものが一因しています。
もし誤って口にしてしまうと害となるものもありますので、「嫌いだから食べないはず」と思わず注意してあげてください。
猫が嫌いな匂いには、本能的なものが一因しています。
もし誤って口にしてしまうと害となるものもありますので、「嫌いだから食べないはず」と思わず注意してあげてください。
 胡椒や唐辛子といった香辛料の強い香りは、猫にとって刺激が強く苦手としています。
何でも好みに応じて食べる人間とは違い、辛さや刺激は猫にとって不要のものなのです。
万が一、口にしてしまうと胃腸を壊したり体調不良となったりする場合も考えられますので、人間の食べるものに何でも興味を持つ猫がいるご家庭は、誤食しないようにしてください。
キッチンに自由に猫が出入りしていると、床に落ちた香辛料が体に付着しグルーミングで舐め取ってしまう場合もあります。
使用後は面倒ですが、毎回拭いて残らないように気をつけてあげてください。
胡椒や唐辛子といった香辛料の強い香りは、猫にとって刺激が強く苦手としています。
何でも好みに応じて食べる人間とは違い、辛さや刺激は猫にとって不要のものなのです。
万が一、口にしてしまうと胃腸を壊したり体調不良となったりする場合も考えられますので、人間の食べるものに何でも興味を持つ猫がいるご家庭は、誤食しないようにしてください。
キッチンに自由に猫が出入りしていると、床に落ちた香辛料が体に付着しグルーミングで舐め取ってしまう場合もあります。
使用後は面倒ですが、毎回拭いて残らないように気をつけてあげてください。
 甘味の中にも爽やかな酸味が美味しいオレンジやグレープフルーツなどの柑橘系は、猫にとって腐敗を連想させるようです。
匂いで食べられるものかどうか判断していることは先述の通りですが、柑橘系は本能から肉や魚が腐った匂いとして捉え、近寄ることも少ないはずです。
他にも柑橘類の皮に含まれるリモネンという成分は、もし猫の体に入った場合に代謝して分解することができず中毒症状を引き起こします。
最悪、命にも関わりますので絶対に与えないでください。
甘味の中にも爽やかな酸味が美味しいオレンジやグレープフルーツなどの柑橘系は、猫にとって腐敗を連想させるようです。
匂いで食べられるものかどうか判断していることは先述の通りですが、柑橘系は本能から肉や魚が腐った匂いとして捉え、近寄ることも少ないはずです。
他にも柑橘類の皮に含まれるリモネンという成分は、もし猫の体に入った場合に代謝して分解することができず中毒症状を引き起こします。
最悪、命にも関わりますので絶対に与えないでください。
 猫も人と同じように喘息になることを知っているでしょうか。
猫の場合は他の動物と比べても症状が人と似ているため、重篤になる前に早期発見する必要があり、異常にも比較的気づきやすいです。
喘息はうまく呼吸することができず、症状が悪化してしまうと呼吸困難になってしまうことも珍しくありません。
喘息になってしまう原因は様々であるため、もし猫が咳を頻繁にしているのであれば喘息になってしまっていることを疑いましょう。
猫も人と同じように喘息になることを知っているでしょうか。
猫の場合は他の動物と比べても症状が人と似ているため、重篤になる前に早期発見する必要があり、異常にも比較的気づきやすいです。
喘息はうまく呼吸することができず、症状が悪化してしまうと呼吸困難になってしまうことも珍しくありません。
喘息になってしまう原因は様々であるため、もし猫が咳を頻繁にしているのであれば喘息になってしまっていることを疑いましょう。
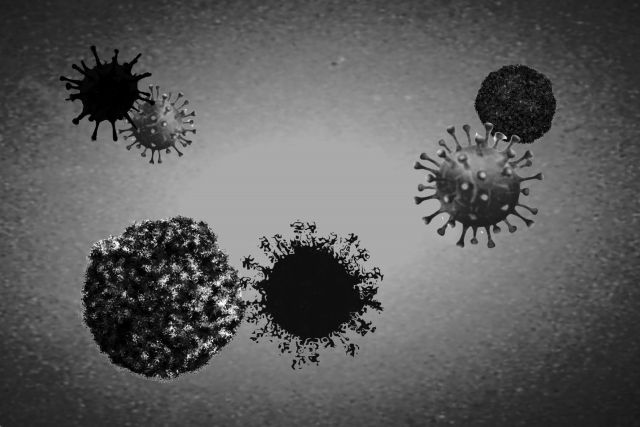 猫が喘息になってしまう原因はアレルギーが関係している場合が多いです。
アレルギーは特定の物質が体内に入ることでさまざまな症状を起こしてしまい、花粉やハウスダストは人もアレルギーの原因となる場合が多く、猫も同じようにアレルギー反応を起こしてしまいます。
それ以外にも消臭剤やヘアスプレー、洗浄剤、たばこの煙などを吸い込むことでもアレルギー反応を起こしてしまう可能性があるため、猫が喘息をしているのであればそれらのアレルギー物質が関係している可能性があります。
猫が喘息になってしまう原因はアレルギーが関係している場合が多いです。
アレルギーは特定の物質が体内に入ることでさまざまな症状を起こしてしまい、花粉やハウスダストは人もアレルギーの原因となる場合が多く、猫も同じようにアレルギー反応を起こしてしまいます。
それ以外にも消臭剤やヘアスプレー、洗浄剤、たばこの煙などを吸い込むことでもアレルギー反応を起こしてしまう可能性があるため、猫が喘息をしているのであればそれらのアレルギー物質が関係している可能性があります。
 猫喘息になってしまうとどのような症状があらわれるようになるのか知っておけば猫喘息を発症していることに早期発見することも可能になります。
喘息は安静にしていれば症状が治まることもありますが、甘く見ていると呼吸困難になってしまうこともあります。
次に、猫喘息の症状を紹介するので、どのような症状があらわれるのか知りたい人は参考にしてください。
基本的に人の喘息と症状は似ているため、猫の様子を頻繁にチェックしていれば早期発見することも可能です。
猫喘息になってしまうとどのような症状があらわれるようになるのか知っておけば猫喘息を発症していることに早期発見することも可能になります。
喘息は安静にしていれば症状が治まることもありますが、甘く見ていると呼吸困難になってしまうこともあります。
次に、猫喘息の症状を紹介するので、どのような症状があらわれるのか知りたい人は参考にしてください。
基本的に人の喘息と症状は似ているため、猫の様子を頻繁にチェックしていれば早期発見することも可能です。
 咳をしている場合も喘息であることを疑いましょう。
元々猫は頻繁に咳をする動物ではないため、繰り返し咳をしているのであれば喘息であったり、肺や気管に異常がある場合があります。
また、発作的に咳をしており、それが1分間以上続いているのであれば異常であるため、喘息になっている可能性があります。
人の場合はゲホゲホ咳をしますが、猫の場合はズーズーやゲッゲッと咳をする特徴があります。
また、咳をする際にはうつ伏せになり、舌を軽く出していることが多いです。
咳を連続していると最悪嘔吐してしまう可能性もあり、喘息の症状が悪化している可能性も出てきます。
咳をする頻度や回数を確認することで症状が和らいでいるのか進行しているのかを確認することができます。
咳をしている場合も喘息であることを疑いましょう。
元々猫は頻繁に咳をする動物ではないため、繰り返し咳をしているのであれば喘息であったり、肺や気管に異常がある場合があります。
また、発作的に咳をしており、それが1分間以上続いているのであれば異常であるため、喘息になっている可能性があります。
人の場合はゲホゲホ咳をしますが、猫の場合はズーズーやゲッゲッと咳をする特徴があります。
また、咳をする際にはうつ伏せになり、舌を軽く出していることが多いです。
咳を連続していると最悪嘔吐してしまう可能性もあり、喘息の症状が悪化している可能性も出てきます。
咳をする頻度や回数を確認することで症状が和らいでいるのか進行しているのかを確認することができます。
 喘息の症状が進行してしまうと肺や気管の機能も低下してしまいます。
そのため、酸素を思うように体に取り入れることができず、呼吸する回数が多くなってしまいます。
また、正常な時よりも体に酸素が供給されていないのですぐに疲れてしまったり、遊ぶ時間も少なくなる傾向があります。
呼吸する回数が多く、時間が経過しても呼吸回数が落ち着かない場合は喘息であったり、呼吸器系に何かしらの異常が起きている可能性があります。
普段であれば活発に行動していた猫が急に元気なかったり、遊ばなくなったのであれば呼吸の回数を確認し、喘息かどうかを把握しましょう。
喘息の症状が進行してしまうと肺や気管の機能も低下してしまいます。
そのため、酸素を思うように体に取り入れることができず、呼吸する回数が多くなってしまいます。
また、正常な時よりも体に酸素が供給されていないのですぐに疲れてしまったり、遊ぶ時間も少なくなる傾向があります。
呼吸する回数が多く、時間が経過しても呼吸回数が落ち着かない場合は喘息であったり、呼吸器系に何かしらの異常が起きている可能性があります。
普段であれば活発に行動していた猫が急に元気なかったり、遊ばなくなったのであれば呼吸の回数を確認し、喘息かどうかを把握しましょう。
 猫喘息から猫を守るためには予防方法を行うことをおすすめします。
猫喘息の原因の大半はアレルギー反応を起こしているので、アレルギー物質を特定し、猫がアレルギー物質を吸い込まないように心がけることが最大の予防策と言えます。
反応してしまうアレルギー物質は猫の個体ごとに異なり、どのようなタイミングで喘息の症状が出ているのかを確認しましょう。
食べ物が関係していれば特定しやすいですが、消臭剤や洗浄剤など吸い込むことでアレルギー反応を起こしてしまう場合は特定するのに時間がかかってしまいやすいです。
猫喘息から猫を守るためには予防方法を行うことをおすすめします。
猫喘息の原因の大半はアレルギー反応を起こしているので、アレルギー物質を特定し、猫がアレルギー物質を吸い込まないように心がけることが最大の予防策と言えます。
反応してしまうアレルギー物質は猫の個体ごとに異なり、どのようなタイミングで喘息の症状が出ているのかを確認しましょう。
食べ物が関係していれば特定しやすいですが、消臭剤や洗浄剤など吸い込むことでアレルギー反応を起こしてしまう場合は特定するのに時間がかかってしまいやすいです。
 猫喘息になってしまったのであれば治療を開始する必要があります。
喘息を甘く見ていると死亡してしまうこともあるため、喘息の疑いがあるのであれば動物病院で診察してもらうようにしましょう。
猫喘息の治療法はいくつか用意されており、症状の具合や原因などによって治療法も変わってきます。
次に、猫喘息の治療方法について詳しく紹介します。
飼い猫が喘息になっている恐れがあるのであれば動物病院に連れて行くと同時にどのような治療が行われるのかも知っておきましょう。
猫喘息になってしまったのであれば治療を開始する必要があります。
喘息を甘く見ていると死亡してしまうこともあるため、喘息の疑いがあるのであれば動物病院で診察してもらうようにしましょう。
猫喘息の治療法はいくつか用意されており、症状の具合や原因などによって治療法も変わってきます。
次に、猫喘息の治療方法について詳しく紹介します。
飼い猫が喘息になっている恐れがあるのであれば動物病院に連れて行くと同時にどのような治療が行われるのかも知っておきましょう。
 喘息は薬でも治療することができ、主に抗炎症薬と気管支拡張薬が使用されます。
アレルギー反応を起こしてしまうと気管が炎症して気管が狭くなってしまっている可能性が高いです。
そのままでは完全に空気の通り道が遮断されてしまい、呼吸をすることができなくなってしまいます。
そのような状態にならないためにも炎症を抑える抗炎症薬や気管を広げる効果がある気管支拡張薬が使用されます。
最初は多めに投与されますが、症状が緩和されていれば徐々に投与する量を減らしていく場合が一般的です。
喘息は薬でも治療することができ、主に抗炎症薬と気管支拡張薬が使用されます。
アレルギー反応を起こしてしまうと気管が炎症して気管が狭くなってしまっている可能性が高いです。
そのままでは完全に空気の通り道が遮断されてしまい、呼吸をすることができなくなってしまいます。
そのような状態にならないためにも炎症を抑える抗炎症薬や気管を広げる効果がある気管支拡張薬が使用されます。
最初は多めに投与されますが、症状が緩和されていれば徐々に投与する量を減らしていく場合が一般的です。
 腕枕をしてもらいスヤスヤ気持ち良さそうに寝ている猫を、テレビや動画などでよく見かけます。
喉をゴロゴロ鳴らしながら腕にギュッと抱き着く様子は、とても愛おしく癒されます。
そんな猫の腕枕をしたがる5つの理由を紹介します。
腕枕をしてもらいスヤスヤ気持ち良さそうに寝ている猫を、テレビや動画などでよく見かけます。
喉をゴロゴロ鳴らしながら腕にギュッと抱き着く様子は、とても愛おしく癒されます。
そんな猫の腕枕をしたがる5つの理由を紹介します。
 布団で一緒に眠る際に猫が腕枕を求めてくるのは、飼い主さんの腕の中がとても暖かいことを知っているからです。
猫にとって飼い主の腕の中はとても安心でき、くっついて一緒に眠ればおたがいの温もりを感じ合える事を知っています。
ふわふわ暖かい服を着ていれば猫にとっても心地が良く、寒い時期は特に腕枕をしたがります。
飼い主にとっても愛猫が安心して眠る姿には癒され、信頼されている実感がわきます。
布団で一緒に眠る際に猫が腕枕を求めてくるのは、飼い主さんの腕の中がとても暖かいことを知っているからです。
猫にとって飼い主の腕の中はとても安心でき、くっついて一緒に眠ればおたがいの温もりを感じ合える事を知っています。
ふわふわ暖かい服を着ていれば猫にとっても心地が良く、寒い時期は特に腕枕をしたがります。
飼い主にとっても愛猫が安心して眠る姿には癒され、信頼されている実感がわきます。
 毎日身の回りの世話をしてくれている飼い主さんは、猫にとってほとんど母親と同じような存在です。
飼い主さんから愛情をもらいたい時に、母親に甘えるように腕枕で眠る時があります。
腕枕をしてもらう事で一番安心でき、喉をゴロゴロ鳴らすのはリラックスをして嬉しいサインでもあります。
猫にとって腕枕は母親に愛情を求める愛情表現でもあります。
毎日身の回りの世話をしてくれている飼い主さんは、猫にとってほとんど母親と同じような存在です。
飼い主さんから愛情をもらいたい時に、母親に甘えるように腕枕で眠る時があります。
腕枕をしてもらう事で一番安心でき、喉をゴロゴロ鳴らすのはリラックスをして嬉しいサインでもあります。
猫にとって腕枕は母親に愛情を求める愛情表現でもあります。
 全ての猫が腕枕が好きだとは限らず、飼い主さんの中には腕枕をしたくてもできない人もいます。
腕枕が嫌いな猫には過去に嫌な思い出があったり、ひとりで眠るのが好きな場合があります。
どうしても猫に腕枕をしたい方の為に方法を幾つか紹介します。
全ての猫が腕枕が好きだとは限らず、飼い主さんの中には腕枕をしたくてもできない人もいます。
腕枕が嫌いな猫には過去に嫌な思い出があったり、ひとりで眠るのが好きな場合があります。
どうしても猫に腕枕をしたい方の為に方法を幾つか紹介します。
 猫は強制されるのを嫌いますので、腕枕をさせてくれるまで時間がかかる場合があります。
性格次第で腕枕を嫌がる猫もいますので、無理矢理抱いたりせずにのんびりと構えて待つ事も大切です。
猫が腕枕をしてくれるのは、飼い主さんとの信頼関係があってこそです。
早く腕枕がしたくて焦ってしまう飼い主さんもいると思いますが、一度失敗してしまうと余計時間がかかってしまう事もありますので注意が必要です。
猫は強制されるのを嫌いますので、腕枕をさせてくれるまで時間がかかる場合があります。
性格次第で腕枕を嫌がる猫もいますので、無理矢理抱いたりせずにのんびりと構えて待つ事も大切です。
猫が腕枕をしてくれるのは、飼い主さんとの信頼関係があってこそです。
早く腕枕がしたくて焦ってしまう飼い主さんもいると思いますが、一度失敗してしまうと余計時間がかかってしまう事もありますので注意が必要です。
 猫は飼い主さんの腕枕に慣れてくると気を許して、長い時間眠り続ける事があります。
気持ち良さそうに寝ている猫を見てるだけで癒されますが、腕が疲れて腕枕を外したい時もあります。
そんな時の腕枕を外す方法を紹介します。
猫は飼い主さんの腕枕に慣れてくると気を許して、長い時間眠り続ける事があります。
気持ち良さそうに寝ている猫を見てるだけで癒されますが、腕が疲れて腕枕を外したい時もあります。
そんな時の腕枕を外す方法を紹介します。
 猫の背中や頭を撫でながら、気持ち良さそうにゴロゴロと喉を鳴らしている隙にそっと腕を抜く方法もあります。
この方法は高確率で猫を起こさずに腕枕を外す事ができ、猫は飼い主さんから撫でてもらっている事で気持ちが良く飼い主さんも腕のしびれから解放されます。
腕枕を外した後もそのまま優しく撫でてあげると、安心して眠り続けるようです。
猫の背中や頭を撫でながら、気持ち良さそうにゴロゴロと喉を鳴らしている隙にそっと腕を抜く方法もあります。
この方法は高確率で猫を起こさずに腕枕を外す事ができ、猫は飼い主さんから撫でてもらっている事で気持ちが良く飼い主さんも腕のしびれから解放されます。
腕枕を外した後もそのまま優しく撫でてあげると、安心して眠り続けるようです。
 猫が老衰した際のサインが6つあることを知っているでしょうか。
サインを確認することで猫が弱っていることを知ることができ、高齢の猫にしたほうがよいさまざまな対策を講じることもできます。
次に、猫が老衰した際のサインをいくつか紹介するので参考にしてください。
猫が老衰した際のサインが6つあることを知っているでしょうか。
サインを確認することで猫が弱っていることを知ることができ、高齢の猫にしたほうがよいさまざまな対策を講じることもできます。
次に、猫が老衰した際のサインをいくつか紹介するので参考にしてください。
 老衰すると食欲が低下してしまいます。
老衰のサインとしては早い段階であらわれる異変であるため、飼い主も気づきやすく、同じ量の餌を与えても残す場合が多くなってしまいます。
食欲が低下してしまう原因は活動する時間が減るためであり、必然的にお腹も減りにくくなってしまいます。
食欲が減れば十分なエネルギーを得ることができないため、思うように体が動かしにくくなり、そのせいで食欲も湧かず、負の連鎖に陥ってしまいます。
また、食事から栄養を摂取する量が減ることで痩せてしまうことが多くなります。
老衰すると食欲が低下してしまいます。
老衰のサインとしては早い段階であらわれる異変であるため、飼い主も気づきやすく、同じ量の餌を与えても残す場合が多くなってしまいます。
食欲が低下してしまう原因は活動する時間が減るためであり、必然的にお腹も減りにくくなってしまいます。
食欲が減れば十分なエネルギーを得ることができないため、思うように体が動かしにくくなり、そのせいで食欲も湧かず、負の連鎖に陥ってしまいます。
また、食事から栄養を摂取する量が減ることで痩せてしまうことが多くなります。
 毛艶や毛並みが悪くことも老衰のサインの一つです。
被毛はさまざまな栄養素やタンパク質で正常な状態を維持することができ、艶が出たり毛並みもよくなります。
しかし、上記でも紹介したように老衰すると食欲が低下してしまうのでタンパク質やそのほかの栄養素も不足してしまいがちです。
その結果老衰すると毛並みなどが悪くなります。
さらに痩せてしまうことでさらに見た目が悪くなってしまいますが、改善することは難しく、余計な手を猫に加えてしまうと余計に体力を奪う原因となってしまいます。
毛艶や毛並みが悪くことも老衰のサインの一つです。
被毛はさまざまな栄養素やタンパク質で正常な状態を維持することができ、艶が出たり毛並みもよくなります。
しかし、上記でも紹介したように老衰すると食欲が低下してしまうのでタンパク質やそのほかの栄養素も不足してしまいがちです。
その結果老衰すると毛並みなどが悪くなります。
さらに痩せてしまうことでさらに見た目が悪くなってしまいますが、改善することは難しく、余計な手を猫に加えてしまうと余計に体力を奪う原因となってしまいます。
 老衰すると夜泣きが酷くなったり、粗相が増える場合があります。
このような異常な行動をしてしまう原因は老衰による脳機能の低下であり、認知症になっているからです。
猫も人と同じように高齢になればなるほど認知症になるリスクが高まり、猫の場合はトイレの位置がわからなくなり、さまざまな場所で排泄してしまったり、夜中に突然大きな声で鳴くようにもなります。
認知症は治すことができない病気でもありますが、動物病院の先生に相談して正しい対処方法を身に付けるようにしましょう。
老衰すると夜泣きが酷くなったり、粗相が増える場合があります。
このような異常な行動をしてしまう原因は老衰による脳機能の低下であり、認知症になっているからです。
猫も人と同じように高齢になればなるほど認知症になるリスクが高まり、猫の場合はトイレの位置がわからなくなり、さまざまな場所で排泄してしまったり、夜中に突然大きな声で鳴くようにもなります。
認知症は治すことができない病気でもありますが、動物病院の先生に相談して正しい対処方法を身に付けるようにしましょう。
 老衰することで異常な行動をするようになるだけではなく、さまざまな病気を誘発させてしまう原因にもなります。
なかには命にも関わる病気も含まれているため、飼い主であれば知っておいて損をすることはありません。
病気になってしまった際に大切なことは早期発見・早期治療が原則であるため、老衰しているサインを見かけるようになったのであればより一層猫の体調チェックをするようにしましょう。
次に、老衰することでなりやすい病気について紹介するので参考にして下さい。
老衰することで異常な行動をするようになるだけではなく、さまざまな病気を誘発させてしまう原因にもなります。
なかには命にも関わる病気も含まれているため、飼い主であれば知っておいて損をすることはありません。
病気になってしまった際に大切なことは早期発見・早期治療が原則であるため、老衰しているサインを見かけるようになったのであればより一層猫の体調チェックをするようにしましょう。
次に、老衰することでなりやすい病気について紹介するので参考にして下さい。
 猫の病気での死亡率の中でも最も高いのがガンであり、約4割の猫がガンで亡くなっているとも言われています。
現代社会では人も寿命が延びていますが、猫も同様に長生きするようになっています。
長く生きることになったことでガン細胞ができやすくなったとも言われ、さまざまなガンになるリスクが高まっていることがガンでの死亡率が高まっている原因です。
ガンの場合は急死してしまうことは少なく、治療を継続するようになることも珍しくありません。
その結果猫と少しでも長く共に生きることができますが、介護をしなければならないため、飼い主には介護の仕方などを身に付ける必要があります。
また、猫の医療のレベルも高まったことも猫が長生きできるようになった理由でもあります。
猫の病気での死亡率の中でも最も高いのがガンであり、約4割の猫がガンで亡くなっているとも言われています。
現代社会では人も寿命が延びていますが、猫も同様に長生きするようになっています。
長く生きることになったことでガン細胞ができやすくなったとも言われ、さまざまなガンになるリスクが高まっていることがガンでの死亡率が高まっている原因です。
ガンの場合は急死してしまうことは少なく、治療を継続するようになることも珍しくありません。
その結果猫と少しでも長く共に生きることができますが、介護をしなければならないため、飼い主には介護の仕方などを身に付ける必要があります。
また、猫の医療のレベルも高まったことも猫が長生きできるようになった理由でもあります。
 老衰してしまった猫に何ができるのか悩んでしまった経験がある人も多いのではないでしょうか。
老衰になるとどうしても最期の時が違うこともあるため、より一層最後にできることを考えやすいです。
次に、老衰した猫にしてあげることを紹介するので参考にしてください。
老衰してしまった猫に何ができるのか悩んでしまった経験がある人も多いのではないでしょうか。
老衰になるとどうしても最期の時が違うこともあるため、より一層最後にできることを考えやすいです。
次に、老衰した猫にしてあげることを紹介するので参考にしてください。
 猫の死に目に会うことが難しいことを知っているでしょうか。
例え飼い猫であったとしても老衰してしまい、最期が近くなると知らない間にどこかに行ってしまい、そのまま会うことがないことも珍しいことではありません。
猫は弱ると誰の目にも触れない場所に隠れる習慣があり、飼い猫でも変わりません。
そのため、老衰した猫がどこかにいってしまったのであればそのまま一匹で逝かせてあげることも一つの方法と言えます。
しかし、見送る側からすれば寂しい別れ方でもあります。
猫の死に目に会うことが難しいことを知っているでしょうか。
例え飼い猫であったとしても老衰してしまい、最期が近くなると知らない間にどこかに行ってしまい、そのまま会うことがないことも珍しいことではありません。
猫は弱ると誰の目にも触れない場所に隠れる習慣があり、飼い猫でも変わりません。
そのため、老衰した猫がどこかにいってしまったのであればそのまま一匹で逝かせてあげることも一つの方法と言えます。
しかし、見送る側からすれば寂しい別れ方でもあります。
 猫の老衰を予防することができるのか知りたい人もいるのではないでしょうか。
老衰してしまうことは猫に限らず生物であれば避けて通ることができない道ではありますが、少しの異常に早く気づくことができれば、長生きすることもあります。
次に、老衰することに対する予防方法を紹介します。
猫の老衰を予防することができるのか知りたい人もいるのではないでしょうか。
老衰してしまうことは猫に限らず生物であれば避けて通ることができない道ではありますが、少しの異常に早く気づくことができれば、長生きすることもあります。
次に、老衰することに対する予防方法を紹介します。
 人も健康体を維持するために定期検診を受けますが、猫も健康診断を受けることをおすすめします。
若くてもどんな病気が潜んでいるのかわからないため、1歳から毎年1回は健康診断するようにしましょう。
しかし、高齢になればなるほど体に異常が起きてしまうリスクが高まるため、7歳以上から毎年2回健康診断を受けることをおすすめします。
飼い主にとっては健康診断の頻度を増やすことは経済的に苦しくなったり、面倒と感じてしまう場合もありますが、大きな病気を見逃してしまった際と比べれば負担は少ないです。
人も健康体を維持するために定期検診を受けますが、猫も健康診断を受けることをおすすめします。
若くてもどんな病気が潜んでいるのかわからないため、1歳から毎年1回は健康診断するようにしましょう。
しかし、高齢になればなるほど体に異常が起きてしまうリスクが高まるため、7歳以上から毎年2回健康診断を受けることをおすすめします。
飼い主にとっては健康診断の頻度を増やすことは経済的に苦しくなったり、面倒と感じてしまう場合もありますが、大きな病気を見逃してしまった際と比べれば負担は少ないです。
 猫は約9500年前から人間のパートナーとして、扱われていたと考えられています。
砂漠地帯に生息しているリビアヤマネコが猫の起源だとすると、エジプトからヨーロッパ、アジアへと広がり中国から日本にやって来たと考えるのが自然かもしれません。
猫がネズミを追いかけたり小さくて素早く動くものを捕らえようとする習性は、リビアヤマネコが小鳥やネズミなどの小動物を獲物にしていたからだと思われます。
現代で猫がペットとして人間と一緒に暮らすようになった過程には、どのような歴史があるのかを調べてみました。
猫は約9500年前から人間のパートナーとして、扱われていたと考えられています。
砂漠地帯に生息しているリビアヤマネコが猫の起源だとすると、エジプトからヨーロッパ、アジアへと広がり中国から日本にやって来たと考えるのが自然かもしれません。
猫がネズミを追いかけたり小さくて素早く動くものを捕らえようとする習性は、リビアヤマネコが小鳥やネズミなどの小動物を獲物にしていたからだと思われます。
現代で猫がペットとして人間と一緒に暮らすようになった過程には、どのような歴史があるのかを調べてみました。
 猫(イエネコ)とリビアヤマネコの共通点は性格にも見られ、ネコ科の動物の中でも人懐っこい所が特徴です。
リビアヤマネコは比較的警戒心が薄く子猫の頃から人間に育てられると家族のような関係になれますが、ペットとして流通できる種類の猫ではなく飼うには無理があります。
海外の一部の動物園でリビアヤマネコを展示している所もあるようですが、残念ながら日本では見る事のできない猫です。
猫の祖先であるリビアヤマネコを実際に見たり飼うチャンスはありませんが、現代に存在している猫から想像できるのではないでしょうか?
猫(イエネコ)とリビアヤマネコの共通点は性格にも見られ、ネコ科の動物の中でも人懐っこい所が特徴です。
リビアヤマネコは比較的警戒心が薄く子猫の頃から人間に育てられると家族のような関係になれますが、ペットとして流通できる種類の猫ではなく飼うには無理があります。
海外の一部の動物園でリビアヤマネコを展示している所もあるようですが、残念ながら日本では見る事のできない猫です。
猫の祖先であるリビアヤマネコを実際に見たり飼うチャンスはありませんが、現代に存在している猫から想像できるのではないでしょうか?
 海外と日本には、猫がネズミ捕りとして活躍してきた歴史があります。
世界中で可愛がられ人間の近くで生活を共にするようになったのは、愛らしい見た目や人懐こい性格の他にネズミによる被害を防ぐ為に飼いはじめたのが理由のひとつです。
ネズミは伝染病を媒介したり穀物を荒らしてしまう為、猫が捕らえる事で感染拡大の予防につながり人間の大切な食料を守ってくれます。
人間に危害を加えない点がどの国でも重宝され、ネコを飼いはじめた理由にあげられます。
海外と日本には、猫がネズミ捕りとして活躍してきた歴史があります。
世界中で可愛がられ人間の近くで生活を共にするようになったのは、愛らしい見た目や人懐こい性格の他にネズミによる被害を防ぐ為に飼いはじめたのが理由のひとつです。
ネズミは伝染病を媒介したり穀物を荒らしてしまう為、猫が捕らえる事で感染拡大の予防につながり人間の大切な食料を守ってくれます。
人間に危害を加えない点がどの国でも重宝され、ネコを飼いはじめた理由にあげられます。
 7世紀にキリスト教が異端とみなしたグリーシス派を「黒猫に姿を変えた悪魔と手を組んでいる」と非難した事から猫が迫害されるようになります。
中世ヨーロッパの魔女裁判によって、猫は「魔女の手先」と疑われ大量虐殺が始まってしまいます。
しかし猫がいなくなった事でペストが大流行してしまい、その原因となるネズミを追い払うためヨーロッパの人々は迫害をやめて再び猫を飼育するようになります。
7世紀にキリスト教が異端とみなしたグリーシス派を「黒猫に姿を変えた悪魔と手を組んでいる」と非難した事から猫が迫害されるようになります。
中世ヨーロッパの魔女裁判によって、猫は「魔女の手先」と疑われ大量虐殺が始まってしまいます。
しかし猫がいなくなった事でペストが大流行してしまい、その原因となるネズミを追い払うためヨーロッパの人々は迫害をやめて再び猫を飼育するようになります。
 日本では約2000年前の弥生時代から猫がいた形跡が残っていて、平安時代には宇多天皇の日記「寛平御記」に登場し古くから愛されていました。
ネズミを獲物とする猫は穀物の倉庫番として重宝され、人間と一緒に暮らす事によって双方に利益が生まれます。
猫は人間の傍にいれば水や食べ物がもらえて、天敵からも守られ安全に暮らせるようになります。
人間はネズミの害から救ってくれた猫を、富や豊かさの象徴や守り神としても親しむようになります。
日本では約2000年前の弥生時代から猫がいた形跡が残っていて、平安時代には宇多天皇の日記「寛平御記」に登場し古くから愛されていました。
ネズミを獲物とする猫は穀物の倉庫番として重宝され、人間と一緒に暮らす事によって双方に利益が生まれます。
猫は人間の傍にいれば水や食べ物がもらえて、天敵からも守られ安全に暮らせるようになります。
人間はネズミの害から救ってくれた猫を、富や豊かさの象徴や守り神としても親しむようになります。
 平安時代になると、ようやく猫は現在のように愛玩動物として飼われるようになりました。
しかし貴重な存在だったため高貴な身分の限られた人物のみにしか飼育は許されず、貴族の間では猫を飼う事が密かに流行っていたようです。
887年に天皇に即位した宇多天皇は猫好きで知られていて、父親から譲り受けた黒猫を可愛がっていました。
「寛平御記」に綴られている猫の様子はよく観察されていて、現代の猫ブログのルーツになるかもしれません。
一条天皇も猫好きで知られていて、猫の誕生日を祝う儀式や飼っていた猫に階位を与えたという話もあります。
平安時代になると、ようやく猫は現在のように愛玩動物として飼われるようになりました。
しかし貴重な存在だったため高貴な身分の限られた人物のみにしか飼育は許されず、貴族の間では猫を飼う事が密かに流行っていたようです。
887年に天皇に即位した宇多天皇は猫好きで知られていて、父親から譲り受けた黒猫を可愛がっていました。
「寛平御記」に綴られている猫の様子はよく観察されていて、現代の猫ブログのルーツになるかもしれません。
一条天皇も猫好きで知られていて、猫の誕生日を祝う儀式や飼っていた猫に階位を与えたという話もあります。
 江戸時代後期には歌舞伎や浮世絵などのモチーフとして使われ、「猫ブーム」旋風が巻き起こっていました。
歌川国芳は江戸時代末期に活躍し、猫にまつわる浮世絵を数多く残した浮世絵師で愛猫家でも知られています。
明治には竹久夢二の美人画に描かれた猫が有名で、文芸作品でも猫が登場するものが多く見られ代表的なものには夏目漱石の「吾輩は猫である」があります。
世界でも、日本でも猫はいくつもの芸術のモチーフとされ、現在も多くの人々に愛され続け経済にも影響を与えるほどです。
第二次世界大戦が終わり庶民の生活にもゆとりがでてくると、猫を家族として飼う家庭も増えました。
猫の人気は年を追うごとに高まっていて、飼われている数も増え続けています。
江戸時代後期には歌舞伎や浮世絵などのモチーフとして使われ、「猫ブーム」旋風が巻き起こっていました。
歌川国芳は江戸時代末期に活躍し、猫にまつわる浮世絵を数多く残した浮世絵師で愛猫家でも知られています。
明治には竹久夢二の美人画に描かれた猫が有名で、文芸作品でも猫が登場するものが多く見られ代表的なものには夏目漱石の「吾輩は猫である」があります。
世界でも、日本でも猫はいくつもの芸術のモチーフとされ、現在も多くの人々に愛され続け経済にも影響を与えるほどです。
第二次世界大戦が終わり庶民の生活にもゆとりがでてくると、猫を家族として飼う家庭も増えました。
猫の人気は年を追うごとに高まっていて、飼われている数も増え続けています。
 猫が高い場所から落ちても怪我をしない理由を知っているでしょうか。
人はもちろん他の動物では大けがをしたり、命を落としてしまうような高さから落ちてもほぼ怪我をすることがない猫ですが、その理由について次に紹介するので参考にしてください。
猫が高い場所から落ちても怪我をしない理由を知っているでしょうか。
人はもちろん他の動物では大けがをしたり、命を落としてしまうような高さから落ちてもほぼ怪我をすることがない猫ですが、その理由について次に紹介するので参考にしてください。
 猫は高い場所から落下しても上記で紹介した理由から怪我をすることがなく、簡単に着地することができます。
しかし、いくら猫でも耐えることができない高さが存在しており、6~7m程度の高さであれば問題ないと言われ、建物でいうと2階くらいの高さです。
猫も落下した際に耐えられる高さを本能的に把握しているため、無謀に飛び降りて怪我をしてしまうことはありません。
ただし、猫の運動能力の差や体重の違いによって耐えられる高さも変わってくるため、肥満体質であり、運動不足の猫では2階の高さから落ちても怪我をしてしまう可能性があります。
猫は高い場所から落下しても上記で紹介した理由から怪我をすることがなく、簡単に着地することができます。
しかし、いくら猫でも耐えることができない高さが存在しており、6~7m程度の高さであれば問題ないと言われ、建物でいうと2階くらいの高さです。
猫も落下した際に耐えられる高さを本能的に把握しているため、無謀に飛び降りて怪我をしてしまうことはありません。
ただし、猫の運動能力の差や体重の違いによって耐えられる高さも変わってくるため、肥満体質であり、運動不足の猫では2階の高さから落ちても怪我をしてしまう可能性があります。
 猫は高い場所から落ちても無難に着地して怪我をしない印象を持たれやすいですが、条件がそろっていなければ怪我をしてしまったり、最悪死亡してしまうこともあります。
そのため、どのようなことで落下時に猫が怪我をしてしまうのかを把握しておくことをおすすめします。
猫は高い場所から落ちても無難に着地して怪我をしない印象を持たれやすいですが、条件がそろっていなければ怪我をしてしまったり、最悪死亡してしまうこともあります。
そのため、どのようなことで落下時に猫が怪我をしてしまうのかを把握しておくことをおすすめします。
 猫は本能的に落ちてはいけない高さを把握しているため、怪我をしてしまうような高さから自発的に飛び降りることはありません。
しかし、誤って滑ってしまい落ちてしまうことはあります。
猫は人と違って歩いている素材が滑りやすいのかそうではないのか判断することができないからです。
特にベランダの手すりは滑りやすい素材であり、表面がツルツルであるため、猫にとっては非常に滑りやすく、何かの対策を講じておくようにしましょう。
猫は本能的に落ちてはいけない高さを把握しているため、怪我をしてしまうような高さから自発的に飛び降りることはありません。
しかし、誤って滑ってしまい落ちてしまうことはあります。
猫は人と違って歩いている素材が滑りやすいのかそうではないのか判断することができないからです。
特にベランダの手すりは滑りやすい素材であり、表面がツルツルであるため、猫にとっては非常に滑りやすく、何かの対策を講じておくようにしましょう。
 運動不足では思うように体を動かすこともできなくなってしまい、体のキレも低下してしまいます。
そのような状態で高い場所から落ちてしまうと着地までに衝撃を緩和できる体勢をとることができず、着地失敗を招いてしまう原因となります。
そのため、運動不足の猫には運動をさせ肥満体質を解消させたり、高い場所に上ることができないような工夫をするようにしましょう。
また、運動不足では必然的に肥満体質になっている場合も多く、体重が重ければ着地時の衝撃も強くなってしまい、怪我の原因となります。
運動不足では思うように体を動かすこともできなくなってしまい、体のキレも低下してしまいます。
そのような状態で高い場所から落ちてしまうと着地までに衝撃を緩和できる体勢をとることができず、着地失敗を招いてしまう原因となります。
そのため、運動不足の猫には運動をさせ肥満体質を解消させたり、高い場所に上ることができないような工夫をするようにしましょう。
また、運動不足では必然的に肥満体質になっている場合も多く、体重が重ければ着地時の衝撃も強くなってしまい、怪我の原因となります。
 猫も本能的に危険な高さであることがわかれば無謀に落ちるような行動をすることはありませんが、上記でも紹介したように不可抗力が原因で落ちてしまうことも充分考えられます。
次に、猫が高い場所から落下してしまうことを予防する方法を紹介します。
高層に住んでいる場合は参考にしてください。
猫も本能的に危険な高さであることがわかれば無謀に落ちるような行動をすることはありませんが、上記でも紹介したように不可抗力が原因で落ちてしまうことも充分考えられます。
次に、猫が高い場所から落下してしまうことを予防する方法を紹介します。
高層に住んでいる場合は参考にしてください。
 脱走防止の柵を設置することで猫が部屋や家から出てしまうことを予防できます。
ちゃんと注意していれば猫が脱走してしまうことはないと考えてしまいやすいですが、いくら注意していても窓や玄関のドアを開けた隙に外に駆け出してしまうことも少なくありません。
窓などが開放されたと同時にジャンプして外に出ようとすることも多く、非常に危険な行動でもあります。
しかし、脱走防止柵を設置していれば不意に外に脱走されてしまうことがなくなり、猫を守ることができます。
脱走防止の柵を設置することで猫が部屋や家から出てしまうことを予防できます。
ちゃんと注意していれば猫が脱走してしまうことはないと考えてしまいやすいですが、いくら注意していても窓や玄関のドアを開けた隙に外に駆け出してしまうことも少なくありません。
窓などが開放されたと同時にジャンプして外に出ようとすることも多く、非常に危険な行動でもあります。
しかし、脱走防止柵を設置していれば不意に外に脱走されてしまうことがなくなり、猫を守ることができます。
 猫が落下してしまったのであれば注意しなければならないポイントがいくつかあります。
落下した後にしっかり様子見をして猫に異常がないかを確認することが大切です。
次に、猫が落下してしまった後の注意点をいくつか紹介するので、参考にしてください。
猫が落下してしまったのであれば注意しなければならないポイントがいくつかあります。
落下した後にしっかり様子見をして猫に異常がないかを確認することが大切です。
次に、猫が落下してしまった後の注意点をいくつか紹介するので、参考にしてください。
 落下した際にすぐに確認することができ、異常にいち早く気づくことができればそれだけ状態が重症化してしまうリスクを下げることができます。
落下した際に鼻血を流していないかやふらつきがないか、呼吸する速度が異常ではないかなどを確認しましょう。
どれか一つでも普段とは違う部分があるのであれば、何かしらの影響を受けている可能性が高いので動物病院で診察してもらいましょう。
脳になんらかの影響があれば上記で紹介したような症状があらわれやすいです。
落下した際にすぐに確認することができ、異常にいち早く気づくことができればそれだけ状態が重症化してしまうリスクを下げることができます。
落下した際に鼻血を流していないかやふらつきがないか、呼吸する速度が異常ではないかなどを確認しましょう。
どれか一つでも普段とは違う部分があるのであれば、何かしらの影響を受けている可能性が高いので動物病院で診察してもらいましょう。
脳になんらかの影響があれば上記で紹介したような症状があらわれやすいです。
 猫は人と同じように骨に強い衝撃が加わることで骨折してしまうことがあります。
次に、猫が骨折してしまう原因を紹介します。
知らない間に猫が骨折してしまったのであれば下記に紹介している原因に当てはまるものがないかを確認しましょう。
猫は人と同じように骨に強い衝撃が加わることで骨折してしまうことがあります。
次に、猫が骨折してしまう原因を紹介します。
知らない間に猫が骨折してしまったのであれば下記に紹介している原因に当てはまるものがないかを確認しましょう。
 落下することで骨折してしまうのは高い場所から落ちた時と考えてしまいがちですが、低い場所からの落下の方が骨折しやすいです。
特に、室内で飼われている猫ほど低い段差で骨折してしまうことがあります。
その理由は運動不足も関係していますが、落下した瞬間から着地するまでの時間が極端に短く、十分な着地体勢をとることができないからです。
そのため、ソファーのふちやバスタブなどの高さからの落下の方が骨折のリスクが高く、逆にタンスなどの高さからの落下では骨折することはほとんどありません。
落下することで骨折してしまうのは高い場所から落ちた時と考えてしまいがちですが、低い場所からの落下の方が骨折しやすいです。
特に、室内で飼われている猫ほど低い段差で骨折してしまうことがあります。
その理由は運動不足も関係していますが、落下した瞬間から着地するまでの時間が極端に短く、十分な着地体勢をとることができないからです。
そのため、ソファーのふちやバスタブなどの高さからの落下の方が骨折のリスクが高く、逆にタンスなどの高さからの落下では骨折することはほとんどありません。
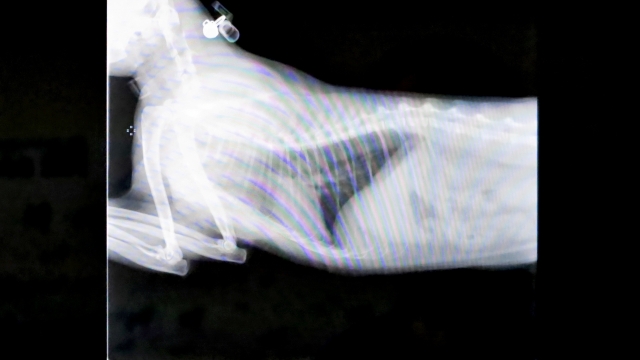 猫が骨折しているかどうかを確認することができれば素早い対応をすることができますが、なかなか見極めることは難しいです。
猫は骨折すると物陰に隠れていたり、食欲や元気がなくなる場合が多いです。
そのほかにも体に触れられることに嫌がったり、トイレでの排泄の格好が不自然になりやすく、足を引きずるように歩くようになります。
最後の足を引きずることは骨折していることを確認しやすいですが、物陰に隠れたり、元気や食欲がないだけでは骨折を疑わない場合も多く、発見が遅れてしまいやすいです。
普段から猫の様子をよく確認し、少しでもいつもと違う部分があると感じるのであればより注意深く観察しましょう。
元気がないことや食欲がないことは骨折以外が原因でもあるので、病院で詳しく検査してもらうようにすることをおすすめします。
猫が骨折しているかどうかを確認することができれば素早い対応をすることができますが、なかなか見極めることは難しいです。
猫は骨折すると物陰に隠れていたり、食欲や元気がなくなる場合が多いです。
そのほかにも体に触れられることに嫌がったり、トイレでの排泄の格好が不自然になりやすく、足を引きずるように歩くようになります。
最後の足を引きずることは骨折していることを確認しやすいですが、物陰に隠れたり、元気や食欲がないだけでは骨折を疑わない場合も多く、発見が遅れてしまいやすいです。
普段から猫の様子をよく確認し、少しでもいつもと違う部分があると感じるのであればより注意深く観察しましょう。
元気がないことや食欲がないことは骨折以外が原因でもあるので、病院で詳しく検査してもらうようにすることをおすすめします。
 猫が骨折してしまったのであれば治療する必要があります。
治療が早ければ早いほど完治までの期間を短くすることもできます。
次に、猫の骨折の治療方法について詳しく紹介するため、どのような方法で骨折を治すのか知りたい人は参考にしてください。
猫が骨折してしまったのであれば治療する必要があります。
治療が早ければ早いほど完治までの期間を短くすることもできます。
次に、猫の骨折の治療方法について詳しく紹介するため、どのような方法で骨折を治すのか知りたい人は参考にしてください。
 プレート法の治療は骨折した場所を開き、金属の板で固定する方法です。
メリットは手術したその翌日には歩くことができることと骨折した骨を元の形に生成しやすいことです。
デメリットは骨が生成されるスピードが遅く、新しくできた骨の強度も低いので、再び骨折してしまうリスクが高いことです。
最悪プレートが折れてしまったり、外れてしまうリスクもあります。
金属製のプレートは骨が再構築された後も取り除くことはないため、その後も体の中に入ったままとなります。
プレート法の治療は骨折した場所を開き、金属の板で固定する方法です。
メリットは手術したその翌日には歩くことができることと骨折した骨を元の形に生成しやすいことです。
デメリットは骨が生成されるスピードが遅く、新しくできた骨の強度も低いので、再び骨折してしまうリスクが高いことです。
最悪プレートが折れてしまったり、外れてしまうリスクもあります。
金属製のプレートは骨が再構築された後も取り除くことはないため、その後も体の中に入ったままとなります。
 髄内ピン法は骨髄部分に金属のピンを通し固定する方法です。
骨折部分を支えることはできますが、固定する力が弱いのでギプスを装着するようになります。
骨折部分を開く方法と開かない方法があり、開かなければ傷や骨折の治りも早いメリットがあります。
開いてしまうとあまりメリットになることは少なく、回復するスピードも遅くなってしまいます。
ギプスを使用しても他の治療法による固定力よりも弱いというデメリットがあります。
髄内ピン法は骨髄部分に金属のピンを通し固定する方法です。
骨折部分を支えることはできますが、固定する力が弱いのでギプスを装着するようになります。
骨折部分を開く方法と開かない方法があり、開かなければ傷や骨折の治りも早いメリットがあります。
開いてしまうとあまりメリットになることは少なく、回復するスピードも遅くなってしまいます。
ギプスを使用しても他の治療法による固定力よりも弱いというデメリットがあります。
 猫はさまざまな原因で骨折してしまいます。
しかし、予防法を行っていればある程度骨折してしまうリスクを下げることができます。
次に、猫の骨折を予防する方法をいくつか紹介します。
過去に骨折をしてしまった経験がある場合やたびたび骨折しているのであれば参考にしてください。
猫はさまざまな原因で骨折してしまいます。
しかし、予防法を行っていればある程度骨折してしまうリスクを下げることができます。
次に、猫の骨折を予防する方法をいくつか紹介します。
過去に骨折をしてしまった経験がある場合やたびたび骨折しているのであれば参考にしてください。
 猫を外に出さないようにすることも骨折予防になります。
外に出れば落下事故はもちろんですが、交通事故に巻き込まれてしまうリスクが高まってしまいます。
そのため、放し飼いにしていればそれだけ骨折してしまうトラブルに巻き込まれてしまいやすくなります。
猫に骨折させないためには室内飼いにして、極力室内で飼育するように心がけましょう。
以前までは放し飼いで急に室内飼いに慣れさせることは難しく、猫もストレスを感じやすくなるため、できるのであれば子猫の時から完全室内飼いをすることをおすすめします。
猫を外に出さないようにすることも骨折予防になります。
外に出れば落下事故はもちろんですが、交通事故に巻き込まれてしまうリスクが高まってしまいます。
そのため、放し飼いにしていればそれだけ骨折してしまうトラブルに巻き込まれてしまいやすくなります。
猫に骨折させないためには室内飼いにして、極力室内で飼育するように心がけましょう。
以前までは放し飼いで急に室内飼いに慣れさせることは難しく、猫もストレスを感じやすくなるため、できるのであれば子猫の時から完全室内飼いをすることをおすすめします。
 猫が骨折した際の治療費はいくら程度になるか知らない人も多いのではないでしょうか。
しかし、どのような原因で骨折してしまうかわからないため、どの程度治療費が必要になるかは知っておいて損することはありません。
骨折の治療費は骨折の具合や治療法によって変化しますが、治療・入院・薬代・検査など一式まとめて10~30万円程度かかる場合が多いです。
過去には80万円程度の治療費になってしまうこともあり、骨折してしまうと余計な費用がかかってしまうことは把握しておきましょう。
猫が骨折した際の治療費はいくら程度になるか知らない人も多いのではないでしょうか。
しかし、どのような原因で骨折してしまうかわからないため、どの程度治療費が必要になるかは知っておいて損することはありません。
骨折の治療費は骨折の具合や治療法によって変化しますが、治療・入院・薬代・検査など一式まとめて10~30万円程度かかる場合が多いです。
過去には80万円程度の治療費になってしまうこともあり、骨折してしまうと余計な費用がかかってしまうことは把握しておきましょう。