犬とドライブに出かける時の注意点
 犬との暮らしに慣れてきたら、一緒にドライブしてお出かけや旅行を楽しんでみたいですよね。
近所の散歩ももちろん楽しいですが、車に乗って外出ができると行動範囲が広がり、愛犬の喜ぶ顔もたくさん見られます。
ただ犬とドライブに出かける時には注意点やマナー等知っておいたほうが良いことがありますので、それらの情報をお伝えします。
ぜひ愛犬との楽しいドライブに役立ててください。
犬との暮らしに慣れてきたら、一緒にドライブしてお出かけや旅行を楽しんでみたいですよね。
近所の散歩ももちろん楽しいですが、車に乗って外出ができると行動範囲が広がり、愛犬の喜ぶ顔もたくさん見られます。
ただ犬とドライブに出かける時には注意点やマナー等知っておいたほうが良いことがありますので、それらの情報をお伝えします。
ぜひ愛犬との楽しいドライブに役立ててください。
犬はクレートやキャリーに入れて座席に固定する
犬を車のどこに乗せるのかということです。
助手席、後部座席、ラゲッジルーム等様々ですが、犬の安全を考えると、クレートやキャリー、ケージに入れて座席に固定するという方法がベストです。
交通事故や揺れ等による怪我を防止するためには、ハードタイプのクレートが良いでしょう。
座席にしっかり固定するグッズも一緒に用意するのがおすすめです。
人間もシートベルトをすることで怪我から身を守っています。
車内でフリーにしておくことは危険な場合が多いので避けたほうが賢明です。
トイレは事前に済ませる
 車に乗る前には必ずトイレを済ませておきます。
排泄をしなければ車には乗せないということを徹底すれば、必ず排泄するように習慣づけられます。
そして長めのドライブの際は途中でトイレタイムを取ったり、帰りの乗車前にもトイレをさせることを忘れないようにしましょう。
また途中でのトイレをさせないために、水分を制限するのは間違っています。
脱水状態になるかもしれませんし、のどが渇いていると一気ににガブ飲みして体調不良の原因にもなりかねません。
適度に水分を与え、トイレタイムが取れるようなドライブ計画を立てましょう。
車に乗る前には必ずトイレを済ませておきます。
排泄をしなければ車には乗せないということを徹底すれば、必ず排泄するように習慣づけられます。
そして長めのドライブの際は途中でトイレタイムを取ったり、帰りの乗車前にもトイレをさせることを忘れないようにしましょう。
また途中でのトイレをさせないために、水分を制限するのは間違っています。
脱水状態になるかもしれませんし、のどが渇いていると一気ににガブ飲みして体調不良の原因にもなりかねません。
適度に水分を与え、トイレタイムが取れるようなドライブ計画を立てましょう。
車内の温度は20度を目安にする
犬にとっては環境が変わることはストレスになることがあります。
車の揺れや独特の匂いに敏感ですが、車内の温度にも気をつけてあげてください。
犬の体に負担をかけない20℃前後が適温です。
暑すぎても寒すぎてもよくありませんが、夏場は特に注意が必要です。
犬が乗っている場所には涼しい風が当たらず、熱中症になりやすいということがあります。
クレートやキャリーは直射日光が当たらないことや温度が適切かどうかを確認しておきましょう。
ドライブ中の違反行為は絶対に避ける
 犬を車に乗せる際、交通違反となる乗せ方があります。
膝の上に乗せて運転していたり、ドアの窓を開けて、顔を外に出したりすることです。
道路交通法では「運転者は視野もしくはハンドル等の操作を妨げる行為となる乗車をさせていけない。」とあります。
犬が窓から顔を出していた時に衝突されて窓から飛び出してしまったり、急ブレーキをかけた時に膝から落ちて怪我をしたりというような事故が実際に起こっています。
助手席にそのまま乗せる行為も犬が怪我をする場合があります。
愛犬の安全を第一に考えましょう。
犬を車に乗せる際、交通違反となる乗せ方があります。
膝の上に乗せて運転していたり、ドアの窓を開けて、顔を外に出したりすることです。
道路交通法では「運転者は視野もしくはハンドル等の操作を妨げる行為となる乗車をさせていけない。」とあります。
犬が窓から顔を出していた時に衝突されて窓から飛び出してしまったり、急ブレーキをかけた時に膝から落ちて怪我をしたりというような事故が実際に起こっています。
助手席にそのまま乗せる行為も犬が怪我をする場合があります。
愛犬の安全を第一に考えましょう。
休憩はこまめに取る
長いドライブは、犬にとって大きなストレスになります。
2~3時間を超えてしまう場合は、途中で車を止め、適度な休憩を取りましょう。
トイレタイムにもつながり、犬の体調を確認することもできます。
犬を車から出して、軽く散歩をしたり飲み物を与えたりして様子を見て、飼い主も一緒にリフレッシュしましょう。
高速道路のサービスエリアや道の駅などにはドッグランも増えてきていますので、そういう場所を上手に利用してください。
停車中に留守番をさせない
 長いドライブになると、犬を車内に留守番させて食事などの時間をとるということがあるかもしれません。
どの季節でもそうですが、特に暑さが厳しい夏場は、エンジンが止まった車中に犬を一匹で留守番させてはいけません。
ほんの短い間でも車内の温度は高温となり、熱中症にかかってしまいます。
また窓を開けて車を離れることも危険です。
飼い主を追いかけて窓から飛び出したりする可能性があるからです。
人間が交代で車内に残るような方法を取り、犬だけにすることは絶対に避けましょう。
長いドライブになると、犬を車内に留守番させて食事などの時間をとるということがあるかもしれません。
どの季節でもそうですが、特に暑さが厳しい夏場は、エンジンが止まった車中に犬を一匹で留守番させてはいけません。
ほんの短い間でも車内の温度は高温となり、熱中症にかかってしまいます。
また窓を開けて車を離れることも危険です。
飼い主を追いかけて窓から飛び出したりする可能性があるからです。
人間が交代で車内に残るような方法を取り、犬だけにすることは絶対に避けましょう。
犬とドライブに出かける時のマナー&ステップ
 人間でも車酔いを起こす人がいるように犬にも車酔いがあります。
車に慣れていない犬にとってはとてもストレスフルな乗り物であることを知っておいてください。
ですから落ち着いて車に乗れるように少しずつステップを踏んで練習をしていきましょう。
人間でも車酔いを起こす人がいるように犬にも車酔いがあります。
車に慣れていない犬にとってはとてもストレスフルな乗り物であることを知っておいてください。
ですから落ち着いて車に乗れるように少しずつステップを踏んで練習をしていきましょう。
ステップ①:クレート・ハーネスには慣れさせておく
犬を乗車させる時にはクレートに入れるか、車用のハーネスに繋いだ状態にします。
まずはそのクレートやハーネスに慣れさせることです。
いきなりクレートに入れようとしても無理なので、少しずつ練習していきます。
クレートの中におやつを用意して自分から入ってもらうというところから始めて、入って静かに待機できる時間を伸ばしていきます。
扉を閉めても大丈夫な状態まで毎日少しずつ時間を増やします。
そうして車に乗せたクレートにも「ハウス」の指示で入れるように準備を整えていきましょう。
ハーネスの場合も同じで少しずつ慣れさせてください。
ステップ②:車内環境に慣れさせる
 犬がクレートやハーネスに慣れたら、車に乗るという行動と、車内の環境に慣れさせてあげる必要があります。
いきなりエンジンを掛けるのではなく、車を止めた状態でおやつやおもちゃを与えて、「車の乗ること=楽しいこと」を覚えさせてください。
車に乗った瞬間に褒めておやつを与えます。
ハーネスをつけた後やクレートの扉を締めた時などにもまたおやつをあげます。
その繰り返しで犬は「車に乗ると良いことがある」と覚えていくのです。
大好きなおもちゃをクレートに入れておくのも良いでしょうし、車に乗ってしばらくおもちゃで遊んであげるのも効果的です。
そして車内の匂いをできるだけ消しておきましょう。
犬の嗅覚は人間の何十倍も敏感なので嫌な匂いがストレスになることがあります。
また犬が乗った後の匂いも消しておくように消臭剤を準備しておきましょう。
犬がクレートやハーネスに慣れたら、車に乗るという行動と、車内の環境に慣れさせてあげる必要があります。
いきなりエンジンを掛けるのではなく、車を止めた状態でおやつやおもちゃを与えて、「車の乗ること=楽しいこと」を覚えさせてください。
車に乗った瞬間に褒めておやつを与えます。
ハーネスをつけた後やクレートの扉を締めた時などにもまたおやつをあげます。
その繰り返しで犬は「車に乗ると良いことがある」と覚えていくのです。
大好きなおもちゃをクレートに入れておくのも良いでしょうし、車に乗ってしばらくおもちゃで遊んであげるのも効果的です。
そして車内の匂いをできるだけ消しておきましょう。
犬の嗅覚は人間の何十倍も敏感なので嫌な匂いがストレスになることがあります。
また犬が乗った後の匂いも消しておくように消臭剤を準備しておきましょう。
ステップ③:車の振動に慣れさせる
車内の環境に犬が慣れてきたら、次は車のエンジンをかけて、車体全体を振動させてみましょう。
クレートは後部座席でしっかりと固定させ、ハーネスもシートベルト等に固定します。
エンジンを掛けて車が振動してもじっとしていたら、すぐに褒めておやつをあげます。
最初は5秒でも構いません。
少しずつ時間を伸ばしていきます。
犬が吠えたりした時にはなでたりかまったりしないで待ちます。
吠えるのをやめた時にすぐ褒めておやつを与えます。
その瞬間を見逃さないで、「おとなしくしていたら良いことがある」ということを理解させましょう。
何度か繰り返せばきちんとわかるようになります。
ステップ④:車を使った移動に慣れさせる
 車体の振動に犬が充分に慣れてきたら、今度は運転にトライしましょう。
最初は家の近くを1周する程度で大丈夫です。
よくある失敗の一つが車でのお出かけが病院で注射を打つことです。
「車に乗ったら病院」では楽しくありません。
公園やドッグランなど楽しいと思える場所に連れていきましょう。
10分程度で行ける場所でも練習と思って車に乗せるとよいでしょう。
犬が静かにして落ち着いている時によく褒めておやつをあげましょう。
そして目的地に着いたら、車から降りてたくさん散歩したり、遊んだりすると犬も車に乗ることが楽しくなってきます。
家の近くから始めて、少しずつ距離を伸ばし30分程度のドライブに付き合ってくれるようになれば安心です。
車体の振動に犬が充分に慣れてきたら、今度は運転にトライしましょう。
最初は家の近くを1周する程度で大丈夫です。
よくある失敗の一つが車でのお出かけが病院で注射を打つことです。
「車に乗ったら病院」では楽しくありません。
公園やドッグランなど楽しいと思える場所に連れていきましょう。
10分程度で行ける場所でも練習と思って車に乗せるとよいでしょう。
犬が静かにして落ち着いている時によく褒めておやつをあげましょう。
そして目的地に着いたら、車から降りてたくさん散歩したり、遊んだりすると犬も車に乗ることが楽しくなってきます。
家の近くから始めて、少しずつ距離を伸ばし30分程度のドライブに付き合ってくれるようになれば安心です。
ステップ⑤:車から降りる時に注意すること
車に乗り終わったら、犬を車外に出してあげます。
実はこの時が一番危険なので、何倍も注意が必要です。
犬は開放されたという気持ちでいっぱいで、テンションも上がっています。
飼い主も無事に目的地に着いた安心感があり、ちょっと油断してしまうことも多いです。
そんな油断もあって、車から降りた途端に走り出してしまい事故に合うというケースが多いのです。
車から降りる時には次の項目にくれぐれも注意して、事故が起こらないようにしましょう。
犬の脱走を防止する
 一番多い事故は犬が脱走してしまうことです。
犬を車外に出す際は、ドアを開く前にハーネスや首輪を装着し、リードに繋いだ状態にして、脱走を阻止します。
小型犬の場合にはリードに繋いだ状態で飼い主が抱っこして車から降ろすと良いでしょう。
またとても抱っこができない体重の犬もいますので、ドアを開けてもすぐに外に出ないというしつけをしましょう。
そのためには普段から「マテ」を教え、許可が出てから車から降りるということを毎回必ず行います。
車から出たときもおすわりをさせて、おやつをあげるようにしていると習慣となり、すぐに走り出そうとしないようになります。
一番多い事故は犬が脱走してしまうことです。
犬を車外に出す際は、ドアを開く前にハーネスや首輪を装着し、リードに繋いだ状態にして、脱走を阻止します。
小型犬の場合にはリードに繋いだ状態で飼い主が抱っこして車から降ろすと良いでしょう。
またとても抱っこができない体重の犬もいますので、ドアを開けてもすぐに外に出ないというしつけをしましょう。
そのためには普段から「マテ」を教え、許可が出てから車から降りるということを毎回必ず行います。
車から出たときもおすわりをさせて、おやつをあげるようにしていると習慣となり、すぐに走り出そうとしないようになります。
飛び降りを防ぐ
中型犬や大型犬の場合、後部座席やラゲッジルームから犬が飛び降りることが多いと思います。
この行動は犬の足に大きな負担となることがわかりました。
前足の関節を痛めたり、怪我につながる可能性があります。
ですからペット用スロープを用意してあげたり、地面と車の間に足場となるステップを付けてあげると、前足に負担がかからず降りることができます。
シニア犬になってくるといろいろ工夫をする飼い主が多いですが、若い内からできるだけジャンプさせずに車から下ろすようにしましょう。
トイレタイムを設ける
 犬の膀胱に尿が溜まっている際は、車から降りたタイミングがトイレタイムとなります。
なるべく水はけの良い場所を選び、終わった後は水をかけたり、きれいに処理することがマナーです。
公共の場所に犬を連れて行く時は特に気をつけてトイレ場所も選ぶようにしましょう。
駐車場などは誰もが通る場所なので、匂いかぎをさせないようにして排泄を避けるべきです。
また飼い主のトイレタイムの時には、車の中で犬だけにならないように配慮することも大切です。
車の外へ出して係留しておくことは連れ去りや脱走の事故がありますのでやめましょう。
犬の膀胱に尿が溜まっている際は、車から降りたタイミングがトイレタイムとなります。
なるべく水はけの良い場所を選び、終わった後は水をかけたり、きれいに処理することがマナーです。
公共の場所に犬を連れて行く時は特に気をつけてトイレ場所も選ぶようにしましょう。
駐車場などは誰もが通る場所なので、匂いかぎをさせないようにして排泄を避けるべきです。
また飼い主のトイレタイムの時には、車の中で犬だけにならないように配慮することも大切です。
車の外へ出して係留しておくことは連れ去りや脱走の事故がありますのでやめましょう。
犬とドライブする際の危険な乗り方
 犬とのドライブは楽しいものですが、残念ながら危険な乗り方をしている飼い主もいます。
安全を守れず命の危険があったり、道路交通法に違反して逮捕されたというケースもあります。
危険な乗せ方を知り、正しい方法で安全に犬とのドライブを楽しみましょう。
犬とのドライブは楽しいものですが、残念ながら危険な乗り方をしている飼い主もいます。
安全を守れず命の危険があったり、道路交通法に違反して逮捕されたというケースもあります。
危険な乗せ方を知り、正しい方法で安全に犬とのドライブを楽しみましょう。
膝の上に乗せながら運転する
直接愛犬を膝の上に乗せるのは危険です。
どんなに注意深く運転している場合でも、運転者の視野やハンドル操作を妨害する可能性があるからです。
このような方法で乗せることは道路交通法に違反しており、実際に現行犯逮捕された人もいます。
犬はいつも飼い主の膝の上に座っているとは限らず、動き回ることが考えられるので、とても危険な行為です。
ほんの近い距離だからというような考えはせず、絶対にやめましょう。
助手席に乗せている
 助手席に人がいないからと、愛犬をそこに座らせたり、もしくは助手席に座っている人の膝に乗せることも、大変危険です。
助手席にはエアバッグがついており、それが膨らんだ際にエアバッグの衝撃で犬が怪我をするという事故も起きています。
後部座席では犬の様子が見られないと心配するのはわかりますが、この記事で紹介しているように少しずつ車に慣れさせ、落ち着いて乗っていられるように努力してみてください。
助手席に人がいないからと、愛犬をそこに座らせたり、もしくは助手席に座っている人の膝に乗せることも、大変危険です。
助手席にはエアバッグがついており、それが膨らんだ際にエアバッグの衝撃で犬が怪我をするという事故も起きています。
後部座席では犬の様子が見られないと心配するのはわかりますが、この記事で紹介しているように少しずつ車に慣れさせ、落ち着いて乗っていられるように努力してみてください。
車内で自由な状態にしている
運転中に車内で愛犬を自由にさせている状態は、道路交通法第55条第2項に抵触するのでよく注意が必要です。
急ブレーキや追突された場合、シートベルトをしていない犬はフロントガラスに飛び込んでしまうかもしれません。
そこまで大怪我はなくとも、ぶつかって怪我をしたり、運転に支障が出ることが考えられます。
窓を開けていて外へ飛び出したという犬も実際にいます。
自由な状態ではなく、ハーネスで車に固定するか、クレートを利用するのが安全で安心な乗り方です。
まとめ
犬を車に乗せる時の注意点と慣れさせるコツを紹介しました。
車に慣れてくると落ち着いていられるようになり、飼い主も犬も安心してドライブができ活動範囲が広がります。
少しずつステップを踏んで車に慣れさせましょう。
そしてくれぐれも危険な乗り方をさせないようにして安全走行を守ってください。
犬とのドライブを想定してデザインされたドッグフレンドリーカーがあったり、車内で使える便利なペット用アイテムもいろいろと販売されています。
上手に活用してドライブを楽しんでください。
犬がため息をつく理由とは?
 犬を長く飼っていたり、よく観察していれば時々ため息をつくことを見たことがあるのではないでしょうか。
犬の人と同じように感情があるため、さまざまな気持な時にため息をします。
ため息をする理由によっては問題視する必要がない場合もあれば注意しなければならない場合もあります。
そのため、頻繁にため息をしている姿を見るのであればどのような理由からため息をついているのかを把握して、より原因に近い理由を知るようにしましょう。
犬を長く飼っていたり、よく観察していれば時々ため息をつくことを見たことがあるのではないでしょうか。
犬の人と同じように感情があるため、さまざまな気持な時にため息をします。
ため息をする理由によっては問題視する必要がない場合もあれば注意しなければならない場合もあります。
そのため、頻繁にため息をしている姿を見るのであればどのような理由からため息をついているのかを把握して、より原因に近い理由を知るようにしましょう。
満足している
散歩をしている際や自宅に帰った際にため息をいるついているのであれば散歩に満足している可能性が高いです。
そのため、散歩中や散歩後にため息をついているのであれば散歩する時間やコースには問題ないと言えます。
そのほかにも周りのにおいを吸うためにため息をしている場合もあります。
においを吸うためには一度肺の中の空気を吐き出したほうが多くの空気を吸い込むことができるため、ため息のように見えてしまいます。
犬はにおいからさまざまな情報を読み取る習慣があるので、新しい散歩コースでは情報が少ないため、においから情報を取得する必要があり、ため息をついてにおいを嗅いでいます。
これらの理由でのため息は全く問題ないので、心配する必要もありません。
リラックスしている
 リラックスしている際にも犬はため息をつきます。
人がため息をすることは精神的に不安などがある場合が多いため、どうしても犬がため息をしていると心配になってしまいがちです。
しかし、リラックスしているだけである場合もあるため、必要以上に心配する必要もありません。
飼い主が最も見かけるため息の理由でもあり、幸せそうな表情をしているのであればリラックスしていることによるため息である可能性が高いです。
遊んだ後や散歩後、食事の後、フセや寝転んでいる際もリラックスしているので、ため息をする可能性も高いです。
寝転んでいるときにマッサージしてあげることでため息をしたのであればマッサージが気持ちいいという意味にもなります。
リラックスしている際にも犬はため息をつきます。
人がため息をすることは精神的に不安などがある場合が多いため、どうしても犬がため息をしていると心配になってしまいがちです。
しかし、リラックスしているだけである場合もあるため、必要以上に心配する必要もありません。
飼い主が最も見かけるため息の理由でもあり、幸せそうな表情をしているのであればリラックスしていることによるため息である可能性が高いです。
遊んだ後や散歩後、食事の後、フセや寝転んでいる際もリラックスしているので、ため息をする可能性も高いです。
寝転んでいるときにマッサージしてあげることでため息をしたのであればマッサージが気持ちいいという意味にもなります。
体調が良くない
犬がため息をすることは良いことだけではなく、悪い理由からしている場合もあります。
犬は体調が悪い時にもため息をつく習性があります。
体にだるさを感じている場合やどこか怪我などで負傷しているときにもため息をつきます。
上記で紹介した良い理由からのため息とは違い、苦しそうな表情をしていたり、食欲がないなどの違いがあるため、よく確認していれば悪い理由からのため息であることがわかります。
体調不良の原因が判明しているのであれば、ゆっくり休ませる必要があります。
しかし、何かの病気からのため息である可能性もあるため、早めに病院に連れていくこともおすすめします。
人にも言えることですが、病気は早期発見できればそれだけ完治するまでの時間が短縮され、重症化するリスクも低くなります。
ストレスや不満を感じている
 犬も人と同じように不安やストレスを感じるとため息をつきます。
ため息をつくことでリラックス効果を得ようとしたり、気持ちを切り替えるために行っている場合が多いです。
ストレスや不安を感じている場合はため息のほかに、体を震わせたり、爪や体を頻繁に舐める動作も行います。
さらに遠く一点を見つめている場合もストレスを感じている可能性が高いです。
このような動作をしながらため息をついているのであれば、どのようなことに対してストレスや不安を感じているのかを理解し、改善するようにしましょう。
散歩の時間や頻度は適切であるかや犬がゆっくり休むことができる空間が用意できているかなどを一度見直してみましょう。
飼い始めた時には新しい環境に対して不安やストレスも感じやすいので、ため息もつきやすい時期でもあります。
犬も人と同じように不安やストレスを感じるとため息をつきます。
ため息をつくことでリラックス効果を得ようとしたり、気持ちを切り替えるために行っている場合が多いです。
ストレスや不安を感じている場合はため息のほかに、体を震わせたり、爪や体を頻繁に舐める動作も行います。
さらに遠く一点を見つめている場合もストレスを感じている可能性が高いです。
このような動作をしながらため息をついているのであれば、どのようなことに対してストレスや不安を感じているのかを理解し、改善するようにしましょう。
散歩の時間や頻度は適切であるかや犬がゆっくり休むことができる空間が用意できているかなどを一度見直してみましょう。
飼い始めた時には新しい環境に対して不安やストレスも感じやすいので、ため息もつきやすい時期でもあります。
何かを要求している
ため息は飼い主になにか要求している場合もあります。
ため息ばかりすると飼い主は心配になり、普段よりも構うようになりがちです。
そのため、犬はため息をつけば構ってくれると覚えこんでしまうこともあります。
このようになってしまうと構ってほしい気持ちが強くなり、自発的にため息をついてしまいます。
そのほかにもため息をついた際におやつを与えていればおやつを要求するためにため息つくこともあります。
要求してくる対象によって変わってきますが、あまり良い習慣とは言い切れません。
一方で、散歩をせがむ際にため息をすれば飼い主も散歩をするタイミングを知ることができ、便利に感じることもあります。
飼い主がため息で要求してくることを知っていれば正しく対処することもできますが、
間違えて上記で紹介した理由からため息をついていると勘違いしてしまうと犬は思い通りにならず、ストレスを感じてしまうことも考えられます。
犬のため息は病気の可能性もある?
 犬のため息は病気の可能性があることを知っているでしょうか。
病気が原因であれば放置することは危険であり、早期に病院に見てもらうようにしましょう。
次に、ため息と関係のある病気を紹介するので参考にしてください。
犬のため息は病気の可能性があることを知っているでしょうか。
病気が原因であれば放置することは危険であり、早期に病院に見てもらうようにしましょう。
次に、ため息と関係のある病気を紹介するので参考にしてください。
呼吸器系や心臓の疾患
呼吸器系や心臓に疾患があるとため息の回数が多くなってしまいます。
特に、僧帽弁閉鎖不全症という心臓の病気になると呼吸が不規則になるので、必然的にため息も多くなります。
呼吸器系の病気であれば肺炎や気管虚脱になるとため息をしやすくなります。
病気からくるため息であるかどうかは、普段の呼吸の仕方などを詳しく様子見しておくことで早めに異変に気付き、症状が悪化してしまうことも防ぎます。
ため息だけで病気かどうかを判断することは難しいので、普段よりも元気がないかや呼吸が荒いかどうかに気付けるかが重要です。
鼻腔狭窄
 鼻腔狭窄は鼻の病気であり、鼻腔が狭くなってしまいます。
鼻の穴が狭くなると当然吸い込む空気の量が少なくなるので、呼吸が荒くなったり、より多くの空気を吸い込むためにため息をします。
そのほかにも鼻水が溜まっていることでも呼吸がしにくくなるのでため息が増えます。
鼻から空気を吸うことが難しくなると吐き気を催すこともあるため、ため息をして呼吸を整えたり、吐くことを我慢しています。
鼻の形状によってなりやすくなるので、犬種でなりにくい場合もあります。
鼻腔狭窄は鼻の病気であり、鼻腔が狭くなってしまいます。
鼻の穴が狭くなると当然吸い込む空気の量が少なくなるので、呼吸が荒くなったり、より多くの空気を吸い込むためにため息をします。
そのほかにも鼻水が溜まっていることでも呼吸がしにくくなるのでため息が増えます。
鼻から空気を吸うことが難しくなると吐き気を催すこともあるため、ため息をして呼吸を整えたり、吐くことを我慢しています。
鼻の形状によってなりやすくなるので、犬種でなりにくい場合もあります。
胃拡張症候群・胃捻転
食後にため息をする回数が多いと胃拡張症候群か胃捻転の可能性があります。
これらの病気は胃が膨れていることや捻じれていることが原因であり、胃にガスが溜まり、パンパンにばることで起きます。
上記では食事をした後にため息をすることは満足している証拠であると紹介しましたが、いつまでもため息が続くのであれば満足しているからではなく、病気である可能性が高いです。
嘔吐してしまうことも多く、嘔吐を繰り返せば胃や腸をに異常があったり、分泌液からくる病気を疑う必要性があります。
どちらにせよ安静にしていたらよくなる病気ではないため、早急に病院で治療してもらいましょう。
胃拡張症候群や胃捻転は大型犬で胸が深い犬種ほど発症しやすいと言われていますが、どの犬種でも発症するリスクはあります。
犬の中でもため息をつきやすい犬種は?
 犬はさまざまな理由からため息をしますが、犬種によってもため息をしやすい場合もあります。
例えばキャバリア・キング・チャールズ・スパニエル・フレンチブルドックなどが当てはまります。
これらの犬種は短頭種という共通点があり、鼻が短いです。
短頭種は元々鼻腔が狭い特徴があり、鼻呼吸で肺に取り入れる酸素の量が制限されてしまい、必然的に口呼吸をする場合が多いです。
特に、運動したときや緊張・興奮した際などには鼻呼吸だけでは苦しくなり、口で呼吸をします。
この口呼吸はため息をしているようにも見えます。
また、短頭種は鼻だけではなく、気管などの器官に異常が起きやすい種類でもあり、運動することで息苦しくなることを知っているので散歩を嫌がったり、いびきをかいてしまう傾向があります。
犬はさまざまな理由からため息をしますが、犬種によってもため息をしやすい場合もあります。
例えばキャバリア・キング・チャールズ・スパニエル・フレンチブルドックなどが当てはまります。
これらの犬種は短頭種という共通点があり、鼻が短いです。
短頭種は元々鼻腔が狭い特徴があり、鼻呼吸で肺に取り入れる酸素の量が制限されてしまい、必然的に口呼吸をする場合が多いです。
特に、運動したときや緊張・興奮した際などには鼻呼吸だけでは苦しくなり、口で呼吸をします。
この口呼吸はため息をしているようにも見えます。
また、短頭種は鼻だけではなく、気管などの器官に異常が起きやすい種類でもあり、運動することで息苦しくなることを知っているので散歩を嫌がったり、いびきをかいてしまう傾向があります。
犬がため息をつく原因が分からない際の対処法
 上記ではため息をする理由について紹介しましたが、なかなか見分けることができないことが多いです。
そのため、満足しているからため息をしていると考えていても実際は不安やストレスからため息をしている場合もあります。
次に、ため息の原因がわからないときの対処方法を紹介するので参考にしてください。
上記ではため息をする理由について紹介しましたが、なかなか見分けることができないことが多いです。
そのため、満足しているからため息をしていると考えていても実際は不安やストレスからため息をしている場合もあります。
次に、ため息の原因がわからないときの対処方法を紹介するので参考にしてください。
犬のストレスの原因を解消する
ため息の原因がわからない場合はストレスが関係している場合が多いです。
ストレスからため息を多くしているまま放置してしまうと胃腸障害を引き起こしてしまうリスクがあり、下痢や嘔吐をしてしまうこともあります。
ストレスが原因であればストレスの原因を解消することが求められます。
そのため、どのような理由でストレスを感じているのかを知ることが大切です。
ストレスの原因がわかれば適切な対応をすればストレスを解消することができ、ため息をする回数も減ってきます。
飼い主との信頼関係が不充分
 飼い主との信頼関係が不十分である場合も犬はストレスを感じてしまいます。
飼い主にしてほしいことを伝えることもできず、甘えることもできないのでどうしても日々の生活でもストレスを溜めてしまいがちです。
ため息のほかに吠えたり、噛み癖がついてしまうこともストレスが原因でもあるので、以前と比べてそれらの行動が多くなったのであれば信頼関係が崩れている証拠です。
散歩する頻度が少なかったり、留守番などが多く一緒に遊ぶ時間が確保できていない可能性が高いです。
犬との信頼関係を築くためには時間が必要になるため、飼い主も焦らず少しずつ犬と接する時間を増やすように心がけましょう。
飼い主との信頼関係が不十分である場合も犬はストレスを感じてしまいます。
飼い主にしてほしいことを伝えることもできず、甘えることもできないのでどうしても日々の生活でもストレスを溜めてしまいがちです。
ため息のほかに吠えたり、噛み癖がついてしまうこともストレスが原因でもあるので、以前と比べてそれらの行動が多くなったのであれば信頼関係が崩れている証拠です。
散歩する頻度が少なかったり、留守番などが多く一緒に遊ぶ時間が確保できていない可能性が高いです。
犬との信頼関係を築くためには時間が必要になるため、飼い主も焦らず少しずつ犬と接する時間を増やすように心がけましょう。
まとめ
犬はさまざまな理由からため息をつきます。
良い理由である場合もありますが、悪い理由からため息をしている場合もあるので、ため息の回数が多くなったと感じるのであればため息の理由を把握するように心がけましょう。
元々ため息をしやすい犬種ではどうしても他の犬種と比べてもため息の回数は多くなりがちですが、だからといってため息の原因を理解しておくことは大切です。
ため息の理由を知るだけでも犬との信頼関係を築くことができ、犬の異変にも気づきやすくなります。一度犬の様子をよく確認してみてはいかがでしょうか。
犬にじゃがいもを与えても大丈夫!
 犬にじゃがいもを与えてもよいのか気になっている人もいるのではないでしょうか。
結論から言うと犬にじゃがいもを与えることは何の問題もありません。
ドックフードの中には穀物が使用されていないグレインフリーという種類のフードがありますが、それらのフードにはじゃがいもが使用されている場合が多く、犬にじゃがいもを与えても問題ない証拠でもあります。
ただし、じゃがいもをそのまま与えるのであれば注意点や与えるコツを把握しておくことをおすすめします。
犬にじゃがいもを与えてもよいのか気になっている人もいるのではないでしょうか。
結論から言うと犬にじゃがいもを与えることは何の問題もありません。
ドックフードの中には穀物が使用されていないグレインフリーという種類のフードがありますが、それらのフードにはじゃがいもが使用されている場合が多く、犬にじゃがいもを与えても問題ない証拠でもあります。
ただし、じゃがいもをそのまま与えるのであれば注意点や与えるコツを把握しておくことをおすすめします。
犬にじゃがいもを与える時の注意点
 犬にとってじゃがいもは食べても問題ない食材ではありますが、与える際に注意しなければならないポイントがいくつかあります。
注意点を把握せずに与えてしまうと体調を崩してしまう可能性があります。
ゆでたじゃがいもなどを与えようと考えている人は参考にしてください。
犬にとってじゃがいもは食べても問題ない食材ではありますが、与える際に注意しなければならないポイントがいくつかあります。
注意点を把握せずに与えてしまうと体調を崩してしまう可能性があります。
ゆでたじゃがいもなどを与えようと考えている人は参考にしてください。
注意点①:少量から食べさせる
じゃがいもは茹でればホクホクしておいしいですが、犬は喉に詰まらせてしまう可能性があります。
そのため、一口サイズに切ったり、ペースト状にして喉に詰まらせないように少量ずつ与えるようにしましょう。
人は雑食であるため、食材をすり潰す歯がありますが、犬はもともと肉食であるため、肉を切り裂く鋭い歯しかなく、
歯で細かくすることができず、そのまま飲み込んでしまうことが多いので、喉に詰まらせてしまうリスクが高いです。
注意点②:糖尿病の犬には与えない
 犬にじゃがいもを与える際は人が食べる時と同じように加熱して与えることが一般的です。
犬にとってもそうしたほうが食べやすいことは事実です。
しかし、加熱したじゃがいもを食べると血糖値が上がりやすくなるため、糖尿病の犬にじゃがいもを与えることはやめましょう。
じゃがいもが血糖値を急上昇してしまうことを知らずに、糖尿病の犬に与えてしまうと非常に危険です。
少量ずつ与えれば血糖値の急上昇を抑えることはできますが、リスクがあるので無理してじゃがいもを与える必要性はありません。
犬にじゃがいもを与える際は人が食べる時と同じように加熱して与えることが一般的です。
犬にとってもそうしたほうが食べやすいことは事実です。
しかし、加熱したじゃがいもを食べると血糖値が上がりやすくなるため、糖尿病の犬にじゃがいもを与えることはやめましょう。
じゃがいもが血糖値を急上昇してしまうことを知らずに、糖尿病の犬に与えてしまうと非常に危険です。
少量ずつ与えれば血糖値の急上昇を抑えることはできますが、リスクがあるので無理してじゃがいもを与える必要性はありません。
注意点③:未成熟・変色のじゃがいもは与えない
じゃがいもの芽には毒があることは周知されているため、犬に与える際も取り除くことが多いですが、緑色に変色したじゃがいもや未成熟のじゃがいもにも毒があるので与えることはしないようにしましょう。
緑色に変色している原因は土の中から出てしまい、光が当たっているからであり、そこには芽に含まれているソラニンだけではなく、チャコニンという天然の毒素が含まれています。
未成熟の芋にも同じような毒素があり、摂取してしまうと中毒症状が出てしまいます。
ちなみに皮にも毒素があるだけではなく、消化にも悪いので与えることは控えましょう。
もともと犬の体は穀物や野菜を消化しにくいので、消化しにくい皮を与えてしまうと下痢などの症状を起こす恐れがあります。
注意点④:ポテチなど人間用の加工品は与えない
 じゃがいもは活用幅が広い食材であり、人用の食べものとして加工されたものが多く流通しています。
犬にじゃがいもを与えてもよいことを知れば人用に加工されたものを与えても問題ないと考えてしまいがちですが、
加工されている物には人が好みやすい味付けにするために油や添加物、食塩などが使用されていることが多いです。
人にとってはあまり害のない物ですが、犬にとってはあまり良いものとは言えないので、人用に加工されたじゃがいもは与えないようにしましょう。
人用のお菓子にはじゃがいもが使用されている場合も多いので、おやつ代わりとして与えないように注意する必要があります。
じゃがいもは活用幅が広い食材であり、人用の食べものとして加工されたものが多く流通しています。
犬にじゃがいもを与えてもよいことを知れば人用に加工されたものを与えても問題ないと考えてしまいがちですが、
加工されている物には人が好みやすい味付けにするために油や添加物、食塩などが使用されていることが多いです。
人にとってはあまり害のない物ですが、犬にとってはあまり良いものとは言えないので、人用に加工されたじゃがいもは与えないようにしましょう。
人用のお菓子にはじゃがいもが使用されている場合も多いので、おやつ代わりとして与えないように注意する必要があります。
注意点⑤:じゃがいもは加熱すると消化しやすい
じゃがいもは生のままでは固く食べにくいだけではなく、消化も悪いです。
生のままでも与えれば食べてしまうこともありますが、下痢などの症状を起こしてしまうリスクが非常に高まります。
生のままでは固いですが、加熱したり、蒸かすことで柔らかくすることができ、消化もしやすくなるので、じゃがいもを与えるのであれば加熱することをおすすめします。
しかし、加熱した後にすぐ与えてしまうと火傷してしまうので、冷やして食べやすいサイズにしてから与えるようにしましょう。
犬はじゃがいもの皮と芽の毒素に弱い
 犬はじゃがいもの芽や皮に含まれているソラニンに弱いと考えられ、人が間違って食べた時よりも症状が悪化してしまうケースが多いです。
また、上記でも紹介したように皮は消化に悪いことも関係して下痢や嘔吐をしてしまうこともあります。
芽が出てしまったじゃがいもであれば芽を取り除くことはもちろんですが、深めに取り除くようにしましょう。
皮も同じように人が食べる際にするよりも少し厚めにとるように心がけましょう。
皮や芽にソラニンが多く含まれているだけではなく、近い部分にも成分が含まれている可能性もあるため、万が一のことを想定しての作業となります。
もったいないと考えてしまう場合もありますが、愛犬の健康管理を最優先しましょう。
犬はじゃがいもの芽や皮に含まれているソラニンに弱いと考えられ、人が間違って食べた時よりも症状が悪化してしまうケースが多いです。
また、上記でも紹介したように皮は消化に悪いことも関係して下痢や嘔吐をしてしまうこともあります。
芽が出てしまったじゃがいもであれば芽を取り除くことはもちろんですが、深めに取り除くようにしましょう。
皮も同じように人が食べる際にするよりも少し厚めにとるように心がけましょう。
皮や芽にソラニンが多く含まれているだけではなく、近い部分にも成分が含まれている可能性もあるため、万が一のことを想定しての作業となります。
もったいないと考えてしまう場合もありますが、愛犬の健康管理を最優先しましょう。
犬にじゃがいもを与えても良い1日の分量
 犬にじゃがいもを与える際には適切な分量を与える必要があります。
じゃがいもはカロリーが高い食材であるため、与えすぎてしまうと肥満体質になってしまいます。
適したじゃがいもの量は体格によって変わり、5㎏の犬であれば20~30g程度がおすすめです。
量を守ることと上記でしましたように小さくして与えることも忘れないようにしましょう。
もし、適量を与えたにも関わらず下痢や嘔吐をするのであれば少し減らして様子を見るようにすることが大切です。
さらに量を減らしたにも関わらず、嘔吐や下痢の症状が出るのであればじゃがいものに対してアレルギーを持っている可能性もあるため、一度病院で検査してもらうようにしましょう。
アレルギーがある場合は痒がる行動をしたり、皮膚に炎症や湿疹が出ることもあります。
犬にじゃがいもを与える際には適切な分量を与える必要があります。
じゃがいもはカロリーが高い食材であるため、与えすぎてしまうと肥満体質になってしまいます。
適したじゃがいもの量は体格によって変わり、5㎏の犬であれば20~30g程度がおすすめです。
量を守ることと上記でしましたように小さくして与えることも忘れないようにしましょう。
もし、適量を与えたにも関わらず下痢や嘔吐をするのであれば少し減らして様子を見るようにすることが大切です。
さらに量を減らしたにも関わらず、嘔吐や下痢の症状が出るのであればじゃがいものに対してアレルギーを持っている可能性もあるため、一度病院で検査してもらうようにしましょう。
アレルギーがある場合は痒がる行動をしたり、皮膚に炎症や湿疹が出ることもあります。
犬にじゃがいもを与えるメリット
 犬にじゃがいもを与えても問題ありませんが、芽や皮を取り除くことや小さく刻むなどの加工をしなければならず、意外と手間もかかってしまいます。
そのため、じゃがいもを与えることで得られるメリットが特にないのであれば無理に与える必要性も低くなります。
しかし、犬にじゃがいもを与えることで得られる効果は多くあり、求めている効果があるのであれば注意点を把握してじゃがいもを与えることをおすすめします。
次に、じゃがいもを犬に与えた際に得られるメリットを紹介するので参考にしてください。
犬にじゃがいもを与えても問題ありませんが、芽や皮を取り除くことや小さく刻むなどの加工をしなければならず、意外と手間もかかってしまいます。
そのため、じゃがいもを与えることで得られるメリットが特にないのであれば無理に与える必要性も低くなります。
しかし、犬にじゃがいもを与えることで得られる効果は多くあり、求めている効果があるのであれば注意点を把握してじゃがいもを与えることをおすすめします。
次に、じゃがいもを犬に与えた際に得られるメリットを紹介するので参考にしてください。
メリット①:便秘解消
食物繊維という言葉を聞いたことがある人も多いと思いますが、2種類に分けることができることを知っているでしょうか。
水溶性食物繊維と不溶性食物繊維に分けることができ、じゃがいもは水溶性食物繊維を多く含んでいます。
水溶性食物繊維は水に溶けやすい性質があり、便を柔らかくすることもできます。
便は固いと腸内でとどまってしまいやすいですが、柔らかくなることで便秘解消の効果が期待されます。
そのため、便秘気味の犬にじゃがいもを与えることをおすすめします。
便秘になると腸内に便が溜まっていくため、重症化してしまうと腹痛の症状が出ることもあります。
ただし、逆に軟便気味である際にじゃがいもを与えてしまうとより軟便になってしまう可能性があるため、注意しましょう。
メリット②:免疫力向上・老化防止
 じゃがいもにはビタミンCが多く含まれており、人はもちろんですが、犬にも必要な栄養素です。
犬の場合は体内でビタミンCを作ることはできますが、それだけでは足らないため、人と同じように食事からビタミンCを摂取する必要があります。
ビタミンCには免疫力を高めたり、コラーゲン不足を防ぐこともできます。
免疫力が低下してしまうとさまざまな病気になるリスクがあり、コラーゲンが不足すれば関節疾患があらわれるリスクが高まり、高齢になった際に歩行できなくなる可能性も充分にあります。
そのほかにも老化防止の効果もビタミンCには期待でき、白内障予防の効果もあります。
犬は高齢になればなるほど白内障になるリスクが高いため、若いころからじゃがいもを与えていれば老犬にあっても視力を失うことを未然に防ぎます。
じゃがいもにはビタミンCが多く含まれており、人はもちろんですが、犬にも必要な栄養素です。
犬の場合は体内でビタミンCを作ることはできますが、それだけでは足らないため、人と同じように食事からビタミンCを摂取する必要があります。
ビタミンCには免疫力を高めたり、コラーゲン不足を防ぐこともできます。
免疫力が低下してしまうとさまざまな病気になるリスクがあり、コラーゲンが不足すれば関節疾患があらわれるリスクが高まり、高齢になった際に歩行できなくなる可能性も充分にあります。
そのほかにも老化防止の効果もビタミンCには期待でき、白内障予防の効果もあります。
犬は高齢になればなるほど白内障になるリスクが高いため、若いころからじゃがいもを与えていれば老犬にあっても視力を失うことを未然に防ぎます。
メリット③:低GIでおやつに最適
じゃがいもは低GIでおやつに最適と考えられています。
低GIとは、血糖値が上昇するスピードが遅いことです。
血糖値が急上昇してしまうと腹持ちが悪く、脂肪も付きやすい傾向がありますが、低GIであればそれらのリスクが低くなります。
上記ではじゃがいもにはカロリーが多く含まれているため、肥満にもなりやすいと紹介しましたが、あくまでも大量に与えた際に起きることであるので、適量を守っていれば逆に太りにくいです。
ただし、低GIになるには加熱する必要があります。
そのため、生で与えると低GIではなくなり、単にカロリーが高い食材を与えているだけになってしまいます。
太りにくく腹持ちもよいのでおやつとして与えれば、食事までおやつをねだってくることも減ってきます。
まとめ
犬にじゃがいもを与えることは問題ではありませんが、初めて与えるのであればアレルギーの心配もあるので少量だけ与えるようにしましょう。
そのほかにも毒が含まれている部分は取り除いたり、消化を良くするために加熱することも大切です。
じゃがいもを与えることで得られるメリットもありますが、与えすぎは逆にデメリットになるので注意が必要です。
しゃがいもを犬に与える際には正しい知識を身に付けてから与えるようにしましょう。
犬はさくらんぼを食べてもOK
 犬にサクランボを与えるのは問題ありません。
さくらんぼは甘く人も好んで食べますが、犬も同じように好んで食べる傾向があります。
犬にさくらんぼを与える際は量に注意するようにしましょう。
いくら食べて害になる成分などが含まれていなくても食べ過ぎてしまうと体調を崩してしまう原因になってしまいます。
犬にさくらんぼを与える際は少量に抑え、食べた後に体調を崩してしまわないか様子見することも大切で、万が一下痢などの症状が起きた場合は与えることを控えることをおすすめします。
犬にサクランボを与えるのは問題ありません。
さくらんぼは甘く人も好んで食べますが、犬も同じように好んで食べる傾向があります。
犬にさくらんぼを与える際は量に注意するようにしましょう。
いくら食べて害になる成分などが含まれていなくても食べ過ぎてしまうと体調を崩してしまう原因になってしまいます。
犬にさくらんぼを与える際は少量に抑え、食べた後に体調を崩してしまわないか様子見することも大切で、万が一下痢などの症状が起きた場合は与えることを控えることをおすすめします。
犬にさくらんぼを与える時の注意点
 犬がさくらんぼを食べることで基本的に体調を崩してしまうことはありませんが、注意しなければならないポイントがいくつかあります。
そのため、さくらんぼを犬に与える際に注意点を把握せずに与えてしまうことは危険です。
なので、愛犬にさくらんぼを与える前に注意点を把握しておくことをおすすめします。
注意点を無視して与えてしまった場合は高い確率で体調を崩してしまい、愛犬を苦しませてしまう原因になってしまいます。
次に、さくらんぼを与える際の注意点を紹介するので覚えておきましょう。
犬がさくらんぼを食べることで基本的に体調を崩してしまうことはありませんが、注意しなければならないポイントがいくつかあります。
そのため、さくらんぼを犬に与える際に注意点を把握せずに与えてしまうことは危険です。
なので、愛犬にさくらんぼを与える前に注意点を把握しておくことをおすすめします。
注意点を無視して与えてしまった場合は高い確率で体調を崩してしまい、愛犬を苦しませてしまう原因になってしまいます。
次に、さくらんぼを与える際の注意点を紹介するので覚えておきましょう。
種は絶対に食べさせない
さくらんぼの実の部分は食べても問題ありませんが、種は絶対に食べさせないようにしましょう。
さくらんぼの種は表面は木のように固くなっています。
硬い種を噛むことで歯を痛めてしまうリスクは低いですが、尖っている形状でもあるため、消化器官を傷つけてしまったり、喉や腸などに詰まってしまう危険性があります。
特に、小型犬ほど腸に詰まってしまうリスクがあるので注意しましょう。
また、さくらんぼの種は外は固いですが、割れると柔らかい部分があり、そこには中毒症状を起こしてしまう成分が含まれ、痙攣や嘔吐、下痢などの症状が出てしまいます。
よほど大量に食べないと中毒症状があらわれることはありませんが、注意したことに越したことはありません。
柄(え)を食べさせるのはNG
 さくらんぼは柄の部分がついたまま販売されていることも多く、人も柄の部分を食べないように犬にも与えないようにしましょう。
柄の部分は消化されないため、胃や腸に詰まってしまったり、喉に引っかかってしまうリスクもあります。
犬は柄の部分をお構いなしに食べてしまうため、柄がついているさくらんぼを与えるのであれば最初に取り外してから与えるようにしましょう。
加工品などは柄が取り外されている場合も多いですが、種は取り除かれていないことも多いので注意が必要です。
さくらんぼは柄の部分がついたまま販売されていることも多く、人も柄の部分を食べないように犬にも与えないようにしましょう。
柄の部分は消化されないため、胃や腸に詰まってしまったり、喉に引っかかってしまうリスクもあります。
犬は柄の部分をお構いなしに食べてしまうため、柄がついているさくらんぼを与えるのであれば最初に取り外してから与えるようにしましょう。
加工品などは柄が取り外されている場合も多いですが、種は取り除かれていないことも多いので注意が必要です。
皮は食べられる
人はさくらんぼを食べる際に皮ごと食べることが一般的であり、犬も皮ごと与えて問題ありません。
さくらんぼの皮が非常に薄いことから食べても問題ないです。
いくら薄い皮と言っても消化しやすいかどうかと言われると消化しにくい部類になります。
そのため、より犬に負担をかけたくないのであれば皮を剥いたさくらんぼを与えるようにしましょう。
また、皮には農薬がついたままになっていることもあるので、皮つきのまま与えるのであれば一度洗ってから与えるようにしましょう。
犬がさくらんぼを食べると得られる良い効果
 犬にさくらんぼを与えることでさまざまな効果を得ることができます。
さくらんぼはあまり気軽に購入できるものではないので、わざわざ犬に与える機会も少ないのではないでしょうか。
しかし、得られる効果を知ることで少し高くてもさくらんぼを犬に与えてメリットを得たいと考える飼い主は少なからずいます。
犬にさくらんぼを与えることでさまざまな効果を得ることができます。
さくらんぼはあまり気軽に購入できるものではないので、わざわざ犬に与える機会も少ないのではないでしょうか。
しかし、得られる効果を知ることで少し高くてもさくらんぼを犬に与えてメリットを得たいと考える飼い主は少なからずいます。
有機酸の疲労回復効果
さくらんぼにはクエン酸などの有機酸が多く含まれている特徴があります。
有機酸には疲労回復効果が期待できるので、ドックランなどで運動量が多い日に与えることで翌日に疲れを持ち越してしまうことを軽減してくれます。
有機酸が疲労回復の役割がある理由は、疲労の原因ともなる乳酸を水と炭酸ガスに分解することができるからです。
疲れの原因となる乳酸を少なくすることで、疲労回復を早めることができ、この効果は犬だけでなく、人にも当てはめることができます。
アントシアニンの抗酸化効果
 さくらんぼにはアントシアニンと呼ばれているポリフェノールの一種が豊富に含まれています。
アントシアニンは抗酸化力を高める効果が期待でき、健康的な体に仕上げてくれます。
アントシアニンの抗酸化作用は主に、血管の拡張や毛細血管の保護など血管類を強めることができます。
そのため、血管や血液が関係している病気を未然に防ぐことが期待でき、動脈硬化や狭心症予防などの効果があります。
高齢になればなるほど血管がもろくなりやすく、詰まりやすいので、老犬のおやつとしてさくらんぼはおすすめです。
さくらんぼにはアントシアニンと呼ばれているポリフェノールの一種が豊富に含まれています。
アントシアニンは抗酸化力を高める効果が期待でき、健康的な体に仕上げてくれます。
アントシアニンの抗酸化作用は主に、血管の拡張や毛細血管の保護など血管類を強めることができます。
そのため、血管や血液が関係している病気を未然に防ぐことが期待でき、動脈硬化や狭心症予防などの効果があります。
高齢になればなるほど血管がもろくなりやすく、詰まりやすいので、老犬のおやつとしてさくらんぼはおすすめです。
血行が良くなる効果
さくらんぼを食べると体が温まることを知っているでしょうか。
多くの果物は食べると体が冷える傾向がありますが、さくらんぼの場合は体が温まり、血行を良くすることができます。
基本的に寒い環境で実ができる果物は体を温めると言われています。
血行が悪くなってしまうと詰まりやすく、血管の病気になってしまうリスクが高まってしまいます。
寒い季節にさくらんぼを与えることで寒さ対策としても与えることができますが、大量に与えることは控えましょう。
便秘を解消する効果
 さくらんぼには食物繊維が多く含まれています。
食物繊維は便通を良くする効果があり、便秘解消に一役買ってくれます。
そのため、便秘に悩まされている愛犬にさくらんぼを与えてみてはいかがでしょうか。
便秘になるとお腹が張ったり、腹痛を起こしてしまうこともあり、軽い症状だと甘く見ないようにしましょう。
毎日の排便する回数や量をチェックすることで愛犬が便秘なのかどうかを知ることができます。
食物繊維は主に、野菜類に含まれていますが、好んで野菜類を食べる犬は少なく、便秘にもなりやすいです。
さくらんぼには食物繊維が多く含まれています。
食物繊維は便通を良くする効果があり、便秘解消に一役買ってくれます。
そのため、便秘に悩まされている愛犬にさくらんぼを与えてみてはいかがでしょうか。
便秘になるとお腹が張ったり、腹痛を起こしてしまうこともあり、軽い症状だと甘く見ないようにしましょう。
毎日の排便する回数や量をチェックすることで愛犬が便秘なのかどうかを知ることができます。
食物繊維は主に、野菜類に含まれていますが、好んで野菜類を食べる犬は少なく、便秘にもなりやすいです。
犬にさくらんぼを食べさせて良い量
 犬にさくらんぼを与える際には量に注意する必要があることを紹介してきましたが、具体的にどの程度の量が適量なのかわからない場合が多いです。
基本的に犬の体重によって与えてもよい量も変わってきます。
例えば犬の体重が1㎏であれば3gが適量となります。
5㎏であれば11g、10㎏であれば18gと変わってきます。
ちなみに、さくらんぼ1粒は約6g前後である場合が多く、1㎏の子犬や小型犬の場合は1粒与えるだけでも多いことになってしまいます。
適量以上与えてしまうと下痢などの症状を起こしてしまったり、さくらんぼにアレルギーがある場合はかゆみや呼吸困難などの症状も出てしまいます。
また、糖分が多いさくらんぼであるため、食べすぎは肥満の原因にもなります。
犬にさくらんぼを与える際には量に注意する必要があることを紹介してきましたが、具体的にどの程度の量が適量なのかわからない場合が多いです。
基本的に犬の体重によって与えてもよい量も変わってきます。
例えば犬の体重が1㎏であれば3gが適量となります。
5㎏であれば11g、10㎏であれば18gと変わってきます。
ちなみに、さくらんぼ1粒は約6g前後である場合が多く、1㎏の子犬や小型犬の場合は1粒与えるだけでも多いことになってしまいます。
適量以上与えてしまうと下痢などの症状を起こしてしまったり、さくらんぼにアレルギーがある場合はかゆみや呼吸困難などの症状も出てしまいます。
また、糖分が多いさくらんぼであるため、食べすぎは肥満の原因にもなります。
まとめ
犬にさくらんぼを与えても問題はありませんが、与える際の注意点や適量を守ることをおすすめします。
特に、種や柄は体調を崩してしまう原因になるため、必ず取り除いてから与えることをおすすめします。
また、さくらんぼを犬に与えることでさまざまな効果を期待することができます。
しかし、犬は元々肉食でもあるため、無理してさくらんぼを犬に与える必要性も低いです。
甘いもの好きの犬も多いため、特別な日などにおやつ感覚として与えることがベストです。
犬の有名なことわざ・慣用句を紹介
 有名なことわざや慣用句には動物に例えに使ったものが多く存在しています。
中には犬にまつわることわざや慣用句もあるので、ここでは犬の有名なことわざや慣用句をご紹介します。
有名なことわざや慣用句には動物に例えに使ったものが多く存在しています。
中には犬にまつわることわざや慣用句もあるので、ここでは犬の有名なことわざや慣用句をご紹介します。
犬に論語
犬に論語と簡単に解説すると「道理の通じない者には何を言っても無駄である」ということです。
詳しく解説すると何かに対して理解する力が無かったり、そもそも聞く耳を持たなかったり、聞いたふりをして話を流したりするような人を批判する意味で使われます。
従って、このことわざは基本的にはマイナスな意味合いになるんですよね。
例えば、ある事柄に対し偏った考え方をしており、他の考え方を受け付けないような人に対しては何を言っても意味はないでしょう。
いくら一生懸命話しても他の考え方を受け入れないので無駄に終わってしまいます。
このような場合に「犬に論語」ということわざを使います。
また相手ではなく自分の状態についてこのことわざを使う場合は、自分にはその話は何らかの理由で理解することができないと伝えたい場合です。
兎を見て犬を呼ぶ
 兔を見て犬を呼ぶとは、事を見極めてから対策をしても遅くないということです。
また、一見手遅れに見えても、対策次第で間に合うこともあるのであきらめてはいけないという意味もあります。
兔を見つけてから猟犬を呼ぶという意味からつけられたことわざなのですが、兔を見つけてから猟犬を読んでも遅すぎるとの意味で手遅れの例えとして用いられることも。
同じ意味のことわざに「兔を見て鷹を放つ」があります。
兔を見て犬を呼ぶとは、事を見極めてから対策をしても遅くないということです。
また、一見手遅れに見えても、対策次第で間に合うこともあるのであきらめてはいけないという意味もあります。
兔を見つけてから猟犬を呼ぶという意味からつけられたことわざなのですが、兔を見つけてから猟犬を読んでも遅すぎるとの意味で手遅れの例えとして用いられることも。
同じ意味のことわざに「兔を見て鷹を放つ」があります。
犬に小判
犬に小判とは猫に小判と同じで、どんなに尊い貴重なものであっても、価値の分からない人が持っていたら何の役にも立たないことの例えを言います。
犬はエサに飛びつきますが、小判を投げても食べないし使うこともできないですもんね。
江戸時代から使われていたようなのですが、実際は猫に小判より犬に小判の方が歴史は古いとのこと。
同じいみのことわざに「犬の前の説教」「犬の銭見たるが如し」などがあります。
犬一代に狸一匹
 犬一代に狸一匹とは大きなチャンスは一生に一度というほど、なかなか巡り合うことはないということのたとえで、絶えず獲物を探し回っている犬であっても、狸のような大きな獲物を取るのは一緒に一度くらいのものという意味です。
例文をご紹介すると「犬一代に狸一匹で、今回のようなチャンスは二度とないから、挑戦してみよう!」と使うことができますね。
類語のことわざには「鍛冶屋一代の剣」などがあります。
犬一代に狸一匹とは大きなチャンスは一生に一度というほど、なかなか巡り合うことはないということのたとえで、絶えず獲物を探し回っている犬であっても、狸のような大きな獲物を取るのは一緒に一度くらいのものという意味です。
例文をご紹介すると「犬一代に狸一匹で、今回のようなチャンスは二度とないから、挑戦してみよう!」と使うことができますね。
類語のことわざには「鍛冶屋一代の剣」などがあります。
犬も歩けば棒に当たる
犬も歩けば棒に当たるは良く耳にすることがあると思いますが、実は2つの意味が存在しています。
1つ目は「あまり出しゃばった行動をすると、思わぬ災難に会う」で、2つ目は「何か行動を起こせば、思ってもいないような幸運に巡り合える」です。
全く真逆の意味ですよね!
もともとは1つ目の意味だったのですが、現在は行動を起こすことのメリットとして使われることも多くなったことわざです。
このことわざは解釈で意味が変わるのですが、「棒に当たる」は棒で殴られるという意味があり、ことわざ全体で捉えると「犬も歩いていれば、人に棒で殴られることがある」となります。
思ってもみない災難ですよね。
また「当たる=幸運」という捉え方をして意味を変かさせたのが「何かをしていれば幸運に巡り合える」という2つ目の解釈になるのです。
つまり「幸運に巡り合うためにも、行動を起こそう」というプラスの意味に転換しているので、使い方によって全く真逆の意味になるなんて面白いことわざですよね!
犬も朋輩鷹も朋輩
 犬も朋輩鷹も朋輩の読み方は「いぬもほうばいたかもほうばい」です。
何だか難しそうなことわざですが、意味は「鷹狩りにおける犬と鷹のように、役割や地位など待遇が異なっていても同じ主人に仕えていれば同僚であることに変わりはないこと」となります。
「朋輩」とは同じ主人に仕える仲間、同僚を指しており、上下関係なく、平等な関係であることを伝えたい時に活用することわざです。
注意しなければいけないのがこのことわざは上の立場の人が下の立場の人に対して使用することわざあるという点です。
目上の人に対してこのことわざを使うと失礼にあたるので使い方には十分注意しましょう。
犬も朋輩鷹も朋輩の読み方は「いぬもほうばいたかもほうばい」です。
何だか難しそうなことわざですが、意味は「鷹狩りにおける犬と鷹のように、役割や地位など待遇が異なっていても同じ主人に仕えていれば同僚であることに変わりはないこと」となります。
「朋輩」とは同じ主人に仕える仲間、同僚を指しており、上下関係なく、平等な関係であることを伝えたい時に活用することわざです。
注意しなければいけないのがこのことわざは上の立場の人が下の立場の人に対して使用することわざあるという点です。
目上の人に対してこのことわざを使うと失礼にあたるので使い方には十分注意しましょう。
孫飼わんより犬の子飼え
孫飼わんより犬の子飼えの意味は、「孫をいくら可愛がっても、孫が老後の面倒を見てくれるとは期待できない」です。
それに、孫が立派な大人になる事には、自分は生きているかさえわかりません。
だとしたら、孫を溺愛するよりも犬の子を育てた方がましだということを伝えることわざになります。
犬は昔から3日面倒を見ると、生涯その恩を忘れることができないと言われています。
孫をいくら可愛がっても、その愛情を返してくれるとは限らないのだから、その愛情の見返りを期待しない方が良いという意味のようですね。
犬の海外のことわざ~イギリス編~
 ことわざは日本だけではなく海外にも存在しています。
中には犬を例えにつかったものもいくつかあるので、ここではイギリスで使われている犬にまつわることわざをご紹介します。
ことわざは日本だけではなく海外にも存在しています。
中には犬を例えにつかったものもいくつかあるので、ここではイギリスで使われている犬にまつわることわざをご紹介します。
子供が生まれたら犬を飼いなさい
子供が生まれたら犬を飼いなさいということわざは正式には誌の範疇に入ります。
「子供が生まれたら犬を飼いなさい。
子供が赤ん坊の時、子供の良き守り手となるでしょう。
子供が幼少期の時、子供の良き遊び相手となるでしょう。
子供が少年の時、良き理解者となるでしょう。
そして子供が成年になった時、自らの死をもって子供に命の尊さを教えるでしょう。」
という内容です。
この内容だけでもとても良い詞だということがわかりますよね。
このことわざの意味は犬が子供に何かをしてもらうということだけではなく、子供が犬に対して特別な感情を持ち、その感情の元で何をしてあげたいのか、何を思うのかを考え行動します。
このように人間だけで暮らしていてもわからないことをたくさん学ぶことができると示しているのでしょうね。
犬を愛さない者は紳士でありえない
 犬を愛さない者は紳士でありえないの意味は、犬はとにかく愛すべき存在であるということを意味しています。
ヨーロッパの他の国々とは異なり、イギリスでは犬を牧羊犬としてではなく、飼い犬として可愛がっていました。
そのような犬を大事にする国であるイギリスならではの歴史的背景から生まれたことわざです。
犬を愛さない者は紳士でありえないの意味は、犬はとにかく愛すべき存在であるということを意味しています。
ヨーロッパの他の国々とは異なり、イギリスでは犬を牧羊犬としてではなく、飼い犬として可愛がっていました。
そのような犬を大事にする国であるイギリスならではの歴史的背景から生まれたことわざです。
犬の海外のことわざ~アメリカ編~
 続いて海外のことわざアメリカ編で犬にまつわることわざについて複数ご紹介します。
海外にも色んな犬を使うことわざがあって面白いですよね!
続いて海外のことわざアメリカ編で犬にまつわることわざについて複数ご紹介します。
海外にも色んな犬を使うことわざがあって面白いですよね!
ライオンの尻尾になるよりは犬の頭になるほうがいい
ライオンの尻尾になるよりは犬の頭になるほうがいいの意味は、大きなライオンの役に立たない尻尾になるよりは、犬の頭になって自分らしく生きた方が良いという例えから生まれたアメリカのことわざです。
一緒下積みで終わるより、小さい組織の中でも重要なポジションにいる方が生き甲斐を感じられるということを意味しています。
人を愛するならその飼い犬も愛せよ
 人を愛するならその飼い犬も愛せよの意味は、主人を尊敬するのであれば、主人の飼っている犬までも大切にするはずであるという考えから生まれたことわざです。
自分のことを愛しているのならば、自分の欠点も含めて全てを愛してほしいという意味があります。
日本では反対の意味のことわざに「坊主憎けりゃ、袈裟まで憎い」というものが当たります。
人を愛するならその飼い犬も愛せよの意味は、主人を尊敬するのであれば、主人の飼っている犬までも大切にするはずであるという考えから生まれたことわざです。
自分のことを愛しているのならば、自分の欠点も含めて全てを愛してほしいという意味があります。
日本では反対の意味のことわざに「坊主憎けりゃ、袈裟まで憎い」というものが当たります。
犬の海外のことわざ~フランス編~
 続いて海外のことわざフランス編をご紹介します。
海外のことわざを見ていると犬も人間も平等という考え方がひしひしと伝わってきて素敵なものが多いのはわかりますね。
フランスのことわざにはどんなものがあるのでしょうか。
続いて海外のことわざフランス編をご紹介します。
海外のことわざを見ていると犬も人間も平等という考え方がひしひしと伝わってきて素敵なものが多いのはわかりますね。
フランスのことわざにはどんなものがあるのでしょうか。
犬は猫を産まない
犬は猫を産まないの意味は「子は親に似る」という意味になります。
当然のことですが、犬からは犬しか生まれませんし、猫からは猫しか生まれません。
日本では「蛙の子は蛙」ということわざが同じ意味で使われています。
どんな親から生まれても子供はその親の子供であることは紛れもない事実。
その親を見て育つのですから、突然変異のような子は産まれないという意味を持っているのでしょうね。
犬も司教様の顔をじっと見る
 犬の司教様の顔をじっと見るの意味には、2つあり、1つ目は「司教様は大衆の目下の人に興味深い目でじろじろと見られても、怒ってはいけない」という意味で、
2つ目は犬の立場に立った場合の考え方で「自分より身分の高い人や目上の人などに、要求したいことや言いたいことがある時は、臆さず堂々と伝えるべきである」ということを意味しています。
現代であれば、上司と部下や先生と生徒、先輩と後輩などの上下関係に置き換えると分かりやすいかもしれませんね!
犬の司教様の顔をじっと見るの意味には、2つあり、1つ目は「司教様は大衆の目下の人に興味深い目でじろじろと見られても、怒ってはいけない」という意味で、
2つ目は犬の立場に立った場合の考え方で「自分より身分の高い人や目上の人などに、要求したいことや言いたいことがある時は、臆さず堂々と伝えるべきである」ということを意味しています。
現代であれば、上司と部下や先生と生徒、先輩と後輩などの上下関係に置き換えると分かりやすいかもしれませんね!
犬の海外のことわざ~中国編~
 続いてのことわざは中国編です。
中国にはさまざまなことわざがありそうですね。
犬にまつわるどんなことわざがあるのかご紹介します。
続いてのことわざは中国編です。
中国にはさまざまなことわざがありそうですね。
犬にまつわるどんなことわざがあるのかご紹介します。
羊頭を掲げて犬肉を売る
羊頭を掲げて犬肉を売るを簡単に説明すると、表向きは立派だが、内容がともなってないことのたとえです。
また、見せかけや宣伝とは違う粗悪なものを売るという意味もあります。
詳しく説明すると、立派なものでお客さんを寄せ付けて、実際にはそうではないものを提供することを表しています。
転じて、表向きは立派だが、内容がともなっていないことを意味するようになりました。
似たようなことわざに「看板に偽りあり」や「牛頭を掲げて馬肉を売る」というようなものもあります。
犬の屁も通らない
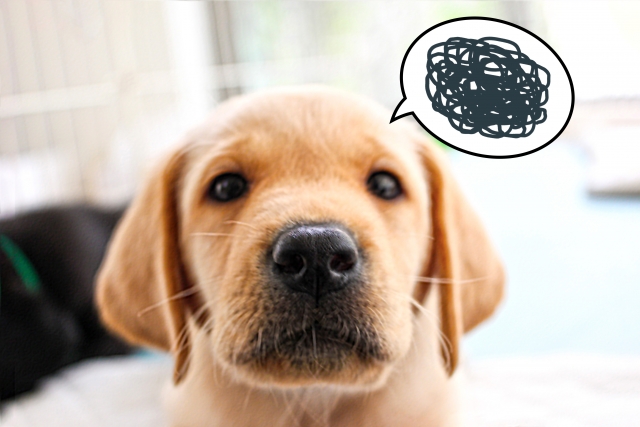 犬の屁も通らないとは、文章がでたらめなことを表すことわざとして使われています。
また、くだらないことを言うなという意味で使うこともあるでしょう。
日本で使われている似たようなことわざには「犬も食わぬ」があります。
犬の屁も通らないとは、文章がでたらめなことを表すことわざとして使われています。
また、くだらないことを言うなという意味で使うこともあるでしょう。
日本で使われている似たようなことわざには「犬も食わぬ」があります。
犬の海外のことわざ~その他の国・地域編~
 次に海外のことわざその他の国地域編をご紹介します。
このように犬にまつわることわざを調べてみると、日本だけではなく海外にもたくさんあることがわかりますね。
次に海外のことわざその他の国地域編をご紹介します。
このように犬にまつわることわざを調べてみると、日本だけではなく海外にもたくさんあることがわかりますね。
タイ:犬に噛みつかれても犬を噛むな
タイで使われていることわざに犬に噛みつかれても犬を噛むなというものがあります。
意味は犬に噛みつかれたからといって誰も犬を噛もうとしないように、バカな相手に攻撃をしかけられてもいちいち相手にすることはないという意味です。
相手より一段高い立場に立って、無駄な争いを断ち切ろうすると知恵でもありますね。
相手が悪意で攻撃してきても、善意をもって答えようすることわざになります。
イエメン:主人を大切に思う者は犬も大切に思う
 つづいてイエメンで使われている主人を大切に思う者は犬も大切に思うということわざです。
意味は大切に思う人、愛するものがあれば、その人の家族やその人に関わずものすべてが大切なもの、愛おしいものに感じられるという意味になります。
主人を尊敬するものは、主人の飼っている犬まで大切にするという考えからきています。
先ほどご紹介したアメリカのことわざ「人を愛するならその飼い犬も愛せよ」と同じような意味ですね。
つづいてイエメンで使われている主人を大切に思う者は犬も大切に思うということわざです。
意味は大切に思う人、愛するものがあれば、その人の家族やその人に関わずものすべてが大切なもの、愛おしいものに感じられるという意味になります。
主人を尊敬するものは、主人の飼っている犬まで大切にするという考えからきています。
先ほどご紹介したアメリカのことわざ「人を愛するならその飼い犬も愛せよ」と同じような意味ですね。
まとめ
今回は、犬にまつわることわざを日本だけではなく海外のものまでご紹介してきました。
いくつわかりましたか?
海外にも犬に関することわざがたくさんあることがわかりましたが、どれも捉え方によっては日本のことわざと意味が似ているものが多かったように思います。
探せばまだまだあると思うので、興味がある方はチャレンジしてみてくださいね!
犬にコーヒーを飲ませたら危険なのはどうして?
 犬にコーヒーを飲ませることは絶対にNGです。
なぜかというと、コーヒーに含まれているカフェインを過剰に摂取すると、カフェイン中毒と呼ばれる命に関わる疾患を引き起こすからです。
犬は人間よりもずっと体が小さいため、カフェイン中毒に陥りやすい傾向にあるのです。
うっかりしてコーヒーが入ったままのカップを置きっぱなしにしていると、匂いに惹かれてなめてしまうかもしれません。
不注意で中毒症状を起こすことのないように気をつけましょう。
犬にコーヒーを飲ませることは絶対にNGです。
なぜかというと、コーヒーに含まれているカフェインを過剰に摂取すると、カフェイン中毒と呼ばれる命に関わる疾患を引き起こすからです。
犬は人間よりもずっと体が小さいため、カフェイン中毒に陥りやすい傾向にあるのです。
うっかりしてコーヒーが入ったままのカップを置きっぱなしにしていると、匂いに惹かれてなめてしまうかもしれません。
不注意で中毒症状を起こすことのないように気をつけましょう。
犬がコーヒーを飲んだ時のカフェイン中毒の症状
 犬がコーヒーを誤飲してカフェイン中毒の恐れがある場合は次のような症状が見られます。
すぐに動物病院で診察してもらいましょう。
また、特別変わった様子がなくても、獣医師の判断を確認するようにし、しばらく様子をよく観察してください。
犬がコーヒーを誤飲してカフェイン中毒の恐れがある場合は次のような症状が見られます。
すぐに動物病院で診察してもらいましょう。
また、特別変わった様子がなくても、獣医師の判断を確認するようにし、しばらく様子をよく観察してください。
興奮状態や大量のよだれ
嘔吐・下痢が出ると同時に、落ち着かない態度になったり、大量のよだれをたらしたりする様子も見せます。
人間もコーヒーを飲んで眠気が覚めますが、これはカフェインが神経を刺激して覚醒させているからです。
少し興奮気味になるわけです。
それと同様に犬も興奮状態になります。
体を震わせたり、ウロウロと落ち着かない様子を見せたりしたら、中毒症状が出ていると考えましょう。
のどが渇いてたくさん水を飲むようになるかもしれません。
嘔吐や下痢
 コーヒーを摂取してすぐに何か異変が起こるというよりも摂取した1~2時間後ほどで 下痢・嘔吐などの症状が現れる可能性があります。
コーヒーは液体なので、体内への吸収が早いとも言われており、急な嘔吐や下痢に苦しむかもしれません。
普段でも消化の悪いものを食べて嘔吐や下痢を起こすことはありますが、一時的なもので元気があればそう問題はありません。
しかし、ぐったりとして元気がないとか逆に興奮状態でよだれが多い、呼吸が荒いなどの症状が見られれば中毒症状の可能性があります。
コーヒーを摂取してすぐに何か異変が起こるというよりも摂取した1~2時間後ほどで 下痢・嘔吐などの症状が現れる可能性があります。
コーヒーは液体なので、体内への吸収が早いとも言われており、急な嘔吐や下痢に苦しむかもしれません。
普段でも消化の悪いものを食べて嘔吐や下痢を起こすことはありますが、一時的なもので元気があればそう問題はありません。
しかし、ぐったりとして元気がないとか逆に興奮状態でよだれが多い、呼吸が荒いなどの症状が見られれば中毒症状の可能性があります。
呼吸困難やけいれん
さらに重度の中毒症状となると、呼吸困難やけいれんなどを引き起こします。
最悪の場合は死亡する悲劇も招いてしまいます。
心臓や脳、腎臓などの臓器に影響を与えるため、持病を持っている犬の場合は特に危険性が高いです。
心拍数が上がり、血圧の低下、体温の低下、尿失禁なども起こりやすい症状です。
犬は人間よりも体内でカフェインを代謝する能力が低いので、中毒症状を起こしやすい体質だと覚えておいてください。
犬の命に危険が及ぶコーヒーの摂取量
 犬の命に危険が及ぶコーヒーの摂取量は犬の体重や個体差によって異なります。
一般的には犬の体重1kgに対しカフェイン量120~200mg程度が致死量と言われています。
おおよそ、コーヒー1杯(150ml)にはカフェインが60~90mg程度含まれているので、体重3kgの犬の場合コーヒー3杯分を飲めば危険だということです。
人間にとってはカフェイン致死量は3g、コーヒー25杯分くらいですので、犬にとってはその20分の1の量でも生命が危ないことを覚えておきましょう。
大型犬から超小型犬まで、危険となるカフェイン量を説明します。
犬の命に危険が及ぶコーヒーの摂取量は犬の体重や個体差によって異なります。
一般的には犬の体重1kgに対しカフェイン量120~200mg程度が致死量と言われています。
おおよそ、コーヒー1杯(150ml)にはカフェインが60~90mg程度含まれているので、体重3kgの犬の場合コーヒー3杯分を飲めば危険だということです。
人間にとってはカフェイン致死量は3g、コーヒー25杯分くらいですので、犬にとってはその20分の1の量でも生命が危ないことを覚えておきましょう。
大型犬から超小型犬まで、危険となるカフェイン量を説明します。
大型犬の致死量
大型犬は体重が25kg以上の犬種を言います。
3000mg(3.0g)前後のカフェインを摂取すると、死に至ってしまうと言われています。
コーヒー1杯におよそ60~90mgのカフェインが含まれているので、約50杯近くになります。
これは相当な量ですから、一度に飲めるものではありません。やはり大型犬の体重は人間の子供くらいありますので致死量まで誤飲することはまれでしょう。
ただ、習慣のようにコーヒーをなめていると命の危険はなくとも健康に影響を与える可能性はあります。
海外では12歳の子供は1日85mgまでとカフェイン摂取量を発表しています。
子供への悪影響を心配しているからです。
子供と変わらない体重の大型犬もリスクを知っておくべきです。
中型犬の致死量
 体重10~25kgの中型犬は、1200mg(1.2g)~3000mg(3.0g)のカフェイン摂取量が命取りとなります。
大型犬よりはずっと体重が軽いので、致死量も半分以下の場合があります。
一概にこの量が危険な致死量というのではなく、少しの量だとしても中毒症状を起こす危険があります。
特に心臓や腎臓に持病を抱えている場合は、少量であっても体調を崩すきっかけとなる可能性があります。
また砂糖や牛乳が入っているコーヒーは、犬は甘いものが好きなので味と匂いを覚えているかもしれません。
飼い主の目を盗んで飲んでいるということもあり、少量でも繰り返すことでだんだんカフェイン量が増えてきますのでよく注意しましょう。
体重10~25kgの中型犬は、1200mg(1.2g)~3000mg(3.0g)のカフェイン摂取量が命取りとなります。
大型犬よりはずっと体重が軽いので、致死量も半分以下の場合があります。
一概にこの量が危険な致死量というのではなく、少しの量だとしても中毒症状を起こす危険があります。
特に心臓や腎臓に持病を抱えている場合は、少量であっても体調を崩すきっかけとなる可能性があります。
また砂糖や牛乳が入っているコーヒーは、犬は甘いものが好きなので味と匂いを覚えているかもしれません。
飼い主の目を盗んで飲んでいるということもあり、少量でも繰り返すことでだんだんカフェイン量が増えてきますのでよく注意しましょう。
小型犬の致死量
体重5~10kg程度の小型犬だと、カフェインで死に至る摂取量は600mg(0.6g)~1200mg(1.2g)程度だと言われています。
今飼育数が多いのはミニチュアダックスフンドやパグなどの小型犬です。
飼い主さんの膝に乗っている犬に、つい一緒に冷めたコーヒーを与えたりしていませんか?
「致死量ではないから大丈夫。」ではなく、半分の量でも危険です。
海外では、体重7kgの犬がカフェインを3g摂取した後に中毒で死亡するというケースが報告されています。
うっかり飲み残しを片付けていなくて犬がなめていたということもありますので管理を徹底しましょう。
先程述べたような中毒症状が出てからでは遅いので、絶対に与えないようにしましょう。
超小型犬の致死量
 体重1~3kgの超小型犬だと、カフェインで死に至ってしまう摂取量は120mg(0.12g)~360mg(0.36g)程度だと言われています。
人間の致死量からすると10分の1程度でも重症化してしまいます。
最も危険性が高い犬種です。
チワワやトイプードル、豆柴など小さな犬種はフードやおやつの量もほんの少しです。
それ以外に人間の嗜好品を与える必要は全くありません。
小型の犬は内臓も小さく、予想される量より少なくても中毒症状が出る可能性があります。
さらに、これらの犬種の子犬ではより注意が必要です。
子犬は消化器官が成犬より発達していません。
細心の注意を払っておきましょう。
体重1~3kgの超小型犬だと、カフェインで死に至ってしまう摂取量は120mg(0.12g)~360mg(0.36g)程度だと言われています。
人間の致死量からすると10分の1程度でも重症化してしまいます。
最も危険性が高い犬種です。
チワワやトイプードル、豆柴など小さな犬種はフードやおやつの量もほんの少しです。
それ以外に人間の嗜好品を与える必要は全くありません。
小型の犬は内臓も小さく、予想される量より少なくても中毒症状が出る可能性があります。
さらに、これらの犬種の子犬ではより注意が必要です。
子犬は消化器官が成犬より発達していません。
細心の注意を払っておきましょう。
犬がコーヒーを飲んだ場合の対処法
 犬がコーヒーを飲むことで起こる危険性がおわかりいただけたことと思います。
もし誤飲誤食をした場合は、たとえ少量でもまず動物病院に連絡し獣医の判断を仰ぎましょう。
症状が出ていると焦ってしまいますが、落ち着いて犬の様子を観察するようにしましょう。
次に詳しく説明します。
犬がコーヒーを飲むことで起こる危険性がおわかりいただけたことと思います。
もし誤飲誤食をした場合は、たとえ少量でもまず動物病院に連絡し獣医の判断を仰ぎましょう。
症状が出ていると焦ってしまいますが、落ち着いて犬の様子を観察するようにしましょう。
次に詳しく説明します。
症状が既にある場合はすぐに動物病院へ連れて行く
既に何らかの危険な症状が犬に現れている場合は、一刻も早く動物病院へ行きましょう。
先程述べたような症状が見られた時には、早い段階で治療することで重症化しないですみます。
苦しそうな様子を見ると動揺してしまいますが、飼い主さんの動揺が犬にとってさらに不安となりますので落ち着いて行動することが一番です。
危険なものだと思うと無理に吐き出させようとしがちですが、それはよくありません。
医師に任せましょう。
誤飲した物のパッケージや下痢・嘔吐したものを持っていっても良いでしょう。
カフェイン中毒の解毒剤はないので、吐き出させる治療や点滴などが行われます。
重症化している際にはそれ以外の治療も必要になり、場合によって手術を行うこともあります。
基本的な治療費は平均して16,000円前後と言われています。
摂取した時の状況を獣医師に連絡して伝える
 病院へすぐに向かいたい時もできればまずかかりつけの獣医師に電話して、コーヒーをどのぐらい摂取したのか、摂取してから経過した時間、そして現在の犬の状況を伝えて、指示を仰ぎましょう。
意思の的確な判断を受けられ、到着してからの処置もスムーズに進みます。
また摂取量や犬の状態で自宅での観察でよいという判断が出るかもしれません。
その場合に家で対処できることなども聞けると思います。
かかりつけの医師であれば、持病やアレルギーの有無を把握しているとは思いますが、念の為そのような点も一緒に伝えておきましょう。
病院が休診日であったり、夜間に誤飲することもあるでしょう。
その時は夜間の受付をしている病院などに電話をして連絡しましょう。
病院へすぐに向かいたい時もできればまずかかりつけの獣医師に電話して、コーヒーをどのぐらい摂取したのか、摂取してから経過した時間、そして現在の犬の状況を伝えて、指示を仰ぎましょう。
意思の的確な判断を受けられ、到着してからの処置もスムーズに進みます。
また摂取量や犬の状態で自宅での観察でよいという判断が出るかもしれません。
その場合に家で対処できることなども聞けると思います。
かかりつけの医師であれば、持病やアレルギーの有無を把握しているとは思いますが、念の為そのような点も一緒に伝えておきましょう。
病院が休診日であったり、夜間に誤飲することもあるでしょう。
その時は夜間の受付をしている病院などに電話をして連絡しましょう。
摂取量が少しだけの場合は様子を見てみる
飲んだ量が少なく、特に異変がない場合は、問題ないこともあるため、1~2時間ほど様子を見ましょう。
症状が出る前までの時間は犬によっても違うので、1~2時間経って大丈夫でも注意深く体調を観察することが大切です。
消化の悪いものは食べさせないようにし、激しい運動も控えましょう。
排泄物も変化はないか、しっかりと翌朝までチェックしてあげてください。
食欲があり元気であれば、いつもと変わりなく過ごしてもらってOKです。
もし、いつもと違い食欲や元気がないように感じられたならば、すぐに動物病院へ連絡して診察を受けてください。
自己判断はよくありませんので、ちょっとした変化でも見逃さないようにしましょう。
犬に与えてはいけないコーヒー関連の食品
 コーヒーだけでなく、コーヒー豆やコーヒーミルクなどの関連食品も、犬には与えてはいけません。
コーヒーゼリーなどにもカフェインが含まれていて、ドリップコーヒーと比べると少ない分量ですが、同様にコーヒーを使ったお菓子も食べさせないようにします。
牛乳や砂糖が入っていると甘く感じるので犬はこっそり口にするかもしれません。
犬には届かない場所で管理するようにしましょう。
またカフェインを含む飲み物は、コーヒーだけではありません。
ココアや紅茶、ウーロン茶、抹茶、ほうじ茶、コーラなどにも入っています。
玉露はコーヒーよりもカフェインが多いほどです。
栄養ドリンクなどにも含まれますので、犬が飲むものは基本的には水またはヤギミルクなどペット用として販売されているものにしておきましょう。
コーヒーだけでなく、コーヒー豆やコーヒーミルクなどの関連食品も、犬には与えてはいけません。
コーヒーゼリーなどにもカフェインが含まれていて、ドリップコーヒーと比べると少ない分量ですが、同様にコーヒーを使ったお菓子も食べさせないようにします。
牛乳や砂糖が入っていると甘く感じるので犬はこっそり口にするかもしれません。
犬には届かない場所で管理するようにしましょう。
またカフェインを含む飲み物は、コーヒーだけではありません。
ココアや紅茶、ウーロン茶、抹茶、ほうじ茶、コーラなどにも入っています。
玉露はコーヒーよりもカフェインが多いほどです。
栄養ドリンクなどにも含まれますので、犬が飲むものは基本的には水またはヤギミルクなどペット用として販売されているものにしておきましょう。
まとめ
犬がコーヒーを飲むとカフェイン中毒になり、命に関わる恐れがあります。
絶対に口に入れないように飼い主である私達がしっかりと管理し、犬を守ってあげましょう。
コーヒー以外にもカフェインが含まれる食品は多いので、知識を持っておくことが大切です。
また万が一カフェインを摂取してしまった場合は、冷静に落ち着いて行動し、動物病院へ連絡しましょう。
少しでも異変を感じたらすぐに診察を受けることが大切です。
犬のお腹がキュルキュル鳴るのは何故?
 愛犬の中がキュルキュル鳴っているのを聞いたことはありませんか?
そんな音を聞くと「お腹が痛いのかな?」と不安になってしまいますよね。
お腹が鳴る原因には確かに体調不良を示しているものもあるのですが、他にもさまざまな理由があります。
ここでは、犬のお腹がキュルキュル鳴る理由についてご紹介します。
愛犬の中がキュルキュル鳴っているのを聞いたことはありませんか?
そんな音を聞くと「お腹が痛いのかな?」と不安になってしまいますよね。
お腹が鳴る原因には確かに体調不良を示しているものもあるのですが、他にもさまざまな理由があります。
ここでは、犬のお腹がキュルキュル鳴る理由についてご紹介します。
理由①:お腹が痛い
人間のでもお腹の調子が悪いとキュルキュル鳴ることがあると思うのですが、それと一緒で犬のお腹が痛いとお腹が鳴ることがあります。
原因としては、胃の調子が悪かったり、異物を食べてしまったり、ご飯が合っていない、お腹にガスが溜まっているなど。
すい炎や寄生虫による感染症など何かしらの炎症や病気を発症している恐れもあるので、注意が必要です。
お腹が痛い場合、愛犬も何かアクションを起こすと思うのでしっかり様子をみてあげてくださいね。
理由②:生理現象
 お腹が空いている時や食べ物を消化しようとしている時に胃や腸が動いて音が鳴ることがあります。
これも人間と同じですよね!
愛犬がいつもと同じ様子で、痛いとかしんどいなどの様子が見られない場合は、生理現象である可能性が高いので、心配する必要はないでしょう。
お腹が空いている時や食べ物を消化しようとしている時に胃や腸が動いて音が鳴ることがあります。
これも人間と同じですよね!
愛犬がいつもと同じ様子で、痛いとかしんどいなどの様子が見られない場合は、生理現象である可能性が高いので、心配する必要はないでしょう。
理由③:環境の変化
犬は環境の変化が苦手です。
普段と違う生活サイクルをしたりすると、お腹の調子が悪くなる子がおり、キュルキュルとなってうずくまったり、動かなくなることも。
食欲も出ないのか食べ物に関心を示さなくなっていることもあるので、そのような場合は便秘の可能性があるでしょう。
人間でも急な環境の変化で便秘になるのと同じように、犬もナイーブな生き物なので、環境に影響される子が多いようです。
お腹の調子が悪い状態は4日程度続くようであれば、一度受診することをおすすめします。
犬のお腹は病気以外でもキュルキュル鳴る
 体調が悪くなくてもお腹がキュルキュルなっている場合は、他の理由も考えられるでしょう。
病気でなくても飼い主からすれば心配ですよね。
そこで病気以外にお腹がキュルキュル鳴る理由についてご紹介します。
体調が悪くなくてもお腹がキュルキュルなっている場合は、他の理由も考えられるでしょう。
病気でなくても飼い主からすれば心配ですよね。
そこで病気以外にお腹がキュルキュル鳴る理由についてご紹介します。
フードが体に合っていない
愛犬がいつも食べているフードですが、それが合わないとお腹がキュルキュルなることがあります。
体質に合っていないフードを食べた場合、消化する時に胃に負担がかかったり、消化不良を起こすことがあり、このときに音が鳴るのです。
また、フードが異常発酵することでお腹にガスが溜まり、ガスを動かすために音が鳴る場合も。
そんな時は一度かかりつけの先生に相談し、愛犬に合ったフードに変えてあげるのがいいかもしれませんね。
ガスがお腹に溜まっている
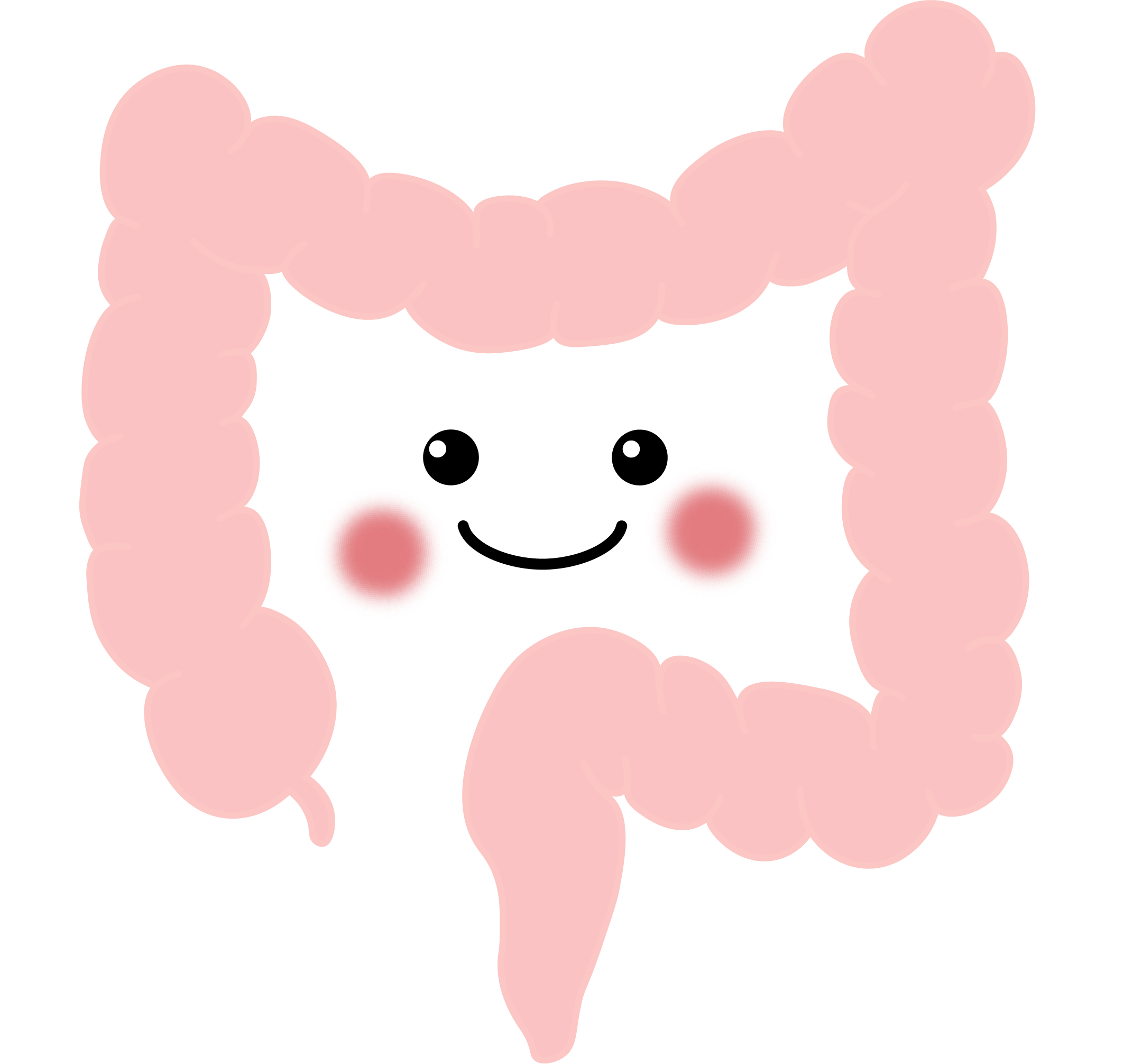 犬は基本的に早食いです。
それに咀嚼していないことも多いですよね。
急いでご飯を食べることで食べ物と一緒に空気を飲み込んでしまったり、ご飯が体内で異常発酵することで、ガスが溜まりお腹が鳴ってしまうのです。
便秘のときも腸内にガスが溜まりやすくなります。
ガスが溜まり過ぎるとおならやげっぷをする頻度が増えるので、そのような現象が頻繁に見られる場合は一度受診することをおすすめします。
犬は基本的に早食いです。
それに咀嚼していないことも多いですよね。
急いでご飯を食べることで食べ物と一緒に空気を飲み込んでしまったり、ご飯が体内で異常発酵することで、ガスが溜まりお腹が鳴ってしまうのです。
便秘のときも腸内にガスが溜まりやすくなります。
ガスが溜まり過ぎるとおならやげっぷをする頻度が増えるので、そのような現象が頻繁に見られる場合は一度受診することをおすすめします。
お腹が空いている
空腹時には、胃や腸といった消化器官が収縮運動をして、食べ物を受け入れるための準備を始めます。
この時に、空気や消化しきれなかった食べ物が動くことで、音が鳴ると考えられます。
明らかにご飯をあげる感覚があいてしまう場合は、一回の量を調整するなどしてあげるのがいいでしょう。
あまりに空腹が続くと胃液を吐くこともあるので、ご飯の時間を再度見直してもいいかもしれませんね。
異物を誤飲した
 犬は基本的に口で物を判断します。
そのため、食べる物かどうかを確認するために誤飲してしまうこともあるでしょう。
誤飲した場合、異物を排出しようとして腸の運動が起こることで、お腹が鳴ることがあります。
また、便秘や嘔吐が見られることもあるので、何か誤飲した物はないか確認し、しっかり様子を見てあげてください。
少しでも様子がおかしい場合は受診するようにしましょう。
犬は基本的に口で物を判断します。
そのため、食べる物かどうかを確認するために誤飲してしまうこともあるでしょう。
誤飲した場合、異物を排出しようとして腸の運動が起こることで、お腹が鳴ることがあります。
また、便秘や嘔吐が見られることもあるので、何か誤飲した物はないか確認し、しっかり様子を見てあげてください。
少しでも様子がおかしい場合は受診するようにしましょう。
運動不足で胃腸機能や食欲が低下している
現在は、さまざまな理由で室内犬が増えてきており、散歩の量も少なくなっている可能性があります。
日頃から運動不足気味な犬は、食欲不振や胃腸の機能が低下してしまうことがあるため、腸が正常に動かず、キュルキュル鳴ることがあるのです。
明らかに運動不足でお腹が鳴っている場合は、少し運動量を増やすなどの調整をしてあげましょう。
犬のお腹キュルキュル=膵炎なのか?
 病気の中でも膵炎の場合、お腹がキュルキュル鳴ることがあります。
膵炎は膵臓に炎症が起こり、消化酵素が膵臓自体を溶かしてしまう病気で、最悪の場合、死に至る怖い病気です。
症状としては、激しい嘔吐や食欲不振、強い腹痛が特徴です。
犬は腹痛を感じると、前足を伸ばして頭を下げ、腰を持ち上げる「祈りのポーズ」をすることがあるので、この姿勢をとってしんどそうにしている場合は膵炎を疑いましょう。
病気の中でも膵炎の場合、お腹がキュルキュル鳴ることがあります。
膵炎は膵臓に炎症が起こり、消化酵素が膵臓自体を溶かしてしまう病気で、最悪の場合、死に至る怖い病気です。
症状としては、激しい嘔吐や食欲不振、強い腹痛が特徴です。
犬は腹痛を感じると、前足を伸ばして頭を下げ、腰を持ち上げる「祈りのポーズ」をすることがあるので、この姿勢をとってしんどそうにしている場合は膵炎を疑いましょう。
犬のお腹キュルキュルに適した対策法は?
 病気以外でお腹がキュルキュルなる場合は、少しの工夫で対策することができます。
ここでは犬のお腹がキュルキュルした場合の対策法についてご紹介します。
病気以外でお腹がキュルキュルなる場合は、少しの工夫で対策することができます。
ここでは犬のお腹がキュルキュルした場合の対策法についてご紹介します。
絶食を24時間させる
犬の軽い不調が原因でお腹が鳴っているのであれば、絶食をさせることで対策することができます。
絶食をさせることで体内の不要物を排出するための時間を確保することができるので、胃の負担を軽減させることができるでしょう。
また、トイレに行く回数も増える可能性が高いので、いつでもトイレできるような環境を整えてあげるのも大切でしょう。
フードを与える回数を増やす
 前述しましたが、お腹が空いてキュルキュルなっている場合は、エサの回数を増やすことで改善できます。
ですが、エサの量を増やすと肥満の原因になってしまう場合があるので、普段を同じ量を複数回に分けて与えるようにし、できるだけ空腹の時間が少なくするよう工夫してあげてください。
それでもお腹が空いている場合は、低カロリーのフードに変更し、量を少しだけ増やすことで解消できるでしょう。
前述しましたが、お腹が空いてキュルキュルなっている場合は、エサの回数を増やすことで改善できます。
ですが、エサの量を増やすと肥満の原因になってしまう場合があるので、普段を同じ量を複数回に分けて与えるようにし、できるだけ空腹の時間が少なくするよう工夫してあげてください。
それでもお腹が空いている場合は、低カロリーのフードに変更し、量を少しだけ増やすことで解消できるでしょう。
マッサージする
信頼する飼い主さんに触れられることで、愛犬はリラックスしたり、精神的な安らぎに繋がります。
お腹がキュルキュル鳴っている場合も正しいマッサージ方法をしてあげることで改善できるでしょう。
その場合、きちんと腸のある場所の確認や強さなどを理解していないと逆効果になることもあるので、体を触って声をかける程度に優しくマッサージしてあげてください。
腸内環境を改善する
 胃腸を健康に保つことは、愛犬の長生きをサポートする秘訣の1つです。
人間でもそれは同じで腸内環境を改善することでとても体調がよくなるのと同じですよね。
そんな時は、乳酸菌のサプリメントなどを与えて、腸内の善玉菌を増やし動きを良くしてあげると、腸内環境が改善され、蠕動運動が活発なったり、ガスの発生が抑えられることがあります。
犬に与えても問題ない整腸剤としては「ビオフェルミン」と「エビオス」があるので、愛犬のお腹が気になる場合は試してきてください。
その場合、しっかり説明書を見て愛犬の体に合った容量を守るようにしましょう。
胃腸を健康に保つことは、愛犬の長生きをサポートする秘訣の1つです。
人間でもそれは同じで腸内環境を改善することでとても体調がよくなるのと同じですよね。
そんな時は、乳酸菌のサプリメントなどを与えて、腸内の善玉菌を増やし動きを良くしてあげると、腸内環境が改善され、蠕動運動が活発なったり、ガスの発生が抑えられることがあります。
犬に与えても問題ない整腸剤としては「ビオフェルミン」と「エビオス」があるので、愛犬のお腹が気になる場合は試してきてください。
その場合、しっかり説明書を見て愛犬の体に合った容量を守るようにしましょう。
まとめ
今回は、犬にお腹がキュルキュル鳴る原因や対策法についてご紹介してきました。
犬のお腹がキュルキュルなる原因には病気もあればその他の問題もあります。
そのため、飼い主さんは何が原因でキュルキュル鳴っているのか把握してあげなければいけません。
キュルキュルが長期間続いて心配な場合は、かかりつけの先生に相談し支持を仰ぎましょう。
明らかに元気でキュルキュルなっている場合は、病気以外の理由が考えられるので、今回ご紹介した対策法を試してみてくださいね。
犬のうんちで要注意な色をチェック
 犬のおしっこやウンチといった排泄物は健康をチェックするためのバロメーターになります。
おしっこやウンチの回数・量・色・臭いなどによって健康状態を確認することができます。
健康な時と体調が悪い時の違いを知るために普段から気にかけ、病気にかからないための健康チェックや対策をするのが大事です。
うんちの色の違いでどんな病気が潜んでいるのかを確認し、愛犬の変化にいち早く気づけるよう心がけましょう。
少しでも気になること、異常が見られた時には素早く動物病院で獣医師に診てもらいましょう。
犬のおしっこやウンチといった排泄物は健康をチェックするためのバロメーターになります。
おしっこやウンチの回数・量・色・臭いなどによって健康状態を確認することができます。
健康な時と体調が悪い時の違いを知るために普段から気にかけ、病気にかからないための健康チェックや対策をするのが大事です。
うんちの色の違いでどんな病気が潜んでいるのかを確認し、愛犬の変化にいち早く気づけるよう心がけましょう。
少しでも気になること、異常が見られた時には素早く動物病院で獣医師に診てもらいましょう。
うんちの色①:赤色
犬の便に血が混じるのにはどんな原因があるのか、どんな病気が潜んでいるかしっかり調べましょう。
血便は何らかの理由で消化管の粘膜が傷ついて出血した血液がうんちと一緒に排泄されたものです。
血便の種類は鮮血が混じった赤い便と、真っ黒なタール便(黒色便)のがあります。
鮮血が混じった赤い便は、出血してからうんちとして排泄されるまでの時間が短く、犬の小腸や結腸、大腸、肛門など、うんちの出口に近い場所で出血していて、黒色のタール便は、出血してからうんちとして排泄されるまでの時間が長く、
血液が酸化して黒くなったもので、犬の食道や胃、十二指腸など、うんちの出口から遠い場所で出血しています。
犬の血便の原因としては感染症(細菌性陽炎、ウイルス性陽炎、寄生虫性陽炎など)や、異物誤飲や、免疫反応の異常(炎症性腸疾患、食物アレルギー)やストレスなど。
さらに、がん(悪性腫瘍)の場合は小腸にできる消化器型リンパ腫や、大腸にできる炎症性ポリープが多くみられます。
症状は、がんの種類や発生場所などによって異なりますが、血便以外にも嘔吐や下痢、便秘、体重減少、食欲不振などの症状が見られるのでいつもと変わった症状が出た場合は早急に病院にいきましょう。
うんちの色②:黒色
 黒いうんちは重い不調のサインであることが多いため、可能な限り早く動物病院を受診すべきです。
黒いうんちは最も健康上のリスクが大きく、胃や腸に腫瘍がある場合や慢性の胃炎、腸炎や、異物などで上部消化管内への出血が発生することがあります。
消化管内に流れ出た血液は、口から入った食べ物と同様に消化されて色が真っ黒に変わり、消化された血液の真っ黒な色がうんちの色として観察されるのです。
この場合、消化管内へ大量の出血が起きていることが疑われ、ときには重度の貧血を起こすほどで貧血そのものが健康に大きな悪影響を及ぼしてしまいます。
したがって、うんちが黒い場合にはなるべく早く動物病院を受診することがをおすすめします。
特に真っ黒な色に加えて、下痢を伴う場合は「タール便」と呼ばれ、便の硬さが普通の場合と比べて緊急性が高いので、よく注意を向けてあげるようにしましょう。
黒いうんちは重い不調のサインであることが多いため、可能な限り早く動物病院を受診すべきです。
黒いうんちは最も健康上のリスクが大きく、胃や腸に腫瘍がある場合や慢性の胃炎、腸炎や、異物などで上部消化管内への出血が発生することがあります。
消化管内に流れ出た血液は、口から入った食べ物と同様に消化されて色が真っ黒に変わり、消化された血液の真っ黒な色がうんちの色として観察されるのです。
この場合、消化管内へ大量の出血が起きていることが疑われ、ときには重度の貧血を起こすほどで貧血そのものが健康に大きな悪影響を及ぼしてしまいます。
したがって、うんちが黒い場合にはなるべく早く動物病院を受診することがをおすすめします。
特に真っ黒な色に加えて、下痢を伴う場合は「タール便」と呼ばれ、便の硬さが普通の場合と比べて緊急性が高いので、よく注意を向けてあげるようにしましょう。
うんちの色③:緑色
犬はまれに緑色のうんちをすることがあります。
原因としては2つあります。
1つ目は、消化物が消化管内に留まる時間が短すぎるとビリルビンが消化管内の細菌の作用を受けず、胆汁に含まれるビリルビンが腸内環境などによって酸化すると緑色のうんちになることがあります。
2つ目は、小腸や大腸の働きが不十分で腸で胆汁が再吸収されず、そのまま排出されると緑色のうんちになることがあります。
また、抗生物質の与えすぎで、腸内細菌が死滅した時も緑色のうんちになることがあります。
そのため緑色のうんちが見られる場合には、消化物(排泄物)が消化管を通過する時間が短縮し、つまってしまい小腸や大腸の働きに異常があると考えられるため、動物病院をすぐに受診する事が大切です。”
うんちの色④:灰白色
排泄されたうんちの黄色みが淡く粘土のように灰白色に感じられる場合では、胆のうに障害があり胆汁の分泌に少ない場合や、
慢性すい炎やすい外分泌不全などですい液が十分分泌されない場合も、消化不良で消化酵素が足りない可能性が考えられます。
各種原因による目や口の粘膜や皮膚が黄色くなる黄疸の可能性が一番で、ほかにはカルシウムの与え過ぎの場合にもみられる症状です。
便の形は、黄疸の場合は不消化の状態で軟便か泥状便が多く、カルシウムの与え過ぎの場合には硬固便で、乾くとぱらぱらで白い粉のようになってしまいます。”
うんちの色⑤:黄色
うんちが黄色または薄い黄土色がかった色の場合は、膵臓に問題を示している可能性があります。
膵臓は膵体・膵右葉・膵左葉の3つのパートから成り胃や十二指腸に隣接した臓器で、蛋白質や脂質、糖質などを分解する消化酵素を含む膵液を分泌したり、
血糖値の調節に関係するインスリンやグルカゴンなどのホルモンを分泌する働きを持っています。
この働きのうち、膵外分泌不全症など膵臓の病気によって消化酵素の分泌に障害が生じると、
脂肪がうまく消化されずにそのままうんちとして排出されるため、形状は軟便や泥状、色が黄色または薄い黄土色になってしまうのです。
犬のうんちの回数の増減でも健康チェックができる
 犬のウンチやおしっこといった排泄物は健康チェックのバロメーターになります。
ウンチやおしっこの回数・量・色・臭いなどによって健康な時とどう異なるので、健康状態を確認することができます。
犬の正常なうんちの回数、量というのは特に決まりがないため、毎日3回以上うんちをする犬もいれば、1日1回の犬もいます。
愛犬の普段のうんちの回数と比較してどうなのかで判断すると良いでしょう。
犬のウンチやおしっこといった排泄物は健康チェックのバロメーターになります。
ウンチやおしっこの回数・量・色・臭いなどによって健康な時とどう異なるので、健康状態を確認することができます。
犬の正常なうんちの回数、量というのは特に決まりがないため、毎日3回以上うんちをする犬もいれば、1日1回の犬もいます。
愛犬の普段のうんちの回数と比較してどうなのかで判断すると良いでしょう。
うんちの回数が少なくなった
普段よりうんちの回数が少ない原因は大きく分けて3つ。
1つ目は「便秘」。
1日に1度も出なかった場合には便秘である可能性が高いです。
コロコロと小さな硬いウンチだった場合も便秘の前兆で、丸2日出ないと問題です。
2つ目は「ご飯の量が少なかったから」。
普段は適切な量をしっかり与えていると思いますが、体調不良などで食べる量が少なかった日やほとんど食べなかった日は、当然ウンチも作られる量が少ないためいつもよりも排便の量が少なくなります。
しかしこれは、普段通りに戻ればうんちの量も戻るでしょう。
3つ目は「病気の可能性」。
何度も排便のポーズをするにも関わらずウンチが少ししか出てこない場合、前立腺や会陰ヘルニアなどの病気である可能性を疑えます。
または犬の場合は5日以上もウンチが出ないと大腸にウンチがたまってしまい、“巨大結腸症”という病気を引き起こしてしまう可能性があります。
うんちの回数が多くなった
 普段より回数が多い場合に考えられることは、消化率の低いフードを食べていると起こることがあります。
特に肥満系のフードは食物繊維が多く不消化物からウンチの量が大量になるので、消化率の高いフードへ変更するとウンチも少なくなります。
また、回数が増えるのは大腸で下痢になっている場合が多く、大腸性の下痢の場合はゼリーの様な粘液便もよく見られるので注意してあげましょう。
さらに、大腸に炎症があって実際に便が溜まっていないのに便意だけを催すときに、排便のポーズをとるだけでうんちが出ない時があります。
その場合は前立腺や会陰ヘルニアなどが原因も考えられるので何度も続く場合は、動物病院で獣医師の診察や検査を受けた方がよいでしょう。
普段より回数が多い場合に考えられることは、消化率の低いフードを食べていると起こることがあります。
特に肥満系のフードは食物繊維が多く不消化物からウンチの量が大量になるので、消化率の高いフードへ変更するとウンチも少なくなります。
また、回数が増えるのは大腸で下痢になっている場合が多く、大腸性の下痢の場合はゼリーの様な粘液便もよく見られるので注意してあげましょう。
さらに、大腸に炎症があって実際に便が溜まっていないのに便意だけを催すときに、排便のポーズをとるだけでうんちが出ない時があります。
その場合は前立腺や会陰ヘルニアなどが原因も考えられるので何度も続く場合は、動物病院で獣医師の診察や検査を受けた方がよいでしょう。
犬のうんちがゼリー状になるのも不調?
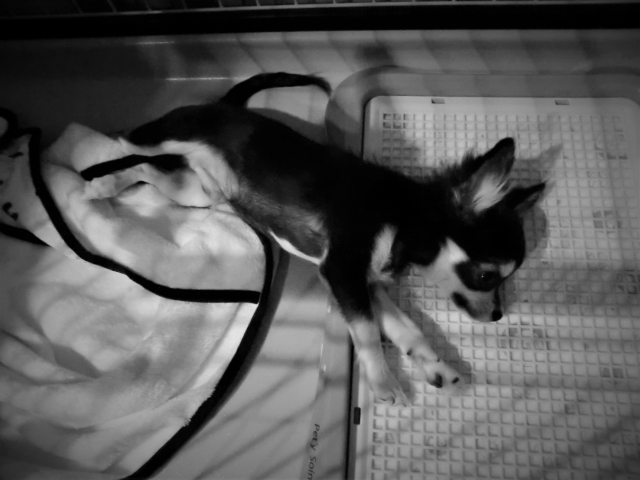 犬がうんちをした時に一緒にうんちと出てくるゼリー状のものは、うんちがスムーズに移動し排出するために腸の中を潤す役割や、腸管内に最近が入り込むのを防ぐバリア機能を持っています。
このゼリー状のものは腸から分泌される粘液や腸粘膜が剥がれ落ちたものです。
腸の表面にある腸粘膜が傷つくとたくさん粘液を分泌して修復しようとするので、ゼリー状のものがうんちと一緒に出るということは不調のサインと考えられます。
犬がうんちをした時に一緒にうんちと出てくるゼリー状のものは、うんちがスムーズに移動し排出するために腸の中を潤す役割や、腸管内に最近が入り込むのを防ぐバリア機能を持っています。
このゼリー状のものは腸から分泌される粘液や腸粘膜が剥がれ落ちたものです。
腸の表面にある腸粘膜が傷つくとたくさん粘液を分泌して修復しようとするので、ゼリー状のものがうんちと一緒に出るということは不調のサインと考えられます。
ゼリー状の正体は粘液便
ゼリー状のものが混ざっているうんちの「粘液便」は、粘液だけが排泄された時や明らかにうんちに粘液が混じっていると分かるうんちのことを言います。
粘液の正体は腸の粘膜から分泌される腸液や腸粘膜が剥がれ落ちたものです。
さらに腸液や腸粘膜は腸管の内側を湿らせて潤いを保ち、消化物や排泄物がスムーズに腸管の中を通過できる働きをしているため普段の便にもゼリー状の粘液が少量含まれていることもありますが、肉眼では確認できません。
異変がある場合はすぐに病院を受診する
 便に粘液が混ざっていると「何かの病気かも」と心配になりますが少量の場合は心配することはありません。
しかし粘液便が続いたり、いつもより粘液の量が多い、血液が混ざっている時などは消化管に不調(食あたり、消化不良、冷え)があったり、
過敏性腸症候群腸(精神的なストレスや自律神経のアンバランスなどが原因で刺激に対して過敏になり、慢性的に便秘や下痢などを起こす病気)など消化管の疾患が見られる場合があります。
また潰瘍性大腸炎(大腸にみられる原因不明の慢性の腸炎で、大腸のもっとも内側の層にある粘膜にびらん(ただれ)や潰瘍(皮膚や粘膜などにできる組織の欠損)ができる病気)も考えられます。
熱が出たり、下痢や嘔吐、食欲不信などの症状が出たときは、大腸が傷いていることがあります。
便に粘液が混ざっていると「何かの病気かも」と心配になりますが少量の場合は心配することはありません。
しかし粘液便が続いたり、いつもより粘液の量が多い、血液が混ざっている時などは消化管に不調(食あたり、消化不良、冷え)があったり、
過敏性腸症候群腸(精神的なストレスや自律神経のアンバランスなどが原因で刺激に対して過敏になり、慢性的に便秘や下痢などを起こす病気)など消化管の疾患が見られる場合があります。
また潰瘍性大腸炎(大腸にみられる原因不明の慢性の腸炎で、大腸のもっとも内側の層にある粘膜にびらん(ただれ)や潰瘍(皮膚や粘膜などにできる組織の欠損)ができる病気)も考えられます。
熱が出たり、下痢や嘔吐、食欲不信などの症状が出たときは、大腸が傷いていることがあります。
まとめ
うんちに混じっている粘液は、腸液や剥がれた腸粘膜が排泄されたものなので少量であれば問題のない可能性が高いです。
しかし、粘液が多量に排泄される場合や他に症状が見られる場合には、医療機関への受診を検討してください。
また、発熱や下痢・嘔吐、いつもより食欲が少ない、うんちに血が混じっているなどの症状の時は治療が必要な大腸炎の可能性もあります。
うんちの状態は体の健康のバロメーターでもありますので、あまり神経質になる必要はありませんが、日頃からうんちのチェックを行いましょう。
病院に行く際にうんちをした時間を記録し、できればジッパー付きの袋に入れて持っていくか、写真を撮って持っていくと良いでしょう。
犬に人間用のアイスを食べさせるリスクとは?
 夏の暑い日、人間であればついつい食べたくなるアイス。
甘くてとても美味しいですよね!
そんな時、愛犬がとても食べたそうに見ていると一口だけと与えてしまうことありませんか?
ですが、犬に人間用のアイスを食べさせることはリスクを伴うことがあります。
今回は人間用のアイスが犬に与えるリスクについてご紹介します。
夏の暑い日、人間であればついつい食べたくなるアイス。
甘くてとても美味しいですよね!
そんな時、愛犬がとても食べたそうに見ていると一口だけと与えてしまうことありませんか?
ですが、犬に人間用のアイスを食べさせることはリスクを伴うことがあります。
今回は人間用のアイスが犬に与えるリスクについてご紹介します。
理由①:中毒を引き起こす成分がある
人間用のアイスには人間にとって何の害がなくても、犬にとっては中毒を引き起こす成分が入っていることがあります。
例えばチョコレートやナッツ(特にマカダミアナッツ)などですね。
ナッツ全般犬にには与えないで欲しいのですが、特にマカダミアナッツには強い中毒症状を起こすことが多いと言われているほか、
のどに詰まって窒息したり、腸閉塞を起こすこともあるため愛犬が口にしないよう十分注意しなければいけません。
理由②:カロリーが高すぎる
 人間用のアイスには大量の糖分が使用されており、犬にとっては糖分過多になってしまう食べ物です。
犬は甘い食べ物が好きなので、ついついアイスを食べていると寄ってきますが、欲しがるから与えるということを繰り返していると肥満の原因になります。
一度与えると何度も要求してくるようになるので、愛犬に長生きしてもらうためにもアイスを与えるのはやめておきましょう。
人間用のアイスには大量の糖分が使用されており、犬にとっては糖分過多になってしまう食べ物です。
犬は甘い食べ物が好きなので、ついついアイスを食べていると寄ってきますが、欲しがるから与えるということを繰り返していると肥満の原因になります。
一度与えると何度も要求してくるようになるので、愛犬に長生きしてもらうためにもアイスを与えるのはやめておきましょう。
理由③:お腹を下す可能性がある
アイスは乳製品を使用しているものが多いです。
人にも乳製品を口にするとお腹を下す人がいるようの、犬の中にも乳糖不耐性といって乳糖をうまく分解できない子がいます。
このような子はアイスを食べたことによって嘔吐や下痢を起こす場合があるためリスク軽減のためには与えないようにしましょう。
嘔吐や下痢を繰り返すとひどい脱水症状が起こり最終的には命を落としてしまうこともありますので、十分に注意する必要があります。
理由④:ぶどう中毒を引き起こす
 アイスには甘いものだけではなく、果物を使ったアイスもあります。
中でもぶどうを使っているアイスはぶどう中毒を起こす可能性があり要注意!
ぶどうのどんな成分が犬の健康を害すのかはっきりとはわかっていないのですが、過去にぶどうを食べた犬が中毒を起こした事例が複数あることがわかっています。
急性の腎障害により、死に至るケースもあるので非常に危険です。
アイスには甘いものだけではなく、果物を使ったアイスもあります。
中でもぶどうを使っているアイスはぶどう中毒を起こす可能性があり要注意!
ぶどうのどんな成分が犬の健康を害すのかはっきりとはわかっていないのですが、過去にぶどうを食べた犬が中毒を起こした事例が複数あることがわかっています。
急性の腎障害により、死に至るケースもあるので非常に危険です。
理由⑤:チョコレートのカカオが中毒物質だから
前述したようにチョコレートは犬にとって有害な成分が含まれています。
チョコレートの主成分であるカカオは犬にとって中毒物質で、カカオに含まれるテオブロミンの作用により、過度の興奮や心拍数の増加などが起こる場合があります。
少しだけと安易な気持ちで与えてしまうと愛犬が苦しむ結果になってしまうので、十分注意してくださいね。
犬にアイスを食べさせる時の注意点
 人間用のアイスを犬に絶対食べさせてはいけないというわけではないですが、与える際にはさまざまな注意が必要になってきます。
ここでは、人間用のアイスを犬に与える時の注意点についてご紹介します。
人間用のアイスを犬に絶対食べさせてはいけないというわけではないですが、与える際にはさまざまな注意が必要になってきます。
ここでは、人間用のアイスを犬に与える時の注意点についてご紹介します。
糖分に注意する
アイスには大量の糖分が含まれており、バニラ味のアイスには角砂糖7個分の砂糖が含まれていると言われています。
甘味が大好きな犬は多いので、アイスを与えるととても喜ぶのですが、人間と同様摂取しすぎると肥満の原因になってしまいます。
肥満になると糖尿病や股関節疾患の原因になったり、心臓や呼吸器などさまざまな器官に負担をかけやすくなるので、どうしても与えたい場合は、味見させる程度の少量にしましょう。
乳製品に注意する
 人間用のアイスには乳製品が含まれているものもあり、乳糖と言われる糖分が含まれています。
離乳期を過ぎた犬はこの糖分を分解するための消化酵素「ラクターゼ」が減少するため、乳糖を体内で分解できない子が多いです。
これを先ほどもご紹介した「乳糖不耐症」というのですが、乳糖が分解できずに大腸に運ばれると、大腸の菌により発酵し、下痢や嘔吐を中心に消化器系症状を引き起こす原因になってしまうのです。
なかには乳製品を食べても平気な子もいますが、少量食べただけでもお腹を壊してしまう子もいるので、最初から与えないのが無難と言えるでしょう。
人間用のアイスには乳製品が含まれているものもあり、乳糖と言われる糖分が含まれています。
離乳期を過ぎた犬はこの糖分を分解するための消化酵素「ラクターゼ」が減少するため、乳糖を体内で分解できない子が多いです。
これを先ほどもご紹介した「乳糖不耐症」というのですが、乳糖が分解できずに大腸に運ばれると、大腸の菌により発酵し、下痢や嘔吐を中心に消化器系症状を引き起こす原因になってしまうのです。
なかには乳製品を食べても平気な子もいますが、少量食べただけでもお腹を壊してしまう子もいるので、最初から与えないのが無難と言えるでしょう。
成分や材料は必ず確認する
一見シンプルな味のアイスでも成分を見ると犬にとって有害になる成分が含まれているものがあります。
先ほどご紹介したようにチョコレート、レーズン、ぶどう、ナッツは特に注意してください。
また、シュガーレスのアイスには甘味料として犬に危険なキシリトールが含まれていることがあります。
このように人間用に作られたアイスにはさまざまな成分が入っているので、犬に与える場合は、十分に成分や材料を確認してからにしましょう。
特に老犬や子犬には食べさせない
 成犬であれば少し程度のアイスを与えるのは問題ないですが、消化機能が不十分な子犬やシニア犬には与えないようにしましょう。
消化器官が未発達な子犬と、消化機能が衰えつつあるシニア犬は下痢や嘔吐などの症状が出やすくなります。
アイスは冷たい分、お腹を冷やすうえに、乳製品も多く含まれるため内臓への負担はとくに大きいでしょう。
アイスに限らず、愛犬が食べなれないものは消化不良を起こしやすいので、最初から与えないのが安心です。
また、人間用に加工されたものには添加物も多く含まれています。
保存料や香料・着色料などこれらの添加物は少量であっても体に有害になるため十分気をつけましょう。
成犬であれば少し程度のアイスを与えるのは問題ないですが、消化機能が不十分な子犬やシニア犬には与えないようにしましょう。
消化器官が未発達な子犬と、消化機能が衰えつつあるシニア犬は下痢や嘔吐などの症状が出やすくなります。
アイスは冷たい分、お腹を冷やすうえに、乳製品も多く含まれるため内臓への負担はとくに大きいでしょう。
アイスに限らず、愛犬が食べなれないものは消化不良を起こしやすいので、最初から与えないのが安心です。
また、人間用に加工されたものには添加物も多く含まれています。
保存料や香料・着色料などこれらの添加物は少量であっても体に有害になるため十分気をつけましょう。
アイスの棒の誤飲に注意する
アイスばかりに囚われがちですが、アイスの棒にも注意が必要です。
アイスは与えなくても少し味がするアイスの棒を舐めさせてあげる方もいるでしょう。
飼い主の前で舐めさせるのはいいにしても、その棒を放っておくと犬が誤飲をしてしまう場合があります。
アイスの棒は何度舐めてもずっと甘いにおいがするので、犬はいつまでも舐めています。
さらには噛んでしまう子もいるでしょう。
棒をかじって飲み込んでしまうと、内臓に傷がついたり、突き破ってしまったりすることもあり、最悪腸閉塞になり手術ということもあります。
そのため、アイスの棒は愛犬の届かないところに捨てるようにしましょう。
犬がどうしてもアイスを食べたがる時はどうする?
 愛犬を涼ませたい時や一緒にアイスを楽しみたいなどどうしても愛犬にアイスを食べさせたい場合はいくつかの方法があります。
ここでは、その方法についてご紹介します。
愛犬を涼ませたい時や一緒にアイスを楽しみたいなどどうしても愛犬にアイスを食べさせたい場合はいくつかの方法があります。
ここでは、その方法についてご紹介します。
手作りアイスを食べさせる
アレルギーを持っている愛犬にアイスを食べさせたい場合には手作りアイスがおすすめです。
愛犬に適した材料を選ぶことができますし、手作りなので添加物が入りません。
愛犬用の特性アイスを作れば、安心して食べさせることができますし、一緒にアイスを楽しむことができるのではないでしょうか。
犬用アイスを食べさせる
 今は犬専用のアイスが販売されています。
犬専用のアイスであれば糖分や添加物が少ないため、安全と言えるでしょう。
なかには乳製品の代わりに豆乳を使ったものもあるので、乳製品に弱い子やアレルギーを持っている子にも安心して与えることができます。
今は犬専用のアイスが販売されています。
犬専用のアイスであれば糖分や添加物が少ないため、安全と言えるでしょう。
なかには乳製品の代わりに豆乳を使ったものもあるので、乳製品に弱い子やアレルギーを持っている子にも安心して与えることができます。
冷たい飲み物やフードを食べさせる
散歩時や夏場に暑がる愛犬の体温を下げたいときにはアイスではなく、冷たい飲み物や手作りご飯でも十分です。
乳製品や糖分を含まない飲料はたくさんあるので、手に入りやすく手軽に使用できるのではないでしょうか。
乳製品の中でもヨーグルトは、乳糖不耐性の子でも食べることができる食品です。
栄養価が高いうえに、整腸作用もあるので、おすすめの食品と言えるでしょう。
ですが、中には糖分が含まれているものもあるので、与える際は無糖のヨーグルトにしてください。
冷凍した果物を食べさせる
 犬が食べても良いと言われているバナナやリンゴなどのフルーツを薄く切って凍らせて与えるのもおすすめです。
季節のフルーツは栄養価も高いですし、冷凍することで長持ちします。
栄養満点のおやつを与えたい時に最適なので、ぜひ試してみてくださいね。
犬が食べても良いと言われているバナナやリンゴなどのフルーツを薄く切って凍らせて与えるのもおすすめです。
季節のフルーツは栄養価も高いですし、冷凍することで長持ちします。
栄養満点のおやつを与えたい時に最適なので、ぜひ試してみてくださいね。
かき氷や氷を食べさせる
愛犬に涼んでもらう際には氷やかき氷もおすすめです。
体温の調節だけではなく、水分補給としても役立ちます。
材料が氷だけなので糖分や添加物の心配もありません。
ですが、シロップなどは糖分過多の原因になるため、与える際には氷の部分だけにしましょう。
他には水の代わりに麦茶を凍らせて与えることもおすすめで、夏場に不足しがちなミネラルの接種できます。
ですが、氷を丸のみしてしまう心配もあるので、愛犬に与える際は安全に食べられるか飼い主さんの目の前で食べてもらうようにしてください。
犬がアイスを食べて中毒・アレルギー症状を起こした場合の対処法
 気をつけていても愛犬がアイスを食べ中毒やアレルギー症状を起こした場合は、愛犬が食べた成分をまずは確認してください。
アレルギー物質を食べてしまった場合は、慌てず愛犬の様子を確認し、嘔吐や下痢が止まらない、皮膚の痒みが強い、掻きむしっているなどの症状が見られる場合はすぐに受診することをおすすめします。
もし、製品に中毒物質が含まれていた場合は、命に関わるものもあるので、すぐに受診してください。
ここで間違っても食べたものを無理やり吐かそうとするのだけはやめましょう。
そして、受診する場合は、食べたものがわかる製品のパッケージや食べた量、時間などをメモして持参すると治療に役立ちます。
気をつけていても愛犬がアイスを食べ中毒やアレルギー症状を起こした場合は、愛犬が食べた成分をまずは確認してください。
アレルギー物質を食べてしまった場合は、慌てず愛犬の様子を確認し、嘔吐や下痢が止まらない、皮膚の痒みが強い、掻きむしっているなどの症状が見られる場合はすぐに受診することをおすすめします。
もし、製品に中毒物質が含まれていた場合は、命に関わるものもあるので、すぐに受診してください。
ここで間違っても食べたものを無理やり吐かそうとするのだけはやめましょう。
そして、受診する場合は、食べたものがわかる製品のパッケージや食べた量、時間などをメモして持参すると治療に役立ちます。
まとめ
今回は愛犬に人間用のアイスを与える際の注意点や与え方などをご紹介してきました。
人間用のアイスは犬にとって好物の味ですが、一度与えると飼い主が食べる度に要求するようになるので、できれば最初から与えないことが無難ですが、
どうしても与えたい場合は、今回ご紹介した注意点を参考に与えるようにしましょう。
犬はピーナッツを食べても大丈夫?
 犬にピーナッツを与えたことはありますか?
なんとなく消化が悪いような気がしますが、与えても問題はないのか、調べてみました。
ピーナッツはアーモンドやくるみなどとは違い、落花生と言われる植物です。
落花生の殻をきちんと外し、薄皮も取った状態そのままであれば犬が食べても大丈夫とのことでした。
ピーナッツが含むオレイン酸は悪玉コレステロールを減らし、ビタミンEは老化防止を助けます。
しかし、大量に与えるのはやはりNGです。
消化不良や下痢を起こし、体調を壊してしまいます。
ピーナッツは犬にとってあまり消化の良くない食べ物だからです。
ここでは、犬にピーナッツを与える際の注意点や与えてはいけない加工品などについて説明していきます。
犬にピーナッツを与えたことはありますか?
なんとなく消化が悪いような気がしますが、与えても問題はないのか、調べてみました。
ピーナッツはアーモンドやくるみなどとは違い、落花生と言われる植物です。
落花生の殻をきちんと外し、薄皮も取った状態そのままであれば犬が食べても大丈夫とのことでした。
ピーナッツが含むオレイン酸は悪玉コレステロールを減らし、ビタミンEは老化防止を助けます。
しかし、大量に与えるのはやはりNGです。
消化不良や下痢を起こし、体調を壊してしまいます。
ピーナッツは犬にとってあまり消化の良くない食べ物だからです。
ここでは、犬にピーナッツを与える際の注意点や与えてはいけない加工品などについて説明していきます。
犬がピーナッツを食べる時の注意点
 ピーナッツはタンパク質が豊富で抗酸化作用が強いビタミンも含んでいる食品です。
犬が食べても問題ありませんが、いくつかの守るべき注意点があります。
注意を守らないと健康に支障が出ることがありますので、次からの詳しい説明を参考にしてください。
ピーナッツはタンパク質が豊富で抗酸化作用が強いビタミンも含んでいる食品です。
犬が食べても問題ありませんが、いくつかの守るべき注意点があります。
注意を守らないと健康に支障が出ることがありますので、次からの詳しい説明を参考にしてください。
注意点①:カロリー
ピーナッツは100gあたり573kcalあり、一般的なドッグフードよりも高カロリーです。
1粒1g程度で約6kcalになる計算です。
少量だけ与えたつもりでも、カロリーの過剰摂取で、肥満に繋がるケースがあります。
おやつ全般に言えることですが、喜んで食べるのでついつい多く与えてしまうものです。
犬のおやつは1日分のカロリーの20%までにすることが望ましいので、体重に合わせた適量を守り、その日のフード量を調整しましょう。
注意点②:誤飲
 ピーナッツをそのまま犬に与えてしまうと、誤飲する可能性が増え、食道や喉に詰まってしまうことがあります。
1粒でも気管や腸につまらせるとたいへんなことになるので、小型犬や子犬、老犬は特に注意しなければいけません。
消化器官が発達していない子犬や弱っている老犬は下痢を起こしやすいものです。
また、殻はほとんど消化できないので食べると腸閉塞になってしまうことがあります。
ピーナッツは殻をむき、生の落花生を柔らかく茹でたものや細かくしたものを与えましょう。
ピーナッツをそのまま犬に与えてしまうと、誤飲する可能性が増え、食道や喉に詰まってしまうことがあります。
1粒でも気管や腸につまらせるとたいへんなことになるので、小型犬や子犬、老犬は特に注意しなければいけません。
消化器官が発達していない子犬や弱っている老犬は下痢を起こしやすいものです。
また、殻はほとんど消化できないので食べると腸閉塞になってしまうことがあります。
ピーナッツは殻をむき、生の落花生を柔らかく茹でたものや細かくしたものを与えましょう。
注意点③:アレルギー
人間のピーナッツアレルギーは意外と多く、激しいショック症状を起こす人がいます。
犬ではアレルギー症状の報告は少ないようですが、絶対にないとは限りません。
犬の場合、口や目の周り、鼻、耳など皮膚を痒がったり、赤みが出たり、脱毛、下痢、軟便、嘔吐などの症状が見られます。
ピーナッツを与えた後に、上記のような疑わしい症状が出た場合は、ピーナッツを与えるのをやめましょう。
そして、動物病院で他にもアレルギーがないかどうかの検査を受けてみることをおすすめします。
犬が食べるとNGなピーナッツ商品
 ピーナッツの加工品はいろいろありますが、犬には人間用の塩味などがついた加工品は与えないようにしましょう。
ピーナッツチョコレートなどのお菓子類や柿の種などは絶対に与えてはいけません。
犬にNGな商品を詳しく解説しますので、ぜひお読みください。
ピーナッツの加工品はいろいろありますが、犬には人間用の塩味などがついた加工品は与えないようにしましょう。
ピーナッツチョコレートなどのお菓子類や柿の種などは絶対に与えてはいけません。
犬にNGな商品を詳しく解説しますので、ぜひお読みください。
ピーナッツバター
犬にとって過剰な塩分と糖分が含まれているピーナッツバターは、あげない方が良い食品です。
犬は甘いものが好きで、味を覚えるとテーブルにあるピーナッツバターをなめてしまうということもあるでしょう。
ピーナッツよりもさらに高カロリー高脂肪のため、与えてしまうと肥満の原因になりかねません。
コング用のペーストにピーナッツ味のものや薬を飲む際の補助食品にも同様のものがありますが、できれば獣医師と相談の上扱うようにしましょう。
ピーナッツのお菓子
 ピーナッツチョコやミックスナッツ、おつまみピーナッツなど、人間用に作られたお菓子・おつまみには塩分が多いため、愛犬の健康を害する恐れがあります。
特にチョコレートはご存知の人も多いかと思いますが、その成分には犬が中毒を起こす危険性が含まれており、絶対に食べさせてはいけない食品です。
チョコレートの致死量は体重1kgあたり100~200mgですので、板チョコ1枚分で小型犬はかなり危険な量となります。
次に塩分ですが、適量の塩分は与えても問題ありませんし、塩分不足も良いものではありません。
しかし、一般的なフードには適量の塩分が含まれていますので、それ以上に与える必要はなく、おつまみなどを与えると体調を崩す原因になってしまいます。
また腎臓や心臓に疾患を持っていると、塩分のとりすぎにより病気が悪化する場合もありますので、お菓子やおつまみ類の加工品は与えないようにしましょう。
ピーナッツチョコやミックスナッツ、おつまみピーナッツなど、人間用に作られたお菓子・おつまみには塩分が多いため、愛犬の健康を害する恐れがあります。
特にチョコレートはご存知の人も多いかと思いますが、その成分には犬が中毒を起こす危険性が含まれており、絶対に食べさせてはいけない食品です。
チョコレートの致死量は体重1kgあたり100~200mgですので、板チョコ1枚分で小型犬はかなり危険な量となります。
次に塩分ですが、適量の塩分は与えても問題ありませんし、塩分不足も良いものではありません。
しかし、一般的なフードには適量の塩分が含まれていますので、それ以上に与える必要はなく、おつまみなどを与えると体調を崩す原因になってしまいます。
また腎臓や心臓に疾患を持っていると、塩分のとりすぎにより病気が悪化する場合もありますので、お菓子やおつまみ類の加工品は与えないようにしましょう。
まとめ
ピーナッツはアレルギーを持っていない犬にとっては、食べても良いものですが、必ずしも与える必要はありません。
注意点を確認した上で適量を与え、肥満にならないように飼い主がうまく調整してあげてください。
愛犬の体調管理をしてあげられるのは飼い主だけですので、正しい知識をもって食事を用意してください。
 犬との暮らしに慣れてきたら、一緒にドライブしてお出かけや旅行を楽しんでみたいですよね。
近所の散歩ももちろん楽しいですが、車に乗って外出ができると行動範囲が広がり、愛犬の喜ぶ顔もたくさん見られます。
ただ犬とドライブに出かける時には注意点やマナー等知っておいたほうが良いことがありますので、それらの情報をお伝えします。
ぜひ愛犬との楽しいドライブに役立ててください。
犬との暮らしに慣れてきたら、一緒にドライブしてお出かけや旅行を楽しんでみたいですよね。
近所の散歩ももちろん楽しいですが、車に乗って外出ができると行動範囲が広がり、愛犬の喜ぶ顔もたくさん見られます。
ただ犬とドライブに出かける時には注意点やマナー等知っておいたほうが良いことがありますので、それらの情報をお伝えします。
ぜひ愛犬との楽しいドライブに役立ててください。
 車に乗る前には必ずトイレを済ませておきます。
排泄をしなければ車には乗せないということを徹底すれば、必ず排泄するように習慣づけられます。
そして長めのドライブの際は途中でトイレタイムを取ったり、帰りの乗車前にもトイレをさせることを忘れないようにしましょう。
また途中でのトイレをさせないために、水分を制限するのは間違っています。
脱水状態になるかもしれませんし、のどが渇いていると一気ににガブ飲みして体調不良の原因にもなりかねません。
適度に水分を与え、トイレタイムが取れるようなドライブ計画を立てましょう。
車に乗る前には必ずトイレを済ませておきます。
排泄をしなければ車には乗せないということを徹底すれば、必ず排泄するように習慣づけられます。
そして長めのドライブの際は途中でトイレタイムを取ったり、帰りの乗車前にもトイレをさせることを忘れないようにしましょう。
また途中でのトイレをさせないために、水分を制限するのは間違っています。
脱水状態になるかもしれませんし、のどが渇いていると一気ににガブ飲みして体調不良の原因にもなりかねません。
適度に水分を与え、トイレタイムが取れるようなドライブ計画を立てましょう。
 犬を車に乗せる際、交通違反となる乗せ方があります。
膝の上に乗せて運転していたり、ドアの窓を開けて、顔を外に出したりすることです。
道路交通法では「運転者は視野もしくはハンドル等の操作を妨げる行為となる乗車をさせていけない。」とあります。
犬が窓から顔を出していた時に衝突されて窓から飛び出してしまったり、急ブレーキをかけた時に膝から落ちて怪我をしたりというような事故が実際に起こっています。
助手席にそのまま乗せる行為も犬が怪我をする場合があります。
愛犬の安全を第一に考えましょう。
犬を車に乗せる際、交通違反となる乗せ方があります。
膝の上に乗せて運転していたり、ドアの窓を開けて、顔を外に出したりすることです。
道路交通法では「運転者は視野もしくはハンドル等の操作を妨げる行為となる乗車をさせていけない。」とあります。
犬が窓から顔を出していた時に衝突されて窓から飛び出してしまったり、急ブレーキをかけた時に膝から落ちて怪我をしたりというような事故が実際に起こっています。
助手席にそのまま乗せる行為も犬が怪我をする場合があります。
愛犬の安全を第一に考えましょう。
 長いドライブになると、犬を車内に留守番させて食事などの時間をとるということがあるかもしれません。
どの季節でもそうですが、特に暑さが厳しい夏場は、エンジンが止まった車中に犬を一匹で留守番させてはいけません。
ほんの短い間でも車内の温度は高温となり、熱中症にかかってしまいます。
また窓を開けて車を離れることも危険です。
飼い主を追いかけて窓から飛び出したりする可能性があるからです。
人間が交代で車内に残るような方法を取り、犬だけにすることは絶対に避けましょう。
長いドライブになると、犬を車内に留守番させて食事などの時間をとるということがあるかもしれません。
どの季節でもそうですが、特に暑さが厳しい夏場は、エンジンが止まった車中に犬を一匹で留守番させてはいけません。
ほんの短い間でも車内の温度は高温となり、熱中症にかかってしまいます。
また窓を開けて車を離れることも危険です。
飼い主を追いかけて窓から飛び出したりする可能性があるからです。
人間が交代で車内に残るような方法を取り、犬だけにすることは絶対に避けましょう。
 人間でも車酔いを起こす人がいるように犬にも車酔いがあります。
車に慣れていない犬にとってはとてもストレスフルな乗り物であることを知っておいてください。
ですから落ち着いて車に乗れるように少しずつステップを踏んで練習をしていきましょう。
人間でも車酔いを起こす人がいるように犬にも車酔いがあります。
車に慣れていない犬にとってはとてもストレスフルな乗り物であることを知っておいてください。
ですから落ち着いて車に乗れるように少しずつステップを踏んで練習をしていきましょう。
 犬がクレートやハーネスに慣れたら、車に乗るという行動と、車内の環境に慣れさせてあげる必要があります。
いきなりエンジンを掛けるのではなく、車を止めた状態でおやつやおもちゃを与えて、「車の乗ること=楽しいこと」を覚えさせてください。
車に乗った瞬間に褒めておやつを与えます。
ハーネスをつけた後やクレートの扉を締めた時などにもまたおやつをあげます。
その繰り返しで犬は「車に乗ると良いことがある」と覚えていくのです。
大好きなおもちゃをクレートに入れておくのも良いでしょうし、車に乗ってしばらくおもちゃで遊んであげるのも効果的です。
そして車内の匂いをできるだけ消しておきましょう。
犬の嗅覚は人間の何十倍も敏感なので嫌な匂いがストレスになることがあります。
また犬が乗った後の匂いも消しておくように消臭剤を準備しておきましょう。
犬がクレートやハーネスに慣れたら、車に乗るという行動と、車内の環境に慣れさせてあげる必要があります。
いきなりエンジンを掛けるのではなく、車を止めた状態でおやつやおもちゃを与えて、「車の乗ること=楽しいこと」を覚えさせてください。
車に乗った瞬間に褒めておやつを与えます。
ハーネスをつけた後やクレートの扉を締めた時などにもまたおやつをあげます。
その繰り返しで犬は「車に乗ると良いことがある」と覚えていくのです。
大好きなおもちゃをクレートに入れておくのも良いでしょうし、車に乗ってしばらくおもちゃで遊んであげるのも効果的です。
そして車内の匂いをできるだけ消しておきましょう。
犬の嗅覚は人間の何十倍も敏感なので嫌な匂いがストレスになることがあります。
また犬が乗った後の匂いも消しておくように消臭剤を準備しておきましょう。
 車体の振動に犬が充分に慣れてきたら、今度は運転にトライしましょう。
最初は家の近くを1周する程度で大丈夫です。
よくある失敗の一つが車でのお出かけが病院で注射を打つことです。
「車に乗ったら病院」では楽しくありません。
公園やドッグランなど楽しいと思える場所に連れていきましょう。
10分程度で行ける場所でも練習と思って車に乗せるとよいでしょう。
犬が静かにして落ち着いている時によく褒めておやつをあげましょう。
そして目的地に着いたら、車から降りてたくさん散歩したり、遊んだりすると犬も車に乗ることが楽しくなってきます。
家の近くから始めて、少しずつ距離を伸ばし30分程度のドライブに付き合ってくれるようになれば安心です。
車体の振動に犬が充分に慣れてきたら、今度は運転にトライしましょう。
最初は家の近くを1周する程度で大丈夫です。
よくある失敗の一つが車でのお出かけが病院で注射を打つことです。
「車に乗ったら病院」では楽しくありません。
公園やドッグランなど楽しいと思える場所に連れていきましょう。
10分程度で行ける場所でも練習と思って車に乗せるとよいでしょう。
犬が静かにして落ち着いている時によく褒めておやつをあげましょう。
そして目的地に着いたら、車から降りてたくさん散歩したり、遊んだりすると犬も車に乗ることが楽しくなってきます。
家の近くから始めて、少しずつ距離を伸ばし30分程度のドライブに付き合ってくれるようになれば安心です。
 一番多い事故は犬が脱走してしまうことです。
犬を車外に出す際は、ドアを開く前にハーネスや首輪を装着し、リードに繋いだ状態にして、脱走を阻止します。
小型犬の場合にはリードに繋いだ状態で飼い主が抱っこして車から降ろすと良いでしょう。
またとても抱っこができない体重の犬もいますので、ドアを開けてもすぐに外に出ないというしつけをしましょう。
そのためには普段から「マテ」を教え、許可が出てから車から降りるということを毎回必ず行います。
車から出たときもおすわりをさせて、おやつをあげるようにしていると習慣となり、すぐに走り出そうとしないようになります。
一番多い事故は犬が脱走してしまうことです。
犬を車外に出す際は、ドアを開く前にハーネスや首輪を装着し、リードに繋いだ状態にして、脱走を阻止します。
小型犬の場合にはリードに繋いだ状態で飼い主が抱っこして車から降ろすと良いでしょう。
またとても抱っこができない体重の犬もいますので、ドアを開けてもすぐに外に出ないというしつけをしましょう。
そのためには普段から「マテ」を教え、許可が出てから車から降りるということを毎回必ず行います。
車から出たときもおすわりをさせて、おやつをあげるようにしていると習慣となり、すぐに走り出そうとしないようになります。
 犬の膀胱に尿が溜まっている際は、車から降りたタイミングがトイレタイムとなります。
なるべく水はけの良い場所を選び、終わった後は水をかけたり、きれいに処理することがマナーです。
公共の場所に犬を連れて行く時は特に気をつけてトイレ場所も選ぶようにしましょう。
駐車場などは誰もが通る場所なので、匂いかぎをさせないようにして排泄を避けるべきです。
また飼い主のトイレタイムの時には、車の中で犬だけにならないように配慮することも大切です。
車の外へ出して係留しておくことは連れ去りや脱走の事故がありますのでやめましょう。
犬の膀胱に尿が溜まっている際は、車から降りたタイミングがトイレタイムとなります。
なるべく水はけの良い場所を選び、終わった後は水をかけたり、きれいに処理することがマナーです。
公共の場所に犬を連れて行く時は特に気をつけてトイレ場所も選ぶようにしましょう。
駐車場などは誰もが通る場所なので、匂いかぎをさせないようにして排泄を避けるべきです。
また飼い主のトイレタイムの時には、車の中で犬だけにならないように配慮することも大切です。
車の外へ出して係留しておくことは連れ去りや脱走の事故がありますのでやめましょう。
 犬とのドライブは楽しいものですが、残念ながら危険な乗り方をしている飼い主もいます。
安全を守れず命の危険があったり、道路交通法に違反して逮捕されたというケースもあります。
危険な乗せ方を知り、正しい方法で安全に犬とのドライブを楽しみましょう。
犬とのドライブは楽しいものですが、残念ながら危険な乗り方をしている飼い主もいます。
安全を守れず命の危険があったり、道路交通法に違反して逮捕されたというケースもあります。
危険な乗せ方を知り、正しい方法で安全に犬とのドライブを楽しみましょう。
 助手席に人がいないからと、愛犬をそこに座らせたり、もしくは助手席に座っている人の膝に乗せることも、大変危険です。
助手席にはエアバッグがついており、それが膨らんだ際にエアバッグの衝撃で犬が怪我をするという事故も起きています。
後部座席では犬の様子が見られないと心配するのはわかりますが、この記事で紹介しているように少しずつ車に慣れさせ、落ち着いて乗っていられるように努力してみてください。
助手席に人がいないからと、愛犬をそこに座らせたり、もしくは助手席に座っている人の膝に乗せることも、大変危険です。
助手席にはエアバッグがついており、それが膨らんだ際にエアバッグの衝撃で犬が怪我をするという事故も起きています。
後部座席では犬の様子が見られないと心配するのはわかりますが、この記事で紹介しているように少しずつ車に慣れさせ、落ち着いて乗っていられるように努力してみてください。
 犬を長く飼っていたり、よく観察していれば時々ため息をつくことを見たことがあるのではないでしょうか。
犬の人と同じように感情があるため、さまざまな気持な時にため息をします。
ため息をする理由によっては問題視する必要がない場合もあれば注意しなければならない場合もあります。
そのため、頻繁にため息をしている姿を見るのであればどのような理由からため息をついているのかを把握して、より原因に近い理由を知るようにしましょう。
犬を長く飼っていたり、よく観察していれば時々ため息をつくことを見たことがあるのではないでしょうか。
犬の人と同じように感情があるため、さまざまな気持な時にため息をします。
ため息をする理由によっては問題視する必要がない場合もあれば注意しなければならない場合もあります。
そのため、頻繁にため息をしている姿を見るのであればどのような理由からため息をついているのかを把握して、より原因に近い理由を知るようにしましょう。
 リラックスしている際にも犬はため息をつきます。
人がため息をすることは精神的に不安などがある場合が多いため、どうしても犬がため息をしていると心配になってしまいがちです。
しかし、リラックスしているだけである場合もあるため、必要以上に心配する必要もありません。
飼い主が最も見かけるため息の理由でもあり、幸せそうな表情をしているのであればリラックスしていることによるため息である可能性が高いです。
遊んだ後や散歩後、食事の後、フセや寝転んでいる際もリラックスしているので、ため息をする可能性も高いです。
寝転んでいるときにマッサージしてあげることでため息をしたのであればマッサージが気持ちいいという意味にもなります。
リラックスしている際にも犬はため息をつきます。
人がため息をすることは精神的に不安などがある場合が多いため、どうしても犬がため息をしていると心配になってしまいがちです。
しかし、リラックスしているだけである場合もあるため、必要以上に心配する必要もありません。
飼い主が最も見かけるため息の理由でもあり、幸せそうな表情をしているのであればリラックスしていることによるため息である可能性が高いです。
遊んだ後や散歩後、食事の後、フセや寝転んでいる際もリラックスしているので、ため息をする可能性も高いです。
寝転んでいるときにマッサージしてあげることでため息をしたのであればマッサージが気持ちいいという意味にもなります。
 犬も人と同じように不安やストレスを感じるとため息をつきます。
ため息をつくことでリラックス効果を得ようとしたり、気持ちを切り替えるために行っている場合が多いです。
ストレスや不安を感じている場合はため息のほかに、体を震わせたり、爪や体を頻繁に舐める動作も行います。
さらに遠く一点を見つめている場合もストレスを感じている可能性が高いです。
このような動作をしながらため息をついているのであれば、どのようなことに対してストレスや不安を感じているのかを理解し、改善するようにしましょう。
散歩の時間や頻度は適切であるかや犬がゆっくり休むことができる空間が用意できているかなどを一度見直してみましょう。
飼い始めた時には新しい環境に対して不安やストレスも感じやすいので、ため息もつきやすい時期でもあります。
犬も人と同じように不安やストレスを感じるとため息をつきます。
ため息をつくことでリラックス効果を得ようとしたり、気持ちを切り替えるために行っている場合が多いです。
ストレスや不安を感じている場合はため息のほかに、体を震わせたり、爪や体を頻繁に舐める動作も行います。
さらに遠く一点を見つめている場合もストレスを感じている可能性が高いです。
このような動作をしながらため息をついているのであれば、どのようなことに対してストレスや不安を感じているのかを理解し、改善するようにしましょう。
散歩の時間や頻度は適切であるかや犬がゆっくり休むことができる空間が用意できているかなどを一度見直してみましょう。
飼い始めた時には新しい環境に対して不安やストレスも感じやすいので、ため息もつきやすい時期でもあります。
 犬のため息は病気の可能性があることを知っているでしょうか。
病気が原因であれば放置することは危険であり、早期に病院に見てもらうようにしましょう。
次に、ため息と関係のある病気を紹介するので参考にしてください。
犬のため息は病気の可能性があることを知っているでしょうか。
病気が原因であれば放置することは危険であり、早期に病院に見てもらうようにしましょう。
次に、ため息と関係のある病気を紹介するので参考にしてください。
 鼻腔狭窄は鼻の病気であり、鼻腔が狭くなってしまいます。
鼻の穴が狭くなると当然吸い込む空気の量が少なくなるので、呼吸が荒くなったり、より多くの空気を吸い込むためにため息をします。
そのほかにも鼻水が溜まっていることでも呼吸がしにくくなるのでため息が増えます。
鼻から空気を吸うことが難しくなると吐き気を催すこともあるため、ため息をして呼吸を整えたり、吐くことを我慢しています。
鼻の形状によってなりやすくなるので、犬種でなりにくい場合もあります。
鼻腔狭窄は鼻の病気であり、鼻腔が狭くなってしまいます。
鼻の穴が狭くなると当然吸い込む空気の量が少なくなるので、呼吸が荒くなったり、より多くの空気を吸い込むためにため息をします。
そのほかにも鼻水が溜まっていることでも呼吸がしにくくなるのでため息が増えます。
鼻から空気を吸うことが難しくなると吐き気を催すこともあるため、ため息をして呼吸を整えたり、吐くことを我慢しています。
鼻の形状によってなりやすくなるので、犬種でなりにくい場合もあります。
 犬はさまざまな理由からため息をしますが、犬種によってもため息をしやすい場合もあります。
例えばキャバリア・キング・チャールズ・スパニエル・フレンチブルドックなどが当てはまります。
これらの犬種は短頭種という共通点があり、鼻が短いです。
短頭種は元々鼻腔が狭い特徴があり、鼻呼吸で肺に取り入れる酸素の量が制限されてしまい、必然的に口呼吸をする場合が多いです。
特に、運動したときや緊張・興奮した際などには鼻呼吸だけでは苦しくなり、口で呼吸をします。
この口呼吸はため息をしているようにも見えます。
また、短頭種は鼻だけではなく、気管などの器官に異常が起きやすい種類でもあり、運動することで息苦しくなることを知っているので散歩を嫌がったり、いびきをかいてしまう傾向があります。
犬はさまざまな理由からため息をしますが、犬種によってもため息をしやすい場合もあります。
例えばキャバリア・キング・チャールズ・スパニエル・フレンチブルドックなどが当てはまります。
これらの犬種は短頭種という共通点があり、鼻が短いです。
短頭種は元々鼻腔が狭い特徴があり、鼻呼吸で肺に取り入れる酸素の量が制限されてしまい、必然的に口呼吸をする場合が多いです。
特に、運動したときや緊張・興奮した際などには鼻呼吸だけでは苦しくなり、口で呼吸をします。
この口呼吸はため息をしているようにも見えます。
また、短頭種は鼻だけではなく、気管などの器官に異常が起きやすい種類でもあり、運動することで息苦しくなることを知っているので散歩を嫌がったり、いびきをかいてしまう傾向があります。
 上記ではため息をする理由について紹介しましたが、なかなか見分けることができないことが多いです。
そのため、満足しているからため息をしていると考えていても実際は不安やストレスからため息をしている場合もあります。
次に、ため息の原因がわからないときの対処方法を紹介するので参考にしてください。
上記ではため息をする理由について紹介しましたが、なかなか見分けることができないことが多いです。
そのため、満足しているからため息をしていると考えていても実際は不安やストレスからため息をしている場合もあります。
次に、ため息の原因がわからないときの対処方法を紹介するので参考にしてください。
 飼い主との信頼関係が不十分である場合も犬はストレスを感じてしまいます。
飼い主にしてほしいことを伝えることもできず、甘えることもできないのでどうしても日々の生活でもストレスを溜めてしまいがちです。
ため息のほかに吠えたり、噛み癖がついてしまうこともストレスが原因でもあるので、以前と比べてそれらの行動が多くなったのであれば信頼関係が崩れている証拠です。
散歩する頻度が少なかったり、留守番などが多く一緒に遊ぶ時間が確保できていない可能性が高いです。
犬との信頼関係を築くためには時間が必要になるため、飼い主も焦らず少しずつ犬と接する時間を増やすように心がけましょう。
飼い主との信頼関係が不十分である場合も犬はストレスを感じてしまいます。
飼い主にしてほしいことを伝えることもできず、甘えることもできないのでどうしても日々の生活でもストレスを溜めてしまいがちです。
ため息のほかに吠えたり、噛み癖がついてしまうこともストレスが原因でもあるので、以前と比べてそれらの行動が多くなったのであれば信頼関係が崩れている証拠です。
散歩する頻度が少なかったり、留守番などが多く一緒に遊ぶ時間が確保できていない可能性が高いです。
犬との信頼関係を築くためには時間が必要になるため、飼い主も焦らず少しずつ犬と接する時間を増やすように心がけましょう。
 犬にじゃがいもを与えてもよいのか気になっている人もいるのではないでしょうか。
結論から言うと犬にじゃがいもを与えることは何の問題もありません。
ドックフードの中には穀物が使用されていないグレインフリーという種類のフードがありますが、それらのフードにはじゃがいもが使用されている場合が多く、犬にじゃがいもを与えても問題ない証拠でもあります。
ただし、じゃがいもをそのまま与えるのであれば注意点や与えるコツを把握しておくことをおすすめします。
犬にじゃがいもを与えてもよいのか気になっている人もいるのではないでしょうか。
結論から言うと犬にじゃがいもを与えることは何の問題もありません。
ドックフードの中には穀物が使用されていないグレインフリーという種類のフードがありますが、それらのフードにはじゃがいもが使用されている場合が多く、犬にじゃがいもを与えても問題ない証拠でもあります。
ただし、じゃがいもをそのまま与えるのであれば注意点や与えるコツを把握しておくことをおすすめします。
 犬にとってじゃがいもは食べても問題ない食材ではありますが、与える際に注意しなければならないポイントがいくつかあります。
注意点を把握せずに与えてしまうと体調を崩してしまう可能性があります。
ゆでたじゃがいもなどを与えようと考えている人は参考にしてください。
犬にとってじゃがいもは食べても問題ない食材ではありますが、与える際に注意しなければならないポイントがいくつかあります。
注意点を把握せずに与えてしまうと体調を崩してしまう可能性があります。
ゆでたじゃがいもなどを与えようと考えている人は参考にしてください。
 犬にじゃがいもを与える際は人が食べる時と同じように加熱して与えることが一般的です。
犬にとってもそうしたほうが食べやすいことは事実です。
しかし、加熱したじゃがいもを食べると血糖値が上がりやすくなるため、糖尿病の犬にじゃがいもを与えることはやめましょう。
じゃがいもが血糖値を急上昇してしまうことを知らずに、糖尿病の犬に与えてしまうと非常に危険です。
少量ずつ与えれば血糖値の急上昇を抑えることはできますが、リスクがあるので無理してじゃがいもを与える必要性はありません。
犬にじゃがいもを与える際は人が食べる時と同じように加熱して与えることが一般的です。
犬にとってもそうしたほうが食べやすいことは事実です。
しかし、加熱したじゃがいもを食べると血糖値が上がりやすくなるため、糖尿病の犬にじゃがいもを与えることはやめましょう。
じゃがいもが血糖値を急上昇してしまうことを知らずに、糖尿病の犬に与えてしまうと非常に危険です。
少量ずつ与えれば血糖値の急上昇を抑えることはできますが、リスクがあるので無理してじゃがいもを与える必要性はありません。
 じゃがいもは活用幅が広い食材であり、人用の食べものとして加工されたものが多く流通しています。
犬にじゃがいもを与えてもよいことを知れば人用に加工されたものを与えても問題ないと考えてしまいがちですが、
加工されている物には人が好みやすい味付けにするために油や添加物、食塩などが使用されていることが多いです。
人にとってはあまり害のない物ですが、犬にとってはあまり良いものとは言えないので、人用に加工されたじゃがいもは与えないようにしましょう。
人用のお菓子にはじゃがいもが使用されている場合も多いので、おやつ代わりとして与えないように注意する必要があります。
じゃがいもは活用幅が広い食材であり、人用の食べものとして加工されたものが多く流通しています。
犬にじゃがいもを与えてもよいことを知れば人用に加工されたものを与えても問題ないと考えてしまいがちですが、
加工されている物には人が好みやすい味付けにするために油や添加物、食塩などが使用されていることが多いです。
人にとってはあまり害のない物ですが、犬にとってはあまり良いものとは言えないので、人用に加工されたじゃがいもは与えないようにしましょう。
人用のお菓子にはじゃがいもが使用されている場合も多いので、おやつ代わりとして与えないように注意する必要があります。
 犬はじゃがいもの芽や皮に含まれているソラニンに弱いと考えられ、人が間違って食べた時よりも症状が悪化してしまうケースが多いです。
また、上記でも紹介したように皮は消化に悪いことも関係して下痢や嘔吐をしてしまうこともあります。
芽が出てしまったじゃがいもであれば芽を取り除くことはもちろんですが、深めに取り除くようにしましょう。
皮も同じように人が食べる際にするよりも少し厚めにとるように心がけましょう。
皮や芽にソラニンが多く含まれているだけではなく、近い部分にも成分が含まれている可能性もあるため、万が一のことを想定しての作業となります。
もったいないと考えてしまう場合もありますが、愛犬の健康管理を最優先しましょう。
犬はじゃがいもの芽や皮に含まれているソラニンに弱いと考えられ、人が間違って食べた時よりも症状が悪化してしまうケースが多いです。
また、上記でも紹介したように皮は消化に悪いことも関係して下痢や嘔吐をしてしまうこともあります。
芽が出てしまったじゃがいもであれば芽を取り除くことはもちろんですが、深めに取り除くようにしましょう。
皮も同じように人が食べる際にするよりも少し厚めにとるように心がけましょう。
皮や芽にソラニンが多く含まれているだけではなく、近い部分にも成分が含まれている可能性もあるため、万が一のことを想定しての作業となります。
もったいないと考えてしまう場合もありますが、愛犬の健康管理を最優先しましょう。
 犬にじゃがいもを与える際には適切な分量を与える必要があります。
じゃがいもはカロリーが高い食材であるため、与えすぎてしまうと肥満体質になってしまいます。
適したじゃがいもの量は体格によって変わり、5㎏の犬であれば20~30g程度がおすすめです。
量を守ることと上記でしましたように小さくして与えることも忘れないようにしましょう。
もし、適量を与えたにも関わらず下痢や嘔吐をするのであれば少し減らして様子を見るようにすることが大切です。
さらに量を減らしたにも関わらず、嘔吐や下痢の症状が出るのであればじゃがいものに対してアレルギーを持っている可能性もあるため、一度病院で検査してもらうようにしましょう。
アレルギーがある場合は痒がる行動をしたり、皮膚に炎症や湿疹が出ることもあります。
犬にじゃがいもを与える際には適切な分量を与える必要があります。
じゃがいもはカロリーが高い食材であるため、与えすぎてしまうと肥満体質になってしまいます。
適したじゃがいもの量は体格によって変わり、5㎏の犬であれば20~30g程度がおすすめです。
量を守ることと上記でしましたように小さくして与えることも忘れないようにしましょう。
もし、適量を与えたにも関わらず下痢や嘔吐をするのであれば少し減らして様子を見るようにすることが大切です。
さらに量を減らしたにも関わらず、嘔吐や下痢の症状が出るのであればじゃがいものに対してアレルギーを持っている可能性もあるため、一度病院で検査してもらうようにしましょう。
アレルギーがある場合は痒がる行動をしたり、皮膚に炎症や湿疹が出ることもあります。
 犬にじゃがいもを与えても問題ありませんが、芽や皮を取り除くことや小さく刻むなどの加工をしなければならず、意外と手間もかかってしまいます。
そのため、じゃがいもを与えることで得られるメリットが特にないのであれば無理に与える必要性も低くなります。
しかし、犬にじゃがいもを与えることで得られる効果は多くあり、求めている効果があるのであれば注意点を把握してじゃがいもを与えることをおすすめします。
次に、じゃがいもを犬に与えた際に得られるメリットを紹介するので参考にしてください。
犬にじゃがいもを与えても問題ありませんが、芽や皮を取り除くことや小さく刻むなどの加工をしなければならず、意外と手間もかかってしまいます。
そのため、じゃがいもを与えることで得られるメリットが特にないのであれば無理に与える必要性も低くなります。
しかし、犬にじゃがいもを与えることで得られる効果は多くあり、求めている効果があるのであれば注意点を把握してじゃがいもを与えることをおすすめします。
次に、じゃがいもを犬に与えた際に得られるメリットを紹介するので参考にしてください。
 じゃがいもにはビタミンCが多く含まれており、人はもちろんですが、犬にも必要な栄養素です。
犬の場合は体内でビタミンCを作ることはできますが、それだけでは足らないため、人と同じように食事からビタミンCを摂取する必要があります。
ビタミンCには免疫力を高めたり、コラーゲン不足を防ぐこともできます。
免疫力が低下してしまうとさまざまな病気になるリスクがあり、コラーゲンが不足すれば関節疾患があらわれるリスクが高まり、高齢になった際に歩行できなくなる可能性も充分にあります。
そのほかにも老化防止の効果もビタミンCには期待でき、白内障予防の効果もあります。
犬は高齢になればなるほど白内障になるリスクが高いため、若いころからじゃがいもを与えていれば老犬にあっても視力を失うことを未然に防ぎます。
じゃがいもにはビタミンCが多く含まれており、人はもちろんですが、犬にも必要な栄養素です。
犬の場合は体内でビタミンCを作ることはできますが、それだけでは足らないため、人と同じように食事からビタミンCを摂取する必要があります。
ビタミンCには免疫力を高めたり、コラーゲン不足を防ぐこともできます。
免疫力が低下してしまうとさまざまな病気になるリスクがあり、コラーゲンが不足すれば関節疾患があらわれるリスクが高まり、高齢になった際に歩行できなくなる可能性も充分にあります。
そのほかにも老化防止の効果もビタミンCには期待でき、白内障予防の効果もあります。
犬は高齢になればなるほど白内障になるリスクが高いため、若いころからじゃがいもを与えていれば老犬にあっても視力を失うことを未然に防ぎます。
 犬にサクランボを与えるのは問題ありません。
さくらんぼは甘く人も好んで食べますが、犬も同じように好んで食べる傾向があります。
犬にさくらんぼを与える際は量に注意するようにしましょう。
いくら食べて害になる成分などが含まれていなくても食べ過ぎてしまうと体調を崩してしまう原因になってしまいます。
犬にさくらんぼを与える際は少量に抑え、食べた後に体調を崩してしまわないか様子見することも大切で、万が一下痢などの症状が起きた場合は与えることを控えることをおすすめします。
犬にサクランボを与えるのは問題ありません。
さくらんぼは甘く人も好んで食べますが、犬も同じように好んで食べる傾向があります。
犬にさくらんぼを与える際は量に注意するようにしましょう。
いくら食べて害になる成分などが含まれていなくても食べ過ぎてしまうと体調を崩してしまう原因になってしまいます。
犬にさくらんぼを与える際は少量に抑え、食べた後に体調を崩してしまわないか様子見することも大切で、万が一下痢などの症状が起きた場合は与えることを控えることをおすすめします。
 犬がさくらんぼを食べることで基本的に体調を崩してしまうことはありませんが、注意しなければならないポイントがいくつかあります。
そのため、さくらんぼを犬に与える際に注意点を把握せずに与えてしまうことは危険です。
なので、愛犬にさくらんぼを与える前に注意点を把握しておくことをおすすめします。
注意点を無視して与えてしまった場合は高い確率で体調を崩してしまい、愛犬を苦しませてしまう原因になってしまいます。
次に、さくらんぼを与える際の注意点を紹介するので覚えておきましょう。
犬がさくらんぼを食べることで基本的に体調を崩してしまうことはありませんが、注意しなければならないポイントがいくつかあります。
そのため、さくらんぼを犬に与える際に注意点を把握せずに与えてしまうことは危険です。
なので、愛犬にさくらんぼを与える前に注意点を把握しておくことをおすすめします。
注意点を無視して与えてしまった場合は高い確率で体調を崩してしまい、愛犬を苦しませてしまう原因になってしまいます。
次に、さくらんぼを与える際の注意点を紹介するので覚えておきましょう。
 さくらんぼは柄の部分がついたまま販売されていることも多く、人も柄の部分を食べないように犬にも与えないようにしましょう。
柄の部分は消化されないため、胃や腸に詰まってしまったり、喉に引っかかってしまうリスクもあります。
犬は柄の部分をお構いなしに食べてしまうため、柄がついているさくらんぼを与えるのであれば最初に取り外してから与えるようにしましょう。
加工品などは柄が取り外されている場合も多いですが、種は取り除かれていないことも多いので注意が必要です。
さくらんぼは柄の部分がついたまま販売されていることも多く、人も柄の部分を食べないように犬にも与えないようにしましょう。
柄の部分は消化されないため、胃や腸に詰まってしまったり、喉に引っかかってしまうリスクもあります。
犬は柄の部分をお構いなしに食べてしまうため、柄がついているさくらんぼを与えるのであれば最初に取り外してから与えるようにしましょう。
加工品などは柄が取り外されている場合も多いですが、種は取り除かれていないことも多いので注意が必要です。
 犬にさくらんぼを与えることでさまざまな効果を得ることができます。
さくらんぼはあまり気軽に購入できるものではないので、わざわざ犬に与える機会も少ないのではないでしょうか。
しかし、得られる効果を知ることで少し高くてもさくらんぼを犬に与えてメリットを得たいと考える飼い主は少なからずいます。
犬にさくらんぼを与えることでさまざまな効果を得ることができます。
さくらんぼはあまり気軽に購入できるものではないので、わざわざ犬に与える機会も少ないのではないでしょうか。
しかし、得られる効果を知ることで少し高くてもさくらんぼを犬に与えてメリットを得たいと考える飼い主は少なからずいます。
 さくらんぼにはアントシアニンと呼ばれているポリフェノールの一種が豊富に含まれています。
アントシアニンは抗酸化力を高める効果が期待でき、健康的な体に仕上げてくれます。
アントシアニンの抗酸化作用は主に、血管の拡張や毛細血管の保護など血管類を強めることができます。
そのため、血管や血液が関係している病気を未然に防ぐことが期待でき、動脈硬化や狭心症予防などの効果があります。
高齢になればなるほど血管がもろくなりやすく、詰まりやすいので、老犬のおやつとしてさくらんぼはおすすめです。
さくらんぼにはアントシアニンと呼ばれているポリフェノールの一種が豊富に含まれています。
アントシアニンは抗酸化力を高める効果が期待でき、健康的な体に仕上げてくれます。
アントシアニンの抗酸化作用は主に、血管の拡張や毛細血管の保護など血管類を強めることができます。
そのため、血管や血液が関係している病気を未然に防ぐことが期待でき、動脈硬化や狭心症予防などの効果があります。
高齢になればなるほど血管がもろくなりやすく、詰まりやすいので、老犬のおやつとしてさくらんぼはおすすめです。
 さくらんぼには食物繊維が多く含まれています。
食物繊維は便通を良くする効果があり、便秘解消に一役買ってくれます。
そのため、便秘に悩まされている愛犬にさくらんぼを与えてみてはいかがでしょうか。
便秘になるとお腹が張ったり、腹痛を起こしてしまうこともあり、軽い症状だと甘く見ないようにしましょう。
毎日の排便する回数や量をチェックすることで愛犬が便秘なのかどうかを知ることができます。
食物繊維は主に、野菜類に含まれていますが、好んで野菜類を食べる犬は少なく、便秘にもなりやすいです。
さくらんぼには食物繊維が多く含まれています。
食物繊維は便通を良くする効果があり、便秘解消に一役買ってくれます。
そのため、便秘に悩まされている愛犬にさくらんぼを与えてみてはいかがでしょうか。
便秘になるとお腹が張ったり、腹痛を起こしてしまうこともあり、軽い症状だと甘く見ないようにしましょう。
毎日の排便する回数や量をチェックすることで愛犬が便秘なのかどうかを知ることができます。
食物繊維は主に、野菜類に含まれていますが、好んで野菜類を食べる犬は少なく、便秘にもなりやすいです。
 犬にさくらんぼを与える際には量に注意する必要があることを紹介してきましたが、具体的にどの程度の量が適量なのかわからない場合が多いです。
基本的に犬の体重によって与えてもよい量も変わってきます。
例えば犬の体重が1㎏であれば3gが適量となります。
5㎏であれば11g、10㎏であれば18gと変わってきます。
ちなみに、さくらんぼ1粒は約6g前後である場合が多く、1㎏の子犬や小型犬の場合は1粒与えるだけでも多いことになってしまいます。
適量以上与えてしまうと下痢などの症状を起こしてしまったり、さくらんぼにアレルギーがある場合はかゆみや呼吸困難などの症状も出てしまいます。
また、糖分が多いさくらんぼであるため、食べすぎは肥満の原因にもなります。
犬にさくらんぼを与える際には量に注意する必要があることを紹介してきましたが、具体的にどの程度の量が適量なのかわからない場合が多いです。
基本的に犬の体重によって与えてもよい量も変わってきます。
例えば犬の体重が1㎏であれば3gが適量となります。
5㎏であれば11g、10㎏であれば18gと変わってきます。
ちなみに、さくらんぼ1粒は約6g前後である場合が多く、1㎏の子犬や小型犬の場合は1粒与えるだけでも多いことになってしまいます。
適量以上与えてしまうと下痢などの症状を起こしてしまったり、さくらんぼにアレルギーがある場合はかゆみや呼吸困難などの症状も出てしまいます。
また、糖分が多いさくらんぼであるため、食べすぎは肥満の原因にもなります。
 有名なことわざや慣用句には動物に例えに使ったものが多く存在しています。
中には犬にまつわることわざや慣用句もあるので、ここでは犬の有名なことわざや慣用句をご紹介します。
有名なことわざや慣用句には動物に例えに使ったものが多く存在しています。
中には犬にまつわることわざや慣用句もあるので、ここでは犬の有名なことわざや慣用句をご紹介します。
 兔を見て犬を呼ぶとは、事を見極めてから対策をしても遅くないということです。
また、一見手遅れに見えても、対策次第で間に合うこともあるのであきらめてはいけないという意味もあります。
兔を見つけてから猟犬を呼ぶという意味からつけられたことわざなのですが、兔を見つけてから猟犬を読んでも遅すぎるとの意味で手遅れの例えとして用いられることも。
同じ意味のことわざに「兔を見て鷹を放つ」があります。
兔を見て犬を呼ぶとは、事を見極めてから対策をしても遅くないということです。
また、一見手遅れに見えても、対策次第で間に合うこともあるのであきらめてはいけないという意味もあります。
兔を見つけてから猟犬を呼ぶという意味からつけられたことわざなのですが、兔を見つけてから猟犬を読んでも遅すぎるとの意味で手遅れの例えとして用いられることも。
同じ意味のことわざに「兔を見て鷹を放つ」があります。
 犬一代に狸一匹とは大きなチャンスは一生に一度というほど、なかなか巡り合うことはないということのたとえで、絶えず獲物を探し回っている犬であっても、狸のような大きな獲物を取るのは一緒に一度くらいのものという意味です。
例文をご紹介すると「犬一代に狸一匹で、今回のようなチャンスは二度とないから、挑戦してみよう!」と使うことができますね。
類語のことわざには「鍛冶屋一代の剣」などがあります。
犬一代に狸一匹とは大きなチャンスは一生に一度というほど、なかなか巡り合うことはないということのたとえで、絶えず獲物を探し回っている犬であっても、狸のような大きな獲物を取るのは一緒に一度くらいのものという意味です。
例文をご紹介すると「犬一代に狸一匹で、今回のようなチャンスは二度とないから、挑戦してみよう!」と使うことができますね。
類語のことわざには「鍛冶屋一代の剣」などがあります。
 犬も朋輩鷹も朋輩の読み方は「いぬもほうばいたかもほうばい」です。
何だか難しそうなことわざですが、意味は「鷹狩りにおける犬と鷹のように、役割や地位など待遇が異なっていても同じ主人に仕えていれば同僚であることに変わりはないこと」となります。
「朋輩」とは同じ主人に仕える仲間、同僚を指しており、上下関係なく、平等な関係であることを伝えたい時に活用することわざです。
注意しなければいけないのがこのことわざは上の立場の人が下の立場の人に対して使用することわざあるという点です。
目上の人に対してこのことわざを使うと失礼にあたるので使い方には十分注意しましょう。
犬も朋輩鷹も朋輩の読み方は「いぬもほうばいたかもほうばい」です。
何だか難しそうなことわざですが、意味は「鷹狩りにおける犬と鷹のように、役割や地位など待遇が異なっていても同じ主人に仕えていれば同僚であることに変わりはないこと」となります。
「朋輩」とは同じ主人に仕える仲間、同僚を指しており、上下関係なく、平等な関係であることを伝えたい時に活用することわざです。
注意しなければいけないのがこのことわざは上の立場の人が下の立場の人に対して使用することわざあるという点です。
目上の人に対してこのことわざを使うと失礼にあたるので使い方には十分注意しましょう。
 ことわざは日本だけではなく海外にも存在しています。
中には犬を例えにつかったものもいくつかあるので、ここではイギリスで使われている犬にまつわることわざをご紹介します。
ことわざは日本だけではなく海外にも存在しています。
中には犬を例えにつかったものもいくつかあるので、ここではイギリスで使われている犬にまつわることわざをご紹介します。
 犬を愛さない者は紳士でありえないの意味は、犬はとにかく愛すべき存在であるということを意味しています。
ヨーロッパの他の国々とは異なり、イギリスでは犬を牧羊犬としてではなく、飼い犬として可愛がっていました。
そのような犬を大事にする国であるイギリスならではの歴史的背景から生まれたことわざです。
犬を愛さない者は紳士でありえないの意味は、犬はとにかく愛すべき存在であるということを意味しています。
ヨーロッパの他の国々とは異なり、イギリスでは犬を牧羊犬としてではなく、飼い犬として可愛がっていました。
そのような犬を大事にする国であるイギリスならではの歴史的背景から生まれたことわざです。
 続いて海外のことわざアメリカ編で犬にまつわることわざについて複数ご紹介します。
海外にも色んな犬を使うことわざがあって面白いですよね!
続いて海外のことわざアメリカ編で犬にまつわることわざについて複数ご紹介します。
海外にも色んな犬を使うことわざがあって面白いですよね!
 人を愛するならその飼い犬も愛せよの意味は、主人を尊敬するのであれば、主人の飼っている犬までも大切にするはずであるという考えから生まれたことわざです。
自分のことを愛しているのならば、自分の欠点も含めて全てを愛してほしいという意味があります。
日本では反対の意味のことわざに「坊主憎けりゃ、袈裟まで憎い」というものが当たります。
人を愛するならその飼い犬も愛せよの意味は、主人を尊敬するのであれば、主人の飼っている犬までも大切にするはずであるという考えから生まれたことわざです。
自分のことを愛しているのならば、自分の欠点も含めて全てを愛してほしいという意味があります。
日本では反対の意味のことわざに「坊主憎けりゃ、袈裟まで憎い」というものが当たります。
 続いて海外のことわざフランス編をご紹介します。
海外のことわざを見ていると犬も人間も平等という考え方がひしひしと伝わってきて素敵なものが多いのはわかりますね。
フランスのことわざにはどんなものがあるのでしょうか。
続いて海外のことわざフランス編をご紹介します。
海外のことわざを見ていると犬も人間も平等という考え方がひしひしと伝わってきて素敵なものが多いのはわかりますね。
フランスのことわざにはどんなものがあるのでしょうか。
 犬の司教様の顔をじっと見るの意味には、2つあり、1つ目は「司教様は大衆の目下の人に興味深い目でじろじろと見られても、怒ってはいけない」という意味で、
2つ目は犬の立場に立った場合の考え方で「自分より身分の高い人や目上の人などに、要求したいことや言いたいことがある時は、臆さず堂々と伝えるべきである」ということを意味しています。
現代であれば、上司と部下や先生と生徒、先輩と後輩などの上下関係に置き換えると分かりやすいかもしれませんね!
犬の司教様の顔をじっと見るの意味には、2つあり、1つ目は「司教様は大衆の目下の人に興味深い目でじろじろと見られても、怒ってはいけない」という意味で、
2つ目は犬の立場に立った場合の考え方で「自分より身分の高い人や目上の人などに、要求したいことや言いたいことがある時は、臆さず堂々と伝えるべきである」ということを意味しています。
現代であれば、上司と部下や先生と生徒、先輩と後輩などの上下関係に置き換えると分かりやすいかもしれませんね!
 続いてのことわざは中国編です。
中国にはさまざまなことわざがありそうですね。
犬にまつわるどんなことわざがあるのかご紹介します。
続いてのことわざは中国編です。
中国にはさまざまなことわざがありそうですね。
犬にまつわるどんなことわざがあるのかご紹介します。
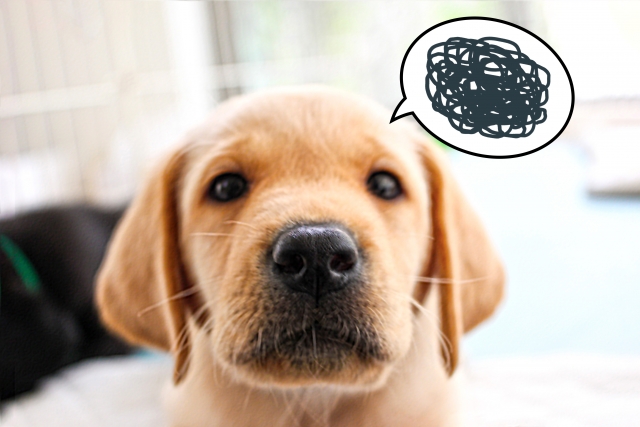 犬の屁も通らないとは、文章がでたらめなことを表すことわざとして使われています。
また、くだらないことを言うなという意味で使うこともあるでしょう。
日本で使われている似たようなことわざには「犬も食わぬ」があります。
犬の屁も通らないとは、文章がでたらめなことを表すことわざとして使われています。
また、くだらないことを言うなという意味で使うこともあるでしょう。
日本で使われている似たようなことわざには「犬も食わぬ」があります。
 次に海外のことわざその他の国地域編をご紹介します。
このように犬にまつわることわざを調べてみると、日本だけではなく海外にもたくさんあることがわかりますね。
次に海外のことわざその他の国地域編をご紹介します。
このように犬にまつわることわざを調べてみると、日本だけではなく海外にもたくさんあることがわかりますね。
 つづいてイエメンで使われている主人を大切に思う者は犬も大切に思うということわざです。
意味は大切に思う人、愛するものがあれば、その人の家族やその人に関わずものすべてが大切なもの、愛おしいものに感じられるという意味になります。
主人を尊敬するものは、主人の飼っている犬まで大切にするという考えからきています。
先ほどご紹介したアメリカのことわざ「人を愛するならその飼い犬も愛せよ」と同じような意味ですね。
つづいてイエメンで使われている主人を大切に思う者は犬も大切に思うということわざです。
意味は大切に思う人、愛するものがあれば、その人の家族やその人に関わずものすべてが大切なもの、愛おしいものに感じられるという意味になります。
主人を尊敬するものは、主人の飼っている犬まで大切にするという考えからきています。
先ほどご紹介したアメリカのことわざ「人を愛するならその飼い犬も愛せよ」と同じような意味ですね。
 犬にコーヒーを飲ませることは絶対にNGです。
なぜかというと、コーヒーに含まれているカフェインを過剰に摂取すると、カフェイン中毒と呼ばれる命に関わる疾患を引き起こすからです。
犬は人間よりもずっと体が小さいため、カフェイン中毒に陥りやすい傾向にあるのです。
うっかりしてコーヒーが入ったままのカップを置きっぱなしにしていると、匂いに惹かれてなめてしまうかもしれません。
不注意で中毒症状を起こすことのないように気をつけましょう。
犬にコーヒーを飲ませることは絶対にNGです。
なぜかというと、コーヒーに含まれているカフェインを過剰に摂取すると、カフェイン中毒と呼ばれる命に関わる疾患を引き起こすからです。
犬は人間よりもずっと体が小さいため、カフェイン中毒に陥りやすい傾向にあるのです。
うっかりしてコーヒーが入ったままのカップを置きっぱなしにしていると、匂いに惹かれてなめてしまうかもしれません。
不注意で中毒症状を起こすことのないように気をつけましょう。
 犬がコーヒーを誤飲してカフェイン中毒の恐れがある場合は次のような症状が見られます。
すぐに動物病院で診察してもらいましょう。
また、特別変わった様子がなくても、獣医師の判断を確認するようにし、しばらく様子をよく観察してください。
犬がコーヒーを誤飲してカフェイン中毒の恐れがある場合は次のような症状が見られます。
すぐに動物病院で診察してもらいましょう。
また、特別変わった様子がなくても、獣医師の判断を確認するようにし、しばらく様子をよく観察してください。
 コーヒーを摂取してすぐに何か異変が起こるというよりも摂取した1~2時間後ほどで 下痢・嘔吐などの症状が現れる可能性があります。
コーヒーは液体なので、体内への吸収が早いとも言われており、急な嘔吐や下痢に苦しむかもしれません。
普段でも消化の悪いものを食べて嘔吐や下痢を起こすことはありますが、一時的なもので元気があればそう問題はありません。
しかし、ぐったりとして元気がないとか逆に興奮状態でよだれが多い、呼吸が荒いなどの症状が見られれば中毒症状の可能性があります。
コーヒーを摂取してすぐに何か異変が起こるというよりも摂取した1~2時間後ほどで 下痢・嘔吐などの症状が現れる可能性があります。
コーヒーは液体なので、体内への吸収が早いとも言われており、急な嘔吐や下痢に苦しむかもしれません。
普段でも消化の悪いものを食べて嘔吐や下痢を起こすことはありますが、一時的なもので元気があればそう問題はありません。
しかし、ぐったりとして元気がないとか逆に興奮状態でよだれが多い、呼吸が荒いなどの症状が見られれば中毒症状の可能性があります。
 犬の命に危険が及ぶコーヒーの摂取量は犬の体重や個体差によって異なります。
一般的には犬の体重1kgに対しカフェイン量120~200mg程度が致死量と言われています。
おおよそ、コーヒー1杯(150ml)にはカフェインが60~90mg程度含まれているので、体重3kgの犬の場合コーヒー3杯分を飲めば危険だということです。
人間にとってはカフェイン致死量は3g、コーヒー25杯分くらいですので、犬にとってはその20分の1の量でも生命が危ないことを覚えておきましょう。
大型犬から超小型犬まで、危険となるカフェイン量を説明します。
犬の命に危険が及ぶコーヒーの摂取量は犬の体重や個体差によって異なります。
一般的には犬の体重1kgに対しカフェイン量120~200mg程度が致死量と言われています。
おおよそ、コーヒー1杯(150ml)にはカフェインが60~90mg程度含まれているので、体重3kgの犬の場合コーヒー3杯分を飲めば危険だということです。
人間にとってはカフェイン致死量は3g、コーヒー25杯分くらいですので、犬にとってはその20分の1の量でも生命が危ないことを覚えておきましょう。
大型犬から超小型犬まで、危険となるカフェイン量を説明します。
 体重10~25kgの中型犬は、1200mg(1.2g)~3000mg(3.0g)のカフェイン摂取量が命取りとなります。
大型犬よりはずっと体重が軽いので、致死量も半分以下の場合があります。
一概にこの量が危険な致死量というのではなく、少しの量だとしても中毒症状を起こす危険があります。
特に心臓や腎臓に持病を抱えている場合は、少量であっても体調を崩すきっかけとなる可能性があります。
また砂糖や牛乳が入っているコーヒーは、犬は甘いものが好きなので味と匂いを覚えているかもしれません。
飼い主の目を盗んで飲んでいるということもあり、少量でも繰り返すことでだんだんカフェイン量が増えてきますのでよく注意しましょう。
体重10~25kgの中型犬は、1200mg(1.2g)~3000mg(3.0g)のカフェイン摂取量が命取りとなります。
大型犬よりはずっと体重が軽いので、致死量も半分以下の場合があります。
一概にこの量が危険な致死量というのではなく、少しの量だとしても中毒症状を起こす危険があります。
特に心臓や腎臓に持病を抱えている場合は、少量であっても体調を崩すきっかけとなる可能性があります。
また砂糖や牛乳が入っているコーヒーは、犬は甘いものが好きなので味と匂いを覚えているかもしれません。
飼い主の目を盗んで飲んでいるということもあり、少量でも繰り返すことでだんだんカフェイン量が増えてきますのでよく注意しましょう。
 体重1~3kgの超小型犬だと、カフェインで死に至ってしまう摂取量は120mg(0.12g)~360mg(0.36g)程度だと言われています。
人間の致死量からすると10分の1程度でも重症化してしまいます。
最も危険性が高い犬種です。
チワワやトイプードル、豆柴など小さな犬種はフードやおやつの量もほんの少しです。
それ以外に人間の嗜好品を与える必要は全くありません。
小型の犬は内臓も小さく、予想される量より少なくても中毒症状が出る可能性があります。
さらに、これらの犬種の子犬ではより注意が必要です。
子犬は消化器官が成犬より発達していません。
細心の注意を払っておきましょう。
体重1~3kgの超小型犬だと、カフェインで死に至ってしまう摂取量は120mg(0.12g)~360mg(0.36g)程度だと言われています。
人間の致死量からすると10分の1程度でも重症化してしまいます。
最も危険性が高い犬種です。
チワワやトイプードル、豆柴など小さな犬種はフードやおやつの量もほんの少しです。
それ以外に人間の嗜好品を与える必要は全くありません。
小型の犬は内臓も小さく、予想される量より少なくても中毒症状が出る可能性があります。
さらに、これらの犬種の子犬ではより注意が必要です。
子犬は消化器官が成犬より発達していません。
細心の注意を払っておきましょう。
 犬がコーヒーを飲むことで起こる危険性がおわかりいただけたことと思います。
もし誤飲誤食をした場合は、たとえ少量でもまず動物病院に連絡し獣医の判断を仰ぎましょう。
症状が出ていると焦ってしまいますが、落ち着いて犬の様子を観察するようにしましょう。
次に詳しく説明します。
犬がコーヒーを飲むことで起こる危険性がおわかりいただけたことと思います。
もし誤飲誤食をした場合は、たとえ少量でもまず動物病院に連絡し獣医の判断を仰ぎましょう。
症状が出ていると焦ってしまいますが、落ち着いて犬の様子を観察するようにしましょう。
次に詳しく説明します。
 病院へすぐに向かいたい時もできればまずかかりつけの獣医師に電話して、コーヒーをどのぐらい摂取したのか、摂取してから経過した時間、そして現在の犬の状況を伝えて、指示を仰ぎましょう。
意思の的確な判断を受けられ、到着してからの処置もスムーズに進みます。
また摂取量や犬の状態で自宅での観察でよいという判断が出るかもしれません。
その場合に家で対処できることなども聞けると思います。
かかりつけの医師であれば、持病やアレルギーの有無を把握しているとは思いますが、念の為そのような点も一緒に伝えておきましょう。
病院が休診日であったり、夜間に誤飲することもあるでしょう。
その時は夜間の受付をしている病院などに電話をして連絡しましょう。
病院へすぐに向かいたい時もできればまずかかりつけの獣医師に電話して、コーヒーをどのぐらい摂取したのか、摂取してから経過した時間、そして現在の犬の状況を伝えて、指示を仰ぎましょう。
意思の的確な判断を受けられ、到着してからの処置もスムーズに進みます。
また摂取量や犬の状態で自宅での観察でよいという判断が出るかもしれません。
その場合に家で対処できることなども聞けると思います。
かかりつけの医師であれば、持病やアレルギーの有無を把握しているとは思いますが、念の為そのような点も一緒に伝えておきましょう。
病院が休診日であったり、夜間に誤飲することもあるでしょう。
その時は夜間の受付をしている病院などに電話をして連絡しましょう。
 コーヒーだけでなく、コーヒー豆やコーヒーミルクなどの関連食品も、犬には与えてはいけません。
コーヒーゼリーなどにもカフェインが含まれていて、ドリップコーヒーと比べると少ない分量ですが、同様にコーヒーを使ったお菓子も食べさせないようにします。
牛乳や砂糖が入っていると甘く感じるので犬はこっそり口にするかもしれません。
犬には届かない場所で管理するようにしましょう。
またカフェインを含む飲み物は、コーヒーだけではありません。
ココアや紅茶、ウーロン茶、抹茶、ほうじ茶、コーラなどにも入っています。
玉露はコーヒーよりもカフェインが多いほどです。
栄養ドリンクなどにも含まれますので、犬が飲むものは基本的には水またはヤギミルクなどペット用として販売されているものにしておきましょう。
コーヒーだけでなく、コーヒー豆やコーヒーミルクなどの関連食品も、犬には与えてはいけません。
コーヒーゼリーなどにもカフェインが含まれていて、ドリップコーヒーと比べると少ない分量ですが、同様にコーヒーを使ったお菓子も食べさせないようにします。
牛乳や砂糖が入っていると甘く感じるので犬はこっそり口にするかもしれません。
犬には届かない場所で管理するようにしましょう。
またカフェインを含む飲み物は、コーヒーだけではありません。
ココアや紅茶、ウーロン茶、抹茶、ほうじ茶、コーラなどにも入っています。
玉露はコーヒーよりもカフェインが多いほどです。
栄養ドリンクなどにも含まれますので、犬が飲むものは基本的には水またはヤギミルクなどペット用として販売されているものにしておきましょう。
 愛犬の中がキュルキュル鳴っているのを聞いたことはありませんか?
そんな音を聞くと「お腹が痛いのかな?」と不安になってしまいますよね。
お腹が鳴る原因には確かに体調不良を示しているものもあるのですが、他にもさまざまな理由があります。
ここでは、犬のお腹がキュルキュル鳴る理由についてご紹介します。
愛犬の中がキュルキュル鳴っているのを聞いたことはありませんか?
そんな音を聞くと「お腹が痛いのかな?」と不安になってしまいますよね。
お腹が鳴る原因には確かに体調不良を示しているものもあるのですが、他にもさまざまな理由があります。
ここでは、犬のお腹がキュルキュル鳴る理由についてご紹介します。
 お腹が空いている時や食べ物を消化しようとしている時に胃や腸が動いて音が鳴ることがあります。
これも人間と同じですよね!
愛犬がいつもと同じ様子で、痛いとかしんどいなどの様子が見られない場合は、生理現象である可能性が高いので、心配する必要はないでしょう。
お腹が空いている時や食べ物を消化しようとしている時に胃や腸が動いて音が鳴ることがあります。
これも人間と同じですよね!
愛犬がいつもと同じ様子で、痛いとかしんどいなどの様子が見られない場合は、生理現象である可能性が高いので、心配する必要はないでしょう。
 体調が悪くなくてもお腹がキュルキュルなっている場合は、他の理由も考えられるでしょう。
病気でなくても飼い主からすれば心配ですよね。
そこで病気以外にお腹がキュルキュル鳴る理由についてご紹介します。
体調が悪くなくてもお腹がキュルキュルなっている場合は、他の理由も考えられるでしょう。
病気でなくても飼い主からすれば心配ですよね。
そこで病気以外にお腹がキュルキュル鳴る理由についてご紹介します。
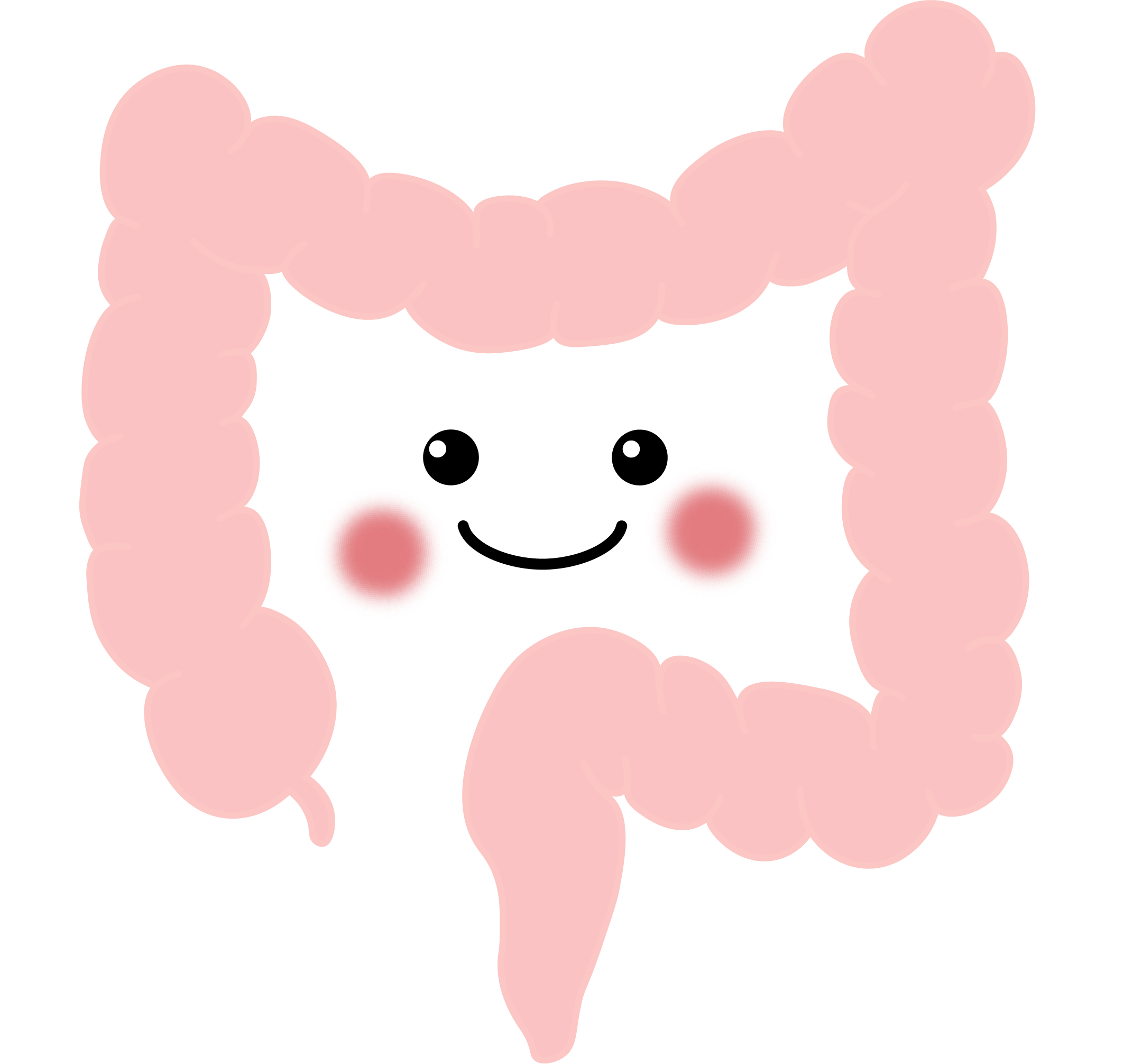 犬は基本的に早食いです。
それに咀嚼していないことも多いですよね。
急いでご飯を食べることで食べ物と一緒に空気を飲み込んでしまったり、ご飯が体内で異常発酵することで、ガスが溜まりお腹が鳴ってしまうのです。
便秘のときも腸内にガスが溜まりやすくなります。
ガスが溜まり過ぎるとおならやげっぷをする頻度が増えるので、そのような現象が頻繁に見られる場合は一度受診することをおすすめします。
犬は基本的に早食いです。
それに咀嚼していないことも多いですよね。
急いでご飯を食べることで食べ物と一緒に空気を飲み込んでしまったり、ご飯が体内で異常発酵することで、ガスが溜まりお腹が鳴ってしまうのです。
便秘のときも腸内にガスが溜まりやすくなります。
ガスが溜まり過ぎるとおならやげっぷをする頻度が増えるので、そのような現象が頻繁に見られる場合は一度受診することをおすすめします。
 犬は基本的に口で物を判断します。
そのため、食べる物かどうかを確認するために誤飲してしまうこともあるでしょう。
誤飲した場合、異物を排出しようとして腸の運動が起こることで、お腹が鳴ることがあります。
また、便秘や嘔吐が見られることもあるので、何か誤飲した物はないか確認し、しっかり様子を見てあげてください。
少しでも様子がおかしい場合は受診するようにしましょう。
犬は基本的に口で物を判断します。
そのため、食べる物かどうかを確認するために誤飲してしまうこともあるでしょう。
誤飲した場合、異物を排出しようとして腸の運動が起こることで、お腹が鳴ることがあります。
また、便秘や嘔吐が見られることもあるので、何か誤飲した物はないか確認し、しっかり様子を見てあげてください。
少しでも様子がおかしい場合は受診するようにしましょう。
 病気の中でも膵炎の場合、お腹がキュルキュル鳴ることがあります。
膵炎は膵臓に炎症が起こり、消化酵素が膵臓自体を溶かしてしまう病気で、最悪の場合、死に至る怖い病気です。
症状としては、激しい嘔吐や食欲不振、強い腹痛が特徴です。
犬は腹痛を感じると、前足を伸ばして頭を下げ、腰を持ち上げる「祈りのポーズ」をすることがあるので、この姿勢をとってしんどそうにしている場合は膵炎を疑いましょう。
病気の中でも膵炎の場合、お腹がキュルキュル鳴ることがあります。
膵炎は膵臓に炎症が起こり、消化酵素が膵臓自体を溶かしてしまう病気で、最悪の場合、死に至る怖い病気です。
症状としては、激しい嘔吐や食欲不振、強い腹痛が特徴です。
犬は腹痛を感じると、前足を伸ばして頭を下げ、腰を持ち上げる「祈りのポーズ」をすることがあるので、この姿勢をとってしんどそうにしている場合は膵炎を疑いましょう。
 病気以外でお腹がキュルキュルなる場合は、少しの工夫で対策することができます。
ここでは犬のお腹がキュルキュルした場合の対策法についてご紹介します。
病気以外でお腹がキュルキュルなる場合は、少しの工夫で対策することができます。
ここでは犬のお腹がキュルキュルした場合の対策法についてご紹介します。
 前述しましたが、お腹が空いてキュルキュルなっている場合は、エサの回数を増やすことで改善できます。
ですが、エサの量を増やすと肥満の原因になってしまう場合があるので、普段を同じ量を複数回に分けて与えるようにし、できるだけ空腹の時間が少なくするよう工夫してあげてください。
それでもお腹が空いている場合は、低カロリーのフードに変更し、量を少しだけ増やすことで解消できるでしょう。
前述しましたが、お腹が空いてキュルキュルなっている場合は、エサの回数を増やすことで改善できます。
ですが、エサの量を増やすと肥満の原因になってしまう場合があるので、普段を同じ量を複数回に分けて与えるようにし、できるだけ空腹の時間が少なくするよう工夫してあげてください。
それでもお腹が空いている場合は、低カロリーのフードに変更し、量を少しだけ増やすことで解消できるでしょう。
 胃腸を健康に保つことは、愛犬の長生きをサポートする秘訣の1つです。
人間でもそれは同じで腸内環境を改善することでとても体調がよくなるのと同じですよね。
そんな時は、乳酸菌のサプリメントなどを与えて、腸内の善玉菌を増やし動きを良くしてあげると、腸内環境が改善され、蠕動運動が活発なったり、ガスの発生が抑えられることがあります。
犬に与えても問題ない整腸剤としては「ビオフェルミン」と「エビオス」があるので、愛犬のお腹が気になる場合は試してきてください。
その場合、しっかり説明書を見て愛犬の体に合った容量を守るようにしましょう。
胃腸を健康に保つことは、愛犬の長生きをサポートする秘訣の1つです。
人間でもそれは同じで腸内環境を改善することでとても体調がよくなるのと同じですよね。
そんな時は、乳酸菌のサプリメントなどを与えて、腸内の善玉菌を増やし動きを良くしてあげると、腸内環境が改善され、蠕動運動が活発なったり、ガスの発生が抑えられることがあります。
犬に与えても問題ない整腸剤としては「ビオフェルミン」と「エビオス」があるので、愛犬のお腹が気になる場合は試してきてください。
その場合、しっかり説明書を見て愛犬の体に合った容量を守るようにしましょう。
 犬のおしっこやウンチといった排泄物は健康をチェックするためのバロメーターになります。
おしっこやウンチの回数・量・色・臭いなどによって健康状態を確認することができます。
健康な時と体調が悪い時の違いを知るために普段から気にかけ、病気にかからないための健康チェックや対策をするのが大事です。
うんちの色の違いでどんな病気が潜んでいるのかを確認し、愛犬の変化にいち早く気づけるよう心がけましょう。
少しでも気になること、異常が見られた時には素早く動物病院で獣医師に診てもらいましょう。
犬のおしっこやウンチといった排泄物は健康をチェックするためのバロメーターになります。
おしっこやウンチの回数・量・色・臭いなどによって健康状態を確認することができます。
健康な時と体調が悪い時の違いを知るために普段から気にかけ、病気にかからないための健康チェックや対策をするのが大事です。
うんちの色の違いでどんな病気が潜んでいるのかを確認し、愛犬の変化にいち早く気づけるよう心がけましょう。
少しでも気になること、異常が見られた時には素早く動物病院で獣医師に診てもらいましょう。
 黒いうんちは重い不調のサインであることが多いため、可能な限り早く動物病院を受診すべきです。
黒いうんちは最も健康上のリスクが大きく、胃や腸に腫瘍がある場合や慢性の胃炎、腸炎や、異物などで上部消化管内への出血が発生することがあります。
消化管内に流れ出た血液は、口から入った食べ物と同様に消化されて色が真っ黒に変わり、消化された血液の真っ黒な色がうんちの色として観察されるのです。
この場合、消化管内へ大量の出血が起きていることが疑われ、ときには重度の貧血を起こすほどで貧血そのものが健康に大きな悪影響を及ぼしてしまいます。
したがって、うんちが黒い場合にはなるべく早く動物病院を受診することがをおすすめします。
特に真っ黒な色に加えて、下痢を伴う場合は「タール便」と呼ばれ、便の硬さが普通の場合と比べて緊急性が高いので、よく注意を向けてあげるようにしましょう。
黒いうんちは重い不調のサインであることが多いため、可能な限り早く動物病院を受診すべきです。
黒いうんちは最も健康上のリスクが大きく、胃や腸に腫瘍がある場合や慢性の胃炎、腸炎や、異物などで上部消化管内への出血が発生することがあります。
消化管内に流れ出た血液は、口から入った食べ物と同様に消化されて色が真っ黒に変わり、消化された血液の真っ黒な色がうんちの色として観察されるのです。
この場合、消化管内へ大量の出血が起きていることが疑われ、ときには重度の貧血を起こすほどで貧血そのものが健康に大きな悪影響を及ぼしてしまいます。
したがって、うんちが黒い場合にはなるべく早く動物病院を受診することがをおすすめします。
特に真っ黒な色に加えて、下痢を伴う場合は「タール便」と呼ばれ、便の硬さが普通の場合と比べて緊急性が高いので、よく注意を向けてあげるようにしましょう。
 犬のウンチやおしっこといった排泄物は健康チェックのバロメーターになります。
ウンチやおしっこの回数・量・色・臭いなどによって健康な時とどう異なるので、健康状態を確認することができます。
犬の正常なうんちの回数、量というのは特に決まりがないため、毎日3回以上うんちをする犬もいれば、1日1回の犬もいます。
愛犬の普段のうんちの回数と比較してどうなのかで判断すると良いでしょう。
犬のウンチやおしっこといった排泄物は健康チェックのバロメーターになります。
ウンチやおしっこの回数・量・色・臭いなどによって健康な時とどう異なるので、健康状態を確認することができます。
犬の正常なうんちの回数、量というのは特に決まりがないため、毎日3回以上うんちをする犬もいれば、1日1回の犬もいます。
愛犬の普段のうんちの回数と比較してどうなのかで判断すると良いでしょう。
 普段より回数が多い場合に考えられることは、消化率の低いフードを食べていると起こることがあります。
特に肥満系のフードは食物繊維が多く不消化物からウンチの量が大量になるので、消化率の高いフードへ変更するとウンチも少なくなります。
また、回数が増えるのは大腸で下痢になっている場合が多く、大腸性の下痢の場合はゼリーの様な粘液便もよく見られるので注意してあげましょう。
さらに、大腸に炎症があって実際に便が溜まっていないのに便意だけを催すときに、排便のポーズをとるだけでうんちが出ない時があります。
その場合は前立腺や会陰ヘルニアなどが原因も考えられるので何度も続く場合は、動物病院で獣医師の診察や検査を受けた方がよいでしょう。
普段より回数が多い場合に考えられることは、消化率の低いフードを食べていると起こることがあります。
特に肥満系のフードは食物繊維が多く不消化物からウンチの量が大量になるので、消化率の高いフードへ変更するとウンチも少なくなります。
また、回数が増えるのは大腸で下痢になっている場合が多く、大腸性の下痢の場合はゼリーの様な粘液便もよく見られるので注意してあげましょう。
さらに、大腸に炎症があって実際に便が溜まっていないのに便意だけを催すときに、排便のポーズをとるだけでうんちが出ない時があります。
その場合は前立腺や会陰ヘルニアなどが原因も考えられるので何度も続く場合は、動物病院で獣医師の診察や検査を受けた方がよいでしょう。
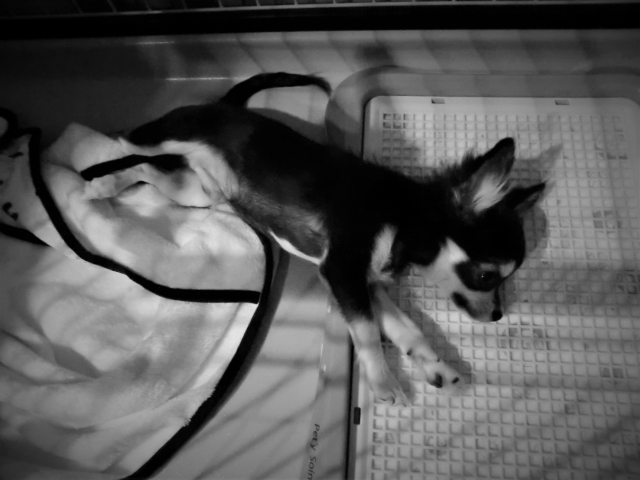 犬がうんちをした時に一緒にうんちと出てくるゼリー状のものは、うんちがスムーズに移動し排出するために腸の中を潤す役割や、腸管内に最近が入り込むのを防ぐバリア機能を持っています。
このゼリー状のものは腸から分泌される粘液や腸粘膜が剥がれ落ちたものです。
腸の表面にある腸粘膜が傷つくとたくさん粘液を分泌して修復しようとするので、ゼリー状のものがうんちと一緒に出るということは不調のサインと考えられます。
犬がうんちをした時に一緒にうんちと出てくるゼリー状のものは、うんちがスムーズに移動し排出するために腸の中を潤す役割や、腸管内に最近が入り込むのを防ぐバリア機能を持っています。
このゼリー状のものは腸から分泌される粘液や腸粘膜が剥がれ落ちたものです。
腸の表面にある腸粘膜が傷つくとたくさん粘液を分泌して修復しようとするので、ゼリー状のものがうんちと一緒に出るということは不調のサインと考えられます。
 便に粘液が混ざっていると「何かの病気かも」と心配になりますが少量の場合は心配することはありません。
しかし粘液便が続いたり、いつもより粘液の量が多い、血液が混ざっている時などは消化管に不調(食あたり、消化不良、冷え)があったり、
過敏性腸症候群腸(精神的なストレスや自律神経のアンバランスなどが原因で刺激に対して過敏になり、慢性的に便秘や下痢などを起こす病気)など消化管の疾患が見られる場合があります。
また潰瘍性大腸炎(大腸にみられる原因不明の慢性の腸炎で、大腸のもっとも内側の層にある粘膜にびらん(ただれ)や潰瘍(皮膚や粘膜などにできる組織の欠損)ができる病気)も考えられます。
熱が出たり、下痢や嘔吐、食欲不信などの症状が出たときは、大腸が傷いていることがあります。
便に粘液が混ざっていると「何かの病気かも」と心配になりますが少量の場合は心配することはありません。
しかし粘液便が続いたり、いつもより粘液の量が多い、血液が混ざっている時などは消化管に不調(食あたり、消化不良、冷え)があったり、
過敏性腸症候群腸(精神的なストレスや自律神経のアンバランスなどが原因で刺激に対して過敏になり、慢性的に便秘や下痢などを起こす病気)など消化管の疾患が見られる場合があります。
また潰瘍性大腸炎(大腸にみられる原因不明の慢性の腸炎で、大腸のもっとも内側の層にある粘膜にびらん(ただれ)や潰瘍(皮膚や粘膜などにできる組織の欠損)ができる病気)も考えられます。
熱が出たり、下痢や嘔吐、食欲不信などの症状が出たときは、大腸が傷いていることがあります。
 夏の暑い日、人間であればついつい食べたくなるアイス。
甘くてとても美味しいですよね!
そんな時、愛犬がとても食べたそうに見ていると一口だけと与えてしまうことありませんか?
ですが、犬に人間用のアイスを食べさせることはリスクを伴うことがあります。
今回は人間用のアイスが犬に与えるリスクについてご紹介します。
夏の暑い日、人間であればついつい食べたくなるアイス。
甘くてとても美味しいですよね!
そんな時、愛犬がとても食べたそうに見ていると一口だけと与えてしまうことありませんか?
ですが、犬に人間用のアイスを食べさせることはリスクを伴うことがあります。
今回は人間用のアイスが犬に与えるリスクについてご紹介します。
 人間用のアイスには大量の糖分が使用されており、犬にとっては糖分過多になってしまう食べ物です。
犬は甘い食べ物が好きなので、ついついアイスを食べていると寄ってきますが、欲しがるから与えるということを繰り返していると肥満の原因になります。
一度与えると何度も要求してくるようになるので、愛犬に長生きしてもらうためにもアイスを与えるのはやめておきましょう。
人間用のアイスには大量の糖分が使用されており、犬にとっては糖分過多になってしまう食べ物です。
犬は甘い食べ物が好きなので、ついついアイスを食べていると寄ってきますが、欲しがるから与えるということを繰り返していると肥満の原因になります。
一度与えると何度も要求してくるようになるので、愛犬に長生きしてもらうためにもアイスを与えるのはやめておきましょう。
 アイスには甘いものだけではなく、果物を使ったアイスもあります。
中でもぶどうを使っているアイスはぶどう中毒を起こす可能性があり要注意!
ぶどうのどんな成分が犬の健康を害すのかはっきりとはわかっていないのですが、過去にぶどうを食べた犬が中毒を起こした事例が複数あることがわかっています。
急性の腎障害により、死に至るケースもあるので非常に危険です。
アイスには甘いものだけではなく、果物を使ったアイスもあります。
中でもぶどうを使っているアイスはぶどう中毒を起こす可能性があり要注意!
ぶどうのどんな成分が犬の健康を害すのかはっきりとはわかっていないのですが、過去にぶどうを食べた犬が中毒を起こした事例が複数あることがわかっています。
急性の腎障害により、死に至るケースもあるので非常に危険です。
 人間用のアイスを犬に絶対食べさせてはいけないというわけではないですが、与える際にはさまざまな注意が必要になってきます。
ここでは、人間用のアイスを犬に与える時の注意点についてご紹介します。
人間用のアイスを犬に絶対食べさせてはいけないというわけではないですが、与える際にはさまざまな注意が必要になってきます。
ここでは、人間用のアイスを犬に与える時の注意点についてご紹介します。
 人間用のアイスには乳製品が含まれているものもあり、乳糖と言われる糖分が含まれています。
離乳期を過ぎた犬はこの糖分を分解するための消化酵素「ラクターゼ」が減少するため、乳糖を体内で分解できない子が多いです。
これを先ほどもご紹介した「乳糖不耐症」というのですが、乳糖が分解できずに大腸に運ばれると、大腸の菌により発酵し、下痢や嘔吐を中心に消化器系症状を引き起こす原因になってしまうのです。
なかには乳製品を食べても平気な子もいますが、少量食べただけでもお腹を壊してしまう子もいるので、最初から与えないのが無難と言えるでしょう。
人間用のアイスには乳製品が含まれているものもあり、乳糖と言われる糖分が含まれています。
離乳期を過ぎた犬はこの糖分を分解するための消化酵素「ラクターゼ」が減少するため、乳糖を体内で分解できない子が多いです。
これを先ほどもご紹介した「乳糖不耐症」というのですが、乳糖が分解できずに大腸に運ばれると、大腸の菌により発酵し、下痢や嘔吐を中心に消化器系症状を引き起こす原因になってしまうのです。
なかには乳製品を食べても平気な子もいますが、少量食べただけでもお腹を壊してしまう子もいるので、最初から与えないのが無難と言えるでしょう。
 成犬であれば少し程度のアイスを与えるのは問題ないですが、消化機能が不十分な子犬やシニア犬には与えないようにしましょう。
消化器官が未発達な子犬と、消化機能が衰えつつあるシニア犬は下痢や嘔吐などの症状が出やすくなります。
アイスは冷たい分、お腹を冷やすうえに、乳製品も多く含まれるため内臓への負担はとくに大きいでしょう。
アイスに限らず、愛犬が食べなれないものは消化不良を起こしやすいので、最初から与えないのが安心です。
また、人間用に加工されたものには添加物も多く含まれています。
保存料や香料・着色料などこれらの添加物は少量であっても体に有害になるため十分気をつけましょう。
成犬であれば少し程度のアイスを与えるのは問題ないですが、消化機能が不十分な子犬やシニア犬には与えないようにしましょう。
消化器官が未発達な子犬と、消化機能が衰えつつあるシニア犬は下痢や嘔吐などの症状が出やすくなります。
アイスは冷たい分、お腹を冷やすうえに、乳製品も多く含まれるため内臓への負担はとくに大きいでしょう。
アイスに限らず、愛犬が食べなれないものは消化不良を起こしやすいので、最初から与えないのが安心です。
また、人間用に加工されたものには添加物も多く含まれています。
保存料や香料・着色料などこれらの添加物は少量であっても体に有害になるため十分気をつけましょう。
 愛犬を涼ませたい時や一緒にアイスを楽しみたいなどどうしても愛犬にアイスを食べさせたい場合はいくつかの方法があります。
ここでは、その方法についてご紹介します。
愛犬を涼ませたい時や一緒にアイスを楽しみたいなどどうしても愛犬にアイスを食べさせたい場合はいくつかの方法があります。
ここでは、その方法についてご紹介します。
 今は犬専用のアイスが販売されています。
犬専用のアイスであれば糖分や添加物が少ないため、安全と言えるでしょう。
なかには乳製品の代わりに豆乳を使ったものもあるので、乳製品に弱い子やアレルギーを持っている子にも安心して与えることができます。
今は犬専用のアイスが販売されています。
犬専用のアイスであれば糖分や添加物が少ないため、安全と言えるでしょう。
なかには乳製品の代わりに豆乳を使ったものもあるので、乳製品に弱い子やアレルギーを持っている子にも安心して与えることができます。
 犬が食べても良いと言われているバナナやリンゴなどのフルーツを薄く切って凍らせて与えるのもおすすめです。
季節のフルーツは栄養価も高いですし、冷凍することで長持ちします。
栄養満点のおやつを与えたい時に最適なので、ぜひ試してみてくださいね。
犬が食べても良いと言われているバナナやリンゴなどのフルーツを薄く切って凍らせて与えるのもおすすめです。
季節のフルーツは栄養価も高いですし、冷凍することで長持ちします。
栄養満点のおやつを与えたい時に最適なので、ぜひ試してみてくださいね。
 気をつけていても愛犬がアイスを食べ中毒やアレルギー症状を起こした場合は、愛犬が食べた成分をまずは確認してください。
アレルギー物質を食べてしまった場合は、慌てず愛犬の様子を確認し、嘔吐や下痢が止まらない、皮膚の痒みが強い、掻きむしっているなどの症状が見られる場合はすぐに受診することをおすすめします。
もし、製品に中毒物質が含まれていた場合は、命に関わるものもあるので、すぐに受診してください。
ここで間違っても食べたものを無理やり吐かそうとするのだけはやめましょう。
そして、受診する場合は、食べたものがわかる製品のパッケージや食べた量、時間などをメモして持参すると治療に役立ちます。
気をつけていても愛犬がアイスを食べ中毒やアレルギー症状を起こした場合は、愛犬が食べた成分をまずは確認してください。
アレルギー物質を食べてしまった場合は、慌てず愛犬の様子を確認し、嘔吐や下痢が止まらない、皮膚の痒みが強い、掻きむしっているなどの症状が見られる場合はすぐに受診することをおすすめします。
もし、製品に中毒物質が含まれていた場合は、命に関わるものもあるので、すぐに受診してください。
ここで間違っても食べたものを無理やり吐かそうとするのだけはやめましょう。
そして、受診する場合は、食べたものがわかる製品のパッケージや食べた量、時間などをメモして持参すると治療に役立ちます。
 犬にピーナッツを与えたことはありますか?
なんとなく消化が悪いような気がしますが、与えても問題はないのか、調べてみました。
ピーナッツはアーモンドやくるみなどとは違い、落花生と言われる植物です。
落花生の殻をきちんと外し、薄皮も取った状態そのままであれば犬が食べても大丈夫とのことでした。
ピーナッツが含むオレイン酸は悪玉コレステロールを減らし、ビタミンEは老化防止を助けます。
しかし、大量に与えるのはやはりNGです。
消化不良や下痢を起こし、体調を壊してしまいます。
ピーナッツは犬にとってあまり消化の良くない食べ物だからです。
ここでは、犬にピーナッツを与える際の注意点や与えてはいけない加工品などについて説明していきます。
犬にピーナッツを与えたことはありますか?
なんとなく消化が悪いような気がしますが、与えても問題はないのか、調べてみました。
ピーナッツはアーモンドやくるみなどとは違い、落花生と言われる植物です。
落花生の殻をきちんと外し、薄皮も取った状態そのままであれば犬が食べても大丈夫とのことでした。
ピーナッツが含むオレイン酸は悪玉コレステロールを減らし、ビタミンEは老化防止を助けます。
しかし、大量に与えるのはやはりNGです。
消化不良や下痢を起こし、体調を壊してしまいます。
ピーナッツは犬にとってあまり消化の良くない食べ物だからです。
ここでは、犬にピーナッツを与える際の注意点や与えてはいけない加工品などについて説明していきます。
 ピーナッツはタンパク質が豊富で抗酸化作用が強いビタミンも含んでいる食品です。
犬が食べても問題ありませんが、いくつかの守るべき注意点があります。
注意を守らないと健康に支障が出ることがありますので、次からの詳しい説明を参考にしてください。
ピーナッツはタンパク質が豊富で抗酸化作用が強いビタミンも含んでいる食品です。
犬が食べても問題ありませんが、いくつかの守るべき注意点があります。
注意を守らないと健康に支障が出ることがありますので、次からの詳しい説明を参考にしてください。
 ピーナッツをそのまま犬に与えてしまうと、誤飲する可能性が増え、食道や喉に詰まってしまうことがあります。
1粒でも気管や腸につまらせるとたいへんなことになるので、小型犬や子犬、老犬は特に注意しなければいけません。
消化器官が発達していない子犬や弱っている老犬は下痢を起こしやすいものです。
また、殻はほとんど消化できないので食べると腸閉塞になってしまうことがあります。
ピーナッツは殻をむき、生の落花生を柔らかく茹でたものや細かくしたものを与えましょう。
ピーナッツをそのまま犬に与えてしまうと、誤飲する可能性が増え、食道や喉に詰まってしまうことがあります。
1粒でも気管や腸につまらせるとたいへんなことになるので、小型犬や子犬、老犬は特に注意しなければいけません。
消化器官が発達していない子犬や弱っている老犬は下痢を起こしやすいものです。
また、殻はほとんど消化できないので食べると腸閉塞になってしまうことがあります。
ピーナッツは殻をむき、生の落花生を柔らかく茹でたものや細かくしたものを与えましょう。
 ピーナッツの加工品はいろいろありますが、犬には人間用の塩味などがついた加工品は与えないようにしましょう。
ピーナッツチョコレートなどのお菓子類や柿の種などは絶対に与えてはいけません。
犬にNGな商品を詳しく解説しますので、ぜひお読みください。
ピーナッツの加工品はいろいろありますが、犬には人間用の塩味などがついた加工品は与えないようにしましょう。
ピーナッツチョコレートなどのお菓子類や柿の種などは絶対に与えてはいけません。
犬にNGな商品を詳しく解説しますので、ぜひお読みください。
 ピーナッツチョコやミックスナッツ、おつまみピーナッツなど、人間用に作られたお菓子・おつまみには塩分が多いため、愛犬の健康を害する恐れがあります。
特にチョコレートはご存知の人も多いかと思いますが、その成分には犬が中毒を起こす危険性が含まれており、絶対に食べさせてはいけない食品です。
チョコレートの致死量は体重1kgあたり100~200mgですので、板チョコ1枚分で小型犬はかなり危険な量となります。
次に塩分ですが、適量の塩分は与えても問題ありませんし、塩分不足も良いものではありません。
しかし、一般的なフードには適量の塩分が含まれていますので、それ以上に与える必要はなく、おつまみなどを与えると体調を崩す原因になってしまいます。
また腎臓や心臓に疾患を持っていると、塩分のとりすぎにより病気が悪化する場合もありますので、お菓子やおつまみ類の加工品は与えないようにしましょう。
ピーナッツチョコやミックスナッツ、おつまみピーナッツなど、人間用に作られたお菓子・おつまみには塩分が多いため、愛犬の健康を害する恐れがあります。
特にチョコレートはご存知の人も多いかと思いますが、その成分には犬が中毒を起こす危険性が含まれており、絶対に食べさせてはいけない食品です。
チョコレートの致死量は体重1kgあたり100~200mgですので、板チョコ1枚分で小型犬はかなり危険な量となります。
次に塩分ですが、適量の塩分は与えても問題ありませんし、塩分不足も良いものではありません。
しかし、一般的なフードには適量の塩分が含まれていますので、それ以上に与える必要はなく、おつまみなどを与えると体調を崩す原因になってしまいます。
また腎臓や心臓に疾患を持っていると、塩分のとりすぎにより病気が悪化する場合もありますので、お菓子やおつまみ類の加工品は与えないようにしましょう。