犬はアーモンドを食べても大丈夫?
 犬にアーモンドを与えてもよいのか気になる人もいるのではないでしょうか。
アーモンドは犬に与えても問題なく、人の間でも注目されているナッツ類であるため、同じ効果を愛犬にも得てほしいなら与えましょう。
ただし、アーモンドは高脂肪であり、消化も悪いので与えすぎてしまうと肥満体質になってしまいやすく、嘔吐や下痢などを起こしてしまう可能性もあるので注意しましょう。
いくら体に良いとされている食材でも食べすぎは体に悪影響を及ぼす原因となってしまいます。
犬にアーモンドを与えてもよいのか気になる人もいるのではないでしょうか。
アーモンドは犬に与えても問題なく、人の間でも注目されているナッツ類であるため、同じ効果を愛犬にも得てほしいなら与えましょう。
ただし、アーモンドは高脂肪であり、消化も悪いので与えすぎてしまうと肥満体質になってしまいやすく、嘔吐や下痢などを起こしてしまう可能性もあるので注意しましょう。
いくら体に良いとされている食材でも食べすぎは体に悪影響を及ぼす原因となってしまいます。
犬にアーモンドを与える際の注意点
 犬にアーモンドを与えても問題はありませんが、いくつか注意しなければならないポイントがあります。
そのため、注意点を把握せずにアーモンドを与えてしまうと何かしらの不調を起こしてしまうリスクがあります。
次に、犬にアーモンドを与える際の注意点を紹介するので参考にしてください。
犬にアーモンドを与えても問題はありませんが、いくつか注意しなければならないポイントがあります。
そのため、注意点を把握せずにアーモンドを与えてしまうと何かしらの不調を起こしてしまうリスクがあります。
次に、犬にアーモンドを与える際の注意点を紹介するので参考にしてください。
どのくらいなら与えても良い?
上記でも紹介したようにアーモンドを犬に与えすぎてしまうと肥満体質になったり、下痢の症状が出てしまうこともあります。
そのため、1日に与えてもよいアーモンドの量を把握しておくことが飼い主には求められます。
基本的に1日に与えてもよいアーモンドの量は明確に決められているわけではありませんが、一つの目安として1日で摂取するカロリーの2割程度と言われています。
普段与えているフードのカロリーを把握することで1日どの程度のカロリーを摂取しているのかを知ることができるので、そこからアーモンドを与えてもよい量を計算しましょう。
あくまでも目安ですが、5㎏程度の小型犬であれば1~3粒程度が無難です。
持病があったり、老犬の場合は動物病院の医師に相談することをおすすめします。
細かく砕いてから与える
 犬がアーモンドを食べる際は歯の形も関係していますが、細かく砕いて食べることができません。
そのため、1粒丸々飲み込んでしまうことも珍しくなく、喉や消化器官などに詰まってしまう恐れがあります。
そのほかにも細かくなっていないまま胃に運ばれてしまうため、それだけ消化にも時間がかかってしまいます。
ただでさえ消化しにくいアーモンドであるため、さらに消化しにくくなってしまい、下痢や嘔吐のリスクが高まります。
犬にアーモンドを与える際には事前に細かく砕く一工夫をしてあげるようにしましょう。
また、茹でることで柔らかくすることができ、消化もしやすくなるのでおすすめです。
アーモンドに一工夫を加えることは面倒と感じてしまうことも多いですが、愛犬のことを第一に考えるのであれば必ず行うようにしましょう。
犬がアーモンドを食べる際は歯の形も関係していますが、細かく砕いて食べることができません。
そのため、1粒丸々飲み込んでしまうことも珍しくなく、喉や消化器官などに詰まってしまう恐れがあります。
そのほかにも細かくなっていないまま胃に運ばれてしまうため、それだけ消化にも時間がかかってしまいます。
ただでさえ消化しにくいアーモンドであるため、さらに消化しにくくなってしまい、下痢や嘔吐のリスクが高まります。
犬にアーモンドを与える際には事前に細かく砕く一工夫をしてあげるようにしましょう。
また、茹でることで柔らかくすることができ、消化もしやすくなるのでおすすめです。
アーモンドに一工夫を加えることは面倒と感じてしまうことも多いですが、愛犬のことを第一に考えるのであれば必ず行うようにしましょう。
犬のアーモンド過剰摂取の危険性とは?
 犬にアーモンドを与える際には適量を与えることが大切であり、過剰摂取してしまうと危険な状態になることもあります。
下痢や嘔吐をしてしまうことはもちろんですが、病気になってしまい、最悪手術などの治療を行わなければならなくなることもあります。
次に、犬にアーモンドを過剰摂取することの危険性を紹介するので、アーモンドを愛犬に与えようと考えている人は参考にしてください。
犬にアーモンドを与える際には適量を与えることが大切であり、過剰摂取してしまうと危険な状態になることもあります。
下痢や嘔吐をしてしまうことはもちろんですが、病気になってしまい、最悪手術などの治療を行わなければならなくなることもあります。
次に、犬にアーモンドを過剰摂取することの危険性を紹介するので、アーモンドを愛犬に与えようと考えている人は参考にしてください。
膵炎や胃腸炎を招くことがある
アーモンドには豊富な脂質が含まれており、エネルギー源にもなるため、犬にとって欠かすことができない栄養素と言えます。
しかし、1粒のアーモンドに多くの脂質が含まれているので、膵臓や胃に負担がかかってしまいます。
脂質は胃で消化され、膵臓から分泌される液でエネルギー源として分解されます。
一度に多くのたんぱく質を摂取してしまうと胃腸炎や膵炎を起こしてしまう危険があります。
アーモンドを食べた際に嘔吐したり、元気がなくなったり、食欲がないのであれば膵炎や胃腸炎になっている可能性があるので、動物病院で診察してもらいましょう。
場合によっては体調が急変して命に関わってしまうこともあるので、軽視しないように注意することも大切です。
高カロリーや脂質の多さにも注意する
 アーモンドにはカロリーが豊富に含まれているので大量に食べてしまうと当然肥満体質になってしまいやすいです。
犬が肥満体質になってしまうと胃寿命が縮んだり、糖尿の誘発、免疫力の低下などさまざまな悪影響を及ぼしてしまいます。
また、体重が重くなってしまうため、各関節にかかる負担も大きくなってしまい、関節痛になってしまうことも考えられます。
健康のために与えているアーモンドでも与える量を間違えるだけで、健康的な体ではなく、不健康な体に近づいてしまうため、逆効果になってしまいます。
特に、運動量が少ない犬は普段から消費するカロリーも少ないため、より短期間で肥満体質になってしまうリスクがあります。
アーモンドには脂質やカロリーが豊富に含まれていることを理解して、カロリーや脂質の過剰摂取にならないように気をつけましょう。
アーモンドにはカロリーが豊富に含まれているので大量に食べてしまうと当然肥満体質になってしまいやすいです。
犬が肥満体質になってしまうと胃寿命が縮んだり、糖尿の誘発、免疫力の低下などさまざまな悪影響を及ぼしてしまいます。
また、体重が重くなってしまうため、各関節にかかる負担も大きくなってしまい、関節痛になってしまうことも考えられます。
健康のために与えているアーモンドでも与える量を間違えるだけで、健康的な体ではなく、不健康な体に近づいてしまうため、逆効果になってしまいます。
特に、運動量が少ない犬は普段から消費するカロリーも少ないため、より短期間で肥満体質になってしまうリスクがあります。
アーモンドには脂質やカロリーが豊富に含まれていることを理解して、カロリーや脂質の過剰摂取にならないように気をつけましょう。
腸閉塞や食道閉塞の危険性がある
犬にアーモンドを与えた際に腸閉塞や食道閉塞になってしまう危険性もあります。
これらの症状は犬がアーモンドを丸のみしたときに起きやすいです。
アーモンドは1粒が大きく形もいびつであるため、腸や食道に詰まりやすいです。
特に、腸や食道が細い小型犬ほど詰まらせてしまうリスクがあります。
原因はアーモンドを喉に詰まらせてしまうことであるため、細かく砕いたり、茹でてペースト状などにすれば事前に腸閉塞や食道閉塞を防ぐことが可能です。
犬はアーモンド以外のナッツ類は大丈夫?
 アーモンドは与える量さえ間違えなければ犬に与えても害を及ぼしてしまうことはありませんが、ほかのナッツ類であればどうなのか気になる人もいるのではないでしょうか。
アーモンドはナッツ類の一つであり、さまざまなナッツ類があります。
それぞれ種類が異なることで含まれる栄養素も異なるため、同じナッツ類でもあるアーモンドが問題ないのであれば与えても悪影響はないと考えるのではなく、一度確認しておくことをおすすめします。
アーモンドは与える量さえ間違えなければ犬に与えても害を及ぼしてしまうことはありませんが、ほかのナッツ類であればどうなのか気になる人もいるのではないでしょうか。
アーモンドはナッツ類の一つであり、さまざまなナッツ類があります。
それぞれ種類が異なることで含まれる栄養素も異なるため、同じナッツ類でもあるアーモンドが問題ないのであれば与えても悪影響はないと考えるのではなく、一度確認しておくことをおすすめします。
カシューナッツはおすすめできない
アーモンドと同じくらい人気があるカシューナッツですが、犬には与えないことをおすすめします。
アーモンドと同じように中毒症状はないので安全性はありますが、消化しにくいこともあり、嘔吐や下痢の原因となってしまいます。
元々アーモンドやカシューナッツは犬にとって必ず必要とはいえないので、無理して与える必要もありません。
確かに豊富な栄養素が含まれているため、得られるメリットもありますが、下痢や嘔吐をしやすいデメリットの方が大きくなってしまいがちです。
マカダミアナッツは絶対NG
 マカダミアナッツを与えることは絶対にしないようにしましょう。
さまざまなナッツ類の中でも一番危険性が高いナッツとも言われています。
マカダミアナッツの中には中毒症状が出てしまう成分が含まれており、犬が食べてしまうとマカダミアナッツ中毒と言われる病気になってしまいます。
摂取してから12時間前後に症状があらわれる場合が多いです。
自然に回復する場合もありますが、死亡してしまうケースもあるので、食べてしまった場合は動物病院で診てもらうようにしましょう。
マカダミアナッツを与えることは絶対にしないようにしましょう。
さまざまなナッツ類の中でも一番危険性が高いナッツとも言われています。
マカダミアナッツの中には中毒症状が出てしまう成分が含まれており、犬が食べてしまうとマカダミアナッツ中毒と言われる病気になってしまいます。
摂取してから12時間前後に症状があらわれる場合が多いです。
自然に回復する場合もありますが、死亡してしまうケースもあるので、食べてしまった場合は動物病院で診てもらうようにしましょう。
まとめ
人にとっては健康的にもよいとされているナッツ類のアーモンドですが、人同様に食べ過ぎてしまうと肥満体質になってしまいやすいデメリットがあります。
また、犬にとっては有毒となるナッツ類もあるため、確認せずに与えることは控えましょう。
正しい知識を身に付けてからアーモンドを与えるように心がけましょう。
警察犬とは?
 警察犬とは、人間より圧倒的に優れた嗅覚を訓練し、足跡追跡能力や臭気選別能力を警察の捜査活動に利用するものです。
主な仕事は、人の残した臭いを元に犯人や犯人の遺留品、行方不明者を捜索する足跡追及活動、犯人の遺留物と容疑者の臭いをかぎ分けて調べる臭気選別活動、迷子や行方不明者、遺留品などを捜索する捜索活動などがあります。
警察犬とは、人間より圧倒的に優れた嗅覚を訓練し、足跡追跡能力や臭気選別能力を警察の捜査活動に利用するものです。
主な仕事は、人の残した臭いを元に犯人や犯人の遺留品、行方不明者を捜索する足跡追及活動、犯人の遺留物と容疑者の臭いをかぎ分けて調べる臭気選別活動、迷子や行方不明者、遺留品などを捜索する捜索活動などがあります。
警察犬になれる犬種とは?
 警察犬には直轄警察犬と嘱託警察犬に分けられており、警察犬として公益社団法人日本警察犬協会が公式に定めている犬種は7種となっています。
警察犬には直轄警察犬と嘱託警察犬に分けられており、警察犬として公益社団法人日本警察犬協会が公式に定めている犬種は7種となっています。
ボクサー
ドイツで作出された比較的新しい犬種で、作業意欲が旺盛、忍耐が強く忠実、勇敢という特性を持っています。
軍用犬や警察犬、イノシシ狩り犬として盛んに用いられてきましたが、知力・体力ともに優れていることから現在では警察犬として認定されています。
毛色はフォーンとブリンドルの2種で、白斑は体表の3分の1を超えてはいけないと言われています。
頭部の白斑は左右対称が望まれ、顔面のブラックマスクは必須とされています。
スクエアな体躯構成と強健な骨格を持つことが要求されることが多いようですね。
エアデールテリア
 19世気後半に作出され、主にカワウソ猟に用いられてきた比較的新しいテリアで、イギリスで初めて警察犬として採用された犬種です。
家庭用として理想的な資質を持っていますが、忍耐強く温順で聡明な判断力を持つ気品があると言われています。
テリア犬種の持つ威厳とハウンドゆずりの優しさを兼ね備えた犬で、きわめて従順。
子供に対しては年齢相応に良き遊び相手となるでしょう。
強壮な体質の犬種として知られ、特にジステンパーに対する抵抗力が強いとのことです。
19世気後半に作出され、主にカワウソ猟に用いられてきた比較的新しいテリアで、イギリスで初めて警察犬として採用された犬種です。
家庭用として理想的な資質を持っていますが、忍耐強く温順で聡明な判断力を持つ気品があると言われています。
テリア犬種の持つ威厳とハウンドゆずりの優しさを兼ね備えた犬で、きわめて従順。
子供に対しては年齢相応に良き遊び相手となるでしょう。
強壮な体質の犬種として知られ、特にジステンパーに対する抵抗力が強いとのことです。
ドーベルマン
20世紀になってドイツで作出された新しい犬種で、感覚が鋭敏、大胆で従順、嗅覚に優れているため番犬や伴侶犬として使われています。
筋肉質な体格とシュッとしたいでたちから、「警察犬と言えばドーベルマン」と言われるほど警察犬の中でも代表的な犬種と言えるでしょう。
知的で落ち着いた性格から訓練時のパフォーマンスも高いとされています。
コリー
 牧羊犬として歴史の長いコリーは、その血統が管理されるようになったのが19世紀になってからと言われています。
美しい毛並みと鋭い観察眼、洞察力を持ち合わせており、警察犬に向いている犬種と言えるでしょう。
その特性から家庭犬、鑑賞犬として評価されるようになり、計画繁殖の結果、体も大型になりました。
警察犬としても活躍できますが、温和で明朗、人に対して献身的な性格をしていることから家庭犬として飼う方も増えてきていますね。
牧羊犬として歴史の長いコリーは、その血統が管理されるようになったのが19世紀になってからと言われています。
美しい毛並みと鋭い観察眼、洞察力を持ち合わせており、警察犬に向いている犬種と言えるでしょう。
その特性から家庭犬、鑑賞犬として評価されるようになり、計画繁殖の結果、体も大型になりました。
警察犬としても活躍できますが、温和で明朗、人に対して献身的な性格をしていることから家庭犬として飼う方も増えてきていますね。
ジャーマンシェパード
警察犬と言えばドーベルマンとジャーマンシェパードではないでしょうか。
ドイツ原産の牧羊犬を改良し現在の姿となった犬種で、世界大戦時には軍用犬として活用され、その後ヨーロッパ諸国や日本まで活躍の幅を広げました。
日本の警察犬を代表する犬種であり、戦後間もない頃から活躍しています。
侵入者に対する警戒心の強さとは逆に、家族に対する忠誠心が高く、信頼のおける家庭犬としても世界中で飼育されるようになってきています。
ラブラドールレトリバー
 17世紀の後半から18世紀の前半にかけて、カナダのラブラドール地方に祖先犬と思われる犬種がいたと言われています。
この地方の人たちは、極寒の気象条件を克服し、厳しい風雪に耐える頑健な作業犬として使役していました。
その後、イギリスに渡って、上流階級のハンターたちが性能の向上と純粋性の維持に心血を注いだことが、今日の繁栄の基礎となったのです。
特に獲物の回収運搬が得意なためリトリーバーの名前がつけられたとのこと。
このような背景が、頑健な体質、優れた嗅覚、ダブルコールの被毛、太い毛の特徴を持つ現在のラブラドールレトリバー犬種を誕生させ、警察犬、猟犬、盲導犬としてはもちろん家庭犬としても高く評価されている犬種です。
17世紀の後半から18世紀の前半にかけて、カナダのラブラドール地方に祖先犬と思われる犬種がいたと言われています。
この地方の人たちは、極寒の気象条件を克服し、厳しい風雪に耐える頑健な作業犬として使役していました。
その後、イギリスに渡って、上流階級のハンターたちが性能の向上と純粋性の維持に心血を注いだことが、今日の繁栄の基礎となったのです。
特に獲物の回収運搬が得意なためリトリーバーの名前がつけられたとのこと。
このような背景が、頑健な体質、優れた嗅覚、ダブルコールの被毛、太い毛の特徴を持つ現在のラブラドールレトリバー犬種を誕生させ、警察犬、猟犬、盲導犬としてはもちろん家庭犬としても高く評価されている犬種です。
ゴールデンレトリバー
狩猟がスポーツとして盛んであった19世紀のスコットランドで、狩猟家のトゥイードマウス卿が、鳥猟犬の中から水辺で撃ち落とした獲物を回収する目的のウォーターリトリーバーの作出に向け、
ウィビーコーテッドリトリーバー、クィードウォータースパニエル、その他セター、ハウンド等の同系異犬種の交配の繰り返しにより誕生したといわれています。
1931年にKCに登録されてから現在まで、頭脳明晰で忍耐強く、明朗温和、活発な性格が広く愛犬家の心をつかんでいます。
アメリカに渡ってからは、洗練度の高い優美な容姿、陽気で従順な性格に改良され、持ち合わせた作業能力、意欲を十分発揮し優れた嗅覚力で、警察犬はもちろん、使役犬として素晴らしい能力を発揮してくれている犬種です。
警察犬は小型犬でもなれる?
 警察犬=大型犬というイメージが強いですが、中には小型犬でも立派に警察犬の任務をこなしている犬種もたくさんいます。
ここでは、警察犬として小型犬がどのように活躍しているのかご紹介します。
警察犬=大型犬というイメージが強いですが、中には小型犬でも立派に警察犬の任務をこなしている犬種もたくさんいます。
ここでは、警察犬として小型犬がどのように活躍しているのかご紹介します。
指定犬種以外でもなれる嘱託警察犬
警察犬には各都道府県警察が飼育管理をし訓練している直轄警察犬と一般の人が飼育管理し訓練をしている嘱託警察犬の2タイプに分かれています。
このうち、嘱託警察犬は指定犬種以外でも活躍できるという決まりがあり、チワワやパピヨン、柴犬といった小型犬が嘱託警察犬として活躍しています。
嘱託警察犬になるには審査が必要
 嘱託警察犬は一般の方は飼育管理するということでどんな犬種でもなれると思いがちですが、なるためには審査が必要です。
嘱託警察犬になるためには、各都道府県警察が毎年、審査会を行い、嘱託する警察犬を選考し指定されます。
試験内容は県警によって違うのですが、相当難関と言われており、こうした技術を見つけるのに専門の訓練士にお願いすることもあるのだとか。
その他にダックスフンドやトイプードルなどが採用されることもあるようです。
嘱託警察犬は一般の方は飼育管理するということでどんな犬種でもなれると思いがちですが、なるためには審査が必要です。
嘱託警察犬になるためには、各都道府県警察が毎年、審査会を行い、嘱託する警察犬を選考し指定されます。
試験内容は県警によって違うのですが、相当難関と言われており、こうした技術を見つけるのに専門の訓練士にお願いすることもあるのだとか。
その他にダックスフンドやトイプードルなどが採用されることもあるようです。
警察犬の仕事内容
 これまでに警察犬の犬種やタイプなどをご紹介してきましたが、実際警察犬の仕事内容はどのようなものなのでしょうか。
ここでは警察犬の仕事内容についてご紹介していきます。
これまでに警察犬の犬種やタイプなどをご紹介してきましたが、実際警察犬の仕事内容はどのようなものなのでしょうか。
ここでは警察犬の仕事内容についてご紹介していきます。
威警犬
犬にほえられることや犬の牙を恐れる人は多いかと思いますが、それらの行動は犬が犯罪者を威嚇するために利用するのが威警犬です。
威警犬が警察と一緒にパトロールを行うことで、犯罪防止に繋がると言われています。
また、パトロ―ル中に不審者を見つけたら、足に噛みつくなど、逮捕のための行動を起こすこともできるでしょう。
威警犬は、存在だけで威圧できるような大型で強そうな犬が選ばれることが多いようです。
気選別犬
 逮捕された容疑者と現場に残された証拠の匂いが一致するかを確認するための警察犬を気選別犬と言います。
匂いが一致した場合、裁判でも利用することのできる立派な証拠となるので優れた嗅覚を持った犬を選別します。
それだけ大きな役割を果たす警察犬なので、訓練は厳しいものとなるのでしょう。
逮捕された容疑者と現場に残された証拠の匂いが一致するかを確認するための警察犬を気選別犬と言います。
匂いが一致した場合、裁判でも利用することのできる立派な証拠となるので優れた嗅覚を持った犬を選別します。
それだけ大きな役割を果たす警察犬なので、訓練は厳しいものとなるのでしょう。
跡追求犬
事件の現場に犯罪が残した遺留品の匂いをかぎ、その匂いから犯人の居場所などを追及する警察犬を跡追及犬と言います。
犯人だけではなく、行方不明になった被害者の持ち物の匂いをかぐことで、被害者をいち早く見つけ出す役割も担っています。
麻薬探知犬
 映画やニュースなどでよく見かけるのが麻薬探知犬ですよね。
空港の税関などにも麻薬探知犬は多く常駐しており、麻薬を国内に持ち込ませないように見張っています。
麻薬の臭いをかぎつけたらすぐに税関職員に報告するよう訓練されています。
映画やニュースなどでよく見かけるのが麻薬探知犬ですよね。
空港の税関などにも麻薬探知犬は多く常駐しており、麻薬を国内に持ち込ませないように見張っています。
麻薬の臭いをかぎつけたらすぐに税関職員に報告するよう訓練されています。
まとめ
今回は警察犬についてご紹介してきました。
警察犬はどんな犬種でもなれる訳ではなく、厳しい訓練を受け、認定を受けた優れた犬種が警察犬として活躍しています。
犬にしかない能力を使い、私たち人間を守ってくれている心強い存在ですよね。
猫も狂犬病になる?
 狂犬病という病気を知っているでしょうか。
名前からして犬の病気であると考えている人も多いですが、実は猫にも感染してしまう病気であり、哺乳類全般に感染してしまう可能性がある病気です。
そのため、猫だからと言って狂犬病にならないわけではありません。
狂犬病が感染してしまう原因は、感染している動物に噛まれるなどすることで体内にウイルスが侵入してしまうからです。
致死率は100%とも言われ、ほぼ助かる見込みもありません。
なので、猫でも感染してしまう狂犬病を犬の病気だと考えないことが重要です。
狂犬病という病気を知っているでしょうか。
名前からして犬の病気であると考えている人も多いですが、実は猫にも感染してしまう病気であり、哺乳類全般に感染してしまう可能性がある病気です。
そのため、猫だからと言って狂犬病にならないわけではありません。
狂犬病が感染してしまう原因は、感染している動物に噛まれるなどすることで体内にウイルスが侵入してしまうからです。
致死率は100%とも言われ、ほぼ助かる見込みもありません。
なので、猫でも感染してしまう狂犬病を犬の病気だと考えないことが重要です。
猫の狂犬病ワクチンの必要性や注意点とは?
 猫も狂犬病に感染してしまうリスクがあることがわかれば狂犬病のワクチン接種が必要なのか気になるのではないでしょうか。
次に、猫に狂犬病のワクチン接種が必要などうかや注意点などを紹介するので、参考にしてください。
狂犬病は致死率は100%であるため、猫のことを考えるのであれば飼い主が知っておいて損をすることはありません。
猫も狂犬病に感染してしまうリスクがあることがわかれば狂犬病のワクチン接種が必要なのか気になるのではないでしょうか。
次に、猫に狂犬病のワクチン接種が必要などうかや注意点などを紹介するので、参考にしてください。
狂犬病は致死率は100%であるため、猫のことを考えるのであれば飼い主が知っておいて損をすることはありません。
ワクチン接種の要否は飼い主が決める
現在の日本では犬はワクチンを摂取することが義務付けられていますが、猫の場合は義務付けられていないため、飼い主の考えで決めることができます。
狂犬病の感染源は感染した動物に噛まれることであるため、完全室内飼いの猫であればワクチン接種の必要性も低いです。
ただし、放し飼いしている場合や一緒に出掛ける機会があるのであればワクチン接種をしておいても損はありません。
どうしても飼い主だけではワクチンを摂取したほうがよいのか判断できない場合は動物病院で相談してみましょう。
猫と海外へ行く時は必ず接種する
 海外に猫を連れていく場合は狂犬病のワクチンを摂取することが義務付けられています。
その理由は猫が検疫対象動物に指定されているためであり、狂犬病などを広げたり、母国に持ち込まないようにするためで、飼い猫を守るためでもあります。
日本では最近狂犬病の発症事例がなく、狂犬病の危険度や知名度が下がっていますが、海外では狂犬病の発症事例は毎年のように確認されている場合もあるため、安心することはできません。
また、日本の場合は室内飼いされている猫が増えていますが、海外では放し飼いしている家庭が多く、いつ海外先で感染している動物に噛まれてしまうかわからないので必ずワクチン接種をするように心がけましょう。
海外に猫を連れていく場合は狂犬病のワクチンを摂取することが義務付けられています。
その理由は猫が検疫対象動物に指定されているためであり、狂犬病などを広げたり、母国に持ち込まないようにするためで、飼い猫を守るためでもあります。
日本では最近狂犬病の発症事例がなく、狂犬病の危険度や知名度が下がっていますが、海外では狂犬病の発症事例は毎年のように確認されている場合もあるため、安心することはできません。
また、日本の場合は室内飼いされている猫が増えていますが、海外では放し飼いしている家庭が多く、いつ海外先で感染している動物に噛まれてしまうかわからないので必ずワクチン接種をするように心がけましょう。
狂犬病にかかった猫の症状は?
 万が一猫が狂犬病に感染してしまったらどのような症状があらわれてしまうのかも知っておきましょう。
あらかじめ、感染した際の症状を知っておくことで感染している疑いを持つことができ、さまざまな対策を講じることができます。
また、症状を知っていれば感染している可能性がある動物に近づくことを未然に防ぐことができ、飼い猫を守るだけではなく、飼い主自身も守ることにつながります。
次に、猫が狂犬病になった際の症状を紹介します。
万が一猫が狂犬病に感染してしまったらどのような症状があらわれてしまうのかも知っておきましょう。
あらかじめ、感染した際の症状を知っておくことで感染している疑いを持つことができ、さまざまな対策を講じることができます。
また、症状を知っていれば感染している可能性がある動物に近づくことを未然に防ぐことができ、飼い猫を守るだけではなく、飼い主自身も守ることにつながります。
次に、猫が狂犬病になった際の症状を紹介します。
前駆期
前駆期は狂犬病の初期症状であり、発症して1日目からあらわれることがあります。
主な症状は性格が変化してしまうことであり、大人しかった猫が異常に攻撃的になってしまったり、鳴く回数が増えることもあります。
攻撃的になることは噛む回数が増えてしまうので、周りの動物に感染を広げてしまう原因となります。
性格が変わってしまうため、飼い主も気づきやすく、異常行動を頻繁に起こしてしまいます。
また、逆に普段であれば甘えることがなかった猫が急に甘えてくるようになる場合もあります。
狂騒期
 狂騒期はより攻撃的な態度になってしまう症状です。
噛み癖がない猫でも噛む回数が増えたり、鳴く回数も増えます。
そのほかにも常に動き回ったり、落ち着かない状態が続いてしまうこともあります。
この症状の時にもっとも感染を広げてしまうリスクがあるため、飼い主も気を付ける必要もあり、動物病院で診察してもらうようにしましょう。
この際にケージに入れて行動することが大切であり、動物病院のスタッフやほかの動物に噛まれないように工夫することが大切です。
狂騒期はより攻撃的な態度になってしまう症状です。
噛み癖がない猫でも噛む回数が増えたり、鳴く回数も増えます。
そのほかにも常に動き回ったり、落ち着かない状態が続いてしまうこともあります。
この症状の時にもっとも感染を広げてしまうリスクがあるため、飼い主も気を付ける必要もあり、動物病院で診察してもらうようにしましょう。
この際にケージに入れて行動することが大切であり、動物病院のスタッフやほかの動物に噛まれないように工夫することが大切です。
麻痺期
麻痺期は発症して3~4日程度経過したらあらわれる症状です。
主に、嚥下機能が麻痺することでよだれを垂れ流し続けてしまい、ご飯をうまく食べることができません。
また、全身に麻痺が広がることで身動きも取れなくなってしまい、近いうちに命を落としてしまいます。
犬であればある程度よだれを垂れ流すことは多いですが、猫の場合はそこまで普段していない行動であるため、異変にも気づきやすいです。
全身に麻痺が広がると呼吸することも困難になってしまい、窒息死に近い状態で死亡してしまうこともあります。
狂犬病の猫の治療法はある?
 狂犬病に猫が感染した場合には治療法があるのかと聞かれるとありません。
現在の医学でも狂犬病の治療法は確立されておらず、死亡率が100%である理由の一つです。
狂犬病は上記でも紹介したように犬だけではなく、猫などの哺乳類に感染してしまい、人にも感染してしまいます。
そのため、人が狂犬病に感染してしまうと同じく治療法がないため、死亡を待つしかないという残酷な病気です。
現実にも飼い犬から狂犬病に感染させられた飼い主が死亡してしまう事例が海外ではあります。
今後医療の技術が進歩すればいずれ狂犬病に対する治療法が見つけられる可能性もありますが、
現在の段階ではいかに狂犬病に感染しないようにするかが重要であり、ワクチン接種が唯一の予防方法となっています。
狂犬病に猫が感染した場合には治療法があるのかと聞かれるとありません。
現在の医学でも狂犬病の治療法は確立されておらず、死亡率が100%である理由の一つです。
狂犬病は上記でも紹介したように犬だけではなく、猫などの哺乳類に感染してしまい、人にも感染してしまいます。
そのため、人が狂犬病に感染してしまうと同じく治療法がないため、死亡を待つしかないという残酷な病気です。
現実にも飼い犬から狂犬病に感染させられた飼い主が死亡してしまう事例が海外ではあります。
今後医療の技術が進歩すればいずれ狂犬病に対する治療法が見つけられる可能性もありますが、
現在の段階ではいかに狂犬病に感染しないようにするかが重要であり、ワクチン接種が唯一の予防方法となっています。
狂犬病は猫から人に感染する?
 狂犬病は人も感染してしまうため、狂犬病に感染している猫から人に感染してしまう可能性も充分あります。
猫に噛まれることで人も狂犬病にかかり、同じく100%死亡してしまいます。
しかし、人から人に感染してしまうことはなく、空気感染してしまうこともないので、感染対象を隔離することで感染拡大を防ぐことができます。
基本的に飼育している動物に噛まれることで感染してしまったり、野生の動物に噛まれることで人に狂犬病が感染してしまう可能性が高いです。
飼い犬や猫が狂犬病に感染してしまったのであれば普段通り接することは危険であり、厚手の手袋などをつけて噛まれても問題ない状態でキャリーに入れて隔離することが大切です。
狂犬病は人も感染してしまうため、狂犬病に感染している猫から人に感染してしまう可能性も充分あります。
猫に噛まれることで人も狂犬病にかかり、同じく100%死亡してしまいます。
しかし、人から人に感染してしまうことはなく、空気感染してしまうこともないので、感染対象を隔離することで感染拡大を防ぐことができます。
基本的に飼育している動物に噛まれることで感染してしまったり、野生の動物に噛まれることで人に狂犬病が感染してしまう可能性が高いです。
飼い犬や猫が狂犬病に感染してしまったのであれば普段通り接することは危険であり、厚手の手袋などをつけて噛まれても問題ない状態でキャリーに入れて隔離することが大切です。
まとめ
狂犬病という名前を知っていても恐ろしい病気であることを知らない人も多いのではないでしょうか。
また、犬だけの病気と考えてしまうことも多いので、狂犬病に対する知識を身に付けておくことが大切です。
狂犬病の最も恐ろしいことは人にも感染してしまうことと治療法が確立されていないこと、感染すると100%死亡してしまうことであり、いかにワクチンで予防するかが重要であることがわかります。
飼い犬や飼い猫を守るためにも狂犬病ワクチンを摂取して命を守るようにしましょう。
干支に猫が入っていない3つの説
 干支といえば十二支です。干支には12種類の動物がいますが、なぜか猫は入っていません。
身近でペットとして人気もある猫が干支に入ってないのはなぜでしょうか?
猫が干支になれなかったいくつかの説をご紹介します。
干支といえば十二支です。干支には12種類の動物がいますが、なぜか猫は入っていません。
身近でペットとして人気もある猫が干支に入ってないのはなぜでしょうか?
猫が干支になれなかったいくつかの説をご紹介します。
説①:ネズミを食べてしまった
ただのネズミではなく、お釈迦様の命を受けて薬を取りに行ったネズミを食べてしまったため、干支になれなかった説があります。
この薬がなかったため、お釈迦様が命を落としたという話で、なぜか猫は悪者になっています。
説②:猫が認知されていなかった
 十二支や干支が作成された頃、中国では猫がまだ広く認知されておらず、あまり飼われていませんでした。
つまり馴染み深くなかったのです。
しかし、猫が人間に飼われていたのは、約4000年前の古代エジプト時代と言われており、他にも約8000年前の古代キプロスが起源という説もあります。
猫は紀元前200年ごろに中東から中国にも広まっていき、5300年前には中国で家畜として飼われていた猫の骨が見つかっています。
その頃の猫が畑の作物を食べるネズミを食べていたことが分かっており、人の近くで暮らしていたことが考えられるのです。
このことから干支ができたころでも、猫は人々と関わりあっていた可能性があります。
十二支や干支が作成された頃、中国では猫がまだ広く認知されておらず、あまり飼われていませんでした。
つまり馴染み深くなかったのです。
しかし、猫が人間に飼われていたのは、約4000年前の古代エジプト時代と言われており、他にも約8000年前の古代キプロスが起源という説もあります。
猫は紀元前200年ごろに中東から中国にも広まっていき、5300年前には中国で家畜として飼われていた猫の骨が見つかっています。
その頃の猫が畑の作物を食べるネズミを食べていたことが分かっており、人の近くで暮らしていたことが考えられるのです。
このことから干支ができたころでも、猫は人々と関わりあっていた可能性があります。
説③:ネズミに騙された
こんなお話があります。
お釈迦様が「元旦の朝に私の元に一番早く来たものから順に、一年交代でその年の守り神にする」というおふれを出しました。
そこで猫はネズミに日にちを確認をしたら、ネズミは猫に1日遅れた日を教えました。
当日、牛はまだ夜が明けないうちに、足が遅いからとの理由で出発をしました。
それに気づいたネズミは牛の背中に乗って一緒にお釈迦様のところに向かいました。
牛が到着するよりも先にネズミは牛の背中から飛び降り、一番乗りとなりました。
その後、牛、虎、兎、竜、蛇、馬、羊、猿、鳥、犬、猪という順でお釈迦様のところに到着しました。
猫は次の日にお釈迦様のところに到着しましたが、時すでに遅しで、十二支には入れませんでした。
騙されたことを知った猫はネズミを追いかけたところから猫がネズミを追いかけるようになった理由だとも言われています。
猫が干支になっている国もある?
 干支は古代中国が発祥と言われています。
アジアやロシア、東ヨーロッパなどにも伝わりました。
しかし、それらの国、全てに猫年がないわけでもないのです。
ここでは猫年がある海外の国々をご紹介します。
干支は古代中国が発祥と言われています。
アジアやロシア、東ヨーロッパなどにも伝わりました。
しかし、それらの国、全てに猫年がないわけでもないのです。
ここでは猫年がある海外の国々をご紹介します。
ベトナムには猫年がある
ベトナムでは日本の兎が猫になっています。なぜベトナムの十二支には猫がいるのでしょうか?
諸説ありますが、このような理由があるようです。
・ベトナムでは兎よりも猫のほうが身近な動物だから
・兎を表す「卯」の読み方がベトナム語の猫を表す言葉に近いから
という理由で兎ではなく、猫年になったのでは?と言われています。
また猫は農作物を食い荒らすネズミを退治してくれる動物であり、猫年生まれの人は思慮深く平和主義、損得勘定が得意、社交的、周囲の環境に適応できるといった占いもあります。
ベトナムは猫年以外にも日本と違う干支がある
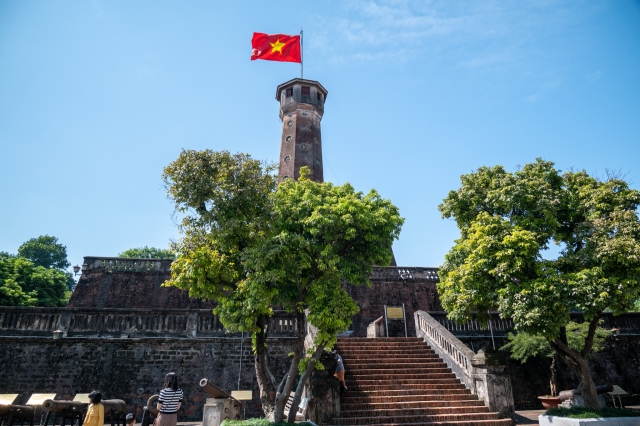 日本では「牛」となっていますが、ベトナムでは「水牛」になっています。
日本では農作業や食料の運搬には欠かせない動物ですが、ベトナムでは牛よりも身近な存在である「水牛」となりました。
また「羊」はベトナムには元々いないので、馴染みがある「ヤギ」になりました。
「猪」は「豚」になっていますが、日本では「豚」が馴染みないので、「猪」に置き換えたようです。
もともとは「豚」で、日本以外の干支のある国は全て「豚」となっています。
日本では「牛」となっていますが、ベトナムでは「水牛」になっています。
日本では農作業や食料の運搬には欠かせない動物ですが、ベトナムでは牛よりも身近な存在である「水牛」となりました。
また「羊」はベトナムには元々いないので、馴染みがある「ヤギ」になりました。
「猪」は「豚」になっていますが、日本では「豚」が馴染みないので、「猪」に置き換えたようです。
もともとは「豚」で、日本以外の干支のある国は全て「豚」となっています。
ベトナム以外で猫年がある国は?
ベトナム以外で「卯(ウサギ年)」が猫年になっている国・地域としてはタイやベラルーシ、チベットなどがあてはまります。
理由は卯の鳴き声「Mao」が猫の鳴き声「Meo」に似ていることと、兎よりも猫が身近な動物であるからです。
また、ブルガリアでは「寅(虎年)」が猫年として扱われます。
なぜ虎ではなく猫なのかという理由はわかっていません。
同じネコ科の豹年がある?
 ブルガリアとは異なり、モンゴルやトルコでは虎年は猫年ではなく、豹年に変わります。
モンゴルの山間部には「ユキヒョウ」という白い豹が生息する地域があることも関係しているのでしょう。
ブルガリアとは異なり、モンゴルやトルコでは虎年は猫年ではなく、豹年に変わります。
モンゴルの山間部には「ユキヒョウ」という白い豹が生息する地域があることも関係しているのでしょう。
まとめ
猫が好きな人にとって、干支に猫が選ばれなかったのは、悲しいと思うかもしれません。
しかし、干支について調べていくとチベット、タイ、ベトナム、ベラルーシではうさぎではなく猫が仲間入りしていたり、中国では馴染みがなかったりと、歴史や文化の違いを発見することができました。
皆さんも干支のお話を家族で話してみてはいかがですか?
犬のリーダーウォークとは?
 散歩での引っ張り癖で悩んでいる飼い主が多いです。
犬がリードを引っ張って歩くことは体に負担をかけていますし、トラブルの原因になることもあります。
リーダーウォークを身につけてリラックスした散歩ができるようにしたいものです。
リーダーウォークとは、飼い主がリーダーとして率先して歩くことです。
歩くスピードや行く先は飼い主が決め、飼い主が止まると犬も止まり、座れと命令されたら座ります。
リーダーウォークができるようになると、生活の様々な場面でとても役立ちますのでぜひ覚えてください。
散歩での引っ張り癖で悩んでいる飼い主が多いです。
犬がリードを引っ張って歩くことは体に負担をかけていますし、トラブルの原因になることもあります。
リーダーウォークを身につけてリラックスした散歩ができるようにしたいものです。
リーダーウォークとは、飼い主がリーダーとして率先して歩くことです。
歩くスピードや行く先は飼い主が決め、飼い主が止まると犬も止まり、座れと命令されたら座ります。
リーダーウォークができるようになると、生活の様々な場面でとても役立ちますのでぜひ覚えてください。
リーダーウォークの教え方
 リーダーウォークは、犬が人よりも前に出ないで歩き、常に飼い主を意識することが必要です。
教え方としては次のステップを繰り返して教えます。
1,まずリードをたるませた状態で犬を左横につけて歩かせます。
2,犬が自分よりも前に行こうとした時に、無言でターンをして反対方向に進みます。
ターンはその場で180°クルッと回ります。
左ターンと右ターンの両方をして、犬に多少ぶつかっても気にせずに回ります。
犬が人よりも先に行きたい方向に進もうとすると、必ず反対方向に人が向くということを繰り返して行うことで、飼い主を意識するようになってきます。
飼い主を意識し、動きに注意することで前に出て引っ張って歩かなくなります。
リーダーウォークは、犬が人よりも前に出ないで歩き、常に飼い主を意識することが必要です。
教え方としては次のステップを繰り返して教えます。
1,まずリードをたるませた状態で犬を左横につけて歩かせます。
2,犬が自分よりも前に行こうとした時に、無言でターンをして反対方向に進みます。
ターンはその場で180°クルッと回ります。
左ターンと右ターンの両方をして、犬に多少ぶつかっても気にせずに回ります。
犬が人よりも先に行きたい方向に進もうとすると、必ず反対方向に人が向くということを繰り返して行うことで、飼い主を意識するようになってきます。
飼い主を意識し、動きに注意することで前に出て引っ張って歩かなくなります。
リーダーウォークを教えるコツ
 リーダーウォークをすることは犬と飼い主との信頼に繋がります。
時間はかかりますが、少しずつ散歩のたびに練習しましょう。
犬は言葉がわかりませんが、ゆっくりでも必ず伝わっていきます。
できるようになると、リラックスした散歩が楽しめますので、次の教えるコツを参考にしてください。
リーダーウォークをすることは犬と飼い主との信頼に繋がります。
時間はかかりますが、少しずつ散歩のたびに練習しましょう。
犬は言葉がわかりませんが、ゆっくりでも必ず伝わっていきます。
できるようになると、リラックスした散歩が楽しめますので、次の教えるコツを参考にしてください。
頻繁にアイコンタクトを取る
リーダーウォークを練習する時にはお互いを意識させることが大切なので、犬とは何度もアイコンタクトを取るようにします。
アイコンタクトが十分にできない場合は、まずその練習をしましょう。
アイコンタクトは全てのしつけの基本で、飼い主に注目させることで犬は飼い主の言葉や行動に従います。
名前を呼んで、目が合えばよく褒めておやつを与えます。
家の中・外・何かに気を取られている時などいつでも、名前を呼ばれたらアイコンタクトができるようにします。
リードが緩む練習をする
 リーダーウォークはリードがいつも緩んだ状態で犬が歩くことです。
引っ張って歩く犬にリードが緩むと良いことがあるのだと発見させ、そのメリットを強く認識させるようにします。
大好きなおやつを用意し、リードが緩んだらすぐに褒めておやつをあげます。
またすぐにリードが張ってしまうかもしれませんが、名前を呼んで誘導し、緩んだらおやつがもらえるということを理解させます。
何度も繰り返して行ってください。
リーダーウォークはリードがいつも緩んだ状態で犬が歩くことです。
引っ張って歩く犬にリードが緩むと良いことがあるのだと発見させ、そのメリットを強く認識させるようにします。
大好きなおやつを用意し、リードが緩んだらすぐに褒めておやつをあげます。
またすぐにリードが張ってしまうかもしれませんが、名前を呼んで誘導し、緩んだらおやつがもらえるということを理解させます。
何度も繰り返して行ってください。
リードとハーネスは無理のない物を使う
首周りが引っ張られてしまう首輪やハーネスは、犬の体に大きな負担をかけるので、リーダーウォークがまだ無理な内は、本当に犬の体に合った首輪・ハーネスをつけてあげます。
胸の部分を支えられるようなハーネスがおすすめです。
またリードの握り方を間違えていることがあります。
正しい握り方はリードの輪っか部分に右手の親指をかけて握ります。
左手でリードをつかんで持ち、両手でしっかり犬をコントロールしましょう。
伸縮するタイプのリードは使わないようにしましょう。
成犬に教える場合は補助器具の検討も
 子犬の頃からリーダーウォークを身に付けさせるのが一番良いですが、いろいろな事情で成犬から飼うことになったり、コントロールできないままで大きくなってしまうことがあります。
成犬の場合も基本的な教え方は同じですが、効果が現れずくじけてしまう飼い主も多いです。
その場合、成犬には補助器具を用いてリーダーウォークを教えるのも手です。
補助器具にはイージーウォークハーネスやジェントルリーダーなどがあり、正しく使うことが必須となります。
使い方が分からない場合や対処が難しい犬にはプロであるドッグトレーナーに相談し、一緒に指導していくことをおすすめします。
子犬の頃からリーダーウォークを身に付けさせるのが一番良いですが、いろいろな事情で成犬から飼うことになったり、コントロールできないままで大きくなってしまうことがあります。
成犬の場合も基本的な教え方は同じですが、効果が現れずくじけてしまう飼い主も多いです。
その場合、成犬には補助器具を用いてリーダーウォークを教えるのも手です。
補助器具にはイージーウォークハーネスやジェントルリーダーなどがあり、正しく使うことが必須となります。
使い方が分からない場合や対処が難しい犬にはプロであるドッグトレーナーに相談し、一緒に指導していくことをおすすめします。
リーダーウォークの必要性
 犬にとって、外の世界は近づいてくる人や犬、いろいろな臭いや音など刺激的なものであふれています。
興奮や警戒心が高ければ、飼い主のことは完全に忘れているかもしれません。
そんな時にこそトラブルは起こりやすく、飼い主にとっても散歩が苦痛になる人もいます。
でも、リーダーウォークができれば飼い主の存在を意識しつつ、リラックスして歩けるようになります。
その必要性を具体的に解説していきましょう。
犬にとって、外の世界は近づいてくる人や犬、いろいろな臭いや音など刺激的なものであふれています。
興奮や警戒心が高ければ、飼い主のことは完全に忘れているかもしれません。
そんな時にこそトラブルは起こりやすく、飼い主にとっても散歩が苦痛になる人もいます。
でも、リーダーウォークができれば飼い主の存在を意識しつつ、リラックスして歩けるようになります。
その必要性を具体的に解説していきましょう。
拾い食いの防止に役立つ
犬がリーダーウォークで飼い主に注意を向ければ、地面にある物を拾い食いしなくなります。
引っ張り癖のある犬はあちこちの臭いに釘付けで、食べてはいけないものや犬の糞などを食べてしまうことが多いので困っている人が多いでしょう。
拾い食いは健康面で問題を起こす可能性があるため、止めさせたい行動です。
しっかり飼い主の隣について歩き、意識を自分に向けさせていると拾い食いを止めさせることができます。
犬を危険から守れる
 犬を常に左側について歩かせることで、左側通行の車から守りやすくなります。
急に人や自転車などが現れた時にもすぐに飼い主が指示を出して待たせたり座らせたりできます。
つまり何か危険が迫った時には、いつでも飼い主の指示を守れることが犬の安全を守ることにつながるのです。
また、リーダーウォークが身についている犬は飼い主の存在を意識しながら余裕を持って歩くため、すれ違う犬や人にも興奮せずに穏やかでいられるでしょう。
犬を常に左側について歩かせることで、左側通行の車から守りやすくなります。
急に人や自転車などが現れた時にもすぐに飼い主が指示を出して待たせたり座らせたりできます。
つまり何か危険が迫った時には、いつでも飼い主の指示を守れることが犬の安全を守ることにつながるのです。
また、リーダーウォークが身についている犬は飼い主の存在を意識しながら余裕を持って歩くため、すれ違う犬や人にも興奮せずに穏やかでいられるでしょう。
人混みでも安心して歩ける
犬と一緒にお出かけしたいけれど、すぐに興奮して引っ張るので連れて行くのは心配と思っている人がおられるでしょう。
そんな時こそリーダーウォークの出番です。
犬が常に横で歩いてくれるので、街中で歩く際の飼い主の精神的な負担も減ります。
先程述べたように都会の車などからも守りやすいので安心して歩けます。
いつも飼い主の指示を聞いてくれる犬と一緒なら、周りの人も犬連れを温かい目で見守ってくれるでしょう。
街中の人が多い場所でも安心して犬と出かけられる日を目指してリーダーウォークを頑張って練習しましょう。
心のバランスが安定する
 リーダーウォークはリードが緩んでいる状態で、犬の体が前のめりになっていません。
周囲への反応も興奮度が低く落ち着いた状態です。
そのような状態は犬の負担も減るので、心に余裕が生まれます。
興奮状態になりにくいので、命令にも耳を傾けやすくなります。
つまり心のバランスが安定し、ゆったりとした気持ちで散歩を楽しめるわけです。
犬が安定していると、飼い主ももちろん穏やかな気持ちでいられます。
お互いに信頼し合った理想的な関係と言えるでしょう。
リーダーウォークはリードが緩んでいる状態で、犬の体が前のめりになっていません。
周囲への反応も興奮度が低く落ち着いた状態です。
そのような状態は犬の負担も減るので、心に余裕が生まれます。
興奮状態になりにくいので、命令にも耳を傾けやすくなります。
つまり心のバランスが安定し、ゆったりとした気持ちで散歩を楽しめるわけです。
犬が安定していると、飼い主ももちろん穏やかな気持ちでいられます。
お互いに信頼し合った理想的な関係と言えるでしょう。
まとめ
リーダーウォークの必要性や教え方のコツを紹介してきました。
「トライしてもうまくいかない。」と思っている人もおられるかもしれません。
刺激の多い場所では簡単にはできないこともあるでしょう。
でも、諦めないで根気よく少しずつ努力してください。
愛犬がこちらを意識して歩けた瞬間の喜びは何物にも代えがたいものになります。
犬のマラセチアとは?
 犬のマラセチアという病気を知っているでしょうか。
犬の皮膚には元々カビの一種でもある真菌が存在しており、正常であれば特に問題ありませんが、なにかしらの原因で異常発生してしまうとさまざまな症状が出てきてしまいます。
マラセチアの症状は手足の先や股・脇・首回りなどに症状が出やすい特徴があり、夏場になると発症しやすく、悪化もしやすいです。
犬種によっても発症してしまう可能性に差はありますが、原因を把握して適切な治療を受ければ完治することができる病気でもあります。
犬のマラセチアという病気を知っているでしょうか。
犬の皮膚には元々カビの一種でもある真菌が存在しており、正常であれば特に問題ありませんが、なにかしらの原因で異常発生してしまうとさまざまな症状が出てきてしまいます。
マラセチアの症状は手足の先や股・脇・首回りなどに症状が出やすい特徴があり、夏場になると発症しやすく、悪化もしやすいです。
犬種によっても発症してしまう可能性に差はありますが、原因を把握して適切な治療を受ければ完治することができる病気でもあります。
犬のマラセチアの症状
 愛犬がマラセチアになっているかどうかを知るためには症状を理解しておくことが重要になります。
マラセチアの症状は皮膚が赤くなるため、普段から皮膚のチェックをしていれば早期発見することも可能です。
そのほかにはフケが多くなったり、べたつきや痒みの症状もあらわれるようになります。
また、独特のにおいが出る特徴もあるため、普段嗅いだことのないにおいをしているのであれば念入りに皮膚の確認をしましょう。
爪付近のマラセチアの症状が悪化してしまうと爪が黒く変色してしまうような症状もあります。
愛犬がマラセチアになっているかどうかを知るためには症状を理解しておくことが重要になります。
マラセチアの症状は皮膚が赤くなるため、普段から皮膚のチェックをしていれば早期発見することも可能です。
そのほかにはフケが多くなったり、べたつきや痒みの症状もあらわれるようになります。
また、独特のにおいが出る特徴もあるため、普段嗅いだことのないにおいをしているのであれば念入りに皮膚の確認をしましょう。
爪付近のマラセチアの症状が悪化してしまうと爪が黒く変色してしまうような症状もあります。
犬のマラセチアの原因
 マラセチアになってしまう原因は解明されているので、原因を改善することでマラセチアを予防したり、症状が悪化してしまうことも防ぎます。
マラセチアの原因は加齢や住む環境が変わったたことなどです。
そのほかにも栄養バランスの乱れが関係している場合もあるため、愛犬がマラセチアになってしまったのであれば一つずつ原因を改善していくようにしましょう。
マラセチアはカビが異常増殖することが原因であるため、菌が増殖してしまう原因を理解すればマラセチアの原因と関連していることが多いです。
例えば菌はしまった環境を好むため、皮脂が多く分泌されていたり、スキンケアが不十分であることもマラセチアの原因となります。
皮脂や汚れは皮膚と皮膚がこすれ合う部分に溜まりやすいため、マラセチアもそのような部位で発症することが多いです。
マラセチアになってしまう原因は解明されているので、原因を改善することでマラセチアを予防したり、症状が悪化してしまうことも防ぎます。
マラセチアの原因は加齢や住む環境が変わったたことなどです。
そのほかにも栄養バランスの乱れが関係している場合もあるため、愛犬がマラセチアになってしまったのであれば一つずつ原因を改善していくようにしましょう。
マラセチアはカビが異常増殖することが原因であるため、菌が増殖してしまう原因を理解すればマラセチアの原因と関連していることが多いです。
例えば菌はしまった環境を好むため、皮脂が多く分泌されていたり、スキンケアが不十分であることもマラセチアの原因となります。
皮脂や汚れは皮膚と皮膚がこすれ合う部分に溜まりやすいため、マラセチアもそのような部位で発症することが多いです。
犬のマラセチアの予防法
 マラセチア菌は健康な犬の皮膚にも存在しており、マラセチアの症状が出てしまう原因は過度に増殖することであるため、シャンプーや食事を工夫すれば予防することが期待できます。
シャンプーで皮膚の汚れや皮脂をしっかりとることで菌が栄養とするものがなくなるため、増殖することを防ぎます。
食事は脂分が少ない物を与えるようにすれば皮脂の分泌を軽減することができ、マラセチア予防としての効果もあります。
対策さえしっかりしておけば高い確率でマラセチアを予防することができ、飼い主がしっかり注意して健康管理を行うようにしましょう。
マラセチア菌は健康な犬の皮膚にも存在しており、マラセチアの症状が出てしまう原因は過度に増殖することであるため、シャンプーや食事を工夫すれば予防することが期待できます。
シャンプーで皮膚の汚れや皮脂をしっかりとることで菌が栄養とするものがなくなるため、増殖することを防ぎます。
食事は脂分が少ない物を与えるようにすれば皮脂の分泌を軽減することができ、マラセチア予防としての効果もあります。
対策さえしっかりしておけば高い確率でマラセチアを予防することができ、飼い主がしっかり注意して健康管理を行うようにしましょう。
犬のマラセチアの治療法
 マラセチアの症状が出てしまっても適切な治療法を行うことで完治することができます。
飼い主が工夫すれば症状が改善される場合もありますが、一度マラセチアを発症してしまったのであれば病院で治療を受けるようにしましょう。
次に、マラセチアの治療方法を紹介するので参考にしてください。
マラセチアの症状が出てしまっても適切な治療法を行うことで完治することができます。
飼い主が工夫すれば症状が改善される場合もありますが、一度マラセチアを発症してしまったのであれば病院で治療を受けるようにしましょう。
次に、マラセチアの治療方法を紹介するので参考にしてください。
治療法①:飲み薬
飲み薬は全身に薬の効果を広がるので、非常に便利な治療方法です。
マラセチアはさまざまな患部に症状があらわれてしまう病気であり、重度であれば体のさまざまな部分がマラセチアになってしまいます。
しかし、飲み薬であればすべての箇所に効果が期待でき、広範囲にマラセチアの症状が出てしまった際に最適です。
そのかわり、肝臓に負担をかけてしまう欠点があり、肝臓が弱い犬には使用できないこともあります。
直接飲ませる方法と飲み物に混ぜて与える方法で摂取することが一般的です。
治療法②:塗り薬
 塗り薬での治療は、マラセチアの症状が出ている場所に直接薬を塗る方法です。
マラセチアの治療法の中でも一番簡単な治療法となっています。
上記で紹介した飲み薬での治療法には副作用が出てしまう可能性がありますが、塗り薬の場合は全身に副作用が起きてしまうことがなく、安心して塗布することが可能です。
しかし、マラセチアの症状が出ている部分が広範囲であれば塗布することに時間がかかってしまうことや塗布した後にすぐに舐めてしまう可能性がある欠点があります。
すぐに舐めてしまう場合は食後に塗布したり、塗布した後に遊んであげて舐めさせないようにしましょう。
塗り薬での治療は、マラセチアの症状が出ている場所に直接薬を塗る方法です。
マラセチアの治療法の中でも一番簡単な治療法となっています。
上記で紹介した飲み薬での治療法には副作用が出てしまう可能性がありますが、塗り薬の場合は全身に副作用が起きてしまうことがなく、安心して塗布することが可能です。
しかし、マラセチアの症状が出ている部分が広範囲であれば塗布することに時間がかかってしまうことや塗布した後にすぐに舐めてしまう可能性がある欠点があります。
すぐに舐めてしまう場合は食後に塗布したり、塗布した後に遊んであげて舐めさせないようにしましょう。
治療法③:シャンプー
薬用シャンプーを使用することで治療できる方法もあります。
普段しているシャンプーを薬用シャンプーに変えるだけでよいため、定期的にシャンプーをしている飼い主であればあまり負担に感じることがありません。
しかし、シャンプーをすることは手間になってしまうだけではなく、時間も必要となります。
そのため、マラセチアの治療方法の中でも最も手間がかかる治療法と言えます。
その代わりに全身に副作用が出てしまうリスクが低いです。
治療法④:原因となる基礎疾患の治療
 一般的に上記で紹介した3つの治療法をすれば症状を抑えることができたり、完治させることができます。
しかし、3つの治療法すべてを試してみても症状が改善されない場合は、基礎疾患が関係している可能性があります。
基礎疾患が原因でマラセチアになってしまっているのであれば根本的原因でもある基礎疾患を直さなければすぐにマラセチアを誘発させてしまいます。
素人ではなかなか基礎疾患を把握することは難しいので動物病院で基礎疾患の有無の確認や治療をするようにしましょう。
一般的に上記で紹介した3つの治療法をすれば症状を抑えることができたり、完治させることができます。
しかし、3つの治療法すべてを試してみても症状が改善されない場合は、基礎疾患が関係している可能性があります。
基礎疾患が原因でマラセチアになってしまっているのであれば根本的原因でもある基礎疾患を直さなければすぐにマラセチアを誘発させてしまいます。
素人ではなかなか基礎疾患を把握することは難しいので動物病院で基礎疾患の有無の確認や治療をするようにしましょう。
まとめ
マラセチアは犬の皮膚の病気であり、体が擦れ、蒸れやすい部分で発症してしまうリスクがあります。
マラセチアの病気は治療法が確立されているので、完治させることもできます。
また、飼い主が気を付けるだけでもマラセチアの予防をすることもできるので、愛犬が苦しまないように皮膚のケアを怠らないようにしましょう。
ペットショップ店員になる方法は?
 ペットが好きな人であればペットショップの店員になりたいと考えている人もいるのではないでしょうか。
ペットショップの店員になるためには専門のスキルがなければ就職できないと考えてしまうことも多いですが、学歴や資格などは求められない傾向があります。
ただし、専門学校などを卒業していたり、資格を有しているのであれば即戦力となり得るので採用される可能性は高いです。
資格や学歴がない場合でも面接を通過することができればアルバイトから始めることができます。
そのため、ペットショップ店員になりたいのであれば、求人情報から探し、応募するようにしましょう。
最初はアルバイトでも経験を積んでいけばいずれ正社員となれる場合もあります。
ペットが好きな人であればペットショップの店員になりたいと考えている人もいるのではないでしょうか。
ペットショップの店員になるためには専門のスキルがなければ就職できないと考えてしまうことも多いですが、学歴や資格などは求められない傾向があります。
ただし、専門学校などを卒業していたり、資格を有しているのであれば即戦力となり得るので採用される可能性は高いです。
資格や学歴がない場合でも面接を通過することができればアルバイトから始めることができます。
そのため、ペットショップ店員になりたいのであれば、求人情報から探し、応募するようにしましょう。
最初はアルバイトでも経験を積んでいけばいずれ正社員となれる場合もあります。
ペットショップ店員の仕事内容
 元々ペット関係の仕事をしたいと考えていればある程度ペットショップ店員の仕事内容を把握していることもありますが、まったく知識や学歴もない人であれば詳しい仕事内容まで知ることは難しいです。
次に、ペットショップ店員の仕事内容を紹介します。
あらかじめ仕事内容を把握していれば自分にあっているのかどうかを確認することもできます。
元々ペット関係の仕事をしたいと考えていればある程度ペットショップ店員の仕事内容を把握していることもありますが、まったく知識や学歴もない人であれば詳しい仕事内容まで知ることは難しいです。
次に、ペットショップ店員の仕事内容を紹介します。
あらかじめ仕事内容を把握していれば自分にあっているのかどうかを確認することもできます。
仕事内容①:販売
ペットショップ店員の仕事は動物を販売することが目的です。
販売する際にはお客の人にさまざまな相談や質問をされることも想定されるので、最低限の知識が求められます。
スーパーなどのレジ打ちとはまた違う販売の仕事であるため、接客することが苦手な人では苦労してしまいます。
また、お客がペットのことを大事にしてくれるかや最後まで世話をすることができるかなども見極める必要もありますが、実質購入意欲があるお客に販売を拒むことは難しく、動物好きで命を尊重している人ほど葛藤してしまうことも多いです。
仕事内容②:生体管理
 ペットは当然生き物であるため、生体管理をしなければなりません。
食材や物などとは違い、品棚に並べていればよいだけではなく、些細な体調不良などにもいち早く築いたり、ストレスなどを与えないようにしなければなりません。
ペットショップの店員のメインの仕事はペットを販売することですが、生体管理をすることのほうが重要度は高いです。
生体管理をするためにはこまめに体調をチェックすることは当然ですが、知識も求められる仕事内容になります。
ペットの種類によって体調不良時にあらわれる症状は違うので、知識と経験がものをいう仕事内容です。
体調不良を見逃してしまい、死亡してしまった場合はペットショップの損害となってしまうため、最も神経をとがらせる仕事内容でもあります。
ペットは当然生き物であるため、生体管理をしなければなりません。
食材や物などとは違い、品棚に並べていればよいだけではなく、些細な体調不良などにもいち早く築いたり、ストレスなどを与えないようにしなければなりません。
ペットショップの店員のメインの仕事はペットを販売することですが、生体管理をすることのほうが重要度は高いです。
生体管理をするためにはこまめに体調をチェックすることは当然ですが、知識も求められる仕事内容になります。
ペットの種類によって体調不良時にあらわれる症状は違うので、知識と経験がものをいう仕事内容です。
体調不良を見逃してしまい、死亡してしまった場合はペットショップの損害となってしまうため、最も神経をとがらせる仕事内容でもあります。
仕事内容③:商品管理
ペットショップ店員の仕事内容で知られているのか上記で紹介した販売やペットの世話であるイメージがありますが、ペットショップに行くとペットだけではなく、さまざまなペット用品も販売されています。
ペットフードであったり、おもちゃなど多種多様用意され、賞味期限が切れていないかや在庫があるのかなどもチェックする必要があります。
また、人気商品を把握しておくことで受注する際の参考にもなります。
ペットショップ店員も事務的作業があることを知っておきましょう。
仕事内容④:清掃
 ペットショップ店員以外でも仕事内容に含まれている場合が多いのが清掃作業です。
ほかの職種でも清掃はほぼ仕事内容に含まれています。
しかし、ペットショップ店員の場合は店内の清掃はもちろんですが、ペットを入れているケースや糞尿なども掃除しなければなりません。
店内が汚れていたり、ペットが飼われている環境が汚れているとどんなに人気で可愛らしいペットを販売していても印象が悪くなり、客足が遠のいてしまいます。
ペットの糞尿の掃除に抵抗感を覚えてしまう人もいますが、ペットショップ店員になるのであれば必ずしなければならない仕事であるため、生理的に無理と感じてしまう人はペット関係の仕事に就くことは難しいです。
糞尿は1日に何回も行う生理現象であるため、1日数回掃除しなければならないことを覚悟しておきましょう。
ペットショップ店員以外でも仕事内容に含まれている場合が多いのが清掃作業です。
ほかの職種でも清掃はほぼ仕事内容に含まれています。
しかし、ペットショップ店員の場合は店内の清掃はもちろんですが、ペットを入れているケースや糞尿なども掃除しなければなりません。
店内が汚れていたり、ペットが飼われている環境が汚れているとどんなに人気で可愛らしいペットを販売していても印象が悪くなり、客足が遠のいてしまいます。
ペットの糞尿の掃除に抵抗感を覚えてしまう人もいますが、ペットショップ店員になるのであれば必ずしなければならない仕事であるため、生理的に無理と感じてしまう人はペット関係の仕事に就くことは難しいです。
糞尿は1日に何回も行う生理現象であるため、1日数回掃除しなければならないことを覚悟しておきましょう。
仕事内容⑤:グルーミング
グルーミングはペットを綺麗にすることであり、主に猫や犬、小動物などに行う作業です。
グルーミングをするタイミングが飼い主が決まった時で、ペットショップを去る際に綺麗な状態にしてあげる場合が多いです。
嫁入りや婿入りのような感じで行うことがあります。
しかし、飼い主が決まったタイミング以外にも定期的にグルーミングをしてあげることもあります。
グルーミングをすることで見栄えを綺麗にすることができるので、お客さんがペットを見て不衛生と感じないようにすることができ、購入意欲を高める効果も期待できます。
ペットショップ店員に必要なスキル
 上記ではペットショップ店員には特別なスキルは必要ないと紹介しましたが、あれば有利になるスキルはあります。
次に、ペットショップ店員におすすめのスキルを紹介します。
資格などではなく、考え方や意欲などに関係することでもあるので、すでにクリアしている場合も少なくありません。
上記ではペットショップ店員には特別なスキルは必要ないと紹介しましたが、あれば有利になるスキルはあります。
次に、ペットショップ店員におすすめのスキルを紹介します。
資格などではなく、考え方や意欲などに関係することでもあるので、すでにクリアしている場合も少なくありません。
店舗運営と接客・販売のスキル
店舗運営と接客・販売スキルがあれば仕事内容をうまくできるようになります。
店舗経営に関するスキルは正社員になり、身に付けておくことで将来店長を任される可能性があります。
店長になれば仕事内容が増えていき、事務的な仕事も増えますが、やりがいを見出すことができる場合もあります。
接客や販売に関するスキルはアルバイトでも正社員でも求められるスキルであり、社交的な人ほどクリアできる場合が多いです。
ペットショップ店員はペットとだけ接していればよいと考えているのであればすぐに考えを改めないと後悔してしまいます。
接客や販売のスキルは実際に働いてみて失敗や達成感を感じながら身に付ける必要があります。
大きい企業であれば研修会などである程度のスキルを身に付けることも可能です。
生体管理の仕事について興味がある
 ペットショップ店員はペットのお世話や健康管理をする必要があります。
世話をするにも健康管理をするにしても知識や技術が必要となってきます。
同僚や先輩などから教えてもらうことが一般的ではありますが、そもそもお世話や健康管理に興味がなければ中々身に付きません。
何事にも興味がないことを覚えることは難しく、ペット関係の仕事に向いていない可能性も出てきます。
ペットの世話の仕方や健康の異常の上場はペットごとに変わってくるので、幅広い知識が求められます。
例えば他のペットショップ店員が気づけないような微細な異常に気づくことができれば症状が悪化してしまうことを防ぐことができ、ペットを助けることができることはもちろんですが、上司などから評価もされます。
ペットショップ店員はペットのお世話や健康管理をする必要があります。
世話をするにも健康管理をするにしても知識や技術が必要となってきます。
同僚や先輩などから教えてもらうことが一般的ではありますが、そもそもお世話や健康管理に興味がなければ中々身に付きません。
何事にも興味がないことを覚えることは難しく、ペット関係の仕事に向いていない可能性も出てきます。
ペットの世話の仕方や健康の異常の上場はペットごとに変わってくるので、幅広い知識が求められます。
例えば他のペットショップ店員が気づけないような微細な異常に気づくことができれば症状が悪化してしまうことを防ぐことができ、ペットを助けることができることはもちろんですが、上司などから評価もされます。
ペットショップ店員に向いてる人
 ペットショップ店員に向いている人もいれば向いていない人もいます。
そのため、ペットショップ店員になるために行動する前に自分が向いているのか向いていないのかを確認しましょう。
もし、向いていないのであれば違う仕事にしたほうが無難かもしれません。
次に、ペットショップ店員に向いている人の特徴を紹介するので参考にしてください。
ペットショップ店員に向いている人もいれば向いていない人もいます。
そのため、ペットショップ店員になるために行動する前に自分が向いているのか向いていないのかを確認しましょう。
もし、向いていないのであれば違う仕事にしたほうが無難かもしれません。
次に、ペットショップ店員に向いている人の特徴を紹介するので参考にしてください。
ペットショップの仕事は辛いと理解している人
ペットショップの仕事はつらいことを知っている人のほうがさまざまな仕事でも耐えることができるのでおすすめです。
一見可愛らしいペットに囲まれて仕事をすることは動物好きであれば天職と思う場合もありますが、現実は体力的にハードであり、接客もするので精神的にも負担がかかることもあります。
また、ペットを大事に扱わない人を見かけたり、病気などでペットがなくなってしまう現場を見ることもあります。
なので甘い考えでペットショップ店員になってしまうとギャップに耐えられないことも珍しくありません。
粘り強くて忍耐力のある人
 ペットショップ店員は粘り強く忍耐力がある人がおすすめです。
上記で紹介したように肉体的・精神的にハードな仕事内容であるため、精神的や体力的に自信があり、耐えられる力がなければ途中で挫折してしまう可能性があります。
また、動物の管理や世話をする際には少しでも意思疎通ができることが求められます。
しかし、動物とは言葉で気持ちを伝えることが難しく、長い時間をかけて信頼関係を築き、意思疎通ができるようになります。
そのため、意思疎通することができずイライラしてしまう人は向いていません。
ペットショップ店員は粘り強く忍耐力がある人がおすすめです。
上記で紹介したように肉体的・精神的にハードな仕事内容であるため、精神的や体力的に自信があり、耐えられる力がなければ途中で挫折してしまう可能性があります。
また、動物の管理や世話をする際には少しでも意思疎通ができることが求められます。
しかし、動物とは言葉で気持ちを伝えることが難しく、長い時間をかけて信頼関係を築き、意思疎通ができるようになります。
そのため、意思疎通することができずイライラしてしまう人は向いていません。
責任感が強い人
ペットショップで扱っている動物たちは命ある生き物であり、責任感が求められます。
少しでも動物の管理を怠ってしまうと体調不良や病気になってしまうので気の抜けない仕事でもあります。
また、責任感が強いことは動物の健康管理ができるだけではなく、店の運営にも大きく関わってきます。
例えば責任感が薄く、動物への愛情が薄かったり、世話がおろそかであればそれだけ病気になっている可能性もあります。
動物の異変に気付かないまま販売してしまうと後からクレームが来てしまいます。
その数が多ければ人気がなくなり、経営不振に陥ってしまいます。
まとめ
ペットショップ店員は一見動物好きであればおすすめできる職業のように見えてしまいますが、
知らない作業内容や精神的や肉体的にもきつい一面もあるため、表面だけではなく本質も理解して仕事に就くようにしましょう。
資格などは必要ないため、アルバイトであれば比較的採用されることも多いので、
正社員として就職する前に一度アルバイトやパートとして働き、自分にペットショップ店員は向いているのかどうかを確認しましょう。
ハチ公はどんな犬?
 皆さんは、忠犬ハチ公をご存知でしょうか。
渋谷駅前にある銅像のモデルとなった秋田犬のハチは、主人との深い繋がりと信頼関係で結ばれた存在として広く海外にもファンがいます。
飼い主が亡き後も変わらずに、自分を可愛がってくれた飼い主の帰りを渋谷駅で待ち続けました。
健気なハチの存在は、当時の様子を知る人達はもちろん全国にまで広がり多くの感動と感銘を与え、渋谷駅を始めゆかりのある地域や建物にはハチ公像や飼い主であった上野博士と嬉しそうにはしゃぐハチ公像が建てられています。
ハチの犬種や生涯をご紹介していきます。
皆さんは、忠犬ハチ公をご存知でしょうか。
渋谷駅前にある銅像のモデルとなった秋田犬のハチは、主人との深い繋がりと信頼関係で結ばれた存在として広く海外にもファンがいます。
飼い主が亡き後も変わらずに、自分を可愛がってくれた飼い主の帰りを渋谷駅で待ち続けました。
健気なハチの存在は、当時の様子を知る人達はもちろん全国にまで広がり多くの感動と感銘を与え、渋谷駅を始めゆかりのある地域や建物にはハチ公像や飼い主であった上野博士と嬉しそうにはしゃぐハチ公像が建てられています。
ハチの犬種や生涯をご紹介していきます。
ハチ公の犬種「秋田犬」はどんな犬?
 秋田犬は、日本犬の中で唯一の大型犬として登録されています。
大型犬であるがゆえに、育てる環境を整え適切なしつけを行う必要があり誰でも飼いやすい犬種ではありません。
あまり見かけることも少ない秋田犬の特徴や性格についてご説明していきます。
秋田犬は、日本犬の中で唯一の大型犬として登録されています。
大型犬であるがゆえに、育てる環境を整え適切なしつけを行う必要があり誰でも飼いやすい犬種ではありません。
あまり見かけることも少ない秋田犬の特徴や性格についてご説明していきます。
秋田犬の身体的特徴
秋田犬の毛色は、赤・白・虎毛の3色があり一番多いとされているのが赤毛となります。
飼い主と共に山に入り狩猟の手伝いをしていた犬として、大きくたくましい体つきとスラリと伸びた足・くるっと巻いた尾を持っています。
秋田で狩猟を行うマタギに重宝されていた犬が由来となっているので、東北の厳しい寒さに強いダブルコートの被毛が特徴です。
寒さには強いですが高温多湿の夏の気候には弱く、地域によっては難しいかもしれません。
また、かなりの運動量を必要としますので散歩はもちろん、ドッグランなどで走り回れるような環境を用意してあげましょう。
力も強く、万が一のときは制御する力が飼い主にも必要となりますので、小さいお子様がいる家庭の場合はよく熟慮してからお迎えしてください。
秋田犬の性格
 秋田犬は、飼い主と認めた人に対して従順で穏やかな性格といわれています。
その一方で、初対面の人や犬に対して警戒心を抱きやすく、攻撃的な面も持ち合わせています。
認めた飼い主以外への反応としては賢いがゆえとも言えますが、パピー期のころからしっかりとしつけを行わないと誰の言うことも聞かなくなりますので、家族に迎えるには覚悟と経験も必要となるでしょう。
また番犬としての活躍も期待されますが、近年では周囲の環境や人との良好な関わりを大切にしたほうが現実的かもしれません。
(駄目なこと・良いこと)の指示が伝わる信頼関係を築ければ、頭が良くて優しい頼もしいパートナーとなってくれます。
秋田犬は、飼い主と認めた人に対して従順で穏やかな性格といわれています。
その一方で、初対面の人や犬に対して警戒心を抱きやすく、攻撃的な面も持ち合わせています。
認めた飼い主以外への反応としては賢いがゆえとも言えますが、パピー期のころからしっかりとしつけを行わないと誰の言うことも聞かなくなりますので、家族に迎えるには覚悟と経験も必要となるでしょう。
また番犬としての活躍も期待されますが、近年では周囲の環境や人との良好な関わりを大切にしたほうが現実的かもしれません。
(駄目なこと・良いこと)の指示が伝わる信頼関係を築ければ、頭が良くて優しい頼もしいパートナーとなってくれます。
秋田犬の歴史
秋田犬は江戸時代以前から狩猟を行うマタギと一緒に山に入り、狩りに欠かせない存在として重宝されていました。
当時は狩りを行う犬のことを(マタギ犬)と呼んでおり、秋田県大館市に生息していた(アキタマタギ犬)が秋田犬のルーツともいわれています。
江戸時代に入ってから秋田犬は闘犬として育てられるようになり、より強い犬を生み出そうと西洋犬との掛け合わせが進められました。
そのため純血腫が減少しましたが、�数少ない秋田犬の保存活動のおかげで昭和に入って天然記念物として指定されています。
しかしその後、太平洋戦争が勃発し食糧難の中で犬を育てる余裕や確保が難しかったことや、軍用犬として使用された際に西洋犬と混血が進んでしまったことにより、再び純血腫の数が激減することになります。
戦後になって、秋田犬の保存活動が再び行われて少ない純血腫を絶やさないように人々が尽力し、活動は日本だけではなく海外にまで及びました。
ちなみに、戦時中に西洋犬と混血した秋田犬はその後アメリカへ渡りましたが、秋田犬をルーツに持つ(アメリカン・アキタ)という犬種がいるのはご存知でしょうか。
秋田犬の大きな体と飼い主にどもまでも忠誠を尽くす性格は、アメリカでも大人気となっているのは周知の事実です。
ハチ公が「忠犬」と呼ばれるようになった物語とは?
 みなさん、何も疑問を感じずに(忠犬)という言葉を使ってるかもしれません。
渋谷に銅像として佇む実際のハチは、忠犬という言葉に全く違和感のない行動と愛情を見せてくれた犬ではないでしょうか。
ここでは、そんな忠犬ハチ公の生涯をご紹介していきます。
みなさん、何も疑問を感じずに(忠犬)という言葉を使ってるかもしれません。
渋谷に銅像として佇む実際のハチは、忠犬という言葉に全く違和感のない行動と愛情を見せてくれた犬ではないでしょうか。
ここでは、そんな忠犬ハチ公の生涯をご紹介していきます。
ハチ公と上野教授の出会い
飼い主である現・東京大学農学部教授だった上野博士は大の犬好きとして知られ、東京都渋谷区にある自宅に秋田県から小さく可愛らしい子犬を引き取りました。
当初は上野教授の娘が飼う予定だったのですが慌ただしく結婚と妊娠が判明し、上野教授が面倒をみることになったその子犬は末広がりの足の形からハチと名付けられました。
当時は外で飼うのが当たり前だった犬を自宅内で寝かせるなどとても可愛がり、大きな愛情を掛けて育てたそうです。
ハチは每日、上野教授の出勤の見送りとお迎えをするために渋谷駅を訪れるようになり、周囲の人達や駅員に見守られ可愛がられました。
上野教授を待ち続けたハチ公
 幸せな每日が続いていましたが、ある朝同じように上野教授を見送った後に自宅に戻ったハチは、何かを感じ悲しげな声で鳴き始めました。
大学で教鞭を取っていた教授が突然倒れ、そのまま帰らぬ人となったのです。
妻と二人暮らしだった上野教授の自宅は売りに出され、妻は故郷へハチは知り合いの家へと新たな生活を始めます。
ですがハチは預けられた家を度々脱走し、可愛がってくれた上野教授の送り迎えのために每日決まった時間に渋谷駅へと向かいます。
いつしか住むところも失い、渋谷駅の周辺で野良犬のような暮らしが続いたある日、新聞記者の目にとまり全国にハチが紹介されることになりました。
その記事は上野博士の妻の目にも入り、心配した妻は上京しハチは懐かしい人と再会を果たします。
それがかつて幸せだったころの思い出を呼び起こす最後の対面となりました。
昭和10年3月8日、大好きな上野教授にひと目会いたいと願いながらハチはその生涯を閉じます。
幸せな每日が続いていましたが、ある朝同じように上野教授を見送った後に自宅に戻ったハチは、何かを感じ悲しげな声で鳴き始めました。
大学で教鞭を取っていた教授が突然倒れ、そのまま帰らぬ人となったのです。
妻と二人暮らしだった上野教授の自宅は売りに出され、妻は故郷へハチは知り合いの家へと新たな生活を始めます。
ですがハチは預けられた家を度々脱走し、可愛がってくれた上野教授の送り迎えのために每日決まった時間に渋谷駅へと向かいます。
いつしか住むところも失い、渋谷駅の周辺で野良犬のような暮らしが続いたある日、新聞記者の目にとまり全国にハチが紹介されることになりました。
その記事は上野博士の妻の目にも入り、心配した妻は上京しハチは懐かしい人と再会を果たします。
それがかつて幸せだったころの思い出を呼び起こす最後の対面となりました。
昭和10年3月8日、大好きな上野教授にひと目会いたいと願いながらハチはその生涯を閉じます。
ハチ公の死因は?
 ハチは死後、現・東京大学で病理解剖が行われ心臓や肝臓にフィラリアの寄生を確認しています。
さらに胃の中から焼き鳥の串も発見され、当時の渋谷駅周辺の屋台で与えられた焼き鳥だった可能性もあります。
これらの要因から、犬にとって今も恐い病気のひとつであるフィラリアと串による消化器官の損傷が死因とされました。
ですが近年になって、その考えが大きく覆されました。
ハチの内臓を保管している東京大学は、2011年にMRIなど最新技術によって再度細かく検査を行ったところ、心臓と肺に大きなガンがあったことが判明しました。
よってハチの死因はおそらくガンであったのではないかと考えられています。
ハチは死後、現・東京大学で病理解剖が行われ心臓や肝臓にフィラリアの寄生を確認しています。
さらに胃の中から焼き鳥の串も発見され、当時の渋谷駅周辺の屋台で与えられた焼き鳥だった可能性もあります。
これらの要因から、犬にとって今も恐い病気のひとつであるフィラリアと串による消化器官の損傷が死因とされました。
ですが近年になって、その考えが大きく覆されました。
ハチの内臓を保管している東京大学は、2011年にMRIなど最新技術によって再度細かく検査を行ったところ、心臓と肺に大きなガンがあったことが判明しました。
よってハチの死因はおそらくガンであったのではないかと考えられています。
まとめ
ハチと上野教授が一緒に暮らした期間は、1年とも1年半ともいわれておりどちらにしても本当に短い間でした。
そんな短い期間でも、お互いを信頼し愛し愛された関係を築いたふたりは、今は天国で仲良く暮らしているでしょう。
犬と人はわかり会える最高のパートナーとなることを実感するハチの一生は、この先も多くの人に感動を与え続けてくれることを願っています。
犬のトリーツとおやつの違い
 皆さんはトリーツをご存知でしょうか。
愛犬が正しく指示に従ったりお留守番をしっかりできたりしたときに与えるものです。
ですが、おやつとトリーツが混同してしまっている場合があるかもしれません。
「おやつのことを言うんじゃないの?」と感じる飼い主様も多いはず。
犬のトリーツとおやつの違いと与え方についてご紹介していきます。
皆さんはトリーツをご存知でしょうか。
愛犬が正しく指示に従ったりお留守番をしっかりできたりしたときに与えるものです。
ですが、おやつとトリーツが混同してしまっている場合があるかもしれません。
「おやつのことを言うんじゃないの?」と感じる飼い主様も多いはず。
犬のトリーツとおやつの違いと与え方についてご紹介していきます。
トリーツはご褒美を指す
長く犬と共に暮らしていても、トリーツという言葉を口にする機会は多くないかもしれません。
それは、家庭で行うしつけに対して「愛犬が大好きなおやつを使って褒めて教える」という言葉が様々な場所で使用されているためでもあります。
「TREATS」という英語は、「ごちそう・もてなし」という意味があります。
つまりは、「おやつ」という意味は含まれていません。
愛犬が指示に従うことができた・良い行動を起こすための動機付けとしてトリーツをごほうびとして与えます。
おやつは間食を指す
 では、おやつはどんな意味を持つ言葉なのでしょう。
漢字で書くと「御八つ」という字になり、はるか昔の江戸時代から習慣となった午後3時(八つ時)の間食が元になっています。
つまりおやつは間食の意味を持ち、特に良いことや指示に従ったから与えるといった動機はないものと考えられています。
愛犬に何か与えるときは、ご飯とおやつの2つに分けられていることが多く、実際にしつけに使用するトリーツは愛犬が喜ぶものや大好きなものであれば、おやつを与えても問題はありません。
では、おやつはどんな意味を持つ言葉なのでしょう。
漢字で書くと「御八つ」という字になり、はるか昔の江戸時代から習慣となった午後3時(八つ時)の間食が元になっています。
つまりおやつは間食の意味を持ち、特に良いことや指示に従ったから与えるといった動機はないものと考えられています。
愛犬に何か与えるときは、ご飯とおやつの2つに分けられていることが多く、実際にしつけに使用するトリーツは愛犬が喜ぶものや大好きなものであれば、おやつを与えても問題はありません。
トリーツの注意点
 では、トリーツを与えるタイミングはいつが良いのでしょうか。
ご褒美は愛犬にとってとても嬉しく、飼い主様との信頼関係を築くことにも役立ちます。
注意点を守って愛犬とより親密な関係性を築いていきましょう。
では、トリーツを与えるタイミングはいつが良いのでしょうか。
ご褒美は愛犬にとってとても嬉しく、飼い主様との信頼関係を築くことにも役立ちます。
注意点を守って愛犬とより親密な関係性を築いていきましょう。
タイミングは早い方が良い
飼い主様の指示を守っておすわりやマテができたり、アイコンタクトがキチンとできたりしたタイミングにすぐ与えてみましょう。
犬は大好きな飼い主様に喜んでもらうことや褒めてくれることが大好きです。
良いこと=トリーツ(ご褒美)を繰り返して、自分の行動が褒められたことを愛犬に覚えさせます。
少しでも間を開けてしまうと、なぜもらえるのかわからずに単におやつがもらえたと勘違いしてしまうかもしれません。
また、指示に従ったけれどすぐ立ち上がってしまったときや動いてしまったときは、与えないようにします。
飼い主様が解除の指示を口にしないうちに与えると、動いたところまでを一括にして覚えてしまうことがあります。
トリーツを先に与えるのは禁止
 玄関のチャイム吠えでお困りの飼い主様は多いかもしれません。
そんなとき、トリーツで犬を大人しくさせる使い方をしていませんか。
吠えた愛犬に対して、先にトリーツを与えて静かにさせても、犬は吠えたらおやつがもらえたと勘違いしてしまいます。
まず愛犬を落ち着かせるためにおすわりやハウスなど簡単な指示で静かにさせましょう。
最初は言うことを聞かずに、玄関に走っていくかもしれませんが少しづつ根気よく続けていくことが大切です。
少しでも静かに出来たらトリーツを与えましょう。
時間を徐々に伸ばしていくことで、例え吠えたとしてもすぐに静かに落ち着いた状態を保つことができるようになります。
ですので、トリーツは静かにさせるためのおやつではなく静かにできたことへのご褒美として利用しましょう。
玄関のチャイム吠えでお困りの飼い主様は多いかもしれません。
そんなとき、トリーツで犬を大人しくさせる使い方をしていませんか。
吠えた愛犬に対して、先にトリーツを与えて静かにさせても、犬は吠えたらおやつがもらえたと勘違いしてしまいます。
まず愛犬を落ち着かせるためにおすわりやハウスなど簡単な指示で静かにさせましょう。
最初は言うことを聞かずに、玄関に走っていくかもしれませんが少しづつ根気よく続けていくことが大切です。
少しでも静かに出来たらトリーツを与えましょう。
時間を徐々に伸ばしていくことで、例え吠えたとしてもすぐに静かに落ち着いた状態を保つことができるようになります。
ですので、トリーツは静かにさせるためのおやつではなく静かにできたことへのご褒美として利用しましょう。
運動と共に行う
トリーツは指示を理解し良い行動をしたときに与えますが、散歩といった体を動かすことが少ない場合が多いのでカロリー過多に繋がることも考えられます。
しつけのトレーニングにトリーツを利用するときは、体を動かす遊びを取り入れて運動とセットにするとより効果的です。
愛犬も楽しく遊びながらご褒美ももらえるので、トレーニングの時間が待ち遠しくなりやる気にも繋がるでしょう。
トリーツの適量はどのくらい?
 時間を置かずにすぐ与えられるように、飼い主様が扱いやすく愛犬がぺろっと食べられる大きさが大切です。
愛犬の体の大きさに関わらず、ごく少量で大きさにすると数ミリ程度でしょうか。
何粒もまとめて与えるのではなく、一粒ずつ与えましょう。
あくまでご褒美ですので、食べごたえや長持ちするような大きさは必要ありません。
すぐに与えられるように、飼い主様は取り出しやすい専用ポーチにトリーツを入れて腰に付けておくと、とても便利です。
時間を置かずにすぐ与えられるように、飼い主様が扱いやすく愛犬がぺろっと食べられる大きさが大切です。
愛犬の体の大きさに関わらず、ごく少量で大きさにすると数ミリ程度でしょうか。
何粒もまとめて与えるのではなく、一粒ずつ与えましょう。
あくまでご褒美ですので、食べごたえや長持ちするような大きさは必要ありません。
すぐに与えられるように、飼い主様は取り出しやすい専用ポーチにトリーツを入れて腰に付けておくと、とても便利です。
トリーツの選び方
 トリーツはご褒美だということをご説明してきましたが、食べ物である必要はありません。
愛犬が好きなもの・喜ぶものであれば、おもちゃやボールといった遊ぶものでもトリーツになります。
犬によっては、食べ物にあまり興味を持たないコもいますので飼い主様が愛犬の喜ぶものを把握し、トリーツとして利用してください。
ドッグフードが大好きなコなら、フードを何粒も用意してあげれば喜びます。
犬の個性や好き嫌いで変わりますので、適切なトリーツを用意してあげましょう。
トリーツはご褒美だということをご説明してきましたが、食べ物である必要はありません。
愛犬が好きなもの・喜ぶものであれば、おもちゃやボールといった遊ぶものでもトリーツになります。
犬によっては、食べ物にあまり興味を持たないコもいますので飼い主様が愛犬の喜ぶものを把握し、トリーツとして利用してください。
ドッグフードが大好きなコなら、フードを何粒も用意してあげれば喜びます。
犬の個性や好き嫌いで変わりますので、適切なトリーツを用意してあげましょう。
トリーツは心の栄養になる
 犬は長い歴史の中で、人と共に暮らし様々なサポートをしてくれる存在として信頼関係を築いてきました。
自分を可愛がってくれる大好きな飼い主様に褒められながら行うしつけやトレーニングは、愛犬の心にも大きく作用します。
褒められることは自信と喜びになり、より飼い主様と深い絆が生まれていきます。
トリーツは愛犬の心にも充足を与えますので、飼い主様は積極的に愛犬と関わりながら褒めていきましょう。
犬は長い歴史の中で、人と共に暮らし様々なサポートをしてくれる存在として信頼関係を築いてきました。
自分を可愛がってくれる大好きな飼い主様に褒められながら行うしつけやトレーニングは、愛犬の心にも大きく作用します。
褒められることは自信と喜びになり、より飼い主様と深い絆が生まれていきます。
トリーツは愛犬の心にも充足を与えますので、飼い主様は積極的に愛犬と関わりながら褒めていきましょう。
まとめ
なかなか上手にしつけが出来なくて困っている飼い主様も、トリーツを効果的に使用しながら愛犬とより良い関係を築くために頑張ってみませんか。
おやつとトリーツを上手く使い分けながら、適切な量をタイミングを逃さずに与えることが大切です。
そのためにも、おやつの分量が日頃多いなと感じる飼い主様は量を見直してトリーツと区別がつくようにすると良いかもしれません。
テレワーク中の猫対策7選
 コロナが流行ってからテレワークで働く場合が多くなっているため、猫を飼っている人であればさまざまなトラブルにあってしまった経験がある人も多いのではないでしょうか。
次に、テレワーク中の猫対策7選を紹介します。
大事な会議などをテレワークで行っている場合は特に要チェックです。
コロナが流行ってからテレワークで働く場合が多くなっているため、猫を飼っている人であればさまざまなトラブルにあってしまった経験がある人も多いのではないでしょうか。
次に、テレワーク中の猫対策7選を紹介します。
大事な会議などをテレワークで行っている場合は特に要チェックです。
対策①:仕事前に食事を準備する
猫がテレワーク中に邪魔をしてくる原因にご飯を催促している場合があります。
そのため、テレワークで仕事を始める前に猫に餌を与えて満腹状態にしておきましょう。
お腹がすいていなければテレワーク中にネコハラもしてこなくなります。
特に、長時間テレワークをする必要があったり、猫のご飯時期とテレワークの時間がかぶってしまうようであれば必ず事前にご飯を与えていたり、用意しておきましょう。
空腹が原因であれば餌を与えればネコハラをしてくることもなくなります。
対策②:仕事前にスキンシップを取る
 テレワーク中にネコハラしてくる原因は寂しい思いや構ってほしい気持ちからしている行動でもあります。
仕事前にしっかりスキンシップをとっておくことで猫も満足して邪魔をしてこなくなります。
遊びたい気持ちからネコハラをしてくるとちょっとやそっとではネコハラをやめてくれません。
そのような状況になってしまうとテレワークどころではなくなってしまいます。
休憩時間にしっかり猫と遊んだり、マッサージするなどしてコミュニケーションをとるようにしましょう。
テレワーク中にネコハラしてくる原因は寂しい思いや構ってほしい気持ちからしている行動でもあります。
仕事前にしっかりスキンシップをとっておくことで猫も満足して邪魔をしてこなくなります。
遊びたい気持ちからネコハラをしてくるとちょっとやそっとではネコハラをやめてくれません。
そのような状況になってしまうとテレワークどころではなくなってしまいます。
休憩時間にしっかり猫と遊んだり、マッサージするなどしてコミュニケーションをとるようにしましょう。
対策③:仕事場の側に猫のスペースを作る
仕事場の傍に猫のためのスペースを作るようにしましょう。
猫は飼い主の顔を見ると落ち着くため、猫から離れて仕事をするよりも傍にいるようにした方が邪魔してこなくなります。
猫のスペースを作る際には猫のお気に入りの寝床を移動させたり、猫のサイズに合った段ボールなどでも代用することができます。
猫を飼っている人であればわかる場合が多いですが、猫は狭いところに入り込む習性があります。
猫は自由奔放な性格のイメージがありますが、飼い主と距離があると傍にくる場合が多いです。
対策④:ケージにいてもらう
 どうしても猫がテレワーク中に邪魔をしてくるのであればケージに入れるようにしましょう。
ケージに入れてしまえばそこから出ることができないため、テレワークに集中することができます。
普段室内で放し飼いをしている人であればケージに閉じ込めてしまうことは可愛そうと感じてしまう人も多いですが、
ケージの中にハンモックやキャットタワーなどがあれば狭い空間でもストレスを与えてしまうことがありません。
別室などに一時的に閉じ込めることができない場合にもケージが大活躍してくれます。
どうしても猫がテレワーク中に邪魔をしてくるのであればケージに入れるようにしましょう。
ケージに入れてしまえばそこから出ることができないため、テレワークに集中することができます。
普段室内で放し飼いをしている人であればケージに閉じ込めてしまうことは可愛そうと感じてしまう人も多いですが、
ケージの中にハンモックやキャットタワーなどがあれば狭い空間でもストレスを与えてしまうことがありません。
別室などに一時的に閉じ込めることができない場合にもケージが大活躍してくれます。
対策⑤:猫ハウス付きの家具を買う
猫ハウス付きの家具が販売されていることを知っているでしょうか。
猫ハウス単体でも猫はリラックスすることができますが、猫ハウス付きの家具であれば飼い主が傍にいるという安心感を与えることもできます。
以前までは猫ハウス付きの家具は非常に珍しかったですが、最近ではテレワークが著しく増加しているため、猫を飼っている人向けの家具も多く販売されています。
デスクに猫の隠れ家がついているようなユニークな家具も販売されているので、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
対策⑥:猫が楽しめる空間作りを行う
 猫が楽しめるような空間を作ることで飼い主に執着してしまうことがなく、テレワークの邪魔もしてこなくなります。
キャットウォークやキャットタワーを設置しているだけでも猫だけで遊ぶことができます。
そのほかにも温かい日差しがさしこむ窓際にフワフワの毛布を用意していれば勝手にお昼寝したり、リラックスしてくれます。
しかし、いくら快適な空間を用意してあげても飼い主との触れあいがなければ寂しくなったり、飼い主に会いに来てしまうため、定期的に猫の様子を見たり、撫でてあげましょう。
猫が楽しめるような空間を作ることで飼い主に執着してしまうことがなく、テレワークの邪魔もしてこなくなります。
キャットウォークやキャットタワーを設置しているだけでも猫だけで遊ぶことができます。
そのほかにも温かい日差しがさしこむ窓際にフワフワの毛布を用意していれば勝手にお昼寝したり、リラックスしてくれます。
しかし、いくら快適な空間を用意してあげても飼い主との触れあいがなければ寂しくなったり、飼い主に会いに来てしまうため、定期的に猫の様子を見たり、撫でてあげましょう。
対策⑦:猫とは別室で仕事する
猫と同じ空間で仕事をすることはテレワーク中に猫対策として紹介しましたが、猫が同じ室内にいるとどうしても邪魔をしてくることがあります。
また、飼い主も猫の様子が気になってしまい、仕事に集中できないことも珍しくありません。
このような状況でテレワークすることは効率が悪いため、猫を別室に連れて行くようにしましょう。
ドアなどをしっかり閉めてテレワーク中に猫が自室に来ないようにすれば仕事に集中することができます。
ただし、長い時間猫を閉じ込めてしまうと個体差はありますが、ストレスを感じてしまうこともあるため注意が必要です。
テレワーク中に猫が乱入してくる理由とは?
 テレワーク中に猫が乱入してくることは多く、普段ではそこまで近づいて来ない猫でも邪魔してくることもあります。
テレワーク中に邪魔をしてしまうことには理由がありますが、猫自身は飼い主の邪魔をするつもりはないため、怒らずに対策を練るようにしましょう。
テレワーク中に猫が乱入してくることは多く、普段ではそこまで近づいて来ない猫でも邪魔してくることもあります。
テレワーク中に邪魔をしてしまうことには理由がありますが、猫自身は飼い主の邪魔をするつもりはないため、怒らずに対策を練るようにしましょう。
不安を感じている
猫がテレワーク中に邪魔をしてくる理由に不安を感じていることが関係している場合もあります。
テレワークを最近始めた際に猫が邪魔してくる理由に当てはまることが多く、飼い主がパソコンの前にずっと座って何かしている光景が今までにないことであるため、不安を感じます。
いつもと違う飼い主の雰囲気に不安を感じてしまい、こっちを見てほしかったり、構って欲しい気持ちから邪魔をしてきます。
邪魔をしてくる際に飼い主の方を見るようにしている場合は不安を感じている場合が多いため、撫でてあげるなどして安心させてあげましょう。
パソコンが暖かいから
 猫は元々温かい場所を好む動物であり、縁側などで日向ぼっこをしている光景をよく見かけるのはそのためです。
電源が入っているパソコンは程よく熱を帯びており、猫にとっては心地よい場所となります。
キーボードの上が温かくなりやすく、上に乗りやすいことからパソコン操作の邪魔をしてしまいがちです。
キーボードが熱を帯びるのはノートパソコンであり、デスクトップ型のキーボードはそこまで温かくならないので、デスクトップ型のパソコンを使用していればキーボードではなく、箱形の装置の上などに位置取りするケースが多くなります。
猫は元々温かい場所を好む動物であり、縁側などで日向ぼっこをしている光景をよく見かけるのはそのためです。
電源が入っているパソコンは程よく熱を帯びており、猫にとっては心地よい場所となります。
キーボードの上が温かくなりやすく、上に乗りやすいことからパソコン操作の邪魔をしてしまいがちです。
キーボードが熱を帯びるのはノートパソコンであり、デスクトップ型のキーボードはそこまで温かくならないので、デスクトップ型のパソコンを使用していればキーボードではなく、箱形の装置の上などに位置取りするケースが多くなります。
パソコンへの好奇心
猫は好奇心が強く、飼い主が熱中して捜査しているパソコンにも興味を持ちます。
パソコンが楽しいものなのかどうか確認して、楽しいものであれば自分も一緒に遊びたいという気持ちが芽生え、パソコンの前に堂々と入ってきます。
上記で紹介した理由からパソコンの邪魔をしてくる場合もありますが、画面やキーボードのにおいを嗅いだり、観察するようにしている場合は暖を取りに来たのではなく、パソコンに興味がある可能性が高いです。
飼い主のことが好きすぎる
 個体差がありますが、飼い主のことが好きすぎる猫であれば自分に構って欲しい気持ちから邪魔をしてきます。
猫に愛されていることは飼い主にとっては嬉しいことではありますが、仕事中ではどうしても邪魔と感じてしまいます。
しかし、素っ気ない態度で接してしまったり、邪魔されることに対して怒るなどしてしまうと信頼関係を崩してしまいます。
普段から甘えてくる猫ほど飼い主のことを独占したい気持ちが強く、パソコンばかりに構っていると嫉妬心からパソコンの画面の前に来て、作業の妨害をしてきます。
個体差がありますが、飼い主のことが好きすぎる猫であれば自分に構って欲しい気持ちから邪魔をしてきます。
猫に愛されていることは飼い主にとっては嬉しいことではありますが、仕事中ではどうしても邪魔と感じてしまいます。
しかし、素っ気ない態度で接してしまったり、邪魔されることに対して怒るなどしてしまうと信頼関係を崩してしまいます。
普段から甘えてくる猫ほど飼い主のことを独占したい気持ちが強く、パソコンばかりに構っていると嫉妬心からパソコンの画面の前に来て、作業の妨害をしてきます。
パソコンへの嫉妬心
テレワークをしていない時期では家に家にいればよく構ってくれたのに、テレワークでパソコンに構う時間が増えてしまうとパソコンに対して嫉妬心を抱く猫もいます。
パソコンに嫉妬心を抱いた猫は敵とみなすため、お得意の猫パンチを繰り出すことも少なくありません。
パソコンへの嫉妬心はそれだけ飼い主を独り占めしたい気持ちの表れでもあるため、テレワークする前にしっかり遊んだりしてコミュニケーションをとるようにしましょう。
攻撃的な猫であればデスクの上からパソコンを落としてしまうなど強硬な手段をとることも考えられます。
まとめ
テレワーク中に猫に邪魔をされた経験がある人も多いのではないでしょうか。
さまざまな理由から猫は邪魔をしてきますが、悪意のある行動ではなく、パソコンへの興味や飼い主を独り占めしたい独占欲、パソコンの温かさを求めるなどが一般的です。
テレワークを邪魔されて作業効率が落ちてしまうのであれば、テレワーク中の対策をしっかりとるようにしましょう。
 犬にアーモンドを与えてもよいのか気になる人もいるのではないでしょうか。
アーモンドは犬に与えても問題なく、人の間でも注目されているナッツ類であるため、同じ効果を愛犬にも得てほしいなら与えましょう。
ただし、アーモンドは高脂肪であり、消化も悪いので与えすぎてしまうと肥満体質になってしまいやすく、嘔吐や下痢などを起こしてしまう可能性もあるので注意しましょう。
いくら体に良いとされている食材でも食べすぎは体に悪影響を及ぼす原因となってしまいます。
犬にアーモンドを与えてもよいのか気になる人もいるのではないでしょうか。
アーモンドは犬に与えても問題なく、人の間でも注目されているナッツ類であるため、同じ効果を愛犬にも得てほしいなら与えましょう。
ただし、アーモンドは高脂肪であり、消化も悪いので与えすぎてしまうと肥満体質になってしまいやすく、嘔吐や下痢などを起こしてしまう可能性もあるので注意しましょう。
いくら体に良いとされている食材でも食べすぎは体に悪影響を及ぼす原因となってしまいます。
 犬にアーモンドを与えても問題はありませんが、いくつか注意しなければならないポイントがあります。
そのため、注意点を把握せずにアーモンドを与えてしまうと何かしらの不調を起こしてしまうリスクがあります。
次に、犬にアーモンドを与える際の注意点を紹介するので参考にしてください。
犬にアーモンドを与えても問題はありませんが、いくつか注意しなければならないポイントがあります。
そのため、注意点を把握せずにアーモンドを与えてしまうと何かしらの不調を起こしてしまうリスクがあります。
次に、犬にアーモンドを与える際の注意点を紹介するので参考にしてください。
 犬がアーモンドを食べる際は歯の形も関係していますが、細かく砕いて食べることができません。
そのため、1粒丸々飲み込んでしまうことも珍しくなく、喉や消化器官などに詰まってしまう恐れがあります。
そのほかにも細かくなっていないまま胃に運ばれてしまうため、それだけ消化にも時間がかかってしまいます。
ただでさえ消化しにくいアーモンドであるため、さらに消化しにくくなってしまい、下痢や嘔吐のリスクが高まります。
犬にアーモンドを与える際には事前に細かく砕く一工夫をしてあげるようにしましょう。
また、茹でることで柔らかくすることができ、消化もしやすくなるのでおすすめです。
アーモンドに一工夫を加えることは面倒と感じてしまうことも多いですが、愛犬のことを第一に考えるのであれば必ず行うようにしましょう。
犬がアーモンドを食べる際は歯の形も関係していますが、細かく砕いて食べることができません。
そのため、1粒丸々飲み込んでしまうことも珍しくなく、喉や消化器官などに詰まってしまう恐れがあります。
そのほかにも細かくなっていないまま胃に運ばれてしまうため、それだけ消化にも時間がかかってしまいます。
ただでさえ消化しにくいアーモンドであるため、さらに消化しにくくなってしまい、下痢や嘔吐のリスクが高まります。
犬にアーモンドを与える際には事前に細かく砕く一工夫をしてあげるようにしましょう。
また、茹でることで柔らかくすることができ、消化もしやすくなるのでおすすめです。
アーモンドに一工夫を加えることは面倒と感じてしまうことも多いですが、愛犬のことを第一に考えるのであれば必ず行うようにしましょう。
 犬にアーモンドを与える際には適量を与えることが大切であり、過剰摂取してしまうと危険な状態になることもあります。
下痢や嘔吐をしてしまうことはもちろんですが、病気になってしまい、最悪手術などの治療を行わなければならなくなることもあります。
次に、犬にアーモンドを過剰摂取することの危険性を紹介するので、アーモンドを愛犬に与えようと考えている人は参考にしてください。
犬にアーモンドを与える際には適量を与えることが大切であり、過剰摂取してしまうと危険な状態になることもあります。
下痢や嘔吐をしてしまうことはもちろんですが、病気になってしまい、最悪手術などの治療を行わなければならなくなることもあります。
次に、犬にアーモンドを過剰摂取することの危険性を紹介するので、アーモンドを愛犬に与えようと考えている人は参考にしてください。
 アーモンドにはカロリーが豊富に含まれているので大量に食べてしまうと当然肥満体質になってしまいやすいです。
犬が肥満体質になってしまうと胃寿命が縮んだり、糖尿の誘発、免疫力の低下などさまざまな悪影響を及ぼしてしまいます。
また、体重が重くなってしまうため、各関節にかかる負担も大きくなってしまい、関節痛になってしまうことも考えられます。
健康のために与えているアーモンドでも与える量を間違えるだけで、健康的な体ではなく、不健康な体に近づいてしまうため、逆効果になってしまいます。
特に、運動量が少ない犬は普段から消費するカロリーも少ないため、より短期間で肥満体質になってしまうリスクがあります。
アーモンドには脂質やカロリーが豊富に含まれていることを理解して、カロリーや脂質の過剰摂取にならないように気をつけましょう。
アーモンドにはカロリーが豊富に含まれているので大量に食べてしまうと当然肥満体質になってしまいやすいです。
犬が肥満体質になってしまうと胃寿命が縮んだり、糖尿の誘発、免疫力の低下などさまざまな悪影響を及ぼしてしまいます。
また、体重が重くなってしまうため、各関節にかかる負担も大きくなってしまい、関節痛になってしまうことも考えられます。
健康のために与えているアーモンドでも与える量を間違えるだけで、健康的な体ではなく、不健康な体に近づいてしまうため、逆効果になってしまいます。
特に、運動量が少ない犬は普段から消費するカロリーも少ないため、より短期間で肥満体質になってしまうリスクがあります。
アーモンドには脂質やカロリーが豊富に含まれていることを理解して、カロリーや脂質の過剰摂取にならないように気をつけましょう。
 アーモンドは与える量さえ間違えなければ犬に与えても害を及ぼしてしまうことはありませんが、ほかのナッツ類であればどうなのか気になる人もいるのではないでしょうか。
アーモンドはナッツ類の一つであり、さまざまなナッツ類があります。
それぞれ種類が異なることで含まれる栄養素も異なるため、同じナッツ類でもあるアーモンドが問題ないのであれば与えても悪影響はないと考えるのではなく、一度確認しておくことをおすすめします。
アーモンドは与える量さえ間違えなければ犬に与えても害を及ぼしてしまうことはありませんが、ほかのナッツ類であればどうなのか気になる人もいるのではないでしょうか。
アーモンドはナッツ類の一つであり、さまざまなナッツ類があります。
それぞれ種類が異なることで含まれる栄養素も異なるため、同じナッツ類でもあるアーモンドが問題ないのであれば与えても悪影響はないと考えるのではなく、一度確認しておくことをおすすめします。
 マカダミアナッツを与えることは絶対にしないようにしましょう。
さまざまなナッツ類の中でも一番危険性が高いナッツとも言われています。
マカダミアナッツの中には中毒症状が出てしまう成分が含まれており、犬が食べてしまうとマカダミアナッツ中毒と言われる病気になってしまいます。
摂取してから12時間前後に症状があらわれる場合が多いです。
自然に回復する場合もありますが、死亡してしまうケースもあるので、食べてしまった場合は動物病院で診てもらうようにしましょう。
マカダミアナッツを与えることは絶対にしないようにしましょう。
さまざまなナッツ類の中でも一番危険性が高いナッツとも言われています。
マカダミアナッツの中には中毒症状が出てしまう成分が含まれており、犬が食べてしまうとマカダミアナッツ中毒と言われる病気になってしまいます。
摂取してから12時間前後に症状があらわれる場合が多いです。
自然に回復する場合もありますが、死亡してしまうケースもあるので、食べてしまった場合は動物病院で診てもらうようにしましょう。
 警察犬とは、人間より圧倒的に優れた嗅覚を訓練し、足跡追跡能力や臭気選別能力を警察の捜査活動に利用するものです。
主な仕事は、人の残した臭いを元に犯人や犯人の遺留品、行方不明者を捜索する足跡追及活動、犯人の遺留物と容疑者の臭いをかぎ分けて調べる臭気選別活動、迷子や行方不明者、遺留品などを捜索する捜索活動などがあります。
警察犬とは、人間より圧倒的に優れた嗅覚を訓練し、足跡追跡能力や臭気選別能力を警察の捜査活動に利用するものです。
主な仕事は、人の残した臭いを元に犯人や犯人の遺留品、行方不明者を捜索する足跡追及活動、犯人の遺留物と容疑者の臭いをかぎ分けて調べる臭気選別活動、迷子や行方不明者、遺留品などを捜索する捜索活動などがあります。
 警察犬には直轄警察犬と嘱託警察犬に分けられており、警察犬として公益社団法人日本警察犬協会が公式に定めている犬種は7種となっています。
警察犬には直轄警察犬と嘱託警察犬に分けられており、警察犬として公益社団法人日本警察犬協会が公式に定めている犬種は7種となっています。
 19世気後半に作出され、主にカワウソ猟に用いられてきた比較的新しいテリアで、イギリスで初めて警察犬として採用された犬種です。
家庭用として理想的な資質を持っていますが、忍耐強く温順で聡明な判断力を持つ気品があると言われています。
テリア犬種の持つ威厳とハウンドゆずりの優しさを兼ね備えた犬で、きわめて従順。
子供に対しては年齢相応に良き遊び相手となるでしょう。
強壮な体質の犬種として知られ、特にジステンパーに対する抵抗力が強いとのことです。
19世気後半に作出され、主にカワウソ猟に用いられてきた比較的新しいテリアで、イギリスで初めて警察犬として採用された犬種です。
家庭用として理想的な資質を持っていますが、忍耐強く温順で聡明な判断力を持つ気品があると言われています。
テリア犬種の持つ威厳とハウンドゆずりの優しさを兼ね備えた犬で、きわめて従順。
子供に対しては年齢相応に良き遊び相手となるでしょう。
強壮な体質の犬種として知られ、特にジステンパーに対する抵抗力が強いとのことです。
 牧羊犬として歴史の長いコリーは、その血統が管理されるようになったのが19世紀になってからと言われています。
美しい毛並みと鋭い観察眼、洞察力を持ち合わせており、警察犬に向いている犬種と言えるでしょう。
その特性から家庭犬、鑑賞犬として評価されるようになり、計画繁殖の結果、体も大型になりました。
警察犬としても活躍できますが、温和で明朗、人に対して献身的な性格をしていることから家庭犬として飼う方も増えてきていますね。
牧羊犬として歴史の長いコリーは、その血統が管理されるようになったのが19世紀になってからと言われています。
美しい毛並みと鋭い観察眼、洞察力を持ち合わせており、警察犬に向いている犬種と言えるでしょう。
その特性から家庭犬、鑑賞犬として評価されるようになり、計画繁殖の結果、体も大型になりました。
警察犬としても活躍できますが、温和で明朗、人に対して献身的な性格をしていることから家庭犬として飼う方も増えてきていますね。
 17世紀の後半から18世紀の前半にかけて、カナダのラブラドール地方に祖先犬と思われる犬種がいたと言われています。
この地方の人たちは、極寒の気象条件を克服し、厳しい風雪に耐える頑健な作業犬として使役していました。
その後、イギリスに渡って、上流階級のハンターたちが性能の向上と純粋性の維持に心血を注いだことが、今日の繁栄の基礎となったのです。
特に獲物の回収運搬が得意なためリトリーバーの名前がつけられたとのこと。
このような背景が、頑健な体質、優れた嗅覚、ダブルコールの被毛、太い毛の特徴を持つ現在のラブラドールレトリバー犬種を誕生させ、警察犬、猟犬、盲導犬としてはもちろん家庭犬としても高く評価されている犬種です。
17世紀の後半から18世紀の前半にかけて、カナダのラブラドール地方に祖先犬と思われる犬種がいたと言われています。
この地方の人たちは、極寒の気象条件を克服し、厳しい風雪に耐える頑健な作業犬として使役していました。
その後、イギリスに渡って、上流階級のハンターたちが性能の向上と純粋性の維持に心血を注いだことが、今日の繁栄の基礎となったのです。
特に獲物の回収運搬が得意なためリトリーバーの名前がつけられたとのこと。
このような背景が、頑健な体質、優れた嗅覚、ダブルコールの被毛、太い毛の特徴を持つ現在のラブラドールレトリバー犬種を誕生させ、警察犬、猟犬、盲導犬としてはもちろん家庭犬としても高く評価されている犬種です。
 警察犬=大型犬というイメージが強いですが、中には小型犬でも立派に警察犬の任務をこなしている犬種もたくさんいます。
ここでは、警察犬として小型犬がどのように活躍しているのかご紹介します。
警察犬=大型犬というイメージが強いですが、中には小型犬でも立派に警察犬の任務をこなしている犬種もたくさんいます。
ここでは、警察犬として小型犬がどのように活躍しているのかご紹介します。
 嘱託警察犬は一般の方は飼育管理するということでどんな犬種でもなれると思いがちですが、なるためには審査が必要です。
嘱託警察犬になるためには、各都道府県警察が毎年、審査会を行い、嘱託する警察犬を選考し指定されます。
試験内容は県警によって違うのですが、相当難関と言われており、こうした技術を見つけるのに専門の訓練士にお願いすることもあるのだとか。
その他にダックスフンドやトイプードルなどが採用されることもあるようです。
嘱託警察犬は一般の方は飼育管理するということでどんな犬種でもなれると思いがちですが、なるためには審査が必要です。
嘱託警察犬になるためには、各都道府県警察が毎年、審査会を行い、嘱託する警察犬を選考し指定されます。
試験内容は県警によって違うのですが、相当難関と言われており、こうした技術を見つけるのに専門の訓練士にお願いすることもあるのだとか。
その他にダックスフンドやトイプードルなどが採用されることもあるようです。
 これまでに警察犬の犬種やタイプなどをご紹介してきましたが、実際警察犬の仕事内容はどのようなものなのでしょうか。
ここでは警察犬の仕事内容についてご紹介していきます。
これまでに警察犬の犬種やタイプなどをご紹介してきましたが、実際警察犬の仕事内容はどのようなものなのでしょうか。
ここでは警察犬の仕事内容についてご紹介していきます。
 逮捕された容疑者と現場に残された証拠の匂いが一致するかを確認するための警察犬を気選別犬と言います。
匂いが一致した場合、裁判でも利用することのできる立派な証拠となるので優れた嗅覚を持った犬を選別します。
それだけ大きな役割を果たす警察犬なので、訓練は厳しいものとなるのでしょう。
逮捕された容疑者と現場に残された証拠の匂いが一致するかを確認するための警察犬を気選別犬と言います。
匂いが一致した場合、裁判でも利用することのできる立派な証拠となるので優れた嗅覚を持った犬を選別します。
それだけ大きな役割を果たす警察犬なので、訓練は厳しいものとなるのでしょう。
 映画やニュースなどでよく見かけるのが麻薬探知犬ですよね。
空港の税関などにも麻薬探知犬は多く常駐しており、麻薬を国内に持ち込ませないように見張っています。
麻薬の臭いをかぎつけたらすぐに税関職員に報告するよう訓練されています。
映画やニュースなどでよく見かけるのが麻薬探知犬ですよね。
空港の税関などにも麻薬探知犬は多く常駐しており、麻薬を国内に持ち込ませないように見張っています。
麻薬の臭いをかぎつけたらすぐに税関職員に報告するよう訓練されています。
 狂犬病という病気を知っているでしょうか。
名前からして犬の病気であると考えている人も多いですが、実は猫にも感染してしまう病気であり、哺乳類全般に感染してしまう可能性がある病気です。
そのため、猫だからと言って狂犬病にならないわけではありません。
狂犬病が感染してしまう原因は、感染している動物に噛まれるなどすることで体内にウイルスが侵入してしまうからです。
致死率は100%とも言われ、ほぼ助かる見込みもありません。
なので、猫でも感染してしまう狂犬病を犬の病気だと考えないことが重要です。
狂犬病という病気を知っているでしょうか。
名前からして犬の病気であると考えている人も多いですが、実は猫にも感染してしまう病気であり、哺乳類全般に感染してしまう可能性がある病気です。
そのため、猫だからと言って狂犬病にならないわけではありません。
狂犬病が感染してしまう原因は、感染している動物に噛まれるなどすることで体内にウイルスが侵入してしまうからです。
致死率は100%とも言われ、ほぼ助かる見込みもありません。
なので、猫でも感染してしまう狂犬病を犬の病気だと考えないことが重要です。
 猫も狂犬病に感染してしまうリスクがあることがわかれば狂犬病のワクチン接種が必要なのか気になるのではないでしょうか。
次に、猫に狂犬病のワクチン接種が必要などうかや注意点などを紹介するので、参考にしてください。
狂犬病は致死率は100%であるため、猫のことを考えるのであれば飼い主が知っておいて損をすることはありません。
猫も狂犬病に感染してしまうリスクがあることがわかれば狂犬病のワクチン接種が必要なのか気になるのではないでしょうか。
次に、猫に狂犬病のワクチン接種が必要などうかや注意点などを紹介するので、参考にしてください。
狂犬病は致死率は100%であるため、猫のことを考えるのであれば飼い主が知っておいて損をすることはありません。
 海外に猫を連れていく場合は狂犬病のワクチンを摂取することが義務付けられています。
その理由は猫が検疫対象動物に指定されているためであり、狂犬病などを広げたり、母国に持ち込まないようにするためで、飼い猫を守るためでもあります。
日本では最近狂犬病の発症事例がなく、狂犬病の危険度や知名度が下がっていますが、海外では狂犬病の発症事例は毎年のように確認されている場合もあるため、安心することはできません。
また、日本の場合は室内飼いされている猫が増えていますが、海外では放し飼いしている家庭が多く、いつ海外先で感染している動物に噛まれてしまうかわからないので必ずワクチン接種をするように心がけましょう。
海外に猫を連れていく場合は狂犬病のワクチンを摂取することが義務付けられています。
その理由は猫が検疫対象動物に指定されているためであり、狂犬病などを広げたり、母国に持ち込まないようにするためで、飼い猫を守るためでもあります。
日本では最近狂犬病の発症事例がなく、狂犬病の危険度や知名度が下がっていますが、海外では狂犬病の発症事例は毎年のように確認されている場合もあるため、安心することはできません。
また、日本の場合は室内飼いされている猫が増えていますが、海外では放し飼いしている家庭が多く、いつ海外先で感染している動物に噛まれてしまうかわからないので必ずワクチン接種をするように心がけましょう。
 万が一猫が狂犬病に感染してしまったらどのような症状があらわれてしまうのかも知っておきましょう。
あらかじめ、感染した際の症状を知っておくことで感染している疑いを持つことができ、さまざまな対策を講じることができます。
また、症状を知っていれば感染している可能性がある動物に近づくことを未然に防ぐことができ、飼い猫を守るだけではなく、飼い主自身も守ることにつながります。
次に、猫が狂犬病になった際の症状を紹介します。
万が一猫が狂犬病に感染してしまったらどのような症状があらわれてしまうのかも知っておきましょう。
あらかじめ、感染した際の症状を知っておくことで感染している疑いを持つことができ、さまざまな対策を講じることができます。
また、症状を知っていれば感染している可能性がある動物に近づくことを未然に防ぐことができ、飼い猫を守るだけではなく、飼い主自身も守ることにつながります。
次に、猫が狂犬病になった際の症状を紹介します。
 狂騒期はより攻撃的な態度になってしまう症状です。
噛み癖がない猫でも噛む回数が増えたり、鳴く回数も増えます。
そのほかにも常に動き回ったり、落ち着かない状態が続いてしまうこともあります。
この症状の時にもっとも感染を広げてしまうリスクがあるため、飼い主も気を付ける必要もあり、動物病院で診察してもらうようにしましょう。
この際にケージに入れて行動することが大切であり、動物病院のスタッフやほかの動物に噛まれないように工夫することが大切です。
狂騒期はより攻撃的な態度になってしまう症状です。
噛み癖がない猫でも噛む回数が増えたり、鳴く回数も増えます。
そのほかにも常に動き回ったり、落ち着かない状態が続いてしまうこともあります。
この症状の時にもっとも感染を広げてしまうリスクがあるため、飼い主も気を付ける必要もあり、動物病院で診察してもらうようにしましょう。
この際にケージに入れて行動することが大切であり、動物病院のスタッフやほかの動物に噛まれないように工夫することが大切です。
 狂犬病に猫が感染した場合には治療法があるのかと聞かれるとありません。
現在の医学でも狂犬病の治療法は確立されておらず、死亡率が100%である理由の一つです。
狂犬病は上記でも紹介したように犬だけではなく、猫などの哺乳類に感染してしまい、人にも感染してしまいます。
そのため、人が狂犬病に感染してしまうと同じく治療法がないため、死亡を待つしかないという残酷な病気です。
現実にも飼い犬から狂犬病に感染させられた飼い主が死亡してしまう事例が海外ではあります。
今後医療の技術が進歩すればいずれ狂犬病に対する治療法が見つけられる可能性もありますが、
現在の段階ではいかに狂犬病に感染しないようにするかが重要であり、ワクチン接種が唯一の予防方法となっています。
狂犬病に猫が感染した場合には治療法があるのかと聞かれるとありません。
現在の医学でも狂犬病の治療法は確立されておらず、死亡率が100%である理由の一つです。
狂犬病は上記でも紹介したように犬だけではなく、猫などの哺乳類に感染してしまい、人にも感染してしまいます。
そのため、人が狂犬病に感染してしまうと同じく治療法がないため、死亡を待つしかないという残酷な病気です。
現実にも飼い犬から狂犬病に感染させられた飼い主が死亡してしまう事例が海外ではあります。
今後医療の技術が進歩すればいずれ狂犬病に対する治療法が見つけられる可能性もありますが、
現在の段階ではいかに狂犬病に感染しないようにするかが重要であり、ワクチン接種が唯一の予防方法となっています。
 狂犬病は人も感染してしまうため、狂犬病に感染している猫から人に感染してしまう可能性も充分あります。
猫に噛まれることで人も狂犬病にかかり、同じく100%死亡してしまいます。
しかし、人から人に感染してしまうことはなく、空気感染してしまうこともないので、感染対象を隔離することで感染拡大を防ぐことができます。
基本的に飼育している動物に噛まれることで感染してしまったり、野生の動物に噛まれることで人に狂犬病が感染してしまう可能性が高いです。
飼い犬や猫が狂犬病に感染してしまったのであれば普段通り接することは危険であり、厚手の手袋などをつけて噛まれても問題ない状態でキャリーに入れて隔離することが大切です。
狂犬病は人も感染してしまうため、狂犬病に感染している猫から人に感染してしまう可能性も充分あります。
猫に噛まれることで人も狂犬病にかかり、同じく100%死亡してしまいます。
しかし、人から人に感染してしまうことはなく、空気感染してしまうこともないので、感染対象を隔離することで感染拡大を防ぐことができます。
基本的に飼育している動物に噛まれることで感染してしまったり、野生の動物に噛まれることで人に狂犬病が感染してしまう可能性が高いです。
飼い犬や猫が狂犬病に感染してしまったのであれば普段通り接することは危険であり、厚手の手袋などをつけて噛まれても問題ない状態でキャリーに入れて隔離することが大切です。
 干支といえば十二支です。干支には12種類の動物がいますが、なぜか猫は入っていません。
身近でペットとして人気もある猫が干支に入ってないのはなぜでしょうか?
猫が干支になれなかったいくつかの説をご紹介します。
干支といえば十二支です。干支には12種類の動物がいますが、なぜか猫は入っていません。
身近でペットとして人気もある猫が干支に入ってないのはなぜでしょうか?
猫が干支になれなかったいくつかの説をご紹介します。
 十二支や干支が作成された頃、中国では猫がまだ広く認知されておらず、あまり飼われていませんでした。
つまり馴染み深くなかったのです。
しかし、猫が人間に飼われていたのは、約4000年前の古代エジプト時代と言われており、他にも約8000年前の古代キプロスが起源という説もあります。
猫は紀元前200年ごろに中東から中国にも広まっていき、5300年前には中国で家畜として飼われていた猫の骨が見つかっています。
その頃の猫が畑の作物を食べるネズミを食べていたことが分かっており、人の近くで暮らしていたことが考えられるのです。
このことから干支ができたころでも、猫は人々と関わりあっていた可能性があります。
十二支や干支が作成された頃、中国では猫がまだ広く認知されておらず、あまり飼われていませんでした。
つまり馴染み深くなかったのです。
しかし、猫が人間に飼われていたのは、約4000年前の古代エジプト時代と言われており、他にも約8000年前の古代キプロスが起源という説もあります。
猫は紀元前200年ごろに中東から中国にも広まっていき、5300年前には中国で家畜として飼われていた猫の骨が見つかっています。
その頃の猫が畑の作物を食べるネズミを食べていたことが分かっており、人の近くで暮らしていたことが考えられるのです。
このことから干支ができたころでも、猫は人々と関わりあっていた可能性があります。
 干支は古代中国が発祥と言われています。
アジアやロシア、東ヨーロッパなどにも伝わりました。
しかし、それらの国、全てに猫年がないわけでもないのです。
ここでは猫年がある海外の国々をご紹介します。
干支は古代中国が発祥と言われています。
アジアやロシア、東ヨーロッパなどにも伝わりました。
しかし、それらの国、全てに猫年がないわけでもないのです。
ここでは猫年がある海外の国々をご紹介します。
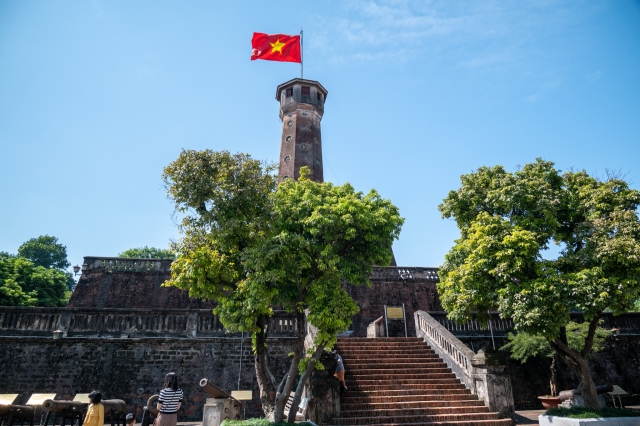 日本では「牛」となっていますが、ベトナムでは「水牛」になっています。
日本では農作業や食料の運搬には欠かせない動物ですが、ベトナムでは牛よりも身近な存在である「水牛」となりました。
また「羊」はベトナムには元々いないので、馴染みがある「ヤギ」になりました。
「猪」は「豚」になっていますが、日本では「豚」が馴染みないので、「猪」に置き換えたようです。
もともとは「豚」で、日本以外の干支のある国は全て「豚」となっています。
日本では「牛」となっていますが、ベトナムでは「水牛」になっています。
日本では農作業や食料の運搬には欠かせない動物ですが、ベトナムでは牛よりも身近な存在である「水牛」となりました。
また「羊」はベトナムには元々いないので、馴染みがある「ヤギ」になりました。
「猪」は「豚」になっていますが、日本では「豚」が馴染みないので、「猪」に置き換えたようです。
もともとは「豚」で、日本以外の干支のある国は全て「豚」となっています。
 ブルガリアとは異なり、モンゴルやトルコでは虎年は猫年ではなく、豹年に変わります。
モンゴルの山間部には「ユキヒョウ」という白い豹が生息する地域があることも関係しているのでしょう。
ブルガリアとは異なり、モンゴルやトルコでは虎年は猫年ではなく、豹年に変わります。
モンゴルの山間部には「ユキヒョウ」という白い豹が生息する地域があることも関係しているのでしょう。
 散歩での引っ張り癖で悩んでいる飼い主が多いです。
犬がリードを引っ張って歩くことは体に負担をかけていますし、トラブルの原因になることもあります。
リーダーウォークを身につけてリラックスした散歩ができるようにしたいものです。
リーダーウォークとは、飼い主がリーダーとして率先して歩くことです。
歩くスピードや行く先は飼い主が決め、飼い主が止まると犬も止まり、座れと命令されたら座ります。
リーダーウォークができるようになると、生活の様々な場面でとても役立ちますのでぜひ覚えてください。
散歩での引っ張り癖で悩んでいる飼い主が多いです。
犬がリードを引っ張って歩くことは体に負担をかけていますし、トラブルの原因になることもあります。
リーダーウォークを身につけてリラックスした散歩ができるようにしたいものです。
リーダーウォークとは、飼い主がリーダーとして率先して歩くことです。
歩くスピードや行く先は飼い主が決め、飼い主が止まると犬も止まり、座れと命令されたら座ります。
リーダーウォークができるようになると、生活の様々な場面でとても役立ちますのでぜひ覚えてください。
 リーダーウォークは、犬が人よりも前に出ないで歩き、常に飼い主を意識することが必要です。
教え方としては次のステップを繰り返して教えます。
1,まずリードをたるませた状態で犬を左横につけて歩かせます。
2,犬が自分よりも前に行こうとした時に、無言でターンをして反対方向に進みます。
ターンはその場で180°クルッと回ります。
左ターンと右ターンの両方をして、犬に多少ぶつかっても気にせずに回ります。
犬が人よりも先に行きたい方向に進もうとすると、必ず反対方向に人が向くということを繰り返して行うことで、飼い主を意識するようになってきます。
飼い主を意識し、動きに注意することで前に出て引っ張って歩かなくなります。
リーダーウォークは、犬が人よりも前に出ないで歩き、常に飼い主を意識することが必要です。
教え方としては次のステップを繰り返して教えます。
1,まずリードをたるませた状態で犬を左横につけて歩かせます。
2,犬が自分よりも前に行こうとした時に、無言でターンをして反対方向に進みます。
ターンはその場で180°クルッと回ります。
左ターンと右ターンの両方をして、犬に多少ぶつかっても気にせずに回ります。
犬が人よりも先に行きたい方向に進もうとすると、必ず反対方向に人が向くということを繰り返して行うことで、飼い主を意識するようになってきます。
飼い主を意識し、動きに注意することで前に出て引っ張って歩かなくなります。
 リーダーウォークをすることは犬と飼い主との信頼に繋がります。
時間はかかりますが、少しずつ散歩のたびに練習しましょう。
犬は言葉がわかりませんが、ゆっくりでも必ず伝わっていきます。
できるようになると、リラックスした散歩が楽しめますので、次の教えるコツを参考にしてください。
リーダーウォークをすることは犬と飼い主との信頼に繋がります。
時間はかかりますが、少しずつ散歩のたびに練習しましょう。
犬は言葉がわかりませんが、ゆっくりでも必ず伝わっていきます。
できるようになると、リラックスした散歩が楽しめますので、次の教えるコツを参考にしてください。
 リーダーウォークはリードがいつも緩んだ状態で犬が歩くことです。
引っ張って歩く犬にリードが緩むと良いことがあるのだと発見させ、そのメリットを強く認識させるようにします。
大好きなおやつを用意し、リードが緩んだらすぐに褒めておやつをあげます。
またすぐにリードが張ってしまうかもしれませんが、名前を呼んで誘導し、緩んだらおやつがもらえるということを理解させます。
何度も繰り返して行ってください。
リーダーウォークはリードがいつも緩んだ状態で犬が歩くことです。
引っ張って歩く犬にリードが緩むと良いことがあるのだと発見させ、そのメリットを強く認識させるようにします。
大好きなおやつを用意し、リードが緩んだらすぐに褒めておやつをあげます。
またすぐにリードが張ってしまうかもしれませんが、名前を呼んで誘導し、緩んだらおやつがもらえるということを理解させます。
何度も繰り返して行ってください。
 子犬の頃からリーダーウォークを身に付けさせるのが一番良いですが、いろいろな事情で成犬から飼うことになったり、コントロールできないままで大きくなってしまうことがあります。
成犬の場合も基本的な教え方は同じですが、効果が現れずくじけてしまう飼い主も多いです。
その場合、成犬には補助器具を用いてリーダーウォークを教えるのも手です。
補助器具にはイージーウォークハーネスやジェントルリーダーなどがあり、正しく使うことが必須となります。
使い方が分からない場合や対処が難しい犬にはプロであるドッグトレーナーに相談し、一緒に指導していくことをおすすめします。
子犬の頃からリーダーウォークを身に付けさせるのが一番良いですが、いろいろな事情で成犬から飼うことになったり、コントロールできないままで大きくなってしまうことがあります。
成犬の場合も基本的な教え方は同じですが、効果が現れずくじけてしまう飼い主も多いです。
その場合、成犬には補助器具を用いてリーダーウォークを教えるのも手です。
補助器具にはイージーウォークハーネスやジェントルリーダーなどがあり、正しく使うことが必須となります。
使い方が分からない場合や対処が難しい犬にはプロであるドッグトレーナーに相談し、一緒に指導していくことをおすすめします。
 犬にとって、外の世界は近づいてくる人や犬、いろいろな臭いや音など刺激的なものであふれています。
興奮や警戒心が高ければ、飼い主のことは完全に忘れているかもしれません。
そんな時にこそトラブルは起こりやすく、飼い主にとっても散歩が苦痛になる人もいます。
でも、リーダーウォークができれば飼い主の存在を意識しつつ、リラックスして歩けるようになります。
その必要性を具体的に解説していきましょう。
犬にとって、外の世界は近づいてくる人や犬、いろいろな臭いや音など刺激的なものであふれています。
興奮や警戒心が高ければ、飼い主のことは完全に忘れているかもしれません。
そんな時にこそトラブルは起こりやすく、飼い主にとっても散歩が苦痛になる人もいます。
でも、リーダーウォークができれば飼い主の存在を意識しつつ、リラックスして歩けるようになります。
その必要性を具体的に解説していきましょう。
 犬を常に左側について歩かせることで、左側通行の車から守りやすくなります。
急に人や自転車などが現れた時にもすぐに飼い主が指示を出して待たせたり座らせたりできます。
つまり何か危険が迫った時には、いつでも飼い主の指示を守れることが犬の安全を守ることにつながるのです。
また、リーダーウォークが身についている犬は飼い主の存在を意識しながら余裕を持って歩くため、すれ違う犬や人にも興奮せずに穏やかでいられるでしょう。
犬を常に左側について歩かせることで、左側通行の車から守りやすくなります。
急に人や自転車などが現れた時にもすぐに飼い主が指示を出して待たせたり座らせたりできます。
つまり何か危険が迫った時には、いつでも飼い主の指示を守れることが犬の安全を守ることにつながるのです。
また、リーダーウォークが身についている犬は飼い主の存在を意識しながら余裕を持って歩くため、すれ違う犬や人にも興奮せずに穏やかでいられるでしょう。
 リーダーウォークはリードが緩んでいる状態で、犬の体が前のめりになっていません。
周囲への反応も興奮度が低く落ち着いた状態です。
そのような状態は犬の負担も減るので、心に余裕が生まれます。
興奮状態になりにくいので、命令にも耳を傾けやすくなります。
つまり心のバランスが安定し、ゆったりとした気持ちで散歩を楽しめるわけです。
犬が安定していると、飼い主ももちろん穏やかな気持ちでいられます。
お互いに信頼し合った理想的な関係と言えるでしょう。
リーダーウォークはリードが緩んでいる状態で、犬の体が前のめりになっていません。
周囲への反応も興奮度が低く落ち着いた状態です。
そのような状態は犬の負担も減るので、心に余裕が生まれます。
興奮状態になりにくいので、命令にも耳を傾けやすくなります。
つまり心のバランスが安定し、ゆったりとした気持ちで散歩を楽しめるわけです。
犬が安定していると、飼い主ももちろん穏やかな気持ちでいられます。
お互いに信頼し合った理想的な関係と言えるでしょう。
 犬のマラセチアという病気を知っているでしょうか。
犬の皮膚には元々カビの一種でもある真菌が存在しており、正常であれば特に問題ありませんが、なにかしらの原因で異常発生してしまうとさまざまな症状が出てきてしまいます。
マラセチアの症状は手足の先や股・脇・首回りなどに症状が出やすい特徴があり、夏場になると発症しやすく、悪化もしやすいです。
犬種によっても発症してしまう可能性に差はありますが、原因を把握して適切な治療を受ければ完治することができる病気でもあります。
犬のマラセチアという病気を知っているでしょうか。
犬の皮膚には元々カビの一種でもある真菌が存在しており、正常であれば特に問題ありませんが、なにかしらの原因で異常発生してしまうとさまざまな症状が出てきてしまいます。
マラセチアの症状は手足の先や股・脇・首回りなどに症状が出やすい特徴があり、夏場になると発症しやすく、悪化もしやすいです。
犬種によっても発症してしまう可能性に差はありますが、原因を把握して適切な治療を受ければ完治することができる病気でもあります。
 愛犬がマラセチアになっているかどうかを知るためには症状を理解しておくことが重要になります。
マラセチアの症状は皮膚が赤くなるため、普段から皮膚のチェックをしていれば早期発見することも可能です。
そのほかにはフケが多くなったり、べたつきや痒みの症状もあらわれるようになります。
また、独特のにおいが出る特徴もあるため、普段嗅いだことのないにおいをしているのであれば念入りに皮膚の確認をしましょう。
爪付近のマラセチアの症状が悪化してしまうと爪が黒く変色してしまうような症状もあります。
愛犬がマラセチアになっているかどうかを知るためには症状を理解しておくことが重要になります。
マラセチアの症状は皮膚が赤くなるため、普段から皮膚のチェックをしていれば早期発見することも可能です。
そのほかにはフケが多くなったり、べたつきや痒みの症状もあらわれるようになります。
また、独特のにおいが出る特徴もあるため、普段嗅いだことのないにおいをしているのであれば念入りに皮膚の確認をしましょう。
爪付近のマラセチアの症状が悪化してしまうと爪が黒く変色してしまうような症状もあります。
 マラセチアになってしまう原因は解明されているので、原因を改善することでマラセチアを予防したり、症状が悪化してしまうことも防ぎます。
マラセチアの原因は加齢や住む環境が変わったたことなどです。
そのほかにも栄養バランスの乱れが関係している場合もあるため、愛犬がマラセチアになってしまったのであれば一つずつ原因を改善していくようにしましょう。
マラセチアはカビが異常増殖することが原因であるため、菌が増殖してしまう原因を理解すればマラセチアの原因と関連していることが多いです。
例えば菌はしまった環境を好むため、皮脂が多く分泌されていたり、スキンケアが不十分であることもマラセチアの原因となります。
皮脂や汚れは皮膚と皮膚がこすれ合う部分に溜まりやすいため、マラセチアもそのような部位で発症することが多いです。
マラセチアになってしまう原因は解明されているので、原因を改善することでマラセチアを予防したり、症状が悪化してしまうことも防ぎます。
マラセチアの原因は加齢や住む環境が変わったたことなどです。
そのほかにも栄養バランスの乱れが関係している場合もあるため、愛犬がマラセチアになってしまったのであれば一つずつ原因を改善していくようにしましょう。
マラセチアはカビが異常増殖することが原因であるため、菌が増殖してしまう原因を理解すればマラセチアの原因と関連していることが多いです。
例えば菌はしまった環境を好むため、皮脂が多く分泌されていたり、スキンケアが不十分であることもマラセチアの原因となります。
皮脂や汚れは皮膚と皮膚がこすれ合う部分に溜まりやすいため、マラセチアもそのような部位で発症することが多いです。
 マラセチア菌は健康な犬の皮膚にも存在しており、マラセチアの症状が出てしまう原因は過度に増殖することであるため、シャンプーや食事を工夫すれば予防することが期待できます。
シャンプーで皮膚の汚れや皮脂をしっかりとることで菌が栄養とするものがなくなるため、増殖することを防ぎます。
食事は脂分が少ない物を与えるようにすれば皮脂の分泌を軽減することができ、マラセチア予防としての効果もあります。
対策さえしっかりしておけば高い確率でマラセチアを予防することができ、飼い主がしっかり注意して健康管理を行うようにしましょう。
マラセチア菌は健康な犬の皮膚にも存在しており、マラセチアの症状が出てしまう原因は過度に増殖することであるため、シャンプーや食事を工夫すれば予防することが期待できます。
シャンプーで皮膚の汚れや皮脂をしっかりとることで菌が栄養とするものがなくなるため、増殖することを防ぎます。
食事は脂分が少ない物を与えるようにすれば皮脂の分泌を軽減することができ、マラセチア予防としての効果もあります。
対策さえしっかりしておけば高い確率でマラセチアを予防することができ、飼い主がしっかり注意して健康管理を行うようにしましょう。
 マラセチアの症状が出てしまっても適切な治療法を行うことで完治することができます。
飼い主が工夫すれば症状が改善される場合もありますが、一度マラセチアを発症してしまったのであれば病院で治療を受けるようにしましょう。
次に、マラセチアの治療方法を紹介するので参考にしてください。
マラセチアの症状が出てしまっても適切な治療法を行うことで完治することができます。
飼い主が工夫すれば症状が改善される場合もありますが、一度マラセチアを発症してしまったのであれば病院で治療を受けるようにしましょう。
次に、マラセチアの治療方法を紹介するので参考にしてください。
 塗り薬での治療は、マラセチアの症状が出ている場所に直接薬を塗る方法です。
マラセチアの治療法の中でも一番簡単な治療法となっています。
上記で紹介した飲み薬での治療法には副作用が出てしまう可能性がありますが、塗り薬の場合は全身に副作用が起きてしまうことがなく、安心して塗布することが可能です。
しかし、マラセチアの症状が出ている部分が広範囲であれば塗布することに時間がかかってしまうことや塗布した後にすぐに舐めてしまう可能性がある欠点があります。
すぐに舐めてしまう場合は食後に塗布したり、塗布した後に遊んであげて舐めさせないようにしましょう。
塗り薬での治療は、マラセチアの症状が出ている場所に直接薬を塗る方法です。
マラセチアの治療法の中でも一番簡単な治療法となっています。
上記で紹介した飲み薬での治療法には副作用が出てしまう可能性がありますが、塗り薬の場合は全身に副作用が起きてしまうことがなく、安心して塗布することが可能です。
しかし、マラセチアの症状が出ている部分が広範囲であれば塗布することに時間がかかってしまうことや塗布した後にすぐに舐めてしまう可能性がある欠点があります。
すぐに舐めてしまう場合は食後に塗布したり、塗布した後に遊んであげて舐めさせないようにしましょう。
 一般的に上記で紹介した3つの治療法をすれば症状を抑えることができたり、完治させることができます。
しかし、3つの治療法すべてを試してみても症状が改善されない場合は、基礎疾患が関係している可能性があります。
基礎疾患が原因でマラセチアになってしまっているのであれば根本的原因でもある基礎疾患を直さなければすぐにマラセチアを誘発させてしまいます。
素人ではなかなか基礎疾患を把握することは難しいので動物病院で基礎疾患の有無の確認や治療をするようにしましょう。
一般的に上記で紹介した3つの治療法をすれば症状を抑えることができたり、完治させることができます。
しかし、3つの治療法すべてを試してみても症状が改善されない場合は、基礎疾患が関係している可能性があります。
基礎疾患が原因でマラセチアになってしまっているのであれば根本的原因でもある基礎疾患を直さなければすぐにマラセチアを誘発させてしまいます。
素人ではなかなか基礎疾患を把握することは難しいので動物病院で基礎疾患の有無の確認や治療をするようにしましょう。
 ペットが好きな人であればペットショップの店員になりたいと考えている人もいるのではないでしょうか。
ペットショップの店員になるためには専門のスキルがなければ就職できないと考えてしまうことも多いですが、学歴や資格などは求められない傾向があります。
ただし、専門学校などを卒業していたり、資格を有しているのであれば即戦力となり得るので採用される可能性は高いです。
資格や学歴がない場合でも面接を通過することができればアルバイトから始めることができます。
そのため、ペットショップ店員になりたいのであれば、求人情報から探し、応募するようにしましょう。
最初はアルバイトでも経験を積んでいけばいずれ正社員となれる場合もあります。
ペットが好きな人であればペットショップの店員になりたいと考えている人もいるのではないでしょうか。
ペットショップの店員になるためには専門のスキルがなければ就職できないと考えてしまうことも多いですが、学歴や資格などは求められない傾向があります。
ただし、専門学校などを卒業していたり、資格を有しているのであれば即戦力となり得るので採用される可能性は高いです。
資格や学歴がない場合でも面接を通過することができればアルバイトから始めることができます。
そのため、ペットショップ店員になりたいのであれば、求人情報から探し、応募するようにしましょう。
最初はアルバイトでも経験を積んでいけばいずれ正社員となれる場合もあります。
 元々ペット関係の仕事をしたいと考えていればある程度ペットショップ店員の仕事内容を把握していることもありますが、まったく知識や学歴もない人であれば詳しい仕事内容まで知ることは難しいです。
次に、ペットショップ店員の仕事内容を紹介します。
あらかじめ仕事内容を把握していれば自分にあっているのかどうかを確認することもできます。
元々ペット関係の仕事をしたいと考えていればある程度ペットショップ店員の仕事内容を把握していることもありますが、まったく知識や学歴もない人であれば詳しい仕事内容まで知ることは難しいです。
次に、ペットショップ店員の仕事内容を紹介します。
あらかじめ仕事内容を把握していれば自分にあっているのかどうかを確認することもできます。
 ペットは当然生き物であるため、生体管理をしなければなりません。
食材や物などとは違い、品棚に並べていればよいだけではなく、些細な体調不良などにもいち早く築いたり、ストレスなどを与えないようにしなければなりません。
ペットショップの店員のメインの仕事はペットを販売することですが、生体管理をすることのほうが重要度は高いです。
生体管理をするためにはこまめに体調をチェックすることは当然ですが、知識も求められる仕事内容になります。
ペットの種類によって体調不良時にあらわれる症状は違うので、知識と経験がものをいう仕事内容です。
体調不良を見逃してしまい、死亡してしまった場合はペットショップの損害となってしまうため、最も神経をとがらせる仕事内容でもあります。
ペットは当然生き物であるため、生体管理をしなければなりません。
食材や物などとは違い、品棚に並べていればよいだけではなく、些細な体調不良などにもいち早く築いたり、ストレスなどを与えないようにしなければなりません。
ペットショップの店員のメインの仕事はペットを販売することですが、生体管理をすることのほうが重要度は高いです。
生体管理をするためにはこまめに体調をチェックすることは当然ですが、知識も求められる仕事内容になります。
ペットの種類によって体調不良時にあらわれる症状は違うので、知識と経験がものをいう仕事内容です。
体調不良を見逃してしまい、死亡してしまった場合はペットショップの損害となってしまうため、最も神経をとがらせる仕事内容でもあります。
 ペットショップ店員以外でも仕事内容に含まれている場合が多いのが清掃作業です。
ほかの職種でも清掃はほぼ仕事内容に含まれています。
しかし、ペットショップ店員の場合は店内の清掃はもちろんですが、ペットを入れているケースや糞尿なども掃除しなければなりません。
店内が汚れていたり、ペットが飼われている環境が汚れているとどんなに人気で可愛らしいペットを販売していても印象が悪くなり、客足が遠のいてしまいます。
ペットの糞尿の掃除に抵抗感を覚えてしまう人もいますが、ペットショップ店員になるのであれば必ずしなければならない仕事であるため、生理的に無理と感じてしまう人はペット関係の仕事に就くことは難しいです。
糞尿は1日に何回も行う生理現象であるため、1日数回掃除しなければならないことを覚悟しておきましょう。
ペットショップ店員以外でも仕事内容に含まれている場合が多いのが清掃作業です。
ほかの職種でも清掃はほぼ仕事内容に含まれています。
しかし、ペットショップ店員の場合は店内の清掃はもちろんですが、ペットを入れているケースや糞尿なども掃除しなければなりません。
店内が汚れていたり、ペットが飼われている環境が汚れているとどんなに人気で可愛らしいペットを販売していても印象が悪くなり、客足が遠のいてしまいます。
ペットの糞尿の掃除に抵抗感を覚えてしまう人もいますが、ペットショップ店員になるのであれば必ずしなければならない仕事であるため、生理的に無理と感じてしまう人はペット関係の仕事に就くことは難しいです。
糞尿は1日に何回も行う生理現象であるため、1日数回掃除しなければならないことを覚悟しておきましょう。
 上記ではペットショップ店員には特別なスキルは必要ないと紹介しましたが、あれば有利になるスキルはあります。
次に、ペットショップ店員におすすめのスキルを紹介します。
資格などではなく、考え方や意欲などに関係することでもあるので、すでにクリアしている場合も少なくありません。
上記ではペットショップ店員には特別なスキルは必要ないと紹介しましたが、あれば有利になるスキルはあります。
次に、ペットショップ店員におすすめのスキルを紹介します。
資格などではなく、考え方や意欲などに関係することでもあるので、すでにクリアしている場合も少なくありません。
 ペットショップ店員はペットのお世話や健康管理をする必要があります。
世話をするにも健康管理をするにしても知識や技術が必要となってきます。
同僚や先輩などから教えてもらうことが一般的ではありますが、そもそもお世話や健康管理に興味がなければ中々身に付きません。
何事にも興味がないことを覚えることは難しく、ペット関係の仕事に向いていない可能性も出てきます。
ペットの世話の仕方や健康の異常の上場はペットごとに変わってくるので、幅広い知識が求められます。
例えば他のペットショップ店員が気づけないような微細な異常に気づくことができれば症状が悪化してしまうことを防ぐことができ、ペットを助けることができることはもちろんですが、上司などから評価もされます。
ペットショップ店員はペットのお世話や健康管理をする必要があります。
世話をするにも健康管理をするにしても知識や技術が必要となってきます。
同僚や先輩などから教えてもらうことが一般的ではありますが、そもそもお世話や健康管理に興味がなければ中々身に付きません。
何事にも興味がないことを覚えることは難しく、ペット関係の仕事に向いていない可能性も出てきます。
ペットの世話の仕方や健康の異常の上場はペットごとに変わってくるので、幅広い知識が求められます。
例えば他のペットショップ店員が気づけないような微細な異常に気づくことができれば症状が悪化してしまうことを防ぐことができ、ペットを助けることができることはもちろんですが、上司などから評価もされます。
 ペットショップ店員に向いている人もいれば向いていない人もいます。
そのため、ペットショップ店員になるために行動する前に自分が向いているのか向いていないのかを確認しましょう。
もし、向いていないのであれば違う仕事にしたほうが無難かもしれません。
次に、ペットショップ店員に向いている人の特徴を紹介するので参考にしてください。
ペットショップ店員に向いている人もいれば向いていない人もいます。
そのため、ペットショップ店員になるために行動する前に自分が向いているのか向いていないのかを確認しましょう。
もし、向いていないのであれば違う仕事にしたほうが無難かもしれません。
次に、ペットショップ店員に向いている人の特徴を紹介するので参考にしてください。
 ペットショップ店員は粘り強く忍耐力がある人がおすすめです。
上記で紹介したように肉体的・精神的にハードな仕事内容であるため、精神的や体力的に自信があり、耐えられる力がなければ途中で挫折してしまう可能性があります。
また、動物の管理や世話をする際には少しでも意思疎通ができることが求められます。
しかし、動物とは言葉で気持ちを伝えることが難しく、長い時間をかけて信頼関係を築き、意思疎通ができるようになります。
そのため、意思疎通することができずイライラしてしまう人は向いていません。
ペットショップ店員は粘り強く忍耐力がある人がおすすめです。
上記で紹介したように肉体的・精神的にハードな仕事内容であるため、精神的や体力的に自信があり、耐えられる力がなければ途中で挫折してしまう可能性があります。
また、動物の管理や世話をする際には少しでも意思疎通ができることが求められます。
しかし、動物とは言葉で気持ちを伝えることが難しく、長い時間をかけて信頼関係を築き、意思疎通ができるようになります。
そのため、意思疎通することができずイライラしてしまう人は向いていません。
 皆さんは、忠犬ハチ公をご存知でしょうか。
渋谷駅前にある銅像のモデルとなった秋田犬のハチは、主人との深い繋がりと信頼関係で結ばれた存在として広く海外にもファンがいます。
飼い主が亡き後も変わらずに、自分を可愛がってくれた飼い主の帰りを渋谷駅で待ち続けました。
健気なハチの存在は、当時の様子を知る人達はもちろん全国にまで広がり多くの感動と感銘を与え、渋谷駅を始めゆかりのある地域や建物にはハチ公像や飼い主であった上野博士と嬉しそうにはしゃぐハチ公像が建てられています。
ハチの犬種や生涯をご紹介していきます。
皆さんは、忠犬ハチ公をご存知でしょうか。
渋谷駅前にある銅像のモデルとなった秋田犬のハチは、主人との深い繋がりと信頼関係で結ばれた存在として広く海外にもファンがいます。
飼い主が亡き後も変わらずに、自分を可愛がってくれた飼い主の帰りを渋谷駅で待ち続けました。
健気なハチの存在は、当時の様子を知る人達はもちろん全国にまで広がり多くの感動と感銘を与え、渋谷駅を始めゆかりのある地域や建物にはハチ公像や飼い主であった上野博士と嬉しそうにはしゃぐハチ公像が建てられています。
ハチの犬種や生涯をご紹介していきます。
 秋田犬は、日本犬の中で唯一の大型犬として登録されています。
大型犬であるがゆえに、育てる環境を整え適切なしつけを行う必要があり誰でも飼いやすい犬種ではありません。
あまり見かけることも少ない秋田犬の特徴や性格についてご説明していきます。
秋田犬は、日本犬の中で唯一の大型犬として登録されています。
大型犬であるがゆえに、育てる環境を整え適切なしつけを行う必要があり誰でも飼いやすい犬種ではありません。
あまり見かけることも少ない秋田犬の特徴や性格についてご説明していきます。
 秋田犬は、飼い主と認めた人に対して従順で穏やかな性格といわれています。
その一方で、初対面の人や犬に対して警戒心を抱きやすく、攻撃的な面も持ち合わせています。
認めた飼い主以外への反応としては賢いがゆえとも言えますが、パピー期のころからしっかりとしつけを行わないと誰の言うことも聞かなくなりますので、家族に迎えるには覚悟と経験も必要となるでしょう。
また番犬としての活躍も期待されますが、近年では周囲の環境や人との良好な関わりを大切にしたほうが現実的かもしれません。
(駄目なこと・良いこと)の指示が伝わる信頼関係を築ければ、頭が良くて優しい頼もしいパートナーとなってくれます。
秋田犬は、飼い主と認めた人に対して従順で穏やかな性格といわれています。
その一方で、初対面の人や犬に対して警戒心を抱きやすく、攻撃的な面も持ち合わせています。
認めた飼い主以外への反応としては賢いがゆえとも言えますが、パピー期のころからしっかりとしつけを行わないと誰の言うことも聞かなくなりますので、家族に迎えるには覚悟と経験も必要となるでしょう。
また番犬としての活躍も期待されますが、近年では周囲の環境や人との良好な関わりを大切にしたほうが現実的かもしれません。
(駄目なこと・良いこと)の指示が伝わる信頼関係を築ければ、頭が良くて優しい頼もしいパートナーとなってくれます。
 みなさん、何も疑問を感じずに(忠犬)という言葉を使ってるかもしれません。
渋谷に銅像として佇む実際のハチは、忠犬という言葉に全く違和感のない行動と愛情を見せてくれた犬ではないでしょうか。
ここでは、そんな忠犬ハチ公の生涯をご紹介していきます。
みなさん、何も疑問を感じずに(忠犬)という言葉を使ってるかもしれません。
渋谷に銅像として佇む実際のハチは、忠犬という言葉に全く違和感のない行動と愛情を見せてくれた犬ではないでしょうか。
ここでは、そんな忠犬ハチ公の生涯をご紹介していきます。
 幸せな每日が続いていましたが、ある朝同じように上野教授を見送った後に自宅に戻ったハチは、何かを感じ悲しげな声で鳴き始めました。
大学で教鞭を取っていた教授が突然倒れ、そのまま帰らぬ人となったのです。
妻と二人暮らしだった上野教授の自宅は売りに出され、妻は故郷へハチは知り合いの家へと新たな生活を始めます。
ですがハチは預けられた家を度々脱走し、可愛がってくれた上野教授の送り迎えのために每日決まった時間に渋谷駅へと向かいます。
いつしか住むところも失い、渋谷駅の周辺で野良犬のような暮らしが続いたある日、新聞記者の目にとまり全国にハチが紹介されることになりました。
その記事は上野博士の妻の目にも入り、心配した妻は上京しハチは懐かしい人と再会を果たします。
それがかつて幸せだったころの思い出を呼び起こす最後の対面となりました。
昭和10年3月8日、大好きな上野教授にひと目会いたいと願いながらハチはその生涯を閉じます。
幸せな每日が続いていましたが、ある朝同じように上野教授を見送った後に自宅に戻ったハチは、何かを感じ悲しげな声で鳴き始めました。
大学で教鞭を取っていた教授が突然倒れ、そのまま帰らぬ人となったのです。
妻と二人暮らしだった上野教授の自宅は売りに出され、妻は故郷へハチは知り合いの家へと新たな生活を始めます。
ですがハチは預けられた家を度々脱走し、可愛がってくれた上野教授の送り迎えのために每日決まった時間に渋谷駅へと向かいます。
いつしか住むところも失い、渋谷駅の周辺で野良犬のような暮らしが続いたある日、新聞記者の目にとまり全国にハチが紹介されることになりました。
その記事は上野博士の妻の目にも入り、心配した妻は上京しハチは懐かしい人と再会を果たします。
それがかつて幸せだったころの思い出を呼び起こす最後の対面となりました。
昭和10年3月8日、大好きな上野教授にひと目会いたいと願いながらハチはその生涯を閉じます。
 ハチは死後、現・東京大学で病理解剖が行われ心臓や肝臓にフィラリアの寄生を確認しています。
さらに胃の中から焼き鳥の串も発見され、当時の渋谷駅周辺の屋台で与えられた焼き鳥だった可能性もあります。
これらの要因から、犬にとって今も恐い病気のひとつであるフィラリアと串による消化器官の損傷が死因とされました。
ですが近年になって、その考えが大きく覆されました。
ハチの内臓を保管している東京大学は、2011年にMRIなど最新技術によって再度細かく検査を行ったところ、心臓と肺に大きなガンがあったことが判明しました。
よってハチの死因はおそらくガンであったのではないかと考えられています。
ハチは死後、現・東京大学で病理解剖が行われ心臓や肝臓にフィラリアの寄生を確認しています。
さらに胃の中から焼き鳥の串も発見され、当時の渋谷駅周辺の屋台で与えられた焼き鳥だった可能性もあります。
これらの要因から、犬にとって今も恐い病気のひとつであるフィラリアと串による消化器官の損傷が死因とされました。
ですが近年になって、その考えが大きく覆されました。
ハチの内臓を保管している東京大学は、2011年にMRIなど最新技術によって再度細かく検査を行ったところ、心臓と肺に大きなガンがあったことが判明しました。
よってハチの死因はおそらくガンであったのではないかと考えられています。
 皆さんはトリーツをご存知でしょうか。
愛犬が正しく指示に従ったりお留守番をしっかりできたりしたときに与えるものです。
ですが、おやつとトリーツが混同してしまっている場合があるかもしれません。
「おやつのことを言うんじゃないの?」と感じる飼い主様も多いはず。
犬のトリーツとおやつの違いと与え方についてご紹介していきます。
皆さんはトリーツをご存知でしょうか。
愛犬が正しく指示に従ったりお留守番をしっかりできたりしたときに与えるものです。
ですが、おやつとトリーツが混同してしまっている場合があるかもしれません。
「おやつのことを言うんじゃないの?」と感じる飼い主様も多いはず。
犬のトリーツとおやつの違いと与え方についてご紹介していきます。
 では、おやつはどんな意味を持つ言葉なのでしょう。
漢字で書くと「御八つ」という字になり、はるか昔の江戸時代から習慣となった午後3時(八つ時)の間食が元になっています。
つまりおやつは間食の意味を持ち、特に良いことや指示に従ったから与えるといった動機はないものと考えられています。
愛犬に何か与えるときは、ご飯とおやつの2つに分けられていることが多く、実際にしつけに使用するトリーツは愛犬が喜ぶものや大好きなものであれば、おやつを与えても問題はありません。
では、おやつはどんな意味を持つ言葉なのでしょう。
漢字で書くと「御八つ」という字になり、はるか昔の江戸時代から習慣となった午後3時(八つ時)の間食が元になっています。
つまりおやつは間食の意味を持ち、特に良いことや指示に従ったから与えるといった動機はないものと考えられています。
愛犬に何か与えるときは、ご飯とおやつの2つに分けられていることが多く、実際にしつけに使用するトリーツは愛犬が喜ぶものや大好きなものであれば、おやつを与えても問題はありません。
 では、トリーツを与えるタイミングはいつが良いのでしょうか。
ご褒美は愛犬にとってとても嬉しく、飼い主様との信頼関係を築くことにも役立ちます。
注意点を守って愛犬とより親密な関係性を築いていきましょう。
では、トリーツを与えるタイミングはいつが良いのでしょうか。
ご褒美は愛犬にとってとても嬉しく、飼い主様との信頼関係を築くことにも役立ちます。
注意点を守って愛犬とより親密な関係性を築いていきましょう。
 玄関のチャイム吠えでお困りの飼い主様は多いかもしれません。
そんなとき、トリーツで犬を大人しくさせる使い方をしていませんか。
吠えた愛犬に対して、先にトリーツを与えて静かにさせても、犬は吠えたらおやつがもらえたと勘違いしてしまいます。
まず愛犬を落ち着かせるためにおすわりやハウスなど簡単な指示で静かにさせましょう。
最初は言うことを聞かずに、玄関に走っていくかもしれませんが少しづつ根気よく続けていくことが大切です。
少しでも静かに出来たらトリーツを与えましょう。
時間を徐々に伸ばしていくことで、例え吠えたとしてもすぐに静かに落ち着いた状態を保つことができるようになります。
ですので、トリーツは静かにさせるためのおやつではなく静かにできたことへのご褒美として利用しましょう。
玄関のチャイム吠えでお困りの飼い主様は多いかもしれません。
そんなとき、トリーツで犬を大人しくさせる使い方をしていませんか。
吠えた愛犬に対して、先にトリーツを与えて静かにさせても、犬は吠えたらおやつがもらえたと勘違いしてしまいます。
まず愛犬を落ち着かせるためにおすわりやハウスなど簡単な指示で静かにさせましょう。
最初は言うことを聞かずに、玄関に走っていくかもしれませんが少しづつ根気よく続けていくことが大切です。
少しでも静かに出来たらトリーツを与えましょう。
時間を徐々に伸ばしていくことで、例え吠えたとしてもすぐに静かに落ち着いた状態を保つことができるようになります。
ですので、トリーツは静かにさせるためのおやつではなく静かにできたことへのご褒美として利用しましょう。
 時間を置かずにすぐ与えられるように、飼い主様が扱いやすく愛犬がぺろっと食べられる大きさが大切です。
愛犬の体の大きさに関わらず、ごく少量で大きさにすると数ミリ程度でしょうか。
何粒もまとめて与えるのではなく、一粒ずつ与えましょう。
あくまでご褒美ですので、食べごたえや長持ちするような大きさは必要ありません。
すぐに与えられるように、飼い主様は取り出しやすい専用ポーチにトリーツを入れて腰に付けておくと、とても便利です。
時間を置かずにすぐ与えられるように、飼い主様が扱いやすく愛犬がぺろっと食べられる大きさが大切です。
愛犬の体の大きさに関わらず、ごく少量で大きさにすると数ミリ程度でしょうか。
何粒もまとめて与えるのではなく、一粒ずつ与えましょう。
あくまでご褒美ですので、食べごたえや長持ちするような大きさは必要ありません。
すぐに与えられるように、飼い主様は取り出しやすい専用ポーチにトリーツを入れて腰に付けておくと、とても便利です。
 トリーツはご褒美だということをご説明してきましたが、食べ物である必要はありません。
愛犬が好きなもの・喜ぶものであれば、おもちゃやボールといった遊ぶものでもトリーツになります。
犬によっては、食べ物にあまり興味を持たないコもいますので飼い主様が愛犬の喜ぶものを把握し、トリーツとして利用してください。
ドッグフードが大好きなコなら、フードを何粒も用意してあげれば喜びます。
犬の個性や好き嫌いで変わりますので、適切なトリーツを用意してあげましょう。
トリーツはご褒美だということをご説明してきましたが、食べ物である必要はありません。
愛犬が好きなもの・喜ぶものであれば、おもちゃやボールといった遊ぶものでもトリーツになります。
犬によっては、食べ物にあまり興味を持たないコもいますので飼い主様が愛犬の喜ぶものを把握し、トリーツとして利用してください。
ドッグフードが大好きなコなら、フードを何粒も用意してあげれば喜びます。
犬の個性や好き嫌いで変わりますので、適切なトリーツを用意してあげましょう。
 犬は長い歴史の中で、人と共に暮らし様々なサポートをしてくれる存在として信頼関係を築いてきました。
自分を可愛がってくれる大好きな飼い主様に褒められながら行うしつけやトレーニングは、愛犬の心にも大きく作用します。
褒められることは自信と喜びになり、より飼い主様と深い絆が生まれていきます。
トリーツは愛犬の心にも充足を与えますので、飼い主様は積極的に愛犬と関わりながら褒めていきましょう。
犬は長い歴史の中で、人と共に暮らし様々なサポートをしてくれる存在として信頼関係を築いてきました。
自分を可愛がってくれる大好きな飼い主様に褒められながら行うしつけやトレーニングは、愛犬の心にも大きく作用します。
褒められることは自信と喜びになり、より飼い主様と深い絆が生まれていきます。
トリーツは愛犬の心にも充足を与えますので、飼い主様は積極的に愛犬と関わりながら褒めていきましょう。
 コロナが流行ってからテレワークで働く場合が多くなっているため、猫を飼っている人であればさまざまなトラブルにあってしまった経験がある人も多いのではないでしょうか。
次に、テレワーク中の猫対策7選を紹介します。
大事な会議などをテレワークで行っている場合は特に要チェックです。
コロナが流行ってからテレワークで働く場合が多くなっているため、猫を飼っている人であればさまざまなトラブルにあってしまった経験がある人も多いのではないでしょうか。
次に、テレワーク中の猫対策7選を紹介します。
大事な会議などをテレワークで行っている場合は特に要チェックです。
 テレワーク中にネコハラしてくる原因は寂しい思いや構ってほしい気持ちからしている行動でもあります。
仕事前にしっかりスキンシップをとっておくことで猫も満足して邪魔をしてこなくなります。
遊びたい気持ちからネコハラをしてくるとちょっとやそっとではネコハラをやめてくれません。
そのような状況になってしまうとテレワークどころではなくなってしまいます。
休憩時間にしっかり猫と遊んだり、マッサージするなどしてコミュニケーションをとるようにしましょう。
テレワーク中にネコハラしてくる原因は寂しい思いや構ってほしい気持ちからしている行動でもあります。
仕事前にしっかりスキンシップをとっておくことで猫も満足して邪魔をしてこなくなります。
遊びたい気持ちからネコハラをしてくるとちょっとやそっとではネコハラをやめてくれません。
そのような状況になってしまうとテレワークどころではなくなってしまいます。
休憩時間にしっかり猫と遊んだり、マッサージするなどしてコミュニケーションをとるようにしましょう。
 どうしても猫がテレワーク中に邪魔をしてくるのであればケージに入れるようにしましょう。
ケージに入れてしまえばそこから出ることができないため、テレワークに集中することができます。
普段室内で放し飼いをしている人であればケージに閉じ込めてしまうことは可愛そうと感じてしまう人も多いですが、
ケージの中にハンモックやキャットタワーなどがあれば狭い空間でもストレスを与えてしまうことがありません。
別室などに一時的に閉じ込めることができない場合にもケージが大活躍してくれます。
どうしても猫がテレワーク中に邪魔をしてくるのであればケージに入れるようにしましょう。
ケージに入れてしまえばそこから出ることができないため、テレワークに集中することができます。
普段室内で放し飼いをしている人であればケージに閉じ込めてしまうことは可愛そうと感じてしまう人も多いですが、
ケージの中にハンモックやキャットタワーなどがあれば狭い空間でもストレスを与えてしまうことがありません。
別室などに一時的に閉じ込めることができない場合にもケージが大活躍してくれます。
 猫が楽しめるような空間を作ることで飼い主に執着してしまうことがなく、テレワークの邪魔もしてこなくなります。
キャットウォークやキャットタワーを設置しているだけでも猫だけで遊ぶことができます。
そのほかにも温かい日差しがさしこむ窓際にフワフワの毛布を用意していれば勝手にお昼寝したり、リラックスしてくれます。
しかし、いくら快適な空間を用意してあげても飼い主との触れあいがなければ寂しくなったり、飼い主に会いに来てしまうため、定期的に猫の様子を見たり、撫でてあげましょう。
猫が楽しめるような空間を作ることで飼い主に執着してしまうことがなく、テレワークの邪魔もしてこなくなります。
キャットウォークやキャットタワーを設置しているだけでも猫だけで遊ぶことができます。
そのほかにも温かい日差しがさしこむ窓際にフワフワの毛布を用意していれば勝手にお昼寝したり、リラックスしてくれます。
しかし、いくら快適な空間を用意してあげても飼い主との触れあいがなければ寂しくなったり、飼い主に会いに来てしまうため、定期的に猫の様子を見たり、撫でてあげましょう。
 テレワーク中に猫が乱入してくることは多く、普段ではそこまで近づいて来ない猫でも邪魔してくることもあります。
テレワーク中に邪魔をしてしまうことには理由がありますが、猫自身は飼い主の邪魔をするつもりはないため、怒らずに対策を練るようにしましょう。
テレワーク中に猫が乱入してくることは多く、普段ではそこまで近づいて来ない猫でも邪魔してくることもあります。
テレワーク中に邪魔をしてしまうことには理由がありますが、猫自身は飼い主の邪魔をするつもりはないため、怒らずに対策を練るようにしましょう。
 猫は元々温かい場所を好む動物であり、縁側などで日向ぼっこをしている光景をよく見かけるのはそのためです。
電源が入っているパソコンは程よく熱を帯びており、猫にとっては心地よい場所となります。
キーボードの上が温かくなりやすく、上に乗りやすいことからパソコン操作の邪魔をしてしまいがちです。
キーボードが熱を帯びるのはノートパソコンであり、デスクトップ型のキーボードはそこまで温かくならないので、デスクトップ型のパソコンを使用していればキーボードではなく、箱形の装置の上などに位置取りするケースが多くなります。
猫は元々温かい場所を好む動物であり、縁側などで日向ぼっこをしている光景をよく見かけるのはそのためです。
電源が入っているパソコンは程よく熱を帯びており、猫にとっては心地よい場所となります。
キーボードの上が温かくなりやすく、上に乗りやすいことからパソコン操作の邪魔をしてしまいがちです。
キーボードが熱を帯びるのはノートパソコンであり、デスクトップ型のキーボードはそこまで温かくならないので、デスクトップ型のパソコンを使用していればキーボードではなく、箱形の装置の上などに位置取りするケースが多くなります。
 個体差がありますが、飼い主のことが好きすぎる猫であれば自分に構って欲しい気持ちから邪魔をしてきます。
猫に愛されていることは飼い主にとっては嬉しいことではありますが、仕事中ではどうしても邪魔と感じてしまいます。
しかし、素っ気ない態度で接してしまったり、邪魔されることに対して怒るなどしてしまうと信頼関係を崩してしまいます。
普段から甘えてくる猫ほど飼い主のことを独占したい気持ちが強く、パソコンばかりに構っていると嫉妬心からパソコンの画面の前に来て、作業の妨害をしてきます。
個体差がありますが、飼い主のことが好きすぎる猫であれば自分に構って欲しい気持ちから邪魔をしてきます。
猫に愛されていることは飼い主にとっては嬉しいことではありますが、仕事中ではどうしても邪魔と感じてしまいます。
しかし、素っ気ない態度で接してしまったり、邪魔されることに対して怒るなどしてしまうと信頼関係を崩してしまいます。
普段から甘えてくる猫ほど飼い主のことを独占したい気持ちが強く、パソコンばかりに構っていると嫉妬心からパソコンの画面の前に来て、作業の妨害をしてきます。