老犬のお漏らし問題とは?
 犬の老化のサインはいろいろあります。
その一つがトイレの失敗です。
老化によって身体機能が衰え、排泄の体勢でよろけたり少し間に合わなかったり。
トイレシートに乗っているつもりがはみ出していることもあります。
毎日の運動で筋力を維持することやトイレシートの工夫などで飼い主がサポートできることも多いです。
ただ人間と同じで、どうしようもない老化現象の一つでもあり、逆に長生きの証でもあるのです。
また、そこには病気が隠れている場合もありますし、頻繁な尿漏れでは対策が必要となります。
ここでは、老犬に多い排尿に関係する病気や尿漏れ対策についてまとめてみました。
犬の老化のサインはいろいろあります。
その一つがトイレの失敗です。
老化によって身体機能が衰え、排泄の体勢でよろけたり少し間に合わなかったり。
トイレシートに乗っているつもりがはみ出していることもあります。
毎日の運動で筋力を維持することやトイレシートの工夫などで飼い主がサポートできることも多いです。
ただ人間と同じで、どうしようもない老化現象の一つでもあり、逆に長生きの証でもあるのです。
また、そこには病気が隠れている場合もありますし、頻繁な尿漏れでは対策が必要となります。
ここでは、老犬に多い排尿に関係する病気や尿漏れ対策についてまとめてみました。
犬のお漏らし対策!老犬の尿頻度と病気
 トイレの失敗は増えてくると、まず洗濯掃除が大変!と感じてしまいがちです。
でも排泄は健康のバロメーター。
その回数や状態などはとても重要なもので、病気のサインになることも多いのです。
トイレシートをチェックし、色や量などいつもと違うことを発見できるようになっておきましょう。
尿頻度が増えた、あるいは減った時に考えられる病気について説明します。
トイレの失敗は増えてくると、まず洗濯掃除が大変!と感じてしまいがちです。
でも排泄は健康のバロメーター。
その回数や状態などはとても重要なもので、病気のサインになることも多いのです。
トイレシートをチェックし、色や量などいつもと違うことを発見できるようになっておきましょう。
尿頻度が増えた、あるいは減った時に考えられる病気について説明します。
尿の頻度一覧①乏尿
乏尿(ぼうにょう)とはオシッコの量が少ない状態のことで、1日400ml未満のことを言います。
さらに少なくなり、100ml未満になると無尿と言われますが、何らかの原因で排尿が困難になっている状態です。
急速な失血や脱水状態からショック状態となり、尿が作れなくなることが多いです。
代表的な病気では急性腎臓病が挙げられます。
急性腎臓病は急激に進行する場合もあり、命に関わる病気ですので、すぐに動物病院で診察を受けましょう。
尿の頻度一覧②尿閉
 尿閉とは、膀胱に尿が溜まっていても排尿できなくなる状態のことを指します。
メス犬よりオス犬に多いとされます。
排尿後でも下腹部が膨らんでいたり、ポタポタと尿漏れがあったり、寝ている場所が濡れていたりします。
代表的な病気では会陰ヘルニア、尿結石などがあり、尿路感染症への注意も必要です。
膀胱に尿が溜まっているかどうかは飼い主さんには判断しづらいので、症状があれば獣医の診察検査を受けましょう。
まずは適切に排尿させてあげ、病気の有無も確認してもらいましょう。
尿閉とは、膀胱に尿が溜まっていても排尿できなくなる状態のことを指します。
メス犬よりオス犬に多いとされます。
排尿後でも下腹部が膨らんでいたり、ポタポタと尿漏れがあったり、寝ている場所が濡れていたりします。
代表的な病気では会陰ヘルニア、尿結石などがあり、尿路感染症への注意も必要です。
膀胱に尿が溜まっているかどうかは飼い主さんには判断しづらいので、症状があれば獣医の診察検査を受けましょう。
まずは適切に排尿させてあげ、病気の有無も確認してもらいましょう。
尿の頻度一覧③頻尿
頻尿とは、排尿の回数が増えることで尿の量が少しずつになっていきます。
考えられる原因は、まず老化によって膀胱の筋肉が低下し尿をたくさん貯められなくなることです。
また膀胱に結石や腫瘍ができたり、細菌が入って炎症を起こすことで尿を貯められず、頻尿になることもあります。
代表的な病気としては尿道炎、膀胱結石、膀胱炎などです。
1回の尿の量は、シートの重さを量ったり、外での排尿では紙コップで計測したりしてみましょう。
尿の頻度一覧④多飲多尿
多飲多尿とは、たくさん水を飲んでたくさんオシッコをすることです。
ただ夏場や運動後はどうしても増えてしまうのでわかりづらいです。
一日だけでなく、数日間状態を観察してみましょう。
多飲多尿は実は様々な病気の早期発見につながるからです。
・水入れがよく空になっている
・排尿時間が長い
・おもらしがあった
などのサインがあれば、一度診察を受けてみることをおすすめします。
代表となる病気は、クッシング症候群、慢性腎臓病、糖尿病、子宮蓄膿症などがあります。
犬のお漏らし対策とは?具体的にどうする?
 老犬のトイレの失敗はやはり辛いものです。
飼い主さんにとっては片付けが大変で、ついイライラしてしまった経験をもつひともいるでしょう。
でも、愛犬が過ごす時間はそう長くはないのかもしれません。
今までたくさん癒やしをくれた愛犬への最後のお世話です。
できるだけお世話が楽にできて、犬も飼い主も快適に過ごせるような工夫を考えてみましょう。
老犬のトイレの失敗はやはり辛いものです。
飼い主さんにとっては片付けが大変で、ついイライラしてしまった経験をもつひともいるでしょう。
でも、愛犬が過ごす時間はそう長くはないのかもしれません。
今までたくさん癒やしをくれた愛犬への最後のお世話です。
できるだけお世話が楽にできて、犬も飼い主も快適に過ごせるような工夫を考えてみましょう。
オムツを履かせる
老犬への一番のお漏らし対策はオムツです。
オムツを履かせることに抵抗がある人もいますが、決して不自由をさせることではありません。
むしろオムツによって自由に部屋で過ごすことができ、犬の運動不足やストレスを解消させることにもつながります。
部屋が汚れることがないので、飼い主も片付けの煩わしさから開放されます。
今は犬用のオムツも多いですし、コスト面から人間用のオムツを改良して使う人も多いです。
またオス犬の場合、お漏らしにはマナーベルトで対応できることもあります。
状況に応じて上手く利用していきましょう。
トイレを室内に変える
室内飼いでもトイレは散歩でしかしないという犬もいます。
朝晩の散歩の時以外は排泄を我慢していることになり、病気かかるリスクも高いです。
若い時は我慢できても、シニアになってからは我慢できずに漏らしてしまうこともあります。
室内トイレを習慣づけると、天候や体調などを考慮して散歩に出かけることができるので犬にかかる負担が減らせます。
一般的には屋外での排泄時にさっとシートを敷いて、その感触を覚えさせ、少しずつ自宅まで近づけていくという方法があります。
教える時はとにかく根気よく何度も繰り返すこと。
トイレのコマンドを教えたり、人工芝を敷いたりと様々な方法にチャレンジしてみましょう。
まとめ
 老犬のお漏らしには、老化での筋肉低下によるものと病気のサインがあります。
トイレの場所を間違える場合は認知症の疑いもあります。
よく観察して少しでも心配があるようなら、適切に病院の診察を受けましょう。
以前より寿命が伸び、長生きできるようになった犬のお世話は大変ですが、その分一緒にいられる時間は愛おしいものです。
お漏らしにイライラせず、犬も飼い主さんも快適に楽しい時間が続くような対策を工夫していきたいですね。
老犬のお漏らしには、老化での筋肉低下によるものと病気のサインがあります。
トイレの場所を間違える場合は認知症の疑いもあります。
よく観察して少しでも心配があるようなら、適切に病院の診察を受けましょう。
以前より寿命が伸び、長生きできるようになった犬のお世話は大変ですが、その分一緒にいられる時間は愛おしいものです。
お漏らしにイライラせず、犬も飼い主さんも快適に楽しい時間が続くような対策を工夫していきたいですね。
犬の寿命を大きさ・犬種別に紹介
 犬は10歳がひとつの節目と言われますが、シニア犬を飼っている方に聞くと、13歳も節目だと話す方が多くいます。
それまで元気に過ごしてきていたのに、10歳や13歳を迎えた頃から病気が増えたり体調を崩しやすくなったりするようですね。
獣医学の進歩により犬の寿命は延びて来ていますが、現在の平均寿命は何年ほどになるのでしょうか。
人間の4~7倍の早さで年を重ねる犬達の平均寿命を、体の大きさごとにご紹介します。
犬は10歳がひとつの節目と言われますが、シニア犬を飼っている方に聞くと、13歳も節目だと話す方が多くいます。
それまで元気に過ごしてきていたのに、10歳や13歳を迎えた頃から病気が増えたり体調を崩しやすくなったりするようですね。
獣医学の進歩により犬の寿命は延びて来ていますが、現在の平均寿命は何年ほどになるのでしょうか。
人間の4~7倍の早さで年を重ねる犬達の平均寿命を、体の大きさごとにご紹介します。
中・大型犬の平均寿命
中・大型犬の平均寿命は、12~14歳ほどになります。
柴犬(豆柴を除く)、甲斐犬、コーギー、ゴールデンレトリバー、秋田犬、ダルメシアンなどの犬種が中・大型犬になります。
ただし、最近では18歳まで生きた柴犬の話なども聞くようになったので、平均寿命は変化してきているようです。
大型犬よりも中型犬の方が長生きの傾向があります。
小型犬の平均寿命
小型犬の平均寿命は13~15歳ほどになります。
トイプードル、マルチーズ、ミニチュアダックスフンド、シーズーなどの犬種が小型犬になります。
豆柴は正式に犬種として認可されていないため柴犬と同じ中型犬に分類されますが、大きさや平均寿命は小型犬とほぼ同じです。
小型犬はほとんどが室内飼育であり、生涯整った環境の中で過ごすことができることもあって、長生きする子が多いようです。
超小型犬の平均寿命
超小型犬の平均寿命は14~16歳ほどになります。
チワワ、ティーカッププードル、ポメラニアンなどの体重3kg前後の犬種です。
細くて小さくてとても弱そうな印象の超小型犬ですが、中・大型犬よりも長生きする子が多いと言われています。
体が小さくて長時間散歩をしなくても十分運動できることや、何かあっても抱き上げられることから、高齢者や子供のいる家庭で飼われることも多く、ひとりで留守番をするなどのストレスが少ないことも長寿の理由かもしれませんね。
犬の寿命がギネス認定!最高は何歳?
 平均寿命は20歳に満たない犬ですが、世界にはギネス記録を持つ超長寿の犬が存在します。
どんな犬種でどのように生活をしていた犬なのでしょうか。
その犬の暮らした環境から、長寿の秘訣を探ってみましょう。
平均寿命は20歳に満たない犬ですが、世界にはギネス記録を持つ超長寿の犬が存在します。
どんな犬種でどのように生活をしていた犬なのでしょうか。
その犬の暮らした環境から、長寿の秘訣を探ってみましょう。
ギネス認定!最高長寿犬
オーストラリアで暮らしていたオーストラリアンキャトルドッグのブルーイーは、29歳5ヶ月も生き抜いた、歴代で最高長寿の記録保持犬と言われています。
1939年まで生きたブルーイーの記録は、2020年現在もまだ破られていません。
でも実は、オーストラリアンキャトルドッグが30年生きたという例もあります。同じオーストラリア育ちのマギーです。
誕生を証明する記録がなかったためギネス認定には至りませんでしたが、ブルーイーもマギーも同じ犬種で牧畜犬として働いていました。
オーストラリアンキャトルドッグは15~22kgほどになる中型犬です。
ギネス認定の長寿犬は、長生きすると言われる小型犬ではなかったようですね。
元気の秘訣は仕事?
記録が古いためブルーイーの生涯は謎に包まれている部分が多くありますが、毎日牧畜犬として活発に動き回って働いていました。
オーストラリアンキャトルドッグは不思議な能力を持っていると言われています。
吠えたり噛んだりすることなく、羊を誘導する力があるのです。
持って生まれた「羊を扱う」という能力を存分に活かした生活を送ることが、ブルーイーの健康の秘訣であり、生き甲斐だったのかもしれませんね。
犬も人間も、何かの使命を持ち役になっている実感を持つことが、長く張りのある生き方につながるのかもしれません。
犬の寿命は人間の寿命だと何歳?
 犬は7歳くらいから老化の兆しが見え始め、ライフステージも成犬から「シニア」と呼ばれる時期に入ります。
もし犬が20歳を超えた場合、人間の年齢に換算すると96歳!
人間だとしてもかなりのご長寿さんだと言えます。
ちなみに犬全体の平均寿命を12~16歳ほどだとすると、人間では64歳~80歳になります。日本人の平均寿命は、男性81歳、女性が87歳なので、犬の方が少し平均寿命は短いようです。
でも犬の平均寿命は少しずつ延びています。いつかは人間に追いつく日もくるかもしれませんね。
犬は7歳くらいから老化の兆しが見え始め、ライフステージも成犬から「シニア」と呼ばれる時期に入ります。
もし犬が20歳を超えた場合、人間の年齢に換算すると96歳!
人間だとしてもかなりのご長寿さんだと言えます。
ちなみに犬全体の平均寿命を12~16歳ほどだとすると、人間では64歳~80歳になります。日本人の平均寿命は、男性81歳、女性が87歳なので、犬の方が少し平均寿命は短いようです。
でも犬の平均寿命は少しずつ延びています。いつかは人間に追いつく日もくるかもしれませんね。
まとめ
 治せる病気が増えてきたことで全体の平均寿命が延びてきているものの、ギネス記録にあるブルーイーのように驚異的な長生きをする犬には、その心の在り方にも理由があるように思います。
そのように考えると、犬が生きるということは時間の長さよりもいかに毎日を楽しくイキイキと過ごせるかということの方が大切なのかもしれません。
そして、その延長線上に「長寿」というおまけがついてきたら、本当に幸せですね。
治せる病気が増えてきたことで全体の平均寿命が延びてきているものの、ギネス記録にあるブルーイーのように驚異的な長生きをする犬には、その心の在り方にも理由があるように思います。
そのように考えると、犬が生きるということは時間の長さよりもいかに毎日を楽しくイキイキと過ごせるかということの方が大切なのかもしれません。
そして、その延長線上に「長寿」というおまけがついてきたら、本当に幸せですね。
ペットにつけてはいけない名前とは?
 ペットを飼うようになれば必然的に名前を付けるようになります。
名前は飼い主が自由に決める場合が多いですが、ペットに付けてはいけない名前があることを知っているでしょうか。
次に、ペットにつけてはいけない名前を紹介するので、新しくペットを飼おうと考えている人や子供が産まれた際に名前付けをする際に参考にしてください。
ペットを飼うようになれば必然的に名前を付けるようになります。
名前は飼い主が自由に決める場合が多いですが、ペットに付けてはいけない名前があることを知っているでしょうか。
次に、ペットにつけてはいけない名前を紹介するので、新しくペットを飼おうと考えている人や子供が産まれた際に名前付けをする際に参考にしてください。
家族と似た名前や同じ名前
ペットの名前に家族と似た名前やまったく同じ名前にすることはおすすめできません。
家族を呼んだ際にペット自身が呼ばれていると勘違いしてしまったり、その逆のパターンも考えられます。
家族が勘違いしてしまっても間違いにすぐに気づくことができますが、ペットの場合は混乱してしまう原因になってしまいます。
そのため、ペットの名前を呼んでも反応しなくなってしまう可能性も考えられます。
ペットと家族どちらにもメリットになることはないので、家族と同じ名前や似た名前をペットにつけることはやめましょう。
長すぎる名前
 長すぎる名前をペットにつけることもおすすめできません。
5文字以上で長い名前となってしまうので、長くても4文字以内にすることをおすすめします。
長い名前はペットが聞き取りにくいデメリットがあり、中々名前を呼ばれていることを認識することができません。
また、長い名前は飼い主や家族も呼ぶ際に面倒と感じてしまう原因となってしまいます。
長い名前でも最終的には略して呼ぶようになってしまうことも少なくありません。
長すぎる名前をペットにつけることもおすすめできません。
5文字以上で長い名前となってしまうので、長くても4文字以内にすることをおすすめします。
長い名前はペットが聞き取りにくいデメリットがあり、中々名前を呼ばれていることを認識することができません。
また、長い名前は飼い主や家族も呼ぶ際に面倒と感じてしまう原因となってしまいます。
長い名前でも最終的には略して呼ぶようになってしまうことも少なくありません。
卑猥または暴力的な名前
ペットに卑猥な言葉を使用したり、暴力的な言葉を名前にしないようにしましょう。
一般的にそのような名前をつけようと考える飼い主はおらず、常識的にタブーとされています。
飼い主がペットの名前を呼ぶ際に飼い主自身の気持ちも下がってしまう原因にもなります。
日本語の場合は卑猥や暴力的な言葉であるか判断しやすいですが、外国語を名前にする場合に本当の意味などをしっかり理解していないと知らない間に誰かを不快な思いにさせてしまっていることも考えられます。
例えばテロという名前を付けると人によってはテロリストを想像してしまう人もいるため、名前に使用することは控えることが無難です。
宗教関連の名前
 現在の日本にはさまざまな外国人が住んでいるため、宗教や信仰は多種多様となっています。
そのため、宗教や信仰に関する名前をペットにつけてしまうと誤解を招いてしまうこともあります。
名前に採用した言葉がどのような意味なのかをしっかり把握してから名前にするのであればある程度誤解を招いたり、トラブルを防ぐこともできますが、よほどの理由がない限りは宗教や信仰に関する名前をつけることはおすすめできません。
例えばある宗教で神とされている名前をペットの名前にしてしまうと、信仰心の強い人であれば神の名前を動物につけることは許されないことだと考えることもあります。
現在の日本にはさまざまな外国人が住んでいるため、宗教や信仰は多種多様となっています。
そのため、宗教や信仰に関する名前をペットにつけてしまうと誤解を招いてしまうこともあります。
名前に採用した言葉がどのような意味なのかをしっかり把握してから名前にするのであればある程度誤解を招いたり、トラブルを防ぐこともできますが、よほどの理由がない限りは宗教や信仰に関する名前をつけることはおすすめできません。
例えばある宗教で神とされている名前をペットの名前にしてしまうと、信仰心の強い人であれば神の名前を動物につけることは許されないことだと考えることもあります。
人前で呼ぶと恥ずかしい名前
人前で呼ぶと恥ずかしいと感じる名前もつけないようにしましょう。
別にペットの名前を人前で呼ぶことはないと考えてしまい、奇をてらいすぎてしまうこともあります。
しかし、ペットの名前を人前で呼ぶ機会や呼ばれる機会が意外と多いです。
例えばペットが犬であればドックランなどに参加した際に名前を呼んで愛犬と遊ぶようになりますが、多くの人に恥ずかしい名前を聞かれてしまいます。
そのほかのペットの場合でも病気などが原因で病院に連れて行くとペットの名前を呼ばれることも多く、恥ずかしい思いをしてしまいます。
そのため、ペットを呼ぶ際や呼ばれる際に恥ずかしいと感じる名前はつけないようにしましょう。
犬の名前を決める時の4つのポイント
 犬の名前を決める際に悩んでしまうことも多いのではないでしょうか。
定番の名前をつけることもできますが、名前が被ってしまうリスクもあるため、どうしても深く考えてしまいがちです。
次に、犬の名前を決める際のポイントを4つ紹介します。
犬の名前決めで悩んでしまっている人は参考にしてください。
犬の名前を決める際に悩んでしまうことも多いのではないでしょうか。
定番の名前をつけることもできますが、名前が被ってしまうリスクもあるため、どうしても深く考えてしまいがちです。
次に、犬の名前を決める際のポイントを4つ紹介します。
犬の名前決めで悩んでしまっている人は参考にしてください。
ポイント①:ペットが聞き取りやすい名前をつける
ペットの名前はペットが自分の名前だとわからないと意味がないので、ペットが聞き取りやすい名前をつけるようにしましょう。
基本的にペットは子音は聞き取りづらい傾向があるため、母音構成の名前をつけることがおすすめです。
ただし、上記でも紹介した家族と名前が似てしまわないように注意したり、「よし」や「待て」のようなしつけをする際に発音する母音を名前に採用することも控えましょう。
母音構成の名前は飼い主や家族が呼びやすいメリットもあります。
ポイント②:混合する名前を避ける
 混同する名前は避けるようにしましょう。
多頭飼いする際にお揃い感のある名前をつけたいと考える場合も多く、飼い主からすれば呼びやすく思えやすいメリットがあります。
しかし、犬にとっては似ている発音になってしまうため、自分が呼ばれているのかどうか判断しにくくなってしまうデメリットがあります。
呼ばれているか判断できないような名前は今後飼っていく中やしつけをする際に大きな弊害になってしまいます。
そのため、多頭飼いしている場合は違う名前をつけるようにしましょう。
混同する名前は避けるようにしましょう。
多頭飼いする際にお揃い感のある名前をつけたいと考える場合も多く、飼い主からすれば呼びやすく思えやすいメリットがあります。
しかし、犬にとっては似ている発音になってしまうため、自分が呼ばれているのかどうか判断しにくくなってしまうデメリットがあります。
呼ばれているか判断できないような名前は今後飼っていく中やしつけをする際に大きな弊害になってしまいます。
そのため、多頭飼いしている場合は違う名前をつけるようにしましょう。
ポイント③:成長した時のことも考える
犬の名前をつける際は子犬の時期である場合が多く、子犬の時の印象を名前につけることがあります。
しかし、成長したときのことも考えて名前をつけないと後悔してしまいます。
例えば子犬の時は体格も小さく、チビと名付けられやすいですが、大人になれば当然体つきもしっかりしてきて大きくなります。
そのため、成犬で大きくなっても名前はチビのままであり、名前と見た目が一致しないようになってしまいます。
また、犬種によって子犬と成犬で毛色が変わってしまうこともあるので、子犬の時の毛色をそのまま名前にするのではなく、一度成犬になっても毛色が変わらないかを調べるようにしましょう。
ポイント④:意味を確認する
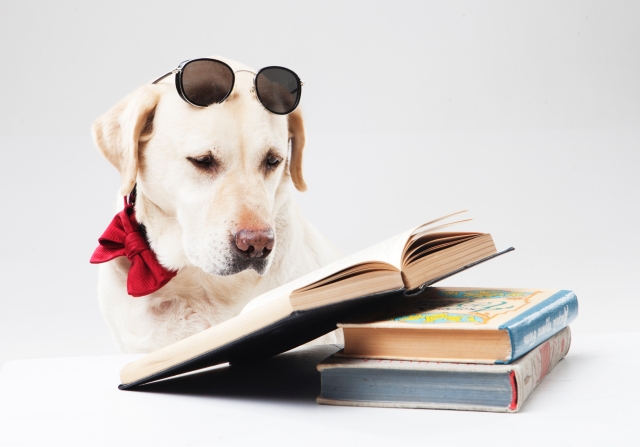 名前によっては海外で恥ずかしい思いをしてしまうこともあり、ありきたりな名前でも海外では違う意味があるため、意味を調べてから名前をつけるようにしましょう。
例えば犬の名前としてメジャーなクロやモコはスペインではお尻、鼻水という名前になってしまいます。
スペインと関りわりがないのであれば特に問題視する必要もありませんが、海外ではそういう意味があることは知っておきましょう。
また、逆に海外の言葉の響きが良いため、海外の言葉を名前にしてしまうこともありますが、後から意味を調べて恥ずかしい思いをしてしまうこともあるので、事前に名前にしようとしている言葉の意味を調べることは大切です。
名前によっては海外で恥ずかしい思いをしてしまうこともあり、ありきたりな名前でも海外では違う意味があるため、意味を調べてから名前をつけるようにしましょう。
例えば犬の名前としてメジャーなクロやモコはスペインではお尻、鼻水という名前になってしまいます。
スペインと関りわりがないのであれば特に問題視する必要もありませんが、海外ではそういう意味があることは知っておきましょう。
また、逆に海外の言葉の響きが良いため、海外の言葉を名前にしてしまうこともありますが、後から意味を調べて恥ずかしい思いをしてしまうこともあるので、事前に名前にしようとしている言葉の意味を調べることは大切です。
まとめ
犬に名前をつけることは当たり前ですが、つけてはいけない名前や後悔してしまう名前などがあります。
犬にとっても名前は一生の物であるため、安易に決めるのではなく、時間をかけて意味などを調べるなどして決めるようにしましょう。
セラピードッグとは?
 セラピードッグとは、人への忠誠心と深い愛情で高齢者を始め、障害を持つ方や病気の治療を必要とする患者さんの身体と精神の機能回復の補助をする犬のことをいいます。
セラピードッグたちが患者さんの心身の状態を向きあい、リハビリに寄り添うことで記憶を取り戻したり、動かなかった手や足が動くようになる効果があります。
そのような犬を育成する法人は近年増えてきており、犬たちの個々の能力や性格を大切に育て、対象となる方々の症状に合わせた治療のケアをしてくれます。
セラピードッグとは、人への忠誠心と深い愛情で高齢者を始め、障害を持つ方や病気の治療を必要とする患者さんの身体と精神の機能回復の補助をする犬のことをいいます。
セラピードッグたちが患者さんの心身の状態を向きあい、リハビリに寄り添うことで記憶を取り戻したり、動かなかった手や足が動くようになる効果があります。
そのような犬を育成する法人は近年増えてきており、犬たちの個々の能力や性格を大切に育て、対象となる方々の症状に合わせた治療のケアをしてくれます。
セラピー犬の仕事内容
 ここ数年セラピードッグという言葉をよく耳にするようにはなりましたが、一体どんな仕事をするのかまで把握している方は少ないのではないでしょうか。
そこでここではセラピー犬の仕事内容についてご紹介します。
ここ数年セラピードッグという言葉をよく耳にするようにはなりましたが、一体どんな仕事をするのかまで把握している方は少ないのではないでしょうか。
そこでここではセラピー犬の仕事内容についてご紹介します。
動物介在療法 AAT(Animal Assisted Therapy)
動物介在療法AATとは、医療現場で治療のために患者さんの心や体のリハビリテーションなどを目的としてセラピードッグが活動する補助療法のことを言います。
精神的または情緒的安定、身体的・社会的な機能の向上を目的を持って取り組むものなので、セラピードッグもハンドラーも2年以上の訓練が必須です。
また、AATで活躍するセラピードッグには忍耐力が要求されるので、ゴールデンレトリバーやラブラドールレトリバー、ジャーマンシェパード、ボーダーコリーなど比較的知能が高い大型犬が向いていると言われています。
AATは主に精神科や介護施設、認知症や身体障害者、パーキンソン病などの患者さんに対して行い、表情が乏しい方や家族関係に問題を抱えている方、人との関りに不安を抱いている方などの治療のために、医療従事者主導で行われることになります。
ですが、治療を受けるにはまず「犬が大好き」という条件が必須となっているので、全ての人に行えるわけではないということを把握しておきましょう。
動物介在活動 AAA(Animal Assisted Activity)
 動物介在療法AATとは、治療が目的ではなく、犬との触れ合いを楽しむことを中心としたレクリエーションのことを言います。
犬と一緒にレクリエーションを楽しみ、触れ合うことで情緒的に安定したり、リラックス効果やストレス解消効果が期待できるでしょう。
高齢者福祉施設の訪問やホスピスなどでよく取り入れられており、一度に大勢の人と触れ合えるメリットがあります。
また家族がいない高齢者がセラピードッグと触れ合うことで、穏やかなスキンシップの時間を持てたり、心身に大きな癒しの効果を与えることもできます。
動物介在療法AATとは、治療が目的ではなく、犬との触れ合いを楽しむことを中心としたレクリエーションのことを言います。
犬と一緒にレクリエーションを楽しみ、触れ合うことで情緒的に安定したり、リラックス効果やストレス解消効果が期待できるでしょう。
高齢者福祉施設の訪問やホスピスなどでよく取り入れられており、一度に大勢の人と触れ合えるメリットがあります。
また家族がいない高齢者がセラピードッグと触れ合うことで、穏やかなスキンシップの時間を持てたり、心身に大きな癒しの効果を与えることもできます。
動物介在教育 AAE(Animal Assisted Education)
動物介在教育AAEとは幼稚園や小学校などの教育現場で、子供たちが動物とのふれあい方や命の大切さを学ぶことを目標とした活動を言います。
近年、生活科や総合学習などのプログラムとして、AAEを導入する教育現場も徐々に増えており、教育活動の一環としてセラピードッグを使います。
またセラピードッグと触れ合うことによって、動物愛護や動物福祉について考える機会になったり、知識を深め理解してもらうことにも繋がるため、貴重な教育活動となるでしょう。
セラピー犬として活躍する方法
 さまざまな活動をしているセラピー犬ですが、どんな犬種でも簡単にセラピー犬になれるかと言えばそうではありません。
受験資格や認定試験などがあり、それらをクリアした優秀な子がセラピー犬として活躍できるわけです。
ここでは、セラピー犬として活動する方法をご紹介します。
さまざまな活動をしているセラピー犬ですが、どんな犬種でも簡単にセラピー犬になれるかと言えばそうではありません。
受験資格や認定試験などがあり、それらをクリアした優秀な子がセラピー犬として活躍できるわけです。
ここでは、セラピー犬として活動する方法をご紹介します。
まずはトレーニングを受ける
セラピー犬になるためには、民間の団体が実施している認定試験に合格し、資格を取得しなければいけません。
そのため、試験に合格するためにさまざまなトレーニングを受ける必要があります。
どんなトレーニングを受けるのかをご紹介します。
トレーニング①:アイコンタクト
 アイコンタクトとは、文字通り人と犬が目を合わせることを言います。
これはセラピー犬だけに限らず犬を飼うとなった以上、しつけの基礎であり、主従関係を築くためにもアイコンタクトは非常に重要と言えるでしょう。
犬はアイコンタクトを通して信頼関係を深め、相手の気持ちや体調を感じ取ったりするので、セラピー犬になるために大前提の条件と言えるでしょう。
アイコンタクトとは、文字通り人と犬が目を合わせることを言います。
これはセラピー犬だけに限らず犬を飼うとなった以上、しつけの基礎であり、主従関係を築くためにもアイコンタクトは非常に重要と言えるでしょう。
犬はアイコンタクトを通して信頼関係を深め、相手の気持ちや体調を感じ取ったりするので、セラピー犬になるために大前提の条件と言えるでしょう。
トレーニング②:同速歩行(ヒール)
ハンドラーのペースに合わせ、同じスピードで歩くことを言います。
アイコンタクトはしつけの基礎でしたが、ヒールは訓練の基礎と言えるでしょう。
人が歩く際に邪魔をしないよう適切な距離を保ちつつ、左側で一緒に歩きます。
早足やゆっくりな速度に対応することはもちろん、障害物がある場合の歩行も訓練します。
医療・福祉・介護の現場では、杖をついたり、車いすに乗っていたりと速度を合わせる相手はさまざまです。
車いすの同速歩行は、ブレーキの音を聞き分けたり、エレベーターに乗ったり、車輪に巻き込まれないよう気をつけたりと決して簡単ではありません。
トレーニング③:ケインウォーク
 主に、高齢者と同速歩行することを言います。
特に遅い歩行に合わせる訓練で、杖をついてゆっくり歩き犬に速度を理解させます。
また、中には棒で虐待を受けていた犬がセラピー犬になる場合もあります。
過去に棒で叩かれたことがある場合は、杖を怖がるのでそれを一緒に乗り越えるのもトレーニングの一つです。
速度だけではなく、不規則な動きにも合わせられるようにするため、高齢の方や杖をついて歩く方はもちろん、ケガや病気の後遺症がある方に合わせて歩く訓練も行います。
主に、高齢者と同速歩行することを言います。
特に遅い歩行に合わせる訓練で、杖をついてゆっくり歩き犬に速度を理解させます。
また、中には棒で虐待を受けていた犬がセラピー犬になる場合もあります。
過去に棒で叩かれたことがある場合は、杖を怖がるのでそれを一緒に乗り越えるのもトレーニングの一つです。
速度だけではなく、不規則な動きにも合わせられるようにするため、高齢の方や杖をついて歩く方はもちろん、ケガや病気の後遺症がある方に合わせて歩く訓練も行います。
トレーニング④:ベッドマナー
ベッドマナーは最終段階の訓練です。
このトレーニングは寝ている人への対応として必要になる訓練です。
部屋に入るところから、ベッドのうえでの動き、ベッドから離れるとき、部屋を出るところまで一連の動きを身につけます。
セラピー犬に適した犬種とは?
 セラピー犬は、一般の家庭で生活している家庭顕から保護犬までどんな子でも目指すことは可能です。
セラピー犬の適正として、人が好きであること、人見知りをしないこと、他の動物を警戒しないこと、初めての場所や大きな音を怖がらないこと、基本のしつけが完璧であること、健康であることなどが求められます。
セラピー犬として活動できる年齢は、団体によって異なりますが、成犬(月齢8か月~1歳以上)が基準となっています。
特に適している犬種はありませんが、人が大好き、優しい、温厚という面から考えると、
大型犬ではゴールデンレトリバー、ラブラドールレトリバー、小型犬ではトイプードルやミニチュアダックスフンドなどがセラピー犬として多く活躍しているのが現状です。
セラピー犬は、一般の家庭で生活している家庭顕から保護犬までどんな子でも目指すことは可能です。
セラピー犬の適正として、人が好きであること、人見知りをしないこと、他の動物を警戒しないこと、初めての場所や大きな音を怖がらないこと、基本のしつけが完璧であること、健康であることなどが求められます。
セラピー犬として活動できる年齢は、団体によって異なりますが、成犬(月齢8か月~1歳以上)が基準となっています。
特に適している犬種はありませんが、人が大好き、優しい、温厚という面から考えると、
大型犬ではゴールデンレトリバー、ラブラドールレトリバー、小型犬ではトイプードルやミニチュアダックスフンドなどがセラピー犬として多く活躍しているのが現状です。
セラピー犬による効果
 最近の実験でアニマルセラピーを受けると赤ちゃんに母乳をあげる時に出されるオキシトシン(愛情ホルモン)が分泌されていることが判明しています。
この研究からセラピー犬は人に癒しを与える効果があると実証され、大きく分けると人間に3つの効果をもたらせてくれているのでここではその3つの効果についてご紹介します。
最近の実験でアニマルセラピーを受けると赤ちゃんに母乳をあげる時に出されるオキシトシン(愛情ホルモン)が分泌されていることが判明しています。
この研究からセラピー犬は人に癒しを与える効果があると実証され、大きく分けると人間に3つの効果をもたらせてくれているのでここではその3つの効果についてご紹介します。
効果①:心理的効果
心理的効果とは、セラピー犬が無条件で心を開いていることで、精神的に心の中のストレスをを軽減する効果があります。
例えば、セラピー犬を抱っこすることで、不安や悩みを周囲に打ち明けることができるようになる患者さんもいるということです。
認知症の患者さんなどは、セラピー犬のことが大好きになり、何かしてあげたいという自発性を生みますし、セラピー犬が静かに寄り添ってくれることで自分を必要としてくれていると感じ、心が豊かになる効果があります。
効果②:社会的効果
 社会的効果とは、孤立や疎外感を感じていた方が自ら社会に出られるようになり人とコミュニケーションを取ろうとする効果のことです。
実際にアニマルセラピーを導入している介護施設では、セラピー犬が間に入ることで周りとなかなか会話ができなかった方が積極的に話せるようになることがあります。
また、引きこもり外出が苦手な場合、セラピー犬に会うという動機づけをすることで社会参加を後押しすることもできるでしょう。
社会的効果とは、孤立や疎外感を感じていた方が自ら社会に出られるようになり人とコミュニケーションを取ろうとする効果のことです。
実際にアニマルセラピーを導入している介護施設では、セラピー犬が間に入ることで周りとなかなか会話ができなかった方が積極的に話せるようになることがあります。
また、引きこもり外出が苦手な場合、セラピー犬に会うという動機づけをすることで社会参加を後押しすることもできるでしょう。
効果③:生理的効果
生理的効果とは、脳の活性化や副交感神経が活発になる効果があります。
例えば、セラピー犬を撫でたり抱っこや名前を呼ぶことで、感情のコントロールや物事を整理処理をする前頭葉の機能が活発になります。
また、副交感神経が活発になることで、精神が安定し、呼吸や脈が落ち着いたり血圧が下がる効果も期待できるでしょう。
リハビリ中の場合、セラピー犬と遊んだ理触れ合いたいという気持ちから、リハビリを頑張ろうという意欲を高める効果もあります。
まとめ
今回はセラピードッグについてご紹介してきました。
セラピードッグは高齢者やケガ、病気の方だけではなく、心に傷を抱えている方の気持ちも変えてくれる素晴らしいパワーを持っています。
そんな犬がたくさん増えればとても嬉しいことですよね。
愛犬を飼っている方でもしセラピー犬にならしたいなと思っている方はぜひ今回の記事を参考にしてみてください。
オス猫は去勢後に性格が変わる?
 去勢手術をすることによって猫の性格が変わることはありません。
しかし、去勢をすることによって性ホルモンが分泌されなくなるので、スプレー行動や鳴くなどの性ホルモンの影響による行動は減ってきます。
また、攻撃的だった猫の行動が和らぐなどのケースもみられますが、去勢手術をすることによる変化には個体差があるので、必ず性格が変わるとは言えません。
去勢手術をすることによって猫の性格が変わることはありません。
しかし、去勢をすることによって性ホルモンが分泌されなくなるので、スプレー行動や鳴くなどの性ホルモンの影響による行動は減ってきます。
また、攻撃的だった猫の行動が和らぐなどのケースもみられますが、去勢手術をすることによる変化には個体差があるので、必ず性格が変わるとは言えません。
中性的な性格になる
オス猫が去勢手術をすると、成長ホルモンが分泌されなくなります。
成長ホルモンには猫の性格を形成するのに強く影響するため、子猫の時の性格をそのまま引き継ぐ傾向が強くなるようです。
また、男性ホルモンの量が減少するので、中世的な性格に変わることが多く、オス特有の攻撃性が和らぐ傾向になるようです。
その他に発情をしないまま手術を行うと去勢後も発情をすることはありませんが、一度でも発情を経験したことのある猫はマーキングしたりすることもあります。
ですが回数は減るでしょう。
甘えん坊な性格になる
 去勢手術を行うことで発情期に交尾ができないというストレスを感じなくてよくなるためストレスが減り、オス猫はのんびりゆったりと生活することができます。
そのためベッタリとくっついて甘えてくることも少なくありません。
また、早くに去勢をすると精神的に成熟することもなく、子猫のころの性格が残り甘えん坊になりやすいともいわれています。
去勢手術を行うことで発情期に交尾ができないというストレスを感じなくてよくなるためストレスが減り、オス猫はのんびりゆったりと生活することができます。
そのためベッタリとくっついて甘えてくることも少なくありません。
また、早くに去勢をすると精神的に成熟することもなく、子猫のころの性格が残り甘えん坊になりやすいともいわれています。
オス猫の去勢後に気をつけたいこと
 オス猫が去勢手術をすることで身体に負担がかかり、術前・術後の体調変化には注意が必要です。
精神的な負担も多く、家に帰ったとたんに落ち着きのない行動をしたり、隅に隠れてしばらく出てこないこともあるでしょう。
身体の調子は少しずつ回復していきますので、そっとしておいてあげてください。
オス猫が去勢手術をすることで身体に負担がかかり、術前・術後の体調変化には注意が必要です。
精神的な負担も多く、家に帰ったとたんに落ち着きのない行動をしたり、隅に隠れてしばらく出てこないこともあるでしょう。
身体の調子は少しずつ回復していきますので、そっとしておいてあげてください。
免疫力と抵抗力が一時的に低下する
去勢手術直後は抵抗力や免疫力が一時的に低下します。
抵抗力や免疫力が下がると、感染症のリスクが高まるので注意しましょう。
また、同居猫がいる場合は、少しの間隔離するなどの対策が必要となる場合があります。
ですが、隔離することでストレスになることもあります。
そのほか、術後2週間前後はシャンプーをすることは控え、手術を受けた猫が安心して過ごせるように配慮をしてあげましょう。
心身共にダメージを受けている
 去勢手術は子孫を望まないことや病気を予防するためには大切なことですが、猫にとってはとても怖い体験をしたことになります。
そのため、去勢手術後の猫は心身ともにかなりのストレスを受けていることもあり、今までと違う行動をとることもあります。
特に、家に着いたとたんに部屋の隅に隠れようとすることも、そんな時は無理やり引きずりだしたりせずに、落ち着くまで見守ってあげましょう。
去勢手術は子孫を望まないことや病気を予防するためには大切なことですが、猫にとってはとても怖い体験をしたことになります。
そのため、去勢手術後の猫は心身ともにかなりのストレスを受けていることもあり、今までと違う行動をとることもあります。
特に、家に着いたとたんに部屋の隅に隠れようとすることも、そんな時は無理やり引きずりだしたりせずに、落ち着くまで見守ってあげましょう。
オス猫の去勢後に変化すること
 オス猫に去勢手術をすることで攻撃性が緩和されたり、病気の予防ができたりとさまざまなメリットがあります。
でも逆にデメリットもあります。
どんなデメリットがあるのでしょうか?
ここでは具体的なデメリットを説明します。
オス猫に去勢手術をすることで攻撃性が緩和されたり、病気の予防ができたりとさまざまなメリットがあります。
でも逆にデメリットもあります。
どんなデメリットがあるのでしょうか?
ここでは具体的なデメリットを説明します。
肥満に陥りやすい
ホルモンバランスが変化することで、太りやすくなります。
食欲が増えるだけでなく、代謝も低下するので、同じ量のフードを食べるだけでも去勢後は太ります。
また、発情の時に比べても手術をする前より運動量が減ります。
とある調査では、去勢手術による肥満のリスクは2倍程度に上がると言われていますので、フードの与えすぎには気を付け、肥満にならないように注意しましょう。
繁殖が不可能になる
 生殖器を取り除いてしまう手術なので、当たり前のことですが、繁殖をすることができません。
この子の子孫を育てたいと思うのなら、去勢手術をするのか、しないのか、手術をするのならいつするのか、よく考え、検討し、計画的に進めましょう。
生殖器を取り除いてしまう手術なので、当たり前のことですが、繁殖をすることができません。
この子の子孫を育てたいと思うのなら、去勢手術をするのか、しないのか、手術をするのならいつするのか、よく考え、検討し、計画的に進めましょう。
発情しなくなる
去勢手術後のオス猫は発情をしなくなり、生殖に関するストレスの全てから解放されます。
また性的な欲求不満からくるストレスが消失し、発情期に起こるマーキングなどの問題行動も消失します。
ときに発情期を経験したあとに去勢手術を受けたオス猫が、手術後にも発情期と同様の行動を見せることがありますが、生殖機能は失われているので、手術前に比べて少なくなります。
まとめ
去勢手術にはメリットもデメリットもあります。
愛猫が全身麻酔で手術するのだから、かなりのリスクもあります。
飼い主にとって悩むところですが、家族のライフスタイルも見据えて、じっくり時間をかけて考えたいところですね。
コストコドッグフード『カークランド』の商品一覧
 コストコドックフードのカークランドでは、さまざまな商品が販売されています。
たくさんあるので購入する際に悩んでしまうこともあります。
次に、カークランドで販売されているおすすめの商品や人気商品を紹介します。
コストパフォーマンスに優れている場合が多いので、安くフードを購入したい人にもおすすめできます。
コストコドックフードのカークランドでは、さまざまな商品が販売されています。
たくさんあるので購入する際に悩んでしまうこともあります。
次に、カークランドで販売されているおすすめの商品や人気商品を紹介します。
コストパフォーマンスに優れている場合が多いので、安くフードを購入したい人にもおすすめできます。
成犬用 ラム・ライス・ベジタブル
リンク
高タンパクであり、低カロリーに仕上げられているフードであり、ラム肉が使用されている特徴もあります。
ラム肉は消化しやすい特徴もあるので、胃腸が弱い犬や食欲が低下してしまいやすい高齢の犬にもおすすめです。
ほかにも玄米や米ぬかも使用されているので、ビタミンやミネラル、食物繊維も豊富にあるため、成長する際に必要な栄養を十分摂取することが可能です。
多頭飼いであればフード代もばかになりませんが、コスパに優れているので安く済みます。
成犬用 チキン・ライス・ベジタブル
リンク
新鮮なチキンが使用されているフードであり、おいしいフードを食べることができます。
関節に必要なグルコサミンや食材から摂取する必要があるアミノ酸も含まれているので、栄養バランスに優れています。
毛並みを良くする効果も期待できるため、健康を維持したり、改善しつつ、見栄えも良くすることが期待できます。
また、消化に良い材料が多く使用されていることで、胃や腸に負担をかけてしまうこともありません。
栄養バランスに優れているなどメリットはありますが、ややフードのにおいが気になってしまうデメリットもあります。
成犬用 サーモン・ポテト
リンク
主原料にサーモンポテトが使用されているフードです。
サーモンは肉類と比べても消化が良く、DHAやEPAも豊富に含まれている特徴があります。
DHAやEPAは犬の体内で作ることができないので、フードなどの食べ物から摂取する必要があり、動脈硬化や高血圧を防ぐ効果が期待できます。
個体差もありますが、高齢になるにつれて病気にもなりやすいので、老犬におすすめのフードと言えます。
また、グレインフリーであり、穀物が一切使用されていない特徴があり、犬の胃や腸に負担をかけません。
成犬用 ターキー・ポテト
リンク
ターキーミールとポテトが主原料となっているフードです。
ターキーは七面鳥のことであり、同じ鶏肉ではありますが、チキンアレルギーがある犬でもターキーであれば食べられるケースは多いです。
また、穀物が使用されていないグレインフリーのフードでもあるので、チキンや穀物にアレルギーがある犬におすすめです。
ただし、必ずしもチキンアレルギーがある犬がターキーを食べられるわけではないので、最初は少量だけ与えて様子を見るようにしましょう。
小型成犬用 チキン・ライス・ベジタブル
リンク
小型犬の成犬用のフードとして販売され、チキンが主原料に使用されています。
総合栄養食であり、ヘルシーに仕上げられています。そのため、成長に必要な栄養が含まれているだけではなく、肥満体質になりにくい特徴もあります。
室内犬の場合はどうしても運動力が少なくなってしまい肥満体質になりやすいですが、脂肪代謝を高めるカルニチンが含まれているため、ダイエットや体型維持をしたい場合にもおすすめです。
また、鶏脂に含まれているリノール酸も含まれているので被毛や皮膚の状態を維持したり、改善することも期待できます。
ヘルシーウェイト
リンク
フード名からわかるように、体重管理ができるフードです。
成犬の健康状態を維持できるだけではなく、体重管理も行うことができるので、肥満体質の犬におすすめで、ダイエットにも成功する可能性が高まります。
カルニチンが含まれているおかげで、脂肪代謝を高めることができ、心臓への負担を軽減することも期待できます。
肥満体質になってしまうと心臓が弱ってしまうこともあるため、早急に体重を落とす必要がある犬にもおすすめです。
さまざまなあるフードの中でも低カロリー、低脂質で仕上げられている特徴もあります。
子犬用 チキン・ライス・ベジタブル
リンク
厳選された食材が使用されているフードで、基本的に1歳未満の子犬や妊娠、授乳中の母犬におすすめです。
総合栄養食でもあるので、非常に栄養バランスが良く、子犬が成長する際に必要な栄養が含まれています。
プロバイオティクスとプレバイオティクスが含まれている特徴もあり、腸内環境を整えたり、免疫力を維持することも期待できます。
子犬は病気にもなりやすいため、免疫力が高まったり、低下することを防ぐことは大きなメリットです。
また、子犬でも食べやすいサイズに仕上げられている特徴もあります。
高齢犬7歳以上 チキン・ライス・エッグ
リンク
栄養バランスに優れていることはもちろんですが、消化がしやすいように仕上げられていることでシニアの犬の胃や腸に負担をかけることはありません。
高齢になればなるほど食が細くなり、栄養不足に陥りやすいですが、消化がしやすいことで高齢犬でも食べやすくなっています。
一袋18㎏も入っているので、多頭飼いしている場合におすすめです。
ただし、一般的なペットショップやコストコでは販売されておらず、ネット販売だけとなっている特徴があります。
コストコドッグフード『カークランド』のメリット
 コストコのドックフードカークランドにはどのようなメリットがあるのかわからない人もいるのではないでしょうか。
メリットを知ることで他のドックフードとは違う部分を見つけることもできます。
次に、カークランドのメリットを紹介するので参考にしてください。
コストコのドックフードカークランドにはどのようなメリットがあるのかわからない人もいるのではないでしょうか。
メリットを知ることで他のドックフードとは違う部分を見つけることもできます。
次に、カークランドのメリットを紹介するので参考にしてください。
コスパが良すぎる
コストコはさまざまな商品を販売している特徴があり、ドックフードの場合も同じことが言えます。
大容量であり、販売価格が安いです。
フード代は犬の大きさによって食べる量も変わりますが、飼っている数が多ければそれだけフード代もかさんでしまいます。
そのため、多頭飼いしている人ほどコストコのカークランドで販売されているフードがおすすめです。
ドックフードはさまざまなメーカーが販売しており、なかにはコスパに優れているフードもあります。
しかし、カークランドのフードはさらに安くコスパに優れています。
大容量タイプがある
 一般的なドックフードは一般的に1㎏前後で販売されていることが多いです。
しかし、カークランドで販売されているドックフードは9~18㎏が主流となっています。
さまざまな商品にも言えることですが、少量ずつ購入するよりも一度にまとめて購入するほうが少し安く購入することができます。
また、頻繁に購入する手間も省けます。
一般的なペット関係の店では大容量タイプは少なく、購入したいドックフードを大容量で購入できない場合もありますが、カークランドであればそのような不満は芽生えません。
一般的なドックフードは一般的に1㎏前後で販売されていることが多いです。
しかし、カークランドで販売されているドックフードは9~18㎏が主流となっています。
さまざまな商品にも言えることですが、少量ずつ購入するよりも一度にまとめて購入するほうが少し安く購入することができます。
また、頻繁に購入する手間も省けます。
一般的なペット関係の店では大容量タイプは少なく、購入したいドックフードを大容量で購入できない場合もありますが、カークランドであればそのような不満は芽生えません。
グレインフリータイプがある
カークランドのドックフードの中にはグレインフリータイプのフードも販売されています。
最近ではグレインフリーのフードも多く販売され始めていますが、まだまだグレインが含まれているフードが多いです。
そのため、グレインフリーのフードを与えたいと考えている人におすすめです。
グレインフリーのフードには穀物などは一切使用されておらず、肉類がメインとなっています。
犬は雑食ではありますが、もともと肉食でもあるので消化器官や歯の構造は肉食のままです。
そのため、グレインが含まれているフードはもともと犬にはあまりあっていないフードと言えます。
コストコドッグフード『カークランド』のデメリット
 コストコドックフードでもあるカークランドはにはメリットもありますが、デメリットも存在しています。
そのため、メリットだけを把握して購入してしまうと後悔してしまうこともあります。
次に、カークランドのデメリットを紹介するので参考にしてください。
コストコドックフードでもあるカークランドはにはメリットもありますが、デメリットも存在しています。
そのため、メリットだけを把握して購入してしまうと後悔してしまうこともあります。
次に、カークランドのデメリットを紹介するので参考にしてください。
原材料に廃棄する部位で造られる「ミール系」を使用
カークランドのフードにはミール系が使用されている特徴があります。
ミール系とは本来廃棄すべき状態の物を使用しているということです。
例えば、ターキーミールであれば七面鳥の肉のことを示していますが、どの部位の肉なのかわからないような材料となります。
人が食べれるような状態ではない可能性も高く、骨や被毛、糞尿が混じっている可能性も捨てきれません。
そのため、愛犬の健康を考えるのであれば一度購入を検討してみることも大切です。
かさ増しに便秘を起こす「ビートパルプ」を使用
 カークランドのフードにはビートパルプという物が使用されています。
ビートパルプとは、サトウダイコンから砂糖の成分を搾り取った後のカスであり、普通であれば廃棄するものです。
また、ビートパルプは便を固くしてしまう効果があり、摂取しすぎてしまうと便秘になる恐れもあります。
ビートパルプの成分はもともと犬に不必要ではありますが、かさ増しのために使用されているだけです。
カークランドのフードが大容量であり、低価格で販売できている理由は、原材料が廃棄レベルの元を使用してかさ増しまでされているからと言っても過言ではありません。
カークランドのフードにはビートパルプという物が使用されています。
ビートパルプとは、サトウダイコンから砂糖の成分を搾り取った後のカスであり、普通であれば廃棄するものです。
また、ビートパルプは便を固くしてしまう効果があり、摂取しすぎてしまうと便秘になる恐れもあります。
ビートパルプの成分はもともと犬に不必要ではありますが、かさ増しのために使用されているだけです。
カークランドのフードが大容量であり、低価格で販売できている理由は、原材料が廃棄レベルの元を使用してかさ増しまでされているからと言っても過言ではありません。
コストコドッグフード『カークランド』のよくある質問
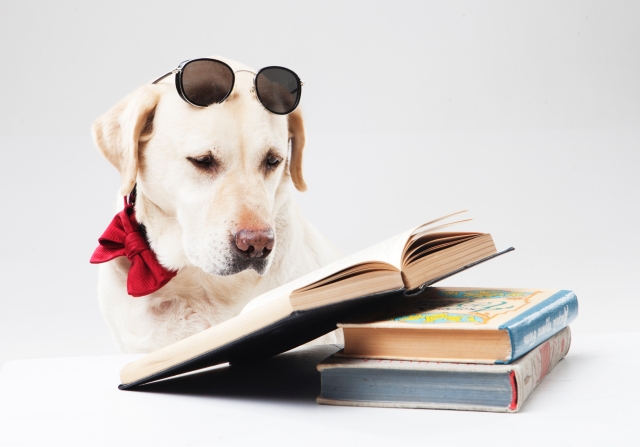 カークランドには上記で紹介したようにコスパに優れているメリットと健康面で不安な要素があるデメリットがあります。
そのため、購入者でもある飼い主にとっては購入してもよいのか悩んでしまいがちです。
次に、カークランドについてよくある質問に対して解説しているので参考にしてください。
カークランドには上記で紹介したようにコスパに優れているメリットと健康面で不安な要素があるデメリットがあります。
そのため、購入者でもある飼い主にとっては購入してもよいのか悩んでしまいがちです。
次に、カークランドについてよくある質問に対して解説しているので参考にしてください。
価格がとても安いけど安全?
カークランドのフードは低価格な魅力はありますが、安すぎると安全なのか不安になる人も多いのではないでしょうか。
確かにカークランドのデメリットにも紹介したように廃棄レベルの材料を使用していますが、添加物や着色料などが使用されていないこともあり、スーパーやホームセンターで販売されているフードと比べても安全です。
もちろん、カークランドより安全性が高く、栄養バランスに優れているフードもありますが価格が高いので、低価格で販売されているカークランドのフードは充分優れていると言えます。
実際に品質は良い?悪い?
 カークランドの品質は充分問題ないレベルと言えるでしょう。
ただし、メリットでもある大容量なことがデメリットになってしまうこともあり、保存期間には注意しましょう。
フードには適した消費期限があり、基本的に開封後一か月以内に使い切る必要があります。
開封してから徐々に酸化していき、次第に品質も劣化してしまいます。
一か月以上たってしまうと品質は格段と劣化しており、廃棄することを覚悟しなければなりません。
そのため、購入する前に一か月で食べきることができるのかを考えましょう。
カークランドの品質は充分問題ないレベルと言えるでしょう。
ただし、メリットでもある大容量なことがデメリットになってしまうこともあり、保存期間には注意しましょう。
フードには適した消費期限があり、基本的に開封後一か月以内に使い切る必要があります。
開封してから徐々に酸化していき、次第に品質も劣化してしまいます。
一か月以上たってしまうと品質は格段と劣化しており、廃棄することを覚悟しなければなりません。
そのため、購入する前に一か月で食べきることができるのかを考えましょう。
サンプルがもらえる場所はある?
犬は人と同じように食べ物に対して好き嫌いがあります。
そのため、カークランドのフードを必ず食べてくれるとは限りません。
そのような時に小袋でもあるサンプルがあれば便利ですが、残念ながらありません。
大袋で購入して食べてくれることを期待するか,知り合いにカークランドのフードを使用している人がいるのであれば少し分けてもらう方法もあります。
また、最近ではフリマアプリやサイトで小袋として販売されている場合もありますが、コスパの良さが薄れてしまうデメリットがあります。
まとめ
コストコドックフードのカークランドは大容量でコスパに良いメリットはありますが、保存がしにくかったり、使用されている材料に不安があるなどのデメリットもあります。
基本的に多頭飼いしている場合や大型犬を飼っている場合におすすめのフードとなっています。
グレインフリーとは?
 グレインフリーという言葉を聞いたことはないでしょうか。
最近ペットフードなどに記載されている言葉ですが、どのようなペットフードであるか理解できていない人も多いです。
グレインとは穀物のことであり、小麦や米のことを示しています。
そのため、グレインフリーとは穀物が一切含まれていないことです。
ちなみに似たような言葉にグルテンフリーというものもありますが、グルテンとはタンパク質のことを示しているので、主に麦のことを示しています。
グルテンフリーは麦のタンパク質がなく、グレインフリーは穀物自体が含まれていないことになります。
グレインフリーという言葉を聞いたことはないでしょうか。
最近ペットフードなどに記載されている言葉ですが、どのようなペットフードであるか理解できていない人も多いです。
グレインとは穀物のことであり、小麦や米のことを示しています。
そのため、グレインフリーとは穀物が一切含まれていないことです。
ちなみに似たような言葉にグルテンフリーというものもありますが、グルテンとはタンパク質のことを示しているので、主に麦のことを示しています。
グルテンフリーは麦のタンパク質がなく、グレインフリーは穀物自体が含まれていないことになります。
グレインフリーがペットに良い理由とは?
 グレインフリーのペットフードが最近販売され始めている理由はペットに良いことがあるからです。
次に、グレインフリーがなぜペットに良いのかを詳しく紹介していきます。
飼っているペットにあっているのであればフレインフリーのペットフードに変えてみてはいかがでしょうか。
グレインフリーのペットフードが最近販売され始めている理由はペットに良いことがあるからです。
次に、グレインフリーがなぜペットに良いのかを詳しく紹介していきます。
飼っているペットにあっているのであればフレインフリーのペットフードに変えてみてはいかがでしょうか。
動物性たんぱく質が摂れる
グレインフリーであれば動物性たんぱく質を多く摂取することができます。
グレインが含まれているフードでは最も多く含まれている材料が穀物になっており、悪い言い方をしてしまうとグレインである穀物でカサ増しされ、肉類があまり含まれていません。
もともと野生の犬は肉食であるため、穀物中心のグレインフードは好ましいとは言い切れません。
その点グレインフリーであればカサ増しの穀物は含まれていないので、必然的に肉類の割合が高くなり、動物性たんぱく質が多く取れます。
犬にとって消化しやすい
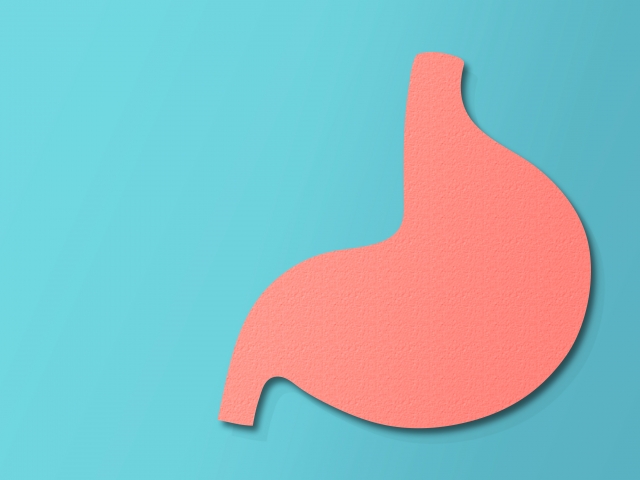 犬にとってグレインフリーのフードは消化しやすいので、胃や腸に負担をかけることがありません。
人と犬では体の構造が違い、穀物を消化するために必要な酵素でもあるアミラーゼを少ししか分泌することができません。
一見犬は雑食性と思われ、実際に肉も野菜も食べることができます。
しかし、犬の先祖は肉食の狼であるため、雑食ではありますが、限りなく肉食に近いと言えます。
また、穀物をすり潰すような歯がなく、消化しやすいようにして飲み込むことができないことも消化しにくい原因となっています。
犬にとってグレインフリーのフードは消化しやすいので、胃や腸に負担をかけることがありません。
人と犬では体の構造が違い、穀物を消化するために必要な酵素でもあるアミラーゼを少ししか分泌することができません。
一見犬は雑食性と思われ、実際に肉も野菜も食べることができます。
しかし、犬の先祖は肉食の狼であるため、雑食ではありますが、限りなく肉食に近いと言えます。
また、穀物をすり潰すような歯がなく、消化しやすいようにして飲み込むことができないことも消化しにくい原因となっています。
グレインフリーのデメリットとは?
 グレインフリーにはメリットとなる部分もありますが、デメリットになってしまう部分もあります。
そのため、メリットだけを重視してグレインフリーのフードを与えてしまうとデメリット部分か重なってしまい、犬に悪影響を与えてしまうことも考えられます。
次に、グレインフリーのデメリットを紹介するので上記で紹介したメリットと同じように理解しておきましょう。
グレインフリーにはメリットとなる部分もありますが、デメリットになってしまう部分もあります。
そのため、メリットだけを重視してグレインフリーのフードを与えてしまうとデメリット部分か重なってしまい、犬に悪影響を与えてしまうことも考えられます。
次に、グレインフリーのデメリットを紹介するので上記で紹介したメリットと同じように理解しておきましょう。
肥満になりやすい
グレインフリーで摂取できる動物性たんぱく質は筋肉をつける役割があるため、必要なたんぱく質ではありますが、植物性のたんぱく質と比べても高タンパクであるため、摂取しすぎると肥満の原因となってしまいます。
肥満はさまざまな病気の原因となってしまうので、避けるべき状態です。
特に、運動量の少ない高齢の犬にグレインフリーを与え続けてしまうと高い確率で肥満体質になってしまいます。
そのため、やんちゃで活発に活動する犬ではないのであれば、毎食グレインフリーを与えることはおすすめできません。
高価なフードが多い
 グレインフリーは販売価格が高い場合が多いです。
グレインが含まれている一般的なフードの場合は原料価格が非常に安い大豆やトウモロコシのカスや小麦でカサ増しされているので、低価格での販売が可能となっています。
しかし、グレインフリーでは当然カサ増しで使用していた小麦などが使用することができないため、結果的に高額になってしまいます。
愛犬は家族同然ではありますが、販売価格が高いことは購入時にネックになってしまうことも少なくありません。
グレインフリーは販売価格が高い場合が多いです。
グレインが含まれている一般的なフードの場合は原料価格が非常に安い大豆やトウモロコシのカスや小麦でカサ増しされているので、低価格での販売が可能となっています。
しかし、グレインフリーでは当然カサ増しで使用していた小麦などが使用することができないため、結果的に高額になってしまいます。
愛犬は家族同然ではありますが、販売価格が高いことは購入時にネックになってしまうことも少なくありません。
グレインフリーとグルテンフリーの違いとは?
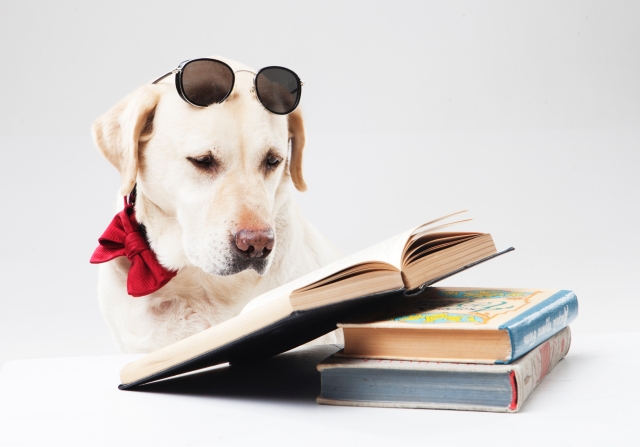 上記でも一部紹介しましたが、グレインフリーとグルテンフリーという似た言葉があります。
言葉は似ていますが、示していることは全く違いので、把握しておきましょう。
グレインフリーは穀物全般が含まれていない物を示しているのに対して、グルテンフリーはライ麦や小麦、大麦など麦類が含まれていないことを示しています。
グルテンフリーの場合は麦類にアレルギーがある犬におすすめです。
そのため、グルテンフリーには麦類の穀物は含まれていませんが、麦以外の穀物は含まれています。
上記でも一部紹介しましたが、グレインフリーとグルテンフリーという似た言葉があります。
言葉は似ていますが、示していることは全く違いので、把握しておきましょう。
グレインフリーは穀物全般が含まれていない物を示しているのに対して、グルテンフリーはライ麦や小麦、大麦など麦類が含まれていないことを示しています。
グルテンフリーの場合は麦類にアレルギーがある犬におすすめです。
そのため、グルテンフリーには麦類の穀物は含まれていませんが、麦以外の穀物は含まれています。
まとめ
グレインフリーは良い面もありますが、当然悪い面もあるため、購入するのであれば慎重に選ぶようにしましょう。
栄養バランスを考えるとグレインフリーばかり与えるのではなく、グレインが含まれているフードを与えることもおすすめです。
食事は健康を維持するために必要不可欠なことであり、愛犬の状態を確認してフードを選びをしましょう。
猫が二足歩行をする理由とは?
 猫は四足歩行が自然な姿ですが、たまに人間のように二足歩行で歩く子がいます。
突然二足歩行をし出すため、飼い主さんはびっくりするかもしれませんね。
ここでは、なぜ猫が二足歩行するのか理由についてご紹介します。
猫は四足歩行が自然な姿ですが、たまに人間のように二足歩行で歩く子がいます。
突然二足歩行をし出すため、飼い主さんはびっくりするかもしれませんね。
ここでは、なぜ猫が二足歩行するのか理由についてご紹介します。
何かに気がついた
猫は予想外に起こるできごとに「んっ?」と思うと同時に無意識に立ってしまうことがあります。
特に見知らぬ動物を観たり、聞きなれない大きな音が聞こえることに反応するでしょう。
散歩中に見知らぬ動物に会った時、自分でも思いがけずに立つ姿勢になってしまうこともしばしば。
まずは立つことで、次のアクションを考えます。
次のアクションには威嚇モードになるか、立つことを辞めて逃げ腰になるかなどその時の状況によりさまざまでしょう。
人間と同じように驚いた時には、体の筋肉がこわばってしまい立つというい無意識反応が起こるようです。
威嚇している
 猫は格闘モードになった時、相手を威嚇するために二足足で立つことがあります。
猫たちの世界では体を大きく見せることで自分を優位に見せるため相手への威嚇行動と言えるでしょう。
相手の方が自分よりも強い雰囲気を察した相手はびっくりして、戦意喪失するといった感じですね、
四足足で地面に立つ時、比較してみると、二足足で立つ時は体のサイズが大きく見えますよね。
まるで龍のように前足も上の方に広げるのでより大きく感じるでしょう。
また、後ろの二本足で立ち、前足を広げることで相手よりも素早い行動ができる体勢でもあります。
ケンカに勝つ自信がある時には、このように急に立つ行動をすることがあるようです。
猫は格闘モードになった時、相手を威嚇するために二足足で立つことがあります。
猫たちの世界では体を大きく見せることで自分を優位に見せるため相手への威嚇行動と言えるでしょう。
相手の方が自分よりも強い雰囲気を察した相手はびっくりして、戦意喪失するといった感じですね、
四足足で地面に立つ時、比較してみると、二足足で立つ時は体のサイズが大きく見えますよね。
まるで龍のように前足も上の方に広げるのでより大きく感じるでしょう。
また、後ろの二本足で立ち、前足を広げることで相手よりも素早い行動ができる体勢でもあります。
ケンカに勝つ自信がある時には、このように急に立つ行動をすることがあるようです。
興味がある
猫は好奇心旺盛な動物なので、好奇心から立つ仕草をすることがあります。
おそらく自分が興味を示す何かがあると察知したことによる行動なので「見たい、聞きたい、知りたい」と興味津々になり、二足足で立つのです。
普段は四足歩行で視線が低いので、二足で立ち体をグイッと伸ばすことによって、目的物を早く発見することができることもあるのでしょう。
また、立つ姿勢になった後、ジャンプして目的のものに向かって行ったりすることもあるため、猫が何かに気づいて立った時は走って行かないように注意が必要な時もあります。
周囲を警戒しているポーズ
 急に相手が表れたとか、大きな音がしたなど急激にびっくりするほどではないものの、ちょっとした雰囲気の変化を察して警戒することは人間でもありますよね。
猫たちは野生の勘で「なんだろう?」と周囲を警戒するときに立つことがあります。
この時は立ち上がってから周囲をキョロキョロと見渡すような仕草をします。
立つことで目の位置が上になり、より高いところから周囲を観察できるのです。
視界が広がるだけではなく、音も聞こえやすくなり異変に気付きやすいでしょう。
猫が警戒から立つのは自分を守るための習性ということになります。
急に相手が表れたとか、大きな音がしたなど急激にびっくりするほどではないものの、ちょっとした雰囲気の変化を察して警戒することは人間でもありますよね。
猫たちは野生の勘で「なんだろう?」と周囲を警戒するときに立つことがあります。
この時は立ち上がってから周囲をキョロキョロと見渡すような仕草をします。
立つことで目の位置が上になり、より高いところから周囲を観察できるのです。
視界が広がるだけではなく、音も聞こえやすくなり異変に気付きやすいでしょう。
猫が警戒から立つのは自分を守るための習性ということになります。
放心状態で立っている
猫はさまざまな理由で立つ行動が見られるのですが、猫によっては立った後に放心状態となることもあります。
一点を見つめていたり、ボーっとしたりと、たったまま呆然となっていることも。
瞬間的に力が入り過ぎた分、ちょっと力が抜けているのかもしれませんね。
ちょっと観察しているとハッと我れに返り、四足歩行に戻るでしょう。
中には、しばらくたったままということもあるかもしれません。
いずれにしても、体のバランスに優れた猫だからこそできるのです。
排泄する時の癖
 トイレで用を足す時に、踏ん張るという意味で立つ猫もいます。
体から排泄物を出す行為の時、人間もですが動物も力が入るもの。
特にウンチの方は便秘などお腹の調子によっては、いつも以上に踏ん張らないといけません。
猫たちもそれは同じで、踏ん張り具合がMAXになったときに無意識で立つようなスタイルになることもあるようです。
思わず立ってしまったという感じに見えたり、トイレのフチに前足をかけて踏ん張る体勢をする子もいるでしょう。
ちょっとしたクセになっている子もいるかもしれませんね。
一生懸命に自然現象と立ち向かっている姿勢なので、声をかけたり邪魔をせずに、そっと見守ってあげましょう。
トイレで用を足す時に、踏ん張るという意味で立つ猫もいます。
体から排泄物を出す行為の時、人間もですが動物も力が入るもの。
特にウンチの方は便秘などお腹の調子によっては、いつも以上に踏ん張らないといけません。
猫たちもそれは同じで、踏ん張り具合がMAXになったときに無意識で立つようなスタイルになることもあるようです。
思わず立ってしまったという感じに見えたり、トイレのフチに前足をかけて踏ん張る体勢をする子もいるでしょう。
ちょっとしたクセになっている子もいるかもしれませんね。
一生懸命に自然現象と立ち向かっている姿勢なので、声をかけたり邪魔をせずに、そっと見守ってあげましょう。
おもちゃを取りたい
猫用のおもちゃやおやつ、キャットタワー、毛布など家の中には猫のお気に入りグッズがたくさんありますよね。
いつもと違った場所に置かれたりしていると、探すようなスタイルで立つことがあるでしょう。
床が定位置のおもちゃがテーブルの上にあったりすると、探すように立つスタイルになることもあります。
体を伸ばせば取れると感じているためと思われます。
器用に後ろ足で立ち、前足を使ってヒョイっとお気に入りのおもちゃを取る姿はとても可愛らしいですよね。
しかし、中にはおやつを盗み食いしようとするために立って探す子もいるので、可愛いですが、食べ過ぎが肥満の原因になるため注意しましょう。
甘えているため
 猫は立つことで可愛らしさを表現しているケースもあります。
確かに立つ上がるとプクっとしたお腹が見えたり、前足でお願いポーズになっていたりと、可愛いポイントが満載!
この時には、飼い主さんの気持ちを惹きつけたいという甘えん坊モード全開の時なので、コミュニケーションやスキンシップをたくさんとってあげてくださいね。
猫は基本的にツンデレな性格なので、甘えてくる姿は貴重と言えるでしょう。
猫は立つことで可愛らしさを表現しているケースもあります。
確かに立つ上がるとプクっとしたお腹が見えたり、前足でお願いポーズになっていたりと、可愛いポイントが満載!
この時には、飼い主さんの気持ちを惹きつけたいという甘えん坊モード全開の時なので、コミュニケーションやスキンシップをたくさんとってあげてくださいね。
猫は基本的にツンデレな性格なので、甘えてくる姿は貴重と言えるでしょう。
猫の二足歩行は負担がかかる?
 猫は基本的に四足歩行の動物なので、二足歩行をする姿は可愛いですが、足腰に負担がかかってしまうのではと心配になってしまいますよね。
ここでは、二足歩行することで猫に負担がないのかをご紹介していきます。
猫は基本的に四足歩行の動物なので、二足歩行をする姿は可愛いですが、足腰に負担がかかってしまうのではと心配になってしまいますよね。
ここでは、二足歩行することで猫に負担がないのかをご紹介していきます。
猫はバランス感覚に優れている
猫はバランス感覚がとても優れている動物です。
三半規管が発達しているため、体のバランスを動きに合わせることができ、他の動物に比べてバランス感覚が良いため、高いところから落ちてもちゃんと着地ができるのです。
これは猫の大きな特徴と言えるでしょう。
こうしたバランス感覚のおかげで、後ろ足で立ってもバランスを調整し立っていることができるようです。
猫の後ろ足は発達している
 また、猫の後ろ足は思っている以上に発達しており、獣医師によると、猫の後ろ足は発達しており力があるため、猫にとって二足立ちは無理な姿勢ではないとのこと。
猫は非常にしなやかな動きをする動物なので、膝を曲げ伸ばし高いところからも難なくジャンプしますが、これら猫の動作に全て後ろ足やお尻の筋肉が関わっています。
そのため猫はびっくりした時や緊張している時などに力が入って体がこわばることがありますが、筋肉が緊張することは猫にとって特に問題がありません。
なので、二足立ちも猫にとっては無理な姿勢ではないということになりますね。
また、猫の後ろ足は思っている以上に発達しており、獣医師によると、猫の後ろ足は発達しており力があるため、猫にとって二足立ちは無理な姿勢ではないとのこと。
猫は非常にしなやかな動きをする動物なので、膝を曲げ伸ばし高いところからも難なくジャンプしますが、これら猫の動作に全て後ろ足やお尻の筋肉が関わっています。
そのため猫はびっくりした時や緊張している時などに力が入って体がこわばることがありますが、筋肉が緊張することは猫にとって特に問題がありません。
なので、二足立ちも猫にとっては無理な姿勢ではないということになりますね。
全く負担がないというわけではない
ですが、全く体に負担がないのか?と言われれば、そうではありません。
やはり猫も本来は四足歩行する動物なので、いつもいつも二足立ちをしたり二足歩行をすると足腰に負担はかかるもの。
なので、猫が自ら二足立ちをする以外に、飼い主がただ可愛い姿を見たいというだけの理由でむやみに二足立ちや二足歩行をさせることはやめましょう。
若いうちは良いかもしれませんが、シニア期に入ると骨が変形したり、関節のクッション部分である軟骨が減ったりすることで痛みが生じて、動きに制限が出てしまうことがあるかもしれません。
また、肥満になると足腰や関節への負担が大きくなるので立てなくなってしまうでしょう。
立つことは猫の本能的行動であり、立てなくなることは猫にとってもストレスとなりかねないため、飼い主さんのエゴで無理やり立たせたりなど余計な負担をかけないようにしてあげてくださいね。
猫が二足歩行で立ち上がる病気とは?
 ここまで猫が二足歩行で立ちあがる理由についてご紹介してきましたが、もしかするとてんかんという病気を発症している可能性もあります。
てんかんは脳の中の神経を通る電気異常によって発作が起こり、体のコントロールを失ってしまう病気です。
猫がてんかんになることは稀ですが、突然起こることもあるため、日頃からの観察が重要です。
てんかんは立つ以外にも四肢が硬直したり、痙攣したり、口から泡を吹くこともあります。
万が一、てんかん発作が起きた場合は、落ち着いて猫の周りに危ないものがないか、落下などの危険がない場所かを確かめ、発作の様子をビデオで撮影しておいてください。
ヘタに手を出すと攻撃される可能性があるため、あまり近く寄らないように発作が収まるのを待ちましょう。
ここまで猫が二足歩行で立ちあがる理由についてご紹介してきましたが、もしかするとてんかんという病気を発症している可能性もあります。
てんかんは脳の中の神経を通る電気異常によって発作が起こり、体のコントロールを失ってしまう病気です。
猫がてんかんになることは稀ですが、突然起こることもあるため、日頃からの観察が重要です。
てんかんは立つ以外にも四肢が硬直したり、痙攣したり、口から泡を吹くこともあります。
万が一、てんかん発作が起きた場合は、落ち着いて猫の周りに危ないものがないか、落下などの危険がない場所かを確かめ、発作の様子をビデオで撮影しておいてください。
ヘタに手を出すと攻撃される可能性があるため、あまり近く寄らないように発作が収まるのを待ちましょう。
まとめ
今回は猫が二足歩行する理由などについてご紹介してきました。
猫が二足歩行をするのはさまざまな理由があることがわかりましたね。
猫の場合、体が柔らかいためそこまで体に負担がかかるということはないのですが、全く負担がかからないというわけではないので、二足歩行姿を見たいからと言ってわざと二足歩行にさせるようなことは辞めておきましょう。
猫もお手ができる?
 お手は犬の芸として有名なしつけの一つであり、あまり猫がお手をするイメージはありません。
そのため、犬と猫では犬の方が賢いというイメージがついてしまっています。
しかし、猫も正しい教え方をすればお手ができるようになります。
猫は意外と知られていませんが記憶力が高く、犬以上とも言われています。
しかし、猫がお手をしたがらない理由には猫の性格が大きく関係しています。
猫は自分に得をすることしかしない考えがあり、自由奔放が好きで束縛されることを嫌がることも関係しています。
得をすることしかしないのであればお手をすれば特になると考えさせることができれば、お手もしてくれるようになります。
猫にとってお得と感じることはおやつをもらえることで、お手ができればおやつを与えるようにしましょう。
このやり方は犬と同じであり、犬同様に猫もお手ができるようになります。
猫によってはお手をすればおやつがもらえるとわかれば、猫が自発的に飼い主の手の上に前足を乗せておやつを催促してくることもあります。
お手は犬の芸として有名なしつけの一つであり、あまり猫がお手をするイメージはありません。
そのため、犬と猫では犬の方が賢いというイメージがついてしまっています。
しかし、猫も正しい教え方をすればお手ができるようになります。
猫は意外と知られていませんが記憶力が高く、犬以上とも言われています。
しかし、猫がお手をしたがらない理由には猫の性格が大きく関係しています。
猫は自分に得をすることしかしない考えがあり、自由奔放が好きで束縛されることを嫌がることも関係しています。
得をすることしかしないのであればお手をすれば特になると考えさせることができれば、お手もしてくれるようになります。
猫にとってお得と感じることはおやつをもらえることで、お手ができればおやつを与えるようにしましょう。
このやり方は犬と同じであり、犬同様に猫もお手ができるようになります。
猫によってはお手をすればおやつがもらえるとわかれば、猫が自発的に飼い主の手の上に前足を乗せておやつを催促してくることもあります。
猫のお手の教え方は?
 猫は犬と同じようにお手をすることができるようにはなりますが、正しい教え方をしなければなりません。
適切な教え方をすればそれだけ短時間でお手をマスターすることもできます。
次に、猫のお手の教え方を紹介します。
犬にお手を教える方法と似ている部分もありますが、猫だけに効果がある教え方もあるのでチェックしましょう。
猫は犬と同じようにお手をすることができるようにはなりますが、正しい教え方をしなければなりません。
適切な教え方をすればそれだけ短時間でお手をマスターすることもできます。
次に、猫のお手の教え方を紹介します。
犬にお手を教える方法と似ている部分もありますが、猫だけに効果がある教え方もあるのでチェックしましょう。
反復練習でお手を教える方法
猫にお手を教えるのであれば反復練習をすることが欠かせません。
犬にも言えることですが、一つのことを覚えさせるためには一回だけ教えてもマスターすることは難しく、何回も繰り返して教え続けなければなりません。
そのため、飼い主も根気強くお手を教える必要があります。
上記でも紹介したように猫は得と感じることであれば芸を覚えるため、猫の興味を釣るためにおやつを用意しましょう。
また、お手を教える際のタイミングも重要であり、程よい空腹時に教えるようにしましょう。
犬の場合はあまりお腹のすき具合を把握する必要はありませんが、猫の場合は満福状態ではおやつも欲しがらないため、得と感じる感情が薄まってしまいます。
一方極度な空腹時ではお腹がすいていることで集中することができません。
なので程よい空腹時のタイミングで挑戦するようにしましょう。
反復練習する際にはまず、飼い主がお手と発言して猫の前足をつかみ、飼い主の手の上に置きます。
最後におやつを与えて終わりです。コツは大きな声て発音良くお手と発言することです。
クリッカーを使用する方法
 クリッカーという道具を活用することでもお手を教えることができます。
クリッカーはおもちゃであり、300円程度で購入することができ、カチッと音がなる特徴があります。
そのほかにも長い棒を用意しましょう。
猫じゃらしのようなおもちゃでも代用することができます。
猫は細長いものを見ると近づく習性があり、棒の先端に鼻先がつけばクリッカーを鳴らします。
この際におやつを与えてもよいですが、この段階では特別与える必要はありません。
次に、棒を上に持ち上げると猫は興味を示し、体を起こし、前足で棒に触れようとします。
この際にクリッカーを再び鳴らします。
この動作を反復することで猫はクリッカーの音で前足を上げればおやつをもらうことができると学びます。
あとはクリッカーの音をお手という声に変えればお手をマスターすることができます。
クリッカーはお手以外のしつけでも活用することができ、クリッカーの音がなればよいことをしていると自覚することができ、効率よく新しい芸を覚えることも期待できます。
クリッカーという道具を活用することでもお手を教えることができます。
クリッカーはおもちゃであり、300円程度で購入することができ、カチッと音がなる特徴があります。
そのほかにも長い棒を用意しましょう。
猫じゃらしのようなおもちゃでも代用することができます。
猫は細長いものを見ると近づく習性があり、棒の先端に鼻先がつけばクリッカーを鳴らします。
この際におやつを与えてもよいですが、この段階では特別与える必要はありません。
次に、棒を上に持ち上げると猫は興味を示し、体を起こし、前足で棒に触れようとします。
この際にクリッカーを再び鳴らします。
この動作を反復することで猫はクリッカーの音で前足を上げればおやつをもらうことができると学びます。
あとはクリッカーの音をお手という声に変えればお手をマスターすることができます。
クリッカーはお手以外のしつけでも活用することができ、クリッカーの音がなればよいことをしていると自覚することができ、効率よく新しい芸を覚えることも期待できます。
猫にお手を教えるコツ
 猫にお手を教える際には教え方のほかにコツも覚えておくようにしましょう。
コツを知っているだけで効率よくお手を教えることができ、猫も早くお手をマスターすることができます。
なかなかお手をマスターしてくれない場合はコツがうまく活用できていない可能性があります。
猫にお手を教える際には教え方のほかにコツも覚えておくようにしましょう。
コツを知っているだけで効率よくお手を教えることができ、猫も早くお手をマスターすることができます。
なかなかお手をマスターしてくれない場合はコツがうまく活用できていない可能性があります。
ご褒美を有効活用する
猫にお手を教えるのであればご褒美を有効活用するようにしましょう。
芸を覚えさせる際には自分に対してメリットとなることがなければ覚えようともしないので、なかなか芸を覚えてくれません。
しかし、決められた行動をすればご褒美が貰えることがわかれば、ご褒美目当てで決められた行動をするようになります。
猫にとってのご褒美は大好物のおやつ以外に、気持ちよく感じる部分を撫でられたり、触られることもご褒美の内に入ります。
習慣化で覚えさせる
 猫にお手を教える際には習慣化させる必要があります。
人にも同じことが言えますが、一度教えられたことでもやらない時間が長ければ忘れてしまいます。
そのため、お手を教える際にはほぼ毎日反復練習を繰り返すようにしましょう。
また、一度お手をマスターしてもそれ以降お手を芸をさせなければ忘れてしまい、お手と発言してもお手をしてくれないこともあります。
このような状況になってしまうと教えていた時間が無駄になってしまうため、一度マスターした芸でも定期的にさせるようにしましょう。
猫にお手を教える際には習慣化させる必要があります。
人にも同じことが言えますが、一度教えられたことでもやらない時間が長ければ忘れてしまいます。
そのため、お手を教える際にはほぼ毎日反復練習を繰り返すようにしましょう。
また、一度お手をマスターしてもそれ以降お手を芸をさせなければ忘れてしまい、お手と発言してもお手をしてくれないこともあります。
このような状況になってしまうと教えていた時間が無駄になってしまうため、一度マスターした芸でも定期的にさせるようにしましょう。
「お手=楽しい」と思わせる
お手は楽しいことであると思わせることができれば早い段階でお手をマスターすることが期待できます。
何事でも言えることですが、楽しいと感じないことを継続的にすることは苦痛であるため、楽しいと思わせながらお手の練習を繰り返すようにしましょう。
お手をした後におやつなどのご褒美を与えた後に、一緒におもちゃなどで遊んであげるようにすればお手が楽しい印象になります。
猫は正直な性格である場合が多いので、お手が楽しいことや嬉しいことであるとわかればお手もマスターしやすいです。
猫のお手は犬のしつけと違う?
 猫にお手を教える際に犬に教える方法に違いを付けたほうが良いのか気になる人も多いのではないでしょうか。
犬と猫では性格も考え方も異なるため、教え方も変える必要があると考えてしまいがちですが、基本犬にお手を教える方法と同じで問題ありません。
犬も猫も褒められれば最も褒められたいと考えるので、お手をした後にしっかり褒めていれば大丈夫です。
警察犬などはより高度なしつけが求められますが、教え方としては反復練習としっかり褒めることであるため、一般家庭で飼っている犬に芸を教える方法と大差はありません。
猫にお手を教える際に犬に教える方法に違いを付けたほうが良いのか気になる人も多いのではないでしょうか。
犬と猫では性格も考え方も異なるため、教え方も変える必要があると考えてしまいがちですが、基本犬にお手を教える方法と同じで問題ありません。
犬も猫も褒められれば最も褒められたいと考えるので、お手をした後にしっかり褒めていれば大丈夫です。
警察犬などはより高度なしつけが求められますが、教え方としては反復練習としっかり褒めることであるため、一般家庭で飼っている犬に芸を教える方法と大差はありません。
まとめ
猫にお手を教えることで犬と同じようにお手をしてくれるようになります。
そのため、猫は芸を覚えることは無理と諦めるのではなく、適切な方法でしつけてみてはいかがでしょうか。
芸を覚えさせることでより一層猫とコミュニケーションをとることができ、絆を強めることもできます。
犬のお手の教え方とポイント
 犬は利口な動物であり、しつけをすればさまざまなことを覚えてくれます。
さまざまあるしつけの中でも基本のしつけでもあるのがお手です。
しつけを覚えるスピードは個体によって変わりますが、教え方によっても差が出てしまいます。
次に、お手の教え方のポイントを紹介するので参考にしてください。
犬は利口な動物であり、しつけをすればさまざまなことを覚えてくれます。
さまざまあるしつけの中でも基本のしつけでもあるのがお手です。
しつけを覚えるスピードは個体によって変わりますが、教え方によっても差が出てしまいます。
次に、お手の教え方のポイントを紹介するので参考にしてください。
ステップ①:犬が自ら前足を上げるようにする
犬にお手を教える際に無理やり犬の前足をつかんで持ち上げることをしていないでしょうか。
この方法は無理やりしているのであっていくらやり続けても犬が自発的に行動していないので、ほとんど効果はありません。
まずはお手をする際にお座りを覚えさせるようにしましょう。
おすわりができて初めてお手の練習をすることができます。
お座りをさせた後に前足を少し触ることで犬は前足を動かしたり、上にあげます。
上にあげた際にすかさず手を下に置き、お手の形を完成させましょう。
この際に誉め言葉を伝えると同時に頭を撫でて褒めてあげましょう。
一見簡単で本当に効果があるのか疑心暗鬼になってしまいやすいですが、最初はこれだけで問題ありません。
あくまでも犬には前足を上げれば褒めてくれるという認識を覚えさせることが目的です。
ここで多くの時間をかけてしまうこともありますが、焦りは禁物であり、飼い主が焦ってしまうと微妙な雰囲気を犬も感じ取ってしまい、ストレスに感じたり、恐怖感を受け付けてしまう原因にもなります。
愛犬とコミュニケーションが取れていないとお手を覚えさせることもほぼ不可能であるため、よく散歩に連れて行ったり、遊んであげて信頼関係を築くことも大切です。
ステップ②:「お手」という言葉を教える
ステップ1を難なくこなせることができれば、お手という言葉を教えるようにしましょう。
と言ってもお手という意味までを覚えさせることは必要なく、あくまでもお手と言われたら前足を上に持ち上げる必要があることを覚えてもらいましょう。
やり方はいたって簡単であり、ステップ1で前足を上にあげる際にお手というようにしましょう。
最初は出遅れ感がありますが、次第に前足を触らなくてもお手だけの言葉で前足を上げてくれるようになります。
この際に発言するお手の言葉はできるだけ発音やボリュームは一定にしてあげれば同じ言葉であることを犬が認識しやすくなります。
ステップ1同様にうまくお手ができるようになれば誉め言葉やおやつなどでご褒美を上げるようにしましょう。
ステップ③:前足を手に乗せる練習
ステップ1や2では犬が自発的に前足を上げるだけであり、自らの意思で飼い主の掌に前足を下すことはしていません。
そのため、最後のステップでもある前足を掌に載せる練習をする必要があります。
やり方はステップ1でやっていることと同じように前足を上げた際に手を素早く前足の下に入れるだけです。
そのあとに飼い主自身から掌を近づけて前足を触れ合うようにしたり、犬が前足を自分から降ろしてきた際に褒めてあげましょう。
ステップ1や2だけでは前足を上にあげれば褒美がもらえると覚えているため、掌に前足を置くことで褒められることをもう一度確認させるようにしましょう。
お手は犬自ら前足を上げ、降ろす必要があるので飼い主自身から掌を近づけて触れさせた場合は褒めたり、褒美を上げないようにしましょう。
この際に誉めてしまうと前足を下す必要がないと間違って覚えてしまうリスクがあります。
どうしても犬自ら前足をおろしてくれないのであれば、犬がつかれるまで待って疲れから降ろしてきたときに褒めてあげることも一つの方法かもしれません。
ステップ④:犬の前足を優しく握る
 ステップ3でお手は完成しているように見えますが、できるのであればお手をしている際に愛犬の前足を軽く握るようにしましょう。
前足を握られることは犬にとって不快な感触であるため、嫌がられる可能性もあります。
しかし、前足を握られることは良いことだと想像させることができれば、今後のしつけでも役に立ちます。
前足の握り方は力を入れずに握ることが大切であり、上下に振ることもしないようにしましょう。
あくまでも軽く握る程度で問題ありません。
しかし、前足を握られることに不快感を感じてしまう犬もいるので、握っている際には反対の手でおやつをあげたり、褒めることを忘れないようにしましょう。
また、いつまでも握り続けていることもあまりよくありません。
おやつを食べている際に握るのをやめることがポイントです。
いつまでも握っていると握られている不快感を感じたまま終わってしまうので、おやつを食べている幸せ感を感じたままお手を終わらせ、良いイメージをつけるようにしましょう。
握られても不快感を感じないようになればお手を完全マスターしているといっても過言ではなく、次にしつけを教えることができたり、ブラッシングする際に暴れてしまうこともなくなります。
ステップ3でお手は完成しているように見えますが、できるのであればお手をしている際に愛犬の前足を軽く握るようにしましょう。
前足を握られることは犬にとって不快な感触であるため、嫌がられる可能性もあります。
しかし、前足を握られることは良いことだと想像させることができれば、今後のしつけでも役に立ちます。
前足の握り方は力を入れずに握ることが大切であり、上下に振ることもしないようにしましょう。
あくまでも軽く握る程度で問題ありません。
しかし、前足を握られることに不快感を感じてしまう犬もいるので、握っている際には反対の手でおやつをあげたり、褒めることを忘れないようにしましょう。
また、いつまでも握り続けていることもあまりよくありません。
おやつを食べている際に握るのをやめることがポイントです。
いつまでも握っていると握られている不快感を感じたまま終わってしまうので、おやつを食べている幸せ感を感じたままお手を終わらせ、良いイメージをつけるようにしましょう。
握られても不快感を感じないようになればお手を完全マスターしているといっても過言ではなく、次にしつけを教えることができたり、ブラッシングする際に暴れてしまうこともなくなります。
犬がお手を覚えない原因とは?
 お手を覚えるスピードに個体差はありますが、飼い主の教え方に問題がある可能性もあります。
教え方が間違っているのであれば正しい教え方にするだけでお手を覚えてくれる可能性も高まります。
次に、犬がお手を覚えない原因を紹介するので、当てはまることがあるのであれば改善しましょう。
お手を覚えるスピードに個体差はありますが、飼い主の教え方に問題がある可能性もあります。
教え方が間違っているのであれば正しい教え方にするだけでお手を覚えてくれる可能性も高まります。
次に、犬がお手を覚えない原因を紹介するので、当てはまることがあるのであれば改善しましょう。
コマンド(指示)が不統一だから
犬への支持が不統一であれば中々覚えてくれない場合が多いです。
指示が不統一であることは犬にとっても戸惑う原因であるため、何かをしなければいけないことを感じ取っていてもうまく伝わっていない可能性があります。
お手の場合は、言葉で指示するようになりますが、お手という言葉で指示をしたのであれば最後までお手という言葉で教えるようにしましょう。
覚えが悪いため、ハンドなど違う言葉で指示してしまうとこんがらがってしまいます。
反抗期を迎えたから
 人に反抗期があるように、犬にも反抗期があります。
犬の場合は生後半年~1年頃が反抗期を迎える目安となっています。
反抗期では言うことを聞いてくれないことがほとんどであるため、反抗期の時にお手などのしつけを教えることはあまり効率的とは言えません。
しつけは幼いころから覚えさせるほうが素直に覚えてくれる可能性はありますが、反抗期を迎えてしまっているのであれば反抗期が収まるまで待つようにしましょう。
どうしても早く教えたいのであれば焦らずにしつけをさせることが大切です。
人に反抗期があるように、犬にも反抗期があります。
犬の場合は生後半年~1年頃が反抗期を迎える目安となっています。
反抗期では言うことを聞いてくれないことがほとんどであるため、反抗期の時にお手などのしつけを教えることはあまり効率的とは言えません。
しつけは幼いころから覚えさせるほうが素直に覚えてくれる可能性はありますが、反抗期を迎えてしまっているのであれば反抗期が収まるまで待つようにしましょう。
どうしても早く教えたいのであれば焦らずにしつけをさせることが大切です。
足を触られたくないから
上記でも紹介したように犬の中には足に触れられることを嫌がる犬は意外と多いです。
お手を教える際には足に触る必要があるので、飼い主は知らない間に嫌がることを犬にしてしまっていることもあります。
嫌がることでも次第に慣れてくることもあるので、焦らずに時間をかけて足に触れることに慣れさせるようにしましょう。
子犬のころから足に触れることをしていれば嫌がられる可能性も低いので、子犬のころからお手を教えたり、足に触れるようにしましょう。
犬のお手でよくある質問
 犬の定番のしつけでもあるお手ですが、初めてお手を教える際や犬を初めて飼い始めたのであればさまざまなことが気になってしまいがちです。
近くに犬を飼っている人や知り合いに犬を飼っている人がいれば聞くことができますが、いないのであれば疑問を解決することもできません。
ここでは、お手に関する質問をいくつか紹介するので、参考にしてください。
犬の定番のしつけでもあるお手ですが、初めてお手を教える際や犬を初めて飼い始めたのであればさまざまなことが気になってしまいがちです。
近くに犬を飼っている人や知り合いに犬を飼っている人がいれば聞くことができますが、いないのであれば疑問を解決することもできません。
ここでは、お手に関する質問をいくつか紹介するので、参考にしてください。
犬にお手を教えるのはいつからがベスト?
まず最初に疑問になりやすいのがいつお手を教えることがベストかです。
教えるタイミングが基本的にはいつからでもよいですが、子犬のころからしつけを教えることで覚えやすく、犬との信頼関係も築けやすいメリットがあります。
しかし、子犬の時には生活に必要なマナーや健康をチェックする方法など子犬または飼い主にも覚えておかなければならないことが多いので、まずはそれらのことができるようになってからお手のしつけをスタートさせましょう。
お手を嫌がる場合はどうすれば良い?
 上記でも紹介したように足に触れられることを嫌がる場合が多く、お手を教える際にも嫌がります。
足に触れられることに嫌がられる原因は不快感を感じているか触られていることに慣れていないかのどちらかである可能性が高いです。
触られることに慣れていないのであれば足に触れる回数を増やしていき、慣れさせるようにしましょう。
不快感を感じていることが原因であれば足に触れている間におやつなどを与えて、足に触れられることは不快なことではないことを覚えさせるようにしましょう。
上記でも紹介したように足に触れられることを嫌がる場合が多く、お手を教える際にも嫌がります。
足に触れられることに嫌がられる原因は不快感を感じているか触られていることに慣れていないかのどちらかである可能性が高いです。
触られることに慣れていないのであれば足に触れる回数を増やしていき、慣れさせるようにしましょう。
不快感を感じていることが原因であれば足に触れている間におやつなどを与えて、足に触れられることは不快なことではないことを覚えさせるようにしましょう。
まとめ
犬にお手を覚えさせることは他のしつけと違って簡単ではありますが、教えることに慣れていないと時間がかかってしまうことも多いです。
しかし、教えることに焦ってしまうことは逆効果であるため、焦らずに教えることが何よりも大切です。
 犬の老化のサインはいろいろあります。
その一つがトイレの失敗です。
老化によって身体機能が衰え、排泄の体勢でよろけたり少し間に合わなかったり。
トイレシートに乗っているつもりがはみ出していることもあります。
毎日の運動で筋力を維持することやトイレシートの工夫などで飼い主がサポートできることも多いです。
ただ人間と同じで、どうしようもない老化現象の一つでもあり、逆に長生きの証でもあるのです。
また、そこには病気が隠れている場合もありますし、頻繁な尿漏れでは対策が必要となります。
ここでは、老犬に多い排尿に関係する病気や尿漏れ対策についてまとめてみました。
犬の老化のサインはいろいろあります。
その一つがトイレの失敗です。
老化によって身体機能が衰え、排泄の体勢でよろけたり少し間に合わなかったり。
トイレシートに乗っているつもりがはみ出していることもあります。
毎日の運動で筋力を維持することやトイレシートの工夫などで飼い主がサポートできることも多いです。
ただ人間と同じで、どうしようもない老化現象の一つでもあり、逆に長生きの証でもあるのです。
また、そこには病気が隠れている場合もありますし、頻繁な尿漏れでは対策が必要となります。
ここでは、老犬に多い排尿に関係する病気や尿漏れ対策についてまとめてみました。
 トイレの失敗は増えてくると、まず洗濯掃除が大変!と感じてしまいがちです。
でも排泄は健康のバロメーター。
その回数や状態などはとても重要なもので、病気のサインになることも多いのです。
トイレシートをチェックし、色や量などいつもと違うことを発見できるようになっておきましょう。
尿頻度が増えた、あるいは減った時に考えられる病気について説明します。
トイレの失敗は増えてくると、まず洗濯掃除が大変!と感じてしまいがちです。
でも排泄は健康のバロメーター。
その回数や状態などはとても重要なもので、病気のサインになることも多いのです。
トイレシートをチェックし、色や量などいつもと違うことを発見できるようになっておきましょう。
尿頻度が増えた、あるいは減った時に考えられる病気について説明します。
 尿閉とは、膀胱に尿が溜まっていても排尿できなくなる状態のことを指します。
メス犬よりオス犬に多いとされます。
排尿後でも下腹部が膨らんでいたり、ポタポタと尿漏れがあったり、寝ている場所が濡れていたりします。
代表的な病気では会陰ヘルニア、尿結石などがあり、尿路感染症への注意も必要です。
膀胱に尿が溜まっているかどうかは飼い主さんには判断しづらいので、症状があれば獣医の診察検査を受けましょう。
まずは適切に排尿させてあげ、病気の有無も確認してもらいましょう。
尿閉とは、膀胱に尿が溜まっていても排尿できなくなる状態のことを指します。
メス犬よりオス犬に多いとされます。
排尿後でも下腹部が膨らんでいたり、ポタポタと尿漏れがあったり、寝ている場所が濡れていたりします。
代表的な病気では会陰ヘルニア、尿結石などがあり、尿路感染症への注意も必要です。
膀胱に尿が溜まっているかどうかは飼い主さんには判断しづらいので、症状があれば獣医の診察検査を受けましょう。
まずは適切に排尿させてあげ、病気の有無も確認してもらいましょう。
 老犬のトイレの失敗はやはり辛いものです。
飼い主さんにとっては片付けが大変で、ついイライラしてしまった経験をもつひともいるでしょう。
でも、愛犬が過ごす時間はそう長くはないのかもしれません。
今までたくさん癒やしをくれた愛犬への最後のお世話です。
できるだけお世話が楽にできて、犬も飼い主も快適に過ごせるような工夫を考えてみましょう。
老犬のトイレの失敗はやはり辛いものです。
飼い主さんにとっては片付けが大変で、ついイライラしてしまった経験をもつひともいるでしょう。
でも、愛犬が過ごす時間はそう長くはないのかもしれません。
今までたくさん癒やしをくれた愛犬への最後のお世話です。
できるだけお世話が楽にできて、犬も飼い主も快適に過ごせるような工夫を考えてみましょう。
 老犬のお漏らしには、老化での筋肉低下によるものと病気のサインがあります。
トイレの場所を間違える場合は認知症の疑いもあります。
よく観察して少しでも心配があるようなら、適切に病院の診察を受けましょう。
以前より寿命が伸び、長生きできるようになった犬のお世話は大変ですが、その分一緒にいられる時間は愛おしいものです。
お漏らしにイライラせず、犬も飼い主さんも快適に楽しい時間が続くような対策を工夫していきたいですね。
老犬のお漏らしには、老化での筋肉低下によるものと病気のサインがあります。
トイレの場所を間違える場合は認知症の疑いもあります。
よく観察して少しでも心配があるようなら、適切に病院の診察を受けましょう。
以前より寿命が伸び、長生きできるようになった犬のお世話は大変ですが、その分一緒にいられる時間は愛おしいものです。
お漏らしにイライラせず、犬も飼い主さんも快適に楽しい時間が続くような対策を工夫していきたいですね。  犬は10歳がひとつの節目と言われますが、シニア犬を飼っている方に聞くと、13歳も節目だと話す方が多くいます。
それまで元気に過ごしてきていたのに、10歳や13歳を迎えた頃から病気が増えたり体調を崩しやすくなったりするようですね。
獣医学の進歩により犬の寿命は延びて来ていますが、現在の平均寿命は何年ほどになるのでしょうか。
人間の4~7倍の早さで年を重ねる犬達の平均寿命を、体の大きさごとにご紹介します。
犬は10歳がひとつの節目と言われますが、シニア犬を飼っている方に聞くと、13歳も節目だと話す方が多くいます。
それまで元気に過ごしてきていたのに、10歳や13歳を迎えた頃から病気が増えたり体調を崩しやすくなったりするようですね。
獣医学の進歩により犬の寿命は延びて来ていますが、現在の平均寿命は何年ほどになるのでしょうか。
人間の4~7倍の早さで年を重ねる犬達の平均寿命を、体の大きさごとにご紹介します。
 平均寿命は20歳に満たない犬ですが、世界にはギネス記録を持つ超長寿の犬が存在します。
どんな犬種でどのように生活をしていた犬なのでしょうか。
その犬の暮らした環境から、長寿の秘訣を探ってみましょう。
平均寿命は20歳に満たない犬ですが、世界にはギネス記録を持つ超長寿の犬が存在します。
どんな犬種でどのように生活をしていた犬なのでしょうか。
その犬の暮らした環境から、長寿の秘訣を探ってみましょう。
 犬は7歳くらいから老化の兆しが見え始め、ライフステージも成犬から「シニア」と呼ばれる時期に入ります。
もし犬が20歳を超えた場合、人間の年齢に換算すると96歳!
人間だとしてもかなりのご長寿さんだと言えます。
ちなみに犬全体の平均寿命を12~16歳ほどだとすると、人間では64歳~80歳になります。日本人の平均寿命は、男性81歳、女性が87歳なので、犬の方が少し平均寿命は短いようです。
でも犬の平均寿命は少しずつ延びています。いつかは人間に追いつく日もくるかもしれませんね。
犬は7歳くらいから老化の兆しが見え始め、ライフステージも成犬から「シニア」と呼ばれる時期に入ります。
もし犬が20歳を超えた場合、人間の年齢に換算すると96歳!
人間だとしてもかなりのご長寿さんだと言えます。
ちなみに犬全体の平均寿命を12~16歳ほどだとすると、人間では64歳~80歳になります。日本人の平均寿命は、男性81歳、女性が87歳なので、犬の方が少し平均寿命は短いようです。
でも犬の平均寿命は少しずつ延びています。いつかは人間に追いつく日もくるかもしれませんね。
 治せる病気が増えてきたことで全体の平均寿命が延びてきているものの、ギネス記録にあるブルーイーのように驚異的な長生きをする犬には、その心の在り方にも理由があるように思います。
そのように考えると、犬が生きるということは時間の長さよりもいかに毎日を楽しくイキイキと過ごせるかということの方が大切なのかもしれません。
そして、その延長線上に「長寿」というおまけがついてきたら、本当に幸せですね。
治せる病気が増えてきたことで全体の平均寿命が延びてきているものの、ギネス記録にあるブルーイーのように驚異的な長生きをする犬には、その心の在り方にも理由があるように思います。
そのように考えると、犬が生きるということは時間の長さよりもいかに毎日を楽しくイキイキと過ごせるかということの方が大切なのかもしれません。
そして、その延長線上に「長寿」というおまけがついてきたら、本当に幸せですね。
 ペットを飼うようになれば必然的に名前を付けるようになります。
名前は飼い主が自由に決める場合が多いですが、ペットに付けてはいけない名前があることを知っているでしょうか。
次に、ペットにつけてはいけない名前を紹介するので、新しくペットを飼おうと考えている人や子供が産まれた際に名前付けをする際に参考にしてください。
ペットを飼うようになれば必然的に名前を付けるようになります。
名前は飼い主が自由に決める場合が多いですが、ペットに付けてはいけない名前があることを知っているでしょうか。
次に、ペットにつけてはいけない名前を紹介するので、新しくペットを飼おうと考えている人や子供が産まれた際に名前付けをする際に参考にしてください。
 長すぎる名前をペットにつけることもおすすめできません。
5文字以上で長い名前となってしまうので、長くても4文字以内にすることをおすすめします。
長い名前はペットが聞き取りにくいデメリットがあり、中々名前を呼ばれていることを認識することができません。
また、長い名前は飼い主や家族も呼ぶ際に面倒と感じてしまう原因となってしまいます。
長い名前でも最終的には略して呼ぶようになってしまうことも少なくありません。
長すぎる名前をペットにつけることもおすすめできません。
5文字以上で長い名前となってしまうので、長くても4文字以内にすることをおすすめします。
長い名前はペットが聞き取りにくいデメリットがあり、中々名前を呼ばれていることを認識することができません。
また、長い名前は飼い主や家族も呼ぶ際に面倒と感じてしまう原因となってしまいます。
長い名前でも最終的には略して呼ぶようになってしまうことも少なくありません。
 現在の日本にはさまざまな外国人が住んでいるため、宗教や信仰は多種多様となっています。
そのため、宗教や信仰に関する名前をペットにつけてしまうと誤解を招いてしまうこともあります。
名前に採用した言葉がどのような意味なのかをしっかり把握してから名前にするのであればある程度誤解を招いたり、トラブルを防ぐこともできますが、よほどの理由がない限りは宗教や信仰に関する名前をつけることはおすすめできません。
例えばある宗教で神とされている名前をペットの名前にしてしまうと、信仰心の強い人であれば神の名前を動物につけることは許されないことだと考えることもあります。
現在の日本にはさまざまな外国人が住んでいるため、宗教や信仰は多種多様となっています。
そのため、宗教や信仰に関する名前をペットにつけてしまうと誤解を招いてしまうこともあります。
名前に採用した言葉がどのような意味なのかをしっかり把握してから名前にするのであればある程度誤解を招いたり、トラブルを防ぐこともできますが、よほどの理由がない限りは宗教や信仰に関する名前をつけることはおすすめできません。
例えばある宗教で神とされている名前をペットの名前にしてしまうと、信仰心の強い人であれば神の名前を動物につけることは許されないことだと考えることもあります。
 犬の名前を決める際に悩んでしまうことも多いのではないでしょうか。
定番の名前をつけることもできますが、名前が被ってしまうリスクもあるため、どうしても深く考えてしまいがちです。
次に、犬の名前を決める際のポイントを4つ紹介します。
犬の名前決めで悩んでしまっている人は参考にしてください。
犬の名前を決める際に悩んでしまうことも多いのではないでしょうか。
定番の名前をつけることもできますが、名前が被ってしまうリスクもあるため、どうしても深く考えてしまいがちです。
次に、犬の名前を決める際のポイントを4つ紹介します。
犬の名前決めで悩んでしまっている人は参考にしてください。
 混同する名前は避けるようにしましょう。
多頭飼いする際にお揃い感のある名前をつけたいと考える場合も多く、飼い主からすれば呼びやすく思えやすいメリットがあります。
しかし、犬にとっては似ている発音になってしまうため、自分が呼ばれているのかどうか判断しにくくなってしまうデメリットがあります。
呼ばれているか判断できないような名前は今後飼っていく中やしつけをする際に大きな弊害になってしまいます。
そのため、多頭飼いしている場合は違う名前をつけるようにしましょう。
混同する名前は避けるようにしましょう。
多頭飼いする際にお揃い感のある名前をつけたいと考える場合も多く、飼い主からすれば呼びやすく思えやすいメリットがあります。
しかし、犬にとっては似ている発音になってしまうため、自分が呼ばれているのかどうか判断しにくくなってしまうデメリットがあります。
呼ばれているか判断できないような名前は今後飼っていく中やしつけをする際に大きな弊害になってしまいます。
そのため、多頭飼いしている場合は違う名前をつけるようにしましょう。
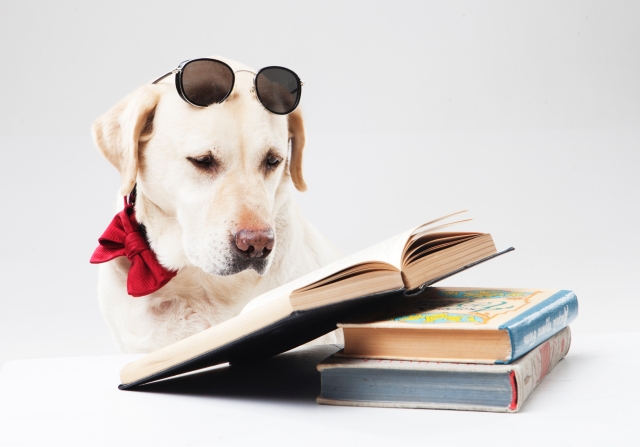 名前によっては海外で恥ずかしい思いをしてしまうこともあり、ありきたりな名前でも海外では違う意味があるため、意味を調べてから名前をつけるようにしましょう。
例えば犬の名前としてメジャーなクロやモコはスペインではお尻、鼻水という名前になってしまいます。
スペインと関りわりがないのであれば特に問題視する必要もありませんが、海外ではそういう意味があることは知っておきましょう。
また、逆に海外の言葉の響きが良いため、海外の言葉を名前にしてしまうこともありますが、後から意味を調べて恥ずかしい思いをしてしまうこともあるので、事前に名前にしようとしている言葉の意味を調べることは大切です。
名前によっては海外で恥ずかしい思いをしてしまうこともあり、ありきたりな名前でも海外では違う意味があるため、意味を調べてから名前をつけるようにしましょう。
例えば犬の名前としてメジャーなクロやモコはスペインではお尻、鼻水という名前になってしまいます。
スペインと関りわりがないのであれば特に問題視する必要もありませんが、海外ではそういう意味があることは知っておきましょう。
また、逆に海外の言葉の響きが良いため、海外の言葉を名前にしてしまうこともありますが、後から意味を調べて恥ずかしい思いをしてしまうこともあるので、事前に名前にしようとしている言葉の意味を調べることは大切です。
 セラピードッグとは、人への忠誠心と深い愛情で高齢者を始め、障害を持つ方や病気の治療を必要とする患者さんの身体と精神の機能回復の補助をする犬のことをいいます。
セラピードッグたちが患者さんの心身の状態を向きあい、リハビリに寄り添うことで記憶を取り戻したり、動かなかった手や足が動くようになる効果があります。
そのような犬を育成する法人は近年増えてきており、犬たちの個々の能力や性格を大切に育て、対象となる方々の症状に合わせた治療のケアをしてくれます。
セラピードッグとは、人への忠誠心と深い愛情で高齢者を始め、障害を持つ方や病気の治療を必要とする患者さんの身体と精神の機能回復の補助をする犬のことをいいます。
セラピードッグたちが患者さんの心身の状態を向きあい、リハビリに寄り添うことで記憶を取り戻したり、動かなかった手や足が動くようになる効果があります。
そのような犬を育成する法人は近年増えてきており、犬たちの個々の能力や性格を大切に育て、対象となる方々の症状に合わせた治療のケアをしてくれます。
 ここ数年セラピードッグという言葉をよく耳にするようにはなりましたが、一体どんな仕事をするのかまで把握している方は少ないのではないでしょうか。
そこでここではセラピー犬の仕事内容についてご紹介します。
ここ数年セラピードッグという言葉をよく耳にするようにはなりましたが、一体どんな仕事をするのかまで把握している方は少ないのではないでしょうか。
そこでここではセラピー犬の仕事内容についてご紹介します。
 動物介在療法AATとは、治療が目的ではなく、犬との触れ合いを楽しむことを中心としたレクリエーションのことを言います。
犬と一緒にレクリエーションを楽しみ、触れ合うことで情緒的に安定したり、リラックス効果やストレス解消効果が期待できるでしょう。
高齢者福祉施設の訪問やホスピスなどでよく取り入れられており、一度に大勢の人と触れ合えるメリットがあります。
また家族がいない高齢者がセラピードッグと触れ合うことで、穏やかなスキンシップの時間を持てたり、心身に大きな癒しの効果を与えることもできます。
動物介在療法AATとは、治療が目的ではなく、犬との触れ合いを楽しむことを中心としたレクリエーションのことを言います。
犬と一緒にレクリエーションを楽しみ、触れ合うことで情緒的に安定したり、リラックス効果やストレス解消効果が期待できるでしょう。
高齢者福祉施設の訪問やホスピスなどでよく取り入れられており、一度に大勢の人と触れ合えるメリットがあります。
また家族がいない高齢者がセラピードッグと触れ合うことで、穏やかなスキンシップの時間を持てたり、心身に大きな癒しの効果を与えることもできます。
 さまざまな活動をしているセラピー犬ですが、どんな犬種でも簡単にセラピー犬になれるかと言えばそうではありません。
受験資格や認定試験などがあり、それらをクリアした優秀な子がセラピー犬として活躍できるわけです。
ここでは、セラピー犬として活動する方法をご紹介します。
さまざまな活動をしているセラピー犬ですが、どんな犬種でも簡単にセラピー犬になれるかと言えばそうではありません。
受験資格や認定試験などがあり、それらをクリアした優秀な子がセラピー犬として活躍できるわけです。
ここでは、セラピー犬として活動する方法をご紹介します。
 アイコンタクトとは、文字通り人と犬が目を合わせることを言います。
これはセラピー犬だけに限らず犬を飼うとなった以上、しつけの基礎であり、主従関係を築くためにもアイコンタクトは非常に重要と言えるでしょう。
犬はアイコンタクトを通して信頼関係を深め、相手の気持ちや体調を感じ取ったりするので、セラピー犬になるために大前提の条件と言えるでしょう。
アイコンタクトとは、文字通り人と犬が目を合わせることを言います。
これはセラピー犬だけに限らず犬を飼うとなった以上、しつけの基礎であり、主従関係を築くためにもアイコンタクトは非常に重要と言えるでしょう。
犬はアイコンタクトを通して信頼関係を深め、相手の気持ちや体調を感じ取ったりするので、セラピー犬になるために大前提の条件と言えるでしょう。
 主に、高齢者と同速歩行することを言います。
特に遅い歩行に合わせる訓練で、杖をついてゆっくり歩き犬に速度を理解させます。
また、中には棒で虐待を受けていた犬がセラピー犬になる場合もあります。
過去に棒で叩かれたことがある場合は、杖を怖がるのでそれを一緒に乗り越えるのもトレーニングの一つです。
速度だけではなく、不規則な動きにも合わせられるようにするため、高齢の方や杖をついて歩く方はもちろん、ケガや病気の後遺症がある方に合わせて歩く訓練も行います。
主に、高齢者と同速歩行することを言います。
特に遅い歩行に合わせる訓練で、杖をついてゆっくり歩き犬に速度を理解させます。
また、中には棒で虐待を受けていた犬がセラピー犬になる場合もあります。
過去に棒で叩かれたことがある場合は、杖を怖がるのでそれを一緒に乗り越えるのもトレーニングの一つです。
速度だけではなく、不規則な動きにも合わせられるようにするため、高齢の方や杖をついて歩く方はもちろん、ケガや病気の後遺症がある方に合わせて歩く訓練も行います。
 セラピー犬は、一般の家庭で生活している家庭顕から保護犬までどんな子でも目指すことは可能です。
セラピー犬の適正として、人が好きであること、人見知りをしないこと、他の動物を警戒しないこと、初めての場所や大きな音を怖がらないこと、基本のしつけが完璧であること、健康であることなどが求められます。
セラピー犬として活動できる年齢は、団体によって異なりますが、成犬(月齢8か月~1歳以上)が基準となっています。
特に適している犬種はありませんが、人が大好き、優しい、温厚という面から考えると、
大型犬ではゴールデンレトリバー、ラブラドールレトリバー、小型犬ではトイプードルやミニチュアダックスフンドなどがセラピー犬として多く活躍しているのが現状です。
セラピー犬は、一般の家庭で生活している家庭顕から保護犬までどんな子でも目指すことは可能です。
セラピー犬の適正として、人が好きであること、人見知りをしないこと、他の動物を警戒しないこと、初めての場所や大きな音を怖がらないこと、基本のしつけが完璧であること、健康であることなどが求められます。
セラピー犬として活動できる年齢は、団体によって異なりますが、成犬(月齢8か月~1歳以上)が基準となっています。
特に適している犬種はありませんが、人が大好き、優しい、温厚という面から考えると、
大型犬ではゴールデンレトリバー、ラブラドールレトリバー、小型犬ではトイプードルやミニチュアダックスフンドなどがセラピー犬として多く活躍しているのが現状です。
 最近の実験でアニマルセラピーを受けると赤ちゃんに母乳をあげる時に出されるオキシトシン(愛情ホルモン)が分泌されていることが判明しています。
この研究からセラピー犬は人に癒しを与える効果があると実証され、大きく分けると人間に3つの効果をもたらせてくれているのでここではその3つの効果についてご紹介します。
最近の実験でアニマルセラピーを受けると赤ちゃんに母乳をあげる時に出されるオキシトシン(愛情ホルモン)が分泌されていることが判明しています。
この研究からセラピー犬は人に癒しを与える効果があると実証され、大きく分けると人間に3つの効果をもたらせてくれているのでここではその3つの効果についてご紹介します。
 社会的効果とは、孤立や疎外感を感じていた方が自ら社会に出られるようになり人とコミュニケーションを取ろうとする効果のことです。
実際にアニマルセラピーを導入している介護施設では、セラピー犬が間に入ることで周りとなかなか会話ができなかった方が積極的に話せるようになることがあります。
また、引きこもり外出が苦手な場合、セラピー犬に会うという動機づけをすることで社会参加を後押しすることもできるでしょう。
社会的効果とは、孤立や疎外感を感じていた方が自ら社会に出られるようになり人とコミュニケーションを取ろうとする効果のことです。
実際にアニマルセラピーを導入している介護施設では、セラピー犬が間に入ることで周りとなかなか会話ができなかった方が積極的に話せるようになることがあります。
また、引きこもり外出が苦手な場合、セラピー犬に会うという動機づけをすることで社会参加を後押しすることもできるでしょう。
 去勢手術をすることによって猫の性格が変わることはありません。
しかし、去勢をすることによって性ホルモンが分泌されなくなるので、スプレー行動や鳴くなどの性ホルモンの影響による行動は減ってきます。
また、攻撃的だった猫の行動が和らぐなどのケースもみられますが、去勢手術をすることによる変化には個体差があるので、必ず性格が変わるとは言えません。
去勢手術をすることによって猫の性格が変わることはありません。
しかし、去勢をすることによって性ホルモンが分泌されなくなるので、スプレー行動や鳴くなどの性ホルモンの影響による行動は減ってきます。
また、攻撃的だった猫の行動が和らぐなどのケースもみられますが、去勢手術をすることによる変化には個体差があるので、必ず性格が変わるとは言えません。
 去勢手術を行うことで発情期に交尾ができないというストレスを感じなくてよくなるためストレスが減り、オス猫はのんびりゆったりと生活することができます。
そのためベッタリとくっついて甘えてくることも少なくありません。
また、早くに去勢をすると精神的に成熟することもなく、子猫のころの性格が残り甘えん坊になりやすいともいわれています。
去勢手術を行うことで発情期に交尾ができないというストレスを感じなくてよくなるためストレスが減り、オス猫はのんびりゆったりと生活することができます。
そのためベッタリとくっついて甘えてくることも少なくありません。
また、早くに去勢をすると精神的に成熟することもなく、子猫のころの性格が残り甘えん坊になりやすいともいわれています。
 オス猫が去勢手術をすることで身体に負担がかかり、術前・術後の体調変化には注意が必要です。
精神的な負担も多く、家に帰ったとたんに落ち着きのない行動をしたり、隅に隠れてしばらく出てこないこともあるでしょう。
身体の調子は少しずつ回復していきますので、そっとしておいてあげてください。
オス猫が去勢手術をすることで身体に負担がかかり、術前・術後の体調変化には注意が必要です。
精神的な負担も多く、家に帰ったとたんに落ち着きのない行動をしたり、隅に隠れてしばらく出てこないこともあるでしょう。
身体の調子は少しずつ回復していきますので、そっとしておいてあげてください。
 去勢手術は子孫を望まないことや病気を予防するためには大切なことですが、猫にとってはとても怖い体験をしたことになります。
そのため、去勢手術後の猫は心身ともにかなりのストレスを受けていることもあり、今までと違う行動をとることもあります。
特に、家に着いたとたんに部屋の隅に隠れようとすることも、そんな時は無理やり引きずりだしたりせずに、落ち着くまで見守ってあげましょう。
去勢手術は子孫を望まないことや病気を予防するためには大切なことですが、猫にとってはとても怖い体験をしたことになります。
そのため、去勢手術後の猫は心身ともにかなりのストレスを受けていることもあり、今までと違う行動をとることもあります。
特に、家に着いたとたんに部屋の隅に隠れようとすることも、そんな時は無理やり引きずりだしたりせずに、落ち着くまで見守ってあげましょう。
 オス猫に去勢手術をすることで攻撃性が緩和されたり、病気の予防ができたりとさまざまなメリットがあります。
でも逆にデメリットもあります。
どんなデメリットがあるのでしょうか?
ここでは具体的なデメリットを説明します。
オス猫に去勢手術をすることで攻撃性が緩和されたり、病気の予防ができたりとさまざまなメリットがあります。
でも逆にデメリットもあります。
どんなデメリットがあるのでしょうか?
ここでは具体的なデメリットを説明します。
 生殖器を取り除いてしまう手術なので、当たり前のことですが、繁殖をすることができません。
この子の子孫を育てたいと思うのなら、去勢手術をするのか、しないのか、手術をするのならいつするのか、よく考え、検討し、計画的に進めましょう。
生殖器を取り除いてしまう手術なので、当たり前のことですが、繁殖をすることができません。
この子の子孫を育てたいと思うのなら、去勢手術をするのか、しないのか、手術をするのならいつするのか、よく考え、検討し、計画的に進めましょう。
 コストコドックフードのカークランドでは、さまざまな商品が販売されています。
たくさんあるので購入する際に悩んでしまうこともあります。
次に、カークランドで販売されているおすすめの商品や人気商品を紹介します。
コストパフォーマンスに優れている場合が多いので、安くフードを購入したい人にもおすすめできます。
コストコドックフードのカークランドでは、さまざまな商品が販売されています。
たくさんあるので購入する際に悩んでしまうこともあります。
次に、カークランドで販売されているおすすめの商品や人気商品を紹介します。
コストパフォーマンスに優れている場合が多いので、安くフードを購入したい人にもおすすめできます。
 コストコのドックフードカークランドにはどのようなメリットがあるのかわからない人もいるのではないでしょうか。
メリットを知ることで他のドックフードとは違う部分を見つけることもできます。
次に、カークランドのメリットを紹介するので参考にしてください。
コストコのドックフードカークランドにはどのようなメリットがあるのかわからない人もいるのではないでしょうか。
メリットを知ることで他のドックフードとは違う部分を見つけることもできます。
次に、カークランドのメリットを紹介するので参考にしてください。
 一般的なドックフードは一般的に1㎏前後で販売されていることが多いです。
しかし、カークランドで販売されているドックフードは9~18㎏が主流となっています。
さまざまな商品にも言えることですが、少量ずつ購入するよりも一度にまとめて購入するほうが少し安く購入することができます。
また、頻繁に購入する手間も省けます。
一般的なペット関係の店では大容量タイプは少なく、購入したいドックフードを大容量で購入できない場合もありますが、カークランドであればそのような不満は芽生えません。
一般的なドックフードは一般的に1㎏前後で販売されていることが多いです。
しかし、カークランドで販売されているドックフードは9~18㎏が主流となっています。
さまざまな商品にも言えることですが、少量ずつ購入するよりも一度にまとめて購入するほうが少し安く購入することができます。
また、頻繁に購入する手間も省けます。
一般的なペット関係の店では大容量タイプは少なく、購入したいドックフードを大容量で購入できない場合もありますが、カークランドであればそのような不満は芽生えません。
 コストコドックフードでもあるカークランドはにはメリットもありますが、デメリットも存在しています。
そのため、メリットだけを把握して購入してしまうと後悔してしまうこともあります。
次に、カークランドのデメリットを紹介するので参考にしてください。
コストコドックフードでもあるカークランドはにはメリットもありますが、デメリットも存在しています。
そのため、メリットだけを把握して購入してしまうと後悔してしまうこともあります。
次に、カークランドのデメリットを紹介するので参考にしてください。
 カークランドのフードにはビートパルプという物が使用されています。
ビートパルプとは、サトウダイコンから砂糖の成分を搾り取った後のカスであり、普通であれば廃棄するものです。
また、ビートパルプは便を固くしてしまう効果があり、摂取しすぎてしまうと便秘になる恐れもあります。
ビートパルプの成分はもともと犬に不必要ではありますが、かさ増しのために使用されているだけです。
カークランドのフードが大容量であり、低価格で販売できている理由は、原材料が廃棄レベルの元を使用してかさ増しまでされているからと言っても過言ではありません。
カークランドのフードにはビートパルプという物が使用されています。
ビートパルプとは、サトウダイコンから砂糖の成分を搾り取った後のカスであり、普通であれば廃棄するものです。
また、ビートパルプは便を固くしてしまう効果があり、摂取しすぎてしまうと便秘になる恐れもあります。
ビートパルプの成分はもともと犬に不必要ではありますが、かさ増しのために使用されているだけです。
カークランドのフードが大容量であり、低価格で販売できている理由は、原材料が廃棄レベルの元を使用してかさ増しまでされているからと言っても過言ではありません。
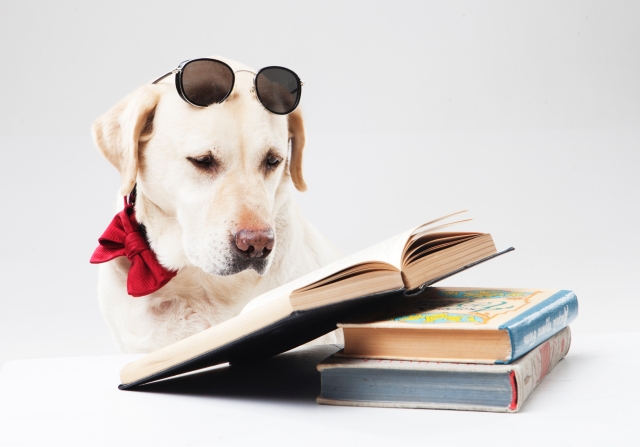 カークランドには上記で紹介したようにコスパに優れているメリットと健康面で不安な要素があるデメリットがあります。
そのため、購入者でもある飼い主にとっては購入してもよいのか悩んでしまいがちです。
次に、カークランドについてよくある質問に対して解説しているので参考にしてください。
カークランドには上記で紹介したようにコスパに優れているメリットと健康面で不安な要素があるデメリットがあります。
そのため、購入者でもある飼い主にとっては購入してもよいのか悩んでしまいがちです。
次に、カークランドについてよくある質問に対して解説しているので参考にしてください。
 カークランドの品質は充分問題ないレベルと言えるでしょう。
ただし、メリットでもある大容量なことがデメリットになってしまうこともあり、保存期間には注意しましょう。
フードには適した消費期限があり、基本的に開封後一か月以内に使い切る必要があります。
開封してから徐々に酸化していき、次第に品質も劣化してしまいます。
一か月以上たってしまうと品質は格段と劣化しており、廃棄することを覚悟しなければなりません。
そのため、購入する前に一か月で食べきることができるのかを考えましょう。
カークランドの品質は充分問題ないレベルと言えるでしょう。
ただし、メリットでもある大容量なことがデメリットになってしまうこともあり、保存期間には注意しましょう。
フードには適した消費期限があり、基本的に開封後一か月以内に使い切る必要があります。
開封してから徐々に酸化していき、次第に品質も劣化してしまいます。
一か月以上たってしまうと品質は格段と劣化しており、廃棄することを覚悟しなければなりません。
そのため、購入する前に一か月で食べきることができるのかを考えましょう。
 グレインフリーという言葉を聞いたことはないでしょうか。
最近ペットフードなどに記載されている言葉ですが、どのようなペットフードであるか理解できていない人も多いです。
グレインとは穀物のことであり、小麦や米のことを示しています。
そのため、グレインフリーとは穀物が一切含まれていないことです。
ちなみに似たような言葉にグルテンフリーというものもありますが、グルテンとはタンパク質のことを示しているので、主に麦のことを示しています。
グルテンフリーは麦のタンパク質がなく、グレインフリーは穀物自体が含まれていないことになります。
グレインフリーという言葉を聞いたことはないでしょうか。
最近ペットフードなどに記載されている言葉ですが、どのようなペットフードであるか理解できていない人も多いです。
グレインとは穀物のことであり、小麦や米のことを示しています。
そのため、グレインフリーとは穀物が一切含まれていないことです。
ちなみに似たような言葉にグルテンフリーというものもありますが、グルテンとはタンパク質のことを示しているので、主に麦のことを示しています。
グルテンフリーは麦のタンパク質がなく、グレインフリーは穀物自体が含まれていないことになります。
 グレインフリーのペットフードが最近販売され始めている理由はペットに良いことがあるからです。
次に、グレインフリーがなぜペットに良いのかを詳しく紹介していきます。
飼っているペットにあっているのであればフレインフリーのペットフードに変えてみてはいかがでしょうか。
グレインフリーのペットフードが最近販売され始めている理由はペットに良いことがあるからです。
次に、グレインフリーがなぜペットに良いのかを詳しく紹介していきます。
飼っているペットにあっているのであればフレインフリーのペットフードに変えてみてはいかがでしょうか。
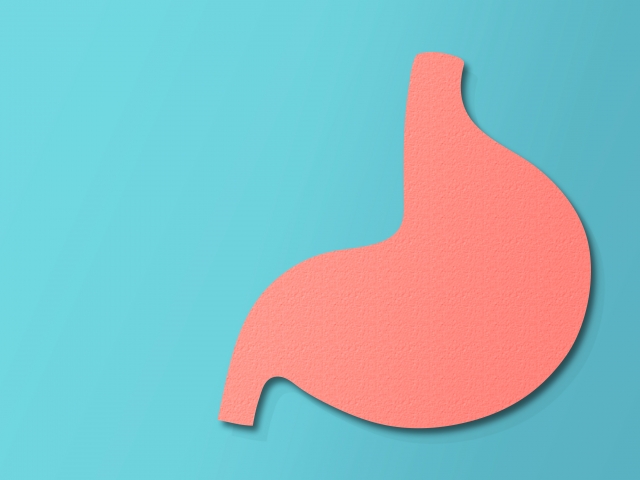 犬にとってグレインフリーのフードは消化しやすいので、胃や腸に負担をかけることがありません。
人と犬では体の構造が違い、穀物を消化するために必要な酵素でもあるアミラーゼを少ししか分泌することができません。
一見犬は雑食性と思われ、実際に肉も野菜も食べることができます。
しかし、犬の先祖は肉食の狼であるため、雑食ではありますが、限りなく肉食に近いと言えます。
また、穀物をすり潰すような歯がなく、消化しやすいようにして飲み込むことができないことも消化しにくい原因となっています。
犬にとってグレインフリーのフードは消化しやすいので、胃や腸に負担をかけることがありません。
人と犬では体の構造が違い、穀物を消化するために必要な酵素でもあるアミラーゼを少ししか分泌することができません。
一見犬は雑食性と思われ、実際に肉も野菜も食べることができます。
しかし、犬の先祖は肉食の狼であるため、雑食ではありますが、限りなく肉食に近いと言えます。
また、穀物をすり潰すような歯がなく、消化しやすいようにして飲み込むことができないことも消化しにくい原因となっています。
 グレインフリーにはメリットとなる部分もありますが、デメリットになってしまう部分もあります。
そのため、メリットだけを重視してグレインフリーのフードを与えてしまうとデメリット部分か重なってしまい、犬に悪影響を与えてしまうことも考えられます。
次に、グレインフリーのデメリットを紹介するので上記で紹介したメリットと同じように理解しておきましょう。
グレインフリーにはメリットとなる部分もありますが、デメリットになってしまう部分もあります。
そのため、メリットだけを重視してグレインフリーのフードを与えてしまうとデメリット部分か重なってしまい、犬に悪影響を与えてしまうことも考えられます。
次に、グレインフリーのデメリットを紹介するので上記で紹介したメリットと同じように理解しておきましょう。
 グレインフリーは販売価格が高い場合が多いです。
グレインが含まれている一般的なフードの場合は原料価格が非常に安い大豆やトウモロコシのカスや小麦でカサ増しされているので、低価格での販売が可能となっています。
しかし、グレインフリーでは当然カサ増しで使用していた小麦などが使用することができないため、結果的に高額になってしまいます。
愛犬は家族同然ではありますが、販売価格が高いことは購入時にネックになってしまうことも少なくありません。
グレインフリーは販売価格が高い場合が多いです。
グレインが含まれている一般的なフードの場合は原料価格が非常に安い大豆やトウモロコシのカスや小麦でカサ増しされているので、低価格での販売が可能となっています。
しかし、グレインフリーでは当然カサ増しで使用していた小麦などが使用することができないため、結果的に高額になってしまいます。
愛犬は家族同然ではありますが、販売価格が高いことは購入時にネックになってしまうことも少なくありません。
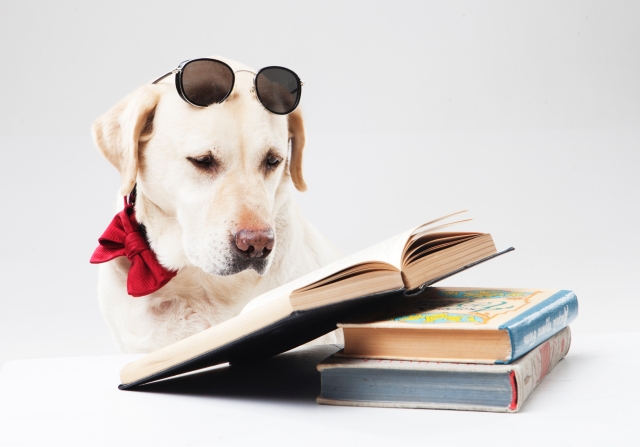 上記でも一部紹介しましたが、グレインフリーとグルテンフリーという似た言葉があります。
言葉は似ていますが、示していることは全く違いので、把握しておきましょう。
グレインフリーは穀物全般が含まれていない物を示しているのに対して、グルテンフリーはライ麦や小麦、大麦など麦類が含まれていないことを示しています。
グルテンフリーの場合は麦類にアレルギーがある犬におすすめです。
そのため、グルテンフリーには麦類の穀物は含まれていませんが、麦以外の穀物は含まれています。
上記でも一部紹介しましたが、グレインフリーとグルテンフリーという似た言葉があります。
言葉は似ていますが、示していることは全く違いので、把握しておきましょう。
グレインフリーは穀物全般が含まれていない物を示しているのに対して、グルテンフリーはライ麦や小麦、大麦など麦類が含まれていないことを示しています。
グルテンフリーの場合は麦類にアレルギーがある犬におすすめです。
そのため、グルテンフリーには麦類の穀物は含まれていませんが、麦以外の穀物は含まれています。
 猫は四足歩行が自然な姿ですが、たまに人間のように二足歩行で歩く子がいます。
突然二足歩行をし出すため、飼い主さんはびっくりするかもしれませんね。
ここでは、なぜ猫が二足歩行するのか理由についてご紹介します。
猫は四足歩行が自然な姿ですが、たまに人間のように二足歩行で歩く子がいます。
突然二足歩行をし出すため、飼い主さんはびっくりするかもしれませんね。
ここでは、なぜ猫が二足歩行するのか理由についてご紹介します。
 猫は格闘モードになった時、相手を威嚇するために二足足で立つことがあります。
猫たちの世界では体を大きく見せることで自分を優位に見せるため相手への威嚇行動と言えるでしょう。
相手の方が自分よりも強い雰囲気を察した相手はびっくりして、戦意喪失するといった感じですね、
四足足で地面に立つ時、比較してみると、二足足で立つ時は体のサイズが大きく見えますよね。
まるで龍のように前足も上の方に広げるのでより大きく感じるでしょう。
また、後ろの二本足で立ち、前足を広げることで相手よりも素早い行動ができる体勢でもあります。
ケンカに勝つ自信がある時には、このように急に立つ行動をすることがあるようです。
猫は格闘モードになった時、相手を威嚇するために二足足で立つことがあります。
猫たちの世界では体を大きく見せることで自分を優位に見せるため相手への威嚇行動と言えるでしょう。
相手の方が自分よりも強い雰囲気を察した相手はびっくりして、戦意喪失するといった感じですね、
四足足で地面に立つ時、比較してみると、二足足で立つ時は体のサイズが大きく見えますよね。
まるで龍のように前足も上の方に広げるのでより大きく感じるでしょう。
また、後ろの二本足で立ち、前足を広げることで相手よりも素早い行動ができる体勢でもあります。
ケンカに勝つ自信がある時には、このように急に立つ行動をすることがあるようです。
 急に相手が表れたとか、大きな音がしたなど急激にびっくりするほどではないものの、ちょっとした雰囲気の変化を察して警戒することは人間でもありますよね。
猫たちは野生の勘で「なんだろう?」と周囲を警戒するときに立つことがあります。
この時は立ち上がってから周囲をキョロキョロと見渡すような仕草をします。
立つことで目の位置が上になり、より高いところから周囲を観察できるのです。
視界が広がるだけではなく、音も聞こえやすくなり異変に気付きやすいでしょう。
猫が警戒から立つのは自分を守るための習性ということになります。
急に相手が表れたとか、大きな音がしたなど急激にびっくりするほどではないものの、ちょっとした雰囲気の変化を察して警戒することは人間でもありますよね。
猫たちは野生の勘で「なんだろう?」と周囲を警戒するときに立つことがあります。
この時は立ち上がってから周囲をキョロキョロと見渡すような仕草をします。
立つことで目の位置が上になり、より高いところから周囲を観察できるのです。
視界が広がるだけではなく、音も聞こえやすくなり異変に気付きやすいでしょう。
猫が警戒から立つのは自分を守るための習性ということになります。
 トイレで用を足す時に、踏ん張るという意味で立つ猫もいます。
体から排泄物を出す行為の時、人間もですが動物も力が入るもの。
特にウンチの方は便秘などお腹の調子によっては、いつも以上に踏ん張らないといけません。
猫たちもそれは同じで、踏ん張り具合がMAXになったときに無意識で立つようなスタイルになることもあるようです。
思わず立ってしまったという感じに見えたり、トイレのフチに前足をかけて踏ん張る体勢をする子もいるでしょう。
ちょっとしたクセになっている子もいるかもしれませんね。
一生懸命に自然現象と立ち向かっている姿勢なので、声をかけたり邪魔をせずに、そっと見守ってあげましょう。
トイレで用を足す時に、踏ん張るという意味で立つ猫もいます。
体から排泄物を出す行為の時、人間もですが動物も力が入るもの。
特にウンチの方は便秘などお腹の調子によっては、いつも以上に踏ん張らないといけません。
猫たちもそれは同じで、踏ん張り具合がMAXになったときに無意識で立つようなスタイルになることもあるようです。
思わず立ってしまったという感じに見えたり、トイレのフチに前足をかけて踏ん張る体勢をする子もいるでしょう。
ちょっとしたクセになっている子もいるかもしれませんね。
一生懸命に自然現象と立ち向かっている姿勢なので、声をかけたり邪魔をせずに、そっと見守ってあげましょう。
 猫は立つことで可愛らしさを表現しているケースもあります。
確かに立つ上がるとプクっとしたお腹が見えたり、前足でお願いポーズになっていたりと、可愛いポイントが満載!
この時には、飼い主さんの気持ちを惹きつけたいという甘えん坊モード全開の時なので、コミュニケーションやスキンシップをたくさんとってあげてくださいね。
猫は基本的にツンデレな性格なので、甘えてくる姿は貴重と言えるでしょう。
猫は立つことで可愛らしさを表現しているケースもあります。
確かに立つ上がるとプクっとしたお腹が見えたり、前足でお願いポーズになっていたりと、可愛いポイントが満載!
この時には、飼い主さんの気持ちを惹きつけたいという甘えん坊モード全開の時なので、コミュニケーションやスキンシップをたくさんとってあげてくださいね。
猫は基本的にツンデレな性格なので、甘えてくる姿は貴重と言えるでしょう。
 猫は基本的に四足歩行の動物なので、二足歩行をする姿は可愛いですが、足腰に負担がかかってしまうのではと心配になってしまいますよね。
ここでは、二足歩行することで猫に負担がないのかをご紹介していきます。
猫は基本的に四足歩行の動物なので、二足歩行をする姿は可愛いですが、足腰に負担がかかってしまうのではと心配になってしまいますよね。
ここでは、二足歩行することで猫に負担がないのかをご紹介していきます。
 また、猫の後ろ足は思っている以上に発達しており、獣医師によると、猫の後ろ足は発達しており力があるため、猫にとって二足立ちは無理な姿勢ではないとのこと。
猫は非常にしなやかな動きをする動物なので、膝を曲げ伸ばし高いところからも難なくジャンプしますが、これら猫の動作に全て後ろ足やお尻の筋肉が関わっています。
そのため猫はびっくりした時や緊張している時などに力が入って体がこわばることがありますが、筋肉が緊張することは猫にとって特に問題がありません。
なので、二足立ちも猫にとっては無理な姿勢ではないということになりますね。
また、猫の後ろ足は思っている以上に発達しており、獣医師によると、猫の後ろ足は発達しており力があるため、猫にとって二足立ちは無理な姿勢ではないとのこと。
猫は非常にしなやかな動きをする動物なので、膝を曲げ伸ばし高いところからも難なくジャンプしますが、これら猫の動作に全て後ろ足やお尻の筋肉が関わっています。
そのため猫はびっくりした時や緊張している時などに力が入って体がこわばることがありますが、筋肉が緊張することは猫にとって特に問題がありません。
なので、二足立ちも猫にとっては無理な姿勢ではないということになりますね。
 ここまで猫が二足歩行で立ちあがる理由についてご紹介してきましたが、もしかするとてんかんという病気を発症している可能性もあります。
てんかんは脳の中の神経を通る電気異常によって発作が起こり、体のコントロールを失ってしまう病気です。
猫がてんかんになることは稀ですが、突然起こることもあるため、日頃からの観察が重要です。
てんかんは立つ以外にも四肢が硬直したり、痙攣したり、口から泡を吹くこともあります。
万が一、てんかん発作が起きた場合は、落ち着いて猫の周りに危ないものがないか、落下などの危険がない場所かを確かめ、発作の様子をビデオで撮影しておいてください。
ヘタに手を出すと攻撃される可能性があるため、あまり近く寄らないように発作が収まるのを待ちましょう。
ここまで猫が二足歩行で立ちあがる理由についてご紹介してきましたが、もしかするとてんかんという病気を発症している可能性もあります。
てんかんは脳の中の神経を通る電気異常によって発作が起こり、体のコントロールを失ってしまう病気です。
猫がてんかんになることは稀ですが、突然起こることもあるため、日頃からの観察が重要です。
てんかんは立つ以外にも四肢が硬直したり、痙攣したり、口から泡を吹くこともあります。
万が一、てんかん発作が起きた場合は、落ち着いて猫の周りに危ないものがないか、落下などの危険がない場所かを確かめ、発作の様子をビデオで撮影しておいてください。
ヘタに手を出すと攻撃される可能性があるため、あまり近く寄らないように発作が収まるのを待ちましょう。
 お手は犬の芸として有名なしつけの一つであり、あまり猫がお手をするイメージはありません。
そのため、犬と猫では犬の方が賢いというイメージがついてしまっています。
しかし、猫も正しい教え方をすればお手ができるようになります。
猫は意外と知られていませんが記憶力が高く、犬以上とも言われています。
しかし、猫がお手をしたがらない理由には猫の性格が大きく関係しています。
猫は自分に得をすることしかしない考えがあり、自由奔放が好きで束縛されることを嫌がることも関係しています。
得をすることしかしないのであればお手をすれば特になると考えさせることができれば、お手もしてくれるようになります。
猫にとってお得と感じることはおやつをもらえることで、お手ができればおやつを与えるようにしましょう。
このやり方は犬と同じであり、犬同様に猫もお手ができるようになります。
猫によってはお手をすればおやつがもらえるとわかれば、猫が自発的に飼い主の手の上に前足を乗せておやつを催促してくることもあります。
お手は犬の芸として有名なしつけの一つであり、あまり猫がお手をするイメージはありません。
そのため、犬と猫では犬の方が賢いというイメージがついてしまっています。
しかし、猫も正しい教え方をすればお手ができるようになります。
猫は意外と知られていませんが記憶力が高く、犬以上とも言われています。
しかし、猫がお手をしたがらない理由には猫の性格が大きく関係しています。
猫は自分に得をすることしかしない考えがあり、自由奔放が好きで束縛されることを嫌がることも関係しています。
得をすることしかしないのであればお手をすれば特になると考えさせることができれば、お手もしてくれるようになります。
猫にとってお得と感じることはおやつをもらえることで、お手ができればおやつを与えるようにしましょう。
このやり方は犬と同じであり、犬同様に猫もお手ができるようになります。
猫によってはお手をすればおやつがもらえるとわかれば、猫が自発的に飼い主の手の上に前足を乗せておやつを催促してくることもあります。
 猫は犬と同じようにお手をすることができるようにはなりますが、正しい教え方をしなければなりません。
適切な教え方をすればそれだけ短時間でお手をマスターすることもできます。
次に、猫のお手の教え方を紹介します。
犬にお手を教える方法と似ている部分もありますが、猫だけに効果がある教え方もあるのでチェックしましょう。
猫は犬と同じようにお手をすることができるようにはなりますが、正しい教え方をしなければなりません。
適切な教え方をすればそれだけ短時間でお手をマスターすることもできます。
次に、猫のお手の教え方を紹介します。
犬にお手を教える方法と似ている部分もありますが、猫だけに効果がある教え方もあるのでチェックしましょう。
 クリッカーという道具を活用することでもお手を教えることができます。
クリッカーはおもちゃであり、300円程度で購入することができ、カチッと音がなる特徴があります。
そのほかにも長い棒を用意しましょう。
猫じゃらしのようなおもちゃでも代用することができます。
猫は細長いものを見ると近づく習性があり、棒の先端に鼻先がつけばクリッカーを鳴らします。
この際におやつを与えてもよいですが、この段階では特別与える必要はありません。
次に、棒を上に持ち上げると猫は興味を示し、体を起こし、前足で棒に触れようとします。
この際にクリッカーを再び鳴らします。
この動作を反復することで猫はクリッカーの音で前足を上げればおやつをもらうことができると学びます。
あとはクリッカーの音をお手という声に変えればお手をマスターすることができます。
クリッカーはお手以外のしつけでも活用することができ、クリッカーの音がなればよいことをしていると自覚することができ、効率よく新しい芸を覚えることも期待できます。
クリッカーという道具を活用することでもお手を教えることができます。
クリッカーはおもちゃであり、300円程度で購入することができ、カチッと音がなる特徴があります。
そのほかにも長い棒を用意しましょう。
猫じゃらしのようなおもちゃでも代用することができます。
猫は細長いものを見ると近づく習性があり、棒の先端に鼻先がつけばクリッカーを鳴らします。
この際におやつを与えてもよいですが、この段階では特別与える必要はありません。
次に、棒を上に持ち上げると猫は興味を示し、体を起こし、前足で棒に触れようとします。
この際にクリッカーを再び鳴らします。
この動作を反復することで猫はクリッカーの音で前足を上げればおやつをもらうことができると学びます。
あとはクリッカーの音をお手という声に変えればお手をマスターすることができます。
クリッカーはお手以外のしつけでも活用することができ、クリッカーの音がなればよいことをしていると自覚することができ、効率よく新しい芸を覚えることも期待できます。
 猫にお手を教える際には教え方のほかにコツも覚えておくようにしましょう。
コツを知っているだけで効率よくお手を教えることができ、猫も早くお手をマスターすることができます。
なかなかお手をマスターしてくれない場合はコツがうまく活用できていない可能性があります。
猫にお手を教える際には教え方のほかにコツも覚えておくようにしましょう。
コツを知っているだけで効率よくお手を教えることができ、猫も早くお手をマスターすることができます。
なかなかお手をマスターしてくれない場合はコツがうまく活用できていない可能性があります。
 猫にお手を教える際には習慣化させる必要があります。
人にも同じことが言えますが、一度教えられたことでもやらない時間が長ければ忘れてしまいます。
そのため、お手を教える際にはほぼ毎日反復練習を繰り返すようにしましょう。
また、一度お手をマスターしてもそれ以降お手を芸をさせなければ忘れてしまい、お手と発言してもお手をしてくれないこともあります。
このような状況になってしまうと教えていた時間が無駄になってしまうため、一度マスターした芸でも定期的にさせるようにしましょう。
猫にお手を教える際には習慣化させる必要があります。
人にも同じことが言えますが、一度教えられたことでもやらない時間が長ければ忘れてしまいます。
そのため、お手を教える際にはほぼ毎日反復練習を繰り返すようにしましょう。
また、一度お手をマスターしてもそれ以降お手を芸をさせなければ忘れてしまい、お手と発言してもお手をしてくれないこともあります。
このような状況になってしまうと教えていた時間が無駄になってしまうため、一度マスターした芸でも定期的にさせるようにしましょう。
 猫にお手を教える際に犬に教える方法に違いを付けたほうが良いのか気になる人も多いのではないでしょうか。
犬と猫では性格も考え方も異なるため、教え方も変える必要があると考えてしまいがちですが、基本犬にお手を教える方法と同じで問題ありません。
犬も猫も褒められれば最も褒められたいと考えるので、お手をした後にしっかり褒めていれば大丈夫です。
警察犬などはより高度なしつけが求められますが、教え方としては反復練習としっかり褒めることであるため、一般家庭で飼っている犬に芸を教える方法と大差はありません。
猫にお手を教える際に犬に教える方法に違いを付けたほうが良いのか気になる人も多いのではないでしょうか。
犬と猫では性格も考え方も異なるため、教え方も変える必要があると考えてしまいがちですが、基本犬にお手を教える方法と同じで問題ありません。
犬も猫も褒められれば最も褒められたいと考えるので、お手をした後にしっかり褒めていれば大丈夫です。
警察犬などはより高度なしつけが求められますが、教え方としては反復練習としっかり褒めることであるため、一般家庭で飼っている犬に芸を教える方法と大差はありません。
 犬は利口な動物であり、しつけをすればさまざまなことを覚えてくれます。
さまざまあるしつけの中でも基本のしつけでもあるのがお手です。
しつけを覚えるスピードは個体によって変わりますが、教え方によっても差が出てしまいます。
次に、お手の教え方のポイントを紹介するので参考にしてください。
犬は利口な動物であり、しつけをすればさまざまなことを覚えてくれます。
さまざまあるしつけの中でも基本のしつけでもあるのがお手です。
しつけを覚えるスピードは個体によって変わりますが、教え方によっても差が出てしまいます。
次に、お手の教え方のポイントを紹介するので参考にしてください。
 ステップ3でお手は完成しているように見えますが、できるのであればお手をしている際に愛犬の前足を軽く握るようにしましょう。
前足を握られることは犬にとって不快な感触であるため、嫌がられる可能性もあります。
しかし、前足を握られることは良いことだと想像させることができれば、今後のしつけでも役に立ちます。
前足の握り方は力を入れずに握ることが大切であり、上下に振ることもしないようにしましょう。
あくまでも軽く握る程度で問題ありません。
しかし、前足を握られることに不快感を感じてしまう犬もいるので、握っている際には反対の手でおやつをあげたり、褒めることを忘れないようにしましょう。
また、いつまでも握り続けていることもあまりよくありません。
おやつを食べている際に握るのをやめることがポイントです。
いつまでも握っていると握られている不快感を感じたまま終わってしまうので、おやつを食べている幸せ感を感じたままお手を終わらせ、良いイメージをつけるようにしましょう。
握られても不快感を感じないようになればお手を完全マスターしているといっても過言ではなく、次にしつけを教えることができたり、ブラッシングする際に暴れてしまうこともなくなります。
ステップ3でお手は完成しているように見えますが、できるのであればお手をしている際に愛犬の前足を軽く握るようにしましょう。
前足を握られることは犬にとって不快な感触であるため、嫌がられる可能性もあります。
しかし、前足を握られることは良いことだと想像させることができれば、今後のしつけでも役に立ちます。
前足の握り方は力を入れずに握ることが大切であり、上下に振ることもしないようにしましょう。
あくまでも軽く握る程度で問題ありません。
しかし、前足を握られることに不快感を感じてしまう犬もいるので、握っている際には反対の手でおやつをあげたり、褒めることを忘れないようにしましょう。
また、いつまでも握り続けていることもあまりよくありません。
おやつを食べている際に握るのをやめることがポイントです。
いつまでも握っていると握られている不快感を感じたまま終わってしまうので、おやつを食べている幸せ感を感じたままお手を終わらせ、良いイメージをつけるようにしましょう。
握られても不快感を感じないようになればお手を完全マスターしているといっても過言ではなく、次にしつけを教えることができたり、ブラッシングする際に暴れてしまうこともなくなります。
 お手を覚えるスピードに個体差はありますが、飼い主の教え方に問題がある可能性もあります。
教え方が間違っているのであれば正しい教え方にするだけでお手を覚えてくれる可能性も高まります。
次に、犬がお手を覚えない原因を紹介するので、当てはまることがあるのであれば改善しましょう。
お手を覚えるスピードに個体差はありますが、飼い主の教え方に問題がある可能性もあります。
教え方が間違っているのであれば正しい教え方にするだけでお手を覚えてくれる可能性も高まります。
次に、犬がお手を覚えない原因を紹介するので、当てはまることがあるのであれば改善しましょう。
 人に反抗期があるように、犬にも反抗期があります。
犬の場合は生後半年~1年頃が反抗期を迎える目安となっています。
反抗期では言うことを聞いてくれないことがほとんどであるため、反抗期の時にお手などのしつけを教えることはあまり効率的とは言えません。
しつけは幼いころから覚えさせるほうが素直に覚えてくれる可能性はありますが、反抗期を迎えてしまっているのであれば反抗期が収まるまで待つようにしましょう。
どうしても早く教えたいのであれば焦らずにしつけをさせることが大切です。
人に反抗期があるように、犬にも反抗期があります。
犬の場合は生後半年~1年頃が反抗期を迎える目安となっています。
反抗期では言うことを聞いてくれないことがほとんどであるため、反抗期の時にお手などのしつけを教えることはあまり効率的とは言えません。
しつけは幼いころから覚えさせるほうが素直に覚えてくれる可能性はありますが、反抗期を迎えてしまっているのであれば反抗期が収まるまで待つようにしましょう。
どうしても早く教えたいのであれば焦らずにしつけをさせることが大切です。
 犬の定番のしつけでもあるお手ですが、初めてお手を教える際や犬を初めて飼い始めたのであればさまざまなことが気になってしまいがちです。
近くに犬を飼っている人や知り合いに犬を飼っている人がいれば聞くことができますが、いないのであれば疑問を解決することもできません。
ここでは、お手に関する質問をいくつか紹介するので、参考にしてください。
犬の定番のしつけでもあるお手ですが、初めてお手を教える際や犬を初めて飼い始めたのであればさまざまなことが気になってしまいがちです。
近くに犬を飼っている人や知り合いに犬を飼っている人がいれば聞くことができますが、いないのであれば疑問を解決することもできません。
ここでは、お手に関する質問をいくつか紹介するので、参考にしてください。
 上記でも紹介したように足に触れられることを嫌がる場合が多く、お手を教える際にも嫌がります。
足に触れられることに嫌がられる原因は不快感を感じているか触られていることに慣れていないかのどちらかである可能性が高いです。
触られることに慣れていないのであれば足に触れる回数を増やしていき、慣れさせるようにしましょう。
不快感を感じていることが原因であれば足に触れている間におやつなどを与えて、足に触れられることは不快なことではないことを覚えさせるようにしましょう。
上記でも紹介したように足に触れられることを嫌がる場合が多く、お手を教える際にも嫌がります。
足に触れられることに嫌がられる原因は不快感を感じているか触られていることに慣れていないかのどちらかである可能性が高いです。
触られることに慣れていないのであれば足に触れる回数を増やしていき、慣れさせるようにしましょう。
不快感を感じていることが原因であれば足に触れている間におやつなどを与えて、足に触れられることは不快なことではないことを覚えさせるようにしましょう。