犬は電車に乗ってOK
 あまり電車の中で犬を連れている人を見かけることが少ないので、電車に犬を乗せることはいけないというイメージがありますが、条件を満たしていれば電車に乗せても問題ありません。
ただし、各鉄道会社によって条件は異なるので、事前に確認しておく必要があります。
ちなみに身体障害者補助犬であれば、無条件ですべての電車に乗ることができます。
どうしても電車に乗って愛犬と移動する必要があるのであれば、必要な物を用意したり、マナーを身に付けておくようにしましょう。
あまり電車の中で犬を連れている人を見かけることが少ないので、電車に犬を乗せることはいけないというイメージがありますが、条件を満たしていれば電車に乗せても問題ありません。
ただし、各鉄道会社によって条件は異なるので、事前に確認しておく必要があります。
ちなみに身体障害者補助犬であれば、無条件ですべての電車に乗ることができます。
どうしても電車に乗って愛犬と移動する必要があるのであれば、必要な物を用意したり、マナーを身に付けておくようにしましょう。
犬と電車に乗る前日までにしておく準備
 上記でも紹介したように犬と電車に乗るためには条件を満たしておく必要があり、場合によっては用意しなければいけない物もあるので、前日までに用意する必要があります。
次に、犬を電車に乗せる際に準備しておくものを紹介するので参考にしてください。
上記でも紹介したように犬と電車に乗るためには条件を満たしておく必要があり、場合によっては用意しなければいけない物もあるので、前日までに用意する必要があります。
次に、犬を電車に乗せる際に準備しておくものを紹介するので参考にしてください。
短距離間の乗車練習を行う
もし、長時間電車で移動しなければならないのであれば、短距離間の乗車練習をしましょう。
初めから長時間の移動は犬にとってはストレスに感じてしまうことも多く、吠えたり、暴れる原因となります。
また、飼い主自身も犬との電車の移動に慣れていない場合も多いので、飼い主も慣れる目的を同時に果たすことができます。
目安は1~2駅程度の短い距離に絞ってみましょう。
できる限り乗客数が少ない時間帯から始め、徐々に周りの人が多い時間帯に変えていき、騒がしい環境でも大人しくできるようにしましょう。
キャリーに慣らす練習をする
 犬を電車に乗せるのであればキャリーは必要不可欠です。
各鉄道会社によって犬を電車に乗せてもよい条件は変わりますが、キャリーの中に入れることはほぼ確定している条件です。
そのため、事前にキャリーの中に入れて落ち着かせる練習をするようにしましょう。
慣れていない空間では不安に感じてしまいやすいですが、回数をこなすことでキャリーの環境に慣れさせることができます。
キャリーにはさまざまな種類や形状で販売されていますが、電車で使用するのであれば顔まで覆うことができるタイプを購入しましょう。
犬を電車に乗せるのであればキャリーは必要不可欠です。
各鉄道会社によって犬を電車に乗せてもよい条件は変わりますが、キャリーの中に入れることはほぼ確定している条件です。
そのため、事前にキャリーの中に入れて落ち着かせる練習をするようにしましょう。
慣れていない空間では不安に感じてしまいやすいですが、回数をこなすことでキャリーの環境に慣れさせることができます。
キャリーにはさまざまな種類や形状で販売されていますが、電車で使用するのであれば顔まで覆うことができるタイプを購入しましょう。
目的地までの乗り換えやルートを調べる
上記でも紹介したように犬を乗せてもよい条件は各鉄道会社によって違うので確認しておくことはもちろんですが、乗り方や料金の確認、乗り換えがあるのであれば乗り換える駅やホームの場所も確認しておきましょう。
どうしても犬を乗せてもよい状態にできているのか不安があるのであれば、改札で駅員に確認を取ってもらうようにしましょう。
駅員が問題ないと判断すれば電車に乗ることもでき、不安を抱えながら愛犬と電車に乗らなくて済むようになります。
犬と電車に乗る当日や乗車前にしておく準備
 犬と電車に乗るためにはさまざまな準備をしなければなりません。
下準備をしておくほど当日になって焦ったり、電車内でトラブルになることを未然に防ぐことができます。
次に、犬と電車に乗る際にしておいたほうが良い準備を紹介するので参考にしてください。
犬と電車に乗るためにはさまざまな準備をしなければなりません。
下準備をしておくほど当日になって焦ったり、電車内でトラブルになることを未然に防ぐことができます。
次に、犬と電車に乗る際にしておいたほうが良い準備を紹介するので参考にしてください。
混雑車両や混雑時間帯は回避する
電車は時間帯によって混んでいる状況が大きく違います。
基本的に通勤や通学する時間帯には混雑してしまう場合が多いので、その時間帯に犬と出かけることは極力避けるようにしましょう。
混雑していればそれだけ雑音が大きくなり、犬が不安になったり、興奮してしまいます。
通勤ラッシュを避けると同時に、各駅停車する電車を選ぶことも大切です。
各駅電車であれば混雑することが多少軽減されることと、万が一車内で犬が暴れてしまっても各駅停車であれば駅に付き次第ホームに降りることができ、犬を落ち着かせることもできます。
乗り物酔いを防ぐため直前の食事は避ける
 人が乗り物酔いすることと同じように犬も乗り物酔いをしてしまうことがあります。
電車は車と違って雑音のほかに振動も大きくなってしまうので、車では酔わなくても電車では酔ってしまうことも十分考えられます。
乗り物酔いを防ぐためには移動の前の食事は避けるようにしましょう。
食べた物が胃にあればどうしても乗り物酔いしてしまうリスクが高まってしまいます。
乗り物酔いしてしまった際には近くの駅に乗せて落ち着かせることが大切であり、時々車内で愛犬の様子をうかがうことで乗り物酔いの早期発見につながります。
人が乗り物酔いすることと同じように犬も乗り物酔いをしてしまうことがあります。
電車は車と違って雑音のほかに振動も大きくなってしまうので、車では酔わなくても電車では酔ってしまうことも十分考えられます。
乗り物酔いを防ぐためには移動の前の食事は避けるようにしましょう。
食べた物が胃にあればどうしても乗り物酔いしてしまうリスクが高まってしまいます。
乗り物酔いしてしまった際には近くの駅に乗せて落ち着かせることが大切であり、時々車内で愛犬の様子をうかがうことで乗り物酔いの早期発見につながります。
排泄は乗車する前に済ませておく
車内の中では排泄物に対して対応することができません。
おしめを付ける方法もありますが、においを完全に遮断することはできないので周りの人に迷惑をかけてしまいます。
そのため、電車に乗る前に排泄させておくことが理想です。
いつも散歩をしているときに排泄する習慣があるのであれば電車に乗る前に散歩をさせて排泄も済ませておきましょう。
室内にトイレを用意している時にはいつもどのタイミングで排泄するのかを確認することも大切です。
キャリー内に普段使うタオルやベッドを入れる
 初めてキャリーに入れると慣れていない空間に戸惑ってしまうことも少なくありません。
そのような場合には普段使用しているにおい付きのタオルをキャリー内に入れておきましょう。
犬はにおいに敏感な生き物であるため、自分のにおいがあれば落ち着いてくれる可能性が高まります。
おもちゃなどもおすすめですが、キャリー内におもちゃを入れてしまうと遊んでしまい、暴れたり、鳴いてしまうこともあります。
一方静かに遊んでくれるのであれば車内の雑音などに意識を向かないようにすることもできるので、使い分ける必要があります。
初めてキャリーに入れると慣れていない空間に戸惑ってしまうことも少なくありません。
そのような場合には普段使用しているにおい付きのタオルをキャリー内に入れておきましょう。
犬はにおいに敏感な生き物であるため、自分のにおいがあれば落ち着いてくれる可能性が高まります。
おもちゃなどもおすすめですが、キャリー内におもちゃを入れてしまうと遊んでしまい、暴れたり、鳴いてしまうこともあります。
一方静かに遊んでくれるのであれば車内の雑音などに意識を向かないようにすることもできるので、使い分ける必要があります。
犬と電車に乗る時のマナー
 犬を電車に乗せるのであればマナーを知っておくことも大切です。
乗せるための条件を満たすことも大切ですが、マナーが守られていないと周りの人に迷惑をかけてしまう可能性が高く、トラブルの原因となります。
次に、愛犬と電車に乗る際のマナーを紹介するので把握しておきましょう。
犬を電車に乗せるのであればマナーを知っておくことも大切です。
乗せるための条件を満たすことも大切ですが、マナーが守られていないと周りの人に迷惑をかけてしまう可能性が高く、トラブルの原因となります。
次に、愛犬と電車に乗る際のマナーを紹介するので把握しておきましょう。
ケースから顔出しさせないように努める
キャリーやケースの中に犬を入れた後に、改札を通過後は頭が出ないようにしましょう。
ケースのデザインによっては周りの環境が犬に見えてしまうこともありますが、布などを被せてできるだけ外の環境を見せないようにしましょう。
車内で顔が出てしまうと犬好きの乗客が勝手に触れてしまい、噛んでしまったり、興奮してしまうのでトラブルの原因となってしまいます。
飼い主からすると狭い空間に愛犬を閉じ込めてしまうことに罪悪感を感じてしまうこともありますが、マナーであるため、守りましょう。
犬が興奮しないようにしつけや練習をする
 誰でも知らない環境に閉じ込められることには不安を感じてしまい、犬にも同じことが言えます。
普段電車に乗る際に使用するキャリーをしないのであればまず、キャリーに慣れてもらうことが大切です。
目的はキャリーの環境に慣れてもらうためであるため、自宅の中で行っても問題ありません。
慣れないうちは暴れたり、すぐに出ようとしてしまう場合が多いですが、頻繁に練習をすることで次第に慣れていくので、焦らずに時間をかけましょう。
そのため、乗車する前日では慣れるのに時間が足りない場合が多いので、余裕をもって1か月程度前から練習することが無難です。
誰でも知らない環境に閉じ込められることには不安を感じてしまい、犬にも同じことが言えます。
普段電車に乗る際に使用するキャリーをしないのであればまず、キャリーに慣れてもらうことが大切です。
目的はキャリーの環境に慣れてもらうためであるため、自宅の中で行っても問題ありません。
慣れないうちは暴れたり、すぐに出ようとしてしまう場合が多いですが、頻繁に練習をすることで次第に慣れていくので、焦らずに時間をかけましょう。
そのため、乗車する前日では慣れるのに時間が足りない場合が多いので、余裕をもって1か月程度前から練習することが無難です。
犬の存在を知らせないようにする
犬の存在を周りの乗客に知らせないようにすることも大切です。
キャリーの中に犬がいることを隠し、存在自体をなくすことができれば周りの乗客から注目されてしまうことを防ぎ、一般の乗客の中に紛れることができます。
電車に犬を乗せることは問題ではありませんが、あまり見かけることがないことが現実であり、実際犬が電車に乗っているとどうしても注目してしまいます。
また、犬アレルギーを持っている人や犬嫌いな人と余計なトラブルを未然に防ぐこともあり、外から犬が見えないようなキャリーを選ぶことも大切です。
動物に対して苦手意識を持つ人に配慮する
 上記でも一部紹介しましたが動物に対して苦手意識を持っている人や同じ車両に乗っている可能性も捨てきれることができず、
そのような人がキャリーの中に犬がいることを知ってしまうとトラブルの原因になってしまいます。
そのようなことを未然に防ぐためにも犬の存在を極力消す必要があります。
キャリーから犬が見えないようにすることも大切ですが、鳴かないように訓練することも大切です。
そのほかにも極力乗客が少ない車両に乗ったり、出入り口の近くにいるなどの工夫をしましょう。
上記でも一部紹介しましたが動物に対して苦手意識を持っている人や同じ車両に乗っている可能性も捨てきれることができず、
そのような人がキャリーの中に犬がいることを知ってしまうとトラブルの原因になってしまいます。
そのようなことを未然に防ぐためにも犬の存在を極力消す必要があります。
キャリーから犬が見えないようにすることも大切ですが、鳴かないように訓練することも大切です。
そのほかにも極力乗客が少ない車両に乗ったり、出入り口の近くにいるなどの工夫をしましょう。
電車内で犬が鳴いた場合はどうする?
車内で犬が鳴いてしまうことや興奮して吠えることも当然あります。
すぐに落ち着いてくれればそのまま目的地に着くまで乗車していても問題ありませんが、一度興奮してしまうと落ち着いてくれる可能性は低く、多くの乗客の迷惑になってしまいます。
鳴き続けてしまうのであれば次の駅で一度降り、ホームで落ち着かせるようにしましょう。
場合によっては一時的にキャリーの中から犬を出して開放させてあげることも必要になります。
万が一の状況に備えて各駅電車に乗ることや時間に余裕をもって出発することも大切です。
犬と電車に乗る時の料金
 条件を満たせば犬と電車に乗ることは可能ですが、料金が必要になることは知っているでしょうか。
知らずに料金を払わずに乗車してしまうとトラブルの原因となります。
長さが70㎝以内であり、縦と横の長さが合わせて90㎝程度でキャリーと犬の重さが10㎏以内であれば290円程度で乗ることができます。
改札口で犬の入っているキャリーを見せれば駅員の人が測定してくれるので基本的に任せていれば料金を指定され、支払えば手回り品切符をもらうことができ、乗車可能になります。
料金は各鉄道会社によって微妙に違うので、一度確認しておきましょう。
条件を満たせば犬と電車に乗ることは可能ですが、料金が必要になることは知っているでしょうか。
知らずに料金を払わずに乗車してしまうとトラブルの原因となります。
長さが70㎝以内であり、縦と横の長さが合わせて90㎝程度でキャリーと犬の重さが10㎏以内であれば290円程度で乗ることができます。
改札口で犬の入っているキャリーを見せれば駅員の人が測定してくれるので基本的に任せていれば料金を指定され、支払えば手回り品切符をもらうことができ、乗車可能になります。
料金は各鉄道会社によって微妙に違うので、一度確認しておきましょう。
まとめ
犬と遠出する際にはどうしても電車を利用しなければならないときもありますが、条件やマナーさえクリアすれば問題なく乗車することはできます。
ただし、犬にはキャリー内の環境や車内の環境にも慣れさせる必要があるので、あらかじめ時間がかかることを念頭に置いて、行動することが求められます。
エリザベスカラーは犬にストレスを与える?
 手術やケガを行った際に、愛犬の首回りにエリザベスカラーを装着しますが、愛犬が動きにくそうにしていたり、嫌がって外そうとしている姿を見るとストレスを感じているのではないかと心配になりますよね。
実はその通りで、エリザベスカラーは犬にとってとてもストレスなんです。
エリザベスカラーをつけることで、視野が狭くなり、音も聞こえにくくなり、ニオイも嗅ぎにくくなるなど、普段よりも情報が入りづらくなってしまうのです。
また、エリザベスカラーは顔をすっぽり覆ってしまう構造になるため普通に歩いていても物にぶつかったりすることが増えてしまいます。
さらに、食事もしにくいので、当然ストレスを感じることになるでしょう。
手術やケガを行った際に、愛犬の首回りにエリザベスカラーを装着しますが、愛犬が動きにくそうにしていたり、嫌がって外そうとしている姿を見るとストレスを感じているのではないかと心配になりますよね。
実はその通りで、エリザベスカラーは犬にとってとてもストレスなんです。
エリザベスカラーをつけることで、視野が狭くなり、音も聞こえにくくなり、ニオイも嗅ぎにくくなるなど、普段よりも情報が入りづらくなってしまうのです。
また、エリザベスカラーは顔をすっぽり覆ってしまう構造になるため普通に歩いていても物にぶつかったりすることが増えてしまいます。
さらに、食事もしにくいので、当然ストレスを感じることになるでしょう。
エリザベスカラーをつけた犬のストレス軽減方法
 愛犬がストレスを感じることがわかっていても、エリザベスカラーを装着しなければいけない場面はあります。
その場合、できるだけストレスを軽減させてあげることが重要です。
まずは、行動範囲にある障害物を取り除いてあげてください。
続いて食事や水分をとりやすいように工夫することも大切!
エリザベスカラーが当たりにくい高さを見極めて、食器の高さを調節してあげましょう。
長時間の留守番をさせる場合は、滑り止めのついた食器を使う、食器スタンドを使うなどの工夫も必要です。
そして、気を紛らわせてあげる工夫や人の目が届く範囲だけ外してあげるなどストレスに感じる時間を少しでも減らしてあげましょう。
愛犬がストレスを感じることがわかっていても、エリザベスカラーを装着しなければいけない場面はあります。
その場合、できるだけストレスを軽減させてあげることが重要です。
まずは、行動範囲にある障害物を取り除いてあげてください。
続いて食事や水分をとりやすいように工夫することも大切!
エリザベスカラーが当たりにくい高さを見極めて、食器の高さを調節してあげましょう。
長時間の留守番をさせる場合は、滑り止めのついた食器を使う、食器スタンドを使うなどの工夫も必要です。
そして、気を紛らわせてあげる工夫や人の目が届く範囲だけ外してあげるなどストレスに感じる時間を少しでも減らしてあげましょう。
犬のおすすめエリザベスカラー:ベル型
エリザベスカラーと言えばそんなに種類がないものと思っている方もいますが、現在は少しでも犬のストレスを少なくするためにさまざまな形のものが販売されています。
まずはベル型タイプのエリザベスカラーをご紹介します。
全身を掻いたり、舐めたりをガードしてくれ、半透明で視界がクリアな商品や、首元部分がクッション生地になった苦しくないものがあります。
ペット用エリザベスカラー
リンク
続いてのベル型エリザベスカラーは、半透明素材で視界がクリアになっているものです。
装着していても愛犬の不安を軽減でき、しっかりとガードしてくれます。
サイズ展開は9種類もあるので、愛犬のサイズに合ったものを選んであげてください。
ぴったりサイズを付けてあげることで、動いても外れにくく首元への負担もかかりにくくなるので、できるだけジャストサイズを選んであげることがベストです。
エリザベスカラー プラスチック製
リンク
首元にふんわり柔らか素材を使用したベル型のエリザベスカラーです。
クリア部分はプラスチック製でしっかり固定でき、首にあたる部分だけ柔らかい布製になっています。
首元に優しい着け心地で愛犬のストレスを軽減でき、ボタンでサイズ調整も可能。
カラーも4色展開なので、愛犬に合ったものを選んであげてくださいね。
エリザベスカラー
リンク
首元に柔らかなフェザー素材を使用しています。
側面はプラスチック製なので、食事の際汚れても簡単に拭き取ることができ、お手入れのしやすさは抜群!
また、ボタン式ながら首回りのサイズも調整でき、大きさもS・M・L・XLの4種類から選べるようになっているので、愛犬の大きさにマッチしたものを選んであげましょう。
犬のおすすめエリザベスカラー:ドーナツ型
ここでは、ドーナツ型のエリザベスカラーをご紹介します。
首・顔周りをガードする時におすすめで、水や食事をとりやすく愛犬のストレスを軽減してくれます。
柔らかいふかふかの素材の商品に加え、デザイン性も豊かな商品も多く揃っています。
こんな商品もあるんだというびっくりするような商品もあるので、ぜひチェックしてみてくださいね!
ビーズ エリザベスカラー
リンク
ひまわりのような見た目が可愛いドーナツ型のエリザベスカラーです。
素材は柔らかいコットン素材を、詰め物にはポリエステル発砲ポリスチレンビーズを使用。
ソフト&軽量なので、愛犬の負担になりにくいでしょう。
また、昼寝もそのまま可能なので、快適です!
デザイン性・機能性を兼ね備えた人気商品となっています。
洗える布製エリザベスカラー
リンク
柔らかくて軽く、ふんわり触感が魅力的な布製のエリザベスカラーです。
着けたまま枕代わりにもなります。
顔周りだけを覆うので、水が飲みやすいのも嬉しいですよね!
着脱も簡単で、頭をリングに通してストッパーで止めるだけでOK!
デザインもタンポポ柄や洋ナシ柄など4種類あり、ファッション感覚で楽しむこともできそうですね!
犬猫用 ドーナツリング
リンク
オーガニック素材の生地で顔周りを包み込んでくれる商品です。
厚みもあるクッションで口先が患部に届きにくいのがポイント。
元気に動きまわって家具や壁にぶつかってもケガをしにくいので、飼い主さんも安心して使用できるのではないでしょうか。
ギンガムチェックとボーダータイプの2バリエーションなので、愛犬のイメージに合わせて選んでみてくださいね。
犬のおすすめエリザベスカラー:ウエア型
エリザベスカラーは首回りにつけるものしかないと思っていた方も多いかと思いますが、現在はウェア型のものも販売されています。
ピタッとヒットし快適に動き回ることができ、普段の洋服のように着用できるので、愛犬に一番ストレスがかかりにくいのが魅力です。
今回ご紹介する商品は獣医師さんが研究を重ねて開発された商品なので、安心して着用することができるのではないでしょうか。
エリザベスカラーに代わる皮膚保護服
リンク
術後の生活を少しでも明るくという思いが込められたおしゃれなウェアです。
首回りから足首までをしっかり多い全身をガード。
通気性・速乾性にも優れているので、いつでもさらっと着用できるのが嬉しいですね。
また、反射テープや防水機能が付いているため、雪や雨の日のお散歩にも最適!
色はレッドとブルーの2色展開となっており、術後や普段のお散歩時にもおすすめです。
皮膚保護服スキンウエア
リンク
獣医師と犬猫の洋服ブランドが共同開発した犬の肌をガードする機能性ウェアです。
縫い目を全て外側にすることで皮膚への刺激を軽減してくれます。
さらに、伸縮性抜群なので、どんな動きにもスムーズに対応。
衛生的な設計を採用し、ウェアを着たまま排泄も可能です。
皮膚を守りながら普段通りにお散歩できるのは嬉しいですね!
犬のおすすめエリザベスカラー:ソフトタイプ
ここではソフトタイプのエリザベスカラーをご紹介していきます。
柔らかいスポンジ素材を使用した商品で、ソフトなつけ心地なので、術後やケガをした愛犬にも負担がかかりません。
また、そのまま昼寝をすることも可能です。
サイズやカラー展開は豊富な商品もあるので、ぜひチェックしてみてくださいね!
ペットソフトエリザベスカラー
リンク
カラフル&おしゃれで着用時もHappyな気持ちになれるデザイン性抜群の商品です。
ふんわり軽いので愛犬のストレスも軽減してくれるでしょう。
歩く時はもちろんご飯を食べる時にも邪魔になりにくいのが嬉しいポイント。
つけたまま枕代わりにして昼寝もできます。
カラー展開で豊富でとにかく可愛いので、デザイン性にもこだわりやすい飼い主さんにおすすめです。
柔らかいエリザベスカラー
リンク
全国版愛犬グッズ冊子「PEPPY」にも掲載された、軽くて動きやすい話題のエリザベスカラーです。
ソフトスポンジ素材を使用したふわふわした生地を使用しているのですが、柔らかすぎず、舐める・掻くのをしっかりガードしてくれます。
マジックテープ式なので、首回りに合わせてサイズの微調整も可能。
ロングタイプやスタンダードタイプなどサイズ展開も豊富なため、愛犬のサイズに合わせて選んであげましょう。
犬のおすすめエリザベスカラー:防水タイプ
ここでは、水などをはじきお手入れが楽チンな防水タイプのエリザベスカラーをご紹介します。
水や食事でエリザベスカラーが汚れてしまっても拭くだけで清潔さをキープできます。
忙しい飼い主さんのおすすめです!
防水エリザベスカラー
リンク
付いているリボンがかわいいデザインで、表面に防水ポリエステルを採用した水に強い商品です。
耐湿性にも優れ、濡れてもへたりにくいのが嬉しいポイントではないでしょうか。
中には弾力性のあるPR綿を使用。
柔らかいので愛犬にストレスもかかりにくく、首輪を装着することもできるので、散歩時にも着用可能です。
リボンの一は装着の仕方によって好きな位置につけることができます。
楽々フラワーエリザベスカラー
リンク
表地は綿100%でデリケートな愛犬の肌に優しい商品です。
生活防水機能も備わっているので、飲み物や食べ物をこぼしても拭き取るだけでOK!
中綿にはマイクロファイバー綿を採用し、犬が好きな触感を実現しています。
おしゃれでデザイン性も抜群です!
実用性はもちろん可愛さも求めている飼い主さんにおすすめ!
犬のおすすめエリザベスカラー:面ファスナータイプ
ここではマジックテープなどで細かくサイズ調整ができる面ファスナータイプのエリザベスカラーをご紹介します。
誰でも簡単に装着できるので、はじめてエリザベスカラーを使用する飼い主さんにもおすすめです。
機能性はもちろんデザイン性にもこだわっている商品なので必見です!
ベル型メッシュタイプ
リンク
メッシュ素材で通気性抜群のベル型商品です。
熱がこもりにくく周りの音も聞き取りやすいのが魅力。
蒸れにくいので、耳や顔周りの炎症時にもぴったり!
フチ部分にパイピング加工を施すことで、家具などに傷がつくのも予防することができます。
ボタンで留めるタイプと面ファスナータイプの2種類があり、微調整可能なので着脱のしやすさであれば面ファスナータイプがおすすめです。
まとめ
今回は術後やケガの際に必須のエリザベスカラーについてご紹介しました。
エリザベスカラーにこれだけの種類が販売されているとはびっくりでしたね!
愛犬にとってストレスとなってしまうエリザベスカラーなのですが、これだけ快適に装着できるものがあるのであれば今後は安心して使用することができるのではないでしょうか。
愛犬にとって一番最適な商品を選んであげてくださいね!
犬は鳥の骨を食べても大丈夫?
 犬に鳥の骨を食べさせても大丈夫なのか心配な人もいるのではないでしょうか。
鳥の骨にはカルシウムやコラーゲンが多く含まれているので、骨を頑丈にしたり、コラーゲンは関節疾患の予防にもなります。
一見鳥の骨は固そうに見えますが、健康な成犬であれば数時間程度で消化します。
そのため、犬に鳥の骨を与えることは一部条件をクリアしているのであれば与えても問題ありません。
人が食べた骨付きにチキンの骨があるのであれば与えてみましょう。
犬に鳥の骨を食べさせても大丈夫なのか心配な人もいるのではないでしょうか。
鳥の骨にはカルシウムやコラーゲンが多く含まれているので、骨を頑丈にしたり、コラーゲンは関節疾患の予防にもなります。
一見鳥の骨は固そうに見えますが、健康な成犬であれば数時間程度で消化します。
そのため、犬に鳥の骨を与えることは一部条件をクリアしているのであれば与えても問題ありません。
人が食べた骨付きにチキンの骨があるのであれば与えてみましょう。
犬が鳥の骨を食べる危険性とは?
 犬に鳥の骨を与えることは基本的に問題ありませんが、危険性があることも理解しておきましょう。
正しい知識なく鳥の骨を与えてしまうと犬を危険な目にあわせてしまうため、飼い主は鳥の骨の危険性を十分理解してから与えるようにしましょう。
次に、犬に鳥の骨を与える際の危険性を紹介します。
犬に鳥の骨を与えることは基本的に問題ありませんが、危険性があることも理解しておきましょう。
正しい知識なく鳥の骨を与えてしまうと犬を危険な目にあわせてしまうため、飼い主は鳥の骨の危険性を十分理解してから与えるようにしましょう。
次に、犬に鳥の骨を与える際の危険性を紹介します。
鳥の骨は中で詰まりやすい
鳥の骨を犬に与えると気道や消化管につまってしまう危険があります。
鳥の骨が気道に詰まってしまうと呼吸をすることができず、呼吸困難に陥ってしまいます。
そのため、犬の異変に気付くことができないと最悪命にかかわってきます。
数分程度で犬が命の危険にさらされる症状であるため、非常に危険です。
また、鳥の骨が消化管に詰まるとそれ以降口にしたものが正常に消化することができず、消化管に次々と重なって詰まってしまいます。
気道のようにすぐに命が危険になるわけではありませんが、食べた物が詰まり続けることは命の危険にもなります。
どちらも命に関わってしまうほどのリスクがあるため、詰まらないように細かく砕くなどの工夫が必要です。
鳥の骨は割れやすく危険
 鳥の骨は割れやすく、鋭い部分ができやすい特徴があります。
鋭利なもので固い素材であるため、飲み込んでしまうと気道や消化管などに刺さってしまう可能性があります。
気道や消化管を傷つけてしまうとさまざまな病気の原因ともなります。
ほかの骨も割れれば鋭利な形になりますが、鳥の骨は格段と割れやすくなっています。
鳥の骨は他の骨とは違い、中が空洞になっており、空を飛ぶために軽量化する必要があるためであると考えられています。
中が空洞であれば耐久性も弱く、犬の顎の力でも十分折ることができ、その際に鋭利な部分が多くなってしまいます。
鳥の骨が刺さらないようにするためには、飼い主が細かく砕いて鋭利な部分がないように工夫したり、粉末にしてフードなどと一緒に与えるなどの方法があります。
鳥の骨は割れやすく、鋭い部分ができやすい特徴があります。
鋭利なもので固い素材であるため、飲み込んでしまうと気道や消化管などに刺さってしまう可能性があります。
気道や消化管を傷つけてしまうとさまざまな病気の原因ともなります。
ほかの骨も割れれば鋭利な形になりますが、鳥の骨は格段と割れやすくなっています。
鳥の骨は他の骨とは違い、中が空洞になっており、空を飛ぶために軽量化する必要があるためであると考えられています。
中が空洞であれば耐久性も弱く、犬の顎の力でも十分折ることができ、その際に鋭利な部分が多くなってしまいます。
鳥の骨が刺さらないようにするためには、飼い主が細かく砕いて鋭利な部分がないように工夫したり、粉末にしてフードなどと一緒に与えるなどの方法があります。
犬が鳥の骨を食べてしまった際の対処法
 犬が鳥の骨を食べると上記で紹介したように体の内側を傷つけてしまう原因となってしまうため、極力食べさせないようにすることも珍しくありません。
しかし、飼い主が鳥の骨を与えたつもりではなくても、知らない間に食べてしまっていることもあります。
万が一犬が鳥の骨を食べてしまった際には適切な対応をすることが飼い主には求められます。
犬が鳥の骨を食べると上記で紹介したように体の内側を傷つけてしまう原因となってしまうため、極力食べさせないようにすることも珍しくありません。
しかし、飼い主が鳥の骨を与えたつもりではなくても、知らない間に食べてしまっていることもあります。
万が一犬が鳥の骨を食べてしまった際には適切な対応をすることが飼い主には求められます。
食べた時の状況を把握する
犬が鳥の骨を食べてしまったことがわかれば、まずは飛べた時の状況を把握するようにしましょう。
食べてしまった鳥の骨の状態や量、いつ頃食べたのかなどを知ることができれば今後の対処方法を見出すこともできます。
そのため、焦らずに冷静になって分析することに集中しましょう。
確認①:骨の状態
鳥の骨の状態によって危険度が変わってきます。
骨の状態の確認とは、食べた鳥の骨が生であったのか加熱されていたのかや骨の大きさなどのことを示しており、わかる範囲で確認しましょう。
鳥の骨は割れやすい特徴がありますが、加熱していれば余計に割れやすく、鋭利な部分が多くなるため、気道などに刺さるリスクも高まってしまいます。
また、サイズが小さければ刺さりにくく、大きければ割れても大きいまま飲み込んでしまうため、刺さりやすいです。
確認②:どんな食べ方だったのか
次に、どんな食べ方をしていたのかを知るようにしましょう。
知らない間に食べてしまっていた場合は確認することがむずかしいですが、食べている最中を目撃していたのであればある程度把握することができます。
少しずつ削るように食べていたのであれば危険度は低いですが、大きく割るように食べていたのであれば鋭利な部分もできやすく危険です。
また、飲み込むように食べていた場合も同じく危険度が高いです。
食べ方を知ることも大切ですが、食べている場面に出くわしたのであれば食べ方を分析する前にいち早く食べることをやめさせることが大切です。
確認③:食べた時間
食べた時間を把握することができれば消化できる時間を割り出すことができます。
何時何分のように正確にわからない場合でもおおよその時間がわかれば消化時間も確認することができます。
消化される時間をあらかじめ知ることができればいつまでも犬の体調を心配する必要がなく、消化される時間を過ぎれば問題が起きることもなくなります。
一般的に鳥の骨は1~2時間程度で消化され、加熱されていればもろくなっているのでさらに早く消化することができます。
その後の様子をチェックする
 犬が鳥の骨を食べてしまったのであれば様子見をすることが大切です。
下痢や嘔吐の症状があらわれ、元気がなくなったり、吐くような動作を繰り返しているのであれば鳥の骨がどこかに刺さっていたり、消化不良を起こしている可能性があります。
このような症状があらわれたのであれば安静にしていても症状が良くなることはあまりないため、早めに病院で治療を受けるようにしましょう。
様子見をする時間は上記で紹介したように鳥の骨を食べた1~2時間程度ですが、万が一のことも考え少し長い時間愛犬の傍をできるだけ離れないようにしましょう。
犬が鳥の骨を食べてしまったのであれば様子見をすることが大切です。
下痢や嘔吐の症状があらわれ、元気がなくなったり、吐くような動作を繰り返しているのであれば鳥の骨がどこかに刺さっていたり、消化不良を起こしている可能性があります。
このような症状があらわれたのであれば安静にしていても症状が良くなることはあまりないため、早めに病院で治療を受けるようにしましょう。
様子見をする時間は上記で紹介したように鳥の骨を食べた1~2時間程度ですが、万が一のことも考え少し長い時間愛犬の傍をできるだけ離れないようにしましょう。
獣医師の元へ向かう
上記でも紹介したように鳥の骨を食べてから体調が悪くなったのであれば早めに獣医師の元に向かうようにしましょう。
下痢や嘔吐を繰り返していることはそれだけ多くの水分も排出してしまっていることでもあるため、脱水症状を誘発させてしまう原因にもなります。
鳥の骨が気道などに刺さり傷つけてしまうことも危険ですが、脱水症状が重度になってしまうことも命に関わってきます。
かかりつけの動物病院を決めていないと病院の元に行くまで時間がかかってしまうため、万が一のことも考え、犬を飼うのであればかかりつけの動物病院を決めておくことや近くの動物病院を探すことも大切です。
まとめ
犬が鳥の骨を食べることはカルシウムやコラーゲンを摂取することができるため、絶対に与えてはいけないということはありませんが、それ以上に危険な行動でもあります。
カルシウムやコラーゲンは違う方法でも摂取することができるため、鳥の骨を与える必要性はありません。
また、万が一の状況のことも考え、誤って鳥の骨を食べてしまったときの適切な対応方法も把握しておきましょう。
猫の熱中症対策に扇風機は使える?
 暑さには比較的強い猫ですが、熱中症になるリスクは低くなく高い湿度は苦痛になります。
扇風機が涼しくする場所は風の当たる部分だけで部屋全体は冷やせず、エアコンみたいに体温を下げる効果はほぼ無いようです。
人間にとっては扇風機の風が心地よく感じても、猫にとっては涼しさは感じられないようです。
扇風機はエアコンの冷気を循環させるために使えば、効率的に室温を保つ事ができます。
暑さには比較的強い猫ですが、熱中症になるリスクは低くなく高い湿度は苦痛になります。
扇風機が涼しくする場所は風の当たる部分だけで部屋全体は冷やせず、エアコンみたいに体温を下げる効果はほぼ無いようです。
人間にとっては扇風機の風が心地よく感じても、猫にとっては涼しさは感じられないようです。
扇風機はエアコンの冷気を循環させるために使えば、効率的に室温を保つ事ができます。
猫の熱中症対策に扇風機を使う場合の注意点や対策
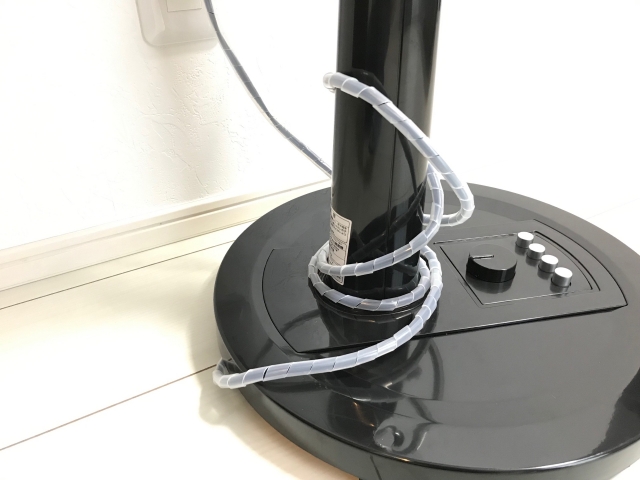 猫は肉球と鼻しか汗をかかず、体内に暑さをため込んでしまうと汗で暑さを発散できずに熱中症になってしまいます。
熱中症になれば人間と同じように命の危険もあります。
そうならない為に扇風機をどのように使えば、熱中症対策なるのかを調べて見ました。
猫は肉球と鼻しか汗をかかず、体内に暑さをため込んでしまうと汗で暑さを発散できずに熱中症になってしまいます。
熱中症になれば人間と同じように命の危険もあります。
そうならない為に扇風機をどのように使えば、熱中症対策なるのかを調べて見ました。
猫が直接風に当たるのを防ぐ
猫は人間と違った体の作りをしていて、体全体に風が当たったとしても涼しいと感じることはありません。
人間のように沢山汗腺がなく、可愛らしい肉球と鼻の頭だけ汗をかきます。
その為被毛に覆われている体に扇風機の風を当てても、人間のように涼しさがわからず不快に思う事もあります。
猫はグレーミングをしたり涼しい場所を探して、自分で体温調節を行いますので扇風機はあまり必要ないようです。
扇風機に近づかせないようにする
 扇風機に触れて事故を起こさないようにする為には、猫が接触しないように対策が必要になります。
好奇心旺盛な猫は小さな子供のように思いがけない行動をしますので、柵やストーブガードなどで扇風機を囲むようにし危険を回避してあげます。
それでも怪我をしてしまう心配がある場合は、壁掛けの扇風機を使ってみるのもいいかもしれません。
愛猫が怪我をしてしまうととても痛々しく可愛そうになりますので、事故が起きないように十分な対策をしてあげて下さい。
扇風機に触れて事故を起こさないようにする為には、猫が接触しないように対策が必要になります。
好奇心旺盛な猫は小さな子供のように思いがけない行動をしますので、柵やストーブガードなどで扇風機を囲むようにし危険を回避してあげます。
それでも怪我をしてしまう心配がある場合は、壁掛けの扇風機を使ってみるのもいいかもしれません。
愛猫が怪我をしてしまうととても痛々しく可愛そうになりますので、事故が起きないように十分な対策をしてあげて下さい。
安全機能が搭載された扇風機を使う
猫や小さな子供がいても安心して使う事ができる、有能な扇風機を選ぶようにします。
例えば転倒防止のチャイルドロック機能が付いているものや、小さいボディでも高性能を誇るサーキュレーターなども推奨されます。
羽根が見えないタワー型扇風機ならば、猫がいたずらをする心配や怪我をしてしまう事もなくなります。
万が一の場合に備えて、安全機能が搭載されている扇風機を選べば安心です。
扇風機が動かないように固定する
 もし猫が扇風機に強く体当たりした場合でも、絶対に倒れないように柱などにくくりつけて固定をします。
固定をする際に細い紐を使ってしまうと、猫がじゃれたり誤飲の原因にもなりますので注意が必要です。
留守番をさせる際には扇風機を他の部屋に移動させて、猫が触れないようにすれば安心です。
飼い主が留守の間は猫にとって不安でもあり開放的にもなりますので、安全に過ごせるようにしてあげる事も大切です。
もし猫が扇風機に強く体当たりした場合でも、絶対に倒れないように柱などにくくりつけて固定をします。
固定をする際に細い紐を使ってしまうと、猫がじゃれたり誤飲の原因にもなりますので注意が必要です。
留守番をさせる際には扇風機を他の部屋に移動させて、猫が触れないようにすれば安心です。
飼い主が留守の間は猫にとって不安でもあり開放的にもなりますので、安全に過ごせるようにしてあげる事も大切です。
扇風機カバーで覆う
扇風機の中の羽根がクルクル動く様子や、ゆっくり左右に首を振る動きは猫の野生本能をくすぐってしまいます。
飼い主が「危ないから近づいちゃ駄目」と注意をしても、一度興味を持ってしまうと知らず知らずのうちに近づいてしまいます。
猫の細い手や尻尾が扇風機に巻き込まれてしまう危険性もありますので、扇風機カバーを覆わせることで隙間に手を入れる行為が防げます。
カバーを前も後ろも隠せるものにすることで十分な安全対策にもなります。
羽がない扇風機を使う
 猫や子供が触っても怪我をしないように、ダイソンなどでは羽根のない扇風機が販売されています。
羽根のない扇風機は猫の興味をそそることがあまりなく、手を突っ込んでしまった場合でも怪我する心配もありません。
野生本能がある猫は飼い主が思いもつかない事に興味を示す時もありますので、扇風機を使用している間は油断をせずに見守ってあげるようにして下さい。
猫や子供が触っても怪我をしないように、ダイソンなどでは羽根のない扇風機が販売されています。
羽根のない扇風機は猫の興味をそそることがあまりなく、手を突っ込んでしまった場合でも怪我する心配もありません。
野生本能がある猫は飼い主が思いもつかない事に興味を示す時もありますので、扇風機を使用している間は油断をせずに見守ってあげるようにして下さい。
電気コードが壊れないようにガードする
猫はひも状のものに興味を示す時期があり、電気コードを噛んで感電してしまう恐れがあります。
野生の血が入っている猫の歯は意外に鋭く、人間から見たら「大丈夫だろう」と思うようなものでも噛んで駄目にしてしまう事があります。
電気コードを保護すれば猫を危険から守る事ができ、扇風機の故障も防げます。
安全グッズを上手に活用して、愛猫が安心して過ごせるようにしてあげて下さい。
猫の熱中症を扇風機以外で防ぐ方法
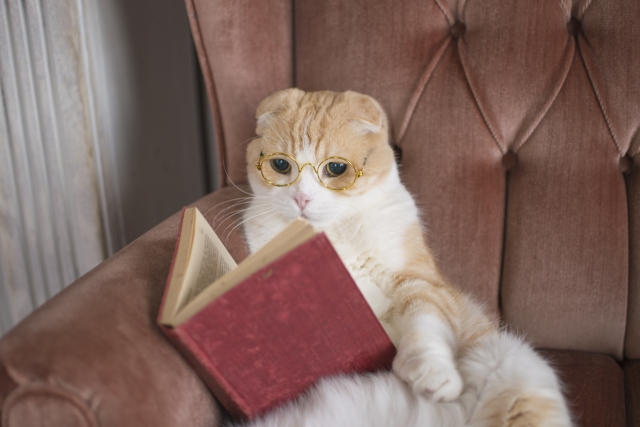 猫の熱中症を防ぐのに扇風機だけでは無理があり、扇風機での事故も数多く報告されています。
扇風機の音を嫌がり、風には不快を感じる猫もいるようです。
そこで扇風機以外で防ぐ方法を幾つか紹介します。
猫の熱中症を防ぐのに扇風機だけでは無理があり、扇風機での事故も数多く報告されています。
扇風機の音を嫌がり、風には不快を感じる猫もいるようです。
そこで扇風機以外で防ぐ方法を幾つか紹介します。
冷却グッズを使用する
暑い夏を快適に過ごせるように猫用の冷却マットや冷却ベッドなどが販売されていて、部屋の涼しい場所に設置してあげれば安心です。
猫によって好き嫌いがあり使ってくれない場合もありますが、様々な商品を試して愛猫に合ったものを選んであげて下さい。
はじめて見るものには警戒心があり、焦らずに見守ってあげるといつの間にか心地よさそうに使ってくれている事もあります。
暑くてバテ気味の猫の様子はとても可愛そうになりますが、スヤスヤ気持ち良さそうに寝ている姿には癒されます。
ブラッシングをして余計な毛を除く
 猫は季節の変わり目になると抜け毛が多くなり、飼い主にとっても抜け毛の後始末が大変になります。
ブラッシングをしてあげるととても気持ち良さそうにし、飼い主に催促をする時の仕草は可愛らしく癒されます。
トリミングが苦手な猫も多くいますが、夏になる前に飼い主の手でブラッシングをして無駄な毛を取り除いてあげます。
長毛種の猫の場合は、短毛種の猫よりも念入りにブラッシングをした方が暑さ対策になるようです。
猫は季節の変わり目になると抜け毛が多くなり、飼い主にとっても抜け毛の後始末が大変になります。
ブラッシングをしてあげるととても気持ち良さそうにし、飼い主に催促をする時の仕草は可愛らしく癒されます。
トリミングが苦手な猫も多くいますが、夏になる前に飼い主の手でブラッシングをして無駄な毛を取り除いてあげます。
長毛種の猫の場合は、短毛種の猫よりも念入りにブラッシングをした方が暑さ対策になるようです。
水飲み場を複数用意する
夏は他の季節と比べて、水の減り方が早く感じる事があります。
猫は体温が上がると水を飲んで調整する事もありますので、飲み水を複数用意してあげるようにします。
脱水症状や熱中症対策のためにも、普通の水と自動給水器を併用して使えば安心です。
猫も人間と同じように汗をかく場所は少なくても、水分補給をきちんとしてあげる事が大切です。
快適なスペースを確保させるようにする
 日常的に行える対策としては、猫が部屋を自由に行き来できるようにし自分で快適な場所を見つけられるようにしてあげます。
エアコンを使っている時はなるべく外気が入らないようにドアを閉め切ってしまいがちですが、猫にとってはあまり涼しいと感じていない事もあります。
猫が通れるだけの隙間を常に用意してあげる事が大切で、風が通ってドアが閉まってしまうような場合はドアストッパーなどを活用すれば安心です。
日常的に行える対策としては、猫が部屋を自由に行き来できるようにし自分で快適な場所を見つけられるようにしてあげます。
エアコンを使っている時はなるべく外気が入らないようにドアを閉め切ってしまいがちですが、猫にとってはあまり涼しいと感じていない事もあります。
猫が通れるだけの隙間を常に用意してあげる事が大切で、風が通ってドアが閉まってしまうような場合はドアストッパーなどを活用すれば安心です。
猫は扇風機が好き?嫌い?
 扇風機の電源を入れると下の台が温かくなり、直接風が当たらない事もあって気持ち良く眠る猫もいます。
動いている時の扇風機の振動は猫の喉笛に似ていて、安らぎを感じて安心する猫もいるようです。
猫は少し高さのある物が好きで、扇風機の下の台を枕として利用している事もあります。
長毛種の猫は短毛種の猫と比べて、涼しい風をあびたいと思う傾向があるようです。
風に当たることが嫌いな猫や、音が苦手な場合は扇風機を嫌がります。
扇風機の電源を入れると下の台が温かくなり、直接風が当たらない事もあって気持ち良く眠る猫もいます。
動いている時の扇風機の振動は猫の喉笛に似ていて、安らぎを感じて安心する猫もいるようです。
猫は少し高さのある物が好きで、扇風機の下の台を枕として利用している事もあります。
長毛種の猫は短毛種の猫と比べて、涼しい風をあびたいと思う傾向があるようです。
風に当たることが嫌いな猫や、音が苦手な場合は扇風機を嫌がります。
まとめ
扇風機は猫の熱中症対策にはあまり役に立たないようですが、エアコンの冷気を循環させるためには必要です。
猫や子供がいても安全機能が搭載されている扇風機も販売されていて、事故やケガの心配を減らしてくれます。
扇風機を上手に活用して暑い夏を乗り切りたいものですね!
猫は寒がり?
 猫の祖先は暖かい場所に住んでいた事もあり、暖かい場所を好む猫が多いようです。
あくまで猫種や個体差がありますが、一般的にヒマラヤンやペルシャなどの長毛種は寒さに強いです。
マンチカンやアメリカン・ショートヘアなどの短毛種は寒さに弱い為、室内で飼っていても温度管理に注意が必要です。
人間から見たら毛に覆われていて暖かそうに見えますが、猫は意外に寒がりで寒い場所に行った後は暖かい所を好むようです。
猫の祖先は暖かい場所に住んでいた事もあり、暖かい場所を好む猫が多いようです。
あくまで猫種や個体差がありますが、一般的にヒマラヤンやペルシャなどの長毛種は寒さに強いです。
マンチカンやアメリカン・ショートヘアなどの短毛種は寒さに弱い為、室内で飼っていても温度管理に注意が必要です。
人間から見たら毛に覆われていて暖かそうに見えますが、猫は意外に寒がりで寒い場所に行った後は暖かい所を好むようです。
猫が寒がっている時に見せる行動
 猫は人間のように話す事ができず、寒がっているのに飼い主が気づけない事もあり可愛そうな思いをさせてしまいます。
そうならないよう猫が快適に過ごせるように、寒い時に見せる行動を調べて見ました。
猫は人間のように話す事ができず、寒がっているのに飼い主が気づけない事もあり可愛そうな思いをさせてしまいます。
そうならないよう猫が快適に過ごせるように、寒い時に見せる行動を調べて見ました。
暖かい所に移動
猫は家で過ごす事が多く、家の中の暖気の集まりやすい場所や日の当たる場所を飼い主よりも良く知っているようです。
寒さを感じた時は暖かい所はどこなのか探り、そこへ移動して気持ち良さそうに過ごします。
日にあたって日向ぼっこをしている様子は、とても可愛らしく癒されます。
寒い日は猫が移動する様子を見ながら追いかけると、暖かい場所を教えてくれます。
体を縮めるように丸める
 猫は寒さを感じると体を小さくして丸める生き物で、体をコンパクトにすることで熱が逃げるのを最小限に抑えています。
丸くなる姿がアンモナイトに似ている事から、アンモニャイトと呼ばれる事もあり寒さを感じているサインのひとつです。
猫が眠っている姿を眺めていると、人間のように体勢を変える様子は何とも言えない可愛らしさがあります。
暖かさを感じて眠っている時の姿は穏やかで、とても気持ち良さそうに見えます。
猫は寒さを感じると体を小さくして丸める生き物で、体をコンパクトにすることで熱が逃げるのを最小限に抑えています。
丸くなる姿がアンモナイトに似ている事から、アンモニャイトと呼ばれる事もあり寒さを感じているサインのひとつです。
猫が眠っている姿を眺めていると、人間のように体勢を変える様子は何とも言えない可愛らしさがあります。
暖かさを感じて眠っている時の姿は穏やかで、とても気持ち良さそうに見えます。
布団の中に潜る
猫は寒さを感じると、布団や毛布などが暖かい事を知っていて潜って体を暖めようとします。
布団や毛布に潜ってしまうと気づかない事もあり、間違って踏んでしまわないよう注意が必要です。
いつもいる場所に見当たらない時は、布団や毛布に潜って気持ち良さそうに過ごしている事もあります。
特に自分の匂いや飼い主の匂いがする布団や毛布は、安心して眠る事ができる様です。
毛が逆立っている
 猫が威嚇している時に毛が逆立つのを見る事が多いと思いますが、寒さを感じても毛を逆立てます。
寒さを感じた時は怒っているのではなく、逆立った毛と毛の間に空気を入れて体から熱が逃げないようにしています。
空気の層を纏う事ができて、体から熱が逃げない仕組みになっています。
猫にも野生の血が流れていて、産まれた時から自分を守れるように備わっているのかもしれません。
猫が威嚇している時に毛が逆立つのを見る事が多いと思いますが、寒さを感じても毛を逆立てます。
寒さを感じた時は怒っているのではなく、逆立った毛と毛の間に空気を入れて体から熱が逃げないようにしています。
空気の層を纏う事ができて、体から熱が逃げない仕組みになっています。
猫にも野生の血が流れていて、産まれた時から自分を守れるように備わっているのかもしれません。
水を飲まなくなる
猫は寒さを感じると、水をあまり摂取しなくなります。
水を飲むことで体が冷えるため、水を飲むのを毛嫌いするようになります。
水分不足は病気を引き起こす恐れがあり、体の不調にもつながってしまいます。
寒い冬でも水分補給がしっかりできるように、過ごしやすい室温にする事が大切です。
水を嫌がるような時は、ぬるま湯にしてあげるのもひとつの方法です。
飼い主に寄り添う
 猫は寒くなると飼い主の膝の上に乗ってくつろいだり、一緒の布団で眠る行動が多く見られるようになります。
猫は気ままな一面もあり、ずっと一緒に布団で寝ていたのに急に来なくなってしまう事もあります。
飼い主にとっては寂しく感じてしまう事もありますが、猫に気を使わずに眠ると体が楽な場合もあります。
多頭飼育をしている場合は猫同士で仲良く寄り添って眠る様子が見られ、その光景には何となく癒されます。
寒い冬はおたがいに温め合う事で、信頼関係も深まるかもしれませんね!
猫は寒くなると飼い主の膝の上に乗ってくつろいだり、一緒の布団で眠る行動が多く見られるようになります。
猫は気ままな一面もあり、ずっと一緒に布団で寝ていたのに急に来なくなってしまう事もあります。
飼い主にとっては寂しく感じてしまう事もありますが、猫に気を使わずに眠ると体が楽な場合もあります。
多頭飼育をしている場合は猫同士で仲良く寄り添って眠る様子が見られ、その光景には何となく癒されます。
寒い冬はおたがいに温め合う事で、信頼関係も深まるかもしれませんね!
猫の正しい寒さ対策
 猫が過ごしやすい室温は18〜26度程度で、その日の気温や体調に合わせて設定をしてあげる必要があります。
人間が使用している冷暖房のエアコンやこたつ、湯たんぽなどを、猫の寒さ対策にどのように用いれば安全なのかを調べて見ました。
猫が過ごしやすい室温は18〜26度程度で、その日の気温や体調に合わせて設定をしてあげる必要があります。
人間が使用している冷暖房のエアコンやこたつ、湯たんぽなどを、猫の寒さ対策にどのように用いれば安全なのかを調べて見ました。
窓や床から離れたところに寝床を作る
猫が寒がっている場合は、寝床などのお気に入りのスペースを寒さから守るために、床や窓など冷気のある場所から離してあげるようにします。
お気に入りの場所ではなく嫌がるような場合は、自分の匂いの付いた毛布など安心できるものを敷いてあげるとストレスやイライラはなくなるようです。
猫にはお気に入りの場所が幾つかありますので、穏やかに過ごせるような場所を探して寒さから守ってあげたいものですね。
冷暖房のエアコンで適温を維持する
 日が落ちて気温がグッと下がった頃に温度を20度前後になるようにタイマーセットをしてあげれば、暑くなり過ぎる心配もなく寒さ対策ができます。
エアコンは安全性が高く適温を維持する事ができますが、エアコンのリモコンに猫が触れてしまわないよう離れた場所へ置くようにします。
猫がリモコンをいたずらしたり、コード類をかじらないよう注意する事も大切です。
日が落ちて気温がグッと下がった頃に温度を20度前後になるようにタイマーセットをしてあげれば、暑くなり過ぎる心配もなく寒さ対策ができます。
エアコンは安全性が高く適温を維持する事ができますが、エアコンのリモコンに猫が触れてしまわないよう離れた場所へ置くようにします。
猫がリモコンをいたずらしたり、コード類をかじらないよう注意する事も大切です。
ブラッシングを行う
毛が抜ける時期にブラッシングを頻繁に行いますが、寒い季節は猫の血行を良くするためにこまめなブラッシングをしてあげるようにします。
乾燥によってブラッシング中に毛が舞ってしまったり、静電気が起きてしまうとブラッシングを嫌がってしまう猫もいます。
静電気が起らないようにブラッシングスプレーを使うのも効果的で、部屋の湿度調節も忘れずに行うようにします。
こたつを用意する
 猫からするとこたつ布団は重く、こたつの中から出たくても出られなくなってしまう心配があります。
猫をこたつに入れる際はあらかじめ猫の抜け道を作ってあげ、温度を低めに設定するなどして危険性を少しでも無くすようにします。
猫用こたつならヒーターが直接体に当たらないよう配慮されていますので、人間のこたつよりも安心して使えます。
好奇心旺盛な猫はコードをかじってしまう心配がありますが、かじっても感電しないように工夫がされていて安全です。
猫からするとこたつ布団は重く、こたつの中から出たくても出られなくなってしまう心配があります。
猫をこたつに入れる際はあらかじめ猫の抜け道を作ってあげ、温度を低めに設定するなどして危険性を少しでも無くすようにします。
猫用こたつならヒーターが直接体に当たらないよう配慮されていますので、人間のこたつよりも安心して使えます。
好奇心旺盛な猫はコードをかじってしまう心配がありますが、かじっても感電しないように工夫がされていて安全です。
湯たんぽを使用する
湯たんぽは電気を使用する暖房器具と異なり、飼い主さんが見守れない時でも活用しやすく安心です。
低温やけどをしないよう注意が必要ですが、やや熱いと感じた時はバスタオルなどでくるんであげるようにします。
湯たんぽは色々なデザインや種類が豊富ですので、選ぶ楽しみもあり愛猫が気に入ってくれるものもきっとあるはずです。
猫が寒い冬を湯たんぽでぬくぬく過ごす様子は、飼い主にとっても癒されるかもしれませんね。
ペット用のヒーターを使う
 ペットヒーターには猫が丸まりながら眠っても体が収まるようなまん丸型や、可愛いねこ鍋型なども販売されていて選ぶ楽しみもあります。
ペット用であればコードを噛んでしまった時の感電の心配や、温度などの操作ができないよう工夫や対策がされています。
人間用のヒーターでは低温やけどなどの心配がありますが、留守番などが多い場合でも安心して使えます。
ケガややけどの心配がいらない、猫専用の暖房器具の購入を考えてみるのもいいかもしれませんね!
ペットヒーターには猫が丸まりながら眠っても体が収まるようなまん丸型や、可愛いねこ鍋型なども販売されていて選ぶ楽しみもあります。
ペット用であればコードを噛んでしまった時の感電の心配や、温度などの操作ができないよう工夫や対策がされています。
人間用のヒーターでは低温やけどなどの心配がありますが、留守番などが多い場合でも安心して使えます。
ケガややけどの心配がいらない、猫専用の暖房器具の購入を考えてみるのもいいかもしれませんね!
まとめ
日本には四季があってそれぞれの季節に風情や魅力がありますが、寒い冬を乗り切るために様々な工夫をしています。
寒さに弱く冬が苦手な猫にとっても寒さ対策は重要で、安全で安心して使える暖房器具が必要になります。
愛猫が病気やケガをしないように見守りながら、お互いが快適に冬を過ごせればいいですね!
犬に布団は必要?
 地域によって特に厳しい真冬の寒さは、愛犬の体調やシニア犬・持病の有無などによって布団を用意してあげたほうが良い場合があります。
また、体温調整が上手にできないパピーやシングルコートの犬は寒さに弱いので、愛犬の状態をよく考えて配慮してあげましょう。
人と同じで、あまりに寒い環境にいることによって体調を崩したり食欲不振になったりして健康にも影響が出てしまいます。
特に夜中や明け方に気温は急降下しますので、部屋を温めていても暖房を止めたあとの愛犬のベッド周りの温度管理として適切な種類を用意します。
地域によって特に厳しい真冬の寒さは、愛犬の体調やシニア犬・持病の有無などによって布団を用意してあげたほうが良い場合があります。
また、体温調整が上手にできないパピーやシングルコートの犬は寒さに弱いので、愛犬の状態をよく考えて配慮してあげましょう。
人と同じで、あまりに寒い環境にいることによって体調を崩したり食欲不振になったりして健康にも影響が出てしまいます。
特に夜中や明け方に気温は急降下しますので、部屋を温めていても暖房を止めたあとの愛犬のベッド周りの温度管理として適切な種類を用意します。
犬が布団に潜る理由
 愛犬と一緒に寝ている飼い主様は、布団に潜り込んでくる愛犬の可愛らしい仕草に毎晩癒やされているのではないでしょうか。
寝返りが出来なくて体が痛いな、と思いながらも幸せな気分を感じる瞬間でもあります。
でもなぜ、布団に潜るのかご存知ですか。
布団に潜る犬の気持ちをご紹介していきます。
愛犬と一緒に寝ている飼い主様は、布団に潜り込んでくる愛犬の可愛らしい仕草に毎晩癒やされているのではないでしょうか。
寝返りが出来なくて体が痛いな、と思いながらも幸せな気分を感じる瞬間でもあります。
でもなぜ、布団に潜るのかご存知ですか。
布団に潜る犬の気持ちをご紹介していきます。
飼い主の匂いがするから
大好きな飼い主様の匂いは、愛犬が一番落ち着くことができます。
信頼している人の匂いがある布団は、ゆっくりと安心して眠れる場所でしょう。
スリッパを咥えて持ち去る犬や、飼い主様が履いている靴下を脱がせて奪っていく犬の動画を見たことはありませんか。
実際に、一緒に暮らしている飼い主様の匂いを嗅いだ犬は、大好きな感情や安心を感じていると科学的に根拠のある研究も行われているようです。
匂いが強く残っているものを好む犬は、家族である飼い主様を近くで感じてリラックスしているんですね。
飼い主と一緒にいたいから
 お散歩で他の犬に会ったとき、「お友達なんだから仲良くね」とか、上手に挨拶できない愛犬に「お友達」がいないから可愛そうと思うことはありませんか。
確かに同じ犬同士で仲良くしている姿は、とても可愛らしく嬉しいことかもしれません。
ですが、愛犬は自分を一番に考えて愛してくれる飼い主様がいてくれれば幸せなんです。
一緒にいてくれて可愛がってくれる存在である飼い主様と、眠るときも一緒にいたいと感じているからこそ同じ布団に潜ってくれるんですね。
お散歩で他の犬に会ったとき、「お友達なんだから仲良くね」とか、上手に挨拶できない愛犬に「お友達」がいないから可愛そうと思うことはありませんか。
確かに同じ犬同士で仲良くしている姿は、とても可愛らしく嬉しいことかもしれません。
ですが、愛犬は自分を一番に考えて愛してくれる飼い主様がいてくれれば幸せなんです。
一緒にいてくれて可愛がってくれる存在である飼い主様と、眠るときも一緒にいたいと感じているからこそ同じ布団に潜ってくれるんですね。
寝心地が良いから
犬は柔らかいものが好きで、とても心地良いと感じます。
暑いときはフローリングや玄関など硬くてひんやりした場所で過ごすこともありますが、頭だけはタオルやペットベッドの上に乗せていることもありますよね。
愛犬の居場所が決まっていない段階で、床に柔らかい敷物やクッションを置いておけば高い確率でその上に落ち着くでしょう。
他にもソファや座椅子など、人がいないときにいつのまにか乗っている姿を見ることも多いのではないでしょうか。
寝心地と柔らかい感触を感じられる布団は、人だけではなく犬にとっても気持ちの良い場所なんです。
寒いと感じているから
 どちらかというと暑さには弱く寒さには強いといわれている犬ですが、寒くても平気なわけではありません。
前述のとおり、シングルコートの犬種やシニア犬など一部の犬は寒さによって体調を崩すこともあり、健康な犬でも寒いよりは適温を好みます。
特に昨今は、大型犬でも室内で育てる傾向にありますので寒さをより感じやすくなってきました。
温かい場所で眠ることは、犬にとって至福の時間でもあります。
どちらかというと暑さには弱く寒さには強いといわれている犬ですが、寒くても平気なわけではありません。
前述のとおり、シングルコートの犬種やシニア犬など一部の犬は寒さによって体調を崩すこともあり、健康な犬でも寒いよりは適温を好みます。
特に昨今は、大型犬でも室内で育てる傾向にありますので寒さをより感じやすくなってきました。
温かい場所で眠ることは、犬にとって至福の時間でもあります。
狭い場所で安心だから
はるか昔、犬の祖先は敵から身を守るために狭い穴蔵で家族や仲間と共に眠りにつきました。
お互いが密着して過ごせば温かいばかりか、目の届かない背後も仲間がいてくれる安心感でゆっくり眠れたようです。
また、子育てにも活用されていた狭い空間は独り立ちするまで寂しさや不安を感じず過ごした経験が刷り込まれ、その頃の習性が現代の犬にも残っており狭く暗い布団の中に潜ると安心できるのです。
犬が布団に潜る際の注意点
 犬が布団に潜ることは、安心感を与える良いことに思いますが危険な場面も多々存在します。
飼い主様にとって困ってしまうことが起きる可能性もありますので、注意が必要となります。
犬の性格に合わせて飼い主様が対処して、安全な環境を用意してあげましょう。
犬が布団に潜ることは、安心感を与える良いことに思いますが危険な場面も多々存在します。
飼い主様にとって困ってしまうことが起きる可能性もありますので、注意が必要となります。
犬の性格に合わせて飼い主様が対処して、安全な環境を用意してあげましょう。
マーキングをする
布団は犬にとってお気に入りの場所である一方、自分の居場所としてマーキングしてしまう犬も少なくないようです。
個体差はありますが、犬の本能的な行動として縄張りを主張するためともいわれています。
もし万が一、布団にオシッコをされても騒がずに拭き取りと洗濯を行ってニオイが残らないようにします。
他にも、ベッドの場合に自分で降りられなくなってトイレまで間に合わずに漏らしてしまうことも。
犬専用のスロープや簡易階段などを設置し、降りたいときに自由に動けるように配慮してあげましょう。
ホリホリしてしまう
 前足で一生懸命、布団をホリホリして寝床を整える様子は見ていてとても微笑ましいものです。
しかし、力の強い犬や大型犬の場合は特に、ホリホリが強すぎて布団が破けたり中綿が飛び出たりして飼い主様が驚くような状態になる可能性も考えられます。
カバーを丈夫なものに取り替えるなどの工夫が必要となります。
また、昼間にしっかり体を動かして疲れた状態にすることも対処法としてある程度は有効と考えられています。
いずれにしても、愛犬の性格や体調を考えて掘らなくても安心して眠れるようにしてあげたいですね。
前足で一生懸命、布団をホリホリして寝床を整える様子は見ていてとても微笑ましいものです。
しかし、力の強い犬や大型犬の場合は特に、ホリホリが強すぎて布団が破けたり中綿が飛び出たりして飼い主様が驚くような状態になる可能性も考えられます。
カバーを丈夫なものに取り替えるなどの工夫が必要となります。
また、昼間にしっかり体を動かして疲れた状態にすることも対処法としてある程度は有効と考えられています。
いずれにしても、愛犬の性格や体調を考えて掘らなくても安心して眠れるようにしてあげたいですね。
怪我の危険性がある
飼い主様が見ていないところで、愛犬がベッドから飛び降りて怪我をしたり腰を痛めたりすることもあります。
何かあっても眠っていると対応が遅れてしまい、愛犬が怪我をしても朝までそのまま、ということも考えられます。
一方で、飼い主様が寝返りしたときに愛犬を潰してしまう・落としてしまうといった事故も少なくありません。
超小型犬やシニア犬は落ち着いて眠れない場合もありますので、一緒に眠るときは十分注意してあげてください。
犬が寒がっているサインは?
 愛犬が寒がっているサインを逃さずに温かさを保ってあげることで、健康と心の安定を守ることが大切となります。
では、愛犬のどんな様子で判断すればよいのでしょうか。
愛犬が寒がっているサインを逃さずに温かさを保ってあげることで、健康と心の安定を守ることが大切となります。
では、愛犬のどんな様子で判断すればよいのでしょうか。
体をコンパクトに縮めている
体を丸めてできる限り冷たい空気に体が触れないようにします。
鼻先を自分の尻尾で覆うような形となり、鼻から取り入れる空気の冷たさを和らげているともいわれています。
自分の居場所でこのようなポーズの場合は安心感も感じられるようですが、犬の体を触って冷えている場合は寒いと感じている目安となるでしょう。
ベッドから出てこない
 朝、いつも起きている時間になってもベッドから出てこないことも寒さを感じているサインと捉えましょう。
人も寒い日の朝は、布団から出るのが嫌ですよね。
なかなか起きられない状態なのは、冷たい空気に触れるのを嫌がっていると考えられます。
朝、いつも起きている時間になってもベッドから出てこないことも寒さを感じているサインと捉えましょう。
人も寒い日の朝は、布団から出るのが嫌ですよね。
なかなか起きられない状態なのは、冷たい空気に触れるのを嫌がっていると考えられます。
体を寄せてくる
飼い主様や家族にピッタリと体を寄せてきたり膝の上に乗ってきたりしているときは、暖を取るための仕草といえます。
ですが、信頼している飼い主様に日頃から体を寄せやすい犬の習性から、甘えている可能性もあります。
いつもと違う様子が見られたら寒がっているのかもしれないので、よく観察して適切な対応を心掛けましょう。
犬の寒さ対策
 愛犬を寒さから守り、快適な生活を送ってもらうために必要な対策を施しましょう。
でも、具体的にはどうしたら良いのか犬飼い初心者さんは特に悩みどころかもしれません。
危険の少ない方法を、愛犬の性格や体調に合わせて選んであげてください。
愛犬を寒さから守り、快適な生活を送ってもらうために必要な対策を施しましょう。
でも、具体的にはどうしたら良いのか犬飼い初心者さんは特に悩みどころかもしれません。
危険の少ない方法を、愛犬の性格や体調に合わせて選んであげてください。
犬用のこたつに入る
最近は犬専用のこたつが売られているのをご存知でしょうか。
人用のこたつを小さくしたような形をしており、布団を掛けて使用しますので電源が入っていなくても冷たい空気が遮断されてぬくぬくと過ごしてくれるでしょう。
四方が囲まれている安心感と適度な暖かさは、飼い主様が留守中でも心配なくお留守番してもらえるはずです。
「中に入れても出てこれなかったら・・」と不安な飼い主様には、布団の一部がカットされているタイプや出入りしやすいようにノレンのように短くなっている布団も販売されています。
性格や体力に合わせて選択肢が多く、多頭飼いにも適しています。
湯たんぽを使う
 昔から使用されてきた湯たんぽは、火を使わずに暖かさを長時間キープすることができるので最近ではまた良さを見直されてきているアイテムです。
ですが、体を動かしにくいシニア犬は特に気づかないうちに低温やけどの可能性も考えられます。
飼い主様が側で注意してあげられないときは、使用を控えたりタオルを巻いたりして調節し安全面に配慮してあげてください。
お湯を入れるタイプの他に、電子レンジで中材を温めて使用するタイプもあります。
他にも、噛じりグセのある愛犬には固いプラスティック製のタイプを選ぶなど素材や大きさも様々に販売されています。
昔から使用されてきた湯たんぽは、火を使わずに暖かさを長時間キープすることができるので最近ではまた良さを見直されてきているアイテムです。
ですが、体を動かしにくいシニア犬は特に気づかないうちに低温やけどの可能性も考えられます。
飼い主様が側で注意してあげられないときは、使用を控えたりタオルを巻いたりして調節し安全面に配慮してあげてください。
お湯を入れるタイプの他に、電子レンジで中材を温めて使用するタイプもあります。
他にも、噛じりグセのある愛犬には固いプラスティック製のタイプを選ぶなど素材や大きさも様々に販売されています。
冷暖房のエアコンを活用する
大型犬や部屋の中でフリーにしている場合、お部屋のエアコンを入れてあげると愛犬がどこにいても暖かさをキープできる手軽な方法として活用できます。
愛犬だけでなく飼い主様や家族も一緒に暖かさを感じられるので、気温の変化に上手に対応してあげることが可能です。
最近では外出時にスマホからエアコンの操作もできるようになり、お留守番も安心して体調管理をしてあげられるでしょう。
ペット用のヒーターを使用する
 ペット用の小型のヒーターも種類が増えてきており、愛犬のベット周りに簡単に設置することができます。
コの字型で立てて使用するタイプや、サークルの床面に置いて下から温めるタイプなど様々な形から選べます。
愛犬が暑さを感じたときに逃げられるように、サークルで使用する場合は何も置いていないスペースを確保することも大切です。
大きさもたくさんあり、サークル内のスペースが取れない場合は小さいタイプを選ぶと良いでしょう。
ペット用の小型のヒーターも種類が増えてきており、愛犬のベット周りに簡単に設置することができます。
コの字型で立てて使用するタイプや、サークルの床面に置いて下から温めるタイプなど様々な形から選べます。
愛犬が暑さを感じたときに逃げられるように、サークルで使用する場合は何も置いていないスペースを確保することも大切です。
大きさもたくさんあり、サークル内のスペースが取れない場合は小さいタイプを選ぶと良いでしょう。
まとめ
もふもふの体は見るからに温かそうで、つい寒さ対策もおざなりになりがちかもしれません。
年齢や体調・犬種や環境によって、犬にも寒さ対策が必要となります。
愛犬の様子をよく観察して、適切な体調管理をしてあげてください。
また、せっかく暖かい環境を作っても快適に過ごしてもらわないと意味がありません。
暑くなったときにクールダウンできるスペースや、飲水の設置も忘れずに用意してあげましょう。
猫と関われる仕事は?専門知識が必要な職業
 猫に関わる仕事をしたいと思った時に、専門知識の有無や資格の必要性を一番に考えるのではないでしょうか?
ペットに関わる仕事は増えていて、自分がしたいものや合ったものの仕事に就くための情報を集めて見ました。
猫に関わる仕事をしたいと思った時に、専門知識の有無や資格の必要性を一番に考えるのではないでしょうか?
ペットに関わる仕事は増えていて、自分がしたいものや合ったものの仕事に就くための情報を集めて見ました。
キャットトリマー
猫専門のトリミング屋さんをキャットトリマーと呼び、仕事内容は人間の美容師とあまり変わりがないようです。
ブラッシングやシャンプーを行い、しっかり乾かしてから毛をカットし綺麗な状態にします。
国家資格はありませんが、民間資格のJKCの公認トリマー1級、2級が必要で専門知識を学ぶには最適な職業です。
資格を取得する場合はトリマー育成の為の専門学校や、通信講座で学ぶ方法があります。
ブリーダー
 猫のブリーダーであれば猫の繁殖を専門にしており、交配~出産まで全てのサポートを行います。
繁殖して生まれた健康な猫を市場に送り出す仕事で、深い知識と経験が必要になります。
産まれた子猫の世話や産後の母猫の健康管理と維持、仕事内容は多岐にわたります。
必要な資格は動物取扱業の届出と、民間資格のJCSA認定ドックブリーダー、ペット繁殖指導員、動物看護師、愛玩動物飼養管理士になります。
ペットに関する知識や技術が学べる専門学校で、資格を取得する事ができます。
猫のブリーダーであれば猫の繁殖を専門にしており、交配~出産まで全てのサポートを行います。
繁殖して生まれた健康な猫を市場に送り出す仕事で、深い知識と経験が必要になります。
産まれた子猫の世話や産後の母猫の健康管理と維持、仕事内容は多岐にわたります。
必要な資格は動物取扱業の届出と、民間資格のJCSA認定ドックブリーダー、ペット繁殖指導員、動物看護師、愛玩動物飼養管理士になります。
ペットに関する知識や技術が学べる専門学校で、資格を取得する事ができます。
ペットセラピスト(猫のストレスケア)
ペットセラピストはペットのストレスを軽減させる専門家のことを指し、ケアを行う事で問題行動を予防する大きな目的があります。
資格がなくても猫のストレスをケアしてあげる事ができますが、資格を取得していれば飼い主からの信頼を得るメリットがあります。
猫専門のペットセラピストになりたい場合は、キャットケアスペシャリストやキャットフレンドリーパーソン検定といった資格を取得する人が多いようです。
キャットシッター
 キャットシッターはペットシッターとも言い、お留守番する猫が快適な環境で過ごせるよう大切に丁寧にお世話をする仕事です。
環境の変化が苦手な猫にとって、暮らし慣れた大好きな家での留守番が一番ストレスを感じずに過ごせる方法です。
必要資格は動物取扱業登録申請と、民間資格の認定ペットシッターになります。
資格を取得する場合はペットシッタースクールや、キャットシッター養成講座の受講する方法があります。
キャットシッターはペットシッターとも言い、お留守番する猫が快適な環境で過ごせるよう大切に丁寧にお世話をする仕事です。
環境の変化が苦手な猫にとって、暮らし慣れた大好きな家での留守番が一番ストレスを感じずに過ごせる方法です。
必要資格は動物取扱業登録申請と、民間資格の認定ペットシッターになります。
資格を取得する場合はペットシッタースクールや、キャットシッター養成講座の受講する方法があります。
動物プロダクション
動物プロダクションには芸能事務所のように、ただ可愛いだけではなく撮影現場できちんと演技ができる動物タレントが多数所属しています。
所属猫の出演作品をより良いものにする為にはしっかりとした調教と演技指導が必要になり、猫が最高のパフォーマンスを発揮できるようにサポートをする仕事です。
必要資格には動物取扱業登録申請があり、資格を取得するには専門学校で動物についての知識を学びます。
動物愛護保護施設(報酬ありのスタッフ)
 飼い主がいない動物を保護する仕事で、正しい動物の飼育方法などの啓発活動も行います。
保護した子が病気になっている場合も多く、回復するまで面倒を見てあげ新しい飼い主を探す活動もあります。
施設の運営資金は寄付によってまかなわれている事が多く、募金活動の仕事も重要です。
動物の福祉を向上させていく仕事の為、日々の動物の観察も必要になります。
必要資格には動物取扱責任者と、動物取扱業登録申請があります。
資格を取得する場合は、専門学校で動物についての知識を学びます。
飼い主がいない動物を保護する仕事で、正しい動物の飼育方法などの啓発活動も行います。
保護した子が病気になっている場合も多く、回復するまで面倒を見てあげ新しい飼い主を探す活動もあります。
施設の運営資金は寄付によってまかなわれている事が多く、募金活動の仕事も重要です。
動物の福祉を向上させていく仕事の為、日々の動物の観察も必要になります。
必要資格には動物取扱責任者と、動物取扱業登録申請があります。
資格を取得する場合は、専門学校で動物についての知識を学びます。
愛玩動物飼養管理士
愛玩動物飼養管理士は動物の愛護活動や正しい飼育の方法を普及啓発を行う為に、十分な知識を得ているスペシャリストの資格です。
公益社団法人日本愛玩動物協会が主催する認定を行う資格で、独学での取得も可能です。
取得する為には教本での勉強後、講習会への出席、課題を提出する事で受験の資格が得られます。
学習を通じてペットに関する知識が身に付けられ、動物関係の仕事に就職する際にも有利です。
猫と関われる仕事は?未経験でもOKな職業
 猫に関しての専門的な知識や資格がないと働けない事もありますが、ある程度の知識とやる気があれば大丈夫なものもあるようです。
学ぶチャンスや余裕のない人の為に、未経験でもOKな職業をいくつか紹介します。
猫に関しての専門的な知識や資格がないと働けない事もありますが、ある程度の知識とやる気があれば大丈夫なものもあるようです。
学ぶチャンスや余裕のない人の為に、未経験でもOKな職業をいくつか紹介します。
ペットショップ店員
猫や他の動物関係の仕事が未経験の場合でも、ペットショップ店員として働くという方法があります。
ペットショップでは、飼育されているペットの世話が主な仕事になります。
最近ではペットホテル、ペットサロンが併設されているペットショップも増えていて、それらの受付などの仕事もあります。
ペットショップの店員になる為には、アルバイトとして就職し正社員を目指すのが一般的です。
多くのペットショップでは猫以外の動物も飼育している為、猫以外の担当になる場合もあります。
動物病院スタッフ(事務・受付など)
 動物病院には獣医や看護師だけではなく、事務や受付などを行うスタッフも必要となります。
入院中の猫のケアや、電話や来院される飼い主からの質問に対する応対をします。
病気についての質問であれば、獣医師に的確に伝え診察の介助を行います。
他にはカルテの管理、会計処理、ダイレクトメールの管理、書類作成、薬の在庫管理、来院予約管理などがあります。
動物病院での勤務となり、専門学校や大学を出ていれば仕事ができます。
動物病院には獣医や看護師だけではなく、事務や受付などを行うスタッフも必要となります。
入院中の猫のケアや、電話や来院される飼い主からの質問に対する応対をします。
病気についての質問であれば、獣医師に的確に伝え診察の介助を行います。
他にはカルテの管理、会計処理、ダイレクトメールの管理、書類作成、薬の在庫管理、来院予約管理などがあります。
動物病院での勤務となり、専門学校や大学を出ていれば仕事ができます。
猫カフェ店員
猫カフェでは経験や資格が問われる事がなく、猫に関わる仕事をしたい方に最適です。
仕事内容も比較的複雑ではなく、初心者にとっても挑戦しやすく注目度が高く人気があります。
その為働きたい人も多く、競争率は高くなってしまいます。
猫カフェの場合は猫だけを飼っていますので、猫が好きな方や中々飼えない人にとってもやりがいのある仕事です。
ペット用品メーカー
 動物に関わる仕事に就きたい場合は、ペット用品メーカーに就職する方法もあります。
ペット用品メーカーは新卒を多く採用しますので、ペット関係の仕事が未経験で資格が無くても就職が可能です。
ペット用品には様々なジャンルがあり、幅広くペットに関わる事ができる魅力があります。
一般採用となる為、就職活動を通じて内定を得る事が条件となります。
動物に関わる仕事に就きたい場合は、ペット用品メーカーに就職する方法もあります。
ペット用品メーカーは新卒を多く採用しますので、ペット関係の仕事が未経験で資格が無くても就職が可能です。
ペット用品には様々なジャンルがあり、幅広くペットに関わる事ができる魅力があります。
一般採用となる為、就職活動を通じて内定を得る事が条件となります。
ペットホテル従業員
ペットホテルは飼い主が家を留守にする時、ペットを預ける場所のことです。
ペットの世話は経験が豊富で資格のあるスタッフが行いますので、ペット関係の仕事が未経験でも掃除や受付などをする従業員として入社することができます。
ペットホテルは猫専門の施設も多く学歴や資格などが問われませんので、どうしても猫に関わる仕事をしたい方におすすめです。
猫と関わる仕事にあると便利な資格
 自分の望む仕事に就きたいと思っても、学歴や資格がないせいで諦めなくてはいけない場合があります。
悔しい思いをしなですむように、猫に関わる仕事をする時に便利な資格をいくつか紹介します。”
自分の望む仕事に就きたいと思っても、学歴や資格がないせいで諦めなくてはいけない場合があります。
悔しい思いをしなですむように、猫に関わる仕事をする時に便利な資格をいくつか紹介します。”
資格①:キャットケアスペシャリスト
日本ペット技能検定協会から認定されている資格で、猫の飼育管理や猫学、動物看護学、ペット社会学、動物介護学などを学ぶ事ができます。
キャットケアスペシャリストを持つ事で、猫に関する知識が得られ顧客に対する信頼度も高くなります。
この資格を取得するには各会社で実施している資格講座を履修し、試験に合格しなくてはなりません。
時間がかかってしまいますが、取得しておけば損はないと思います。
資格②:キャットシッター
 キャットシッターのスペシャリストを目指すための資格で、日本ペット技能検定協会で取得する事ができます。
ヒューマンアカデミーの「キャットスペシャリスト」ならキャットシッターの資格も同時に取得が可能です。
猫と関わる仕事をする場合に持っていると役立ちます。
お客様次第の仕事ですので収入などは安定しませんが、副業をはじめたいと考えている方におすすめです。
キャットシッターのスペシャリストを目指すための資格で、日本ペット技能検定協会で取得する事ができます。
ヒューマンアカデミーの「キャットスペシャリスト」ならキャットシッターの資格も同時に取得が可能です。
猫と関わる仕事をする場合に持っていると役立ちます。
お客様次第の仕事ですので収入などは安定しませんが、副業をはじめたいと考えている方におすすめです。
資格③:動物看護師資格
動物看護師になりたい場合や、猫と関わる様々な仕事をする上でも役に立つ資格です。
取得する為には大学、短大、専門学校で所定の動物看護学を学ぶ必要があります。
動物看護師は現在統一化する為に、動物看護認定統一試験を実施しています。
動物看護師は獣医師をサポートする役目としても重要で、きちんとした知識があればこそ的確にできる仕事です。
まとめ
猫に関わる仕事には様々な種類があり、学歴や資格がなくても問われないものと駄目なものがあります。
時間や学ぶ余裕がない人は未経験でも大丈夫な所からはじめ、自分に向いているかどうかを試してみるのもいいかもしれません。
猫はとても可愛らしく癒されますが、生き物のですので甘い考えでは務まらない場合もあります。
資格を取得する事で自分にとっての自信にもなり、猫に寄り添った仕事ができるのではないでしょうか?
猫は犬より賢い?犬との違い
 テレビで放送されている盲導犬や警察犬などが活躍する姿は、人間よりも頭がいいのではと思う事があります。
猫も人間と一緒に暮らしているうちに、芸まではいかなくても驚く行動を見せてくれます。
猫と犬の賢さの違いを調べて見ました。
テレビで放送されている盲導犬や警察犬などが活躍する姿は、人間よりも頭がいいのではと思う事があります。
猫も人間と一緒に暮らしているうちに、芸まではいかなくても驚く行動を見せてくれます。
猫と犬の賢さの違いを調べて見ました。
脳化指数では犬の方が賢い
脳化指数では犬が1.2で、人間の子供の3〜4歳程度と同じくらいの知能があります。
猫は1.0で人間の子供の2歳程度と同じくらいの知能ですので、ほんの些細な差ではありますが犬の方が賢いと言えるかもしれません。
しかし犬のようにトイレのしつけが難しくなく、ドアも自分で開けられる事から猫の方が賢いと主張する人もいます。
脳化指数はあくまでも目安で猫と犬にも個人差があり、統計すれば犬の方が賢いのかもしれません。
猫が賢いのは自発的に学習するから
 猫は勝手気ままに行動する習性がある動物で、誰かに教わるのではなく自発的に学習するスタイルが身についています。
ドアの向こうに目的の物があれば、人間の様子を見ながらドアの開け方を学習します。
いつももらえるおやつの引き出しがあれば、自分で引き出しを開けて食べようとします。
外に出たい時には飼い主の行動をよく観察していて、玄関や窓が開く瞬間を逃さず素早い動きを見せます。
猫は飼い主が「いつ覚えたのだろう」と思う事をやって、日々驚かせ笑わせてもくれるようです。
猫は勝手気ままに行動する習性がある動物で、誰かに教わるのではなく自発的に学習するスタイルが身についています。
ドアの向こうに目的の物があれば、人間の様子を見ながらドアの開け方を学習します。
いつももらえるおやつの引き出しがあれば、自分で引き出しを開けて食べようとします。
外に出たい時には飼い主の行動をよく観察していて、玄関や窓が開く瞬間を逃さず素早い動きを見せます。
猫は飼い主が「いつ覚えたのだろう」と思う事をやって、日々驚かせ笑わせてもくれるようです。
猫にも見られる帰巣本能
動物の帰巣本能は嗅覚や方向感覚に頼るだけではなく、体内時計や磁気を感知する器官など様々な能力を働かせて機能しています。
犬ほどではありませんが、賢い猫にも少なからず帰巣本能があります。
飼い主が探しても見つからず、諦めていた頃に何もなかったように帰ってくる事もあります。
猫の帰巣本能は個体差が激しいようで、迷子になって帰ってこない場合もあります。
必ず帰ってくるという保証はありませんので、できるだけ迷子にならないように注意してあげる事が大切です。
猫が賢い理由
 猫は犬よりも劣る面もありますが、脳は人間と似ている構造をしています。
そのせいもあり人間の行動を見て学習し、ドアや引き出しなどを器用に開ける事が出来る様です。
他にも賢い理由を詳しく調べてみました。
猫は犬よりも劣る面もありますが、脳は人間と似ている構造をしています。
そのせいもあり人間の行動を見て学習し、ドアや引き出しなどを器用に開ける事が出来る様です。
他にも賢い理由を詳しく調べてみました。
短期記憶力が優れている
短期記憶とはほんの数十秒~1分間くらいしか残らない記憶の事で、瞬間的に見た物を覚えるという能力です。
猫はこの短期記憶が人間よりも優れていて、なんと10分以上もあり人間の20倍だと言われています。
この短期記憶力が発揮されるのは、猫が興味を持つものに限られています。
おやつには優れた能力を発揮しますが、おもちゃや他の物にはあまり期待できないようです。
衝撃的なことは長期間覚えられる
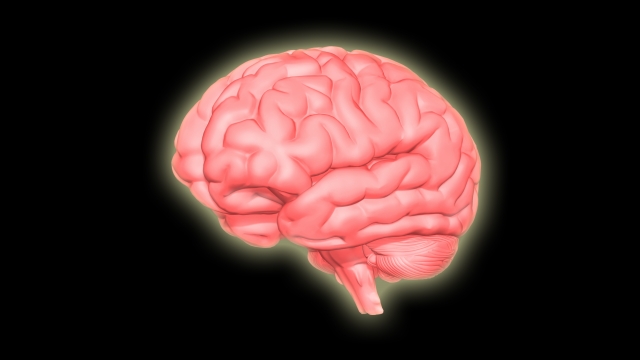 短期記憶とは違い、長い期間覚えていられる記憶のことを長期記憶と言います。
猫はインパクトの大きい怖い記憶なども長く覚えている為、その時の記憶が蘇り反応を起こす事もあります。
キャリーケースに入り車に乗せられて動物病院に行き、注射や爪切りなど嫌な思いをした事は記憶に残っています。
その為キャリーバックや車、動物病院を見るだけで嫌がったり逃げ出してしまいます。
薬を無理に飲まされた事も覚えていて、準備をしている飼い主の様子を見ただけで避けようとします。
短期記憶とは違い、長い期間覚えていられる記憶のことを長期記憶と言います。
猫はインパクトの大きい怖い記憶なども長く覚えている為、その時の記憶が蘇り反応を起こす事もあります。
キャリーケースに入り車に乗せられて動物病院に行き、注射や爪切りなど嫌な思いをした事は記憶に残っています。
その為キャリーバックや車、動物病院を見るだけで嫌がったり逃げ出してしまいます。
薬を無理に飲まされた事も覚えていて、準備をしている飼い主の様子を見ただけで避けようとします。
大脳皮質が発達している
猫は記憶力や学習に大きく関係している脳の部位「大脳皮質」がとても発達しています。
大脳皮質は犬の2倍の厚さがあり、人間のように感情豊かな動物です。
トイレのルールをすぐに覚えてくれ、怒られた場合は同じ事をあまり繰り返しません。
毎日同じ時間にすり寄っておやつをねだり、可愛らしいしぐさや表情を見せてくれます。
悪い事をした時や飼い主に思いが通じなかった時などは、とてもがっかりしているように見え様々な感情が感じられます。
自立心が高くて記憶力も優れた猫
 猫は自立心がとても高い生き物で、犬のように芸をしないのではなく誰かの為に覚えようとは思わないようです。
中には飼い主の教え方次第で、芸を覚えて楽しませてくれる猫もいます。
単独行動をしながら生きていく為に必要なのは、自身の安全を守る力です。
猫の記憶力は自分を守るために発達し、台所に美味しいものがあるのを覚えていてキッチン台に乗る事があります。
人間用のトイレの仕方をいつの間にか覚えて、上手に使用する姿には驚かされます。
猫は自立心がとても高い生き物で、犬のように芸をしないのではなく誰かの為に覚えようとは思わないようです。
中には飼い主の教え方次第で、芸を覚えて楽しませてくれる猫もいます。
単独行動をしながら生きていく為に必要なのは、自身の安全を守る力です。
猫の記憶力は自分を守るために発達し、台所に美味しいものがあるのを覚えていてキッチン台に乗る事があります。
人間用のトイレの仕方をいつの間にか覚えて、上手に使用する姿には驚かされます。
猫の賢い種類ランキングTOP5
 猫の人気ランキングをテレビなどで見かける事がありますが、それぞれに特徴や魅力があり可愛らしく癒されます。
種類の多い猫の中から、飼う時の目安にもなる賢い猫トップ5を紹介します。
猫の人気ランキングをテレビなどで見かける事がありますが、それぞれに特徴や魅力があり可愛らしく癒されます。
種類の多い猫の中から、飼う時の目安にもなる賢い猫トップ5を紹介します。
5位:アビシニアン
見た目からも上品で賢さが伝わり美しいという印象ですが、実はとても甘えん坊で人間が大好きです。
ツンデレではなく簡単な言葉が理解でき、名前を呼ぶと飛んでくるようなデレデレな感じが際立つ猫です。
運動神経が良く活発で好奇心旺盛ですので、犬のようにボールを投げると取ってくる猫もいます。
他の猫に比べて優れた記憶力と学習能力があり、あまり大きい声では鳴きません。
4位:シャム猫
 生まれた時は真っ白ですが、成長していくうちに顔や耳、足や尻尾にポイントとなる色が入ります。
好奇心と賢さを兼ね添えていますので、しつけがしやすくテーブルの上に上がらないように訓練することもできます。
感受性が強く愛情深い所があり人間を見た時に「この人は優しそう」と感じたり、人間が発する雰囲気を読み取って接近したり離れたりもします。
人を良く観察しているせいか家のドアを開ける確率が高く、スマートで飼いやすい猫種です。
生まれた時は真っ白ですが、成長していくうちに顔や耳、足や尻尾にポイントとなる色が入ります。
好奇心と賢さを兼ね添えていますので、しつけがしやすくテーブルの上に上がらないように訓練することもできます。
感受性が強く愛情深い所があり人間を見た時に「この人は優しそう」と感じたり、人間が発する雰囲気を読み取って接近したり離れたりもします。
人を良く観察しているせいか家のドアを開ける確率が高く、スマートで飼いやすい猫種です。
3位:ペルシャ猫
毛が長くふわふわしているのが特徴で、性格は温和で穏やかマイペースです。
甘えん坊な所もあり、人間と温かい関係を築くことができます。
この性格の通り鳴くこともほとんどなく、静かな場所でゆったりのんびりして遊ぶことが多いです。
世界中の猫好きから愛されていて、「猫の王様」とも呼ばれるほどです。
新しい環境に他の猫と比べて早く対応できますが、あまりかまい過ぎない方が良いようです。
2位:スコティッシュフォールド
 折りたたまれた耳と、丸くて大きな瞳が特徴の可愛らしい猫です。
はじめてみた時には他の猫とは違った折れた耳で違和感を感じると思いますが、見慣れてしまうチャームポイントにも見えてきます。
人懐っこく甘えん坊な優しい性格で、鳴き声もあまり大きくなく周りに迷惑をかける心配がいりません。
人見知りがなく愛情の交流がしっかりでき、飼い主さんラブなのでとても飼いやすい猫です。
折りたたまれた耳と、丸くて大きな瞳が特徴の可愛らしい猫です。
はじめてみた時には他の猫とは違った折れた耳で違和感を感じると思いますが、見慣れてしまうチャームポイントにも見えてきます。
人懐っこく甘えん坊な優しい性格で、鳴き声もあまり大きくなく周りに迷惑をかける心配がいりません。
人見知りがなく愛情の交流がしっかりでき、飼い主さんラブなのでとても飼いやすい猫です。
1位:ロシアンブルー
グレーの毛色とエメラルドグリーンの瞳が特徴で、スラットしていて上品な感じの猫です。
神経質ですが大人しく忠実な所がありますので、物分かりが良くしつけする時の手間もあまりかかりません。
専用グッズにまたたびを使って誘導すればすぐ覚えてくれ、フリスビーを投げれば持って帰ってくるようになる猫もいます。
人見知りな面もあり慣れるまで時間がかかりますが、一度慣れてしまえば飼い主に従順になり甘えてくるツンデレ猫です。
まとめ
同じ失敗繰り返して飼い主を呆れさせる事もありますが、猫には賢い要素が幾つかあり、時には飼い主を驚かせてくれます。
犬のように従順で賢い所はなくても、一緒に生活をしていく中で癒しを与えてくれるだけでも大きな存在になっているもしれませんね!
ちくわは猫に食べさせても大丈夫?
 ちくわは猫に食べさせても大丈夫かと気になる方も多いと思います。
この記事ではちくわを猫にあげても大丈夫かについてお話いたします。
そもそもちくわは主原料が魚です。
なので健康的な猫であれば基本的に与えられても問題はありません。
しかし、ちくわは人間の食用に製造していて、含まれる塩分量が猫用ではない可能性がございます。
販売品によっては猫にとって塩分が強すぎる物もあるそうです。
また猫は泌尿器系の病気(腎臓病や尿路結石)が多いため塩分の取りすぎは体に悪影響を与えます。
特に塩分濃度が高い食品(塩漬けた魚など)は嘔吐してしまいます。
【絶対に安全な食べ物】とは一概に決めることはできません。
猫の為にも最低限の知識は備える事も必要ですね。
ちくわは猫に食べさせても大丈夫かと気になる方も多いと思います。
この記事ではちくわを猫にあげても大丈夫かについてお話いたします。
そもそもちくわは主原料が魚です。
なので健康的な猫であれば基本的に与えられても問題はありません。
しかし、ちくわは人間の食用に製造していて、含まれる塩分量が猫用ではない可能性がございます。
販売品によっては猫にとって塩分が強すぎる物もあるそうです。
また猫は泌尿器系の病気(腎臓病や尿路結石)が多いため塩分の取りすぎは体に悪影響を与えます。
特に塩分濃度が高い食品(塩漬けた魚など)は嘔吐してしまいます。
【絶対に安全な食べ物】とは一概に決めることはできません。
猫の為にも最低限の知識は備える事も必要ですね。
ちくわを好んで食べる猫はいる?
 【おさかなくわえた野良猫】という言葉があるように猫の餌と言えば魚のイメージガツオいですよね。
キャットフードの中でもヒラメや鯛などが代表的です。
その影響か魚肉加工品(ちくわ)を与える家庭も少なくないはずです。
ちくわは魚肉から製造される食べ物なので、好んで食べる猫も多いです。
どこの家庭でもちくわとかまぼこは冷蔵庫にあるおてごろ価格商品です。
だだしちくはなどの魚肉加工品を猫に日常的に与えるのはデメリットがあります。
なのにメリットはそこまでありません。
こちらでは猫にちくわの猫にとってのリスクなどをまとめます
【おさかなくわえた野良猫】という言葉があるように猫の餌と言えば魚のイメージガツオいですよね。
キャットフードの中でもヒラメや鯛などが代表的です。
その影響か魚肉加工品(ちくわ)を与える家庭も少なくないはずです。
ちくわは魚肉から製造される食べ物なので、好んで食べる猫も多いです。
どこの家庭でもちくわとかまぼこは冷蔵庫にあるおてごろ価格商品です。
だだしちくはなどの魚肉加工品を猫に日常的に与えるのはデメリットがあります。
なのにメリットはそこまでありません。
こちらでは猫にちくわの猫にとってのリスクなどをまとめます
ちくわを猫に与える時の注意点
 猫はちくわを食べても大丈夫なのか心配になりますよね。
少量であれば猫がちくわを食べても平気なのか心配になる気持ちもわかります。
カニカマや魚肉ソーセージと同様ちくわも塩分が高く、アレルギー症状を起こすリスクもあります。
この記事では猫にちくわ与える注意点を紹介します。
猫はちくわを食べても大丈夫なのか心配になりますよね。
少量であれば猫がちくわを食べても平気なのか心配になる気持ちもわかります。
カニカマや魚肉ソーセージと同様ちくわも塩分が高く、アレルギー症状を起こすリスクもあります。
この記事では猫にちくわ与える注意点を紹介します。
注意点①:塩分の摂りすぎ
人間の場合、塩分過多は高血圧の原因にもなりやすいのでなるべく塩分を取りすぎないように気を付けている方もおおいと思います。
人間も塩分を摂りすぎると健康に害が出るように、猫も塩分を摂取しすぎると体に悪いです。
毎回あげたりと、おやつ化することは止めましょう。
ちくわに含まれる食塩分は1本あたり約0.7gとなっており、猫の品種や体格など個体差はありますが猫が1日に摂取しても良い適切な塩分量は約2〜3g程度となっています。
ちくわに加えて他のおやつや食べ物を与えてしまうと適切な塩分量を超えてしまう恐れがあり、猫の体に影響を与えてしまうので気をつけましょう。
適切な塩分量を超えてしまうと腎臓へと負担がかかります。
猫の死因としても腎不全は多く挙げられているので塩分の取り過ぎを気をつけるに越したことはありません。
注意点②:人間向けに含まれた成分
 二つ目に注意すべきことはちくわには人間向けに含まれた成分が猫にとって害になる可能性があることです。
例えばあるちくわの中には「加工でん粉」、「調味料(アミノ酸等)」、「貝Ca」などの加工物が入っています。
ちくわのメーカーや商品によっては添加物や合成成分などが多く含まれているものがあり、猫の体に悪影響を及ぼす可能性があります。
もし猫にちくわをあげる際には無添加や保存料、殺菌料が入っていない無添加のちくわをあげるようにしましょう。
二つ目に注意すべきことはちくわには人間向けに含まれた成分が猫にとって害になる可能性があることです。
例えばあるちくわの中には「加工でん粉」、「調味料(アミノ酸等)」、「貝Ca」などの加工物が入っています。
ちくわのメーカーや商品によっては添加物や合成成分などが多く含まれているものがあり、猫の体に悪影響を及ぼす可能性があります。
もし猫にちくわをあげる際には無添加や保存料、殺菌料が入っていない無添加のちくわをあげるようにしましょう。
注意点③:アレルギー
3点目に注意すべきことはアレルギーです。
魚アレルギーを持つ猫にとって、ちくわは魚と同様食べてはいけません。
また、ちくわの商品によっては乳製品や卵など他のアレルギー成分が入っているものもあります。
猫にちくわを与える際は成分表を確認し、猫が持つアレルギー成分が入っていないものを選ぶようにしましょう。
猫が食物アレルギーを発症すると様々な症状があらわれます。
症状としては主に「下痢・軟便・血便」「嘔吐」「お腹の張り」「痒みを伴う発疹・かぶれ」「脱毛」「発熱」などが挙げられます。
ちくわを猫に与えすぎると出る悪影響
 それでは、猫にちくわを与えすぎることでどのような悪影響が出てきてしますのでしょうか。
ここでは猫に出てくる悪影響についてご紹介したいと思います。
それでは、猫にちくわを与えすぎることでどのような悪影響が出てきてしますのでしょうか。
ここでは猫に出てくる悪影響についてご紹介したいと思います。
がん
まず一つ目に「がん」があげられます。
ちくわに含まれる添加物や保存料などにより免疫障害や発がん性、ホルモン異常や内臓異常などの病気を引き起こすリスクが増えます。
これはちくわに限ったことではないのですが、添加物を含む食べ物を長期的に摂っていると発がん性を持つようになるものもあります。
がんは猫の死因のトップであることが多く、添加物の食べ物で命を落とすことがないように注意したいものです。
慢性腎不全や尿石症
 二つ目に「慢性腎不全や尿石症」があげられます。
猫は塩分を体外に出すことが苦手なので、人間の食べ物を食べさせ過ぎると、腎臓に負荷がかかり、膀胱にまで害が及びます。
腎臓がダメージを受けて十分に機能しなくなる状態を「腎不全」といい、これが長期間続くと慢性腎臓病(慢性腎不全)となります。
慢性腎不全は猫の死因ランキングで二番目に高い病気です。
また、尿石症とは腎臓から尿管、膀胱、尿道の中に結晶や結石ができる病気で、膀胱や尿道を傷つけたり、尿道に詰まったりします。
重度の尿路結石症(尿石症)を発症すると、結石が尿道に詰まる尿道閉塞や、排尿困難から腎機能の低下を引き起こし、尿毒症などを誘発する場合があるので大変危険な病気です。
一般的な尿石症の症状はトイレに行く回数が増える、トイレとまったく関係ない場所で排尿をするなどがあげられます。
慢性腎不全や尿石症は食事を含めた予防対策でコントロールすることができる病気なので飼い主は注意しましょう。
二つ目に「慢性腎不全や尿石症」があげられます。
猫は塩分を体外に出すことが苦手なので、人間の食べ物を食べさせ過ぎると、腎臓に負荷がかかり、膀胱にまで害が及びます。
腎臓がダメージを受けて十分に機能しなくなる状態を「腎不全」といい、これが長期間続くと慢性腎臓病(慢性腎不全)となります。
慢性腎不全は猫の死因ランキングで二番目に高い病気です。
また、尿石症とは腎臓から尿管、膀胱、尿道の中に結晶や結石ができる病気で、膀胱や尿道を傷つけたり、尿道に詰まったりします。
重度の尿路結石症(尿石症)を発症すると、結石が尿道に詰まる尿道閉塞や、排尿困難から腎機能の低下を引き起こし、尿毒症などを誘発する場合があるので大変危険な病気です。
一般的な尿石症の症状はトイレに行く回数が増える、トイレとまったく関係ない場所で排尿をするなどがあげられます。
慢性腎不全や尿石症は食事を含めた予防対策でコントロールすることができる病気なので飼い主は注意しましょう。
高血圧や肥満
最後に「高血圧や肥満」です。
塩分=悪い物とは一概に言えないのですが、大量に摂取することで、高血圧や肥満を引き起こすことが少なくありません。
高血圧により損傷を受ける組織として最も症状が出やすいのが眼です。
眼球内出血、網膜剥離、緑内障などが起こり失明する例もよくみられます。
他には腎臓、心臓、脳にも損傷を与えます。
高血圧になると肥満は様々な病気の原因になり、普段は症状が現れなくても、気づかないうちに健康に影響を与えている可能性があります。
糖尿病や骨格系疾患、心臓血管系疾患、がんなどのリスクを高めることになります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は猫にちくわを食べさせても良いのか?というテーマで解説をしてきました。
猫にちくわを与えてしまうことで様々な病気を引き起こしたり、猫にとって悪影響を及ぼしてしまう可能性があるので与える際には細心の注意を払って与えるようにしましょう。
犬には癒し効果がある
 仕事で疲れた時、落ち込んでいるとき、ペットと一緒にいると癒されますよね。
ペットには高い癒し効果があり、精神面や身体面のケアを行い病気の改善を目指すために、医療活動の一環としても取り入れられることもあります。
ペットと触れ合うことで自律神経が整い、他人とのかかわりが増えたりすることで、精神的なゆとりや充足感を得られるなど、様々な良い影響が期待できるでしょう。
なぜ癒し効果があるのかというと、犬は他の動物よりも忠誠心が強く、飼い主のことを心から信頼する生き物です。
犬を撫でたりすると、その優しいぬくもりが肌を通して伝わります。
犬の暖かさが伝わると、人間の脳内には幸せホルモンのオキシトシンが分泌され、愛情を感じて癒されます。
疲れている時こそ積極的に触れ合うことが大切かもしれませんね。
仕事で疲れた時、落ち込んでいるとき、ペットと一緒にいると癒されますよね。
ペットには高い癒し効果があり、精神面や身体面のケアを行い病気の改善を目指すために、医療活動の一環としても取り入れられることもあります。
ペットと触れ合うことで自律神経が整い、他人とのかかわりが増えたりすることで、精神的なゆとりや充足感を得られるなど、様々な良い影響が期待できるでしょう。
なぜ癒し効果があるのかというと、犬は他の動物よりも忠誠心が強く、飼い主のことを心から信頼する生き物です。
犬を撫でたりすると、その優しいぬくもりが肌を通して伝わります。
犬の暖かさが伝わると、人間の脳内には幸せホルモンのオキシトシンが分泌され、愛情を感じて癒されます。
疲れている時こそ積極的に触れ合うことが大切かもしれませんね。
犬との暮らしで癒し効果が得られるメカニズム
 ペットを飼っている人なら誰しも癒されたと感じたことがあるのではないでしょうか。
実際に、癒されたといってもどのような時に癒されて、どのような効果があるのかを考えたことは少ないのではないかと思います。
そこで、犬との暮らしで癒し効果が得られるメカニズムを紹介したいと思います。
ペットを飼っている人なら誰しも癒されたと感じたことがあるのではないでしょうか。
実際に、癒されたといってもどのような時に癒されて、どのような効果があるのかを考えたことは少ないのではないかと思います。
そこで、犬との暮らしで癒し効果が得られるメカニズムを紹介したいと思います。
ゆとりある生活を実現
犬がいる生活を送ると、世話や散歩などで朝から活動することが増え、運動量なども増加します。
中には犬に話しかけている方も多いのではないのでしょうか。
普段一人でいる時に言葉を発しない生活が犬がいることで会話の相手ができるため、身にためていたストレスが解消されることもあるかと思います。
運動をしない人も犬の散歩をすることで運動量が増加して健康的に過ごせるようになるかもしれません。
運動する機会が増える
 犬を飼うことで必ず行うことの一つが散歩。
一人で散歩をしようとしてもついつい面倒になって、今日はいいやと思ったこともあるのではないでしょうか。
しかし犬があなたと散歩に行くのを楽しみにしていた場合、断れません。
雨が降っていても、暑くても犬は待ってくれません。
体調が悪い時にも行かなくてはいけないこともあるかもしれません。
毎日の散歩は、人間の運動量を増やして健康を増進してくれます。
小型犬なら近所を10分程度歩き回れば満足するでしょう。
しかし大型犬となると大きな公園や広場で走り回らせないといけません。
大変だと感じるかもしれませんが、運動不足を解消する為に犬を飼うという人もいるくらい犬との散歩は楽しいものです。
もしくは、おもちゃを買って一緒に遊ぶのもいいかもしれないですね。
犬を飼うことで必ず行うことの一つが散歩。
一人で散歩をしようとしてもついつい面倒になって、今日はいいやと思ったこともあるのではないでしょうか。
しかし犬があなたと散歩に行くのを楽しみにしていた場合、断れません。
雨が降っていても、暑くても犬は待ってくれません。
体調が悪い時にも行かなくてはいけないこともあるかもしれません。
毎日の散歩は、人間の運動量を増やして健康を増進してくれます。
小型犬なら近所を10分程度歩き回れば満足するでしょう。
しかし大型犬となると大きな公園や広場で走り回らせないといけません。
大変だと感じるかもしれませんが、運動不足を解消する為に犬を飼うという人もいるくらい犬との散歩は楽しいものです。
もしくは、おもちゃを買って一緒に遊ぶのもいいかもしれないですね。
楽しい家族時間が過ごせる
犬が家庭にいると、夫婦または家族間のコミュニケーションが活発となり、楽しい時間が過ごせます。
ペットを家庭に飼い始めてから、飼う前に比べてお子さんや夫婦で過ごす時間が増えたという方も多く、
より豊かで楽しい家族時間が過ごせるようになったと感じる方も多いようです。
また、お子さんと一緒に犬の散歩に行き、お子さんの運動量も増えますね。
さらに、インターネットでのコミュニケーションが発達した現代社会では、SNSを通じてペットの共通点を通して新たな人々と知り合うきっかけが増えることもあります。
犬はうつ病患者にも癒しを与える
 実は犬との触れ合いは、うつ病患者が犬と触れ合うと、精神的なつらさが軽減され、大きな癒し効果を得られると言われています。
犬は飼い主さんに愛を注いでくるその為、安心感が生まれて、ストレスが発散されるのです。
相手の目線や自分がどう思われるかを考えなくてよいのは、うつ病の人にとってとても効果的だといわれています。
飼い主さんのことが大好きで、共に生活を過ごすことがうつ病患者の方にとってストレス軽減になり、癒されるんですね。
遊ぶだけではなく、一緒に寝たり、散歩をしたりと人間の生活を共に過ごせることが犬の強みでもあります。
そんな犬の存在は病気の人をも癒す効果があるといっても過言ではありません。
実は犬との触れ合いは、うつ病患者が犬と触れ合うと、精神的なつらさが軽減され、大きな癒し効果を得られると言われています。
犬は飼い主さんに愛を注いでくるその為、安心感が生まれて、ストレスが発散されるのです。
相手の目線や自分がどう思われるかを考えなくてよいのは、うつ病の人にとってとても効果的だといわれています。
飼い主さんのことが大好きで、共に生活を過ごすことがうつ病患者の方にとってストレス軽減になり、癒されるんですね。
遊ぶだけではなく、一緒に寝たり、散歩をしたりと人間の生活を共に過ごせることが犬の強みでもあります。
そんな犬の存在は病気の人をも癒す効果があるといっても過言ではありません。
犬の癒しホルモンは子どもにも効果的
 大型犬は子供が怖がってしまいことも多いかと思います。
しかし、犬はとても人懐っこい性格であるため、子どもに怯えたりすることが少なく、親の代わりとなって、子供の世話や相手をしてくれます。
犬は忠実である為、多少赤ちゃんに叩かれても平気な顔をします。時には親の代わりに躾けてもくれるので、慣れてくれば長々と子どもの相手をしてくれます。
愛されていると感じると、人間の心に癒しを与えてくれます。
犬を膝に乗せたり、犬の頭をなでたりするとそのぬくもりがと肌を通して伝わってきて、人間の脳の中にオキシトシンが分泌されます。
このオキシトシンは「幸せホルモン」や「愛情ホルモン」などと呼ばれていて疲れを軽減させたり、心を安定させる効果があるといわれています。
大型犬は子供が怖がってしまいことも多いかと思います。
しかし、犬はとても人懐っこい性格であるため、子どもに怯えたりすることが少なく、親の代わりとなって、子供の世話や相手をしてくれます。
犬は忠実である為、多少赤ちゃんに叩かれても平気な顔をします。時には親の代わりに躾けてもくれるので、慣れてくれば長々と子どもの相手をしてくれます。
愛されていると感じると、人間の心に癒しを与えてくれます。
犬を膝に乗せたり、犬の頭をなでたりするとそのぬくもりがと肌を通して伝わってきて、人間の脳の中にオキシトシンが分泌されます。
このオキシトシンは「幸せホルモン」や「愛情ホルモン」などと呼ばれていて疲れを軽減させたり、心を安定させる効果があるといわれています。
犬の動画を見るだけでも癒しが得られる
 実は、犬に直接触れていなくても、動画を見るだけで幸せ・愛情ホルモンのオキシトシンが分泌されます。
動物たちと触れ合ったり見つめ合ったりすると、自分が受け入れられたような、肯定的な気持ちになります。
そうすると、自分で自分を認めてあげる「自己効力感」が高まったり、何かを達成したような気持ちになります。
人間は可愛いものを愛でると母性が働き、オキシトシンが分泌されます。
オキシトシンがバランス良く出ている時は、精神状態が安定します。
動物を撫でる時もですが、直接触れなくても「可愛い!癒される!」と思うことがありますよね。
その気持ちが人間の母性を刺激し、心の乱れを落ち着かせてくれ精神的に安定するのです。
実は、犬に直接触れていなくても、動画を見るだけで幸せ・愛情ホルモンのオキシトシンが分泌されます。
動物たちと触れ合ったり見つめ合ったりすると、自分が受け入れられたような、肯定的な気持ちになります。
そうすると、自分で自分を認めてあげる「自己効力感」が高まったり、何かを達成したような気持ちになります。
人間は可愛いものを愛でると母性が働き、オキシトシンが分泌されます。
オキシトシンがバランス良く出ている時は、精神状態が安定します。
動物を撫でる時もですが、直接触れなくても「可愛い!癒される!」と思うことがありますよね。
その気持ちが人間の母性を刺激し、心の乱れを落ち着かせてくれ精神的に安定するのです。
まとめ
犬を飼うことで様々効果があることが分かりましたね。
時には癒し効果、時には運動量増加など、多くの健康的な効果があるため、犬が飼いたくなった方もいるのではないでしょうか。
犬の世話をしっかりとでき、犬が大好きな方が世の中に増えることを願っています。
 あまり電車の中で犬を連れている人を見かけることが少ないので、電車に犬を乗せることはいけないというイメージがありますが、条件を満たしていれば電車に乗せても問題ありません。
ただし、各鉄道会社によって条件は異なるので、事前に確認しておく必要があります。
ちなみに身体障害者補助犬であれば、無条件ですべての電車に乗ることができます。
どうしても電車に乗って愛犬と移動する必要があるのであれば、必要な物を用意したり、マナーを身に付けておくようにしましょう。
あまり電車の中で犬を連れている人を見かけることが少ないので、電車に犬を乗せることはいけないというイメージがありますが、条件を満たしていれば電車に乗せても問題ありません。
ただし、各鉄道会社によって条件は異なるので、事前に確認しておく必要があります。
ちなみに身体障害者補助犬であれば、無条件ですべての電車に乗ることができます。
どうしても電車に乗って愛犬と移動する必要があるのであれば、必要な物を用意したり、マナーを身に付けておくようにしましょう。
 上記でも紹介したように犬と電車に乗るためには条件を満たしておく必要があり、場合によっては用意しなければいけない物もあるので、前日までに用意する必要があります。
次に、犬を電車に乗せる際に準備しておくものを紹介するので参考にしてください。
上記でも紹介したように犬と電車に乗るためには条件を満たしておく必要があり、場合によっては用意しなければいけない物もあるので、前日までに用意する必要があります。
次に、犬を電車に乗せる際に準備しておくものを紹介するので参考にしてください。
 犬を電車に乗せるのであればキャリーは必要不可欠です。
各鉄道会社によって犬を電車に乗せてもよい条件は変わりますが、キャリーの中に入れることはほぼ確定している条件です。
そのため、事前にキャリーの中に入れて落ち着かせる練習をするようにしましょう。
慣れていない空間では不安に感じてしまいやすいですが、回数をこなすことでキャリーの環境に慣れさせることができます。
キャリーにはさまざまな種類や形状で販売されていますが、電車で使用するのであれば顔まで覆うことができるタイプを購入しましょう。
犬を電車に乗せるのであればキャリーは必要不可欠です。
各鉄道会社によって犬を電車に乗せてもよい条件は変わりますが、キャリーの中に入れることはほぼ確定している条件です。
そのため、事前にキャリーの中に入れて落ち着かせる練習をするようにしましょう。
慣れていない空間では不安に感じてしまいやすいですが、回数をこなすことでキャリーの環境に慣れさせることができます。
キャリーにはさまざまな種類や形状で販売されていますが、電車で使用するのであれば顔まで覆うことができるタイプを購入しましょう。
 犬と電車に乗るためにはさまざまな準備をしなければなりません。
下準備をしておくほど当日になって焦ったり、電車内でトラブルになることを未然に防ぐことができます。
次に、犬と電車に乗る際にしておいたほうが良い準備を紹介するので参考にしてください。
犬と電車に乗るためにはさまざまな準備をしなければなりません。
下準備をしておくほど当日になって焦ったり、電車内でトラブルになることを未然に防ぐことができます。
次に、犬と電車に乗る際にしておいたほうが良い準備を紹介するので参考にしてください。
 人が乗り物酔いすることと同じように犬も乗り物酔いをしてしまうことがあります。
電車は車と違って雑音のほかに振動も大きくなってしまうので、車では酔わなくても電車では酔ってしまうことも十分考えられます。
乗り物酔いを防ぐためには移動の前の食事は避けるようにしましょう。
食べた物が胃にあればどうしても乗り物酔いしてしまうリスクが高まってしまいます。
乗り物酔いしてしまった際には近くの駅に乗せて落ち着かせることが大切であり、時々車内で愛犬の様子をうかがうことで乗り物酔いの早期発見につながります。
人が乗り物酔いすることと同じように犬も乗り物酔いをしてしまうことがあります。
電車は車と違って雑音のほかに振動も大きくなってしまうので、車では酔わなくても電車では酔ってしまうことも十分考えられます。
乗り物酔いを防ぐためには移動の前の食事は避けるようにしましょう。
食べた物が胃にあればどうしても乗り物酔いしてしまうリスクが高まってしまいます。
乗り物酔いしてしまった際には近くの駅に乗せて落ち着かせることが大切であり、時々車内で愛犬の様子をうかがうことで乗り物酔いの早期発見につながります。
 初めてキャリーに入れると慣れていない空間に戸惑ってしまうことも少なくありません。
そのような場合には普段使用しているにおい付きのタオルをキャリー内に入れておきましょう。
犬はにおいに敏感な生き物であるため、自分のにおいがあれば落ち着いてくれる可能性が高まります。
おもちゃなどもおすすめですが、キャリー内におもちゃを入れてしまうと遊んでしまい、暴れたり、鳴いてしまうこともあります。
一方静かに遊んでくれるのであれば車内の雑音などに意識を向かないようにすることもできるので、使い分ける必要があります。
初めてキャリーに入れると慣れていない空間に戸惑ってしまうことも少なくありません。
そのような場合には普段使用しているにおい付きのタオルをキャリー内に入れておきましょう。
犬はにおいに敏感な生き物であるため、自分のにおいがあれば落ち着いてくれる可能性が高まります。
おもちゃなどもおすすめですが、キャリー内におもちゃを入れてしまうと遊んでしまい、暴れたり、鳴いてしまうこともあります。
一方静かに遊んでくれるのであれば車内の雑音などに意識を向かないようにすることもできるので、使い分ける必要があります。
 犬を電車に乗せるのであればマナーを知っておくことも大切です。
乗せるための条件を満たすことも大切ですが、マナーが守られていないと周りの人に迷惑をかけてしまう可能性が高く、トラブルの原因となります。
次に、愛犬と電車に乗る際のマナーを紹介するので把握しておきましょう。
犬を電車に乗せるのであればマナーを知っておくことも大切です。
乗せるための条件を満たすことも大切ですが、マナーが守られていないと周りの人に迷惑をかけてしまう可能性が高く、トラブルの原因となります。
次に、愛犬と電車に乗る際のマナーを紹介するので把握しておきましょう。
 誰でも知らない環境に閉じ込められることには不安を感じてしまい、犬にも同じことが言えます。
普段電車に乗る際に使用するキャリーをしないのであればまず、キャリーに慣れてもらうことが大切です。
目的はキャリーの環境に慣れてもらうためであるため、自宅の中で行っても問題ありません。
慣れないうちは暴れたり、すぐに出ようとしてしまう場合が多いですが、頻繁に練習をすることで次第に慣れていくので、焦らずに時間をかけましょう。
そのため、乗車する前日では慣れるのに時間が足りない場合が多いので、余裕をもって1か月程度前から練習することが無難です。
誰でも知らない環境に閉じ込められることには不安を感じてしまい、犬にも同じことが言えます。
普段電車に乗る際に使用するキャリーをしないのであればまず、キャリーに慣れてもらうことが大切です。
目的はキャリーの環境に慣れてもらうためであるため、自宅の中で行っても問題ありません。
慣れないうちは暴れたり、すぐに出ようとしてしまう場合が多いですが、頻繁に練習をすることで次第に慣れていくので、焦らずに時間をかけましょう。
そのため、乗車する前日では慣れるのに時間が足りない場合が多いので、余裕をもって1か月程度前から練習することが無難です。
 上記でも一部紹介しましたが動物に対して苦手意識を持っている人や同じ車両に乗っている可能性も捨てきれることができず、
そのような人がキャリーの中に犬がいることを知ってしまうとトラブルの原因になってしまいます。
そのようなことを未然に防ぐためにも犬の存在を極力消す必要があります。
キャリーから犬が見えないようにすることも大切ですが、鳴かないように訓練することも大切です。
そのほかにも極力乗客が少ない車両に乗ったり、出入り口の近くにいるなどの工夫をしましょう。
上記でも一部紹介しましたが動物に対して苦手意識を持っている人や同じ車両に乗っている可能性も捨てきれることができず、
そのような人がキャリーの中に犬がいることを知ってしまうとトラブルの原因になってしまいます。
そのようなことを未然に防ぐためにも犬の存在を極力消す必要があります。
キャリーから犬が見えないようにすることも大切ですが、鳴かないように訓練することも大切です。
そのほかにも極力乗客が少ない車両に乗ったり、出入り口の近くにいるなどの工夫をしましょう。
 条件を満たせば犬と電車に乗ることは可能ですが、料金が必要になることは知っているでしょうか。
知らずに料金を払わずに乗車してしまうとトラブルの原因となります。
長さが70㎝以内であり、縦と横の長さが合わせて90㎝程度でキャリーと犬の重さが10㎏以内であれば290円程度で乗ることができます。
改札口で犬の入っているキャリーを見せれば駅員の人が測定してくれるので基本的に任せていれば料金を指定され、支払えば手回り品切符をもらうことができ、乗車可能になります。
料金は各鉄道会社によって微妙に違うので、一度確認しておきましょう。
条件を満たせば犬と電車に乗ることは可能ですが、料金が必要になることは知っているでしょうか。
知らずに料金を払わずに乗車してしまうとトラブルの原因となります。
長さが70㎝以内であり、縦と横の長さが合わせて90㎝程度でキャリーと犬の重さが10㎏以内であれば290円程度で乗ることができます。
改札口で犬の入っているキャリーを見せれば駅員の人が測定してくれるので基本的に任せていれば料金を指定され、支払えば手回り品切符をもらうことができ、乗車可能になります。
料金は各鉄道会社によって微妙に違うので、一度確認しておきましょう。
 手術やケガを行った際に、愛犬の首回りにエリザベスカラーを装着しますが、愛犬が動きにくそうにしていたり、嫌がって外そうとしている姿を見るとストレスを感じているのではないかと心配になりますよね。
実はその通りで、エリザベスカラーは犬にとってとてもストレスなんです。
エリザベスカラーをつけることで、視野が狭くなり、音も聞こえにくくなり、ニオイも嗅ぎにくくなるなど、普段よりも情報が入りづらくなってしまうのです。
また、エリザベスカラーは顔をすっぽり覆ってしまう構造になるため普通に歩いていても物にぶつかったりすることが増えてしまいます。
さらに、食事もしにくいので、当然ストレスを感じることになるでしょう。
手術やケガを行った際に、愛犬の首回りにエリザベスカラーを装着しますが、愛犬が動きにくそうにしていたり、嫌がって外そうとしている姿を見るとストレスを感じているのではないかと心配になりますよね。
実はその通りで、エリザベスカラーは犬にとってとてもストレスなんです。
エリザベスカラーをつけることで、視野が狭くなり、音も聞こえにくくなり、ニオイも嗅ぎにくくなるなど、普段よりも情報が入りづらくなってしまうのです。
また、エリザベスカラーは顔をすっぽり覆ってしまう構造になるため普通に歩いていても物にぶつかったりすることが増えてしまいます。
さらに、食事もしにくいので、当然ストレスを感じることになるでしょう。
 愛犬がストレスを感じることがわかっていても、エリザベスカラーを装着しなければいけない場面はあります。
その場合、できるだけストレスを軽減させてあげることが重要です。
まずは、行動範囲にある障害物を取り除いてあげてください。
続いて食事や水分をとりやすいように工夫することも大切!
エリザベスカラーが当たりにくい高さを見極めて、食器の高さを調節してあげましょう。
長時間の留守番をさせる場合は、滑り止めのついた食器を使う、食器スタンドを使うなどの工夫も必要です。
そして、気を紛らわせてあげる工夫や人の目が届く範囲だけ外してあげるなどストレスに感じる時間を少しでも減らしてあげましょう。
愛犬がストレスを感じることがわかっていても、エリザベスカラーを装着しなければいけない場面はあります。
その場合、できるだけストレスを軽減させてあげることが重要です。
まずは、行動範囲にある障害物を取り除いてあげてください。
続いて食事や水分をとりやすいように工夫することも大切!
エリザベスカラーが当たりにくい高さを見極めて、食器の高さを調節してあげましょう。
長時間の留守番をさせる場合は、滑り止めのついた食器を使う、食器スタンドを使うなどの工夫も必要です。
そして、気を紛らわせてあげる工夫や人の目が届く範囲だけ外してあげるなどストレスに感じる時間を少しでも減らしてあげましょう。
 犬に鳥の骨を食べさせても大丈夫なのか心配な人もいるのではないでしょうか。
鳥の骨にはカルシウムやコラーゲンが多く含まれているので、骨を頑丈にしたり、コラーゲンは関節疾患の予防にもなります。
一見鳥の骨は固そうに見えますが、健康な成犬であれば数時間程度で消化します。
そのため、犬に鳥の骨を与えることは一部条件をクリアしているのであれば与えても問題ありません。
人が食べた骨付きにチキンの骨があるのであれば与えてみましょう。
犬に鳥の骨を食べさせても大丈夫なのか心配な人もいるのではないでしょうか。
鳥の骨にはカルシウムやコラーゲンが多く含まれているので、骨を頑丈にしたり、コラーゲンは関節疾患の予防にもなります。
一見鳥の骨は固そうに見えますが、健康な成犬であれば数時間程度で消化します。
そのため、犬に鳥の骨を与えることは一部条件をクリアしているのであれば与えても問題ありません。
人が食べた骨付きにチキンの骨があるのであれば与えてみましょう。
 犬に鳥の骨を与えることは基本的に問題ありませんが、危険性があることも理解しておきましょう。
正しい知識なく鳥の骨を与えてしまうと犬を危険な目にあわせてしまうため、飼い主は鳥の骨の危険性を十分理解してから与えるようにしましょう。
次に、犬に鳥の骨を与える際の危険性を紹介します。
犬に鳥の骨を与えることは基本的に問題ありませんが、危険性があることも理解しておきましょう。
正しい知識なく鳥の骨を与えてしまうと犬を危険な目にあわせてしまうため、飼い主は鳥の骨の危険性を十分理解してから与えるようにしましょう。
次に、犬に鳥の骨を与える際の危険性を紹介します。
 鳥の骨は割れやすく、鋭い部分ができやすい特徴があります。
鋭利なもので固い素材であるため、飲み込んでしまうと気道や消化管などに刺さってしまう可能性があります。
気道や消化管を傷つけてしまうとさまざまな病気の原因ともなります。
ほかの骨も割れれば鋭利な形になりますが、鳥の骨は格段と割れやすくなっています。
鳥の骨は他の骨とは違い、中が空洞になっており、空を飛ぶために軽量化する必要があるためであると考えられています。
中が空洞であれば耐久性も弱く、犬の顎の力でも十分折ることができ、その際に鋭利な部分が多くなってしまいます。
鳥の骨が刺さらないようにするためには、飼い主が細かく砕いて鋭利な部分がないように工夫したり、粉末にしてフードなどと一緒に与えるなどの方法があります。
鳥の骨は割れやすく、鋭い部分ができやすい特徴があります。
鋭利なもので固い素材であるため、飲み込んでしまうと気道や消化管などに刺さってしまう可能性があります。
気道や消化管を傷つけてしまうとさまざまな病気の原因ともなります。
ほかの骨も割れれば鋭利な形になりますが、鳥の骨は格段と割れやすくなっています。
鳥の骨は他の骨とは違い、中が空洞になっており、空を飛ぶために軽量化する必要があるためであると考えられています。
中が空洞であれば耐久性も弱く、犬の顎の力でも十分折ることができ、その際に鋭利な部分が多くなってしまいます。
鳥の骨が刺さらないようにするためには、飼い主が細かく砕いて鋭利な部分がないように工夫したり、粉末にしてフードなどと一緒に与えるなどの方法があります。
 犬が鳥の骨を食べると上記で紹介したように体の内側を傷つけてしまう原因となってしまうため、極力食べさせないようにすることも珍しくありません。
しかし、飼い主が鳥の骨を与えたつもりではなくても、知らない間に食べてしまっていることもあります。
万が一犬が鳥の骨を食べてしまった際には適切な対応をすることが飼い主には求められます。
犬が鳥の骨を食べると上記で紹介したように体の内側を傷つけてしまう原因となってしまうため、極力食べさせないようにすることも珍しくありません。
しかし、飼い主が鳥の骨を与えたつもりではなくても、知らない間に食べてしまっていることもあります。
万が一犬が鳥の骨を食べてしまった際には適切な対応をすることが飼い主には求められます。
 犬が鳥の骨を食べてしまったのであれば様子見をすることが大切です。
下痢や嘔吐の症状があらわれ、元気がなくなったり、吐くような動作を繰り返しているのであれば鳥の骨がどこかに刺さっていたり、消化不良を起こしている可能性があります。
このような症状があらわれたのであれば安静にしていても症状が良くなることはあまりないため、早めに病院で治療を受けるようにしましょう。
様子見をする時間は上記で紹介したように鳥の骨を食べた1~2時間程度ですが、万が一のことも考え少し長い時間愛犬の傍をできるだけ離れないようにしましょう。
犬が鳥の骨を食べてしまったのであれば様子見をすることが大切です。
下痢や嘔吐の症状があらわれ、元気がなくなったり、吐くような動作を繰り返しているのであれば鳥の骨がどこかに刺さっていたり、消化不良を起こしている可能性があります。
このような症状があらわれたのであれば安静にしていても症状が良くなることはあまりないため、早めに病院で治療を受けるようにしましょう。
様子見をする時間は上記で紹介したように鳥の骨を食べた1~2時間程度ですが、万が一のことも考え少し長い時間愛犬の傍をできるだけ離れないようにしましょう。
 暑さには比較的強い猫ですが、熱中症になるリスクは低くなく高い湿度は苦痛になります。
扇風機が涼しくする場所は風の当たる部分だけで部屋全体は冷やせず、エアコンみたいに体温を下げる効果はほぼ無いようです。
人間にとっては扇風機の風が心地よく感じても、猫にとっては涼しさは感じられないようです。
扇風機はエアコンの冷気を循環させるために使えば、効率的に室温を保つ事ができます。
暑さには比較的強い猫ですが、熱中症になるリスクは低くなく高い湿度は苦痛になります。
扇風機が涼しくする場所は風の当たる部分だけで部屋全体は冷やせず、エアコンみたいに体温を下げる効果はほぼ無いようです。
人間にとっては扇風機の風が心地よく感じても、猫にとっては涼しさは感じられないようです。
扇風機はエアコンの冷気を循環させるために使えば、効率的に室温を保つ事ができます。
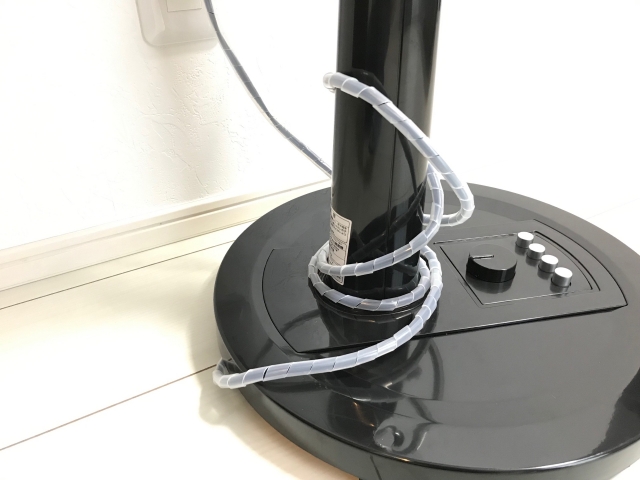 猫は肉球と鼻しか汗をかかず、体内に暑さをため込んでしまうと汗で暑さを発散できずに熱中症になってしまいます。
熱中症になれば人間と同じように命の危険もあります。
そうならない為に扇風機をどのように使えば、熱中症対策なるのかを調べて見ました。
猫は肉球と鼻しか汗をかかず、体内に暑さをため込んでしまうと汗で暑さを発散できずに熱中症になってしまいます。
熱中症になれば人間と同じように命の危険もあります。
そうならない為に扇風機をどのように使えば、熱中症対策なるのかを調べて見ました。
 扇風機に触れて事故を起こさないようにする為には、猫が接触しないように対策が必要になります。
好奇心旺盛な猫は小さな子供のように思いがけない行動をしますので、柵やストーブガードなどで扇風機を囲むようにし危険を回避してあげます。
それでも怪我をしてしまう心配がある場合は、壁掛けの扇風機を使ってみるのもいいかもしれません。
愛猫が怪我をしてしまうととても痛々しく可愛そうになりますので、事故が起きないように十分な対策をしてあげて下さい。
扇風機に触れて事故を起こさないようにする為には、猫が接触しないように対策が必要になります。
好奇心旺盛な猫は小さな子供のように思いがけない行動をしますので、柵やストーブガードなどで扇風機を囲むようにし危険を回避してあげます。
それでも怪我をしてしまう心配がある場合は、壁掛けの扇風機を使ってみるのもいいかもしれません。
愛猫が怪我をしてしまうととても痛々しく可愛そうになりますので、事故が起きないように十分な対策をしてあげて下さい。
 もし猫が扇風機に強く体当たりした場合でも、絶対に倒れないように柱などにくくりつけて固定をします。
固定をする際に細い紐を使ってしまうと、猫がじゃれたり誤飲の原因にもなりますので注意が必要です。
留守番をさせる際には扇風機を他の部屋に移動させて、猫が触れないようにすれば安心です。
飼い主が留守の間は猫にとって不安でもあり開放的にもなりますので、安全に過ごせるようにしてあげる事も大切です。
もし猫が扇風機に強く体当たりした場合でも、絶対に倒れないように柱などにくくりつけて固定をします。
固定をする際に細い紐を使ってしまうと、猫がじゃれたり誤飲の原因にもなりますので注意が必要です。
留守番をさせる際には扇風機を他の部屋に移動させて、猫が触れないようにすれば安心です。
飼い主が留守の間は猫にとって不安でもあり開放的にもなりますので、安全に過ごせるようにしてあげる事も大切です。
 猫や子供が触っても怪我をしないように、ダイソンなどでは羽根のない扇風機が販売されています。
羽根のない扇風機は猫の興味をそそることがあまりなく、手を突っ込んでしまった場合でも怪我する心配もありません。
野生本能がある猫は飼い主が思いもつかない事に興味を示す時もありますので、扇風機を使用している間は油断をせずに見守ってあげるようにして下さい。
猫や子供が触っても怪我をしないように、ダイソンなどでは羽根のない扇風機が販売されています。
羽根のない扇風機は猫の興味をそそることがあまりなく、手を突っ込んでしまった場合でも怪我する心配もありません。
野生本能がある猫は飼い主が思いもつかない事に興味を示す時もありますので、扇風機を使用している間は油断をせずに見守ってあげるようにして下さい。
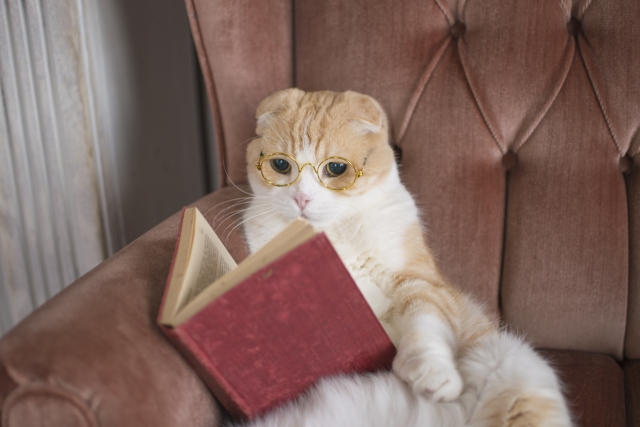 猫の熱中症を防ぐのに扇風機だけでは無理があり、扇風機での事故も数多く報告されています。
扇風機の音を嫌がり、風には不快を感じる猫もいるようです。
そこで扇風機以外で防ぐ方法を幾つか紹介します。
猫の熱中症を防ぐのに扇風機だけでは無理があり、扇風機での事故も数多く報告されています。
扇風機の音を嫌がり、風には不快を感じる猫もいるようです。
そこで扇風機以外で防ぐ方法を幾つか紹介します。
 猫は季節の変わり目になると抜け毛が多くなり、飼い主にとっても抜け毛の後始末が大変になります。
ブラッシングをしてあげるととても気持ち良さそうにし、飼い主に催促をする時の仕草は可愛らしく癒されます。
トリミングが苦手な猫も多くいますが、夏になる前に飼い主の手でブラッシングをして無駄な毛を取り除いてあげます。
長毛種の猫の場合は、短毛種の猫よりも念入りにブラッシングをした方が暑さ対策になるようです。
猫は季節の変わり目になると抜け毛が多くなり、飼い主にとっても抜け毛の後始末が大変になります。
ブラッシングをしてあげるととても気持ち良さそうにし、飼い主に催促をする時の仕草は可愛らしく癒されます。
トリミングが苦手な猫も多くいますが、夏になる前に飼い主の手でブラッシングをして無駄な毛を取り除いてあげます。
長毛種の猫の場合は、短毛種の猫よりも念入りにブラッシングをした方が暑さ対策になるようです。
 日常的に行える対策としては、猫が部屋を自由に行き来できるようにし自分で快適な場所を見つけられるようにしてあげます。
エアコンを使っている時はなるべく外気が入らないようにドアを閉め切ってしまいがちですが、猫にとってはあまり涼しいと感じていない事もあります。
猫が通れるだけの隙間を常に用意してあげる事が大切で、風が通ってドアが閉まってしまうような場合はドアストッパーなどを活用すれば安心です。
日常的に行える対策としては、猫が部屋を自由に行き来できるようにし自分で快適な場所を見つけられるようにしてあげます。
エアコンを使っている時はなるべく外気が入らないようにドアを閉め切ってしまいがちですが、猫にとってはあまり涼しいと感じていない事もあります。
猫が通れるだけの隙間を常に用意してあげる事が大切で、風が通ってドアが閉まってしまうような場合はドアストッパーなどを活用すれば安心です。
 扇風機の電源を入れると下の台が温かくなり、直接風が当たらない事もあって気持ち良く眠る猫もいます。
動いている時の扇風機の振動は猫の喉笛に似ていて、安らぎを感じて安心する猫もいるようです。
猫は少し高さのある物が好きで、扇風機の下の台を枕として利用している事もあります。
長毛種の猫は短毛種の猫と比べて、涼しい風をあびたいと思う傾向があるようです。
風に当たることが嫌いな猫や、音が苦手な場合は扇風機を嫌がります。
扇風機の電源を入れると下の台が温かくなり、直接風が当たらない事もあって気持ち良く眠る猫もいます。
動いている時の扇風機の振動は猫の喉笛に似ていて、安らぎを感じて安心する猫もいるようです。
猫は少し高さのある物が好きで、扇風機の下の台を枕として利用している事もあります。
長毛種の猫は短毛種の猫と比べて、涼しい風をあびたいと思う傾向があるようです。
風に当たることが嫌いな猫や、音が苦手な場合は扇風機を嫌がります。
 猫の祖先は暖かい場所に住んでいた事もあり、暖かい場所を好む猫が多いようです。
あくまで猫種や個体差がありますが、一般的にヒマラヤンやペルシャなどの長毛種は寒さに強いです。
マンチカンやアメリカン・ショートヘアなどの短毛種は寒さに弱い為、室内で飼っていても温度管理に注意が必要です。
人間から見たら毛に覆われていて暖かそうに見えますが、猫は意外に寒がりで寒い場所に行った後は暖かい所を好むようです。
猫の祖先は暖かい場所に住んでいた事もあり、暖かい場所を好む猫が多いようです。
あくまで猫種や個体差がありますが、一般的にヒマラヤンやペルシャなどの長毛種は寒さに強いです。
マンチカンやアメリカン・ショートヘアなどの短毛種は寒さに弱い為、室内で飼っていても温度管理に注意が必要です。
人間から見たら毛に覆われていて暖かそうに見えますが、猫は意外に寒がりで寒い場所に行った後は暖かい所を好むようです。
 猫は人間のように話す事ができず、寒がっているのに飼い主が気づけない事もあり可愛そうな思いをさせてしまいます。
そうならないよう猫が快適に過ごせるように、寒い時に見せる行動を調べて見ました。
猫は人間のように話す事ができず、寒がっているのに飼い主が気づけない事もあり可愛そうな思いをさせてしまいます。
そうならないよう猫が快適に過ごせるように、寒い時に見せる行動を調べて見ました。
 猫は寒さを感じると体を小さくして丸める生き物で、体をコンパクトにすることで熱が逃げるのを最小限に抑えています。
丸くなる姿がアンモナイトに似ている事から、アンモニャイトと呼ばれる事もあり寒さを感じているサインのひとつです。
猫が眠っている姿を眺めていると、人間のように体勢を変える様子は何とも言えない可愛らしさがあります。
暖かさを感じて眠っている時の姿は穏やかで、とても気持ち良さそうに見えます。
猫は寒さを感じると体を小さくして丸める生き物で、体をコンパクトにすることで熱が逃げるのを最小限に抑えています。
丸くなる姿がアンモナイトに似ている事から、アンモニャイトと呼ばれる事もあり寒さを感じているサインのひとつです。
猫が眠っている姿を眺めていると、人間のように体勢を変える様子は何とも言えない可愛らしさがあります。
暖かさを感じて眠っている時の姿は穏やかで、とても気持ち良さそうに見えます。
 猫が威嚇している時に毛が逆立つのを見る事が多いと思いますが、寒さを感じても毛を逆立てます。
寒さを感じた時は怒っているのではなく、逆立った毛と毛の間に空気を入れて体から熱が逃げないようにしています。
空気の層を纏う事ができて、体から熱が逃げない仕組みになっています。
猫にも野生の血が流れていて、産まれた時から自分を守れるように備わっているのかもしれません。
猫が威嚇している時に毛が逆立つのを見る事が多いと思いますが、寒さを感じても毛を逆立てます。
寒さを感じた時は怒っているのではなく、逆立った毛と毛の間に空気を入れて体から熱が逃げないようにしています。
空気の層を纏う事ができて、体から熱が逃げない仕組みになっています。
猫にも野生の血が流れていて、産まれた時から自分を守れるように備わっているのかもしれません。
 猫は寒くなると飼い主の膝の上に乗ってくつろいだり、一緒の布団で眠る行動が多く見られるようになります。
猫は気ままな一面もあり、ずっと一緒に布団で寝ていたのに急に来なくなってしまう事もあります。
飼い主にとっては寂しく感じてしまう事もありますが、猫に気を使わずに眠ると体が楽な場合もあります。
多頭飼育をしている場合は猫同士で仲良く寄り添って眠る様子が見られ、その光景には何となく癒されます。
寒い冬はおたがいに温め合う事で、信頼関係も深まるかもしれませんね!
猫は寒くなると飼い主の膝の上に乗ってくつろいだり、一緒の布団で眠る行動が多く見られるようになります。
猫は気ままな一面もあり、ずっと一緒に布団で寝ていたのに急に来なくなってしまう事もあります。
飼い主にとっては寂しく感じてしまう事もありますが、猫に気を使わずに眠ると体が楽な場合もあります。
多頭飼育をしている場合は猫同士で仲良く寄り添って眠る様子が見られ、その光景には何となく癒されます。
寒い冬はおたがいに温め合う事で、信頼関係も深まるかもしれませんね!
 猫が過ごしやすい室温は18〜26度程度で、その日の気温や体調に合わせて設定をしてあげる必要があります。
人間が使用している冷暖房のエアコンやこたつ、湯たんぽなどを、猫の寒さ対策にどのように用いれば安全なのかを調べて見ました。
猫が過ごしやすい室温は18〜26度程度で、その日の気温や体調に合わせて設定をしてあげる必要があります。
人間が使用している冷暖房のエアコンやこたつ、湯たんぽなどを、猫の寒さ対策にどのように用いれば安全なのかを調べて見ました。
 日が落ちて気温がグッと下がった頃に温度を20度前後になるようにタイマーセットをしてあげれば、暑くなり過ぎる心配もなく寒さ対策ができます。
エアコンは安全性が高く適温を維持する事ができますが、エアコンのリモコンに猫が触れてしまわないよう離れた場所へ置くようにします。
猫がリモコンをいたずらしたり、コード類をかじらないよう注意する事も大切です。
日が落ちて気温がグッと下がった頃に温度を20度前後になるようにタイマーセットをしてあげれば、暑くなり過ぎる心配もなく寒さ対策ができます。
エアコンは安全性が高く適温を維持する事ができますが、エアコンのリモコンに猫が触れてしまわないよう離れた場所へ置くようにします。
猫がリモコンをいたずらしたり、コード類をかじらないよう注意する事も大切です。
 猫からするとこたつ布団は重く、こたつの中から出たくても出られなくなってしまう心配があります。
猫をこたつに入れる際はあらかじめ猫の抜け道を作ってあげ、温度を低めに設定するなどして危険性を少しでも無くすようにします。
猫用こたつならヒーターが直接体に当たらないよう配慮されていますので、人間のこたつよりも安心して使えます。
好奇心旺盛な猫はコードをかじってしまう心配がありますが、かじっても感電しないように工夫がされていて安全です。
猫からするとこたつ布団は重く、こたつの中から出たくても出られなくなってしまう心配があります。
猫をこたつに入れる際はあらかじめ猫の抜け道を作ってあげ、温度を低めに設定するなどして危険性を少しでも無くすようにします。
猫用こたつならヒーターが直接体に当たらないよう配慮されていますので、人間のこたつよりも安心して使えます。
好奇心旺盛な猫はコードをかじってしまう心配がありますが、かじっても感電しないように工夫がされていて安全です。
 ペットヒーターには猫が丸まりながら眠っても体が収まるようなまん丸型や、可愛いねこ鍋型なども販売されていて選ぶ楽しみもあります。
ペット用であればコードを噛んでしまった時の感電の心配や、温度などの操作ができないよう工夫や対策がされています。
人間用のヒーターでは低温やけどなどの心配がありますが、留守番などが多い場合でも安心して使えます。
ケガややけどの心配がいらない、猫専用の暖房器具の購入を考えてみるのもいいかもしれませんね!
ペットヒーターには猫が丸まりながら眠っても体が収まるようなまん丸型や、可愛いねこ鍋型なども販売されていて選ぶ楽しみもあります。
ペット用であればコードを噛んでしまった時の感電の心配や、温度などの操作ができないよう工夫や対策がされています。
人間用のヒーターでは低温やけどなどの心配がありますが、留守番などが多い場合でも安心して使えます。
ケガややけどの心配がいらない、猫専用の暖房器具の購入を考えてみるのもいいかもしれませんね!
 地域によって特に厳しい真冬の寒さは、愛犬の体調やシニア犬・持病の有無などによって布団を用意してあげたほうが良い場合があります。
また、体温調整が上手にできないパピーやシングルコートの犬は寒さに弱いので、愛犬の状態をよく考えて配慮してあげましょう。
人と同じで、あまりに寒い環境にいることによって体調を崩したり食欲不振になったりして健康にも影響が出てしまいます。
特に夜中や明け方に気温は急降下しますので、部屋を温めていても暖房を止めたあとの愛犬のベッド周りの温度管理として適切な種類を用意します。
地域によって特に厳しい真冬の寒さは、愛犬の体調やシニア犬・持病の有無などによって布団を用意してあげたほうが良い場合があります。
また、体温調整が上手にできないパピーやシングルコートの犬は寒さに弱いので、愛犬の状態をよく考えて配慮してあげましょう。
人と同じで、あまりに寒い環境にいることによって体調を崩したり食欲不振になったりして健康にも影響が出てしまいます。
特に夜中や明け方に気温は急降下しますので、部屋を温めていても暖房を止めたあとの愛犬のベッド周りの温度管理として適切な種類を用意します。
 愛犬と一緒に寝ている飼い主様は、布団に潜り込んでくる愛犬の可愛らしい仕草に毎晩癒やされているのではないでしょうか。
寝返りが出来なくて体が痛いな、と思いながらも幸せな気分を感じる瞬間でもあります。
でもなぜ、布団に潜るのかご存知ですか。
布団に潜る犬の気持ちをご紹介していきます。
愛犬と一緒に寝ている飼い主様は、布団に潜り込んでくる愛犬の可愛らしい仕草に毎晩癒やされているのではないでしょうか。
寝返りが出来なくて体が痛いな、と思いながらも幸せな気分を感じる瞬間でもあります。
でもなぜ、布団に潜るのかご存知ですか。
布団に潜る犬の気持ちをご紹介していきます。
 お散歩で他の犬に会ったとき、「お友達なんだから仲良くね」とか、上手に挨拶できない愛犬に「お友達」がいないから可愛そうと思うことはありませんか。
確かに同じ犬同士で仲良くしている姿は、とても可愛らしく嬉しいことかもしれません。
ですが、愛犬は自分を一番に考えて愛してくれる飼い主様がいてくれれば幸せなんです。
一緒にいてくれて可愛がってくれる存在である飼い主様と、眠るときも一緒にいたいと感じているからこそ同じ布団に潜ってくれるんですね。
お散歩で他の犬に会ったとき、「お友達なんだから仲良くね」とか、上手に挨拶できない愛犬に「お友達」がいないから可愛そうと思うことはありませんか。
確かに同じ犬同士で仲良くしている姿は、とても可愛らしく嬉しいことかもしれません。
ですが、愛犬は自分を一番に考えて愛してくれる飼い主様がいてくれれば幸せなんです。
一緒にいてくれて可愛がってくれる存在である飼い主様と、眠るときも一緒にいたいと感じているからこそ同じ布団に潜ってくれるんですね。
 どちらかというと暑さには弱く寒さには強いといわれている犬ですが、寒くても平気なわけではありません。
前述のとおり、シングルコートの犬種やシニア犬など一部の犬は寒さによって体調を崩すこともあり、健康な犬でも寒いよりは適温を好みます。
特に昨今は、大型犬でも室内で育てる傾向にありますので寒さをより感じやすくなってきました。
温かい場所で眠ることは、犬にとって至福の時間でもあります。
どちらかというと暑さには弱く寒さには強いといわれている犬ですが、寒くても平気なわけではありません。
前述のとおり、シングルコートの犬種やシニア犬など一部の犬は寒さによって体調を崩すこともあり、健康な犬でも寒いよりは適温を好みます。
特に昨今は、大型犬でも室内で育てる傾向にありますので寒さをより感じやすくなってきました。
温かい場所で眠ることは、犬にとって至福の時間でもあります。
 犬が布団に潜ることは、安心感を与える良いことに思いますが危険な場面も多々存在します。
飼い主様にとって困ってしまうことが起きる可能性もありますので、注意が必要となります。
犬の性格に合わせて飼い主様が対処して、安全な環境を用意してあげましょう。
犬が布団に潜ることは、安心感を与える良いことに思いますが危険な場面も多々存在します。
飼い主様にとって困ってしまうことが起きる可能性もありますので、注意が必要となります。
犬の性格に合わせて飼い主様が対処して、安全な環境を用意してあげましょう。
 前足で一生懸命、布団をホリホリして寝床を整える様子は見ていてとても微笑ましいものです。
しかし、力の強い犬や大型犬の場合は特に、ホリホリが強すぎて布団が破けたり中綿が飛び出たりして飼い主様が驚くような状態になる可能性も考えられます。
カバーを丈夫なものに取り替えるなどの工夫が必要となります。
また、昼間にしっかり体を動かして疲れた状態にすることも対処法としてある程度は有効と考えられています。
いずれにしても、愛犬の性格や体調を考えて掘らなくても安心して眠れるようにしてあげたいですね。
前足で一生懸命、布団をホリホリして寝床を整える様子は見ていてとても微笑ましいものです。
しかし、力の強い犬や大型犬の場合は特に、ホリホリが強すぎて布団が破けたり中綿が飛び出たりして飼い主様が驚くような状態になる可能性も考えられます。
カバーを丈夫なものに取り替えるなどの工夫が必要となります。
また、昼間にしっかり体を動かして疲れた状態にすることも対処法としてある程度は有効と考えられています。
いずれにしても、愛犬の性格や体調を考えて掘らなくても安心して眠れるようにしてあげたいですね。
 愛犬が寒がっているサインを逃さずに温かさを保ってあげることで、健康と心の安定を守ることが大切となります。
では、愛犬のどんな様子で判断すればよいのでしょうか。
愛犬が寒がっているサインを逃さずに温かさを保ってあげることで、健康と心の安定を守ることが大切となります。
では、愛犬のどんな様子で判断すればよいのでしょうか。
 朝、いつも起きている時間になってもベッドから出てこないことも寒さを感じているサインと捉えましょう。
人も寒い日の朝は、布団から出るのが嫌ですよね。
なかなか起きられない状態なのは、冷たい空気に触れるのを嫌がっていると考えられます。
朝、いつも起きている時間になってもベッドから出てこないことも寒さを感じているサインと捉えましょう。
人も寒い日の朝は、布団から出るのが嫌ですよね。
なかなか起きられない状態なのは、冷たい空気に触れるのを嫌がっていると考えられます。
 愛犬を寒さから守り、快適な生活を送ってもらうために必要な対策を施しましょう。
でも、具体的にはどうしたら良いのか犬飼い初心者さんは特に悩みどころかもしれません。
危険の少ない方法を、愛犬の性格や体調に合わせて選んであげてください。
愛犬を寒さから守り、快適な生活を送ってもらうために必要な対策を施しましょう。
でも、具体的にはどうしたら良いのか犬飼い初心者さんは特に悩みどころかもしれません。
危険の少ない方法を、愛犬の性格や体調に合わせて選んであげてください。
 昔から使用されてきた湯たんぽは、火を使わずに暖かさを長時間キープすることができるので最近ではまた良さを見直されてきているアイテムです。
ですが、体を動かしにくいシニア犬は特に気づかないうちに低温やけどの可能性も考えられます。
飼い主様が側で注意してあげられないときは、使用を控えたりタオルを巻いたりして調節し安全面に配慮してあげてください。
お湯を入れるタイプの他に、電子レンジで中材を温めて使用するタイプもあります。
他にも、噛じりグセのある愛犬には固いプラスティック製のタイプを選ぶなど素材や大きさも様々に販売されています。
昔から使用されてきた湯たんぽは、火を使わずに暖かさを長時間キープすることができるので最近ではまた良さを見直されてきているアイテムです。
ですが、体を動かしにくいシニア犬は特に気づかないうちに低温やけどの可能性も考えられます。
飼い主様が側で注意してあげられないときは、使用を控えたりタオルを巻いたりして調節し安全面に配慮してあげてください。
お湯を入れるタイプの他に、電子レンジで中材を温めて使用するタイプもあります。
他にも、噛じりグセのある愛犬には固いプラスティック製のタイプを選ぶなど素材や大きさも様々に販売されています。
 ペット用の小型のヒーターも種類が増えてきており、愛犬のベット周りに簡単に設置することができます。
コの字型で立てて使用するタイプや、サークルの床面に置いて下から温めるタイプなど様々な形から選べます。
愛犬が暑さを感じたときに逃げられるように、サークルで使用する場合は何も置いていないスペースを確保することも大切です。
大きさもたくさんあり、サークル内のスペースが取れない場合は小さいタイプを選ぶと良いでしょう。
ペット用の小型のヒーターも種類が増えてきており、愛犬のベット周りに簡単に設置することができます。
コの字型で立てて使用するタイプや、サークルの床面に置いて下から温めるタイプなど様々な形から選べます。
愛犬が暑さを感じたときに逃げられるように、サークルで使用する場合は何も置いていないスペースを確保することも大切です。
大きさもたくさんあり、サークル内のスペースが取れない場合は小さいタイプを選ぶと良いでしょう。
 猫に関わる仕事をしたいと思った時に、専門知識の有無や資格の必要性を一番に考えるのではないでしょうか?
ペットに関わる仕事は増えていて、自分がしたいものや合ったものの仕事に就くための情報を集めて見ました。
猫に関わる仕事をしたいと思った時に、専門知識の有無や資格の必要性を一番に考えるのではないでしょうか?
ペットに関わる仕事は増えていて、自分がしたいものや合ったものの仕事に就くための情報を集めて見ました。
 猫のブリーダーであれば猫の繁殖を専門にしており、交配~出産まで全てのサポートを行います。
繁殖して生まれた健康な猫を市場に送り出す仕事で、深い知識と経験が必要になります。
産まれた子猫の世話や産後の母猫の健康管理と維持、仕事内容は多岐にわたります。
必要な資格は動物取扱業の届出と、民間資格のJCSA認定ドックブリーダー、ペット繁殖指導員、動物看護師、愛玩動物飼養管理士になります。
ペットに関する知識や技術が学べる専門学校で、資格を取得する事ができます。
猫のブリーダーであれば猫の繁殖を専門にしており、交配~出産まで全てのサポートを行います。
繁殖して生まれた健康な猫を市場に送り出す仕事で、深い知識と経験が必要になります。
産まれた子猫の世話や産後の母猫の健康管理と維持、仕事内容は多岐にわたります。
必要な資格は動物取扱業の届出と、民間資格のJCSA認定ドックブリーダー、ペット繁殖指導員、動物看護師、愛玩動物飼養管理士になります。
ペットに関する知識や技術が学べる専門学校で、資格を取得する事ができます。
 キャットシッターはペットシッターとも言い、お留守番する猫が快適な環境で過ごせるよう大切に丁寧にお世話をする仕事です。
環境の変化が苦手な猫にとって、暮らし慣れた大好きな家での留守番が一番ストレスを感じずに過ごせる方法です。
必要資格は動物取扱業登録申請と、民間資格の認定ペットシッターになります。
資格を取得する場合はペットシッタースクールや、キャットシッター養成講座の受講する方法があります。
キャットシッターはペットシッターとも言い、お留守番する猫が快適な環境で過ごせるよう大切に丁寧にお世話をする仕事です。
環境の変化が苦手な猫にとって、暮らし慣れた大好きな家での留守番が一番ストレスを感じずに過ごせる方法です。
必要資格は動物取扱業登録申請と、民間資格の認定ペットシッターになります。
資格を取得する場合はペットシッタースクールや、キャットシッター養成講座の受講する方法があります。
 飼い主がいない動物を保護する仕事で、正しい動物の飼育方法などの啓発活動も行います。
保護した子が病気になっている場合も多く、回復するまで面倒を見てあげ新しい飼い主を探す活動もあります。
施設の運営資金は寄付によってまかなわれている事が多く、募金活動の仕事も重要です。
動物の福祉を向上させていく仕事の為、日々の動物の観察も必要になります。
必要資格には動物取扱責任者と、動物取扱業登録申請があります。
資格を取得する場合は、専門学校で動物についての知識を学びます。
飼い主がいない動物を保護する仕事で、正しい動物の飼育方法などの啓発活動も行います。
保護した子が病気になっている場合も多く、回復するまで面倒を見てあげ新しい飼い主を探す活動もあります。
施設の運営資金は寄付によってまかなわれている事が多く、募金活動の仕事も重要です。
動物の福祉を向上させていく仕事の為、日々の動物の観察も必要になります。
必要資格には動物取扱責任者と、動物取扱業登録申請があります。
資格を取得する場合は、専門学校で動物についての知識を学びます。
 猫に関しての専門的な知識や資格がないと働けない事もありますが、ある程度の知識とやる気があれば大丈夫なものもあるようです。
学ぶチャンスや余裕のない人の為に、未経験でもOKな職業をいくつか紹介します。
猫に関しての専門的な知識や資格がないと働けない事もありますが、ある程度の知識とやる気があれば大丈夫なものもあるようです。
学ぶチャンスや余裕のない人の為に、未経験でもOKな職業をいくつか紹介します。
 動物病院には獣医や看護師だけではなく、事務や受付などを行うスタッフも必要となります。
入院中の猫のケアや、電話や来院される飼い主からの質問に対する応対をします。
病気についての質問であれば、獣医師に的確に伝え診察の介助を行います。
他にはカルテの管理、会計処理、ダイレクトメールの管理、書類作成、薬の在庫管理、来院予約管理などがあります。
動物病院での勤務となり、専門学校や大学を出ていれば仕事ができます。
動物病院には獣医や看護師だけではなく、事務や受付などを行うスタッフも必要となります。
入院中の猫のケアや、電話や来院される飼い主からの質問に対する応対をします。
病気についての質問であれば、獣医師に的確に伝え診察の介助を行います。
他にはカルテの管理、会計処理、ダイレクトメールの管理、書類作成、薬の在庫管理、来院予約管理などがあります。
動物病院での勤務となり、専門学校や大学を出ていれば仕事ができます。
 動物に関わる仕事に就きたい場合は、ペット用品メーカーに就職する方法もあります。
ペット用品メーカーは新卒を多く採用しますので、ペット関係の仕事が未経験で資格が無くても就職が可能です。
ペット用品には様々なジャンルがあり、幅広くペットに関わる事ができる魅力があります。
一般採用となる為、就職活動を通じて内定を得る事が条件となります。
動物に関わる仕事に就きたい場合は、ペット用品メーカーに就職する方法もあります。
ペット用品メーカーは新卒を多く採用しますので、ペット関係の仕事が未経験で資格が無くても就職が可能です。
ペット用品には様々なジャンルがあり、幅広くペットに関わる事ができる魅力があります。
一般採用となる為、就職活動を通じて内定を得る事が条件となります。
 自分の望む仕事に就きたいと思っても、学歴や資格がないせいで諦めなくてはいけない場合があります。
悔しい思いをしなですむように、猫に関わる仕事をする時に便利な資格をいくつか紹介します。”
自分の望む仕事に就きたいと思っても、学歴や資格がないせいで諦めなくてはいけない場合があります。
悔しい思いをしなですむように、猫に関わる仕事をする時に便利な資格をいくつか紹介します。”
 キャットシッターのスペシャリストを目指すための資格で、日本ペット技能検定協会で取得する事ができます。
ヒューマンアカデミーの「キャットスペシャリスト」ならキャットシッターの資格も同時に取得が可能です。
猫と関わる仕事をする場合に持っていると役立ちます。
お客様次第の仕事ですので収入などは安定しませんが、副業をはじめたいと考えている方におすすめです。
キャットシッターのスペシャリストを目指すための資格で、日本ペット技能検定協会で取得する事ができます。
ヒューマンアカデミーの「キャットスペシャリスト」ならキャットシッターの資格も同時に取得が可能です。
猫と関わる仕事をする場合に持っていると役立ちます。
お客様次第の仕事ですので収入などは安定しませんが、副業をはじめたいと考えている方におすすめです。
 テレビで放送されている盲導犬や警察犬などが活躍する姿は、人間よりも頭がいいのではと思う事があります。
猫も人間と一緒に暮らしているうちに、芸まではいかなくても驚く行動を見せてくれます。
猫と犬の賢さの違いを調べて見ました。
テレビで放送されている盲導犬や警察犬などが活躍する姿は、人間よりも頭がいいのではと思う事があります。
猫も人間と一緒に暮らしているうちに、芸まではいかなくても驚く行動を見せてくれます。
猫と犬の賢さの違いを調べて見ました。
 猫は勝手気ままに行動する習性がある動物で、誰かに教わるのではなく自発的に学習するスタイルが身についています。
ドアの向こうに目的の物があれば、人間の様子を見ながらドアの開け方を学習します。
いつももらえるおやつの引き出しがあれば、自分で引き出しを開けて食べようとします。
外に出たい時には飼い主の行動をよく観察していて、玄関や窓が開く瞬間を逃さず素早い動きを見せます。
猫は飼い主が「いつ覚えたのだろう」と思う事をやって、日々驚かせ笑わせてもくれるようです。
猫は勝手気ままに行動する習性がある動物で、誰かに教わるのではなく自発的に学習するスタイルが身についています。
ドアの向こうに目的の物があれば、人間の様子を見ながらドアの開け方を学習します。
いつももらえるおやつの引き出しがあれば、自分で引き出しを開けて食べようとします。
外に出たい時には飼い主の行動をよく観察していて、玄関や窓が開く瞬間を逃さず素早い動きを見せます。
猫は飼い主が「いつ覚えたのだろう」と思う事をやって、日々驚かせ笑わせてもくれるようです。
 猫は犬よりも劣る面もありますが、脳は人間と似ている構造をしています。
そのせいもあり人間の行動を見て学習し、ドアや引き出しなどを器用に開ける事が出来る様です。
他にも賢い理由を詳しく調べてみました。
猫は犬よりも劣る面もありますが、脳は人間と似ている構造をしています。
そのせいもあり人間の行動を見て学習し、ドアや引き出しなどを器用に開ける事が出来る様です。
他にも賢い理由を詳しく調べてみました。
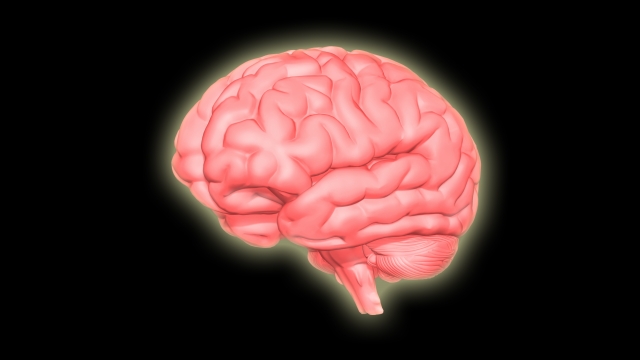 短期記憶とは違い、長い期間覚えていられる記憶のことを長期記憶と言います。
猫はインパクトの大きい怖い記憶なども長く覚えている為、その時の記憶が蘇り反応を起こす事もあります。
キャリーケースに入り車に乗せられて動物病院に行き、注射や爪切りなど嫌な思いをした事は記憶に残っています。
その為キャリーバックや車、動物病院を見るだけで嫌がったり逃げ出してしまいます。
薬を無理に飲まされた事も覚えていて、準備をしている飼い主の様子を見ただけで避けようとします。
短期記憶とは違い、長い期間覚えていられる記憶のことを長期記憶と言います。
猫はインパクトの大きい怖い記憶なども長く覚えている為、その時の記憶が蘇り反応を起こす事もあります。
キャリーケースに入り車に乗せられて動物病院に行き、注射や爪切りなど嫌な思いをした事は記憶に残っています。
その為キャリーバックや車、動物病院を見るだけで嫌がったり逃げ出してしまいます。
薬を無理に飲まされた事も覚えていて、準備をしている飼い主の様子を見ただけで避けようとします。
 猫は自立心がとても高い生き物で、犬のように芸をしないのではなく誰かの為に覚えようとは思わないようです。
中には飼い主の教え方次第で、芸を覚えて楽しませてくれる猫もいます。
単独行動をしながら生きていく為に必要なのは、自身の安全を守る力です。
猫の記憶力は自分を守るために発達し、台所に美味しいものがあるのを覚えていてキッチン台に乗る事があります。
人間用のトイレの仕方をいつの間にか覚えて、上手に使用する姿には驚かされます。
猫は自立心がとても高い生き物で、犬のように芸をしないのではなく誰かの為に覚えようとは思わないようです。
中には飼い主の教え方次第で、芸を覚えて楽しませてくれる猫もいます。
単独行動をしながら生きていく為に必要なのは、自身の安全を守る力です。
猫の記憶力は自分を守るために発達し、台所に美味しいものがあるのを覚えていてキッチン台に乗る事があります。
人間用のトイレの仕方をいつの間にか覚えて、上手に使用する姿には驚かされます。
 猫の人気ランキングをテレビなどで見かける事がありますが、それぞれに特徴や魅力があり可愛らしく癒されます。
種類の多い猫の中から、飼う時の目安にもなる賢い猫トップ5を紹介します。
猫の人気ランキングをテレビなどで見かける事がありますが、それぞれに特徴や魅力があり可愛らしく癒されます。
種類の多い猫の中から、飼う時の目安にもなる賢い猫トップ5を紹介します。
 生まれた時は真っ白ですが、成長していくうちに顔や耳、足や尻尾にポイントとなる色が入ります。
好奇心と賢さを兼ね添えていますので、しつけがしやすくテーブルの上に上がらないように訓練することもできます。
感受性が強く愛情深い所があり人間を見た時に「この人は優しそう」と感じたり、人間が発する雰囲気を読み取って接近したり離れたりもします。
人を良く観察しているせいか家のドアを開ける確率が高く、スマートで飼いやすい猫種です。
生まれた時は真っ白ですが、成長していくうちに顔や耳、足や尻尾にポイントとなる色が入ります。
好奇心と賢さを兼ね添えていますので、しつけがしやすくテーブルの上に上がらないように訓練することもできます。
感受性が強く愛情深い所があり人間を見た時に「この人は優しそう」と感じたり、人間が発する雰囲気を読み取って接近したり離れたりもします。
人を良く観察しているせいか家のドアを開ける確率が高く、スマートで飼いやすい猫種です。
 折りたたまれた耳と、丸くて大きな瞳が特徴の可愛らしい猫です。
はじめてみた時には他の猫とは違った折れた耳で違和感を感じると思いますが、見慣れてしまうチャームポイントにも見えてきます。
人懐っこく甘えん坊な優しい性格で、鳴き声もあまり大きくなく周りに迷惑をかける心配がいりません。
人見知りがなく愛情の交流がしっかりでき、飼い主さんラブなのでとても飼いやすい猫です。
折りたたまれた耳と、丸くて大きな瞳が特徴の可愛らしい猫です。
はじめてみた時には他の猫とは違った折れた耳で違和感を感じると思いますが、見慣れてしまうチャームポイントにも見えてきます。
人懐っこく甘えん坊な優しい性格で、鳴き声もあまり大きくなく周りに迷惑をかける心配がいりません。
人見知りがなく愛情の交流がしっかりでき、飼い主さんラブなのでとても飼いやすい猫です。
 ちくわは猫に食べさせても大丈夫かと気になる方も多いと思います。
この記事ではちくわを猫にあげても大丈夫かについてお話いたします。
そもそもちくわは主原料が魚です。
なので健康的な猫であれば基本的に与えられても問題はありません。
しかし、ちくわは人間の食用に製造していて、含まれる塩分量が猫用ではない可能性がございます。
販売品によっては猫にとって塩分が強すぎる物もあるそうです。
また猫は泌尿器系の病気(腎臓病や尿路結石)が多いため塩分の取りすぎは体に悪影響を与えます。
特に塩分濃度が高い食品(塩漬けた魚など)は嘔吐してしまいます。
【絶対に安全な食べ物】とは一概に決めることはできません。
猫の為にも最低限の知識は備える事も必要ですね。
ちくわは猫に食べさせても大丈夫かと気になる方も多いと思います。
この記事ではちくわを猫にあげても大丈夫かについてお話いたします。
そもそもちくわは主原料が魚です。
なので健康的な猫であれば基本的に与えられても問題はありません。
しかし、ちくわは人間の食用に製造していて、含まれる塩分量が猫用ではない可能性がございます。
販売品によっては猫にとって塩分が強すぎる物もあるそうです。
また猫は泌尿器系の病気(腎臓病や尿路結石)が多いため塩分の取りすぎは体に悪影響を与えます。
特に塩分濃度が高い食品(塩漬けた魚など)は嘔吐してしまいます。
【絶対に安全な食べ物】とは一概に決めることはできません。
猫の為にも最低限の知識は備える事も必要ですね。
 【おさかなくわえた野良猫】という言葉があるように猫の餌と言えば魚のイメージガツオいですよね。
キャットフードの中でもヒラメや鯛などが代表的です。
その影響か魚肉加工品(ちくわ)を与える家庭も少なくないはずです。
ちくわは魚肉から製造される食べ物なので、好んで食べる猫も多いです。
どこの家庭でもちくわとかまぼこは冷蔵庫にあるおてごろ価格商品です。
だだしちくはなどの魚肉加工品を猫に日常的に与えるのはデメリットがあります。
なのにメリットはそこまでありません。
こちらでは猫にちくわの猫にとってのリスクなどをまとめます
【おさかなくわえた野良猫】という言葉があるように猫の餌と言えば魚のイメージガツオいですよね。
キャットフードの中でもヒラメや鯛などが代表的です。
その影響か魚肉加工品(ちくわ)を与える家庭も少なくないはずです。
ちくわは魚肉から製造される食べ物なので、好んで食べる猫も多いです。
どこの家庭でもちくわとかまぼこは冷蔵庫にあるおてごろ価格商品です。
だだしちくはなどの魚肉加工品を猫に日常的に与えるのはデメリットがあります。
なのにメリットはそこまでありません。
こちらでは猫にちくわの猫にとってのリスクなどをまとめます
 猫はちくわを食べても大丈夫なのか心配になりますよね。
少量であれば猫がちくわを食べても平気なのか心配になる気持ちもわかります。
カニカマや魚肉ソーセージと同様ちくわも塩分が高く、アレルギー症状を起こすリスクもあります。
この記事では猫にちくわ与える注意点を紹介します。
猫はちくわを食べても大丈夫なのか心配になりますよね。
少量であれば猫がちくわを食べても平気なのか心配になる気持ちもわかります。
カニカマや魚肉ソーセージと同様ちくわも塩分が高く、アレルギー症状を起こすリスクもあります。
この記事では猫にちくわ与える注意点を紹介します。
 二つ目に注意すべきことはちくわには人間向けに含まれた成分が猫にとって害になる可能性があることです。
例えばあるちくわの中には「加工でん粉」、「調味料(アミノ酸等)」、「貝Ca」などの加工物が入っています。
ちくわのメーカーや商品によっては添加物や合成成分などが多く含まれているものがあり、猫の体に悪影響を及ぼす可能性があります。
もし猫にちくわをあげる際には無添加や保存料、殺菌料が入っていない無添加のちくわをあげるようにしましょう。
二つ目に注意すべきことはちくわには人間向けに含まれた成分が猫にとって害になる可能性があることです。
例えばあるちくわの中には「加工でん粉」、「調味料(アミノ酸等)」、「貝Ca」などの加工物が入っています。
ちくわのメーカーや商品によっては添加物や合成成分などが多く含まれているものがあり、猫の体に悪影響を及ぼす可能性があります。
もし猫にちくわをあげる際には無添加や保存料、殺菌料が入っていない無添加のちくわをあげるようにしましょう。
 それでは、猫にちくわを与えすぎることでどのような悪影響が出てきてしますのでしょうか。
ここでは猫に出てくる悪影響についてご紹介したいと思います。
それでは、猫にちくわを与えすぎることでどのような悪影響が出てきてしますのでしょうか。
ここでは猫に出てくる悪影響についてご紹介したいと思います。
 二つ目に「慢性腎不全や尿石症」があげられます。
猫は塩分を体外に出すことが苦手なので、人間の食べ物を食べさせ過ぎると、腎臓に負荷がかかり、膀胱にまで害が及びます。
腎臓がダメージを受けて十分に機能しなくなる状態を「腎不全」といい、これが長期間続くと慢性腎臓病(慢性腎不全)となります。
慢性腎不全は猫の死因ランキングで二番目に高い病気です。
また、尿石症とは腎臓から尿管、膀胱、尿道の中に結晶や結石ができる病気で、膀胱や尿道を傷つけたり、尿道に詰まったりします。
重度の尿路結石症(尿石症)を発症すると、結石が尿道に詰まる尿道閉塞や、排尿困難から腎機能の低下を引き起こし、尿毒症などを誘発する場合があるので大変危険な病気です。
一般的な尿石症の症状はトイレに行く回数が増える、トイレとまったく関係ない場所で排尿をするなどがあげられます。
慢性腎不全や尿石症は食事を含めた予防対策でコントロールすることができる病気なので飼い主は注意しましょう。
二つ目に「慢性腎不全や尿石症」があげられます。
猫は塩分を体外に出すことが苦手なので、人間の食べ物を食べさせ過ぎると、腎臓に負荷がかかり、膀胱にまで害が及びます。
腎臓がダメージを受けて十分に機能しなくなる状態を「腎不全」といい、これが長期間続くと慢性腎臓病(慢性腎不全)となります。
慢性腎不全は猫の死因ランキングで二番目に高い病気です。
また、尿石症とは腎臓から尿管、膀胱、尿道の中に結晶や結石ができる病気で、膀胱や尿道を傷つけたり、尿道に詰まったりします。
重度の尿路結石症(尿石症)を発症すると、結石が尿道に詰まる尿道閉塞や、排尿困難から腎機能の低下を引き起こし、尿毒症などを誘発する場合があるので大変危険な病気です。
一般的な尿石症の症状はトイレに行く回数が増える、トイレとまったく関係ない場所で排尿をするなどがあげられます。
慢性腎不全や尿石症は食事を含めた予防対策でコントロールすることができる病気なので飼い主は注意しましょう。
 仕事で疲れた時、落ち込んでいるとき、ペットと一緒にいると癒されますよね。
ペットには高い癒し効果があり、精神面や身体面のケアを行い病気の改善を目指すために、医療活動の一環としても取り入れられることもあります。
ペットと触れ合うことで自律神経が整い、他人とのかかわりが増えたりすることで、精神的なゆとりや充足感を得られるなど、様々な良い影響が期待できるでしょう。
なぜ癒し効果があるのかというと、犬は他の動物よりも忠誠心が強く、飼い主のことを心から信頼する生き物です。
犬を撫でたりすると、その優しいぬくもりが肌を通して伝わります。
犬の暖かさが伝わると、人間の脳内には幸せホルモンのオキシトシンが分泌され、愛情を感じて癒されます。
疲れている時こそ積極的に触れ合うことが大切かもしれませんね。
仕事で疲れた時、落ち込んでいるとき、ペットと一緒にいると癒されますよね。
ペットには高い癒し効果があり、精神面や身体面のケアを行い病気の改善を目指すために、医療活動の一環としても取り入れられることもあります。
ペットと触れ合うことで自律神経が整い、他人とのかかわりが増えたりすることで、精神的なゆとりや充足感を得られるなど、様々な良い影響が期待できるでしょう。
なぜ癒し効果があるのかというと、犬は他の動物よりも忠誠心が強く、飼い主のことを心から信頼する生き物です。
犬を撫でたりすると、その優しいぬくもりが肌を通して伝わります。
犬の暖かさが伝わると、人間の脳内には幸せホルモンのオキシトシンが分泌され、愛情を感じて癒されます。
疲れている時こそ積極的に触れ合うことが大切かもしれませんね。
 ペットを飼っている人なら誰しも癒されたと感じたことがあるのではないでしょうか。
実際に、癒されたといってもどのような時に癒されて、どのような効果があるのかを考えたことは少ないのではないかと思います。
そこで、犬との暮らしで癒し効果が得られるメカニズムを紹介したいと思います。
ペットを飼っている人なら誰しも癒されたと感じたことがあるのではないでしょうか。
実際に、癒されたといってもどのような時に癒されて、どのような効果があるのかを考えたことは少ないのではないかと思います。
そこで、犬との暮らしで癒し効果が得られるメカニズムを紹介したいと思います。
 犬を飼うことで必ず行うことの一つが散歩。
一人で散歩をしようとしてもついつい面倒になって、今日はいいやと思ったこともあるのではないでしょうか。
しかし犬があなたと散歩に行くのを楽しみにしていた場合、断れません。
雨が降っていても、暑くても犬は待ってくれません。
体調が悪い時にも行かなくてはいけないこともあるかもしれません。
毎日の散歩は、人間の運動量を増やして健康を増進してくれます。
小型犬なら近所を10分程度歩き回れば満足するでしょう。
しかし大型犬となると大きな公園や広場で走り回らせないといけません。
大変だと感じるかもしれませんが、運動不足を解消する為に犬を飼うという人もいるくらい犬との散歩は楽しいものです。
もしくは、おもちゃを買って一緒に遊ぶのもいいかもしれないですね。
犬を飼うことで必ず行うことの一つが散歩。
一人で散歩をしようとしてもついつい面倒になって、今日はいいやと思ったこともあるのではないでしょうか。
しかし犬があなたと散歩に行くのを楽しみにしていた場合、断れません。
雨が降っていても、暑くても犬は待ってくれません。
体調が悪い時にも行かなくてはいけないこともあるかもしれません。
毎日の散歩は、人間の運動量を増やして健康を増進してくれます。
小型犬なら近所を10分程度歩き回れば満足するでしょう。
しかし大型犬となると大きな公園や広場で走り回らせないといけません。
大変だと感じるかもしれませんが、運動不足を解消する為に犬を飼うという人もいるくらい犬との散歩は楽しいものです。
もしくは、おもちゃを買って一緒に遊ぶのもいいかもしれないですね。
 実は犬との触れ合いは、うつ病患者が犬と触れ合うと、精神的なつらさが軽減され、大きな癒し効果を得られると言われています。
犬は飼い主さんに愛を注いでくるその為、安心感が生まれて、ストレスが発散されるのです。
相手の目線や自分がどう思われるかを考えなくてよいのは、うつ病の人にとってとても効果的だといわれています。
飼い主さんのことが大好きで、共に生活を過ごすことがうつ病患者の方にとってストレス軽減になり、癒されるんですね。
遊ぶだけではなく、一緒に寝たり、散歩をしたりと人間の生活を共に過ごせることが犬の強みでもあります。
そんな犬の存在は病気の人をも癒す効果があるといっても過言ではありません。
実は犬との触れ合いは、うつ病患者が犬と触れ合うと、精神的なつらさが軽減され、大きな癒し効果を得られると言われています。
犬は飼い主さんに愛を注いでくるその為、安心感が生まれて、ストレスが発散されるのです。
相手の目線や自分がどう思われるかを考えなくてよいのは、うつ病の人にとってとても効果的だといわれています。
飼い主さんのことが大好きで、共に生活を過ごすことがうつ病患者の方にとってストレス軽減になり、癒されるんですね。
遊ぶだけではなく、一緒に寝たり、散歩をしたりと人間の生活を共に過ごせることが犬の強みでもあります。
そんな犬の存在は病気の人をも癒す効果があるといっても過言ではありません。
 大型犬は子供が怖がってしまいことも多いかと思います。
しかし、犬はとても人懐っこい性格であるため、子どもに怯えたりすることが少なく、親の代わりとなって、子供の世話や相手をしてくれます。
犬は忠実である為、多少赤ちゃんに叩かれても平気な顔をします。時には親の代わりに躾けてもくれるので、慣れてくれば長々と子どもの相手をしてくれます。
愛されていると感じると、人間の心に癒しを与えてくれます。
犬を膝に乗せたり、犬の頭をなでたりするとそのぬくもりがと肌を通して伝わってきて、人間の脳の中にオキシトシンが分泌されます。
このオキシトシンは「幸せホルモン」や「愛情ホルモン」などと呼ばれていて疲れを軽減させたり、心を安定させる効果があるといわれています。
大型犬は子供が怖がってしまいことも多いかと思います。
しかし、犬はとても人懐っこい性格であるため、子どもに怯えたりすることが少なく、親の代わりとなって、子供の世話や相手をしてくれます。
犬は忠実である為、多少赤ちゃんに叩かれても平気な顔をします。時には親の代わりに躾けてもくれるので、慣れてくれば長々と子どもの相手をしてくれます。
愛されていると感じると、人間の心に癒しを与えてくれます。
犬を膝に乗せたり、犬の頭をなでたりするとそのぬくもりがと肌を通して伝わってきて、人間の脳の中にオキシトシンが分泌されます。
このオキシトシンは「幸せホルモン」や「愛情ホルモン」などと呼ばれていて疲れを軽減させたり、心を安定させる効果があるといわれています。
 実は、犬に直接触れていなくても、動画を見るだけで幸せ・愛情ホルモンのオキシトシンが分泌されます。
動物たちと触れ合ったり見つめ合ったりすると、自分が受け入れられたような、肯定的な気持ちになります。
そうすると、自分で自分を認めてあげる「自己効力感」が高まったり、何かを達成したような気持ちになります。
人間は可愛いものを愛でると母性が働き、オキシトシンが分泌されます。
オキシトシンがバランス良く出ている時は、精神状態が安定します。
動物を撫でる時もですが、直接触れなくても「可愛い!癒される!」と思うことがありますよね。
その気持ちが人間の母性を刺激し、心の乱れを落ち着かせてくれ精神的に安定するのです。
実は、犬に直接触れていなくても、動画を見るだけで幸せ・愛情ホルモンのオキシトシンが分泌されます。
動物たちと触れ合ったり見つめ合ったりすると、自分が受け入れられたような、肯定的な気持ちになります。
そうすると、自分で自分を認めてあげる「自己効力感」が高まったり、何かを達成したような気持ちになります。
人間は可愛いものを愛でると母性が働き、オキシトシンが分泌されます。
オキシトシンがバランス良く出ている時は、精神状態が安定します。
動物を撫でる時もですが、直接触れなくても「可愛い!癒される!」と思うことがありますよね。
その気持ちが人間の母性を刺激し、心の乱れを落ち着かせてくれ精神的に安定するのです。