犬の心臓病とは?
 犬の心臓病は10~15%に起こると言われています。
心臓がポンプとして働くためには、心臓の筋肉や弁が正しいリズムで動き、血管に血液をスムーズに送り出すようにしなければいけません。これらのどの部分に異常が起きても、心臓はきちんと働く事ができず、心臓病になってしまうのです。
心臓病になると、心臓がポンプとしての役割を果たせなくなり、全身に血液を送る事ができなくなっていきます。
その結果、全身に十分な酸素や栄養を送る事ができず疲労や呼吸困難、食欲の低下などが見られるようになり、体に水分がたまるようになると浮腫みが出たり、お腹がふくれる事があります。
そんな心臓病ですが、その中でも最も多い心臓病は僧帽弁閉鎖不全症というもので、次にこの僧帽弁閉鎖不全症についてご紹介していきます。
犬の心臓病は10~15%に起こると言われています。
心臓がポンプとして働くためには、心臓の筋肉や弁が正しいリズムで動き、血管に血液をスムーズに送り出すようにしなければいけません。これらのどの部分に異常が起きても、心臓はきちんと働く事ができず、心臓病になってしまうのです。
心臓病になると、心臓がポンプとしての役割を果たせなくなり、全身に血液を送る事ができなくなっていきます。
その結果、全身に十分な酸素や栄養を送る事ができず疲労や呼吸困難、食欲の低下などが見られるようになり、体に水分がたまるようになると浮腫みが出たり、お腹がふくれる事があります。
そんな心臓病ですが、その中でも最も多い心臓病は僧帽弁閉鎖不全症というもので、次にこの僧帽弁閉鎖不全症についてご紹介していきます。
最も多い心臓病は僧帽弁閉鎖不全症
僧帽弁は、左心室と左心房の間の弁で、左心室から大動脈へ血液を送り出す時に、血液が左心房へ逆流するのを防いでいます。この弁が変性し、上手く閉まらなくなると、血液が左心室から左心房へ逆流します。
弁の変性は、5歳以下の犬にはまれですが、例外なのが、キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルで、若くして弁の変性を起こすことがわかっています。
僧帽弁が上手く閉じなくなってしまうと、血液の一部が逆流してしまうので、全身へ上手く血液を送り出せなくなります。
初期の段階では、心臓が頑張って働く事により、全身に大きな影響はありませんが、頑張り続けた心臓が限界を抑えると、血液を十分に送れなくなり、心不全の状態になります。
早期の場合は、無症状で、定期健診時などに心臓の雑音によって発見される事がほとんどですが、一番最初に見られる症状は咳で、痰を吐き出すような咳が、主に興奮時や夜~朝方に認められるようになります。
更に進行すると、疲れやすくなったり痩せてきたりといった症状が出るようになります。
そこから更に心不全の状態へ進行すると、肺の中で血液が鬱滞し、肺水腫となり、チアノーゼが見られるようになったり、不整脈による失神が見られるようになり、死亡する可能性もある怖い病気です。
早期発見が大事になってきますので、定期的な健康診断と少しでもおかしな咳が見られるようであれば受診しましょう。
犬の心臓病の症状
 心臓病が早期の場合、自覚症状は全くありませんが、心臓病が進行してくると咳や疲れやすくなったり、浮腫み・腹水・失神・呼吸困難・突然死などの症状を示すようになります。
その中でも典型的な症状は咳なのですが、咳をしているから心臓病だと言うわけではありませんが、中型犬以上の犬の場合は、心臓病が原因で咳をするケースが非常に多くなっており、小型犬の場合は、心臓病以外、たとえば気管の障害が原因で咳をする事が多いのですが、それでも高齢の小型犬が咳をすれば、やはり心臓病を疑う必要があるでしょう。
初期症状はないと先ほどご紹介しましたが、ほとんどの心臓病で初期から心雑音というものが出てきます。
心雑音は聴診器を使用すればすぐにわかりますが、飼い主さんにはわからない事なので、予防接種の際や定期健診の際など定期的に聴診を受ける事が大切です。
心臓病が早期の場合、自覚症状は全くありませんが、心臓病が進行してくると咳や疲れやすくなったり、浮腫み・腹水・失神・呼吸困難・突然死などの症状を示すようになります。
その中でも典型的な症状は咳なのですが、咳をしているから心臓病だと言うわけではありませんが、中型犬以上の犬の場合は、心臓病が原因で咳をするケースが非常に多くなっており、小型犬の場合は、心臓病以外、たとえば気管の障害が原因で咳をする事が多いのですが、それでも高齢の小型犬が咳をすれば、やはり心臓病を疑う必要があるでしょう。
初期症状はないと先ほどご紹介しましたが、ほとんどの心臓病で初期から心雑音というものが出てきます。
心雑音は聴診器を使用すればすぐにわかりますが、飼い主さんにはわからない事なので、予防接種の際や定期健診の際など定期的に聴診を受ける事が大切です。
犬の心臓病のステージ分類

POINT
心臓病の正常な血液の流れは全身→右心房→右心室→肺→左心房→左心室→全身となるのですが
心臓病の場合は
全身→右心房→右心室→肺→左心房→左心室→左心房→左心室→全身
という異常な血液の流れになってしまいます。
犬の心臓病にはステージ分類がされており
・ステージA
・ステージB1
・ステージB2
・ステージC
・ステージD
と分かれています。
次の項目からステージ分類別に詳しく状態などをご紹介していきます。
ステージA
まずは、ステージAについてご紹介していきましょう。
ステージAに分類されるのは心疾患のリスクがある犬種となっています。
具体的にあげると、中高齢の室内犬・キャバリアキングチャールズスパニエル・レトリーバー・ボクサー・ニューファンランド・ジャーマンシェパードドッグ・チワワ・ポメラニアン・ヨークシャテリア・フレンチブルドッグ・ビーグル・ミニチュアシュナウザー・ボクサー・サモエド・ドーベルマン・プードル・ポメラニアン・マルチーズ・コリー・シェットランドシープドッグ・グレードデーン・セントバーナードなどになります。
ご紹介した全ての犬種が心臓病になるとは限りませんが、高齢になると出てきやすくなりますので、定期健診か欠かさず受けるようにしましょう。
ステージB1
ステージB1に分類される状態は、聴診により心雑音が聞こえるが、症状はないという状態です。
正常では左心室の血液は全身に流れますが、この病気では血液の一部が左心房にも流れてしまうため、全身に流れる血液の量が減少してしまう事がわかっています。
心臓病の初期では、全身への血液量を減らさないように、心臓が頑張って働いている状態です。
ステージB2
ステージB2の分類は、症状はないが、だんだん心臓が大きくなっている状態です。
頑張り過ぎた心臓はポンプ機能が次第に低下していきます。
すると、全身に送れなかった血液が徐々に心臓にたまっていき、心臓はゆっくりと大きくなっていきます。
特に左心房は、血液を送り出したはずなのに逆流によって血液が帰ってきてしまうため、顕著に大きくなっているのがわかるようになります。
ステージC
ステージCに分類される状態は、さらに心臓が大きくなり症状が現れる状態と肺や全身の臓器に異常がでてくるという状態です。
心臓病で現れる症状は様々ですが、最初に見られるのは咳や運動不耐性が多いです。
咳の症状は、左心房がどんどん大きくなり、気管を押し上げてしまう事で起こります。
また、運動不耐性とは運動を嫌がるようになったり、すぐに疲れやすくなったりする事です。
そして、全身の臓器に異常が出てくる状態というのは、血液の流れが悪くなり左心房がどんどん大きくなると、次は肺に血液がたまってしまいます。必要以上に肺に血液がたまると肺水腫という状態に陥り、呼吸困難で救急搬送されるケースも見られます。全身に送り出す血液量も減ってしまいますので、様々な臓器に影響が出ますが、特に腎臓の働きが著しく悪くなるケースが多いでしょう。
ステージD
ステージDに分類される状態とは、難治性心不全の状態になります。
心不全とは、心臓の機能が低下し、全身に血液や酸素が十分に送り出せなくなる状態の事です。
症状としては、息切れ・疲労感・呼吸困難・浮腫・動悸・胸痛などがあり、重症化すると安静時でも症状が現れるようになります。
難治性心不全とは、心不全がさらに重症化した状態で、強心剤が必要となるくらい悪い状態になっており、予後は極めて不良となります。
通常の治療法では、効果がなく、補助循環治療や心臓移植が必要となるレベルです。
犬の心臓病への治療薬について
 犬の心臓病への治療薬は初期段階では、血管拡張薬という血液の巡りを良くして心臓の負担を軽くする薬を使用します。
しかし、投薬を行うという事は、体に何らかの変化を与える事にもなりますので、その変化を飼い主さんはきちんと理解しておく必要があるでしょう。
薬を処方された時には、その薬がどんな風に体に作用するのか、そのために気をつける事は何なのか、飼い主さんも積極的に先生に質問して下さい。
最終的に心臓病は投薬のみで良くなる事もありますが、一般的には手術が必要なケースの方が多いので、薬のみで治療したいのか、手術のケースも考えて治療したいのかを先生としっかり相談しましょう。
犬の心臓病への治療薬は初期段階では、血管拡張薬という血液の巡りを良くして心臓の負担を軽くする薬を使用します。
しかし、投薬を行うという事は、体に何らかの変化を与える事にもなりますので、その変化を飼い主さんはきちんと理解しておく必要があるでしょう。
薬を処方された時には、その薬がどんな風に体に作用するのか、そのために気をつける事は何なのか、飼い主さんも積極的に先生に質問して下さい。
最終的に心臓病は投薬のみで良くなる事もありますが、一般的には手術が必要なケースの方が多いので、薬のみで治療したいのか、手術のケースも考えて治療したいのかを先生としっかり相談しましょう。
投薬だけでの半年後の生存率は50%と言われる
手術成績が向上しても現在、僧帽弁閉鎖不全症の手術を積極的に行っている獣医師は、全国レベルを見てもそう多くはありません。日本国内では極わずかと言えるでしょう。
ですので、実際には投薬治療のみで対処されているケースがほとんどになりますが、実際手術が出来ないケースも多くあります。
てんかんなど、他の重篤な病気を併発している場合や、体力的に麻酔や人工心肺を使用する事が難しい時には投薬と定期健診で診ていくしかないのです。
僧帽弁閉鎖不全症の投薬治療を開始した場合、約半年後の生存率が50%と統計が出ており、発症した時点で既に高齢であれば、その半年は犬にとって十分な年月だと言えるかもしれません。
しかし、若くして発症してしまった場合の半年はあまりにも短すぎますよね。投薬治療と言っても、病気を根本的に治すものではなく、対処療法になりますので、進行してしまった場合は残念ですが、もう走りまわる事はできないと考える方がいいでしょう。
でも、現在の医学は日々進歩していますので、素晴らしい薬も沢山あります。望みは捨てないで下さいね。
薬の副作用はある?
薬の使い始めは、飼い主さんの目にもはっきりわかるくらい、しっかり効く事が多いのですが、副作用が全くないという薬はありませんので理解しておきましょう。
例えば、心臓病の薬を飲み始めて肝臓や腎臓の検査数値が上がってしまい、それらに対する薬を追加しなければならない事もあります。状態に合わせて薬を調整していくうちに、1回の服薬が7錠ではおさまらなくなってしまいます。
薬で体調をコントロールしているわけですので、飲み忘れは絶対にいけませんし、そのプレッシャーは飼い主さんにとってプレッシャーになっていくはずですが、1回でも薬を忘れてしまうと命の危険にさらしてしまうという結果になりかねません。
しかし、手術をするにも相当なリスクが伴ってしまうという事も考え、最終的には手術をするのか内科的治療でいくのかは飼い主さんの判断のゆだねられます。
愛犬の年齢や症状、正確などを考慮して治療方法を選択するようにしましょう。
そして、投薬のみで治療をする事になっても、完治する薬ではないという事を理解した上で薬でのコントロールを続けるようにして欲しいと思います。
まとめ
 今回は犬の心臓病についてご紹介してきました。
心臓病の中でも最も多い僧帽弁閉鎖不全症にスポット当てて詳しくご紹介してきましたが、この心臓病は罹ってしまったら絶対に死んでしまうという病気ではありませんが、出来るだけ早期発見が望ましい病気です。
若い年齢でもまれに罹りますが、大半は高齢になってからですので、日頃からの定期健診は必須になってきます。
元気であっても、咳が出たり、普段と違う様子が見られる場合は、すぐに受診するようにしましょう。
今回は犬の心臓病についてご紹介してきました。
心臓病の中でも最も多い僧帽弁閉鎖不全症にスポット当てて詳しくご紹介してきましたが、この心臓病は罹ってしまったら絶対に死んでしまうという病気ではありませんが、出来るだけ早期発見が望ましい病気です。
若い年齢でもまれに罹りますが、大半は高齢になってからですので、日頃からの定期健診は必須になってきます。
元気であっても、咳が出たり、普段と違う様子が見られる場合は、すぐに受診するようにしましょう。 猫が腎臓病になる原因
 猫の病気として必ずあげられるのが腎臓病です。
7才以上になると、そのうちの約3~4割の猫は腎臓病といわれています。さらに15才以上になれば8割の猫と割合も増えていますが、その原因はいまだにはっきりとは分かっていません。
一説に、猫はあまり水を飲まないため歯肉炎や口内炎によるウイルスが原因とか、生まれつきの遺伝性疾患によるものと考えられています。一度悪くなると元には戻せない腎臓、早期発見も難しい病気です。
どのような症状が見られたら腎臓病を疑えばいいのか、また普段から気をつけていきたいことなどをご紹介していきますので、愛猫の様子を観察してみてください。
猫の病気として必ずあげられるのが腎臓病です。
7才以上になると、そのうちの約3~4割の猫は腎臓病といわれています。さらに15才以上になれば8割の猫と割合も増えていますが、その原因はいまだにはっきりとは分かっていません。
一説に、猫はあまり水を飲まないため歯肉炎や口内炎によるウイルスが原因とか、生まれつきの遺伝性疾患によるものと考えられています。一度悪くなると元には戻せない腎臓、早期発見も難しい病気です。
どのような症状が見られたら腎臓病を疑えばいいのか、また普段から気をつけていきたいことなどをご紹介していきますので、愛猫の様子を観察してみてください。
猫がもっともかかるのは慢性腎臓病
腎臓病といっても、急性腎臓病と慢性腎臓病がありますが、猫がかかりやすいのは慢性腎臓病です。
腎臓の機能がゆっくりと低下していくために早期発見をするのがかなり難しい病気とされてきました。そのため気づいた時にはかなり進行した状態ということも少なくありません。
腎臓が炎症をおこして線維化した結果、機能を果たせなくなり最終的には死につながるのです。シニア猫の死因第一位にもあがるほどで、残念なことに一度腎臓機能が低下すると治すことはできません。
ヒマラヤンやペルシャ猫は生まれつきの遺伝子により、慢性腎臓病になりやすい傾向があります。
腎臓病と診断されたら、進行をおくらせることしかできない怖い病気でもあるのです。猫を飼った以上は腎臓病は覚悟しておかなければならない病気とも言えるため、日頃から私たちが気をつけてあげられる事を覚えておく必要があるとも言えるでしょう。
猫の腎臓病の症状
 猫にとって腎臓病は避けては通れない病気です。腎臓は体の中を流れる血液を濾過し、老廃物は尿として体外へ排出させ、必要な栄養分は再吸収しています。
大切な働きをする腎臓が腎臓病になると、毒素や老廃物が体内にたまり最後は死に至ってしまうのです。
腎臓の機能は一度低下してしまうと元には戻せません。進行を遅らせることしかできないため、少しでも早く病気であることな気づいてあげることしかできないのです。
では腎臓病になるとどのような症状がみられるのでしょうか。
猫にとって腎臓病は避けては通れない病気です。腎臓は体の中を流れる血液を濾過し、老廃物は尿として体外へ排出させ、必要な栄養分は再吸収しています。
大切な働きをする腎臓が腎臓病になると、毒素や老廃物が体内にたまり最後は死に至ってしまうのです。
腎臓の機能は一度低下してしまうと元には戻せません。進行を遅らせることしかできないため、少しでも早く病気であることな気づいてあげることしかできないのです。
では腎臓病になるとどのような症状がみられるのでしょうか。
POINT
①脱水症状
②水を飲む量が増える
③尿毒症
④貧血
⑤高血圧これらの症状に気づいた時には腎臓病はかなり進行しています。猫に長生きしてもらうためにも動物病院に連れて行き、今後の治療方法などについて相談する事をおすすめします。
脱水
腎臓病が進行すると水分の吸収が不十分になってしまい、以前に比べると水を飲む量は増えていても、ほとんどは尿として排出されてしまいます。そうなった時には、猫の体は脱水症状をおこしてしまうのです。
最近元気がない、あまり動かなくなった、何故か辛そうなどの症状が見られたら脱水症状をおこしている可能性があります。
確かめる方法として一度猫の首の後ろの皮膚をつまんでみてください。もし脱水症状ならば皮膚の戻りが悪くなります。
予防方としては、いつでも新鮮な水をたくさん飲めるように水場を増やしてあげると良いですね。特に子猫やシニア猫は気をつけて飲みやすい場所に置いてやり、こまめに様子を伺うようにしてください。
水を多く飲むようになる
猫が腎臓病になると水を飲む量が増え、それに伴い尿の回数や量も増加します。腎臓の機能が低下することにより水分の吸収が悪くなるため、水を飲む量が格段に増えてしまうのです。
尿の色も普段と違い、薄い色でニオイも猫特有のきついニオイではなくなります。最近猫の尿があまり匂わなくなったと感じたら要注意です。
もともと猫の祖先は砂漠地帯に住んでいたため、水をそれほど飲むことはありませんでした。そのために尿は濃縮された濃い色でニオイもかなりきついのが平常とされてきたのですが、腎臓にはかなりの負担がかかっているのです。
その関係から猫は腎臓病になりやすいと考えられてきました。いくら水を飲んでも腎臓で吸収されず排出されてしまうため、腎臓病になると水を飲む量が増えるというわけです。
尿毒症
腎臓機能が低下すると血中に排泄できない老廃物が蓄積し尿毒症になってしまいます。猫は食欲が低下し、食べられても気持ちの悪さから嘔吐が増え体重が減少し始めます。
さらに排泄できない毒性物質が血中に含まれたまま他の臓器をめぐって害を与え続け、脱水や体温低下を引き起こします。
脳にまでまわってしまうと、痙攣(けいれん)などの神経症状が現れてくるのです。腎臓が全く機能しなくなる腎不全になると末期症状で死を覚悟しなければなりません。
猫に苦しい思いをさせるだけでなく、飼い主も弱っていく愛猫を側で見ているのは大変辛いものです。
言葉を話せない猫だからこそ、普段からちょっとしたことでも見逃さないように観察し、早期発見・早期治療を行えるようにしてあげなければなりませんね。
貧血
貧血も腎臓病になると見られる症状の1つです。貧血とは赤血球の中にあるヘモグロビン濃度が薄まると起こります。
赤血球をつくるホルモンが減少すると、体の隅々にまで酸素を行き渡らせる働きができなくなり、臓器に異常が出てしまうのです。
貧血になると猫は元気がなくなり食欲も低下します。呼吸や脈も速くなって疲れやすくなり、動けなくなってしまうのです。口の中を見ると歯茎や舌が白っぽいなどの症状も見られるようになります。
またシニア猫は特に気をつけなければなりませんが、貧血になると骨も弱くなってしまうのです。さらに進行すれば輸血を必要とするほどまでになるため、貧血くらいと甘くみないようにしなければなりません。
高血圧
腎臓病により腎臓の機能が低下してしまうと、血圧の調整にも支障が出始めてきます。健康な腎臓なら体に不必要な老廃物は体外へ排出させる働きをしますが、腎臓病になると、その働きが出来なくなってしまいます。
そのため血圧を上げて腎臓に血液をどんどんと流れさせ、老廃物を排出させようとするのです。血圧が上がるだけでなく、腎臓にはさらなる負担がかかる事になり寿命を縮めてしまうことになります。
ただでさえ猫は水をあまり飲まず、健康であっても腎臓に負担をかけてしまう動物です。普段からのライフスタイルや、フードなどでも、腎臓病を予防できることにつなげてあげなければなりませんね。
猫の腎臓病の予防方法
 猫が腎臓病にならないようにするには、飼ったその日から気を付けていけることが沢山あります。可愛いからといって、いくら欲しがっても人間の食べ物は猫に与えないようにします。
人間の食べ物にはかなりの塩分が入っていますよね。人間にとって少量でも猫にとっては大敵です。必ずキャットフードを与えるようにしてください。
なるべくなら低タンパク・低リンのフードがおすすめです。
次に水はいつでも飲みたい時に飲めるよう、新鮮な水を用意してあげておくと安心です。飲んだ水の量と尿の色や量、ニオイのチェックも健康状態を把握するのに役立ちます。
普段から定期的に検診に連れていくことも大切です。もし少しでも様子がおかしい、上記でご説明したような症状があれば、すぐに動物病院で診てもらうようにしてくださいね。
猫が腎臓病にならないようにするには、飼ったその日から気を付けていけることが沢山あります。可愛いからといって、いくら欲しがっても人間の食べ物は猫に与えないようにします。
人間の食べ物にはかなりの塩分が入っていますよね。人間にとって少量でも猫にとっては大敵です。必ずキャットフードを与えるようにしてください。
なるべくなら低タンパク・低リンのフードがおすすめです。
次に水はいつでも飲みたい時に飲めるよう、新鮮な水を用意してあげておくと安心です。飲んだ水の量と尿の色や量、ニオイのチェックも健康状態を把握するのに役立ちます。
普段から定期的に検診に連れていくことも大切です。もし少しでも様子がおかしい、上記でご説明したような症状があれば、すぐに動物病院で診てもらうようにしてくださいね。
猫の腎臓病の治療薬は?
 猫の慢性腎臓病に使われている治療薬は2種類あります。1つはセミントラ、もう1つはラプロスです。
腎臓病にはステージ4まであり、どちらの治療薬もステージ2~3の腎臓病の猫が対象になります。
セミントラは液剤の治療薬で、無味無臭のため薬を飲ませるは簡単です。普段のフードに混ぜて与えれば猫も警戒することなく食べてくれます。動物病院で処方してもらうと、およそ5,000~6,000円ほどの価格です。通販でも手に入る治療薬で平均3,600円前後で販売されています。
ラプロスは2,017年に承認された比較的新しい治療薬です。本当は猫用ではなく、人間の血流改善のためにつくられた薬でしたが、これが猫の腎臓病にも効果ありとされ2,017年の4月より発売されることとなりました。こちらは錠剤のため、薬を嫌がる猫には飲ませにくいかもしれませんね。朝晩1錠ずつで、1ヶ月約1万円ほどかかります。
病状によっては2つの治療薬を併用する方がよい場合もあるので、病院できちんと処方してもらうのが良いでしょう。
猫の慢性腎臓病に使われている治療薬は2種類あります。1つはセミントラ、もう1つはラプロスです。
腎臓病にはステージ4まであり、どちらの治療薬もステージ2~3の腎臓病の猫が対象になります。
セミントラは液剤の治療薬で、無味無臭のため薬を飲ませるは簡単です。普段のフードに混ぜて与えれば猫も警戒することなく食べてくれます。動物病院で処方してもらうと、およそ5,000~6,000円ほどの価格です。通販でも手に入る治療薬で平均3,600円前後で販売されています。
ラプロスは2,017年に承認された比較的新しい治療薬です。本当は猫用ではなく、人間の血流改善のためにつくられた薬でしたが、これが猫の腎臓病にも効果ありとされ2,017年の4月より発売されることとなりました。こちらは錠剤のため、薬を嫌がる猫には飲ませにくいかもしれませんね。朝晩1錠ずつで、1ヶ月約1万円ほどかかります。
病状によっては2つの治療薬を併用する方がよい場合もあるので、病院できちんと処方してもらうのが良いでしょう。
まとめ
 猫にとって腎臓病はついてまわる病気です。
しかし日頃から猫の様子をチェックし、腎臓に負担をかけないフードを与えるなど配慮してあげると予防をすることもできます。
猫は大切な家族の一員です、私たち飼い主も猫の体のことを出来るだけ知り、健康で長生きしてもらえるように気を配らなければなりません。それでも万が一病気になってしまったら、現状を維持し進行を遅らせることができるよう治療薬を使うなど方法を考えていくべきでしょう。
猫にとって腎臓病はついてまわる病気です。
しかし日頃から猫の様子をチェックし、腎臓に負担をかけないフードを与えるなど配慮してあげると予防をすることもできます。
猫は大切な家族の一員です、私たち飼い主も猫の体のことを出来るだけ知り、健康で長生きしてもらえるように気を配らなければなりません。それでも万が一病気になってしまったら、現状を維持し進行を遅らせることができるよう治療薬を使うなど方法を考えていくべきでしょう。
猫の爪は伸ばしっぱなしは危ない!
 犬の散歩は日常的に行っているかと思いますが、猫の場合は散歩という習慣はないですよね。
犬のように外で一緒に歩きながら散歩をさせていると、地面で擦れますので爪は適度な長さに保たれますが、猫の場合は100%飼い主さんが爪のケアをしてあげる必要があります。
そこで、今回は猫の爪は何故伸ばしっぱなしだと危ないのかをまずご紹介してきましょう。
犬の散歩は日常的に行っているかと思いますが、猫の場合は散歩という習慣はないですよね。
犬のように外で一緒に歩きながら散歩をさせていると、地面で擦れますので爪は適度な長さに保たれますが、猫の場合は100%飼い主さんが爪のケアをしてあげる必要があります。
そこで、今回は猫の爪は何故伸ばしっぱなしだと危ないのかをまずご紹介してきましょう。
猫は爪を伸ばすとどうなる?
猫の爪を伸ばしたままにしておくと、家具を傷つけるだけではなく、猫自身にもさまざまなトラブルが発生してしまいます。
よくあるケースをご紹介しておきましょう。
・巻き爪になり肉球に食い込んでしまう
・爪が折れたり、割れたりする
・爪に何か引っかかってけがをする
・骨格が変形してしまう
などのリスクが伴ってきます。
今は、爪とぎ用のアイテムなども販売しており、それらのアイテムを活用するのもいいのですが、高齢になってくると爪とぎの頻度も少なくなってきますので、伸びすぎないようにしっかり飼い主さんがケアをしてあげるようにして下さい。
猫の伸びた爪に引っかかれると感染症に?
また、爪が伸びてしまうと飼い主さんにも「猫ひっかき病」や「パスツレラ症」にかかってしまうリスクも出てきてしまいます。
猫ひっかき症もパスツレラ症も感染症ですが、猫ひっかき病は、猫にひっかかれたところから菌が侵入し、赤く腫れあがってしまうもので、ひどい場合は、発熱や倦怠感・関節痛・吐き気などの原因になります。
パスツレラ症は犬や猫が日常に保菌している事が多く、引っ掻かかれて感染した部位の熱や腫れ、あるいは化膿などの変化が見られます。
また肺炎や気管支炎といった呼吸器系に関わる疾患を引き起こす事もあり、また髄膜炎を発症する事もあります。
そして、鼻や喉の違和感をはじめ、持病の重症化に繋がるケースもあり場合によっては死に至ってしまう事もある怖い病気です。
猫の爪の構造を知ろう
 猫の場合は、飼い主さんが100%爪のケアをしてあげないといけませんので、まずは猫の爪の構造を知っておく事が大切です。
爪の根本にあるピンク色の部分には、血管と神経が通っており、誤って切ってしまうと痛みと共に出血も伴ってしまいますので注意が必要です。
定期的なケアが必要な理由は長期間爪を伸ばしたままにしておくと、血管と神経も一緒に伸びてくる事になり、短くするためには血管と神経も一緒に切ってしまわないといけなくなってしまうためです。
そうなると猫に対しとても苦痛を強いる事になってしまい可哀想ですよね。
自分で切るのが難しいと感じる場合は、動物病院やサロンでも切ってくれますのでお願いしましょう。
猫の場合は、飼い主さんが100%爪のケアをしてあげないといけませんので、まずは猫の爪の構造を知っておく事が大切です。
爪の根本にあるピンク色の部分には、血管と神経が通っており、誤って切ってしまうと痛みと共に出血も伴ってしまいますので注意が必要です。
定期的なケアが必要な理由は長期間爪を伸ばしたままにしておくと、血管と神経も一緒に伸びてくる事になり、短くするためには血管と神経も一緒に切ってしまわないといけなくなってしまうためです。
そうなると猫に対しとても苦痛を強いる事になってしまい可哀想ですよね。
自分で切るのが難しいと感じる場合は、動物病院やサロンでも切ってくれますのでお願いしましょう。
猫の爪切りの頻度やタイミングは?
 猫の爪切りの頻度は1か月に1度切るようにすれば十分でしょう。
爪切りを嫌がる猫は結構多いのですが、そのような場合は、一度に全ての爪を切ってしまうのではなく、日にちをあけて少しずつ切っていくようにして下さい。
爪切りのタイミングは、猫が食事や水飲み・熟睡など何かをしている前後は避けるようにしなければ、猫自身がその行動と爪切りを結びつけてしまいますのでその行動をしなくなってしまう可能性が出てきます。
良いタイミングと言えば、猫が部屋の中をウロウロしていたりぼーっと何かを見つめている時に、何気なしに自然に抱き上げて手早く行うのが理想的です。
ここでも、注意してもらいたいのが爪切りを察知し逃げ出そうとしている猫を無理やり抱っこして強制的に行うのはやめましょう。
自分でできない場合は、先ほどもご紹介しましたが、動物病院やサロンで行ってもらうようにして下さいね。
猫の爪切りの頻度は1か月に1度切るようにすれば十分でしょう。
爪切りを嫌がる猫は結構多いのですが、そのような場合は、一度に全ての爪を切ってしまうのではなく、日にちをあけて少しずつ切っていくようにして下さい。
爪切りのタイミングは、猫が食事や水飲み・熟睡など何かをしている前後は避けるようにしなければ、猫自身がその行動と爪切りを結びつけてしまいますのでその行動をしなくなってしまう可能性が出てきます。
良いタイミングと言えば、猫が部屋の中をウロウロしていたりぼーっと何かを見つめている時に、何気なしに自然に抱き上げて手早く行うのが理想的です。
ここでも、注意してもらいたいのが爪切りを察知し逃げ出そうとしている猫を無理やり抱っこして強制的に行うのはやめましょう。
自分でできない場合は、先ほどもご紹介しましたが、動物病院やサロンで行ってもらうようにして下さいね。
猫の爪切り手順は?動画も紹介!
 猫の爪切りはハードルが高いイメージですが、次にご紹介する4つのステップを踏めばスムーズに爪切りを行う事ができるでしょう。
1:体全体をバスタオルで包む
爪を切る時は。愛猫を後ろから抱っこし、爪切りを持つ手と反対の手で愛猫の手を持ちます。
体全体をバスタオルでくるむと、落ち着いてくれるので大人しくなる場合もあります。
2:肉球を押す
指で肉球を押して、爪を出します。
そうすると爪がよく見えて切りやすくなるでしょう。
3:血管と神経から2ミリを意識する
先ほどもご紹介しましたが、爪の根本のピンク色の部分には血管と神経が通っており、切ると痛みや出血を伴く事になってしまいますので、ピンクの部分から1~2ミリほど残して切るように意識しましょう。
4:しっかり褒める
爪が綺麗に切り終わったら、沢山褒めてあげて下さい。
褒めてもらえると愛猫も嬉しいので、次から爪切りがやりやすくなるかもしれません。
爪切り手順の動画も上げておきますので、是非ご覧になって下さいね。
猫の爪切りはハードルが高いイメージですが、次にご紹介する4つのステップを踏めばスムーズに爪切りを行う事ができるでしょう。
1:体全体をバスタオルで包む
爪を切る時は。愛猫を後ろから抱っこし、爪切りを持つ手と反対の手で愛猫の手を持ちます。
体全体をバスタオルでくるむと、落ち着いてくれるので大人しくなる場合もあります。
2:肉球を押す
指で肉球を押して、爪を出します。
そうすると爪がよく見えて切りやすくなるでしょう。
3:血管と神経から2ミリを意識する
先ほどもご紹介しましたが、爪の根本のピンク色の部分には血管と神経が通っており、切ると痛みや出血を伴く事になってしまいますので、ピンクの部分から1~2ミリほど残して切るように意識しましょう。
4:しっかり褒める
爪が綺麗に切り終わったら、沢山褒めてあげて下さい。
褒めてもらえると愛猫も嬉しいので、次から爪切りがやりやすくなるかもしれません。
爪切り手順の動画も上げておきますので、是非ご覧になって下さいね。
猫の爪切りグッズ紹介
 では、最後に愛猫の爪を切る際に便利なグッズをご紹介したいと思います。
今は様々な爪切りグッズを販売していますので、その中でも人気があるものを2つピックアップしていきますね。
では、最後に愛猫の爪を切る際に便利なグッズをご紹介したいと思います。
今は様々な爪切りグッズを販売していますので、その中でも人気があるものを2つピックアップしていきますね。
グッズ①
最初は、デルビコのギロチンタイプ爪切りです。
・ハサミタイプでは愛猫がすごく嫌がる
・毎回トリミングに行くのが面倒
・家で簡単に爪のケアをしたい
という方におすすめです。
ギロチンタイプは振動が少なく、深爪しにくいタイプになっていますので、サロンや病院でもギロチンタイプを使用している所が多いです。
あまり大きなものだと女性の場合は、握りいかと思いますがこの爪切りは女性でも握りやすいハンドル設計になっています。
初めての方がいきなり爪切りをするのはコツをつかめていないので、難しいかと思います。
まずは竹串などを使って練習してから実践するようにして下さい。
値段は798円で超リーズナブルなので購入しやすいのではないでしょうか。
商品のURLを上げておきますね。
https://item.rakuten.co.jp/kom-kom/r1409191500a/
グッズ②
2つ目は、電動の爪切りです。
低騒音・低振動で怖がりな猫にも使用できるでしょう。
ハサミで爪切りをしていると、とっさに動いた際にケガをさせてしまったりする事が多いのですが、電動であればケガをする事がないので安全に爪切りができます。
この電動爪切りは3種類のやすりサイズが選べますので、体の大きさによって調整はできますし、スピード調整も2段階式になっており、爪の太さなどでスピードを変更する事ができます。
値段は2,180円とリーズナブルになっており、簡単に爪切りができる事から人気のアイテムとして急上昇です。
この商品のURLは以下になります。
https://item.rakuten.co.jp/difang/difang-03/?iasid=07rpp_10095___ek-k9y382qq-2n-92672317-5e0e-4a46-ac6b-0a8cb8da34ce
まとめ
 今回は猫の爪切りについてご紹介してきました。
猫は犬と違って動きが素早く、爪切りを察知するとすごく抵抗する子もいます。
そうなってしまった際に、爪を伸ばし過ぎていると愛猫もそうですが、飼い主さんもケガをしてしまう可能性がありますので、小さい頃から爪切りに慣らしておくの事が一番大切でしょう。
しかし、何回行っても慣れない子もいますので、そうなった場合は、スムーズの爪切りが行える手順を参考に頑張ってみて下さいね。
それでもダメな場合は、面倒かもしれませんが病院やサロンで切ってもらうようにしましょう。
今回は猫の爪切りについてご紹介してきました。
猫は犬と違って動きが素早く、爪切りを察知するとすごく抵抗する子もいます。
そうなってしまった際に、爪を伸ばし過ぎていると愛猫もそうですが、飼い主さんもケガをしてしまう可能性がありますので、小さい頃から爪切りに慣らしておくの事が一番大切でしょう。
しかし、何回行っても慣れない子もいますので、そうなった場合は、スムーズの爪切りが行える手順を参考に頑張ってみて下さいね。
それでもダメな場合は、面倒かもしれませんが病院やサロンで切ってもらうようにしましょう。
犬にカレーは食べさせてはダメ!
 何かの拍子にふと食べたくなるカレー。
スパイスの香りが食欲をそそります。
すると、飼い主さんが夢中で食べているかたわらに、鼻をクンクンさせて目を輝かせた愛犬が!
このおいしさをシェアしたい、してもいいのかな?と迷ってしまうかもしれません。
でもちょっと待って。そのカレー、犬には絶対に食べさせてはダメです。
犬用のカレーが売っているのだから問題ないのでは?と思う方もいるでしょうが、人間用と犬用には決定的な材料の違いがあります。
人間用のカレーの中には、犬にとって命の危険を伴う食材が使われているのです。
人間も犬も同じ哺乳類ですが、人間には問題が起きなくても、犬には致命的な食材がたくさん存在します。
カレーの中に含まれる犬にとっての毒素とは何なのでしょうか。
注意したい食材について見ていきましょう。
何かの拍子にふと食べたくなるカレー。
スパイスの香りが食欲をそそります。
すると、飼い主さんが夢中で食べているかたわらに、鼻をクンクンさせて目を輝かせた愛犬が!
このおいしさをシェアしたい、してもいいのかな?と迷ってしまうかもしれません。
でもちょっと待って。そのカレー、犬には絶対に食べさせてはダメです。
犬用のカレーが売っているのだから問題ないのでは?と思う方もいるでしょうが、人間用と犬用には決定的な材料の違いがあります。
人間用のカレーの中には、犬にとって命の危険を伴う食材が使われているのです。
人間も犬も同じ哺乳類ですが、人間には問題が起きなくても、犬には致命的な食材がたくさん存在します。
カレーの中に含まれる犬にとっての毒素とは何なのでしょうか。
注意したい食材について見ていきましょう。
犬はカレーの具材である玉ねぎが危険?
カレーには色々な種類があります。
インドカレー、ネパールカレー、キーマカレー、そして、家庭で作る日本のカレー。
使われる食材やスパイスにも少しずつ違いがあります。
POINT
その中で、犬にとって最も危険な野菜は、玉ねぎです。
日本の家庭のカレーのように、あからさまに玉ねぎの存在がわかるものもあれば、玉ねぎをじっくり炒めてペースト状にした「あめ色玉ねぎ」を隠し味のように練り込んだものなどがあります。
つまり、一見してわからなくても、原材料に玉ねぎが使用されているものはとても多いのです。
そして、玉ねぎに含まれる「アリルプロピルジスルファイド」という成分が、犬の赤血球に作用し、溶血を起こします。
「溶血」とは、文字通り血が溶けてしまうこと。
赤血球が破壊され、おしっことして流れ出てしまうことがあるのです。
犬の体の大きさや摂り込んでしまった玉ねぎの量によって表れる症状は異なりますが、危険な量が何グラムかということを知るよりも、「絶対に与えない」ということの方が大切です。
犬の反応には個体差があります。一般論で推し量らずに、「与えない」ということを徹底しましょう。
犬がカレーを食べた時の症状
 犬が人間用のカレーを食べると、どのような症状が出るのでしょうか。
玉ねぎ中毒以外にも、注意が必要な症状がいくつかあります。
当てはまる症状が出た時は、早めに獣医さんに相談するか、動物病院に連れて行くことをおすすめします。
その際、いつどこで、どのような状況でどのくらい食べたかということを初め、どのような症状が出てどのくらい続いているかなども獣医さんに伝えられるようにしておくと、スムーズに治療に入ることができるでしょう。
犬が人間用のカレーを食べると、どのような症状が出るのでしょうか。
玉ねぎ中毒以外にも、注意が必要な症状がいくつかあります。
当てはまる症状が出た時は、早めに獣医さんに相談するか、動物病院に連れて行くことをおすすめします。
その際、いつどこで、どのような状況でどのくらい食べたかということを初め、どのような症状が出てどのくらい続いているかなども獣医さんに伝えられるようにしておくと、スムーズに治療に入ることができるでしょう。
症状①玉ねぎ中毒
先ほどお話しした玉ねぎ中毒は、最も危険な症状です。
玉ねぎに含まれる「アリルプロピルジスルファイド」が犬の体に入り込むと、赤血球を破壊します。
これは生の状態だけでなく、カレーの具のように加熱していても同じなので注意してください。
赤血球が破壊されることで、貧血や血尿、そして便の色にも変化が見られることがあります。
また、解毒作用のある肝臓にも負担がかかることから、肝機能の低下にも注意が必要です。
悪化すると痙攣を起こすこともあります。
痙攣すると誤って舌を噛み切ってしまう危険性もありますので、口の中に窒息しない程度にタオルを詰め込んで応急処置をしましょう。
症状②消化不良や胃腸障害
カレーに含まれる香辛料が作用して、胃腸障害や消化不良が起こることもあります。
この場合、嘔吐や下痢といった症状が表れます。
犬用のカレーには、犬が摂取して問題のない香辛料のみが使われていて、その量もほんのわずかです。
しかし、人間用のカレーには、人間の味覚に合わせて大量の香辛料がブレンドされています。
人間が食べても体がポカポカしてくるのですから、犬に刺激が強すぎるのも想像できるのではないでしょうか。
玉ねぎに加えて香辛料の刺激までもが犬の胃腸を攻撃し、体は強い拒絶反応を起こします。
脱水症状になりかねませんので、注意してください。
症状③塩分過多
犬は塩分を過剰に摂取すると、命の危険があります。
人間の食べ物を犬に与えてはいけない理由の一つに、塩分があるのです。
人間は味覚がマヒしていることもあり、塩分がないとうまみを感じない動物です。
そのため、カレーにも「美味しい」と感じるだけの塩分が含まれています。
この塩分は犬が一日に摂取する塩分量をはるかに上回る量です。
もしも犬が人間用のカレーを食べれば、慢性的な塩分過多になります。
その証拠に、犬用のカレーを食べてみてください。ほとんど塩気を感じず、見た目や匂いから想像するようなおいしさは全く感じないはずです。
犬には、人間がおいしいと感じるだけの塩分は全く必要ないのです。
犬が玉ねぎ中毒になった時の発症期間
 玉ねぎ中毒は、主に血液に影響をもたらします。
食べたものはいったん胃で消化され、腸へと送られる中で血管に吸収されます。
その時点で赤血球の破壊が始まることになるため、症状が出るまでに早くて1日、通常は3~4日かかるようです。
翌日ならともかく、数日経ってしまうと、何が原因なのかわからなくなってしまいそうですが、血尿などが起こったらカレーが原因であると考えられるでしょう。
その前に下痢や嘔吐などの症状が出る可能性が高いので、異変に気付いた時点で動物病院に相談して対策を施しましょう。
玉ねぎ中毒は、主に血液に影響をもたらします。
食べたものはいったん胃で消化され、腸へと送られる中で血管に吸収されます。
その時点で赤血球の破壊が始まることになるため、症状が出るまでに早くて1日、通常は3~4日かかるようです。
翌日ならともかく、数日経ってしまうと、何が原因なのかわからなくなってしまいそうですが、血尿などが起こったらカレーが原因であると考えられるでしょう。
その前に下痢や嘔吐などの症状が出る可能性が高いので、異変に気付いた時点で動物病院に相談して対策を施しましょう。
犬がカレーを食べた時の状況確認や対処法
 もしも犬がカレーを食べてしまったら、まずは様子を見るしかありません。
せめて、少しでもカレーが薄まるように水分を摂らせてみることくらいしか対策はないでしょう。
その後、嘔吐や下痢の症状が表れたら、脱水にご注意ください。
背中の皮を引っ張って、すぐに元に戻るようであれば大丈夫ですが、なかなか元に戻らないようなら脱水が起きて危険な状態です。
しかし嘔吐の最中に水を飲ませると、さらに嘔吐を誘発します。犬が自発的に飲もうとするのを止めるのはかわいそうですが、少なくとも落ち着くまでは、飼い主さんが無理矢理水を飲ませることは控えましょう。
嘔吐が治まって30分ほど経ってから水を与える方が安心です。
下痢の場合も、水が腸に刺激を与える可能性があるため、同様の注意が必要です。
もしも犬がカレーを食べてしまったら、まずは様子を見るしかありません。
せめて、少しでもカレーが薄まるように水分を摂らせてみることくらいしか対策はないでしょう。
その後、嘔吐や下痢の症状が表れたら、脱水にご注意ください。
背中の皮を引っ張って、すぐに元に戻るようであれば大丈夫ですが、なかなか元に戻らないようなら脱水が起きて危険な状態です。
しかし嘔吐の最中に水を飲ませると、さらに嘔吐を誘発します。犬が自発的に飲もうとするのを止めるのはかわいそうですが、少なくとも落ち着くまでは、飼い主さんが無理矢理水を飲ませることは控えましょう。
嘔吐が治まって30分ほど経ってから水を与える方が安心です。
下痢の場合も、水が腸に刺激を与える可能性があるため、同様の注意が必要です。
POINT
嘔吐も下痢も、落ち着いたところでふやかしフードやウェットフードを少量ずつ与えれば、栄養と水分が両方摂取できます。
しかしどちらも口にできないほど症状が重い場合は、すぐに獣医さんに相談しましょう。
犬が食べたら危ないカレー以外の料理はある?
 カレーだけでなく、犬が食べては危険な料理はたくさんあります。
人間用に調理されたものは全て危険だと言っても過言ではありません。
すき焼き、ポトフ、シチュー、酢豚、かき揚げなどのように、明かに玉ねぎの存在がわかる料理はもちろん、ハンバーグ、チキンライスが入ったオムライスなど、材料として細かく刻んだ玉ねぎが入っている料理など、思わぬところに玉ねぎやそのエキスが含まれているのです。
また、全くネギ類を使用しないお好み焼きやロールキャベツだったとしても、食べる時に使用するソースやケチャップに玉ねぎが入っています。
仮に、調味料は醤油しか使わないとしても、今度は塩分量が問題になります。 もしも犬がそれらの料理を食べて問題がなかったとしても、犬はその時に人間の料理のおいしさを学びます。 するとドッグフードが物足りなくなり、食べなくなる犬もいます。
人間としては、犬が喜ぶ姿を見たいがために気まぐれで与えた料理の一口かもしれませんが、犬にとってはその後の生活を変えてしまう大きな事件になりかねません。
人間の味を教えることは極力避けるようにしましょう。
カレーだけでなく、犬が食べては危険な料理はたくさんあります。
人間用に調理されたものは全て危険だと言っても過言ではありません。
すき焼き、ポトフ、シチュー、酢豚、かき揚げなどのように、明かに玉ねぎの存在がわかる料理はもちろん、ハンバーグ、チキンライスが入ったオムライスなど、材料として細かく刻んだ玉ねぎが入っている料理など、思わぬところに玉ねぎやそのエキスが含まれているのです。
また、全くネギ類を使用しないお好み焼きやロールキャベツだったとしても、食べる時に使用するソースやケチャップに玉ねぎが入っています。
仮に、調味料は醤油しか使わないとしても、今度は塩分量が問題になります。 もしも犬がそれらの料理を食べて問題がなかったとしても、犬はその時に人間の料理のおいしさを学びます。 するとドッグフードが物足りなくなり、食べなくなる犬もいます。
人間としては、犬が喜ぶ姿を見たいがために気まぐれで与えた料理の一口かもしれませんが、犬にとってはその後の生活を変えてしまう大きな事件になりかねません。
人間の味を教えることは極力避けるようにしましょう。
まとめ
 家族全員が食卓を囲む時、一緒にいる犬だけが何も食べられないなんてかわいそう、と感じる飼い主さんも多いと思います。
しかし、「ほんの一口」が、犬の命を脅かし、苦しめる結果になったら悔やんでも悔やみきれませんよね。
どうしても犬に同じ料理を、と考えるなら、材料を切った段階で食べても問題のない食材だけを少し取り分け、油や味付けをせずに火を通して小皿に準備しておくなど、工夫して与えるようにすると良いでしょう。
その時は味付けもせず、素材のままで与えてあげてくださいね。
犬が飼い主さんの皿から分けてほしいとせがむようであれば、犬用に準備した小皿を飼い主さんの手元に置き、そこから犬に与えるのも良い方法です。
犬は「パパ(ママ)と同じものを食べた!」と、きっと満足してくれるでしょう。
家族全員が食卓を囲む時、一緒にいる犬だけが何も食べられないなんてかわいそう、と感じる飼い主さんも多いと思います。
しかし、「ほんの一口」が、犬の命を脅かし、苦しめる結果になったら悔やんでも悔やみきれませんよね。
どうしても犬に同じ料理を、と考えるなら、材料を切った段階で食べても問題のない食材だけを少し取り分け、油や味付けをせずに火を通して小皿に準備しておくなど、工夫して与えるようにすると良いでしょう。
その時は味付けもせず、素材のままで与えてあげてくださいね。
犬が飼い主さんの皿から分けてほしいとせがむようであれば、犬用に準備した小皿を飼い主さんの手元に置き、そこから犬に与えるのも良い方法です。
犬は「パパ(ママ)と同じものを食べた!」と、きっと満足してくれるでしょう。
犬がうるさい理由とは?
 犬の散歩をしていると、通りすがりの家の中から犬の声が聞こえてくることがあります。
すれ違う犬同士が吠え合ったり、救急車の音とともに遠吠えが聞こえてきたりすることもあります。
人間が言葉で意思を伝えるのと同様に、犬は吠えることで自分の気持ちを伝えようとしているのですが、時にその声が「うるさい」と思われてしまうことがあります。
犬が激しく吠える時、何を伝えよう、訴えようとしているのでしょうか。
犬の気持ちを探ってみましょう。
犬の散歩をしていると、通りすがりの家の中から犬の声が聞こえてくることがあります。
すれ違う犬同士が吠え合ったり、救急車の音とともに遠吠えが聞こえてきたりすることもあります。
人間が言葉で意思を伝えるのと同様に、犬は吠えることで自分の気持ちを伝えようとしているのですが、時にその声が「うるさい」と思われてしまうことがあります。
犬が激しく吠える時、何を伝えよう、訴えようとしているのでしょうか。
犬の気持ちを探ってみましょう。
警戒心
たとえば、来客を知らせるチャイムの音や、集合住宅などで近隣の部屋から聞こえる物音などに反応して、激しく連続して吠える犬がいます。
また、外を他の犬が通っただけで反応して吠える犬もいます。
安全な住処に侵入者がいる、追い払わなくては!と感じたり、飼い主さんに「侵入者だ!気をつけて!」と訴えているのかもしれません。
番犬気質の犬の場合、警戒心が強く、家族以外の誰かが自分の住処に訪れることに敏感になりやすい傾向があります。
家や飼い主さんを守ろうとする気持ちの表れでもあるのでしょう。
その性格自体は悪くないのですが、あまりに激しく長く吠える犬の場合、近所から「うるさい」と思われていまうこともあります。
また、頻繁に吠えることで、飼い主さんや家族までもがうるさいを感じてしまうことがあるかもしれません。
要求を伝えたい
飼い主さんに対して激しく吠える時は、かまってほしい、お腹が空いた、散歩に行きたいなど、自分の要求を訴えていることがあります。
散歩中であれば、飼い主さんが誰かと立ち話をしていて犬が退屈してしまうと、「もう行こうよ!」と吠えることもあります。
これは、「吠えたら(飼い主さんが)自分の思い通りに動いてくれた」という経験から起こることも多いようです。
また、散歩やご飯の時間が決まっている家庭では、その時間になると犬が吠えて催促するということもあります。
自分の要求を、吠えるという行為で叶えてきた犬は、激しく吠えることで飼い主さんに意思を伝えようとすることが多くなります。
興奮している
飼い主さんと引っ張りっこや持って来いなどで激しく遊んでいる時や、新しいおもちゃを与えられた時、そして人間が大好きな犬であれば、来客があった時など、犬は楽しくて嬉しくて、つい大きな声で吠えてしまうことがあります。
気分が上がってしまい、興奮状態になっているのです。
あまりエスカレートさせると、吠えるだけでは気持ちがおさまらず、噛んでしまうこともあります。
特に犬に慣れていない来客の場合は注意しましょう。
興奮した時の噛む力は、感情の抑えがきかないので強くなりがちです。
小型犬であっても痛みを感じるので、中型犬、大型犬になると、来客は痛みとともに恐怖を感じることにもあります。
近所の犬がうるさい場合の苦情はどこにする?
 自分の家に犬がいる家庭でも、近所の犬の吠える声が連続して聞こえると耳障りに感じることがあります。
赤ちゃんがいる家庭や、体調がすぐれない時などは、毎日その声を聞かされるのは苦痛ですよね。
犬が吠え続けることで、生活や精神状態が影響を受ける場合、どうにかしなければなりません。
そんな時、どんな対処方法があるのでしょうか。
いくつかの選択肢を見てみましょう。
自分の家に犬がいる家庭でも、近所の犬の吠える声が連続して聞こえると耳障りに感じることがあります。
赤ちゃんがいる家庭や、体調がすぐれない時などは、毎日その声を聞かされるのは苦痛ですよね。
犬が吠え続けることで、生活や精神状態が影響を受ける場合、どうにかしなければなりません。
そんな時、どんな対処方法があるのでしょうか。
いくつかの選択肢を見てみましょう。
直接伝えたりマンションの大家を通す
一番簡単なのは、吠える犬の飼い主さん本人に直接伝えて理解していただくことです。
でも地域になじみが薄ければ、ほとんどのご近所さんは挨拶すらしたことがないかもしれません。
そんな場合、集合住宅であれば、マンションの大家さんや理事長さん、または管理人さんや管理会社の方を通して伝えることも有効な手段です。
中立的な第三者に間に入ってもらうことで、穏やかに解決できることもあります。
一方、戸建ての家であれば、町内会の会長さんや、近所で顔の広そうな方に相談してみるのも一つの方法です。
直接伝えることに抵抗がある時は、こうして周りの協力者を頼ることを考えてみましょう。
警察に通報
直接飼い主本人に伝えることや、第三者に協力を仰ぐことが難しい場合は、警察に通報するという方法もあります。
ただし110番通報ではありません。
警察署のホームページ(http://www.police-map.com/)で、通報したい犬の飼い主が住む場所の所轄警察署を調べ、そちらに直接出向くか、電話で伝える必要があります。
その際、以下のことがスムーズに伝えられるように準備しておきましょう。
POINT
・犬の飼い主の住所と氏名
・犬の吠える声の大きさや頻度
・自分がどのような被害(不眠などの健康被害)を受けているか
・自分ではどのような対策をしてきたか、など
また、この時、自分の住所と氏名も聞かれます。
犬の飼い主さんには匿名で注意してもらうことができますので、きちんと対応してもらうためにも、自身の情報も伝えるようにしましょう。
しかし、注意はできても警察には強制権がありません。
犬の飼い主の対応によって100%解決にならない場合もあるので、そのことは認識しておきましょう。
保健所を通す
警察署と同様に、犬の飼い主が住んでいる住所を管轄する保健所に連絡することもできます。
管轄の保健所は、厚生省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/)で確認することができます。
この場合も、直接管轄の保健所へ出向くか電話連絡で伝えることが可能です。
また、伝えるべき内容も警察署と同じになります。
犬の飼い主に苦情を伝える担当者が、警察官になるか保健所の人になるかの違いだけで、警察も保健所も対応は同じになります。
従って、やはりこちらにも強制力はなく、犬の飼い主の自主性に任せることになりますので、解決できることを100%保証してくれる方法とはならないことを理解しておきましょう。
自身に苦情がきた場合の対策
 犬の吠える声が激しく、自分自身が苦情を受けてしまうこともあるかもしれません。
「近所の人みんなが迷惑している」なんて言われたら、ドキッとしてしまいますよね。
そんな時、大切な愛犬が悪者にならずに済むには、どんなことができるでしょうか。
苦情はきていなくても気になっている飼い主さんも、ぜひ実践してみてください。
犬の吠える声が激しく、自分自身が苦情を受けてしまうこともあるかもしれません。
「近所の人みんなが迷惑している」なんて言われたら、ドキッとしてしまいますよね。
そんな時、大切な愛犬が悪者にならずに済むには、どんなことができるでしょうか。
苦情はきていなくても気になっている飼い主さんも、ぜひ実践してみてください。
ペットのしつけを行なう
セミナーや動物病院で開催している「しつけ教室」を利用したり、専門のトレーナーさんに基本的なしつけをお願いするのも良い方法ですが、もっと簡単にしつけ方法を学ぶこともできます。
しつけのDVDや書籍の利用です。
しつけに特化した内容であるため、飼い主さんの悩みに合わせて専門的な立場の方がアドバイスや実際のやり方をレクチャーしてくれています。
時間やお金に制約があって、しつけ教室やドッグトレーナーを利用する余裕がない場合は、こうしたDVDや書籍で勉強してみましょう。
吠えることをやめさせることは、近所迷惑の解決だけでなく、吠える犬の心の声を理解し、飼い主さんと愛犬とがより良い関係を築くきっかけにもなるはずです。
罰を与えることで、吠えることをやめさせることはできません。
しっかりとした本当の知識を学びましょう。
防音対策をする
先にお話しした「しつけ」は、一朝一夕でできるものではありません。
しつけができるようになるまでの間、犬の声を外に漏らさない工夫をしましょう。
たとえば、防音カーテンを利用すれば、外に漏れる音を1/5~1/8に減らすことができます。
併せて防音シートを窓に貼ると、より効果は高まるでしょう。
また、暑い時期は窓を開けたくなりますが、できるだけエアコンを使用して窓を開けないようにすることも大切です。
もしも屋外で犬を飼育しているなら、しつけができるまで音を遮ることは難しくなります。
できることなら、この機会に室内飼育に切り替えることを検討してはいかがでしょうか。
外を歩く人や犬に反応して吠えていた犬であれば、室内に入れることで解決することも考えられます。
まとめ
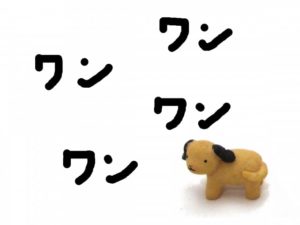 犬は、よほどのことがない限り、「吠えたいから吠える」ようなことはありません。
犬は、よほどのことがない限り、「吠えたいから吠える」ようなことはありません。
POINT
そこには必ず理由があります。
しかし、ただ吠える声だけを聞かされる人にとっては、犬が吠える理由よりも、単純に「うるさい」という気持ちだけを感じることになります。
犬が何を求めて何を訴えているかを理解し、解決してあげられるのは飼い主さんだけです。
正しい知識を身に着け、犬の心に耳を傾けましょう。
犬の意識を正しい方向へ導くことができれば、口輪や電気ショックを与える虐待のような器具を使わなくても、犬はきちんと吠えるのをやめて飼い主さんに要求を伝えることができるようになるはずです。
ポメチワとは?
 いきなりですが、ポメチワとはご存じでしょうか?
想像はつくかと思うのですが、ポメチワとはミックス犬の事です。
ミックス犬とは、違う犬種の親から生まれた犬の事で、ミックス犬またはハーフ犬と呼ばれる事もあり、両親ともに純血種である事が原則となっています。
そんなミックス犬を作出するブリーダーさんが増えてきているように感じますね。
そこで今回は、ミックス犬の中でもポメチワにスポットをあてて解明していきたいと思います。
いきなりですが、ポメチワとはご存じでしょうか?
想像はつくかと思うのですが、ポメチワとはミックス犬の事です。
ミックス犬とは、違う犬種の親から生まれた犬の事で、ミックス犬またはハーフ犬と呼ばれる事もあり、両親ともに純血種である事が原則となっています。
そんなミックス犬を作出するブリーダーさんが増えてきているように感じますね。
そこで今回は、ミックス犬の中でもポメチワにスポットをあてて解明していきたいと思います。
ポメチワの歴史
ポメラニアンの起源は、ドイツとポーランドの国境にまたがるポメラニアン地方に土着していた、ジャーマン・スピッツやサモエドだと言われており、チワワの起源は、古代メキシコに存在したとされるテチチという犬だと考えられています。
ロングコートチワワを作出する際にポメラニアンと掛け合わされたため、チワワは元々ポメラニアンに似ているのです。
ポメチワは近年人気が急上昇しているミックス犬ブームによって作出され、潤んだ瞳がたまらなく可愛いと人気を集めています。
ポメラニアンもチワワも古くから愛玩犬として愛されてきた歴史があるので、今後も愛され続けていくのではないでしょうか。
ポメチワはどの犬との組み合わせ?
ポメチワとは先ほどもご紹介しましたが、ポメラニアンとチワワを両親に持つミックス犬です。
他にはマルプーと言って、マルチーズとプードルを両親に持つミックス犬も人気です。
ポメチワという呼び名以外に「チワラニアン」や「チワポメ」と呼ばれる事もあります。
ポメチワが生まれる組み合わせは以下の2通りとなっています。
POINT
・ポメラニアン(父親)×チワワ(母親)
・チワワ(父親)×ポメラニアン(母親)
で、ミックス犬をさらに交配させると、遺伝的な疾患を持った子犬が生まれやすくなってしまうので禁止となっています。
ポメチワの特徴
 ポメラニアンとチワワと言えば、どちらも愛らしい真ん丸な瞳がチャームポイントですよね。
そんな両親を持つポメチワは、どのような愛らしい特徴をしているのでしょうか?
そこで、ここではポメチワの外見的特徴や被毛・毛色などを詳しくご紹介していきたいと思います。
ポメラニアンとチワワと言えば、どちらも愛らしい真ん丸な瞳がチャームポイントですよね。
そんな両親を持つポメチワは、どのような愛らしい特徴をしているのでしょうか?
そこで、ここではポメチワの外見的特徴や被毛・毛色などを詳しくご紹介していきたいと思います。
外見の特徴や大きさ
ポメチワの外見的特徴は、先ほどもご紹介したように大きくまん丸い瞳になります。
目鼻立ちがはっきりしており、チワワの持つ大きな耳が受け継がれている事が多いようです。
ちょこんとついた尻尾は、さまざまな形があってバリエーション豊かとなっています。
一般的にポメチワは、ポメラニアンに似た外見をしている事が多く、ミックス犬とは気づかれない事も。
元々ロングコートチワワを作出する際に、チワワとポメラニアンを掛け合わせていたため、尚更ポメラニアンに似るのではないかと言われています。
ポメチワの大きさは、体高24㎝、体重3㎏程度の超小型犬~小型犬に分類されます。
一般的なチワワよりも少々大きくなる事がほとんどで、ポメラニアンとほぼ同じくらいの大きさに成長するでしょう。
被毛は白・黒以外の毛色がある
ポメラニアンもチワワも元々美しい毛並みをもつ犬種ですので、ポメチワもその毛並みを受け継ぎゴージャスな被毛になる事が多いと言われています。
毛質はチワワより、ポメラニアンの特徴を受け継いでおり、個体によって差はありますが、ボリュームのあるストレートな毛並みを持つ子犬が多く生まれます。
ポメチワの被毛は、ダブルコートで、抜け毛が多くなるため、日常的に小まめなブラッシングが必要となってきます。
毎日が忙しい方やブラッシングが面倒だなと感じる方は、他の犬種を検討した方がいいかもしれません。
毛色はバリエーションが豊富で、ブラックやホワイトの他にも、チョコレート・クリーク・ブラウン・グレー・レッド・オレンジ・セーブル・ブルー・パーティーカラー・ブラックタンが確認されており、飼い主さんが好みの色を探しやすいのが、人気の秘訣の一つでもあるでしょう。
性格
ポメチワの性格ですが、勇敢で活発なチワワの気質と、活発で好奇心旺盛なポメラニアンの気質が組み合わさり、チョコマカと活発に動き回る遊びが大好きなタイプです。
飼い主さんやその家族に対しては愛情深く、甘え上手、ですので、何でも言う事を聞いてあげているとワガママになってしまいますので、飼い始めのしつけが大切になってくるでしょう。
またどちらの親犬種にも共通している警戒心の強さ・飼い主に対する忠誠心が性格のベースとして現れる事が多いと言えます。
この性格上、尚更しつけを徹底的にしておかないと、噛み癖や吠え癖がついてしまう事になってしまいますので注意しましょう。
その癖さえなければ、陽気でフレンドリーですし、聞き分けの良い素直なパートナーとしてどこでも一緒に連れていけるようになりますよ。
寿命
ポメチワの平均寿命は、10歳~15歳と言われており、通常の犬と同じ程度の寿命であると言えます。
ミックス犬なので、純血と比較して遺伝疾患が少ないと言われている事が長生きに繋がっており、また生活環境に気を付ける事でさらに寿命を延ばす事ができるでしょう。
では、長生きしてもらうコツを少しだけご紹介しておきます。
POINT
まずは、十分な運動をさせてあげる事とストレスを抱え込まない事で、散歩は1日2回30分程度を目安にしてもらえれば十分運動していると言えますし、ストレスのない日常を過ごす事ができます。
次に被毛の手入れをする事になり、先ほどもご紹介しましたが、ポメチワは毛が多く、抜け毛も多いのでこまめなブラッシングとトリミングが必要となります。
定期的なシャンプーを行う事も大切で犬の体の衛生面を整える事として重要になってくるでしょう。
ポメチワの値段
 ポメチワの値段ですが、15万円前後が平均相場のようで、比較的リーズナブルな値段になっています。
しかし、血統や外見の美しさ次第では、もう少し高くなる事もあるようです。
ミックス犬ですので、ペットショップなどでは販売されていないだろうと思っている方も多いかもしれませんが、ポメチワはミック犬の中でも珍しくペットショップでも販売されている事が多いです。
多くのミックス犬を取り扱っているミックス犬専用店であれば高確率で販売されていると言われていますので、気になる方はミックス犬専門店を探してみて下さいね。
ポメチワの値段ですが、15万円前後が平均相場のようで、比較的リーズナブルな値段になっています。
しかし、血統や外見の美しさ次第では、もう少し高くなる事もあるようです。
ミックス犬ですので、ペットショップなどでは販売されていないだろうと思っている方も多いかもしれませんが、ポメチワはミック犬の中でも珍しくペットショップでも販売されている事が多いです。
多くのミックス犬を取り扱っているミックス犬専用店であれば高確率で販売されていると言われていますので、気になる方はミックス犬専門店を探してみて下さいね。
まとめ
 今回はポメラニアンとチワワのミックス、ポメチワについてご紹介してきました。
ポメチワを身近で見た事がない方も多いでしょうが、本当にとても愛らしい外見をしており見たら絶対飼いたくなっちゃいますよ。
ポメチワを飼う上でグルーミングやトリミングが欠かせないという事だったので、それがしっかりできる方は、是非ミックス犬専門店へポメチワを見に行ってみて下さいね。
今回はポメラニアンとチワワのミックス、ポメチワについてご紹介してきました。
ポメチワを身近で見た事がない方も多いでしょうが、本当にとても愛らしい外見をしており見たら絶対飼いたくなっちゃいますよ。
ポメチワを飼う上でグルーミングやトリミングが欠かせないという事だったので、それがしっかりできる方は、是非ミックス犬専門店へポメチワを見に行ってみて下さいね。
スコティッシュフォールドとは?
 折れた耳が愛らしいスコティッシュフォールド。
人間になつきやすい穏やかな性格なので、初心者でも飼いやすく人気のある猫種です。
そんなスコティッシュフォールドは、1961年にスコットランドの中部であるテイサイドという地域で生まれた白猫が起源となっています。
偶然発見された耳の折れた猫は、生んだ子猫も折れた耳だったので、その特徴を繁栄させることにしました。
スコティッシュフォールドと名付けられたのは、1994年です。まだ30年にも満たない歴史の浅い猫種になります。
折れた耳に加え、まん丸の頭と目が一層愛らしさを感じさせます。他の猫のようにキリッとしたかっこいい目つきでないのも特徴的です。
体重は、生まれたばかりであれば100グラム前後です。その後は3〜5キロが平均的な体重になります。
折れた耳が愛らしいスコティッシュフォールド。
人間になつきやすい穏やかな性格なので、初心者でも飼いやすく人気のある猫種です。
そんなスコティッシュフォールドは、1961年にスコットランドの中部であるテイサイドという地域で生まれた白猫が起源となっています。
偶然発見された耳の折れた猫は、生んだ子猫も折れた耳だったので、その特徴を繁栄させることにしました。
スコティッシュフォールドと名付けられたのは、1994年です。まだ30年にも満たない歴史の浅い猫種になります。
折れた耳に加え、まん丸の頭と目が一層愛らしさを感じさせます。他の猫のようにキリッとしたかっこいい目つきでないのも特徴的です。
体重は、生まれたばかりであれば100グラム前後です。その後は3〜5キロが平均的な体重になります。
スコティッシュフォールドの性格
 スコティッシュフォールドは、その愛らしい見た目と同様、人懐こく穏やかな性格です。
一見あっさりしている感じでも甘えん坊の一面を持っています。
スコティッシュフォールドのオスは、去勢を行うと性格が変わることもあります。
去勢を行うと甘えん坊のままになり、行わないと頑固になっていきます。
メスの場合、避妊手術を行っても特に性格は変わりません。
それでは、オスとメスの性格を細かくご紹介していきます。
スコティッシュフォールドは、その愛らしい見た目と同様、人懐こく穏やかな性格です。
一見あっさりしている感じでも甘えん坊の一面を持っています。
スコティッシュフォールドのオスは、去勢を行うと性格が変わることもあります。
去勢を行うと甘えん坊のままになり、行わないと頑固になっていきます。
メスの場合、避妊手術を行っても特に性格は変わりません。
それでは、オスとメスの性格を細かくご紹介していきます。
オスの性格
スコティッシュフォールドのオスの性格は、素直な性格で、感情表現がストレートです。
とても甘えん坊で、飼い主さんがたっぷりスキンシップをしてあげないと寂しくなっていじけてしまうことも。
怒っていたずらしてしまうかもしれません。
基本的に、普段はしないようないたずらをすることがあれば、それは「かまって欲しい」サインです。
一緒に過ごす時間を確保するようにしましょう。
また、去勢を行うことで性格が変わります。
去勢を行うといつまでも甘えん坊なままです。
攻撃性が和らぐので、マーキングなどの問題行動も抑えられます。
一方、去勢を行わないと成長につれて子どもっぽさがなくなり、頑固で我が道を貫く性格になっていきます。
メスの性格
一方、メスの性格は、感情を隠しがちです。喜怒哀楽が少なく、クールに見えることもあります。
そのため、オスと比べてあっさりしていて、飼い主さんは距離を感じてしまうかもしれませんが、マイペースでのんびりした性格によるものになります。
基本的にはスコティッシュフォールドは穏やかで甘えん坊の性格なので、甘えるときとツンとしているときのギャップがあり、愛らしいです。
また、去勢によって性格が大きく変わるオスとは異なり、メスは避妊手術を行っても特に性格は変わりません。
落ち着いた性格のまま成長していくことが多いです。
メスは性格が悪く凶暴という話も
 基本的には穏やかでのんびりした性格です。
しかし、ストレスがたまっているとき、オスはいたずらしてアピールするなど感情をストレートに出すことができますが、メスは、感情をあらわにしないでため込む傾向があります。
そのたまったストレスが爆発したときに凶暴になってしまうこともあるでしょう。
ですのでクールなメスがストレスを爆発させてしまうと、飼い主さんによっては性格が悪く凶暴に見えてしまうかもしれません。
たまったストレスを放置すると、心身が弱り、問題行動や病気のもとになることもありますので、飼い主さんが行動の変化を敏感にキャッチできるよう、日ごろから観察を心がけましょう。
基本的には穏やかでのんびりした性格です。
しかし、ストレスがたまっているとき、オスはいたずらしてアピールするなど感情をストレートに出すことができますが、メスは、感情をあらわにしないでため込む傾向があります。
そのたまったストレスが爆発したときに凶暴になってしまうこともあるでしょう。
ですのでクールなメスがストレスを爆発させてしまうと、飼い主さんによっては性格が悪く凶暴に見えてしまうかもしれません。
たまったストレスを放置すると、心身が弱り、問題行動や病気のもとになることもありますので、飼い主さんが行動の変化を敏感にキャッチできるよう、日ごろから観察を心がけましょう。
環境によって凶暴になるケースがある
 環境によって、スコティッシュフォールドがストレスがたまり、凶暴になってしまうということがあります。
性格はとても甘えん坊でおとなしく、少しの音でも敏感に感じてしまいやすいです。
一匹でお留守番となると、それがストレスになってしまうこともあります。
スコティッシュフォールドもそれぞれ性格や好みが違います。
飼い主さんが愛猫の変化に気づけるよう、毎日観察していくことが大切です。
また、しっかりしつけをしないと凶暴化するケースもあります。
スコティッシュフォールドの特性や習性をしっかり理解したうえで、ダメなことはダメと叱りましょう。
環境によって、スコティッシュフォールドがストレスがたまり、凶暴になってしまうということがあります。
性格はとても甘えん坊でおとなしく、少しの音でも敏感に感じてしまいやすいです。
一匹でお留守番となると、それがストレスになってしまうこともあります。
スコティッシュフォールドもそれぞれ性格や好みが違います。
飼い主さんが愛猫の変化に気づけるよう、毎日観察していくことが大切です。
また、しっかりしつけをしないと凶暴化するケースもあります。
スコティッシュフォールドの特性や習性をしっかり理解したうえで、ダメなことはダメと叱りましょう。
まとめ
 スコティッシュフォールドの特徴や性格についてご理解いただけたでしょうか?
折れた耳と丸い顔や体がとても愛らしい猫種です。そのうえ、とても人懐こくてのんびりした性格といわれています。
とはいえ、一匹一匹個性があり、性格もさまざまです。
どんなことやモノにストレスを感じるかもそれぞれですので、飼い主さんがしっかり愛猫の性格や飼い方を身につけて、ストレスを防ぐことが愛猫と楽しく過ごすうえでは大切になってきます。
スコティッシュフォールドの特徴や性格についてご理解いただけたでしょうか?
折れた耳と丸い顔や体がとても愛らしい猫種です。そのうえ、とても人懐こくてのんびりした性格といわれています。
とはいえ、一匹一匹個性があり、性格もさまざまです。
どんなことやモノにストレスを感じるかもそれぞれですので、飼い主さんがしっかり愛猫の性格や飼い方を身につけて、ストレスを防ぐことが愛猫と楽しく過ごすうえでは大切になってきます。
犬用バリカンを使って自宅でトリミングしてみよう!
 ペットを飼っているご家庭は、誰もがトリミング費用に悩みを抱えているのではないでしょうか。
特に犬の場合は、毛が伸びるのが早い犬種も沢山いるため、定期的なトリミングが大切になってきます。
犬種によっては、1か月に1回程度トリミングを行わないといけない犬種もいますが、経済的にも時間的にも余裕がない方はどうしても数か月放置してしまうという事もあるでしょう。
そんなトリミングですが、コツを掴めば自宅で簡単にできるのです。
一般的な方法としてはバリカンで全体を刈ってしまい、ハサミで整えるやり方なのですが、どんなバリカンを使えばいいのかわかりませんよね。
そこで今回はペット用のバリカンについて詳しくご紹介していきたいと思います。
ペットを飼っているご家庭は、誰もがトリミング費用に悩みを抱えているのではないでしょうか。
特に犬の場合は、毛が伸びるのが早い犬種も沢山いるため、定期的なトリミングが大切になってきます。
犬種によっては、1か月に1回程度トリミングを行わないといけない犬種もいますが、経済的にも時間的にも余裕がない方はどうしても数か月放置してしまうという事もあるでしょう。
そんなトリミングですが、コツを掴めば自宅で簡単にできるのです。
一般的な方法としてはバリカンで全体を刈ってしまい、ハサミで整えるやり方なのですが、どんなバリカンを使えばいいのかわかりませんよね。
そこで今回はペット用のバリカンについて詳しくご紹介していきたいと思います。
犬用バリカンと人間用バリカンとの違い?
 犬用バリカンと人間用バリカンではまず刃に違いがあり、犬の毛は人間の毛と比べると細くて柔らかく、毛の質が違っていますので、人間用のバリカンではうまくカットする事ができません。
また、毛が硬い犬種もいますので、そんな犬種に人間用バリカンを使用すると故障してしまう恐れが出てきます。
そして、犬は激しい振動や音に敏感な子が多く、人間用バリカンは振動や音が比較的大きな物が多いので、恐怖感を感じてしまう可能性もあり、バリカンを使用する事を嫌がるようになってしまいますので、愛犬をカットする場合は、犬用バリカンを使用する方が無難でしょう。
犬用バリカンと人間用バリカンではまず刃に違いがあり、犬の毛は人間の毛と比べると細くて柔らかく、毛の質が違っていますので、人間用のバリカンではうまくカットする事ができません。
また、毛が硬い犬種もいますので、そんな犬種に人間用バリカンを使用すると故障してしまう恐れが出てきます。
そして、犬は激しい振動や音に敏感な子が多く、人間用バリカンは振動や音が比較的大きな物が多いので、恐怖感を感じてしまう可能性もあり、バリカンを使用する事を嫌がるようになってしまいますので、愛犬をカットする場合は、犬用バリカンを使用する方が無難でしょう。
犬用バリカンの選び方のポイントとは?
 犬用バリカンと一言で言っても、今は豊富な種類が販売されていますので、どのような事に重点を置いて購入すればいいのか悩んでしまうのではないでしょうか。
ネットでの購入が手っ取り早いと思うかと思いますが、バリカンの場合は、持った時の感覚や重さなども重要になってきますので、実際に店舗に足を運び手に持って選んでもらう方がいいでしょう。
そこで、ここでは犬用バリカンの選び方のポイントをいくつかご紹介しますので、是非参考にしてみて下さいね。
犬用バリカンと一言で言っても、今は豊富な種類が販売されていますので、どのような事に重点を置いて購入すればいいのか悩んでしまうのではないでしょうか。
ネットでの購入が手っ取り早いと思うかと思いますが、バリカンの場合は、持った時の感覚や重さなども重要になってきますので、実際に店舗に足を運び手に持って選んでもらう方がいいでしょう。
そこで、ここでは犬用バリカンの選び方のポイントをいくつかご紹介しますので、是非参考にしてみて下さいね。
①コードレスの物を選ぶ
バリカン初心者の方は、まずコードレスタイプのものがおすすめです。
邪魔になりやすい電源コードがない事で操作性が上がり、2人がかりで作業する場合にも便利です。
コードを繋いでも外しても使える2WAY仕様になっているものも販売されていますので、技術レベルや使用場所に合わせて使い分けられるバリカンがいいでしょう。
コードレスタイプの場合は、充電が足りなくなったり刃が熱くなってしまったりと、一度に全身をカットできない時もあるかと思いますが、そんな時は一度にカットせず日に分けて部分ごとにカットしていくという方法もあります。
②使い易さで選ぶ
バリカンの適切な重量は「20分持ち続けても疲れない重さ」です。
カット作業は20分以上かかる事が多く、その間に疲れてしまう事のないようなバリカンを選ぶようにしましょう。
バリカンにもプロ用と家庭用が販売されており、プロ用は比較的重量があるため、その面でも初心者は家庭用の商品がおすすめと言えます。
数ある商品の中で特に軽いものでは100g以下でしたので、その数字も参考にして頂ければわかりやすいのではないでしょうか。
③手入れのし易さで選ぶ
バリカンは刃の切れ味を維持するため、使用する度に掃除や注油が必要です。
長く安全に使いたいものなので、手入れのしやすさは非常に重要なポイントとなるのではないでしょうか。
毎回お手入れをする事を考えると、内部に入り込んだ細かい毛を効率的に取り除ける、水洗い可能な商品がベストと言えます。
購入する際、掃除ブラシやオイルが付属しているかどうかもチェックして購入するようにして下さいね。
④機能性で選ぶ
犬の聴覚は臭覚に次いで鋭いと言われており、その聴力は人間の約4倍~10倍とされています。
さらに1900年代に行われた実験で、小さな音を聞き分ける能力が人間より16倍も敏感だったという結果も残っています。
つまり、人間でもうるさいと感じるバリカンの音は、犬にはとてつもなく大きな騒音として聞こえているという事なのです。
犬用のバリカンには静音設計が搭載されたタイプもありますので、できればそちらのタイプを選択してあげるようにしましょう。
犬の中でも特に音や振動に敏感だと思われる愛犬には㏈で表記された騒音レベルを確認しておく事も重要です。
⑤刃のサイズで選ぶ
犬用バリカンには大きく分けて全身用と部分用があり、全身カットをするには幅4.5㎝、長さ3~5㎜の刃が最適です。
また、複数のアタッチメントが付属している部分であれば、好みの仕上がりに合わせて使い分けが可能になります。
気になる部分のみをカットしたいのであれば、1㎜の刃が搭載されたバリカンが最適です。
刃が小さいためケガをさせる可能性も少なく、顔周りなど危険な場所にも安心して使用する事ができます。
今は、セットになって販売されているものもありますので、全身用と部分用両方必要であれば、そちらを購入する方が効率が良いかもしれません。
犬用バリカンの使い方のコツとは?
最初にご紹介しましたが、初心者の方でも使い方のコツさえ掴めば自宅で簡単にトリミングができるようになります。
そのコツについてご紹介していきましょう。
POINT
しっかりブラッシングをした後に、バリカンを皮膚に対して平行にあてます。
刃を立て過ぎてしまうと、刃で皮膚を傷つけてしまう危険性がありますので注意して下さい。
平行に当てたら、ゆっくりとまっすぐ動かします。
毛の流れに沿ってゆっくり順にカットしていくのですが、色々な所からカットしていくと虎刈りになってしまいますので、1か所ずつ丁寧にカットして下さい。
慣れるまでは足裏の肉球周りなどから始めていくといいでしょう。
愛犬がじっとできない場合は、一人がおやつなどで気を引いている間に、一人がカットしていくという方法もあります。
犬用バリカンのおすすめ人気ランキング6選
最後に、犬用バリカンおすすめ人気ランキング6選をご紹介します。
購入する際、是非参考にしてみて下さいね。
リンク
完全防水のセラミック刃!便利な13点セットです!
ペットクリッパーズの特徴は
・安全設計:セーフティガードが付いているので、万が一の時でも安心
・コード、コードレス両対応:お風呂場などコンセントがない場所ではコードレスで、充電をし忘れた場合やコードレスでパワーが落ちてきた場合などは、コードで使用できます。
・セラミック刃:刃は、ペットに優しく丈夫なセラミック素材を使用しています。
0.8㎜~2.0㎜まで5段階で微調整する事ができます。
・アタッチメント6種が付属:便利な6つのアタッチメントが付属していますので、ペットに合わせて使用できます。
・マニュアル付属:どうやってカットすればいいのかわからない人のために、わかりやすいマニュアルが付いてきます。
・日本国内メーカーによる安心の1年保証
・PSE認証済み
そして、より良い使い心地を目指すために、改良された点が4つあります。
・静音設計:50㏈の静音設計なので、音や振動が怖い愛犬にも安心して使用する事ができます。
・残量表示:残量がデジタルで確認できるので、充電切れの心配がありません。
・安全防水:バリカンを丸ごと洗う事ができるので、お風呂で利用でき、安全・安心・清潔を常に保つ事ができます。
・速さ調節2段階:バリカンの速さが2段階で調整できるので、バリカンの扱いに慣れていない方でも、ゆっくりカットする事ができます。
リンク
乾電池式のバリカンで、手軽に使用できます!
コードレスバリカンミニは、小型犬の全身カットや大型犬の部分カットに最適なバリカンです。
特徴としては
・手軽に使えるスリム&軽量タイプ
気づいた時にさっと使用でき、小型なので隅々まで素早くカットする事ができます。
・安心の優しいモーター音
乾電池式でも、優しい騒動音を実現。
音に敏感な愛犬のための静音設計です。
・切れ味の良いセラミック刃
可動刃は、肌辺りの良いソフトなセラミック製。
ミニ刃でもスムーズなカットを可能にしています。
・刈りすぎ防止 アタッチメント付き
刃先に装着するだけで簡単に使用できるアタッチメント付き。
3㎜または6㎜の長さにカットできます。
・優れた騒動力の電池式
アルカリ単3電池で約1週間使用OK
リンク
抜群の切れ味で、短時間で理想の姿にカットできるバリカンです!
・高性能モーターを採用しているため、力強いパワーで刃を動かす事ができます。
連続使用できる定格時間は20分です。
・刃は廃カーボンスチールを採用しており、切れ味に優れた硬質の刃です。
・可動刃と固定刃の合わせ面、刃先の斜め面の両面碇石研磨仕上げで鋭い刃先になっています。
可動刃のピッチを深く粗く設計し、被毛を捉えやすくなっています。
・3㎜、6㎜、9㎜のステンレスコームタイプアタッチメント付き
・充電してコードレスとしても、ACアダプターを繋いだ状態でも使用できます。
約8時間のフル充電で約50分、約5時間の充電で約30分動かす事ができ、定格時間20分を超えると高温になってしまうので、10分休ませ掃除を注油をしてから再度使用するようにしましょう。
リンク
ひとかきでごっそり!抜け毛を90%取り除くケア用品です!
バリカンとは違うのですが、バリカンをしてしまうと毛質が変わってしまったり、毛が伸びるまで時間がかかってしまう犬種用のケア用品となっています。
・軽くブラッシングするだけで、抜け毛の最大90%を取り除きます
・ファーミネーターで定期的にブラッシングする事で、愛犬の被毛のケアになるだけではなく、洋服についた抜け毛や、部屋に散らばった抜け毛が減り、毎日の掃除が楽になります。
・ファーミネーターは、短毛種用・長毛種用・そして体の大きさに合わせて、ワンちゃん用は10種類あり、他の動物用のものもあります。
刃が鋭いですが、特殊なエッジで抜け毛や不要な毛だけをすくい取る仕組みになっており、皮膚や被毛を引っ張る事がないので痛みは感じませんので安心して下さいね。
愛犬の場合は、週1回程度ブラッシングして頂くだけで十分です。
リンク
スマートなボディでプロ並みに綺麗にカットができるバリカンです!
パナソニックが販売するプロトリマーは、持ちやすいスリム&軽量ボディにプロ仕様のカット能力で、手のひらサイズの小型タイプです。
フル充電で60分使用可能
細かなうぶ毛をさっとすっきりでき、頬や目元、口元などのうぶ毛カットも可能です。
低振動・低静音設計になっていますので、音や振動を怖がるワンちゃんに最適なバリカンとなっています。
全身カット用ではなく、耳周りや首回りなど細部トリミング用となっていますので、全体カットをしたい場合は全身用バリカンと併用して使用するようにしましょう。
リンク
初心者にもおすすめ!自宅で簡単にトリミング!
・静音設計でリラックス
静かな音でリラックスできる40~50㏈という静音設計になっており、臆病な愛犬でも安心して使用できます。
振動も少ないので、体に負担をかける事なく、カットができるでしょう。
・電源がなくても使用OK
充電式とコードありの2つの使い方ができ、プロ用並みの使い勝手の良さになっています。
1回5時間程度でフル充電ができ、充電後は約70分間使用する事ができます。
長時間使っても放熱効果が高いので、愛犬に熱を感じさせる心配がありません。
・豊富なアタッチメントで調節が楽
セットで付属しているアタッチメントが豊富で微調節も簡単です。
こだわりのトリミングから初心者まで簡単に使いこなせるようになっています。
・PSE認証済み
刃は切れ味抜群で品質が落ちにくいセラミックボタンを使っており、モーターも強力で24枚刃なので、パワフルで全犬種に対応しています。
さらに安全性が高い電化製品に与えられるPSE認証を取得しているので、ペットに優しいトリミングができます。
プードルとは?

クルクルの巻き毛につぶらな瞳、まるでぬいぐるみのような容姿のトイプードルは、沢山種類があり最近では、小さいティーカッププードルやタイニープードルにも人気が集まってきています。
そんなトイプードルについて今回は詳しくご紹介していきたいと思っています。
まずはプードルの歴史から解説していきましょう。
プードルの歴史
 実はプードルは小型犬ではなく大型犬だった!!という事を知っていましたでしょうか?
実はプードルは小型犬ではなく大型犬だった!!という事を知っていましたでしょうか?
プードルの歴史は古く、東西ヨーロッパやロシアに分布していた犬が元になったと言われており、その頃のプードルは大型犬に分類されていました。
犬種として固定化されたのは、ドイツからフランスに持ち込まれてからのようです。
泳ぎが得意なプードルはドイツ語で「水辺でバシャバシャ泳ぐ」という意味の「プデル」から付けられたと言われており、鴨猟の回収犬として重宝されたと言われています。
プードルの特徴

プードルは非常に賢く、社交的な性格・飼い主に従順な性格が特徴で、他の動物とも友好関係を築きやすいと言われています。
水に強く泳ぎが得意な事から、水遊びをしたり、オモチャを取ってくる遊びを好む子が多いです。
見た目の特徴ですが、シングルコートの巻き毛は抜けにくく、体臭もほとんどない事でしょう。
そのため、アレルギー体質の人でも心配が少なく、家庭で飼いやすい犬種として人気を集めています。
ただし、毛が絡まりやすく毛玉ができやすいので、定期的なトリミングが必要となってきます。
プードルの寿命
 トイプードルの平均寿命はこれまで12~14歳とされていましたが、最近では15~16歳と以前に比べ3~4年ほど長くなったと言われており、全犬種の中でも比較的寿命が長い犬種と言えるでしょう。
トイプードルの平均寿命はこれまで12~14歳とされていましたが、最近では15~16歳と以前に比べ3~4年ほど長くなったと言われており、全犬種の中でも比較的寿命が長い犬種と言えるでしょう。
寿命が長くなった背景には、フードの質の向上や、療養食やサプリメントの豊富さではないかと言われており、それは全犬種にもあてはまる事です。
フードの水分含量・柔らかさも様々で、子犬から老犬まで年齢や体調に合わせた適切なフードが選べるようになっています。
さらに、犬に関する医療技術も向上しており、人間と同じような医療機器を揃えた動物病院も増加している事も関係していると言えます。
プードルの種類と値段
 プードルの種類は大きく分けてスタンダード・ミディアム・ミニチュア・トイの4つで、そこにティーカップやタイニーという種類も追加されていますが、正式には最初にご紹介した4つの種類と言われています。
プードルの種類は大きく分けてスタンダード・ミディアム・ミニチュア・トイの4つで、そこにティーカップやタイニーという種類も追加されていますが、正式には最初にご紹介した4つの種類と言われています。
どの種類も性格は同じで、落ち着きがあって社交的。
理解力に優れ飼い主に従順なので、しつけがしやすいでしょう。
値段に関しては種類によって違ってきますので、ここでは種類の特徴と値段についてご紹介していきます。
スタンダードプードル

スタンダードプードルは4種類の大きさがあるプードルの基本です。
体が一番大きく、体高約45~60㎝、体重約16~25㎏が標準サイズの大型犬です。
元々活発な犬種であるとともに体が大きいので、毎日1時間程度の散歩が欠かせません。
泳ぎが得意な犬種ですので、夏場や水辺に連れて行ってあげるのもいいですね。賢さや穏やかな性格を活かし、アメリカやカナダでは盲導犬としても活躍しています。
スタンダードプードルのお値段ですが、35万円前後となっており、ペットショップでは中々販売していないので、ブリーダーさんから購入するのがいいでしょう。
ミディアムプードル

ミディアムプードルは、体高約35~45㎝、体重8~15㎏で柴犬くらいの中型犬に分類されます。
JKCの認定を受けたのが2003年とサイズの歴史は浅いため、まだまだわかっていない事が多く、国によってはミディアムサイズを認めていないという所があります。
スタンダードと同様、穏やかで従順な性格。
ミディアムも散歩やドッグランなどでの定期的で十分な運動が必要となってきます。
ミディアムプードルの値段ですが、平均価格が約34万円で、最高価格は48万円、最低価格は19万円となっています。
こちらもあまりペットショップでは見ないので、ブリーダーさんに相談してみるのがいいでしょう。
ミニチュアプードル

ミニチュアプードルは、体高約28~35㎝、体重5~8㎏の小型犬です。
日本ではあまり見かけませんが、スタンダードプードルを改良し、17世紀ごろには存在していたと言われています。
他のプードルと同様に活発で賢く、運動神経抜群なので、海外ではトリュフを探す探知犬や災害救助犬・サーカスなどで活躍する事も多い人気のサイズとなっています。
社交的で穏やかな性格ですが、小型犬ならではの神経質で怖がりなところもありますので、子犬の頃から吠え癖や噛み癖がつかないようなしつけが必要です。
ミニチュアプードルの値段は、大きな差があり5万円以下の子から50万円以上もする子までいます。
ペットショップでも販売していますし、ブリーダーからも購入でき、非常に人気が高い種類と言えるでしょう。
トイプードル

今、一番人気となっているのがトイプードルで、ペットショップでも見ない事はないくらいですね。
体高26~28㎝、体重3~4㎏の超小型犬で、人気のため国内では安易なブリーディングで何らかの疾患を抱えて子犬も多くなっています。
飼う時には、信頼できるブリーダーやペットショップを見極める事が大切なポイントと言えるでしょう。
犬は小型犬になるほど神経質な傾向があり、トイプードルの場合は超小型犬に分類されていますので、神経質で警戒心が強い綿があります。
賢く学習能力が高いので、しつけはしやすいですが、飼い始めにしっかりしたしつけをしておかないと吠え癖や噛み癖が出てきてしまう事があるでしょう。
トイプードルの値段は、20~30万円となっています。
タイニープードル

タイニープードルはアメリカで作出されたサイズで、日本のJKCではまだ非公認となっています。
体高25㎝以下で、体重は2~3㎏とトイプードルよりもさらに小さなサイズです。
骨格が小さく鼻の長さが短めの傾向があり、作出が難しく、サイズがまだ不安定で思ったより大きくなる事もあります。
飼う時には、信頼できるブリーダーで親や祖父母犬のサイズまで確認するようにして下さい。
性格は明るく賢い反面、神経質な部分もあるので、留守が多い家庭はメンタル面にも気を配る必要が出てきます。
タイニープードルの値段は、20~45万円となっています。
ティーカッププードル

ティーカッププードルもアメリカで作出され、日本のJKCではまだ非公認となっています。
体高23㎝以下で体重は2㎏、ティーカップに入れれるほどの小ささからその名前が付けられたと言われています。
骨や関節が弱い場面があり、ちょっとした段差が負担になってしまいますので、散歩や家の中の環境に気を遣う必要が出てくるでしょう。
基本のプードルの性格に加え、怖がりで神経質な面があります。甘えん坊なので飼い主さんに対する依存が高まりやすく、メンタル面には注意が必要です。
ティーカッププードルの値段は、30~40万円で飼育件数が少ない種類になりますので、信頼できるブリーダーから購入する事をおすすめします。
まとめ

今回はプードルについてご紹介してきました。
主流になっているトイプードルをイメージしていましたが、プードルにも様々な大きさや性格があるのがわかりましたね。
ペットショップで購入できる種類もいますが、できれば信頼できるブリーダーを探しそこで購入する事をおすすめします。 猫がお腹を見せるのは降参の意味ではない

遊んでいるときやリラックスしているとき、猫はあお向けスタイルになります。お腹を見せるときは降参を意味していると思っている人が多いかと思います。
実施はそうではないようです。動物はお腹を見せたら、降参もしくは服従していることを表していると言われています。
しかし、猫の場合、猫同士がケンカをした際、劣勢になったほうがお腹を見せます。お腹を見せると不利に感じられますが、あお向けになることで前足で相手を抱え込んで噛みつき、後ろ足でキックしたり攻撃できるからです。
つまり、猫がお腹を見せるのは、反撃体制のためであり、降参を意味するのではないということです。
猫がお腹を見せる理由は?

とは言え、お腹は、内臓が詰まっている大切な場所です。誰にでもお腹を見せる訳ではなく、心を許している飼い主さんへ見せることが多いです。
ケンカの際の反撃体制とは違って、飼い主さんへお腹を見せるというのは別の意味があります。お腹を見せる理由を5つご紹介していきたいと思います。
お腹を見せる理由①飼い主への信頼
猫が飼い主さんへお腹を見せるのは「この人は安心できる存在」という意味になります。
お腹は内臓が詰まっていて骨がないので、とても大切で弱い部分です。油断の許さぬ相手には決して見せないでしょう。つまり「あなたを信頼していますよ」ということのメッセージになります。
通常、子猫は母猫に甘えるとき、お腹を見せます。小さいうちから生活を共にしていると、猫にとって飼い主さんは母猫のような存在になるのでしょう。お腹が空いたときやかまって欲しい時など、甘えたいアピールの一つとしてお腹を見せるようになります。つまり、猫がお腹を見せるのは、飼い主さんへの信頼からくる甘えの行動です。
お腹を見せる理由②飼い主への欲求
他にも、飼い主さんへお腹を見せるのは「撫でて欲しい」とか「一緒に遊んで欲しい」といった、かまってほしいときです。
そんなとき、猫はお腹を見せるとともに体をくねらせたり、しっぽを動かしたりしています。こんなときは、猫とたくさん触れ合ってください!
また、飼い主さんが帰宅した際、目の前で床に転がってお腹を見せるのは、飼い主さんを待ちわびていて嬉しいという気持ちの表現です。こんなときも、思い切り甘やかしてあげましょう。
他にも、飼い主さんが他のことに気を取られているとき、目の前でいきなりゴロンと転がってお腹を見せるなども、自分に関心を向けてほしいという気持ちの表れになります。
お腹を見せる理由③リラックス状態
猫は、心を許している人や環境の前では決してお腹を見せることはありません。必ず安心できる場所で、リラックスしているときにお腹を見せることがあります。猫なりに気分転換をしているのでしょう。
日向ぼっこしているときや、静かな夜になったとときなどにお腹を見せていたり、背中を床に擦りつけてクネクネしているときなどは、かまったりせずそっとしておきましょう。
猫も自分の世界に入って、気持ちも体ものびのびとしたいという表れなのかもしれません。ですので、いきなりお腹を触ったりなどすると、ビックリされることもあります。
お腹を見せる理由④居場所の安心感
猫は、知らない人や環境、モノに対しては強く警戒します。そのようなときには、間違っても弱い部分であるお腹を見せるといった行為は決してしません。
猫は、自分の居心地の良い環境をとても大切に考えます。自分がわかっている場所や環境であれば、信頼できる飼い主さんに対して、安心感を感じてお腹を見せます。たとえ、飼い主さんが近くにいても、あまり馴染みのないなどよく知らない場所では決してお腹を出すことはないでしょう。
猫にとって安心できる場所であれば心も身体もリラックス状態となり、猫はお腹を見せることができるのです。
お腹を見せる理由⑤暑い思っている
猫がお腹を見せる別の理由としては、体の熱を逃がすためです。
暑い夏の日などに猫がお腹を見せて寝ている姿を見たことがありませんか。暑い日に、ひやっとするフローリングなどであお向けになって昼寝をしているのは、暑さから熱を逃がすためにお腹を出して寝ているのです。犬でも人間でも暑いと感じると、涼しい場所へ行ってゴロンと寝転がるということをしますね。
しかし、暑いからといって体から熱を出したい!と思ったとしても、もちろん猫自身が安心できる環境でなければこのような行動はできません。安心できる安全な場所であるからこそ初めてお腹を見せるということができるのです。
猫がお腹を見せてくねくねする理由は発情期だから?
 メスの猫がお腹を見せて体をくねくねしていることがあるのは発情期が考えられます。
メスの猫がお腹を見せて体をくねくねしていることがあるのは発情期が考えられます。
メス猫で、避妊手術をしていないと、生後半年くらい経ったあとの春や秋の初めに発情期になる可能性があります。
メス猫は発情期になると、コロンと転がり、背中を床に擦り付けてくねくねと体を動かすことで、オス猫にアピールします。そうすることでオス猫が寄ってくるのです。
室内で、オス猫がいない環境であっても、発情期になると、コロンと転がってくねくね体を動かして大きな声鳴くようなります。
まとめ

猫がお腹を見せる理由についてご紹介してきましたがいかがでしたでしょうか。
ケンカなどをして降参しているということではなく、主に飼い主さんへの信頼の現れであったり、リラックスしている、あるいは暑いと感じているということなどお分かりいただけたかと思います。
それはなによりも、猫は安心できると感じる場所でなければこのような行動をすることはありません。
あなたの愛猫がこのような行動を見せることがあれば、それは、あなたを信頼し、安心できる環境であると感じているほかありません。そのような関係や環境づくりができるといいですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
 クルクルの巻き毛につぶらな瞳、まるでぬいぐるみのような容姿のトイプードルは、沢山種類があり最近では、小さいティーカッププードルやタイニープードルにも人気が集まってきています。
そんなトイプードルについて今回は詳しくご紹介していきたいと思っています。
まずはプードルの歴史から解説していきましょう。
クルクルの巻き毛につぶらな瞳、まるでぬいぐるみのような容姿のトイプードルは、沢山種類があり最近では、小さいティーカッププードルやタイニープードルにも人気が集まってきています。
そんなトイプードルについて今回は詳しくご紹介していきたいと思っています。
まずはプードルの歴史から解説していきましょう。
 実はプードルは小型犬ではなく大型犬だった!!という事を知っていましたでしょうか?
プードルの歴史は古く、東西ヨーロッパやロシアに分布していた犬が元になったと言われており、その頃のプードルは大型犬に分類されていました。
犬種として固定化されたのは、ドイツからフランスに持ち込まれてからのようです。
泳ぎが得意なプードルはドイツ語で「水辺でバシャバシャ泳ぐ」という意味の「プデル」から付けられたと言われており、鴨猟の回収犬として重宝されたと言われています。
実はプードルは小型犬ではなく大型犬だった!!という事を知っていましたでしょうか?
プードルの歴史は古く、東西ヨーロッパやロシアに分布していた犬が元になったと言われており、その頃のプードルは大型犬に分類されていました。
犬種として固定化されたのは、ドイツからフランスに持ち込まれてからのようです。
泳ぎが得意なプードルはドイツ語で「水辺でバシャバシャ泳ぐ」という意味の「プデル」から付けられたと言われており、鴨猟の回収犬として重宝されたと言われています。
 プードルは非常に賢く、社交的な性格・飼い主に従順な性格が特徴で、他の動物とも友好関係を築きやすいと言われています。
水に強く泳ぎが得意な事から、水遊びをしたり、オモチャを取ってくる遊びを好む子が多いです。
見た目の特徴ですが、シングルコートの巻き毛は抜けにくく、体臭もほとんどない事でしょう。
そのため、アレルギー体質の人でも心配が少なく、家庭で飼いやすい犬種として人気を集めています。
ただし、毛が絡まりやすく毛玉ができやすいので、定期的なトリミングが必要となってきます。
プードルは非常に賢く、社交的な性格・飼い主に従順な性格が特徴で、他の動物とも友好関係を築きやすいと言われています。
水に強く泳ぎが得意な事から、水遊びをしたり、オモチャを取ってくる遊びを好む子が多いです。
見た目の特徴ですが、シングルコートの巻き毛は抜けにくく、体臭もほとんどない事でしょう。
そのため、アレルギー体質の人でも心配が少なく、家庭で飼いやすい犬種として人気を集めています。
ただし、毛が絡まりやすく毛玉ができやすいので、定期的なトリミングが必要となってきます。
 トイプードルの平均寿命はこれまで12~14歳とされていましたが、最近では15~16歳と以前に比べ3~4年ほど長くなったと言われており、全犬種の中でも比較的寿命が長い犬種と言えるでしょう。
寿命が長くなった背景には、フードの質の向上や、療養食やサプリメントの豊富さではないかと言われており、それは全犬種にもあてはまる事です。
フードの水分含量・柔らかさも様々で、子犬から老犬まで年齢や体調に合わせた適切なフードが選べるようになっています。
さらに、犬に関する医療技術も向上しており、人間と同じような医療機器を揃えた動物病院も増加している事も関係していると言えます。
トイプードルの平均寿命はこれまで12~14歳とされていましたが、最近では15~16歳と以前に比べ3~4年ほど長くなったと言われており、全犬種の中でも比較的寿命が長い犬種と言えるでしょう。
寿命が長くなった背景には、フードの質の向上や、療養食やサプリメントの豊富さではないかと言われており、それは全犬種にもあてはまる事です。
フードの水分含量・柔らかさも様々で、子犬から老犬まで年齢や体調に合わせた適切なフードが選べるようになっています。
さらに、犬に関する医療技術も向上しており、人間と同じような医療機器を揃えた動物病院も増加している事も関係していると言えます。
 プードルの種類は大きく分けてスタンダード・ミディアム・ミニチュア・トイの4つで、そこにティーカップやタイニーという種類も追加されていますが、正式には最初にご紹介した4つの種類と言われています。
どの種類も性格は同じで、落ち着きがあって社交的。
理解力に優れ飼い主に従順なので、しつけがしやすいでしょう。
値段に関しては種類によって違ってきますので、ここでは種類の特徴と値段についてご紹介していきます。
プードルの種類は大きく分けてスタンダード・ミディアム・ミニチュア・トイの4つで、そこにティーカップやタイニーという種類も追加されていますが、正式には最初にご紹介した4つの種類と言われています。
どの種類も性格は同じで、落ち着きがあって社交的。
理解力に優れ飼い主に従順なので、しつけがしやすいでしょう。
値段に関しては種類によって違ってきますので、ここでは種類の特徴と値段についてご紹介していきます。
 スタンダードプードルは4種類の大きさがあるプードルの基本です。
体が一番大きく、体高約45~60㎝、体重約16~25㎏が標準サイズの大型犬です。
元々活発な犬種であるとともに体が大きいので、毎日1時間程度の散歩が欠かせません。
泳ぎが得意な犬種ですので、夏場や水辺に連れて行ってあげるのもいいですね。賢さや穏やかな性格を活かし、アメリカやカナダでは盲導犬としても活躍しています。
スタンダードプードルのお値段ですが、35万円前後となっており、ペットショップでは中々販売していないので、ブリーダーさんから購入するのがいいでしょう。
スタンダードプードルは4種類の大きさがあるプードルの基本です。
体が一番大きく、体高約45~60㎝、体重約16~25㎏が標準サイズの大型犬です。
元々活発な犬種であるとともに体が大きいので、毎日1時間程度の散歩が欠かせません。
泳ぎが得意な犬種ですので、夏場や水辺に連れて行ってあげるのもいいですね。賢さや穏やかな性格を活かし、アメリカやカナダでは盲導犬としても活躍しています。
スタンダードプードルのお値段ですが、35万円前後となっており、ペットショップでは中々販売していないので、ブリーダーさんから購入するのがいいでしょう。
 ミディアムプードルは、体高約35~45㎝、体重8~15㎏で柴犬くらいの中型犬に分類されます。
JKCの認定を受けたのが2003年とサイズの歴史は浅いため、まだまだわかっていない事が多く、国によってはミディアムサイズを認めていないという所があります。
スタンダードと同様、穏やかで従順な性格。
ミディアムも散歩やドッグランなどでの定期的で十分な運動が必要となってきます。
ミディアムプードルの値段ですが、平均価格が約34万円で、最高価格は48万円、最低価格は19万円となっています。
こちらもあまりペットショップでは見ないので、ブリーダーさんに相談してみるのがいいでしょう。
ミディアムプードルは、体高約35~45㎝、体重8~15㎏で柴犬くらいの中型犬に分類されます。
JKCの認定を受けたのが2003年とサイズの歴史は浅いため、まだまだわかっていない事が多く、国によってはミディアムサイズを認めていないという所があります。
スタンダードと同様、穏やかで従順な性格。
ミディアムも散歩やドッグランなどでの定期的で十分な運動が必要となってきます。
ミディアムプードルの値段ですが、平均価格が約34万円で、最高価格は48万円、最低価格は19万円となっています。
こちらもあまりペットショップでは見ないので、ブリーダーさんに相談してみるのがいいでしょう。
 ミニチュアプードルは、体高約28~35㎝、体重5~8㎏の小型犬です。
日本ではあまり見かけませんが、スタンダードプードルを改良し、17世紀ごろには存在していたと言われています。
他のプードルと同様に活発で賢く、運動神経抜群なので、海外ではトリュフを探す探知犬や災害救助犬・サーカスなどで活躍する事も多い人気のサイズとなっています。
社交的で穏やかな性格ですが、小型犬ならではの神経質で怖がりなところもありますので、子犬の頃から吠え癖や噛み癖がつかないようなしつけが必要です。
ミニチュアプードルの値段は、大きな差があり5万円以下の子から50万円以上もする子までいます。
ペットショップでも販売していますし、ブリーダーからも購入でき、非常に人気が高い種類と言えるでしょう。
ミニチュアプードルは、体高約28~35㎝、体重5~8㎏の小型犬です。
日本ではあまり見かけませんが、スタンダードプードルを改良し、17世紀ごろには存在していたと言われています。
他のプードルと同様に活発で賢く、運動神経抜群なので、海外ではトリュフを探す探知犬や災害救助犬・サーカスなどで活躍する事も多い人気のサイズとなっています。
社交的で穏やかな性格ですが、小型犬ならではの神経質で怖がりなところもありますので、子犬の頃から吠え癖や噛み癖がつかないようなしつけが必要です。
ミニチュアプードルの値段は、大きな差があり5万円以下の子から50万円以上もする子までいます。
ペットショップでも販売していますし、ブリーダーからも購入でき、非常に人気が高い種類と言えるでしょう。
 今、一番人気となっているのがトイプードルで、ペットショップでも見ない事はないくらいですね。
体高26~28㎝、体重3~4㎏の超小型犬で、人気のため国内では安易なブリーディングで何らかの疾患を抱えて子犬も多くなっています。
飼う時には、信頼できるブリーダーやペットショップを見極める事が大切なポイントと言えるでしょう。
犬は小型犬になるほど神経質な傾向があり、トイプードルの場合は超小型犬に分類されていますので、神経質で警戒心が強い綿があります。
賢く学習能力が高いので、しつけはしやすいですが、飼い始めにしっかりしたしつけをしておかないと吠え癖や噛み癖が出てきてしまう事があるでしょう。
トイプードルの値段は、20~30万円となっています。
今、一番人気となっているのがトイプードルで、ペットショップでも見ない事はないくらいですね。
体高26~28㎝、体重3~4㎏の超小型犬で、人気のため国内では安易なブリーディングで何らかの疾患を抱えて子犬も多くなっています。
飼う時には、信頼できるブリーダーやペットショップを見極める事が大切なポイントと言えるでしょう。
犬は小型犬になるほど神経質な傾向があり、トイプードルの場合は超小型犬に分類されていますので、神経質で警戒心が強い綿があります。
賢く学習能力が高いので、しつけはしやすいですが、飼い始めにしっかりしたしつけをしておかないと吠え癖や噛み癖が出てきてしまう事があるでしょう。
トイプードルの値段は、20~30万円となっています。
 タイニープードルはアメリカで作出されたサイズで、日本のJKCではまだ非公認となっています。
体高25㎝以下で、体重は2~3㎏とトイプードルよりもさらに小さなサイズです。
骨格が小さく鼻の長さが短めの傾向があり、作出が難しく、サイズがまだ不安定で思ったより大きくなる事もあります。
飼う時には、信頼できるブリーダーで親や祖父母犬のサイズまで確認するようにして下さい。
性格は明るく賢い反面、神経質な部分もあるので、留守が多い家庭はメンタル面にも気を配る必要が出てきます。
タイニープードルの値段は、20~45万円となっています。
タイニープードルはアメリカで作出されたサイズで、日本のJKCではまだ非公認となっています。
体高25㎝以下で、体重は2~3㎏とトイプードルよりもさらに小さなサイズです。
骨格が小さく鼻の長さが短めの傾向があり、作出が難しく、サイズがまだ不安定で思ったより大きくなる事もあります。
飼う時には、信頼できるブリーダーで親や祖父母犬のサイズまで確認するようにして下さい。
性格は明るく賢い反面、神経質な部分もあるので、留守が多い家庭はメンタル面にも気を配る必要が出てきます。
タイニープードルの値段は、20~45万円となっています。
 ティーカッププードルもアメリカで作出され、日本のJKCではまだ非公認となっています。
体高23㎝以下で体重は2㎏、ティーカップに入れれるほどの小ささからその名前が付けられたと言われています。
骨や関節が弱い場面があり、ちょっとした段差が負担になってしまいますので、散歩や家の中の環境に気を遣う必要が出てくるでしょう。
基本のプードルの性格に加え、怖がりで神経質な面があります。甘えん坊なので飼い主さんに対する依存が高まりやすく、メンタル面には注意が必要です。
ティーカッププードルの値段は、30~40万円で飼育件数が少ない種類になりますので、信頼できるブリーダーから購入する事をおすすめします。
ティーカッププードルもアメリカで作出され、日本のJKCではまだ非公認となっています。
体高23㎝以下で体重は2㎏、ティーカップに入れれるほどの小ささからその名前が付けられたと言われています。
骨や関節が弱い場面があり、ちょっとした段差が負担になってしまいますので、散歩や家の中の環境に気を遣う必要が出てくるでしょう。
基本のプードルの性格に加え、怖がりで神経質な面があります。甘えん坊なので飼い主さんに対する依存が高まりやすく、メンタル面には注意が必要です。
ティーカッププードルの値段は、30~40万円で飼育件数が少ない種類になりますので、信頼できるブリーダーから購入する事をおすすめします。
 今回はプードルについてご紹介してきました。
主流になっているトイプードルをイメージしていましたが、プードルにも様々な大きさや性格があるのがわかりましたね。
ペットショップで購入できる種類もいますが、できれば信頼できるブリーダーを探しそこで購入する事をおすすめします。
今回はプードルについてご紹介してきました。
主流になっているトイプードルをイメージしていましたが、プードルにも様々な大きさや性格があるのがわかりましたね。
ペットショップで購入できる種類もいますが、できれば信頼できるブリーダーを探しそこで購入する事をおすすめします。  遊んでいるときやリラックスしているとき、猫はあお向けスタイルになります。お腹を見せるときは降参を意味していると思っている人が多いかと思います。
実施はそうではないようです。動物はお腹を見せたら、降参もしくは服従していることを表していると言われています。
しかし、猫の場合、猫同士がケンカをした際、劣勢になったほうがお腹を見せます。お腹を見せると不利に感じられますが、あお向けになることで前足で相手を抱え込んで噛みつき、後ろ足でキックしたり攻撃できるからです。
つまり、猫がお腹を見せるのは、反撃体制のためであり、降参を意味するのではないということです。
遊んでいるときやリラックスしているとき、猫はあお向けスタイルになります。お腹を見せるときは降参を意味していると思っている人が多いかと思います。
実施はそうではないようです。動物はお腹を見せたら、降参もしくは服従していることを表していると言われています。
しかし、猫の場合、猫同士がケンカをした際、劣勢になったほうがお腹を見せます。お腹を見せると不利に感じられますが、あお向けになることで前足で相手を抱え込んで噛みつき、後ろ足でキックしたり攻撃できるからです。
つまり、猫がお腹を見せるのは、反撃体制のためであり、降参を意味するのではないということです。
 とは言え、お腹は、内臓が詰まっている大切な場所です。誰にでもお腹を見せる訳ではなく、心を許している飼い主さんへ見せることが多いです。
ケンカの際の反撃体制とは違って、飼い主さんへお腹を見せるというのは別の意味があります。お腹を見せる理由を5つご紹介していきたいと思います。
とは言え、お腹は、内臓が詰まっている大切な場所です。誰にでもお腹を見せる訳ではなく、心を許している飼い主さんへ見せることが多いです。
ケンカの際の反撃体制とは違って、飼い主さんへお腹を見せるというのは別の意味があります。お腹を見せる理由を5つご紹介していきたいと思います。
 メスの猫がお腹を見せて体をくねくねしていることがあるのは発情期が考えられます。
メス猫で、避妊手術をしていないと、生後半年くらい経ったあとの春や秋の初めに発情期になる可能性があります。
メス猫は発情期になると、コロンと転がり、背中を床に擦り付けてくねくねと体を動かすことで、オス猫にアピールします。そうすることでオス猫が寄ってくるのです。
室内で、オス猫がいない環境であっても、発情期になると、コロンと転がってくねくね体を動かして大きな声鳴くようなります。
メスの猫がお腹を見せて体をくねくねしていることがあるのは発情期が考えられます。
メス猫で、避妊手術をしていないと、生後半年くらい経ったあとの春や秋の初めに発情期になる可能性があります。
メス猫は発情期になると、コロンと転がり、背中を床に擦り付けてくねくねと体を動かすことで、オス猫にアピールします。そうすることでオス猫が寄ってくるのです。
室内で、オス猫がいない環境であっても、発情期になると、コロンと転がってくねくね体を動かして大きな声鳴くようなります。
 猫がお腹を見せる理由についてご紹介してきましたがいかがでしたでしょうか。
ケンカなどをして降参しているということではなく、主に飼い主さんへの信頼の現れであったり、リラックスしている、あるいは暑いと感じているということなどお分かりいただけたかと思います。
それはなによりも、猫は安心できると感じる場所でなければこのような行動をすることはありません。
あなたの愛猫がこのような行動を見せることがあれば、それは、あなたを信頼し、安心できる環境であると感じているほかありません。そのような関係や環境づくりができるといいですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
猫がお腹を見せる理由についてご紹介してきましたがいかがでしたでしょうか。
ケンカなどをして降参しているということではなく、主に飼い主さんへの信頼の現れであったり、リラックスしている、あるいは暑いと感じているということなどお分かりいただけたかと思います。
それはなによりも、猫は安心できると感じる場所でなければこのような行動をすることはありません。
あなたの愛猫がこのような行動を見せることがあれば、それは、あなたを信頼し、安心できる環境であると感じているほかありません。そのような関係や環境づくりができるといいですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。



 犬の心臓病への治療薬は初期段階では、血管拡張薬という血液の巡りを良くして心臓の負担を軽くする薬を使用します。
しかし、投薬を行うという事は、体に何らかの変化を与える事にもなりますので、その変化を飼い主さんはきちんと理解しておく必要があるでしょう。
犬の心臓病への治療薬は初期段階では、血管拡張薬という血液の巡りを良くして心臓の負担を軽くする薬を使用します。
しかし、投薬を行うという事は、体に何らかの変化を与える事にもなりますので、その変化を飼い主さんはきちんと理解しておく必要があるでしょう。
 今回は犬の心臓病についてご紹介してきました。
今回は犬の心臓病についてご紹介してきました。
 猫にとって腎臓病は避けては通れない病気です。腎臓は体の中を流れる血液を濾過し、老廃物は尿として体外へ排出させ、必要な栄養分は再吸収しています。
猫にとって腎臓病は避けては通れない病気です。腎臓は体の中を流れる血液を濾過し、老廃物は尿として体外へ排出させ、必要な栄養分は再吸収しています。
 猫の慢性腎臓病に使われている治療薬は2種類あります。1つはセミントラ、もう1つはラプロスです。
猫の慢性腎臓病に使われている治療薬は2種類あります。1つはセミントラ、もう1つはラプロスです。
 猫にとって腎臓病はついてまわる病気です。
猫にとって腎臓病はついてまわる病気です。
 猫の場合は、飼い主さんが100%爪のケアをしてあげないといけませんので、まずは猫の爪の構造を知っておく事が大切です。
爪の根本にあるピンク色の部分には、血管と神経が通っており、誤って切ってしまうと痛みと共に出血も伴ってしまいますので注意が必要です。
定期的なケアが必要な理由は長期間爪を伸ばしたままにしておくと、血管と神経も一緒に伸びてくる事になり、短くするためには血管と神経も一緒に切ってしまわないといけなくなってしまうためです。
そうなると猫に対しとても苦痛を強いる事になってしまい可哀想ですよね。
猫の場合は、飼い主さんが100%爪のケアをしてあげないといけませんので、まずは猫の爪の構造を知っておく事が大切です。
爪の根本にあるピンク色の部分には、血管と神経が通っており、誤って切ってしまうと痛みと共に出血も伴ってしまいますので注意が必要です。
定期的なケアが必要な理由は長期間爪を伸ばしたままにしておくと、血管と神経も一緒に伸びてくる事になり、短くするためには血管と神経も一緒に切ってしまわないといけなくなってしまうためです。
そうなると猫に対しとても苦痛を強いる事になってしまい可哀想ですよね。

 猫の爪切りはハードルが高いイメージですが、次にご紹介する4つのステップを踏めばスムーズに爪切りを行う事ができるでしょう。
猫の爪切りはハードルが高いイメージですが、次にご紹介する4つのステップを踏めばスムーズに爪切りを行う事ができるでしょう。
 では、最後に愛猫の爪を切る際に便利なグッズをご紹介したいと思います。
今は様々な爪切りグッズを販売していますので、その中でも人気があるものを
では、最後に愛猫の爪を切る際に便利なグッズをご紹介したいと思います。
今は様々な爪切りグッズを販売していますので、その中でも人気があるものを 今回は猫の爪切りについてご紹介してきました。
猫は犬と違って動きが素早く、爪切りを察知するとすごく抵抗する子もいます。
そうなってしまった際に、爪を伸ばし過ぎていると愛猫もそうですが、飼い主さんもケガをしてしまう可能性がありますので、小さい頃から爪切りに慣らしておくの事が一番大切でしょう。
しかし、何回行っても慣れない子もいますので、そうなった場合は、スムーズの爪切りが行える手順を参考に頑張ってみて下さいね。
それでもダメな場合は、
今回は猫の爪切りについてご紹介してきました。
猫は犬と違って動きが素早く、爪切りを察知するとすごく抵抗する子もいます。
そうなってしまった際に、爪を伸ばし過ぎていると愛猫もそうですが、飼い主さんもケガをしてしまう可能性がありますので、小さい頃から爪切りに慣らしておくの事が一番大切でしょう。
しかし、何回行っても慣れない子もいますので、そうなった場合は、スムーズの爪切りが行える手順を参考に頑張ってみて下さいね。
それでもダメな場合は、 何かの拍子にふと食べたくなるカレー。
スパイスの香りが食欲をそそります。
すると、飼い主さんが夢中で食べているかたわらに、鼻をクンクンさせて目を輝かせた愛犬が!
このおいしさをシェアしたい、してもいいのかな?と迷ってしまうかもしれません。
何かの拍子にふと食べたくなるカレー。
スパイスの香りが食欲をそそります。
すると、飼い主さんが夢中で食べているかたわらに、鼻をクンクンさせて目を輝かせた愛犬が!
このおいしさをシェアしたい、してもいいのかな?と迷ってしまうかもしれません。
 犬が人間用のカレーを食べると、どのような症状が出るのでしょうか。
犬が人間用のカレーを食べると、どのような症状が出るのでしょうか。
 玉ねぎ中毒は、主に血液に影響をもたらします。
食べたものはいったん胃で消化され、腸へと送られる中で血管に吸収されます。
その時点で赤血球の破壊が始まることになるため、症状が出るまでに早くて1日、通常は3~4日かかるようです。
玉ねぎ中毒は、主に血液に影響をもたらします。
食べたものはいったん胃で消化され、腸へと送られる中で血管に吸収されます。
その時点で赤血球の破壊が始まることになるため、症状が出るまでに早くて1日、通常は3~4日かかるようです。
 もしも犬がカレーを食べてしまったら、まずは様子を見るしかありません。
せめて、
もしも犬がカレーを食べてしまったら、まずは様子を見るしかありません。
せめて、 カレーだけでなく、犬が食べては危険な料理はたくさんあります。
カレーだけでなく、犬が食べては危険な料理はたくさんあります。
 家族全員が食卓を囲む時、一緒にいる犬だけが何も食べられないなんてかわいそう、と感じる飼い主さんも多いと思います。
しかし、「ほんの一口」が、犬の命を脅かし、苦しめる結果になったら悔やんでも悔やみきれませんよね。
どうしても犬に同じ料理を、と考えるなら、材料を切った段階で食べても問題のない食材だけを少し取り分け、油や味付けをせずに火を通して小皿に準備しておくなど、工夫して与えるようにすると良いでしょう。
家族全員が食卓を囲む時、一緒にいる犬だけが何も食べられないなんてかわいそう、と感じる飼い主さんも多いと思います。
しかし、「ほんの一口」が、犬の命を脅かし、苦しめる結果になったら悔やんでも悔やみきれませんよね。
どうしても犬に同じ料理を、と考えるなら、材料を切った段階で食べても問題のない食材だけを少し取り分け、油や味付けをせずに火を通して小皿に準備しておくなど、工夫して与えるようにすると良いでしょう。
 犬の散歩をしていると、通りすがりの家の中から犬の声が聞こえてくることがあります。
すれ違う犬同士が吠え合ったり、救急車の音とともに遠吠えが聞こえてきたりすることもあります。
犬の散歩をしていると、通りすがりの家の中から犬の声が聞こえてくることがあります。
すれ違う犬同士が吠え合ったり、救急車の音とともに遠吠えが聞こえてきたりすることもあります。
 自分の家に犬がいる家庭でも、近所の犬の吠える声が連続して聞こえると耳障りに感じることがあります。
赤ちゃんがいる家庭や、体調がすぐれない時などは、毎日その声を聞かされるのは
自分の家に犬がいる家庭でも、近所の犬の吠える声が連続して聞こえると耳障りに感じることがあります。
赤ちゃんがいる家庭や、体調がすぐれない時などは、毎日その声を聞かされるのは 犬の吠える声が激しく、自分自身が苦情を受けてしまうこともあるかもしれません。
犬の吠える声が激しく、自分自身が苦情を受けてしまうこともあるかもしれません。
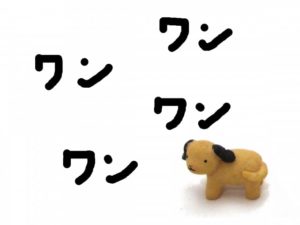 犬は、よほどのことがない限り、
犬は、よほどのことがない限り、 いきなりですが、ポメチワとはご存じでしょうか?
想像はつくかと思うのですが、ポメチワとは
いきなりですが、ポメチワとはご存じでしょうか?
想像はつくかと思うのですが、ポメチワとは
 ポメチワの値段ですが、15万円前後が平均相場のようで、比較的リーズナブルな値段になっています。
しかし、血統や外見の美しさ次第では、もう少し高くなる事もあるようです。
ポメチワの値段ですが、15万円前後が平均相場のようで、比較的リーズナブルな値段になっています。
しかし、血統や外見の美しさ次第では、もう少し高くなる事もあるようです。
 今回はポメラニアンとチワワのミックス、ポメチワについてご紹介してきました。
今回はポメラニアンとチワワのミックス、ポメチワについてご紹介してきました。
 折れた耳が愛らしいスコティッシュフォールド。
折れた耳が愛らしいスコティッシュフォールド。
 スコティッシュフォールドは、その愛らしい見た目と同様、人懐こく穏やかな性格です。
スコティッシュフォールドは、その愛らしい見た目と同様、人懐こく穏やかな性格です。
 基本的には穏やかでのんびりした性格です。
基本的には穏やかでのんびりした性格です。

 ペットを飼っているご家庭は、
ペットを飼っているご家庭は、
 犬用バリカンと一言で言っても、今は豊富な種類が販売されていますので、どのような事に重点を置いて購入すればいいのか悩んでしまうのではないでしょうか。
ネットでの購入が手っ取り早いと思うかと思いますが、
犬用バリカンと一言で言っても、今は豊富な種類が販売されていますので、どのような事に重点を置いて購入すればいいのか悩んでしまうのではないでしょうか。
ネットでの購入が手っ取り早いと思うかと思いますが、