 犬は人間のように汗腺が発達していないため、夏の暑さにとても弱い動物です。唯一汗をかけるのは、肉球の部分だけになります。
そのため体温が上昇すると、パンティングと言われる口呼吸(舌を出してハァハァする)で体温を下げようとします。
この行動が見られる前に対策をしましょう。
具体的には、これからご紹介する、冷却マット、リネン素材のベッド、保冷剤、凍ったペットボトルなどが有効です。
それぞれどのような使い方ができるかをご紹介します。
犬は人間のように汗腺が発達していないため、夏の暑さにとても弱い動物です。唯一汗をかけるのは、肉球の部分だけになります。
そのため体温が上昇すると、パンティングと言われる口呼吸(舌を出してハァハァする)で体温を下げようとします。
この行動が見られる前に対策をしましょう。
具体的には、これからご紹介する、冷却マット、リネン素材のベッド、保冷剤、凍ったペットボトルなどが有効です。
それぞれどのような使い方ができるかをご紹介します。
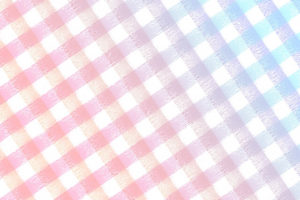 ペットショップなどでは、動物専用の冷却マットが販売されています。
動物の大きさに合わせて、A4用紙ほどのものから大型犬でも十分に利用できる、1mほどの物まで様々です。
ペットショップなどでは、動物専用の冷却マットが販売されています。
動物の大きさに合わせて、A4用紙ほどのものから大型犬でも十分に利用できる、1mほどの物まで様々です。
 「リネン」という言葉はよく耳にしますが、日本語に訳すと「亜麻布(麻)」のことを表します。
麻はサラサラした感触で熱伝導率が非常に高く、夏には人間も気持ちよく着られる素材ですよね。
このリネン素材で作られた犬用のベッドなら、夏場でも涼しさを感じられそうです。リネンは水に強いという性質も持ちます。
ベッドを長く使用していると、匂いが付いたりして少しずつ汚れも目立ってきます。
そんな時でもこのベッドなら洗濯して使うことができます。
冬場はこのベッドにフリースなどを敷いておけば暖かいベッドとしても使えますので、一つあると重宝しますよ。
「リネン」という言葉はよく耳にしますが、日本語に訳すと「亜麻布(麻)」のことを表します。
麻はサラサラした感触で熱伝導率が非常に高く、夏には人間も気持ちよく着られる素材ですよね。
このリネン素材で作られた犬用のベッドなら、夏場でも涼しさを感じられそうです。リネンは水に強いという性質も持ちます。
ベッドを長く使用していると、匂いが付いたりして少しずつ汚れも目立ってきます。
そんな時でもこのベッドなら洗濯して使うことができます。
冬場はこのベッドにフリースなどを敷いておけば暖かいベッドとしても使えますので、一つあると重宝しますよ。
 ケーキやアイスクリームを買った時などにもらえる保冷剤。ホームセンターなどではアイスボックスに入れて使えるような大きめの保冷剤も売っていますよね。
これを使って、犬の暑さ対策をすることもできます。
保冷剤を凍らせて、フェイルタオルなどで簡単な袋を作って入れておけば、犬は気が向いた時にお腹や頭を乗せてクールダウンすることができます。
タオルに包んでベッドの敷物の下に入れてあげることも良いでしょう。
保冷剤のように、繰り返し使える便利な暑さ対策グッズを利用することは、省エネにもつながります。
また、身近な物で作ることができるので、すぐに暑さ対策をしてあげられます。
ケーキやアイスクリームを買った時などにもらえる保冷剤。ホームセンターなどではアイスボックスに入れて使えるような大きめの保冷剤も売っていますよね。
これを使って、犬の暑さ対策をすることもできます。
保冷剤を凍らせて、フェイルタオルなどで簡単な袋を作って入れておけば、犬は気が向いた時にお腹や頭を乗せてクールダウンすることができます。
タオルに包んでベッドの敷物の下に入れてあげることも良いでしょう。
保冷剤のように、繰り返し使える便利な暑さ対策グッズを利用することは、省エネにもつながります。
また、身近な物で作ることができるので、すぐに暑さ対策をしてあげられます。
 今すぐ何かできないか、という時におすすめなのが、凍ったペットボトルの暑さ対策です。
手で簡単につぶせるようになっているペットボトル以外なら、どんなペットボトルでも利用できます。
凍らせたペットボトルを布に巻いて、愛犬に与えるだけなので、手軽に暑さ対策ができます。
2、3本用意しておけば、ペットボトルの中が水になってしまっても、すぐに新しいものと交換できるので、冷却を切らさずに使うことができます。
水は凍ると膨張する性質があるので、ペットボトルいっぱいに水を入れないように気をつけてくださいね。
もし立てて冷凍庫に入れられるスペースがあるなら、蓋は閉めずにラップなどで軽く閉じるようにすれば、ペットボトルが破裂することを防げますよ。
今すぐ何かできないか、という時におすすめなのが、凍ったペットボトルの暑さ対策です。
手で簡単につぶせるようになっているペットボトル以外なら、どんなペットボトルでも利用できます。
凍らせたペットボトルを布に巻いて、愛犬に与えるだけなので、手軽に暑さ対策ができます。
2、3本用意しておけば、ペットボトルの中が水になってしまっても、すぐに新しいものと交換できるので、冷却を切らさずに使うことができます。
水は凍ると膨張する性質があるので、ペットボトルいっぱいに水を入れないように気をつけてくださいね。
もし立てて冷凍庫に入れられるスペースがあるなら、蓋は閉めずにラップなどで軽く閉じるようにすれば、ペットボトルが破裂することを防げますよ。
 屋外に犬小屋を置いて飼育している場合でも、暑さ対策をすることは可能です。
室内飼育であれば、エアコンで室温を調節したり、常に愛犬の様子を見ていることができますが、屋外飼育になると常に愛犬の様子を見ていることはできません。
室内以上に屋外飼育の時は、愛犬の環境に気を配ってあげてくださいね。
次の項目で、屋外飼育の暑さ対策について見ていきましょう。
屋外に犬小屋を置いて飼育している場合でも、暑さ対策をすることは可能です。
室内飼育であれば、エアコンで室温を調節したり、常に愛犬の様子を見ていることができますが、屋外飼育になると常に愛犬の様子を見ていることはできません。
室内以上に屋外飼育の時は、愛犬の環境に気を配ってあげてくださいね。
次の項目で、屋外飼育の暑さ対策について見ていきましょう。
 犬小屋の位置を確認しましょう。
もしもずっと日光を浴びて暑くなるような場所に犬小屋を設置している場合は、犬小屋自体が熱くなってしまう危険性があります。
暑い時期は自宅の北側など、できるだけ涼しさを保てる場所に犬小屋を移動させてあげましょう。
そうすることで、犬小屋が必要以上に熱くなるのを防ぎ、涼しくしてあげることができます。
できればこの時、風通しが良く、静かに落ち着ける場所を選んであげることがベストです。
犬小屋の位置を確認しましょう。
もしもずっと日光を浴びて暑くなるような場所に犬小屋を設置している場合は、犬小屋自体が熱くなってしまう危険性があります。
暑い時期は自宅の北側など、できるだけ涼しさを保てる場所に犬小屋を移動させてあげましょう。
そうすることで、犬小屋が必要以上に熱くなるのを防ぎ、涼しくしてあげることができます。
できればこの時、風通しが良く、静かに落ち着ける場所を選んであげることがベストです。
 犬小屋を移動できない場合は、犬小屋が直射日光に当たらないような環境を整えましょう。
犬小屋の温度が上がることで、中にいる犬が熱中症になってしまう危険性があります。
よしずなどで日よけを作ってあげたり、日曜大工が得意であれば、犬小屋用を日差しから守る大きな囲いを作ってあげたりするのも良いかもしれませんね。
犬小屋と、愛犬が動く範囲を直射日光の強い日差しから遮ってあげましょう。逃げ場をたくさん作ってあげることが大切です。
犬小屋を移動できない場合は、犬小屋が直射日光に当たらないような環境を整えましょう。
犬小屋の温度が上がることで、中にいる犬が熱中症になってしまう危険性があります。
よしずなどで日よけを作ってあげたり、日曜大工が得意であれば、犬小屋用を日差しから守る大きな囲いを作ってあげたりするのも良いかもしれませんね。
犬小屋と、愛犬が動く範囲を直射日光の強い日差しから遮ってあげましょう。逃げ場をたくさん作ってあげることが大切です。
 夏場は食べ物が痛みやすい時期です。同時に水もすぐにぬるくなり、傷んでしまいます。
また、屋外では昆虫などが入り込んでしまうことも多いので注意が必要です。
ボールなどに水を入れて与えている場合は、小まめに交換しましょう。
氷を細かく砕いて水の中に入れておくと、少し清涼感が長持ちするのでおすすめです。
大きい氷をそのまま入れると、誤って飲み込んで詰まらせてしまうこともあるため、入れる時は細かくするのがポイントです。
夏場は食べ物が痛みやすい時期です。同時に水もすぐにぬるくなり、傷んでしまいます。
また、屋外では昆虫などが入り込んでしまうことも多いので注意が必要です。
ボールなどに水を入れて与えている場合は、小まめに交換しましょう。
氷を細かく砕いて水の中に入れておくと、少し清涼感が長持ちするのでおすすめです。
大きい氷をそのまま入れると、誤って飲み込んで詰まらせてしまうこともあるため、入れる時は細かくするのがポイントです。
 夏場は、日陰であっても地面が太陽の熱によってあたためられます。
そんな時は、ホームセンターなどで手に入るスノコを1枚置いてあげることをおすすめします。
地面に直接触れずに済むのはもちろんですが、スノコと地面の間の隙間に空気が通ることで、直接地面にいるよりも暑さを軽減することができるでしょう。
少し高額になりますが、風呂場などで使われるヒノキのスノコにすれば、耐水性もあるので長持ちします。スノコは地面の湿気からも犬の体を守ってくれます。
屋外で飼育する場合は季節に関わらず使用すると、健康管理にも役立ちそうですね。
夏場は、日陰であっても地面が太陽の熱によってあたためられます。
そんな時は、ホームセンターなどで手に入るスノコを1枚置いてあげることをおすすめします。
地面に直接触れずに済むのはもちろんですが、スノコと地面の間の隙間に空気が通ることで、直接地面にいるよりも暑さを軽減することができるでしょう。
少し高額になりますが、風呂場などで使われるヒノキのスノコにすれば、耐水性もあるので長持ちします。スノコは地面の湿気からも犬の体を守ってくれます。
屋外で飼育する場合は季節に関わらず使用すると、健康管理にも役立ちそうですね。
 屋外で飼育している場合、室内飼育よりも暑さを直接感じることになります。
暑い時期は脱水などによる夏バテにも十分注意が必要です。
いつもドライフードを与えている場合は、そのフードにスープやミルクを入れてあげたり、ウェットフードに替えたりして、栄養とともに水分が補給できるような工夫をしましょう。
食欲が無さそうな時は、少し匂いの強いレバーなどを少し添えてみるのもおすすめです。
フードを与える時は、同時に水も新しく替えてあげてくださいね。
屋外で飼育している場合、室内飼育よりも暑さを直接感じることになります。
暑い時期は脱水などによる夏バテにも十分注意が必要です。
いつもドライフードを与えている場合は、そのフードにスープやミルクを入れてあげたり、ウェットフードに替えたりして、栄養とともに水分が補給できるような工夫をしましょう。
食欲が無さそうな時は、少し匂いの強いレバーなどを少し添えてみるのもおすすめです。
フードを与える時は、同時に水も新しく替えてあげてくださいね。
 ブラッシングは犬の健康管理において、室内飼育、屋外飼育に限らず必要なものですが、特に屋外飼育の場合は、小まめにブラッシングをしましょう。
犬の内側のふわふわした毛(アンダーコート)を取り除いてあげることで、体の風通しが良くなります。また、屋外にいると、ノミ、ダニ、蚊などの害虫も付きやすくなります。
予防薬はもちろん、ブラッシングをすることで、こうした害虫の除去もできます。
いつもよりもシャンプーの回数を増やすことでも、不要なアンダーコートを取り除くことができます。
シャンプーすれば皮膚も清潔に保つことができますので、ブラッシングと並行して行うと良いでしょう。
ブラッシングは犬の健康管理において、室内飼育、屋外飼育に限らず必要なものですが、特に屋外飼育の場合は、小まめにブラッシングをしましょう。
犬の内側のふわふわした毛(アンダーコート)を取り除いてあげることで、体の風通しが良くなります。また、屋外にいると、ノミ、ダニ、蚊などの害虫も付きやすくなります。
予防薬はもちろん、ブラッシングをすることで、こうした害虫の除去もできます。
いつもよりもシャンプーの回数を増やすことでも、不要なアンダーコートを取り除くことができます。
シャンプーすれば皮膚も清潔に保つことができますので、ブラッシングと並行して行うと良いでしょう。
 日中、犬がひとりでお留守番する時、当然防犯対策として、しっかり窓を閉めて出かけることになると思います。
閉め切った室内は空気が動かず、窓から差し込む日光で室温はどんどん上昇します。
初めにお話ししたとおり、犬は肉球以外で汗をかくことができないため、室温の上昇とともに体温も上がってしまいます。
犬が過ごす場所の日照環境にもよりますが、外気温が25℃を超えるような日の留守番はエアコンの使用が必要になることがあります。
日中、犬がひとりでお留守番する時、当然防犯対策として、しっかり窓を閉めて出かけることになると思います。
閉め切った室内は空気が動かず、窓から差し込む日光で室温はどんどん上昇します。
初めにお話ししたとおり、犬は肉球以外で汗をかくことができないため、室温の上昇とともに体温も上がってしまいます。
犬が過ごす場所の日照環境にもよりますが、外気温が25℃を超えるような日の留守番はエアコンの使用が必要になることがあります。
 梅雨のない北海道は別として、日本の夏場の気候は高温多湿になります。
この時期は人間がいてもいなくても、愛犬のために24時間エアコンをフル稼働させることをおすすめします。
特に子犬やシニア犬は抵抗力が落ちていますので、クーラーは必須です。
子犬は自分が脱水になっていても気づかずにはしゃいでしまい、どうにもならなくなって初めて倒れ込むということもあります。
元気だから大丈夫だと安心していると、突然意識を失うようなこともありますので油断しないようにしましょう。
マンションの高層階で風通しが良く夜間は涼しいということであれば、日中だけの使用でも問題ありませんが、人間以上に犬は暑さを感じやすいので、注意してあげてくださいね。
梅雨のない北海道は別として、日本の夏場の気候は高温多湿になります。
この時期は人間がいてもいなくても、愛犬のために24時間エアコンをフル稼働させることをおすすめします。
特に子犬やシニア犬は抵抗力が落ちていますので、クーラーは必須です。
子犬は自分が脱水になっていても気づかずにはしゃいでしまい、どうにもならなくなって初めて倒れ込むということもあります。
元気だから大丈夫だと安心していると、突然意識を失うようなこともありますので油断しないようにしましょう。
マンションの高層階で風通しが良く夜間は涼しいということであれば、日中だけの使用でも問題ありませんが、人間以上に犬は暑さを感じやすいので、注意してあげてくださいね。
 昼間の12時から15時ころは、1日の中で一番気温が上昇する時間帯です。
この時間帯はエアコンをタイマーセットで点け、扇風機で室内の空気を循環させると、効率良く室内温度を一定に保つことができます。
時期や地域によっては、西日でも室温が急上昇しますので、タイマーセットの時間帯を長めに取るようにしてください。
エアコンからの冷気は、室内の下に向かって流れて滞留します。
エアコンの風が来る辺りに扇風機を設置し、真上に向かって風を当てることで、冷たい空気が上に昇り、暖かい空気が下に降りてきて冷やされ、エネルギーが無駄にならずに室内を冷やすことができます。
昼間の12時から15時ころは、1日の中で一番気温が上昇する時間帯です。
この時間帯はエアコンをタイマーセットで点け、扇風機で室内の空気を循環させると、効率良く室内温度を一定に保つことができます。
時期や地域によっては、西日でも室温が急上昇しますので、タイマーセットの時間帯を長めに取るようにしてください。
エアコンからの冷気は、室内の下に向かって流れて滞留します。
エアコンの風が来る辺りに扇風機を設置し、真上に向かって風を当てることで、冷たい空気が上に昇り、暖かい空気が下に降りてきて冷やされ、エネルギーが無駄にならずに室内を冷やすことができます。
 犬によって暑さや寒さの感じ方は違いますが、夏場は人間よりもバテやすくなっています。
散歩の時間や日中の過ごし方などに配慮して、犬が少しでも快適に、元気に夏を乗り切れるようにしてあげたいですね。
暑さ対策は、エアコンの使用や身近なものを使った工夫で、思ったよりも簡単に行うことができます。
是非、気温が上がる時期になる前に、しっかりと対策をしてあげてくださいね。
犬によって暑さや寒さの感じ方は違いますが、夏場は人間よりもバテやすくなっています。
散歩の時間や日中の過ごし方などに配慮して、犬が少しでも快適に、元気に夏を乗り切れるようにしてあげたいですね。
暑さ対策は、エアコンの使用や身近なものを使った工夫で、思ったよりも簡単に行うことができます。
是非、気温が上がる時期になる前に、しっかりと対策をしてあげてくださいね。  犬は当然ですが、全身を被毛で覆われています。
猫のように自分で毛づくろいすることもなく、人間が放っておけば、その被毛は伸び続けたり柔らかいアンダーコートが絡み合って皮膚を傷めたり、毛玉で身動きが取れなくなるようなこともあります。
だからブラッシングは飼い主さんが行う必要があります。でも、犬のブラッシングって実はその他にも様々な効果があります。
犬のブラッシングの必要性について、詳しく見ていきましょう。
犬は当然ですが、全身を被毛で覆われています。
猫のように自分で毛づくろいすることもなく、人間が放っておけば、その被毛は伸び続けたり柔らかいアンダーコートが絡み合って皮膚を傷めたり、毛玉で身動きが取れなくなるようなこともあります。
だからブラッシングは飼い主さんが行う必要があります。でも、犬のブラッシングって実はその他にも様々な効果があります。
犬のブラッシングの必要性について、詳しく見ていきましょう。
 それでは、実際にブラッシングを行うのは、どのくらいの頻度が最適なのでしょうか。
犬には短毛種、長毛種で被毛の様子が大きく異なります。
また、換毛期の有無やシングルコート、ダブルコートでも変わってきます。
ここでは大きく短毛種と長毛種に分けてお話ししていきましょう。
それでは、実際にブラッシングを行うのは、どのくらいの頻度が最適なのでしょうか。
犬には短毛種、長毛種で被毛の様子が大きく異なります。
また、換毛期の有無やシングルコート、ダブルコートでも変わってきます。
ここでは大きく短毛種と長毛種に分けてお話ししていきましょう。
 スムースコート・チワワ、フレンチブルドッグ、イタリアン・グレーハウンド、ラブラドールレトリーバーなど、
被毛が立ち上がることなく皮膚と一体化しているような短毛種の場合は、週に1回ほどのブラッシングが良いでしょう。
動くことで被毛が絡んだりすることもほとんどないため、それほど頻繁に行う必要はありません。
被毛と皮膚の距離が近いため、力を入れすぎないように注意してくださいね。
ただし、短中毛種と言われる柴犬や甲斐犬などの場合は、毎日のブラッシングが必要です。
特に換毛期は一日数回のブラッシングをおすすめします。
スムースコート・チワワ、フレンチブルドッグ、イタリアン・グレーハウンド、ラブラドールレトリーバーなど、
被毛が立ち上がることなく皮膚と一体化しているような短毛種の場合は、週に1回ほどのブラッシングが良いでしょう。
動くことで被毛が絡んだりすることもほとんどないため、それほど頻繁に行う必要はありません。
被毛と皮膚の距離が近いため、力を入れすぎないように注意してくださいね。
ただし、短中毛種と言われる柴犬や甲斐犬などの場合は、毎日のブラッシングが必要です。
特に換毛期は一日数回のブラッシングをおすすめします。
 ヨークシャーテリア、シーズー、アフガンハウンド、ゴールデンレトリーバーなどに代表される長毛種の場合は、
週に2~3回はブラッシングをしてあげると良いでしょう。
特に洋服を着せたり、ハーネスを付けたりして散歩をさせるようであれば、前足の内側の毛が絡みやすくなるため、毎日ブラッシングでほぐすことをおすすめします。長毛種は短毛種に比べて、当然被毛が絡みやすくなります。
また、地面にこすって汚れやすくもなりますし、毛の中に草の実や虫も入りやすくなります。短毛種よりも注意が必要です。
毛が細く絡みやすい場合は、ブラッシングスプレーなどを使用すると、とかしやすくなり、被毛のコーティングもできます。
静電気を抑える効果もありますので、長毛種はスプレーを使用するのが効果的です。
ヨークシャーテリア、シーズー、アフガンハウンド、ゴールデンレトリーバーなどに代表される長毛種の場合は、
週に2~3回はブラッシングをしてあげると良いでしょう。
特に洋服を着せたり、ハーネスを付けたりして散歩をさせるようであれば、前足の内側の毛が絡みやすくなるため、毎日ブラッシングでほぐすことをおすすめします。長毛種は短毛種に比べて、当然被毛が絡みやすくなります。
また、地面にこすって汚れやすくもなりますし、毛の中に草の実や虫も入りやすくなります。短毛種よりも注意が必要です。
毛が細く絡みやすい場合は、ブラッシングスプレーなどを使用すると、とかしやすくなり、被毛のコーティングもできます。
静電気を抑える効果もありますので、長毛種はスプレーを使用するのが効果的です。
 ブラッシングには、犬とのスキンシップや健康管理などのメリットがたくさんありますが、中にはどうしても嫌がってやらせてくれない犬もいることでしょう。
そんな犬をブラッシング好きにするにはどうしたら良いのでしょうか?
これからお話しすることに心当たりがあれば、ちょっと気をつけてあげると変わるかもしれませんよ!
ブラッシングには、犬とのスキンシップや健康管理などのメリットがたくさんありますが、中にはどうしても嫌がってやらせてくれない犬もいることでしょう。
そんな犬をブラッシング好きにするにはどうしたら良いのでしょうか?
これからお話しすることに心当たりがあれば、ちょっと気をつけてあげると変わるかもしれませんよ!
 どうせブラッシングをやるのなら、徹底的にやりたい!毛玉全滅が目標!
もしかしたら、そんな風に意気込んでブラッシングをしていませんか?
もしも愛犬が遊びたいと思っている時に長時間おとなしくするように強制したり、毛玉をほぐしたいからと何度も何度もブラシで毛玉を引っ張ったりしていないでしょうか。
そんな時、飼い主さんが真剣にブラッシングをする先で、肝心の犬は苦痛に耐えているかもしれません。
一度のブラッシングで全身くまなく綺麗にしようとは考えない方が良いでしょう。日常的なお手入れであれば、今日は足、明日は体、という具合でも良いのです。
そして、毛玉は指でそっとほぐした後でコームやブラシでとかす方が、犬に痛みを感じさせずに済みます。
犬が落ち着いてリラックスできる時間に、優しくブラッシングしてあげることを心掛けてみると良いですよ。
どうせブラッシングをやるのなら、徹底的にやりたい!毛玉全滅が目標!
もしかしたら、そんな風に意気込んでブラッシングをしていませんか?
もしも愛犬が遊びたいと思っている時に長時間おとなしくするように強制したり、毛玉をほぐしたいからと何度も何度もブラシで毛玉を引っ張ったりしていないでしょうか。
そんな時、飼い主さんが真剣にブラッシングをする先で、肝心の犬は苦痛に耐えているかもしれません。
一度のブラッシングで全身くまなく綺麗にしようとは考えない方が良いでしょう。日常的なお手入れであれば、今日は足、明日は体、という具合でも良いのです。
そして、毛玉は指でそっとほぐした後でコームやブラシでとかす方が、犬に痛みを感じさせずに済みます。
犬が落ち着いてリラックスできる時間に、優しくブラッシングしてあげることを心掛けてみると良いですよ。
 犬は嬉しい出来事を記憶して学習します。
例えば、ブラッシングの後に大げさに褒めてあげたり、場合によっては大好物のおやつをあげたりすることで、ブラッシング=嬉しい事、美味しいこと、と記憶します。
その記憶が定着すれば、ブラシやコームは自分にとって良い事のサインです。
ブラッシングが大嫌いな犬がいきなり好きになるとは限りませんが、少なくとも飼い主さんがブラシを見せても逃げ回らずに、おとなしくやらせてくれる程度にはなるでしょう。
そこからゆっくりとブラッシングが心地よいものだということを教えてあげてくださいね。”
犬は嬉しい出来事を記憶して学習します。
例えば、ブラッシングの後に大げさに褒めてあげたり、場合によっては大好物のおやつをあげたりすることで、ブラッシング=嬉しい事、美味しいこと、と記憶します。
その記憶が定着すれば、ブラシやコームは自分にとって良い事のサインです。
ブラッシングが大嫌いな犬がいきなり好きになるとは限りませんが、少なくとも飼い主さんがブラシを見せても逃げ回らずに、おとなしくやらせてくれる程度にはなるでしょう。
そこからゆっくりとブラッシングが心地よいものだということを教えてあげてくださいね。”
 ブラッシングを好きにさせる方法の一つとして、犬が気持ちいいと感じる場所を触ってやることも効果的です。
犬は眉間から頭にかけて触られると、緊張が解けてゆったりとした気持ちになります。この辺りからブラシを当てていくとスムーズにブラッシングができるでしょう。
また、せわしなく手を動かすよりも、ゆっくりと優しくマッサージするようにブラシを動かしてやれば、より一層落ち着いてやらせてくれるのではないでしょうか。
人間がマッサージを受けるように、犬のブラッシングも静かな環境でリラクゼーションの施術のように行えると良いですね。
ブラッシングを好きにさせる方法の一つとして、犬が気持ちいいと感じる場所を触ってやることも効果的です。
犬は眉間から頭にかけて触られると、緊張が解けてゆったりとした気持ちになります。この辺りからブラシを当てていくとスムーズにブラッシングができるでしょう。
また、せわしなく手を動かすよりも、ゆっくりと優しくマッサージするようにブラシを動かしてやれば、より一層落ち着いてやらせてくれるのではないでしょうか。
人間がマッサージを受けるように、犬のブラッシングも静かな環境でリラクゼーションの施術のように行えると良いですね。
 ブラッシングは特に難しいお世話ではありませんが、やり方を間違えてしまうと犬が大嫌いなものになってしまい、思うように触らせてもらえなくなってしまいます。
完璧に綺麗にしようとは考えず、犬の気持ちよく感じる時間ややり方を工夫して、少しずつでも確実にブラッシングができる環境づくりができると良いですね。
ブラッシングは特に難しいお世話ではありませんが、やり方を間違えてしまうと犬が大嫌いなものになってしまい、思うように触らせてもらえなくなってしまいます。
完璧に綺麗にしようとは考えず、犬の気持ちよく感じる時間ややり方を工夫して、少しずつでも確実にブラッシングができる環境づくりができると良いですね。  最近の犬は室内犬が一般的になっており、外で飼うという犬は珍しいかもしれません。
しかし、家の事情などで、どうしても室内で飼えないという方もいるでしょう。ですが、冬の寒い時期に外で飼うという事に関してデメリットがあり、動物病院でも外飼いの愛犬が運ばれてくるというのも少なくないそうです。
そこで、冬の寒い時期に愛犬を外で飼うとどのような事が起こるのかご紹介しましょう。
犬というのは童謡でもあるように、雪の中でもかけまわるという寒さに強いイメージがありますが、寒さに強い犬と弱い犬がいます。
簡単に分けると、寒さに強い犬は大型犬、弱い犬は小型犬と言われています。
大型犬と言っても、毛がない犬種などは寒さに弱いようです。小型犬を外で飼うという事は滅多にないかと思いますが、寒さに弱い犬を外で飼うと下次のような事を起こってしまう可能性があります。
最近の犬は室内犬が一般的になっており、外で飼うという犬は珍しいかもしれません。
しかし、家の事情などで、どうしても室内で飼えないという方もいるでしょう。ですが、冬の寒い時期に外で飼うという事に関してデメリットがあり、動物病院でも外飼いの愛犬が運ばれてくるというのも少なくないそうです。
そこで、冬の寒い時期に愛犬を外で飼うとどのような事が起こるのかご紹介しましょう。
犬というのは童謡でもあるように、雪の中でもかけまわるという寒さに強いイメージがありますが、寒さに強い犬と弱い犬がいます。
簡単に分けると、寒さに強い犬は大型犬、弱い犬は小型犬と言われています。
大型犬と言っても、毛がない犬種などは寒さに弱いようです。小型犬を外で飼うという事は滅多にないかと思いますが、寒さに弱い犬を外で飼うと下次のような事を起こってしまう可能性があります。
 ここでは、寒さに強い犬種についてご紹介します。
寒さに強い犬は、寒い地域原産の犬種がほとんどで、特徴としては、被毛の構造だけでなく、体の大きさにも特徴があります。
小型犬種に比べ、中型・大型犬種の方が比較的寒さに強い犬と言われています。
体が、小さいと体積に比べ表面積が大きくなり、体表から体温が奪われにくくなるのに対し、体が大きいと体積に比べた表面積が小さくなり外の気温が変化しても体温が変化しにくいためです。
寒さに強い犬の秘密は被毛の構造にあり、ダブルコートである事と春から夏にかけて抜け毛が多くなるという事です。
ダブルコートの犬種は、固くて太いオーバーコートがあり、その内側に柔らかなアンダーコートという二重毛になっています。
アンダーコートは防寒の役目を果たしていますので、寒さに強い犬種は全てダブルコートです。冬になるとアンダーコートが発達し、厳しい寒さに耐える事ができるのです。
ここで、具体的な犬種をご紹介します。
・シベリアンハスキー
・サモエド
・ゴールデンレトリバー
・ラブラドールレトリバー
・コーギー
・柴犬
・秋田犬
・日本スピッツ
ここでは、寒さに強い犬種についてご紹介します。
寒さに強い犬は、寒い地域原産の犬種がほとんどで、特徴としては、被毛の構造だけでなく、体の大きさにも特徴があります。
小型犬種に比べ、中型・大型犬種の方が比較的寒さに強い犬と言われています。
体が、小さいと体積に比べ表面積が大きくなり、体表から体温が奪われにくくなるのに対し、体が大きいと体積に比べた表面積が小さくなり外の気温が変化しても体温が変化しにくいためです。
寒さに強い犬の秘密は被毛の構造にあり、ダブルコートである事と春から夏にかけて抜け毛が多くなるという事です。
ダブルコートの犬種は、固くて太いオーバーコートがあり、その内側に柔らかなアンダーコートという二重毛になっています。
アンダーコートは防寒の役目を果たしていますので、寒さに強い犬種は全てダブルコートです。冬になるとアンダーコートが発達し、厳しい寒さに耐える事ができるのです。
ここで、具体的な犬種をご紹介します。
・シベリアンハスキー
・サモエド
・ゴールデンレトリバー
・ラブラドールレトリバー
・コーギー
・柴犬
・秋田犬
・日本スピッツ
 外飼いできる寒さに強い犬種でも万が一の事がありますので、寒さ対策は必要です。
そこで、ここでは外飼いの犬にできる5つの寒さ対策をご紹介します。
外飼いできる寒さに強い犬種でも万が一の事がありますので、寒さ対策は必要です。
そこで、ここでは外飼いの犬にできる5つの寒さ対策をご紹介します。
 まずは散歩についてですが、寒くなくても必要なものになります。
犬にとって散歩というのは、必要な筋肉を作ってくれたり、新陳代謝を上げてくれるという大事なものです。そして、人間と同じように室内や散歩に行かずじっとしていると犬もストレスがかかってしまいます。
そうならないためにも、適度な運動は犬にはとてもいいものです。
しかし、かなり寒い時期に散歩をするという事に抵抗を感じる飼い主さんもいるでしょう。
そこで、ポイントになるのが、日中の暖かい時間帯に散歩をする、お腹や体を冷やさないように腹巻や服を着せてあげるという事です。
これで、寒さを感じる事なく愛犬も散歩を楽しめるでしょう。
まずは散歩についてですが、寒くなくても必要なものになります。
犬にとって散歩というのは、必要な筋肉を作ってくれたり、新陳代謝を上げてくれるという大事なものです。そして、人間と同じように室内や散歩に行かずじっとしていると犬もストレスがかかってしまいます。
そうならないためにも、適度な運動は犬にはとてもいいものです。
しかし、かなり寒い時期に散歩をするという事に抵抗を感じる飼い主さんもいるでしょう。
そこで、ポイントになるのが、日中の暖かい時間帯に散歩をする、お腹や体を冷やさないように腹巻や服を着せてあげるという事です。
これで、寒さを感じる事なく愛犬も散歩を楽しめるでしょう。
 冬の時期に外飼いをしている犬は、一日中寒い風にさらされています。
そこで、小屋も防寒対策をしてあげましょう。
例えば、小屋の外側を段ボールで覆ったり、床にジョイントマットや発泡スチロール、断熱剤などを敷く。小屋の入り口にのれんやカーテンを付けて、少しでも風や雨、雪が入ってこないようにしてあげて下さい。
最近の小屋は木製ではなく、プラスチックでできているものも多いですが、覆ってあげるだけで覆わない時と温度は全く違います。
一日中、外にいるわけですので、快適に過ごせるようにしてあげて下さいね。
冬の時期に外飼いをしている犬は、一日中寒い風にさらされています。
そこで、小屋も防寒対策をしてあげましょう。
例えば、小屋の外側を段ボールで覆ったり、床にジョイントマットや発泡スチロール、断熱剤などを敷く。小屋の入り口にのれんやカーテンを付けて、少しでも風や雨、雪が入ってこないようにしてあげて下さい。
最近の小屋は木製ではなく、プラスチックでできているものも多いですが、覆ってあげるだけで覆わない時と温度は全く違います。
一日中、外にいるわけですので、快適に過ごせるようにしてあげて下さいね。
 小屋を暖かくするというのも大事な寒さ対策なのですが、もう一つお願いしたいのが小屋を移動するという事です。
小屋を購入する際に、外で飼う事を前提とするならば、足つきの小屋の購入をおすすめします。
小屋を地面に直に置くと、地面の冷たさがそのまま伝わってしまいますので、足つきの小屋を使用する事で、温度の下がり方は緩やかになるでしょう。
既に小屋を購入してしまっている方は、すのこの上に小屋を置くという方法でも構いません。
そして、日の当たる場所に小屋を置いてあげる、雨や雪が直に当たらないように屋根の下に小屋を設置するなど、少しでも暖かい環境で快適に過ごせるよう小屋の位置も外飼いをする場合は非常に重要になります。
小屋を暖かくするというのも大事な寒さ対策なのですが、もう一つお願いしたいのが小屋を移動するという事です。
小屋を購入する際に、外で飼う事を前提とするならば、足つきの小屋の購入をおすすめします。
小屋を地面に直に置くと、地面の冷たさがそのまま伝わってしまいますので、足つきの小屋を使用する事で、温度の下がり方は緩やかになるでしょう。
既に小屋を購入してしまっている方は、すのこの上に小屋を置くという方法でも構いません。
そして、日の当たる場所に小屋を置いてあげる、雨や雪が直に当たらないように屋根の下に小屋を設置するなど、少しでも暖かい環境で快適に過ごせるよう小屋の位置も外飼いをする場合は非常に重要になります。
 外飼いをしている愛犬が老犬・子犬・そして病中病後の場合は、室内へ入れてあげて下さい。
老犬・子犬・病中病後の犬は抵抗力が弱く、寒い時期に一日中外にいる事で、感染症などの病気になってしまうリスクが非常に高まります。
ずっと外飼いをしていたのに、急に室内にという事に対し少し大変かと思いますが、大事な愛犬を病気から守るためです。
外で飼われていたため、いきなり室内となると愛犬もとまどいはあるかもしれません。ですが、すぐに慣れてくれるかと思いますよ。
外飼いをしている愛犬が老犬・子犬・そして病中病後の場合は、室内へ入れてあげて下さい。
老犬・子犬・病中病後の犬は抵抗力が弱く、寒い時期に一日中外にいる事で、感染症などの病気になってしまうリスクが非常に高まります。
ずっと外飼いをしていたのに、急に室内にという事に対し少し大変かと思いますが、大事な愛犬を病気から守るためです。
外で飼われていたため、いきなり室内となると愛犬もとまどいはあるかもしれません。ですが、すぐに慣れてくれるかと思いますよ。
 最後は、防寒グッズを利用するという事です。
例えば、使わなくなった毛布や布団など、少しでも寒さをしのげるものを活用しましょう。
そして、今は犬用の防寒グッズというのも沢山販売されています。おすすめな防寒グッズに関しては次の項目でご紹介します。
最後は、防寒グッズを利用するという事です。
例えば、使わなくなった毛布や布団など、少しでも寒さをしのげるものを活用しましょう。
そして、今は犬用の防寒グッズというのも沢山販売されています。おすすめな防寒グッズに関しては次の項目でご紹介します。
電子レンジで5分チンするだけで使える簡単湯たんぽ!専用カバーもついてます!
簡単に使用できる加熱式のペット用湯たんぽです! 電気が必要なくレンジで5分チンするだけでぽっかぽか。 外飼い用の愛犬にも快適に過ごせてもらえますよ! 洗濯可能な専用カバーもついており、アルミ断熱カバーもついていますので、暖かさを長持ちさせる事ができます。 温める際に使う専用のレンジパックついており、そこに入れてレンジでチンするので、衛生面も安心ですね。 保温持続時間の目目安は約2時間30分になっています。 人間には物足りない暖かさかもしれませんが、犬には快適な温度になっていますのでご安心下さいね!
レンジでチンして朝までぽっかぽか湯たんぽ!
加熱式のペット用湯たんぽです。 寒い時期に重宝するあったかグッズになっていますので、外飼いの愛犬にも快適に使用して頂けます。 レンジでチンしてカバーに入れて使うだけで心地良い温かさが続く保温パッドになっており、製品には炭を使用。 遠赤外線効果+アルミの断熱素材が冷気をシャットアウトしてくれ、愛犬の体を暖かく包み込んでくれます。 コードレスになっていますので、場所を選ばずどこでも使用できます。 モコモコカバーは洗濯可能で、いつでも清潔に使用できますね。 加熱する時にはレンジ用の専用パックがついていますので、レンジでチンをする際はそのパックに入れればレンジの衛星面も心配する事なく使用できます。 寒い時期の外飼いの愛犬の体を寒さから守ってあげましょう!
可愛い!ハリネズミ型簡単湯たんぽ
可愛いハリネズミ型の湯たんぽで、電子レンジでチンするだけで簡単に使用できます。 もちろん繰り返し使用も可能です。 1分~1分半の加熱でも心地よい温かさになってくれ、思わず眠くなってしまうワンちゃんの続出です! ハリネズミの素材はフワフワしており、まさにワンちゃんが好みの柔らかさ! もし舐めてしまっても有害になるエチレングリコールは入っていませんので安心して下さいね。 洗濯可能なカバーになっていますので、いつでも清潔に使って頂けます。 1度の加熱でなんと4時間暖かさが持続するんです! 一日中外にいる愛犬に1ついかがでしょうか?ト
両面使える!ボア付きマルチブランケット
片方にボア、もう片方がかつらぎ地になっており、使い分けができるマルチブランケットです。 寒い時期にはボア面を使用し、寒さがましになる時期にはかつらぎ面を使用というように、ワンちゃんが毎日快適で過ごせるように使ってあげて下さい。 日本製ですので、安心して使用して頂けます。 洗濯機OKですので、いつでも清潔な状態で使って頂く事が可能です。 老犬が立ち上がる時に踏ん張りが効くので、足の負担になりません。 嵩張らず、持ち運びが便利な上に、軽いので場所を選ばず使用できるのはうれしいですね! もちろん、外飼いの愛犬の防寒対策アイテムにももってこいの商品になっていますので、1枚いかがですか?
2枚合わせで超暖かい!毛布ブランケットです。
表面には100%超極細繊維のマイクロミンクフリース面料を使用し、裏面には厚手のシェルパを使用しているので、保温性が抜群です。 この2素材を2枚合わせにする事で、生地と生式地の間に空気の層が生まれるので、空気の断熱効果により保温力がアップします! さらにボリューム感も生まれ、フワフワした仕上がりに! マイクロミンクフリースは、ほつれにくく滑らかな肌さわりで、ミルクのような高級感のあるスタイルになっており、柔らかな肌触りで、細い繊維1本1本に空気をため込むため軽くて暖かい! シェルパ面は、ウールのような感触で、モコモコした肌触りになっており、保温性が抜群な上、繊維の密度が高いので、毛玉や毛抜けが出にくくなっています。 オールシーズン仕様になっていますので、夏はクーラーの冷え防止にも使用できますよ!
レッドチェックのおしゃれな毛布セットです!
サイズは80×60のビックサイズで大型犬でも使用できるレッドチェックの毛布セット! とても厚みがあり寒い時期でも快適にしようできます。 ポリエステル製で丸洗いが可能。 2枚セットになっているので、洗い替えにもいいですね! 二重構造になっており、ずれにくくなっていますので、小屋の中に入れて愛犬が動いても安心です。 分厚いですが、軽くて場所を選びませんので、お出かけの際にも嵩張りません。 購入されたお客さまの口コミを見てみると、生地のしっかり感と大きさ、それに2枚セットでこのお値段にびっくりされており、お値段以上の商品だと好評です。 おしゃれな柄になっているので、プレゼントにも最適です!
コストパフォーマンス抜群!デザイン性も高いドッグウェアです。
送料がかかってもワンコイン近くで購入でき、ソフトでしっかりした生地になっているのでコスパ性抜群の防寒ウェアです。 愛犬にストレスを感じさせる事なく、着せる事ができますよ! サイズ展開はXS~XLで、デザインは何と8種類もありどれも可愛いキャラクター仕様になっています。 表地、裏地ともに、とてもソフトで快適な生地を使用しており、着心地もいい感じです。 伸縮性と通気性があるので、寒い冬にピッタリのウェアではないでしょうか。 夏には向いていませんが、春秋冬と年間を通して着せる事ができるウェアになっています。 丸洗いができ、何度洗っても型崩れする事なく、丈夫だという評価を頂いています。
綿100%!とっても暖かいボアジャケット
綿100%でとっても暖かいボアジャケットです。 サイズ展開はS~XLで、色はアーミーグリーン、ピンク、ブルーと3色ありますので、女の子でも男の子でも大丈夫です! ボタン式になっており、脱ぐのも着せるのも簡単なデザインになっています。 リード通しの穴もついているので、とても便利です! 洗濯可能で、多少の雨風にも耐えられ、風も通しにくくなっています。 裏地は肌に優しい綿生地を使用し、縫製もしっかりしており、型崩れしにくく柔らかくて暖かい! 散歩時や外飼いのワンちゃんに1枚いかがでしょうか? サイズがわからない場合は、1サイズ大きめのサイズを購入して下さいね。
袖や裾の赤い差し色が可愛い!!ボーダーロンパースです。
シンプルな作りになっていますが、袖や裾に赤い差し色が入っており遊び心のある可愛いデザインになっています。 サイズはS~XXLで、カラーはブラック×レッド、ブルー×レッドの2色です。 コットン100%で皮膚の弱い愛犬でも安心して着て頂け、伸縮性も高く着脱もとっても簡単! 愛犬も動きやすく快適に過ごして頂けます。 寒さ対策だけでなく、抜け毛対策や肌の保護にも最適なオールインワンロンパースです。 お腹周りを工夫して作られているので、おしっこで濡れる心配がありません。 伸縮性はありますが、個体差によって1~3センチの誤差が出る場合がありますので、必ずサイズ表で確認し、それでもわからなければ1サイズ大きめのサイズを購入する事をおすすめします!
 ペットとして猫を飼っていると、外を出歩く猫や外で飼っている場合身体の汚れが気になってきます。
猫は本来毛づくろいで自分の身体をきれいに保つことができるので、基本的にはシャンプーは必要ないと言われています。
しかし、長毛種の猫や屋外で飼っている猫のシャンプーをしたい飼い主さん向けにこの記事で解説します。
ペットとして猫を飼っていると、外を出歩く猫や外で飼っている場合身体の汚れが気になってきます。
猫は本来毛づくろいで自分の身体をきれいに保つことができるので、基本的にはシャンプーは必要ないと言われています。
しかし、長毛種の猫や屋外で飼っている猫のシャンプーをしたい飼い主さん向けにこの記事で解説します。
 ここからは、具体的に猫のシャンプーのやり方を解説します。
①必要な道具を準備する
②シャンプーの下準備
③具体的なシャンプーのやり方
猫は本来水に濡れることを嫌う動物ですので、シャンプーの段取りをマスターしてなるべく短時間で猫のシャンプーをしてあげられるようにしましょう。
ここからは、具体的に猫のシャンプーのやり方を解説します。
①必要な道具を準備する
②シャンプーの下準備
③具体的なシャンプーのやり方
猫は本来水に濡れることを嫌う動物ですので、シャンプーの段取りをマスターしてなるべく短時間で猫のシャンプーをしてあげられるようにしましょう。
 まずはたらいに汲んでおいたお湯の中にゆっくり足から浸けていきます。
シャンプーに慣れている子であればシャワーで直接顔から遠い方から身体を濡らします。
シャワーヘッドをなるべく猫の身体に密着させて嫌がらない程度の優しい水圧に調整します。
シャワーを怖がる猫は、たらいのお湯を少しずつ手ですくいながら身体の毛を濡らします。
被毛だけではなく、毛の根元の皮膚までしっかり濡らすように意識しましょう。怖がらなくても大丈夫だよ、と優しくいつも通りのトーンで話しかけながら行うことで猫も安心感を得られます。
まずはたらいに汲んでおいたお湯の中にゆっくり足から浸けていきます。
シャンプーに慣れている子であればシャワーで直接顔から遠い方から身体を濡らします。
シャワーヘッドをなるべく猫の身体に密着させて嫌がらない程度の優しい水圧に調整します。
シャワーを怖がる猫は、たらいのお湯を少しずつ手ですくいながら身体の毛を濡らします。
被毛だけではなく、毛の根元の皮膚までしっかり濡らすように意識しましょう。怖がらなくても大丈夫だよ、と優しくいつも通りのトーンで話しかけながら行うことで猫も安心感を得られます。
 猫の身体がしっかり濡れたらシャンプーで洗っていきます。シャンプーは必ず猫専用のものを使いましょう。
人間用はもちろん、犬用でも皮膚に悪影響を与えることがあります。猫用のリンスインシャンプ―や泡が出てくるプッシュタイプも販売されています。
猫は顔が濡れることを嫌がりますので、なるべく顔から遠いところから洗います。
四肢や肛門、しっぽは汚れが気になるものの触られるのを嫌がる部分でもあります。猫が嫌がる前にササっと終わらせましょう。
顔を洗うときはシャンプーはつけずに、ぬるま湯だけでそっと拭き取るようにします。耳や鼻に水が入らないように気をつけましょう。
猫の身体がしっかり濡れたらシャンプーで洗っていきます。シャンプーは必ず猫専用のものを使いましょう。
人間用はもちろん、犬用でも皮膚に悪影響を与えることがあります。猫用のリンスインシャンプ―や泡が出てくるプッシュタイプも販売されています。
猫は顔が濡れることを嫌がりますので、なるべく顔から遠いところから洗います。
四肢や肛門、しっぽは汚れが気になるものの触られるのを嫌がる部分でもあります。猫が嫌がる前にササっと終わらせましょう。
顔を洗うときはシャンプーはつけずに、ぬるま湯だけでそっと拭き取るようにします。耳や鼻に水が入らないように気をつけましょう。
 しっかりシャンプーで洗えたらシャンプーを流します。シャンプー後にすぐ猫は顔を洗ったり毛づくろいをしようとします。
猫が舐めてしまわないよう、流し残しがないようにしっかり流しましょう。
顔を流すのを嫌がる場合は、後頭部からゆっくりお湯をかけて流すか、スポンジにお湯を含ませて拭き洗いにしてあげましょう。
流すときのシャンプーの温度は37~38度のぬるま湯にします。濡らす時とおなじ方法でシャワーかたらいにきれいなお湯を汲みなおして流していきます。
しっかりシャンプーで洗えたらシャンプーを流します。シャンプー後にすぐ猫は顔を洗ったり毛づくろいをしようとします。
猫が舐めてしまわないよう、流し残しがないようにしっかり流しましょう。
顔を流すのを嫌がる場合は、後頭部からゆっくりお湯をかけて流すか、スポンジにお湯を含ませて拭き洗いにしてあげましょう。
流すときのシャンプーの温度は37~38度のぬるま湯にします。濡らす時とおなじ方法でシャワーかたらいにきれいなお湯を汲みなおして流していきます。
 猫はドライヤーを嫌う子が多いです。その理由は、猫の聴覚が人の3倍近くあるため、ドライヤーの「ゴー」という大きな音を怖がります。
幼猫期からシャンプーとドライヤーをして慣れている子もいます。スイッチを入れても逃げ出さないようであれば、ドライヤーを使って乾かします。
ドライヤーが難しい場合は、吸水性の高いタオルを使ってタオルドライでしっかり拭きます。
長時間濡れたままにしておくと体調を崩す恐れがありますので、部屋の中を暖かくしておきましょう。暖かい季節や気温の高い日をシャンプーの日を選ぶことも大切です。
猫はドライヤーを嫌う子が多いです。その理由は、猫の聴覚が人の3倍近くあるため、ドライヤーの「ゴー」という大きな音を怖がります。
幼猫期からシャンプーとドライヤーをして慣れている子もいます。スイッチを入れても逃げ出さないようであれば、ドライヤーを使って乾かします。
ドライヤーが難しい場合は、吸水性の高いタオルを使ってタオルドライでしっかり拭きます。
長時間濡れたままにしておくと体調を崩す恐れがありますので、部屋の中を暖かくしておきましょう。暖かい季節や気温の高い日をシャンプーの日を選ぶことも大切です。
 猫の毛は二層構造になっています。上毛と下毛があり乾きにくくなっています。吸水性の高いタオルで拭いた後に、温度の低いドライヤーで手をかざしながら根元までしっかり乾かします。
皮膚から30cmほど話した距離から風をあて、毛をかきわけながら水分を外に飛ばすイメージで乾かしましょう。
ドライヤーの風をあてながらブラシで毛をかきわけたり、タオルで拭きあげながら風を当てると乾きが早くなるので試してみてくださいね。
ドライヤーを怖がる猫におすすめなのが布団乾燥機で乾かす方法です。
布団乾燥機は音もドライヤーより小さく、広範囲に優しい音風があたるので比較的穏やかに猫の毛を乾かすことができます。
同様に、ファンヒーターで乾かしたり、こたつの近くで自然乾燥させている人もいるようです。家の猫に合った乾かし方を見つけてみてくださいね。
猫の毛は二層構造になっています。上毛と下毛があり乾きにくくなっています。吸水性の高いタオルで拭いた後に、温度の低いドライヤーで手をかざしながら根元までしっかり乾かします。
皮膚から30cmほど話した距離から風をあて、毛をかきわけながら水分を外に飛ばすイメージで乾かしましょう。
ドライヤーの風をあてながらブラシで毛をかきわけたり、タオルで拭きあげながら風を当てると乾きが早くなるので試してみてくださいね。
ドライヤーを怖がる猫におすすめなのが布団乾燥機で乾かす方法です。
布団乾燥機は音もドライヤーより小さく、広範囲に優しい音風があたるので比較的穏やかに猫の毛を乾かすことができます。
同様に、ファンヒーターで乾かしたり、こたつの近くで自然乾燥させている人もいるようです。家の猫に合った乾かし方を見つけてみてくださいね。
 結論から言いますと、猫に人間用のシャンプーは使ってはいけません。
人間の皮膚と猫の皮膚にいくつかの違いがあるからです。
まず一つ目が、人間と猫の皮膚のphの違いです。人間の肌は猫よりも酸性ですので、人間のシャンプーは猫にとって酸性が強すぎます。
二つ目に、猫は人間と違って汗腺がありません。
ですので、猫に人間用のシャンプーを使うと毛や皮膚が乾きすぎてしまいます。猫の肌トラブルは感染症にかかりやすくなる可能性があります。
この二つの理由から、猫には人間用シャンプーは使わないようにしましょう。
結論から言いますと、猫に人間用のシャンプーは使ってはいけません。
人間の皮膚と猫の皮膚にいくつかの違いがあるからです。
まず一つ目が、人間と猫の皮膚のphの違いです。人間の肌は猫よりも酸性ですので、人間のシャンプーは猫にとって酸性が強すぎます。
二つ目に、猫は人間と違って汗腺がありません。
ですので、猫に人間用のシャンプーを使うと毛や皮膚が乾きすぎてしまいます。猫の肌トラブルは感染症にかかりやすくなる可能性があります。
この二つの理由から、猫には人間用シャンプーは使わないようにしましょう。
 ここでは、猫のシャンプーによるストレスを抑える無香料・微香料の猫用シャンプーを全部で五つ紹介します。ペットショップやホームセンターでも猫用シャンプーは購入できますが、ネットで購入した方がお買い得な場合がありますので、値段や送料を兼ね合わせて購入の参考にしてみてください。
ここでは、猫のシャンプーによるストレスを抑える無香料・微香料の猫用シャンプーを全部で五つ紹介します。ペットショップやホームセンターでも猫用シャンプーは購入できますが、ネットで購入した方がお買い得な場合がありますので、値段や送料を兼ね合わせて購入の参考にしてみてください。
細かな泡が毛の間に入り込んですっきり汚れを落とす!
キャットフォーミングシャンプーは、水を使わずに拭き取るタイプのシャンプーです。 界面活性剤なし、ノンアルコール、超電解イオン水でシャンプーができる皮膚に優しいシャンプーになっています。 シャンプー後に身体を舐めて毛づくろいをするけれど、洗い流してない身体を舐めて大丈夫かな?と心配になる人もいると思いますが、猫が口に入れても安全な天然成分100%・精油不使用です。 シャンプーの泡をを被毛全体に揉みこんだら、コーミングとドライヤーでサッと乾かしてシャンプー完了という手軽さで人気の商品です。 香りは「無香料」と「ダマスクローズ」2種類がありますので、無香料をお求めの場合は購入の際に注意しましょう。
猫の身体を洗浄・消臭・除菌できる無香料の拭き取るシャンプー!
ウォーターレスシャンプー無香料は、天然由来成分で洗浄・消臭・除菌ができる拭きとるタイプの簡易シャンプーです。 泡ムースタイプなので、おしり周りや四肢の部分シャンプーにおすすめです。 濡らしたり乾かしたりする手間が省けるのは猫にとっても飼い主にとっても良いことですね。 汗腺がない猫はシャンプー後に毛が水分不足でパサつくことがありますが、保湿成分フコイダンが配合されているため潤いを保ってくれます! 洗い終わりに泡を濡れタオルで拭きとってあげれば、水嫌いな猫の全身洗いにも使えます。 香りが強いシャンプーは人間にとってはいい香りと感じても、猫にとっては香りが強すぎる場合がほとんどです。 このシャンプーは無香料ですので、猫にとってのストレスも軽減できるでしょう。
リンスインシャンプーが水入らずで拭き取るだけ!
ポンプ式で泡が出てくるので、猫の身体の汚れが気になる部分に泡をつけて拭き取るだけの簡単シャンプーです。 敏感な猫の肌にも刺激が少なくなるよう実験済みの商品です。猫の皮膚や被毛の気になる汚れや臭いを泡で拭き取ります。 リンスインなので静電気防止効果、花粉やハウスダストなどの付着予防、毛玉の発生予防効果が期待できます。 弱酸性・無着色・防腐剤無添加・無香料となっているので、天然素材のリンスインシャンプ―でおすすめです。 同じライオンからは、子犬子猫用の低刺激シャンプー&リンスや、顔周りも洗える泡リンスインシャンプーなど種類豊富に販売しています。 家の猫の月齢やシャンプーの好き嫌いなどに合わせて購入するシャンプーを選びましょう。
皮膚が弱い猫におすすめ!獣医もすすめる動物シャンプー
ノルバサンシャンプーは医薬部外品として人気が高い動物用シャンプーです。 身体の隅々までしっかり洗浄できて、気になるペットの嫌な臭いの消臭や外を出歩いた後の四肢の殺菌もできます。 刺激成分を含んでいないため、大人の猫だけではなく仔猫にも使用が可能です。 酢酸クロルヘキシジンがシャンプー後も皮膚を細菌や真菌から守ってくれるのがありがたいですね。 薬用とはありますが、コンディショナーが配合されているため、パサつくことなく洗い上がりの被毛もフワフワに仕上がります。 外で飼っている猫や、外を歩いて雨や水たまりで濡れて体全体の汚れが気になりだしたら、ノルバサンシャンプー0.5がおすすめです。 月齢や猫の種類を選ばずにどの子でも安心して使える優れものです。ト
皮膚が弱い猫にもにやさしい低刺激性の猫専用シャンプー!
低刺激なアミノ酸系ベースを主成分としており、シャンプーによる猫の皮膚のトラブルを予防し、安全性に特化した猫専用シャンプーです。 乾かした後は被毛がふわふわでボリーム感もアップするとして人気な商品です。 細かい泡質で滑りも良く、猫の細くて柔らかい被毛の隙間に入り込んでホコリや汚れを取り除きます。 UVカット成分が配合されており、日向ぼっこが大好きな猫の被毛と皮膚を紫外線から保護してくれます。毛色の変色や劣化を防いでくれるので、白猫や毛の色が薄い猫にはありがたい成分です。 植物性フラボノイド成分が配合されているので、おしり周りや四肢などの臭いの元から消臭し、シャンプー後も悪臭の発生を防いでくれる商品です。
天然成分100%で安心!トリートメントインで長毛種にもおすすめ
速乾サラつやトリートメント成分が細くて柔らかい猫の被毛をコーティングしてくれるので、タオルドライでも水切れ抜群です! 猫が嫌がるドライヤーの時間を短縮できるので、乾かすのに時間がかかる長毛種の猫を飼っている人に人気な猫シャンプーです。 弱酸性・無着色・無香料タイプで洗浄成分100%が植物性なので安心して使うことができます。 きめが細かく、なめらかな泡がおしり周りや臭いが気になる部分の汚れをすっきり洗い流すことが可能です。 シルクプロテインとローヤルゼリー配合で上質な仕上がりに飼い主も猫も大満足できるプレミアムシャンプーです。 値段も安くシャンプーとトリートメントが一気にできるので、仕事や家事で忙しい飼い主さんにもおすすめです。
詰め替え用が嬉しい!無添加リンスインシャンプー
パッケージを見てまず目に入るのが「無添加」の文字の動物シャンプー。防腐剤不使用の無添加リンスインシャンプーなので、でデリケート肌の猫にも安心して使うことができます。 長毛種の猫のシャンプーは量もある程度必要になるので、詰め替え用があるのが嬉しいですね。 ヤシ油を使った植物由来の洗浄成分で、ふんわり優しい泡で汚れを落とします。 アロエベラエキス、ローズマリーエキス、カミツレエキスの3種のハーブエキス配合のリンスインタイプのシャンプーで、毛のパサつきを抑えます。 シャンプーの香りはマイルドなフローラルの香りになっています。 屋外で飼っている猫や、庭の草むらで遊んだりするのが好きな猫には別売ノミとりタイプもおすすめです。
漢方とハーブが猫と飼い主の肌に優しい!
天然系素材100%の抽出物だけで作られている長毛種専用シャンプーで、猫だけでなく犬にも使えます。 香りは天然香料を使用しており、漢方やハーブ、植物エキスが配合されています。 漢方やハーブがシャンプー後に乾燥しやすい猫の肌を保湿し、汚れがつきにくくなるよう清潔に保ちます。 天然素材なので洗う人の手にもやさしい動物シャンプーです。 天然由来の洗浄成分が、毛づくろいできれいにできなかったいやな臭いや黄ばみなどの汚れをを落とす強力な洗浄力を持っています。 天然成分が長毛種の猫の被毛の根元と皮膚まで浸透し、シャンプー後もさわやかなハーブの香りが持続します。 3~15倍に薄めて使う濃縮タイプですので、長毛種でシャンプー量がたくさん必要な大型の猫にはおすすめです。
売り切れ続出!製薬会社が作る猫用シャンプー!
薬用酢酸クロルヘキシジンシャンプーは、皮膚や被毛をきれいに洗い流し、殺菌から消臭まで嬉しい効果が期待できる犬猫兼用のシャンプーです。 販売元のフジタ製薬はシャンプーの他にも犬猫用の医薬品も開発している会社です。 あまり聞きなれないクロルヘキシジンという配合成分は、実は動物病院でも多く使われている成分です。 クロルヘキシジンはフェノール系の消毒剤で、猫の皮膚トラブルによくある最近、真菌、ウィルスなどから守ってくれる抗菌作用があります。 薬品と聞くと少し心配になる人もいると思いますが、この薬用酢酸クロルヘキシジンシャンプーは毒性も刺激性も低く、濃度が低いものでもしっかりと殺菌効果を発揮します。 安全性が高く、利き目が長持ちすることで人気があります。 Amazonや楽天市場でも欠品の場合が多いので、もし気になっていて販売しているのを見かけたら購入をおすすめします。
長毛猫でもしっとりまとまるゾイックのロングシャンプー!
ペット用低刺激シャンプーを多く取り扱うZOICからロングヘア―におすすめのペットシャンプーがこのロングシャンプーです。 長毛の成猫におすすめのシャンプーで、リンスと合わせて使えば更にうるおいがあるしっとりとした仕上がりが期待できます。 シャンプー後に丁寧にコーミングしてあげることで、毛並みがまとまり、ツヤが出るのが特徴です。 複数匹飼っている方や動物病院用に4000mのものも販売されています。容器は使用後も捨てやすいように簡単に潰せるクラッシュボトルになっています。 シャンプーの香りは、自然なキンセンカの花の香りが広がりるフローラルムスクの香りです。 同じシリーズの中には、汚れがひどいときに使うゾイックNホワイトニングシャンプー、デリケートな肌の仔猫用のゾイックNパピドールシャンプーなども販売されています。
 Q1:子犬・子猫用シャンプーは何歳まで使える?
A1:泡タイプ、低刺激など、子犬・子猫用のシャンプーは成犬・成猫にも多くのメリットがあります。年齢に関わらず、成長してからも使用しても問題ありません。
Q2:シャンプーが大嫌いで自宅でトライしたところ、大暴れしたため諦めました。短毛で室内飼育ですが、シャンプーは必要ですか?
A2:短毛種であれば無理にシャンプーをする必要はありません。猫は本来体臭も少なく、毛づくろいができるので身体をきれいに保つことができます。長毛種であったり、太り過ぎて毛づくろいが上手にできない部分は人間の手で洗ってあげる必要が出てきます。
Q3:猫は生後何ヶ月からシャンプーしても大丈夫でしょうか?
A3:猫のシャンプーは早くても生後3~4ヶ月以降にしましょう。それまでは、拭くタイプのペット用ウェットシートなどで汚れは拭き取ってあげます。
Q1:子犬・子猫用シャンプーは何歳まで使える?
A1:泡タイプ、低刺激など、子犬・子猫用のシャンプーは成犬・成猫にも多くのメリットがあります。年齢に関わらず、成長してからも使用しても問題ありません。
Q2:シャンプーが大嫌いで自宅でトライしたところ、大暴れしたため諦めました。短毛で室内飼育ですが、シャンプーは必要ですか?
A2:短毛種であれば無理にシャンプーをする必要はありません。猫は本来体臭も少なく、毛づくろいができるので身体をきれいに保つことができます。長毛種であったり、太り過ぎて毛づくろいが上手にできない部分は人間の手で洗ってあげる必要が出てきます。
Q3:猫は生後何ヶ月からシャンプーしても大丈夫でしょうか?
A3:猫のシャンプーは早くても生後3~4ヶ月以降にしましょう。それまでは、拭くタイプのペット用ウェットシートなどで汚れは拭き取ってあげます。  柔軟な体を持った猫は、色々な座り方ができますね。
猫の座り方には特徴と名前があり、座り方を見ただけでその時の猫の気持ちが分かるんですよ。
まわりに敵もなくリラックスしている時、逆にちょっと警戒している時、遊んで欲しい、ご飯が欲しいと何かをねだっている時。
もしかするとその座り方は、信頼している飼い主さんの前でしか見せない姿かもしれません。よく知られている座り方には6種類あり、猫が今どんな気持ちでいるのかを知って、もっと猫との絆を深めていきましょう。
柔軟な体を持った猫は、色々な座り方ができますね。
猫の座り方には特徴と名前があり、座り方を見ただけでその時の猫の気持ちが分かるんですよ。
まわりに敵もなくリラックスしている時、逆にちょっと警戒している時、遊んで欲しい、ご飯が欲しいと何かをねだっている時。
もしかするとその座り方は、信頼している飼い主さんの前でしか見せない姿かもしれません。よく知られている座り方には6種類あり、猫が今どんな気持ちでいるのかを知って、もっと猫との絆を深めていきましょう。
 猫がいつもと違う座り方をしていたら、ちょっと気をつけて様子をみてあげてください。それは病気や怪我によるため、座り方を変えているのかもしれません。
痛い所をかばうと普段と違う座り方をします。シニア猫ならなおさらです。少しでもおかしいなと感じたら、よく観察し早めに動物病院経連れて行ってあげることをおすすめします。
猫がいつもと違う座り方をしていたら、ちょっと気をつけて様子をみてあげてください。それは病気や怪我によるため、座り方を変えているのかもしれません。
痛い所をかばうと普段と違う座り方をします。シニア猫ならなおさらです。少しでもおかしいなと感じたら、よく観察し早めに動物病院経連れて行ってあげることをおすすめします。
 「猫の座りダコ」ご存知ですか?猫のカカト部分に小さなハゲた部分があれば、それが座りダコです。
猫は家の中で固いフローリングや畳の上に座ることにより、カカトに体重がかかっており、そのためにタコができてしまうのです。
ハゲてしまうのはフローリングなどで擦れるため。痛くないのかなと思ってしまいますね。少しでも予防できるよう、座りダコの対策方法をご紹介してみます。
「猫の座りダコ」ご存知ですか?猫のカカト部分に小さなハゲた部分があれば、それが座りダコです。
猫は家の中で固いフローリングや畳の上に座ることにより、カカトに体重がかかっており、そのためにタコができてしまうのです。
ハゲてしまうのはフローリングなどで擦れるため。痛くないのかなと思ってしまいますね。少しでも予防できるよう、座りダコの対策方法をご紹介してみます。
 猫の座り方には6種類あります。座り方をみれば猫の気持ちだけでなく、飼い主と猫との信頼関係までもがわかるのです。
猫の気持ちを察し、これからさらに猫との絆を深めていけると良いですね。
気持ちだけでなく、そこに潜んでいる怪我や病気にも気をつけ、大切な家族の一員として守っていかなければなりません。
猫の座り方には6種類あります。座り方をみれば猫の気持ちだけでなく、飼い主と猫との信頼関係までもがわかるのです。
猫の気持ちを察し、これからさらに猫との絆を深めていけると良いですね。
気持ちだけでなく、そこに潜んでいる怪我や病気にも気をつけ、大切な家族の一員として守っていかなければなりません。  愛犬を1匹飼っていると「1匹だったら可哀そうだな」「兄弟を作ってあげると毎日が楽しく過ごせるのではないだろうか」と考える方も多いのではないでしょうか。
犬を飼うという事は命を預かるという事ですので、「多すぎて面倒が見切れない」では絶対にダメなのです。
そして、頭数が増えると必然的に費用もかかってきますので、そこも考えないといけませんし、その他にも多頭飼をしようと思っている方は注意が必要な事がいくつかあります。
そこで、今回は多頭飼いについてご紹介していくのですが、まずは、多頭飼いをする際に注意しないといけない事をご紹介します。
愛犬を1匹飼っていると「1匹だったら可哀そうだな」「兄弟を作ってあげると毎日が楽しく過ごせるのではないだろうか」と考える方も多いのではないでしょうか。
犬を飼うという事は命を預かるという事ですので、「多すぎて面倒が見切れない」では絶対にダメなのです。
そして、頭数が増えると必然的に費用もかかってきますので、そこも考えないといけませんし、その他にも多頭飼をしようと思っている方は注意が必要な事がいくつかあります。
そこで、今回は多頭飼いについてご紹介していくのですが、まずは、多頭飼いをする際に注意しないといけない事をご紹介します。
 多頭飼いをする際、同じ犬種でないといけないという訳ではなく、犬種はどんな犬種でもいいのですが、大きさをまずは考えてみて下さい。
大幅なサイズの違いがあると思わぬケガの原因にもなりかねません。
チワワやヨークシャーなどの超小型犬を飼っていて2匹目に20㎏を超えるような中型犬を同居させる場合、大きな犬は遊んで噛んだつもりでも小さな犬にとっては致命傷になる事もあります。
噛まなくても少し足が当たっただけで、骨折をしてしまったり、寝ている時に上に乗ってしまうなどの危険性も出てくるでしょう。
また、犬の習性から小さくて動き回る物を見ると思わず飛び掛かってしまう事もあったりと、大きな犬は比較的温和な性格をしていますが、本能的にこのような事に出くわす事もありますので注意が必要になってきます。
多頭飼いをする際、同じ犬種でないといけないという訳ではなく、犬種はどんな犬種でもいいのですが、大きさをまずは考えてみて下さい。
大幅なサイズの違いがあると思わぬケガの原因にもなりかねません。
チワワやヨークシャーなどの超小型犬を飼っていて2匹目に20㎏を超えるような中型犬を同居させる場合、大きな犬は遊んで噛んだつもりでも小さな犬にとっては致命傷になる事もあります。
噛まなくても少し足が当たっただけで、骨折をしてしまったり、寝ている時に上に乗ってしまうなどの危険性も出てくるでしょう。
また、犬の習性から小さくて動き回る物を見ると思わず飛び掛かってしまう事もあったりと、大きな犬は比較的温和な性格をしていますが、本能的にこのような事に出くわす事もありますので注意が必要になってきます。
 犬を何匹も買うという事は、それに伴い出費も倍々に嵩んでいきます。
多頭飼いを始めてみたものの「経済的に余裕がなくなったから放棄」などは絶対にあってはならないものです。
ですので、頭数が増えてもきちんとした管理が可能なのか、しっかり検討するようにして下さい。
頭数を増やす前に、どんな犬種にするのか(中型犬や大型犬であれば小型犬の倍以上の費用がかかってきます)、年間にかかってくる医療費・トリミング費用・食費・その他にかかってくる諸々の費用など概算してみてからそうするのかを決めるようにしましょう。
犬を何匹も買うという事は、それに伴い出費も倍々に嵩んでいきます。
多頭飼いを始めてみたものの「経済的に余裕がなくなったから放棄」などは絶対にあってはならないものです。
ですので、頭数が増えてもきちんとした管理が可能なのか、しっかり検討するようにして下さい。
頭数を増やす前に、どんな犬種にするのか(中型犬や大型犬であれば小型犬の倍以上の費用がかかってきます)、年間にかかってくる医療費・トリミング費用・食費・その他にかかってくる諸々の費用など概算してみてからそうするのかを決めるようにしましょう。
 多頭飼いする場合、最初から一緒に複数まとめて飼う場合と、先住犬がおり、追加で新しい犬を飼うという場合があります。
最初から一緒に生活している場合は問題ないのですが、先住犬がいる場合は、先住犬が新しい子を受け入れる事でストレスを感じていないかと注意しなければなりません。
先住犬が複数いる場合は、そこまでストレスに感じるという事はないようですが、先住犬が1匹の場合は、かなりのストレスになると言われています。
今まで飼い主さんを独り占め出来たのに、同居犬が来た事によって、生活が一変するわけです。
そこからやきもちや新しい犬の溶射ないじゃれつきは体調を崩す原因になりやすいのです。
性格が甘え上手な先住犬ほと、この傾向が強く、ストレスから下痢や吐き気・食欲不振を起こす事があります。
おおむね2週間~3週間もすれば慣れてしまいますが、あまりに重度な症状であれば病院へ連れていくようにしましょう。
多頭飼いする場合、最初から一緒に複数まとめて飼う場合と、先住犬がおり、追加で新しい犬を飼うという場合があります。
最初から一緒に生活している場合は問題ないのですが、先住犬がいる場合は、先住犬が新しい子を受け入れる事でストレスを感じていないかと注意しなければなりません。
先住犬が複数いる場合は、そこまでストレスに感じるという事はないようですが、先住犬が1匹の場合は、かなりのストレスになると言われています。
今まで飼い主さんを独り占め出来たのに、同居犬が来た事によって、生活が一変するわけです。
そこからやきもちや新しい犬の溶射ないじゃれつきは体調を崩す原因になりやすいのです。
性格が甘え上手な先住犬ほと、この傾向が強く、ストレスから下痢や吐き気・食欲不振を起こす事があります。
おおむね2週間~3週間もすれば慣れてしまいますが、あまりに重度な症状であれば病院へ連れていくようにしましょう。
 新しい犬を迎え入れると決めた場合、先住犬と顔合わせをさせる事になりますが、この時、いきなり目の前に連れていくのはNG。
このような事をすると先住犬が困惑してしまいます。
あまりに困惑してしまい動揺してしまった結果、飛びついたり噛みついたりする危険性もありますので、まずはゲージ越しの顔合わせから始めましょう。
新しく来た子が子犬であれば病気を持ってくる場合も多いですし、ゲージ越しの顔合わせなら病気の感染の確率も少なくなります。
ゲージ越しに喧嘩する様子がなければ、飼い主さんの監視の下で、一緒に遊ばせたりしながら徐々に慣らすようにしていきましょう。
新しい犬を迎え入れると決めた場合、先住犬と顔合わせをさせる事になりますが、この時、いきなり目の前に連れていくのはNG。
このような事をすると先住犬が困惑してしまいます。
あまりに困惑してしまい動揺してしまった結果、飛びついたり噛みついたりする危険性もありますので、まずはゲージ越しの顔合わせから始めましょう。
新しく来た子が子犬であれば病気を持ってくる場合も多いですし、ゲージ越しの顔合わせなら病気の感染の確率も少なくなります。
ゲージ越しに喧嘩する様子がなければ、飼い主さんの監視の下で、一緒に遊ばせたりしながら徐々に慣らすようにしていきましょう。
 子犬が持ち込んで感染する病気の代表はケンネルコフという呼吸器の感染症や耳ダニなどの寄生虫が多いと言われています。
しかし、先住犬にワクチンを接種していれば、重篤な病気が感染する事はないので安心して下さい。
すでに複数飼育している状況で子犬を新たに飼う場合、感染症の広がりを防ぐために1週間ほど新しくきた子犬だけを隔離して飼育する検疫期間を設けるとなおいいでしょう。
検疫期間を設ける事ができれば、なんらかの病気を持ち込んでいてもその期間の間に発見できて感染が広がる前に対処する事が可能です。
子犬が持ち込んで感染する病気の代表はケンネルコフという呼吸器の感染症や耳ダニなどの寄生虫が多いと言われています。
しかし、先住犬にワクチンを接種していれば、重篤な病気が感染する事はないので安心して下さい。
すでに複数飼育している状況で子犬を新たに飼う場合、感染症の広がりを防ぐために1週間ほど新しくきた子犬だけを隔離して飼育する検疫期間を設けるとなおいいでしょう。
検疫期間を設ける事ができれば、なんらかの病気を持ち込んでいてもその期間の間に発見できて感染が広がる前に対処する事が可能です。
 同じ犬種の場合は、オスとメスを組み合わせると子供ができてしまうかもしれません。
相性がありますので、オスとメスと一緒にしたら必ず子供ができるというわけではありませんが、確率でいうと50%ほどでしょう。
子供ができてもいいのであれば問題はないのですが、子供が増えたら困るという方であれば避妊手術や去勢手術も必要になってきます。
ですので、繁殖の事も考えて飼う性別を決定する必要があるでしょう。
オスとメスの組み合わせの方が仲良くしやすいというイメージですが、同姓同士でも十分仲良くする事はできます。
繁殖の考慮も必要ですが、先住犬の性格の考慮も必要かもしれませんね。
同じ犬種の場合は、オスとメスを組み合わせると子供ができてしまうかもしれません。
相性がありますので、オスとメスと一緒にしたら必ず子供ができるというわけではありませんが、確率でいうと50%ほどでしょう。
子供ができてもいいのであれば問題はないのですが、子供が増えたら困るという方であれば避妊手術や去勢手術も必要になってきます。
ですので、繁殖の事も考えて飼う性別を決定する必要があるでしょう。
オスとメスの組み合わせの方が仲良くしやすいというイメージですが、同姓同士でも十分仲良くする事はできます。
繁殖の考慮も必要ですが、先住犬の性格の考慮も必要かもしれませんね。
 多頭飼いを行う前に、どんな風にしつけを行い、どんな飼い方をすれば愛犬たちが仲良く生活していけるのかを考えないといけません。
全ての愛犬に同じように可愛がるのはもちろんですが、同じようにしつけやルールも重要になってきます。
しつけやルールをしっかり身に付けさせておかなとトラブルが発生するもとになってしまいますので、ここでは多頭飼いをする場合のしつけやルールについてご紹介していきます。
多頭飼いを行う前に、どんな風にしつけを行い、どんな飼い方をすれば愛犬たちが仲良く生活していけるのかを考えないといけません。
全ての愛犬に同じように可愛がるのはもちろんですが、同じようにしつけやルールも重要になってきます。
しつけやルールをしっかり身に付けさせておかなとトラブルが発生するもとになってしまいますので、ここでは多頭飼いをする場合のしつけやルールについてご紹介していきます。
 犬は元々群れで生活をする生き物ですので、上下関係を重視する傾向があります。
多頭飼いにおける群れのリーダーは、飼い主さんで、先住犬は単身で飼われていた時からリーダーから愛されているのは自分であると認識しています。
新しく迎えた犬にばかりに目を向けてしまうとやきもちを焼いて問題行動を起こしたり、体調不良になったりと精神的に不安定になってしまい、新しく来た犬にも影響を与えかねません。
そうならないように、しっかり順位付けをする意味でも褒める場合は先住犬から褒めるという事を忘れないようにして下さい。
犬は元々群れで生活をする生き物ですので、上下関係を重視する傾向があります。
多頭飼いにおける群れのリーダーは、飼い主さんで、先住犬は単身で飼われていた時からリーダーから愛されているのは自分であると認識しています。
新しく迎えた犬にばかりに目を向けてしまうとやきもちを焼いて問題行動を起こしたり、体調不良になったりと精神的に不安定になってしまい、新しく来た犬にも影響を与えかねません。
そうならないように、しっかり順位付けをする意味でも褒める場合は先住犬から褒めるという事を忘れないようにして下さい。
 子犬はとにかくハイテンションで、家の中を走りまわったり、跳ねたりし勢いが衰える事が中々ありません。まだ良し悪しがわかっていないので、飼い主さんにも先住犬にも遠慮なく向かってきます。
迎えたばかりの頃は先住犬もどのように接していいのかわからないし、何だか鬱陶しい的な感じで一緒の空間にいない場合が多いのですが、ある日先住犬が見かねて子犬に「ワン!!」と一喝し、子犬が大人しくなったなんて声も多く聞きます。
飼い主さんから先住犬が怒った!ケガをしてしまうかもと焦ってしまうかもしれませんが、これは先住犬が子犬に対し「それはダメよ!」と教えているのかもしれません。
家でやってはいけないルールを一番知っているのは先住犬でそれを子犬に教えているのです。
犬同士の関係性は飼い主さんが作るのではなく、犬同士で自然に任せるのがいいのかもしれませんね。
子犬はとにかくハイテンションで、家の中を走りまわったり、跳ねたりし勢いが衰える事が中々ありません。まだ良し悪しがわかっていないので、飼い主さんにも先住犬にも遠慮なく向かってきます。
迎えたばかりの頃は先住犬もどのように接していいのかわからないし、何だか鬱陶しい的な感じで一緒の空間にいない場合が多いのですが、ある日先住犬が見かねて子犬に「ワン!!」と一喝し、子犬が大人しくなったなんて声も多く聞きます。
飼い主さんから先住犬が怒った!ケガをしてしまうかもと焦ってしまうかもしれませんが、これは先住犬が子犬に対し「それはダメよ!」と教えているのかもしれません。
家でやってはいけないルールを一番知っているのは先住犬でそれを子犬に教えているのです。
犬同士の関係性は飼い主さんが作るのではなく、犬同士で自然に任せるのがいいのかもしれませんね。
 多頭飼いをするにはそれなりの覚悟が必要ですし、楽しいばかりではありません。
しかし、そのようなデメリットばかりではなく、メリットも沢山あります。
そこで、ここでは多頭飼いのメリットについてご紹介していきたいと思います。
多頭飼いをするにはそれなりの覚悟が必要ですし、楽しいばかりではありません。
しかし、そのようなデメリットばかりではなく、メリットも沢山あります。
そこで、ここでは多頭飼いのメリットについてご紹介していきたいと思います。
 オオカミを祖先に持つ犬は、元々大自然の中を走り回って生活をしてきました。
現在は、犬も家族の一員として考えるようになり、室内飼いが多くなってきましたが、その結果、思い切り走り回ったり遊んだりする機会が少なくなってしまっているのが現状です。
運動不足になると、身心共に健康的ではなく、ストレスをため込んでしまい、噛みつきや無駄吠えなどの問題行動の原因になる事も出てくるのです。
おでかけやドッグランに行って定期的にストレスを発散させてあげる事でももちろんいいのですが、できれば毎日運動させてあげたいもの。
そんな時に多頭飼いをしていると飼い主さんが遊んであげなくても、犬同士で勝手に遊んでくれますので、運動不足やストレス解消になりとても良い事と言えるでしょう。
オオカミを祖先に持つ犬は、元々大自然の中を走り回って生活をしてきました。
現在は、犬も家族の一員として考えるようになり、室内飼いが多くなってきましたが、その結果、思い切り走り回ったり遊んだりする機会が少なくなってしまっているのが現状です。
運動不足になると、身心共に健康的ではなく、ストレスをため込んでしまい、噛みつきや無駄吠えなどの問題行動の原因になる事も出てくるのです。
おでかけやドッグランに行って定期的にストレスを発散させてあげる事でももちろんいいのですが、できれば毎日運動させてあげたいもの。
そんな時に多頭飼いをしていると飼い主さんが遊んであげなくても、犬同士で勝手に遊んでくれますので、運動不足やストレス解消になりとても良い事と言えるでしょう。
 一緒に暮らしている愛犬同士に年齢の差がある場合、上の子は下の子の運動量に合わせて生活をするようになります。
健康的に「ちょっと頑張って運動する」という事ができると、若さを保つ秘訣になり、歳の割には元気な子という年齢の取り方ができるようになるでしょう。
下の子も上の子がいる事で、学ぶ事が多くあり、何があっても守ってくれるという安心感もありますので心身共に健康的でいられるでしょう。
一緒に暮らしている愛犬同士に年齢の差がある場合、上の子は下の子の運動量に合わせて生活をするようになります。
健康的に「ちょっと頑張って運動する」という事ができると、若さを保つ秘訣になり、歳の割には元気な子という年齢の取り方ができるようになるでしょう。
下の子も上の子がいる事で、学ぶ事が多くあり、何があっても守ってくれるという安心感もありますので心身共に健康的でいられるでしょう。
 犬は基本良く寝ますので、お留守番の時は寝ている事が多いのですが、一匹で留守番をしていると帰宅した時に部屋の中が荒らされていたり、いたずらをしたりという子も沢山います。
これは一人で留守番をさせられた、置いていかれたという寂しさなどから引き起こされるものですが、多頭飼いをしていると、留守番の際にも、他の犬もいますので、一緒に遊びながら楽しく留守番ができるようになります。
現に、一匹では留守番させられなかったけど、家族を増やしたら大人しく留守番をしてくれるようになったという声も多く聞かれています。
人間も一人でいると寂しいのと同じで、犬も同じなのです。
犬は基本良く寝ますので、お留守番の時は寝ている事が多いのですが、一匹で留守番をしていると帰宅した時に部屋の中が荒らされていたり、いたずらをしたりという子も沢山います。
これは一人で留守番をさせられた、置いていかれたという寂しさなどから引き起こされるものですが、多頭飼いをしていると、留守番の際にも、他の犬もいますので、一緒に遊びながら楽しく留守番ができるようになります。
現に、一匹では留守番させられなかったけど、家族を増やしたら大人しく留守番をしてくれるようになったという声も多く聞かれています。
人間も一人でいると寂しいのと同じで、犬も同じなのです。
 今回は、犬の多頭飼いについてご紹介してきました。
多頭飼いは大変というイメージを持っている方も多いかもしれませんが、飼い主さんの覚悟があれば大変な事はあっても楽しさは倍増します。
そして、多頭飼いならではのメリットも沢山ありますので、悪いイメージばかりではないという事を今回この記事を読んでわかって頂けると嬉しいです。
今回は、犬の多頭飼いについてご紹介してきました。
多頭飼いは大変というイメージを持っている方も多いかもしれませんが、飼い主さんの覚悟があれば大変な事はあっても楽しさは倍増します。
そして、多頭飼いならではのメリットも沢山ありますので、悪いイメージばかりではないという事を今回この記事を読んでわかって頂けると嬉しいです。