柴犬はストーブが好き?話題の小太郎くんとは?
 SNSで話題急上昇中の小太郎くんは、冬になるとストーブの前が定位置になるユニークな柴犬です。
柴犬は硬くてしっかりとしたオーバーコートと、断熱効果の高いアンダーコートの2層で体が覆われています。
だからとても暑がりな犬種です。
その分、雪の中でも震えることなく元気に走り回ることができるような、とても寒さに強い犬なのです。
しかし小太郎くんの場合は少し違うようです。
小太郎くんは、どうしてストーブの前から動かなくなってしまうのでしょうか。
寒いから?それとも他に理由が?
今日は、そんな小太郎くん一家の日常を、少しだけ覗かせてもらいましょう。
SNSで話題急上昇中の小太郎くんは、冬になるとストーブの前が定位置になるユニークな柴犬です。
柴犬は硬くてしっかりとしたオーバーコートと、断熱効果の高いアンダーコートの2層で体が覆われています。
だからとても暑がりな犬種です。
その分、雪の中でも震えることなく元気に走り回ることができるような、とても寒さに強い犬なのです。
しかし小太郎くんの場合は少し違うようです。
小太郎くんは、どうしてストーブの前から動かなくなってしまうのでしょうか。
寒いから?それとも他に理由が?
今日は、そんな小太郎くん一家の日常を、少しだけ覗かせてもらいましょう。
柴犬の小太郎くんとは?
柴犬の小太郎くんがネットで話題を集め始めたのは5歳の頃。
飼い主さんがSNSに画像を投稿したのがきっかけでした。
その後、「決してストーブの前から離れない犬」として人気が急上昇!
そして、小太郎くんの魅力はそれだけではありません。
若い成犬らしく、毛並みがとても綺麗。
顔つきにも気品があり、なかなかのイケメン柴です。
小太郎くんの姿を見るだけでも、何だか嬉しくなってしまいます。
そんなイケメンぶりもファンが増える理由の一つかもしれませんね。
ストーブの前にいるのは定番
小太郎くんがストーブの前にいる姿がSNSに上がったのは5歳の時でしたが、実は毎年冬になると、暖かいストーブの前から離れなくなるそうです。
暖かい温風が出てくるストーブが大好きなのですね。
でも写真を見るとストーブの真正面、しかもその距離30センチに満たないのでは?
お腹全体で全力で温風に当たっています。
熱くないのかな。
実際に飼い主さんには「ストーブガードを付けてみては?」というコメントも寄せらているそうです。
本当につらければ近づかないから大丈夫なのでしょうが、平気だというのもすごいですね。
柴犬の小太郎くんと赤ちゃんのストーブ攻防戦
実は小太郎くんの人気を2分する存在が、このご家庭には存在します。
生後間もない人間の赤ちゃんです。
ジッとストーブの前で暖まっている小太郎くんの後ろで、赤ちゃんが一生懸命アクションを起こしています。
「遊ぼう!」と誘っているような、「ぼくもストーブにあたりたい!」と場所を奪いに行っているような、小太郎くんがストーブの前にいる時は、赤ちゃんも参戦しています。
犬のお兄ちゃんは、小さな人間の弟分とどんなやり取りをしているのでしょうね。
暖まりたい小太郎くんと赤ちゃんの関係性
ストーブの前でまったりしている小太郎くんは、赤ちゃんがやって来ても決してその場所を譲ろうとしません。
飼い主さんは当初、その様子を見て、小太郎くんがストーブで暖まりたいから絶対譲らずにがんばっているのだと思っていたそうです。
しかしSNSで「赤ちゃんが危険に晒されないように、ストーブの熱から守っている」という意見を聞いて、そんな見方もあったのだと考え方が変わったと話していました。
言われてみれば、赤ちゃんが転がっている姿を見ている小太郎くんは、どことなく守護神のような顔つきですよね。
「危ないからこれ以上来るなよ」と言っているのかもしれません。
とても赤ちゃん想いの小太郎くん
小太郎くんは、赤ちゃんのことを弟分として考えている様子もあるそうです。
静かに見守ってあげたり、赤ちゃんが立ち上がろうとすればそれを応援している仕草を見せたり、とても弟想いの一面を見せることも。
小太郎くんにとってこの赤ちゃんは、大切な家族という群れの一員なのでしょう。
だから早く一人前になれるように育てようとしているのかもしれませんね。
そんな小太郎くんを見て、飼い主さんは、赤ちゃんも小太郎くん想いな子に育ってほしいと話していました。
生まれた時から犬に守られて育つことができるなんて素敵ですね。
きっとこの赤ちゃんは、自分と違う命に対して優しくなれる子に成長することでしょう。
まとめ
 ストーブの前に座り、決して動こうとしない小太郎くん。
面白柴犬の投稿かなぁと思いきや、赤ちゃんとのふれあいには心温まるものがありました。
人間と犬は一緒に暮してきた歴史が長い分、ふとした時に犬の人間的な一面を垣間見ることができるのかもしれません。
それにしても小太郎くん、本当にあんなにストーブに近づいて熱くないのかな。
飼い主さんはストーブガード購入も検討しますと話していましたが、もし購入したら、ストーブガードを前にした小太郎くんの姿も見てみたいですね。
ストーブの前に座り、決して動こうとしない小太郎くん。
面白柴犬の投稿かなぁと思いきや、赤ちゃんとのふれあいには心温まるものがありました。
人間と犬は一緒に暮してきた歴史が長い分、ふとした時に犬の人間的な一面を垣間見ることができるのかもしれません。
それにしても小太郎くん、本当にあんなにストーブに近づいて熱くないのかな。
飼い主さんはストーブガード購入も検討しますと話していましたが、もし購入したら、ストーブガードを前にした小太郎くんの姿も見てみたいですね。
柴犬飼いあるある!ツンデレのツン編
 柴犬は飼い主さんやその家族には従順で忠誠ですが、いきなり何故かつれなくなってしまうなんて事は日常茶飯事なのです。
実はツンデレは柴犬の得意過ぎる分野ですので、息をするように、普通の事という訳ですね。
なので、飼い主さんは常に、見事に踊らされているという事になっちゃっているのです。
そこで、ここでは柴犬あるあるのツンデレの「ツン」部分をご紹介しましょう。
柴犬は飼い主さんやその家族には従順で忠誠ですが、いきなり何故かつれなくなってしまうなんて事は日常茶飯事なのです。
実はツンデレは柴犬の得意過ぎる分野ですので、息をするように、普通の事という訳ですね。
なので、飼い主さんは常に、見事に踊らされているという事になっちゃっているのです。
そこで、ここでは柴犬あるあるのツンデレの「ツン」部分をご紹介しましょう。
見てないふりをする
ふと、視線を感じていると思って愛犬の柴犬を見てみると、確かに見ている!
「もしかして、遊んで欲しいのかな?」と飼い主さんもウキウキしながら近づいていくと、その後、愛犬が取った行動は「全然見てないし」と言っているように全く違うところを見ているのです。
柴犬はベタベタする事は好まない犬種というのはわかっていても、「自分だけが愛犬を想う気持ちが大きいのかな」と思う事もありますよね。
ところが、数分たつと「遊んで~」とベタベタ。
このような態度がまた魅力で飼い主さんはメロメロになってしまうみたいです。
露骨に無視する
おやつも何もなく「お手」をいうと、やってくれるのはやってくれるのですが、顔が全く自分を見ていない。。。
このような事も日常茶飯事。
指示は聞いているけど完全無視状態。
こんなに露骨な無視の仕方、中々人間にはできません。
なぜ、このような態度を取ったかというと「おやつを持っていないから」という事があるからで、ここでおやつを持っていると自分からお手をするのだとか。
ずいぶんしっかりしている犬種なんですね。
撫でようと思ったら逃げる
飼い主さんの目の前でご機嫌の顔をしてこっちを見ているので「何か期待しているのかな?撫でてほしいのかな?」と思い、飼い主さんが撫でてあげようと手を伸ばした瞬間、見事な身のこなしで避けられる。
なんて事も柴犬には普通です。
ナデナデを避けるだけではなく、何事もなかったかのように、その場から颯爽といなくなってしまいます。
突然のツン対応に、飼い主さんは切ない空気だけが残ってしまう結果となってしまうのです。
柴犬飼いあるある!ツンデレのデレ編
 柴犬と言えば、キリっとした顔立ちを崩さず見知らぬ人には警戒し、決して簡単に愛想をふりまかない。
かと思うと飼い主さんにはとても忠実で、番犬としてしっかり家族を守る。
そんな勇敢な性格を持っています。
そこで、次は柴犬あるあるツンデレの「デレ」編をご紹介します。
柴犬と言えば、キリっとした顔立ちを崩さず見知らぬ人には警戒し、決して簡単に愛想をふりまかない。
かと思うと飼い主さんにはとても忠実で、番犬としてしっかり家族を守る。
そんな勇敢な性格を持っています。
そこで、次は柴犬あるあるツンデレの「デレ」編をご紹介します。
されるがままの姿にメロメロ
ツンデレが得意な柴犬も、甘えん坊モードに一歩入ってしまうと、とにかくされるがままになってしまいます。
眠っている間に、遊ばれてしまっても、安心しきっているのか目も開けずスヤスヤ。
熟睡していても、安心できる飼い主さんが傍にいて、何をされても全く目を開ける事はありません。
「ツン」を見た後にこんな「デレ」を見てしまうと可愛くて仕方ないですよね。
飼い主への愛が止まらない
番犬のイメージが強い柴犬ですが、やっぱり純粋な犬種なのです。
大好きな飼い主さんやその家族には沢山甘えたい!という事で、穏やかな顔で飼い主さんの腕を掴んで離さない、「大好き!」と言わんばかりの顔でこっちを見てくれると、飼い主さんに対する愛情の深さがマジマジと感じますよね。
お互いの気持ちが通じあっている事も感じられ、飼い主さんはますますメロメロになってしまうのではないでしょうか。
甘えて眠る姿
普段は番犬として家族を守ると言う役割を担っている愛犬ですが、飼い主さんに甘えたいという気持ちも同じくらいあります。
時には、飼い主さんの腕に抱かれてスヤスヤ。。。
抱っこされながらでも熟睡してしまうという、飼い主さん大好き感!
安心しきって寝てしまう姿を見れるのも柴犬ならではかもしれません。
それだけ飼い主さんを頼りにしているし、飼い主さんが傍にいればリラックスできているという事なので、ある意味人間と似ているような部分があるのかもしれないですね。
一緒にまったりゴロゴロ
飼い主さんがまったり過ごしていると、ピタッとくっついてくる愛犬。
甘えたそうな真ん丸な目でこちらを見つめ、愛犬までもがまったりゴロゴロモードに。
「撫でてよ!」と言いたそうな可愛い目でこちらを見られると、撫でてあげられずにはいられません。
撫でている間も完全にリラックスモードで、最後には熟睡。。。
こんな姿も日常茶飯事に見れます。
想像するだけで笑顔が出てしまう可愛い部分ですね。
柴犬のツンデレな性格が出てる?柴距離の謎
 いきなりですが柴距離という言葉をご存じですか?
柴距離という言葉が表しているように、柴犬特有のツンデレな性格が出ている距離感なのですが、ここでは、その柴距離についてご紹介していきます。
柴距離が理解できると、自然と愛犬に接する行動や態度も変わってくるかもしれませんね。
いきなりですが柴距離という言葉をご存じですか?
柴距離という言葉が表しているように、柴犬特有のツンデレな性格が出ている距離感なのですが、ここでは、その柴距離についてご紹介していきます。
柴距離が理解できると、自然と愛犬に接する行動や態度も変わってくるかもしれませんね。
柴距離の概要
柴距離とは、柴犬特有の微妙な距離感をあける事で、大好きな飼い主さんに対してもべったりではなく、手が届くか届かないかほどの距離感をあえてあけて座ったり、寛いだり。。。
飼い主さんが遊びに誘っても気が乗らないと遊んでくれないし、呼んでも、近くまではくるのに体は触れさせない。
テンション高く遊び回っていたのに、急に冷める。
警官氏が強く、他の犬や人に必要以上に近寄らない。
など、柴距離は他の犬種にはない柴犬の特徴的な性質の事を飼い主さんたちは柴距離と呼んでいるのです。
柴距離は何故存在する?
柴犬特有の微妙な距離感、柴距離が何故存在するのか。
という事は、今現在でもまだ判明しておらず、推測ですが、柴犬はオオカミに近いと言われている遺伝子を持っているため、野生の本能が関係しているのではないかという説もあるようです。
飼い主さんは柴距離が始まったら、そっとしておいてあげるのがいいのかもしれませんね。
数分後には甘えたモードの愛犬になっているのでしょう。
まとめ
 今回は柴犬のツンデレについてご紹介してきました。
他の犬種には中々見られない、柴犬特有のツンデレな性格や、柴距離は初めて柴犬を飼う飼い主さんには最初戸惑ってしまうのかもしれませんが、この行動は決して飼い主さんを嫌っているのではないという事を知っておきましょう。
理由は判明されていませんが、本能的なものが大きく影響しているようなので、「柴犬はこれが普通」と身構えて甘えてくるのを待っているのがいいのかもしれません。
柴犬は本当に飼い主さんやその家族に一途で愛してくれています。
そんな柴犬にメロメロになる方が多いので、人気ランキングでは常に上位にいるのでしょう。
今回は柴犬のツンデレについてご紹介してきました。
他の犬種には中々見られない、柴犬特有のツンデレな性格や、柴距離は初めて柴犬を飼う飼い主さんには最初戸惑ってしまうのかもしれませんが、この行動は決して飼い主さんを嫌っているのではないという事を知っておきましょう。
理由は判明されていませんが、本能的なものが大きく影響しているようなので、「柴犬はこれが普通」と身構えて甘えてくるのを待っているのがいいのかもしれません。
柴犬は本当に飼い主さんやその家族に一途で愛してくれています。
そんな柴犬にメロメロになる方が多いので、人気ランキングでは常に上位にいるのでしょう。
犬友アプリとは?
 こんにちは!みなさんの愛犬には気が合うお友達はいますか?人と同じで犬も、すぐ意気投合して仲良くなれるコとちょっと苦手かも・・・というコがいますよね。
また飼い主さん同士の相性もあるし、面倒に思われるかもしれません。
しかし毎日の愛犬との生活の中で、不安に思う事や心配事など色々と共有できる犬友アプリは、手軽なコミュニケーションツールとして利用する飼い主さんが増えてきています。
こんにちは!みなさんの愛犬には気が合うお友達はいますか?人と同じで犬も、すぐ意気投合して仲良くなれるコとちょっと苦手かも・・・というコがいますよね。
また飼い主さん同士の相性もあるし、面倒に思われるかもしれません。
しかし毎日の愛犬との生活の中で、不安に思う事や心配事など色々と共有できる犬友アプリは、手軽なコミュニケーションツールとして利用する飼い主さんが増えてきています。
そもそも犬友とは?
犬友とは、犬と暮らしている飼い主さん同士がお友達になる事を言います。
散歩コースで毎日会うワンちゃんや飼い主さんと仲良くなったり、SNSなどで愛犬と同じ犬種のサークルを見つけて参加したり、またはペットショップなどオフ会を開催しているところもあるので、犬友を作る機会は意外と多い事がわかります。
住んでいるところが近所であれば、一緒にお出かけする事もできるので、今まで知らなかった場所や情報を教え合う事も気軽にできるのは嬉しいですよね。
愛犬の社会化やお友達作りはもちろんですが、飼い主さん同士の交流も楽しめます。
犬友アプリを使うメリット
犬友を作るアプリは今、たくさんあります。
アプリごとに色々な特色がありますので、使いやすいと思うアプリを探してみましょう。
犬友アプリを使うと、遠くに住んでいるワンちゃんや飼い主さんともお友達になる事が出来ますし、忙しかったり、会ってお話しするのはちょっとな・・という飼い主さんも気軽にインターネット上で友達を作る事が出来ます。
かかりつけの動物病院で獣医さんに聞くほどでは無いけれど、みんなはどうしているだろう?これっておかしいかな?などちょっとした疑問も聞きやすいので、オススメですよ。
犬友と画像や動画をシェアするアプリ
 可愛い愛犬のベストショットや思い出の動画をシェアできるアプリは、普段から使っている飼い主さんも多いのではないでしょうか。
飼い主さんに一番人気がある画像・動画共有アプリは、愛犬の日常をUPする事で他の飼い主さんとの会話が生まれて交流できるので、肩に力を入れずに楽しむ事が出来ますよね。
オススメのアプリをいくつかご紹介していきますので、気になったアプリがあったら是非ダウンロードしてみて下さいね。
可愛い愛犬のベストショットや思い出の動画をシェアできるアプリは、普段から使っている飼い主さんも多いのではないでしょうか。
飼い主さんに一番人気がある画像・動画共有アプリは、愛犬の日常をUPする事で他の飼い主さんとの会話が生まれて交流できるので、肩に力を入れずに楽しむ事が出来ますよね。
オススメのアプリをいくつかご紹介していきますので、気になったアプリがあったら是非ダウンロードしてみて下さいね。
犬猫アルバム(Our Pets)
画像共有アプリとして多くの飼い主さんから支持されているアプリです。
愛犬のベストショットをUPして、たくさんの人から「いいね!」をもらいましょう。
また他の可愛いワンちゃんに「いいね!」をしてチャットで交流する事も出来ます。
画像だけ、のシンプルなやり取りなので初心者さんにも使いやすいのではないでしょうか。
愛犬と同じ犬種だけなどピンポイントの設定はできませんが、ワンちゃんに限らない可愛いペット達の画像を見るのも楽しいですよ。
ペットスマイル
愛犬との楽しい毎日や行事など思い出の画像や動画をコメントと共にUPすることができます。
愛犬に関する毎週・毎月の忘れてはいけないスケジュールを登録しておくとアラートで知らせてくれるので、ウッカリ!の心配がなくて便利ですよ。
悩み事や心配事など他のユーザーさんと情報交換をしながら楽しく犬友を作ることができるこちらのアプリは、日頃買い物で利用するショップもフォローできるので仕入れた情報を素早く目で確認して取り入れる事もできます。
ペットスマイル事業部からのお役立ち情報や企画などの記事も読めるので、盛り沢山のアプリと言えます。
犬友と愛犬の健康をシェアするアプリ
 今、側にいる愛犬が初めて家族に迎えたワンちゃんであれば、「あの時、こうやっていれば・・」など後悔している事がひとつやふたつはあるのではないでしょうか。
人と同じく個性を持つ犬は、環境や接し方によって育ち方も変わりますし、病気の前兆も見過ごしてしまう可能性もあります。
そんな時に獣医師さんやトレーナーさんのサポートが受けられたり、犬友さんと交流が持てるアプリがあるだけで飼い主さんの気持ちに安心感も生まれますよね。
今、側にいる愛犬が初めて家族に迎えたワンちゃんであれば、「あの時、こうやっていれば・・」など後悔している事がひとつやふたつはあるのではないでしょうか。
人と同じく個性を持つ犬は、環境や接し方によって育ち方も変わりますし、病気の前兆も見過ごしてしまう可能性もあります。
そんな時に獣医師さんやトレーナーさんのサポートが受けられたり、犬友さんと交流が持てるアプリがあるだけで飼い主さんの気持ちに安心感も生まれますよね。
まとめ
 なかなか外出して犬友を作る事が難しい飼い主さんも、気軽に登録・交流できるアプリがたくさんあります。
飼い主さんがどんな目的で犬友を作りたいのかを考えて、内容やライフスタイルに合ったアプリを選んでみてくださいね。
また他の飼い主さんとコミュニケーションを取る際、顔が見えず文章では抑揚が分かりにくい事が難点とも言えます。
お互いが楽しく過ごせるよう注意して、愛犬との充実した毎日に生かしてくださいね。
なかなか外出して犬友を作る事が難しい飼い主さんも、気軽に登録・交流できるアプリがたくさんあります。
飼い主さんがどんな目的で犬友を作りたいのかを考えて、内容やライフスタイルに合ったアプリを選んでみてくださいね。
また他の飼い主さんとコミュニケーションを取る際、顔が見えず文章では抑揚が分かりにくい事が難点とも言えます。
お互いが楽しく過ごせるよう注意して、愛犬との充実した毎日に生かしてくださいね。
柴犬をもふもふしたい!その魅力とは?
 外出の際に愛犬と散歩をしている飼い主の方を見かける事がありますが、犬種に違いはあっても仲睦まじい光景にはとても癒されます。
日本の犬として代表的な柴犬の後ろ姿には、言葉では言い表せないような可愛らしさがあります。
表情や動作にも目を引くものがあり、そばに行って触れてみたくなってしまいます。
2017年に犬種別犬登録頭数が5位で、アメリカでは年間1,000頭以上も登録されています。
小柄で室内でも飼いやすいと、日本や海外でも人気のある柴犬の魅力を紹介します。
外出の際に愛犬と散歩をしている飼い主の方を見かける事がありますが、犬種に違いはあっても仲睦まじい光景にはとても癒されます。
日本の犬として代表的な柴犬の後ろ姿には、言葉では言い表せないような可愛らしさがあります。
表情や動作にも目を引くものがあり、そばに行って触れてみたくなってしまいます。
2017年に犬種別犬登録頭数が5位で、アメリカでは年間1,000頭以上も登録されています。
小柄で室内でも飼いやすいと、日本や海外でも人気のある柴犬の魅力を紹介します。
柴犬の魅力
犬種が増えている中で、柴犬は流行に左右されずに根強い人気を持っています。
毛色には赤、黒、白、胡麻があり触り心地が良く、飼い主には友好的で愛嬌があり色々なしぐさで楽しませてくれます。
顔は野性的で素朴さを感じさせますが、ピンと立った三角の耳やくるりと巻いたしっぽにはとても可愛らしさがあります。
小さいけれど引き締まった体で病気に強く丈夫な所や、利口でしつけが楽な事もあり初めて犬を飼いたい人でも世話がしやすい魅力があります。
おしりまでもふもふな柴犬
表情やしぐさだけでも可愛らしい柴犬ですが、座った時のおしりはもふもふしていて目を奪われ桃や鈴カステラをイメージしてしまいます。
飼い主の方には見慣れた光景でも、犬を飼えない人にはとても癒しを与えてくれ何度でも見たい気持ちになります。
散歩をしている時のもふもふなおしりとくるりと巻いたしっぽには人を魅了する力があり、車を運転している最中でもつい目がいってしまいます。
柴犬は存在するだけで知らず知らずのうちに、たくさんの人を笑顔にさせてくれます。
もふもふ柴犬と赤ちゃん
犬は人に付くと言われているように、赤ちゃんの体温は犬にとって心地が良くそばにいると落ち着くようです。
自分よりも小さく弱いと感じるものには野性的な面は見せずに、見守るように寄り添う事があります。
ぬいぐるみもコロコロで可愛い
お米屋さんの看板犬をイメージした忠犬もちしばのぬいぐるみは、首にっかかった柴と書かれてある前掛けに愛らしさを感じます。
柴犬のコロコロとした所や、もふもふ感が出ていてつい抱いてしまいたくなります。
本物の柴犬のような動きはなくても、そばに置いて見ているだけでもキュートな目が可愛らしく癒されます。
忠犬もちしばのぬいぐるみには幾つかの種類があり、それぞれに毛色や表情にあった名前が付いていて親しみが感じられます。
自分好みの忠犬もちしばで、もふもふ感を実感しながら楽しい時間を過ごすのもいいかもしれません。
柴犬は海外でも人気!もふもふな小豆柴とは?
 柴犬の愛嬌のあるキツネ顔やタヌキ顔が海外でも人気を集めていて、セラピードックにもなれる癒し犬としても高い評価を得ています。
小豆柴は柴犬同様に飼い主に忠実でしつけがしやすい面があり、赤毛、胡麻、黒毛が多く白毛の子もいてもふもふ感があります。
可愛い表情とコミカルな動きで、癒しを与えてくれる小豆柴の魅力を紹介します。
柴犬の愛嬌のあるキツネ顔やタヌキ顔が海外でも人気を集めていて、セラピードックにもなれる癒し犬としても高い評価を得ています。
小豆柴は柴犬同様に飼い主に忠実でしつけがしやすい面があり、赤毛、胡麻、黒毛が多く白毛の子もいてもふもふ感があります。
可愛い表情とコミカルな動きで、癒しを与えてくれる小豆柴の魅力を紹介します。
小豆柴の人気は海外レベル
小豆柴は世界最小の柴犬の種類で、成犬になっても小型犬のままです。
理想の室内犬としても人気が高く、ぬいぐるみのようにコロコロしていて可愛いと海外でも人気を集めています。
くるりと巻いたしっぽやもふもふ感のあるおしりには魅力があり、わがままな一面があってもキュートな目で見つめられるとつい許してしまいたくなります。
小豆柴には帰巣本能があり迷い犬なる心配がなく、飼育設備や餌代が少なくて済む利点もあります。
小豆柴に会える「小豆柴の郷」
秋葉原にある「小豆柴の郷」は小豆柴カフェで、飲み物を味わいながら小豆柴の遊んでいる姿を見たり触れ合う事ができます。
営業時間は11:00〜20:00迄となっていて、年中無休ですが列ができてしまう程の人気があります。
予約ができないため、受付でのチケットの購入が必要になります。
店内では8匹の小豆柴が迎えてくれ、30分の制限時間の中で癒しを与えてくれます。
犬特有の臭いがあるのではと不安になる方もいると思いますが、3台の空気清浄機とこまめな清掃を心がけている事もありほぼ無臭で快適な時間を過ごす事ができます。
まとめ
 日本でも海外でも人気を集めている柴犬と小豆柴にはいくつもの魅力があり、飼い主や周りの人に癒しを与えてくれ疲れや嫌な事を忘れさせてくれます。
犬を飼っている方にとって自分の愛犬が最高だとは思いますが、柴犬には日本犬の懐かしさがあり親しみを感じてしまいます。
様々な事情で犬の飼えない人には「忠犬もちしば」のぬいぐるみや「小豆柴の郷」がおすすめです。
日本でも海外でも人気を集めている柴犬と小豆柴にはいくつもの魅力があり、飼い主や周りの人に癒しを与えてくれ疲れや嫌な事を忘れさせてくれます。
犬を飼っている方にとって自分の愛犬が最高だとは思いますが、柴犬には日本犬の懐かしさがあり親しみを感じてしまいます。
様々な事情で犬の飼えない人には「忠犬もちしば」のぬいぐるみや「小豆柴の郷」がおすすめです。
愛犬が泣くのはどうして?
 犬は「鳴く」とは言いますが、「泣く」とはあまり表現されません。
しかし、犬も「泣く」ことがあります。
人間のように感情がたかぶって涙を流すというわけではありませんが、目の異常や保護のために泣くことがあるのです。
愛犬が涙を流すようなことがあったら、目の観察をしてみてあげてくださいね。
次の項目から、犬が泣くときにどんなことが考えられるかを見ていきましょう。
犬は「鳴く」とは言いますが、「泣く」とはあまり表現されません。
しかし、犬も「泣く」ことがあります。
人間のように感情がたかぶって涙を流すというわけではありませんが、目の異常や保護のために泣くことがあるのです。
愛犬が涙を流すようなことがあったら、目の観察をしてみてあげてくださいね。
次の項目から、犬が泣くときにどんなことが考えられるかを見ていきましょう。
病気のサインで泣く
頻繁に犬が泣く時は、「結膜炎」や「角膜炎」など、目の炎症を起こしている可能性があります。
まつ毛が目に刺さる「逆さまつ毛」が原因で泣くこともあります。
結膜炎:目に何らかの刺激(花粉、細菌、ウィルス、目の周りの毛など)がを受けることで、結膜に炎症が起こります。
涙で目ヤニも増え、目の周りにも赤みが出ます。
目を気にして掻いてしまうことで悪化すると、角膜炎に進行してしまうこともあるため、注意が必要です。
角膜炎:結膜炎の他に、緑内障から進行して起こることもある病気です。
犬の黒目を覆う角膜に炎症が起こります。
また、結膜炎と同様に、外部からの刺激によっても発症します。
目ヤニや涙が大量に出て、痛みも伴います。
悪化すると角膜が白濁したり、潰瘍となったりするので、早急に治療が必要です。
逆さまつ毛:まつ毛が目に向かって伸びることで、角膜などに突き刺さります。
そこから細菌感染や物理的な刺激により、涙や目ヤニが増加します。
痛み、痒みにより目の周りが赤くなる、またはけいれんなどが起こることもあります。
刺さったまつ毛によって角膜に穴が開いたり、結膜炎、角膜炎の原因になることもあります。
目の健康のために泣く
犬にとっての涙は、目の健康を守るために発生する生理現象です。
例えば散歩中などに異物やゴミが目に入ると、それを目から排出させるために涙を流します。
悲しいことがあった人間のように、ボロボロと涙がこぼれ落ちるようになることもあります。
放っておくと涙の跡が涙焼けになり、ただれて炎症が広がるおそれがあります。
柔らかい布やコットンなどで、涙はすぐに拭き取るようにしましょう。
また、この時に目に異物がないかも必ず確認してください。
もし取り出しにくい場所に異物があった場合は、無理に取ろうとすることで逆に犬の目を傷つけてしまうことになりかねませんので、獣医さんに診てもらうようにすることをおすすめします。
犬が泣くのは悲しいから?
 犬が涙を流すと悲しげに見えてしまいますが、実際には犬の感情と涙には、人間のような関係性はないと言われています。
先にお話しした病気や異物が原因だと考えられています。
でも犬にも「悲しい」という気持ちは存在します。
犬が悲しみを感じた時、どのような行動や表情を見せるのでしょうか。
様々な事例もご紹介します。
犬が涙を流すと悲しげに見えてしまいますが、実際には犬の感情と涙には、人間のような関係性はないと言われています。
先にお話しした病気や異物が原因だと考えられています。
でも犬にも「悲しい」という気持ちは存在します。
犬が悲しみを感じた時、どのような行動や表情を見せるのでしょうか。
様々な事例もご紹介します。
犬は悲しみでは泣かない
犬の悲しみが涙で表現されるわけではないことは、もうお分かりいただけたと思います。
では、悲しい気持ちになった時、犬はどのような行動を見せるのでしょうか。
例えば、大好きな飼い主さんと離れ離れになってしまうような時に、犬は悲しそうな表情でクンクンと鼻鳴きしたり、大好きなおやつもフードも全く食べなくなってしまったりすることがあります。
お気に入りのおもちゃで遊ぶこともやめてしまい、自分のベッドや、飼い主さんが出て行った玄関で丸まって動かなくなる犬もいます。
犬が悲しいという気持ちを抱いた時は、全ての興味を絶たれて元気がなくなり、シュンとしてしまうことが多くなるようです。
墓の上で泣く犬の不思議
海外の動画で、亡くなったおばあちゃんのお墓に寄り添うように横たわって、しきりにしゃくりあげるような犬の姿がありました。
その犬は、大好きなおばあちゃんがその墓石の下に埋められてしまったことを理解していたのでしょう。
犬は「死ぬ」ということを理解していないと言われています。
だからこの犬も、大好きなおばあちゃんが死んでしまったとは思っていないかもしれません。
でも、おばあちゃんが「会えないところに行ってしまった」ことを知り、悲しんでいるように見えます。
犬にとっては、死んだかどうかが問題なのではなく、「目の前から姿を消してしまった」という事実が悲しみなのではないかと思います。
人間と犬が、単なる飼い主とペットという関係を超えたパートナーであることを、改めて感じた動画でした。
犬が悲しい感情を抱く時
犬が悲しいと感じる時、その理由の一番に挙げられるのは、やはり家族や親しい犬友達など、大好きな誰かと離れ離れになる時ではないでしょうか。
帰ってくるのがわかっているはずなのに、飼い主さんが買い物やゴミ捨てに出ようとしただけで、犬は「行っちゃうの?」と悲しげな視線を投げかけてきたりします。
また、引っ越しなどで仲の良い犬友達が家族と一緒に挨拶に来た時にも、いつもと違う空気を感じて「お別れ」を理解し、悲しむことがあります。
人間の言葉が理解できなくても、「会えなくなる」という事実を、犬は感じられるようです。
それとは違い、飼い主さんに怒られた時にも、悲しい気持ちになる犬もいます。
犬にとっては遊びの一つで、きっと飼い主さんも喜んでくれると思ってやったのに、なぜか激怒されてしまった。
楽しみたかったのに怒られて無視されてしまったら、犬はとても悲しくなるでしょう。
でも、良い事と悪い事はしっかり教えなくてはなりません。
この場合の悲しみは、犬の大切な勉強です。
まとめ
 犬が涙を流す時、それは悲しみの表現ではなく、目の異常や違和感を知らせるサインです。
見逃さないように注意し、適切なケアと通院を心掛けていただきたいと思います。
でも、犬が誰かとの別れなどで丸まってシュンとしていたら、それは悲しい気持ちを抱えている時かもしれません。
どうかそんな時は、優しく寄り添って、犬の悲しみを和らげてあげてくださいね。
犬が涙を流す時、それは悲しみの表現ではなく、目の異常や違和感を知らせるサインです。
見逃さないように注意し、適切なケアと通院を心掛けていただきたいと思います。
でも、犬が誰かとの別れなどで丸まってシュンとしていたら、それは悲しい気持ちを抱えている時かもしれません。
どうかそんな時は、優しく寄り添って、犬の悲しみを和らげてあげてくださいね。
夏に犬が遊べる涼しいお出かけスポット~関東~
 犬は自身で体温調整することが苦手な動物であるため、夏は特に弱いです。
しかし、一日中エアコンの効いた室内にいることも犬にとってはよくありません。
そのため、屋外に出て遊ばすことも大切ですが、涼しい場所を選ぶことも必要になってきます。
次に、夏でも涼しく遊べるスポットを関東に絞って紹介します。
夏場でも犬にストレスを感じさせずに遊ばせたいと考えている人は参考にしてください。
犬は自身で体温調整することが苦手な動物であるため、夏は特に弱いです。
しかし、一日中エアコンの効いた室内にいることも犬にとってはよくありません。
そのため、屋外に出て遊ばすことも大切ですが、涼しい場所を選ぶことも必要になってきます。
次に、夏でも涼しく遊べるスポットを関東に絞って紹介します。
夏場でも犬にストレスを感じさせずに遊ばせたいと考えている人は参考にしてください。
東京都:国営昭和記念公園
東京都にある国営昭和記念公園は西立川駅の目の前にある公園であり、アクセスに非常に優れています。
5つのコースが用意されており、すべてのコースで楽しむことができます。
気分に合わせたり、季節によって散歩するコースを変えることで愛犬の気分転換をさせることもできます。
季節によって植物や野鳥などにも違いが現れるため、一年中通して楽しむことが可能になっています。
サイクリングコースも用意されているため、愛犬と一緒にサイクリングを楽しむこともできます。
売店の数も多く揃っていたり、バーべキューを行うことができる施設があるなど充実した公園です。
公園内には広大な池も存在しており、夏場でも涼しさを感じながら散歩することができ、水鳥を観察することもできます。
東京都:夕やけ小やけふれあいの里
東京都にある夕やけ小やけふれあいの里は童謡でも有名な夕焼け小焼けのモデルとなった施設になっています。
そのため、童謡の風景を思い浮かべるような環境になっており、夕焼けの綺麗さは絶景です。
そのため、涼しくなった夕暮れ時に散歩することで美しい風景を堪能することができます。
散歩だけではなく、宿泊施設も整っているため、一泊することも可能になっています。
また、日帰り入浴も可能になっているため、散歩で流した汗を流してから帰宅することもできます。
年中通してさまざまなイベントを行っており、夏場では星を眺めたり、田植えなどの体験も可能となっています。
愛犬だけではなく、家族連れで訪れることでより楽しむことができ、よい思い出作りをすることもできます。
千葉県:県立幕張海浜公園
千葉県にある県立幕張海浜公園の特徴はなんといっても総面積が71万9000㎡あることであり、幕張から都心近くまで伸びていることです。
そのため、愛犬を思いっきり遊ばすことができ、ストレス発散させることができます。
都心になればなるほど思いっきり走らせることができる環境が少なくなるため、貴重な散歩スポットでもあります。
海が近くにあるため、夏場でも比較的涼しく、愛犬も快適に走り回ることができます。
広大な広場以外にも公園や日本庭園も用意されています。
県立幕張海浜公園は7つのブロックに分かれており、それぞれブロックごとに施設の内容も変わっています。
犬の散歩には広大な広場でもあるD・Eブロックがおすすめです。
マリンスタジアムも県立幕張海浜公園の一部となっています。
い
千葉県:成田ゆめ牧場
千葉県にある成田ゆめ牧場は緑あふれる牧場であり、ウサギや牛、ヒツジなど多くの動物と触れ合うことができます。
家族連れを訪れることで子供に思い出を作ってあげることができます。
また、さまざまな体験コースも用意されているため、牛の乳しぼりなどを体験することが可能になっています。
動物と触れ合うことは犬にとってはあまりメリットに感じない場合も多いですが、ドッグランの施設も併設されているため、愛犬と一緒に楽しむことができます。
ドッグランにはさまざまな愛犬家が揃っている場合が多く、愛犬仲間を増やすことも可能になっています。
犬だけではなく、さまざまな動物が好きな人におすすめのスポットになっています。
やや標高が高い丘で営業していることもあり、夏場でも涼しいです。
る
夏に犬がお出かけする時の対策
 夏に愛犬とお出かけすることはストレス発散や運動不足解消にもつながりますが、上記でも紹介したように体温調整ができない動物であるため、さまざまな対策を行っておく必要があります。
対策なしで夏場にお出かけすることは危険であり、愛犬の健康を損ねてしまうリスクがあります。
次に、夏に犬と一緒にお出かけする際の対策を紹介します。
初めて愛犬と夏を過ごす方やどのような対策をすれば愛犬にとって良いのかを知りたい人は参考にしてください。
夏に愛犬とお出かけすることはストレス発散や運動不足解消にもつながりますが、上記でも紹介したように体温調整ができない動物であるため、さまざまな対策を行っておく必要があります。
対策なしで夏場にお出かけすることは危険であり、愛犬の健康を損ねてしまうリスクがあります。
次に、夏に犬と一緒にお出かけする際の対策を紹介します。
初めて愛犬と夏を過ごす方やどのような対策をすれば愛犬にとって良いのかを知りたい人は参考にしてください。
対策①トレイの準備と水分補給
愛犬と出かける際にはトイレの準備と水分補給ができるように準備しておきましょう。
トイレの準備は夏場に限った話ではなく、出かけるのであれば飼い主として持ち運ぶことがマナーとっています。
トイレの準備はビニール袋やスコップがあれば問題ありません。
水分補給も水で問題ないため、ペットボトルや犬専用の水筒を持参することをおすすめします。
夏場にはより水分を失ってしまうため、定期的に水分補給を行うようにしましょう。
特に、初めて行く施設や公園では水道の位置を把握できていない場合も多く、いつでも水分補給できるようにしましょう。
人と同じように水分が不足してしまうと脱水症状や熱中症になってしまいます。
対策②コンクリートは避ける
夏場は太陽から注がれる熱い太陽光だけではなく、地面にも注意しなければなりません。
人は靴を履いているため、感じにくくなっていますが、犬は直接地面に触れて歩くため、暑くなっている地面は避けて歩くようにしましょう。
特に、コンクリートやアスファルトなどは熱を帯びやすい地面であるため、極力避けることが好ましいです。
真夏ではやけどしてしまう恐れもあります。
土がむき出しになっている地面や芝生の地面がおすすめであり、やけどのリスクを大幅に削減することができます。
なかには犬に履かせる靴も販売されていますが、犬によっては嫌がってしまうこともあります。
対策③炎天下で長時間過ごさない
炎天下の中長時間過ごしてしまうと熱中症や脱水症状に陥ってしまうリスクがあります。
そのため、定期的に日陰で休憩させたり、水分補給をさせることが大切です。
炎天下での散歩は人でも苦痛に感じてしまいますが、汗をかいて体温調整することができない犬にとってはより苦行になってしまいます。
愛犬を夏場に散歩させたいのであれば昼間ではなく、朝方や夕暮れに行うことをおすすめします。
昼間の散歩は人だけではなく、愛犬によっても体に悪いため、行わないことが無難です。
特に体力がない老犬の場合は命に関わるため、夏の散歩は時間帯関係なく控えたり、曇りなど比較的気温が低いときに行いましょう。
対策④海辺でも肉球の火傷に注意
夏場には海辺で散歩すれば気温が涼しく夏におすすめのスポットと思われがちですが、注意しなければならないスポットでもあります。
海辺は気温は低いですが、太陽光の熱を帯びた砂浜では上記で紹介したコンクリートと同じくらい暑くなっています。
そのため、肉球をやけどしてしまう原因にもなるため、海辺で散歩させる際には注意しましょう。
どうしても愛犬と海辺に行きたいのであれば暑い砂浜は歩かないようにして、海水で濡れている浪打間際で散歩するように心がけましょう。
浪打間際の砂浜は暑くないため、愛犬も喜んで散歩したり、そのまま海に突っ込んでリラックスさせることもできます。
対策⑤冷たい水やジュースはあげない
上記では水分補給をすることが大切と紹介しましたが、冷たい水やジュースは与えないように注意しましょう。
冷たい水の方が体を冷やすことができるため、夏場の飲みとしてはおすすめな気がしますが、消化器系を悪くしてしまう原因になってしまいます。
人にも言えることですが、急激に冷たいものを胃や腸に入れてしまうと腸や胃の働きが悪くなってしまい、下痢や腹痛・食欲不振の原因にもなってしまいます。
また、糖分やさまざまな添加物が入れられている飲み物も本来摂取する飲み物ではないため、体調を崩してしまいかねます。
そのため、夏場での水分補給には常温の水がおすすめであり、愛犬にとっても負担が少ないです。
まとめ
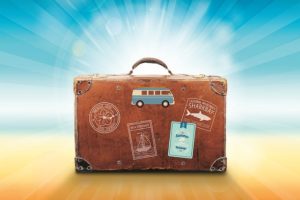 夏は人でもへばってしまう季節であり、体温調整することが難しい犬ではより苦痛を感じてしまう季節です。
しかし、室内ではストレスを感じてしまうため、夏場でも定期的に出かける必要があります。
夏場に犬とお出かけする場合は比較的涼しいスポットを選ぶことも大切ですが、注意しなければならないポイントも把握しておくようにしましょう。
夏場のお出かけするポイントを把握するだけでも愛犬にとって体に負担がかからないため、快適に散歩をすることができ、ストレス発散にもつながります。
夏は人でもへばってしまう季節であり、体温調整することが難しい犬ではより苦痛を感じてしまう季節です。
しかし、室内ではストレスを感じてしまうため、夏場でも定期的に出かける必要があります。
夏場に犬とお出かけする場合は比較的涼しいスポットを選ぶことも大切ですが、注意しなければならないポイントも把握しておくようにしましょう。
夏場のお出かけするポイントを把握するだけでも愛犬にとって体に負担がかからないため、快適に散歩をすることができ、ストレス発散にもつながります。
柴犬のおしりアタック!攻撃の理由は?
 柴犬を飼育している人でおしりアタックされた経験がある人も多くいるのではないでしょうか。
おしりアタックは強く当たってくる場合のありますが、飼い主の近くに座る際に少しお尻を当てながら座るなどさまざまなアタック方法があります。
次に、柴犬が行うおしりアタックの理由を紹介します。
おしりアタックしてくる理由を知りたい人は参考にしてください。
柴犬を飼育している人でおしりアタックされた経験がある人も多くいるのではないでしょうか。
おしりアタックは強く当たってくる場合のありますが、飼い主の近くに座る際に少しお尻を当てながら座るなどさまざまなアタック方法があります。
次に、柴犬が行うおしりアタックの理由を紹介します。
おしりアタックしてくる理由を知りたい人は参考にしてください。
おしりをぶつける理由
柴犬に限った話ではありませんが、おしりアタックする理由はその人物に対しての信頼の表れです。
慕っているやリラックスしていることの証拠であるため、愛犬がおしりアタックしてきたときはかまってあげることをおすすめします。
遊びたいときにも行う行動でもあります。
信頼とは別に安心感を求める際にも行い、不安やストレスを感じている時にも行うため、そばにいるだけでも愛犬にとっては安心しています。
場合によってはそこそこ強い勢いでおしりアタックをすることもあり、攻撃されていると勘違いしないようにしましょう。
愛犬がおしりアタックしてくれた時はそれだけ大切な存在という意味であるため、喜びましょう。
家族以外へぶつける理由
柴犬だけではなくさまざまの犬が行う行動におしりアタックがありますが、家族以外にも行うことがあります。
初めて会う人にも行う行動であり、家族に行う場合とは少し違った理由があります。
家族や飼い主におしりアタックをする理由は信頼ですが、初めて会う人に行う場合は挨拶として行っている場合が多いです。
特に、相手と仲良くなりたいと犬が感じている時に行う行動であるため、一緒に遊んだりすることですぐになついてくれる可能性も高いです。
さまざまな犬種が行う行動ですが、警戒心が強い犬よりも人懐っこい犬種の方が行う場合が多くなっています。
柴犬がおしりを上げるのは何故?
 柴犬はおしりアタックのほかにおしりを上げる行動も行います。
たびたび行う機会が多いポーズであるため、柴犬を飼っている人であれば一度は見たことがあるのではないでしょうか。
次に、柴犬が行うおしりを上げるポーズの理由を詳しく紹介します。
おしりを上げる意味を理解することで愛犬が考えていることを知ることができ、適した行動を行うことも可能になります。
柴犬はおしりアタックのほかにおしりを上げる行動も行います。
たびたび行う機会が多いポーズであるため、柴犬を飼っている人であれば一度は見たことがあるのではないでしょうか。
次に、柴犬が行うおしりを上げるポーズの理由を詳しく紹介します。
おしりを上げる意味を理解することで愛犬が考えていることを知ることができ、適した行動を行うことも可能になります。
プレイバウは遊びたい証拠
犬がお尻を上げることをプレイバウと呼ばれており、遊びたいという気持ちの表れです。
敵意がないことを示している場合もあり、一緒に遊んであげることでより強い信頼関係を築くことができます。
遊んでほしいときに遊んであげることで愛犬にストレスをためてしまうこともありません。
遊んでほしいときにおしりを上げた場合は耳がピンっと立っていたり、しっぽを振るなどさまざまな行動も同時に行います。
表情も遊んでほしそうにしていることもあり、プレイバウをする理由が遊んでほしいと理解できる場合も多くなっています。
可愛いボディランゲージの一種でもあります。
お祈りポーズは要注意
おしりを上げる理由は上記で紹介したプレイバウのほかにお祈りのポーズを行っている場合もあります。
お祈りのポーズはプレイバウと同じでお尻を上げるポーズを行います。
祈りのポーズを行っている場合は遊んでほしいのではなく、体調不良の表れです。
そのため、遊んであげることは逆効果であり、どのような症状で苦しんでいるのかをいち早く把握することが求められます。
場合によっては病院で診てもらう必要もあります。
下痢や腹痛の症状がある場合に行うケーズが多いですが、内臓に疾患があるときにも行う行動であるため、注意が必要です。
プレイバウとの違いは耳が垂れていたり、焦点が定まっていないなど、全体的に元気がない表情をしています。
症状によっては一刻を争う場合もあり、プレイバウとの違いを把握し、すぐに適切な行動を行うことが飼い主には求められます。
まとめ
 柴犬に限った話ではありませんが、さまざまな理由でお尻をぶつけてきたり、お尻を上げる行動を行います。
可愛いポーズでもありますが、どのような意味で行っているのかも把握しておくようにしましょう。
祈りのポーズをしている場合は命にも関わる場合もあるため、犬の行動には注意しておくことが大切です。
愛犬がお尻を上げている理由を把握して適した行動を行うことが愛犬にとってもメリットになります。
柴犬に限った話ではありませんが、さまざまな理由でお尻をぶつけてきたり、お尻を上げる行動を行います。
可愛いポーズでもありますが、どのような意味で行っているのかも把握しておくようにしましょう。
祈りのポーズをしている場合は命にも関わる場合もあるため、犬の行動には注意しておくことが大切です。
愛犬がお尻を上げている理由を把握して適した行動を行うことが愛犬にとってもメリットになります。
可哀想な犬の飼い方とは?
 多頭飼いと言えば、複数の犬を飼っている状態の事を言いますが、飼い主さんは一匹だと寂しいからと愛犬の事を思い、飼っている方が多かったり、赤ちゃんを産んで増えたりとご家庭によって様々です。
また、周辺の人からしたら「可哀想な飼い方をしている」と思っている人も多いでしょう。
しかし、愛犬はどう思っているのでしょうか。
多頭飼いにはデメリットもあるのですが、メリットももちろんあるのです。
それを可哀想と思うのか幸せと思うのかは考え方の違いによって違いますので、ここでは多頭飼いは可哀想なのか?という事をご紹介していきます。
多頭飼いと言えば、複数の犬を飼っている状態の事を言いますが、飼い主さんは一匹だと寂しいからと愛犬の事を思い、飼っている方が多かったり、赤ちゃんを産んで増えたりとご家庭によって様々です。
また、周辺の人からしたら「可哀想な飼い方をしている」と思っている人も多いでしょう。
しかし、愛犬はどう思っているのでしょうか。
多頭飼いにはデメリットもあるのですが、メリットももちろんあるのです。
それを可哀想と思うのか幸せと思うのかは考え方の違いによって違いますので、ここでは多頭飼いは可哀想なのか?という事をご紹介していきます。
多頭飼いは可哀相?メリットは?
犬は本来群れを作って生活をする生き物ですので、多頭飼育をした場合は、自然と群れのルールを覚えます。
愛犬を飼っていればわかっている方もいるかもしれませんが、犬は自分を犬と自覚しているというのは少なく、自分を人間だと思っている事がかなり多いそうです。
しかし、それは人間と自分という生活を送っているからであって、多頭飼いの場合は、仲間の犬がいるので、自分も犬だと自覚できるはず。
そして、1匹で飼っている場合は、どうしてもわがままになりがちになってしまいますが、多頭飼育で暮らしている犬たちは、その傾向が少なくルールの上で生活しているので、おりこうさんが多いのです。
おりこうさんの理由は群れで生活しているので社会性が見に付くという以外に、飼い主さん側の意識の変化による事の方が大きいと言われており、多頭飼育をしていると過保護な状況が改善され、飼い主によるしつけも厳しくなっていく傾向にあります。
多頭飼いによるデメリット
多頭飼いをする飼い主さんはまず先住犬がおり、先住犬が寂しくないように2頭目、3頭目を飼うという方が多いです。
先住犬としては、今まで自分だけが愛情を独占されていたのに、2頭目が現れた事により、大きなストレスを抱えてしまう事になります。
また、多くのご家庭の場合、2頭目は赤ちゃんの状態でやってくる事が多く、先住犬にとっては遊びざかりのやんちゃでしつこい子犬の相手をする事に対してもストレスを感じてしまいます。
このように、多頭飼いをする経緯にもよりますが、先住犬がいる場合は、まず先住犬を優先に構ってあげる事が大切です。
2~4週間すれば慣れてくるかと思うのですが、ストレスにより食欲低下や下痢・嘔吐などをする子も出てきてしまいますので、慣れてくるまでは先住犬の様子をしっかり見てあげるようにして下さいね。
可哀相な犬の飼い方を防ぐ方法
 動物を飼うという事は、命を預かるという事で、家族の一員として人生を全うするまで飼い続けるという飼い主さんの責任も発生してきます。
その意識を持っている飼い主さんの元であれば、幸せに暮らしていけると思うのですが、その意識を持てない飼い主さんもおり、残念ですが、そのような飼い主さんの元では可哀想な飼い方をしてしまうという結果になってしまいますので、可哀想な飼い方をしないためにも飼い主さんがもう一度考えないといけない事があります。
ここでは、可哀想な犬の飼い方を防ぐ方法をご紹介します。
動物を飼うという事は、命を預かるという事で、家族の一員として人生を全うするまで飼い続けるという飼い主さんの責任も発生してきます。
その意識を持っている飼い主さんの元であれば、幸せに暮らしていけると思うのですが、その意識を持てない飼い主さんもおり、残念ですが、そのような飼い主さんの元では可哀想な飼い方をしてしまうという結果になってしまいますので、可哀想な飼い方をしないためにも飼い主さんがもう一度考えないといけない事があります。
ここでは、可哀想な犬の飼い方を防ぐ方法をご紹介します。
犬を飼う目的を考える
犬を飼おうと思った時、何らかの目的が飼い主さんにはあるはずです。
そしてその目的によって飼う種類なども考える必要があります。
具体的には
POINT
・子供の情操教育のため
・番犬のため
・作業犬にするため
・繁殖させるため
・生活の伴侶として
など、様々ですが、初めて飼う方にとってはどんな種類がいいのか悩んでしまいます。
そのような時は獣医師や飼育経験の多い方などのアドバイスを受ける事をおすすめします。
また、保健所の動物保護担当や動物愛護団体などには飼い主さんを待っている犬が沢山いますので、実際に訪問し相談をしながら決めるのもいいでしょう。
家族全員から同意を得る
犬を飼う時に家族全員の同意を得ましたか?
もし家族の中に一人でも動物好きの人がいたとしても、その人が全て愛犬の面倒を見るのは不可能で、少なくとも一緒に住んでいる家族にも面倒を見てもらう必要が出てきます。
ですので、家族全員の理解と協力が必要になってきます。
飼いたいという願望は叶えてあげたいものですが、実際には、一番家にいる事が多いお母さんやおじいちゃん、おばあちゃんなどに負担がかかってくるかと思いますので、必ず同意を得る事が必須となってくるでしょう。
どのような犬が良いのか考える
飼う目的によって犬の種類などを考えると同時に、家の環境も考えてみる必要が出てきます。
無理な環境での飼育は飼われる犬にとって可哀想なだけでなく、近隣などに迷惑をかける事にも繋がってきますので、犬の大きさや性質、性別などについても考え、家庭環境の中で一番飼いやすく、問題を起こす危険性がない犬種を選択するという事が大切でしょう。
純血種か雑種かというのは余り気にする必要はなく、あくまでも犬の性質などを重点的において考えるようにして下さい。
心構えをしっかりと持つ
犬を飼うという事は、命を預かり最後までしっかり責任を持ってお世話をするという事です。
そして、家族の一員として、生活していく上で、喜びや悲しみを一緒にわかちあう良き伴侶として迎え入れる心構えをしっかり持つという事が大切です。
犬を飼うのは、人間の子供を育てる以上に世話やお金がかかってくるのもですので、一時的な感情や気まぐれで飼い始めるような事は絶対にしないで下さいね。
屋外で飼う場合の準備
今は室内犬として犬を飼う方の方が多くなってきましたが、屋外で飼う方の中にはいるでしょう。
屋外で犬を飼う場合、広い庭がある家は、その一部を愛犬用に囲って運動場とゲージを造ってあげるのが理想的。
しかし、囲いの中でも放して飼う場合は、穴を掘る習性や相当な跳躍力がある事を念頭に入れ、柵の高さや穴を掘っても大丈夫なようにコンクリートで埋めるなどの準備が必要です。
庭先などで飼う場合は、人通りの多い場所や密集している所、子供が集まる場所などは周囲の人に対する十分な配慮も必要ですので、道路や隣接地に出るような飼い方はやめましょう。
室内で飼う場合の準備
室内で犬を飼う事は今普通となっていますが、室外で飼う以上に人との共同生活ができるようにしつけをしなければいけません。
室内で飼うとなると、常に愛犬と一緒にいるという事で、甘やかしてしまう傾向が多いので、結果、社会性が見についていないわがままな犬になってしまいます。
まずはトイレのしつけから始めて十分なマナーをしつけによって身につけさせるようにしましょう。
先ほどもご紹介しましたが、犬は自分を犬と思っていません。
自分は犬でリーダーは飼い主さんという事を理解させるためにも、飼い始めた最初にしっかりしつけをする事が大切になってきます。
可哀想な犬の話
最後に可哀想な犬のお話を2つご紹介します。
題名は
・世界で一番悲しい犬のラナ
・飼い主に捨てられたローラ
という実話です。
犬は人間とは違い、駆け引きなどなく純粋に飼い主さんの心にそして家族の心にそっと寄り添ってくれます。
だからこそ、それ以上の愛情をもって育ててあげて欲しいという願いを込めてこのお話を送ります。
世界で一番悲しい犬のラナ
2015年にネット上に掲載された写真が話題となり動物保護施設で過ごすラナの存在が公になりました。
暗くて狭いシェルターの中で、うなだれるその姿は「世界で一番悲しい犬」と呼ばれています。
彼女はどうしてそんなに悲しみに暮れていたのか?
その理由はとても残酷なもので、当時、無事里親が見つかったラナは、新しい家族と幸せな生活を送るだろうと思われていたのですが、信じられない事にその里親はラナをまた施設へ送り返してきたのです。
送り返してきた理由として、彼女が新しい飼い主を激しく威嚇し、噛みつこうとしたため。
元々他の兄弟と比べて体が小さかったラナは、異常に食べ物を守ろうとする癖があったようです。
そして新しい飼い主から食べ物を守ろうと威嚇してしまい施設へ送り返される事になってしまったのです。
2度目の里親には、先住犬がおり、その犬の遊び相手としてラナを選んだのですが、ラナは人間にスキンシップを求めるような犬ではなく、甘えたいという性格ではなかったのでまた送り返されてしまい、次の保護期限までに里親が見つからなければ殺処分という事を言い渡されてしまいました。
施設の中で何度も心に傷を負ってしまったラナ。
彼女のパーソナリティーを理解した上で、また人間を信頼してもいいんだよと彼女を暖かく迎え入れてくれる事のできる里親が見つかればと願うばかりです。
その願いが届いたのか、殺処分寸前のところで、ラナを引き取りたいと申し出る人が現れ、ラナは再び新しい家族の元で暮らす事ができるようになりました!
これがラナにとって最後の家族になりますように。。。
飼い主に捨てられたローラ
ゴールデンレトリバーのローラは、無責任な飼い主に捨てられ変わり果てた姿となってしまった可哀想な犬でした。
ローラを保護した当時、ガリガリにやせ細り、路上を彷徨っていたそうです。
その姿はゴールデンレトリバーの面影など感じられず、生きているのが不思議なくらい衰弱しており、中耳炎や皮膚炎も患っている状態で、足は重度の感染症を引き越していました。
ボロボロになった口の中には犬歯しか残っておらず、後の検査で乳腺に腫瘍を抱えている事も判明します。
そんなローラを保護した方は彼女を病院へ連れて行きましたが、治療には莫大な費用がかかると告げられてしまい、その治療費をネット上で募金を募りながら治療が受けられる日を待っていたそうです。
ローラを捨てた飼い主は何故ローラにこんな仕打ちをしたのでしょうか?
どちらにしても、命を粗末にした事実には変わりはなく、ローラと同じような環境に置かれている犬が全国には沢山います。
このように飼い主の身勝手な理由で捨てられた犬たちはどう思っているのでしょう?
幸せになるために生まれてきたはずなのに、殺される最後になってしまうのは余りにも可哀想ですよね。
このような犬を出さないように、犬を飼う場合は、しっかり責任・愛情を持って最後まで飼ってあげる事が鉄則です。
まとめ
 今回は可哀想な犬についてご紹介してきました。
可哀想な犬というのは、飼い主さんから見てそうなのか?愛犬から見てそうなのか?周りから見てそうなのか?正解はありませんが、最終的には、愛犬が幸せだったなと思える最後にしてあげたいと思いますよね。
そして、犬を飼うという事に対し、簡単な気持ちではなくしっかり心構えを持つ事が日宇陽不可欠になってきますので、その気持ちがあるのか?もう一度自分に問いかけて決めるようにしましょう。
ラナやローラのような犬を出してしまう事は悲しみ以外の何物でもありませんし、このような犬が出てしまうのは犬のせいではなく、人間のせいなのです。
この事をもう一度考えて犬を受け入れるようにして下さい。
今回は可哀想な犬についてご紹介してきました。
可哀想な犬というのは、飼い主さんから見てそうなのか?愛犬から見てそうなのか?周りから見てそうなのか?正解はありませんが、最終的には、愛犬が幸せだったなと思える最後にしてあげたいと思いますよね。
そして、犬を飼うという事に対し、簡単な気持ちではなくしっかり心構えを持つ事が日宇陽不可欠になってきますので、その気持ちがあるのか?もう一度自分に問いかけて決めるようにしましょう。
ラナやローラのような犬を出してしまう事は悲しみ以外の何物でもありませんし、このような犬が出てしまうのは犬のせいではなく、人間のせいなのです。
この事をもう一度考えて犬を受け入れるようにして下さい。
猫の顔文字コピペ一覧~楽しい~
 猫の顔文字はさまざまあり、∩(^ω^∩) ´pゝω・)ニャンなどが有名でメールなどに記入するだけでも楽しさが伝わってきます。
そのほかにもりょうかいっ ~(=^・ω・^)ゞ ぴっ!! (ノФωФ)ノなどがあり、前者の場合はさまざまな用途で使用することができ、使用できる割合も比較的高く、顔文字の完成度も高いため、相手にも伝わりやすいです。
後者の顔文字の場合は猫が好奇心を抱いている時に見せる目がギラギラしている表情をうまく表現されていますが、猫の目をイメージしているとわからない人では猫の表情がもとになっているとわからない場合もあります。
猫の顔文字で文章にも楽しさが伝わるため、メールなどで使用されることが多いです。
猫の顔文字はさまざまあり、∩(^ω^∩) ´pゝω・)ニャンなどが有名でメールなどに記入するだけでも楽しさが伝わってきます。
そのほかにもりょうかいっ ~(=^・ω・^)ゞ ぴっ!! (ノФωФ)ノなどがあり、前者の場合はさまざまな用途で使用することができ、使用できる割合も比較的高く、顔文字の完成度も高いため、相手にも伝わりやすいです。
後者の顔文字の場合は猫が好奇心を抱いている時に見せる目がギラギラしている表情をうまく表現されていますが、猫の目をイメージしているとわからない人では猫の表情がもとになっているとわからない場合もあります。
猫の顔文字で文章にも楽しさが伝わるため、メールなどで使用されることが多いです。
猫の顔文字コピペ一覧~喜び~
 喜びの猫の顔文字には(=・ω・=) (=^・ω・^=) (ฅ^・ω・^ ฅ)などがあり、さまざまな場面で使用することができます喜びを表現したいときはもちろんですが、何気ない文章の語尾にも使うことができ、最もスタンだーとな顔文字になっています。
イコールを猫の髭をイメージしており、猫であることを容易にイメージさせることができます。
(ฅ^・ω・^ ฅ)の顔文字では両手を挙げて肉球を見せている姿の顔文字であり、少し凝った顔文字でもあります。
~(=^・ω・^)旦は猫がお茶を運んでいる姿の顔文字であり、うれしかった時やお礼の時に活用することをおすすめします。
∩(=^・ω・^=)は片手を挙げている顔文字で、了承した時に使用することができます。
喜びの猫の顔文字には(=・ω・=) (=^・ω・^=) (ฅ^・ω・^ ฅ)などがあり、さまざまな場面で使用することができます喜びを表現したいときはもちろんですが、何気ない文章の語尾にも使うことができ、最もスタンだーとな顔文字になっています。
イコールを猫の髭をイメージしており、猫であることを容易にイメージさせることができます。
(ฅ^・ω・^ ฅ)の顔文字では両手を挙げて肉球を見せている姿の顔文字であり、少し凝った顔文字でもあります。
~(=^・ω・^)旦は猫がお茶を運んでいる姿の顔文字であり、うれしかった時やお礼の時に活用することをおすすめします。
∩(=^・ω・^=)は片手を挙げている顔文字で、了承した時に使用することができます。
猫の顔文字コピペ一覧~泣く~
 泣いている猫の顔文字には(´-ω-`)」や(=‐ω‐=)がスタンダートであり、シンプルな顔文字であるため、理解されやすいですどちらも目が横棒で表示されているため、悲しい表情であることを伝えることができます。
(=;ェ;=)の顔文字では実際に涙を流している顔文字になっているため、より悲しいときに使用することをおすすめします。
≦(∩ェ∩)≧...ニャン は両手で目を押さえて泣いている姿の顔文字であり、可愛い顔文字でありながら悲しさも伝わってきます。
泣いている猫の顔文字に中には可愛らしい顔文字も多くありますが、(=;ω;=)のように少し変わりづらく、泣いているのかもわかりずらいも顔文字も存在しています。
泣いている猫の顔文字には(´-ω-`)」や(=‐ω‐=)がスタンダートであり、シンプルな顔文字であるため、理解されやすいですどちらも目が横棒で表示されているため、悲しい表情であることを伝えることができます。
(=;ェ;=)の顔文字では実際に涙を流している顔文字になっているため、より悲しいときに使用することをおすすめします。
≦(∩ェ∩)≧...ニャン は両手で目を押さえて泣いている姿の顔文字であり、可愛い顔文字でありながら悲しさも伝わってきます。
泣いている猫の顔文字に中には可愛らしい顔文字も多くありますが、(=;ω;=)のように少し変わりづらく、泣いているのかもわかりずらいも顔文字も存在しています。
猫の顔文字コピペ一覧~怒り~
 猫の顔文字の怒りでは(=`ω´=) ム!がスタンダードであり、意味も伝わりやすい顔文字に仕上がっています。
ツリ目がうまく表現されていることで怒っていたり、不機嫌であることを伝えることができ、ム!の言葉があることでより怒っていることを伝えることが可能です。
(「ФДФ)「は目をギラつかせながら片手を挙げている顔文字であり、引っかかれることを相手に想像させることができます。
(p`・ω・´) qは両手を握ってこれから猫パンチをする顔文字であり、怒っていることを伝えつつも可愛さも伝えることができます。
そのため、怒りをマイルドに包んで相手に伝えることが可能です。
(p`ω´) qも似ている顔文字ですが、目が吊り上がっているため、より怒っていることを伝えることができます。
猫の顔文字の怒りでは(=`ω´=) ム!がスタンダードであり、意味も伝わりやすい顔文字に仕上がっています。
ツリ目がうまく表現されていることで怒っていたり、不機嫌であることを伝えることができ、ム!の言葉があることでより怒っていることを伝えることが可能です。
(「ФДФ)「は目をギラつかせながら片手を挙げている顔文字であり、引っかかれることを相手に想像させることができます。
(p`・ω・´) qは両手を握ってこれから猫パンチをする顔文字であり、怒っていることを伝えつつも可愛さも伝えることができます。
そのため、怒りをマイルドに包んで相手に伝えることが可能です。
(p`ω´) qも似ている顔文字ですが、目が吊り上がっているため、より怒っていることを伝えることができます。
猫の顔文字は全身も表現可能?
 猫の顔文字には全身を表現されている顔文字も存在しています。
体まで表現した顔文字になると横一列では表現しきれない場合が多く、縦数列を使って仕上げられることが多いです。
しかし、大きな顔文字になることもあり、使用されることも少ないです。
次に、コンパクトに表示できる体全体の顔文字を紹介します。
全身を表すことができる顔文字を知りたい人は参考にしてください。
猫の顔文字には全身を表現されている顔文字も存在しています。
体まで表現した顔文字になると横一列では表現しきれない場合が多く、縦数列を使って仕上げられることが多いです。
しかし、大きな顔文字になることもあり、使用されることも少ないです。
次に、コンパクトに表示できる体全体の顔文字を紹介します。
全身を表すことができる顔文字を知りたい人は参考にしてください。
全身を表す猫の顔文字
一般的な猫の顔文字は猫の顔だけを表示させる顔文字であるため、体は表示されていません。
しかし、ᓚᘏᗢ ᗢᘏᓗ は猫の全身が描かれている顔文字に仕上げられています。
互いの猫が向き合っているような顔文字であり、香箱座りしているように見えます。
二匹が向かい合っているため、可愛らしいです。
二匹で表示することが一般的ですが、一匹でも使用することができます。
猫が寝ている顔文字でもあるため、お昼寝などをする際の語尾に使用することで可愛らしさを強調することができます。
猫耳が特徴的な顔文字
 猫といえば耳がピンと立っている姿を想像する人も多くいるのではないでしょうか。
(^・x・^)は猫の耳がうまく表現できている顔文字であり、さまざまな場面で活用することができます。
スタンダードな顔文字であるため、猫の顔文字を使いたいと考えている人におすすめです。
シンプルな顔文字でもあるため、さまざまなアレンジを加えやすい特徴もあります。
(=^・・^)は横にイコールを記入した顔文字であり、猫が横を向いている姿になっています。
「^」を取り入れれば耳が特徴的な猫の顔文字に仕上げることができるため、上記までに紹介した顔文字の耳の部分を変えるだけでも耳を印象付けることができます。
「^」を使って耳が可愛らしい猫の顔文字を作ってみてはいかがでしょうか。
猫といえば耳がピンと立っている姿を想像する人も多くいるのではないでしょうか。
(^・x・^)は猫の耳がうまく表現できている顔文字であり、さまざまな場面で活用することができます。
スタンダードな顔文字であるため、猫の顔文字を使いたいと考えている人におすすめです。
シンプルな顔文字でもあるため、さまざまなアレンジを加えやすい特徴もあります。
(=^・・^)は横にイコールを記入した顔文字であり、猫が横を向いている姿になっています。
「^」を取り入れれば耳が特徴的な猫の顔文字に仕上げることができるため、上記までに紹介した顔文字の耳の部分を変えるだけでも耳を印象付けることができます。
「^」を使って耳が可愛らしい猫の顔文字を作ってみてはいかがでしょうか。
可愛い!海外文字で猫の手を表現
猫の顔文字はどれも可愛らしく仕上げられていますが、なかには見たことがない文字が使用されています
なかでも「ฅ」はタイの言葉であり、タイ語の子音「kh」で「コー・コン」という名前です。
猫の手を表している際によく使われる言葉であり、可愛らしさを強調することができます。
「ฅ」は猫の顔文字で多用されていますが、タイでは廃語であるため、使われることはありません。
また、「ฅ」と非常に似ている「ต」という、文字も存在しています。
まとめ
顔文字は数多く存在していますが、なかでも猫の顔文字は可愛いこともあり、人気があります。
特に、若い女性が使用することもあり、文章に可愛らしさを表現することができます。
猫は喜怒哀楽が激しい生き物であるため、猫の顔文字にもさまざまな感情を表している顔文字があります。
猫の顔文字を使用して地味な文章に華を加えてみてはいかがでしょうか。
 SNSで話題急上昇中の小太郎くんは、冬になるとストーブの前が定位置になるユニークな柴犬です。
柴犬は硬くてしっかりとしたオーバーコートと、断熱効果の高いアンダーコートの2層で体が覆われています。
だからとても暑がりな犬種です。
その分、雪の中でも震えることなく元気に走り回ることができるような、とても寒さに強い犬なのです。
しかし小太郎くんの場合は少し違うようです。
小太郎くんは、どうしてストーブの前から動かなくなってしまうのでしょうか。
寒いから?それとも他に理由が?
今日は、そんな小太郎くん一家の日常を、少しだけ覗かせてもらいましょう。
SNSで話題急上昇中の小太郎くんは、冬になるとストーブの前が定位置になるユニークな柴犬です。
柴犬は硬くてしっかりとしたオーバーコートと、断熱効果の高いアンダーコートの2層で体が覆われています。
だからとても暑がりな犬種です。
その分、雪の中でも震えることなく元気に走り回ることができるような、とても寒さに強い犬なのです。
しかし小太郎くんの場合は少し違うようです。
小太郎くんは、どうしてストーブの前から動かなくなってしまうのでしょうか。
寒いから?それとも他に理由が?
今日は、そんな小太郎くん一家の日常を、少しだけ覗かせてもらいましょう。
 ストーブの前に座り、決して動こうとしない小太郎くん。
面白柴犬の投稿かなぁと思いきや、赤ちゃんとのふれあいには心温まるものがありました。
人間と犬は一緒に暮してきた歴史が長い分、ふとした時に犬の人間的な一面を垣間見ることができるのかもしれません。
それにしても小太郎くん、本当にあんなにストーブに近づいて熱くないのかな。
飼い主さんはストーブガード購入も検討しますと話していましたが、もし購入したら、ストーブガードを前にした小太郎くんの姿も見てみたいですね。
ストーブの前に座り、決して動こうとしない小太郎くん。
面白柴犬の投稿かなぁと思いきや、赤ちゃんとのふれあいには心温まるものがありました。
人間と犬は一緒に暮してきた歴史が長い分、ふとした時に犬の人間的な一面を垣間見ることができるのかもしれません。
それにしても小太郎くん、本当にあんなにストーブに近づいて熱くないのかな。
飼い主さんはストーブガード購入も検討しますと話していましたが、もし購入したら、ストーブガードを前にした小太郎くんの姿も見てみたいですね。
 柴犬は飼い主さんやその家族には従順で忠誠ですが、いきなり何故かつれなくなってしまうなんて事は日常茶飯事なのです。
実はツンデレは柴犬の得意過ぎる分野ですので、息をするように、普通の事という訳ですね。
なので、飼い主さんは常に、見事に踊らされているという事になっちゃっているのです。
そこで、ここでは柴犬あるあるのツンデレの「ツン」部分をご紹介しましょう。
柴犬は飼い主さんやその家族には従順で忠誠ですが、いきなり何故かつれなくなってしまうなんて事は日常茶飯事なのです。
実はツンデレは柴犬の得意過ぎる分野ですので、息をするように、普通の事という訳ですね。
なので、飼い主さんは常に、見事に踊らされているという事になっちゃっているのです。
そこで、ここでは柴犬あるあるのツンデレの「ツン」部分をご紹介しましょう。
 柴犬と言えば、キリっとした顔立ちを崩さず見知らぬ人には警戒し、決して簡単に愛想をふりまかない。
かと思うと飼い主さんにはとても忠実で、番犬としてしっかり家族を守る。
そんな勇敢な性格を持っています。
そこで、次は柴犬あるあるツンデレの「デレ」編をご紹介します。
柴犬と言えば、キリっとした顔立ちを崩さず見知らぬ人には警戒し、決して簡単に愛想をふりまかない。
かと思うと飼い主さんにはとても忠実で、番犬としてしっかり家族を守る。
そんな勇敢な性格を持っています。
そこで、次は柴犬あるあるツンデレの「デレ」編をご紹介します。
 いきなりですが柴距離という言葉をご存じですか?
柴距離という言葉が表しているように、柴犬特有のツンデレな性格が出ている距離感なのですが、ここでは、その柴距離についてご紹介していきます。
柴距離が理解できると、自然と愛犬に接する行動や態度も変わってくるかもしれませんね。
いきなりですが柴距離という言葉をご存じですか?
柴距離という言葉が表しているように、柴犬特有のツンデレな性格が出ている距離感なのですが、ここでは、その柴距離についてご紹介していきます。
柴距離が理解できると、自然と愛犬に接する行動や態度も変わってくるかもしれませんね。
 今回は柴犬のツンデレについてご紹介してきました。
他の犬種には中々見られない、柴犬特有のツンデレな性格や、柴距離は初めて柴犬を飼う飼い主さんには最初戸惑ってしまうのかもしれませんが、この行動は決して飼い主さんを嫌っているのではないという事を知っておきましょう。
理由は判明されていませんが、本能的なものが大きく影響しているようなので、「柴犬はこれが普通」と身構えて甘えてくるのを待っているのがいいのかもしれません。
柴犬は本当に飼い主さんやその家族に一途で愛してくれています。
そんな柴犬にメロメロになる方が多いので、人気ランキングでは常に上位にいるのでしょう。
今回は柴犬のツンデレについてご紹介してきました。
他の犬種には中々見られない、柴犬特有のツンデレな性格や、柴距離は初めて柴犬を飼う飼い主さんには最初戸惑ってしまうのかもしれませんが、この行動は決して飼い主さんを嫌っているのではないという事を知っておきましょう。
理由は判明されていませんが、本能的なものが大きく影響しているようなので、「柴犬はこれが普通」と身構えて甘えてくるのを待っているのがいいのかもしれません。
柴犬は本当に飼い主さんやその家族に一途で愛してくれています。
そんな柴犬にメロメロになる方が多いので、人気ランキングでは常に上位にいるのでしょう。
 こんにちは!みなさんの愛犬には気が合うお友達はいますか?人と同じで犬も、すぐ意気投合して仲良くなれるコとちょっと苦手かも・・・というコがいますよね。
また飼い主さん同士の相性もあるし、面倒に思われるかもしれません。
しかし毎日の愛犬との生活の中で、不安に思う事や心配事など色々と共有できる犬友アプリは、手軽なコミュニケーションツールとして利用する飼い主さんが増えてきています。
こんにちは!みなさんの愛犬には気が合うお友達はいますか?人と同じで犬も、すぐ意気投合して仲良くなれるコとちょっと苦手かも・・・というコがいますよね。
また飼い主さん同士の相性もあるし、面倒に思われるかもしれません。
しかし毎日の愛犬との生活の中で、不安に思う事や心配事など色々と共有できる犬友アプリは、手軽なコミュニケーションツールとして利用する飼い主さんが増えてきています。
 可愛い愛犬のベストショットや思い出の動画をシェアできるアプリは、普段から使っている飼い主さんも多いのではないでしょうか。
飼い主さんに一番人気がある画像・動画共有アプリは、愛犬の日常をUPする事で他の飼い主さんとの会話が生まれて交流できるので、肩に力を入れずに楽しむ事が出来ますよね。
オススメのアプリをいくつかご紹介していきますので、気になったアプリがあったら是非ダウンロードしてみて下さいね。
可愛い愛犬のベストショットや思い出の動画をシェアできるアプリは、普段から使っている飼い主さんも多いのではないでしょうか。
飼い主さんに一番人気がある画像・動画共有アプリは、愛犬の日常をUPする事で他の飼い主さんとの会話が生まれて交流できるので、肩に力を入れずに楽しむ事が出来ますよね。
オススメのアプリをいくつかご紹介していきますので、気になったアプリがあったら是非ダウンロードしてみて下さいね。
 今、側にいる愛犬が初めて家族に迎えたワンちゃんであれば、「あの時、こうやっていれば・・」など後悔している事がひとつやふたつはあるのではないでしょうか。
人と同じく個性を持つ犬は、環境や接し方によって育ち方も変わりますし、病気の前兆も見過ごしてしまう可能性もあります。
そんな時に獣医師さんやトレーナーさんのサポートが受けられたり、犬友さんと交流が持てるアプリがあるだけで飼い主さんの気持ちに安心感も生まれますよね。
今、側にいる愛犬が初めて家族に迎えたワンちゃんであれば、「あの時、こうやっていれば・・」など後悔している事がひとつやふたつはあるのではないでしょうか。
人と同じく個性を持つ犬は、環境や接し方によって育ち方も変わりますし、病気の前兆も見過ごしてしまう可能性もあります。
そんな時に獣医師さんやトレーナーさんのサポートが受けられたり、犬友さんと交流が持てるアプリがあるだけで飼い主さんの気持ちに安心感も生まれますよね。
 なかなか外出して犬友を作る事が難しい飼い主さんも、気軽に登録・交流できるアプリがたくさんあります。
飼い主さんがどんな目的で犬友を作りたいのかを考えて、内容やライフスタイルに合ったアプリを選んでみてくださいね。
また他の飼い主さんとコミュニケーションを取る際、顔が見えず文章では抑揚が分かりにくい事が難点とも言えます。
お互いが楽しく過ごせるよう注意して、愛犬との充実した毎日に生かしてくださいね。
なかなか外出して犬友を作る事が難しい飼い主さんも、気軽に登録・交流できるアプリがたくさんあります。
飼い主さんがどんな目的で犬友を作りたいのかを考えて、内容やライフスタイルに合ったアプリを選んでみてくださいね。
また他の飼い主さんとコミュニケーションを取る際、顔が見えず文章では抑揚が分かりにくい事が難点とも言えます。
お互いが楽しく過ごせるよう注意して、愛犬との充実した毎日に生かしてくださいね。
 外出の際に愛犬と散歩をしている飼い主の方を見かける事がありますが、犬種に違いはあっても仲睦まじい光景にはとても癒されます。
日本の犬として代表的な柴犬の後ろ姿には、言葉では言い表せないような可愛らしさがあります。
表情や動作にも目を引くものがあり、そばに行って触れてみたくなってしまいます。
2017年に犬種別犬登録頭数が5位で、アメリカでは年間1,000頭以上も登録されています。
小柄で室内でも飼いやすいと、日本や海外でも人気のある柴犬の魅力を紹介します。
外出の際に愛犬と散歩をしている飼い主の方を見かける事がありますが、犬種に違いはあっても仲睦まじい光景にはとても癒されます。
日本の犬として代表的な柴犬の後ろ姿には、言葉では言い表せないような可愛らしさがあります。
表情や動作にも目を引くものがあり、そばに行って触れてみたくなってしまいます。
2017年に犬種別犬登録頭数が5位で、アメリカでは年間1,000頭以上も登録されています。
小柄で室内でも飼いやすいと、日本や海外でも人気のある柴犬の魅力を紹介します。
 柴犬の愛嬌のあるキツネ顔やタヌキ顔が海外でも人気を集めていて、セラピードックにもなれる癒し犬としても高い評価を得ています。
小豆柴は柴犬同様に飼い主に忠実でしつけがしやすい面があり、赤毛、胡麻、黒毛が多く白毛の子もいてもふもふ感があります。
可愛い表情とコミカルな動きで、癒しを与えてくれる小豆柴の魅力を紹介します。
柴犬の愛嬌のあるキツネ顔やタヌキ顔が海外でも人気を集めていて、セラピードックにもなれる癒し犬としても高い評価を得ています。
小豆柴は柴犬同様に飼い主に忠実でしつけがしやすい面があり、赤毛、胡麻、黒毛が多く白毛の子もいてもふもふ感があります。
可愛い表情とコミカルな動きで、癒しを与えてくれる小豆柴の魅力を紹介します。
 日本でも海外でも人気を集めている柴犬と小豆柴にはいくつもの魅力があり、飼い主や周りの人に癒しを与えてくれ疲れや嫌な事を忘れさせてくれます。
犬を飼っている方にとって自分の愛犬が最高だとは思いますが、柴犬には日本犬の懐かしさがあり親しみを感じてしまいます。
様々な事情で犬の飼えない人には「忠犬もちしば」のぬいぐるみや「小豆柴の郷」がおすすめです。
日本でも海外でも人気を集めている柴犬と小豆柴にはいくつもの魅力があり、飼い主や周りの人に癒しを与えてくれ疲れや嫌な事を忘れさせてくれます。
犬を飼っている方にとって自分の愛犬が最高だとは思いますが、柴犬には日本犬の懐かしさがあり親しみを感じてしまいます。
様々な事情で犬の飼えない人には「忠犬もちしば」のぬいぐるみや「小豆柴の郷」がおすすめです。
 犬は「鳴く」とは言いますが、「泣く」とはあまり表現されません。
しかし、犬も「泣く」ことがあります。
人間のように感情がたかぶって涙を流すというわけではありませんが、目の異常や保護のために泣くことがあるのです。
愛犬が涙を流すようなことがあったら、目の観察をしてみてあげてくださいね。
次の項目から、犬が泣くときにどんなことが考えられるかを見ていきましょう。
犬は「鳴く」とは言いますが、「泣く」とはあまり表現されません。
しかし、犬も「泣く」ことがあります。
人間のように感情がたかぶって涙を流すというわけではありませんが、目の異常や保護のために泣くことがあるのです。
愛犬が涙を流すようなことがあったら、目の観察をしてみてあげてくださいね。
次の項目から、犬が泣くときにどんなことが考えられるかを見ていきましょう。
 犬が涙を流すと悲しげに見えてしまいますが、実際には犬の感情と涙には、人間のような関係性はないと言われています。
先にお話しした病気や異物が原因だと考えられています。
でも犬にも「悲しい」という気持ちは存在します。
犬が悲しみを感じた時、どのような行動や表情を見せるのでしょうか。
様々な事例もご紹介します。
犬が涙を流すと悲しげに見えてしまいますが、実際には犬の感情と涙には、人間のような関係性はないと言われています。
先にお話しした病気や異物が原因だと考えられています。
でも犬にも「悲しい」という気持ちは存在します。
犬が悲しみを感じた時、どのような行動や表情を見せるのでしょうか。
様々な事例もご紹介します。
 犬が涙を流す時、それは悲しみの表現ではなく、目の異常や違和感を知らせるサインです。
見逃さないように注意し、適切なケアと通院を心掛けていただきたいと思います。
でも、犬が誰かとの別れなどで丸まってシュンとしていたら、それは悲しい気持ちを抱えている時かもしれません。
どうかそんな時は、優しく寄り添って、犬の悲しみを和らげてあげてくださいね。
犬が涙を流す時、それは悲しみの表現ではなく、目の異常や違和感を知らせるサインです。
見逃さないように注意し、適切なケアと通院を心掛けていただきたいと思います。
でも、犬が誰かとの別れなどで丸まってシュンとしていたら、それは悲しい気持ちを抱えている時かもしれません。
どうかそんな時は、優しく寄り添って、犬の悲しみを和らげてあげてくださいね。
 犬は自身で体温調整することが苦手な動物であるため、夏は特に弱いです。
しかし、一日中エアコンの効いた室内にいることも犬にとってはよくありません。
そのため、屋外に出て遊ばすことも大切ですが、涼しい場所を選ぶことも必要になってきます。
次に、夏でも涼しく遊べるスポットを関東に絞って紹介します。
夏場でも犬にストレスを感じさせずに遊ばせたいと考えている人は参考にしてください。
犬は自身で体温調整することが苦手な動物であるため、夏は特に弱いです。
しかし、一日中エアコンの効いた室内にいることも犬にとってはよくありません。
そのため、屋外に出て遊ばすことも大切ですが、涼しい場所を選ぶことも必要になってきます。
次に、夏でも涼しく遊べるスポットを関東に絞って紹介します。
夏場でも犬にストレスを感じさせずに遊ばせたいと考えている人は参考にしてください。
 夏に愛犬とお出かけすることはストレス発散や運動不足解消にもつながりますが、上記でも紹介したように体温調整ができない動物であるため、さまざまな対策を行っておく必要があります。
対策なしで夏場にお出かけすることは危険であり、愛犬の健康を損ねてしまうリスクがあります。
次に、夏に犬と一緒にお出かけする際の対策を紹介します。
初めて愛犬と夏を過ごす方やどのような対策をすれば愛犬にとって良いのかを知りたい人は参考にしてください。
夏に愛犬とお出かけすることはストレス発散や運動不足解消にもつながりますが、上記でも紹介したように体温調整ができない動物であるため、さまざまな対策を行っておく必要があります。
対策なしで夏場にお出かけすることは危険であり、愛犬の健康を損ねてしまうリスクがあります。
次に、夏に犬と一緒にお出かけする際の対策を紹介します。
初めて愛犬と夏を過ごす方やどのような対策をすれば愛犬にとって良いのかを知りたい人は参考にしてください。
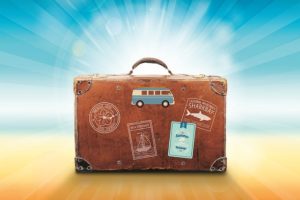 夏は人でもへばってしまう季節であり、体温調整することが難しい犬ではより苦痛を感じてしまう季節です。
しかし、室内ではストレスを感じてしまうため、夏場でも定期的に出かける必要があります。
夏場に犬とお出かけする場合は比較的涼しいスポットを選ぶことも大切ですが、注意しなければならないポイントも把握しておくようにしましょう。
夏場のお出かけするポイントを把握するだけでも愛犬にとって体に負担がかからないため、快適に散歩をすることができ、ストレス発散にもつながります。
夏は人でもへばってしまう季節であり、体温調整することが難しい犬ではより苦痛を感じてしまう季節です。
しかし、室内ではストレスを感じてしまうため、夏場でも定期的に出かける必要があります。
夏場に犬とお出かけする場合は比較的涼しいスポットを選ぶことも大切ですが、注意しなければならないポイントも把握しておくようにしましょう。
夏場のお出かけするポイントを把握するだけでも愛犬にとって体に負担がかからないため、快適に散歩をすることができ、ストレス発散にもつながります。
 柴犬を飼育している人でおしりアタックされた経験がある人も多くいるのではないでしょうか。
おしりアタックは強く当たってくる場合のありますが、飼い主の近くに座る際に少しお尻を当てながら座るなどさまざまなアタック方法があります。
次に、柴犬が行うおしりアタックの理由を紹介します。
おしりアタックしてくる理由を知りたい人は参考にしてください。
柴犬を飼育している人でおしりアタックされた経験がある人も多くいるのではないでしょうか。
おしりアタックは強く当たってくる場合のありますが、飼い主の近くに座る際に少しお尻を当てながら座るなどさまざまなアタック方法があります。
次に、柴犬が行うおしりアタックの理由を紹介します。
おしりアタックしてくる理由を知りたい人は参考にしてください。
 柴犬はおしりアタックのほかにおしりを上げる行動も行います。
たびたび行う機会が多いポーズであるため、柴犬を飼っている人であれば一度は見たことがあるのではないでしょうか。
次に、柴犬が行うおしりを上げるポーズの理由を詳しく紹介します。
おしりを上げる意味を理解することで愛犬が考えていることを知ることができ、適した行動を行うことも可能になります。
柴犬はおしりアタックのほかにおしりを上げる行動も行います。
たびたび行う機会が多いポーズであるため、柴犬を飼っている人であれば一度は見たことがあるのではないでしょうか。
次に、柴犬が行うおしりを上げるポーズの理由を詳しく紹介します。
おしりを上げる意味を理解することで愛犬が考えていることを知ることができ、適した行動を行うことも可能になります。
 柴犬に限った話ではありませんが、さまざまな理由でお尻をぶつけてきたり、お尻を上げる行動を行います。
可愛いポーズでもありますが、どのような意味で行っているのかも把握しておくようにしましょう。
祈りのポーズをしている場合は命にも関わる場合もあるため、犬の行動には注意しておくことが大切です。
愛犬がお尻を上げている理由を把握して適した行動を行うことが愛犬にとってもメリットになります。
柴犬に限った話ではありませんが、さまざまな理由でお尻をぶつけてきたり、お尻を上げる行動を行います。
可愛いポーズでもありますが、どのような意味で行っているのかも把握しておくようにしましょう。
祈りのポーズをしている場合は命にも関わる場合もあるため、犬の行動には注意しておくことが大切です。
愛犬がお尻を上げている理由を把握して適した行動を行うことが愛犬にとってもメリットになります。
 多頭飼いと言えば、複数の犬を飼っている状態の事を言いますが、飼い主さんは一匹だと寂しいからと愛犬の事を思い、飼っている方が多かったり、赤ちゃんを産んで増えたりとご家庭によって様々です。
また、周辺の人からしたら「可哀想な飼い方をしている」と思っている人も多いでしょう。
しかし、愛犬はどう思っているのでしょうか。
多頭飼いにはデメリットもあるのですが、メリットももちろんあるのです。
それを可哀想と思うのか幸せと思うのかは考え方の違いによって違いますので、ここでは多頭飼いは可哀想なのか?という事をご紹介していきます。
多頭飼いと言えば、複数の犬を飼っている状態の事を言いますが、飼い主さんは一匹だと寂しいからと愛犬の事を思い、飼っている方が多かったり、赤ちゃんを産んで増えたりとご家庭によって様々です。
また、周辺の人からしたら「可哀想な飼い方をしている」と思っている人も多いでしょう。
しかし、愛犬はどう思っているのでしょうか。
多頭飼いにはデメリットもあるのですが、メリットももちろんあるのです。
それを可哀想と思うのか幸せと思うのかは考え方の違いによって違いますので、ここでは多頭飼いは可哀想なのか?という事をご紹介していきます。
 動物を飼うという事は、命を預かるという事で、家族の一員として人生を全うするまで飼い続けるという飼い主さんの責任も発生してきます。
その意識を持っている飼い主さんの元であれば、幸せに暮らしていけると思うのですが、その意識を持てない飼い主さんもおり、残念ですが、そのような飼い主さんの元では可哀想な飼い方をしてしまうという結果になってしまいますので、可哀想な飼い方をしないためにも飼い主さんがもう一度考えないといけない事があります。
ここでは、可哀想な犬の飼い方を防ぐ方法をご紹介します。
動物を飼うという事は、命を預かるという事で、家族の一員として人生を全うするまで飼い続けるという飼い主さんの責任も発生してきます。
その意識を持っている飼い主さんの元であれば、幸せに暮らしていけると思うのですが、その意識を持てない飼い主さんもおり、残念ですが、そのような飼い主さんの元では可哀想な飼い方をしてしまうという結果になってしまいますので、可哀想な飼い方をしないためにも飼い主さんがもう一度考えないといけない事があります。
ここでは、可哀想な犬の飼い方を防ぐ方法をご紹介します。
 今回は可哀想な犬についてご紹介してきました。
可哀想な犬というのは、飼い主さんから見てそうなのか?愛犬から見てそうなのか?周りから見てそうなのか?正解はありませんが、最終的には、愛犬が幸せだったなと思える最後にしてあげたいと思いますよね。
そして、犬を飼うという事に対し、簡単な気持ちではなくしっかり心構えを持つ事が日宇陽不可欠になってきますので、その気持ちがあるのか?もう一度自分に問いかけて決めるようにしましょう。
ラナやローラのような犬を出してしまう事は悲しみ以外の何物でもありませんし、このような犬が出てしまうのは犬のせいではなく、人間のせいなのです。
この事をもう一度考えて犬を受け入れるようにして下さい。
今回は可哀想な犬についてご紹介してきました。
可哀想な犬というのは、飼い主さんから見てそうなのか?愛犬から見てそうなのか?周りから見てそうなのか?正解はありませんが、最終的には、愛犬が幸せだったなと思える最後にしてあげたいと思いますよね。
そして、犬を飼うという事に対し、簡単な気持ちではなくしっかり心構えを持つ事が日宇陽不可欠になってきますので、その気持ちがあるのか?もう一度自分に問いかけて決めるようにしましょう。
ラナやローラのような犬を出してしまう事は悲しみ以外の何物でもありませんし、このような犬が出てしまうのは犬のせいではなく、人間のせいなのです。
この事をもう一度考えて犬を受け入れるようにして下さい。
 猫の顔文字はさまざまあり、∩(^ω^∩) ´pゝω・)ニャンなどが有名でメールなどに記入するだけでも楽しさが伝わってきます。
そのほかにもりょうかいっ ~(=^・ω・^)ゞ ぴっ!! (ノФωФ)ノなどがあり、前者の場合はさまざまな用途で使用することができ、使用できる割合も比較的高く、顔文字の完成度も高いため、相手にも伝わりやすいです。
後者の顔文字の場合は猫が好奇心を抱いている時に見せる目がギラギラしている表情をうまく表現されていますが、猫の目をイメージしているとわからない人では猫の表情がもとになっているとわからない場合もあります。
猫の顔文字で文章にも楽しさが伝わるため、メールなどで使用されることが多いです。
猫の顔文字はさまざまあり、∩(^ω^∩) ´pゝω・)ニャンなどが有名でメールなどに記入するだけでも楽しさが伝わってきます。
そのほかにもりょうかいっ ~(=^・ω・^)ゞ ぴっ!! (ノФωФ)ノなどがあり、前者の場合はさまざまな用途で使用することができ、使用できる割合も比較的高く、顔文字の完成度も高いため、相手にも伝わりやすいです。
後者の顔文字の場合は猫が好奇心を抱いている時に見せる目がギラギラしている表情をうまく表現されていますが、猫の目をイメージしているとわからない人では猫の表情がもとになっているとわからない場合もあります。
猫の顔文字で文章にも楽しさが伝わるため、メールなどで使用されることが多いです。
 喜びの猫の顔文字には(=・ω・=) (=^・ω・^=) (ฅ^・ω・^ ฅ)などがあり、さまざまな場面で使用することができます喜びを表現したいときはもちろんですが、何気ない文章の語尾にも使うことができ、最もスタンだーとな顔文字になっています。
イコールを猫の髭をイメージしており、猫であることを容易にイメージさせることができます。
(ฅ^・ω・^ ฅ)の顔文字では両手を挙げて肉球を見せている姿の顔文字であり、少し凝った顔文字でもあります。
~(=^・ω・^)旦は猫がお茶を運んでいる姿の顔文字であり、うれしかった時やお礼の時に活用することをおすすめします。
∩(=^・ω・^=)は片手を挙げている顔文字で、了承した時に使用することができます。
喜びの猫の顔文字には(=・ω・=) (=^・ω・^=) (ฅ^・ω・^ ฅ)などがあり、さまざまな場面で使用することができます喜びを表現したいときはもちろんですが、何気ない文章の語尾にも使うことができ、最もスタンだーとな顔文字になっています。
イコールを猫の髭をイメージしており、猫であることを容易にイメージさせることができます。
(ฅ^・ω・^ ฅ)の顔文字では両手を挙げて肉球を見せている姿の顔文字であり、少し凝った顔文字でもあります。
~(=^・ω・^)旦は猫がお茶を運んでいる姿の顔文字であり、うれしかった時やお礼の時に活用することをおすすめします。
∩(=^・ω・^=)は片手を挙げている顔文字で、了承した時に使用することができます。
 泣いている猫の顔文字には(´-ω-`)」や(=‐ω‐=)がスタンダートであり、シンプルな顔文字であるため、理解されやすいですどちらも目が横棒で表示されているため、悲しい表情であることを伝えることができます。
(=;ェ;=)の顔文字では実際に涙を流している顔文字になっているため、より悲しいときに使用することをおすすめします。
≦(∩ェ∩)≧...ニャン は両手で目を押さえて泣いている姿の顔文字であり、可愛い顔文字でありながら悲しさも伝わってきます。
泣いている猫の顔文字に中には可愛らしい顔文字も多くありますが、(=;ω;=)のように少し変わりづらく、泣いているのかもわかりずらいも顔文字も存在しています。
泣いている猫の顔文字には(´-ω-`)」や(=‐ω‐=)がスタンダートであり、シンプルな顔文字であるため、理解されやすいですどちらも目が横棒で表示されているため、悲しい表情であることを伝えることができます。
(=;ェ;=)の顔文字では実際に涙を流している顔文字になっているため、より悲しいときに使用することをおすすめします。
≦(∩ェ∩)≧...ニャン は両手で目を押さえて泣いている姿の顔文字であり、可愛い顔文字でありながら悲しさも伝わってきます。
泣いている猫の顔文字に中には可愛らしい顔文字も多くありますが、(=;ω;=)のように少し変わりづらく、泣いているのかもわかりずらいも顔文字も存在しています。
 猫の顔文字の怒りでは(=`ω´=) ム!がスタンダードであり、意味も伝わりやすい顔文字に仕上がっています。
ツリ目がうまく表現されていることで怒っていたり、不機嫌であることを伝えることができ、ム!の言葉があることでより怒っていることを伝えることが可能です。
(「ФДФ)「は目をギラつかせながら片手を挙げている顔文字であり、引っかかれることを相手に想像させることができます。
(p`・ω・´) qは両手を握ってこれから猫パンチをする顔文字であり、怒っていることを伝えつつも可愛さも伝えることができます。
そのため、怒りをマイルドに包んで相手に伝えることが可能です。
(p`ω´) qも似ている顔文字ですが、目が吊り上がっているため、より怒っていることを伝えることができます。
猫の顔文字の怒りでは(=`ω´=) ム!がスタンダードであり、意味も伝わりやすい顔文字に仕上がっています。
ツリ目がうまく表現されていることで怒っていたり、不機嫌であることを伝えることができ、ム!の言葉があることでより怒っていることを伝えることが可能です。
(「ФДФ)「は目をギラつかせながら片手を挙げている顔文字であり、引っかかれることを相手に想像させることができます。
(p`・ω・´) qは両手を握ってこれから猫パンチをする顔文字であり、怒っていることを伝えつつも可愛さも伝えることができます。
そのため、怒りをマイルドに包んで相手に伝えることが可能です。
(p`ω´) qも似ている顔文字ですが、目が吊り上がっているため、より怒っていることを伝えることができます。
 猫の顔文字には全身を表現されている顔文字も存在しています。
体まで表現した顔文字になると横一列では表現しきれない場合が多く、縦数列を使って仕上げられることが多いです。
しかし、大きな顔文字になることもあり、使用されることも少ないです。
次に、コンパクトに表示できる体全体の顔文字を紹介します。
全身を表すことができる顔文字を知りたい人は参考にしてください。
猫の顔文字には全身を表現されている顔文字も存在しています。
体まで表現した顔文字になると横一列では表現しきれない場合が多く、縦数列を使って仕上げられることが多いです。
しかし、大きな顔文字になることもあり、使用されることも少ないです。
次に、コンパクトに表示できる体全体の顔文字を紹介します。
全身を表すことができる顔文字を知りたい人は参考にしてください。
 猫といえば耳がピンと立っている姿を想像する人も多くいるのではないでしょうか。
(^・x・^)は猫の耳がうまく表現できている顔文字であり、さまざまな場面で活用することができます。
スタンダードな顔文字であるため、猫の顔文字を使いたいと考えている人におすすめです。
シンプルな顔文字でもあるため、さまざまなアレンジを加えやすい特徴もあります。
(=^・・^)は横にイコールを記入した顔文字であり、猫が横を向いている姿になっています。
「^」を取り入れれば耳が特徴的な猫の顔文字に仕上げることができるため、上記までに紹介した顔文字の耳の部分を変えるだけでも耳を印象付けることができます。
「^」を使って耳が可愛らしい猫の顔文字を作ってみてはいかがでしょうか。
猫といえば耳がピンと立っている姿を想像する人も多くいるのではないでしょうか。
(^・x・^)は猫の耳がうまく表現できている顔文字であり、さまざまな場面で活用することができます。
スタンダードな顔文字であるため、猫の顔文字を使いたいと考えている人におすすめです。
シンプルな顔文字でもあるため、さまざまなアレンジを加えやすい特徴もあります。
(=^・・^)は横にイコールを記入した顔文字であり、猫が横を向いている姿になっています。
「^」を取り入れれば耳が特徴的な猫の顔文字に仕上げることができるため、上記までに紹介した顔文字の耳の部分を変えるだけでも耳を印象付けることができます。
「^」を使って耳が可愛らしい猫の顔文字を作ってみてはいかがでしょうか。