チワワが幼少期から死ぬときまで患いやすい病気
 チワワは人気ランキングの上位に常に入っている大人気の犬種です。
魅力は愛くるしい目ではないでしょうか。
臆病な性格ですが比較的飼いやすい犬種と言われています。
そんなチワワですが幼少期から死ぬ時までに患いやすい病気というものはいくつかあります。
ここでは、その病気について詳しく解説いきたいと思います。
チワワは人気ランキングの上位に常に入っている大人気の犬種です。
魅力は愛くるしい目ではないでしょうか。
臆病な性格ですが比較的飼いやすい犬種と言われています。
そんなチワワですが幼少期から死ぬ時までに患いやすい病気というものはいくつかあります。
ここでは、その病気について詳しく解説いきたいと思います。
水頭症
水頭症は、遺伝や脳挫傷などの後天性のものもありますが、ほとんどは先天性の奇形が原因です。
どんな犬種でも水頭症は発症します。
しかし、チワワはアップルヘッドと言われる独特の丸い頭をしているため、水頭症が特に発症しやすくなっています。
症状としては運動障害、知覚障害、麻痺や斜視など。
治療は水頭症を根本的に治すものではなく、脳圧を下げるための薬の服用など症状を軽減する対処療法が中心です。
場合によっては、脳と腹腔を結ぶバイパス手術などが行われることもあります。
完治が難しい病気なので、水頭症と診断された場合は残念ながらどのような予後を過ごさせてあげるかを考えなければなりません。
低血糖症
 低血糖症とは、血液の糖分濃度が低下する病気で、体の冷えや長時間の空腹、内臓障害などによる栄養九州の悪化が原因で起こります。
特にチワワは体が小さいので生後3か月までの子犬は、1回の食事量が少なく、6時間~12時間食事をしないだけでも低血糖を起こすことも。
低血糖状態が長く続くと命を落とす可能性があるので、チワワがぐったりしている場合はすぐに病院へ行きましょう。
チワワは活発な犬種なので、低血糖症を起こす可能性が子犬だけではなく成犬でも老犬でも起こりやすいもので、チワワと低血糖症は切っても切れない仲と覚えておきましょう。
低血糖症とは、血液の糖分濃度が低下する病気で、体の冷えや長時間の空腹、内臓障害などによる栄養九州の悪化が原因で起こります。
特にチワワは体が小さいので生後3か月までの子犬は、1回の食事量が少なく、6時間~12時間食事をしないだけでも低血糖を起こすことも。
低血糖状態が長く続くと命を落とす可能性があるので、チワワがぐったりしている場合はすぐに病院へ行きましょう。
チワワは活発な犬種なので、低血糖症を起こす可能性が子犬だけではなく成犬でも老犬でも起こりやすいもので、チワワと低血糖症は切っても切れない仲と覚えておきましょう。
僧帽弁閉鎖不全症
チワワの40%がかかると言われている僧帽弁閉鎖不全症。
一般的には心臓弁膜症と呼ばれる心臓の病気で、大型犬よりも小型犬に多く発症します。
心臓内で血流が逆流してしまい、診察をすると雑音が聞こえるだけで他の症状は特にありません。
しかし、進行すれば肺水腫や不整脈を起こし突然死する可能性もある怖い病気です。
治療法は食事療法や薬の投与などがあり、運動も制限されます。
症状が雑音のみとわかりにくいので、定期的な健康診断を受けるようにしましょう。
チワワは突然死が多い?死ぬ前は元気だった?
 突然死とは症状が出てから24時間以内に死亡してしまうことを言い、チワワはこの突然死が多い犬種と言われています。
朝は普通にご飯を食べていつも通りに過ごしていたのに、飼い主さんが仕事から帰宅したら死んでいたというようなケースもあります。
死ぬ前は元気だったのに…と飼い主さんは突然の死にショックが大きいでしょう。
そこで、今回はチワワの突然死は何が理由で起こるのかご紹介していきます。
突然死とは症状が出てから24時間以内に死亡してしまうことを言い、チワワはこの突然死が多い犬種と言われています。
朝は普通にご飯を食べていつも通りに過ごしていたのに、飼い主さんが仕事から帰宅したら死んでいたというようなケースもあります。
死ぬ前は元気だったのに…と飼い主さんは突然の死にショックが大きいでしょう。
そこで、今回はチワワの突然死は何が理由で起こるのかご紹介していきます。
突然死の理由①心臓病
チワワの突然死の原因として最も多いと言われているのは心臓病で、患ってしまうとほとんどの子が命を奪われていまします。
先ほどもご紹介しまししたが、チワワで見られる心臓病には先天性と後天性があり、先天性では動脈管開存症、肺動脈狭窄症、心室中隔欠損症、心臓中核欠損症などがあります。
後天性の心臓病では僧帽弁閉鎖不全症、三尖弁閉鎖不全症などがあり、先天性でも後天性でも心臓の中の血液の流れが変化してしまう病気なので突然死を起こしやすい大変怖い病気ばかりです。
心臓の音を聞けば見つかる病気もあれば、わからず突然死してしまうこともあり、心臓の音が変化しない病気としては不整脈があります。
不整脈も心臓を急に止めてしまう怖い病気です。
突然死の理由②発作
 てんかんに代表される発作も突然死の原因となり、全般発作(大きな発作)は意識のある間に上手く呼吸をすることが不可能になり、呼吸困難によって突然死を引き起こします。
原因は様々あり、原因が特にない突発性てんかん、脳腫瘍、脳炎、水頭症など脳の病気や、腎臓や肝臓の病気による有毒蓄積によって脳が障害を受け、発作を起こす場合があります。
水頭症になりやすい犬種のチワワは発作がよく見られ、なんの前触れもなく突然起こる場合もあれば、
少しぼ~っとしている軽い発作、全身の筋肉の痙攣を引き起こす大きな発作まだ様々ですが、その中でも突然死を引き起こす発作は全般発作になります。
飼い主さんの日々の観察が大切となりますので、少しでも変わった様子が見られた場合は病院で診察を受けるようにしてください。
てんかんに代表される発作も突然死の原因となり、全般発作(大きな発作)は意識のある間に上手く呼吸をすることが不可能になり、呼吸困難によって突然死を引き起こします。
原因は様々あり、原因が特にない突発性てんかん、脳腫瘍、脳炎、水頭症など脳の病気や、腎臓や肝臓の病気による有毒蓄積によって脳が障害を受け、発作を起こす場合があります。
水頭症になりやすい犬種のチワワは発作がよく見られ、なんの前触れもなく突然起こる場合もあれば、
少しぼ~っとしている軽い発作、全身の筋肉の痙攣を引き起こす大きな発作まだ様々ですが、その中でも突然死を引き起こす発作は全般発作になります。
飼い主さんの日々の観察が大切となりますので、少しでも変わった様子が見られた場合は病院で診察を受けるようにしてください。
突然死の理由③犬種の特徴
チワワは他の犬種と比べて突然死を起こしやすい犬種と言われていますが、特に統計的な根拠はなく、飼育されている頭数が多いためではないかと推測されています。
チワワは他の犬種に比べ圧倒的に体が小さく、生活環境や小さなきっかけで体調が変化しやすいデリケートな犬種です。
この体の小ささが寒さや暑さ、他の犬種にすればなんてこともない嘔吐や下痢という軽い症状でも急激に体調が悪化し、死亡する原因となります。
チワワの突然死防止法?死ぬときを回避できる?
 チワワにとって生活の急激な変化がストレスとなり、突然死を引き起こしてしまう原因となりますので、生活環境に注意をし、隠れた病気がないかを注意深く観察することが重要となってきます。
突然死を防ぐためには、チワワと十分なコミュニケーションをとることが必要となり、しっかりご飯を食べているか、便や尿に異常はないかなどがすぐわかるようにしておきましょう。
日々の小さな変化や軽い症状であってもチワワにとっては命取りになる可能性が大きいので、少しでも様子がおかしいと感じた場合は病院で診察を受けることをオススメします。
様々な検査を実施してもらい問題が発見できれば、突然死を回避できるかもしれません。
チワワにとって生活の急激な変化がストレスとなり、突然死を引き起こしてしまう原因となりますので、生活環境に注意をし、隠れた病気がないかを注意深く観察することが重要となってきます。
突然死を防ぐためには、チワワと十分なコミュニケーションをとることが必要となり、しっかりご飯を食べているか、便や尿に異常はないかなどがすぐわかるようにしておきましょう。
日々の小さな変化や軽い症状であってもチワワにとっては命取りになる可能性が大きいので、少しでも様子がおかしいと感じた場合は病院で診察を受けることをオススメします。
様々な検査を実施してもらい問題が発見できれば、突然死を回避できるかもしれません。
まとめ
 今回はチワワの突然死についてご紹介してきました。
チワワは他の犬種に比べ突然死が起こりやすい犬種ですが、飼いやすいという理由でチワワを飼っている方が多いです。
しかし、チワワを飼った以上は、チワワがなりやすい病気や突然死はどのようにして起こるのかということを飼い主さんは事前に調査しておく必要があります。
そうすることで、なりやすい病気や発作も回避することができ、突然死を防ぐことができるでしょう。
今回はチワワの突然死についてご紹介してきました。
チワワは他の犬種に比べ突然死が起こりやすい犬種ですが、飼いやすいという理由でチワワを飼っている方が多いです。
しかし、チワワを飼った以上は、チワワがなりやすい病気や突然死はどのようにして起こるのかということを飼い主さんは事前に調査しておく必要があります。
そうすることで、なりやすい病気や発作も回避することができ、突然死を防ぐことができるでしょう。
猫の気持ちがわかる?鳴き声編
 猫というのはツンデレが上手で、その気ままな素振りがまた可愛いと大きな魅力となっていますよね。
そんな時、愛猫は何を考えているのでしょう?
それがわかれば飼い主さんは愛猫の気持ちがわかり、嬉しいですし、助かる部分もあるのではないでしょうか。
そこで、今回はまず鳴き声で猫の気持ちがわかる方法をご紹介しましょう。
猫というのはツンデレが上手で、その気ままな素振りがまた可愛いと大きな魅力となっていますよね。
そんな時、愛猫は何を考えているのでしょう?
それがわかれば飼い主さんは愛猫の気持ちがわかり、嬉しいですし、助かる部分もあるのではないでしょうか。
そこで、今回はまず鳴き声で猫の気持ちがわかる方法をご紹介しましょう。
シャー、ウーと鳴く
 猫が「シャー!ウー!」と鳴いている時は明らかに機嫌が良い鳴き声ではないという事はわかりますよね。
しかもその時の体をよくみてみると毛が逆立っています。
この鳴き方は怒りを感じた時や警戒している時に出す声で、興奮状態になっていますので、無理になだめたりしするのではなく落ち着くまで見守ってあげましょう。
例えば、先住猫がいる状態で新しい猫を迎えいれた時、この鳴き方をしているようであれば、喧嘩をしないように注意深く観察しておくようにしないと喧嘩が始まってしまうとケガをする可能性があります。
猫が「シャー!ウー!」と鳴いている時は明らかに機嫌が良い鳴き声ではないという事はわかりますよね。
しかもその時の体をよくみてみると毛が逆立っています。
この鳴き方は怒りを感じた時や警戒している時に出す声で、興奮状態になっていますので、無理になだめたりしするのではなく落ち着くまで見守ってあげましょう。
例えば、先住猫がいる状態で新しい猫を迎えいれた時、この鳴き方をしているようであれば、喧嘩をしないように注意深く観察しておくようにしないと喧嘩が始まってしまうとケガをする可能性があります。
ニャオ、ニャーと鳴く
 小さい子に猫の事を「あれは何ていう動物?」と聞くと「ニャーニャー」と言いませんか?
まさに猫のイメージがこの鳴き声なんですよね。
猫が「ニャオ」「ニャー」と穏やかに泣いている時は猫にとっては挨拶のようなもの。
そして次に何かアクションを起こす前触れでもありますので、挨拶であればいいのですが、アクションを起こす前触れだったらびっくりしてしまう可能性も出てきますので、じっくり猫の様子を観察してから触れるようにしましょう。
小さい子に猫の事を「あれは何ていう動物?」と聞くと「ニャーニャー」と言いませんか?
まさに猫のイメージがこの鳴き声なんですよね。
猫が「ニャオ」「ニャー」と穏やかに泣いている時は猫にとっては挨拶のようなもの。
そして次に何かアクションを起こす前触れでもありますので、挨拶であればいいのですが、アクションを起こす前触れだったらびっくりしてしまう可能性も出てきますので、じっくり猫の様子を観察してから触れるようにしましょう。
ゴロゴロと喉を鳴らす
 喉の奥から「ゴロゴロ」と慣らしているのは鳴き声ではないかもしれませんが、これも猫にとっては重要な合図になります。
この鳴き声は猫がリラックスしている時や甘えている時のサインです。
もし、飼い主さんが愛猫を撫でている時にこの鳴き声が聞こえてきたら、飼い主さんを信頼して甘えているという証拠になりますので、飼い主さんにとっては嬉しい鳴き声になるのではないでしょうか。
喉の奥から「ゴロゴロ」と慣らしているのは鳴き声ではないかもしれませんが、これも猫にとっては重要な合図になります。
この鳴き声は猫がリラックスしている時や甘えている時のサインです。
もし、飼い主さんが愛猫を撫でている時にこの鳴き声が聞こえてきたら、飼い主さんを信頼して甘えているという証拠になりますので、飼い主さんにとっては嬉しい鳴き声になるのではないでしょうか。
猫の気持ちがわかる?行動編
 愛猫を眺めているだけで癒されますが、たまに「面白い事をするな」「何をしているんだろ?」というような事をする場面があります。
その行動の理由がわかると飼い主さんも今よりもっと愛猫の気持ちがわかるのではないでしょうか。
そこで、ここでは猫の気持ちがわかる、よく見られる行動をご紹介していきましょう。
愛猫を眺めているだけで癒されますが、たまに「面白い事をするな」「何をしているんだろ?」というような事をする場面があります。
その行動の理由がわかると飼い主さんも今よりもっと愛猫の気持ちがわかるのではないでしょうか。
そこで、ここでは猫の気持ちがわかる、よく見られる行動をご紹介していきましょう。
体をなめてくる
猫はよく体をなめてくる事があるのですが、猫の下はザラザラしていてよく見ると舌にトゲのような突起物があります。
これは猫の特徴で、水を飲む時やグルーミングをする時に役立っているのです。
舌は、猫にとって生きて行く上で、欠かすことができない重要な器官となっているのですね。
そんな舌で飼い主さんをなめてくるというのは、愛猫の飼い主さんへの愛情表現と考えて良いでしょう。
大好きで大事な飼い主さんやその家族に対し「グルーミングをしてあげるよ」という気持ちでいてくれているという証拠です。
猫のすりすり
 猫が自分の体をすりすり擦り付けてくる行動もよく見られます。
この行動をしてくると「甘えているのかな?」と思うもの。
もちろん、そういう意味も含まれているのですが、実際は自分の匂いをこすりつける「マーキング」という行動になります。
大好きな飼い主さんに他の匂いがついているのが嫌で一生懸命自分の匂いをつけようとしていると考えると愛猫がそれだけ自分を好きでいてくれているんだと嬉しい気持ちになりますね。
猫が自分の体をすりすり擦り付けてくる行動もよく見られます。
この行動をしてくると「甘えているのかな?」と思うもの。
もちろん、そういう意味も含まれているのですが、実際は自分の匂いをこすりつける「マーキング」という行動になります。
大好きな飼い主さんに他の匂いがついているのが嫌で一生懸命自分の匂いをつけようとしていると考えると愛猫がそれだけ自分を好きでいてくれているんだと嬉しい気持ちになりますね。
毛づくろい
 暇あれば愛猫が自分の体を舐めている事ありませんか?
この行動は毛づくろい(グルーミング)と言われているもので、猫にとっては習慣のようなもの。
毛づくろいをして自分についた汚れや匂いを取り除き綺麗に保つようにしているのです。
しかし、他の理由がある場合もあり、それは不安な時にリラックスさせるために行っている事もあります。
逆にリラックスしているので毛づくろいをするという事もあるようなので、時々によって毛づくろいをしている気持ちを汲み取ってあげられたらいいですね。
暇あれば愛猫が自分の体を舐めている事ありませんか?
この行動は毛づくろい(グルーミング)と言われているもので、猫にとっては習慣のようなもの。
毛づくろいをして自分についた汚れや匂いを取り除き綺麗に保つようにしているのです。
しかし、他の理由がある場合もあり、それは不安な時にリラックスさせるために行っている事もあります。
逆にリラックスしているので毛づくろいをするという事もあるようなので、時々によって毛づくろいをしている気持ちを汲み取ってあげられたらいいですね。
集団行動
 猫は好き勝手に行動するというイメージですが、野良猫を見てもらえばわかるように集団で集まっている事がありますよね?
自宅で猫を多頭飼いする場合、結果的には集団行動をする事になるのですが、猫によってパワーバランスが違いますので、集団行動をする中で微妙な距離感が保たれています。
日当たりが良い場所でじっとしている子、風が気持ち良い場所にいる子など様々なので、よく観察してあげて下さい。
猫は好き勝手に行動するというイメージですが、野良猫を見てもらえばわかるように集団で集まっている事がありますよね?
自宅で猫を多頭飼いする場合、結果的には集団行動をする事になるのですが、猫によってパワーバランスが違いますので、集団行動をする中で微妙な距離感が保たれています。
日当たりが良い場所でじっとしている子、風が気持ち良い場所にいる子など様々なので、よく観察してあげて下さい。
猫の気持ちがわかる?しっぽ編
 しっぽには「尾堆」という小さな骨が連なって出来ており、しなやかで様々な動きをする事ができます。
役割は、身体のバランスを取る事はもちろんですが、猫同士のコミュニケーションにも役立っており、尻尾の動かし方でも猫がどんな気持ちなのか読み取る事ができます。
そこで、ここでは尻尾の動きによる猫の気持ちをご紹介しましょう。
しっぽには「尾堆」という小さな骨が連なって出来ており、しなやかで様々な動きをする事ができます。
役割は、身体のバランスを取る事はもちろんですが、猫同士のコミュニケーションにも役立っており、尻尾の動かし方でも猫がどんな気持ちなのか読み取る事ができます。
そこで、ここでは尻尾の動きによる猫の気持ちをご紹介しましょう。
しっぽを速く動かす
 しっぽを「ブンブン!」と音が聞こえてきそうなくらい早く動かしている時は、犬であれば喜びのサインなのですが、猫の場合は機嫌がよくなかったり、戦う相手をみつけてしまったところという状態かもしれません。
犬では喜びの動作、猫では機嫌が悪い動作と真逆の動作なので、ついつい触ってしまいそうになるかもしれませんが、このような行動をしている時は触ったり、抱っこしたりせず、そっとしておくのが一番でしょう。
しっぽを「ブンブン!」と音が聞こえてきそうなくらい早く動かしている時は、犬であれば喜びのサインなのですが、猫の場合は機嫌がよくなかったり、戦う相手をみつけてしまったところという状態かもしれません。
犬では喜びの動作、猫では機嫌が悪い動作と真逆の動作なので、ついつい触ってしまいそうになるかもしれませんが、このような行動をしている時は触ったり、抱っこしたりせず、そっとしておくのが一番でしょう。
しっぽを速く小さく動かす
 「ピクピク」と小さく早くしっぽが動いている時があるのですが、その時の猫の気持ちは特に複雑な感じになっているようで、状況によっては、何か考えごとをしていたり、不安を感じていたり、緊張しているケースが考えられます。
先ほどご紹介したしっぽを早く動かす動作と同じで機嫌がよいという状態ではないので、無理に触ったり、構ったりするのはやめましょう。
そっとしておいてあげると落ち着いてきますのでそれまで自由にさせておいてあげて下さい。
「ピクピク」と小さく早くしっぽが動いている時があるのですが、その時の猫の気持ちは特に複雑な感じになっているようで、状況によっては、何か考えごとをしていたり、不安を感じていたり、緊張しているケースが考えられます。
先ほどご紹介したしっぽを早く動かす動作と同じで機嫌がよいという状態ではないので、無理に触ったり、構ったりするのはやめましょう。
そっとしておいてあげると落ち着いてきますのでそれまで自由にさせておいてあげて下さい。
しっぽを足の間に入れる
しっぽをくるりと後ろ足の間に巻き込んでいるのは「怖い」と感じているサインです。
このサインは犬も同様ですね。
カメのように身体を小さくして防御のスタイルととっていると考えられます。
家にきてすぐに猫がこのような行動をしたら、環境の変化かもしれませんので、何に怯えているのかを飼い主さんがしっかり把握してあげる事が重要。
具体的には掃除機や洗濯機から発する音などは恐怖以外の何ものでもありません。
そうしたものからできるだけ遠ざけるようし、ストレスをためないようにしてあげましょう。
しっぽが垂直になっている
 ピンと立ったしっぽは、「嬉しい!」という気持ちの表れです。
飼い主さんやその家族が家に帰った時にこの行動をしてくれていたら喜んでくれている証拠ですので飼い主さんかたしたら嬉しい行動ですね。
元々この行動は、子猫が母猫に近づく際に、存在をアピールする行動と言われており、友好的な気持ちを相手に伝えるために行うと考えられています。
飼い主さんに対して行われているようであれば、甘えている時や遊んでほしい時なので、構ったり、撫でたりしてあげて下さい。
ピンと立ったしっぽは、「嬉しい!」という気持ちの表れです。
飼い主さんやその家族が家に帰った時にこの行動をしてくれていたら喜んでくれている証拠ですので飼い主さんかたしたら嬉しい行動ですね。
元々この行動は、子猫が母猫に近づく際に、存在をアピールする行動と言われており、友好的な気持ちを相手に伝えるために行うと考えられています。
飼い主さんに対して行われているようであれば、甘えている時や遊んでほしい時なので、構ったり、撫でたりしてあげて下さい。
猫の気持ちがわかる?仕草編
 人間にとっては一つ一つの仕草が可愛くてたまらなくても、猫にとっては様々な気持ちが詰まっています。
何気なくしている仕草でも全てに意味がありますので、その仕草から感情を読み取れるようチャレンジしてみるのも楽しいかもしれません。
そこで、ここでは、猫の気持ちがわかる仕草をご紹介していきましょう。
人間にとっては一つ一つの仕草が可愛くてたまらなくても、猫にとっては様々な気持ちが詰まっています。
何気なくしている仕草でも全てに意味がありますので、その仕草から感情を読み取れるようチャレンジしてみるのも楽しいかもしれません。
そこで、ここでは、猫の気持ちがわかる仕草をご紹介していきましょう。
体を縮める
 きるだけ身体を小さく見せようとうずくまったり、耳を折りたたんで丸まったりしている場合は、怖がっていると考えてよいでしょう。
あまりの恐怖を感じている場合は、身体に力が入り硬直して動かなくなったりする事もあるのです。
そんな時は、怖がっているものが何なのかを探り、見えないようにしたり遠ざけたりなどして落ち着ける環境を作ってあげて下さい。
きるだけ身体を小さく見せようとうずくまったり、耳を折りたたんで丸まったりしている場合は、怖がっていると考えてよいでしょう。
あまりの恐怖を感じている場合は、身体に力が入り硬直して動かなくなったりする事もあるのです。
そんな時は、怖がっているものが何なのかを探り、見えないようにしたり遠ざけたりなどして落ち着ける環境を作ってあげて下さい。
片足を上げながら止まる
 招き猫のように前足を片方だけあげてフリーズしてしまっている場合もありますが、それは「逃げるか?猫パンチしようか?」と次の行動を考えている最中です。
それは誰に対してなにかわかりませんが、そんな場面を見てしまったら飼い主さんも構えてしまうかもしれませんね。
その仕草を見てしまった場合は、そっとしておくのが一番です。
招き猫のように前足を片方だけあげてフリーズしてしまっている場合もありますが、それは「逃げるか?猫パンチしようか?」と次の行動を考えている最中です。
それは誰に対してなにかわかりませんが、そんな場面を見てしまったら飼い主さんも構えてしまうかもしれませんね。
その仕草を見てしまった場合は、そっとしておくのが一番です。
威嚇
 全身の毛を逆立てて背中を丸め、自分の身体を大きく見せようとする仕草は全力で威嚇しているサインで、しっぽをよく観察してみるとタヌキのように膨らんでいる事も特徴の一つでしょう。
「シャー!」と鳴きながらこのような仕草をしている場合は、怒っている、威嚇している状態ですので、無理に触ったりしないようにしましょう。
猫のするどい爪で引っ掻かれてしまう可能性があります。
全身の毛を逆立てて背中を丸め、自分の身体を大きく見せようとする仕草は全力で威嚇しているサインで、しっぽをよく観察してみるとタヌキのように膨らんでいる事も特徴の一つでしょう。
「シャー!」と鳴きながらこのような仕草をしている場合は、怒っている、威嚇している状態ですので、無理に触ったりしないようにしましょう。
猫のするどい爪で引っ掻かれてしまう可能性があります。
耳が横に寝た状態
 猫の耳はとても優秀で、人間には聞こえない音もキャッチできると言われています。
そんな耳がペタッとしている時は、この上ない心地よさを感じている状態でリラックスモードです。
傍で見ていてもとても愛らしい仕草ですよね。
気持ちいい時やくつろいでいる時の脱力状態で耳にあらわれているのです。
猫の耳はとても優秀で、人間には聞こえない音もキャッチできると言われています。
そんな耳がペタッとしている時は、この上ない心地よさを感じている状態でリラックスモードです。
傍で見ていてもとても愛らしい仕草ですよね。
気持ちいい時やくつろいでいる時の脱力状態で耳にあらわれているのです。
猫の気持ちがわかる?仕事を邪魔する猫の心理
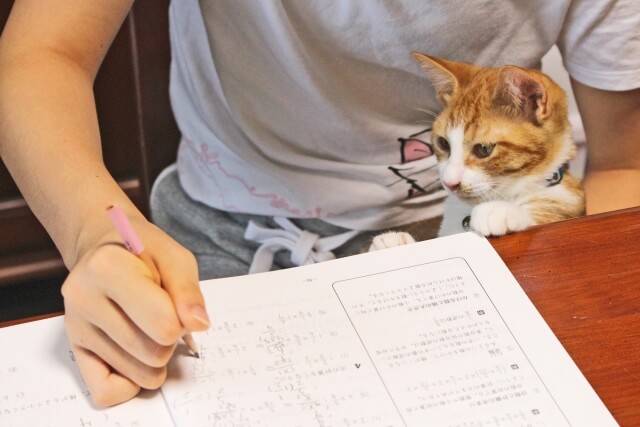 猫は自由自在に動き回れる生き物なので、飼い主さんが大好きなあまり何処に行ってもついてくる事があります。
一番困るのは仕事を邪魔してくること。
本を読んでいるのに本の上に乗ってきて動かない、パソコンを打とうとすればキーボードの上に座って動かないなど。
可愛い行動なのですがどうしていいものか困ってしまいます。
この行動は愛情表現ではなく自分に注目して欲しいというアピール。
本当に邪魔だったら無視しても問題ありません。
猫は自由自在に動き回れる生き物なので、飼い主さんが大好きなあまり何処に行ってもついてくる事があります。
一番困るのは仕事を邪魔してくること。
本を読んでいるのに本の上に乗ってきて動かない、パソコンを打とうとすればキーボードの上に座って動かないなど。
可愛い行動なのですがどうしていいものか困ってしまいます。
この行動は愛情表現ではなく自分に注目して欲しいというアピール。
本当に邪魔だったら無視しても問題ありません。
まとめ
 今回は猫も気持ちをご紹介してきました。
猫は様々な行動や仕草をしますが、その一つ一つに意味があったんですね。
何気なく見ていた事でも本当はこんな意味があったんだとわかれば飼い主さんも今後どのように愛猫と接すればいいのかわかった気がしませんか?
猫の気持ちをわかっていれば、猫の事を今までよりもっと理解してあげられますね。
今回は猫も気持ちをご紹介してきました。
猫は様々な行動や仕草をしますが、その一つ一つに意味があったんですね。
何気なく見ていた事でも本当はこんな意味があったんだとわかれば飼い主さんも今後どのように愛猫と接すればいいのかわかった気がしませんか?
猫の気持ちをわかっていれば、猫の事を今までよりもっと理解してあげられますね。
犬がふてくされるのはなぜ?
 犬も人間と同じように感情というものがあり、いつも喜んでいる訳ではなく、悲しんでいる時もあれば、しんどくなって元気がない時もあります。
そしてふてくされる事もあるのです。
犬がふてくされる理由が様々考えられるのですが、今回はそれをご紹介していきたいと思います。
犬も人間と同じように感情というものがあり、いつも喜んでいる訳ではなく、悲しんでいる時もあれば、しんどくなって元気がない時もあります。
そしてふてくされる事もあるのです。
犬がふてくされる理由が様々考えられるのですが、今回はそれをご紹介していきたいと思います。
原因①わがまま
 犬も人間の子供と同様、自由気ままに育ててしまうとわがままになってしまう事があります。
犬がわがままになる主な原因は、飼い主さんとの主従関係が正しく築けていない事かもしれないとのこと。
飼い主さんがしっかりしつけをしていなかったり、甘やかしてばかりいると犬は「自分は飼い主より立場が上だ」と勘違いしてしまうことがあるのです。
そのように育ってしまうと自分の要求が通らなかったりするとすぐに機嫌が悪くなって「何で自分より立場が下の人に怒られなければいけないの」という感じでふてくされるという事があります。
犬も人間の子供と同様、自由気ままに育ててしまうとわがままになってしまう事があります。
犬がわがままになる主な原因は、飼い主さんとの主従関係が正しく築けていない事かもしれないとのこと。
飼い主さんがしっかりしつけをしていなかったり、甘やかしてばかりいると犬は「自分は飼い主より立場が上だ」と勘違いしてしまうことがあるのです。
そのように育ってしまうと自分の要求が通らなかったりするとすぐに機嫌が悪くなって「何で自分より立場が下の人に怒られなければいけないの」という感じでふてくされるという事があります。
原因②ホルモンバランスの崩れ
 犬には発情期というものがあります。
オスの場合はそこまできつくないのですが、メスとなると自律神経が乱れホルモンバランスが崩れてしまい、イライラしたりちょっとした事で機嫌が悪くなりふてくされてしまうという事があります。
これはメスである以上、仕方がない事なのでいつもよりイライラしたりふてくされる回数が多いなと思った時は、そっとしておいてあげましょう。
この時は犬も何故イライラしたりふてくされるのかわかっていない場合が多いです。
発情期以外にも病気やストレスでホルモンバランスが崩れる事もありますので、発情期が過ぎた後も機嫌が悪い状態が続いたり、体調が悪そうであればすぐに受診するようにして下さいね。
犬には発情期というものがあります。
オスの場合はそこまできつくないのですが、メスとなると自律神経が乱れホルモンバランスが崩れてしまい、イライラしたりちょっとした事で機嫌が悪くなりふてくされてしまうという事があります。
これはメスである以上、仕方がない事なのでいつもよりイライラしたりふてくされる回数が多いなと思った時は、そっとしておいてあげましょう。
この時は犬も何故イライラしたりふてくされるのかわかっていない場合が多いです。
発情期以外にも病気やストレスでホルモンバランスが崩れる事もありますので、発情期が過ぎた後も機嫌が悪い状態が続いたり、体調が悪そうであればすぐに受診するようにして下さいね。
原因③体調が悪い
 これは人間も同様の事が言えると思いますが、体調が悪いとできるだけ構って欲しくないのでそっけない態度を取ったり、イライラしてふてくされたりします。
それだけ体調は悪い時は余裕がないと言えるでしょう。
そんな時、飼い主さんは愛犬の体調をしっかり観察してあげる事が大切です。
体調が悪い場合、ふてくされている態度だけではわからない事も多いので、
・ご飯はしっかり食べているか?
・水分をしっかり補給しているか?
・おしっこや便はしているか?
という健康観察が大事になってきます。
すぐに病院へ連れて行く事がなさそうであれば少し様子をみてそれでもよくならない場合は受診しましょう。
これは人間も同様の事が言えると思いますが、体調が悪いとできるだけ構って欲しくないのでそっけない態度を取ったり、イライラしてふてくされたりします。
それだけ体調は悪い時は余裕がないと言えるでしょう。
そんな時、飼い主さんは愛犬の体調をしっかり観察してあげる事が大切です。
体調が悪い場合、ふてくされている態度だけではわからない事も多いので、
・ご飯はしっかり食べているか?
・水分をしっかり補給しているか?
・おしっこや便はしているか?
という健康観察が大事になってきます。
すぐに病院へ連れて行く事がなさそうであれば少し様子をみてそれでもよくならない場合は受診しましょう。
原因④ストレス
 これも人間と同様で犬もストレスがたまるとイライラしてしまいがち。
ストレスの原因は犬によって違いますが、人間にとっては何ともない事でも犬にとっては大きなストレスの1つになっている事もあるのです。
具体的にあげると睡眠不足や運動不足。
犬にとっては大切なコミュニケーションツールである運動や散歩は不足すると欲求不満になってストレスを抱えてしまう事になります。
そして、理不尽な怒り方も絶対にNG。
このように犬というのは人間社会で生活するという事がストレスを抱えやすい状況であるという事を飼い主さんは覚えておいてあげて下さいね。
これも人間と同様で犬もストレスがたまるとイライラしてしまいがち。
ストレスの原因は犬によって違いますが、人間にとっては何ともない事でも犬にとっては大きなストレスの1つになっている事もあるのです。
具体的にあげると睡眠不足や運動不足。
犬にとっては大切なコミュニケーションツールである運動や散歩は不足すると欲求不満になってストレスを抱えてしまう事になります。
そして、理不尽な怒り方も絶対にNG。
このように犬というのは人間社会で生活するという事がストレスを抱えやすい状況であるという事を飼い主さんは覚えておいてあげて下さいね。
犬がふてくされる時の仕草
 では、犬がふてくされている時どのような仕草をしているのでしょうか?
普段何気なくしている仕草がもしかしたらふてくされている仕草なのかもしれません。
そこで、ここでは犬がふてくされている時の仕草をご紹介しましょう。
では、犬がふてくされている時どのような仕草をしているのでしょうか?
普段何気なくしている仕草がもしかしたらふてくされている仕草なのかもしれません。
そこで、ここでは犬がふてくされている時の仕草をご紹介しましょう。
触ろうとすると噛む
 飼い主さんが構ってあげようと撫でたり触ったりした時にふてくされていれば無視をする事もありますが、ふてくされ度がマックスになってしまうと噛んできたり唸りだしたりします。
飼い主さんはただ触ろうとしただけなのに噛まれたり唸ったりされるとただただびっくり。
しかし、そんな時は何故愛犬がふてくされているのか原因を考えてみて、機嫌が良くなるまでほおっておくのが一番です。
決して、無理やり引っ張り出して怒ったり、スキンシップを取ろうとしないようにしましょう。
飼い主さんが構ってあげようと撫でたり触ったりした時にふてくされていれば無視をする事もありますが、ふてくされ度がマックスになってしまうと噛んできたり唸りだしたりします。
飼い主さんはただ触ろうとしただけなのに噛まれたり唸ったりされるとただただびっくり。
しかし、そんな時は何故愛犬がふてくされているのか原因を考えてみて、機嫌が良くなるまでほおっておくのが一番です。
決して、無理やり引っ張り出して怒ったり、スキンシップを取ろうとしないようにしましょう。
あくびを何回もする
 あくびをしている仕草を見ているとただ「眠たいだけなんだ」と思ってしまいがちですが、何回もあくびをしている時は機嫌が悪い場合があります。
あくびというのはリラックス状態を示している事もあるのですが、機嫌が悪いという全く正反対の状態の事もあるのです。
わかりやすい例をあげると、愛犬をきつく叱ったりした後に何回もあくびをしている時は強いストレスがかかっている状態で、あくびをする事で緊張状態をほぐしたいと思っているという事になります。
そんな時は、愛犬が好きな遊びや散歩に連れて行くなどしてストレス発散させてあげるのがいいかもしれませんね。
あくびをしている仕草を見ているとただ「眠たいだけなんだ」と思ってしまいがちですが、何回もあくびをしている時は機嫌が悪い場合があります。
あくびというのはリラックス状態を示している事もあるのですが、機嫌が悪いという全く正反対の状態の事もあるのです。
わかりやすい例をあげると、愛犬をきつく叱ったりした後に何回もあくびをしている時は強いストレスがかかっている状態で、あくびをする事で緊張状態をほぐしたいと思っているという事になります。
そんな時は、愛犬が好きな遊びや散歩に連れて行くなどしてストレス発散させてあげるのがいいかもしれませんね。
飼い主に無関心
 飼い主さんがスキンシップを取ろうとしても一切興味を示さなかったり、いつもなら大好きなおもちゃを見ると飛んでくるのにずっと寝たまま。
明らかに耳や動いているので聞こえてはいるのですが、ふてくされてしまっている時は飼い主さんにも無関心になってしまいます。
そんな仕草をされたら飼い主さんも悲しくなってしまうでしょうが、落ち着くまではそっとしておくようにしましょう。
飼い主さんがスキンシップを取ろうとしても一切興味を示さなかったり、いつもなら大好きなおもちゃを見ると飛んでくるのにずっと寝たまま。
明らかに耳や動いているので聞こえてはいるのですが、ふてくされてしまっている時は飼い主さんにも無関心になってしまいます。
そんな仕草をされたら飼い主さんも悲しくなってしまうでしょうが、落ち着くまではそっとしておくようにしましょう。
がっかりしてふて寝
 おやつをくれると思ったのにくれなかった時や怒られた時などにふて寝をする仕草を見せる事があります。
そんな時に、飼い主さんが呼びかけたり構ったりしようとしても全く反応なし。
完全に寝たふりをしてそのまま本当に寝てしまう事も。
ふて寝しているなと思ったら、飼い主さんはそれ以上構ったりせずそっとしておくようにしましょう。
しつこくしてしまうとストレスがたまったり、もっと機嫌が悪くなったりします。
おやつをくれると思ったのにくれなかった時や怒られた時などにふて寝をする仕草を見せる事があります。
そんな時に、飼い主さんが呼びかけたり構ったりしようとしても全く反応なし。
完全に寝たふりをしてそのまま本当に寝てしまう事も。
ふて寝しているなと思ったら、飼い主さんはそれ以上構ったりせずそっとしておくようにしましょう。
しつこくしてしまうとストレスがたまったり、もっと機嫌が悪くなったりします。
不機嫌に睨んでくる
 人間にも喜怒哀楽がありますが、犬も同様に喜怒哀楽がはっきりしています。
嬉しい時は大きい目でこっちを見てくれますが、機嫌が悪い時は口角を下げて口を閉じたままで不機嫌そうにこちらを睨んできます。
明らかにムスッとした表情ですのですぐにわかるでしょう。
そんな時はスキンシップを取ってみて下さい。
すぐに機嫌が良くなって一緒に遊びだすようであれば問題ないのですが、無視したり嫌がったりするようであればまさしく機嫌が悪いという状態です。
人間にも喜怒哀楽がありますが、犬も同様に喜怒哀楽がはっきりしています。
嬉しい時は大きい目でこっちを見てくれますが、機嫌が悪い時は口角を下げて口を閉じたままで不機嫌そうにこちらを睨んできます。
明らかにムスッとした表情ですのですぐにわかるでしょう。
そんな時はスキンシップを取ってみて下さい。
すぐに機嫌が良くなって一緒に遊びだすようであれば問題ないのですが、無視したり嫌がったりするようであればまさしく機嫌が悪いという状態です。
反抗期?呼んでも来ない
 飼い主さんが愛犬を呼ぶといつもなら飛んできてくれるのに、ふてくされている時は無視です。
そんな時、愛犬を見てみると耳だけは動いています。
聞こえているのに無視しているのです。
あまりしつこく呼び続けると「うるさいな」といわんばかりにより遠くへ行ってしまう事もあります。
それだけイライラする事があったという事なので、ほおっておきましょう。
飼い主さんが愛犬を呼ぶといつもなら飛んできてくれるのに、ふてくされている時は無視です。
そんな時、愛犬を見てみると耳だけは動いています。
聞こえているのに無視しているのです。
あまりしつこく呼び続けると「うるさいな」といわんばかりにより遠くへ行ってしまう事もあります。
それだけイライラする事があったという事なので、ほおっておきましょう。
犬がふてくされる時の対処法
 犬がふてくされる原因やふてくされている時の仕草をご紹介してきますが、実際に愛犬がふてくされている事を知ってしまうと飼い主さんもどう対処すればいいのか戸惑ってしまいますよね。
そこで、ここでは、犬がふてくされている時の対処法をご紹介していきましょう。
犬がふてくされる原因やふてくされている時の仕草をご紹介してきますが、実際に愛犬がふてくされている事を知ってしまうと飼い主さんもどう対処すればいいのか戸惑ってしまいますよね。
そこで、ここでは、犬がふてくされている時の対処法をご紹介していきましょう。
定期的に運動させる
 ふてくされてしまう原因には運動不足になっているという事もあると先ほどご紹介しましたね。
運動不足でストレスがたまってしまっている場合には、定期的に運動をさせてあげて下さい。
可能であれば、週に一度は公園やドッグランなので遊んであげたり走らせてあげるとストレスが発散され、睡眠の質もよくなり睡眠不足も解消されるという一石二鳥です。
ふてくされるという事も少なくなっていくでしょう。
ふてくされてしまう原因には運動不足になっているという事もあると先ほどご紹介しましたね。
運動不足でストレスがたまってしまっている場合には、定期的に運動をさせてあげて下さい。
可能であれば、週に一度は公園やドッグランなので遊んであげたり走らせてあげるとストレスが発散され、睡眠の質もよくなり睡眠不足も解消されるという一石二鳥です。
ふてくされるという事も少なくなっていくでしょう。
放置する
一時的なふてくされであれば、時間が経つと機嫌も良くなっている事が多いので、基本的に放置しておいてあげるのが一番です。
放置し、静かに過ごす事も犬にとっては気分をリフレッシュする事ができますので、そのような心のメンテナンスの時間も大切にしてあげて下さいね。
しかし、ふてくされる頻度が何回もあるようだったら、日頃の接し方やケアの仕方を見直してストレスの原因を少しでも取り除いてあげるのが大切です。
スキンシップ
 犬にとって飼い主とのスキンシップは非常に重要なものです。
あまりにスキンシップが少ないと愛犬は「愛されていないのかも」と欲求不満になってストレスがたまってしまいます。
愛犬がふてくされている事が多い場合は、スキンシップ不足という事もありますので、そんな時はしっかりスキンシップをはかり愛情を与えてあげましょう。
多頭買いをしている場合は、一匹だけに偏ってしまうと他の犬が拗ねたりふてくされたりしてしまいますので、満遍なくスキンシップをはかるようにして下さいね。
犬にとって飼い主とのスキンシップは非常に重要なものです。
あまりにスキンシップが少ないと愛犬は「愛されていないのかも」と欲求不満になってストレスがたまってしまいます。
愛犬がふてくされている事が多い場合は、スキンシップ不足という事もありますので、そんな時はしっかりスキンシップをはかり愛情を与えてあげましょう。
多頭買いをしている場合は、一匹だけに偏ってしまうと他の犬が拗ねたりふてくされたりしてしまいますので、満遍なくスキンシップをはかるようにして下さいね。
しつける
 わがままが原因でふてくされているのであればしっかりしつけをする事が大切です。
ふてくされる原因でご紹介しましたが、わがままになる理由は飼い主さんとの上下関係が築かれていないからかと思われます。
最初からしつけをしっかり行い主従関係を築けているのであれば、飼い主さんから怒られても、自分の欲求が通らなくてもストレスに感じる事が少なくなり、ふてくされる事なく飼い主さんの言う事を聞くでしょう。
しつけをするという事は褒める事も入っていますので、普段から褒めてあげる事ができていればしつけも問題なくできるようになります。
わがままが原因でふてくされているのであればしっかりしつけをする事が大切です。
ふてくされる原因でご紹介しましたが、わがままになる理由は飼い主さんとの上下関係が築かれていないからかと思われます。
最初からしつけをしっかり行い主従関係を築けているのであれば、飼い主さんから怒られても、自分の欲求が通らなくてもストレスに感じる事が少なくなり、ふてくされる事なく飼い主さんの言う事を聞くでしょう。
しつけをするという事は褒める事も入っていますので、普段から褒めてあげる事ができていればしつけも問題なくできるようになります。
おもちゃで遊ぶ
 構ってあげられていない事が原因でふてくされている場合は、大好きなおもちゃで遊んであげるのもいいですね。
おもちゃを使うと飼い主さん側から愛犬への一緒に遊んであげるという明確な意思表示になりますので、犬は構ってもらえているんだとわかりやすく伝わります。
ここで、ダラダラするのではなくメリハリをつける事が大切。
おもちゃを出したら遊ぶ時間、出していない時は遊ぶ時間ではないとはっきりさせておくと、愛犬も時間を意識するようになりますので、しつけをする時にも役立つでしょう。
構ってあげられていない事が原因でふてくされている場合は、大好きなおもちゃで遊んであげるのもいいですね。
おもちゃを使うと飼い主さん側から愛犬への一緒に遊んであげるという明確な意思表示になりますので、犬は構ってもらえているんだとわかりやすく伝わります。
ここで、ダラダラするのではなくメリハリをつける事が大切。
おもちゃを出したら遊ぶ時間、出していない時は遊ぶ時間ではないとはっきりさせておくと、愛犬も時間を意識するようになりますので、しつけをする時にも役立つでしょう。
まとめ
 今回は犬がふれくされる原因や仕草、対処法をご紹介してきました。
こうして見てみると犬は人間の事をよく観察していますよね。
そして人間ともよく似ているなと感じました。
犬が人間の事をしっかり見てくれているのだから、人間もしっかり犬の様子を観察してあげる事が大切ではないでしょうか。
そして、ふてくされているような仕草が見られたら原因を探りストレスを軽減させてあげたり、気持ちを理解してあげる事が大切ですね。
今回は犬がふれくされる原因や仕草、対処法をご紹介してきました。
こうして見てみると犬は人間の事をよく観察していますよね。
そして人間ともよく似ているなと感じました。
犬が人間の事をしっかり見てくれているのだから、人間もしっかり犬の様子を観察してあげる事が大切ではないでしょうか。
そして、ふてくされているような仕草が見られたら原因を探りストレスを軽減させてあげたり、気持ちを理解してあげる事が大切ですね。
犬にもほくろがある?
 犬とのスキンシップの時に、ほくろみたいなものを見つけたら気になりますね。
犬は全身を毛に覆われているので、人間ほど紫外線の影響は多くないと言われますが、やはり鼻の先など毛の薄い部分にはシミやほくろができることがあります。
ほくろそのものは病気ではありませんが、皮膚がんなどの腫瘍との違いを知っておき、気になる場合は早めに診察を受けましょう。
犬とのスキンシップの時に、ほくろみたいなものを見つけたら気になりますね。
犬は全身を毛に覆われているので、人間ほど紫外線の影響は多くないと言われますが、やはり鼻の先など毛の薄い部分にはシミやほくろができることがあります。
ほくろそのものは病気ではありませんが、皮膚がんなどの腫瘍との違いを知っておき、気になる場合は早めに診察を受けましょう。
犬にもほくろはある
 ほくろはメラニン色素がたくさん皮膚に沈着したものです。
メラニン色素は紫外線などの刺激を受けることで多く発生することがわかっています。
わたしたちが困る肌のシミやほくろも多くの紫外線が関係しています。
そして、それは犬も同じです。
歳を取るとお腹や鼻、唇などにほくろやシミが現れやすくなります。
やはり被毛の薄い部分は紫外線の刺激をたくさん受けることが多いからです。
ほくろは色が均一で周りとの境界線がはっきりしているのが特徴です。
ほくろはメラニン色素がたくさん皮膚に沈着したものです。
メラニン色素は紫外線などの刺激を受けることで多く発生することがわかっています。
わたしたちが困る肌のシミやほくろも多くの紫外線が関係しています。
そして、それは犬も同じです。
歳を取るとお腹や鼻、唇などにほくろやシミが現れやすくなります。
やはり被毛の薄い部分は紫外線の刺激をたくさん受けることが多いからです。
ほくろは色が均一で周りとの境界線がはっきりしているのが特徴です。
ほくろであればガンにならない?
見慣れない黒いほくろのようなものを見つけると、飼い主は「ガンなのでは?」と不安になってしまいます。
実際「犬 ほくろ」と検索すると腫瘍についてのサイトがたくさん見受けられるからです。
ですが、ほくろがガンに発展することはあまりありません。
見た目は気になりますが、そのままにしておいても問題はなく大丈夫です。
腫瘍には良性と悪性があり、良性腫瘍はほくろの一種と考えられています。
ただ、周囲との境界がはっきりしていない場合や急に大きくなった場合などはほくろと断定できないので、素人判断を避けて獣医の診察を受けましょう。
メラノーマには気をつけて!
 犬の皮膚腫瘍として極めて悪性度が高いのがメラノーマです。
メラノーマは悪性黒色腫と呼ばれる皮膚がんの一種で、ほくろと同じくメラニン細胞に関係しています。
進行が早く自覚症状もあまりないので、早期に発見することが難しい病気です。
ほくろと見分けることは重要になりますので、メラノーマの特徴や治療方法、ほくろとの見分け方などを知っておきましょう。
犬の皮膚腫瘍として極めて悪性度が高いのがメラノーマです。
メラノーマは悪性黒色腫と呼ばれる皮膚がんの一種で、ほくろと同じくメラニン細胞に関係しています。
進行が早く自覚症状もあまりないので、早期に発見することが難しい病気です。
ほくろと見分けることは重要になりますので、メラノーマの特徴や治療方法、ほくろとの見分け方などを知っておきましょう。
メラノーマって何?
 犬の皮膚にできるメラノーマは、皮膚がんの中でもおよそ6%を占める病気です。
黒く色素沈着していてほくろと似ているのですが、ほくろが悪性メラノーマに変化するわけではありません。
また黒くないメラノーマも30%程度あります。
発生する原因は外部からの長く続く刺激と免疫の低下と言われています。
メラノーマは足先や肉球付近、口腔内に発生することが多く、肉眼で発見できる場所なのでスキンシップをいつも行うようにしましょう。
犬の皮膚にできるメラノーマは、皮膚がんの中でもおよそ6%を占める病気です。
黒く色素沈着していてほくろと似ているのですが、ほくろが悪性メラノーマに変化するわけではありません。
また黒くないメラノーマも30%程度あります。
発生する原因は外部からの長く続く刺激と免疫の低下と言われています。
メラノーマは足先や肉球付近、口腔内に発生することが多く、肉眼で発見できる場所なのでスキンシップをいつも行うようにしましょう。
ほくろとメラノーマの見分け方
ほくろもメラノーマもメラニン色素が関係しています。
そのためよく似ているので次の点に注目して観察しましょう。
・盛り上がっているかどうか
・境い目ははっきりしているか
・急に大きくなってきたか
・色がまだら
・形が丸やだ円ではない
ほくろはその境い目がはっきりとして形も丸やだ円形なので、そうではなかったり最近急に大きくなってきたように思う場合はメラノーマである可能性があります。
すぐに動物病院で診察を受けましょう。
メラノーマの判断は針を指して一部の細胞を顕微鏡で調べる細胞診というもので診断します。
はっきりしない場合は病理検査や血液検査も行います。
メラノーマの治療方法
メラノーマの治療では外科手術が一番の選択となります。
状況によってはメラノーマ腫瘍の周囲も含めて広い範囲を除去しなければならないケースもあります。
それだけ再発が多い悪性ガンだからです。
抗がん剤はメラノーマには効果が薄く、副作用のリスクも高いため局所的な治療として使われることが多いです。
放射線治療は設備が必要で、取り切れなかった腫瘍部分や手術不可能な部分に行うことがあります。
ただ毎回全身麻酔が必要ですし、放射線でガンをすべて取り除くことはできません。
がん治療の代替療法も研究が進んでいます。
食事により免疫力を上げたり、手術後の生活に十分な配慮をして改善している例も多く上がってきています。
まとめ
 犬も人間も紫外線を長時間浴びることでのリスクがあります。
シミやほくろもその結果なのでやはりケアが必要ということですね。
またほくろとよく似たメラノーマという病気もあるため、発見した時はできるだけ診察をしてもらうことをおすすめします。
日差しの暑い時間帯の散歩を避けたり、体の免疫力を上げるように普段から心がけてあげましょう。
犬も人間も紫外線を長時間浴びることでのリスクがあります。
シミやほくろもその結果なのでやはりケアが必要ということですね。
またほくろとよく似たメラノーマという病気もあるため、発見した時はできるだけ診察をしてもらうことをおすすめします。
日差しの暑い時間帯の散歩を避けたり、体の免疫力を上げるように普段から心がけてあげましょう。
 チワワは人気ランキングの上位に常に入っている大人気の犬種です。
魅力は愛くるしい目ではないでしょうか。
臆病な性格ですが比較的飼いやすい犬種と言われています。
そんなチワワですが幼少期から死ぬ時までに患いやすい病気というものはいくつかあります。
ここでは、その病気について詳しく解説いきたいと思います。
チワワは人気ランキングの上位に常に入っている大人気の犬種です。
魅力は愛くるしい目ではないでしょうか。
臆病な性格ですが比較的飼いやすい犬種と言われています。
そんなチワワですが幼少期から死ぬ時までに患いやすい病気というものはいくつかあります。
ここでは、その病気について詳しく解説いきたいと思います。
 低血糖症とは、血液の糖分濃度が低下する病気で、体の冷えや長時間の空腹、内臓障害などによる栄養九州の悪化が原因で起こります。
特にチワワは体が小さいので生後3か月までの子犬は、1回の食事量が少なく、6時間~12時間食事をしないだけでも低血糖を起こすことも。
低血糖状態が長く続くと命を落とす可能性があるので、チワワがぐったりしている場合はすぐに病院へ行きましょう。
チワワは活発な犬種なので、低血糖症を起こす可能性が子犬だけではなく成犬でも老犬でも起こりやすいもので、チワワと低血糖症は切っても切れない仲と覚えておきましょう。
低血糖症とは、血液の糖分濃度が低下する病気で、体の冷えや長時間の空腹、内臓障害などによる栄養九州の悪化が原因で起こります。
特にチワワは体が小さいので生後3か月までの子犬は、1回の食事量が少なく、6時間~12時間食事をしないだけでも低血糖を起こすことも。
低血糖状態が長く続くと命を落とす可能性があるので、チワワがぐったりしている場合はすぐに病院へ行きましょう。
チワワは活発な犬種なので、低血糖症を起こす可能性が子犬だけではなく成犬でも老犬でも起こりやすいもので、チワワと低血糖症は切っても切れない仲と覚えておきましょう。
 突然死とは症状が出てから24時間以内に死亡してしまうことを言い、チワワはこの突然死が多い犬種と言われています。
朝は普通にご飯を食べていつも通りに過ごしていたのに、飼い主さんが仕事から帰宅したら死んでいたというようなケースもあります。
死ぬ前は元気だったのに…と飼い主さんは突然の死にショックが大きいでしょう。
そこで、今回はチワワの突然死は何が理由で起こるのかご紹介していきます。
突然死とは症状が出てから24時間以内に死亡してしまうことを言い、チワワはこの突然死が多い犬種と言われています。
朝は普通にご飯を食べていつも通りに過ごしていたのに、飼い主さんが仕事から帰宅したら死んでいたというようなケースもあります。
死ぬ前は元気だったのに…と飼い主さんは突然の死にショックが大きいでしょう。
そこで、今回はチワワの突然死は何が理由で起こるのかご紹介していきます。
 てんかんに代表される発作も突然死の原因となり、全般発作(大きな発作)は意識のある間に上手く呼吸をすることが不可能になり、呼吸困難によって突然死を引き起こします。
原因は様々あり、原因が特にない突発性てんかん、脳腫瘍、脳炎、水頭症など脳の病気や、腎臓や肝臓の病気による有毒蓄積によって脳が障害を受け、発作を起こす場合があります。
水頭症になりやすい犬種のチワワは発作がよく見られ、なんの前触れもなく突然起こる場合もあれば、
少しぼ~っとしている軽い発作、全身の筋肉の痙攣を引き起こす大きな発作まだ様々ですが、その中でも突然死を引き起こす発作は全般発作になります。
飼い主さんの日々の観察が大切となりますので、少しでも変わった様子が見られた場合は病院で診察を受けるようにしてください。
てんかんに代表される発作も突然死の原因となり、全般発作(大きな発作)は意識のある間に上手く呼吸をすることが不可能になり、呼吸困難によって突然死を引き起こします。
原因は様々あり、原因が特にない突発性てんかん、脳腫瘍、脳炎、水頭症など脳の病気や、腎臓や肝臓の病気による有毒蓄積によって脳が障害を受け、発作を起こす場合があります。
水頭症になりやすい犬種のチワワは発作がよく見られ、なんの前触れもなく突然起こる場合もあれば、
少しぼ~っとしている軽い発作、全身の筋肉の痙攣を引き起こす大きな発作まだ様々ですが、その中でも突然死を引き起こす発作は全般発作になります。
飼い主さんの日々の観察が大切となりますので、少しでも変わった様子が見られた場合は病院で診察を受けるようにしてください。
 チワワにとって生活の急激な変化がストレスとなり、突然死を引き起こしてしまう原因となりますので、生活環境に注意をし、隠れた病気がないかを注意深く観察することが重要となってきます。
突然死を防ぐためには、チワワと十分なコミュニケーションをとることが必要となり、しっかりご飯を食べているか、便や尿に異常はないかなどがすぐわかるようにしておきましょう。
日々の小さな変化や軽い症状であってもチワワにとっては命取りになる可能性が大きいので、少しでも様子がおかしいと感じた場合は病院で診察を受けることをオススメします。
様々な検査を実施してもらい問題が発見できれば、突然死を回避できるかもしれません。
チワワにとって生活の急激な変化がストレスとなり、突然死を引き起こしてしまう原因となりますので、生活環境に注意をし、隠れた病気がないかを注意深く観察することが重要となってきます。
突然死を防ぐためには、チワワと十分なコミュニケーションをとることが必要となり、しっかりご飯を食べているか、便や尿に異常はないかなどがすぐわかるようにしておきましょう。
日々の小さな変化や軽い症状であってもチワワにとっては命取りになる可能性が大きいので、少しでも様子がおかしいと感じた場合は病院で診察を受けることをオススメします。
様々な検査を実施してもらい問題が発見できれば、突然死を回避できるかもしれません。
 今回はチワワの突然死についてご紹介してきました。
チワワは他の犬種に比べ突然死が起こりやすい犬種ですが、飼いやすいという理由でチワワを飼っている方が多いです。
しかし、チワワを飼った以上は、チワワがなりやすい病気や突然死はどのようにして起こるのかということを飼い主さんは事前に調査しておく必要があります。
そうすることで、なりやすい病気や発作も回避することができ、突然死を防ぐことができるでしょう。
今回はチワワの突然死についてご紹介してきました。
チワワは他の犬種に比べ突然死が起こりやすい犬種ですが、飼いやすいという理由でチワワを飼っている方が多いです。
しかし、チワワを飼った以上は、チワワがなりやすい病気や突然死はどのようにして起こるのかということを飼い主さんは事前に調査しておく必要があります。
そうすることで、なりやすい病気や発作も回避することができ、突然死を防ぐことができるでしょう。  猫というのはツンデレが上手で、その気ままな素振りがまた可愛いと大きな魅力となっていますよね。
そんな時、愛猫は何を考えているのでしょう?
それがわかれば飼い主さんは愛猫の気持ちがわかり、嬉しいですし、助かる部分もあるのではないでしょうか。
そこで、今回はまず鳴き声で猫の気持ちがわかる方法をご紹介しましょう。
猫というのはツンデレが上手で、その気ままな素振りがまた可愛いと大きな魅力となっていますよね。
そんな時、愛猫は何を考えているのでしょう?
それがわかれば飼い主さんは愛猫の気持ちがわかり、嬉しいですし、助かる部分もあるのではないでしょうか。
そこで、今回はまず鳴き声で猫の気持ちがわかる方法をご紹介しましょう。
 猫が「シャー!ウー!」と鳴いている時は明らかに機嫌が良い鳴き声ではないという事はわかりますよね。
しかもその時の体をよくみてみると毛が逆立っています。
この鳴き方は怒りを感じた時や警戒している時に出す声で、興奮状態になっていますので、無理になだめたりしするのではなく落ち着くまで見守ってあげましょう。
例えば、先住猫がいる状態で新しい猫を迎えいれた時、この鳴き方をしているようであれば、喧嘩をしないように注意深く観察しておくようにしないと喧嘩が始まってしまうとケガをする可能性があります。
猫が「シャー!ウー!」と鳴いている時は明らかに機嫌が良い鳴き声ではないという事はわかりますよね。
しかもその時の体をよくみてみると毛が逆立っています。
この鳴き方は怒りを感じた時や警戒している時に出す声で、興奮状態になっていますので、無理になだめたりしするのではなく落ち着くまで見守ってあげましょう。
例えば、先住猫がいる状態で新しい猫を迎えいれた時、この鳴き方をしているようであれば、喧嘩をしないように注意深く観察しておくようにしないと喧嘩が始まってしまうとケガをする可能性があります。
 小さい子に猫の事を「あれは何ていう動物?」と聞くと「ニャーニャー」と言いませんか?
まさに猫のイメージがこの鳴き声なんですよね。
猫が「ニャオ」「ニャー」と穏やかに泣いている時は猫にとっては挨拶のようなもの。
そして次に何かアクションを起こす前触れでもありますので、挨拶であればいいのですが、アクションを起こす前触れだったらびっくりしてしまう可能性も出てきますので、じっくり猫の様子を観察してから触れるようにしましょう。
小さい子に猫の事を「あれは何ていう動物?」と聞くと「ニャーニャー」と言いませんか?
まさに猫のイメージがこの鳴き声なんですよね。
猫が「ニャオ」「ニャー」と穏やかに泣いている時は猫にとっては挨拶のようなもの。
そして次に何かアクションを起こす前触れでもありますので、挨拶であればいいのですが、アクションを起こす前触れだったらびっくりしてしまう可能性も出てきますので、じっくり猫の様子を観察してから触れるようにしましょう。
 喉の奥から「ゴロゴロ」と慣らしているのは鳴き声ではないかもしれませんが、これも猫にとっては重要な合図になります。
この鳴き声は猫がリラックスしている時や甘えている時のサインです。
もし、飼い主さんが愛猫を撫でている時にこの鳴き声が聞こえてきたら、飼い主さんを信頼して甘えているという証拠になりますので、飼い主さんにとっては嬉しい鳴き声になるのではないでしょうか。
喉の奥から「ゴロゴロ」と慣らしているのは鳴き声ではないかもしれませんが、これも猫にとっては重要な合図になります。
この鳴き声は猫がリラックスしている時や甘えている時のサインです。
もし、飼い主さんが愛猫を撫でている時にこの鳴き声が聞こえてきたら、飼い主さんを信頼して甘えているという証拠になりますので、飼い主さんにとっては嬉しい鳴き声になるのではないでしょうか。
 愛猫を眺めているだけで癒されますが、たまに「面白い事をするな」「何をしているんだろ?」というような事をする場面があります。
その行動の理由がわかると飼い主さんも今よりもっと愛猫の気持ちがわかるのではないでしょうか。
そこで、ここでは猫の気持ちがわかる、よく見られる行動をご紹介していきましょう。
愛猫を眺めているだけで癒されますが、たまに「面白い事をするな」「何をしているんだろ?」というような事をする場面があります。
その行動の理由がわかると飼い主さんも今よりもっと愛猫の気持ちがわかるのではないでしょうか。
そこで、ここでは猫の気持ちがわかる、よく見られる行動をご紹介していきましょう。
 猫が自分の体をすりすり擦り付けてくる行動もよく見られます。
この行動をしてくると「甘えているのかな?」と思うもの。
もちろん、そういう意味も含まれているのですが、実際は自分の匂いをこすりつける「マーキング」という行動になります。
大好きな飼い主さんに他の匂いがついているのが嫌で一生懸命自分の匂いをつけようとしていると考えると愛猫がそれだけ自分を好きでいてくれているんだと嬉しい気持ちになりますね。
猫が自分の体をすりすり擦り付けてくる行動もよく見られます。
この行動をしてくると「甘えているのかな?」と思うもの。
もちろん、そういう意味も含まれているのですが、実際は自分の匂いをこすりつける「マーキング」という行動になります。
大好きな飼い主さんに他の匂いがついているのが嫌で一生懸命自分の匂いをつけようとしていると考えると愛猫がそれだけ自分を好きでいてくれているんだと嬉しい気持ちになりますね。
 暇あれば愛猫が自分の体を舐めている事ありませんか?
この行動は毛づくろい(グルーミング)と言われているもので、猫にとっては習慣のようなもの。
毛づくろいをして自分についた汚れや匂いを取り除き綺麗に保つようにしているのです。
しかし、他の理由がある場合もあり、それは不安な時にリラックスさせるために行っている事もあります。
逆にリラックスしているので毛づくろいをするという事もあるようなので、時々によって毛づくろいをしている気持ちを汲み取ってあげられたらいいですね。
暇あれば愛猫が自分の体を舐めている事ありませんか?
この行動は毛づくろい(グルーミング)と言われているもので、猫にとっては習慣のようなもの。
毛づくろいをして自分についた汚れや匂いを取り除き綺麗に保つようにしているのです。
しかし、他の理由がある場合もあり、それは不安な時にリラックスさせるために行っている事もあります。
逆にリラックスしているので毛づくろいをするという事もあるようなので、時々によって毛づくろいをしている気持ちを汲み取ってあげられたらいいですね。
 猫は好き勝手に行動するというイメージですが、野良猫を見てもらえばわかるように集団で集まっている事がありますよね?
自宅で猫を多頭飼いする場合、結果的には集団行動をする事になるのですが、猫によってパワーバランスが違いますので、集団行動をする中で微妙な距離感が保たれています。
日当たりが良い場所でじっとしている子、風が気持ち良い場所にいる子など様々なので、よく観察してあげて下さい。
猫は好き勝手に行動するというイメージですが、野良猫を見てもらえばわかるように集団で集まっている事がありますよね?
自宅で猫を多頭飼いする場合、結果的には集団行動をする事になるのですが、猫によってパワーバランスが違いますので、集団行動をする中で微妙な距離感が保たれています。
日当たりが良い場所でじっとしている子、風が気持ち良い場所にいる子など様々なので、よく観察してあげて下さい。
 しっぽには「尾堆」という小さな骨が連なって出来ており、しなやかで様々な動きをする事ができます。
役割は、身体のバランスを取る事はもちろんですが、猫同士のコミュニケーションにも役立っており、尻尾の動かし方でも猫がどんな気持ちなのか読み取る事ができます。
そこで、ここでは尻尾の動きによる猫の気持ちをご紹介しましょう。
しっぽには「尾堆」という小さな骨が連なって出来ており、しなやかで様々な動きをする事ができます。
役割は、身体のバランスを取る事はもちろんですが、猫同士のコミュニケーションにも役立っており、尻尾の動かし方でも猫がどんな気持ちなのか読み取る事ができます。
そこで、ここでは尻尾の動きによる猫の気持ちをご紹介しましょう。
 しっぽを「ブンブン!」と音が聞こえてきそうなくらい早く動かしている時は、犬であれば喜びのサインなのですが、猫の場合は機嫌がよくなかったり、戦う相手をみつけてしまったところという状態かもしれません。
犬では喜びの動作、猫では機嫌が悪い動作と真逆の動作なので、ついつい触ってしまいそうになるかもしれませんが、このような行動をしている時は触ったり、抱っこしたりせず、そっとしておくのが一番でしょう。
しっぽを「ブンブン!」と音が聞こえてきそうなくらい早く動かしている時は、犬であれば喜びのサインなのですが、猫の場合は機嫌がよくなかったり、戦う相手をみつけてしまったところという状態かもしれません。
犬では喜びの動作、猫では機嫌が悪い動作と真逆の動作なので、ついつい触ってしまいそうになるかもしれませんが、このような行動をしている時は触ったり、抱っこしたりせず、そっとしておくのが一番でしょう。
 「ピクピク」と小さく早くしっぽが動いている時があるのですが、その時の猫の気持ちは特に複雑な感じになっているようで、状況によっては、何か考えごとをしていたり、不安を感じていたり、緊張しているケースが考えられます。
先ほどご紹介したしっぽを早く動かす動作と同じで機嫌がよいという状態ではないので、無理に触ったり、構ったりするのはやめましょう。
そっとしておいてあげると落ち着いてきますのでそれまで自由にさせておいてあげて下さい。
「ピクピク」と小さく早くしっぽが動いている時があるのですが、その時の猫の気持ちは特に複雑な感じになっているようで、状況によっては、何か考えごとをしていたり、不安を感じていたり、緊張しているケースが考えられます。
先ほどご紹介したしっぽを早く動かす動作と同じで機嫌がよいという状態ではないので、無理に触ったり、構ったりするのはやめましょう。
そっとしておいてあげると落ち着いてきますのでそれまで自由にさせておいてあげて下さい。
 ピンと立ったしっぽは、「嬉しい!」という気持ちの表れです。
飼い主さんやその家族が家に帰った時にこの行動をしてくれていたら喜んでくれている証拠ですので飼い主さんかたしたら嬉しい行動ですね。
元々この行動は、子猫が母猫に近づく際に、存在をアピールする行動と言われており、友好的な気持ちを相手に伝えるために行うと考えられています。
飼い主さんに対して行われているようであれば、甘えている時や遊んでほしい時なので、構ったり、撫でたりしてあげて下さい。
ピンと立ったしっぽは、「嬉しい!」という気持ちの表れです。
飼い主さんやその家族が家に帰った時にこの行動をしてくれていたら喜んでくれている証拠ですので飼い主さんかたしたら嬉しい行動ですね。
元々この行動は、子猫が母猫に近づく際に、存在をアピールする行動と言われており、友好的な気持ちを相手に伝えるために行うと考えられています。
飼い主さんに対して行われているようであれば、甘えている時や遊んでほしい時なので、構ったり、撫でたりしてあげて下さい。
 人間にとっては一つ一つの仕草が可愛くてたまらなくても、猫にとっては様々な気持ちが詰まっています。
何気なくしている仕草でも全てに意味がありますので、その仕草から感情を読み取れるようチャレンジしてみるのも楽しいかもしれません。
そこで、ここでは、猫の気持ちがわかる仕草をご紹介していきましょう。
人間にとっては一つ一つの仕草が可愛くてたまらなくても、猫にとっては様々な気持ちが詰まっています。
何気なくしている仕草でも全てに意味がありますので、その仕草から感情を読み取れるようチャレンジしてみるのも楽しいかもしれません。
そこで、ここでは、猫の気持ちがわかる仕草をご紹介していきましょう。
 きるだけ身体を小さく見せようとうずくまったり、耳を折りたたんで丸まったりしている場合は、怖がっていると考えてよいでしょう。
あまりの恐怖を感じている場合は、身体に力が入り硬直して動かなくなったりする事もあるのです。
そんな時は、怖がっているものが何なのかを探り、見えないようにしたり遠ざけたりなどして落ち着ける環境を作ってあげて下さい。
きるだけ身体を小さく見せようとうずくまったり、耳を折りたたんで丸まったりしている場合は、怖がっていると考えてよいでしょう。
あまりの恐怖を感じている場合は、身体に力が入り硬直して動かなくなったりする事もあるのです。
そんな時は、怖がっているものが何なのかを探り、見えないようにしたり遠ざけたりなどして落ち着ける環境を作ってあげて下さい。
 招き猫のように前足を片方だけあげてフリーズしてしまっている場合もありますが、それは「逃げるか?猫パンチしようか?」と次の行動を考えている最中です。
それは誰に対してなにかわかりませんが、そんな場面を見てしまったら飼い主さんも構えてしまうかもしれませんね。
その仕草を見てしまった場合は、そっとしておくのが一番です。
招き猫のように前足を片方だけあげてフリーズしてしまっている場合もありますが、それは「逃げるか?猫パンチしようか?」と次の行動を考えている最中です。
それは誰に対してなにかわかりませんが、そんな場面を見てしまったら飼い主さんも構えてしまうかもしれませんね。
その仕草を見てしまった場合は、そっとしておくのが一番です。
 全身の毛を逆立てて背中を丸め、自分の身体を大きく見せようとする仕草は全力で威嚇しているサインで、しっぽをよく観察してみるとタヌキのように膨らんでいる事も特徴の一つでしょう。
「シャー!」と鳴きながらこのような仕草をしている場合は、怒っている、威嚇している状態ですので、無理に触ったりしないようにしましょう。
猫のするどい爪で引っ掻かれてしまう可能性があります。
全身の毛を逆立てて背中を丸め、自分の身体を大きく見せようとする仕草は全力で威嚇しているサインで、しっぽをよく観察してみるとタヌキのように膨らんでいる事も特徴の一つでしょう。
「シャー!」と鳴きながらこのような仕草をしている場合は、怒っている、威嚇している状態ですので、無理に触ったりしないようにしましょう。
猫のするどい爪で引っ掻かれてしまう可能性があります。
 猫の耳はとても優秀で、人間には聞こえない音もキャッチできると言われています。
そんな耳がペタッとしている時は、この上ない心地よさを感じている状態でリラックスモードです。
傍で見ていてもとても愛らしい仕草ですよね。
気持ちいい時やくつろいでいる時の脱力状態で耳にあらわれているのです。
猫の耳はとても優秀で、人間には聞こえない音もキャッチできると言われています。
そんな耳がペタッとしている時は、この上ない心地よさを感じている状態でリラックスモードです。
傍で見ていてもとても愛らしい仕草ですよね。
気持ちいい時やくつろいでいる時の脱力状態で耳にあらわれているのです。
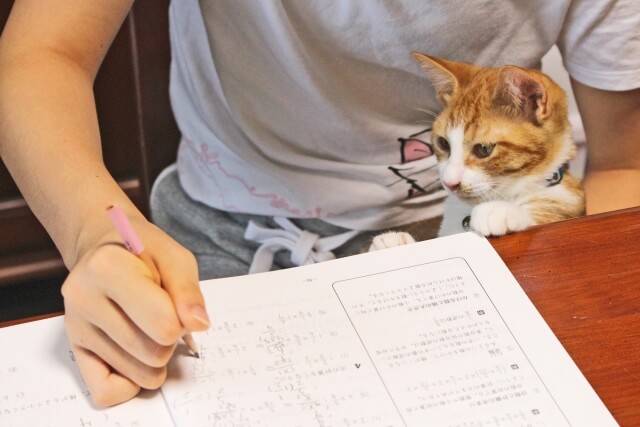 猫は自由自在に動き回れる生き物なので、飼い主さんが大好きなあまり何処に行ってもついてくる事があります。
一番困るのは仕事を邪魔してくること。
本を読んでいるのに本の上に乗ってきて動かない、パソコンを打とうとすればキーボードの上に座って動かないなど。
可愛い行動なのですがどうしていいものか困ってしまいます。
この行動は愛情表現ではなく自分に注目して欲しいというアピール。
本当に邪魔だったら無視しても問題ありません。
猫は自由自在に動き回れる生き物なので、飼い主さんが大好きなあまり何処に行ってもついてくる事があります。
一番困るのは仕事を邪魔してくること。
本を読んでいるのに本の上に乗ってきて動かない、パソコンを打とうとすればキーボードの上に座って動かないなど。
可愛い行動なのですがどうしていいものか困ってしまいます。
この行動は愛情表現ではなく自分に注目して欲しいというアピール。
本当に邪魔だったら無視しても問題ありません。
 今回は猫も気持ちをご紹介してきました。
猫は様々な行動や仕草をしますが、その一つ一つに意味があったんですね。
何気なく見ていた事でも本当はこんな意味があったんだとわかれば飼い主さんも今後どのように愛猫と接すればいいのかわかった気がしませんか?
猫の気持ちをわかっていれば、猫の事を今までよりもっと理解してあげられますね。
今回は猫も気持ちをご紹介してきました。
猫は様々な行動や仕草をしますが、その一つ一つに意味があったんですね。
何気なく見ていた事でも本当はこんな意味があったんだとわかれば飼い主さんも今後どのように愛猫と接すればいいのかわかった気がしませんか?
猫の気持ちをわかっていれば、猫の事を今までよりもっと理解してあげられますね。
 犬も人間と同じように感情というものがあり、いつも喜んでいる訳ではなく、悲しんでいる時もあれば、しんどくなって元気がない時もあります。
そしてふてくされる事もあるのです。
犬がふてくされる理由が様々考えられるのですが、今回はそれをご紹介していきたいと思います。
犬も人間と同じように感情というものがあり、いつも喜んでいる訳ではなく、悲しんでいる時もあれば、しんどくなって元気がない時もあります。
そしてふてくされる事もあるのです。
犬がふてくされる理由が様々考えられるのですが、今回はそれをご紹介していきたいと思います。
 犬も人間の子供と同様、自由気ままに育ててしまうとわがままになってしまう事があります。
犬がわがままになる主な原因は、飼い主さんとの主従関係が正しく築けていない事かもしれないとのこと。
飼い主さんがしっかりしつけをしていなかったり、甘やかしてばかりいると犬は「自分は飼い主より立場が上だ」と勘違いしてしまうことがあるのです。
そのように育ってしまうと自分の要求が通らなかったりするとすぐに機嫌が悪くなって「何で自分より立場が下の人に怒られなければいけないの」という感じでふてくされるという事があります。
犬も人間の子供と同様、自由気ままに育ててしまうとわがままになってしまう事があります。
犬がわがままになる主な原因は、飼い主さんとの主従関係が正しく築けていない事かもしれないとのこと。
飼い主さんがしっかりしつけをしていなかったり、甘やかしてばかりいると犬は「自分は飼い主より立場が上だ」と勘違いしてしまうことがあるのです。
そのように育ってしまうと自分の要求が通らなかったりするとすぐに機嫌が悪くなって「何で自分より立場が下の人に怒られなければいけないの」という感じでふてくされるという事があります。
 犬には発情期というものがあります。
オスの場合はそこまできつくないのですが、メスとなると自律神経が乱れホルモンバランスが崩れてしまい、イライラしたりちょっとした事で機嫌が悪くなりふてくされてしまうという事があります。
これはメスである以上、仕方がない事なのでいつもよりイライラしたりふてくされる回数が多いなと思った時は、そっとしておいてあげましょう。
この時は犬も何故イライラしたりふてくされるのかわかっていない場合が多いです。
発情期以外にも病気やストレスでホルモンバランスが崩れる事もありますので、発情期が過ぎた後も機嫌が悪い状態が続いたり、体調が悪そうであればすぐに受診するようにして下さいね。
犬には発情期というものがあります。
オスの場合はそこまできつくないのですが、メスとなると自律神経が乱れホルモンバランスが崩れてしまい、イライラしたりちょっとした事で機嫌が悪くなりふてくされてしまうという事があります。
これはメスである以上、仕方がない事なのでいつもよりイライラしたりふてくされる回数が多いなと思った時は、そっとしておいてあげましょう。
この時は犬も何故イライラしたりふてくされるのかわかっていない場合が多いです。
発情期以外にも病気やストレスでホルモンバランスが崩れる事もありますので、発情期が過ぎた後も機嫌が悪い状態が続いたり、体調が悪そうであればすぐに受診するようにして下さいね。
 これは人間も同様の事が言えると思いますが、体調が悪いとできるだけ構って欲しくないのでそっけない態度を取ったり、イライラしてふてくされたりします。
それだけ体調は悪い時は余裕がないと言えるでしょう。
そんな時、飼い主さんは愛犬の体調をしっかり観察してあげる事が大切です。
体調が悪い場合、ふてくされている態度だけではわからない事も多いので、
・ご飯はしっかり食べているか?
・水分をしっかり補給しているか?
・おしっこや便はしているか?
という健康観察が大事になってきます。
すぐに病院へ連れて行く事がなさそうであれば少し様子をみてそれでもよくならない場合は受診しましょう。
これは人間も同様の事が言えると思いますが、体調が悪いとできるだけ構って欲しくないのでそっけない態度を取ったり、イライラしてふてくされたりします。
それだけ体調は悪い時は余裕がないと言えるでしょう。
そんな時、飼い主さんは愛犬の体調をしっかり観察してあげる事が大切です。
体調が悪い場合、ふてくされている態度だけではわからない事も多いので、
・ご飯はしっかり食べているか?
・水分をしっかり補給しているか?
・おしっこや便はしているか?
という健康観察が大事になってきます。
すぐに病院へ連れて行く事がなさそうであれば少し様子をみてそれでもよくならない場合は受診しましょう。
 これも人間と同様で犬もストレスがたまるとイライラしてしまいがち。
ストレスの原因は犬によって違いますが、人間にとっては何ともない事でも犬にとっては大きなストレスの1つになっている事もあるのです。
具体的にあげると睡眠不足や運動不足。
犬にとっては大切なコミュニケーションツールである運動や散歩は不足すると欲求不満になってストレスを抱えてしまう事になります。
そして、理不尽な怒り方も絶対にNG。
このように犬というのは人間社会で生活するという事がストレスを抱えやすい状況であるという事を飼い主さんは覚えておいてあげて下さいね。
これも人間と同様で犬もストレスがたまるとイライラしてしまいがち。
ストレスの原因は犬によって違いますが、人間にとっては何ともない事でも犬にとっては大きなストレスの1つになっている事もあるのです。
具体的にあげると睡眠不足や運動不足。
犬にとっては大切なコミュニケーションツールである運動や散歩は不足すると欲求不満になってストレスを抱えてしまう事になります。
そして、理不尽な怒り方も絶対にNG。
このように犬というのは人間社会で生活するという事がストレスを抱えやすい状況であるという事を飼い主さんは覚えておいてあげて下さいね。
 では、犬がふてくされている時どのような仕草をしているのでしょうか?
普段何気なくしている仕草がもしかしたらふてくされている仕草なのかもしれません。
そこで、ここでは犬がふてくされている時の仕草をご紹介しましょう。
では、犬がふてくされている時どのような仕草をしているのでしょうか?
普段何気なくしている仕草がもしかしたらふてくされている仕草なのかもしれません。
そこで、ここでは犬がふてくされている時の仕草をご紹介しましょう。
 飼い主さんが構ってあげようと撫でたり触ったりした時にふてくされていれば無視をする事もありますが、ふてくされ度がマックスになってしまうと噛んできたり唸りだしたりします。
飼い主さんはただ触ろうとしただけなのに噛まれたり唸ったりされるとただただびっくり。
しかし、そんな時は何故愛犬がふてくされているのか原因を考えてみて、機嫌が良くなるまでほおっておくのが一番です。
決して、無理やり引っ張り出して怒ったり、スキンシップを取ろうとしないようにしましょう。
飼い主さんが構ってあげようと撫でたり触ったりした時にふてくされていれば無視をする事もありますが、ふてくされ度がマックスになってしまうと噛んできたり唸りだしたりします。
飼い主さんはただ触ろうとしただけなのに噛まれたり唸ったりされるとただただびっくり。
しかし、そんな時は何故愛犬がふてくされているのか原因を考えてみて、機嫌が良くなるまでほおっておくのが一番です。
決して、無理やり引っ張り出して怒ったり、スキンシップを取ろうとしないようにしましょう。
 あくびをしている仕草を見ているとただ「眠たいだけなんだ」と思ってしまいがちですが、何回もあくびをしている時は機嫌が悪い場合があります。
あくびというのはリラックス状態を示している事もあるのですが、機嫌が悪いという全く正反対の状態の事もあるのです。
わかりやすい例をあげると、愛犬をきつく叱ったりした後に何回もあくびをしている時は強いストレスがかかっている状態で、あくびをする事で緊張状態をほぐしたいと思っているという事になります。
そんな時は、愛犬が好きな遊びや散歩に連れて行くなどしてストレス発散させてあげるのがいいかもしれませんね。
あくびをしている仕草を見ているとただ「眠たいだけなんだ」と思ってしまいがちですが、何回もあくびをしている時は機嫌が悪い場合があります。
あくびというのはリラックス状態を示している事もあるのですが、機嫌が悪いという全く正反対の状態の事もあるのです。
わかりやすい例をあげると、愛犬をきつく叱ったりした後に何回もあくびをしている時は強いストレスがかかっている状態で、あくびをする事で緊張状態をほぐしたいと思っているという事になります。
そんな時は、愛犬が好きな遊びや散歩に連れて行くなどしてストレス発散させてあげるのがいいかもしれませんね。
 飼い主さんがスキンシップを取ろうとしても一切興味を示さなかったり、いつもなら大好きなおもちゃを見ると飛んでくるのにずっと寝たまま。
明らかに耳や動いているので聞こえてはいるのですが、ふてくされてしまっている時は飼い主さんにも無関心になってしまいます。
そんな仕草をされたら飼い主さんも悲しくなってしまうでしょうが、落ち着くまではそっとしておくようにしましょう。
飼い主さんがスキンシップを取ろうとしても一切興味を示さなかったり、いつもなら大好きなおもちゃを見ると飛んでくるのにずっと寝たまま。
明らかに耳や動いているので聞こえてはいるのですが、ふてくされてしまっている時は飼い主さんにも無関心になってしまいます。
そんな仕草をされたら飼い主さんも悲しくなってしまうでしょうが、落ち着くまではそっとしておくようにしましょう。
 おやつをくれると思ったのにくれなかった時や怒られた時などにふて寝をする仕草を見せる事があります。
そんな時に、飼い主さんが呼びかけたり構ったりしようとしても全く反応なし。
完全に寝たふりをしてそのまま本当に寝てしまう事も。
ふて寝しているなと思ったら、飼い主さんはそれ以上構ったりせずそっとしておくようにしましょう。
しつこくしてしまうとストレスがたまったり、もっと機嫌が悪くなったりします。
おやつをくれると思ったのにくれなかった時や怒られた時などにふて寝をする仕草を見せる事があります。
そんな時に、飼い主さんが呼びかけたり構ったりしようとしても全く反応なし。
完全に寝たふりをしてそのまま本当に寝てしまう事も。
ふて寝しているなと思ったら、飼い主さんはそれ以上構ったりせずそっとしておくようにしましょう。
しつこくしてしまうとストレスがたまったり、もっと機嫌が悪くなったりします。
 人間にも喜怒哀楽がありますが、犬も同様に喜怒哀楽がはっきりしています。
嬉しい時は大きい目でこっちを見てくれますが、機嫌が悪い時は口角を下げて口を閉じたままで不機嫌そうにこちらを睨んできます。
明らかにムスッとした表情ですのですぐにわかるでしょう。
そんな時はスキンシップを取ってみて下さい。
すぐに機嫌が良くなって一緒に遊びだすようであれば問題ないのですが、無視したり嫌がったりするようであればまさしく機嫌が悪いという状態です。
人間にも喜怒哀楽がありますが、犬も同様に喜怒哀楽がはっきりしています。
嬉しい時は大きい目でこっちを見てくれますが、機嫌が悪い時は口角を下げて口を閉じたままで不機嫌そうにこちらを睨んできます。
明らかにムスッとした表情ですのですぐにわかるでしょう。
そんな時はスキンシップを取ってみて下さい。
すぐに機嫌が良くなって一緒に遊びだすようであれば問題ないのですが、無視したり嫌がったりするようであればまさしく機嫌が悪いという状態です。
 飼い主さんが愛犬を呼ぶといつもなら飛んできてくれるのに、ふてくされている時は無視です。
そんな時、愛犬を見てみると耳だけは動いています。
聞こえているのに無視しているのです。
あまりしつこく呼び続けると「うるさいな」といわんばかりにより遠くへ行ってしまう事もあります。
それだけイライラする事があったという事なので、ほおっておきましょう。
飼い主さんが愛犬を呼ぶといつもなら飛んできてくれるのに、ふてくされている時は無視です。
そんな時、愛犬を見てみると耳だけは動いています。
聞こえているのに無視しているのです。
あまりしつこく呼び続けると「うるさいな」といわんばかりにより遠くへ行ってしまう事もあります。
それだけイライラする事があったという事なので、ほおっておきましょう。
 犬がふてくされる原因やふてくされている時の仕草をご紹介してきますが、実際に愛犬がふてくされている事を知ってしまうと飼い主さんもどう対処すればいいのか戸惑ってしまいますよね。
そこで、ここでは、犬がふてくされている時の対処法をご紹介していきましょう。
犬がふてくされる原因やふてくされている時の仕草をご紹介してきますが、実際に愛犬がふてくされている事を知ってしまうと飼い主さんもどう対処すればいいのか戸惑ってしまいますよね。
そこで、ここでは、犬がふてくされている時の対処法をご紹介していきましょう。
 ふてくされてしまう原因には運動不足になっているという事もあると先ほどご紹介しましたね。
運動不足でストレスがたまってしまっている場合には、定期的に運動をさせてあげて下さい。
可能であれば、週に一度は公園やドッグランなので遊んであげたり走らせてあげるとストレスが発散され、睡眠の質もよくなり睡眠不足も解消されるという一石二鳥です。
ふてくされるという事も少なくなっていくでしょう。
ふてくされてしまう原因には運動不足になっているという事もあると先ほどご紹介しましたね。
運動不足でストレスがたまってしまっている場合には、定期的に運動をさせてあげて下さい。
可能であれば、週に一度は公園やドッグランなので遊んであげたり走らせてあげるとストレスが発散され、睡眠の質もよくなり睡眠不足も解消されるという一石二鳥です。
ふてくされるという事も少なくなっていくでしょう。
 犬にとって飼い主とのスキンシップは非常に重要なものです。
あまりにスキンシップが少ないと愛犬は「愛されていないのかも」と欲求不満になってストレスがたまってしまいます。
愛犬がふてくされている事が多い場合は、スキンシップ不足という事もありますので、そんな時はしっかりスキンシップをはかり愛情を与えてあげましょう。
多頭買いをしている場合は、一匹だけに偏ってしまうと他の犬が拗ねたりふてくされたりしてしまいますので、満遍なくスキンシップをはかるようにして下さいね。
犬にとって飼い主とのスキンシップは非常に重要なものです。
あまりにスキンシップが少ないと愛犬は「愛されていないのかも」と欲求不満になってストレスがたまってしまいます。
愛犬がふてくされている事が多い場合は、スキンシップ不足という事もありますので、そんな時はしっかりスキンシップをはかり愛情を与えてあげましょう。
多頭買いをしている場合は、一匹だけに偏ってしまうと他の犬が拗ねたりふてくされたりしてしまいますので、満遍なくスキンシップをはかるようにして下さいね。
 わがままが原因でふてくされているのであればしっかりしつけをする事が大切です。
ふてくされる原因でご紹介しましたが、わがままになる理由は飼い主さんとの上下関係が築かれていないからかと思われます。
最初からしつけをしっかり行い主従関係を築けているのであれば、飼い主さんから怒られても、自分の欲求が通らなくてもストレスに感じる事が少なくなり、ふてくされる事なく飼い主さんの言う事を聞くでしょう。
しつけをするという事は褒める事も入っていますので、普段から褒めてあげる事ができていればしつけも問題なくできるようになります。
わがままが原因でふてくされているのであればしっかりしつけをする事が大切です。
ふてくされる原因でご紹介しましたが、わがままになる理由は飼い主さんとの上下関係が築かれていないからかと思われます。
最初からしつけをしっかり行い主従関係を築けているのであれば、飼い主さんから怒られても、自分の欲求が通らなくてもストレスに感じる事が少なくなり、ふてくされる事なく飼い主さんの言う事を聞くでしょう。
しつけをするという事は褒める事も入っていますので、普段から褒めてあげる事ができていればしつけも問題なくできるようになります。
 構ってあげられていない事が原因でふてくされている場合は、大好きなおもちゃで遊んであげるのもいいですね。
おもちゃを使うと飼い主さん側から愛犬への一緒に遊んであげるという明確な意思表示になりますので、犬は構ってもらえているんだとわかりやすく伝わります。
ここで、ダラダラするのではなくメリハリをつける事が大切。
おもちゃを出したら遊ぶ時間、出していない時は遊ぶ時間ではないとはっきりさせておくと、愛犬も時間を意識するようになりますので、しつけをする時にも役立つでしょう。
構ってあげられていない事が原因でふてくされている場合は、大好きなおもちゃで遊んであげるのもいいですね。
おもちゃを使うと飼い主さん側から愛犬への一緒に遊んであげるという明確な意思表示になりますので、犬は構ってもらえているんだとわかりやすく伝わります。
ここで、ダラダラするのではなくメリハリをつける事が大切。
おもちゃを出したら遊ぶ時間、出していない時は遊ぶ時間ではないとはっきりさせておくと、愛犬も時間を意識するようになりますので、しつけをする時にも役立つでしょう。
 今回は犬がふれくされる原因や仕草、対処法をご紹介してきました。
こうして見てみると犬は人間の事をよく観察していますよね。
そして人間ともよく似ているなと感じました。
犬が人間の事をしっかり見てくれているのだから、人間もしっかり犬の様子を観察してあげる事が大切ではないでしょうか。
そして、ふてくされているような仕草が見られたら原因を探りストレスを軽減させてあげたり、気持ちを理解してあげる事が大切ですね。
今回は犬がふれくされる原因や仕草、対処法をご紹介してきました。
こうして見てみると犬は人間の事をよく観察していますよね。
そして人間ともよく似ているなと感じました。
犬が人間の事をしっかり見てくれているのだから、人間もしっかり犬の様子を観察してあげる事が大切ではないでしょうか。
そして、ふてくされているような仕草が見られたら原因を探りストレスを軽減させてあげたり、気持ちを理解してあげる事が大切ですね。  犬とのスキンシップの時に、ほくろみたいなものを見つけたら気になりますね。
犬は全身を毛に覆われているので、人間ほど紫外線の影響は多くないと言われますが、やはり鼻の先など毛の薄い部分にはシミやほくろができることがあります。
ほくろそのものは病気ではありませんが、皮膚がんなどの腫瘍との違いを知っておき、気になる場合は早めに診察を受けましょう。
犬とのスキンシップの時に、ほくろみたいなものを見つけたら気になりますね。
犬は全身を毛に覆われているので、人間ほど紫外線の影響は多くないと言われますが、やはり鼻の先など毛の薄い部分にはシミやほくろができることがあります。
ほくろそのものは病気ではありませんが、皮膚がんなどの腫瘍との違いを知っておき、気になる場合は早めに診察を受けましょう。
 ほくろはメラニン色素がたくさん皮膚に沈着したものです。
メラニン色素は紫外線などの刺激を受けることで多く発生することがわかっています。
わたしたちが困る肌のシミやほくろも多くの紫外線が関係しています。
そして、それは犬も同じです。
歳を取るとお腹や鼻、唇などにほくろやシミが現れやすくなります。
やはり被毛の薄い部分は紫外線の刺激をたくさん受けることが多いからです。
ほくろは色が均一で周りとの境界線がはっきりしているのが特徴です。
ほくろはメラニン色素がたくさん皮膚に沈着したものです。
メラニン色素は紫外線などの刺激を受けることで多く発生することがわかっています。
わたしたちが困る肌のシミやほくろも多くの紫外線が関係しています。
そして、それは犬も同じです。
歳を取るとお腹や鼻、唇などにほくろやシミが現れやすくなります。
やはり被毛の薄い部分は紫外線の刺激をたくさん受けることが多いからです。
ほくろは色が均一で周りとの境界線がはっきりしているのが特徴です。
 犬の皮膚腫瘍として極めて悪性度が高いのがメラノーマです。
メラノーマは悪性黒色腫と呼ばれる皮膚がんの一種で、ほくろと同じくメラニン細胞に関係しています。
進行が早く自覚症状もあまりないので、早期に発見することが難しい病気です。
ほくろと見分けることは重要になりますので、メラノーマの特徴や治療方法、ほくろとの見分け方などを知っておきましょう。
犬の皮膚腫瘍として極めて悪性度が高いのがメラノーマです。
メラノーマは悪性黒色腫と呼ばれる皮膚がんの一種で、ほくろと同じくメラニン細胞に関係しています。
進行が早く自覚症状もあまりないので、早期に発見することが難しい病気です。
ほくろと見分けることは重要になりますので、メラノーマの特徴や治療方法、ほくろとの見分け方などを知っておきましょう。
 犬の皮膚にできるメラノーマは、皮膚がんの中でもおよそ6%を占める病気です。
黒く色素沈着していてほくろと似ているのですが、ほくろが悪性メラノーマに変化するわけではありません。
また黒くないメラノーマも30%程度あります。
発生する原因は外部からの長く続く刺激と免疫の低下と言われています。
メラノーマは足先や肉球付近、口腔内に発生することが多く、肉眼で発見できる場所なのでスキンシップをいつも行うようにしましょう。
犬の皮膚にできるメラノーマは、皮膚がんの中でもおよそ6%を占める病気です。
黒く色素沈着していてほくろと似ているのですが、ほくろが悪性メラノーマに変化するわけではありません。
また黒くないメラノーマも30%程度あります。
発生する原因は外部からの長く続く刺激と免疫の低下と言われています。
メラノーマは足先や肉球付近、口腔内に発生することが多く、肉眼で発見できる場所なのでスキンシップをいつも行うようにしましょう。
 犬も人間も紫外線を長時間浴びることでのリスクがあります。
シミやほくろもその結果なのでやはりケアが必要ということですね。
またほくろとよく似たメラノーマという病気もあるため、発見した時はできるだけ診察をしてもらうことをおすすめします。
日差しの暑い時間帯の散歩を避けたり、体の免疫力を上げるように普段から心がけてあげましょう。
犬も人間も紫外線を長時間浴びることでのリスクがあります。
シミやほくろもその結果なのでやはりケアが必要ということですね。
またほくろとよく似たメラノーマという病気もあるため、発見した時はできるだけ診察をしてもらうことをおすすめします。
日差しの暑い時間帯の散歩を避けたり、体の免疫力を上げるように普段から心がけてあげましょう。