犬用(ペット用)湯たんぽの種類
 寒い冬、冷え込む夜には暖かくしてぐっすり眠りたいもの。
犬だって寒がりの子や老犬、子犬には暖かくしてあげたいですね。
そんな時、役に立つのがペット用湯たんぽです。
なんと言っても湯たんぽは安全性の高いものが一番。
安全で使いやすい商品がいろいろ出ているので、どんなところに気をつけて選べばよいのかポイントをまとめていきます。
さらに犬用湯たんぽとして人気のおすすめ商品を8点紹介しますので、愛犬にぴったりな湯たんぽを見つける参考にしてくださいね。
寒い冬、冷え込む夜には暖かくしてぐっすり眠りたいもの。
犬だって寒がりの子や老犬、子犬には暖かくしてあげたいですね。
そんな時、役に立つのがペット用湯たんぽです。
なんと言っても湯たんぽは安全性の高いものが一番。
安全で使いやすい商品がいろいろ出ているので、どんなところに気をつけて選べばよいのかポイントをまとめていきます。
さらに犬用湯たんぽとして人気のおすすめ商品を8点紹介しますので、愛犬にぴったりな湯たんぽを見つける参考にしてくださいね。
電子レンジタイプ
犬用湯たんぽとして手軽に使えるのは電子レンジタイプです。
保温材入りの本体を電子レンジで数分温めるだけで、暖かさを維持する湯たんぽに変身します。
忙しい時でも簡単なので、とても便利です。
しかし加熱しすぎて触れられないほど熱くなることがあり、火傷の可能性があります。
説明書を必ず読んでレンジにかける時間を守りましょう。
またレンジによって必要時間が少し異なる場合もあるので、まだ暖かくないと感じたら少しだけ時間を延長して様子を見ましょう。
お湯タイプ
 人間用の湯たんぽと同じで沸かしたお湯を入れて使うタイプです。
家にあるという飼い主さんもいるでしょう。
壊れにくい素材で作られているので、ワンちゃんが噛んだりしても大丈夫です。
しかし毎回お湯を沸かす必要があるため、準備が少し面倒なところが難点です。
また熱いお湯を入れる際に火傷しないようにも気をつけましょう。
ゴム製の湯たんぽは氷を入れて夏に保冷剤として使うことができるという便利なものもあります。
暑がりの子にはこちらもおすすめです。
人間用の湯たんぽと同じで沸かしたお湯を入れて使うタイプです。
家にあるという飼い主さんもいるでしょう。
壊れにくい素材で作られているので、ワンちゃんが噛んだりしても大丈夫です。
しかし毎回お湯を沸かす必要があるため、準備が少し面倒なところが難点です。
また熱いお湯を入れる際に火傷しないようにも気をつけましょう。
ゴム製の湯たんぽは氷を入れて夏に保冷剤として使うことができるという便利なものもあります。
暑がりの子にはこちらもおすすめです。
犬用(ペット用)湯たんぽの選び方
犬用湯たんぽとして様々な商品が販売されています。
どれを選んだら良いのか正直困りますよね。
ここでは湯たんぽの選び方としてチェックするポイントをサイズや素材など4つ紹介していきます。
目を通してもらって、愛犬にぴったり、かつ飼い主さんが使いやすそうな商品を選ぶ参考にしてください。
選び方①サイズ
 大型犬と小型犬ではその大きさはかなり違います。
だからペットの体型に適したサイズの湯たんぽを選ぶことは重要なポイントです。
また湯たんぽをどの場所で使うのかということも考えてみてください。
ハウスの中・ベッドの下など使う場所によってもサイズが変わってきます。
せっかく買ったのに、いざ使おうとするとサイズが小さかったでは困りますよね。
それから外出先でも使いたいという場合には、コンパクトなものが便利です。
ペットの体型と湯たんぽを使う場所、どちらも考慮して選びましょう。
大型犬と小型犬ではその大きさはかなり違います。
だからペットの体型に適したサイズの湯たんぽを選ぶことは重要なポイントです。
また湯たんぽをどの場所で使うのかということも考えてみてください。
ハウスの中・ベッドの下など使う場所によってもサイズが変わってきます。
せっかく買ったのに、いざ使おうとするとサイズが小さかったでは困りますよね。
それから外出先でも使いたいという場合には、コンパクトなものが便利です。
ペットの体型と湯たんぽを使う場所、どちらも考慮して選びましょう。
選び方②カバー付き
 犬は毛に覆われていますが、肌はとても薄く敏感です。
直接肌に湯たんぽを触れてしまうと、低温火傷などを引き起こす恐れが高いです。
必ずカバー付きの商品を選びましょう。
カバーが付いていることで汚れても洗濯ができて、いつも清潔に使えるという利点もあります。
カバーがなければ、タオルなどでくるんであげたりしても大丈夫です。
老犬に湯たんぽを使う時には、カバーが付いていても長時間同じ場所に触れていることがないようにしましょう。
こまめに温度を確かめて、暑すぎることがないように注意が必要です。
犬は毛に覆われていますが、肌はとても薄く敏感です。
直接肌に湯たんぽを触れてしまうと、低温火傷などを引き起こす恐れが高いです。
必ずカバー付きの商品を選びましょう。
カバーが付いていることで汚れても洗濯ができて、いつも清潔に使えるという利点もあります。
カバーがなければ、タオルなどでくるんであげたりしても大丈夫です。
老犬に湯たんぽを使う時には、カバーが付いていても長時間同じ場所に触れていることがないようにしましょう。
こまめに温度を確かめて、暑すぎることがないように注意が必要です。
選び方③頑丈な素材
湯たんぽの中にはお湯を入れたり、保温材を使用しています。
犬が噛んだり、また壊れたりした時に熱いお湯などがでてくると大変危険です。
湯たんぽに使用されている素材が頑丈なものかどうかをしっかりと確認しましょう。
お湯タイプの場合はプラスチック・金属・陶器製のものがおすすめです。
電子レンジタイプはレンジの加熱に耐えられる素材ですが、保温材がジェルの場合は中が出てきやすいこともあるので要注意です。
ジェルの成分は毒性は低いものですが、たくさん食べてしまうとやはり危険です。
厚いカバーを付けるようなものを選ぶようにしましょう。
選び方④保温時間
 冷え込む夜や留守番させている時に湯たんぽを使うという人は多いと思います。
使い始めの温度と7,8時間たった時の温度はもちろん違いますよね。
暖かさが持続する時間をチェックしてみることも必要です。
冷えるのが早い湯たんぽでは効率が悪くなります。
データによると電子レンジタイプのもののほうがお湯を入れるものより持続時間は長いようです。
もちろん大きさや使う環境(気温)によっても違いはあると思いますので、商品説明を確認してください。
冷え込む夜や留守番させている時に湯たんぽを使うという人は多いと思います。
使い始めの温度と7,8時間たった時の温度はもちろん違いますよね。
暖かさが持続する時間をチェックしてみることも必要です。
冷えるのが早い湯たんぽでは効率が悪くなります。
データによると電子レンジタイプのもののほうがお湯を入れるものより持続時間は長いようです。
もちろん大きさや使う環境(気温)によっても違いはあると思いますので、商品説明を確認してください。
犬用(ペット用)湯たんぽの人気おすすめ8選
 犬用湯たんぽの人気オススメ商品を8点、紹介します。
お湯を入れるタイプと電子レンジタイプそれぞれ選んでみました。
それぞれに特徴があり、使いやすさは飼い主さんによっても違うと思います。
愛犬に合うものはどれか、先程の選び方4つのポイントを参考に見比べてみてください。
犬用湯たんぽの人気オススメ商品を8点、紹介します。
お湯を入れるタイプと電子レンジタイプそれぞれ選んでみました。
それぞれに特徴があり、使いやすさは飼い主さんによっても違うと思います。
愛犬に合うものはどれか、先程の選び方4つのポイントを参考に見比べてみてください。
YEEZEN/湯たんぽ ミニ シリコン 注水式
22×9.5cmというコンパクトサイズなので特に小型犬のワンちゃんのベッドの中に入れやすく、お散歩や車の移動中でも持ち運びしやすい湯たんぽです。
素材は天然シリコンで、開け口が広くお湯を入れやすい点も特徴です。
ペット用ではないので、カバーは付いていますがお湯の温度には注意して火傷のないように気をつけましょう。
また冷水を入れることもできるので、夏の保冷剤としてもケージの中に入れるなど活躍しそうです。
お出かけに一つあると夏冬どちらでも重宝しそうですね。
TONGMO/湯たんぽ かわいいカバー付き
サイズは31×19㎝で1,8lのお湯を入れて使うタイプです。
可愛いソフトベロアのカバーが付いているのが人気です。
柔らかい本体は安全性の高い医療用PVC素材で作られており、安心して使用できます。
コンパクトサイズなのでスーツケースやキャリーバッグにも入れやすく、旅行に行く際も気軽に持っていける商品です。
ペット用の湯たんぽではないので、お湯の温度を確認したり、タオルで包むなどの工夫をする必要があります。
タンゲ化学工業/立つ湯たんぽ
 容器が自立できるので、お湯を注いだあとも本体に触れることなくカバーを掛けられたり、取っ手を持ちながら運ぶことも可能です。
お湯を捨てる時には立てた状態でキャップを外せばOKです。
使う側の安全のことを考えられた商品です。
カバー付きではないので、タオルなどでくるんで温度を確認して使うようにしましょう。
サイズは27×22×10cmで2,6lのお湯を入れて使うタイプなので、やや大きめサイズです。
ベッドの中を温めておくのに良いですね。
容器が自立できるので、お湯を注いだあとも本体に触れることなくカバーを掛けられたり、取っ手を持ちながら運ぶことも可能です。
お湯を捨てる時には立てた状態でキャップを外せばOKです。
使う側の安全のことを考えられた商品です。
カバー付きではないので、タオルなどでくるんで温度を確認して使うようにしましょう。
サイズは27×22×10cmで2,6lのお湯を入れて使うタイプなので、やや大きめサイズです。
ベッドの中を温めておくのに良いですね。
三鈴星印/犬にも使える 湯タンポミニ
ミニサイズ(容量1,5l)の湯たんぽで、価格も高くないので気軽に使用できる湯たんぽがほしいという飼い主さんにぴったりな商品です。
犬にも使えるという名前の通り人ももちろん使えますし、ミニサイズ以外にもサイズが3つあるので、中・大型犬にも使えそうです。
製品は安心して使えるSGマークが付いているので問題はありません。
お湯を入れるタイプですが、持ち手が付いていて使いやすいところと氷を入れると夏場の保冷剤としても使えることがポイントです。
尾上製作所/ミニ湯たんぽ
 直径16cmのコンパクトサイズで、持ち運びにも便利なミニ湯たんぽ。
価格も安く、お試しに使ってみるのも良いし、小さな子犬にも最適です。
お湯を入れて使うタイプで650mlのお湯が入ります。
セットで付いてくるカバーは手触りもよく可愛らしいので子犬には温かい癒やしとなるでしょう。
本体は安心の日本製、SGマークも付いています。
ペット用ではないので、お湯の温度には注意して時々様子を見るようにして使いましょう。
直径16cmのコンパクトサイズで、持ち運びにも便利なミニ湯たんぽ。
価格も安く、お試しに使ってみるのも良いし、小さな子犬にも最適です。
お湯を入れて使うタイプで650mlのお湯が入ります。
セットで付いてくるカバーは手触りもよく可愛らしいので子犬には温かい癒やしとなるでしょう。
本体は安心の日本製、SGマークも付いています。
ペット用ではないので、お湯の温度には注意して時々様子を見るようにして使いましょう。
貝沼産業/ユカホットライト
電子レンジで温めて手軽に使えるタイプです。
頑丈で、たとえワンちゃんが噛んでしまっても簡単には壊れません。
また、適温に到達したあとはそれ以上温度が上がらないので、火傷の危険性も少ないです。
噛み癖がある子や動きの少ない老犬でも安心ですね。
サイズは幅240×奥行350×高さ30mmで外出先にキャリーバッグに入れていく時も持っていきやすいでしょう。
ふわふわの触り心地の良いカバーはブラウン・ピンク・ベージュから選べます。
コスパと使いやすさの良い湯たんぽです。
プラタ/ぽかぽかあったか犬猫用湯たんぽ
 ふわふわの可愛らしいカバーが付いてくる湯たんぽです。
レンジの中でも衛生的に使えるように、専用のレンジパックもセットとして付属しているので、飼い主さんも安心して使えます。
またカバーは洗濯可能なので、いつも清潔に使えます。
カバーの内側はアルミ加工で下からの冷気を遮断できるようになっており、保温性を高めてくれます。
サイズは高さが4cm、25cmの円形なので、場所を選ばず小型犬に使いやすいサイズです。
ふわふわの可愛らしいカバーが付いてくる湯たんぽです。
レンジの中でも衛生的に使えるように、専用のレンジパックもセットとして付属しているので、飼い主さんも安心して使えます。
またカバーは洗濯可能なので、いつも清潔に使えます。
カバーの内側はアルミ加工で下からの冷気を遮断できるようになっており、保温性を高めてくれます。
サイズは高さが4cm、25cmの円形なので、場所を選ばず小型犬に使いやすいサイズです。
ドギーマンハヤシ/レンジでチンしてぽっかぽか
電子レンジで温めるタイプの湯たんぽです。
本体の保温材が頑丈なプラスチック素材で製造されており、ワンちゃんが強く噛んでも壊れない仕組みになっています。
ワンちゃんが湯たんぽの上に乗っても安定しています。
もこもこのカバーが付いていて、更にカバーの内側はアルミ層になっているので保温力も高いです。
留守番や冷える夜中でも安心して使える商品です。
サイズは幅250×奥行250×高さ40mm。
電子レンジで約5分チンすればよいので、簡単で使いやすさは抜群ですね。
まとめ
 オススメのペット用湯たんぽを紹介しましたが、いかがでしたか?
安全で、飼い主さんが使いやすい物を選ぶことがワンちゃんにも最適だと思います。
選ぶポイントを参考に湯たんぽで冷え込む冬を快適に暖かくして過ごしてくださいね。
オススメのペット用湯たんぽを紹介しましたが、いかがでしたか?
安全で、飼い主さんが使いやすい物を選ぶことがワンちゃんにも最適だと思います。
選ぶポイントを参考に湯たんぽで冷え込む冬を快適に暖かくして過ごしてくださいね。
猫用食器の種類や素材
 猫の食器を購入する際には、食べやすさと価格、見た目、手入れのしやすさが考えられます。
猫を飼っている人も増えて種類も豊富で、素材も考慮されたものが販売されています。
愛猫に合った食器で楽しく食事をしてもらうには、どんな点を注意すればいいのかを調べて見ました。
猫の食器を購入する際には、食べやすさと価格、見た目、手入れのしやすさが考えられます。
猫を飼っている人も増えて種類も豊富で、素材も考慮されたものが販売されています。
愛猫に合った食器で楽しく食事をしてもらうには、どんな点を注意すればいいのかを調べて見ました。
プラスチック製
 プラスチック製は他の素材に比べてリーズナブルで、軽くて扱いやすくとても便利な食器が多くあります。
軽いため餌を食べている最中に動いてしまう事がありますが、滑り止めが付いているものなら動く心配がなく安心して食事を楽しめます。
傷つきやすく傷の隙間に汚れが入りこんでしまい落ちにくくなってしまうため、長期間の使用やウエットフードをあげるのは避けた方が無難です。
プラスチック製は他の素材に比べてリーズナブルで、軽くて扱いやすくとても便利な食器が多くあります。
軽いため餌を食べている最中に動いてしまう事がありますが、滑り止めが付いているものなら動く心配がなく安心して食事を楽しめます。
傷つきやすく傷の隙間に汚れが入りこんでしまい落ちにくくなってしまうため、長期間の使用やウエットフードをあげるのは避けた方が無難です。
陶磁器製
 陶磁器製は、程良い重さがあるため安定感があり、傷つくにくい素材で清潔に使う事ができます。
温かいままで餌を与えたい時などには冷めにくく、電子レンジ対応のものであれば器のまま温められるのでとても便利です。
割れやすいデメリットがありますので、取り扱いには注意が必要になります。
陶磁器製は、程良い重さがあるため安定感があり、傷つくにくい素材で清潔に使う事ができます。
温かいままで餌を与えたい時などには冷めにくく、電子レンジ対応のものであれば器のまま温められるのでとても便利です。
割れやすいデメリットがありますので、取り扱いには注意が必要になります。
ステンレス製
 ステンレス製は、手が滑って落としてしまった時にも壊れる心配がなく、錆びにくく汚れが落ちやすいため毎日のお手入れが簡単です。
金属製のため冬場は冷たく、猫によって臭いを嫌がり餌を食べてくれない事もあります。
軽いため安定感があまりなく動いてしまいますので、滑り止めが付いている食器なら安心です。
ステンレス製は、手が滑って落としてしまった時にも壊れる心配がなく、錆びにくく汚れが落ちやすいため毎日のお手入れが簡単です。
金属製のため冬場は冷たく、猫によって臭いを嫌がり餌を食べてくれない事もあります。
軽いため安定感があまりなく動いてしまいますので、滑り止めが付いている食器なら安心です。
猫用食器は機能性が大事!おすすめの選び方とは?
 猫によって性格が違うように、食事の仕方にも癖やこだわりをもっています。
様々な機能性を持った食器が販売されていますので、上手に使いこなすための注意点や愛猫に合ったおすすめな商品を紹介します。
猫によって性格が違うように、食事の仕方にも癖やこだわりをもっています。
様々な機能性を持った食器が販売されていますので、上手に使いこなすための注意点や愛猫に合ったおすすめな商品を紹介します。
猫のクセに適した食器を選ぶ
 食べこぼしが多い場合には食べやすい角度が付いている「そり返し」のものや、内側にフチのある「二段構造」のものがおすすめです。
餌を食べている途中でやめる事がなくなり、飼い主の掃除の手間も省いてくれます。
早食いの場合には、食器内に凸凹が付いているものが良く、凸凹の隙間に餌が入って食べづらく自然にゆっくり食事をしてくれるようになります。
あまり時間がかかってしまうような時には、通常の食器で少しずつ与えてあげるようにします。
食べこぼしが多い場合には食べやすい角度が付いている「そり返し」のものや、内側にフチのある「二段構造」のものがおすすめです。
餌を食べている途中でやめる事がなくなり、飼い主の掃除の手間も省いてくれます。
早食いの場合には、食器内に凸凹が付いているものが良く、凸凹の隙間に餌が入って食べづらく自然にゆっくり食事をしてくれるようになります。
あまり時間がかかってしまうような時には、通常の食器で少しずつ与えてあげるようにします。
食べやすい食器を選ぶ
食器の形状やサイズが重要なポイントになり、浅すぎず深すぎないものを選ぶようにします。
深すぎてしまうと食べ残してしまう原因になり、浅い場合は食べている最中に器の外にこぼれてしまう可能性があります。
食べている様子を観察して、猫の顔が食器の底に付くぐらいのものが適しています。
吐き癖がある猫や高齢の場合は、台座付き食器か、食器の下に浅型のプラスチックケースなどを置いて高さを調節してあげると楽に食事ができます。
安定感のある食器を選ぶ
食事の最中に食器が動いてしまうと落ち着いて食べる事ができず、ストレスの原因になってしまいます。
ゆっくり食事を楽しんでもらうには、安定性が高く重みのある商品を選ぶようにします。
軽い食器を使いたい場合には、底に滑り止めが付いているものか滑り止めシートを張ってあげれば安心です。
ストレスにならない食器を選ぶ
 餌を食べている最中にヒゲが食器に触れるのを嫌がる場合は、横幅の広い楕円形のものか一回り大きなサイズのものが適しています。
食器にこだわりを持つ猫は多く、ストレスをためないようにヒゲの幅に合った食器を選んであげるようにします。
餌を食べている最中にヒゲが食器に触れるのを嫌がる場合は、横幅の広い楕円形のものか一回り大きなサイズのものが適しています。
食器にこだわりを持つ猫は多く、ストレスをためないようにヒゲの幅に合った食器を選んであげるようにします。
猫用食器の人気おすすめ9選
 愛猫に合った食器を選ぶ際には素材、機能性が重要になりますが、使い勝手や手入れのしやすさなども気になる要素のひとつです。
数種類ある中の猫用食器から人気のある物を9つ選んで、人気の秘密や特徴を詳しく紹介します。
愛猫に合った食器を選ぶ際には素材、機能性が重要になりますが、使い勝手や手入れのしやすさなども気になる要素のひとつです。
数種類ある中の猫用食器から人気のある物を9つ選んで、人気の秘密や特徴を詳しく紹介します。
ハリオ/にゃんぷれダブル PTS-NYD
耐熱容器で有名なハリオ社で作られている有田焼フードボールで、3種類ある色の中から選ぶ事ができ電子レンジ、食洗機が使えます。
食欲や年齢に合わせて使い分けがしたい時などに嬉しい機能が付いていて、シンプルな形ですが上下をひっくり返す事ができボウルに入れるフードの量が変えられます。
ボールの底には角型のくぼみが施されているため、フードが残り少なくなっても食べやすくそり返しでこぼれるのも防いでくれます。
ハリオ/にゃんぷれショートヘア PTS-NYS
猫の顔がすっぽり入る大きさの有田焼の食器で、底はとても平らで滑り止めマットも付いているため安定感があります。
滑り止めマットは食器にのせる事もでき、フタとしても使えます。
食器の底には凸凹が施されフードが皿の中で滑りにくくなっていて、熱湯、電子レンジ、食洗機が使える万能な食器です。
iikuru/フードボウル x688
 見た目がフードボウルには見えないおしゃれな食器で、レッド、ブルー、イエローの3種類から選ぶ事ができます。
今までにない形をしていてボウルに中に頭を入れた状態で食べれますので、マイペースでゆっくり食事を楽しみたい猫に向いています。
見た目がフードボウルには見えないおしゃれな食器で、レッド、ブルー、イエローの3種類から選ぶ事ができます。
今までにない形をしていてボウルに中に頭を入れた状態で食べれますので、マイペースでゆっくり食事を楽しみたい猫に向いています。
PetMate/WETNOZ ファットキャット
真ん中だけが少しだけくぼんでいますが平たい形状をしているため、食器にヒゲが当たらずストレスを軽減してくれます。
固定されていますので食べている最中に動く事がなく、落ち着いて食事が楽しめます。
マルカン/こぼれにくい陶器食器 CT-274
 シンプルな陶器製の食器で食器の縁の部分が返しになっているため、周りにフードがこぼれにくく飛び散るのを防いでくれます。
洗う際に、返しの内側を洗う手間がかかってしまうデメリットがあります。
シンプルな陶器製の食器で食器の縁の部分が返しになっているため、周りにフードがこぼれにくく飛び散るのを防いでくれます。
洗う際に、返しの内側を洗う手間がかかってしまうデメリットがあります。
AnieChorus/グルメリーフ50
葉っぱの形をした食器で高さがあまりなく、平たい形状をしているため安定感があります。
横幅が16㎝あり幅広でヒゲが当たらない構造になっていますので、猫のストレスを少なくしてくれます。
皿の中央部分に向かって傾斜があり、フードが皿の上で散らばるのを防いで食べやすくなっています。
湯切りがありふやかして食べさせたい時に便利で、電子レンジも使う事ができます。
ペティオ/necoco 脚付き陶器食器
脚付きの陶器製の食器で猫の食べ方を研究して作られていて、ヒゲや頭が皿にあたらない構造になっています。
縁の部分が2段構造になっていてこぼれにくく、ドライとウェットフード用があります。
フードが入る部分の内側に傾斜がついていますので、少なくなってもフードが中央に集まり食べやすくなります。
猫壱/ハッピーダイニング 脚付ウォーターボウル 猫柄
 セラミック素材で出来た丈夫なウォーターボウルで、ボウルの内側には飲んだ水の量がわかる便利な目盛が付いています。
猫は体に異常がある場合いつもとは違った量の水を飲む事がありますので、健康管理にも役立ってくれます。
縁の部分には返しがあり水がこぼれにくく、他の食器と比べて素材の匂いが水に移る心配がなく安心です。
セラミック素材で出来た丈夫なウォーターボウルで、ボウルの内側には飲んだ水の量がわかる便利な目盛が付いています。
猫は体に異常がある場合いつもとは違った量の水を飲む事がありますので、健康管理にも役立ってくれます。
縁の部分には返しがあり水がこぼれにくく、他の食器と比べて素材の匂いが水に移る心配がなく安心です。
猫壱/ハッピーダイニング 脚付フードボウル
脚が付いているため高さがあり首を曲げながら食べる必要がなく、のどに食べ物が詰まりにくい構造になっています。
吐き戻し効果もあり、食事をする際の負担やストレスを減らしてくれます。
食べやすい形状で1位を獲得している商品で、サイズも充実していますので愛猫に合ったものが選びやすくなります。
まとめ
 毎日食事をする際に欠かせない猫用食器は重要な役割をしていて、美味しそうに食事をする姿はとても癒しを与えてくれます。
素材や機能性が工夫された商品が多く、選ぶ際には悩んでしまいますが、愛猫の様子を観察しながら状態に合ったもの選ぶ事が大切です。
毎日食事をする際に欠かせない猫用食器は重要な役割をしていて、美味しそうに食事をする姿はとても癒しを与えてくれます。
素材や機能性が工夫された商品が多く、選ぶ際には悩んでしまいますが、愛猫の様子を観察しながら状態に合ったもの選ぶ事が大切です。
犬に唐辛子はNGの理由
 犬にとって唐辛子はNGな食べ物です。
当たり前のようですが、なぜダメなのかを知らない人も多いはず。
まず最初に、唐辛子が犬にとって、なぜ危険な食べ物なのかを解説しましょう!
犬にとって唐辛子はNGな食べ物です。
当たり前のようですが、なぜダメなのかを知らない人も多いはず。
まず最初に、唐辛子が犬にとって、なぜ危険な食べ物なのかを解説しましょう!
唐辛子の成分が危険
まず最初に、唐辛子の成分が危険というのが挙げられます。
唐辛子には「カプサイシン」という辛味成分が入っています。
これは人間にとっても摂取のしすぎは脅威で、カプサイシンを摂りすぎるとお腹を壊したり、気分が悪くなったりといった症状が現れます。
犬にとっても同様で、「カプサイシン」は犬の胃腸を刺激し、下痢や嘔吐などの症状を引き起こしてしまうのです。
炎症が起こるため
また、唐辛子などの刺激物を大量に食べてしまうと、呼吸器官や食道器官にも炎症が生じてしまうこともあります。
唐辛子は、犬にとって、直接的に内臓にダメージを与える非常に危険な食べ物です。
ワンちゃんのためにも必ず食べさせないようにしなければいけません。
どうして食べちゃうの?
 人間であれば、ひとくち食べただけで「辛い!」となって吐き出しますが、ワンちゃんは吐き出すことはありません。
どうしてワンちゃんは唐辛子を思わず食べてしまうのでしょうか?
これには犬と人間との味覚の違いが関係しています。
実は、犬は人間よりも味覚が鈍く、唐辛子を食べても辛さをあまり感じません。
そのため、思わず最後まで食べてしまうのです。
人間であれば、ひとくち食べただけで「辛い!」となって吐き出しますが、ワンちゃんは吐き出すことはありません。
どうしてワンちゃんは唐辛子を思わず食べてしまうのでしょうか?
これには犬と人間との味覚の違いが関係しています。
実は、犬は人間よりも味覚が鈍く、唐辛子を食べても辛さをあまり感じません。
そのため、思わず最後まで食べてしまうのです。
犬が唐辛子を食べた時の対処法
ここからは、犬が誤って唐辛子を食べてしまった時の対処法を解説します。
しっかりと読んでおき、万が一の事態に、適切な行動ができるようにしておきましょう!
今後食べることがないようにする
まずは、大前提ですが犬食べてしまうような場所に、唐辛子を置かないようにしましょう。
唐辛子に含まれるカプサイシンは、人間には肥満防止や食欲増進などの作用があると言われていますが、犬にとっては食べるメリットはひとつもないのです。
必ず、ワンちゃんの手の届かないところに唐辛子は保存して下さい!
また、犬が盗み食いをしていた場合は、今後一切食べることがないように、尚更注意が必要です。
様子を覗う
仮にワンちゃんが唐辛子を食べてしまっていた場合、その量が少量であればとりあえずは、そのまま様子を見ましょう。
ほんの少しの唐辛子であれば、体調も崩す大丈夫な場合があります。
ですが、万が一食べてしまっていた場合などは、なんらかの症状が見られないかなどしっかりと注意をして観察してあげて下さいね!
水分補給をさせる
また、ワンちゃんが唐辛子を食べてしまった場合、脱水症状にも注意をする必要があります。
唐辛子を食べると、下痢の原因をしてしまい、それが原因で脱水症状になってしまうことがあるからです。
脱水状態を防ぐためにも、もしワンちゃんが唐辛子を食べてしまったら、こまめに少しずつ、水分補給をするようにして下さい。
犬のしつけに唐辛子スプレーは必要?
 さて、もうひとつ気になるのが「犬のしつけ用唐辛子スプレー」です。
犬にとって唐辛子はNGなのですが、これは大丈夫なのでしょうか?そもそも効果や使用する必要はあるのでしょうか?
さて、もうひとつ気になるのが「犬のしつけ用唐辛子スプレー」です。
犬にとって唐辛子はNGなのですが、これは大丈夫なのでしょうか?そもそも効果や使用する必要はあるのでしょうか?
唐辛子スプレーの効果と必要性
しつけ用の唐辛子スプレーは、販売されているだけあって多少なりとも効果はあります。
ですが、このようなしつけ用品は唐辛子の臭いに効果を頼るものです。
日常的にそれを使うことで、犬がその臭いに慣れてしまったとしたら、しつけ用品としての効果はなくなります。
犬は唐辛子の匂いが嫌い
実際に、唐辛子の匂いは、犬からすると心身共に受けつけない刺激臭です。
それによりワンちゃんの体調が崩れてしまう可能性も考えると、唐辛子を使用したしつけ用スプレーは使う必要性はないと言えます。
たとえ少量の唐辛子スプレーでも、症状として、くしゃみが止まらない、鼻が痒いなどが出てしまうことも…。
まとめ
この記事では、犬に唐辛子がNGな理由と、唐辛子によって引き起こされる症状、しつけ用唐辛子スプレーについて解説しました。
唐辛子は犬にとっては、不必要なものです。
飼い主さんがしっかりと管理をして、ワンちゃんを守ってあげて下さいね!
猫にヨーグルトを与えても大丈夫?
愛猫に牛乳の飲ませてあげるという飼い主さんも多いのではないでしょうか?<
そんな中、ふと疑問に思うのが「ヨーグルトは猫に食べさせても大丈夫なの?」ということ。
結論から述べると、猫にヨーグルトを食べさせるのは大丈夫です。
というのも、ヨーグルトは牛乳よりも「乳糖」が少なく、下痢や中毒のリスクが低いためです。
そのような観点から見ていくと、ヨーグルトは牛乳よりも比較的安全な食べ物とも言えます。
猫にヨーグルトを与える際のメリット・栄養効果
 では、ここからは猫にヨーグルトを食べさせるメリットや、ヨーグルトに含まれる栄養などをもう少し詳しく見ていきましょう。
では、ここからは猫にヨーグルトを食べさせるメリットや、ヨーグルトに含まれる栄養などをもう少し詳しく見ていきましょう。
免疫力の上昇
腸内環境が整うと、免疫力が上がるというメリットが存在します。
ヨーグルトに含まれる乳酸菌は、腸内環境を整える力があり、その結果、ヨーグルトを食べることで猫の免疫力が上げるということです。
歯周病や口内炎の時
また、猫が歯周病や口内炎の時にも食べさせるメリットがあります。
なんと、乳酸菌は腸内環境を整え免疫力をあげるだけでなく、口腔内の細菌を減らしてくれる働きも持っているからです。
口腔内の細菌が減ることで、歯周病や口内炎の改善に繋がります。
下痢や便秘の時
意外かもしれませんが、猫が下痢や便秘の時にもヨーグルトは大活躍します。
腸内環境の悪化が原因で生じた一時的な下痢や便秘は、ヨーグルトで改善することも。
その一方で、病気などで生じた下痢や便秘の時にはヨーグルトによる改善は期待できず、むしろさらに悪化させてしまうこともあります。
上記にさえ気をつけておけば、下痢や便秘の時にヨーグルトを食べさせるのはアリだと言えるでしょう。
ヨーグルトを与えると腎不全が治る?
さて、もうひとつ耳にするメリットが「腎不全が治る」というもの。
果たしてこれは事実なのでしょうか?
ネット上のブログなどでは腎不全が治ったという報告例も見られますが、残念なことにヨーグルトが腎不全の完治に効果があるとは言えないのが現状です。
というのも、それが科学的に根拠を持った真実なのかが解明されていないからです。
むしろ、一度失った腎機能は戻らないというのが定説とされています。
猫にヨーグルトを与える時のデメリット・注意点
 猫にヨーグルトを食べさせるメリットがたくさんあるのはお分かり頂けたでしょうか?
その一方で、注意したいのがデメリットです。
ここからは、メリットと合わせて知っておきたい「猫にヨーグルトを食べさせるデメリット」を解説していきます。
猫にヨーグルトを食べさせるメリットがたくさんあるのはお分かり頂けたでしょうか?
その一方で、注意したいのがデメリットです。
ここからは、メリットと合わせて知っておきたい「猫にヨーグルトを食べさせるデメリット」を解説していきます。
下痢や嘔吐をする
最初に紹介するデメリットは、下痢や嘔吐を起こしてしまうかもしれないというものです。
ヨーグルトの与えすぎは、アレルギー反応や乳糖不耐性、体質に合わないなどで、下痢や嘔吐に繋がる場合があります。
そのため、与えすぎるのは厳禁。
猫にヨーグルトを与えるときは、体調の様子を見ながら少しずつ与えるようにしましょう。
虫歯になる
また、虫歯になってしまう可能性があるというデメリットも存在します。
虫歯になると言われている原因は、ヨーグルトに含まれる人工甘味料・砂糖。
そのため、猫にヨーグルトを与える時には、甘味料・砂糖が含まれていないヨーグルトを選ぶようにして下さい。
尿路結石になる?
また、猫にヨーグルトを与えると尿路結石になるとも言われています。
尿路結石になると言われる理由は、ヨーグルトにミネラルが含まれているためです。
しかし、小さじ1~2杯ほどの量を、週に数回食べたからといって、尿路結石になることは通常考えられません。
与えすぎないよう、量だけ考慮していれば大丈夫でしょう。
猫にヨーグルトを与える方法
 ここからは、実際に猫にヨーグルトを与えるときにどのように与えればいいのか、頻度などを紹介します。
ここまで読んで、ヨーグルトを食べさせたいなと考えている飼い主さんは、ぜひ今から紹介することを守って、食べさせてあげて下さいね!
ここからは、実際に猫にヨーグルトを与えるときにどのように与えればいいのか、頻度などを紹介します。
ここまで読んで、ヨーグルトを食べさせたいなと考えている飼い主さんは、ぜひ今から紹介することを守って、食べさせてあげて下さいね!
与える頻度
まずは、猫にヨーグルトを与える頻度です。
先ほど紹介したように、食べさせすぎることは良くありません。
猫にヨーグルトを与える頻度は、多くても3日に1回が目安となります。
ですが、猫ちゃんの体調を観察することは怠らず、様子を見ながら食べさせるようにしましょう。
また、子猫は内臓が未発達なので、成猫になってから与えるようにして下さい。
与えてもいい量
では、ヨーグルトを与えるときには、1回でどれ程の量であれば大丈夫なのでしょうか?
1回に与えても良いヨーグルトの量は、小さじ2杯が目安となります。
少ない気がしますが、猫にとってはこれが適量であり、この量も猫ちゃんの様子によって減らしたりする必要があります。
人間用はプレーン味のみ
ヨーグルトを選ぶときに注意しておきたいのが、人工甘味料・砂糖が入っているものはNGだということです。
先ほども紹介したように、ヨーグルトに含まれる人工甘味料・砂糖は猫ちゃんの虫歯の原因となってしまいます。
味つきのヨーグルトは、基本的に人工甘味料や砂糖などが使用されているため、避けましょう。
また、フルーツが入ったタイプは、アレルギーなどを起こすこともあるため、こちらも与えるのはNGです。
猫用ヨーグルトを与える
人工甘味料・砂糖が入っていないヨーグルトを自分で選ぶ自信がない方は、猫専用のヨーグルトがおすすめです。
最近では、猫のために作られたヨーグルトもあるのでこちらの方がより安心することもできます。
砂糖なしがベスト
ヨーグルトを選ぶときに合わせて注意しておきたいのが、脂肪分。
意外なことにヨーグルトは、脂肪分が多く含まています。
そのため、肥満や虫歯を避けるためにも無脂肪タイプがベストです。
まとめ
この記事では、猫がヨーグルトを食べてもだ丈夫なのか?や食べさせるメリット、注意点、などを解説しました。
ぜひ、この記事も参考にしながら、可愛い愛猫のために適切なヨーグルトライフを提供してあげて下さいね。
犬の歯磨きはなぜ必要?
犬の歯磨きがなぜ必要なのか知っていますか?
犬も人間と同様に歯磨きをしないと、歯石が溜まったり、口内で細菌が繁殖してしまいます。
そうなると、歯肉炎、やがては歯周病などへと…。
そういったことにならない為にも、ワンちゃんもしっかりとした歯磨きが必要となってくるのです。
犬が噛む!歯磨き中に噛まれる理由は?
 「歯磨きをしないといけないのは分かってるんだけど…噛まれちゃう…」という飼い主さんも多いはず。
そう、犬はそんな簡単に歯磨きをさせてはくれないんです。
では、犬が歯磨きをさせてくれない理由は何にあるのでしょうか?
「歯磨きをしないといけないのは分かってるんだけど…噛まれちゃう…」という飼い主さんも多いはず。
そう、犬はそんな簡単に歯磨きをさせてはくれないんです。
では、犬が歯磨きをさせてくれない理由は何にあるのでしょうか?
口内トラブル
犬が歯磨きをさせてくれない理由のひとつに「口内トラブル」が挙げられます。
例えば、歯磨きの頻度が少なかったりすると、すでに歯周病などになってしまっていることも…。
こういった時や、口の中を怪我している時には、患部を触られることを嫌がり、思わず飼い主さんの手を噛んでしまいます。
ストレス
また、犬にとって口の周りを触られることに強い抵抗があることも忘れてはいけません。
ワンちゃんにとって、口とは人間が思っている以上に触られたくない場所なのです。
そのため、口内に異物(歯ブラシなど)を入れられる歯磨きはストレスとなり、耐えきれずに噛んでしまうということがあります。”
犬が歯磨きを嫌がる!おすすめの手順は?
 犬が歯磨きを嫌がる理由はお分かり頂けたでしょうか?
それでも、飼い主である以上、愛犬の歯磨きは避けては通れない道。
ここからは「でも、どうしたらいいの?」という飼い主さんのために、まずは歯磨きを始める手順を紹介します。
犬が歯磨きを嫌がる理由はお分かり頂けたでしょうか?
それでも、飼い主である以上、愛犬の歯磨きは避けては通れない道。
ここからは「でも、どうしたらいいの?」という飼い主さんのために、まずは歯磨きを始める手順を紹介します。
歯磨きの頻度
まず最初に、歯磨きがどうしてもできないという場合は、最初から毎日する必要はありません。
犬の歯垢は3~5日経つと歯石に変化します。
そのため、少なくとも3日に1度は歯磨きをする必要がありますが、最初はこれをクリアしていればオッケー程度に考えておきましょう。
最初から素直に歯磨きをさせてくれる犬は滅多におらず、繰り返し歯磨きをすることでワンちゃんも次第に慣れていき、おとなしく歯磨きをさせてくれるようになるのです。
最初は口の周辺から触る
では、ここからは実際の歯磨きまでの手順です。
歯磨きをしたくても、いきなりワンちゃんの顔を押さえて始めてはいけません。
当然、ワンちゃんもびっくりしてしまいます!
最初は顔や口の周辺から触り、ワンちゃんを慣れさせることが大切。
慣れてきたなと感じたら、次は前歯、犬歯から奥歯というように徐々に触り、歯磨きではなく、「歯を触られること」をまず犬に慣れさせましょう。
ガーゼを使って犬の歯磨きをする
ワンちゃんが歯を触られることに慣れてきたら、次はガーゼを使いましょう。
ガーゼも順序通りの部位から触れ、今度は「歯をガーゼで擦ること」に慣れさせる必要があります。
これができないと、より異物感の強い歯ブラシを使っての歯磨きはできません。
歯ブラシを使って犬の歯磨きをする
ここからは、実際に歯ブラシに慣れさせていきます。
歯ブラシを使うときは、まず、歯ブラシの匂いを嗅がせたり、見せたりして、歯ブラシという存在を教えてあげましょう。
歯ブラシという存在に慣れてきたのであれば、その後は指やガーゼと同じ様に、前歯から少しずつ「歯ブラシで触られること」に慣れさせていきます。
これを繰り返していれば、次第にワンちゃんも歯磨きに抵抗をなくしていきます。
犬が歯磨きを嫌がる!できないを解決するコツは?
 それでもまだ「歯磨きを嫌がる、させてくれない!」という場合もあるかと思います。
そんな飼い主さんに、ここからは、歯磨きを嫌がる犬に歯磨きをするコツを5つ紹介します!
「どうしても歯磨きができない」という飼い主さんは必読ですよ!
それでもまだ「歯磨きを嫌がる、させてくれない!」という場合もあるかと思います。
そんな飼い主さんに、ここからは、歯磨きを嫌がる犬に歯磨きをするコツを5つ紹介します!
「どうしても歯磨きができない」という飼い主さんは必読ですよ!
長時間はしない
最初にコツと合わせて注意点を紹介します。
それは「長時間歯磨きをしないこと」です。
特に最初の方はワンちゃんも歯磨きを良いものとは思っていません。
そんな中、無理矢理長時間の歯磨きをすると、ワンちゃんの歯磨き嫌いはますますひどくなってしまいます。
そうなると、2回目、3回目はなおのこと難しいです…。
まずは、歯磨きは嫌なものではないということをワンちゃんに教えること。
これがワンちゃんの歯磨きを成功させる最初のコツとなります。
練習は早い時期に
これはワンちゃんを飼いだして間もない飼い主さんへ、将来気持ちよく歯磨きをするためのコツです。
犬は1歳以上になると、歯磨きに慣れさせることが困難になります。
そのため、ワンちゃんを家に迎えたばかりだという場合は、根気よく、子犬の内から歯磨きの練習をすることが大切になってきます。
2人がかりで犬の歯を磨く
次のコツは「無理して1人で歯磨きをしない」ということです。
無理に1人で行おうとすれば、意図せず犬を傷つけたりしてしまうことも考えられます。
そうなれば、「歯磨き=嫌なこと」と記憶してしまい、今後も歯磨きをすることは難しくなります。
1人で出来ないときは、2人がかりで歯磨きを行うのも手です。
そうすることで、ワンちゃんに「気持ちよい歯磨き」をすることができるかもしれません。
ご褒美と歯磨きをセットにする
次のコツは「ご褒美を与える」ということ。
歯磨きを何度やっても成功しない時には、ワンちゃんに「歯磨きを頑張ったご褒美」を与えてあげましょう!
ご褒美におやつなどを与えることで「歯磨きをする=良いことがある」と記憶させれば、おとなしく歯磨きをさせてくれる可能性がアップします。
どうしても嫌がる場合は動物病院へ
最後に紹介するのは、「一度病院に行ってみる」です。
強く歯磨きを拒む場合、既に何かしらの病気が進行していることも考えられます。
何をしてもダメだという時には、ワンちゃんを病院に連れて行き、一度診てもらうというのも飼い主としての役目となります。
犬が歯磨きを嫌がる時の便利グッズ
ここからは、ワンちゃんの歯磨きを簡単にできる「犬用歯磨きグッズ」を紹介します。
「歯磨きが苦手だな〜」と感じている飼い主さんは、是非一度使ってみて下さいね!
歯磨きガム
 歯磨きアイテムの中で最もメジャーなのが、犬用歯磨きガムです。
これは、ワンちゃんがおやつと思って、ガムを食べているだけで、歯磨きができる優れもの。
飼い主さんにとって、時間も労力もかからないが嬉しいポイントです。
ワンちゃんに歯磨きガムを与えるときは、犬の口幅より、少しだけ長めの物を選んで、噛ませてあげて下さい。
歯磨きアイテムの中で最もメジャーなのが、犬用歯磨きガムです。
これは、ワンちゃんがおやつと思って、ガムを食べているだけで、歯磨きができる優れもの。
飼い主さんにとって、時間も労力もかからないが嬉しいポイントです。
ワンちゃんに歯磨きガムを与えるときは、犬の口幅より、少しだけ長めの物を選んで、噛ませてあげて下さい。
スポンジブラシ
次に紹介するのは「スポンジブラシ」。
固い歯ブラシよりも柔らかいスポンジブラシを好むワンちゃんも多くいます。
歯ブラシになると急に嫌がる!というような子にはぜひ一度試してみて下さいね!
また、歯磨きの練習でガーゼの段階で嫌がるという場合にも、スポンジブラシを用いた歯磨き練習は効果的です。
歯磨き可能な犬のおもちゃ
 また、犬用おもちゃの中にも、歯のケアをすることができるものがあります。
歯磨きの頻度やレベルに心配があるという飼い主さんは、歯磨きガム同様に、こういった歯のケアをできるおもちゃを持つのもおすすめ。
ワンちゃんの噛む力や体格、犬種などに合わせて、おもちゃを選んであげて下さいね!
また、犬用おもちゃの中にも、歯のケアをすることができるものがあります。
歯磨きの頻度やレベルに心配があるという飼い主さんは、歯磨きガム同様に、こういった歯のケアをできるおもちゃを持つのもおすすめ。
ワンちゃんの噛む力や体格、犬種などに合わせて、おもちゃを選んであげて下さいね!
まとめ
この記事では、愛犬が歯磨きを嫌がる理由や対処法、歯磨きの仕方などを解説しました。
ワンちゃんの歯磨きは大変ですが、絶対にしないといけないことでもあります。
ぜひ、この記事も参考にしながら、可愛い愛犬の歯磨きをしてあげて下さいね!
犬用知育玩具の人気おすすめ9選
 犬用の知育玩具を購入することで愛犬を躾けることができたり、遊び道具としてももちろん使用することもできます。
次に、おすすめの犬用の知育玩具9選を紹介します。
そのため、愛犬のための玩具を購入したい人は参考にしてください。
犬用の知育玩具を購入することで愛犬を躾けることができたり、遊び道具としてももちろん使用することもできます。
次に、おすすめの犬用の知育玩具9選を紹介します。
そのため、愛犬のための玩具を購入したい人は参考にしてください。
ドギーマン/みえる!IQステップボール
 ワンちゃんが遊びやすいボールの形状に仕上げられている知育玩具です。
そのため、多くのワンちゃんの食いつきがよく、購入してあげることで高確率で遊んでくれます。
購入したにも関わらず、遊んでくれないことは飼い主にとっては悲しいですよね。
しかし、そのような心配がないため、初めて犬用の知育玩具を購入しようと考えている人は購入を検討してくださいね。
また、中に餌を入れることができ、透明に仕上げられていることで餌があることを認識させることができ、転がせば餌が出ることをわかりやすいです。
ワンちゃんが遊びやすいボールの形状に仕上げられている知育玩具です。
そのため、多くのワンちゃんの食いつきがよく、購入してあげることで高確率で遊んでくれます。
購入したにも関わらず、遊んでくれないことは飼い主にとっては悲しいですよね。
しかし、そのような心配がないため、初めて犬用の知育玩具を購入しようと考えている人は購入を検討してくださいね。
また、中に餌を入れることができ、透明に仕上げられていることで餌があることを認識させることができ、転がせば餌が出ることをわかりやすいです。
Petneces/ノーズワーク
ワンちゃんの嗅覚をより磨くことができる知育玩具であり、遊びながら餌を探すことができます。
使い方はいたって簡単であり、さまざまな場所に餌を隠せれる場所が存在しており、そこにワンちゃんが好きな餌やおやつを隠すだけです。
あとはにおいを頼りにワンちゃんが見事餌までたどり着けるかを試す知育玩具です。
ワンちゃんにとっては好きなおやつを食べることができ、飼い主にとっては餌を探している可愛らしい姿を見ることができ、両者にとって幸せな時間が訪れますよ。
WeinaBingo/犬用 玩具ボール
 普通のボールではなく、耐久性に優れている素材で作られていることで長い間愛用することができ、噛みついても割れたり、壊れてしまう心配がいりません。
そのため、噛み癖があるワンちゃんや活発なワンちゃんにおすすめの知育玩具ですよ。
投げて遊ぶだけではなく、音が鳴る仕組みに仕上げられていることで知育玩具に警戒心が強いワンちゃんにも興味を持ってもらうことができます。
軽量化もされていることで子犬の知育玩具としても使用することができ、安全性も保障されています。
普通のボールではなく、耐久性に優れている素材で作られていることで長い間愛用することができ、噛みついても割れたり、壊れてしまう心配がいりません。
そのため、噛み癖があるワンちゃんや活発なワンちゃんにおすすめの知育玩具ですよ。
投げて遊ぶだけではなく、音が鳴る仕組みに仕上げられていることで知育玩具に警戒心が強いワンちゃんにも興味を持ってもらうことができます。
軽量化もされていることで子犬の知育玩具としても使用することができ、安全性も保障されています。
Ninonly/音が鳴る ぬいぐるみ10点セット
 音が出るぬいぐるみであるため、噛むことで楽しく遊ぶことができ、噛み癖があるワンちゃんにおすすめです。
また、さまざまな形のぬいぐるみが10個セットで販売されていることでワンちゃんが興味を抱くぬいぐるみが高い確率で含まれています。
どれも可愛らしいデザインに仕上げられていることで可愛らしい知育玩具を購入したい人におすすめですね。
また、知育玩具だけではなく、普通のぬいぐるみとしても十分飾ることができるポテンシャルになっています。
音が出るぬいぐるみであるため、噛むことで楽しく遊ぶことができ、噛み癖があるワンちゃんにおすすめです。
また、さまざまな形のぬいぐるみが10個セットで販売されていることでワンちゃんが興味を抱くぬいぐるみが高い確率で含まれています。
どれも可愛らしいデザインに仕上げられていることで可愛らしい知育玩具を購入したい人におすすめですね。
また、知育玩具だけではなく、普通のぬいぐるみとしても十分飾ることができるポテンシャルになっています。
のぞみ通貨/フィットネスリング
輪っかの形状に仕上げられている知育玩具であり、弾力性に優れているEVA素材が使用されています。
そのため、激しく噛んでも切れてしまうことがなく、長く愛用しつづけることも可能ですよ。
投げて使用することもでき、フリスピーの玩具としても活用することも可能でさまざまな遊び方で使用することができます。
軽く仕上げられていることと素材の特性上、水にも浮く性質があり、陸上だけではなく、海やプールなどでも浮かばせて遊ばせれることも可能ですよ。
ベネボーン/噛むおもちゃ ミニ チキン味
 骨の形状に作られている知育玩具であり、本当にチキンの風味がするように仕上がっています。
そのため、ワンちゃんの食いつきが非常によく、高い確率で遊んでくれますよ。
また、香料や着色剤は一切使用されていないため、噛んでも有害の成分が染み出てしまう心配もありません。
また、飲み込みにくいY字のデザインに仕上げていることで誤って飲み込んでしまうことも防ぎます。
噛みつきやすいようなカーブがデザインされていることでワンちゃんにとってはストレスが溜まりませんね。
骨の形状に作られている知育玩具であり、本当にチキンの風味がするように仕上がっています。
そのため、ワンちゃんの食いつきが非常によく、高い確率で遊んでくれますよ。
また、香料や着色剤は一切使用されていないため、噛んでも有害の成分が染み出てしまう心配もありません。
また、飲み込みにくいY字のデザインに仕上げていることで誤って飲み込んでしまうことも防ぎます。
噛みつきやすいようなカーブがデザインされていることでワンちゃんにとってはストレスが溜まりませんね。
ドギーマン/カムガムアミーバー ダンベル
全体が格子状に作られていることで中におやつを入れることで遊ぶせることができます。
おやつが直接見えるため、食いつきが非常によくなります。
天然ゴムが素材に使用されていることで健康を害してしまう心配がなく安心して使用することができますよ。
また、柔らかい素材でもあるため、顎や歯を痛めてしまう心配もありません。
無数の棘が取り付けられていることでデンタルケアアイテムとしても使用することができます。
噛みつきやすいデザインであることで、ボール遊びが苦手なワンちゃんでも遊びやすくなっていますよ。
ドギーマン/毎日ハミガキコットン ループ Sサイズ
 コットン糸が強く編み込まれて作られた知育玩具であり、噛んで良し。
引っ張って良しとさまざまな使用方法で遊ばせることができます。
一人遊び用の知育玩具としてだけではなく、飼い主と引っ張り合いを楽しむことででき、ワンちゃんとのコミュニケーションをとることも可能ですよ。
そのため、一緒にワンちゃんと遊びたい人におすすめの知育玩具です。
網目に歯がしっかり入り込みやすく仕上がっていることで遊び道具だけではなく、デンタルケアアイテムとしても使用することができます。
コットン糸が強く編み込まれて作られた知育玩具であり、噛んで良し。
引っ張って良しとさまざまな使用方法で遊ばせることができます。
一人遊び用の知育玩具としてだけではなく、飼い主と引っ張り合いを楽しむことででき、ワンちゃんとのコミュニケーションをとることも可能ですよ。
そのため、一緒にワンちゃんと遊びたい人におすすめの知育玩具です。
網目に歯がしっかり入り込みやすく仕上がっていることで遊び道具だけではなく、デンタルケアアイテムとしても使用することができます。
ペットステージ/ウッディー・タフ・スティック
ワンちゃんは自然の木の匂いが好きと言われています。
そのため、庭や公園などで散歩をするとどこからともなく木の枝を拾ってくることはそういう理由が関係しているんですよ。
天然の木を一度チップ上にし、再び固めた知育玩具であり、本物の木の匂いを発します。
突起物などが存在しないため、口内を傷つけてしまう心配がなく、安心して使うことができます。
ワンちゃんの大きさに合うようにさまざまなサイズ別に販売されていることで適したサイズを購入するようにしましょう。
犬用知育玩具の効果とは?
 犬用の知育玩具を使用することでどのような効果が期待できるのか知らない人も多くいるのではないでしょうか。
次に、知育玩具で遊ばせることで得られる効果について紹介します。
ワンちゃんに知育玩具を与えようと考えている人は参考にしてください。
犬用の知育玩具を使用することでどのような効果が期待できるのか知らない人も多くいるのではないでしょうか。
次に、知育玩具で遊ばせることで得られる効果について紹介します。
ワンちゃんに知育玩具を与えようと考えている人は参考にしてください。
留守番中でも楽しい
大好きなワンちゃんといつも一緒にいることができない場合が多く、仕事や買い物などで留守番をさせることも多いです。
そのような場合はワンちゃんが遊び相手がいなくなるため、寂しい思いをしてしまいます。
しかし、知育玩具を与えれ上げれば一人でも楽しく遊ぶことができ、ストレス発散やさみしさ軽減の効果が得られます。
そのため、寂しがり屋なワンちゃんや甘えん坊な性格のワンちゃんにはおすすめです。
知育玩具で遊ぶことに集中させることで悪戯を軽減することも期待できますよ。
運動不足の解消になる
 人でも同じことが言えますが、ある程度体を動かさなければ運動不足になってしまい、肥満体質になりやすく、病気を誘発してしまうリスクも高まります。
散歩をすれば運動不足を解消することはできますが、天気や飼い主の都合上どうしても散歩をすることができない場合もあるのではないでしょうか。
そのような時に知育玩具を与えて遊ばせることで体を動かすことができ、軽い運動をすることが可能になります。
運動不足気味のワンちゃんにはおすすめのグッズであり、健康的な体に近づけることも期待できますよ。
人でも同じことが言えますが、ある程度体を動かさなければ運動不足になってしまい、肥満体質になりやすく、病気を誘発してしまうリスクも高まります。
散歩をすれば運動不足を解消することはできますが、天気や飼い主の都合上どうしても散歩をすることができない場合もあるのではないでしょうか。
そのような時に知育玩具を与えて遊ばせることで体を動かすことができ、軽い運動をすることが可能になります。
運動不足気味のワンちゃんにはおすすめのグッズであり、健康的な体に近づけることも期待できますよ。
ストレス解消に役立つ
普段おとなしいワンちゃんでも本能で活発に行動したいという衝動が少なからずあり、そのような感情を発散させる機会がなければどうしてもストレスをためてしまいがちです。
ストレスが溜まってしまうとワンちゃんだけではなく、飼い主にとっても良い状況とは言えません。
知育玩具にはストレス発散の効果も期待でき、噛んだり、引っ張ったりと本能で行動することができます。
ストレスが発散できないと家具などに噛みついたりしてしまうため、知育玩具でストレスを発散させることは家具など家を守ることにもつながります。
フードでのんびり退屈しのぎ
 知育玩具でフード与えられたワンちゃんは留守番でも退屈しにくく、昼寝などをしてのんびり過ごすことも可能になります。
ワンちゃんの中には家族の行動を敏感に読み取る習慣がある場合もあり、飼い主などが忙しく行動しているとワンちゃんも早く食べようとしたり、あえて食べ残して興味を抱かせようと行動することもあります。
このような状況が長期間続いてしまうと健康を損ねてしまう原因になったり、ストレスが溜まってしまいます。
知育玩具でフードを与えることで飼い主もゆっくり準備をすることもでき、ワンちゃんも安心して食事をすることが可能になります。
知育玩具でフード与えられたワンちゃんは留守番でも退屈しにくく、昼寝などをしてのんびり過ごすことも可能になります。
ワンちゃんの中には家族の行動を敏感に読み取る習慣がある場合もあり、飼い主などが忙しく行動しているとワンちゃんも早く食べようとしたり、あえて食べ残して興味を抱かせようと行動することもあります。
このような状況が長期間続いてしまうと健康を損ねてしまう原因になったり、ストレスが溜まってしまいます。
知育玩具でフードを与えることで飼い主もゆっくり準備をすることもでき、ワンちゃんも安心して食事をすることが可能になります。
犬用知育玩具の選び方
犬用の知育玩具はさまざまな種類が販売されており、形状や用途も多種多様です。
そのため、購入する際に用途に合った知育玩具を購入する必要が出てきますね。
次に、知育玩具の選び方を詳しく紹介するため、購入を検討している人は参考にしてくださいね。
目的から選ぶ
 知育玩具は考える力を育てる目的や暇つぶし用などさまざまな用途別に販売されています。
そのため、知育玩具を購入するのであればどのような目的で知育玩具を購入するのかを明確に決めておくことをおすすめします。
普段のワンちゃんの行動をよく観察して暇そうにしている時間が長かったり、あまり遊んであげることができないのであれば暇つぶし用の知育玩具がおすすめですよ。
きちんと躾をしたかったり、芸を覚えさせたいのであれば頭を使うような知育玩具を購入しましょう。
知育玩具は考える力を育てる目的や暇つぶし用などさまざまな用途別に販売されています。
そのため、知育玩具を購入するのであればどのような目的で知育玩具を購入するのかを明確に決めておくことをおすすめします。
普段のワンちゃんの行動をよく観察して暇そうにしている時間が長かったり、あまり遊んであげることができないのであれば暇つぶし用の知育玩具がおすすめですよ。
きちんと躾をしたかったり、芸を覚えさせたいのであれば頭を使うような知育玩具を購入しましょう。
難易度から選ぶ
知育玩具によっては難易度が高い種類も販売されており、いきなり難易度が高いと遊ぶことを断念してしまう可能性が高いです。
そのため、初めて知育玩具を購入するのであれば難易度が低めの知育玩具を購入することをおすすめします。
難易度が低い知育玩具で遊ぶことに慣れてきたり、飽きてしまったら少し難易度が高い知育玩具を購入し、徐々に難易度を上げていくようにしましょう。
特に、考える力を身につけるように販売されている知育玩具が難易度別に販売されています。
おもちゃの大きさから選ぶ
 知育玩具といってもさまざまな大きさに作られており、適した大きさの知育玩具を購入するようにしましょう。
小さすぎると飲み込んでしまう危険性があるため、ワンちゃんの大きさを考慮して安全性を確保できる大きさの知育玩具がおすすめですよ。
しかし、大きすぎる知育玩具では遊びづらさが目立ってしまい、遊んでくれなくなる可能性があります。
基本的に大型犬の場合は大きめで小型犬の場合は小さめの知育玩具を購入するようにすれば問題ありませんよ。
知育玩具といってもさまざまな大きさに作られており、適した大きさの知育玩具を購入するようにしましょう。
小さすぎると飲み込んでしまう危険性があるため、ワンちゃんの大きさを考慮して安全性を確保できる大きさの知育玩具がおすすめですよ。
しかし、大きすぎる知育玩具では遊びづらさが目立ってしまい、遊んでくれなくなる可能性があります。
基本的に大型犬の場合は大きめで小型犬の場合は小さめの知育玩具を購入するようにすれば問題ありませんよ。
できる遊びから選ぶ
知育玩具の中には中におやつを入れるタイプが多く販売されていますが、パズルやボールなどの種類も販売されており、購入する際に悩んでしまいがちです。
ワンちゃんができる遊びの知育玩具から購入することが大切であり、パズルなどは比較的難易度が高いため、ボールの中におやつを入れることができるタイプの物から選びましょう。
知育玩具の遊び方を覚えることでさまざまな種類に知育玩具でも遊ぶことができるようになり、ワンちゃんもさまざまな方法で楽しむことが可能になりますよ。
愛犬の好みから選ぶ
ワンちゃんであればすべての知育玩具で遊んでくれるとは限りませんね。
そのため、知育玩具を購入する際には愛犬が遊ぶことが好きな種類の知育玩具を購入するようにしましょう。
特に、知育目的の場合は好みが違うと全く遊んでくれないため、無駄な買い物になってしまいやすいです。
そのような状況にならないためにもわんちゃんが普段どのようなおもちゃで遊んでいるのかを観察し、似たタイプの知育玩具を選ぶようにしましょう。
知育目的用は複雑な構造になっている場合も多く、遊んでくれないリスクも高まることを覚えておきましょうね。
頑丈なものを選ぶ
ワンちゃんは知育玩具で遊ぶ際に力を込めて噛んだり、引っ張ったりするため、頑丈な作りになっている物を選ぶようにしましょう。
頑丈ではない知育玩具では遊んでいる最中に壊れてしまい、知育玩具としての機能を発揮することができなくなります。
また、壊れた際にワンちゃんの歯や口の中を傷つけてしまう可能性も高いです。
プラスチックなど素材が硬い物であれば壊れやすく、怪我をさせてしまうリスクも高いため、弾力性のある素材で作られている知育玩具がおすすめですよ。
まとめ
 犬用の知育玩具がさまざまな種類が販売されており、目的も異なるため、正しい選び方の元購入することが大切です。
知育玩具を与えることでワンちゃんの健康を維持することにもつながるため、留守にさせてしまう機会が多いのであれば購入することをおすすめします。
犬用の知育玩具がさまざまな種類が販売されており、目的も異なるため、正しい選び方の元購入することが大切です。
知育玩具を与えることでワンちゃんの健康を維持することにもつながるため、留守にさせてしまう機会が多いのであれば購入することをおすすめします。
猫の目やにの原因は?
いつも通りに愛猫を見ているとふと気になることが…!
「あれ?こんなに目やに出てたっけ?病気?」
一度そう思ってしまうと、気になって仕方がないものです。猫も人間同様に目やにが出ますが、その原因はなんなのでしょうか?
生理現象によるもの
猫も生理現象として、日常的に目やにを出しています。
これは、目に入ったホコリなどの老廃物を出すための自然現象です。
少量の目やにが、日常的にで続けている場合は、自然現象での目やになので、そんなに心配する必要はありません。
病気のサインかも…?
ですが、あまりにも目やにの量が多いと、飼い主としては「何か病気かな?」と不安になるもの。
実際に、猫の「目やに」は、隠れた病気のサインとなるものがあります。
もし、いつもの目やにとの違いを感じたり、目やにの異常を感じたら、動物病院に相談する、獣医師さんに診てもらうなどの対処をしましょう。
猫の目やにの色や症状は病気のサイン?
 では、実際にどのような「目やに」であれば病気のサインを疑わなくてはいけないのでしょうか?
ここからは「目やにの色」「猫ちゃんの症状」から、病気のサインである可能性があるもの見ていきましょう。
では、実際にどのような「目やに」であれば病気のサインを疑わなくてはいけないのでしょうか?
ここからは「目やにの色」「猫ちゃんの症状」から、病気のサインである可能性があるもの見ていきましょう。
黄色の目やに
まずは目やにの色が「黄色」である場合。
黄色の目やにが出ていて、ウインクするように片目を閉じていたり、痛そうにしている場合は、目を怪我している可能性があります。
外傷が見当たらなくても、眼球に傷がついている場合などがあるので放置は禁物です。
本来であれば、目薬だけで治っていたはずなのに、放置してしまったばかりに手術をしなくてはいけなくなった…なんてケースも。
怪我の可能性を感じたら、すぐに病院に行きましょう!
緑色の目やに
では、目やにが「緑色」だったときはどうでしょう?
目やにが緑色である場合は、主に細菌感染が疑われます。
結膜炎など、目のみに感染を起こしている場合もあれば、ヘルペスやクラミジアといった猫風邪の症状のひとつとして起こっている場合も。
こちらも放置をしてしまうと、猫ちゃんが目を擦ってしまい二次的に怪我に繋がる場合があるので早めに病院で診てもらいましょう。
赤茶色や茶色の目やに
目やにの色が「茶色」「赤茶色」の場合は自然現象の目やにと考えられます。
通常の目やにであれば、目の縁や目頭に少量だけ付着する様子が見受けられます。
ですが、もし目やにの量が異常に出ていたり、ドロドロとした目やにの場合は何か猫ちゃんにあったのかもしれません。
不安な場合は、一度動物病院に連れて行くことをお勧めします。
片目だけ白い目やに
次に、目やにの症状(目やにの出かた)も一緒に見ていきましょう。
「白い目やに」が片目だけ出ている場合。
このようなときは、黄色い目やにが出ているときと同様に、外傷による目やにが疑われます。
また、クラミジア感染によって、片目から炎症が進行している場合も…。
急いで動物病院で診察してもらうことをお勧めします。
涙のような目やに
次に、目やにの症状が「涙のように出ている」場合です。
このようなときは、なんらかのアレルギーである可能性が高いです。
多いのは、ハウスダストなどのアレルギー。
アレルギー反応のひとつとして目やにが出ている場合は、同時に顔や身体を痒がったり、くしゃみをする場合があります。
ドロドロした目やに
「ドロドロしたような目やに」が出ている場合は、何らかの感染症などが疑われます。
普通の目やには湿っていますが、決してドロドロというような状態ではありません。
もし、少しでもドロドロを感じたり、いつもと違うなと違和感を覚えたら、大事をとって動物病院に行くのもいいでしょう。
猫の目やにの取り方
 ここからは、猫の目やにの取り方を紹介します。
目元を触られるのを嫌がる猫も多いですが、目やにを放置していると、猫も痒がり、二次的に皮膚などを傷つけてしまうこともあります。
猫は自分ではめやにを取ることができないので、飼い主であるなたがしっかりと取ってあげましょう!
ここからは、猫の目やにの取り方を紹介します。
目元を触られるのを嫌がる猫も多いですが、目やにを放置していると、猫も痒がり、二次的に皮膚などを傷つけてしまうこともあります。
猫は自分ではめやにを取ることができないので、飼い主であるなたがしっかりと取ってあげましょう!
ガーゼやノンアルコールのウェットティッシュを使う
猫の目やにを取ってあげる場合は、なるべく柔らかい、湿ったもので拭き取ってあげましょう。
目やには時間が経つと乾燥し、固くなってしまいます。
ティッシュペーパーなどは紙も硬く、それで固まった目やにを無理に取ろうとすると猫の目や皮膚を傷つけてしまう可能性があります。
おすすめなのは、ちゃんとした犬・猫用のウェットティッシュ。
湿っているため、目やにがふやけ、取れやすくなります。
もし人間用のウェットティッシュを使う場合などは、ノンアルコールであるものを使うといった配慮も大切です。
また、湿らせたガーゼなどもおすすめです。
力を入れず撫でるように拭く
目やにを拭き取ってあげるときは「力を入れず、撫でるように」拭き取ってあげましょう。
間違って猫の目に指が入ってしまわないように、猫の頭を固定し、目元から鼻の方の向かって撫でるように拭き取るというのが基本です。
また、1回で全ての目やにが取れない場合は、優しく、数回に分けてを繰り返しましょう。
猫をリラックスさせる
 また、目やにをとる時は、猫をリラックスさせた状態にすることも大切です。
突然目の付近を触ると猫ちゃんもびっくりしてしまいます!
そうなると、当然猫ちゃんも大人しく目やにを拭き取らせてはくれません。
最初は、体や顔まわりを撫でながら、猫ちゃんがリラックスしてきたなと感じたら、撫でる動作のようにスムーズに拭き取ってあげましょう。
また、目やにをとる時は、猫をリラックスさせた状態にすることも大切です。
突然目の付近を触ると猫ちゃんもびっくりしてしまいます!
そうなると、当然猫ちゃんも大人しく目やにを拭き取らせてはくれません。
最初は、体や顔まわりを撫でながら、猫ちゃんがリラックスしてきたなと感じたら、撫でる動作のようにスムーズに拭き取ってあげましょう。
取りづらい目やにはどうする?
もし一度で拭き取れない目やにがあった場合は、濡れたガーゼなどでふやかさなければいけません。
目やには時間が経つと固まって拭き取りにくくなってしまいます。
無理に拭き取ろうとすると、目の周りの毛が抜けてしまったり、誤って猫ちゃんの目を傷つけてしまうことも考えられるので注意して下さいね!
まとめ
この記事では、猫の「目やに」について色や症状から分かる病気のサインや対処法などを解説しました。
目やにも猫ちゃんの具合を確認するための大事な指標です。
ぜひ、この記事も参考にしながら、猫ちゃんの体調を気遣ってあげて下さいね!
猫の多頭飼いで失敗しない方法や注意点
猫を見ていると、ほんとに癒されますよね!
飼い主の言うことを聞かずに、マイペースに自由気ままに生活している姿が、少し憎かったり、でもそれ以上に可愛かったりと…。
そんな猫ちゃんにもっと囲まれて生活したいと言う思いや、今いる猫の遊び相手にと多頭飼いを考えている飼い主さんも多いのではないでしょうか?
でも、猫の多頭飼いは簡単なものではありません。
とりあえず始めたけど、失敗した…なんてことも少なくないのです。
猫の多頭飼いを始める前に、まずは失敗しない方法や注意点を見ていきましょう!
先住猫が新入り猫に寛容か見極める
 まずは、先住猫(今すでに家にいる猫)が新入りの猫に寛容かを見極めましょう。
例えば、先住猫が飼い主さんを独り占めしたいタイプの場合、新入り猫を受け入れることはストレスになります。
そのストレスから体調を崩したり、今までしなかったような悪さをしてしまう子も…。
多頭飼いが難しそうであれば、先住猫のために諦めるか、相性の良い猫を迎えるなど、考慮や工夫が必要です。
まずは、先住猫(今すでに家にいる猫)が新入りの猫に寛容かを見極めましょう。
例えば、先住猫が飼い主さんを独り占めしたいタイプの場合、新入り猫を受け入れることはストレスになります。
そのストレスから体調を崩したり、今までしなかったような悪さをしてしまう子も…。
多頭飼いが難しそうであれば、先住猫のために諦めるか、相性の良い猫を迎えるなど、考慮や工夫が必要です。
先住猫を優先してあげる
また、実際に多頭飼いを始めたら「先住猫を優先する」ことも必要になってきます。
「この子(先住猫)は寛容だから大丈夫!」と思っていても、いざ新入り猫が入ってきて、その子ばかりを可愛がっていると先住猫は新入りを認めません。
ときには、新入り猫をいじめてしまうこともあります。
多頭飼いで一番大切なのは「どんな時でも先住猫を優先してあげる」こと。
新入り猫を可愛がりたい気持ちも分かりますが、先住猫のためにも、何事もこの子を優先してあげましょう。
例えば、ご飯を与えるときも、先住猫に与えてから、新入り猫に与えるといった配慮が必要になってきます。
多頭飼いができる環境を作る
多頭飼いを始める「事前の環境作り」も大切です。
猫を多頭飼いする前に、必ず物件(アパートやマンション)の契約書を確認し、多頭飼いをしても良いのか調べておいて下さい。
物件によっては、飼育頭数に制限があることも。
また、猫が増える分トイレの数も増やさないといけないなど、空間的な問題も生じます。
猫を多頭飼いできるだけのスペースはあるか?ここの見極めも大切になってきます。
防災グッズを用意しておく
最後に「防災グッズ」を用意しておくのも重要です。
災害が発生したり、住居に何かしたのトラブルが起きたときには、もちろん猫ちゃんたちも一緒に避難し、避難先でも守らなくてはいけません。
多頭飼いをしていれば、当然移動するのも一苦労です。
もしもの時を考えて、多頭飼いに適した大きなキャリーバックや食料、トイレなどの日用品を必ずそろえておきましょう。
猫の多頭飼いは相性が大切
 では、ここからは実際に猫を多頭飼いするときに、どのように新入り猫を選べばいいのかを、相性という観点から紹介します。
新入り猫を探しているという飼い主さんは必読ですよ!
では、ここからは実際に猫を多頭飼いするときに、どのように新入り猫を選べばいいのかを、相性という観点から紹介します。
新入り猫を探しているという飼い主さんは必読ですよ!
子猫(オス)と成猫(オス)
子猫(オス)と成猫(オス)の場合は注意が必要です。
去勢をしていない成猫の場合、本能的に子猫を攻撃する可能性があります。
最悪の場合は子猫を殺してしまうことも…。
オス同士で多頭飼いをする場合は、少なくとも子猫が成猫になるまでは、飼い主さんの目の届く範囲で飼育して下さい。
子猫と子猫
子猫と子猫の場合は、性別に関わらず、相性抜群!
1歳以下の子猫は環境に順応しやすく、子猫同士で仲良くなる可能性が非常に高いです。
猫の多頭飼いを考えた時には、もっとも最適な組み合わせとも言えます。
成猫(オス)と成猫(メス)
成猫(オス)と成猫(メス)の場合、多頭飼いは少し難しいかもしれません。
まず最初に、交配の予定がなければ避妊・去勢手術をしておく必要があります。
成猫同士の多頭飼いは複雑です。
というのも、それぞれの性格が既に確立しており、それによって相性が決まるためです。
成猫同士の多頭飼いを考えている時には、しっかりとトライアル期間を設けるなど、慎重なアプローチをすることが必要になってきます。
子猫(メス)と成猫(メス)
子猫(メス)と成猫(メス)の場合は、多少注意が必要なものの比較的安心です。
というのも、オス同士と違って縄張り争いなどがないためです。
その一方で、メス同士の場合は、どちらも神経質になってしまう場合があるので、お互いににストレスが溜まっていないかなどのチェックは必要になってきます。
年齢で相性は変わる?
 では、猫の年齢によって相性は変わってくるのでしょうか?
「子猫と成猫」の場合は、成猫の性格次第では比較的、良い相性が望めます。
成猫は自身の性格が確立しており、温厚な性格であれば、新入り子猫に対しては寛容に受け入れやすいからです。
一方で「シニア猫と子猫」になると注意が必要にもなります。
シニア猫は、毎日、新入りの子猫が遊びまわっているとそれをストレスに感じてしまうことがあるからです。
また、猫の年齢を見た時に、比較的同じ歳くらいの方が良いという見解もあります。
では、猫の年齢によって相性は変わってくるのでしょうか?
「子猫と成猫」の場合は、成猫の性格次第では比較的、良い相性が望めます。
成猫は自身の性格が確立しており、温厚な性格であれば、新入り子猫に対しては寛容に受け入れやすいからです。
一方で「シニア猫と子猫」になると注意が必要にもなります。
シニア猫は、毎日、新入りの子猫が遊びまわっているとそれをストレスに感じてしまうことがあるからです。
また、猫の年齢を見た時に、比較的同じ歳くらいの方が良いという見解もあります。
多頭飼いに向いてる猫の性格
 次に、どのような性格の先住猫であれば、多頭飼いに向いているかを見ていきましょう。
先住猫が甘えん坊、または寂しがり屋な性格の場合は多頭飼いに向いていると言えます。
その子がお留守番などが多いのであれば尚更です。
先住猫も家に1匹でいるのは寂しいもの。
そんな中、もう1匹遊び相手にでもなってくれる猫が現れれば、不安やストレスも解消されます。
場合によっては、むしろ多頭飼いをしてあげた方が良いかもしれません!
次に、どのような性格の先住猫であれば、多頭飼いに向いているかを見ていきましょう。
先住猫が甘えん坊、または寂しがり屋な性格の場合は多頭飼いに向いていると言えます。
その子がお留守番などが多いのであれば尚更です。
先住猫も家に1匹でいるのは寂しいもの。
そんな中、もう1匹遊び相手にでもなってくれる猫が現れれば、不安やストレスも解消されます。
場合によっては、むしろ多頭飼いをしてあげた方が良いかもしれません!
多頭飼いに向かない猫の性格
逆に、先住猫が「自立心の強い一匹狼タイプ」であれば多頭飼いは向かない性格と言えるでしょう。
新入り猫がくることで、自身の生活が乱され、それをストレスに感じることが多いためです。
もしも先住猫が「自立心の強い一匹狼タイプ」であれば、新入り猫も同様に「一匹狼タイプ」の子を選んであげれば、多頭飼いが成功する確率がアップします。
まとめ
この記事では、猫の多頭飼いについて「多頭飼いの注意点」や「相性の良い猫とは?」を解説しました。
猫の多頭飼いは簡単なものではありませんが、成功すると飼い主であるあなたにとっても、先住猫にとってもよいものとなります。
ぜひ、この記事を参考にしながら多頭飼いを成功させてみて下さいね!
猫の鼻水の色で病気が分かる?
「猫の鼻水が止まらなくて心配…」という悩みを抱える飼い主さんもいるでしょう。
しかも、鼻水が「ピンク色」「緑っぽい」となればなおさら心配ですよね。
実際に、鼻水の様子は、猫に潜んでいる病気のサインとなることも。
まずは「猫の鼻水の色」から分かる病気のサインを見ていきましょう。
ピンク色の鼻水
鼻水がピンク色の場合、血液が混じっている可能性があります。
血液が混じる主な原因は、怪我や鼻炎の悪化が原因で鼻粘膜から出血していることがあげられます。
ピンク色の鼻水が止まらなく、慢性化している時には、鼻腔内腫瘍(びくうないしゅよう)といった病気も考えられるので病院に連れて行きましょう。
緑がかった黄色
緑がかった黄色の鼻水はが出る場合は、細菌やウイルスによる感染症、歯周病が考えられます。
最初は色に驚くかもしれませんが、これはあまり心配せずとも大丈夫です。
緑がかった黄色になるのは、真菌や細菌の死骸が鼻水に混ざって体外に出ている証拠。このような場合は様子を見てもいいでしょう。
その一方で、同時に猫の口臭がきつくなったり、鼻水の強い粘り、といった場合は歯周病に関連しているものもあります。
このような時は、病院に連れていってあげましょう。
透明の鼻水
透明でサラサラした鼻水が出る場合はこんな時です。
・アレルギー性鼻炎の初期症状
・ウイルス性鼻炎の初期症状(後に緑や黄色に変化)
・異物刺激によるもの
いずれにせよ、この状態ではそこまで心配するような症状ではないと言えます。
ですが、次第に鼻水の色が変化していくことも…。
例えば、鼻水の透明がピンク色に変化していった時には、循環血液量過剰というのも考えられます。
赤(鼻血)
赤色の場合は、人間と同じでいわゆる「鼻血」です。
突発的に、1日で治るような場合は怪我が考えられます。
ですが、鼻血が慢性的な場合は、ピンク色の時と同様に鼻腔内腫瘍(びくうないしゅよう)による鼻出血が考えられます。
猫の鼻水に伴う症状と原因
 また、鼻水に伴う症状から猫にひそむ病気を見つけることもできます。
ここからは鼻水と合わせて確認しておきたい他の症状を見ていきましょう。
また、鼻水に伴う症状から猫にひそむ病気を見つけることもできます。
ここからは鼻水と合わせて確認しておきたい他の症状を見ていきましょう。
目やに
まずは「目やに」です。
目やにと鼻水が同時に出ている場合は、
・猫風邪(細菌やウイルスによる感染症)
・クラミジア感染症
・その他感染症
など多くの病気の可能性が考えられます。
目やにの発生が伴う病気の可能性は非常に多岐にわたるので、続く場合は一度病院で診てもらいましょう。
発熱
次に「発熱」です。
鼻水と発熱が同時に生じた場合は、細菌やウイルスによる呼吸器感染症が主に疑われます。
ですが、これだけで病気を確定することは難しく、素人では判断できません。
鼻水+発熱という症状も心配ですが、発熱により極度にごはんを食べなくなる猫もいます。
これに伴い栄養不足や脱水を起こす可能性もありますので、あまりにも猫がぐったりしている場合が急いで病院に連れていきましょう。
くしゃみ
次は「くしゃみ」を伴う場合です。
細菌やウイルスによる感染症にかかってしまった場合、猫も人間と同様に、鼻水と一緒にくしゃみをする時があります。
花粉やアレルギーなどの場合もくしゃみを伴います。
他の症状と比べて、重大な病気が隠れている可能性はやや低めなので、鼻水+くしゃみの時は少し様子を見てもいいかもしれません。
猫の鼻水が出た際の対処法や治し方
 猫の鼻水が出ているのに、それを放ったらかしにするわけにはいきませんよね?
ここからは、鼻水が出ている時にどのような対処や治し方があるのかを紹介します。
まずはこれを実践してみましょう。
猫の鼻水が出ているのに、それを放ったらかしにするわけにはいきませんよね?
ここからは、鼻水が出ている時にどのような対処や治し方があるのかを紹介します。
まずはこれを実践してみましょう。
鼻水の拭き取り方
猫の鼻水を拭いてあげる時は、ティッシュなどで「優しく」拭き取るが基本となります。
目頭から鼻の方へ向かって拭くことで猫も嫌がりません。
また、鼻水は時間が経ってしまうと固まってしまうので、こまめに拭いてあげるようにして下さい。
鼻水が固まってしまいティッシュじゃ取れないという時には、塗れたコットンやガーゼで固まった鼻水をふやかすと拭き取ることができます。
病院で診てもらう
飼い主と言えども、猫の病気に関しては素人です。
勝手な判断で病院に連れていかないことで、隠れた病気が進行し、猫もあなたも辛い思いをすることも考えられます。
猫の鼻水が止まらない、伴って体調が悪そうな場合は迅速に病院に連れていきましょう。
また、どんな症状だとしても、動物病院で獣医師さんに診てもらえれば、あなたの大きな不安も解消できます。
病院に連れて行く時には、その症状がいつからか、色や状態などはどうかをメモをしていくと便利です。
薬を出してもらう
動物病院に連れて行けばひとまずは安心しても良いでしょう。
猫ちゃんのために薬を処方された時は、用量・用法を守りながら、しっかり飲ませてあげて下さい。
猫は嫌がるかもしれませんが、根気強く飲ませ続けることが、その子のためにもなります。
まとめ
この記事では「猫の鼻水」について、色や伴う症状から分かる病気の可能性、そんな時の対処法などを解説しました。
猫の鼻水には、思いがけない病気が隠れていたり、反対に心配しすぎて病院に連れて行ったけど些細なことだったということもあります。
ですが、何もせずに後悔するような結果になるのが一番いけません。
些細な症状でもあなたが不安を抱えたり、猫が辛そうであれば病院に連れていってあげましょう。 犬はみかんを食べて大丈夫
 人が食べている食べ物の中にも、犬が食べて大丈夫な食べ物があります。
ではみかんはどうでしょうか?
結論、みかんは犬も食べることができます!
しかしいくつか注意しなければいけない点もあります。
最初に、みかんを食べるメリットと犬にみかんを与えるときの注意点をご紹介します。
みかんを食べさせる時は、メリットと注意点を把握した上で与えるようにしましょう。
人が食べている食べ物の中にも、犬が食べて大丈夫な食べ物があります。
ではみかんはどうでしょうか?
結論、みかんは犬も食べることができます!
しかしいくつか注意しなければいけない点もあります。
最初に、みかんを食べるメリットと犬にみかんを与えるときの注意点をご紹介します。
みかんを食べさせる時は、メリットと注意点を把握した上で与えるようにしましょう。
みかんの利点
 みかんには100gあたり35mgのビタミンCが含まれるため、人間のビタミンC補給には適した果物です。
しかし犬は、ビタミンCを食事で摂取しなくても自身の体内で生成することができるため、積極的に与える必要はありません。
ただ、犬は年齢を重ねるごとにビタミンを生成する力が不足すると考えられており、さらに夏場はビタミンCが不足しやすい季節となります。
高齢の犬や、夏場には、みかんを与えてビタミンCを補給してあげるのも良いかもしれませんね。
また、みかんにはビタミンCの他にも健康維持が期待できる成分がたくさん含まれています。
みかんには100gあたり35mgのビタミンCが含まれるため、人間のビタミンC補給には適した果物です。
しかし犬は、ビタミンCを食事で摂取しなくても自身の体内で生成することができるため、積極的に与える必要はありません。
ただ、犬は年齢を重ねるごとにビタミンを生成する力が不足すると考えられており、さらに夏場はビタミンCが不足しやすい季節となります。
高齢の犬や、夏場には、みかんを与えてビタミンCを補給してあげるのも良いかもしれませんね。
また、みかんにはビタミンCの他にも健康維持が期待できる成分がたくさん含まれています。
水分たっぷり
水を飲んでほしくてもなかなか飲んでくれないとき、特に熱中症が気になる季節には、水分補給をさせたくても飲んでくれないと困ることがあると思います。
そういったときには、甘味のあるみかんを与えることで水分を補給してあげるとよいでしょう。
与えすぎは下痢などの消化器症状につながる恐れがあるので、いつものお水にみかん汁を数滴たらして試してみましょう。
カリウム
カリウムは、体内で水分の調整を行う役割を担い、体内で増えすぎたナトリウムの排泄を促す働きもあります。
クエン酸
 柑橘系には疲労回復効果が期待できる栄養素「クエン酸」が多く含まれています。
細胞が酸化し、それを修復させようとする状態が疲労に繋がります。
この細胞修復にクエン酸が使われるため、疲労回復につながると考えられています。
柑橘系には疲労回復効果が期待できる栄養素「クエン酸」が多く含まれています。
細胞が酸化し、それを修復させようとする状態が疲労に繋がります。
この細胞修復にクエン酸が使われるため、疲労回復につながると考えられています。
セルロース(食物繊維)
みかんに多く含まれるセルロースには腸内環境を整える効果があるとされています。
動物病院では便秘気味の犬に食物繊維が多く含まれている食事を進められることはよくあります。
みかんのみで便秘が改善するかは個体差がありますが、腸内環境を整えてくれる効果はあると言えそうです。
犬にみかんを与える際の注意点
 犬にみかんを与えることは問題ないですが、以下の点を守らないと愛犬を危険な目に合わせてしまう可能性もあります。
必ずみかんを与える際は注意点があることを把握するようにしましょう。
犬にみかんを与えることは問題ないですが、以下の点を守らないと愛犬を危険な目に合わせてしまう可能性もあります。
必ずみかんを与える際は注意点があることを把握するようにしましょう。
与え過ぎない
 みかんは前述の通り、ビタミンCだけでなく水分も豊富に含まれています。
与え過ぎると下痢になるおそれがあります。
また、食物繊維も多いため、消化しにくいという側面もあります。
そのため、消化されずにうんちに混ざって出てくるという話もあります。
下痢や消化不良を起こさないためにも、与え過ぎには十分注意してください。
食べすぎを防ぐためにもトッピングやおやつにとどめることをおすすめします。
目安としては犬が1日に必要とするエネルギーの10%程度に収まるようにしましょう。
ドッグフードとの栄養バランスも考えながら取り入れてください。
ただし、みかんはカロリーが低めなので10%で計算すると量が多すぎ、お腹を壊す原因になりかねません。
必要なフード量の見た目が10%程度になるように調節する方法がおすすめです。
みかんは前述の通り、ビタミンCだけでなく水分も豊富に含まれています。
与え過ぎると下痢になるおそれがあります。
また、食物繊維も多いため、消化しにくいという側面もあります。
そのため、消化されずにうんちに混ざって出てくるという話もあります。
下痢や消化不良を起こさないためにも、与え過ぎには十分注意してください。
食べすぎを防ぐためにもトッピングやおやつにとどめることをおすすめします。
目安としては犬が1日に必要とするエネルギーの10%程度に収まるようにしましょう。
ドッグフードとの栄養バランスも考えながら取り入れてください。
ただし、みかんはカロリーが低めなので10%で計算すると量が多すぎ、お腹を壊す原因になりかねません。
必要なフード量の見た目が10%程度になるように調節する方法がおすすめです。
果実部分のみを与える
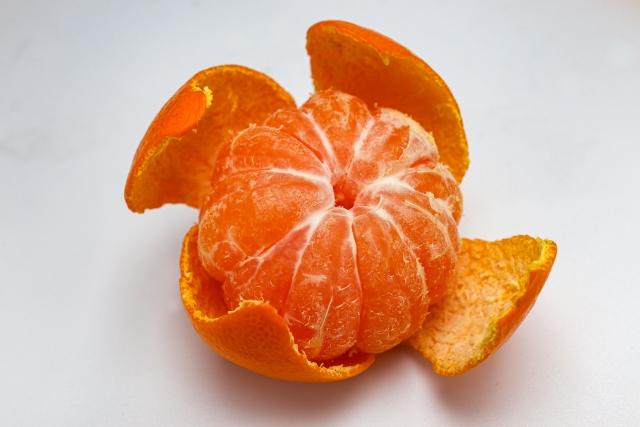 みかんの果実や薄皮には中毒性はないものの、外皮や種などには中毒性のある物質が含まれています。
与えるときは、皮や種の部分を取り除くのを忘れないようにしてください。
ちなみに、みかんに関わらず、柑橘系全般の外皮には、犬にとって中毒性のあるソラレンという物質が含まれています。
過剰摂取することで、嘔吐や下痢などの症状が現れる可能性があるので、与える際には外皮をむき、果実部分だけを与えるようにしましょう。
みかんの果実や薄皮には中毒性はないものの、外皮や種などには中毒性のある物質が含まれています。
与えるときは、皮や種の部分を取り除くのを忘れないようにしてください。
ちなみに、みかんに関わらず、柑橘系全般の外皮には、犬にとって中毒性のあるソラレンという物質が含まれています。
過剰摂取することで、嘔吐や下痢などの症状が現れる可能性があるので、与える際には外皮をむき、果実部分だけを与えるようにしましょう。
アレルギー
犬のなかにはみかんにアレルギーをもつ子もいます。
与えるときは、少量ずつ、様子を見ながらにしましょう。
万が一体調を崩した場合は、すぐに獣医師に相談してください。
病気
「心臓病」や「腎臓病」「腎不全」「癌」など「持病のある犬」「薬を飲んでいる犬」「療法食を食べている犬」は、みかんを与える前に必ずかかりつけの獣医師に相談してください。
みかんの成分(特にカリウム)が薬と作用したり、病状に影響を与えたりする可能性も考えられます。
犬にみかんの加工品を与えても大丈夫?
 みかんの缶詰やゼリー・ジュース等の加工品には砂糖が多く含まれていることがあるため、愛犬には与えないようにしましょう。
与える場合には、加工していないみかんを適量与えるのが安心です。
・みかんゼリー
・みかんジュース
・オレンジジュース
・冷凍みかん
・みかんアイス
などには注意が必要です。
みかんの缶詰やゼリー・ジュース等の加工品には砂糖が多く含まれていることがあるため、愛犬には与えないようにしましょう。
与える場合には、加工していないみかんを適量与えるのが安心です。
・みかんゼリー
・みかんジュース
・オレンジジュース
・冷凍みかん
・みかんアイス
などには注意が必要です。
グレープフルーツなどほかの柑橘類は食べられる?
 オレンジやグレープフルーツをはじめとする柑橘類は、犬が食べても問題はないですが、消化に良くないので熱心に与える必要はありません。
また、薬を服用中の犬にはグレープフルーツを食べさせないでください。
「フラノクマリン」という成分によって薬の分解が遅くなり、薬が効きすぎてしまう恐れがあります。
オレンジやグレープフルーツをはじめとする柑橘類は、犬が食べても問題はないですが、消化に良くないので熱心に与える必要はありません。
また、薬を服用中の犬にはグレープフルーツを食べさせないでください。
「フラノクマリン」という成分によって薬の分解が遅くなり、薬が効きすぎてしまう恐れがあります。
子犬や老犬にみかんを与えても大丈夫?
 離乳した子犬ならみかんを与えても大丈夫です。
ただ、酸味が強く、胃を荒らすこともありますので、様子を見ながら与え、量もほんの少しにしましょう。
また、「老犬」にはみかんの絞り汁を与えると食べやすくなります。
いずれの場合も、下痢や嘔吐、軟便が見られたらみかんを与えるのをやめて、動物病院を受診してください。
そのほか、シニア犬や薬を服用している犬の場合も、ビタミンCが不足しがちだと言われています。
犬がシニア世代に入っている、もしくは薬を服用させているという場合は、みかんを与えてみましょう。
ただし、薬を服用している場合は、食べ合わせの問題があるため、一度かかりつけの獣医師に相談してください。
離乳した子犬ならみかんを与えても大丈夫です。
ただ、酸味が強く、胃を荒らすこともありますので、様子を見ながら与え、量もほんの少しにしましょう。
また、「老犬」にはみかんの絞り汁を与えると食べやすくなります。
いずれの場合も、下痢や嘔吐、軟便が見られたらみかんを与えるのをやめて、動物病院を受診してください。
そのほか、シニア犬や薬を服用している犬の場合も、ビタミンCが不足しがちだと言われています。
犬がシニア世代に入っている、もしくは薬を服用させているという場合は、みかんを与えてみましょう。
ただし、薬を服用している場合は、食べ合わせの問題があるため、一度かかりつけの獣医師に相談してください。
まとめ
 みかんのメリットや与え方の注意点などをご紹介しました。
注意事項を押さえれば、犬にみかんを与えることは問題ありません。
ただし、主食はあくまでもドッグフードなどであり、みかんを主食にしないように注意しましょう。
食べさせる場合には、まずは少量のみ・果肉部分のみをおやつとしてあげてください。
愛犬の様子をきちんと観察しつつ、最適なあげ方をするようにしましょう!
みかんのメリットや与え方の注意点などをご紹介しました。
注意事項を押さえれば、犬にみかんを与えることは問題ありません。
ただし、主食はあくまでもドッグフードなどであり、みかんを主食にしないように注意しましょう。
食べさせる場合には、まずは少量のみ・果肉部分のみをおやつとしてあげてください。
愛犬の様子をきちんと観察しつつ、最適なあげ方をするようにしましょう!
 寒い冬、冷え込む夜には暖かくしてぐっすり眠りたいもの。
犬だって寒がりの子や老犬、子犬には暖かくしてあげたいですね。
そんな時、役に立つのがペット用湯たんぽです。
なんと言っても湯たんぽは安全性の高いものが一番。
安全で使いやすい商品がいろいろ出ているので、どんなところに気をつけて選べばよいのかポイントをまとめていきます。
さらに犬用湯たんぽとして人気のおすすめ商品を8点紹介しますので、愛犬にぴったりな湯たんぽを見つける参考にしてくださいね。
寒い冬、冷え込む夜には暖かくしてぐっすり眠りたいもの。
犬だって寒がりの子や老犬、子犬には暖かくしてあげたいですね。
そんな時、役に立つのがペット用湯たんぽです。
なんと言っても湯たんぽは安全性の高いものが一番。
安全で使いやすい商品がいろいろ出ているので、どんなところに気をつけて選べばよいのかポイントをまとめていきます。
さらに犬用湯たんぽとして人気のおすすめ商品を8点紹介しますので、愛犬にぴったりな湯たんぽを見つける参考にしてくださいね。
 人間用の湯たんぽと同じで沸かしたお湯を入れて使うタイプです。
家にあるという飼い主さんもいるでしょう。
壊れにくい素材で作られているので、ワンちゃんが噛んだりしても大丈夫です。
しかし毎回お湯を沸かす必要があるため、準備が少し面倒なところが難点です。
また熱いお湯を入れる際に火傷しないようにも気をつけましょう。
ゴム製の湯たんぽは氷を入れて夏に保冷剤として使うことができるという便利なものもあります。
暑がりの子にはこちらもおすすめです。
人間用の湯たんぽと同じで沸かしたお湯を入れて使うタイプです。
家にあるという飼い主さんもいるでしょう。
壊れにくい素材で作られているので、ワンちゃんが噛んだりしても大丈夫です。
しかし毎回お湯を沸かす必要があるため、準備が少し面倒なところが難点です。
また熱いお湯を入れる際に火傷しないようにも気をつけましょう。
ゴム製の湯たんぽは氷を入れて夏に保冷剤として使うことができるという便利なものもあります。
暑がりの子にはこちらもおすすめです。
 大型犬と小型犬ではその大きさはかなり違います。
だからペットの体型に適したサイズの湯たんぽを選ぶことは重要なポイントです。
また湯たんぽをどの場所で使うのかということも考えてみてください。
ハウスの中・ベッドの下など使う場所によってもサイズが変わってきます。
せっかく買ったのに、いざ使おうとするとサイズが小さかったでは困りますよね。
それから外出先でも使いたいという場合には、コンパクトなものが便利です。
ペットの体型と湯たんぽを使う場所、どちらも考慮して選びましょう。
大型犬と小型犬ではその大きさはかなり違います。
だからペットの体型に適したサイズの湯たんぽを選ぶことは重要なポイントです。
また湯たんぽをどの場所で使うのかということも考えてみてください。
ハウスの中・ベッドの下など使う場所によってもサイズが変わってきます。
せっかく買ったのに、いざ使おうとするとサイズが小さかったでは困りますよね。
それから外出先でも使いたいという場合には、コンパクトなものが便利です。
ペットの体型と湯たんぽを使う場所、どちらも考慮して選びましょう。
 犬は毛に覆われていますが、肌はとても薄く敏感です。
直接肌に湯たんぽを触れてしまうと、低温火傷などを引き起こす恐れが高いです。
必ずカバー付きの商品を選びましょう。
カバーが付いていることで汚れても洗濯ができて、いつも清潔に使えるという利点もあります。
カバーがなければ、タオルなどでくるんであげたりしても大丈夫です。
老犬に湯たんぽを使う時には、カバーが付いていても長時間同じ場所に触れていることがないようにしましょう。
こまめに温度を確かめて、暑すぎることがないように注意が必要です。
犬は毛に覆われていますが、肌はとても薄く敏感です。
直接肌に湯たんぽを触れてしまうと、低温火傷などを引き起こす恐れが高いです。
必ずカバー付きの商品を選びましょう。
カバーが付いていることで汚れても洗濯ができて、いつも清潔に使えるという利点もあります。
カバーがなければ、タオルなどでくるんであげたりしても大丈夫です。
老犬に湯たんぽを使う時には、カバーが付いていても長時間同じ場所に触れていることがないようにしましょう。
こまめに温度を確かめて、暑すぎることがないように注意が必要です。
 冷え込む夜や留守番させている時に湯たんぽを使うという人は多いと思います。
使い始めの温度と7,8時間たった時の温度はもちろん違いますよね。
暖かさが持続する時間をチェックしてみることも必要です。
冷えるのが早い湯たんぽでは効率が悪くなります。
データによると電子レンジタイプのもののほうがお湯を入れるものより持続時間は長いようです。
もちろん大きさや使う環境(気温)によっても違いはあると思いますので、商品説明を確認してください。
冷え込む夜や留守番させている時に湯たんぽを使うという人は多いと思います。
使い始めの温度と7,8時間たった時の温度はもちろん違いますよね。
暖かさが持続する時間をチェックしてみることも必要です。
冷えるのが早い湯たんぽでは効率が悪くなります。
データによると電子レンジタイプのもののほうがお湯を入れるものより持続時間は長いようです。
もちろん大きさや使う環境(気温)によっても違いはあると思いますので、商品説明を確認してください。
 犬用湯たんぽの人気オススメ商品を8点、紹介します。
お湯を入れるタイプと電子レンジタイプそれぞれ選んでみました。
それぞれに特徴があり、使いやすさは飼い主さんによっても違うと思います。
愛犬に合うものはどれか、先程の選び方4つのポイントを参考に見比べてみてください。
犬用湯たんぽの人気オススメ商品を8点、紹介します。
お湯を入れるタイプと電子レンジタイプそれぞれ選んでみました。
それぞれに特徴があり、使いやすさは飼い主さんによっても違うと思います。
愛犬に合うものはどれか、先程の選び方4つのポイントを参考に見比べてみてください。
 容器が自立できるので、お湯を注いだあとも本体に触れることなくカバーを掛けられたり、取っ手を持ちながら運ぶことも可能です。
お湯を捨てる時には立てた状態でキャップを外せばOKです。
使う側の安全のことを考えられた商品です。
カバー付きではないので、タオルなどでくるんで温度を確認して使うようにしましょう。
サイズは27×22×10cmで2,6lのお湯を入れて使うタイプなので、やや大きめサイズです。
ベッドの中を温めておくのに良いですね。
容器が自立できるので、お湯を注いだあとも本体に触れることなくカバーを掛けられたり、取っ手を持ちながら運ぶことも可能です。
お湯を捨てる時には立てた状態でキャップを外せばOKです。
使う側の安全のことを考えられた商品です。
カバー付きではないので、タオルなどでくるんで温度を確認して使うようにしましょう。
サイズは27×22×10cmで2,6lのお湯を入れて使うタイプなので、やや大きめサイズです。
ベッドの中を温めておくのに良いですね。
 直径16cmのコンパクトサイズで、持ち運びにも便利なミニ湯たんぽ。
価格も安く、お試しに使ってみるのも良いし、小さな子犬にも最適です。
お湯を入れて使うタイプで650mlのお湯が入ります。
セットで付いてくるカバーは手触りもよく可愛らしいので子犬には温かい癒やしとなるでしょう。
本体は安心の日本製、SGマークも付いています。
ペット用ではないので、お湯の温度には注意して時々様子を見るようにして使いましょう。
直径16cmのコンパクトサイズで、持ち運びにも便利なミニ湯たんぽ。
価格も安く、お試しに使ってみるのも良いし、小さな子犬にも最適です。
お湯を入れて使うタイプで650mlのお湯が入ります。
セットで付いてくるカバーは手触りもよく可愛らしいので子犬には温かい癒やしとなるでしょう。
本体は安心の日本製、SGマークも付いています。
ペット用ではないので、お湯の温度には注意して時々様子を見るようにして使いましょう。
 ふわふわの可愛らしいカバーが付いてくる湯たんぽです。
レンジの中でも衛生的に使えるように、専用のレンジパックもセットとして付属しているので、飼い主さんも安心して使えます。
またカバーは洗濯可能なので、いつも清潔に使えます。
カバーの内側はアルミ加工で下からの冷気を遮断できるようになっており、保温性を高めてくれます。
サイズは高さが4cm、25cmの円形なので、場所を選ばず小型犬に使いやすいサイズです。
ふわふわの可愛らしいカバーが付いてくる湯たんぽです。
レンジの中でも衛生的に使えるように、専用のレンジパックもセットとして付属しているので、飼い主さんも安心して使えます。
またカバーは洗濯可能なので、いつも清潔に使えます。
カバーの内側はアルミ加工で下からの冷気を遮断できるようになっており、保温性を高めてくれます。
サイズは高さが4cm、25cmの円形なので、場所を選ばず小型犬に使いやすいサイズです。
 オススメのペット用湯たんぽを紹介しましたが、いかがでしたか?
安全で、飼い主さんが使いやすい物を選ぶことがワンちゃんにも最適だと思います。
選ぶポイントを参考に湯たんぽで冷え込む冬を快適に暖かくして過ごしてくださいね。
オススメのペット用湯たんぽを紹介しましたが、いかがでしたか?
安全で、飼い主さんが使いやすい物を選ぶことがワンちゃんにも最適だと思います。
選ぶポイントを参考に湯たんぽで冷え込む冬を快適に暖かくして過ごしてくださいね。  猫の食器を購入する際には、食べやすさと価格、見た目、手入れのしやすさが考えられます。
猫を飼っている人も増えて種類も豊富で、素材も考慮されたものが販売されています。
愛猫に合った食器で楽しく食事をしてもらうには、どんな点を注意すればいいのかを調べて見ました。
猫の食器を購入する際には、食べやすさと価格、見た目、手入れのしやすさが考えられます。
猫を飼っている人も増えて種類も豊富で、素材も考慮されたものが販売されています。
愛猫に合った食器で楽しく食事をしてもらうには、どんな点を注意すればいいのかを調べて見ました。
 プラスチック製は他の素材に比べてリーズナブルで、軽くて扱いやすくとても便利な食器が多くあります。
軽いため餌を食べている最中に動いてしまう事がありますが、滑り止めが付いているものなら動く心配がなく安心して食事を楽しめます。
傷つきやすく傷の隙間に汚れが入りこんでしまい落ちにくくなってしまうため、長期間の使用やウエットフードをあげるのは避けた方が無難です。
プラスチック製は他の素材に比べてリーズナブルで、軽くて扱いやすくとても便利な食器が多くあります。
軽いため餌を食べている最中に動いてしまう事がありますが、滑り止めが付いているものなら動く心配がなく安心して食事を楽しめます。
傷つきやすく傷の隙間に汚れが入りこんでしまい落ちにくくなってしまうため、長期間の使用やウエットフードをあげるのは避けた方が無難です。
 陶磁器製は、程良い重さがあるため安定感があり、傷つくにくい素材で清潔に使う事ができます。
温かいままで餌を与えたい時などには冷めにくく、電子レンジ対応のものであれば器のまま温められるのでとても便利です。
割れやすいデメリットがありますので、取り扱いには注意が必要になります。
陶磁器製は、程良い重さがあるため安定感があり、傷つくにくい素材で清潔に使う事ができます。
温かいままで餌を与えたい時などには冷めにくく、電子レンジ対応のものであれば器のまま温められるのでとても便利です。
割れやすいデメリットがありますので、取り扱いには注意が必要になります。
 ステンレス製は、手が滑って落としてしまった時にも壊れる心配がなく、錆びにくく汚れが落ちやすいため毎日のお手入れが簡単です。
金属製のため冬場は冷たく、猫によって臭いを嫌がり餌を食べてくれない事もあります。
軽いため安定感があまりなく動いてしまいますので、滑り止めが付いている食器なら安心です。
ステンレス製は、手が滑って落としてしまった時にも壊れる心配がなく、錆びにくく汚れが落ちやすいため毎日のお手入れが簡単です。
金属製のため冬場は冷たく、猫によって臭いを嫌がり餌を食べてくれない事もあります。
軽いため安定感があまりなく動いてしまいますので、滑り止めが付いている食器なら安心です。
 猫によって性格が違うように、食事の仕方にも癖やこだわりをもっています。
様々な機能性を持った食器が販売されていますので、上手に使いこなすための注意点や愛猫に合ったおすすめな商品を紹介します。
猫によって性格が違うように、食事の仕方にも癖やこだわりをもっています。
様々な機能性を持った食器が販売されていますので、上手に使いこなすための注意点や愛猫に合ったおすすめな商品を紹介します。
 食べこぼしが多い場合には食べやすい角度が付いている「そり返し」のものや、内側にフチのある「二段構造」のものがおすすめです。
餌を食べている途中でやめる事がなくなり、飼い主の掃除の手間も省いてくれます。
早食いの場合には、食器内に凸凹が付いているものが良く、凸凹の隙間に餌が入って食べづらく自然にゆっくり食事をしてくれるようになります。
あまり時間がかかってしまうような時には、通常の食器で少しずつ与えてあげるようにします。
食べこぼしが多い場合には食べやすい角度が付いている「そり返し」のものや、内側にフチのある「二段構造」のものがおすすめです。
餌を食べている途中でやめる事がなくなり、飼い主の掃除の手間も省いてくれます。
早食いの場合には、食器内に凸凹が付いているものが良く、凸凹の隙間に餌が入って食べづらく自然にゆっくり食事をしてくれるようになります。
あまり時間がかかってしまうような時には、通常の食器で少しずつ与えてあげるようにします。
 餌を食べている最中にヒゲが食器に触れるのを嫌がる場合は、横幅の広い楕円形のものか一回り大きなサイズのものが適しています。
食器にこだわりを持つ猫は多く、ストレスをためないようにヒゲの幅に合った食器を選んであげるようにします。
餌を食べている最中にヒゲが食器に触れるのを嫌がる場合は、横幅の広い楕円形のものか一回り大きなサイズのものが適しています。
食器にこだわりを持つ猫は多く、ストレスをためないようにヒゲの幅に合った食器を選んであげるようにします。
 愛猫に合った食器を選ぶ際には素材、機能性が重要になりますが、使い勝手や手入れのしやすさなども気になる要素のひとつです。
数種類ある中の猫用食器から人気のある物を9つ選んで、人気の秘密や特徴を詳しく紹介します。
愛猫に合った食器を選ぶ際には素材、機能性が重要になりますが、使い勝手や手入れのしやすさなども気になる要素のひとつです。
数種類ある中の猫用食器から人気のある物を9つ選んで、人気の秘密や特徴を詳しく紹介します。
 見た目がフードボウルには見えないおしゃれな食器で、レッド、ブルー、イエローの3種類から選ぶ事ができます。
今までにない形をしていてボウルに中に頭を入れた状態で食べれますので、マイペースでゆっくり食事を楽しみたい猫に向いています。
見た目がフードボウルには見えないおしゃれな食器で、レッド、ブルー、イエローの3種類から選ぶ事ができます。
今までにない形をしていてボウルに中に頭を入れた状態で食べれますので、マイペースでゆっくり食事を楽しみたい猫に向いています。
 シンプルな陶器製の食器で食器の縁の部分が返しになっているため、周りにフードがこぼれにくく飛び散るのを防いでくれます。
洗う際に、返しの内側を洗う手間がかかってしまうデメリットがあります。
シンプルな陶器製の食器で食器の縁の部分が返しになっているため、周りにフードがこぼれにくく飛び散るのを防いでくれます。
洗う際に、返しの内側を洗う手間がかかってしまうデメリットがあります。
 セラミック素材で出来た丈夫なウォーターボウルで、ボウルの内側には飲んだ水の量がわかる便利な目盛が付いています。
猫は体に異常がある場合いつもとは違った量の水を飲む事がありますので、健康管理にも役立ってくれます。
縁の部分には返しがあり水がこぼれにくく、他の食器と比べて素材の匂いが水に移る心配がなく安心です。
セラミック素材で出来た丈夫なウォーターボウルで、ボウルの内側には飲んだ水の量がわかる便利な目盛が付いています。
猫は体に異常がある場合いつもとは違った量の水を飲む事がありますので、健康管理にも役立ってくれます。
縁の部分には返しがあり水がこぼれにくく、他の食器と比べて素材の匂いが水に移る心配がなく安心です。
 毎日食事をする際に欠かせない猫用食器は重要な役割をしていて、美味しそうに食事をする姿はとても癒しを与えてくれます。
素材や機能性が工夫された商品が多く、選ぶ際には悩んでしまいますが、愛猫の様子を観察しながら状態に合ったもの選ぶ事が大切です。
毎日食事をする際に欠かせない猫用食器は重要な役割をしていて、美味しそうに食事をする姿はとても癒しを与えてくれます。
素材や機能性が工夫された商品が多く、選ぶ際には悩んでしまいますが、愛猫の様子を観察しながら状態に合ったもの選ぶ事が大切です。  犬にとって唐辛子はNGな食べ物です。
当たり前のようですが、なぜダメなのかを知らない人も多いはず。
まず最初に、唐辛子が犬にとって、なぜ危険な食べ物なのかを解説しましょう!
犬にとって唐辛子はNGな食べ物です。
当たり前のようですが、なぜダメなのかを知らない人も多いはず。
まず最初に、唐辛子が犬にとって、なぜ危険な食べ物なのかを解説しましょう!
 人間であれば、ひとくち食べただけで「辛い!」となって吐き出しますが、ワンちゃんは吐き出すことはありません。
どうしてワンちゃんは唐辛子を思わず食べてしまうのでしょうか?
これには犬と人間との味覚の違いが関係しています。
実は、犬は人間よりも味覚が鈍く、唐辛子を食べても辛さをあまり感じません。
そのため、思わず最後まで食べてしまうのです。
人間であれば、ひとくち食べただけで「辛い!」となって吐き出しますが、ワンちゃんは吐き出すことはありません。
どうしてワンちゃんは唐辛子を思わず食べてしまうのでしょうか?
これには犬と人間との味覚の違いが関係しています。
実は、犬は人間よりも味覚が鈍く、唐辛子を食べても辛さをあまり感じません。
そのため、思わず最後まで食べてしまうのです。
 さて、もうひとつ気になるのが「犬のしつけ用唐辛子スプレー」です。
犬にとって唐辛子はNGなのですが、これは大丈夫なのでしょうか?そもそも効果や使用する必要はあるのでしょうか?
さて、もうひとつ気になるのが「犬のしつけ用唐辛子スプレー」です。
犬にとって唐辛子はNGなのですが、これは大丈夫なのでしょうか?そもそも効果や使用する必要はあるのでしょうか?
 では、ここからは猫にヨーグルトを食べさせるメリットや、ヨーグルトに含まれる栄養などをもう少し詳しく見ていきましょう。
では、ここからは猫にヨーグルトを食べさせるメリットや、ヨーグルトに含まれる栄養などをもう少し詳しく見ていきましょう。
 猫にヨーグルトを食べさせるメリットがたくさんあるのはお分かり頂けたでしょうか?
その一方で、注意したいのがデメリットです。
ここからは、メリットと合わせて知っておきたい「猫にヨーグルトを食べさせるデメリット」を解説していきます。
猫にヨーグルトを食べさせるメリットがたくさんあるのはお分かり頂けたでしょうか?
その一方で、注意したいのがデメリットです。
ここからは、メリットと合わせて知っておきたい「猫にヨーグルトを食べさせるデメリット」を解説していきます。
 ここからは、実際に猫にヨーグルトを与えるときにどのように与えればいいのか、頻度などを紹介します。
ここまで読んで、ヨーグルトを食べさせたいなと考えている飼い主さんは、ぜひ今から紹介することを守って、食べさせてあげて下さいね!
ここからは、実際に猫にヨーグルトを与えるときにどのように与えればいいのか、頻度などを紹介します。
ここまで読んで、ヨーグルトを食べさせたいなと考えている飼い主さんは、ぜひ今から紹介することを守って、食べさせてあげて下さいね!
 「歯磨きをしないといけないのは分かってるんだけど…噛まれちゃう…」という飼い主さんも多いはず。
そう、犬はそんな簡単に歯磨きをさせてはくれないんです。
では、犬が歯磨きをさせてくれない理由は何にあるのでしょうか?
「歯磨きをしないといけないのは分かってるんだけど…噛まれちゃう…」という飼い主さんも多いはず。
そう、犬はそんな簡単に歯磨きをさせてはくれないんです。
では、犬が歯磨きをさせてくれない理由は何にあるのでしょうか?
 犬が歯磨きを嫌がる理由はお分かり頂けたでしょうか?
それでも、飼い主である以上、愛犬の歯磨きは避けては通れない道。
ここからは「でも、どうしたらいいの?」という飼い主さんのために、まずは歯磨きを始める手順を紹介します。
犬が歯磨きを嫌がる理由はお分かり頂けたでしょうか?
それでも、飼い主である以上、愛犬の歯磨きは避けては通れない道。
ここからは「でも、どうしたらいいの?」という飼い主さんのために、まずは歯磨きを始める手順を紹介します。
 それでもまだ「歯磨きを嫌がる、させてくれない!」という場合もあるかと思います。
そんな飼い主さんに、ここからは、歯磨きを嫌がる犬に歯磨きをするコツを5つ紹介します!
「どうしても歯磨きができない」という飼い主さんは必読ですよ!
それでもまだ「歯磨きを嫌がる、させてくれない!」という場合もあるかと思います。
そんな飼い主さんに、ここからは、歯磨きを嫌がる犬に歯磨きをするコツを5つ紹介します!
「どうしても歯磨きができない」という飼い主さんは必読ですよ!
 歯磨きアイテムの中で最もメジャーなのが、犬用歯磨きガムです。
これは、ワンちゃんがおやつと思って、ガムを食べているだけで、歯磨きができる優れもの。
飼い主さんにとって、時間も労力もかからないが嬉しいポイントです。
ワンちゃんに歯磨きガムを与えるときは、犬の口幅より、少しだけ長めの物を選んで、噛ませてあげて下さい。
歯磨きアイテムの中で最もメジャーなのが、犬用歯磨きガムです。
これは、ワンちゃんがおやつと思って、ガムを食べているだけで、歯磨きができる優れもの。
飼い主さんにとって、時間も労力もかからないが嬉しいポイントです。
ワンちゃんに歯磨きガムを与えるときは、犬の口幅より、少しだけ長めの物を選んで、噛ませてあげて下さい。
 また、犬用おもちゃの中にも、歯のケアをすることができるものがあります。
歯磨きの頻度やレベルに心配があるという飼い主さんは、歯磨きガム同様に、こういった歯のケアをできるおもちゃを持つのもおすすめ。
ワンちゃんの噛む力や体格、犬種などに合わせて、おもちゃを選んであげて下さいね!
また、犬用おもちゃの中にも、歯のケアをすることができるものがあります。
歯磨きの頻度やレベルに心配があるという飼い主さんは、歯磨きガム同様に、こういった歯のケアをできるおもちゃを持つのもおすすめ。
ワンちゃんの噛む力や体格、犬種などに合わせて、おもちゃを選んであげて下さいね!
 犬用の知育玩具を購入することで愛犬を躾けることができたり、遊び道具としてももちろん使用することもできます。
次に、おすすめの犬用の知育玩具9選を紹介します。
そのため、愛犬のための玩具を購入したい人は参考にしてください。
犬用の知育玩具を購入することで愛犬を躾けることができたり、遊び道具としてももちろん使用することもできます。
次に、おすすめの犬用の知育玩具9選を紹介します。
そのため、愛犬のための玩具を購入したい人は参考にしてください。
 ワンちゃんが遊びやすいボールの形状に仕上げられている知育玩具です。
そのため、多くのワンちゃんの食いつきがよく、購入してあげることで高確率で遊んでくれます。
購入したにも関わらず、遊んでくれないことは飼い主にとっては悲しいですよね。
しかし、そのような心配がないため、初めて犬用の知育玩具を購入しようと考えている人は購入を検討してくださいね。
また、中に餌を入れることができ、透明に仕上げられていることで餌があることを認識させることができ、転がせば餌が出ることをわかりやすいです。
ワンちゃんが遊びやすいボールの形状に仕上げられている知育玩具です。
そのため、多くのワンちゃんの食いつきがよく、購入してあげることで高確率で遊んでくれます。
購入したにも関わらず、遊んでくれないことは飼い主にとっては悲しいですよね。
しかし、そのような心配がないため、初めて犬用の知育玩具を購入しようと考えている人は購入を検討してくださいね。
また、中に餌を入れることができ、透明に仕上げられていることで餌があることを認識させることができ、転がせば餌が出ることをわかりやすいです。
 普通のボールではなく、耐久性に優れている素材で作られていることで長い間愛用することができ、噛みついても割れたり、壊れてしまう心配がいりません。
そのため、噛み癖があるワンちゃんや活発なワンちゃんにおすすめの知育玩具ですよ。
投げて遊ぶだけではなく、音が鳴る仕組みに仕上げられていることで知育玩具に警戒心が強いワンちゃんにも興味を持ってもらうことができます。
軽量化もされていることで子犬の知育玩具としても使用することができ、安全性も保障されています。
普通のボールではなく、耐久性に優れている素材で作られていることで長い間愛用することができ、噛みついても割れたり、壊れてしまう心配がいりません。
そのため、噛み癖があるワンちゃんや活発なワンちゃんにおすすめの知育玩具ですよ。
投げて遊ぶだけではなく、音が鳴る仕組みに仕上げられていることで知育玩具に警戒心が強いワンちゃんにも興味を持ってもらうことができます。
軽量化もされていることで子犬の知育玩具としても使用することができ、安全性も保障されています。
 音が出るぬいぐるみであるため、噛むことで楽しく遊ぶことができ、噛み癖があるワンちゃんにおすすめです。
また、さまざまな形のぬいぐるみが10個セットで販売されていることでワンちゃんが興味を抱くぬいぐるみが高い確率で含まれています。
どれも可愛らしいデザインに仕上げられていることで可愛らしい知育玩具を購入したい人におすすめですね。
また、知育玩具だけではなく、普通のぬいぐるみとしても十分飾ることができるポテンシャルになっています。
音が出るぬいぐるみであるため、噛むことで楽しく遊ぶことができ、噛み癖があるワンちゃんにおすすめです。
また、さまざまな形のぬいぐるみが10個セットで販売されていることでワンちゃんが興味を抱くぬいぐるみが高い確率で含まれています。
どれも可愛らしいデザインに仕上げられていることで可愛らしい知育玩具を購入したい人におすすめですね。
また、知育玩具だけではなく、普通のぬいぐるみとしても十分飾ることができるポテンシャルになっています。
 骨の形状に作られている知育玩具であり、本当にチキンの風味がするように仕上がっています。
そのため、ワンちゃんの食いつきが非常によく、高い確率で遊んでくれますよ。
また、香料や着色剤は一切使用されていないため、噛んでも有害の成分が染み出てしまう心配もありません。
また、飲み込みにくいY字のデザインに仕上げていることで誤って飲み込んでしまうことも防ぎます。
噛みつきやすいようなカーブがデザインされていることでワンちゃんにとってはストレスが溜まりませんね。
骨の形状に作られている知育玩具であり、本当にチキンの風味がするように仕上がっています。
そのため、ワンちゃんの食いつきが非常によく、高い確率で遊んでくれますよ。
また、香料や着色剤は一切使用されていないため、噛んでも有害の成分が染み出てしまう心配もありません。
また、飲み込みにくいY字のデザインに仕上げていることで誤って飲み込んでしまうことも防ぎます。
噛みつきやすいようなカーブがデザインされていることでワンちゃんにとってはストレスが溜まりませんね。
 コットン糸が強く編み込まれて作られた知育玩具であり、噛んで良し。
引っ張って良しとさまざまな使用方法で遊ばせることができます。
一人遊び用の知育玩具としてだけではなく、飼い主と引っ張り合いを楽しむことででき、ワンちゃんとのコミュニケーションをとることも可能ですよ。
そのため、一緒にワンちゃんと遊びたい人におすすめの知育玩具です。
網目に歯がしっかり入り込みやすく仕上がっていることで遊び道具だけではなく、デンタルケアアイテムとしても使用することができます。
コットン糸が強く編み込まれて作られた知育玩具であり、噛んで良し。
引っ張って良しとさまざまな使用方法で遊ばせることができます。
一人遊び用の知育玩具としてだけではなく、飼い主と引っ張り合いを楽しむことででき、ワンちゃんとのコミュニケーションをとることも可能ですよ。
そのため、一緒にワンちゃんと遊びたい人におすすめの知育玩具です。
網目に歯がしっかり入り込みやすく仕上がっていることで遊び道具だけではなく、デンタルケアアイテムとしても使用することができます。
 犬用の知育玩具を使用することでどのような効果が期待できるのか知らない人も多くいるのではないでしょうか。
次に、知育玩具で遊ばせることで得られる効果について紹介します。
ワンちゃんに知育玩具を与えようと考えている人は参考にしてください。
犬用の知育玩具を使用することでどのような効果が期待できるのか知らない人も多くいるのではないでしょうか。
次に、知育玩具で遊ばせることで得られる効果について紹介します。
ワンちゃんに知育玩具を与えようと考えている人は参考にしてください。
 人でも同じことが言えますが、ある程度体を動かさなければ運動不足になってしまい、肥満体質になりやすく、病気を誘発してしまうリスクも高まります。
散歩をすれば運動不足を解消することはできますが、天気や飼い主の都合上どうしても散歩をすることができない場合もあるのではないでしょうか。
そのような時に知育玩具を与えて遊ばせることで体を動かすことができ、軽い運動をすることが可能になります。
運動不足気味のワンちゃんにはおすすめのグッズであり、健康的な体に近づけることも期待できますよ。
人でも同じことが言えますが、ある程度体を動かさなければ運動不足になってしまい、肥満体質になりやすく、病気を誘発してしまうリスクも高まります。
散歩をすれば運動不足を解消することはできますが、天気や飼い主の都合上どうしても散歩をすることができない場合もあるのではないでしょうか。
そのような時に知育玩具を与えて遊ばせることで体を動かすことができ、軽い運動をすることが可能になります。
運動不足気味のワンちゃんにはおすすめのグッズであり、健康的な体に近づけることも期待できますよ。
 知育玩具でフード与えられたワンちゃんは留守番でも退屈しにくく、昼寝などをしてのんびり過ごすことも可能になります。
ワンちゃんの中には家族の行動を敏感に読み取る習慣がある場合もあり、飼い主などが忙しく行動しているとワンちゃんも早く食べようとしたり、あえて食べ残して興味を抱かせようと行動することもあります。
このような状況が長期間続いてしまうと健康を損ねてしまう原因になったり、ストレスが溜まってしまいます。
知育玩具でフードを与えることで飼い主もゆっくり準備をすることもでき、ワンちゃんも安心して食事をすることが可能になります。
知育玩具でフード与えられたワンちゃんは留守番でも退屈しにくく、昼寝などをしてのんびり過ごすことも可能になります。
ワンちゃんの中には家族の行動を敏感に読み取る習慣がある場合もあり、飼い主などが忙しく行動しているとワンちゃんも早く食べようとしたり、あえて食べ残して興味を抱かせようと行動することもあります。
このような状況が長期間続いてしまうと健康を損ねてしまう原因になったり、ストレスが溜まってしまいます。
知育玩具でフードを与えることで飼い主もゆっくり準備をすることもでき、ワンちゃんも安心して食事をすることが可能になります。
 知育玩具は考える力を育てる目的や暇つぶし用などさまざまな用途別に販売されています。
そのため、知育玩具を購入するのであればどのような目的で知育玩具を購入するのかを明確に決めておくことをおすすめします。
普段のワンちゃんの行動をよく観察して暇そうにしている時間が長かったり、あまり遊んであげることができないのであれば暇つぶし用の知育玩具がおすすめですよ。
きちんと躾をしたかったり、芸を覚えさせたいのであれば頭を使うような知育玩具を購入しましょう。
知育玩具は考える力を育てる目的や暇つぶし用などさまざまな用途別に販売されています。
そのため、知育玩具を購入するのであればどのような目的で知育玩具を購入するのかを明確に決めておくことをおすすめします。
普段のワンちゃんの行動をよく観察して暇そうにしている時間が長かったり、あまり遊んであげることができないのであれば暇つぶし用の知育玩具がおすすめですよ。
きちんと躾をしたかったり、芸を覚えさせたいのであれば頭を使うような知育玩具を購入しましょう。
 知育玩具といってもさまざまな大きさに作られており、適した大きさの知育玩具を購入するようにしましょう。
小さすぎると飲み込んでしまう危険性があるため、ワンちゃんの大きさを考慮して安全性を確保できる大きさの知育玩具がおすすめですよ。
しかし、大きすぎる知育玩具では遊びづらさが目立ってしまい、遊んでくれなくなる可能性があります。
基本的に大型犬の場合は大きめで小型犬の場合は小さめの知育玩具を購入するようにすれば問題ありませんよ。
知育玩具といってもさまざまな大きさに作られており、適した大きさの知育玩具を購入するようにしましょう。
小さすぎると飲み込んでしまう危険性があるため、ワンちゃんの大きさを考慮して安全性を確保できる大きさの知育玩具がおすすめですよ。
しかし、大きすぎる知育玩具では遊びづらさが目立ってしまい、遊んでくれなくなる可能性があります。
基本的に大型犬の場合は大きめで小型犬の場合は小さめの知育玩具を購入するようにすれば問題ありませんよ。
 犬用の知育玩具がさまざまな種類が販売されており、目的も異なるため、正しい選び方の元購入することが大切です。
知育玩具を与えることでワンちゃんの健康を維持することにもつながるため、留守にさせてしまう機会が多いのであれば購入することをおすすめします。
犬用の知育玩具がさまざまな種類が販売されており、目的も異なるため、正しい選び方の元購入することが大切です。
知育玩具を与えることでワンちゃんの健康を維持することにもつながるため、留守にさせてしまう機会が多いのであれば購入することをおすすめします。  では、実際にどのような「目やに」であれば病気のサインを疑わなくてはいけないのでしょうか?
ここからは「目やにの色」「猫ちゃんの症状」から、病気のサインである可能性があるもの見ていきましょう。
では、実際にどのような「目やに」であれば病気のサインを疑わなくてはいけないのでしょうか?
ここからは「目やにの色」「猫ちゃんの症状」から、病気のサインである可能性があるもの見ていきましょう。
 ここからは、猫の目やにの取り方を紹介します。
目元を触られるのを嫌がる猫も多いですが、目やにを放置していると、猫も痒がり、二次的に皮膚などを傷つけてしまうこともあります。
猫は自分ではめやにを取ることができないので、飼い主であるなたがしっかりと取ってあげましょう!
ここからは、猫の目やにの取り方を紹介します。
目元を触られるのを嫌がる猫も多いですが、目やにを放置していると、猫も痒がり、二次的に皮膚などを傷つけてしまうこともあります。
猫は自分ではめやにを取ることができないので、飼い主であるなたがしっかりと取ってあげましょう!
 また、目やにをとる時は、猫をリラックスさせた状態にすることも大切です。
突然目の付近を触ると猫ちゃんもびっくりしてしまいます!
そうなると、当然猫ちゃんも大人しく目やにを拭き取らせてはくれません。
最初は、体や顔まわりを撫でながら、猫ちゃんがリラックスしてきたなと感じたら、撫でる動作のようにスムーズに拭き取ってあげましょう。
また、目やにをとる時は、猫をリラックスさせた状態にすることも大切です。
突然目の付近を触ると猫ちゃんもびっくりしてしまいます!
そうなると、当然猫ちゃんも大人しく目やにを拭き取らせてはくれません。
最初は、体や顔まわりを撫でながら、猫ちゃんがリラックスしてきたなと感じたら、撫でる動作のようにスムーズに拭き取ってあげましょう。
 まずは、先住猫(今すでに家にいる猫)が新入りの猫に寛容かを見極めましょう。
例えば、先住猫が飼い主さんを独り占めしたいタイプの場合、新入り猫を受け入れることはストレスになります。
そのストレスから体調を崩したり、今までしなかったような悪さをしてしまう子も…。
多頭飼いが難しそうであれば、先住猫のために諦めるか、相性の良い猫を迎えるなど、考慮や工夫が必要です。
まずは、先住猫(今すでに家にいる猫)が新入りの猫に寛容かを見極めましょう。
例えば、先住猫が飼い主さんを独り占めしたいタイプの場合、新入り猫を受け入れることはストレスになります。
そのストレスから体調を崩したり、今までしなかったような悪さをしてしまう子も…。
多頭飼いが難しそうであれば、先住猫のために諦めるか、相性の良い猫を迎えるなど、考慮や工夫が必要です。
 では、ここからは実際に猫を多頭飼いするときに、どのように新入り猫を選べばいいのかを、相性という観点から紹介します。
新入り猫を探しているという飼い主さんは必読ですよ!
では、ここからは実際に猫を多頭飼いするときに、どのように新入り猫を選べばいいのかを、相性という観点から紹介します。
新入り猫を探しているという飼い主さんは必読ですよ!
 では、猫の年齢によって相性は変わってくるのでしょうか?
「子猫と成猫」の場合は、成猫の性格次第では比較的、良い相性が望めます。
成猫は自身の性格が確立しており、温厚な性格であれば、新入り子猫に対しては寛容に受け入れやすいからです。
一方で「シニア猫と子猫」になると注意が必要にもなります。
シニア猫は、毎日、新入りの子猫が遊びまわっているとそれをストレスに感じてしまうことがあるからです。
また、猫の年齢を見た時に、比較的同じ歳くらいの方が良いという見解もあります。
では、猫の年齢によって相性は変わってくるのでしょうか?
「子猫と成猫」の場合は、成猫の性格次第では比較的、良い相性が望めます。
成猫は自身の性格が確立しており、温厚な性格であれば、新入り子猫に対しては寛容に受け入れやすいからです。
一方で「シニア猫と子猫」になると注意が必要にもなります。
シニア猫は、毎日、新入りの子猫が遊びまわっているとそれをストレスに感じてしまうことがあるからです。
また、猫の年齢を見た時に、比較的同じ歳くらいの方が良いという見解もあります。
 次に、どのような性格の先住猫であれば、多頭飼いに向いているかを見ていきましょう。
先住猫が甘えん坊、または寂しがり屋な性格の場合は多頭飼いに向いていると言えます。
その子がお留守番などが多いのであれば尚更です。
先住猫も家に1匹でいるのは寂しいもの。
そんな中、もう1匹遊び相手にでもなってくれる猫が現れれば、不安やストレスも解消されます。
場合によっては、むしろ多頭飼いをしてあげた方が良いかもしれません!
次に、どのような性格の先住猫であれば、多頭飼いに向いているかを見ていきましょう。
先住猫が甘えん坊、または寂しがり屋な性格の場合は多頭飼いに向いていると言えます。
その子がお留守番などが多いのであれば尚更です。
先住猫も家に1匹でいるのは寂しいもの。
そんな中、もう1匹遊び相手にでもなってくれる猫が現れれば、不安やストレスも解消されます。
場合によっては、むしろ多頭飼いをしてあげた方が良いかもしれません!
 また、鼻水に伴う症状から猫にひそむ病気を見つけることもできます。
ここからは鼻水と合わせて確認しておきたい他の症状を見ていきましょう。
また、鼻水に伴う症状から猫にひそむ病気を見つけることもできます。
ここからは鼻水と合わせて確認しておきたい他の症状を見ていきましょう。
 猫の鼻水が出ているのに、それを放ったらかしにするわけにはいきませんよね?
ここからは、鼻水が出ている時にどのような対処や治し方があるのかを紹介します。
まずはこれを実践してみましょう。
猫の鼻水が出ているのに、それを放ったらかしにするわけにはいきませんよね?
ここからは、鼻水が出ている時にどのような対処や治し方があるのかを紹介します。
まずはこれを実践してみましょう。
 人が食べている食べ物の中にも、犬が食べて大丈夫な食べ物があります。
ではみかんはどうでしょうか?
結論、みかんは犬も食べることができます!
しかしいくつか注意しなければいけない点もあります。
最初に、みかんを食べるメリットと犬にみかんを与えるときの注意点をご紹介します。
みかんを食べさせる時は、メリットと注意点を把握した上で与えるようにしましょう。
人が食べている食べ物の中にも、犬が食べて大丈夫な食べ物があります。
ではみかんはどうでしょうか?
結論、みかんは犬も食べることができます!
しかしいくつか注意しなければいけない点もあります。
最初に、みかんを食べるメリットと犬にみかんを与えるときの注意点をご紹介します。
みかんを食べさせる時は、メリットと注意点を把握した上で与えるようにしましょう。
 みかんには100gあたり35mgのビタミンCが含まれるため、人間のビタミンC補給には適した果物です。
しかし犬は、ビタミンCを食事で摂取しなくても自身の体内で生成することができるため、積極的に与える必要はありません。
ただ、犬は年齢を重ねるごとにビタミンを生成する力が不足すると考えられており、さらに夏場はビタミンCが不足しやすい季節となります。
高齢の犬や、夏場には、みかんを与えてビタミンCを補給してあげるのも良いかもしれませんね。
また、みかんにはビタミンCの他にも健康維持が期待できる成分がたくさん含まれています。
みかんには100gあたり35mgのビタミンCが含まれるため、人間のビタミンC補給には適した果物です。
しかし犬は、ビタミンCを食事で摂取しなくても自身の体内で生成することができるため、積極的に与える必要はありません。
ただ、犬は年齢を重ねるごとにビタミンを生成する力が不足すると考えられており、さらに夏場はビタミンCが不足しやすい季節となります。
高齢の犬や、夏場には、みかんを与えてビタミンCを補給してあげるのも良いかもしれませんね。
また、みかんにはビタミンCの他にも健康維持が期待できる成分がたくさん含まれています。
 柑橘系には疲労回復効果が期待できる栄養素「クエン酸」が多く含まれています。
細胞が酸化し、それを修復させようとする状態が疲労に繋がります。
この細胞修復にクエン酸が使われるため、疲労回復につながると考えられています。
柑橘系には疲労回復効果が期待できる栄養素「クエン酸」が多く含まれています。
細胞が酸化し、それを修復させようとする状態が疲労に繋がります。
この細胞修復にクエン酸が使われるため、疲労回復につながると考えられています。
 犬にみかんを与えることは問題ないですが、以下の点を守らないと愛犬を危険な目に合わせてしまう可能性もあります。
必ずみかんを与える際は注意点があることを把握するようにしましょう。
犬にみかんを与えることは問題ないですが、以下の点を守らないと愛犬を危険な目に合わせてしまう可能性もあります。
必ずみかんを与える際は注意点があることを把握するようにしましょう。
 みかんは前述の通り、ビタミンCだけでなく水分も豊富に含まれています。
与え過ぎると下痢になるおそれがあります。
また、食物繊維も多いため、消化しにくいという側面もあります。
そのため、消化されずにうんちに混ざって出てくるという話もあります。
下痢や消化不良を起こさないためにも、与え過ぎには十分注意してください。
食べすぎを防ぐためにもトッピングやおやつにとどめることをおすすめします。
目安としては犬が1日に必要とするエネルギーの10%程度に収まるようにしましょう。
ドッグフードとの栄養バランスも考えながら取り入れてください。
ただし、みかんはカロリーが低めなので10%で計算すると量が多すぎ、お腹を壊す原因になりかねません。
必要なフード量の見た目が10%程度になるように調節する方法がおすすめです。
みかんは前述の通り、ビタミンCだけでなく水分も豊富に含まれています。
与え過ぎると下痢になるおそれがあります。
また、食物繊維も多いため、消化しにくいという側面もあります。
そのため、消化されずにうんちに混ざって出てくるという話もあります。
下痢や消化不良を起こさないためにも、与え過ぎには十分注意してください。
食べすぎを防ぐためにもトッピングやおやつにとどめることをおすすめします。
目安としては犬が1日に必要とするエネルギーの10%程度に収まるようにしましょう。
ドッグフードとの栄養バランスも考えながら取り入れてください。
ただし、みかんはカロリーが低めなので10%で計算すると量が多すぎ、お腹を壊す原因になりかねません。
必要なフード量の見た目が10%程度になるように調節する方法がおすすめです。
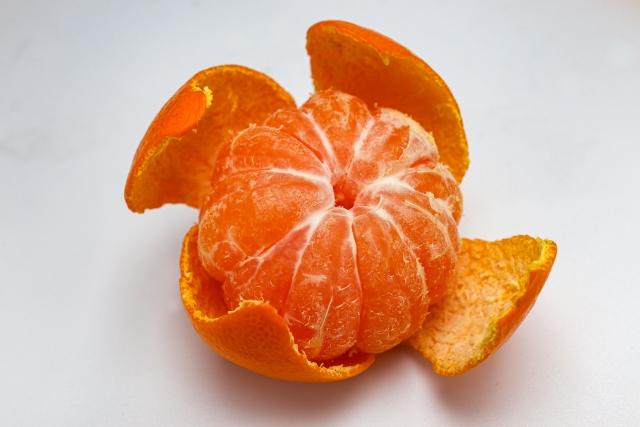 みかんの果実や薄皮には中毒性はないものの、外皮や種などには中毒性のある物質が含まれています。
与えるときは、皮や種の部分を取り除くのを忘れないようにしてください。
ちなみに、みかんに関わらず、柑橘系全般の外皮には、犬にとって中毒性のあるソラレンという物質が含まれています。
過剰摂取することで、嘔吐や下痢などの症状が現れる可能性があるので、与える際には外皮をむき、果実部分だけを与えるようにしましょう。
みかんの果実や薄皮には中毒性はないものの、外皮や種などには中毒性のある物質が含まれています。
与えるときは、皮や種の部分を取り除くのを忘れないようにしてください。
ちなみに、みかんに関わらず、柑橘系全般の外皮には、犬にとって中毒性のあるソラレンという物質が含まれています。
過剰摂取することで、嘔吐や下痢などの症状が現れる可能性があるので、与える際には外皮をむき、果実部分だけを与えるようにしましょう。
 みかんの缶詰やゼリー・ジュース等の加工品には砂糖が多く含まれていることがあるため、愛犬には与えないようにしましょう。
与える場合には、加工していないみかんを適量与えるのが安心です。
・みかんゼリー
・みかんジュース
・オレンジジュース
・冷凍みかん
・みかんアイス
などには注意が必要です。
みかんの缶詰やゼリー・ジュース等の加工品には砂糖が多く含まれていることがあるため、愛犬には与えないようにしましょう。
与える場合には、加工していないみかんを適量与えるのが安心です。
・みかんゼリー
・みかんジュース
・オレンジジュース
・冷凍みかん
・みかんアイス
などには注意が必要です。
 オレンジやグレープフルーツをはじめとする柑橘類は、犬が食べても問題はないですが、消化に良くないので熱心に与える必要はありません。
また、薬を服用中の犬にはグレープフルーツを食べさせないでください。
「フラノクマリン」という成分によって薬の分解が遅くなり、薬が効きすぎてしまう恐れがあります。
オレンジやグレープフルーツをはじめとする柑橘類は、犬が食べても問題はないですが、消化に良くないので熱心に与える必要はありません。
また、薬を服用中の犬にはグレープフルーツを食べさせないでください。
「フラノクマリン」という成分によって薬の分解が遅くなり、薬が効きすぎてしまう恐れがあります。
 離乳した子犬ならみかんを与えても大丈夫です。
ただ、酸味が強く、胃を荒らすこともありますので、様子を見ながら与え、量もほんの少しにしましょう。
また、「老犬」にはみかんの絞り汁を与えると食べやすくなります。
いずれの場合も、下痢や嘔吐、軟便が見られたらみかんを与えるのをやめて、動物病院を受診してください。
そのほか、シニア犬や薬を服用している犬の場合も、ビタミンCが不足しがちだと言われています。
犬がシニア世代に入っている、もしくは薬を服用させているという場合は、みかんを与えてみましょう。
ただし、薬を服用している場合は、食べ合わせの問題があるため、一度かかりつけの獣医師に相談してください。
離乳した子犬ならみかんを与えても大丈夫です。
ただ、酸味が強く、胃を荒らすこともありますので、様子を見ながら与え、量もほんの少しにしましょう。
また、「老犬」にはみかんの絞り汁を与えると食べやすくなります。
いずれの場合も、下痢や嘔吐、軟便が見られたらみかんを与えるのをやめて、動物病院を受診してください。
そのほか、シニア犬や薬を服用している犬の場合も、ビタミンCが不足しがちだと言われています。
犬がシニア世代に入っている、もしくは薬を服用させているという場合は、みかんを与えてみましょう。
ただし、薬を服用している場合は、食べ合わせの問題があるため、一度かかりつけの獣医師に相談してください。
 みかんのメリットや与え方の注意点などをご紹介しました。
注意事項を押さえれば、犬にみかんを与えることは問題ありません。
ただし、主食はあくまでもドッグフードなどであり、みかんを主食にしないように注意しましょう。
食べさせる場合には、まずは少量のみ・果肉部分のみをおやつとしてあげてください。
愛犬の様子をきちんと観察しつつ、最適なあげ方をするようにしましょう!
みかんのメリットや与え方の注意点などをご紹介しました。
注意事項を押さえれば、犬にみかんを与えることは問題ありません。
ただし、主食はあくまでもドッグフードなどであり、みかんを主食にしないように注意しましょう。
食べさせる場合には、まずは少量のみ・果肉部分のみをおやつとしてあげてください。
愛犬の様子をきちんと観察しつつ、最適なあげ方をするようにしましょう!