子犬のトイプードルの体重推移
 生まれて数ヶ月のトイプードルの子犬のあまりの可愛らしさに、新しい家族としてお迎えした経験のあるご家族も多いかと思います。
ふわふわの巻毛に丸々と太った体つき。
そんな小さい体で毎日大騒ぎをする元気の良さに振り回されながら、健康で元気に育ってくれているのか、特に初めて迎えたワンちゃんだとわからないことも多くて不安を感じるかもしれません。
こちらの記事では、そんな飼い主さんの不安を取り払い、ワンちゃんが一生を元気でいてくれるためのフードや体重推移をご紹介してきます。
個体差がありますので、「絶対」なことはありません。あくまで参考としてご覧くださいね。
生まれて数ヶ月のトイプードルの子犬のあまりの可愛らしさに、新しい家族としてお迎えした経験のあるご家族も多いかと思います。
ふわふわの巻毛に丸々と太った体つき。
そんな小さい体で毎日大騒ぎをする元気の良さに振り回されながら、健康で元気に育ってくれているのか、特に初めて迎えたワンちゃんだとわからないことも多くて不安を感じるかもしれません。
こちらの記事では、そんな飼い主さんの不安を取り払い、ワンちゃんが一生を元気でいてくれるためのフードや体重推移をご紹介してきます。
個体差がありますので、「絶対」なことはありません。あくまで参考としてご覧くださいね。
子犬の平均的な体重推移
生まれたばかりのトイプードルの子犬の体重は、数百グラムという小ささ。
お母さん犬のおっぱいを飲みながら、一般の家庭に家族として迎えられる頃として大体、2~3ヶ月くらいと考えると体重はおよそ1kg前後です。
ペットショップやブリーダーからやってきた子犬は、すでに離乳を終えてフードを口にしていますので、ここからは早いスピードで体重も増加をしていきます。
生後3ヶ月:約2kg前後
半年:約2~4kg前後
8ヶ月:2.5~3.5kg前後
8~9ヶ月過ぎ:成長も落ち着きはじめる
1才:ほぼ成長は止まり、このワンちゃんの基本の体重となる
成犬の平均体重について
 小型犬は、10ヶ月を過ぎると成犬の仲間入りをします。
ですが運動量が増えてくるので、筋肉や脂肪など蓄えるのもこの時期です。
1才を過ぎてからも多少の体重増加は想像の範囲となりますので、愛犬の体重が増えていても心配せずに、成長を見守りましょう。
逆に体重が減っていったりあまりにも急激な体重増加などが見受けられたら、早めにかかりつけの動物病院で診てもらってください。
小型犬は、10ヶ月を過ぎると成犬の仲間入りをします。
ですが運動量が増えてくるので、筋肉や脂肪など蓄えるのもこの時期です。
1才を過ぎてからも多少の体重増加は想像の範囲となりますので、愛犬の体重が増えていても心配せずに、成長を見守りましょう。
逆に体重が減っていったりあまりにも急激な体重増加などが見受けられたら、早めにかかりつけの動物病院で診てもらってください。
トイプードルなのかどうかは体高で決まる
プードルは体高(大きさ)によってタイプが分かれており、一般社団法人ジャパンケネルクラブ(JKC)に登録されているプードルのサイズ別名称は次の通りです。
・トイプードル 体高28cm~24cm
・ミニチュアプードル 体高35cm~28cm
・ミディアムプードル 体高45cm~35cm
・スタンダードプードル 体高60~45cm
トイプードルや大型に分類されるスタンダードプードルは街中でもよく見かけたり、名前を聞くことは多いですよね。
中型犬の大きさがあるミニチュアプードルやミディアムプードルはJKCに登録さている個体数も少なく、飼われてている数が圧倒的に少ないので、ちょっとレアなサイズです。
また、トイプードルの中でも圧倒的に小さいサイズのティーカップやタイニーなどの名称が付いているサイズの子がいます。
こちらはJKCに公認された大きさではないので、トイプードルのくくりになります。
トイプードルの成長に合わせたフードや育て方
 健康で元気に育てるために、適切な種類のフードを選び、適正量を正確に与える必要があります。
食に興味を持ち始めるこの頃に、欲しがるだけ与えてしまうと肥満になり成犬になった後に様々な問題が出る場合もありますので、飼い主さんが責任を持って管理しましょう。
健康で元気に育てるために、適切な種類のフードを選び、適正量を正確に与える必要があります。
食に興味を持ち始めるこの頃に、欲しがるだけ与えてしまうと肥満になり成犬になった後に様々な問題が出る場合もありますので、飼い主さんが責任を持って管理しましょう。
離乳食を与えるのは歯が生えてきたら
現行の子犬の引き渡し月齢規制や、多くの飼い主さんがペットショップやブリーダーから子犬をお迎えする時期は、乳歯も生え揃って離乳食を始めている頃となります。
なので、お迎えした日から、ミルクではなく離乳食として、ドライフードをお湯でふやかして食べやすくしてあげましょう。
フードの種類や分量は、ペットショップやブリーダーに確認して出来るだけ同じものを与えます。
ドッグフードは大人の歯が生えてきたら
 乳歯が抜けて大人の歯・永久歯が生えはじめたら、通常のドッグフードを与えていきます。
時期として生後4ヶ月ごろから生え変わり始めますので、様子を見ながら少しずつふやかすフードを硬めにしていき、通常のフードに切り替えます。
個体差がありますが、だいたい1才前後には完全に生え変わりが完了するでしょう。
フードには対象年齢が決められているタイプが多く、「パピー用」「成犬用」「シニア」などおおまかなくくりや、ドライ・ウェット・セミモイストの水分量の違いによって分けられています。
対象年齢がないフードもありますが、フードを食べ始めの頃は、パピータイプがベストです。
ドライは歯の汚れをキレイにしてくれる効果も期待でき、万が一の災害にも保存が効くので食べ慣れておくと良いかもしれません。
乳歯が抜けて大人の歯・永久歯が生えはじめたら、通常のドッグフードを与えていきます。
時期として生後4ヶ月ごろから生え変わり始めますので、様子を見ながら少しずつふやかすフードを硬めにしていき、通常のフードに切り替えます。
個体差がありますが、だいたい1才前後には完全に生え変わりが完了するでしょう。
フードには対象年齢が決められているタイプが多く、「パピー用」「成犬用」「シニア」などおおまかなくくりや、ドライ・ウェット・セミモイストの水分量の違いによって分けられています。
対象年齢がないフードもありますが、フードを食べ始めの頃は、パピータイプがベストです。
ドライは歯の汚れをキレイにしてくれる効果も期待でき、万が一の災害にも保存が効くので食べ慣れておくと良いかもしれません。
フードをシニア用に切り替えるタイミング
子犬期・成犬期を元気に過ごした後、益々の健康を願いフードをシニア専用に切り替える必要があります。
人間でいうと、若い時は脂やお肉など何を食べても太らず美味しく食べていた食事も、ある一定の年齢を超えるともう少し落ち着いた食事を好むようになりますよね。
成犬と同じフードを同じ分量与えると、カロリーの摂りすぎによる肥満や胃腸障害などで下痢を起こすこともあります。
小型犬は、7才を過ぎるとシニアとして食事の見直しを考える時期となります。
シニア専用フードへ切り替えを考えましょう。
まだまだ若いから大丈夫、と考えがちですが、見た目と違って少しづつ体には変化が出始める頃です。
早め早めのケアが、愛犬の満足な毎日の生活に繋がっていくことを忘れずに対処していきたいですね。
まとめ
 人間以上のスピードで、子犬期からシニアまであっという間に駆け抜けていくワンちゃんの美味しい毎日を安全に過ごしてもたう為に、飼い主さんが様子をよく見ながら、その時々に必要な判断をすることが大切です。
家族である愛犬の健康的な食生活を守ってあげたいですね。
人間以上のスピードで、子犬期からシニアまであっという間に駆け抜けていくワンちゃんの美味しい毎日を安全に過ごしてもたう為に、飼い主さんが様子をよく見ながら、その時々に必要な判断をすることが大切です。
家族である愛犬の健康的な食生活を守ってあげたいですね。
猫にブロッコリーを与えるメリット
 猫にブロッコリーを与えてもいいのでしょうか?
ブロッコリーは栄養価が高くて、わたしたちは利用しやすい野菜ですが猫にとってはどうなのか、気になります。
結論から言うと、ブロッコリーを猫に与える際のメリットとしては、老化防止や抗ガン作用、便秘解消や貧血の予防などが挙げられます。
ブロッコリーはビタミンやカロチン、食物繊維が豊富なので、猫にとっても体に良い効果が期待される野菜なのです。
つまり与えた場合のメリットは大きそうですね。
ブロッコリーには上記のような様々なメリットがあるためキャットフードだけという飼い主さんも積極的に与えてみたい食べ物です。
ただし、守るべき注意点もあるのでこの記事を参考にしてください。
猫にブロッコリーを与えてもいいのでしょうか?
ブロッコリーは栄養価が高くて、わたしたちは利用しやすい野菜ですが猫にとってはどうなのか、気になります。
結論から言うと、ブロッコリーを猫に与える際のメリットとしては、老化防止や抗ガン作用、便秘解消や貧血の予防などが挙げられます。
ブロッコリーはビタミンやカロチン、食物繊維が豊富なので、猫にとっても体に良い効果が期待される野菜なのです。
つまり与えた場合のメリットは大きそうですね。
ブロッコリーには上記のような様々なメリットがあるためキャットフードだけという飼い主さんも積極的に与えてみたい食べ物です。
ただし、守るべき注意点もあるのでこの記事を参考にしてください。
猫にブロッコリーを与える時の注意点
 与えるメリットが多いブロッコリーですが、やはり猫にとっては注意点があります。
人間と同じ体ではなく、体重もずっと軽いので必ず注意点を守ってあげてください。
どんな食べ物でもまずはアレルギーのチェックが必要です。
そして持病があったり、体調が悪い時にはメリットよりもデメリットが大きくなることもあります。
次にブロッコリーを与えてはいけない猫の状態について、調理方法、量などを解説しますのでよく読んで参考にしてください。
与えるメリットが多いブロッコリーですが、やはり猫にとっては注意点があります。
人間と同じ体ではなく、体重もずっと軽いので必ず注意点を守ってあげてください。
どんな食べ物でもまずはアレルギーのチェックが必要です。
そして持病があったり、体調が悪い時にはメリットよりもデメリットが大きくなることもあります。
次にブロッコリーを与えてはいけない猫の状態について、調理方法、量などを解説しますのでよく読んで参考にしてください。
特定の条件の猫には与えない
特定の条件の猫とは、
・ブロッコリーのアレルギーを持つ猫
・子猫・シニア猫
・甲状腺機能低下症の猫
・体調が優れない猫
などのことです。
当てはまる猫にはブロッコリーを与えないようにしましょう。
ブロッコリーにはゴイトロゲンという成分が含まれており、それが甲状腺機能を低下させることになります。
またスルフォラファンという成分もヨウ素の取り込みを阻害するもので、甲状腺機能低下症を悪化させる可能性があります。
せっかく健康のためにと思ったブロッコリーでも、持病がある猫には逆効果となりますので注意しましょう。
茹でてから食べさせる
 次に調理方法の注意です。
肉食の猫は野菜を消化するのは苦手です。
さらにブロッコリーは、生の状態だと非常に硬く、内臓に負担をかけてしまい、消化不良の原因となる場合があるので、茹でて与えましょう。
あまり長時間ゆでてしまうと、ビタミンが消失するので短時間ゆで、できればその茹で汁も一緒にご飯にかけたりすると良いでしょう。
電子レンジを使うのもおすすめです。
少量の水をかけてレンジにかければビタミンの損失も少なくてすみます。
次に調理方法の注意です。
肉食の猫は野菜を消化するのは苦手です。
さらにブロッコリーは、生の状態だと非常に硬く、内臓に負担をかけてしまい、消化不良の原因となる場合があるので、茹でて与えましょう。
あまり長時間ゆでてしまうと、ビタミンが消失するので短時間ゆで、できればその茹で汁も一緒にご飯にかけたりすると良いでしょう。
電子レンジを使うのもおすすめです。
少量の水をかけてレンジにかければビタミンの損失も少なくてすみます。
食べさせ過ぎない
栄養があると聞くとついたくさんあげたほうがいいのかなと思いがちですが、食べすぎはよくありません。
なぜなら猫は野菜を消化することが得意ではないからです。
そのため、一度にブロッコリーをたくさん食べさせると、消化不良を引き起こし、嘔吐や下痢といった症状が出ます。
茹でたブロッコリーを小さじ1杯程度が適量かと思われます。
そして茹でたブロッコリーは細かく刻んであげましょう。
人間用のサラダなどにも使う時に少しだけ取り分けて刻むと手間もかかりません。
猫はブロッコリーの葉や茎を食べても大丈夫?
 ブロッコリーの葉や茎についても猫に食べさせても特に問題はありません。
特に葉は蕾の部分よりもポリフェノールが多く含まれています。
ポリフェノールは抗酸化作用があり、老化防止に役立つ栄養価の高い成分です。
ただ農薬がかかっていることもあるのできれいに水洗いした後、なるべく安全な内葉だけを食べさせましょう。
茎の場合は、皮を剥いて、細かく切って食べさせます。
茎は外側が硬いので、茹でてから中側を細かく刻むと良いでしょう。
ブロッコリーの葉や茎についても猫に食べさせても特に問題はありません。
特に葉は蕾の部分よりもポリフェノールが多く含まれています。
ポリフェノールは抗酸化作用があり、老化防止に役立つ栄養価の高い成分です。
ただ農薬がかかっていることもあるのできれいに水洗いした後、なるべく安全な内葉だけを食べさせましょう。
茎の場合は、皮を剥いて、細かく切って食べさせます。
茎は外側が硬いので、茹でてから中側を細かく刻むと良いでしょう。
猫はブロッコリースプラウトやカリフラワーを食べても良い?
 ブロッコリースプラウトはブロッコリーの新芽のことで、とても栄養価が高く人間や犬には問題ありませんが、猫はブロッコリースプラウトを食べた際、嘔吐や炎症などを引き起こす可能性があります。
そのためブロッコリースプラウトは避けた方が無難です。
一方、カリフラワーはブロッコリーと同じアブラナ科の野菜です。
ビタミンも多く食べるメリットは同じですが、与えすぎると甲状腺の機能を低下させることになるので少量を食べさせるようにしましょう。
ブロッコリースプラウトはブロッコリーの新芽のことで、とても栄養価が高く人間や犬には問題ありませんが、猫はブロッコリースプラウトを食べた際、嘔吐や炎症などを引き起こす可能性があります。
そのためブロッコリースプラウトは避けた方が無難です。
一方、カリフラワーはブロッコリーと同じアブラナ科の野菜です。
ビタミンも多く食べるメリットは同じですが、与えすぎると甲状腺の機能を低下させることになるので少量を食べさせるようにしましょう。
まとめ
 猫にブロッコリーを与えることの効果や注意点などを説明しました。
同じブロッコリーでもスプラウトは良くないことは覚えておきたいです。
ブロッコリーは栄養価も高く手に入りやすい野菜なので、健康維持に役立てましょう。
メリットも多いですが、猫の状態によってはデメリットになってしまうことがあります。
健康観察をしっかりして注意点を守り、適量を食べさせるようにしてください。
飼い主さんとの楽しみの一つになるといいですね。
猫にブロッコリーを与えることの効果や注意点などを説明しました。
同じブロッコリーでもスプラウトは良くないことは覚えておきたいです。
ブロッコリーは栄養価も高く手に入りやすい野菜なので、健康維持に役立てましょう。
メリットも多いですが、猫の状態によってはデメリットになってしまうことがあります。
健康観察をしっかりして注意点を守り、適量を食べさせるようにしてください。
飼い主さんとの楽しみの一つになるといいですね。
猫が飼い主にすりすりする理由
 猫が飼い主に対して体をすりするするには理由があります。
飼い猫であったり、人懐っこい猫であれば行いやすい行動ですが、さまざまな理由から行っています。
次に、猫が飼い主に体をすりすりしてくる理由について紹介します。
なぜ体をこすりつけてくるのかを知りたい人は参考にしてください。
こすり付けてくる理由を知ることで猫の気持ちを知ることができます。
コミュニケーション方法の一つでもあるため、こすり付けた際に邪険にしないようにしましょう。
猫が飼い主に対して体をすりするするには理由があります。
飼い猫であったり、人懐っこい猫であれば行いやすい行動ですが、さまざまな理由から行っています。
次に、猫が飼い主に体をすりすりしてくる理由について紹介します。
なぜ体をこすりつけてくるのかを知りたい人は参考にしてください。
こすり付けてくる理由を知ることで猫の気持ちを知ることができます。
コミュニケーション方法の一つでもあるため、こすり付けた際に邪険にしないようにしましょう。
セルフマッサージ
猫が体をすりすりする理由にセルフマッサージである可能性があります。
猫は体を撫でられることが好きな動物であり、撫でてもらうことを催促するために体をすりすりしてきます。
顔をこすりつけるのであれば顔を撫でてほしい気持ちであり、体をこすりつけるのであれば体を撫でてほしい気持ちの表れです。
また、撫でてほしい気持ちとは別で体を飼い主にすりすりすることで気持ちいいと感じている場合もあります。
体が痒い際に家の柱などですりすりすることもあります。
挨拶
人は挨拶する際に言葉を発したり、行動で示しますが、猫の場合は体をこすりつけて挨拶を行います。
どのような猫に対しても体をこすりつける挨拶をするのではなく、目上の者に対して行う習性があります。
そのため、飼い主に体をこすりつけるのであれば飼い主のことを上の立場であることを示している可能性が高く、正しい従者関係が築けている証拠です。
猫が飼い主よりも立場が上という考えでは懐きにくくなり、ワガママな性格になりやすいです。
スキンシップ
 猫は人に対してだけではなく猫同士でも体をこすりつけるようにします。
猫同士が体をこすりつけることをアロラビングと呼ばれており、スキンシップの一環と考えられています。
人でいうハグと同じであり、信頼している相手に対して行う行動でもあります。
人に対してスキンシップしてくることはそれだけ飼い主のことを信頼している証拠です。
顔をこすりつける場合は撫でてほしい気持ちや構ってほしい気持ちの表れでもあり、一緒に遊んであげましょう。
猫は人に対してだけではなく猫同士でも体をこすりつけるようにします。
猫同士が体をこすりつけることをアロラビングと呼ばれており、スキンシップの一環と考えられています。
人でいうハグと同じであり、信頼している相手に対して行う行動でもあります。
人に対してスキンシップしてくることはそれだけ飼い主のことを信頼している証拠です。
顔をこすりつける場合は撫でてほしい気持ちや構ってほしい気持ちの表れでもあり、一緒に遊んであげましょう。
マーキング
体をこすりつけることはマーキングの意味合いがある場合もあります。
猫は自分のものと主張する場合に体をこすりつけ対象に匂いを付けます。
猫には臭腺がいくつかあり、頬の部分にもあるため、頬をこすりつけている場合はマーキングされている可能性が高いです。
飼い主のことを自分のものと思われていることは飼い主にとって喜ばしいことではないでしょうか。
地面などに体をこすりつけている場合は体が痒い可能性もありますが、縄張りの主張をしている場合もあります。
猫が物や床に体をこすりつける理由
 猫は人に対してだけではなく、床や物に対しても体をこすりつける場合もあります。
人に体をこすりつける理由は上記で紹介しましたが、床や物が対象の場合は理由が異なります。
そのため、床や物に対して頻繁に体をこすりつけている場合は理由を把握しておくことをおすすめします。
次に、猫が床や物に体をこすりつける理由について紹介します。
猫が本来行う行動でもあるため、問題視する必要性は低いですが、痒みが原因の場合は病気の可能性もあり、注意が必要です。
猫は人に対してだけではなく、床や物に対しても体をこすりつける場合もあります。
人に体をこすりつける理由は上記で紹介しましたが、床や物が対象の場合は理由が異なります。
そのため、床や物に対して頻繁に体をこすりつけている場合は理由を把握しておくことをおすすめします。
次に、猫が床や物に体をこすりつける理由について紹介します。
猫が本来行う行動でもあるため、問題視する必要性は低いですが、痒みが原因の場合は病気の可能性もあり、注意が必要です。
興奮
猫は興奮すると物や床に体をこすりつけるようにします。
キャットニップやまたたびの香りには猫を恍惚状態にする成分が含まれており、興奮状態になったり、軽い痙攣の症状が現れます。
キャットニップやまたたびの匂いがないにも関わらず、興奮している場合は歯磨き粉や果物のキウイの匂いが原因の可能性があります。
歯磨き粉やキウイにはまたたびの香りと同じ成分があり、同じく猫は興奮状態に陥ってしまいます。
成分が体から抜ければ興奮状態も沈静化してきます。
発情期
いままで床に体をこすりつける行動をしていなかったにも関わらず、頻繁に行うようになった場合は発情期が訪れた可能性が高いです。
猫は発情期に入ると体を床や物にこすりつける習性があります。
当然発情期は過ぎれば体をこすりつけなくなります。
また、去勢手術や避妊手術を行っていれば発情期も訪れなくなるため、発情期が原因で体をこすりつけることもなくなります。
放し飼いで外で妊娠させたくないのであれば体をこすりつける頻度を観察し、発情期が訪れれば外出させないようにしましょう。
綺麗にしたい
 猫は元々砂浴びという行動をする習性があり、体をこすりつけることで汚れを落とす効果があります。
そのため、床などに体をこすりつけている場合は体を綺麗にしたいという気持ちがある可能性が高く、ノミなどの影響で痒みの症状が現れている場合もあります。
綺麗にするために体をこすりつける場合はフローリングのようなツルツルした場所ではなく、カーペットやアスファルトなど汚れが落ちやすい環境で行う場合が多いことが特徴的です。
猫は元々砂浴びという行動をする習性があり、体をこすりつけることで汚れを落とす効果があります。
そのため、床などに体をこすりつけている場合は体を綺麗にしたいという気持ちがある可能性が高く、ノミなどの影響で痒みの症状が現れている場合もあります。
綺麗にするために体をこすりつける場合はフローリングのようなツルツルした場所ではなく、カーペットやアスファルトなど汚れが落ちやすい環境で行う場合が多いことが特徴的です。
痒い
体を痒いとさまざまな物に対して体をこすりつけるようにして、痒みを軽減させようとします。
猫は人とは異なり、痒い場所に手が届かないため、物や床などを利用して痒みをとります。
皮膚に痒みが現れることは何かしらの異常が皮膚に発生している可能性があり、皮膚の状態をチェックすることをおすすめします。
皮膚病を発症しているのであれば早急に治療を開始する必要があり、悪化する前に完治させましょう。
ノミやダニ、汚れなどで痒みが起きやすいです。
番外編!猫の変わったすりすりとは?
 猫はさまざまな理由ですりすりを行う場合が多く、上記で紹介した人に対してすりすりする場合もあれば物や床に行うこともあります。
それ以外にも変わったすりすりの仕方をすることもあり、それぞれに理由も存在しています。
次に、変わったすりすりをする理由について紹介します。
さまざまなすりすりする理由を知ることで猫の気持ちを把握することもでき、ストレスを与えてしまうことも軽減できます。
一風変わったすりすりの仕方をする猫がいる場合は参考にしてください。
猫はさまざまな理由ですりすりを行う場合が多く、上記で紹介した人に対してすりすりする場合もあれば物や床に行うこともあります。
それ以外にも変わったすりすりの仕方をすることもあり、それぞれに理由も存在しています。
次に、変わったすりすりをする理由について紹介します。
さまざまなすりすりする理由を知ることで猫の気持ちを把握することもでき、ストレスを与えてしまうことも軽減できます。
一風変わったすりすりの仕方をする猫がいる場合は参考にしてください。
すりすり&噛む
すりすりしながら噛む場合は甘えたい気持ちやじゃれあいたい気持ちの表れです。
そのため、一緒に遊んであげたり、撫でてあげることで猫は満足します。
しかし、ストレスが溜まっている時にもすりすりしながら噛んでくることもあり、どちらの理由で行っているのかを把握する必要があります。
撫でていると猫は喜ぶ場合は多いですが、撫で方がしつこかったり、痛い部分に触れられると当然ストレスを感じてしまい、やめてほしい気持ちの表れですりすりと噛む行動をします。
すりすり&頭突き
すりすりしたり頭突きすることは愛情表現の一種と考えられています。
いきなり頭突きされると驚いてしまうことも多く、それなりの勢いで頭突きしてくるため、痛さを感じてしまうことも多いです。
一見敵意むき出しの行動ではありますが、愛情表現の一種であり、飼い主のことを信頼している証拠です。
そのため、頭突きされても叱ることは逆効果になってしまうため、撫でてあげたり、構ってあげるようにしましょう。
猫はさまざまな行動で愛情表現を行いますが、頭突きは最上位の愛情表現でもあります。
まとめ
 猫はさまざまな理由から体をこすりつける行動を行います。
愛情表現であったり、単に体が痒いだけなどさまざまな理由が考えられ、どの理由が当てはまるのかを考えるようにしましょう。
体をこすりつけることは何かしらの気持ちの表れである可能性が高いですが、痒みが理由の場合は皮膚に異常が起きている可能性もあり、一度皮膚をチェックするようにしましょう。
赤く炎症していると治療を受ける必要もあるため、定期的に皮膚チェックを行うことをおすすめします。
猫はさまざまな理由から体をこすりつける行動を行います。
愛情表現であったり、単に体が痒いだけなどさまざまな理由が考えられ、どの理由が当てはまるのかを考えるようにしましょう。
体をこすりつけることは何かしらの気持ちの表れである可能性が高いですが、痒みが理由の場合は皮膚に異常が起きている可能性もあり、一度皮膚をチェックするようにしましょう。
赤く炎症していると治療を受ける必要もあるため、定期的に皮膚チェックを行うことをおすすめします。
猫と電車に乗る方法
 猫と電車に乗る機会は少ないですが、遠出する際や病院などに連れて行く際に利用する場合もあります。
電車は公共の移動手段であるため、周りの乗客に配慮する必要があります。
ルールを守り、事前に準備する物を用意していれば猫を電車に乗せることは可能です。
トラブルを未然に防ぐためにも猫を電車に乗せる必要があるのであればエチケットを把握しつつ猫を電車に慣れさせるなどを行わなければなりません。
次に、猫と電車に乗る方法について紹介しまします。
猫と電車に乗る機会は少ないですが、遠出する際や病院などに連れて行く際に利用する場合もあります。
電車は公共の移動手段であるため、周りの乗客に配慮する必要があります。
ルールを守り、事前に準備する物を用意していれば猫を電車に乗せることは可能です。
トラブルを未然に防ぐためにも猫を電車に乗せる必要があるのであればエチケットを把握しつつ猫を電車に慣れさせるなどを行わなければなりません。
次に、猫と電車に乗る方法について紹介しまします。
お出かけグッズに慣れさせる
猫と電車に乗る場合はキャリーバッグやハーネスを利用する場合が多いため、それらのグッズに慣れさせておくようにしましょう。
特に、キャリーバッグの中に入れて電車移動する場合が多いため、キャリーバッグ慣れさせることは必須です。
お出かけグッズに慣れさせないままキャリーバッグで移動させることは猫が暴れるリスクが高いため、行わないようにしましょう。
キャリーバッグに入れて移動する練習をしたり、キャリーバッグ内の環境を整えるなどの工夫をしましょう。
ホームでも猫に気配りを
 電車内でも気を付けなければならないことが多いですが、忘れてしまいがちなホームでの気配りも重要です。
ホームは多くの人が行き来したり、アナウンスなどで騒がしい環境です。
特に、ホームを通過する電車の音は騒音であり、猫にストレスを与えてしまいます。
騒がしい環境は猫が嫌う環境であるため、キャリーバッグにタオルなどをかけてできるだけ騒音を感じさせないようにしましょう。
騒音を聞くと興奮してしまい、暴れてしまうリスクが高く、落ち着くまで時間がかかってしまいます。
電車内でも気を付けなければならないことが多いですが、忘れてしまいがちなホームでの気配りも重要です。
ホームは多くの人が行き来したり、アナウンスなどで騒がしい環境です。
特に、ホームを通過する電車の音は騒音であり、猫にストレスを与えてしまいます。
騒がしい環境は猫が嫌う環境であるため、キャリーバッグにタオルなどをかけてできるだけ騒音を感じさせないようにしましょう。
騒音を聞くと興奮してしまい、暴れてしまうリスクが高く、落ち着くまで時間がかかってしまいます。
乗車中に気をつけたいこと
猫と電車に乗る際に最も注意する必要があるときが乗車中です。
最も長い時間を乗車に費やす場合が多いため、それだけ注意点も多くなっています。
乗車中はホームのように騒がしい環境ではありませんが、揺れが激しいため、いかに揺れを感じさせないようにするかが重要です。
可能であれば膝の上にキャリーバッグを置き、揺れを軽減させるようにしましょう。
混雑しており、座ることができない場合は、電車の先頭か最後尾の隅に移動するようにしましょう。
電車は中心が最も揺れやすいため、前後どちらかに移動するだけでも揺れが抑えられます。
新幹線で指定席を予約すのであれば先頭車両の席を指定するようにしましょう。
揺れを軽減することでストレスを与えにくくでき、酔いも防ぐことができます。
猫と電車に乗る時の注意点やマナー
 猫と電車に乗るときの注意点やマナーを身につけることでトラブルを未然に防いだり、猫に余計なストレスを与えにくくなります。
都心部は電車内が混雑している場合が多いため、より注意点やマナーを身につける必要が高いです。
また、できるだけ混雑する時間帯を避けて電車を利用することも必要な配慮です。
次に、猫と電車に乗る際の注意点とマナーについて紹介します。
初めて猫と電車に乗ろうと考えている人は参考にして、周りの乗客に迷惑をかけないようにしましょう。
猫と電車に乗るときの注意点やマナーを身につけることでトラブルを未然に防いだり、猫に余計なストレスを与えにくくなります。
都心部は電車内が混雑している場合が多いため、より注意点やマナーを身につける必要が高いです。
また、できるだけ混雑する時間帯を避けて電車を利用することも必要な配慮です。
次に、猫と電車に乗る際の注意点とマナーについて紹介します。
初めて猫と電車に乗ろうと考えている人は参考にして、周りの乗客に迷惑をかけないようにしましょう。
猫をかまいすぎない
初めて猫と電車に乗ると猫のことが心配になり、ついついキャリーバッグの中を覗いてしまいがちです。
しかし、猫のことが心配であっても落ちついているのであればそのまま、構いすぎないようにしましょう。
猫に構ってしまうと猫が甘えてきたり、周りの環境に気づいて興奮してしまうリスクがあります。
乗車中はいかに静かにさせることが重要になるため、猫に触れたり、話しかけないようにしましょう。
周りの乗客の中には猫が一緒に電車に乗っていることを知るだけでも不快に感じてしまう場合もあり、いかに猫と一緒にいることを感じさせないかも重要です。
鳴き声がうるさい場合は一旦外へ
 普段とは違う環境になると猫は不安になりやすく、普段よりも大きな声で鳴いてしまう場合があります。
また、興奮してしまう場合も暴れてしまったり、声を荒げてしまう可能性が高く、うるさくなってしまいます。
そのような場合は周りの乗客の迷惑になってしまうため、可能であればいったん外に出るようにしましょう。
一度うるさく騒ぎ始めてしまうと電車の中では落ち着く可能性は低く、ホームなどで落ち着くまで待つ必要があります。
そのため、電車に乗り遅れる可能性もあり、早めに出かけることも大切です。
普段とは違う環境になると猫は不安になりやすく、普段よりも大きな声で鳴いてしまう場合があります。
また、興奮してしまう場合も暴れてしまったり、声を荒げてしまう可能性が高く、うるさくなってしまいます。
そのような場合は周りの乗客の迷惑になってしまうため、可能であればいったん外に出るようにしましょう。
一度うるさく騒ぎ始めてしまうと電車の中では落ち着く可能性は低く、ホームなどで落ち着くまで待つ必要があります。
そのため、電車に乗り遅れる可能性もあり、早めに出かけることも大切です。
猫をバッグから出さない
猫をキャリーバッグの外に出すことはご法度であり、エチケットが守られていません。
猫が窮屈な思いをして可哀そうと感じてしまう場合もありますが、猫には我慢してもらう必要があり、飼い主も我慢しましょう。
キャリーバッグの外に出してしまうと他の乗客に多大な迷惑をかけてしまい、トラブルに発展してしまうリスクも高まります。
また、逃走してしまう可能性もあり、より多くの乗客に迷惑をかけてしまいます。最悪乗客に怪我を負わせてしまう場合もあります。
猫と電車に乗る時の必需品や便利アイテム
 猫と電車に乗るのであれば必需品がいくつかあり必ず用意しておきましょう。
必需品を用意せずに電車に乗ってしまうとトラブルの原因になりったり、猫にストレスを与えてしまいます。
また、飼い主自身も手間が増えたり、さまざまなことに配慮しなければならなくなり、ルール違反でもあります。
便利なアイテムも用意していればより快適に電車移動が可能になります。
次に、猫と電車に乗る際の必需品と便利アイテムをそれぞれ紹介します。
猫と電車に乗るのであれば必需品がいくつかあり必ず用意しておきましょう。
必需品を用意せずに電車に乗ってしまうとトラブルの原因になりったり、猫にストレスを与えてしまいます。
また、飼い主自身も手間が増えたり、さまざまなことに配慮しなければならなくなり、ルール違反でもあります。
便利なアイテムも用意していればより快適に電車移動が可能になります。
次に、猫と電車に乗る際の必需品と便利アイテムをそれぞれ紹介します。
電車移動する際の必需品
猫を電車移動させる場合の必需品はキャリーバッグやタオルにおもちゃです。
特に、キャリーバッグは必需品中の必需品であり、キャリーバッグなしで電車移動させることはできません。
タオルはさまざまなことで活用できるほか、キャリーバッグに被せることで猫を落ち着かせることも可能になります。
おもちゃは普段遊んでいる物が好ましく、遊ばせていることで周りの環境の変化に気づかせにくくできます。
そのほかはティッシュがゴミ袋、トイレシートがあればより快適に電車移動が可能となります
用意すると便利なグッズ
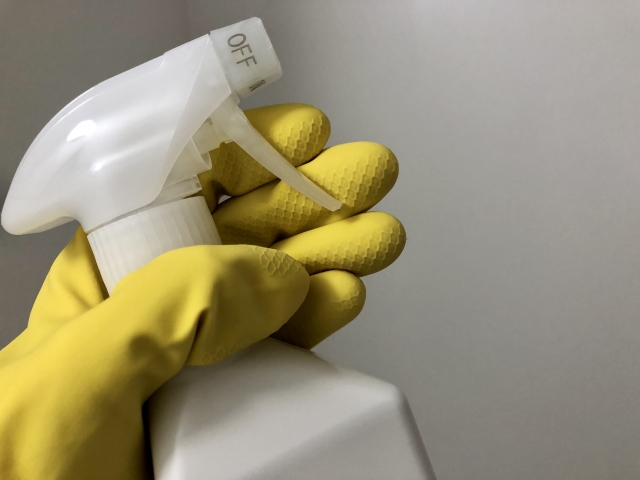 必需品とは別に便利なグッズを用意しておくことで快適に電車移動することができ、余裕がある場合や初めて電車移動する場合は用意しておくことをおすすめします。
ゴム手袋や消臭剤があれば万が一嘔吐してしまっても衛生面に配慮しながら片付けることができます。
また、毛が座席などに付着してしまった際は粘着ローラーがあれば簡単に毛を掃除することができ便利です。
酔いやすい猫の場合は動物病院で処方された酔い止め薬も持参しておいたり、事前に飲ませておきましょう。
必需品とは別に便利なグッズを用意しておくことで快適に電車移動することができ、余裕がある場合や初めて電車移動する場合は用意しておくことをおすすめします。
ゴム手袋や消臭剤があれば万が一嘔吐してしまっても衛生面に配慮しながら片付けることができます。
また、毛が座席などに付着してしまった際は粘着ローラーがあれば簡単に毛を掃除することができ便利です。
酔いやすい猫の場合は動物病院で処方された酔い止め薬も持参しておいたり、事前に飲ませておきましょう。
猫が電車に乗る時の料金は?
 猫を電車に乗せる際に料金が必要になる場合があることを知っているでしょうか。
知らなかった場合は無賃乗車になる可能性があり、注意しましょう。
猫の料金はで鉄道会社によって異なり、有料の場合もあれば無料で利用できる場合があります。
基本的に関東は無料で乗れる場合が多いですが、関西の場合は料金が発生する場合が多いです。
猫は手回り品扱いになり、自動券売機で購入できる場合もありますが、駅員から購入する場合もあり、わからないのであれば駅員に聞くようにしましょう。
猫を電車に乗せる際に料金が必要になる場合があることを知っているでしょうか。
知らなかった場合は無賃乗車になる可能性があり、注意しましょう。
猫の料金はで鉄道会社によって異なり、有料の場合もあれば無料で利用できる場合があります。
基本的に関東は無料で乗れる場合が多いですが、関西の場合は料金が発生する場合が多いです。
猫は手回り品扱いになり、自動券売機で購入できる場合もありますが、駅員から購入する場合もあり、わからないのであれば駅員に聞くようにしましょう。
まとめ
 猫を電車に乗せる場合にはさまざまなことに対して注意しなければならず、周りの乗客に迷惑をかけてしまう可能性もあります。
乗客に迷惑をかけないように猫を電車に乗せる必要があり、キャリーバッグやタオルなどの必需品のほかに便利グッズも用意しておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。
どうしてもトラブルが起きやすいことであるため、可能な限りは自家用車やタクシーを利用することをおすすめします。
ある程度騒音などの環境に慣れさせることが無難です。
猫を電車に乗せる場合にはさまざまなことに対して注意しなければならず、周りの乗客に迷惑をかけてしまう可能性もあります。
乗客に迷惑をかけないように猫を電車に乗せる必要があり、キャリーバッグやタオルなどの必需品のほかに便利グッズも用意しておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。
どうしてもトラブルが起きやすいことであるため、可能な限りは自家用車やタクシーを利用することをおすすめします。
ある程度騒音などの環境に慣れさせることが無難です。 猫を飼うのに必要な部屋の広さは?
 猫を飼う際にどの程度の広さの部屋が必要なのか気になる人もいるのではないでしょうか。
ペットの中には部屋の広さが狭いとストレスに感じてしまう場合もありますが、猫の場合はそこまで部屋の広さのことを考えなくても問題ありません。
例え8畳1Kの部屋でも猫は問題なく飼うことができます。
猫は広い縄張り意識があるイメージがありますが、室内で飼う場合は定期的に餌をもらうことができ、狩りを行う必要がなくなるため、広い縄張りも必要なくなります。
そのため、部屋が狭くても問題なく、餌がもらえることが猫にとっては重要な要素です。
欲を言うのであれば高さと長さがある部屋がおすすめです。
猫は上から警戒する習性があり、高さがある部屋の方が安心します。
長さとは正方形の部屋よりも長方形の部屋の方がおすすめという意味です。
猫は興奮すると走る習性があり、犬とは違って円を描くように走ることはなく、直線的に走る場合が多いです。
走ってもすぐに壁に当たってしまうことは猫にとっては面白くなく、心からはしゃぐことができません。
猫を飼う際にどの程度の広さの部屋が必要なのか気になる人もいるのではないでしょうか。
ペットの中には部屋の広さが狭いとストレスに感じてしまう場合もありますが、猫の場合はそこまで部屋の広さのことを考えなくても問題ありません。
例え8畳1Kの部屋でも猫は問題なく飼うことができます。
猫は広い縄張り意識があるイメージがありますが、室内で飼う場合は定期的に餌をもらうことができ、狩りを行う必要がなくなるため、広い縄張りも必要なくなります。
そのため、部屋が狭くても問題なく、餌がもらえることが猫にとっては重要な要素です。
欲を言うのであれば高さと長さがある部屋がおすすめです。
猫は上から警戒する習性があり、高さがある部屋の方が安心します。
長さとは正方形の部屋よりも長方形の部屋の方がおすすめという意味です。
猫は興奮すると走る習性があり、犬とは違って円を描くように走ることはなく、直線的に走る場合が多いです。
走ってもすぐに壁に当たってしまうことは猫にとっては面白くなく、心からはしゃぐことができません。
猫を飼う部屋の注意点やポイント
 猫を飼う部屋にはさまざまな注意点やポイントがあるため、猫に適している部屋になっているかを確認するようにしましょう。
猫にとって快適な部屋にすることでストレスを与えてしまうことがなく、快適に生活させることができます。
注意点を知ることでどのような部屋が猫にとって理想的なのかを知ることができます。
次に、猫を飼う際の部屋の注意点について紹介します。
猫にとって理想的な部屋にしたい人や猫にストレスを与えたくない人は参考にしてください。
猫を飼う部屋にはさまざまな注意点やポイントがあるため、猫に適している部屋になっているかを確認するようにしましょう。
猫にとって快適な部屋にすることでストレスを与えてしまうことがなく、快適に生活させることができます。
注意点を知ることでどのような部屋が猫にとって理想的なのかを知ることができます。
次に、猫を飼う際の部屋の注意点について紹介します。
猫にとって理想的な部屋にしたい人や猫にストレスを与えたくない人は参考にしてください。
誤食や拾い食いに気をつける
 猫は好奇心旺盛な性格であればひも状の物や糸くずを飲み込んでしまう可能性があります。
誤飲してしまうと消化器系に悪い影響を及ぼしてしまう可能性が高く、腹痛や下痢・嘔吐などの症状が現れてしまいます。
そのため、猫が活動する部屋には口に入れてしまいやすい物はできるだけ置かないようにしましょう。
ほかにも小さなおもちゃなども口に入れてしまいやすいため、注意しましょう。
拾い食いすることを躾けることは難しため、拾い食いしてしまいやすい物を取り除くほうが手っ取り早いです。
猫は好奇心旺盛な性格であればひも状の物や糸くずを飲み込んでしまう可能性があります。
誤飲してしまうと消化器系に悪い影響を及ぼしてしまう可能性が高く、腹痛や下痢・嘔吐などの症状が現れてしまいます。
そのため、猫が活動する部屋には口に入れてしまいやすい物はできるだけ置かないようにしましょう。
ほかにも小さなおもちゃなども口に入れてしまいやすいため、注意しましょう。
拾い食いすることを躾けることは難しため、拾い食いしてしまいやすい物を取り除くほうが手っ取り早いです。
部屋の温度に注意する
部屋の温度を最適にすることで快適に過ごすことができるようになります。
猫も人と同じように部屋の温度が暑かったり、寒いと快適に過ごすことができないだけではなく、体調を崩してしまう原因にもなります。
部屋の温度は人が快適に過ごせる温度で問題ありません。
注意することは人が出かけてしまう際にエアコンなどの機器を停止してしまうことであり、冬や夏の季節であれば猫が活動する部屋だけエアコンをつけておくことをおすすめします。
特に、夏場は熱中症になりやすく、冬の場合は毛布などを用意していれば温かさを得られるますが、涼しさは気軽に与えることができないため、エアコンをつけっぱなしにしておきましょう。
猫が嫌がる匂いを避ける
猫が嫌がる匂いはストレスを与えてしまう原因になるため、控えましょう。
猫が嫌う匂いはフローラル系や柑橘系の匂いであり、芳香剤や洗剤などに使用されている場合が多いです。
柑橘系のフルーツを食べると匂いが漂ってしまいやすいため、換気などして匂いをなくすように配慮しましょう。
柑橘系の匂いの成分には猫に悪い影響を及ぼしてしまうリスクもあり、柑橘系の匂いには特に注意しましょう。
不快なにおいを嗅ぎ続けることは嗅覚に異常が起きるだけではなく、さまざまな体調不良を誘発してしまう原因にもなります。
棚の上に物を置かない
 猫は高い場所で警戒する習性があるため、部屋にも高い場所を用意しておく必要があります。
タンスや食器棚などの上が高くなりやすく、猫にとっては過ごしやすい空間となります。
しかし、高い場所に物を置いてしまうと猫が落としてしまう可能性があります。
物によっては壊れてしまうリスクもあるため、高い場所には物を置かないようにしましょう。
棚の上はさまざまな物を置いてしまいやすいため、猫が活動する部屋の場合には片付けることをおすすめします。
また、万が一落とされても怪我をしない物や壊れない物に変えるようにしましょう。
猫は高い場所で警戒する習性があるため、部屋にも高い場所を用意しておく必要があります。
タンスや食器棚などの上が高くなりやすく、猫にとっては過ごしやすい空間となります。
しかし、高い場所に物を置いてしまうと猫が落としてしまう可能性があります。
物によっては壊れてしまうリスクもあるため、高い場所には物を置かないようにしましょう。
棚の上はさまざまな物を置いてしまいやすいため、猫が活動する部屋の場合には片付けることをおすすめします。
また、万が一落とされても怪我をしない物や壊れない物に変えるようにしましょう。
部屋で飼う猫のストレス解消法
 部屋で猫を飼うのであればいかにストレスを解消するかが大切になります。
猫を放し飼いすることもできますが、事故にあってしまったり、誤飲してしまう可能性も高まります。
そのため、室内飼いの方が安全面は格段と高いですが、ストレスが溜まりやすいデメリットがあります。
室内で猫を飼うのであればストレスを発散させる方法を知っておくことも大切です。
次に、部屋で猫を飼う際のストレス発散方法を紹介します。
ストレスはさまざまな体調不良の原因にもなるため、ストレス発散させることが重要です。
部屋で猫を飼うのであればいかにストレスを解消するかが大切になります。
猫を放し飼いすることもできますが、事故にあってしまったり、誤飲してしまう可能性も高まります。
そのため、室内飼いの方が安全面は格段と高いですが、ストレスが溜まりやすいデメリットがあります。
室内で猫を飼うのであればストレスを発散させる方法を知っておくことも大切です。
次に、部屋で猫を飼う際のストレス発散方法を紹介します。
ストレスはさまざまな体調不良の原因にもなるため、ストレス発散させることが重要です。
高い場所を行き来できる工夫をする
 猫は高い場所が好きであるため、高い場所が確保できるように部屋を仕上げる必要があります。
高い場所がないと知らない間にストレスをため込んでしまっている可能性があります。
高い場所を確保するためにはキャットタワーがおすすめであり、高い場所で行き来できるように工夫することが理想的です。
全体が見渡せれるようにすることで猫もストレスが溜まりにくく、快適にすごすことが可能になります。
キャットタワーや高い家具を設置することが難しいのであれば段差違いになっている家具を並べることでも問題ありません。
猫は高い場所が好きであるため、高い場所が確保できるように部屋を仕上げる必要があります。
高い場所がないと知らない間にストレスをため込んでしまっている可能性があります。
高い場所を確保するためにはキャットタワーがおすすめであり、高い場所で行き来できるように工夫することが理想的です。
全体が見渡せれるようにすることで猫もストレスが溜まりにくく、快適にすごすことが可能になります。
キャットタワーや高い家具を設置することが難しいのであれば段差違いになっている家具を並べることでも問題ありません。
日当たりの良い場所に特等席を用意
猫は日光浴を好む傾向があり、太陽の位置によって日光浴ができる場所が異なりますが、それぞれの時間帯に応じて移動して日光浴を行います。
そのため、猫が日光浴できる特等席を用意してあげましょう。
よく太陽の光が当たり、風などが当たらない場所がおすすめであり、特等席には専用のベッドや座布団を置いておきましょう。
また、すでに特定の場所で日光浴をしているのであればそのような場所にクッションなどを置いてあげることもおすすめです。
外がよく見える場所にする
 どうしても部屋で飼うと封鎖的な空間に長時間いるようになるため、ストレスが溜まりやすいです。
封鎖的な空間でも開放感を与えることでストレス発散につながり、外が見えるように工夫しましょう。
特に、猫にとって快適な場所でもあるキャットタワーなど高い場所から外が見えるように配置し、風や外の匂いが嗅げるようにすることもおすすめです。
外との触れ合いを増やすことでストレス発散することができ、ストレスが溜まりにくくなります。
どうしても部屋で飼うと封鎖的な空間に長時間いるようになるため、ストレスが溜まりやすいです。
封鎖的な空間でも開放感を与えることでストレス発散につながり、外が見えるように工夫しましょう。
特に、猫にとって快適な場所でもあるキャットタワーなど高い場所から外が見えるように配置し、風や外の匂いが嗅げるようにすることもおすすめです。
外との触れ合いを増やすことでストレス発散することができ、ストレスが溜まりにくくなります。
部屋と部屋の行き来を自由にする
猫を部屋で飼うのであれば自由に部屋の行き来ができるようにしましょう。
猫は束縛と不自由を嫌う動物であるため、部屋の行き来ができないとストレスが溜まりやすく、できるだけ家の中を自由に歩けるようにしましょう。
しかし、どうしても猫に入ってほしくない場所もあり、そのような場所だけ猫が入らないようにしましょう。
より多くの部屋を行き来できるようにすれば自由度が高まりますが、それだけ猫に入られても問題ない部屋にしなければなりません。
まとめ
 猫は餌をもらえればそこまで部屋の広さに注意する必要はありませんが、束縛を嫌う動物でもあるため、部屋の行き来ができるようにすることが理想的です。
また、高い所や日光浴ができる場所を好む傾向があり、猫を部屋で飼うのであれば日当たりがよく、キャットタワーなどを設置して猫が過ごしやすい部屋に仕上げましょう。
猫は犬とは異なり、散歩などさせる必要性は低く、室内で飼う場合も多いですが、いかに猫に適した部屋に仕上げるかが重要です。
猫は餌をもらえればそこまで部屋の広さに注意する必要はありませんが、束縛を嫌う動物でもあるため、部屋の行き来ができるようにすることが理想的です。
また、高い所や日光浴ができる場所を好む傾向があり、猫を部屋で飼うのであれば日当たりがよく、キャットタワーなどを設置して猫が過ごしやすい部屋に仕上げましょう。
猫は犬とは異なり、散歩などさせる必要性は低く、室内で飼う場合も多いですが、いかに猫に適した部屋に仕上げるかが重要です。
 生まれて数ヶ月のトイプードルの子犬のあまりの可愛らしさに、新しい家族としてお迎えした経験のあるご家族も多いかと思います。
ふわふわの巻毛に丸々と太った体つき。
そんな小さい体で毎日大騒ぎをする元気の良さに振り回されながら、健康で元気に育ってくれているのか、特に初めて迎えたワンちゃんだとわからないことも多くて不安を感じるかもしれません。
こちらの記事では、そんな飼い主さんの不安を取り払い、ワンちゃんが一生を元気でいてくれるためのフードや体重推移をご紹介してきます。
個体差がありますので、「絶対」なことはありません。あくまで参考としてご覧くださいね。
生まれて数ヶ月のトイプードルの子犬のあまりの可愛らしさに、新しい家族としてお迎えした経験のあるご家族も多いかと思います。
ふわふわの巻毛に丸々と太った体つき。
そんな小さい体で毎日大騒ぎをする元気の良さに振り回されながら、健康で元気に育ってくれているのか、特に初めて迎えたワンちゃんだとわからないことも多くて不安を感じるかもしれません。
こちらの記事では、そんな飼い主さんの不安を取り払い、ワンちゃんが一生を元気でいてくれるためのフードや体重推移をご紹介してきます。
個体差がありますので、「絶対」なことはありません。あくまで参考としてご覧くださいね。
 小型犬は、10ヶ月を過ぎると成犬の仲間入りをします。
ですが運動量が増えてくるので、筋肉や脂肪など蓄えるのもこの時期です。
1才を過ぎてからも多少の体重増加は想像の範囲となりますので、愛犬の体重が増えていても心配せずに、成長を見守りましょう。
逆に体重が減っていったりあまりにも急激な体重増加などが見受けられたら、早めにかかりつけの動物病院で診てもらってください。
小型犬は、10ヶ月を過ぎると成犬の仲間入りをします。
ですが運動量が増えてくるので、筋肉や脂肪など蓄えるのもこの時期です。
1才を過ぎてからも多少の体重増加は想像の範囲となりますので、愛犬の体重が増えていても心配せずに、成長を見守りましょう。
逆に体重が減っていったりあまりにも急激な体重増加などが見受けられたら、早めにかかりつけの動物病院で診てもらってください。
 健康で元気に育てるために、適切な種類のフードを選び、適正量を正確に与える必要があります。
食に興味を持ち始めるこの頃に、欲しがるだけ与えてしまうと肥満になり成犬になった後に様々な問題が出る場合もありますので、飼い主さんが責任を持って管理しましょう。
健康で元気に育てるために、適切な種類のフードを選び、適正量を正確に与える必要があります。
食に興味を持ち始めるこの頃に、欲しがるだけ与えてしまうと肥満になり成犬になった後に様々な問題が出る場合もありますので、飼い主さんが責任を持って管理しましょう。
 乳歯が抜けて大人の歯・永久歯が生えはじめたら、通常のドッグフードを与えていきます。
時期として生後4ヶ月ごろから生え変わり始めますので、様子を見ながら少しずつふやかすフードを硬めにしていき、通常のフードに切り替えます。
個体差がありますが、だいたい1才前後には完全に生え変わりが完了するでしょう。
フードには対象年齢が決められているタイプが多く、「パピー用」「成犬用」「シニア」などおおまかなくくりや、ドライ・ウェット・セミモイストの水分量の違いによって分けられています。
対象年齢がないフードもありますが、フードを食べ始めの頃は、パピータイプがベストです。
ドライは歯の汚れをキレイにしてくれる効果も期待でき、万が一の災害にも保存が効くので食べ慣れておくと良いかもしれません。
乳歯が抜けて大人の歯・永久歯が生えはじめたら、通常のドッグフードを与えていきます。
時期として生後4ヶ月ごろから生え変わり始めますので、様子を見ながら少しずつふやかすフードを硬めにしていき、通常のフードに切り替えます。
個体差がありますが、だいたい1才前後には完全に生え変わりが完了するでしょう。
フードには対象年齢が決められているタイプが多く、「パピー用」「成犬用」「シニア」などおおまかなくくりや、ドライ・ウェット・セミモイストの水分量の違いによって分けられています。
対象年齢がないフードもありますが、フードを食べ始めの頃は、パピータイプがベストです。
ドライは歯の汚れをキレイにしてくれる効果も期待でき、万が一の災害にも保存が効くので食べ慣れておくと良いかもしれません。
 人間以上のスピードで、子犬期からシニアまであっという間に駆け抜けていくワンちゃんの美味しい毎日を安全に過ごしてもたう為に、飼い主さんが様子をよく見ながら、その時々に必要な判断をすることが大切です。
家族である愛犬の健康的な食生活を守ってあげたいですね。
人間以上のスピードで、子犬期からシニアまであっという間に駆け抜けていくワンちゃんの美味しい毎日を安全に過ごしてもたう為に、飼い主さんが様子をよく見ながら、その時々に必要な判断をすることが大切です。
家族である愛犬の健康的な食生活を守ってあげたいですね。  猫にブロッコリーを与えてもいいのでしょうか?
ブロッコリーは栄養価が高くて、わたしたちは利用しやすい野菜ですが猫にとってはどうなのか、気になります。
結論から言うと、ブロッコリーを猫に与える際のメリットとしては、老化防止や抗ガン作用、便秘解消や貧血の予防などが挙げられます。
ブロッコリーはビタミンやカロチン、食物繊維が豊富なので、猫にとっても体に良い効果が期待される野菜なのです。
つまり与えた場合のメリットは大きそうですね。
ブロッコリーには上記のような様々なメリットがあるためキャットフードだけという飼い主さんも積極的に与えてみたい食べ物です。
ただし、守るべき注意点もあるのでこの記事を参考にしてください。
猫にブロッコリーを与えてもいいのでしょうか?
ブロッコリーは栄養価が高くて、わたしたちは利用しやすい野菜ですが猫にとってはどうなのか、気になります。
結論から言うと、ブロッコリーを猫に与える際のメリットとしては、老化防止や抗ガン作用、便秘解消や貧血の予防などが挙げられます。
ブロッコリーはビタミンやカロチン、食物繊維が豊富なので、猫にとっても体に良い効果が期待される野菜なのです。
つまり与えた場合のメリットは大きそうですね。
ブロッコリーには上記のような様々なメリットがあるためキャットフードだけという飼い主さんも積極的に与えてみたい食べ物です。
ただし、守るべき注意点もあるのでこの記事を参考にしてください。
 与えるメリットが多いブロッコリーですが、やはり猫にとっては注意点があります。
人間と同じ体ではなく、体重もずっと軽いので必ず注意点を守ってあげてください。
どんな食べ物でもまずはアレルギーのチェックが必要です。
そして持病があったり、体調が悪い時にはメリットよりもデメリットが大きくなることもあります。
次にブロッコリーを与えてはいけない猫の状態について、調理方法、量などを解説しますのでよく読んで参考にしてください。
与えるメリットが多いブロッコリーですが、やはり猫にとっては注意点があります。
人間と同じ体ではなく、体重もずっと軽いので必ず注意点を守ってあげてください。
どんな食べ物でもまずはアレルギーのチェックが必要です。
そして持病があったり、体調が悪い時にはメリットよりもデメリットが大きくなることもあります。
次にブロッコリーを与えてはいけない猫の状態について、調理方法、量などを解説しますのでよく読んで参考にしてください。
 次に調理方法の注意です。
肉食の猫は野菜を消化するのは苦手です。
さらにブロッコリーは、生の状態だと非常に硬く、内臓に負担をかけてしまい、消化不良の原因となる場合があるので、茹でて与えましょう。
あまり長時間ゆでてしまうと、ビタミンが消失するので短時間ゆで、できればその茹で汁も一緒にご飯にかけたりすると良いでしょう。
電子レンジを使うのもおすすめです。
少量の水をかけてレンジにかければビタミンの損失も少なくてすみます。
次に調理方法の注意です。
肉食の猫は野菜を消化するのは苦手です。
さらにブロッコリーは、生の状態だと非常に硬く、内臓に負担をかけてしまい、消化不良の原因となる場合があるので、茹でて与えましょう。
あまり長時間ゆでてしまうと、ビタミンが消失するので短時間ゆで、できればその茹で汁も一緒にご飯にかけたりすると良いでしょう。
電子レンジを使うのもおすすめです。
少量の水をかけてレンジにかければビタミンの損失も少なくてすみます。
 ブロッコリーの葉や茎についても猫に食べさせても特に問題はありません。
特に葉は蕾の部分よりもポリフェノールが多く含まれています。
ポリフェノールは抗酸化作用があり、老化防止に役立つ栄養価の高い成分です。
ただ農薬がかかっていることもあるのできれいに水洗いした後、なるべく安全な内葉だけを食べさせましょう。
茎の場合は、皮を剥いて、細かく切って食べさせます。
茎は外側が硬いので、茹でてから中側を細かく刻むと良いでしょう。
ブロッコリーの葉や茎についても猫に食べさせても特に問題はありません。
特に葉は蕾の部分よりもポリフェノールが多く含まれています。
ポリフェノールは抗酸化作用があり、老化防止に役立つ栄養価の高い成分です。
ただ農薬がかかっていることもあるのできれいに水洗いした後、なるべく安全な内葉だけを食べさせましょう。
茎の場合は、皮を剥いて、細かく切って食べさせます。
茎は外側が硬いので、茹でてから中側を細かく刻むと良いでしょう。
 ブロッコリースプラウトはブロッコリーの新芽のことで、とても栄養価が高く人間や犬には問題ありませんが、猫はブロッコリースプラウトを食べた際、嘔吐や炎症などを引き起こす可能性があります。
そのためブロッコリースプラウトは避けた方が無難です。
一方、カリフラワーはブロッコリーと同じアブラナ科の野菜です。
ビタミンも多く食べるメリットは同じですが、与えすぎると甲状腺の機能を低下させることになるので少量を食べさせるようにしましょう。
ブロッコリースプラウトはブロッコリーの新芽のことで、とても栄養価が高く人間や犬には問題ありませんが、猫はブロッコリースプラウトを食べた際、嘔吐や炎症などを引き起こす可能性があります。
そのためブロッコリースプラウトは避けた方が無難です。
一方、カリフラワーはブロッコリーと同じアブラナ科の野菜です。
ビタミンも多く食べるメリットは同じですが、与えすぎると甲状腺の機能を低下させることになるので少量を食べさせるようにしましょう。
 猫にブロッコリーを与えることの効果や注意点などを説明しました。
同じブロッコリーでもスプラウトは良くないことは覚えておきたいです。
ブロッコリーは栄養価も高く手に入りやすい野菜なので、健康維持に役立てましょう。
メリットも多いですが、猫の状態によってはデメリットになってしまうことがあります。
健康観察をしっかりして注意点を守り、適量を食べさせるようにしてください。
飼い主さんとの楽しみの一つになるといいですね。
猫にブロッコリーを与えることの効果や注意点などを説明しました。
同じブロッコリーでもスプラウトは良くないことは覚えておきたいです。
ブロッコリーは栄養価も高く手に入りやすい野菜なので、健康維持に役立てましょう。
メリットも多いですが、猫の状態によってはデメリットになってしまうことがあります。
健康観察をしっかりして注意点を守り、適量を食べさせるようにしてください。
飼い主さんとの楽しみの一つになるといいですね。  猫が飼い主に対して体をすりするするには理由があります。
飼い猫であったり、人懐っこい猫であれば行いやすい行動ですが、さまざまな理由から行っています。
次に、猫が飼い主に体をすりすりしてくる理由について紹介します。
なぜ体をこすりつけてくるのかを知りたい人は参考にしてください。
こすり付けてくる理由を知ることで猫の気持ちを知ることができます。
コミュニケーション方法の一つでもあるため、こすり付けた際に邪険にしないようにしましょう。
猫が飼い主に対して体をすりするするには理由があります。
飼い猫であったり、人懐っこい猫であれば行いやすい行動ですが、さまざまな理由から行っています。
次に、猫が飼い主に体をすりすりしてくる理由について紹介します。
なぜ体をこすりつけてくるのかを知りたい人は参考にしてください。
こすり付けてくる理由を知ることで猫の気持ちを知ることができます。
コミュニケーション方法の一つでもあるため、こすり付けた際に邪険にしないようにしましょう。
 猫は人に対してだけではなく猫同士でも体をこすりつけるようにします。
猫同士が体をこすりつけることをアロラビングと呼ばれており、スキンシップの一環と考えられています。
人でいうハグと同じであり、信頼している相手に対して行う行動でもあります。
人に対してスキンシップしてくることはそれだけ飼い主のことを信頼している証拠です。
顔をこすりつける場合は撫でてほしい気持ちや構ってほしい気持ちの表れでもあり、一緒に遊んであげましょう。
猫は人に対してだけではなく猫同士でも体をこすりつけるようにします。
猫同士が体をこすりつけることをアロラビングと呼ばれており、スキンシップの一環と考えられています。
人でいうハグと同じであり、信頼している相手に対して行う行動でもあります。
人に対してスキンシップしてくることはそれだけ飼い主のことを信頼している証拠です。
顔をこすりつける場合は撫でてほしい気持ちや構ってほしい気持ちの表れでもあり、一緒に遊んであげましょう。
 猫は人に対してだけではなく、床や物に対しても体をこすりつける場合もあります。
人に体をこすりつける理由は上記で紹介しましたが、床や物が対象の場合は理由が異なります。
そのため、床や物に対して頻繁に体をこすりつけている場合は理由を把握しておくことをおすすめします。
次に、猫が床や物に体をこすりつける理由について紹介します。
猫が本来行う行動でもあるため、問題視する必要性は低いですが、痒みが原因の場合は病気の可能性もあり、注意が必要です。
猫は人に対してだけではなく、床や物に対しても体をこすりつける場合もあります。
人に体をこすりつける理由は上記で紹介しましたが、床や物が対象の場合は理由が異なります。
そのため、床や物に対して頻繁に体をこすりつけている場合は理由を把握しておくことをおすすめします。
次に、猫が床や物に体をこすりつける理由について紹介します。
猫が本来行う行動でもあるため、問題視する必要性は低いですが、痒みが原因の場合は病気の可能性もあり、注意が必要です。
 猫は元々砂浴びという行動をする習性があり、体をこすりつけることで汚れを落とす効果があります。
そのため、床などに体をこすりつけている場合は体を綺麗にしたいという気持ちがある可能性が高く、ノミなどの影響で痒みの症状が現れている場合もあります。
綺麗にするために体をこすりつける場合はフローリングのようなツルツルした場所ではなく、カーペットやアスファルトなど汚れが落ちやすい環境で行う場合が多いことが特徴的です。
猫は元々砂浴びという行動をする習性があり、体をこすりつけることで汚れを落とす効果があります。
そのため、床などに体をこすりつけている場合は体を綺麗にしたいという気持ちがある可能性が高く、ノミなどの影響で痒みの症状が現れている場合もあります。
綺麗にするために体をこすりつける場合はフローリングのようなツルツルした場所ではなく、カーペットやアスファルトなど汚れが落ちやすい環境で行う場合が多いことが特徴的です。
 猫はさまざまな理由ですりすりを行う場合が多く、上記で紹介した人に対してすりすりする場合もあれば物や床に行うこともあります。
それ以外にも変わったすりすりの仕方をすることもあり、それぞれに理由も存在しています。
次に、変わったすりすりをする理由について紹介します。
さまざまなすりすりする理由を知ることで猫の気持ちを把握することもでき、ストレスを与えてしまうことも軽減できます。
一風変わったすりすりの仕方をする猫がいる場合は参考にしてください。
猫はさまざまな理由ですりすりを行う場合が多く、上記で紹介した人に対してすりすりする場合もあれば物や床に行うこともあります。
それ以外にも変わったすりすりの仕方をすることもあり、それぞれに理由も存在しています。
次に、変わったすりすりをする理由について紹介します。
さまざまなすりすりする理由を知ることで猫の気持ちを把握することもでき、ストレスを与えてしまうことも軽減できます。
一風変わったすりすりの仕方をする猫がいる場合は参考にしてください。
 猫はさまざまな理由から体をこすりつける行動を行います。
愛情表現であったり、単に体が痒いだけなどさまざまな理由が考えられ、どの理由が当てはまるのかを考えるようにしましょう。
体をこすりつけることは何かしらの気持ちの表れである可能性が高いですが、痒みが理由の場合は皮膚に異常が起きている可能性もあり、一度皮膚をチェックするようにしましょう。
赤く炎症していると治療を受ける必要もあるため、定期的に皮膚チェックを行うことをおすすめします。
猫はさまざまな理由から体をこすりつける行動を行います。
愛情表現であったり、単に体が痒いだけなどさまざまな理由が考えられ、どの理由が当てはまるのかを考えるようにしましょう。
体をこすりつけることは何かしらの気持ちの表れである可能性が高いですが、痒みが理由の場合は皮膚に異常が起きている可能性もあり、一度皮膚をチェックするようにしましょう。
赤く炎症していると治療を受ける必要もあるため、定期的に皮膚チェックを行うことをおすすめします。  猫と電車に乗る機会は少ないですが、遠出する際や病院などに連れて行く際に利用する場合もあります。
電車は公共の移動手段であるため、周りの乗客に配慮する必要があります。
ルールを守り、事前に準備する物を用意していれば猫を電車に乗せることは可能です。
トラブルを未然に防ぐためにも猫を電車に乗せる必要があるのであればエチケットを把握しつつ猫を電車に慣れさせるなどを行わなければなりません。
次に、猫と電車に乗る方法について紹介しまします。
猫と電車に乗る機会は少ないですが、遠出する際や病院などに連れて行く際に利用する場合もあります。
電車は公共の移動手段であるため、周りの乗客に配慮する必要があります。
ルールを守り、事前に準備する物を用意していれば猫を電車に乗せることは可能です。
トラブルを未然に防ぐためにも猫を電車に乗せる必要があるのであればエチケットを把握しつつ猫を電車に慣れさせるなどを行わなければなりません。
次に、猫と電車に乗る方法について紹介しまします。
 電車内でも気を付けなければならないことが多いですが、忘れてしまいがちなホームでの気配りも重要です。
ホームは多くの人が行き来したり、アナウンスなどで騒がしい環境です。
特に、ホームを通過する電車の音は騒音であり、猫にストレスを与えてしまいます。
騒がしい環境は猫が嫌う環境であるため、キャリーバッグにタオルなどをかけてできるだけ騒音を感じさせないようにしましょう。
騒音を聞くと興奮してしまい、暴れてしまうリスクが高く、落ち着くまで時間がかかってしまいます。
電車内でも気を付けなければならないことが多いですが、忘れてしまいがちなホームでの気配りも重要です。
ホームは多くの人が行き来したり、アナウンスなどで騒がしい環境です。
特に、ホームを通過する電車の音は騒音であり、猫にストレスを与えてしまいます。
騒がしい環境は猫が嫌う環境であるため、キャリーバッグにタオルなどをかけてできるだけ騒音を感じさせないようにしましょう。
騒音を聞くと興奮してしまい、暴れてしまうリスクが高く、落ち着くまで時間がかかってしまいます。
 猫と電車に乗るときの注意点やマナーを身につけることでトラブルを未然に防いだり、猫に余計なストレスを与えにくくなります。
都心部は電車内が混雑している場合が多いため、より注意点やマナーを身につける必要が高いです。
また、できるだけ混雑する時間帯を避けて電車を利用することも必要な配慮です。
次に、猫と電車に乗る際の注意点とマナーについて紹介します。
初めて猫と電車に乗ろうと考えている人は参考にして、周りの乗客に迷惑をかけないようにしましょう。
猫と電車に乗るときの注意点やマナーを身につけることでトラブルを未然に防いだり、猫に余計なストレスを与えにくくなります。
都心部は電車内が混雑している場合が多いため、より注意点やマナーを身につける必要が高いです。
また、できるだけ混雑する時間帯を避けて電車を利用することも必要な配慮です。
次に、猫と電車に乗る際の注意点とマナーについて紹介します。
初めて猫と電車に乗ろうと考えている人は参考にして、周りの乗客に迷惑をかけないようにしましょう。
 普段とは違う環境になると猫は不安になりやすく、普段よりも大きな声で鳴いてしまう場合があります。
また、興奮してしまう場合も暴れてしまったり、声を荒げてしまう可能性が高く、うるさくなってしまいます。
そのような場合は周りの乗客の迷惑になってしまうため、可能であればいったん外に出るようにしましょう。
一度うるさく騒ぎ始めてしまうと電車の中では落ち着く可能性は低く、ホームなどで落ち着くまで待つ必要があります。
そのため、電車に乗り遅れる可能性もあり、早めに出かけることも大切です。
普段とは違う環境になると猫は不安になりやすく、普段よりも大きな声で鳴いてしまう場合があります。
また、興奮してしまう場合も暴れてしまったり、声を荒げてしまう可能性が高く、うるさくなってしまいます。
そのような場合は周りの乗客の迷惑になってしまうため、可能であればいったん外に出るようにしましょう。
一度うるさく騒ぎ始めてしまうと電車の中では落ち着く可能性は低く、ホームなどで落ち着くまで待つ必要があります。
そのため、電車に乗り遅れる可能性もあり、早めに出かけることも大切です。
 猫と電車に乗るのであれば必需品がいくつかあり必ず用意しておきましょう。
必需品を用意せずに電車に乗ってしまうとトラブルの原因になりったり、猫にストレスを与えてしまいます。
また、飼い主自身も手間が増えたり、さまざまなことに配慮しなければならなくなり、ルール違反でもあります。
便利なアイテムも用意していればより快適に電車移動が可能になります。
次に、猫と電車に乗る際の必需品と便利アイテムをそれぞれ紹介します。
猫と電車に乗るのであれば必需品がいくつかあり必ず用意しておきましょう。
必需品を用意せずに電車に乗ってしまうとトラブルの原因になりったり、猫にストレスを与えてしまいます。
また、飼い主自身も手間が増えたり、さまざまなことに配慮しなければならなくなり、ルール違反でもあります。
便利なアイテムも用意していればより快適に電車移動が可能になります。
次に、猫と電車に乗る際の必需品と便利アイテムをそれぞれ紹介します。
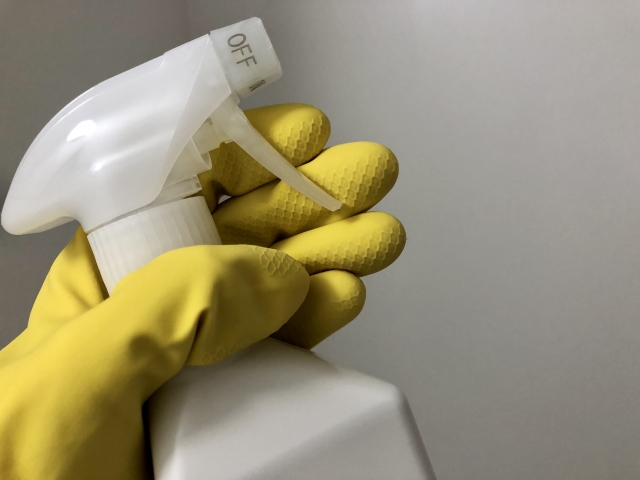 必需品とは別に便利なグッズを用意しておくことで快適に電車移動することができ、余裕がある場合や初めて電車移動する場合は用意しておくことをおすすめします。
ゴム手袋や消臭剤があれば万が一嘔吐してしまっても衛生面に配慮しながら片付けることができます。
また、毛が座席などに付着してしまった際は粘着ローラーがあれば簡単に毛を掃除することができ便利です。
酔いやすい猫の場合は動物病院で処方された酔い止め薬も持参しておいたり、事前に飲ませておきましょう。
必需品とは別に便利なグッズを用意しておくことで快適に電車移動することができ、余裕がある場合や初めて電車移動する場合は用意しておくことをおすすめします。
ゴム手袋や消臭剤があれば万が一嘔吐してしまっても衛生面に配慮しながら片付けることができます。
また、毛が座席などに付着してしまった際は粘着ローラーがあれば簡単に毛を掃除することができ便利です。
酔いやすい猫の場合は動物病院で処方された酔い止め薬も持参しておいたり、事前に飲ませておきましょう。
 猫を電車に乗せる際に料金が必要になる場合があることを知っているでしょうか。
知らなかった場合は無賃乗車になる可能性があり、注意しましょう。
猫の料金はで鉄道会社によって異なり、有料の場合もあれば無料で利用できる場合があります。
基本的に関東は無料で乗れる場合が多いですが、関西の場合は料金が発生する場合が多いです。
猫は手回り品扱いになり、自動券売機で購入できる場合もありますが、駅員から購入する場合もあり、わからないのであれば駅員に聞くようにしましょう。
猫を電車に乗せる際に料金が必要になる場合があることを知っているでしょうか。
知らなかった場合は無賃乗車になる可能性があり、注意しましょう。
猫の料金はで鉄道会社によって異なり、有料の場合もあれば無料で利用できる場合があります。
基本的に関東は無料で乗れる場合が多いですが、関西の場合は料金が発生する場合が多いです。
猫は手回り品扱いになり、自動券売機で購入できる場合もありますが、駅員から購入する場合もあり、わからないのであれば駅員に聞くようにしましょう。
 猫を電車に乗せる場合にはさまざまなことに対して注意しなければならず、周りの乗客に迷惑をかけてしまう可能性もあります。
乗客に迷惑をかけないように猫を電車に乗せる必要があり、キャリーバッグやタオルなどの必需品のほかに便利グッズも用意しておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。
どうしてもトラブルが起きやすいことであるため、可能な限りは自家用車やタクシーを利用することをおすすめします。
ある程度騒音などの環境に慣れさせることが無難です。
猫を電車に乗せる場合にはさまざまなことに対して注意しなければならず、周りの乗客に迷惑をかけてしまう可能性もあります。
乗客に迷惑をかけないように猫を電車に乗せる必要があり、キャリーバッグやタオルなどの必需品のほかに便利グッズも用意しておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。
どうしてもトラブルが起きやすいことであるため、可能な限りは自家用車やタクシーを利用することをおすすめします。
ある程度騒音などの環境に慣れさせることが無難です。  猫を飼う際にどの程度の広さの部屋が必要なのか気になる人もいるのではないでしょうか。
ペットの中には部屋の広さが狭いとストレスに感じてしまう場合もありますが、猫の場合はそこまで部屋の広さのことを考えなくても問題ありません。
例え8畳1Kの部屋でも猫は問題なく飼うことができます。
猫は広い縄張り意識があるイメージがありますが、室内で飼う場合は定期的に餌をもらうことができ、狩りを行う必要がなくなるため、広い縄張りも必要なくなります。
そのため、部屋が狭くても問題なく、餌がもらえることが猫にとっては重要な要素です。
欲を言うのであれば高さと長さがある部屋がおすすめです。
猫は上から警戒する習性があり、高さがある部屋の方が安心します。
長さとは正方形の部屋よりも長方形の部屋の方がおすすめという意味です。
猫は興奮すると走る習性があり、犬とは違って円を描くように走ることはなく、直線的に走る場合が多いです。
走ってもすぐに壁に当たってしまうことは猫にとっては面白くなく、心からはしゃぐことができません。
猫を飼う際にどの程度の広さの部屋が必要なのか気になる人もいるのではないでしょうか。
ペットの中には部屋の広さが狭いとストレスに感じてしまう場合もありますが、猫の場合はそこまで部屋の広さのことを考えなくても問題ありません。
例え8畳1Kの部屋でも猫は問題なく飼うことができます。
猫は広い縄張り意識があるイメージがありますが、室内で飼う場合は定期的に餌をもらうことができ、狩りを行う必要がなくなるため、広い縄張りも必要なくなります。
そのため、部屋が狭くても問題なく、餌がもらえることが猫にとっては重要な要素です。
欲を言うのであれば高さと長さがある部屋がおすすめです。
猫は上から警戒する習性があり、高さがある部屋の方が安心します。
長さとは正方形の部屋よりも長方形の部屋の方がおすすめという意味です。
猫は興奮すると走る習性があり、犬とは違って円を描くように走ることはなく、直線的に走る場合が多いです。
走ってもすぐに壁に当たってしまうことは猫にとっては面白くなく、心からはしゃぐことができません。
 猫を飼う部屋にはさまざまな注意点やポイントがあるため、猫に適している部屋になっているかを確認するようにしましょう。
猫にとって快適な部屋にすることでストレスを与えてしまうことがなく、快適に生活させることができます。
注意点を知ることでどのような部屋が猫にとって理想的なのかを知ることができます。
次に、猫を飼う際の部屋の注意点について紹介します。
猫にとって理想的な部屋にしたい人や猫にストレスを与えたくない人は参考にしてください。
猫を飼う部屋にはさまざまな注意点やポイントがあるため、猫に適している部屋になっているかを確認するようにしましょう。
猫にとって快適な部屋にすることでストレスを与えてしまうことがなく、快適に生活させることができます。
注意点を知ることでどのような部屋が猫にとって理想的なのかを知ることができます。
次に、猫を飼う際の部屋の注意点について紹介します。
猫にとって理想的な部屋にしたい人や猫にストレスを与えたくない人は参考にしてください。
 猫は好奇心旺盛な性格であればひも状の物や糸くずを飲み込んでしまう可能性があります。
誤飲してしまうと消化器系に悪い影響を及ぼしてしまう可能性が高く、腹痛や下痢・嘔吐などの症状が現れてしまいます。
そのため、猫が活動する部屋には口に入れてしまいやすい物はできるだけ置かないようにしましょう。
ほかにも小さなおもちゃなども口に入れてしまいやすいため、注意しましょう。
拾い食いすることを躾けることは難しため、拾い食いしてしまいやすい物を取り除くほうが手っ取り早いです。
猫は好奇心旺盛な性格であればひも状の物や糸くずを飲み込んでしまう可能性があります。
誤飲してしまうと消化器系に悪い影響を及ぼしてしまう可能性が高く、腹痛や下痢・嘔吐などの症状が現れてしまいます。
そのため、猫が活動する部屋には口に入れてしまいやすい物はできるだけ置かないようにしましょう。
ほかにも小さなおもちゃなども口に入れてしまいやすいため、注意しましょう。
拾い食いすることを躾けることは難しため、拾い食いしてしまいやすい物を取り除くほうが手っ取り早いです。
 猫は高い場所で警戒する習性があるため、部屋にも高い場所を用意しておく必要があります。
タンスや食器棚などの上が高くなりやすく、猫にとっては過ごしやすい空間となります。
しかし、高い場所に物を置いてしまうと猫が落としてしまう可能性があります。
物によっては壊れてしまうリスクもあるため、高い場所には物を置かないようにしましょう。
棚の上はさまざまな物を置いてしまいやすいため、猫が活動する部屋の場合には片付けることをおすすめします。
また、万が一落とされても怪我をしない物や壊れない物に変えるようにしましょう。
猫は高い場所で警戒する習性があるため、部屋にも高い場所を用意しておく必要があります。
タンスや食器棚などの上が高くなりやすく、猫にとっては過ごしやすい空間となります。
しかし、高い場所に物を置いてしまうと猫が落としてしまう可能性があります。
物によっては壊れてしまうリスクもあるため、高い場所には物を置かないようにしましょう。
棚の上はさまざまな物を置いてしまいやすいため、猫が活動する部屋の場合には片付けることをおすすめします。
また、万が一落とされても怪我をしない物や壊れない物に変えるようにしましょう。
 部屋で猫を飼うのであればいかにストレスを解消するかが大切になります。
猫を放し飼いすることもできますが、事故にあってしまったり、誤飲してしまう可能性も高まります。
そのため、室内飼いの方が安全面は格段と高いですが、ストレスが溜まりやすいデメリットがあります。
室内で猫を飼うのであればストレスを発散させる方法を知っておくことも大切です。
次に、部屋で猫を飼う際のストレス発散方法を紹介します。
ストレスはさまざまな体調不良の原因にもなるため、ストレス発散させることが重要です。
部屋で猫を飼うのであればいかにストレスを解消するかが大切になります。
猫を放し飼いすることもできますが、事故にあってしまったり、誤飲してしまう可能性も高まります。
そのため、室内飼いの方が安全面は格段と高いですが、ストレスが溜まりやすいデメリットがあります。
室内で猫を飼うのであればストレスを発散させる方法を知っておくことも大切です。
次に、部屋で猫を飼う際のストレス発散方法を紹介します。
ストレスはさまざまな体調不良の原因にもなるため、ストレス発散させることが重要です。
 猫は高い場所が好きであるため、高い場所が確保できるように部屋を仕上げる必要があります。
高い場所がないと知らない間にストレスをため込んでしまっている可能性があります。
高い場所を確保するためにはキャットタワーがおすすめであり、高い場所で行き来できるように工夫することが理想的です。
全体が見渡せれるようにすることで猫もストレスが溜まりにくく、快適にすごすことが可能になります。
キャットタワーや高い家具を設置することが難しいのであれば段差違いになっている家具を並べることでも問題ありません。
猫は高い場所が好きであるため、高い場所が確保できるように部屋を仕上げる必要があります。
高い場所がないと知らない間にストレスをため込んでしまっている可能性があります。
高い場所を確保するためにはキャットタワーがおすすめであり、高い場所で行き来できるように工夫することが理想的です。
全体が見渡せれるようにすることで猫もストレスが溜まりにくく、快適にすごすことが可能になります。
キャットタワーや高い家具を設置することが難しいのであれば段差違いになっている家具を並べることでも問題ありません。
 どうしても部屋で飼うと封鎖的な空間に長時間いるようになるため、ストレスが溜まりやすいです。
封鎖的な空間でも開放感を与えることでストレス発散につながり、外が見えるように工夫しましょう。
特に、猫にとって快適な場所でもあるキャットタワーなど高い場所から外が見えるように配置し、風や外の匂いが嗅げるようにすることもおすすめです。
外との触れ合いを増やすことでストレス発散することができ、ストレスが溜まりにくくなります。
どうしても部屋で飼うと封鎖的な空間に長時間いるようになるため、ストレスが溜まりやすいです。
封鎖的な空間でも開放感を与えることでストレス発散につながり、外が見えるように工夫しましょう。
特に、猫にとって快適な場所でもあるキャットタワーなど高い場所から外が見えるように配置し、風や外の匂いが嗅げるようにすることもおすすめです。
外との触れ合いを増やすことでストレス発散することができ、ストレスが溜まりにくくなります。
 猫は餌をもらえればそこまで部屋の広さに注意する必要はありませんが、束縛を嫌う動物でもあるため、部屋の行き来ができるようにすることが理想的です。
また、高い所や日光浴ができる場所を好む傾向があり、猫を部屋で飼うのであれば日当たりがよく、キャットタワーなどを設置して猫が過ごしやすい部屋に仕上げましょう。
猫は犬とは異なり、散歩などさせる必要性は低く、室内で飼う場合も多いですが、いかに猫に適した部屋に仕上げるかが重要です。
猫は餌をもらえればそこまで部屋の広さに注意する必要はありませんが、束縛を嫌う動物でもあるため、部屋の行き来ができるようにすることが理想的です。
また、高い所や日光浴ができる場所を好む傾向があり、猫を部屋で飼うのであれば日当たりがよく、キャットタワーなどを設置して猫が過ごしやすい部屋に仕上げましょう。
猫は犬とは異なり、散歩などさせる必要性は低く、室内で飼う場合も多いですが、いかに猫に適した部屋に仕上げるかが重要です。