猫が日向ぼっこをする理由と効果
 猫は暖かい場所が大好きですよね。
特に日向ぼっこをしている猫を見ることが多く、とても気持ち良さそうにしている姿はほんと可愛いです。
ですが、猫にとって日向ぼっこは気持ちいいだけではなく、良いことがたくさんあることがわかりました。
そこでここでは、猫が日向ぼっこをする理由と効果についてご紹介していきます。
猫は暖かい場所が大好きですよね。
特に日向ぼっこをしている猫を見ることが多く、とても気持ち良さそうにしている姿はほんと可愛いです。
ですが、猫にとって日向ぼっこは気持ちいいだけではなく、良いことがたくさんあることがわかりました。
そこでここでは、猫が日向ぼっこをする理由と効果についてご紹介していきます。
体内時計を調整できる
動物のほとんどは人間のように時間を見ることができないため、同じ時間に目が覚めたり、空腹を訴えたりする時間が同じなのは体内時計を頼りに生活しているということになります。
日向ぼっこをすると太陽の高さや方向を無意識にキャッチすることができ、季節や時間を体感して、体内時計のずれを調節しているのです。
良質な睡眠がとれる
 日向ぼっこをしていると、猫は気持ち良さそうにウトウトしていますよね。
それは、暖かい日差しが布団のように心地よく、体が温まって眠くなってくるからです。
猫はもともと、体力温存のためによく寝る動物ですが、暖かい場所ではより睡眠の質が高まり、起きると活発になれると言われています。
日向ぼっこをしていると、猫は気持ち良さそうにウトウトしていますよね。
それは、暖かい日差しが布団のように心地よく、体が温まって眠くなってくるからです。
猫はもともと、体力温存のためによく寝る動物ですが、暖かい場所ではより睡眠の質が高まり、起きると活発になれると言われています。
精神を安定させる
猫も人間と同じで、太陽の光を浴びると幸せホルモンと言われている「セロトニン」の分泌が活性化されると言われています。
このセロトニンには、精神状態を整えてくれる作用があるとされており、分泌量が増えると情緒が安定するというデータも。
なので、猫がリラックスして日向ぼっこができるよう、窓際に外をよく眺められるような猫タワーを置いたり、よりくつげるよう猫ベッドや、ラックを設置するなどして愛猫のためのスペースを確保したあげることがおすすめです!
免疫力が高まる
 日向ぼっこをすると、体の体温があがり、全身の血流の流れが良くなります。
それによって、新陳代謝が活発になり、免疫力がアップ。
免疫力が高まるということは、病気を予防できたり長生きにも繋がるといっても過言ではないでしょう。
日向ぼっこをすると、体の体温があがり、全身の血流の流れが良くなります。
それによって、新陳代謝が活発になり、免疫力がアップ。
免疫力が高まるということは、病気を予防できたり長生きにも繋がるといっても過言ではないでしょう。
骨が強くなる
猫は日光を浴びると、皮脂腺でビタミンDが作られ、それを毛づくろいすることで、体内に取り込めるという説があります。
ビタミンDには、骨づくりに欠かせないカルシウムの吸収をサポートしてくれる大事な栄養素です。
ぜひ、日向ぼっこ中の愛猫の毛づくろいに注目してみてくださいね!
毛の手触りがフワフワになる
 湿気を多く含んだ被毛は、ジットリ、ベットリとして綺麗好きな猫にとっては不快以外のなにものでもありません。
そこで、日向ぼっこをすることで、毛に含まれる水分が蒸発してフワフワになるのです。
また、湿気によるジメジメが解消されることで、皮膚病にもかかりにくくなると言われています。
湿気を多く含んだ被毛は、ジットリ、ベットリとして綺麗好きな猫にとっては不快以外のなにものでもありません。
そこで、日向ぼっこをすることで、毛に含まれる水分が蒸発してフワフワになるのです。
また、湿気によるジメジメが解消されることで、皮膚病にもかかりにくくなると言われています。
被毛の消毒が可能
布団を干して日光消毒をしたり、医療器具を紫外線消毒器で殺菌するのと同じで、日向ぼっこをすると、日光に含まれる紫外線によって被毛が消毒されます。
また、ダニなどの寄生虫や体毛に付着したさまざまな細菌が繁殖しにくくなるのです。
綺麗好きな猫には嬉しい効果ですよね!
猫が日向ぼっこをする時の注意点
 猫が日向ぼっこを好きなことがわかりましたが、メリットばかりではなく注意しなければいけないこともあります。
猫自身が自分では気づけないことも多いので、飼い主さんが日頃から日向ぼっこをしている様子をしっかり観察してあげることが大切です。
ここでは猫が日向ぼっこをする際の注意点をご紹介します。
猫が日向ぼっこを好きなことがわかりましたが、メリットばかりではなく注意しなければいけないこともあります。
猫自身が自分では気づけないことも多いので、飼い主さんが日頃から日向ぼっこをしている様子をしっかり観察してあげることが大切です。
ここでは猫が日向ぼっこをする際の注意点をご紹介します。
熱中症
猫は比較的暑さに強いのですが、熱中症にならないわけではありません。
特に湿度が高く、気温が高い日本の夏には猫も熱中症を発症するリスクが高くなります。
猫は多少暑くでも日向ぼっこをする続ける傾向があり、その最中に知らず知らず熱中症になってしまうことも。
そのようなことがないように以下のような対策を取るようにしてあげてください。
・クーラーで室温の管理をする(28度程度が理想)
・レースのカーテンをつけることによって直射日光をさける
・水をすぐに飲める環境を作る
特に猫は、水が冷たかったり遠い場所にあったりなど少し気に入らない点があると、水を飲まないことがあります。
愛猫がお気に入りの日向ぼっこの場所から動きたがらない場合は、近くに飲み水を用意してあげると良いでしょう。
日向に置いた水は水温でぬるくなり猫が好んで飲んでくれます。
ただし、赤カビなどが発生しやすいため、毎日水を取り替えて容器をキレイに洗ってあげてくださいね。
紫外線
 皮膚がんを気にして紫外線対策をしている方も多いかと思いますが、猫も同様に皮膚がんになる可能性があります。
猫は頭や首の色素の薄い部位に発生する傾向があり、特に白猫に注意が必要です。
窓ガラスにUVカット機能のあるシートを貼ったり、窓ガラスそのものをUVカット機能のあるものにしたりするなどの工夫をしてあげてくださいね。
皮膚がんを気にして紫外線対策をしている方も多いかと思いますが、猫も同様に皮膚がんになる可能性があります。
猫は頭や首の色素の薄い部位に発生する傾向があり、特に白猫に注意が必要です。
窓ガラスにUVカット機能のあるシートを貼ったり、窓ガラスそのものをUVカット機能のあるものにしたりするなどの工夫をしてあげてくださいね。
高層症候群
猫の高層症候群とは、猫が2階以上の高い場所から落ちてケガをしてしまうことを言います。
別名「キャット・フライング・シンドローム」とも呼ばれていますが、猫は高い場所から飛び降りることはできても、建物の2階以上の高さから落ちてしまうことは普通ではありません。
なぜ数十メートル以上の高さから突然飛び降りてしまうのかの原因は、はっきりわかっていませんが、いくら猫といってもそんな高さから飛び降りれば死んでしまいます。
猫にとってお気に入りの場所だったとしても、2階以上のベランダやバルコニーからは出さないようにしましょう。
猫は高い場所から落ちても平気だと思っている人もいますが、そのようなことは決してありませんので、重傷を負ったり最悪の場合命を落とす可能性があります。
猫の日向ぼっこを室内飼いで行う方法
 野良猫の場合は、常に外にいるのでいつでも自由に日向ぼっこができますが、室内飼いの場合は、どうやって日向ぼっこをさせてあげればいいかと悩んでいる方もいるでしょう。
ここでは、猫の日向ぼっこを室内飼いで行う方法についてご紹介していきます。
野良猫の場合は、常に外にいるのでいつでも自由に日向ぼっこができますが、室内飼いの場合は、どうやって日向ぼっこをさせてあげればいいかと悩んでいる方もいるでしょう。
ここでは、猫の日向ぼっこを室内飼いで行う方法についてご紹介していきます。
猫がくつろげる場所を窓際につくる
室内でも猫に日向ぼっこをさせてあげる場合は、まず陽の当たる場に猫がくつろげる場所を作ってあげましょう。
窓が高くて床まで日光が入りにくい時には、棚やキャットタワーなどを置いて、窓と同じ高さに猫が行けるようにしてあげてください。
窓から外も見えるので、猫にとっては嬉しい場所となるでしょう。
クッションや箱などを置いたり、または物を片付けてスペースを作ったりして、猫がくつろいで寝転がったり座ったりできるようにしてあげるのもいいですね。
さらには、窓に直接つけることができる猫用のハンモックが販売されているので、家具を置けない時でも猫に日向ぼっこを楽しんでもらうことができます。
猫用の日向ぼっこの場所を用意する
 猫の日向ぼっこは、できればガラス越しではなく、日光浴ができるようにしたいもの。
網戸にして脱走防止の柵をつけておき、日光浴させるという方法も良いでしょう。
ベランダに直接出すのは危険ですが、ネットを張って脱走できないようにしたうえで出したり、大型ケージごとベランダや縁側に出したりといった方法で、ガラス越しでなくても日光を浴びることができます。
どんな状況でも外に出すことで、脱走や他の猫との接触の危険があるので、飼い主さんが必ず見ているようにしてあげてください。
猫の日向ぼっこは、できればガラス越しではなく、日光浴ができるようにしたいもの。
網戸にして脱走防止の柵をつけておき、日光浴させるという方法も良いでしょう。
ベランダに直接出すのは危険ですが、ネットを張って脱走できないようにしたうえで出したり、大型ケージごとベランダや縁側に出したりといった方法で、ガラス越しでなくても日光を浴びることができます。
どんな状況でも外に出すことで、脱走や他の猫との接触の危険があるので、飼い主さんが必ず見ているようにしてあげてください。
陽の当たる部屋の出入りを自由にする
猫が日向ぼっことをするには、陽の当たる場所に猫がいけるようにしなければいけません。
ただし、窓際だと何かの拍子で猫が脱走してしまう可能性もあるので、開けないように気をつけるだけではなく、脱走防止の網やネットをつけるなどしておくと良いでしょう。
猫が入ってもよい場所には、尖ったものや誤飲しそうな細かいもの、猫がかじってしまう観葉植物などを置かないようにして、心配なく猫に日向ぼっこをさせられるようにしてあげてください。
陽の当たる部屋はカーテンで締め切らないようにして、猫が日光浴ができるようにしてあげると良いでしょう。
そして、猫が自分の意思で日陰に行ったり、別の部屋に行ったりできるように、閉じ込めないようにしてくださいね。
まとめ
今回は猫の日向ぼっこについてご紹介してきました。
猫が日向ぼっこをしている姿を見ていると思わずこちらも眠たくなってしまうくらい気持ち良い表情をしていますが、注意しなければいけない点もあるので、日頃から飼い主さんの様子観察が必要です。
猫がキックする5つの理由
 猫が甘えてくる姿はとっても可愛いですが、高速でキックされるのは可愛いとばかりも言っていられず、「痛い!」と叫んでしまうこともあると思います。
猫キックは一体どんな時に、どんな気持ちでしてくるのでしょうか?
猫の気持ちから、5つの理由が考えられるのでそれを紹介します。
猫が甘えてくる姿はとっても可愛いですが、高速でキックされるのは可愛いとばかりも言っていられず、「痛い!」と叫んでしまうこともあると思います。
猫キックは一体どんな時に、どんな気持ちでしてくるのでしょうか?
猫の気持ちから、5つの理由が考えられるのでそれを紹介します。
理由①:構って欲しいと伝えている
猫キックをする理由でまず考えられるのは、「飼い主さん、構って!」という気持ちです。
何かに集中する飼い主さんや、出掛けようとする飼い主さんに、「こっちを見て!」と気を引くために、猫キックを繰り出すのです。
これを聞いただけでも、可愛くてもうメロメロになってしまいそうですね。
飼い主さんの気を引くときのキックはある程度加減をしていて、甘噛みもしてきたりします。
「ねぇねぇ、見て。」という猫の甘えたい気持ちが現れているのだと思うとむげにはできません。
理由②:やめて欲しいという意思表示
 2つ目の理由は①とは反対のものです。
人間に触られたくないなどの「嫌!」という気持ちをキックで示すことがあります。
表情や態度、声など色々なものを使い、猫は「やめて」と気持ちを伝えますが、しつこく嫌なことをされると、猫キックをしてその人物を攻撃するようです。
やめてほしいというキックは猫が本気でやっている時なので、怒っていてかなり痛いことが多いです。
しっぽをバタバタ振ったり、耳を横にしていたりすることもあるので、そういう時は猫をそっとしておいてあげてください。
2つ目の理由は①とは反対のものです。
人間に触られたくないなどの「嫌!」という気持ちをキックで示すことがあります。
表情や態度、声など色々なものを使い、猫は「やめて」と気持ちを伝えますが、しつこく嫌なことをされると、猫キックをしてその人物を攻撃するようです。
やめてほしいというキックは猫が本気でやっている時なので、怒っていてかなり痛いことが多いです。
しっぽをバタバタ振ったり、耳を横にしていたりすることもあるので、そういう時は猫をそっとしておいてあげてください。
理由③:遊びで狩りの練習をしている
元々猫は狩猟動物です。
たとえ家猫として生まれ、暮らしている時間が長くても、狩猟本能はなくなりません。
ですから、猫キックを完全にやめさせることは不可能です。
子猫の時からキックをして遊びで狩りの練習をすることは大切な一面でもあります。
最初は可愛い遊びでも興奮してきて、つい強くキックすることもあります。
さらに興奮すると噛み付くこともあるので、適度なところでやめさせてクールダウンするということも大切です。
理由④:運動不足やストレスから
 飼い主さんに対してではなく、何か物に対してキックを行うこともあります。
特に家の中にいる若い猫にはよく見られます。
クッションやソファなどに向けてキックを繰り返している場合は、運動やストレス解消のために体を動かしていると考えられます。
つまり退屈しているわけです。
人間のやんちゃな子供が家の中で暴れてしまうことがありますね。
それと同じ状態ですので、余っている体力を発散させてあげると解決することが多いです。
飼い主さんに対してではなく、何か物に対してキックを行うこともあります。
特に家の中にいる若い猫にはよく見られます。
クッションやソファなどに向けてキックを繰り返している場合は、運動やストレス解消のために体を動かしていると考えられます。
つまり退屈しているわけです。
人間のやんちゃな子供が家の中で暴れてしまうことがありますね。
それと同じ状態ですので、余っている体力を発散させてあげると解決することが多いです。
理由⑤:猫同士で行うコミュニケーション
最後は一緒に飼われている猫同士でキックをしている場合です。
猫同士の蹴り合いだと、ただコミュニケーションを取っているだけの可能性があります。
特に仔猫は狩猟本能の名残で、遊びのつもりでキックを行うことがあります。
また、猫同士が若くてお互いに運動不足の解消のため、プロレスごっこのように遊んでいるとも考えられます。
楽しいコミュニケーションならよいのですが、興奮しすぎて喧嘩になる場合もあるので要注意です。
猫が怪我をしないようによく観察してください。
猫キックをやめさせたい時の対処法
 猫キックの理由はさまざまあることがわかりました。
甘えているだけでも飼い主さんが痛いことも多く、猫のストレスや興奮状態を考えるとやめさせる手立ても知っておきたいものです。
次の対処法は効果があるので、困った際には一度試してみてください。
猫キックの理由はさまざまあることがわかりました。
甘えているだけでも飼い主さんが痛いことも多く、猫のストレスや興奮状態を考えるとやめさせる手立ても知っておきたいものです。
次の対処法は効果があるので、困った際には一度試してみてください。
しつこく構うのは止める
猫の方からじゃれついてきたとしても、途中で飽きてしまうと、猫は構われるのを嫌がり、解放されたくて猫キックをしてきます。
なので、しつこく構うのは止めましょう。
猫は気が変わりやすいので、その気分を察知してあげるのも飼い主さんの役目かもしれません。
あまりしつこいと、猫との関係性が悪くなることがあります。
キックが出たら、「おしまい」のサインと思いましょう。
キックされる前にエネルギーを使わせる
 特に若い猫の場合、運動不足や退屈を紛らわせるためにキックをしていることが多いです。
エネルギーがあり余っており、それを発散する機会がないのはかわいそうです。
猫キックが出る前に運動や遊びで解消させるということができれば、ストレスにもならずに済みます。
元気な猫の場合、1日に30分は遊んで運動しないとストレスに繋がると言われていますので、キャットタワーを作ってあげたり、飼い主さんとの遊び時間を増やしたりしてみるとエネルギーが発散されるでしょう。
特に若い猫の場合、運動不足や退屈を紛らわせるためにキックをしていることが多いです。
エネルギーがあり余っており、それを発散する機会がないのはかわいそうです。
猫キックが出る前に運動や遊びで解消させるということができれば、ストレスにもならずに済みます。
元気な猫の場合、1日に30分は遊んで運動しないとストレスに繋がると言われていますので、キャットタワーを作ってあげたり、飼い主さんとの遊び時間を増やしたりしてみるとエネルギーが発散されるでしょう。
おもちゃ(けりぐるみ)を与える
エネルギーの発散とも似ていますが、けりぐるみとなるおもちゃを与えてキックさせてしまうという方法があります。
人間の代わりとしてけりぐるみなどのおもちゃを与えることで、猫キックをする標的が人間からおもちゃに切り替わるので、怪我のリスクも減ります。
狩りの練習という猫の本能によることも多いので、専用グッズが販売されているものを活用している人も多いです。
猫が抱きつきやすい形をしていて、中にマタタビの実や粉末が入っているものや興味を引く音が出る仕掛けがあるものなど、工夫されています。
そのおもちゃを使って遊んであげるのもおすすめです。
顔に息を吹きかける
 猫は顔に息を吹きかけられると、強い嫌悪感を覚えます。
そのため、猫にキックされて痛いと思った時は、猫の顔に息を吹きかけて、猫キックを防ぎましょう。
息を吹きかけるという方法は、いたずらをやめさせるときにも有効なので覚えておくと役に立ちます。
驚いてキックをやめたり、その場から去っていったりします。
でも、何回も息を吹きかけていると猫に嫌われるので、気をつけてください。
猫は顔に息を吹きかけられると、強い嫌悪感を覚えます。
そのため、猫にキックされて痛いと思った時は、猫の顔に息を吹きかけて、猫キックを防ぎましょう。
息を吹きかけるという方法は、いたずらをやめさせるときにも有効なので覚えておくと役に立ちます。
驚いてキックをやめたり、その場から去っていったりします。
でも、何回も息を吹きかけていると猫に嫌われるので、気をつけてください。
まとめ
猫キックをする心理と対処法を紹介しました。
猫は飼い主さんと遊びたいという気持ちの表れの他、本能からの狩りの練習や運動不足の発散をしていることが多いのです。
キックで痛い目にあう前にけりぐるみを与えてあげたり、一緒に遊んであげたりすることでストレス発散にも繋がります。
対処法を参考に、愛猫の心理を察知して関係性をより高めてください。
猫に野菜は必要?
 大切なペットである猫の健康には気をつけたいですね。
食事内容にも注意して、野菜を食べたほうが良いのかどうか悩んでいる人もいると思います。
でも、結論から言って猫に野菜は必要ではありません。
完全な肉食動物ですので、野菜を食べなくても健康上問題は起こりません。
その点について詳しく、また食べても良い野菜・危険な野菜について解説します。
大切なペットである猫の健康には気をつけたいですね。
食事内容にも注意して、野菜を食べたほうが良いのかどうか悩んでいる人もいると思います。
でも、結論から言って猫に野菜は必要ではありません。
完全な肉食動物ですので、野菜を食べなくても健康上問題は起こりません。
その点について詳しく、また食べても良い野菜・危険な野菜について解説します。
必要な栄養は全てキャットフードに含まれている
猫はキャットフードをメインとして食生活が成り立っています。
商品によっては、野菜が原材料に使用されていることもあります。
猫にとって必要な栄養はキャットフードに含まれているので、それだけでも問題はありません。
ただ、フードに含まれている野菜は加工されているため、本来の栄養素は損なわれていると考えられます。
野菜の栄養素を与えたいのであれば、フードに少し加えるようにするとよいでしょう。
猫にとって野菜は消化しにくい
 野菜にはお肉に含まれていない栄養素や酵素が含まれているため、それらを補うために与えることは悪いことではありません。
しかし、野菜を生のまま与え過ぎると、消化不良を起こしてしまう可能性があるため、注意が必要です。
猫は腸が短く、野菜や果物の消化に適していません。
葉っぱをかじって毛玉を吐き出していることもあります。
野菜を与えるときはごく少量をゆでたり、刻んだりしてあげましょう。
野菜にはお肉に含まれていない栄養素や酵素が含まれているため、それらを補うために与えることは悪いことではありません。
しかし、野菜を生のまま与え過ぎると、消化不良を起こしてしまう可能性があるため、注意が必要です。
猫は腸が短く、野菜や果物の消化に適していません。
葉っぱをかじって毛玉を吐き出していることもあります。
野菜を与えるときはごく少量をゆでたり、刻んだりしてあげましょう。
猫にとって野菜は摂取する必要がない
猫の味覚は人間の10分の1以下なので、人間のように味わって野菜を食べることがないようです。
フードに含まれる肉や魚の匂いに反応するので、匂いの少ない野菜に興味を示さない猫も多いです。
フードに野菜を加えても全く食べようとしなければ、無理に食べさせなくてもかまいません。
必要な栄養分はキャットフードで賄うことが可能です。
もちろん、人間用の味付けした野菜や野菜ジュースなどの加工品は与えないようにしましょう。
猫が食べてもいい野菜
 猫は肉食動物なので野菜は必要ありませんが、ビタミンや食物繊維、酵素などが多く含まれるので栄養を補うものとして利用できます。
例えば皮膚の健康や便秘の解消などには効果があると言われています。
猫が食べても良い野菜について詳しく解説します。
猫は肉食動物なので野菜は必要ありませんが、ビタミンや食物繊維、酵素などが多く含まれるので栄養を補うものとして利用できます。
例えば皮膚の健康や便秘の解消などには効果があると言われています。
猫が食べても良い野菜について詳しく解説します。
大根
大根は猫にとって有害な野菜ではありません。
与え方によっては、そのまま生でも食べさせることが可能です。
大根は水分が豊富で、ビタミンB・Cや鉄分、カリウムなどのミネラルや酵素も含んでいます。
水分補給として利用すると良いでしょう。
与え方としては酵素を壊さない生の大根おろしがおすすめです。
ただし、大根はアブラナ科の野菜で甲状腺に負担をかけることがあるため、甲状腺に問題がある場合は注意しましょう。
きゅうり
 きゅうりは猫にとってほぼ悪影響はない野菜です。
きゅうりの90%以上は水分で出来ているため、脂肪分やナトリウムがとても少なく、低カロリーで健康的です。
夏の熱中症対策としてもおやつ代わりに与えられます。
利尿作用のあるカリウム、視力維持や皮膚を守るβカロチンなどの栄養があります。
体を冷やす野菜なので、与えすぎるとお腹が冷えて下痢になるかもしれません。
猫の口に合うように少量を小さくカットして与えるようにしてください。
きゅうりは猫にとってほぼ悪影響はない野菜です。
きゅうりの90%以上は水分で出来ているため、脂肪分やナトリウムがとても少なく、低カロリーで健康的です。
夏の熱中症対策としてもおやつ代わりに与えられます。
利尿作用のあるカリウム、視力維持や皮膚を守るβカロチンなどの栄養があります。
体を冷やす野菜なので、与えすぎるとお腹が冷えて下痢になるかもしれません。
猫の口に合うように少量を小さくカットして与えるようにしてください。
さつまいも
猫に人気で安全な野菜です。
さつまいもの味や食感が大好きだという猫も少なくありません。
ビタミンやミネラル、食物繊維が多く、便秘解消の効果があります。
ただしさつまいもは炭水化物をたくさん含んでいるので、食べ過ぎは肥満の元になります。
炭水化物の消化は猫にとって苦手なので、生よりも茹でたり焼き芋にしたりして、皮を取り少量をおやつとして与えるようにしましょう。
にんじん
 にんじんは低カロリー且つ栄養価もとても高いため、猫にとって健康的で良い野菜だと認められています。
そのため、トリーツなどに含まれていることも多い野菜です。
抗酸化作用を持つβカロチンが多いので疲労からの回復や老化防止に役立ちます。
食物繊維が豊富で便秘解消にも効果があります。
人参はすりおろして与えると、消化吸収もアップするのでおすすめです。
皮付きでも問題ありませんが、よく洗ってから使いましょう。
にんじんは低カロリー且つ栄養価もとても高いため、猫にとって健康的で良い野菜だと認められています。
そのため、トリーツなどに含まれていることも多い野菜です。
抗酸化作用を持つβカロチンが多いので疲労からの回復や老化防止に役立ちます。
食物繊維が豊富で便秘解消にも効果があります。
人参はすりおろして与えると、消化吸収もアップするのでおすすめです。
皮付きでも問題ありませんが、よく洗ってから使いましょう。
かぼちゃ
かぼちゃは栄養価が高いため、手作りのフードならば、かぼちゃもメニューに加えても良いかもしれません。
かぼちゃにはビタミン・カリウム・鉄分など豊富に含まれ、風邪予防や老化防止に効果があります。
高カロリーであるため、ダイエットには向きません。
与えすぎると肥満の原因にもなるので注意が必要です。
かぼちゃは加熱して柔らかくしてから与えましょう。
皮や種も取り除くようにしてください。
小松菜
 小松菜はほうれん草よりもアクが少量で、シュウ酸の含有量もほうれん草と比較して1/15程度しかないので、量を調整すれば安心です。
ビタミン類も豊富で肝臓のサポートもしてくれます。
骨や歯を丈夫にするカルシウムも多いので、若い時から少し与えると良いでしょう。
小松菜はアブラナ科の野菜で、甲状腺ホルモンに影響を及ぼすので、甲状腺機能が低下している場合は避けたほうが良いです。
与える際には火を通し、小さくカットして消化を助けるようにしましょう。
小松菜はほうれん草よりもアクが少量で、シュウ酸の含有量もほうれん草と比較して1/15程度しかないので、量を調整すれば安心です。
ビタミン類も豊富で肝臓のサポートもしてくれます。
骨や歯を丈夫にするカルシウムも多いので、若い時から少し与えると良いでしょう。
小松菜はアブラナ科の野菜で、甲状腺ホルモンに影響を及ぼすので、甲状腺機能が低下している場合は避けたほうが良いです。
与える際には火を通し、小さくカットして消化を助けるようにしましょう。
猫が食べてはいけない野菜
 猫に与えても問題のない野菜はいずれも消化の負担にならないように、加熱やサイズに注意して与えてください。
次に猫が食べてはいけない野菜を紹介します。
健康に影響を及ぼす可能性があるものなので、ぜひ覚えておいてください。
猫に与えても問題のない野菜はいずれも消化の負担にならないように、加熱やサイズに注意して与えてください。
次に猫が食べてはいけない野菜を紹介します。
健康に影響を及ぼす可能性があるものなので、ぜひ覚えておいてください。
ネギ・玉ねぎ
猫に食べさせてはいけない野菜はまずネギ・玉ねぎです。
食べてしまったネギ・玉ねぎの量によっては、生命を失うことを覚悟しなければならないほどの症状が出ることもあります。
ねぎ類に含まれる有機チオ硫酸化合物という成分が貧血を引き起こします。
貧血になると体内の細胞に十分酸素を送れなくなり、様々な症状が出てきます。
下痢や嘔吐、発熱、血尿、元気がないなどで軽いものであっても、放っておくとどんどん進むので大変危険です。
少量であっても絶対に与えてはいけない食べ物です。
にんにく
 にんにくはネギ属という分類の野菜で、ネギと同じ有機チオ硫酸化合物が含まれています。
にんにくは玉ねぎと比較すると、猛毒性が低くて、重症化はしづらいと言われています。
ですが、大量に食べると下痢などの不調を生み出します。
ネギ類と同様に貧血を起こしてしまうので、少量でも食べないように管理することが大切です。
調理に使うことが多いにんにくなので、すりおろしたものを猫がうっかりなめたりしないように注意してください。
にんにくはネギ属という分類の野菜で、ネギと同じ有機チオ硫酸化合物が含まれています。
にんにくは玉ねぎと比較すると、猛毒性が低くて、重症化はしづらいと言われています。
ですが、大量に食べると下痢などの不調を生み出します。
ネギ類と同様に貧血を起こしてしまうので、少量でも食べないように管理することが大切です。
調理に使うことが多いにんにくなので、すりおろしたものを猫がうっかりなめたりしないように注意してください。
ニラ
ニラもネギ類に含まれるため、有機チオ硫酸化合物が含まれ、中毒症状を引き起こす危険性があります。
加熱してもその成分は壊れることはありません。
ニラは猫草のように見えることがあるため、間違って食べることのないように買ってきたニラや家庭菜園では十分注意してください。
また食べたあとの中毒症状はすぐに出るわけではなく、数日後いきなり重度の貧血になってぐったりと意識がなくなることもあります。
アスパラガス
 生のアスパラガスも猫に与えてはいけない野菜です。
アスパラガスに含まれているアルカロイドは、薬効成分のある植物毒であるため、解毒能力の弱い猫にとっては摂取NGです。
食べると腹痛・嘔吐・痙攣を起こすことがあり、心臓や腎臓、呼吸器系にも影響が出ると言われています。
また茎の周りにあるはかまと言われる葉の部分にも中毒性があります。
茹でてからなら大丈夫という見解もありますが、特に猫に与える必要性はないため、アスパラガスは与えないようにしましょう。
生のアスパラガスも猫に与えてはいけない野菜です。
アスパラガスに含まれているアルカロイドは、薬効成分のある植物毒であるため、解毒能力の弱い猫にとっては摂取NGです。
食べると腹痛・嘔吐・痙攣を起こすことがあり、心臓や腎臓、呼吸器系にも影響が出ると言われています。
また茎の周りにあるはかまと言われる葉の部分にも中毒性があります。
茹でてからなら大丈夫という見解もありますが、特に猫に与える必要性はないため、アスパラガスは与えないようにしましょう。
アボカド
アボカドにはペルシンという毒素が含まれていて、人間には無害ですが猫には有害です。
アボカドをたくさん摂取すると、嘔吐や下痢などの症状を起こします。
胃腸の炎症や消化不良、呼吸不全も起こり得るので注意です。
外国のペットフードにアボカドが含まれていることもありますが、実はアボカドには千以上の種類があり、フードに入っているアボカドはペルシンが少なく、さらに無害になる工夫がしてあるものです。
日本で販売されているアボカドはペルシンの量が多いため、毒性が強く危険な野菜です。
まとめ
猫に与えても問題ない野菜もありますが、基本的には野菜類を与えなくても大丈夫です。
野菜全般に含まれるセルロースという成分を猫は分解することができないので、消化不良になりやすいからです。
食べても良い野菜でも量によってはかえって健康を損なうことがあります。
また危険な野菜を食べて中毒になることは絶対に避けなければいけません。
調理中にうっかり猫に食べられたりしないように、食品管理を厳重にすることが一番大切です。
猫が家に帰ってこない5つの理由とは?
 家の中で生活することを推奨される猫ですが、外と出入りが自由だったりドアを開けた隙を狙って飛び出してしまったりする場合があります。
家の中に不満がある場合はもちろんですが、快適で猫にとって暮らしやすい環境であっても、戻ってこない時の猫の気持ちについて考えてみました。
家の中で生活することを推奨される猫ですが、外と出入りが自由だったりドアを開けた隙を狙って飛び出してしまったりする場合があります。
家の中に不満がある場合はもちろんですが、快適で猫にとって暮らしやすい環境であっても、戻ってこない時の猫の気持ちについて考えてみました。
理由①:家にいることがストレス
変化を嫌う猫にとって、室内の模様替えや新しく家族になった後輩猫の存在など大きなストレスとなります。
面倒見の良い性格だと、他の猫や子猫のお世話を甲斐甲斐しくしてくれる猫もいますが、今まで自分だけだった空間に知らない猫が来るのですから大抵の場合は落ち着かなくなるでしょう。
また、近所で大きな工事による騒音が長期間続いている時なども、日頃聞き慣れない大きな音にストレスを感じているかもしれません。
その場から離れたい気持ちが強くなり、脱走の可能性も考えられる状態です。
理由②:帰り道が分からない
 外に出てしまった猫は、野良猫の存在や興味を惹かれるものを追ってしまい帰り道がわからなくなることがあります。
男の子の場合、縄張りを侵されたと思われその地域に住む野良猫に追われて帰れなくなることも考えられます。
不可抗力ですが、暖かく暗い場所を求めて車の荷台に入り込み遠くの場所へ運ばれてしまった猫のニュースも度々あります。
外に出てしまった猫は、野良猫の存在や興味を惹かれるものを追ってしまい帰り道がわからなくなることがあります。
男の子の場合、縄張りを侵されたと思われその地域に住む野良猫に追われて帰れなくなることも考えられます。
不可抗力ですが、暖かく暗い場所を求めて車の荷台に入り込み遠くの場所へ運ばれてしまった猫のニュースも度々あります。
理由③:発情期だから
去勢や避妊手術をしていない猫の場合、発情期を迎えることは避けられません。
基本的に、発情を迎えた女の子の鳴き声やフェロモンに反応して男の子が発情する仕組みとなっていますので、野良猫が発情した鳴き声を聞いたお家にいる男の子が、相手を探して家を出てしまう可能性が高いといえます。
猫の発情期は暖かい季節である春と秋の年2回ですが、夜間でも街灯やお店の明かりが眩しい環境の場合、年に3回以上発情する猫もいます。
理由④:外が魅力的に見えた
 野良猫の生活をしていた経験がある猫や、好奇心旺盛な性格の場合に外の世界に興味を持ち家から出てしまうこともあります。
鳥の存在や他の猫の姿を見つけて、面白そうだと感じて外に行きたい気持ちになる心理は当然でしょう。
また、家の中に猫の本能を刺激するような上下運動が出来なかったり遊びが足りなかったりして、退屈を感じていることもありますので環境作りも大切となります。
野良猫の生活をしていた経験がある猫や、好奇心旺盛な性格の場合に外の世界に興味を持ち家から出てしまうこともあります。
鳥の存在や他の猫の姿を見つけて、面白そうだと感じて外に行きたい気持ちになる心理は当然でしょう。
また、家の中に猫の本能を刺激するような上下運動が出来なかったり遊びが足りなかったりして、退屈を感じていることもありますので環境作りも大切となります。
理由⑤:事故に遭ってしまった
交通量の多い場所や人通りのある場所など、車による不慮の事故の他にも自転車との接触など交通事故に遭う危険性が高まります。
また、他の猫との喧嘩やイタズラによる負傷も考えられるでしょう。
怪我をした猫は、自力で動ける場合に物陰や目立たない場所でじっとしていることが多く、家に帰れない状態となります。
猫が帰ってこない時の探し方
 家から出てしまった猫が帰って来ない時、飼い主様は気が気ではないはずです。
ですが、闇雲に探し回るよりも他の人の手を借りて効率的に探したほうが早いかもしれません。
ここでは、どのような方法があるかご紹介していきます。
家から出てしまった猫が帰って来ない時、飼い主様は気が気ではないはずです。
ですが、闇雲に探し回るよりも他の人の手を借りて効率的に探したほうが早いかもしれません。
ここでは、どのような方法があるかご紹介していきます。
インターネットで情報を集める
ネットは、迷子のペット情報や掲示板の他に専用サイトなど数多くの情報に繋がります。
ご自宅周辺で保護された猫の情報や目撃情報も確認できるので、不特定多数の猫好きの目を借りて情報収集してみましょう。
また、保健所に収容された場合に保護日や体の特徴の他にも写真付きで情報がアップされます。
一般の人も簡単に閲覧できるので、こちらもしっかりチェックしましょう。
捜索チラシを作成する
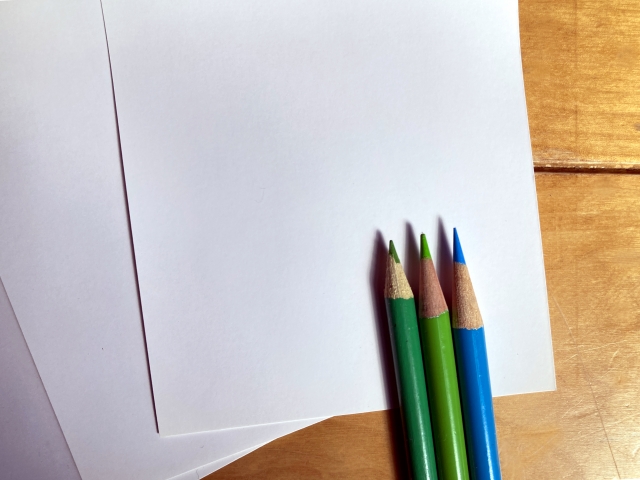 外の世界を知らない猫の場合、家の近くで動けなくなっていることがほとんどです。
いなくなってすぐであれば、猫の写真と特徴を記載したチラシを作って近所の方に周知してもらうのも効果的です。
住宅地であれば、庭の植え込みや物置の影などに隠れていることも多くあります。
また、コンビニやお店など多くの人が集まる場所にお願いして、店頭に貼らせてもらう人もいます。
内容やレイアウトに悩んでしまう場合は、捜索チラシの例文もインターネットで見つけることができますので利用してください。
外の世界を知らない猫の場合、家の近くで動けなくなっていることがほとんどです。
いなくなってすぐであれば、猫の写真と特徴を記載したチラシを作って近所の方に周知してもらうのも効果的です。
住宅地であれば、庭の植え込みや物置の影などに隠れていることも多くあります。
また、コンビニやお店など多くの人が集まる場所にお願いして、店頭に貼らせてもらう人もいます。
内容やレイアウトに悩んでしまう場合は、捜索チラシの例文もインターネットで見つけることができますので利用してください。
ペット探偵に捜索を依頼する
迷子になったペットを専門で探してくれる業者も多数あります。
捜索日数や範囲・業者によって料金に差がありますが、夜間の捜索にも対応してくれる場合がありますので飼い主様が動けない時間帯の捜索を任せることも可能です。
どこのペット探偵に頼むか、しっかりと見極めることも大切になりますので、口コミや評判を確認して納得の上で依頼をしましょう。
保健所や警察などに連絡する
 他に、保護されて保健所に収容されたり、警察に届けがある場合も考えられますので、最寄りの警察署や管轄の保健所へ必ず連絡をしてください。
特徴や居なくなったおおよその時間や日にちを詳しく連絡しておくことで、後日迷子猫の届けがあった場合に連絡をしてくれます。
他に、保護されて保健所に収容されたり、警察に届けがある場合も考えられますので、最寄りの警察署や管轄の保健所へ必ず連絡をしてください。
特徴や居なくなったおおよその時間や日にちを詳しく連絡しておくことで、後日迷子猫の届けがあった場合に連絡をしてくれます。
猫が帰ってこない事態を防ぐ対策
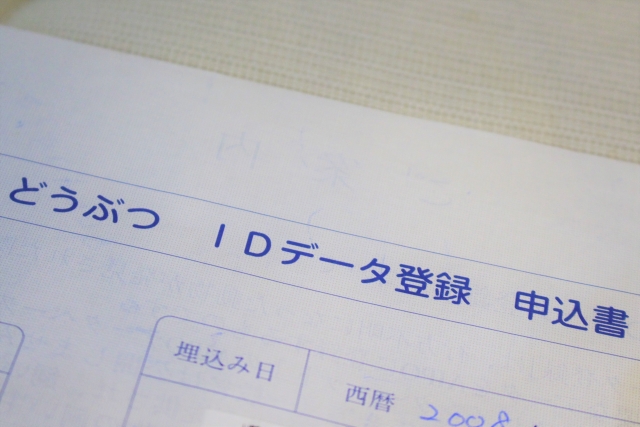 注意していても、隙を狙って外に出てしまう可能性があります。
しかし、飼い主として脱走の危険を限りなくゼロに近づける対策を行うことが大切です。
注意していても、隙を狙って外に出てしまう可能性があります。
しかし、飼い主として脱走の危険を限りなくゼロに近づける対策を行うことが大切です。
猫の姿を捉えた写真を撮影しておく
普段、よく猫の姿を撮影する方は多いかもしれません。
捜索チラシを作成する時や、インターネットを活用する時など全身が写っている写真があると特徴がよく伝わります。
また、尻尾の長さや模様・後ろ姿などがよくわかる写真を複数枚撮っておくと安心です。
網戸やドアなどの鍵のかけ忘れに注意する
 網戸のちょっとした隙間でも手を入れて開けてしまう猫も多く、「閉めているから大丈夫」とは言い切れません。
また、器用な猫ならドアノブに手を掛けて開けてしまう場合も考えられます。
戸建てのお家で一番多いのが、お風呂場の小窓の閉め忘れではないでしょうか。
換気のために開けていた窓から、出てしまうこともあります。
猫は思う以上に器用にどこからでも出入りしますので、万が一を考えて戸締りと鍵を掛けることを忘れないようにしたいですね。
網戸のちょっとした隙間でも手を入れて開けてしまう猫も多く、「閉めているから大丈夫」とは言い切れません。
また、器用な猫ならドアノブに手を掛けて開けてしまう場合も考えられます。
戸建てのお家で一番多いのが、お風呂場の小窓の閉め忘れではないでしょうか。
換気のために開けていた窓から、出てしまうこともあります。
猫は思う以上に器用にどこからでも出入りしますので、万が一を考えて戸締りと鍵を掛けることを忘れないようにしたいですね。
マイクロチップや迷子札を着用させる
猫にはまだまだ普及されている状態ではありませんが、マイクロチップの装着や首輪の迷子札が帰宅率をアップします。
迷子札は飼い主様の連絡先を記載しておけば、保護した人が連絡をくれる可能性が高くなりますのでぜひ装着させましょう。
マイクロチップは、動物病院や専門の施設で読み取り器を使用して、飼い主様の情報を確認します。
何らかの原因で首輪が外れてしまった場合、収容されている施設で確認することが可能となります。
まとめ
大切にしている家族が行方不明になったり事故にあったりして辛い思いをさせないように、戸締りはもちろん過ごしやすい環境を整えてあげましょう。
また、もし家から出てしまった場合は多くの人の手を借りてマンパワーで行動することが早い発見に繋がります。
この機会に、もしものことを考えて環境の見直しをしてみてはいかがでしょうか。
猫飼いが観葉植物を置く時の注意点
 猫を飼っている部屋に観葉植物はありますか?
肉食動物の猫ですが、植物で遊んでいてうっかり口に入れてしまうこともあります。
植物には毒性があって、下痢や嘔吐などの症状が出る危険なものもあるので、正しい知識を持っておくことが大切です。
この記事では観葉植物を置く時の注意点と安全な植物・危険な植物について解説します。
猫を飼っている部屋に観葉植物はありますか?
肉食動物の猫ですが、植物で遊んでいてうっかり口に入れてしまうこともあります。
植物には毒性があって、下痢や嘔吐などの症状が出る危険なものもあるので、正しい知識を持っておくことが大切です。
この記事では観葉植物を置く時の注意点と安全な植物・危険な植物について解説します。
風が当たりにくい場所に置く
観葉植物は必ず猫の安全を考えて置き場所を決めましょう。
まずは風が当たりにくい場所に置くことです。
扇風機やエアコンの風、窓から入ってくる風などで葉が揺れてしまうと、猫はついついじゃれついてしまいます。
それは猫が動くものに好奇心を抱いて追いかけたくなる習性があるからです。
じゃれて遊んでいるうちに、噛んでちぎれた葉っぱが口に入ったり、うっかり誤飲したりする可能性があるので注意しなければいけません。
窓側に置いて日光を植物に当てるときには、窓を閉めておきましょう。
天井に近くて高い場所に置く
 留守番中や目を離したすきに観葉植物を倒してしまったり、いたずらしたりすることも心配です。
また猫は丸い容器の中にいると落ち着くという習性があり、植木鉢が気になることがあります。
ですから、観葉植物を天井から吊るすなど、猫の手が届かない位置に置くことが大切です。
棚や窓辺などの足場が存在すると、飛び乗る危険性がありますので周囲をよく見渡して、その場所で大丈夫かどうかも確認しましょう。
高い場所に置いても猫は身軽で簡単に登れてしまうので、いたずらが可能かもしれません。
一緒に過ごせる時間帯にその場所に置いてみて、どんな行動をするか観察してみるなどの工夫をしてみてください。
留守番中や目を離したすきに観葉植物を倒してしまったり、いたずらしたりすることも心配です。
また猫は丸い容器の中にいると落ち着くという習性があり、植木鉢が気になることがあります。
ですから、観葉植物を天井から吊るすなど、猫の手が届かない位置に置くことが大切です。
棚や窓辺などの足場が存在すると、飛び乗る危険性がありますので周囲をよく見渡して、その場所で大丈夫かどうかも確認しましょう。
高い場所に置いても猫は身軽で簡単に登れてしまうので、いたずらが可能かもしれません。
一緒に過ごせる時間帯にその場所に置いてみて、どんな行動をするか観察してみるなどの工夫をしてみてください。
猫にも安全なおすすめ観葉植物一覧
 猫にとって安全で無害なおすすめの観葉植物を紹介します。
部屋のどこに置くと良いのかを考えたら、その場所に似合う観葉植物で猫にも安全な物を選んでください。
猫も観葉植物も癒やしてくれる存在になってくれることでしょう。
猫にとって安全で無害なおすすめの観葉植物を紹介します。
部屋のどこに置くと良いのかを考えたら、その場所に似合う観葉植物で猫にも安全な物を選んでください。
猫も観葉植物も癒やしてくれる存在になってくれることでしょう。
パキラ
パキラはブラジル原産の植物で、大きな葉とよじれた幹が特徴です。
人気のある観葉植物で、部屋の自然な雰囲気を盛り上げてくれます。
猫が食べても大丈夫な観葉植物で、ある程度高さがあるため、登ってしまったり、鉢を倒さないようにしたりと、置き方の工夫が必要となります。
パキラは適度な日当たりが必要なので、窓辺に置くのが良いでしょう。
エアコンの風が直接当たると枯れる原因になるので、風が当たらない場所に置いてください。
ガジュマル
 ガジュマルは沖縄などの暖かい地方で有名な植物で、「精霊の宿る木」と呼ばれています。
猫が食べても無害であるため、安心して屋内に置くことが可能です。
小さい木もあるのでテーブルに置く際は猫が落としたり、倒したりしないように対策しましょう。
ガジュマルは数年経てば、ベランダなどでも栽培できます。
夏の直射日光は当てないようにしないと葉やけするので、置き場所にも気をつけましょう。
ガジュマルは沖縄などの暖かい地方で有名な植物で、「精霊の宿る木」と呼ばれています。
猫が食べても無害であるため、安心して屋内に置くことが可能です。
小さい木もあるのでテーブルに置く際は猫が落としたり、倒したりしないように対策しましょう。
ガジュマルは数年経てば、ベランダなどでも栽培できます。
夏の直射日光は当てないようにしないと葉やけするので、置き場所にも気をつけましょう。
エバーフレッシュ
エバーフレッシュはネムノキの一種で熱帯が原産の植物なので、暑さに強いです。
ほっそりした葉は夜になると水分の蒸発を防ぐため閉じるので、ネムノキと呼ばれています。
猫が葉を食べても無害であるため、安心して屋内に置くことができます。
暑さに強いメリットと丈夫で育てやすいので観葉植物としての人気も高いです。
アジアンチックは雰囲気をプラスしてくれるのでおすすめです。
寒さに弱いので室内の温かいところに置いて冬越しさせましょう。
シュロチク
 シュロチクはヤシ科に分類される中国原産の観葉植物です。
日本では江戸時代から親しまれていて、アジアンテイストや和モダンな雰囲気にも合うスマートな印象です。
日差しが苦手で、半日陰でも育ちます。
耐寒性がすぐれているため、年間を通して、屋内でも屋外でも育てることができる初心者にもおすすめの植物です。
葉が細くて、猫がかじりやすいので、置き場所や置き方に工夫が必要です。
シュロチクはヤシ科に分類される中国原産の観葉植物です。
日本では江戸時代から親しまれていて、アジアンテイストや和モダンな雰囲気にも合うスマートな印象です。
日差しが苦手で、半日陰でも育ちます。
耐寒性がすぐれているため、年間を通して、屋内でも屋外でも育てることができる初心者にもおすすめの植物です。
葉が細くて、猫がかじりやすいので、置き場所や置き方に工夫が必要です。
テーブルヤシ
テーブルヤシはヤシの中でも小さい種類です。
名前の通り、テーブルの上などに置いて楽しめる観葉植物です。
トロピカルな雰囲気が好きな人におすすめです。
日当たりは必要ですが、陰でも大丈夫なので気温が安定した場所で育ててください。
猫が口にしても無害ですが、葉のサイズが小さく、食べやすい形なので、置き方や場所を工夫し、猫にもテーブルヤシにとっても安全な環境作りをしましょう。
猫にとって危険な観葉植物一覧
 次に猫にとって危険な観葉植物を解説します。
猫に毒性がある植物は700種類以上もあるので全てを覚えられませんが、名前が知られていて人気のある植物の中から危険なものをお伝えします。
選ぶ際にはこれらは避けておき、すでに家にある場合はその対策をしてください。
次に猫にとって危険な観葉植物を解説します。
猫に毒性がある植物は700種類以上もあるので全てを覚えられませんが、名前が知られていて人気のある植物の中から危険なものをお伝えします。
選ぶ際にはこれらは避けておき、すでに家にある場合はその対策をしてください。
ユリ
美しい花のユリを含めユリ科に分類される植物は、猫にとって最も危険な植物です。
花や花粉、葉や茎、球根など、全てに強い毒性を有しています。
拒食症的症状や嘔吐、腎臓機能不全を引き起こしてしまうため、最も気をつけるべき植物です。
花を生けている花瓶の水をなめただけでも中毒になることがあります。
猫を飼っている人は猫がいる部屋には置かないようにし、近づけない工夫をしてください。
ドラセナ
 ドラセナは葉の形や色が綺麗で人気がある観葉植物です。
「幸福の木」とも呼ばれ、贈り物でいただくこともあるでしょう。
しかし、全草に猛毒性があり、下痢や嘔吐、手足の腫れや麻痺などの症状を引き起こすことがあります。
こちらも猫のいる部屋には置かず、別の場所で管理するようにしましょう。
ドラセナは葉の形や色が綺麗で人気がある観葉植物です。
「幸福の木」とも呼ばれ、贈り物でいただくこともあるでしょう。
しかし、全草に猛毒性があり、下痢や嘔吐、手足の腫れや麻痺などの症状を引き起こすことがあります。
こちらも猫のいる部屋には置かず、別の場所で管理するようにしましょう。
アイビー
アイビーも馴染みのある植物で、簡単に育てられる初心者向けのものです。
観葉植物として人気のあるアイビーですが、腹痛や口の渇き、嘔吐や下痢という中毒症状を引き起こします。
アイビーの垂れ下がったツルは猫の興味を引きやすく、ついいたずらしたくなることが多いです。
口にするとかゆみが起こり、神経症状が出る場合もあります。
寄植えの中にも用いられることが多い植物なので、他の花と一緒に飾っていることもあるでしょう。
猫の体調を崩す恐れがあるので、同じ部屋に置くことは避けましょう。
ポトス
 ポトスは育てやすく人気がある植物です。
しかし、実は葉と茎に毒性があり、猫がかじってしまうと皮膚炎や口内の炎症などを引き起こすことがあります。
ポトスは部屋の天井など高いところから配置することがよく見られますが、それは猫にとっては絶好の遊び場です。
飛び乗って遊んでいるうちに葉をかじって、食欲がなくなって衰弱する危険性があります。
ポトスをすでに飾っている人は猫が入らない部屋で管理しましょう。
ポトスは育てやすく人気がある植物です。
しかし、実は葉と茎に毒性があり、猫がかじってしまうと皮膚炎や口内の炎症などを引き起こすことがあります。
ポトスは部屋の天井など高いところから配置することがよく見られますが、それは猫にとっては絶好の遊び場です。
飛び乗って遊んでいるうちに葉をかじって、食欲がなくなって衰弱する危険性があります。
ポトスをすでに飾っている人は猫が入らない部屋で管理しましょう。
ウンベラータ
ウンベラータは葉がハート形でおしゃれな観葉植物です。
明るいグリーンカラーでインテリアとして最適で、初心者にも育てやすい植物です。
人気の観葉植物ですが、かじると口内を刺激され、よだれや痒みなどの症状が出ます。
猫や犬などペットが誤飲すると痙攣を起こすケースがあります。
また小さな子供でもウンベラータの毒性が現れる可能性があるので、できるだけ避けたほうが良いでしょう。
猫が観葉植物で遊んでしまう時の対処法
 猫に安全で無害な観葉植物でも遊んでしまって、葉がボロボロになることがあります。
またひっくり返してしまうと部屋の中がたいへんなことになります。
特に若い猫は活発なため、遊びの対象になってしまうことが多いようです。
いたずらを避けるための方法をいくつか解説しますので、参考にしてください。
猫に安全で無害な観葉植物でも遊んでしまって、葉がボロボロになることがあります。
またひっくり返してしまうと部屋の中がたいへんなことになります。
特に若い猫は活発なため、遊びの対象になってしまうことが多いようです。
いたずらを避けるための方法をいくつか解説しますので、参考にしてください。
観葉植物にカバーをつける
猫に鉢を倒されたり、土を掘り返されたりなど、悩みがある場合は、プランターカバーの取り付けを推奨します。
カバーは鉢より大きく、ある程度重さがある方が倒れにくいので安全です。
土の上にウッドチップをかぶせておくことも猫が掘り起こすのを予防できます。
大きめの麻袋などを鉢ごと覆ってしまうのも一つの方法です。
植物を買ったお店で相談してみるのも良いですね。
木酢液をスプレーする
 木酢液はいたずら対策をしても、猫がどうしても植物で遊んでしまう時、土を掘り返してしまう場合などに使用しましょう。
木酢液は炭を焼くときに発生する煙を冷やし液体にしたもので、植物の病気や害虫予防のために使う害のない液体です。
ホームセンターで売っていますが、原液のままでは使えないので適切に薄めて使用するようにしましょう。
猫は柑橘系や酢の匂いが嫌なので、その習性を利用して木酢液を植物にかけることでいたずら対策になります。
木酢液はいたずら対策をしても、猫がどうしても植物で遊んでしまう時、土を掘り返してしまう場合などに使用しましょう。
木酢液は炭を焼くときに発生する煙を冷やし液体にしたもので、植物の病気や害虫予防のために使う害のない液体です。
ホームセンターで売っていますが、原液のままでは使えないので適切に薄めて使用するようにしましょう。
猫は柑橘系や酢の匂いが嫌なので、その習性を利用して木酢液を植物にかけることでいたずら対策になります。
まとめ
観葉植物は癒やしとなり、空気をきれいにする力も持っています。
でも、猫にとって危険な観葉植物は意外と多く、安全であってもいたずらしないような工夫が必要です。
観葉植物の種類や置く場所に注意して、猫の安全を確保できるようにしてください。
特に若い猫は好奇心が強く、思わぬ危険を呼ぶかもしれません。
しっかりと知識を持って猫との暮らしを大切に守ってあげてください。 犬に蕎麦は食べさせても大丈夫?
 結論から言うと、犬に蕎麦を食べさせるのは大丈夫です。
実は、蕎麦には犬にも食べさせたくなるほどの多くの栄養素があり、食べさせるメリットがたくさんあるんです。
ですが、その一方で、与えるときには蕎麦アレルギーや食べさせ方などにいくつかの注意点があります。
詳しく見ていきましょう。
結論から言うと、犬に蕎麦を食べさせるのは大丈夫です。
実は、蕎麦には犬にも食べさせたくなるほどの多くの栄養素があり、食べさせるメリットがたくさんあるんです。
ですが、その一方で、与えるときには蕎麦アレルギーや食べさせ方などにいくつかの注意点があります。
詳しく見ていきましょう。
蕎麦の成分と栄養素
 そもそも蕎麦には、どのような成分・栄養素があるのでしょうか?
そもそも蕎麦には、どのような成分・栄養素があるのでしょうか?
ビタミンB1・ビタミンB2
蕎麦には、「ビタミンB1」と「ビタミンB2」が多く含まれています。
ビタミンB1には疲労回復の効果が、ビタミンB2には免疫力の向上、成長の促進、栄養・脂質の代謝をあげるなどの効果があります。
ルチン
蕎麦に含まれる栄養素でもっとも代表的なのが「ルチン」です。
ルチンは、ポリフェノールの一種であり、抗酸化や毛細血管を強くする効果があります。
食物繊維
蕎麦には「食物繊維」が含まれているのも特徴的です。
食物繊維には、腸の動きを活発にし便通を良くする働きなどがあります。
蕎麦を食べさせるメリット
 蕎麦に含まれる成分・栄養素はたくさんあることはお分かり頂けたでしょうか?
これらの栄養素は犬にとって、とてもいい働きをしてくれます。
では、具体的には犬に蕎麦を食べさせるメリットには何があるのでしょうか?
まず最初に、蕎麦に含まれる「ルチン」には毛細血管を強くする働きがあるため、「動脈硬化や高血圧の予防」につながるとされています。
シニア犬などには特にメリットと言えるでしょう。
また、疲労回復の効果や栄養の代謝をあげる効果のあるビタミンB1・ビタミンB2は「健康維持」というメリットを、腸の動きを活発にしてくれる食物繊維には「便通をよくする」などのメリットを犬にもたらしてくれます。
蕎麦に含まれる成分・栄養素はたくさんあることはお分かり頂けたでしょうか?
これらの栄養素は犬にとって、とてもいい働きをしてくれます。
では、具体的には犬に蕎麦を食べさせるメリットには何があるのでしょうか?
まず最初に、蕎麦に含まれる「ルチン」には毛細血管を強くする働きがあるため、「動脈硬化や高血圧の予防」につながるとされています。
シニア犬などには特にメリットと言えるでしょう。
また、疲労回復の効果や栄養の代謝をあげる効果のあるビタミンB1・ビタミンB2は「健康維持」というメリットを、腸の動きを活発にしてくれる食物繊維には「便通をよくする」などのメリットを犬にもたらしてくれます。
蕎麦を食べさせる時の注意点
 そんな蕎麦ですが、犬に食べさせるときには注意も必要です。
ここからは、実際にどのようなことに注意しながら犬に与えればよいのかを見ていきましょう。
そんな蕎麦ですが、犬に食べさせるときには注意も必要です。
ここからは、実際にどのようなことに注意しながら犬に与えればよいのかを見ていきましょう。
①アレルギー
まず最初に、注意をしなければいけないのは「アレルギーの可能性」です。
人間でも、蕎麦アレルギーとはよく聞くことですよね。
犬は人間ほど多い割合で蕎麦アレルギーを持っているわけではないのですが、やはり一定数の蕎麦アレルギーの子もいます。
これは蕎麦という食材だけに限らず、全ての食材で同じです。
そのため、愛犬に初めて蕎麦を与えるときには十分注意して下さい。
蕎麦を初めて与えるという時には「極少量」「動物病院にすぐ行けるタイミングで」の2つを守り、万が一のときに備えておきましょう。
②与え方
次に、蕎麦の与え方にも注意が必要です。
蕎麦を犬に与えるときには、基本的に「茹でて」「冷まして」「細かく切って」の3つが基本となります。
人間同様に、蕎麦を茹でずに与えてしまうと下痢や嘔吐につながりますし、熱いまま与えてしまうと犬も口の中などを火傷してしまいます。
また、蕎麦はしっかりと細かく切って食べさせないと、喉につまらせてしまいます。
犬への蕎麦の与え方にはもうひとつ注意点があり、それが「味付けをしない」ことです。
例えば、そばつゆをつけて蕎麦を与えてしまうと、塩分が非常に強くなってしまい犬にとっては毒となってしまいます。
また、わさびやネギなどの薬味も犬にとっては非常に危険なもの。
こういったリスクを避けるためにも、犬に蕎麦を与えるときには味付けのしていない、茹でただけの蕎麦を与えるようにしましょう。
③適量
 最後に紹介する注意点は「適量を与える」ということです。
蕎麦は食物繊維を多く含んでいるため、便通が良くなるというメリットを持つ一方で、食べすぎると下痢になってしまうというデメリットもあります。
また、蕎麦だけに限りませんが、犬は自身で食べる量を調整することが難しいので、大量に与えてしまうとそれを全て食べてしまい下痢や嘔吐などの体調不良を起こすことがあります。
蕎麦を犬に与えるときには、1日に食べても大丈夫な蕎麦の適量を守って食べさせるようにしましょう。
【犬の体重】→【与えてよい蕎麦の量】
4kg未満(超小型犬) → 10g〜15g程度
5kg(小型犬程度) → 20g〜25g程度
10kg(中型犬程度) → 30~35g程度
20kg~(大型犬程度) → 50g~程度
最後に紹介する注意点は「適量を与える」ということです。
蕎麦は食物繊維を多く含んでいるため、便通が良くなるというメリットを持つ一方で、食べすぎると下痢になってしまうというデメリットもあります。
また、蕎麦だけに限りませんが、犬は自身で食べる量を調整することが難しいので、大量に与えてしまうとそれを全て食べてしまい下痢や嘔吐などの体調不良を起こすことがあります。
蕎麦を犬に与えるときには、1日に食べても大丈夫な蕎麦の適量を守って食べさせるようにしましょう。
【犬の体重】→【与えてよい蕎麦の量】
4kg未満(超小型犬) → 10g〜15g程度
5kg(小型犬程度) → 20g〜25g程度
10kg(中型犬程度) → 30~35g程度
20kg~(大型犬程度) → 50g~程度
まとめ
この記事では、犬に蕎麦を与えても大丈夫か?について紹介しました。
犬に蕎麦を食べさせることで、「動脈硬化や高血圧の予防」「健康維持」などの多くのメリットがありますが、その一方でアレルギーや与え方に飼い主の注意が必要な食べ物でもあります。
愛犬に蕎麦を与えるときには、ぜひこの記事を参考にしてみてくださいね! 犬に山芋は食べさせても大丈夫?
 山芋といえば、「山のうなぎ」と言われるほど高い栄養価を持っており、日本では古くから食べられている食材のひとつです。
さて、そんな山芋ですが果たして犬は食べても大丈夫なのでしょうか?
結論からいうと、犬は山芋を食べても大丈夫です。
山芋には犬にとっても嬉しいたくさんの栄養素があります。
ですが食べさせるときにはいくつかの注意点があり、これを知っておかないと愛犬を傷つけてしまうことにも…。
それでは、犬に山芋を食べさせるメリットやデメリットなどを詳しく見ていきましょう。
山芋といえば、「山のうなぎ」と言われるほど高い栄養価を持っており、日本では古くから食べられている食材のひとつです。
さて、そんな山芋ですが果たして犬は食べても大丈夫なのでしょうか?
結論からいうと、犬は山芋を食べても大丈夫です。
山芋には犬にとっても嬉しいたくさんの栄養素があります。
ですが食べさせるときにはいくつかの注意点があり、これを知っておかないと愛犬を傷つけてしまうことにも…。
それでは、犬に山芋を食べさせるメリットやデメリットなどを詳しく見ていきましょう。
山芋の成分・栄養素と食べるメリット
 「山のうなぎ」とも言われる山芋には、そもそも犬にとってどのような栄養素があるのでしょうか?
「山のうなぎ」とも言われる山芋には、そもそも犬にとってどのような栄養素があるのでしょうか?
アミラーゼ
アミラーゼとは、でんぷんやグリコーゲンの消化を助ける酵素の一つで胃腸薬にも使用されています。
胃もたれや食欲不振を改善するなどの、整腸作用の効果が期待できます。
人間の場合はこのアミラーゼが唾液に含まれていますが、犬の唾液には含まれておらず、犬は自身の体でアミラーゼを生成することはできません。
そのため、山芋などの食材で摂取をしましょう。
アルギニン
また、山芋にはアルギニンという、疲労回復効果や免疫力の向上が期待できる成分も含まれています。
その他にも、体脂肪の代謝を促したり、血流を促進させる、解毒効果など多くの健康維持のための効果を持っています。
ビタミンB・ビタミンC
また、ビタミンB・Cをはじめとしたビタミン群が多く含まれています。
ビタミンCには免疫機能を向上させる効果が、ビタミンBにはたんぱく質などの分解を助けエネルギーに変換する働きがあります。
山芋を食べさせるデメリット
 では、犬に山芋を食べさせるデメリットには何があるのでしょうか?
山芋を与えるデメリットのひとつに「肥満になる可能性がある」ことが挙げられます。
山芋は炭水化物なので、食べすぎてしまうと太ってしまう可能性も…。
また同時に、お腹を壊す可能性も出てきます。
犬に山芋を与える場合には、愛犬の体調をみながら適切な量を与えるようにしましょう。
また、シュウ酸カルシウムにも注意しなけれないけません。
私たち人間でも、山芋を触って、手が痒くなってしまったという経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか?
これはシュウ酸カルシウムによるものです。
犬にとっても同様に、このシュウ酸カルシウムは脅威となり得ます。
そのため、山芋を与えるときには皮膚に気を付ける必要があり、アトピー持ちの犬(皮膚が弱い犬)などは山芋が触れることで皮膚の炎症がひどくなってしまうことも…。
皮膚が弱いのであれば食べさせないのがベストです。
同時に、シュウ酸やカリウムを含んでいるため、腎疾患や腎臓結石症、尿路結石の犬にも山芋は食べさせないのがベストです。
では、犬に山芋を食べさせるデメリットには何があるのでしょうか?
山芋を与えるデメリットのひとつに「肥満になる可能性がある」ことが挙げられます。
山芋は炭水化物なので、食べすぎてしまうと太ってしまう可能性も…。
また同時に、お腹を壊す可能性も出てきます。
犬に山芋を与える場合には、愛犬の体調をみながら適切な量を与えるようにしましょう。
また、シュウ酸カルシウムにも注意しなけれないけません。
私たち人間でも、山芋を触って、手が痒くなってしまったという経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか?
これはシュウ酸カルシウムによるものです。
犬にとっても同様に、このシュウ酸カルシウムは脅威となり得ます。
そのため、山芋を与えるときには皮膚に気を付ける必要があり、アトピー持ちの犬(皮膚が弱い犬)などは山芋が触れることで皮膚の炎症がひどくなってしまうことも…。
皮膚が弱いのであれば食べさせないのがベストです。
同時に、シュウ酸やカリウムを含んでいるため、腎疾患や腎臓結石症、尿路結石の犬にも山芋は食べさせないのがベストです。
山芋を食べさせる時の注意点
 ここからは、犬に山芋を与えるときに注意するべきことを解説します。
先ほど紹介した、皮膚に触れないようにするということ以外にも犬に山芋を食べさせるときには注意したいことがあります。
詳しくみていきましょう。
ここからは、犬に山芋を与えるときに注意するべきことを解説します。
先ほど紹介した、皮膚に触れないようにするということ以外にも犬に山芋を食べさせるときには注意したいことがあります。
詳しくみていきましょう。
①与え方
 まずは山芋の与え方ですが、「できるだけ小さくカットしたもの」「すりおろしたもの」を食べさせるようにして下さい。
これは、消化不良による下痢や嘔吐を防ぐためです。
これは山芋に限らず、食材全てに当てはまりますが、人間では消化できるサイズのものでも犬にとっては消化できないことがあります。
どんなものも、必ず小さくカット、すりおろすなどの工夫をしてワンちゃんに食べさせるようにして下さい。
また、「アレルギーの可能性」も考えて与えることも大切です。
山芋に限らず、犬は初めて食べるものにアレルギー反応を起こすことがあります。
初めて山芋を与えるという時には「極少量」「動物病院にすぐ行けるタイミングで」の2つを守って与えるようにして下さい。
まずは山芋の与え方ですが、「できるだけ小さくカットしたもの」「すりおろしたもの」を食べさせるようにして下さい。
これは、消化不良による下痢や嘔吐を防ぐためです。
これは山芋に限らず、食材全てに当てはまりますが、人間では消化できるサイズのものでも犬にとっては消化できないことがあります。
どんなものも、必ず小さくカット、すりおろすなどの工夫をしてワンちゃんに食べさせるようにして下さい。
また、「アレルギーの可能性」も考えて与えることも大切です。
山芋に限らず、犬は初めて食べるものにアレルギー反応を起こすことがあります。
初めて山芋を与えるという時には「極少量」「動物病院にすぐ行けるタイミングで」の2つを守って与えるようにして下さい。
②適量
先ほども紹介したように、山芋は100gあたり120キロカロリーもあり、炭水化物なので食べすぎると肥満の原因となります。
そのため、適切な量を守って与えることがポイントとなってきます。
山芋を与えるときには以下を参考にして適量を食べさせましょう。
【犬の体重】→【与えてよい山芋の量】
5kg(小型犬程度) → 30g
10kg(中型犬程度) → 60g
20kg(大型犬程度) → 120g
まとめ
この記事では、犬に山芋を食べさせても大丈夫か?食べさせるメリット・デメリット、与え方の注意点などを解説しました。
山芋は栄養価が高い分、食べさせすぎや与え方の注意点もいくつかあります。
ぜひ、この記事を参考に、愛犬に山芋を食べさせてあげて下さいね! 犬に刺身は食べさせても大丈夫?
 私たち人間の主食の1つとも言える食材が「魚」です。
魚といえば、刺身などで食べることも多いのではないでしょうか?
飼い主さんが刺身を食べていると、物欲しそうな目でこちらを眺めてくる犬も多いですよね!
でも、犬に刺身を与えても大丈夫なのでしょうか…?
結論からいうと、犬に刺身を食べさせるのは大丈夫です。
実は、刺身には食べさせることで得られるメリットもたくさん!
ですが、与えるときにはいくつかの注意点もあります。詳しくみていきましょう。
私たち人間の主食の1つとも言える食材が「魚」です。
魚といえば、刺身などで食べることも多いのではないでしょうか?
飼い主さんが刺身を食べていると、物欲しそうな目でこちらを眺めてくる犬も多いですよね!
でも、犬に刺身を与えても大丈夫なのでしょうか…?
結論からいうと、犬に刺身を食べさせるのは大丈夫です。
実は、刺身には食べさせることで得られるメリットもたくさん!
ですが、与えるときにはいくつかの注意点もあります。詳しくみていきましょう。
刺身に含まれる成分と栄養素
 刺身(魚)の最大の栄養素はたんぱく質です。
たんぱく質は、三大栄養素のひとつでもあり、犬にとっても非常に大切な栄養となります。
刺身なのに大丈夫?と思う方も多いかと思いますが、犬はもともと肉食動物であり、魚といえども生のお肉からたんぱく質を得るのはおかしなことではないので、安心して下さい。
その他にも、魚にはEPAやDHAという必須脂肪酸が含まれています。
これらの必須脂肪酸は、血液中の中性脂肪を低下させたり、脳の機能上効果のアップ、血液をサラサラに、がん予防などの効果があります。
このように、刺身(魚)を食べさせることには非常に多くのメリットがありますが、一方で注意することもあります。
ここからは、刺身を食べさせるときの注意点をみていきましょう。
刺身(魚)の最大の栄養素はたんぱく質です。
たんぱく質は、三大栄養素のひとつでもあり、犬にとっても非常に大切な栄養となります。
刺身なのに大丈夫?と思う方も多いかと思いますが、犬はもともと肉食動物であり、魚といえども生のお肉からたんぱく質を得るのはおかしなことではないので、安心して下さい。
その他にも、魚にはEPAやDHAという必須脂肪酸が含まれています。
これらの必須脂肪酸は、血液中の中性脂肪を低下させたり、脳の機能上効果のアップ、血液をサラサラに、がん予防などの効果があります。
このように、刺身(魚)を食べさせることには非常に多くのメリットがありますが、一方で注意することもあります。
ここからは、刺身を食べさせるときの注意点をみていきましょう。
刺身を食べさせる時の注意点
 刺身を食べさせるときには、大きく3つの注意点があります。
愛犬に刺身を食べさせるときには必ずこれを読んで、守るようにして下さいね!
刺身を食べさせるときには、大きく3つの注意点があります。
愛犬に刺身を食べさせるときには必ずこれを読んで、守るようにして下さいね!
①寄生虫や危険な成分に気をつける
まず最初に注意したいのは、寄生虫に気をつけるということ。
ーーーーアニサキス寄生虫ーーーー
刺身などの生の魚には、アニサキス寄生虫が寄生している可能性があります。
有名な寄生虫なので、聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか?
アニサキス寄生虫は、胃壁や腸壁に刺入して食中毒(アニサキス症)を起こす原因となり、もしなってしまうと激しい痛み、嘔吐、内臓疾患などの症状が出てきます。
非常に危険な寄生虫なので、注意しましょう。
ーーー寄生虫以外の危険成分ーーー
また、刺身には寄生虫以外にも危険な成分が含まれています。
そのうちのひとつが「チアミナーゼ」です。
チアミナーゼには、ビタミンB1の吸収を阻害するという性質があり、過剰にこれを摂取してしまうとビタミンB1欠乏症を引き起こす可能性があります。
他にも、魚によっては「ヒスタミン」という菌を持っているものもいます。
ヒスタミンを摂取してしまうと、ヒスタミン食中毒を起こしてしまい、下痢や嘔吐、顔まわりの腫れ、蕁麻疹などの症状が出てきます。
②与え方は…加熱してがベスト!
 最初に紹介したように、刺身など、魚を生で食べても問題はありません。
ですが、魚を生で食べることで下痢や嘔吐などを起こす可能性は高くなります。
そういったリスクを考えると、基本的には、犬に魚を与えるときには、生よりも加熱して与える方がベスト!
もし、刺身で食べさせることにどうしても抵抗があるのであれば、加熱して与えるとよいでしょう。
最初に紹介したように、刺身など、魚を生で食べても問題はありません。
ですが、魚を生で食べることで下痢や嘔吐などを起こす可能性は高くなります。
そういったリスクを考えると、基本的には、犬に魚を与えるときには、生よりも加熱して与える方がベスト!
もし、刺身で食べさせることにどうしても抵抗があるのであれば、加熱して与えるとよいでしょう。
③適量を与える
次に注意したいのは「与える量」です。
まず最初に、初めて魚を犬に与えるというときにはアレルギーを持っている可能性があるので、多くを与えるのは厳禁!
初めて食べるときには「極少量」、万が一のときに「動物病院にすぐ行けるタイミングで」の2つを守って与えるようにして下さい。
今までに何度か魚を食べているという犬にも、与えすぎは要注意です。
1日にたくさんの量を与えてしまうと、消化不良を引き起こし、下痢や嘔吐につながってしまいます。
では、犬に魚を食べさせる場合、どれくらいの量を与えるのがベストなのでしょうか?
犬の体の大きさによって1日に与えてよい適量は変わってきますが、一般的には以下の量とされています。
【犬の体重】→【与えてよい魚の量】
5kg(小型犬程度) → 10g以下
10kg(中型犬程度) → 15~20g程度
20kg(大型犬程度) → 40g程度
このように見ると、意外と1日に与えてもよい量は少ないことが分かります。
くれぐれも、犬への魚の与えすぎには注意しましょう。
犬にあげてもいい?ダメ?魚一覧
 刺身によって、与えてもいい魚の種類、ダメな魚の種類はあるの?と疑問を持つ方も多いでしょう。
ここでは、代表的に刺身とされることが多い魚を与えてもいいか、ダメなのかを解説していきます。
刺身によって、与えてもいい魚の種類、ダメな魚の種類はあるの?と疑問を持つ方も多いでしょう。
ここでは、代表的に刺身とされることが多い魚を与えてもいいか、ダメなのかを解説していきます。
サーモン
 まずは、サーモンです。
サーモンは魚に食べさせても大丈夫な魚ですが、刺身はNGです。
というのも、生のサーモンにはアニサキス寄生虫の他にも、リケッチア細菌などが含まれていることが多いためです。
そのため、刺身ではなく、加熱して食べさせるようにして下さい。
また、サーモンには、アスタキサンチンは抗酸化物質が入っています。
ちなみに、これはサーモンのピンク色の元とも言われています。
アスタキサンチンには、ビタミンEの500倍以上の抗がん効果があると言われており、闘病中の犬にも食べさせることがあるほどです。
まずは、サーモンです。
サーモンは魚に食べさせても大丈夫な魚ですが、刺身はNGです。
というのも、生のサーモンにはアニサキス寄生虫の他にも、リケッチア細菌などが含まれていることが多いためです。
そのため、刺身ではなく、加熱して食べさせるようにして下さい。
また、サーモンには、アスタキサンチンは抗酸化物質が入っています。
ちなみに、これはサーモンのピンク色の元とも言われています。
アスタキサンチンには、ビタミンEの500倍以上の抗がん効果があると言われており、闘病中の犬にも食べさせることがあるほどです。
ブリ
 ブリは犬が刺身で食べても問題ない魚です。
その一方で、食べさせるときには「与えすぎはダメ」という注意点があります。
ブリは魚の中でも脂の多い魚。
たくさん食べてしまうと愛犬の肥満の原因となってしまいます。
もし食べさせるときには、できるだけ脂の部分は取り除いて与えるようにしましょう。
ブリは犬が刺身で食べても問題ない魚です。
その一方で、食べさせるときには「与えすぎはダメ」という注意点があります。
ブリは魚の中でも脂の多い魚。
たくさん食べてしまうと愛犬の肥満の原因となってしまいます。
もし食べさせるときには、できるだけ脂の部分は取り除いて与えるようにしましょう。
タイ
 タイも犬が刺身で食べても大丈夫な魚です。
さらに、ブリと違い「低脂肪」「糖質もほとんどなし」という特徴もあるので、愛犬が肥満になるリスクも回避することができます。
その一方で、他の魚よりも骨に注意しなければいけません。
タイの骨は大きいものから小さいものまで全て鋭いので、もし食べてしまうと内臓を傷つけることも…。
タイを食べさせるときには、しっかりと骨を取り除いてからにしましょう。
タイも犬が刺身で食べても大丈夫な魚です。
さらに、ブリと違い「低脂肪」「糖質もほとんどなし」という特徴もあるので、愛犬が肥満になるリスクも回避することができます。
その一方で、他の魚よりも骨に注意しなければいけません。
タイの骨は大きいものから小さいものまで全て鋭いので、もし食べてしまうと内臓を傷つけることも…。
タイを食べさせるときには、しっかりと骨を取り除いてからにしましょう。
マグロ
 マグロも犬が刺身で食べても大丈夫な魚です。
また、マグロにはオメガ3不飽和脂肪酸というものも豊富に含まれており、皮膚〜骨まで総合的に愛犬の健康維持を助けてくれます。
赤み、血合い、トロなどどの部分を与えても問題はありませんが、それぞれの特徴を知って、愛犬にとって適切な部位を与えるのがよいでしょう。
マグロの赤みには、たんぱく質が豊富(最も多い)で脂肪が少ないという特徴があります。
一方で、血合いには、たんぱく質の他にも鉄分、タウリン、ビタミンEなどの多くの栄養素がまんべんなく含まれています。
トロの部分は、脂肪分が多く、カロリー高いぶん、EHA・DHA・ビタミン群(A、D、E)が多く含まれています。
マグロも犬が刺身で食べても大丈夫な魚です。
また、マグロにはオメガ3不飽和脂肪酸というものも豊富に含まれており、皮膚〜骨まで総合的に愛犬の健康維持を助けてくれます。
赤み、血合い、トロなどどの部分を与えても問題はありませんが、それぞれの特徴を知って、愛犬にとって適切な部位を与えるのがよいでしょう。
マグロの赤みには、たんぱく質が豊富(最も多い)で脂肪が少ないという特徴があります。
一方で、血合いには、たんぱく質の他にも鉄分、タウリン、ビタミンEなどの多くの栄養素がまんべんなく含まれています。
トロの部分は、脂肪分が多く、カロリー高いぶん、EHA・DHA・ビタミン群(A、D、E)が多く含まれています。
カツオ
 カツオも犬に食べさせても大丈夫な魚ですが、刺身で食べさせるのはNG。
というのも、カツオにはアニサキス寄生虫が体内に潜んでいる可能性が非常に高いためです。
ですが、蒸したり、焼いたりして与える分にはおすすめな栄養満点の魚です。
特にカツオには、ビタミンB12が多く含まれており、これには神経機能・睡眠リズムの正常化をはかる、貧血を予防するといった効果があるとされています。
カツオも犬に食べさせても大丈夫な魚ですが、刺身で食べさせるのはNG。
というのも、カツオにはアニサキス寄生虫が体内に潜んでいる可能性が非常に高いためです。
ですが、蒸したり、焼いたりして与える分にはおすすめな栄養満点の魚です。
特にカツオには、ビタミンB12が多く含まれており、これには神経機能・睡眠リズムの正常化をはかる、貧血を予防するといった効果があるとされています。
カンパチ
 最後に紹介するのは、カンパチ。カンパチは刺身で犬に与えても大丈夫です。
カンパチを犬に与えるときには、特に血合いの部分がおすすめで、血合いにはビタミンやミネラルが多く含まれています。
血合いに含まれる栄養素は、犬の脳の働きをよいものにしてくれるので、シニア犬などにはぜひ食べさせてみましょう。
最後に紹介するのは、カンパチ。カンパチは刺身で犬に与えても大丈夫です。
カンパチを犬に与えるときには、特に血合いの部分がおすすめで、血合いにはビタミンやミネラルが多く含まれています。
血合いに含まれる栄養素は、犬の脳の働きをよいものにしてくれるので、シニア犬などにはぜひ食べさせてみましょう。
まとめ
この記事では、犬に刺身(魚)を食べさせても大丈夫か?を解説しました。
たんぱく質が多く含まれる魚は、犬にとっておすすめの食材ともいえますが、与えるときにはアニサキス寄生虫などの注意点もあります。
ぜひ、愛犬に刺身を食べさせるときにはこの記事を参考にしてみて下さいね。 犬が爪切りを嫌がる理由
 犬の爪は伸ばしたままにしていると、肉球に食い込んでしまったり、骨や関節の変形、思いがけない怪我につながることがあります。
そのため犬には定期的な爪切りが必要であり、月に1回程度はケアをしてあげなくてはいけません。
ですが、犬の中にはとっても爪切りを嫌がる子がいます。
なかには、暴れたり、勢いあまって飼い主の手を噛んでしまったりする子も…。
では、なぜ爪切りを嫌がる犬は、そこまで何をしても嫌がるのでしょうか?
実は、これにはちゃんとして理由があります。
犬の爪は伸ばしたままにしていると、肉球に食い込んでしまったり、骨や関節の変形、思いがけない怪我につながることがあります。
そのため犬には定期的な爪切りが必要であり、月に1回程度はケアをしてあげなくてはいけません。
ですが、犬の中にはとっても爪切りを嫌がる子がいます。
なかには、暴れたり、勢いあまって飼い主の手を噛んでしまったりする子も…。
では、なぜ爪切りを嫌がる犬は、そこまで何をしても嫌がるのでしょうか?
実は、これにはちゃんとして理由があります。
爪切りが怖い
犬が爪切りを嫌がる理由のひとつめが、「爪切りが怖い」です。
この「怖い」には2種類あり、ひとつが「爪切りという行為が怖い」というもの、もうひとつが「足先を触られるのが怖い」です。
基本的に、このどちらの「怖い」も背景にはトラウマがあります。
例えば、以前爪切りをしたときに痛い思いなどをした場合は「爪切りという行為を怖い」と思ってますし、爪切り中でなくても、足先を触られて痛い思いをしたことがある子は「足先を触れられるのが怖い」と思っています。
このように「爪切りが怖い」というような子には、根気よく爪切りに慣れさせ、怖くないよということを教えていかなくてはなりません。
体を触られるのが嫌い
 また、単に体を触られるが嫌いな犬もいます。
犬は基本的に、手足の先や尻尾、顔まわり、お尻などを触られるのが苦手です。
爪切りをするときには、当然手足の先を触ることになりますので、これが嫌いで爪切りを嫌う子もいます。
また、突然触ったり、強く掴む、長時間おさえつけるというのも犬は非常に嫌がるので、爪切りをするときは、こういったことをしないようにも注意しなくてはいけません。
また、単に体を触られるが嫌いな犬もいます。
犬は基本的に、手足の先や尻尾、顔まわり、お尻などを触られるのが苦手です。
爪切りをするときには、当然手足の先を触ることになりますので、これが嫌いで爪切りを嫌う子もいます。
また、突然触ったり、強く掴む、長時間おさえつけるというのも犬は非常に嫌がるので、爪切りをするときは、こういったことをしないようにも注意しなくてはいけません。
爪切りが不快
また、犬が爪切りを嫌がる理由のひとつに「爪切りが不快」というものもあります。
例えば、爪切りをする体勢が悪かったり、無理に手足をひっぱられる、周りの環境が落ち着かないという場合には、犬は爪切りを不快に感じてしまいます。
犬が爪切りを嫌がる場合は、体勢がキツそうじゃないか、手足を無理にひっぱってないかなどを一度確認すると良いでしょう。
爪切りを嫌がる犬への対処法と対策
 ここからは、爪切りを嫌がる犬への対処法や、暴れる・噛むという子への対策を8つ解説します。
愛犬の爪切りに悩んでいる飼い主さんは必見ですよ!
ここからは、爪切りを嫌がる犬への対処法や、暴れる・噛むという子への対策を8つ解説します。
愛犬の爪切りに悩んでいる飼い主さんは必見ですよ!
【下準備】①爪切りの道具に慣れさせる
まず最初に、爪切りをする前に「爪切り道具に慣れさせる」ということをしましょう。
爪切りにトラウマのある子は、爪切り道具ですら怖いものと思っているかもしれません…。
なかには、爪切りを見ただけで逃げ出すという子もいるでしょう。
そういった子には、爪切り=怖くないものということを教えなければいけません。
まずは、爪切りを持ったままおやつを与えるなどをし、爪切り=いいことが起きると思わせるようにすることが必要になってきます。
【下準備】②体を触られるのに慣れさせる
 また、先ほど紹介したように、犬の中には体を触られるのが苦手な子もいます。
そのため、爪切りをする前に、まずは体、特に手足を触られることに慣れさせなければいけません。
飼い主が意識的に日常から手足を触ってスキンシップを取ることで、ワンちゃんも徐々に慣れていきます。
最初は手足を一切触らせてくれない子もいますが、そのような子には、触らせてくれる部分を触り、徐々にそれを手足に近づけていくなどの根気と工夫が必要です。
また、先ほど紹介したように、犬の中には体を触られるのが苦手な子もいます。
そのため、爪切りをする前に、まずは体、特に手足を触られることに慣れさせなければいけません。
飼い主が意識的に日常から手足を触ってスキンシップを取ることで、ワンちゃんも徐々に慣れていきます。
最初は手足を一切触らせてくれない子もいますが、そのような子には、触らせてくれる部分を触り、徐々にそれを手足に近づけていくなどの根気と工夫が必要です。
③楽な姿勢を見つけてあげる
実際に爪切りをするときには、できるだけ犬の「楽な姿勢」を見つけてあげましょう。
犬の爪切りの際には飼い主さんも、少なからず緊張します。
それにより愛犬を力づくで抑える姿勢になってしまったり、愛犬の姿勢まで意識がまわらず、よく見たら無理な体勢だったなんてことも…。
基本的には、愛犬の手足だけを持つのではなく、抱っこしたり、体を愛犬と密着させるなどをして、愛犬の負担のない、且つ安心させてあげられる楽な姿勢で爪切りをしてあげましょう。
④言葉をかけてあげる、褒めてあげる
 また、スムーズに爪切りに慣れさせるためにも、言葉をかけてあげる、褒めてあげるということも大切になってきます。
犬にとっても、やはり慣れないときの爪切りはストレスになるものです。
爪切りをする前、爪切り中に、飼い主が「今から爪切りをするよ」「すぐ終わるからね」などと声をかけてあげると犬も安心しますし、爪切り後には「よく我慢できたね」「すごーい」などと褒めてあげると犬も爪切りに対しての悪い印象が薄れていきます。
どんなに愛犬が暴れても、ほとんど爪切りをさせてくれなくても、不満に思わず愛犬を労る、褒めるような言葉を積極的にかけてあげましょう。
また、スムーズに爪切りに慣れさせるためにも、言葉をかけてあげる、褒めてあげるということも大切になってきます。
犬にとっても、やはり慣れないときの爪切りはストレスになるものです。
爪切りをする前、爪切り中に、飼い主が「今から爪切りをするよ」「すぐ終わるからね」などと声をかけてあげると犬も安心しますし、爪切り後には「よく我慢できたね」「すごーい」などと褒めてあげると犬も爪切りに対しての悪い印象が薄れていきます。
どんなに愛犬が暴れても、ほとんど爪切りをさせてくれなくても、不満に思わず愛犬を労る、褒めるような言葉を積極的にかけてあげましょう。
⑤おやつでポジティブにさせる
また、どうしても爪切りをさせてくれない場合は「おやつでポジティブにさせる作戦」も効果的です。
犬のしつけやトリックをするときにおやつを使いますが、これはおやつ(ご褒美)をもらうことで、「その行動をする=いいことが起きる」と覚えるため。
爪切りも同様に、爪切りをする前、爪一本を切らせてくれたら、爪切り後にと、おやつを与えることで犬も徐々に「爪切り=いいこと」とポジティブに捉えてくれるようになります。
⑥エリザベスカラーを使う
 また、どうしても爪切り中に愛犬に噛まれてしまうという場合には、エリザベスカラーを使うのもおすすめです。
エリザベスカラーとは、外傷を持った子が、傷口をなめることで傷を悪化させることを防ぐ為の円錐台形状の保護具のこと。
首に装着するのが一般的です。
これを装着することで、犬も噛むことができなくなります。
また、どうしても爪切り中に愛犬に噛まれてしまうという場合には、エリザベスカラーを使うのもおすすめです。
エリザベスカラーとは、外傷を持った子が、傷口をなめることで傷を悪化させることを防ぐ為の円錐台形状の保護具のこと。
首に装着するのが一般的です。
これを装着することで、犬も噛むことができなくなります。
⑦タオルで包んであげる
 また、爪切り中に暴れる犬(小型犬や子犬など)の中には、タオルで包んで、抱きあげることで大人しくなる子もいます。
こうすることで、不思議なことに落ち着くみたいなのです。
小さなタオルではなく、バスタオルなどの犬をすっぽりと包める大きめのものを用意すると良いでしょう。
また、爪切り中に暴れる犬(小型犬や子犬など)の中には、タオルで包んで、抱きあげることで大人しくなる子もいます。
こうすることで、不思議なことに落ち着くみたいなのです。
小さなタオルではなく、バスタオルなどの犬をすっぽりと包める大きめのものを用意すると良いでしょう。
⑧タオルで目隠しをする
また、タオルで犬を大人しくさせるもう一つの方法に、タオルで犬の目隠しをするという手法もあります。
爪切りに恐怖心がある犬には特に効果的で、見せないことで爪切りへの恐怖感を和らげることができます。
すぐに大人しくなることはないでしょうが、根気よく繰り替えしていきましょう。
無理に爪切りをするのはNG!
飼い主の皆様に知っておいていただきたいのは、「無理に爪切りをするのはNG」だということ。
爪切りに慣れていない犬が恐怖心やストレスを感じるのは当たり前であり、それを無理に押さえつけてしようとしたりすると、犬も爪切りを嫌いになってしまいます。
また、いつまでたっても愛犬が爪切りを嫌がるという悪循環にも繋がってしまいます。
根気をもって、最初は一本からでもいいので、爪切りをさせれくれるような犬との関係を築いていきましょう。
まとめ
 この記事では、犬が爪切りを嫌がる理由と、その対処法などを解説しました。
犬に爪切りを慣れさせ、自然にさせてもらえるようになることは根気のいる作業です。
ぜひ、この記事を参考に無理をせずに爪切りをしてあげてくださいね!
この記事では、犬が爪切りを嫌がる理由と、その対処法などを解説しました。
犬に爪切りを慣れさせ、自然にさせてもらえるようになることは根気のいる作業です。
ぜひ、この記事を参考に無理をせずに爪切りをしてあげてくださいね! 犬に伏せを教える理由と必要性
 犬を飼ってからまず教えるものといえば、「おすわり」「待て」そして「伏せ」ですよね。
でも、犬に「伏せ」を教えるのはなぜなのでしょうか?
「おすわり」と「待て」を教える意味は、ワンちゃんを待機させるためだというのが分かりますが「伏せ」を教える必要性はあまり感じられません。
実は「伏せ」を教える理由も「おすわり」と同じく、犬を待機させるためなんです。
「おすわり」と区別して教える理由は、「伏せ」の方がより楽な姿勢になるから。
犬もお腹を地面につけれるので、長時間リラックスして待機することができます。
これが犬に「伏せ」を教える理由と必要性です。
犬を飼ってからまず教えるものといえば、「おすわり」「待て」そして「伏せ」ですよね。
でも、犬に「伏せ」を教えるのはなぜなのでしょうか?
「おすわり」と「待て」を教える意味は、ワンちゃんを待機させるためだというのが分かりますが「伏せ」を教える必要性はあまり感じられません。
実は「伏せ」を教える理由も「おすわり」と同じく、犬を待機させるためなんです。
「おすわり」と区別して教える理由は、「伏せ」の方がより楽な姿勢になるから。
犬もお腹を地面につけれるので、長時間リラックスして待機することができます。
これが犬に「伏せ」を教える理由と必要性です。
教える前に準備するもの・心構え
さて、犬に「伏せ」を教える前に準備しておきたいもの、心構えがあります。
飼い主さんは必読ですよ!
おやつ
 まずは「伏せ」などをのトレーニングをする前に、おやつを準備しておきましょう。
犬は、おやつなどのご褒美をもらうことで、何がよい行動なのかを知っていきます。
そのため「伏せ」などのトレーニング時も、成功したらおやつを与えるというようにし、何がよい行動なのかを犬に理解させます。
この、おやつというご褒美がないと、犬も何をすればよいのかが分からなくなってしまうので、必ずおやつは準備してくださいね!
まずは「伏せ」などをのトレーニングをする前に、おやつを準備しておきましょう。
犬は、おやつなどのご褒美をもらうことで、何がよい行動なのかを知っていきます。
そのため「伏せ」などのトレーニング時も、成功したらおやつを与えるというようにし、何がよい行動なのかを犬に理解させます。
この、おやつというご褒美がないと、犬も何をすればよいのかが分からなくなってしまうので、必ずおやつは準備してくださいね!
怒らず、褒める心構え
もうひとつ準備したいのは、トレーニングが上手くいかなくても「怒らない」、成功したら「褒める」という心構えです。
何度やっても失敗してまう犬もいるでしょう。
それでも、飼い主であるあなたはイライラして怒るようなことをしてはいけず、できたらその分オーバーにでも褒めてあげなければいけません。
そうすることで、犬もだんだんとあなたの言っていることが分かるようになってきます。
犬と人間は本来であればコミュニケーションができない生き物同士。
気長にやっていきましょう。
動画で分かる!伏せの教え方
ここからは「動画で分かる伏せの教え方」です。
まずは動画を見ていただき、後に詳しく文章でも解説します。
まずは「おすわり」の状態から
 「伏せ」を教えるときには、「おすわり」の状態から始めます。
「おすわり」がまだできない子は、先にそちらをマスターして「伏せ」に挑戦するようにしてくださいね!
片手におやつを握り、まず犬に「おすわり」をさせます。
「おすわり」の状態になったら、鼻先にその手を持っていき、おやつに関心を向けさせながら、徐々にゆっくりと手を下げていきます。
「伏せ」を教えるときには、「おすわり」の状態から始めます。
「おすわり」がまだできない子は、先にそちらをマスターして「伏せ」に挑戦するようにしてくださいね!
片手におやつを握り、まず犬に「おすわり」をさせます。
「おすわり」の状態になったら、鼻先にその手を持っていき、おやつに関心を向けさせながら、徐々にゆっくりと手を下げていきます。
おやつをかじらせながら、徐々に下げていく
 手を下げるときは、舐めさせたり、かじらせたりしながらでも大丈夫!
犬にとって、手に握ったおやつがいつも鼻先にあり、それが食べれそうで食べれない状態にするのがポイントです。
おやつを握った飼い主さんの手が犬の鼻先になかったりすると、犬もその場から動いてしまい、「おすわり」の体勢が崩れてしまい、「伏せ」も失敗してしまうので注意してくださいね!
手を下げるときは、舐めさせたり、かじらせたりしながらでも大丈夫!
犬にとって、手に握ったおやつがいつも鼻先にあり、それが食べれそうで食べれない状態にするのがポイントです。
おやつを握った飼い主さんの手が犬の鼻先になかったりすると、犬もその場から動いてしまい、「おすわり」の体勢が崩れてしまい、「伏せ」も失敗してしまうので注意してくださいね!
ひじが完全についたら、成功!
 おやつを徐々に下げていき、後ろ足、お腹、そしてひじが完全に床に付いたら「伏せ」成功です。
それができるまでは、おやつを与えず、何度でも繰り返しましょう。
おやつを徐々に下げていき、後ろ足、お腹、そしてひじが完全に床に付いたら「伏せ」成功です。
それができるまでは、おやつを与えず、何度でも繰り返しましょう。
伏せの状態になったら「伏せ」と号令
 ひじまで床に付き、理想の「伏せ」の状態になったら、初めて「伏せっ」と号令をかけます。
その前に、何度も「伏せ」を連呼したりすると、犬もどの状態がよいのか混乱することに…。
号令するときは「一度だけ」「はっきりと言う」を忘れずにして下さいね!
ひじまで床に付き、理想の「伏せ」の状態になったら、初めて「伏せっ」と号令をかけます。
その前に、何度も「伏せ」を連呼したりすると、犬もどの状態がよいのか混乱することに…。
号令するときは「一度だけ」「はっきりと言う」を忘れずにして下さいね!
伏せの状態にならないなら、トンネルトレーニングを
また、犬にとっては「伏せ」の状態にならない、お尻だけ上がってしまうことがあります。
この場合、無理に手で押さえつけるなどは絶対にしてはいけません。
どうしても「伏せ」の状態にならないなら、トンネルトレーニングを行いましょう。
トンネルトレーニングとは、飼い主さんが膝をトンネル状になるようにして座り、その下をおやつで誘導しながら犬に潜らせるというもの。
そうすることで、犬も自然と足を広げれるようになり、お尻だけ上がった状態になることを防ぐことができます。
ぜひ、試してみて下さいね!
「伏せ」からの「おすわり」も
ここまでは「伏せ」の教え方を解説してきました。
ある程度「伏せ」ができるようになったら、次に練習したいのが「伏せ」からの「おすわり」です。
「伏せ」ばかりを練習していると、どんな時も「伏せ」をすればいいと思ってしまう場合も…。
それを防ぐために、いつもと逆の「伏せ」からの「おすわり」も行い、「伏せ」は「伏せ」であることをしっかりと認識させましょう。
まとめ
 この記事では、犬に「伏せ」を教える方法を動画を見ながら解説しました。
「伏せ」は、ワンちゃんには是非とも教えておきたいことのひとつです。
決して簡単なことではないですが、気長に、犬を褒めてあげることを忘れることなく、ぜひ挑戦してみて下さいね!
この記事では、犬に「伏せ」を教える方法を動画を見ながら解説しました。
「伏せ」は、ワンちゃんには是非とも教えておきたいことのひとつです。
決して簡単なことではないですが、気長に、犬を褒めてあげることを忘れることなく、ぜひ挑戦してみて下さいね!
 猫は暖かい場所が大好きですよね。
特に日向ぼっこをしている猫を見ることが多く、とても気持ち良さそうにしている姿はほんと可愛いです。
ですが、猫にとって日向ぼっこは気持ちいいだけではなく、良いことがたくさんあることがわかりました。
そこでここでは、猫が日向ぼっこをする理由と効果についてご紹介していきます。
猫は暖かい場所が大好きですよね。
特に日向ぼっこをしている猫を見ることが多く、とても気持ち良さそうにしている姿はほんと可愛いです。
ですが、猫にとって日向ぼっこは気持ちいいだけではなく、良いことがたくさんあることがわかりました。
そこでここでは、猫が日向ぼっこをする理由と効果についてご紹介していきます。
 日向ぼっこをしていると、猫は気持ち良さそうにウトウトしていますよね。
それは、暖かい日差しが布団のように心地よく、体が温まって眠くなってくるからです。
猫はもともと、体力温存のためによく寝る動物ですが、暖かい場所ではより睡眠の質が高まり、起きると活発になれると言われています。
日向ぼっこをしていると、猫は気持ち良さそうにウトウトしていますよね。
それは、暖かい日差しが布団のように心地よく、体が温まって眠くなってくるからです。
猫はもともと、体力温存のためによく寝る動物ですが、暖かい場所ではより睡眠の質が高まり、起きると活発になれると言われています。
 日向ぼっこをすると、体の体温があがり、全身の血流の流れが良くなります。
それによって、新陳代謝が活発になり、免疫力がアップ。
免疫力が高まるということは、病気を予防できたり長生きにも繋がるといっても過言ではないでしょう。
日向ぼっこをすると、体の体温があがり、全身の血流の流れが良くなります。
それによって、新陳代謝が活発になり、免疫力がアップ。
免疫力が高まるということは、病気を予防できたり長生きにも繋がるといっても過言ではないでしょう。
 湿気を多く含んだ被毛は、ジットリ、ベットリとして綺麗好きな猫にとっては不快以外のなにものでもありません。
そこで、日向ぼっこをすることで、毛に含まれる水分が蒸発してフワフワになるのです。
また、湿気によるジメジメが解消されることで、皮膚病にもかかりにくくなると言われています。
湿気を多く含んだ被毛は、ジットリ、ベットリとして綺麗好きな猫にとっては不快以外のなにものでもありません。
そこで、日向ぼっこをすることで、毛に含まれる水分が蒸発してフワフワになるのです。
また、湿気によるジメジメが解消されることで、皮膚病にもかかりにくくなると言われています。
 猫が日向ぼっこを好きなことがわかりましたが、メリットばかりではなく注意しなければいけないこともあります。
猫自身が自分では気づけないことも多いので、飼い主さんが日頃から日向ぼっこをしている様子をしっかり観察してあげることが大切です。
ここでは猫が日向ぼっこをする際の注意点をご紹介します。
猫が日向ぼっこを好きなことがわかりましたが、メリットばかりではなく注意しなければいけないこともあります。
猫自身が自分では気づけないことも多いので、飼い主さんが日頃から日向ぼっこをしている様子をしっかり観察してあげることが大切です。
ここでは猫が日向ぼっこをする際の注意点をご紹介します。
 皮膚がんを気にして紫外線対策をしている方も多いかと思いますが、猫も同様に皮膚がんになる可能性があります。
猫は頭や首の色素の薄い部位に発生する傾向があり、特に白猫に注意が必要です。
窓ガラスにUVカット機能のあるシートを貼ったり、窓ガラスそのものをUVカット機能のあるものにしたりするなどの工夫をしてあげてくださいね。
皮膚がんを気にして紫外線対策をしている方も多いかと思いますが、猫も同様に皮膚がんになる可能性があります。
猫は頭や首の色素の薄い部位に発生する傾向があり、特に白猫に注意が必要です。
窓ガラスにUVカット機能のあるシートを貼ったり、窓ガラスそのものをUVカット機能のあるものにしたりするなどの工夫をしてあげてくださいね。
 野良猫の場合は、常に外にいるのでいつでも自由に日向ぼっこができますが、室内飼いの場合は、どうやって日向ぼっこをさせてあげればいいかと悩んでいる方もいるでしょう。
ここでは、猫の日向ぼっこを室内飼いで行う方法についてご紹介していきます。
野良猫の場合は、常に外にいるのでいつでも自由に日向ぼっこができますが、室内飼いの場合は、どうやって日向ぼっこをさせてあげればいいかと悩んでいる方もいるでしょう。
ここでは、猫の日向ぼっこを室内飼いで行う方法についてご紹介していきます。
 猫の日向ぼっこは、できればガラス越しではなく、日光浴ができるようにしたいもの。
網戸にして脱走防止の柵をつけておき、日光浴させるという方法も良いでしょう。
ベランダに直接出すのは危険ですが、ネットを張って脱走できないようにしたうえで出したり、大型ケージごとベランダや縁側に出したりといった方法で、ガラス越しでなくても日光を浴びることができます。
どんな状況でも外に出すことで、脱走や他の猫との接触の危険があるので、飼い主さんが必ず見ているようにしてあげてください。
猫の日向ぼっこは、できればガラス越しではなく、日光浴ができるようにしたいもの。
網戸にして脱走防止の柵をつけておき、日光浴させるという方法も良いでしょう。
ベランダに直接出すのは危険ですが、ネットを張って脱走できないようにしたうえで出したり、大型ケージごとベランダや縁側に出したりといった方法で、ガラス越しでなくても日光を浴びることができます。
どんな状況でも外に出すことで、脱走や他の猫との接触の危険があるので、飼い主さんが必ず見ているようにしてあげてください。
 猫が甘えてくる姿はとっても可愛いですが、高速でキックされるのは可愛いとばかりも言っていられず、「痛い!」と叫んでしまうこともあると思います。
猫キックは一体どんな時に、どんな気持ちでしてくるのでしょうか?
猫の気持ちから、5つの理由が考えられるのでそれを紹介します。
猫が甘えてくる姿はとっても可愛いですが、高速でキックされるのは可愛いとばかりも言っていられず、「痛い!」と叫んでしまうこともあると思います。
猫キックは一体どんな時に、どんな気持ちでしてくるのでしょうか?
猫の気持ちから、5つの理由が考えられるのでそれを紹介します。
 2つ目の理由は①とは反対のものです。
人間に触られたくないなどの「嫌!」という気持ちをキックで示すことがあります。
表情や態度、声など色々なものを使い、猫は「やめて」と気持ちを伝えますが、しつこく嫌なことをされると、猫キックをしてその人物を攻撃するようです。
やめてほしいというキックは猫が本気でやっている時なので、怒っていてかなり痛いことが多いです。
しっぽをバタバタ振ったり、耳を横にしていたりすることもあるので、そういう時は猫をそっとしておいてあげてください。
2つ目の理由は①とは反対のものです。
人間に触られたくないなどの「嫌!」という気持ちをキックで示すことがあります。
表情や態度、声など色々なものを使い、猫は「やめて」と気持ちを伝えますが、しつこく嫌なことをされると、猫キックをしてその人物を攻撃するようです。
やめてほしいというキックは猫が本気でやっている時なので、怒っていてかなり痛いことが多いです。
しっぽをバタバタ振ったり、耳を横にしていたりすることもあるので、そういう時は猫をそっとしておいてあげてください。
 飼い主さんに対してではなく、何か物に対してキックを行うこともあります。
特に家の中にいる若い猫にはよく見られます。
クッションやソファなどに向けてキックを繰り返している場合は、運動やストレス解消のために体を動かしていると考えられます。
つまり退屈しているわけです。
人間のやんちゃな子供が家の中で暴れてしまうことがありますね。
それと同じ状態ですので、余っている体力を発散させてあげると解決することが多いです。
飼い主さんに対してではなく、何か物に対してキックを行うこともあります。
特に家の中にいる若い猫にはよく見られます。
クッションやソファなどに向けてキックを繰り返している場合は、運動やストレス解消のために体を動かしていると考えられます。
つまり退屈しているわけです。
人間のやんちゃな子供が家の中で暴れてしまうことがありますね。
それと同じ状態ですので、余っている体力を発散させてあげると解決することが多いです。
 猫キックの理由はさまざまあることがわかりました。
甘えているだけでも飼い主さんが痛いことも多く、猫のストレスや興奮状態を考えるとやめさせる手立ても知っておきたいものです。
次の対処法は効果があるので、困った際には一度試してみてください。
猫キックの理由はさまざまあることがわかりました。
甘えているだけでも飼い主さんが痛いことも多く、猫のストレスや興奮状態を考えるとやめさせる手立ても知っておきたいものです。
次の対処法は効果があるので、困った際には一度試してみてください。
 特に若い猫の場合、運動不足や退屈を紛らわせるためにキックをしていることが多いです。
エネルギーがあり余っており、それを発散する機会がないのはかわいそうです。
猫キックが出る前に運動や遊びで解消させるということができれば、ストレスにもならずに済みます。
元気な猫の場合、1日に30分は遊んで運動しないとストレスに繋がると言われていますので、キャットタワーを作ってあげたり、飼い主さんとの遊び時間を増やしたりしてみるとエネルギーが発散されるでしょう。
特に若い猫の場合、運動不足や退屈を紛らわせるためにキックをしていることが多いです。
エネルギーがあり余っており、それを発散する機会がないのはかわいそうです。
猫キックが出る前に運動や遊びで解消させるということができれば、ストレスにもならずに済みます。
元気な猫の場合、1日に30分は遊んで運動しないとストレスに繋がると言われていますので、キャットタワーを作ってあげたり、飼い主さんとの遊び時間を増やしたりしてみるとエネルギーが発散されるでしょう。
 猫は顔に息を吹きかけられると、強い嫌悪感を覚えます。
そのため、猫にキックされて痛いと思った時は、猫の顔に息を吹きかけて、猫キックを防ぎましょう。
息を吹きかけるという方法は、いたずらをやめさせるときにも有効なので覚えておくと役に立ちます。
驚いてキックをやめたり、その場から去っていったりします。
でも、何回も息を吹きかけていると猫に嫌われるので、気をつけてください。
猫は顔に息を吹きかけられると、強い嫌悪感を覚えます。
そのため、猫にキックされて痛いと思った時は、猫の顔に息を吹きかけて、猫キックを防ぎましょう。
息を吹きかけるという方法は、いたずらをやめさせるときにも有効なので覚えておくと役に立ちます。
驚いてキックをやめたり、その場から去っていったりします。
でも、何回も息を吹きかけていると猫に嫌われるので、気をつけてください。
 大切なペットである猫の健康には気をつけたいですね。
食事内容にも注意して、野菜を食べたほうが良いのかどうか悩んでいる人もいると思います。
でも、結論から言って猫に野菜は必要ではありません。
完全な肉食動物ですので、野菜を食べなくても健康上問題は起こりません。
その点について詳しく、また食べても良い野菜・危険な野菜について解説します。
大切なペットである猫の健康には気をつけたいですね。
食事内容にも注意して、野菜を食べたほうが良いのかどうか悩んでいる人もいると思います。
でも、結論から言って猫に野菜は必要ではありません。
完全な肉食動物ですので、野菜を食べなくても健康上問題は起こりません。
その点について詳しく、また食べても良い野菜・危険な野菜について解説します。
 野菜にはお肉に含まれていない栄養素や酵素が含まれているため、それらを補うために与えることは悪いことではありません。
しかし、野菜を生のまま与え過ぎると、消化不良を起こしてしまう可能性があるため、注意が必要です。
猫は腸が短く、野菜や果物の消化に適していません。
葉っぱをかじって毛玉を吐き出していることもあります。
野菜を与えるときはごく少量をゆでたり、刻んだりしてあげましょう。
野菜にはお肉に含まれていない栄養素や酵素が含まれているため、それらを補うために与えることは悪いことではありません。
しかし、野菜を生のまま与え過ぎると、消化不良を起こしてしまう可能性があるため、注意が必要です。
猫は腸が短く、野菜や果物の消化に適していません。
葉っぱをかじって毛玉を吐き出していることもあります。
野菜を与えるときはごく少量をゆでたり、刻んだりしてあげましょう。
 猫は肉食動物なので野菜は必要ありませんが、ビタミンや食物繊維、酵素などが多く含まれるので栄養を補うものとして利用できます。
例えば皮膚の健康や便秘の解消などには効果があると言われています。
猫が食べても良い野菜について詳しく解説します。
猫は肉食動物なので野菜は必要ありませんが、ビタミンや食物繊維、酵素などが多く含まれるので栄養を補うものとして利用できます。
例えば皮膚の健康や便秘の解消などには効果があると言われています。
猫が食べても良い野菜について詳しく解説します。
 きゅうりは猫にとってほぼ悪影響はない野菜です。
きゅうりの90%以上は水分で出来ているため、脂肪分やナトリウムがとても少なく、低カロリーで健康的です。
夏の熱中症対策としてもおやつ代わりに与えられます。
利尿作用のあるカリウム、視力維持や皮膚を守るβカロチンなどの栄養があります。
体を冷やす野菜なので、与えすぎるとお腹が冷えて下痢になるかもしれません。
猫の口に合うように少量を小さくカットして与えるようにしてください。
きゅうりは猫にとってほぼ悪影響はない野菜です。
きゅうりの90%以上は水分で出来ているため、脂肪分やナトリウムがとても少なく、低カロリーで健康的です。
夏の熱中症対策としてもおやつ代わりに与えられます。
利尿作用のあるカリウム、視力維持や皮膚を守るβカロチンなどの栄養があります。
体を冷やす野菜なので、与えすぎるとお腹が冷えて下痢になるかもしれません。
猫の口に合うように少量を小さくカットして与えるようにしてください。
 にんじんは低カロリー且つ栄養価もとても高いため、猫にとって健康的で良い野菜だと認められています。
そのため、トリーツなどに含まれていることも多い野菜です。
抗酸化作用を持つβカロチンが多いので疲労からの回復や老化防止に役立ちます。
食物繊維が豊富で便秘解消にも効果があります。
人参はすりおろして与えると、消化吸収もアップするのでおすすめです。
皮付きでも問題ありませんが、よく洗ってから使いましょう。
にんじんは低カロリー且つ栄養価もとても高いため、猫にとって健康的で良い野菜だと認められています。
そのため、トリーツなどに含まれていることも多い野菜です。
抗酸化作用を持つβカロチンが多いので疲労からの回復や老化防止に役立ちます。
食物繊維が豊富で便秘解消にも効果があります。
人参はすりおろして与えると、消化吸収もアップするのでおすすめです。
皮付きでも問題ありませんが、よく洗ってから使いましょう。
 小松菜はほうれん草よりもアクが少量で、シュウ酸の含有量もほうれん草と比較して1/15程度しかないので、量を調整すれば安心です。
ビタミン類も豊富で肝臓のサポートもしてくれます。
骨や歯を丈夫にするカルシウムも多いので、若い時から少し与えると良いでしょう。
小松菜はアブラナ科の野菜で、甲状腺ホルモンに影響を及ぼすので、甲状腺機能が低下している場合は避けたほうが良いです。
与える際には火を通し、小さくカットして消化を助けるようにしましょう。
小松菜はほうれん草よりもアクが少量で、シュウ酸の含有量もほうれん草と比較して1/15程度しかないので、量を調整すれば安心です。
ビタミン類も豊富で肝臓のサポートもしてくれます。
骨や歯を丈夫にするカルシウムも多いので、若い時から少し与えると良いでしょう。
小松菜はアブラナ科の野菜で、甲状腺ホルモンに影響を及ぼすので、甲状腺機能が低下している場合は避けたほうが良いです。
与える際には火を通し、小さくカットして消化を助けるようにしましょう。
 猫に与えても問題のない野菜はいずれも消化の負担にならないように、加熱やサイズに注意して与えてください。
次に猫が食べてはいけない野菜を紹介します。
健康に影響を及ぼす可能性があるものなので、ぜひ覚えておいてください。
猫に与えても問題のない野菜はいずれも消化の負担にならないように、加熱やサイズに注意して与えてください。
次に猫が食べてはいけない野菜を紹介します。
健康に影響を及ぼす可能性があるものなので、ぜひ覚えておいてください。
 にんにくはネギ属という分類の野菜で、ネギと同じ有機チオ硫酸化合物が含まれています。
にんにくは玉ねぎと比較すると、猛毒性が低くて、重症化はしづらいと言われています。
ですが、大量に食べると下痢などの不調を生み出します。
ネギ類と同様に貧血を起こしてしまうので、少量でも食べないように管理することが大切です。
調理に使うことが多いにんにくなので、すりおろしたものを猫がうっかりなめたりしないように注意してください。
にんにくはネギ属という分類の野菜で、ネギと同じ有機チオ硫酸化合物が含まれています。
にんにくは玉ねぎと比較すると、猛毒性が低くて、重症化はしづらいと言われています。
ですが、大量に食べると下痢などの不調を生み出します。
ネギ類と同様に貧血を起こしてしまうので、少量でも食べないように管理することが大切です。
調理に使うことが多いにんにくなので、すりおろしたものを猫がうっかりなめたりしないように注意してください。
 生のアスパラガスも猫に与えてはいけない野菜です。
アスパラガスに含まれているアルカロイドは、薬効成分のある植物毒であるため、解毒能力の弱い猫にとっては摂取NGです。
食べると腹痛・嘔吐・痙攣を起こすことがあり、心臓や腎臓、呼吸器系にも影響が出ると言われています。
また茎の周りにあるはかまと言われる葉の部分にも中毒性があります。
茹でてからなら大丈夫という見解もありますが、特に猫に与える必要性はないため、アスパラガスは与えないようにしましょう。
生のアスパラガスも猫に与えてはいけない野菜です。
アスパラガスに含まれているアルカロイドは、薬効成分のある植物毒であるため、解毒能力の弱い猫にとっては摂取NGです。
食べると腹痛・嘔吐・痙攣を起こすことがあり、心臓や腎臓、呼吸器系にも影響が出ると言われています。
また茎の周りにあるはかまと言われる葉の部分にも中毒性があります。
茹でてからなら大丈夫という見解もありますが、特に猫に与える必要性はないため、アスパラガスは与えないようにしましょう。
 家の中で生活することを推奨される猫ですが、外と出入りが自由だったりドアを開けた隙を狙って飛び出してしまったりする場合があります。
家の中に不満がある場合はもちろんですが、快適で猫にとって暮らしやすい環境であっても、戻ってこない時の猫の気持ちについて考えてみました。
家の中で生活することを推奨される猫ですが、外と出入りが自由だったりドアを開けた隙を狙って飛び出してしまったりする場合があります。
家の中に不満がある場合はもちろんですが、快適で猫にとって暮らしやすい環境であっても、戻ってこない時の猫の気持ちについて考えてみました。
 外に出てしまった猫は、野良猫の存在や興味を惹かれるものを追ってしまい帰り道がわからなくなることがあります。
男の子の場合、縄張りを侵されたと思われその地域に住む野良猫に追われて帰れなくなることも考えられます。
不可抗力ですが、暖かく暗い場所を求めて車の荷台に入り込み遠くの場所へ運ばれてしまった猫のニュースも度々あります。
外に出てしまった猫は、野良猫の存在や興味を惹かれるものを追ってしまい帰り道がわからなくなることがあります。
男の子の場合、縄張りを侵されたと思われその地域に住む野良猫に追われて帰れなくなることも考えられます。
不可抗力ですが、暖かく暗い場所を求めて車の荷台に入り込み遠くの場所へ運ばれてしまった猫のニュースも度々あります。
 野良猫の生活をしていた経験がある猫や、好奇心旺盛な性格の場合に外の世界に興味を持ち家から出てしまうこともあります。
鳥の存在や他の猫の姿を見つけて、面白そうだと感じて外に行きたい気持ちになる心理は当然でしょう。
また、家の中に猫の本能を刺激するような上下運動が出来なかったり遊びが足りなかったりして、退屈を感じていることもありますので環境作りも大切となります。
野良猫の生活をしていた経験がある猫や、好奇心旺盛な性格の場合に外の世界に興味を持ち家から出てしまうこともあります。
鳥の存在や他の猫の姿を見つけて、面白そうだと感じて外に行きたい気持ちになる心理は当然でしょう。
また、家の中に猫の本能を刺激するような上下運動が出来なかったり遊びが足りなかったりして、退屈を感じていることもありますので環境作りも大切となります。
 家から出てしまった猫が帰って来ない時、飼い主様は気が気ではないはずです。
ですが、闇雲に探し回るよりも他の人の手を借りて効率的に探したほうが早いかもしれません。
ここでは、どのような方法があるかご紹介していきます。
家から出てしまった猫が帰って来ない時、飼い主様は気が気ではないはずです。
ですが、闇雲に探し回るよりも他の人の手を借りて効率的に探したほうが早いかもしれません。
ここでは、どのような方法があるかご紹介していきます。
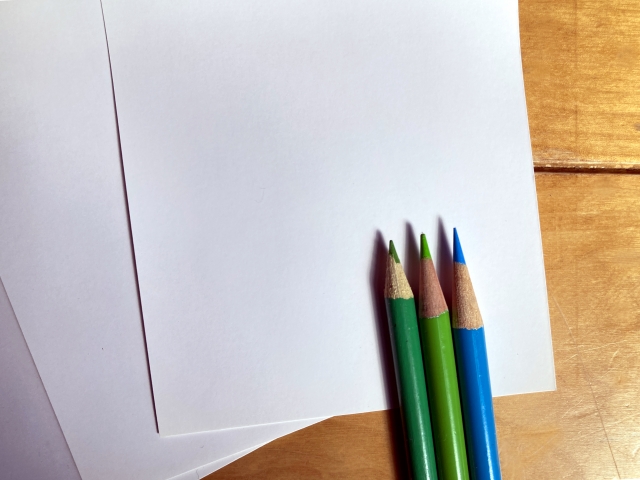 外の世界を知らない猫の場合、家の近くで動けなくなっていることがほとんどです。
いなくなってすぐであれば、猫の写真と特徴を記載したチラシを作って近所の方に周知してもらうのも効果的です。
住宅地であれば、庭の植え込みや物置の影などに隠れていることも多くあります。
また、コンビニやお店など多くの人が集まる場所にお願いして、店頭に貼らせてもらう人もいます。
内容やレイアウトに悩んでしまう場合は、捜索チラシの例文もインターネットで見つけることができますので利用してください。
外の世界を知らない猫の場合、家の近くで動けなくなっていることがほとんどです。
いなくなってすぐであれば、猫の写真と特徴を記載したチラシを作って近所の方に周知してもらうのも効果的です。
住宅地であれば、庭の植え込みや物置の影などに隠れていることも多くあります。
また、コンビニやお店など多くの人が集まる場所にお願いして、店頭に貼らせてもらう人もいます。
内容やレイアウトに悩んでしまう場合は、捜索チラシの例文もインターネットで見つけることができますので利用してください。
 他に、保護されて保健所に収容されたり、警察に届けがある場合も考えられますので、最寄りの警察署や管轄の保健所へ必ず連絡をしてください。
特徴や居なくなったおおよその時間や日にちを詳しく連絡しておくことで、後日迷子猫の届けがあった場合に連絡をしてくれます。
他に、保護されて保健所に収容されたり、警察に届けがある場合も考えられますので、最寄りの警察署や管轄の保健所へ必ず連絡をしてください。
特徴や居なくなったおおよその時間や日にちを詳しく連絡しておくことで、後日迷子猫の届けがあった場合に連絡をしてくれます。
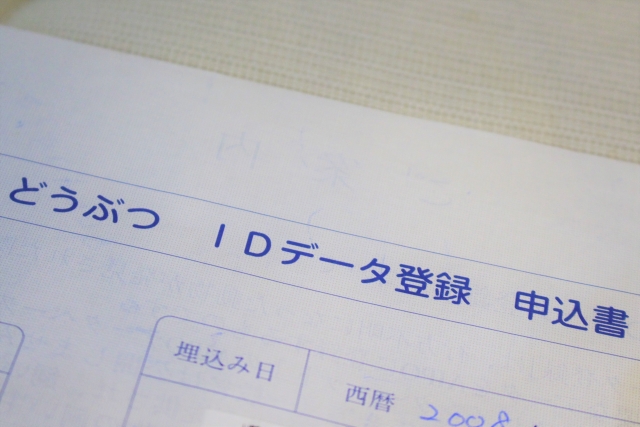 注意していても、隙を狙って外に出てしまう可能性があります。
しかし、飼い主として脱走の危険を限りなくゼロに近づける対策を行うことが大切です。
注意していても、隙を狙って外に出てしまう可能性があります。
しかし、飼い主として脱走の危険を限りなくゼロに近づける対策を行うことが大切です。
 網戸のちょっとした隙間でも手を入れて開けてしまう猫も多く、「閉めているから大丈夫」とは言い切れません。
また、器用な猫ならドアノブに手を掛けて開けてしまう場合も考えられます。
戸建てのお家で一番多いのが、お風呂場の小窓の閉め忘れではないでしょうか。
換気のために開けていた窓から、出てしまうこともあります。
猫は思う以上に器用にどこからでも出入りしますので、万が一を考えて戸締りと鍵を掛けることを忘れないようにしたいですね。
網戸のちょっとした隙間でも手を入れて開けてしまう猫も多く、「閉めているから大丈夫」とは言い切れません。
また、器用な猫ならドアノブに手を掛けて開けてしまう場合も考えられます。
戸建てのお家で一番多いのが、お風呂場の小窓の閉め忘れではないでしょうか。
換気のために開けていた窓から、出てしまうこともあります。
猫は思う以上に器用にどこからでも出入りしますので、万が一を考えて戸締りと鍵を掛けることを忘れないようにしたいですね。
 猫を飼っている部屋に観葉植物はありますか?
肉食動物の猫ですが、植物で遊んでいてうっかり口に入れてしまうこともあります。
植物には毒性があって、下痢や嘔吐などの症状が出る危険なものもあるので、正しい知識を持っておくことが大切です。
この記事では観葉植物を置く時の注意点と安全な植物・危険な植物について解説します。
猫を飼っている部屋に観葉植物はありますか?
肉食動物の猫ですが、植物で遊んでいてうっかり口に入れてしまうこともあります。
植物には毒性があって、下痢や嘔吐などの症状が出る危険なものもあるので、正しい知識を持っておくことが大切です。
この記事では観葉植物を置く時の注意点と安全な植物・危険な植物について解説します。
 留守番中や目を離したすきに観葉植物を倒してしまったり、いたずらしたりすることも心配です。
また猫は丸い容器の中にいると落ち着くという習性があり、植木鉢が気になることがあります。
ですから、観葉植物を天井から吊るすなど、猫の手が届かない位置に置くことが大切です。
棚や窓辺などの足場が存在すると、飛び乗る危険性がありますので周囲をよく見渡して、その場所で大丈夫かどうかも確認しましょう。
高い場所に置いても猫は身軽で簡単に登れてしまうので、いたずらが可能かもしれません。
一緒に過ごせる時間帯にその場所に置いてみて、どんな行動をするか観察してみるなどの工夫をしてみてください。
留守番中や目を離したすきに観葉植物を倒してしまったり、いたずらしたりすることも心配です。
また猫は丸い容器の中にいると落ち着くという習性があり、植木鉢が気になることがあります。
ですから、観葉植物を天井から吊るすなど、猫の手が届かない位置に置くことが大切です。
棚や窓辺などの足場が存在すると、飛び乗る危険性がありますので周囲をよく見渡して、その場所で大丈夫かどうかも確認しましょう。
高い場所に置いても猫は身軽で簡単に登れてしまうので、いたずらが可能かもしれません。
一緒に過ごせる時間帯にその場所に置いてみて、どんな行動をするか観察してみるなどの工夫をしてみてください。
 猫にとって安全で無害なおすすめの観葉植物を紹介します。
部屋のどこに置くと良いのかを考えたら、その場所に似合う観葉植物で猫にも安全な物を選んでください。
猫も観葉植物も癒やしてくれる存在になってくれることでしょう。
猫にとって安全で無害なおすすめの観葉植物を紹介します。
部屋のどこに置くと良いのかを考えたら、その場所に似合う観葉植物で猫にも安全な物を選んでください。
猫も観葉植物も癒やしてくれる存在になってくれることでしょう。
 ガジュマルは沖縄などの暖かい地方で有名な植物で、「精霊の宿る木」と呼ばれています。
猫が食べても無害であるため、安心して屋内に置くことが可能です。
小さい木もあるのでテーブルに置く際は猫が落としたり、倒したりしないように対策しましょう。
ガジュマルは数年経てば、ベランダなどでも栽培できます。
夏の直射日光は当てないようにしないと葉やけするので、置き場所にも気をつけましょう。
ガジュマルは沖縄などの暖かい地方で有名な植物で、「精霊の宿る木」と呼ばれています。
猫が食べても無害であるため、安心して屋内に置くことが可能です。
小さい木もあるのでテーブルに置く際は猫が落としたり、倒したりしないように対策しましょう。
ガジュマルは数年経てば、ベランダなどでも栽培できます。
夏の直射日光は当てないようにしないと葉やけするので、置き場所にも気をつけましょう。
 シュロチクはヤシ科に分類される中国原産の観葉植物です。
日本では江戸時代から親しまれていて、アジアンテイストや和モダンな雰囲気にも合うスマートな印象です。
日差しが苦手で、半日陰でも育ちます。
耐寒性がすぐれているため、年間を通して、屋内でも屋外でも育てることができる初心者にもおすすめの植物です。
葉が細くて、猫がかじりやすいので、置き場所や置き方に工夫が必要です。
シュロチクはヤシ科に分類される中国原産の観葉植物です。
日本では江戸時代から親しまれていて、アジアンテイストや和モダンな雰囲気にも合うスマートな印象です。
日差しが苦手で、半日陰でも育ちます。
耐寒性がすぐれているため、年間を通して、屋内でも屋外でも育てることができる初心者にもおすすめの植物です。
葉が細くて、猫がかじりやすいので、置き場所や置き方に工夫が必要です。
 次に猫にとって危険な観葉植物を解説します。
猫に毒性がある植物は700種類以上もあるので全てを覚えられませんが、名前が知られていて人気のある植物の中から危険なものをお伝えします。
選ぶ際にはこれらは避けておき、すでに家にある場合はその対策をしてください。
次に猫にとって危険な観葉植物を解説します。
猫に毒性がある植物は700種類以上もあるので全てを覚えられませんが、名前が知られていて人気のある植物の中から危険なものをお伝えします。
選ぶ際にはこれらは避けておき、すでに家にある場合はその対策をしてください。
 ドラセナは葉の形や色が綺麗で人気がある観葉植物です。
「幸福の木」とも呼ばれ、贈り物でいただくこともあるでしょう。
しかし、全草に猛毒性があり、下痢や嘔吐、手足の腫れや麻痺などの症状を引き起こすことがあります。
こちらも猫のいる部屋には置かず、別の場所で管理するようにしましょう。
ドラセナは葉の形や色が綺麗で人気がある観葉植物です。
「幸福の木」とも呼ばれ、贈り物でいただくこともあるでしょう。
しかし、全草に猛毒性があり、下痢や嘔吐、手足の腫れや麻痺などの症状を引き起こすことがあります。
こちらも猫のいる部屋には置かず、別の場所で管理するようにしましょう。
 ポトスは育てやすく人気がある植物です。
しかし、実は葉と茎に毒性があり、猫がかじってしまうと皮膚炎や口内の炎症などを引き起こすことがあります。
ポトスは部屋の天井など高いところから配置することがよく見られますが、それは猫にとっては絶好の遊び場です。
飛び乗って遊んでいるうちに葉をかじって、食欲がなくなって衰弱する危険性があります。
ポトスをすでに飾っている人は猫が入らない部屋で管理しましょう。
ポトスは育てやすく人気がある植物です。
しかし、実は葉と茎に毒性があり、猫がかじってしまうと皮膚炎や口内の炎症などを引き起こすことがあります。
ポトスは部屋の天井など高いところから配置することがよく見られますが、それは猫にとっては絶好の遊び場です。
飛び乗って遊んでいるうちに葉をかじって、食欲がなくなって衰弱する危険性があります。
ポトスをすでに飾っている人は猫が入らない部屋で管理しましょう。
 猫に安全で無害な観葉植物でも遊んでしまって、葉がボロボロになることがあります。
またひっくり返してしまうと部屋の中がたいへんなことになります。
特に若い猫は活発なため、遊びの対象になってしまうことが多いようです。
いたずらを避けるための方法をいくつか解説しますので、参考にしてください。
猫に安全で無害な観葉植物でも遊んでしまって、葉がボロボロになることがあります。
またひっくり返してしまうと部屋の中がたいへんなことになります。
特に若い猫は活発なため、遊びの対象になってしまうことが多いようです。
いたずらを避けるための方法をいくつか解説しますので、参考にしてください。
 木酢液はいたずら対策をしても、猫がどうしても植物で遊んでしまう時、土を掘り返してしまう場合などに使用しましょう。
木酢液は炭を焼くときに発生する煙を冷やし液体にしたもので、植物の病気や害虫予防のために使う害のない液体です。
ホームセンターで売っていますが、原液のままでは使えないので適切に薄めて使用するようにしましょう。
猫は柑橘系や酢の匂いが嫌なので、その習性を利用して木酢液を植物にかけることでいたずら対策になります。
木酢液はいたずら対策をしても、猫がどうしても植物で遊んでしまう時、土を掘り返してしまう場合などに使用しましょう。
木酢液は炭を焼くときに発生する煙を冷やし液体にしたもので、植物の病気や害虫予防のために使う害のない液体です。
ホームセンターで売っていますが、原液のままでは使えないので適切に薄めて使用するようにしましょう。
猫は柑橘系や酢の匂いが嫌なので、その習性を利用して木酢液を植物にかけることでいたずら対策になります。
 結論から言うと、犬に蕎麦を食べさせるのは大丈夫です。
実は、蕎麦には犬にも食べさせたくなるほどの多くの栄養素があり、食べさせるメリットがたくさんあるんです。
ですが、その一方で、与えるときには蕎麦アレルギーや食べさせ方などにいくつかの注意点があります。
詳しく見ていきましょう。
結論から言うと、犬に蕎麦を食べさせるのは大丈夫です。
実は、蕎麦には犬にも食べさせたくなるほどの多くの栄養素があり、食べさせるメリットがたくさんあるんです。
ですが、その一方で、与えるときには蕎麦アレルギーや食べさせ方などにいくつかの注意点があります。
詳しく見ていきましょう。
 そもそも蕎麦には、どのような成分・栄養素があるのでしょうか?
そもそも蕎麦には、どのような成分・栄養素があるのでしょうか?
 蕎麦に含まれる成分・栄養素はたくさんあることはお分かり頂けたでしょうか?
これらの栄養素は犬にとって、とてもいい働きをしてくれます。
では、具体的には犬に蕎麦を食べさせるメリットには何があるのでしょうか?
まず最初に、蕎麦に含まれる「ルチン」には毛細血管を強くする働きがあるため、「動脈硬化や高血圧の予防」につながるとされています。
シニア犬などには特にメリットと言えるでしょう。
また、疲労回復の効果や栄養の代謝をあげる効果のあるビタミンB1・ビタミンB2は「健康維持」というメリットを、腸の動きを活発にしてくれる食物繊維には「便通をよくする」などのメリットを犬にもたらしてくれます。
蕎麦に含まれる成分・栄養素はたくさんあることはお分かり頂けたでしょうか?
これらの栄養素は犬にとって、とてもいい働きをしてくれます。
では、具体的には犬に蕎麦を食べさせるメリットには何があるのでしょうか?
まず最初に、蕎麦に含まれる「ルチン」には毛細血管を強くする働きがあるため、「動脈硬化や高血圧の予防」につながるとされています。
シニア犬などには特にメリットと言えるでしょう。
また、疲労回復の効果や栄養の代謝をあげる効果のあるビタミンB1・ビタミンB2は「健康維持」というメリットを、腸の動きを活発にしてくれる食物繊維には「便通をよくする」などのメリットを犬にもたらしてくれます。
 そんな蕎麦ですが、犬に食べさせるときには注意も必要です。
ここからは、実際にどのようなことに注意しながら犬に与えればよいのかを見ていきましょう。
そんな蕎麦ですが、犬に食べさせるときには注意も必要です。
ここからは、実際にどのようなことに注意しながら犬に与えればよいのかを見ていきましょう。
 最後に紹介する注意点は「適量を与える」ということです。
蕎麦は食物繊維を多く含んでいるため、便通が良くなるというメリットを持つ一方で、食べすぎると下痢になってしまうというデメリットもあります。
また、蕎麦だけに限りませんが、犬は自身で食べる量を調整することが難しいので、大量に与えてしまうとそれを全て食べてしまい下痢や嘔吐などの体調不良を起こすことがあります。
蕎麦を犬に与えるときには、1日に食べても大丈夫な蕎麦の適量を守って食べさせるようにしましょう。
【犬の体重】→【与えてよい蕎麦の量】
4kg未満(超小型犬) → 10g〜15g程度
5kg(小型犬程度) → 20g〜25g程度
10kg(中型犬程度) → 30~35g程度
20kg~(大型犬程度) → 50g~程度
最後に紹介する注意点は「適量を与える」ということです。
蕎麦は食物繊維を多く含んでいるため、便通が良くなるというメリットを持つ一方で、食べすぎると下痢になってしまうというデメリットもあります。
また、蕎麦だけに限りませんが、犬は自身で食べる量を調整することが難しいので、大量に与えてしまうとそれを全て食べてしまい下痢や嘔吐などの体調不良を起こすことがあります。
蕎麦を犬に与えるときには、1日に食べても大丈夫な蕎麦の適量を守って食べさせるようにしましょう。
【犬の体重】→【与えてよい蕎麦の量】
4kg未満(超小型犬) → 10g〜15g程度
5kg(小型犬程度) → 20g〜25g程度
10kg(中型犬程度) → 30~35g程度
20kg~(大型犬程度) → 50g~程度
 山芋といえば、「山のうなぎ」と言われるほど高い栄養価を持っており、日本では古くから食べられている食材のひとつです。
さて、そんな山芋ですが果たして犬は食べても大丈夫なのでしょうか?
結論からいうと、犬は山芋を食べても大丈夫です。
山芋には犬にとっても嬉しいたくさんの栄養素があります。
ですが食べさせるときにはいくつかの注意点があり、これを知っておかないと愛犬を傷つけてしまうことにも…。
それでは、犬に山芋を食べさせるメリットやデメリットなどを詳しく見ていきましょう。
山芋といえば、「山のうなぎ」と言われるほど高い栄養価を持っており、日本では古くから食べられている食材のひとつです。
さて、そんな山芋ですが果たして犬は食べても大丈夫なのでしょうか?
結論からいうと、犬は山芋を食べても大丈夫です。
山芋には犬にとっても嬉しいたくさんの栄養素があります。
ですが食べさせるときにはいくつかの注意点があり、これを知っておかないと愛犬を傷つけてしまうことにも…。
それでは、犬に山芋を食べさせるメリットやデメリットなどを詳しく見ていきましょう。
 「山のうなぎ」とも言われる山芋には、そもそも犬にとってどのような栄養素があるのでしょうか?
「山のうなぎ」とも言われる山芋には、そもそも犬にとってどのような栄養素があるのでしょうか?
 では、犬に山芋を食べさせるデメリットには何があるのでしょうか?
山芋を与えるデメリットのひとつに「肥満になる可能性がある」ことが挙げられます。
山芋は炭水化物なので、食べすぎてしまうと太ってしまう可能性も…。
また同時に、お腹を壊す可能性も出てきます。
犬に山芋を与える場合には、愛犬の体調をみながら適切な量を与えるようにしましょう。
また、シュウ酸カルシウムにも注意しなけれないけません。
私たち人間でも、山芋を触って、手が痒くなってしまったという経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか?
これはシュウ酸カルシウムによるものです。
犬にとっても同様に、このシュウ酸カルシウムは脅威となり得ます。
そのため、山芋を与えるときには皮膚に気を付ける必要があり、アトピー持ちの犬(皮膚が弱い犬)などは山芋が触れることで皮膚の炎症がひどくなってしまうことも…。
皮膚が弱いのであれば食べさせないのがベストです。
同時に、シュウ酸やカリウムを含んでいるため、腎疾患や腎臓結石症、尿路結石の犬にも山芋は食べさせないのがベストです。
では、犬に山芋を食べさせるデメリットには何があるのでしょうか?
山芋を与えるデメリットのひとつに「肥満になる可能性がある」ことが挙げられます。
山芋は炭水化物なので、食べすぎてしまうと太ってしまう可能性も…。
また同時に、お腹を壊す可能性も出てきます。
犬に山芋を与える場合には、愛犬の体調をみながら適切な量を与えるようにしましょう。
また、シュウ酸カルシウムにも注意しなけれないけません。
私たち人間でも、山芋を触って、手が痒くなってしまったという経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか?
これはシュウ酸カルシウムによるものです。
犬にとっても同様に、このシュウ酸カルシウムは脅威となり得ます。
そのため、山芋を与えるときには皮膚に気を付ける必要があり、アトピー持ちの犬(皮膚が弱い犬)などは山芋が触れることで皮膚の炎症がひどくなってしまうことも…。
皮膚が弱いのであれば食べさせないのがベストです。
同時に、シュウ酸やカリウムを含んでいるため、腎疾患や腎臓結石症、尿路結石の犬にも山芋は食べさせないのがベストです。
 ここからは、犬に山芋を与えるときに注意するべきことを解説します。
先ほど紹介した、皮膚に触れないようにするということ以外にも犬に山芋を食べさせるときには注意したいことがあります。
詳しくみていきましょう。
ここからは、犬に山芋を与えるときに注意するべきことを解説します。
先ほど紹介した、皮膚に触れないようにするということ以外にも犬に山芋を食べさせるときには注意したいことがあります。
詳しくみていきましょう。
 まずは山芋の与え方ですが、「できるだけ小さくカットしたもの」「すりおろしたもの」を食べさせるようにして下さい。
これは、消化不良による下痢や嘔吐を防ぐためです。
これは山芋に限らず、食材全てに当てはまりますが、人間では消化できるサイズのものでも犬にとっては消化できないことがあります。
どんなものも、必ず小さくカット、すりおろすなどの工夫をしてワンちゃんに食べさせるようにして下さい。
また、「アレルギーの可能性」も考えて与えることも大切です。
山芋に限らず、犬は初めて食べるものにアレルギー反応を起こすことがあります。
初めて山芋を与えるという時には「極少量」「動物病院にすぐ行けるタイミングで」の2つを守って与えるようにして下さい。
まずは山芋の与え方ですが、「できるだけ小さくカットしたもの」「すりおろしたもの」を食べさせるようにして下さい。
これは、消化不良による下痢や嘔吐を防ぐためです。
これは山芋に限らず、食材全てに当てはまりますが、人間では消化できるサイズのものでも犬にとっては消化できないことがあります。
どんなものも、必ず小さくカット、すりおろすなどの工夫をしてワンちゃんに食べさせるようにして下さい。
また、「アレルギーの可能性」も考えて与えることも大切です。
山芋に限らず、犬は初めて食べるものにアレルギー反応を起こすことがあります。
初めて山芋を与えるという時には「極少量」「動物病院にすぐ行けるタイミングで」の2つを守って与えるようにして下さい。
 私たち人間の主食の1つとも言える食材が「魚」です。
魚といえば、刺身などで食べることも多いのではないでしょうか?
飼い主さんが刺身を食べていると、物欲しそうな目でこちらを眺めてくる犬も多いですよね!
でも、犬に刺身を与えても大丈夫なのでしょうか…?
結論からいうと、犬に刺身を食べさせるのは大丈夫です。
実は、刺身には食べさせることで得られるメリットもたくさん!
ですが、与えるときにはいくつかの注意点もあります。詳しくみていきましょう。
私たち人間の主食の1つとも言える食材が「魚」です。
魚といえば、刺身などで食べることも多いのではないでしょうか?
飼い主さんが刺身を食べていると、物欲しそうな目でこちらを眺めてくる犬も多いですよね!
でも、犬に刺身を与えても大丈夫なのでしょうか…?
結論からいうと、犬に刺身を食べさせるのは大丈夫です。
実は、刺身には食べさせることで得られるメリットもたくさん!
ですが、与えるときにはいくつかの注意点もあります。詳しくみていきましょう。
 刺身(魚)の最大の栄養素はたんぱく質です。
たんぱく質は、三大栄養素のひとつでもあり、犬にとっても非常に大切な栄養となります。
刺身なのに大丈夫?と思う方も多いかと思いますが、犬はもともと肉食動物であり、魚といえども生のお肉からたんぱく質を得るのはおかしなことではないので、安心して下さい。
その他にも、魚にはEPAやDHAという必須脂肪酸が含まれています。
これらの必須脂肪酸は、血液中の中性脂肪を低下させたり、脳の機能上効果のアップ、血液をサラサラに、がん予防などの効果があります。
このように、刺身(魚)を食べさせることには非常に多くのメリットがありますが、一方で注意することもあります。
ここからは、刺身を食べさせるときの注意点をみていきましょう。
刺身(魚)の最大の栄養素はたんぱく質です。
たんぱく質は、三大栄養素のひとつでもあり、犬にとっても非常に大切な栄養となります。
刺身なのに大丈夫?と思う方も多いかと思いますが、犬はもともと肉食動物であり、魚といえども生のお肉からたんぱく質を得るのはおかしなことではないので、安心して下さい。
その他にも、魚にはEPAやDHAという必須脂肪酸が含まれています。
これらの必須脂肪酸は、血液中の中性脂肪を低下させたり、脳の機能上効果のアップ、血液をサラサラに、がん予防などの効果があります。
このように、刺身(魚)を食べさせることには非常に多くのメリットがありますが、一方で注意することもあります。
ここからは、刺身を食べさせるときの注意点をみていきましょう。
 刺身を食べさせるときには、大きく3つの注意点があります。
愛犬に刺身を食べさせるときには必ずこれを読んで、守るようにして下さいね!
刺身を食べさせるときには、大きく3つの注意点があります。
愛犬に刺身を食べさせるときには必ずこれを読んで、守るようにして下さいね!
 最初に紹介したように、刺身など、魚を生で食べても問題はありません。
ですが、魚を生で食べることで下痢や嘔吐などを起こす可能性は高くなります。
そういったリスクを考えると、基本的には、犬に魚を与えるときには、生よりも加熱して与える方がベスト!
もし、刺身で食べさせることにどうしても抵抗があるのであれば、加熱して与えるとよいでしょう。
最初に紹介したように、刺身など、魚を生で食べても問題はありません。
ですが、魚を生で食べることで下痢や嘔吐などを起こす可能性は高くなります。
そういったリスクを考えると、基本的には、犬に魚を与えるときには、生よりも加熱して与える方がベスト!
もし、刺身で食べさせることにどうしても抵抗があるのであれば、加熱して与えるとよいでしょう。
 刺身によって、与えてもいい魚の種類、ダメな魚の種類はあるの?と疑問を持つ方も多いでしょう。
ここでは、代表的に刺身とされることが多い魚を与えてもいいか、ダメなのかを解説していきます。
刺身によって、与えてもいい魚の種類、ダメな魚の種類はあるの?と疑問を持つ方も多いでしょう。
ここでは、代表的に刺身とされることが多い魚を与えてもいいか、ダメなのかを解説していきます。
 まずは、サーモンです。
サーモンは魚に食べさせても大丈夫な魚ですが、刺身はNGです。
というのも、生のサーモンにはアニサキス寄生虫の他にも、リケッチア細菌などが含まれていることが多いためです。
そのため、刺身ではなく、加熱して食べさせるようにして下さい。
また、サーモンには、アスタキサンチンは抗酸化物質が入っています。
ちなみに、これはサーモンのピンク色の元とも言われています。
アスタキサンチンには、ビタミンEの500倍以上の抗がん効果があると言われており、闘病中の犬にも食べさせることがあるほどです。
まずは、サーモンです。
サーモンは魚に食べさせても大丈夫な魚ですが、刺身はNGです。
というのも、生のサーモンにはアニサキス寄生虫の他にも、リケッチア細菌などが含まれていることが多いためです。
そのため、刺身ではなく、加熱して食べさせるようにして下さい。
また、サーモンには、アスタキサンチンは抗酸化物質が入っています。
ちなみに、これはサーモンのピンク色の元とも言われています。
アスタキサンチンには、ビタミンEの500倍以上の抗がん効果があると言われており、闘病中の犬にも食べさせることがあるほどです。
 ブリは犬が刺身で食べても問題ない魚です。
その一方で、食べさせるときには「与えすぎはダメ」という注意点があります。
ブリは魚の中でも脂の多い魚。
たくさん食べてしまうと愛犬の肥満の原因となってしまいます。
もし食べさせるときには、できるだけ脂の部分は取り除いて与えるようにしましょう。
ブリは犬が刺身で食べても問題ない魚です。
その一方で、食べさせるときには「与えすぎはダメ」という注意点があります。
ブリは魚の中でも脂の多い魚。
たくさん食べてしまうと愛犬の肥満の原因となってしまいます。
もし食べさせるときには、できるだけ脂の部分は取り除いて与えるようにしましょう。
 タイも犬が刺身で食べても大丈夫な魚です。
さらに、ブリと違い「低脂肪」「糖質もほとんどなし」という特徴もあるので、愛犬が肥満になるリスクも回避することができます。
その一方で、他の魚よりも骨に注意しなければいけません。
タイの骨は大きいものから小さいものまで全て鋭いので、もし食べてしまうと内臓を傷つけることも…。
タイを食べさせるときには、しっかりと骨を取り除いてからにしましょう。
タイも犬が刺身で食べても大丈夫な魚です。
さらに、ブリと違い「低脂肪」「糖質もほとんどなし」という特徴もあるので、愛犬が肥満になるリスクも回避することができます。
その一方で、他の魚よりも骨に注意しなければいけません。
タイの骨は大きいものから小さいものまで全て鋭いので、もし食べてしまうと内臓を傷つけることも…。
タイを食べさせるときには、しっかりと骨を取り除いてからにしましょう。
 マグロも犬が刺身で食べても大丈夫な魚です。
また、マグロにはオメガ3不飽和脂肪酸というものも豊富に含まれており、皮膚〜骨まで総合的に愛犬の健康維持を助けてくれます。
赤み、血合い、トロなどどの部分を与えても問題はありませんが、それぞれの特徴を知って、愛犬にとって適切な部位を与えるのがよいでしょう。
マグロの赤みには、たんぱく質が豊富(最も多い)で脂肪が少ないという特徴があります。
一方で、血合いには、たんぱく質の他にも鉄分、タウリン、ビタミンEなどの多くの栄養素がまんべんなく含まれています。
トロの部分は、脂肪分が多く、カロリー高いぶん、EHA・DHA・ビタミン群(A、D、E)が多く含まれています。
マグロも犬が刺身で食べても大丈夫な魚です。
また、マグロにはオメガ3不飽和脂肪酸というものも豊富に含まれており、皮膚〜骨まで総合的に愛犬の健康維持を助けてくれます。
赤み、血合い、トロなどどの部分を与えても問題はありませんが、それぞれの特徴を知って、愛犬にとって適切な部位を与えるのがよいでしょう。
マグロの赤みには、たんぱく質が豊富(最も多い)で脂肪が少ないという特徴があります。
一方で、血合いには、たんぱく質の他にも鉄分、タウリン、ビタミンEなどの多くの栄養素がまんべんなく含まれています。
トロの部分は、脂肪分が多く、カロリー高いぶん、EHA・DHA・ビタミン群(A、D、E)が多く含まれています。
 カツオも犬に食べさせても大丈夫な魚ですが、刺身で食べさせるのはNG。
というのも、カツオにはアニサキス寄生虫が体内に潜んでいる可能性が非常に高いためです。
ですが、蒸したり、焼いたりして与える分にはおすすめな栄養満点の魚です。
特にカツオには、ビタミンB12が多く含まれており、これには神経機能・睡眠リズムの正常化をはかる、貧血を予防するといった効果があるとされています。
カツオも犬に食べさせても大丈夫な魚ですが、刺身で食べさせるのはNG。
というのも、カツオにはアニサキス寄生虫が体内に潜んでいる可能性が非常に高いためです。
ですが、蒸したり、焼いたりして与える分にはおすすめな栄養満点の魚です。
特にカツオには、ビタミンB12が多く含まれており、これには神経機能・睡眠リズムの正常化をはかる、貧血を予防するといった効果があるとされています。
 最後に紹介するのは、カンパチ。カンパチは刺身で犬に与えても大丈夫です。
カンパチを犬に与えるときには、特に血合いの部分がおすすめで、血合いにはビタミンやミネラルが多く含まれています。
血合いに含まれる栄養素は、犬の脳の働きをよいものにしてくれるので、シニア犬などにはぜひ食べさせてみましょう。
最後に紹介するのは、カンパチ。カンパチは刺身で犬に与えても大丈夫です。
カンパチを犬に与えるときには、特に血合いの部分がおすすめで、血合いにはビタミンやミネラルが多く含まれています。
血合いに含まれる栄養素は、犬の脳の働きをよいものにしてくれるので、シニア犬などにはぜひ食べさせてみましょう。
 犬の爪は伸ばしたままにしていると、肉球に食い込んでしまったり、骨や関節の変形、思いがけない怪我につながることがあります。
そのため犬には定期的な爪切りが必要であり、月に1回程度はケアをしてあげなくてはいけません。
ですが、犬の中にはとっても爪切りを嫌がる子がいます。
なかには、暴れたり、勢いあまって飼い主の手を噛んでしまったりする子も…。
では、なぜ爪切りを嫌がる犬は、そこまで何をしても嫌がるのでしょうか?
実は、これにはちゃんとして理由があります。
犬の爪は伸ばしたままにしていると、肉球に食い込んでしまったり、骨や関節の変形、思いがけない怪我につながることがあります。
そのため犬には定期的な爪切りが必要であり、月に1回程度はケアをしてあげなくてはいけません。
ですが、犬の中にはとっても爪切りを嫌がる子がいます。
なかには、暴れたり、勢いあまって飼い主の手を噛んでしまったりする子も…。
では、なぜ爪切りを嫌がる犬は、そこまで何をしても嫌がるのでしょうか?
実は、これにはちゃんとして理由があります。
 また、単に体を触られるが嫌いな犬もいます。
犬は基本的に、手足の先や尻尾、顔まわり、お尻などを触られるのが苦手です。
爪切りをするときには、当然手足の先を触ることになりますので、これが嫌いで爪切りを嫌う子もいます。
また、突然触ったり、強く掴む、長時間おさえつけるというのも犬は非常に嫌がるので、爪切りをするときは、こういったことをしないようにも注意しなくてはいけません。
また、単に体を触られるが嫌いな犬もいます。
犬は基本的に、手足の先や尻尾、顔まわり、お尻などを触られるのが苦手です。
爪切りをするときには、当然手足の先を触ることになりますので、これが嫌いで爪切りを嫌う子もいます。
また、突然触ったり、強く掴む、長時間おさえつけるというのも犬は非常に嫌がるので、爪切りをするときは、こういったことをしないようにも注意しなくてはいけません。
 ここからは、爪切りを嫌がる犬への対処法や、暴れる・噛むという子への対策を8つ解説します。
愛犬の爪切りに悩んでいる飼い主さんは必見ですよ!
ここからは、爪切りを嫌がる犬への対処法や、暴れる・噛むという子への対策を8つ解説します。
愛犬の爪切りに悩んでいる飼い主さんは必見ですよ!
 また、先ほど紹介したように、犬の中には体を触られるのが苦手な子もいます。
そのため、爪切りをする前に、まずは体、特に手足を触られることに慣れさせなければいけません。
飼い主が意識的に日常から手足を触ってスキンシップを取ることで、ワンちゃんも徐々に慣れていきます。
最初は手足を一切触らせてくれない子もいますが、そのような子には、触らせてくれる部分を触り、徐々にそれを手足に近づけていくなどの根気と工夫が必要です。
また、先ほど紹介したように、犬の中には体を触られるのが苦手な子もいます。
そのため、爪切りをする前に、まずは体、特に手足を触られることに慣れさせなければいけません。
飼い主が意識的に日常から手足を触ってスキンシップを取ることで、ワンちゃんも徐々に慣れていきます。
最初は手足を一切触らせてくれない子もいますが、そのような子には、触らせてくれる部分を触り、徐々にそれを手足に近づけていくなどの根気と工夫が必要です。
 また、スムーズに爪切りに慣れさせるためにも、言葉をかけてあげる、褒めてあげるということも大切になってきます。
犬にとっても、やはり慣れないときの爪切りはストレスになるものです。
爪切りをする前、爪切り中に、飼い主が「今から爪切りをするよ」「すぐ終わるからね」などと声をかけてあげると犬も安心しますし、爪切り後には「よく我慢できたね」「すごーい」などと褒めてあげると犬も爪切りに対しての悪い印象が薄れていきます。
どんなに愛犬が暴れても、ほとんど爪切りをさせてくれなくても、不満に思わず愛犬を労る、褒めるような言葉を積極的にかけてあげましょう。
また、スムーズに爪切りに慣れさせるためにも、言葉をかけてあげる、褒めてあげるということも大切になってきます。
犬にとっても、やはり慣れないときの爪切りはストレスになるものです。
爪切りをする前、爪切り中に、飼い主が「今から爪切りをするよ」「すぐ終わるからね」などと声をかけてあげると犬も安心しますし、爪切り後には「よく我慢できたね」「すごーい」などと褒めてあげると犬も爪切りに対しての悪い印象が薄れていきます。
どんなに愛犬が暴れても、ほとんど爪切りをさせてくれなくても、不満に思わず愛犬を労る、褒めるような言葉を積極的にかけてあげましょう。
 また、どうしても爪切り中に愛犬に噛まれてしまうという場合には、エリザベスカラーを使うのもおすすめです。
エリザベスカラーとは、外傷を持った子が、傷口をなめることで傷を悪化させることを防ぐ為の円錐台形状の保護具のこと。
首に装着するのが一般的です。
これを装着することで、犬も噛むことができなくなります。
また、どうしても爪切り中に愛犬に噛まれてしまうという場合には、エリザベスカラーを使うのもおすすめです。
エリザベスカラーとは、外傷を持った子が、傷口をなめることで傷を悪化させることを防ぐ為の円錐台形状の保護具のこと。
首に装着するのが一般的です。
これを装着することで、犬も噛むことができなくなります。
 また、爪切り中に暴れる犬(小型犬や子犬など)の中には、タオルで包んで、抱きあげることで大人しくなる子もいます。
こうすることで、不思議なことに落ち着くみたいなのです。
小さなタオルではなく、バスタオルなどの犬をすっぽりと包める大きめのものを用意すると良いでしょう。
また、爪切り中に暴れる犬(小型犬や子犬など)の中には、タオルで包んで、抱きあげることで大人しくなる子もいます。
こうすることで、不思議なことに落ち着くみたいなのです。
小さなタオルではなく、バスタオルなどの犬をすっぽりと包める大きめのものを用意すると良いでしょう。
 この記事では、犬が爪切りを嫌がる理由と、その対処法などを解説しました。
犬に爪切りを慣れさせ、自然にさせてもらえるようになることは根気のいる作業です。
ぜひ、この記事を参考に無理をせずに爪切りをしてあげてくださいね!
この記事では、犬が爪切りを嫌がる理由と、その対処法などを解説しました。
犬に爪切りを慣れさせ、自然にさせてもらえるようになることは根気のいる作業です。
ぜひ、この記事を参考に無理をせずに爪切りをしてあげてくださいね!  犬を飼ってからまず教えるものといえば、「おすわり」「待て」そして「伏せ」ですよね。
でも、犬に「伏せ」を教えるのはなぜなのでしょうか?
「おすわり」と「待て」を教える意味は、ワンちゃんを待機させるためだというのが分かりますが「伏せ」を教える必要性はあまり感じられません。
実は「伏せ」を教える理由も「おすわり」と同じく、犬を待機させるためなんです。
「おすわり」と区別して教える理由は、「伏せ」の方がより楽な姿勢になるから。
犬もお腹を地面につけれるので、長時間リラックスして待機することができます。
これが犬に「伏せ」を教える理由と必要性です。
犬を飼ってからまず教えるものといえば、「おすわり」「待て」そして「伏せ」ですよね。
でも、犬に「伏せ」を教えるのはなぜなのでしょうか?
「おすわり」と「待て」を教える意味は、ワンちゃんを待機させるためだというのが分かりますが「伏せ」を教える必要性はあまり感じられません。
実は「伏せ」を教える理由も「おすわり」と同じく、犬を待機させるためなんです。
「おすわり」と区別して教える理由は、「伏せ」の方がより楽な姿勢になるから。
犬もお腹を地面につけれるので、長時間リラックスして待機することができます。
これが犬に「伏せ」を教える理由と必要性です。
 まずは「伏せ」などをのトレーニングをする前に、おやつを準備しておきましょう。
犬は、おやつなどのご褒美をもらうことで、何がよい行動なのかを知っていきます。
そのため「伏せ」などのトレーニング時も、成功したらおやつを与えるというようにし、何がよい行動なのかを犬に理解させます。
この、おやつというご褒美がないと、犬も何をすればよいのかが分からなくなってしまうので、必ずおやつは準備してくださいね!
まずは「伏せ」などをのトレーニングをする前に、おやつを準備しておきましょう。
犬は、おやつなどのご褒美をもらうことで、何がよい行動なのかを知っていきます。
そのため「伏せ」などのトレーニング時も、成功したらおやつを与えるというようにし、何がよい行動なのかを犬に理解させます。
この、おやつというご褒美がないと、犬も何をすればよいのかが分からなくなってしまうので、必ずおやつは準備してくださいね!
 「伏せ」を教えるときには、「おすわり」の状態から始めます。
「おすわり」がまだできない子は、先にそちらをマスターして「伏せ」に挑戦するようにしてくださいね!
片手におやつを握り、まず犬に「おすわり」をさせます。
「おすわり」の状態になったら、鼻先にその手を持っていき、おやつに関心を向けさせながら、徐々にゆっくりと手を下げていきます。
「伏せ」を教えるときには、「おすわり」の状態から始めます。
「おすわり」がまだできない子は、先にそちらをマスターして「伏せ」に挑戦するようにしてくださいね!
片手におやつを握り、まず犬に「おすわり」をさせます。
「おすわり」の状態になったら、鼻先にその手を持っていき、おやつに関心を向けさせながら、徐々にゆっくりと手を下げていきます。
 手を下げるときは、舐めさせたり、かじらせたりしながらでも大丈夫!
犬にとって、手に握ったおやつがいつも鼻先にあり、それが食べれそうで食べれない状態にするのがポイントです。
おやつを握った飼い主さんの手が犬の鼻先になかったりすると、犬もその場から動いてしまい、「おすわり」の体勢が崩れてしまい、「伏せ」も失敗してしまうので注意してくださいね!
手を下げるときは、舐めさせたり、かじらせたりしながらでも大丈夫!
犬にとって、手に握ったおやつがいつも鼻先にあり、それが食べれそうで食べれない状態にするのがポイントです。
おやつを握った飼い主さんの手が犬の鼻先になかったりすると、犬もその場から動いてしまい、「おすわり」の体勢が崩れてしまい、「伏せ」も失敗してしまうので注意してくださいね!
 おやつを徐々に下げていき、後ろ足、お腹、そしてひじが完全に床に付いたら「伏せ」成功です。
それができるまでは、おやつを与えず、何度でも繰り返しましょう。
おやつを徐々に下げていき、後ろ足、お腹、そしてひじが完全に床に付いたら「伏せ」成功です。
それができるまでは、おやつを与えず、何度でも繰り返しましょう。
 ひじまで床に付き、理想の「伏せ」の状態になったら、初めて「伏せっ」と号令をかけます。
その前に、何度も「伏せ」を連呼したりすると、犬もどの状態がよいのか混乱することに…。
号令するときは「一度だけ」「はっきりと言う」を忘れずにして下さいね!
ひじまで床に付き、理想の「伏せ」の状態になったら、初めて「伏せっ」と号令をかけます。
その前に、何度も「伏せ」を連呼したりすると、犬もどの状態がよいのか混乱することに…。
号令するときは「一度だけ」「はっきりと言う」を忘れずにして下さいね!
 この記事では、犬に「伏せ」を教える方法を動画を見ながら解説しました。
「伏せ」は、ワンちゃんには是非とも教えておきたいことのひとつです。
決して簡単なことではないですが、気長に、犬を褒めてあげることを忘れることなく、ぜひ挑戦してみて下さいね!
この記事では、犬に「伏せ」を教える方法を動画を見ながら解説しました。
「伏せ」は、ワンちゃんには是非とも教えておきたいことのひとつです。
決して簡単なことではないですが、気長に、犬を褒めてあげることを忘れることなく、ぜひ挑戦してみて下さいね!