
【完全版】猫のトリミングは必要?やり方やトリミングの頻度を解説
2021/01/31
目次
猫のトリミングは必要?

最近はペットとして犬だけでなく猫も飼われるようになってきました。
犬と違って散歩やしつけがいらないのですが、猫にもケアは必要です。
それは、食事・トイレはもちろんのこと、爪切りやブラッシングなどのトリミングも必要になってきます。
トリミングといえば、犬に必要なお手入れというイメージが強いかもしれません。
しかし、猫にもブラッシング、カットやシャンプー、耳掃除、爪切りなどお手入れが必要で、これらのことをトリミングと言います。
今回は、猫にトリミングが必要な理由やトリミングのやり方、頻度などご紹介していきたいと思います。
大切な家族に一員である猫ちゃんが快適に過ごせるよう、トリミングについて学んでみてくださいね!
猫は自分でトリミングが可能

猫にもトリミングが必要と申しましたが、実は猫はある程度、自分でトリミングをすることができます。
よく猫が体を舐めて毛づくろいしているのを見かけませんか?
これは猫が自分でブラッシングやシャンプーをしているのです。
殺菌作用のある唾液を使って、身体を舐めることでシャンプーをしているような役割を果たしています。
また、自分で爪を噛んだり引っ張ったりして長さを整えるなど爪切りも自分ですることができます。
猫がトリミングできない場所もある
自分でトリミングができるなんて猫はすごい能力を持っていますね。
しかし、やはり自分でトリミングできる範囲には限界があります。
背中など猫の舌が届きにくい場所は汚れやすくなっており、唾液だけで身体中の汚れを落とすことはできません。
仮に舐めることができても、汚れを舐めることで雑菌が身体に入り、病気になってしまうこともあります。
また、身体を舐めすぎることで、皮膚病を発症しやすくなることも。
爪切りにおいては、猫自身に任せていいのではないかと思いがちですが、室内で飼われている猫には、爪切りが必要になってきます。
古い層の爪を剥がし、新しい爪にする爪とぎと違って、爪切りは、健康で快適に生活するためのものです。
延び放題の爪が肉球に刺さってしまうと怪我や病気の原因になってしまいます。
このような理由から、猫にもトリミングが必要になってきます。
猫のトリミングのやり方

猫は、ある程度は自分で身体を手入れすることはできます。
しかし、身体全身のケアは難しく、私たち人間がケアしてあげる必要が出てきます。
プロの方にお願いするという方法が安心ではありますが、自宅でできるほうが節約にもなりますし、猫自身も自宅の方が安心してリラックスできるでしょう。
トリミングは身体全身を触れることになるので、成猫になってから始めるのは大変です。
できるだけ小さい内から少しずつ行い、トリミングが嫌いにならないよう慣らして行くことが重要です。
トリミングはどんなことをするのか、やり方をまとめてみました。
爪切りの方法

猫の爪の中には血管と神経が通っています。
そのため、切りすぎてしまうと、痛みとともに出血してしまうので、深爪にならないように注意しましょう。
爪の細くなっている先端を切るようにすると良いですね。
猫の種類や活動の具合によって変わってきますが、2〜3週間に1回程度爪切りを行うようにすれば適度な長さを保つことができます。
歯磨きの方法

猫は人間よりも、歯垢が歯石になるスピードがとても早いので、歯周病になりやすいです。
ですので歯磨きが重要になってきます。
飼い主さんにとって歯磨きも大変な作業でしょう。
猫が歯磨きを嫌がったときは、歯磨き用のウェットシートやガーゼなどで歯の汚れを落としてください。
また、歯磨きガムやおもちゃなどのデンタルケア製品を使用するのも良いでしょう。
人間においては、歯磨きは毎食後行うのが理想といわれていますが、1日1回、難しければ2日に1回などを目標にすると良いかもしれません。
ブラッシングの方法
人間用のブラシはプラスチックやナイロン製が多く、静電気や切れ毛のもとになります。
猫へのブラッシングは猫用ブラシを使用しましょう。
プロ使用のスリッカーブラシや獣毛ブラシなどが良いでしょう。
ブラッシングのコツは毛並みにそって優しくとかすことです。
絡まった毛などはスリッカーブラシできれいにとくことができますが、毛玉になってしまったものはブラシでほぐそうとすると皮膚を引っ張り痛みが生じるのでやらないようにしてください。
また、背骨や腰骨、胸骨など骨のある部分にブラシが当たると嫌がる可能性があります。
その部分は避けるようにブラッシングしましょう。
頻度は、毎日が理想的です。
少なくとも3日に1回は行うようにしてください。
シャンプーの方法

もともと猫は、水に濡れるのを嫌う動物です。
ですのでシャンプーは大変な作業です。
耳の中に水が入らないように気をつけましょう。
そして、なるべく手短に済ませることがポイントです。
水を嫌がり暴れる場合は、拭くだけでシャンプーできる使い捨てのシートを利用するのも1つの方法です。
通常は、ブラッシングだけでも十分に皮膚を清潔に保つことができますので、シャンプーは年に1回程度で良いでしょう。
耳掃除の方法
シャンプーと同様に、耳掃除の頻度はそれほど多くする必要はありません。
オリーブオイルか動物用のクリーニングローションでティッシュもしくはコットンを湿らせ、外耳部分をやさしく拭き取ってください。
強くこすると耳に傷がつき、炎症の原因になりますので気をつけましょう。
綿棒の使用は、外耳を傷つける可能性があるため避けたほうが賢明です。
耳掃除を必要以上にしてしまうと耳を傷つけてしまうので、1ヶ月に1〜2回程度が目安になるかと思います。
獣医師など指示がある場合は、それに従って行うようにしましょう。
目やに取りの方法
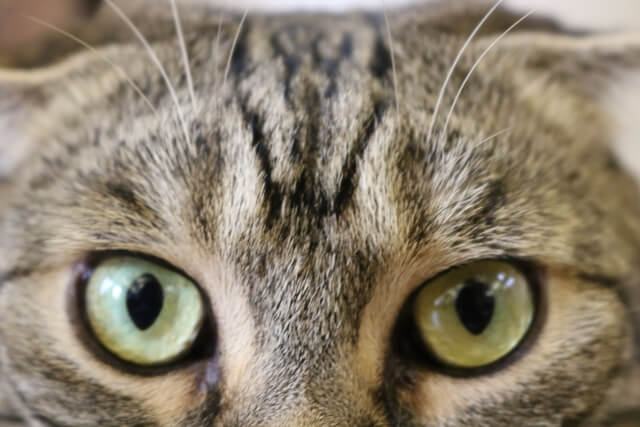
寝起きのときなどについている少量の目やには、放っておいてもかまいませんが、気になるようでしたら取ってあげてください。
水を含ませたコットンや、ペット用ウェットティッシュなど、目の周りにも使用できるタイプのものを使用します。
人間用のウェットティッシュはアルコール成分が含まれている可能性があり、猫に害があるので使わないようにしましょう。
汚れが目立ったら拭き取るようにしてください。
猫のトリミングの頻度

トリミングのやり方は分かったところで、どのくらいの頻度で行えばいいのか気になりますね。
ブラッシングについてはできれば毎日するのが理想的でしょう。
他のトリミングについては、それぞれ頻度が違うのでご紹介していきたいと思います。
耳掃除は月に1回ほど
私たち人間と同じように、過度な耳掃除は良くありません。
耳に問題のない猫であれば、ほとんど耳掃除は必要ありません。
飼い主さんのほうでよく観察してあげて、汚れが気になったときに耳掃除をしてあげましょう。
1ヶ月に1回程度で十分です。
しかし、耳の病気にかかってしまっている場合は、獣医師に相談の上で行うようにすると良いです。
爪切りは年齢による

猫の爪の伸び方は、年齢によって異なるといわれています。
子猫の場合は1週間に1回、成猫は、2週間に1回、高齢の猫は3週間に1回程度が目安になります。
爪の伸び方は、活動時間や、活動内容によっても多少異なってきます。
肉球を軽く押してみて、爪が尖っていたら爪切りをするようにすると良いでしょう。
シャンプーは半年に1回ほど
室内で飼われている猫は、汚れが少ないため、頻繁にシャンプーをする必要はありません。
被毛の汚れやニオイが気にならなければ半年1回ほどで十分です。
長毛でパーマがかった被毛を持つ猫に場合、毛のベタつきが気になったらシャンプーしてあげましょう。
外でも活動する猫の場合は、汚れやすく、ノミやダニを持ち帰ってくる可能性が高いです。
その場合は、シャンプーの回数を増やしてください。
とはいえ、洗いすぎてしまうと却って皮膚炎の原因になってしまいます。
皮膚の健康を保つために、洗い過ぎには注意しましょう。
カットは毛玉の有無や種類に合わせる

猫のカットは、被毛の長さによって異なります。
短毛種の場合、基本的にカットは必要ありません。
長毛種の場合も、必ずしも必要というわけではありません。
しかし、長毛種の猫は、夏には熱中症になりやすくなるため、カットが必要になってくることもあります。
また、毛玉の有無や毛の状態などを観察し、必要であればカットしましょう。
被毛のカットは、猫にとって負担が大きいため、体調が悪そうであったり、いつもと違う様子の場合は、体調が整ってから行うと良いでしょう。
飼い主さん自身でのカットが不安な場合は、トリマーや獣医師に相談してから行うのが良いかもしれません。
まとめ

いかがでしたでしょうか?
トリミングの必要性、やり方、頻度などお分かりいただけたかと思います。
猫は私たちが思っている以上に皮膚が薄いです。
また、皮膚が切れてもほとんど出血しないので、誤って猫の皮膚を傷をつけても気づかなこともあります。
ですので、毛玉など気になっても、ハサミなど使用するのは避けましょう。
毛玉の除去やカットなどはプロにお願いするほうが安心です。
犬のトリミングは一般的なこととして捉えられていますが、猫の場合、受け入れてくれるところはそれほど多くないというのが現状です。
また、嫌がっているのに無理やりトリミングを行うと、強くストレスを感じ、体調を崩してしまうということも少なくありません。
トリミングを行うために鎮静剤を用いるという動物病院などもあるようです。
薬を使用するということが不安な飼い主さんは、どのようにトリミングを行っているのか事前に確認すると良いでしょう。
ただ、ハサミを使用しないようなトリミングであれば、飼い主さんの日々のケアで十分に健康を保つことができます。
猫の日々の様子を一番分かっているのも、猫が信頼を寄せているのも飼い主さんです。
愛情を込めて猫のケアをしてあげれば、健康が保たれるだけでなく、さらにお互いの信頼関係が強くなりますね!
この記事を読んだ人におすすめの記事
-

【これで安心】iphoneからの操作や録画も可能!ペット用監...
ペット用監視カメラの選び方 仕事などで家を離れる際にペットがいい子にしているか気になってしまいますよね。 そのような時に...
ペット用品
犬
猫
知って得する
-

猫用キャリーバッグの人気おすすめ10選|目的別に徹底解説
猫用キャリーバッグ(リュック)の種類 猫の通院や一緒に出かける時などに活躍してくれるキャリーバックは、飼い主と猫にとって...
ペット用品
猫
知って得する
-

可愛いペット用骨壺のおすすめ8選|失敗しない選び方やサイズも...
ペット用骨壺のおすすめの選び方は? 今、ペット用の骨壺は様々な種類が販売されています。 大切なのは自身のペットに合った骨...
ペット用品
犬
猫
知って得する
-

【知って得する】猫が集会している理由?!猫集会の謎を解説!
猫集会とは? 猫が同じような間隔をあけて集まっているのを見かけたことはありませんか? これこそまさに「猫集会」です。 近...
ペットの気持ち
猫
知って得する
-

【猫用食器の人気おすすめ10選】おしゃれ食器や猫に優しい設計...
猫用食器・餌入れの選び方とは? 猫を飼った際に必ず飼うのが猫用の食器ですよね。 どんなのでも良いと思っている方も多いです...
ペット用品
猫
知って得する
-

【もう悩まない!】自動給餌器のタイプ別おすすめ20選!選ぶ時...
自動給餌器のおすすめ商品:トレイタイプ 自動給餌器は飼い主が長時間留守をする際などでも餌をあげることができる便利なアイテ...
ペット用品
犬
猫
飼い主さんの悩み
「猫の特集」新着記事
-

暖かいだけじゃない!猫が日向ぼっこをする理由と効果とは?熱中...
猫が日向ぼっこをする理由と効果 猫は暖かい場所が大好きですよね。 特に日向ぼっこをしている猫を見ることが多く、とても気持...
ペットの気持ち
猫
知って得する
-

猫キック!猫が蹴る5つの理由とは?やめさせたい時の対処法も
猫がキックする5つの理由 猫が甘えてくる姿はとっても可愛いですが、高速でキックされるのは可愛いとばかりも言っていられず、...
ペットの気持ち
猫
飼い主さんの悩み
-

猫に野菜は必要?食べてもいい野菜・食べてはいけない野菜
猫に野菜は必要? 大切なペットである猫の健康には気をつけたいですね。 食事内容にも注意して、野菜を食べたほうが良いのかど...
猫
知って得する
飼い主さんの悩み
-

猫が家に帰ってこない5つの理由とは?探し方と今後の対策も
猫が家に帰ってこない5つの理由とは? 家の中で生活することを推奨される猫ですが、外と出入りが自由だったりドアを開けた隙を...
猫
知って得する
飼い主さんの悩み






